|
電波暗室 2006/1-12
- 2006/12/31(日)
コミックマーケット71@東京ビッグサイト、第3日目。
一般参加。
6:45、列に並ぶ。10:07、入場。これまでの最短記録だなぁ。コミケスタッフの入場整理スキル向上の
おかげ。でも、9:30に国際展示場駅についた友人のS降は、10:30に入場できたとのこと。西館からだ
けど。まぁ、それはそれ。寒さに耐えて、体力を消耗して、ってことに意味があるのです。修行です。
15:00、撤収。肩が限界。
16:00、アトレ大井町のさぼてんにて食事。
17:53、東京発のぞみ新大阪行き。20:15、京都着。
これから荷物を整理して実家に帰ります。2006年、このサイトを訪れていただいた皆さんに感謝します。
よいお年をお迎えください。山Dはマリみてを読みながら、年を越す予定です。
次回の更新は、年明け2007年の1/2になると思います。1/1はお休みです。
(21:00記す)
- 2006/12/30(土)
コミックマーケット71@東京ビッグサイト、第2日目。
サークル参加。西ーれ61a、「山Dの電波暗室」
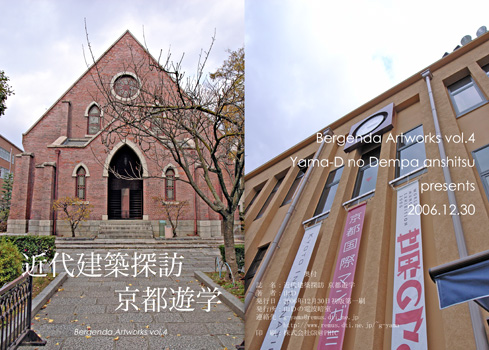
新刊「近代建築探訪 京都遊学」、A5版フルカラー24ページ。頒価500円。
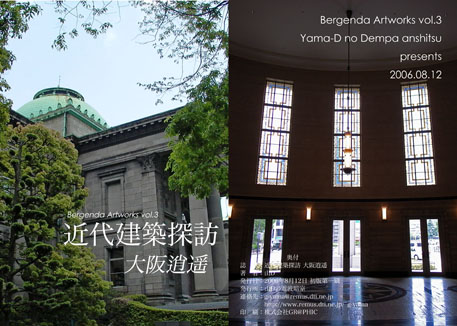
既刊「近代建築探訪 大阪逍遥」、B5版フルカラー16ページ。頒価500円。
サークルにお越し頂きました皆さん、ありがとうございました。
本をお買い上げいただきました皆さん、ありがとうございました。
両隣のサークルさん、お世話になりました。お疲れさまでした。
いやあ、くたくたです。6時間立ち続けたのにはさすがに疲れました。
あ、もうMacのバッテリーが切れてしまいます。ひとまず、これで。
夏は既刊を含めて、再販しないといけないかも。お金が。。。
あ、そうそうハニワサブレの差しいれをいただきました。いつもありがとうございます。(17:12記す)
さあ、あした一日頑張ろう。
アップしようとしたら、バッテリーが切れました。
いまはもう京都に帰ってきました。
(12/31、20:50追記)
- 2006/12/29(金)
コミックマーケット71@東京ビッグサイト、第1日目。
一般参加。
9:30、大井町到着。ホテルに荷物を預けて、りんかい線で出発。
15:15、ホテルへ帰ってくる。1日目終了。会場内はすこし暖かいものの、例年のごとく汗をかく
というほどではない。じっとしていると寒くなってくる。風が強いので寒さは京都と変わらず。
「時をかける少女」の本(健全)を2冊買えたのがよかった。そうそう、いろいろ忘れ物をしたの
で、これから現地調達しなければならない。行きのタクシーで布ガムテープ。あと家に折りたたみ
椅子。それから金庫。金庫というのは単に紙でできた箱で、いつも使っているものだった。1時間
後に食事予定。あまり歩いていないけれど、すでに左足がよくない状態。食事に行ったときにバン
テリンも買ってこよう。(15:45記す)
18:00、食事終了。さぼてんにて。メイン=ロースカツ、サブ=メンチカツ、サイド=梅しそ巻き
チキンカツ、サラダ=ポテト、デザート=黒酢シャーベット。5つを選ぶというシステムの定食だ
ったが、ちょっとカツが多すぎた。そうそう、わたしが自分から「梅しそ」の入ったものを選んだ
ということは、ちょっと特筆すべきことかもしれない。
東京在住の友達と飲みに行くというS雄さんと別れて、大井町アトレの有隣堂へ。レジを終えるこ
ろには先ほどまでの膨満感も、足の痛みも感じなくなっていた。やはり書店の魔力はすごいなぁ。
本日買った同人誌以外の本
「マリア様がみてる クリスクロス」、今野緒雪著。集英社刊。440円。
シリーズ最新刊。ほんの二三日前に新刊がそろそろか?とチェックしていたのに見逃していた。
「げんしけん」第9巻(完結)、木尾士目著。アフタヌーンKC。514円。
コミケに来て、げんしけんを読む。まっとうな行為かもしれない。青春は過ぎ去りましたが。
「となりの801ちゃん」、小島アジコ著。おおぞら出版刊。1000円。
立ち読みして、衝動買い。わたくしは”アイラブ腐女子”というわけではないのですが。801ちゃん
というのは京都市御薗橋801商店街の実在するマスコットキャラらしくて、わたしの祖父母の家が
この御薗橋から歩いて5分のところにあったので、ついつい反応してしまった次第。
「yom yom」(ヨムヨム)、小説新潮1月号別冊。680円。
赤いカバーに新潮文庫のキャラクターyondaのイラストのペーパーバック。川上弘美、梨木香歩、
阿川佐知子、恩田陸、重松清、江國香織、角田光代、石田衣良から穂村弘に豊崎由美...あげれば
きりもなし、あーお腹いっぱいというくらいのラインアップ。梨木香歩の家守奇譚の追加版6篇が
掲載されていたので買いました。
18:30-45、大井町ショッパーズ内の百円ショップで明日のサークル参加で使う小間物を調達。その後、
QBハウスを発見。サークル参加は接客も大事だなと思い、散髪することに。いや、本当は今日の強風
で髪をいちいち直すのがめんどうになったから。きのうは結局、寒いなか散髪に行くのがめんどくさか
ったからということなのかも。わたしの行動はどうも一貫性に欠けている。10分1000円。こざっぱり
しました。
上腕にも痛みが出てきたので薬局でバンテリンを購入。ああ、なんだか大井町に住んでいるかのような
行動。旅行とはちょっとちがう感覚。なんだかんだで、約10年だもの。街にも慣れるもの。心地よい。
あとはサークルチェックして、本を読んで、風呂に入って。
サークル参加なので明日は7時起床でOK。ゆるゆるすごします。
(19:55記す)
- 2006/12/28(木)
仕事納め。終了間際にトラブル発生...またか!だいたい、いつもいつもどうして最終日に集中
するのだー。しかし、これは思ったより短時間で解決。やた。
しかし、システムの立ち下げの時にトラブル発生。EWSのディスクに障害発生。立ち下げるに
は立ち上げなおす(リブートする)しかない。これがまた1時間以上かかる。おかしい、こんな
にかかるはずはない。と画面を見るとエラーの行列が。。。とりあえず電源を落とせる状態にま
でなった(エラー無視)が、年明けの立ち上げで地獄を見ることが確定。憂鬱だ。
そもそも毎年毎年、構内を停電にするのがおかしいのだ。せっかく安定して走ってるシステムを
立ち下げたり、立ち上げたりすることが、どれだけシステムに負担になっているのか。無駄なメ
ンテ時間もくうし。なんとかしてほしいなぁ。
しかし、年末に北陸に出張しているみんなに比べればましなのかもなぁ。この天候だと帰ってこ
れないかもしれないし。
本当は今日、印刷屋に行く前に髪を切りにいくつもりだったのだが、この年末は急激に冷えると
いうかもうさぶいので下手に切るのはよくないと思いなおし中止。その結果、禁断の技を使って
しまった。。うっとおしいもみあげだけ切る!あれだけ自制してきたのであるが、とうとうたが
がはずれてしまいました。だめな私。
さて、明日から冬コミ、お祭りです。楽しんでこよう!
6時間後に出発。すでに、左足と腰がやられかけているがテーピングで補強。がんばろう。
- 2006/12/27(水)
スタンドで食事。本年最後。
NCの用事、少々。
あまり、年の瀬って感じがしない。やっぱり雪が降らないからかなぁ。
そういえば、今年も年賀状書く余裕がやっぱりなかったことに気づいた。
冬コミの準備は明日する。きょうはのんびりすごそう。
ひさしぶりに「どうでしょう」をリアルタイムに見られることだし。
ひとつ思い出した。いま「藤森照信の原・現代住宅再見3」を読んでいるのだが、そのなかに
『立原道造の「ヒアシンスハウス」』という章がある。立原道造…、どこかで見たことがある。
建築関係じゃない。それとは関係のないところで見た。だからひっかかる。どこだ?どこだ?
家に帰ってきてわかった。木下牧子作曲の合唱曲「夢見たものは」の詩が立原道造なのだ。えっ
同姓同名の別人だろうって?一瞬そうかと思って「~住宅再見3」の経歴を見ると、間違いな
いことがわかった。「東京帝国大学の建築学科に在学中から青春の抒情派詩人として知られて
いた。」と書いてあるから。建築の方でも才能があったらしいのだけれど、24歳で夭折して
いることをはじめて知った。ヒアシンスハウスは彼が友人に送ったスケッチを元につい最近建
築されたものだという。そのスケッチは、およそ建築家というよりも、まさに詩人のそれといっ
た方がふさわしいような、柔らかな線で綴られたものだった。建築と詩作、あまり結びつきに
くいゆえに、世の中にはあまり知られていないことのような気がする。特に合唱方面には。
天才というものはいるものだな。彼の建築と、詩の両方を見るとそう感じる。
ちょっとした発見をしたような気分。
- 2006/12/26(火)
風邪薬の効果で、喉の痛みはとれる。今回はほとんど熱が出なかったので助かった。腰は徐々に回復
しているが、ずっと座っていたあとに立つとなかなかまっすぐにならない。きょうは洗面所の掃除を
完了。替え刃のリリース機構が固まって動かなかったカミソリ(シック・ウルトラ)の修理もする。
いままで無理矢理はめてたのが、これでスムーズに付け替え可能に。早くやればよかった。相変わら
ず台所掃除に着手できない。腰が警戒しているのかも知れぬ。
原稿がすんでちょっと余裕ができたので「ジョン・シンメトリー」で遊んでみる。これは何かという
とデジカメ画像を左右対称もしくは、上下対称にコピーして、その2枚を適当なところではりあわせ
るというもの。百聞は一見にしかず。ごらんください。

熊本市電・改。

新型モールトン。
という具合。本家本元はこちら、シンメトリー倶楽部で、”ジョン・シンメトリー”という写真
集が出版されている。二つの胴体を持つ犬のカバーが目印。
見ての通りリアルなのにアンリアルな、いわくいいがたい雰囲気を持った写真が現出してしまうのが
とても面白くて夢中になってしまう。ただ、これを画像ソフトなんかでやろうとすると結構めんどう
なのだ。はりあわせる位置をイメージしてからでないとうまくいかないのだが、はじめから完成写真
のイメージができたら面白いはずもなく、偶然生まれる効果が楽しいわけで。そこで、そういうソフト
が出来ている。
わたしが使ったのは「しんぶんし」というMac用ソフト。検索すれば出てくると思う。それからWin用
はこちら。
みなさんも自分のデジカメ画像で遊んでみてください。
- 2006/12/25(月)
給料日。マンションの更新料を振り込む。12月末までだったのでぎりぎりだ。12月分の家賃もある
から、毎年のことながらきつい。どうして家賃一ヶ月分も払いこまないといけないのか、よくよく
考えると疑問だ。
腰の調子はあまり変わらず。でも、なんとかトイレ掃除をやり遂げる。台所掃除よりは腰の負担は
少ないので助かる。台所の続きは、腰が治ってからだなぁ。この調子だともっともちらかっている
部屋の整理整頓ができない可能性が高い。。。一番、かがんだり立ったりしないといけないうえ、本
の移動を伴う(重い)から。年末には本がさらに増えるというのに。うーむ。
すこしだけサークルチェックを行う。まだ集中力はそれほど回復していないので、早々にやめる。
1日目は行くところはほとんどなさそうな雰囲気。3日目に集中している。熱い大晦日になりそうだ。
- 2006/12/24(日)
朝、起きると喉風邪を引いてました。
昨日、年内の合唱が終わったことで気が抜けたんだろうか。ついでに、というべきか金曜日から
患っていた腰痛が本格的に到来。テーピングでごまかすのもさすがに限界で、まっすぐ立って歩
けないのだ。なので、腰をかがめたへっぴりごしで湿布を買いにいく。頭痛薬と湿布は切らした
らだめだわ。本当は、一日休みの今日は部屋の掃除をやってしまうつもりだったのに、台所の途
中でリタイアとなった。
腰痛の原因は、冬コミ本づくりの作業姿勢だろうと思う。ちゃぷ台の上に置いて、あぐらをかき
ながらだったのが相当負担だった。机の上を片付けて椅子に座ろう。だいたい今、椅子はベラン
ダに置いてあって、雲とか空の鑑賞用となっているし。
掃除したかったよ。。。
風邪の方がダメージは少ないけれど熱が出るとやっかい。安静にして、早めに寝ます。
DS LiteでWi-Fi通信に挑戦。SSID、WEPパスワード、MACアドレスの設定さえ問題なければ、
即座に接続できることがわかった。いまのところ用途はゲームの通信対戦くらいしかないけれど
この機能を使って、DSならもっと面白いものが開発できるんじゃないだろうか。この前読んだユ
リイカで知ったのだけれど、"DS"は何の略か皆さん知ってますか?Dual Screenかと思いきや、
じつは"Developers' System"。開発環境、開発システムってこと。ゲームの開発者に何か作っ
てやろう!って気にさせるハードという意味なのだろうな。個人でだってできるかもしれないとい
う気がする。PSPならやる前から匙をなげてしまいそうだけれど。やれることが多いことが必ずし
も良いということではないみたい。ゲーム(ハード)に関しては。
さて、明日はクリスマス。CDでメサイアでも聞こうか。
好きなアリアの言葉を記す。
*34a Air(Soprano)
How beautiful are the feet of them
that preach the gospel of peace,
and bring glad tidings of good things.
(Isaiah 52:7/Romans 10:15)
*40 Air(Soprano)
I know that my Redeemer liverth,
and that he shall stand
at the latter day upon the earth.
And though worms destory this body,
yet in my flesh shall I see God.
(Job 19:25-26)
For now is Christ risen from the dead,
the first fruits of them that sleep.
(I Corinthians 15:20)
結局、全曲聴きました。よかった、音楽には合唱にはやっぱり救いがあるとわかって。
- 2006/12/23(土)
入稿してきました。データチェックと、ゲラ刷りのために時間がかかるということなので、
そこからモールトンで5分ほど走ってMoku2+4(小径自転車専門店)に行く。鈴鹿のレース以来、
フロントディレイラー(前側の変速機)がインナーからアウターへ戻らなくなる現象が出ていたか
らだ。どういうことかというと、インギアは軽いので登坂のときに使って、アウトギアは重いので
通常+高速時に使うのだが、登りおえたあとにさあスピード出すぞ!というときに変速が切りかわ
らないので、失速してしまうのだ。これにはほとほと参ってしまった。自分でケーブルを微調整し
ても全く直らないので、メカニックにお願いするしかない。
結局、3分ほどの調整であっけなく直ってしまう。でも、見た感じやっぱりプロでないと調整でき
なさそうである。自転車の機構って単純そうに見えるけれども、じつは見た目ほど単純ではないの
だなって思う。その後、店の人と1時間半ほど話し込んでしまった。自転車屋なのに、自転車の話
をほとんどしなかったのが、このお店らしいといえばらしいのかも。ところで、ここのお店はいわ
ゆる街の自転車屋さんと違って、作業場の泥臭い感じが店頭にはほとんどない。どこか、おしゃれ
な喫茶店のごとき内装とディスプレイなので、居心地がいいのである。作業スペースは店の奥にあ
るのだけれど、そこもとても整理されている。自転車に興味がある人は、一度行ってみてほしい。
ホームページ→http://www.2plus4.net/
印刷所指定の時間にもどり、ゲラのチェック。問題なし。あとは、上質紙に印刷したときにどうな
るのかだけが心配。こればっかりはあがってくるまでわからない。ともかく、これで本ができます。
ふーっと一息。
ところで、ついに買ってしまいました!

NINTENDO DS Lite -Crystal White- with MacBook
DS Liteは明らかにMacを意識してますね。岩田社長はMacユーザーだと聞いたことがあるのだけ
れど。そういうわけで、わが家のMacBookとそろえるために、あえてノーマルのWhiteを選択。
並べてみるといい感じ。
それで、ソフトはというと「漢検DS」と「みんなのDSカーリング」。漢検はともかく、カーリ
ングはどうなんだ?って思っている人がいるかもしれない。でも、これとてもよくできてます。
日本カーリング協会公認・監修だし、あのチーム青森のカーリング娘もご推薦!こういうマイナー
スポーツ(トリノで注目されたけれど、基本的には競技人口が少ないので)のゲームというのは、
言ってみれば、色物扱いされやすい。少なくとも、いままでのハードでは。でも、DSでは違うと
言いたい。あのカーリングのストーンを投げる動作、ブラシでこする動作がDSではゲームの操作
として違和感なくできるからだ。だって、タッチスクリーンの上を本当にこするんだもの!
しかし、なかなか勝てません。とりあえず、練習モードでカームアラウンドというんだったか、
すでにあるストーンの真後ろにカーブさせて回り込ませて停止させるテクニックを身につけない
と運頼みなってしまうのだ。。。
値段は破格の1890円。安くても、面白いものは面白い。
(DSのソフト自体が安いのが多いけれど、その中でも特に安い)
17:00-20:00、本年最後のNC練習。ひどいよ!ベース。一ヶ月前に楽譜渡しているし、前回も
練習した曲なのに、はじめて見るかのような顔つきと音で歌うのはやめてほしいなぁ。。。ぷん
すか。隣で歌っているとわかるんだ。ちゃんと練習してきた人、やる気をもって歌っている人と
先週から今日さっきまで楽譜開いていない人との違いは。
20:00-22:30、NC忘年会。忘年会出るひまがあるなら、家帰って音程さらえ!とまでは、私も言
わない。でも、でも、言いたくなる。我慢する。信頼しあいながら、お互いに補いあいながら、対
等の立場で歌えるベースの仲間が帰って来て欲しい。一方的に音とってこいなんて、誰も言いたく
ない。消耗するだけだし。
- 2006/12/22(金)
校正終了。忙しいのに無理してくれた友人に感謝。ありがとう。明日の朝、入稿してきます。
冬コミ:土曜日(二日目)、西れ-61a「山Dの電波暗室」にて参加します!新刊あります。
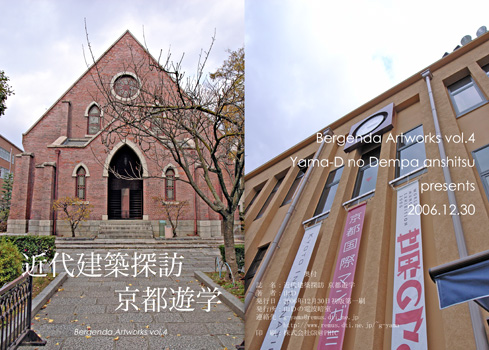
新刊「近代建築探訪 京都遊学」、A5版フルカラー24ページ。頒価500円。
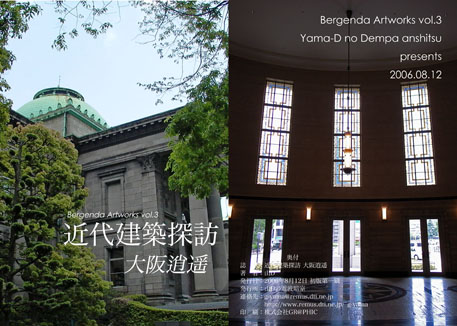
既刊「近代建築探訪 大阪逍遥」、B5版フルカラー16ページ。頒価500円。
- 2006/12/21(木)
冬コミ本、なんとか間に合いそうです。
今日はもう寝ます。
冬コミ本進捗
表紙・裏表紙 100%
序章・中表紙 100%(最終校正中)
4,5頁 100%(最終校正中)
6,7頁 100%(最終校正中)
8,9頁 100%(最終校正中)
10,11頁 100%(最終校正中)
12,13頁 100%(最終校正中)
14,15頁 100%(最終校正中)
16,17頁 100%(最終校正中)
18,19頁 100%(最終校正中)
20,21頁 100%(最終校正中)
22,23頁 100%(最終校正中)
- 2006/12/20(水)
スタンドで夕食。今日治してもらった歯のおかげで、すこぶる快調。
きょう買った本
「よつばと!」6巻、あずまきよひこ著。メディアワークス刊。600円。
読んでいる余裕ないのに、買ってしまった。買ったという事実が精神安定につながるのだろう。
冬コミ本進捗
表紙・裏表紙 100%
序章・中表紙 90%(文章作成・校正中)
4,5頁 95%(最終レイアウト中)
6,7頁 95%(最終レイアウト中)
8,9頁 95%(最終レイアウト中)
10,11頁 95%(最終レイアウト中)
12,13頁 95%(最終レイアウト中)
14,15頁 95%(最終レイアウト中)
16,17頁 95%(最終レイアウト中)
18,19頁 95%(最終レイアウト中)
20,21頁 95%(最終レイアウト中)
22,23頁 90%(文章作成・校正中)
文章全部書きました。校正してもらったやつの直しがまだだけど。。。
いよいよ、明日が最終日。
去年の冬に刊行した「京都断章」の序文を見ると「雪降る京都にて」と書いていた。今年は全然
そんな気配がないのが、ちょっと残念である。暖冬なんだろうね。底冷えは相変わらずだけれど。
疲れた。ちょっとベランダに出て、空気を吸ってこよう。
- 2006/12/19(火)
昨日よりも、今日のほうがなぜか頭痛がひどくて、体もだるい。集中力もやや欠け気味。昨日は
いろいろドーピングしていたから、きょうはその反動が来ているのかもしれないなぁ。
某健康食品会社の「にんにく」を注文する。以前、断続的に二ヶ月ほど試したところ、朝の目覚め
が違ったので、ちょっと継続してみようかと思ったのだ。もし、体質が改善されたらレポートしよ
うと思う。三ヶ月ほど待たれよ。って、合唱のオフシーズンに元気になったら、まるで合唱で健康
を害してたみたいだなぁ(無関係とは言い切れないのだけど...)。いやいや、2007年のスローガ
ンは「元気になる合唱」。基礎体力・筋力をつけて簡単に疲れない身体をつくるのである。
冬コミ本進捗
表紙・裏表紙 100%
序章・中表紙 80%
4,5頁 90%(文章作成・校正中)
6,7頁 90%(文章作成・校正中)
8,9頁 90%(文章作成・校正中)
10,11頁 90%(文章作成・校正中)
12,13頁 90%(文章作成・校正中)
14,15頁 90%(文章作成・校正中)
16,17頁 90%(文章作成・校正中)
18,19頁 90%(文章作成・校正中)
20,21頁 90%(文章作成・校正中)
22,23頁 50%
残りは、序文とあとがき。
- 2006/12/18(月)
12月もなかばをすぎて、いよいよ押し迫ってきたわけであるが、懸案なのは大掃除のことである。
今年の冬コミは29,30,31と大晦日にかぶっている。例年、30日の終了後に帰京するか、一泊して
31日の昼頃に帰ってきていた。帰宅後に部屋の掃除をして、夕方実家に帰るという寸法である。
ところが今年はどうあっても帰ってくるのは19~20時ごろになってしまう。これでは掃除をしてい
る時間がない。となれば、年末にいたるまでに少しずつやっていくほかない。
というわけで、まず風呂掃除から。風呂に入るまえに、薬局で買ってきた特価品の風呂用洗剤を
しゅっしゅ、しゅっしゅと浴槽から、洗い場まで一心不乱にかけまくる。ちょっと楽しい。大半
はこすらずに落ちるが、やはり頑固なのはある。めんどくさがりのくせに、やるときは徹底的に
やってしまう性格なので一生懸命にこする。洗い場の床から高さ5cmくらいまではじつは汚れて
いることを発見。全体がアイボリーなので、普段は気づかないけれど洗剤がついていた部分と、
そうでないところで明らかに色が違う!そういうのは許せないというか気になるので、またごし
ごしやる。
結局、その後風呂に入ってた時間より、洗ってた時間の方が長かったなぁ。
ともかく、ひとつ掃除終わり。つぎは、台所だな。
(トイレは普段からまめに掃除しているのだ)
冬コミ本進捗
表紙・裏表紙 100%
序章・中表紙 80%
4,5頁 90%(文章作成・校正中)
6,7頁 90%(文章作成・校正中)
8,9頁 90%(文章作成・校正中)
10,11頁 90%(文章作成・校正中)
12,13頁 90%(文章作成・校正中)
14,15頁 90%(文章作成・校正中)
16,17頁 90%(文章作成・校正中)
18,19頁 90%(文章作成・校正中)
20,21頁 50%
22,23頁 50%
土曜日の午前中にひとつ、きょうふたつ書いたので、残り3つ。
ラストスパート。序文で手こずらないようにしないといけない。
- 2006/12/17(日)
BKクリスマスコンサート、無事終了しました。聞きに来てくださった方ありがとうございます。
自分でいうのもなんですけど、ヤンニラウル、クレーク、レクイエム、どれも音楽の中身がぎゅっと
つまった、音楽的にも気持ち的にもいい演奏ができたんじゃないかと思います。課題はもちろんある
のです。正直最後の練習のときまで、ここまで出来ると思っていなかった。でも、違った。本番のマ
ジックとかいうのがありますけど、それでもない。みんなが持っていた底力がきちんと発揮された。
そう思います。8年目にして、ようやく大人の演奏ができたんじゃないかと。毎年の演奏会で、指揮者
がステージで言うのです「いつまで経っても未熟な合唱団で。。。」と。でも、今年はそういう言葉
がなかった。指揮者も何か感じるところがあったのだと思います。そして、何よりも歌い手が自覚し
たと思います。いつまでも未熟ではいられないとみんなが思ったからできた。そう思います。これは
合唱団としては、足がかりに過ぎないのは確かです。この数週間でできたことを、初回の練習ででき
るようになれば、もっともっといい歌が歌えるはず。きょうのこの演奏会が、新たな出発点になれば
いいな、いやそうしようと思います。
いつもの文章と調子が違いますね。まぁ、きょうだけは許してください。
ちょっと頭が痛くなってきました。たぶん、明日の朝はひどい頭痛でしょう。いま、ちょうど頭痛
薬がきれています。しんどくなると思います。でも、いまはそれでもいいという感じです。
さて、明日からは原稿です。締め切りまで5日間。
きもちをきりかえて、頑張ります。
おやすみなさい。
- 2006/12/16(土)
暗譜が難しい曲がひとつあって、昨日いまさらながら、歌詞だけを書き出してみた。こうすると、
音程に惑わされずに歌詞の繰り返しの構造がわりとよく見えてくる。本当は他パートとの関係まで
やってみるといいのだろうけど、それは楽譜上で見る。音程って書いたけど、じつはベースはGの
音しかないのでした。。。
NC練習、17:00-21:00。新曲含めて10曲程度をさらう。一曲にかけられる時間が少ないので、
前回来ていないひとは、自分で予習しておいて欲しかった。ベースは、わたし以外は前回来て
いない人達ばっかりだったので、率先して歌わねば音が消える。途中で、明日本番だというこ
とに気づいて少しセーブしたのだけれど、ちゃんとできてるテナー系に申し訳ないくらい歌え
ない。つぎの本番まで、二ヶ月もないから何とかしないと!でも、どうすればいいのかなぁ。
BKでも、NCでも悩みはあまり変わらなかったりする。
帰宅途中、宴会会場に向かうM川さんを目撃。こちらに気づかずに一気に地下鉄の階段を駆け上が
っていかれる。すごいバイタリティだ。
さて、あしたはBKのクリスマスコンサート本番です。悔いの残らないように、あとちょっと頑張る
所存。
ああ、でも正直NC練習は疲れた。あしたの準備は、あしたしよう。いまは楽譜だけみる。
おやすみなさい。
- 2006/12/15(金)
BK練習、18:30-21:00。本番前、最後の練習。
帰宅後、暗譜が不十分な箇所をさらう。集中しすぎて、ちょっと車に酔ったみたいな感じになる。
気持ち悪い。。。きょうは原稿せず。
寝ます。
- 2006/12/14(木)
だんだん髪がうっとおしくなってきた。誘惑に駆られて、うっとおしい部分(もみあげとか)を自分で
切ってしまおうかとも思ったが、土曜日まで待って散髪に行けばいいのだ。あとちょっと待て、という
ときの我慢がわたしには足りぬ。辛抱、辛抱。
最近、ポストにマンション物件のチラシがよく入っている。間取りを見るのが好きなので、捨てずにと
っておくのだ。それにしても、高い。こんなのみんなよく買えるな。現実的には2000万円以下でないと
ローンがきついと思う。そんな「優良物件」はなかなか見あたらない。ここはやっぱり「夢の三億」頼
みかなぁ。
冬コミ本進捗
表紙・裏表紙 100%
序章・中表紙 80%
4,5頁 90%(文章作成・校正中)
6,7頁 90%(文章作成・校正中)
8,9頁 90%(文章作成・校正中)
10,11頁 90%(文章作成・校正中)
12,13頁 90%(文章作成・校正中)
14,15頁 50%
16,17頁 50%
18,19頁 50%
20,21頁 50%
22,23頁 50%
ようやく、文字数制限のある文章書きに慣れてきたかもしれない。しかし、前書き・後書きを含めてあと
6つも残っている。勝負はやっぱりこの土曜日か。演奏会前日ってのが、ヘビーだ。
- 2006/12/13(水)
原稿を初めてから、肩がこりこりです。
印刷する紙をどうしようか考えている。選択肢は3つ。コート紙、マットコート紙、そして上質紙だ。
東京・横浜篇、大阪逍遙は写真メインだったのでコート紙以外の選択はなかったけれど、京都断章では
読み物としてとらえていたから、光沢をおさえたマットコート紙にした。今回の本も読み物なので、
マットでもいいのだけれど、一つ問題がある。マットの場合、版ずれが起きるのだ。通常の写真なら
気にならないけれど、文字の部分の黒が4色のリッチブラッックにならず、茶色っぽくみえてしまう。
黒インキのみにすればいいのだけれど、写真と文字が同じページにあるので1色にはできない。これ
がイラストレーターなら可能なはずなんだけれど。。で、上質紙が版ずれを起こさないかどうかわか
らないが、マットよりもさらにしっとりした仕上がりになるのだ。たしかに発色はコートにはかなわ
ないけれど、手触りものふくめて考えると今回の本にいちばんあっているのではないかと思う。手許
にある印刷屋の見本紙を見る限りでは、十分「あり」だといえる。上質紙印刷の経験がある人、いな
いかなぁ。意見を聞いてみたい。
冬コミ本進捗
表紙・裏表紙 100%
序章・中表紙 80%
4,5頁 90%(文章作成・校正中)
6,7頁 90%(文章作成・校正中)
8,9頁 90%(文章作成・校正中)
10,11頁 50%
12,13頁 50%
14,15頁 50%
16,17頁 50%
18,19頁 50%
20,21頁 50%
22,23頁 50%
予定通り、ふたつ書いた。二つでも結構きついものがあった。とにかく、いまくじけていられない。
頑張ろう。寝たら死んでしまう!
- 2006/12/12(火)
あぁ、そういえば今日は亡くなった父の誕生日であった。そして明日は母の誕生日である。だから何か
するという訳でもないのだけれど、憶えている。
昨日帰りがけに会社の近くの本屋で冬コミカタログ購入。2400円って、高くなったなぁ。三日間開催
だから仕方ないのか。さっそく、うちのサークルのカットを確認。グレースケールでの入稿ができる
ようになったのだが、とてもきれいに出ていた。BW二値だと印刷の出方が読めなかったので助かる。
ぱらぱらとめくっていると、だんだん「祭り」のイメージが沸いてきた。夏とは違う、年越しの祭り
はまた雰囲気が違うものです。楽しみ。
19:30より、近くの大型喫茶店(そんな呼び名があるのか)で原稿執筆開始。で、ひとつめの建物の
第一稿があがったのが、21:00近く。うう、やはり期間があくと感覚が鈍るのかもしれない。それと自
ら決定した文字数制限の壁は想像以上にきつかった。こんなペースでは間に合わない!多いに危機感を
募らせる初日となってしまった。毎回、レイアウトが出来た時点で「おっ、余裕あるか?」などと思っ
てしまうのだけれど、とんでもない。のど元過ぎれば熱さを忘れるとはこのことだなぁ。もうひとつ要
因があって、会話を楽しんでいる人達の後ろに座ってしまったということ。そこしか空いてなかったの
で仕方がない。会話の音量というのは結構気になるもの。聞き取れない言語だったら、BGMにしてし
まえるんだけどな。煮詰まってきたところで、自習系の人たちのスペースに空きができたので移動した
けれど、そのころには疲れていて、ふたつめの原稿には手が着かず。
ともかく、明日からは一日二つ(現実的なライン)を目標に頑張る。しかし、毎日喫茶店だと太るか?
(カフェラテ+ケーキ1品食べるから)
冬コミ本進捗
表紙・裏表紙 100%
序章・中表紙 80%
4,5頁 90%(文章作成・校正中)
6,7頁 50%
8,9頁 50%
10,11頁 50%
12,13頁 50%
14,15頁 50%
16,17頁 50%
18,19頁 50%
20,21頁 50%
22,23頁 50%
- 2006/12/11(月)
スポーツや、囲碁・将棋などのゲームなどにはルールというものがあって、それがあるから成り立つの
であって、例えば野球で二塁から一気にホームベースに突っ込むことはできないし、サッカーでゴール
キーパーを二人に増やすことはできない。ルールを破る人がいれば、当然ゲームが成り立たないので、
そういう行為を行う人を排除するシステムがルールと共に存在する。それが審判制度である。ゴルフの
ように、自己審判のものもあるけれど、一人で競技をするわけではないので、実際には相互監視が働い
いていると考えてよい。
で、何が言いたいかというと、仕事を行うときにつきまとう「会議」というやっかいな代物に対して、
審判制度を導入することを提唱したいのだ。
もっと端的に言うと「会議のルールを破る人」を排除したい。会議にはルールがある。暗黙知としての
ルールが。それを明文化して、誰もがわかる形にする。そして、それを守れない人は参加してはいけな
いことにする。途中だったら、レッドカードを出して退場させる。議論上の敵となる人を排除するので
はもちろんない。議論を正常に行うプラットホームを造るためのシステムである。
ルールブックの何番でもいい、今日のわたしはそこに「一度決まったことを蒸し返さない」「議題の前
提条件をちゃんと理解してくる」という二つを赤字で書き記したいと、心底思った。
以上をまとめると「会議が伸びたのでBKの追加練習には参加できませんでした」ということになるのだ
った。とほほ。
これから原稿やります。眠りたい。。。
(一時間経過)
冬コミ本進捗
表紙・裏表紙 100%
序章・中表紙 80%
4,5頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
6,7頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
8,9頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
10,11頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
12,13頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
14,15頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
16,17頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
18,19頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
20,21頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
22,23頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
全レイアウト終了。最後のは、かなりトリッキー?かもしれないけれど、他のページとの整合性は
一応とれているとは思う。苦労したー。昨日作成したページをあとがきと兼用にするという構想だ
ったけれど、今日作ったページだけが異質なレイアウトなので、こちらをやはり最後にもってくる
ことにする。文字数がもっとも多いページでもあるので。あとがきにつながる文章の流れも頭に浮
かんだことでもあるし。予定通り、明日からは文章フェーズに移行。
たぶん、あしたの朝はちゃんと起きられないと思う。。。
では、おやすみなさい。
- 2006/12/10(日)
BK練習、12:50-15:30。
BKミニコンサート@城陽文化、15:30-16:20。
BK練習、16:20-17:00。
実は、以外と練習時間が長かったということを、帰りの電車における疲労度で気づいた。
冬コミ本進捗
表紙・裏表紙 100%
序章・中表紙 80%
4,5頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
6,7頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
8,9頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
10,11頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
12,13頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
14,15頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
16,17頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
18,19頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
20,21頁 0%
22,23頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
えっと、昨日の進捗には間違いがあって、残りは2つだったのだ。帰宅後、そのうちの一つを作成し
たので、これでやっと残り一つ。今日作成したものは、ラストに持ってきて、あとがきを兼ねるとい
う構想が浮かぶ。これ以外のページの並びはまだ決めていなかったりする。
明日は仕事で帰宅が遅くなりそうなのだけれど、残り一つを完成させて文章フェーズに入りたい。
つまり、またMacBookを持って喫茶店にこもるということデス。いや、案外気に入っているのだ、そ
のスタイルは。次の日の午前中の集中力が、やや犠牲になるのだけれど、ランナーズハイの文章版と
いうべき「ライターズハイ」感覚が途中から確実に起こってくるからだ。適度に歯止めをかけないと、
予定文章量をオーバーするくらい(それをあとで削る作業では当然ながらハイにはならない)。
別にハイになりたいのではなくて、文章が紡がれているときの加速感というのは、わたしは本を作って
いるんだ!という実感につながるからだと思う。一週間まるまる時間が空いていて、仕事もしなくてい
いから、原稿を作れ、っていう状態があってもたぶんできない。限られた時間、もう寝たい、今日はこ
こまででいいやっていうあきらめ、そんなものを克服することが、面白くて楽しんでいる、そんな気が
する。Mなんだと思う、同人作家というものは。女性編集者に怒られたいとか、そういうのではない。
共に作業をする編集者がいるならば、その人も一緒に楽しんで欲しいし、苦労も(ちょっとだけでも)
分かち合いたいって思う。
- 2006/12/9(土)
NC練習休みの日。終日、冬コミ原稿作業。
冬コミ本進捗
表紙・裏表紙 100%
序章・中表紙 80%
4,5頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
6,7頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
8,9頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
10,11頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
12,13頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
14,15頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
16,17頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
18,19頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
20,21頁 0%
22,23頁 0%
レイアウトを行うのと同時に各章のタイトルのみ決定する。作業中、タイトルを基にした文章が頭の中
で練り上げられていく。前から書こうと思っていたこと、何を書こうか迷っていたこと、それがすべて
タイトルという10文字にも満たないセンテンスによって一つの流れとなり、整理されていく。タイトル
一つが、本文と同じくらい重要な意味を持つことを知る。
あと、1章分だけなんだけれども、これが一番手強い。もう2:44だ。やりはじめると4:00近くになる。
今日のところは、これで終了。あしたは忙しいから、もう寝る。
そっけない日記で申し訳ない。お休みなさい。
- 2006/12/8(金)
今朝見た夢は興味深かった。BKメンバーのKさんと、NCメンバーのMさん、そしてわたしの3人が何かの曲
のソロをつとめるということで、指揮をする友人を加えた4人で練習をしているのである。なぜか屋外の
ようだ。Kさんが歌い終わったあと、即座に私が入らないといけないのだが、何度やっても入りがうまく
できずにつまってしまい、「んもー!」と友人に怒られてしまうのだった。それにしても、なぜこのメン
バーなのか。MさんがいなければBKつながりなのでまだわかるけれど。Mさんは同じ会社で、仕事も近い
からかも知れぬ。Mさんの仕事はいま大変な修羅場にあるので、それが頭に残っていたのかも。
BK練習、18:40-21:00。
宴会には出ず、帰る。たまっていた団費を2年分払ったらすってんてんになってしまったからだ。まぁ、本
づくりに集中しないといけないから、というのが本当の理由。
帰宅途中、寺町御池のメガネ屋のショーウィンドーにみなれたロゴをみつける。わたしが今日していた
ネクタイのブランドだ。サルバトーレ・フェラガモの眼鏡フレームなんてあるんだ。。。知らなかった。
冬コミ本進捗
表紙・裏表紙 100%
序章・中表紙 80%
4,5頁 50%(写真・文章レイアウト決定)
6,7頁 0%
8,9頁 0%
10,11頁 0%
12,13頁 0%
14,15頁 0%
16,17頁 0%
18,19頁 0%
20,21頁 0%
22,23頁 0%
はやめに帰宅したものの、やっぱりレイアウト作業は難しい。文章を書くほうが楽かもしれないなぁ。
かなり疲れた。きょう、もう一つやっておきたかったけれど、もう限界。明日はピッチをあげてかから
ないと、日曜日は作業時間の捻出が難しいからなぁ。
- 2006/12/7(木)
仕事帰りに京都駅前の近鉄にあるソフマップでプリンタを購入。HPのPSC1510というオールインプリンタ。
プリント+スキャナー+コピー機能が入っているというのに、最近ではこれがスタンダードモデルらしい。
それでその価格が非常にびっくりしたのだが、9870円!13年前にはじめてモノクロのインクジェットを買っ
たときは確か29800円。6年ほど前に買った同じHPのカラープリンタ(もちろんプリント機能のみ)も25000円
くらいはしていたように思う。すごいなものだと言うよりほかない。
それで、この買い物にはつっこみどころがあると思う。自分でばらすと「なんでHPなの?」っていう疑問だ。
エプソンかキャノンではなくて、あえてHPを選んでいるのは「普通紙への印刷がきれい」だという理由。
これは6年前も今も変わらないHPのポリシーみたいなものだ。店頭で印刷見本としておいてあるものは、たい
がいフォト専用用紙などの専用紙に印刷したものだけれど、HPはあえてそれはやらずに普通紙に印刷したも
の使っていた(すべての店でそうだったかはわからないけど)。専用紙は値が張る。普段印刷に使うのは圧
倒的に普通紙だ。ならば普通紙の品質を見せるのが良いはずだ、ということだろう。私はこの考えに賛同し
たから、以前もそして今回もHPを選んだのだ。
だから、マニュアルに誤字があったり、付属ソフトの使い方やインストールの段取りがそこはかとなくわかり
にくいってことも許せる。あ、今回はじめてきづいたのだけれどマニュアルの紙が日本にはないタイプの紙だ
った。その紙は、HPがかつて発売していた携帯コンピュータHP100LXのマニュアルの紙と同じ手触り、独特の
同じ匂いだったので、非常になつかしさを感じた。
きのう買ったユリイカ、読んでいないときは常に裏表紙を向けてしまう。そこには全面に白黒の女性のポート
レイトを使った広告が載っているのだけれど、この写真がとにかくいいのだ。魅力的という単純なものではな
く、ほのかなエロス?というべきものを感じるから。誘われるというのではなく、ひきこまれる眼差しと口唇と
胸元。なんか、いいです。というわけで、買ったばかりのプリンタで早速コピーを取った次第。。。
冬コミ本進捗
表紙・裏表紙 100%
序章・中表紙 80%(文字フォーマット決定)
4,5頁 0%
6,7頁 0%
8,9頁 0%
10,11頁 0%
12,13頁 0%
14,15頁 0%
16,17頁 0%
18,19頁 0%
20,21頁 0%
22,23頁 0%
印刷を繰り返して、実サイズでの文字の見え方がわかった。これまで小さすぎて実用でないと思っていた
9ptの文字が、送り幅を十分とってやることで、非常に読みやすくなることに気づかされた。すべては相対
的な価値判断なのだ。
- 2006/12/6(水)
今日買った本
「ユリイカ」2006年6月号、特集Nintendo。1300円。
正確に言うならばこの本は、本屋で買ったのではなく、本屋から買ったのである。会社の技術発表会が
毎年この時期にあるののだけれど、いくつかの書店が出張してきて学術書などを売るのである。では、
なぜ「ユリイカ」かというと、今年の招待講演が任天堂の岩田聡社長だったからだ。とにかく、書店は
毎年、招待講演や特別講演に関係のある書籍を並べるのであるが、まさかユリイカの特集まで見つけだ
してくるとは驚きである。正直脱帽した。技術者ばかりの発表会で、ユリイカのような詩と批評の雑誌
が売れるのか?という疑問はあるけれど、まあ現にここに最低一人はいたのだから目論みは当たってい
るということになる。じつは岩田社長の講演は昨日であり、講演そのものは聞けていない。非常に残念
である。例年二日行われるうち、どちらか一日しか出張できないのでやむをえない。
単にそれを補完するために買ったのではなくて、表紙に「鼎談:ブルボン小林、」という文字が見えた
からだったりする。ブルボン小林とは、作家長嶋有がゲーム批評やエッセイを書くときのペンネームな
のである。ブルボン小林のゲームに対するまなざしは鋭い。そして面白い。というわけでそれだけで買
うことにした。事実、今日の講演が始まるまで椅子に座って読んでいたのだが、すくなくとも2回くら
い吹き出して笑ってしまった。彼の文章を周りに人がたくさんいるところで読むのは危険である。
鼎談以外の論説を一部だけ帰りの電車で読んだが(澤野雅樹「DSの思想」)、じつに秀逸だった。
こういう文章、批評文を読んだとき感じるのは、ただひたすらの文章快楽、愉悦であり、安寧感であ
る。そう、心落ち着くのだ。
BK追加練習、19:00-21:00参加。
すぐに帰宅するつもりでタクシーに乗ろうと思ったら、1000円しかなかったので徒歩にスイッチ。
冬コミ本進捗
表紙・裏表紙 100%
序章・中表紙 75%
4,5頁 0%
6,7頁 0%
8,9頁 0%
10,11頁 0%
12,13頁 0%
14,15頁 0%
16,17頁 0%
18,19頁 0%
20,21頁 0%
22,23頁 0%
序章部分の文字フォーマットと、中表紙を作成。文字の大きさは実際に印刷してみないと感覚がつかめ
ないので難しい。最近はそれほど高いものではないし、あしたプリンターを買ってこようかと思う。必要
な投資は惜しみなく行わないといけない。機会損失と比べて十分安いと判断されるならば。
- 2006/12/5(火)
仕事後、歯医者へ。前回の治療の際に結局神経を抜いてしまったので、きょうはその穴に代わりのもの?を
詰める作業だった。治療後は、仮の「ふた」をつけるのだけれど、今日はしばらく痛むというか、じんじん
とした違和感が続いて何か噛んだりするのがちょっとおっくうになってしまった。というわけで、夕飯は大
正軒でラーメン。次週はようやく欠けた部分を整形するための型どり。治療の峠は越えたので、ちょっと安心。
何度も書くようだけれど、ここの歯医者は当たりだったなぁ。「次回も来ないと」って思う歯医者って、な
かなかないのでは?それも歯医者嫌いだった人間にそう思わせてしまうくらいの(別に先生や助手の人が
美人だからとかそういう理由ではない)。
冬コミ本作成の前に、ちょっとだけMacでゲームをやる。”QUAKE4”というプレーヤー視点の3Dアクション
ゲーム。銃を撃って撃ってうちまくって、せまりくる敵のエイリアンを倒しつつ、様々なミッションをこなし
ていくもので、シリーズ4作目。1~3はWindowsマシンでやっていたのだけれど、4では格段に敵エイリアン
の動きがナチュラルで、まるで人が操っているかのよう。なもんで、単純にまっすぐ撃つだけでは簡単によけ
られてしまう。ストレス発散のつもりが、ちょっといらいらさせられる。けれど、こちらにもPCが操る仲間
がいるので、彼らと協力してより戦術的な楽しみかたができるので、ゲームとしての面白みは増している。
で、きょうやったシーンは、浮遊戦車に乗って空中の的を迎撃する任務。「浮遊」してるもんだから、逆道
なんかでは車体がなめらかに傾く。それはもう酔ってくれといわんばかりに。前作までの3D視点では酔っ
たことは皆無なんだけれど、今回はちょっと注意が必要かも。っていうか、みごとに酔ったので30分ほど休
んでから、本づくりを開始した。
興味のある人に情報。QUAKE4は初代MacBook(2.0GHz,メモリ2.0GHz)のパワーでも、最低解像度ならな
んとかゲームになります。でも人によって感覚は違うと思うので、試用版をダウンロードして自分で確かめ
てください。その際、v1.3のパッチをあてないと音が出ません。それから重要なこと。このゲームは日本で
はMac版は現在、発売されていません。なので、輸入ゲーム専門店か、ネットで海外から直接買うしかあり
ません。わたしは、東京の友人がたまたま銀座のアップルストアにあったのを見つけてくれて、入手できま
したが。もちろん、英語版です(そもそも日本語版はなし)。簡単な英語ばっかりなので、ミッションの内
容はわかります。兵士達がしゃべっている会話なんかは、さっぱりですが。会話にヒントとかがあるゲーム
ではないので、問題なし(もしあったら困る。。。)。
冬コミ本進捗
表紙・裏表紙 100%
序章・中表紙 0%
4,5頁 0%
6,7頁 0%
8,9頁 0%
10,11頁 0%
12,13頁 0%
14,15頁 0%
16,17頁 0%
18,19頁 0%
20,21頁 0%
22,23頁 0%
- 2006/12/4(月)
冬コミ本製作要項を検討。
体裁:A5判、中綴じ24頁、フルカラー。
スケジュール:
4-10、レイアウト・本文。
11-17、本文、文章校正。
18-21、文章校正・直し、仕上げ。
22、入稿。
26、印刷完了。
30、冬コミ二日目にて頒布。
本の判型を決めるのに結構悩んで、手近な建築本などを手にとって参考にする。一番重視したいのは、手になじむか
ということ。読み物なので、電車のなかとかで読めるサイズがいいと思った。そこからA5に決定。つぎにスケジュー
ル作成。印刷屋の最終締め切りをHPで確認。若干、余裕を持たせてみるけどぎりぎり。最後に、レイアウト原図?
(全頁のイメージを見開きでラフに書いてみる)を作成。。。のはずが、枠組みを書いたところで、猛烈に眠たくな
ってきた。ということで、続きは明日にします。各頁ごとにフォーマットを統一するのか、レイアウトを変えるのか
については、未だに悩み中。文字のサイズと、送り幅だけは今回そろえようとは思っているのだけど。
- 2006/12/3(日)
熊本土産(賞味期限間近!)を届けるために小一時間ほど実家へ。その後、取って返して撮影の続きへ。先月25日に
オープンしたばかりの京都国際マンガミュージアムに向かう。ここは以前紹介した龍池小学校を改修したものなのだ。
塗装を旧毎日新聞社ビルのような暖色系の茶色に塗り直した姿が、とてもしっくりきている。「新しい古さ」のよう
な感覚。建物以外で、際だっていたのはかつてのグラウンド。ここに新たな施設を建てることはせず、グラウンドの
まま、ただし全面芝生に改良されていた。かつての小学校時代のように、来館した子供達がおおはしゃぎで遊んでい
る姿を見ると、この地域にひさしく途絶えていた「活力」を見るようで、ちょっと気分がよかった。あ、本のネタっ
ぽいこと書いてますな。この部分もし、かぶってしまったら許してください。
時間がなかったので入館はせず、後日改めて来ることにする。帰り道に、あっと気づく。グラウンドの隅にたってい
た「二条殿交番」が全面改修されて、モダンな姿になっているじゃないか。ミュージアムの色合いと、とてもあって
いる。あってはいるんだけれど、かつての交番はなかなかしぶい近代建築だったのだ。。。確か、写真は撮っていた
はずだけど。。。。ちょっと、残念。
つづいて室町通りにある京都芸術センター、旧明倫小学校へ。何度も撮影しているけれど、何度でも訪れたくなる
建物なのだ。本当に小学校だったのかっていうくらい、こりにこった意匠があちこちに。これは、写真のセレクト
に迷うこと必至だわ(今回はエッセイ主体なので、ひとつの章の枚数は抑えるのだ)。マンガミュージアムを楽しめ
るくらいの時間をすごしてしまった。でも、向こうはたぶん内部撮影はできないだろうからなぁ。
帰宅後、MacのApertureで写真整理。Photoshopよりも、こっちのほうがもしかしたら使い易いかもしれない。
例によってApertureは30日のトライアル版。ちょっと製品版が欲しくなってきた。
16:30-17:30、自宅にてBKの曲復習。
18:00-21:00、BK追加練習。
昨日のNCでの腹筋・背筋トレーニングがきつかったかも。いきなりだったから、もろに筋肉痛になってしまった。
声が出せないってほどじゃないけれど。歌い方を整理する。バリトンにもうちょっと厚みをくわえて、ベースが
安定すればよくなるかも。しかし、わたしはベースの下なのに、しっかりした声が出せない。。。NCのときのよ
うに上にいった方がいいのかな。。。でも、人数比とかもろもろ考えると頑張るしかない。頑張ろう。頑張れ。
飲み会(?)には出ず、すぐに帰宅。
- 2006/12/2(土)
午後から烏丸今出川の同志社今出川キャンパスの近代建築を撮影。今回はGRDigitalだけでなく、友人に借りた
LUMIX DMC-FZ7を投入。GRDigtalは単焦点28mmの広角レンズなので建物の全景をとらえるのには適しているの
だけれど、写真を構成したとき広角ばかりだと誌面が単調になる可能性がある。このことは前回の本のときに、
TAM氏に指摘されていたことだった。画角が組み合わさることで、誌面に張りが生まれる。で、望遠ならばLUMIX
LC5にもついているが、3倍である。今回のターゲットはこれでは足りないのだ。で、FZ7はどうかというと、12倍!
しかも手ぶれ補正つき。
今日、撮影してみてわかったのはFZ7というカメラの使いやすさだった。本体は小さいのに、すごくホールドし易
い。なので、そもそも手ぶれ補正がなくてもぶれる機会が少なくなっていた。それからレスポンスが小気味よくて、
撮りたい瞬間に撮れる。建築写真のような固定写真よりも、街中のスナップに使いたいなぁと思わせるものがある。
じつはGRDigitalの液晶よりも発色がよいのも、確認し易くて好みであった(モニター上での絵はまだ確認してい
ない)。
約1時間かけて撮影。同時に頭のなかで、エッセイの文章が練られはじめていた。やっぱり現場での印象というの
はとても大事である。書くことがないかも...と心配していた建物でも、撮っていくうちに様々な意匠や、ポイント
となる部分が浮かびあがってきたからだ。
ところで今回もっとも12倍ズームを活用したかった建物は、現在改修工事中であった。すっぽりと覆いがかぶせら
れていて、キャンパスに入った瞬間わかったものだかから、がっかり。工事は2003年に始まったというから、在学
中に一度もその姿を目にすることなく卒業していく学生がいるわけで、それはちょっとどころかかなり可哀想なこ
とだと思った。このキャンパスのシンボルだというのに。似た経験は、わたしも中学のときにあるのだけれど、本
のネタに使いたいので、ここでは書かないでおく。ごめんなさい。
12倍の活用はできなかったけれど、望遠を使うことができるのは、撮影自体にもリズムが出て、とても助かった。
快く貸してくれた友人に感謝。ありがとう。
撮影後、馴染みの時計屋にいく。そこでとても面白いものを見せて貰う。時計のオーバーホール報告書だ。スイス
にあるIWCという会社は、名門中の名門だが、その名門たる所以は高い技術力もさることながら、徹底した顧客対
応にあることで有名なのだ。それは、過去に販売した時計、一台一台すべてが台帳に記録されているということ。
この台帳をもとに、どれだけ古い時計でも永久に修理可能となっている...というのはすべて時計の事情通ならば
誰でも知っていることなのだが、今日初めてそのことを実感した。
みせてもらったIWCオーバーホール報告書には、時計のシリアル、担当者のサイン、完了日「Nov.6/2006」のほか
に、「AUG.15/1952」「Shriro、TOKYO」が記載されていた。前者は販売日、後者は販売先である。今から50年前
の日付だ!販売先となっているShriroとは当時のIWCの日本代理店であり、その時計のオーナーの記憶とも、きちん
と符号がとれていると、店主が教えてくれた。PCもない時代だから、紙の台帳なのだ。戦後間もない時期、極東の敗
戦国にやってきた1本の時計まできちんと記録されていて、それが今現在でも参照できる。顧客主義を掲げる企業は
日本に、世界に数多くあれど、IWCのこの徹底ぶりを目にして、その主義を掲げて恥じずにいられるだろうかと思う。
かくのごとく、時計の世界は面白くて深いのデス。
(ROLEXや、OMEGAだけがスイス時計じゃないのだ!)。
NC練習、17:00-21:00。15分ほど、腹筋、背筋のトレーニング。もへ、結構きつい。ブレスは入るようになった
けれど、音程までよくなるわけではないのだった。そんな都合のいいトレーニングはないよねぇ。全8曲の音取り
終了。あとは個人練習。集中力を使うので、かなり疲れた。
- 2006/12/1(金)
ああ、師走だ。ほんとに早いな。
今朝の夢は、6x6判サイズの用紙が20cmほど積み重なっていて、それがすべて試験問題になっているのを、
必死で解かないといけないというもの。回答は4択くらいなのだが、回答用紙が別でそれも一問題ごとに別の
紙に書かないといけない。おまけにそれが3cmx3cmくらいの小ささ。もちろん、夢のなかのわたしはいらいら
しっぱなし。あと10分しかないのに、4分の1くらいしかできていない。TOEICみたいなもので、全問解くこ
とは不可能に近いのかもしれない。途中、これは後ろからやればブレークスルーがあるかも、って思ってぱら
ぱらめくってみると「聞き取り問題」なんてのがあって、放送を聞かないと答えられないものばかりだった。
そんな放送いつやってたんだよーと泣きたくなる。
そのうち、締め切りがやってきて、途中から何かに追われるように逃げ出すわたし、ほかの回答者たち。どう
も本当に何かが追ってくるみたいで、逃げながら回答を解答用紙に書き散らしては、途中でどんどん放りなげ
ていく...そんなところで夢は終わった。
6x6判が出てきたのは「ハッセルブラッド紀行」を読んでるからだと思うけど、試験はどこから来たのか?
BK練習、18:30-21:00。ちょっとだけ、むなしくなる瞬間。僕がローテーションブレスしてる間くらいは、
響きのある声で、フォルテで、ピアノで歌って欲しい。みんなの声が聞こえない。前向きに考えて落ち込ま
ないようにするのにも限度がある。
BK宴会、21:15-24:30。きょうは、あまりしゃべらなかった。どうしてだろう。
さあ、明日から頑張って冬コミ本を作るのだ。えいえいおー。
- 2006/11/30(木)
今朝の夢は、大学か企業の研究室っぽいところが舞台。いつもははしごで二階に登るのだが、なぜか封鎖されて
いて、しかたなくエレベーターで上るという出だし。途中、退職した元上司の部長が登場したので肝を冷やした。
「サマー/タイム/トラベラー」読了。この作品は、そこら中にSFの要素と、新旧のSF作品への傾倒が見られる
ので、SF好きでないひとにはちょっと敷居が高いというか、読みづらい部分があるかもしれない。それらをよけ
てみてみれば、これは間違いなく「ありきたりの青春小説」(帯の惹句より)だった。ネタバレのないなかで、
印象に残った言葉をふたつだけ引用。
「手の届く最良のものをつかまえて、そいつと共に歳をとれ。」
「愛するものを手にいれて、そいつといっしょに歳をとれ。」
それはモールトン(自転車)であったり、IWC(時計)であったり、ハッセル(カメラ)であったり、あるいは
また「誰か」であったりするのかもしれない。
SF読みは基本的にロマンチストなんだ。
今日のBGM
・「フタリ」、MONKEY MAJIK。AVEX。
映画「夜のピクニック」主題歌。ラフな平井堅という印象の声だけど、じつはカナダ人だった!びっくり。
日本語ネイティブにしか聞こえない。今現在の標準的な日本語は、外国人によってしか保存されないのでは
ないか?という逆説的な考えが頭に浮かぶ。
・「小さな星」、奥華子。PONY CANYON。
映画「時をかける少女」主題歌の「ガーネット」が記憶に新しいどころか、いまでもくりかえし聞いている
ところに新曲リリース!この人は本当にどこから声が出ているんだろうか。メルヘンな声に、純情な歌詞が
えらく似合っていて、聞いていてちょっと照れる。でも心をうつ、何か。
- 2006/11/29(水)
今朝の夢はわりと不思議なシチューエーションのもの多し。夢のなかで、「あ、この光景は二回目だ」って思って
いるのに、起きてから考えると初めて見る状況のものがあった。わりと、同じパターンの夢を見る方なのだけど、
こういうタイプは珍しいな。
夜、友人と私的なコンクールお疲れ様会。焼酎には黒と白とあることを知る。「黒って何?」って聞くまえに、
「黒麹と、白麹ってのがあるねん」と先回りして答えられたので驚く。「聞くと思ったから」だそうです。わた
しはそんなにわかりやすいのか、友人が鋭いのか。締めはうどん。よく考えると、こういうノーマルな「おあげ、
きぬさや」のうどんを食べるのはすごく久しぶりだ。実家にいるころは、土曜日の昼などに店屋物でよくとって
いたけれど、マンションにうつってからはそういうことがなくなったから。ラーメンは毎日食べられないけれど、
きつねうどんならOKな私である。
熊本から帰ってきてもう三日。ようやく、ほっこりできた気がする。感謝。
どうでしょうを見て、ひと笑いしてから眠りまする。
- 2006/11/28(火)
今朝は一転、あまりよろしくない夢で目を覚ます。
「喜びと悲しみは隣合わせ、愛と憎しみは背中合わせ」("長崎BREEZE"よりbyさだまさし)みたいなものだろうか??
実家用に買ってきた熊本土産の包装を気になってみてみる。”常温5日、冷蔵10日”の文字が!あわてて、冷蔵庫に入
れた。ふー、つぎに実家に行けるのは週末なのであぶないところだった。急に気になったのは、熊本で練習場を借りた
ときにお世話になった方々へ、おみやげを持って行ったときに同じようなことがあったからだ。VineとNCで同じとこ
ろを借りたのだが、練習はVineの方が先。なので、Vineのメンバーである友人にNCの分のおみやげを先に渡して貰うよ
うにお願いしていた。ところが、先方は練習が始まるやすぐに帰宅されたらしく、渡すことがままならず。別のひとに
託そうとしたところ、賞味期限は4日しかなく、これも断念となった。ところが、わたしが翌日の練習場用に用意した
お土産は友人が選んだものと同じものだったのに、なんと賞味期限は10日もあったのだ。で、結局後で合流したときに
交換して、なんとかお土産を託すことができたのだった。同じものとはいえ、箱の大きさなどは違ったので、種類が違う
のだと思うけれど、根本的に違いようがない。なぜなら、お土産は「生八つ橋」。倍以上差があったのはいまでも不思議。
そういえば、あしたは創立記念日(何の?)。
早天祈祷会行こうかなぁ(絶対無理なので却下)。
- 2006/11/27(月)
朝、「寸止め」ぎみではあったが、とても幸せな夢で目を覚ます。内容は秘密だ。
もとよりそういうつもりではなかったのだが、仕事を休ませてもらった。帰宅してほっと一息つくと気が抜けたのか、
想像以上に疲れていることがわかったからだ。はじめから休みをとって、表彰式も見て、宴会にも出て、たぶん空きの
ある良いホテルに泊まって寛いで、ゆっくり帰ってくればよかったのじゃないの?と思うかもしれないけれど、演奏後
から打ち上げまでというのは正直しんどい時間帯だし、打ち上げもそれなりに気を遣う(出ていれば確実に会計を担当
することになるから気が抜けない)。演奏のあとは、友人と少し会話をして、それからささやかな夕飯を食べて、夜道
を歩いてホテルに帰り、本を読み、眠くなってきたら眠るという時間がいちばん欲しい。みっちりの団体行動の反動か
もしれない。ひとりか、二人、三人くらいまでの単位がいい。でも、熊本に残っているとたぶんそれは難しいし、たと
え行動したとしても、物理的に近いところで団体行動が行われているというのは心理的には負担である。だから、京都
に帰ったのだと思う。
だけど、帰ってきてからひとつだけ後悔した。馬刺しを食べるのを忘れていたからだ。九州に到着してからの食事を思
い返すと、じつはまともな食事を摂っていなかった。まったく無意識だった。
25日:(早朝)船内にてパン二種類、カップヌードル。(朝)九州横断特急車中にてコンビニおむすび2ヶ。(昼)
MOSバーガーにて、バーガーとオニポテセット(←じつは大好き)。(夕)のど飴。(夜)コンビニのカツ重。
26日:(朝)コンビニおむすび2ヶ。(昼)弁当(わりと豪華だった)。(夕)MOSバーガーにて、同メニュー。
こうやって列挙してみると、学生のときの貧乏旅行となんら変わらない。いい大人がまったくもう!
で、きょうは夕食だけは、近所の定食屋で、いつもよりちょっとだけ高いのを食べた。われながら安くできている。
疲れているから食欲がなかったので仕方ない。食事のかわりに、誕生週らしく気分だけは豪勢にと1万円を財布にい
れて買い物にでかけた(熊本ではお金を使っていないので。)
今日買ったDVD
・「TOPをねらえ2!」2、3巻。バンダイビジュアル。(ともに中古品)ふたつで6000円弱。
何か映画でも買おうかなと思ったが「買ってまで見たい映画」は今のところ「時をかける少女」くらいしかなく
て、いまだに全国各地で規模は小さいながらも上映が続いている状態では、まだ当分先。で、1巻以来見る機会
を逃していた本作を購入。
今日買った本
・「ハッセルブラッド紀行」、田中長徳著、えい出版社刊。1500円。
ハッセルブラッドというのは6x6判という正方形のフォーマットのフィルムを使用する、スウェーデン製のカメラ
である。現行機種もちゃんと存在するものの、40年近く前の機種が現役で使われているという、そう一般の人にも
有名な「ライカ」に匹敵するか、あるいはそれ以上の「高級精密ブランドカメラ」である。口絵の写真をみてもわ
かるのだが、そこから生み出される写真以前に、工業製品として完成されたともいうべきフォルムを、このカメラ
はもっている。もうそれだけでほれぼれしてしまう。つぎに買うとしたら、このカメラだと決めている。田中長徳
氏のいつもながらの哲学的語り口の文章に加えて、京都で撮影した(氏はよく京都に滞在する)作品が収められて
いる。
・「藤森照信の原・現代住宅再見3」、藤森照信著、下村純一撮影、TOTO出版刊。2400円。
シリーズ第三集。「住宅の射程」のテーマとかぶっているけれど、「建築家」のつくる住宅とはなんなのか?とい
うことを建築家や、住み手への取材を通じて明らかにしていく。そうは見えないが、じつは歴史書である。著者が
建築史家であるから当然なのかもしれないが、ぱっと見ただけでは「なんだ、ちょっと変わった住宅の紹介本」か
と思われてしまう危険性がある。それはとても残念なので、店頭でみかけることがあったら、ちょっと立ち読みし
てみて欲しい。
しめて、約1万円。われながら計算ぴったり!それにしても、わたしには食事よりも、本を優先させる傾向があると
いうことが、改めてよくわかった(書店の引力には逆らえないし、逆らうのはかえって健康によくない)。
- 2006/11/26(日)
全国合唱コンクール第二日目@熊本県立劇場。
11/26追記
いろいろあるかもしれないけれど、全国大会という場で、ほかの団とは違った表現はできたと思うし、お客さん
にも伝わった感はある。音楽的な評価はどうだったかはわからない。ただ、音楽に対するどん欲な取り組み、と
いう点では足りない部分があったのは否めない。いまは、悲観的でも、自虐的でもないつもり。演奏をすること
自体は楽しかった。この80人の仲間といつも一緒に練習ができればいいのに、とだけ思った。もっと面白い音楽
がそれこそ毎週できるだろうから。この想像は楽しくて、でもちょっと切ない。われわれは社会人合唱団だから。
- 2006/11/25(土)
全国合唱コンクール第一日目@熊本県立劇場。
誕生日。
11/26追記
誕生日を祝ってくれる誰かがいることは、それだけでとても幸福なことだと思った。
フェリーであっけなく寝てしまったため、オーダーができていない。熊本入りしてすぐにホテルに荷物を預けて
から、ホテルの一階にあるモスバーガーで検討。前日だというのに参加メンバーが確定していないので、電話で
いろいろたずねる。最終的には予想で作成。いつもながら難しい。作成後、練習場へ。
練習そのものよりも、一日中、マネージのことばかり考えていたためそちらで疲れた。個人的には、練習の密度が
いつもに比べて薄まっているように感じられた日だった。必死さ?みたいなものの欠如かなぁ。
- 2006/11/24(金)
熊本に向けて、大阪南港より出発。
11/26追記
乗船手続き中、NCとVineのメンバーに会う。同じフェリー。彼らは車。到着後、別府駅まで乗せてもらうことに。
フェリーの旅の良さを再認識。ただ、パブリックスペースがもっと欲しいなと思う。まぁ、翌朝6:30着だと、
すぐ寝ないといけないし、こういう構造は仕方ないのかも。(さらに追記予定)
- 2006/11/23(木)
雨が降りそうなので中止かな?と思っていたのだけれど、幸いにも雨が降らなかったため、自転車仲間のみんなと、
大原に紅葉ツアーに行ってきた(17人参加)。主催者がBD-1ユーザーのためか、17台中14台がBD-1で、モールトン
は3台のみ。これはこれで珍しいかもしれない。途中、満員の京都バスのお客さんの注目をかなり集めていたと思う。
いや、しかし今回はじめて大原、三千院への参道へ行ったのだけれど、ほんとにすごい人だ。そして、これぞ観光地
という商魂ありありの沿道の店。そういう光景に少々、くらくら来たのだけれど、まぁ本当に美しい紅葉が見れたの
でよしとするか。昼食を終えたころ14時にみんなから別れて帰途についた。ここまではずっと登りだったので、帰り
はびゅんびゅん。道が狭いのと、砂利や木の枝が多かったのでかなり怖かった。ヘルメット持って行くべきだったな。
1時間ほどで自宅に着く。
今回、唯一困ったのがフロントの変速。登りでインナーギア(ギアが軽い)を使ったあと、平地でスピードを出す段
になってアウター側にチェンジしないのだ。変速のケーブルの張りの調整がどうも狂ってしまったらしい。止まって、
変速できるように調整をしても、走っているときに変速できなくなってしまう。実は鈴鹿のレース中からこの現象は
出ていたのだけれど、レース後駅に向かう途中では回復していた。輪行の際にケーブルを分割してしまったことで、
いったん直ったものがリセットされた様子。来週か、明日出発する前にMoku2+4(自転車屋さん)で本格的に調整し
なおして貰わないといけない。
小休止の後、大阪へ。17:30-20:40、NC練習。
本番は80人なのに、きょうは20人。当日練習になって、この状態が、がらっと変わってしまうかと思うと、怖くも
あり、楽しみでもあり、複雑な気分になる。どちらかというと、大きく覆されてしまう(ベースは特に)ので、そ
れが毎回ストレスだ。いつも、本番に近い状態で練習ができればいいのだけれど、NCに限ってはそれは無理な相談
ということになるのだろうか。毎回練習に出ていたのは、なんだったのかって、ふとしたときに思わないでもない。
ぼやいていても仕方がないのだけれど。
ともかく、頑張ります。
いい気持ちで、すがすがしい気持ちで、熊本から帰ってきたいな。
- 2006/11/22(水)
スタンドで夕食。帰宅後、冬の本について構想を考える。予告では「東西四大学」ということで、東京、関西の
大学建築を取り上げるつもりだったのだが、エッセイ形式に変えるにあたり、取材や再訪のしやすさを考えて、
企画を変更することにした。前々回の京都断章の続編の位置づけで、京都学校建築(タイトル未定)がテーマ。
烏丸今出川にある母校をメインに、8~10の建物を取り上げるつもりでいくつかをリストアップ。すごいなぁ、
こうやって並べてみると重文か登録文化財のオンパレードだわ。2~3の建物については思い出深いエピソード
もあるので書きやすいだろうが、ほかは建築の印象だけで語らないといけない。母校の建物にしても、デジカメ
を買ってからは撮りにいったことがないのでじつはソース自体がない。ということで撮影に行きたいのだけれど、
明日、明後日は天気がよくなさそうだし、コンクール明けは大学の学園祭で建物の写真を撮るような状態ではな
くなってしまう。12月までお預けになりそう。ともかく、11月のうちにソースのあるものは文章考えておかない
と、今回もまたぎりぎりになっちゃうなぁ。
明日は、コンクール前関西での最終練習。あ、そうそう、船のなかで本を読むまえにオーダー考えないといけな
かった!思い出してよかった。まぁ、大概は現地で臨機応変に変わるのだけれど、初めて合流する人もいるわけ
だから立ち位置はびしっと決めておきたい。(全国コンクールに出る合唱団とはときどき思えなくなる。)
スケジュール、会計、弁当、移動、練習場所、宿泊、予算、衣装。。。。ほかにも考えないといけないことは
たくさんあったことに気づいた。あした頑張ろう。今日はゆっくりする。
最近、Wiiが欲しいなぁと思っている。大人の事情で、PS3が普及することはとても重要なのだけれど、それは
それとして、やっぱりあのWiiリモコンのインパクトは大きくて、ゲームをそんなにやらない私でもいいなって
思ってしまう。欲しいと思う一番の理由はBLEACHのゲームが出ること。BLEACHって知ってますか?ジャンプで
連載している死神が主人公の漫画なのだが、ジャンプらしく、そこはそれ、戦いにつぐ戦い。で、登場する
死神達の武器が日本刀。つまり、剣戟が中心になっている。ひとりひとりの刀に特長があるのがなかなか面白い
のだけど、それがWiiでゲームになる。これは、どういうことかというと、まさに「チャンバラ」をゲームでや
れるわけです。やー、とぅ、っぐぐぐ、えい、うおー卍解!とか、いう「なりきり」がうちで楽しめると。どこ
まで動きが追従するのかわからないけれど、これは是非とも体感したい。
ってなことを、BKのK岡に熱く語ったところ「その前にでっかいTV買ったら?」と言われてしまった。確かに13
インチの液晶では無理があるかも。いやいや、心意気ですよゲームは。どれだけ没入できるか、集中できるかは、
画面の大きさじゃない。このありあまる想像力で補えばいい。
うむ、しかし12/11に、Wiiなんか買ってしまったら(発売日には手に入らないかも)原稿は確実に落ちてしま
うような気がする。。。それはダメ。しばらくは我慢しよう。
- 2006/11/21(火)
今日買った本:
「サマー/タイム/トラベラー」1・2巻、新城カズマ著、ハヤカワ文庫JA。各660円。
会社近くの本屋で、熊本に持って行く文庫本を探した。久しぶりにSFが読みたかったので選択。決め手は、第37回
星雲賞(日本長編部門)受賞作だったこと。特にこれが読みたい!っていう本がないとき、やっぱり星雲賞はあて
になります。ちなみに今年の3月に紹介した「老ヴォールの惑星」は第37回の短編部門を受賞してました。ほえー。
もう一つの決め手は結構ミーハー。カバーイラストが鶴田謙二だったから。
ところで女性の人ってSFは読むんだろうか。ファンタジーは男女を問わないと思うのだけれど、SFってなると、
極端に男女比に差がつくような気がする。きょう、もう一冊買った本があって「鋼の錬金術師」15巻なんだけれど
これは女性に大人気なのだ。この漫画は、錬金術が使える国家錬金術師という人たちがいる世界が舞台の冒険活劇
なのだけれど、物語の根幹を成す錬金術については、話の筋上、一部に理論的な説明があるものの、根本的なとこ
ろでは、「そういう世界」というものが「設定」されているから存在しうるものだと思う。多くのファンタジーに
存在する魔法と同じで、「ある」と決められているものだ。これに対して、SFと呼ばれるものは同じように実在は
しないであろう超科学や、超常の現象が登場するけれども、その「設定」は一通りで説明されることはほとんどな
いと思う。幾重にも折り重なって、論理的に構築された「設定」なのだ。つまり、非常に乱暴なくくりをすると、
設定の単純さか、複雑さがファンタジーとSFを分けているのではないかと思う(作品の善し悪しとはむろん無関係)。
で、男性と女性というところに話をもっていくと、とかく男というものは小難しい設定や、論理構築を好むもので、
逆に女性は「現実的」なので、「非現実的」なものの設定は「単純な方がいい」と思うのではないだろうか。たか
だか空想のものに、そんなに大仰な理論を構えてどうするの?って思われているような気がする。やるんなら設定
は一個くらいにしなさいよ、そう魔法が使える!はい、設定おしまい、ってな感じで。
以上、わたしの推測でしかないので、そうでもないよーという女性はいるかもしれないし、読んでみたら良かった
って思う人もいるかもしれない。このあたりは、友人の意見を聞いてみたいと思う。
推薦するので、SF読んでみない?>私信。
- 2006/11/20(月)
11月も下旬に突入。文房具店やコンビニの店先で、年賀状の印刷受付が始まっているのを見かける。来年の干支は
「亥」であるけれど、これがまた難しいなぁ。年賀状のデザインを考えるとき、まず基調にするのはその干支の動物
だと思う。動物によっては既存のキャラクターがあって、イメージしやすい。犬ならスヌーピー、うさぎならミッフ
ィーとかね。ネズミだったら、世界一著作権にうるさい会社のシンボルキャラクターなどもそう。でも、イノシシっ
て古今東西、物語やアニメ、漫画の主人公になったことがあるのだろうかって思う。だから、絵をかけっていわれて
も簡単に描けないのだ。そうなると、あとは干支とは無関係のデザインでいくしかなくて、だから難しい。
とはいっても、去年などは結局、年賀状は書かなかったのだ。冬コミの準備(はじめてのオフセットだった)であた
ふたしていたし、BKの演奏会がわりと遅めだったので疲れ切っていた。今年もまずは演奏会ありき、冬コミありき、
なので年賀状に力を割けるかどうか、正直自信がない。年賀状をもらってうれしい、っていう感覚も最近ずいぶんと
薄れてしまったことも意欲がわかない理由。なのに、出すのならば、それなりのクオリティーのものを出したいとい
う自意識があるものだから、どうしてもハードルが高くなる。めんどくさがりなのに、凝り性っていうこの性分は、
ときにやっかいだ。
あ、さっきちょっとイメージ(干支以外)が浮かんだので、書く気になったらそれでいこう。なんのかんのいっても、
いったんデザインを始めると楽しいからなぁ。
熊本への交通手段を確定させる。行きは大阪南港からフェリーで、別府へ。そこから九州横断特急で熊本へ。大阪
南港を18:50に出て、熊本には翌日の11:21分着。ちょっとだけ「旅」とか「旅情」を感じさせるコース設定。
フェリーは二等寝台を予約。インターネットから予約すると2割引らしいが、そんな高率の割引でいいのか?
ただでさえ原油が高くなっているのに、とフェリー会社の行く末を気にしてしまう(時刻表を見ると2007年1月
の運行から、所要時間が10分延びており、航行速度を下げることで原油高に対応している様子)。
フェリーで行くからには、晴れて欲しい。陸地の明かりのない静かな瀬戸内海を煌々と照らす銀河を見上げたいのさ。
で、ついでに宿の方について再検討してみた。以前書いたけれど、わざわざ個人手配したのに、NCの団体予約と
同じ宿になってしまったのだ。それをNCのHさんに話したところ「直前になると旅行会社が押さえていた分が、
放出されるかも」というアドバイスをもらった。うーん、一理ある。で、先に予約につかった楽天トラベルを検索。
結果は。。。予約可能2件!前から大幅ダウン。しかも一番高いのと、一番安いのしか残ってないョ。うーむ、
各ホテルの直接予約を検索しても、空きは一件もない。予想外れか、もっともっと直前になればあるのかなぁ。
夕飯に、コンビニで売っていたカボチャのポタージュスープを飲む。カボチャそのものは、味とか、食感が好きに
なれず、「食べられないことはないが、あまり好きではなく、子供のころは食べなかった」野菜である。だが、ス
ープや、ケーキといったものに混入された形のものはOKなのだ。自分でも不思議に思っている。
あ、そうそう、左の顎関節の痛みは消えました。楽観療法の効果があったってことか。
(要、経過観察ではある。)
- 2006/11/19(日)
静養、というか雨に降りこめられていた。昨晩は、短時間にいろいろな夢を見たが、どれもあまり良い夢では
なかった。特に最後に見たやつなどは忘れてしまいたいのだけれど、そういう夢に限って鮮烈に記憶されてし
まうもののようだ。
午後から夜にかけて実家へ帰る。母からオーストラリアの様子を聞く。わたしの従兄弟(母の妹の息子)の
結婚式に親族代表として行っていたのである。海外挙式ではなく、従兄弟はアデレードの大学病院に勤めて
いる駆け出しの外科医で、現地在住なのである。香港とオーストラリアで育ち、日本に住んだことはない。
国籍も英国籍である。オーストラリアの人と結婚するのかと思ったら、留学生だった日本人の女性が相手ら
しい。こういうのを「捕まった」(母談)というのだろうか。
英語、広東語、日本語が入り混じるパーティだったが、関西のおばちゃん精神でなんとかなったものらしい。
あんたは英語がわかるから大丈夫やろ?などと母は言うが、わからなくてもなんとかなる!という開き直り
精神のある母の方が社交的には向いているような気がするのだが。わたしは気が弱い。
途中、いとこの嫁が冗談で「カナダに移住したい」などと言ったらしいのだが、それを叔母(いとこの母親)
が聞きとがめて「カナダなんかにいったら、才能が潰れる。外科の技術を磨くにはアメリカへ行きなさい!」な
どと言い返して、はやくも嫁姑争い(一方的?)があるようだ。「あんたんとこもそうなる」とは、叔母が母に
言った言葉だが、誠に遺憾ながらそういう予定が立ちそうもないので心配いらないと思う。
ところで、その嫁のことを母は「○○ちゃん」と呼んでいたので気になって尋ねてみると、わたしの友人と同じ
名前だった(なので愛称も同じ)。なんの前触れもなく呼ぶものだから、一瞬、母が友人のことを知っている
のか?と錯覚。よく考えれば会ったことはないし、まぁ、単なる偶然なんだけれど。私が想像してしまう人物
と違う人のことを、同じ呼び名で語られることの違和感はずっと続いた。なぜだか、落ち着かない気持ち。
アデレードは、京都のようなこじんまりした街だという。いとこがどこかへ移住してしまわないうちに、一度
訪ねてみたいと思うのだけど、実現するかなぁ。
夕食後、口を開けると左の顎関節が痛む...右奥歯をかばって食事をしているせいだと思いたいけれど、もし
顎関節症だったら、この時期かなり痛い。痛いどころじゃない。頑張ってやってきた結果がそうだったら、
救われない。とりあえず、楽観的になるように努める。明日になったら、治ってるさ。
- 2006/11/18(土)
NC練習、15:00-21:00。
水、木、金、土と歌いっぱなしなのと乾燥のため、ちと喉がつらい。
NCとBKを単純に比較できないけれど、この曲を歌うぞ!っていう気概がBKの男声には決定的に足りないような
気がする。もっと単純に言うと、根性がないってことだ。金曜日と土曜日のこの練習の濃さの違いはなんなんだ
と考えて、思い至った結論。
あと一ヶ月、どうやって鍛えようか。
- 2006/11/17(金)
BK練習、18:30-21:00。
BK宴会、21:30-23:30。
水曜日のベース補習の成果はそれなりにあったと思う今日の練習。ようやく整理されたかなぁという程度
だけど。逆に弱点がよりはっきりしてきた。ただ、演奏会一ヶ月前としては、かなりよくないのには変わ
らない。楽譜の見方が総じてよくないので指揮者の音楽についていけていない。気づいたひとには注意し
てみるのだけど、こういうものはくせみたいなところがあるので、なかなか直らないようだ。困った。
あと、どうも最近音が簡単に下がりやすくなっている。ちょっと前まではこれほどひどくなかったと思う
のだけど、人数が増えてきたせいかなぁ。途中、S田さんから注意を受ける。必死になりすぎて、ベース
全体が見れていなかった。自分だけ頑張ってもだめなんだ。とはいえ。。。
虫歯があるのに、最近チョコレートがやたら食べたくなる。てっとりばやく血糖値をあげられるからか
もしれない。わたしは昔からよく、「空腹で頭痛」になることがあって、そのせいかエネルギー補給に
は体が敏感になっているのだ。冬場を生き抜くための生存本能ともいえる。全然食べなくても平気なと
きもあるのだけど、いま食べないと確実に死にそうになる!というときの体調には微妙な違いがあり、
これを人に説明するのは難しい。わたしが一人で行動することが多いのは、そのタイミングを同行者に
強要することができない、あるいはみんなにあわせるのが苦手という理由がある。旅行などは特にそう
だったりする。まぁ、そんなことばかりいってると、大人になれないので、すこしずつ改めよう、ある
いは体質改善しようとは思っている今日このごろ。
オーストラリアより、母帰国。明日、練習前に少しだけ実家に帰るか。
- 2006/11/16(木)
20:10-21:50、NC京都補習。烏丸今出川某所にて。
22:00-22:30、補習参加のTJさんと夕食。Coco一番屋にて、肉じゃがカレー。
仕事、同じプロジェクトの運用開始可否の会議で、じつに3回目のリジェクトをくらう。
何度同じ説明をしているのか。納得してもらえず。開発と工場の板挟み。いい加減決まってくれないと、
精神的ダメージが大きい。また新しい資料作らないとならないよ...。四面楚歌が続く。
- 2006/11/15(水)
実家の近所にある歯医者から、逃亡すること10年。あのとき完治させなかったツケがまわってきたか
どうかはさだかではないが、とりあえず欠けた歯はけっこう深い虫歯でありました。しかし、十分治療
可能という説明を受けて、昨日の晩から仕事が終わるまでの不安はあっという間に解消されたのであった。
これまでいくつかの歯医者にかかってきたけれど、これほど丁寧に歯の状態、これからの治療方針、今日
は何をやるかを説明してもらったのははじめてである。具体的な治療をする前から、これほど気が楽にな
ったのはこの説明の力が大きいと思う。なんの下調べもなく、とびこんだ会社近くの歯医者であったけれ
どよかったなぁと思っている。あと、印象的だったのが歯のレントゲンを撮ったあと、すぐに診療台にそ
なえつけの液晶モニターで、その画像が見られるようになってたこと。その画像を元に説明を受けたわけ
だが、世界はえらく変わったものだ。
というわけで、これからゆっくり治してゆきます。
19:00-21:00、BKベース補習。おうき会館にて。参加できないかと思っていたけれど、今日は治療がな
いに等しかったので間に合った。
21:10-22:00、夕食。おうき会館近くの花一輪にて。ここはなんでもおいしいです。少人数のときしか
食べにいかないので、BKメンバーでも知らない人は多いと思う。
今日買った本
「住宅の射程」、磯崎新、安藤忠雄、藤森照信、伊東豊雄著、TOTO出版。1600円。
夕食後、烏丸を下がっていると大垣書店がまだ開いていることに気づいた。そうだ、BKの宴会帰りだと
当然しまっているが、いまはまだ22:30だ。閉店は23:00。寄らない理由がないよね?と自問自答して
店に入った。そろそろ、冬コミの本の中身について具体的なイメージをしないといけないが、建築コー
ナーによることで、だいぶと刺激を受けたように思う。やる気になってきた!で、買った本であるが、
少しでも建築に関わっている人ならば、この4人がいかに豪華メンバーかわかるというもの。「21世紀
の住宅論」という講演会の記録である。しかし、やっぱり建築を知っているひとなら、少しおやっと思
うはずだ。なぜ、おやっ?なのか、そして、住宅というものについて思ったこと、それは後日書こうと
思う。
なぜなら、もう寝ないといけない時間なのだ。練習があったので、金曜日の晩のような感覚だったのだ
けど、帰宅した23:00は十分遅い時間。しかも、今は24:30を回っている。
おやすみなさい。
そういえば、あした(16日)はNC京都補習だ。。。
- 2006/11/14(火)
なんの変哲も無かった右奥歯(奥から二番目)の側面が突如として欠けてしまいました。じつは一週
間前に、口をゆすいでいるときに何か固いものがあって、はき出すと歯の一部だったのです。で、場
所が特定できないでいたら、二三日前からパンを噛むとき、どうも歯茎にあたって痛いような感触が
あって、どうもそのあたりじゃないかと疑って、鏡を見ながらすこしいじっていたら、欠けました。
恐ろしいです。別に歯痛などはないのですが。。。空いた空間が痛々しいのと舌でさわった感触が奇
妙なことこのうえない。欠けた部分は黒ずんでいたので、長い年月をかけて蝕まれたものと推察。鏡
で見る限り現在欠けた部分周辺には黒ずみはなさそうなのですが、これ以上拡大するのは勘弁です。
というわけで、明日急遽歯医者に行ってきます。
ちょっと、動転しているせいかですます調になってしまいました。
たまにはいいか。
- 2006/11/13(月)
きのうあれだけ気をつけていたのに、今日少し喉に変調がみられる。うーむ、あぶないあぶない。
コンクールまであと二週間。乗り切らないと。うがいなどしてみる。
ところで、冬コミ本の製作について、一年前のスケジュールはどうだったか見るため、過去の暗室
を参照してみた。すると、コンクールも終わって12月に入ってからやっと構想を練り始めていたこ
とがわかる。原稿も喫茶店に数日こもってすごいスピードで書いているし、突貫作業だった。たぶ
ん、思い出してみるに去年の11月はコンクール(NC、YKのダブル)+いろいろあって精神的な余
裕がまったくなかったから、着手する気力すらなかったと思う。今だって、好転しているとはいい
がたい状況だけれど、コンクールはNCだけだし、なにより曲の負担が少ないことがありがたい。
(マネージだけはいつも心配。昨日、考え込んでしばらく眠れなかった。)
実際の作業はコンクール後になるとしても、構想や準備面だけは11月のうちに終えておこうと思う。
ところで、暗室を振り返っているときに偶然見つけた。去年の電気あんか導入日は、11月11日だった。
つまり今年よりも一日早いのだ。急激に寒くなったから、今年の方が絶対早いと思いこんでいたのだ
けれど、寒さの感じ方がかわっていなければ、この時期の気温としては同じくらい(平年並み)という
ことなんだろう。ただ、去年はゆるやかーに変わっていったとは思う。
いやはや、こうやって見ると日記っていうのは面白い。続けていると意味が発生してくるもんなんだなぁ。。。
- 2006/11/12(日)
ちょおいと、モールトンで散歩するかなぁと、出かけたのだけれどあまりに寒すぎて20分ほどで
帰ってくる。これからの季節は十分に準備(衣類、食料など)してからでないといけないな。
途中、空と京都タワーの風景を写真に収めたくなって構図を探したのだが、28mmのGRでは思う
ような画にならない。よっぽど近づかないとタワーが小さくなりすぎてしまうのだ。こういう
とき望遠を使って雲とタワーだけを切り取りたいなと思う。

結局、真下まで行ってしまった。

帰宅後、自分の部屋から。
きのうから、敷き毛布に引き続いて掛け毛布を導入。今日からは、足下に電気あんかをいれる。
これでなんとか風邪をひかずに済む。加湿器はまだいらないかも。
- 2006/11/11(土)
13:00-15:00、学部・院生時代のOB会。京都、平安会館にて。恩師の壮健な様子を見て安心する。誰も来て
いないだろうと思っていたら、同期が4人も来ていたのは驚いた。その中に、同じ学会に出ていた同期もいた。
友達というような関係ではなく、互いに切磋し、その存在を認めあえるような、そんな男だ。事業が近い会社
に入って、それぞれ8年ほど経って再会した今日。今も、変わらない存在感に刺激を受ける。そのことが嬉しか
った。再会を誓って別れた。
16:15-17:45、中高大の同級生の結婚式二次会。大阪、梅田にて。ほんの数m先にいる友は、なんだか別世界
にいるように感じられる。二次会というものの雰囲気、出席者、出し物、すべてに現実感がなくて、客観的に
冷静に見つめている自分がいる。会が終わって一番に会場を出ると友と奥さんが待っていた。少しだけ交わした
言葉で、昔のままの変わらない友だと気づく。そのことでやっと現実に戻る。救われた気持ちになる。
18:00-21:00、NC練習。桜宮にて。到着時、ベース0人。残り30分になるまでわたし一人(最終的に二人!)。
ディバイドの練習をすることになっていたのにできやしない(最大3つに分かれるのだ)。ローテーションブレ
スもできない。他パートと同じ音になるところでしかブレスを吸えないってことだ。一人で歌うことには慣れて
いる。それがつらいわけでもない。むしろ、余計な音がなくっていいとすら思う。これでベース全員そろったと
きに、ちょっとでも幅のある音色なんぞだしやがったら容赦しない。そんなやつは熊本に来たって、オンステさ
せてやらない。私は傲慢か?
帰宅前、コンビニで買い物。またしても衝動的に「BOMB(ボム)」12月号を買ってしまう。全然、そんな気な
かったのになぁ。上戸彩かわいい。
- 2006/11/10(金)
BK練習、18:45-21:00。うまくかみ合わない感じ。どうしたらいいだろ。
明日、忙しいため宴会に出ずに帰る。帰宅後、録画していた番組を見ようと思ったら、バレーだかなんだかが
延長になったせいで途中で切れていた。やり場のない怒りってのはこういうのか。うまくいかないときは、い
ろいろ悪いことが重なるものだ。
水曜日、どうでしょうの後にたけしのコマネチ大学数学科という番組をやっていた。その名の通り、古今の有名
な数学の問題を、コマネチ大学数学研究会(たけし軍団)、マス北野(たけし)、現役東大生がそれぞれ解くと
いうもの。数学は得意ではないけれど、こういう番組は好きだ。そのときやっていた問題は、「ビュッフォンの
針」という問題を変形させたもの。問題を記すので、興味のある方はやってみてください。頭のいい中学生くら
いなら、解いちゃうかもしれない。
問い:10cm四方のタイルがしきつめられた上に、直径3cmのコインを投げたとき、コインが4枚のタイルにかか
る確率を求めよ。
もともとの「針」の問題は、ある長さの針を、直線が等間隔に平行に何本も引かれているうえに投げたとき、線
にかかる確率を求めるというもの。で、この問題と先ほどの問いもそうだが、本当に面白いのは問題を解いた後
のこと。確率は計算できるけれども、実際にコインを投げたり、針を投げたりしても求めることができる。番組
中でもコマ大の面々は、銭湯のタイルに牛乳瓶のふたを投げて確率を求めていた。この確率の精度を高めれば高
めるほど、「ある数学的なもの」が正確に求められるのだ。
それは円周率π(パイ)。本家の「針」の問題からは想像つきにくいけれど、タイルとコインの問題からは、
コインという円が出てくるから、なんとなくイメージが沸く。
このことを知ったとき、「数学ってのは本当に鮮やかだ」と思えた。
そういう瞬間があるから、人間は何かを学ぶことをやめられないのかもしれない。
音楽だって、そうだ。もっともっといい瞬間があるはずだろう。あきらめたり、妥協したら見えないものがある。
ともかく、頑張ろう。いろんなことを。
- 2006/11/9(木)
朝食がパンの時や、夜、すこし一息いれるときにミルクティーを飲む。牛乳が切れているときは、紅茶になる
のだけれど、そういうときはとても悲しい。そもそもノーマルの紅茶はあまり好きではないのだ。どうしても、
舌と馴染まない。飲み終わったあと、舌の表面をコーティングされたみたいになるのが嫌だ。それが、どうだ
ろう、牛乳をいれるだけでまるで別の飲み物に変わってしまう。舌に浸透してくる感じがする。味わって飲み
たいと思うようになる。コーヒーも似たようなものだ。つまり、牛乳が好きなんだ、私は。
出演タレントよりも、画面に登場しないディレクターの方が元気いっぱいの番組「水曜どうでしょう」。KBS
京都ではそのどうでしょうの再放送版、「どうでしょうリターンズ」を毎週水曜日に放映中である。現在、
どうでしょう班一行はアラスカのユーコン川、150kmをテント生活を送りながらカヌーでくだっている。
録画していたきのうの放送を見ると、カヌーを川岸につけるとき(手順とタイミングが重要)に藤村Dが
どういうわけか興奮して「イェーイ、イェーイ、イェーイ!」と三連呼。この連呼が、わけもなく、そして
どうしようもなくツボに入ってしまって、爆笑してしまった。で、巻き戻してもう一度見ると、やはり同じ
ように爆笑。なんでこんなに可笑しいんだろう?と自分でもいぶかしみながらも、見ると笑いを我慢できな
くなってしまい、結局十回くらい見ては笑いを繰り返してしまった。ちょっと変か、私。いや、でも笑わそ
うと思ったことで笑ってしまうよりも、こういう笑いの方が気持ちいいじゃないか。笑う門には福来たる、
ですよ奥さん!
- 2006/11/8(水)
今日から冬用の背広にしたのに、帰り道では更にコートが欲しいくらいであった。変化が急激すぎて、服装
がついていかない。毎年、全国コンクールの時期に冬服を買うのだけれど、今年はいらんかなぁと思っていた。
九州もこんなに寒いんだろうか?服を買わないかわりに、いい加減くたびれた靴を新調するか、と考えていた
昨日までの計画は見直さなくてはならぬ。
「光ってみえるもの、あれは」、快調なペースで読んでいるつもりだったが、ようやく5分の2といったところ。
意外と量がある。あと、いつものくせで気になる文章があると、いちいち本を閉じて物思ってしまうのだが、
そういう箇所がわりとあるからかもしれない。
やはり出た、Intel Core 2 Duo搭載のMacBook。予想よりやや遅かったけど、商売的にはこの時期が正しい。
http://www.apple.com/jp/macbook/macbook.html
「スクーターの値段でスポーツカーを手に入れるようなもの。」(Appleの解説)は言い過ぎ(笑)。
わたしのMacBook(Intel Core Duo搭載、2.0GHz)よりも、最大で25%速いということだが、
いまのところ遅いと感じたことはないなぁ。なお、ぱっと見た感じでは、CPUと二次キャッシュ
以外のスペックは変更ないみたい。たぶん、どこのサイトでも触れていることだと思うけれど、
明日以降、店頭在庫処分をやっているうちに、安くでCore Duo版の旧モデルを買って、浮いた
分をメモり増設に回すほうが賢いと思う。PCの性能はCPUよりもメモリの量ですよ!
- 2006/11/7(火)
他人の書いたプログラムを読むのはしんどいというのは世の常で、トラブルのため、昨日、今日とそんな
ことをしていたら大層疲れてしまった。目がだるい、頭が重い。眠い。しんどいので早く帰りたいなぁと
思っていると、もっと大きなトラブルが重なって、帰るに帰れなくなってしまうのも世の常。こういうと
きは、すっぱりとうっちゃってしまって、つぎの日に考える方が快方に向かうことが多い。最低限、なん
とかなるだろうという応急処置だけして、帰宅した。忘れないように途中で頭痛薬を買う。昨日、じつは
薬がなくて、結局一晩中頭が痛くて眠れなかったのだ。頭痛は冷やしても完全には治らない、薬を切らし
てはじめてわかる(というか毎回認識しなおす)、これも世の常。
眠たいので、眠りたいけれど、早く寝ると夜中に目がさめて、また眠れなくなるのがこわくて、眠れない。
こういうときの有効な対処方法を、未だに確立できないでいる。
外でも走ってこようかな。。。
あまりの体調のアンバランスさに、少々、参っている最近なのだった。
外は寒いので、ピアノインストゥルメンタル専門のインターネットラジオを聞いて過ごす。
眠さというよりも、心地よいまどろみに変わってきた。
- 2006/11/6(月)
仕事の終わりかけより頭痛発症。なんでこんなにしょっちゅう頭痛になるのか。
微熱少々。まだよくなってなかったか。
冬コミ、当選しました。土曜日(二日目)、西れ-61a「山Dの電波暗室」です。
新刊の構想をちょうど昨日あたりから練っていたところ。今回は、二冊目と同じく近代建築写真+エッセイ
というスタイルになりそう。文章が多いと急がないといけないような気がするのだが、じつは、文章量とし
てみると一冊目、三冊目の解説文章の方が、二冊目のエッセイよりも多いように思う。まぁ、ともかく頑張
ってみます。
今日買った本
「光ってみえるもの、あれは」、川上弘美著、中公文庫。590円。
「真鶴」はどうしたんだよ!という声が聞こえてきそうであるが、金曜日に少し読んだところ、ちょっと
ダウナーな雰囲気の文章だったため、少し寝かせたくなった。で、同じ金曜日に友人にすすめられたこち
らの方を立ち読みしたところ、するすると読み進んで止まらなくなったので買ってきた次第。作品自体が
刊行されているのは知っていたけれど、もともと新聞小説であるということで敬遠していたのだ。
新聞小説というのは毎日紙面の下の方にあるあれです。どうも子供のころ新聞小説の文面をいくつか読ん
でみて、面白いと思ったことがなくて、そのイメージがずっと尾を引いていたのである。なぜ面白くない
と思うか、それは第一に一回の文章が短いのでストーリーがなかなか進行しない。いや、正確には読み続
ければ進行するに違いないのだが、一話完結ではないから、その日一日だけ読んで面白いかというと、こ
れが全然面白くもなんともないのである。結構いらちなのだ。それに、文章や会話が非常に中途半端なと
ころで切れるので、これがまたいらいら度を増す要因になっている。
だったら、毎日切り取って何日かたまったら読めばいいのかもしれない。実際、母は若いころそれを実践
していたという。が、海のものとも山のものともわからないうちから毎日切り取って、続けて読んだら、
つまらなかったということになるとショックである。第一、わたしは毎日切り取りをするほど勤勉ではな
いので、絶対とぎれるに決まっているのだ。我慢が効かない性質でもあるので、途中で少し読んじゃった
りするかもしれない(だめな人間だ!)。というわけで、この手法はやったことがない。
では、まとまって本になればちゃんと読めるのじゃないか?と思われるかもしれないが、きれぎれに読ん
だ文章を、面白くないと一度感じてしまったら、それをまとめて読みたいとは思わないと思う。
で、この本の話になるのだけれど、まるで一話完結のように一回一回の文章の固まりがきちんと整ってい
るのだ。章にわかれているけれど、その途中、途中で一行のブランクがある。おそらく分量からして、新聞
一日分だと思う。一日、一日の文章が面白い。どこをとりだしても、くすっと笑えたり、ふーむとうならさ
れたりする。それでいて、続けて読むときちんとストーリーというかエピソードなんだけれど、話がつなが
っている。これは、連作短編を得意とする(と私は思っている)川上弘美ならではのことだと思う。どんな
新聞小説でもここまでうまいことはたぶんない。あるとすれば、夏目漱石の「吾輩は猫である」くらいか。
って、ほかに新聞小説を読んだことがないのでひどくいい加減な推測だけど。
「(山Dが気に入るタイプの小説だから)読むといいと思う」って言ってくれた友人の言は正しかったなぁ。
さすがです。ありがとう。
ところで、新聞小説ってどうやって書いてるんだろう。四コマ漫画と同じで、毎日書くのかなぁ。
- 2006/11/5(日)
体調やや回復。気分転換のため、少しだけ散歩。

うちの近所のルーブル美術館へ(嘘)

京都市美術館(本当)
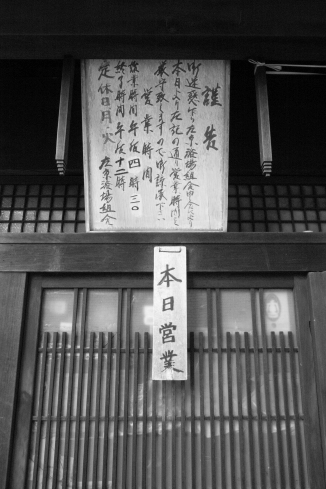
柳湯(新柳馬場仁王門下ル)
京都市美術館ではルーブル美術館展、向かいの近代美術館ではプライスコレクション展と話題の展示が
重なっているせいか、たくさんの人出。疎水縁で絵を描いている人も多い。人が多い美術展は苦手なの
でどちらも素通り。体力がなかったというのが一番の理由だけれど。
二条から五条までの縦の通りには、まだ通ったことのないところが結構あることに気づいた。
- 2006/11/4(土)
早朝より、頭痛・嘔吐。4月の東京カンタート当日朝と同じ症状。
食欲はないが、症状を悪化させないため、栄養だけ補給。ぶどうパンとスライスチーズを口にする。
伏せる。
- 2006/11/3(金)
NC全国マネージ、ほぼ決着。当日の動きを検討。現地情報が欲しいところ。
BK練習、18:00-21:00。
BK宴会、21:30-24:30。マネ会同時進行。
- 2006/11/2(木)
NC全国マネージ、結論は明日に延期。
昨日より、とうとう冬の掛け布団+敷き毛布を導入。暑いと思うような日中もあった10月に比べると、さすがに
11月は冷えるということをようやく体感。夏と同じ寝床ではお腹が痛くなるのも道理である。そんな馬鹿なとお
思いでしょうが、うちの部屋は保温がよくて窓をあけなければ夏ふとん一枚で寝ても大丈夫だったのですよ。い
やそれにしても、例年はこの時期までひっぱったことはないので、やっぱり今年は残暑が長かったということな
んだろう。今年の冬は暖冬だろうか。それとも急転直下、厳冬になるのだろうか。冬コミの待機行列時以外は、
寒い冬でも割と平気。
ああ、毛布にくるまるって気持ちいい。冬ならではの感触。
- 2006/11/1(水)
NC全国マネージ、昼、夕方。ようやく決着に向かうが、結論は明日。
今日買った本
「東京人生 since1962」、荒木経惟著、バジリコ株式会社刊。1500円。
荒木経惟の写真集を買ったのは実は初めてである。この写真集は彼自身が選んだベストショットを編んだと
帯に書いてある通り、本当にいいとこ取りと言っていいと思う。彼の名は一般には「過激なヌードを撮る変
なおじさん」として知られていて、それは正しい認識ではあるけれど、ヌード以外の写真を見たことがない
のは非常にもったいないと言うしかない。立ち読みでもいいから、一度それ以外の写真を見ることをお薦め
したい。「天才アラーキー」の名前は伊達じゃない。
この本にも被写体としてたくさん出てくるけれど、本当に奥さん(荒木陽子)を愛していたんだなぁという
ことが、じんわりと伝わってくる。
『一人に幸せは来ないってわかってる。愛しい人と一緒じゃなきゃね。』
「真鶴」、川上弘美著、文藝春秋刊。1429円。
えーっと、表紙に『サイン本』と書いてあったのでつい。それにしてもいつのまにサイン会なんてやったん
ですか、ジュンク堂さん。行きたかったよ。。。!
お腹が痛いので正露丸飲んで寝ます。
- 2006/10/31(火)
NC全国マネージ、随時。いろいろと調整が続き未だ決着せず。熊本市内の交通事情がよくわからないのが
一番の困りどころ。距離と時間が比例するとは限らないからね。鉄道は定時運行だとしても、本数の問題
がある。全国に散らばるNC団員。出身者が現時点で一人もいない(一人いたが英国留学中...)のはやや
つらい。それにしても、毎年のことながら、まったくシード団体の特権(早めに動ける)がいかせていな
いのは、マネージのやり方に問題があるんだろうなぁ。
あまり時事ネタはここでは書かないのだけれど、前に紹介した失敗学を読んでいたせいもあるが、これは
ちょっとなぁというニュースがあった。新幹線新駅の問題で、JRへの工事費支払い期限がせまっている
ことで、納入しない立場をとっている滋賀県だけれど、記者の「JRからの損害賠償請求も考えられるが、
どう思うか?」という問いに対して、知事の答えが「そのときなってみて考えればいいのでは」であった。
新駅計画の是非についてはここで述べないけれど、想定されうるあらゆる「失敗」について、シミュレーション
するのが組織の長の役割だとすると、かなり無責任な発言に思える。新駅に投資するよりも請求の額+裁判
の費用が多いor少ない(あるいは多い)、そういうところまで考えておくべきだと思う。でなければ、新駅
が建設されようとされまいと、必ず何らかの「失敗」が県政に起こるような気がしてしまうのだけれど。
「マーフィーの法則」の一番始めに書かれている法則を思い出す。
"If anything can go wrong, it will."
(失敗する可能性のあるものは、失敗する。)
そろそろ、日中の暑さもほとんどなくなり、いつの間にやら乾燥シーズン。きょうはお風呂の湯を張った
まま眠ることにします。風邪に気をつけないと。最近、薬局に並んでいる「鼻うがい」、一度試してみよ
うかと思っている今日このごろ。
- 2006/10/30(月)
NC全国マネージ、随時。かなりばたばたする。明日も続行。
昨日、熊本のホテルを予約した。誕生日でもあるし、今回は少し良いところに泊まろうかなぁと考えて、いつもの
楽天トラベルで検索してみたら、なんと。。。ほとんど選択肢がない!JALもANAも、とにかく1万円以上の
ホテルはひとつも空きがない状態。別口や、ホテルのHPでも一部屋もないなんて。しまった...ちょっと行動が
遅すぎたみたい。だってもー一ヶ月切っているわけだし。で、あるところをとにかく見て回って、雰囲気の良さそ
うな6000円のビジネスホテルをなんとか予約できた。雰囲気の良さそうって重要なのだ。気持ち良く眠れるかどう
かは次の日の演奏におおいに影響があることだから。
で、その直後、団で手配していたホテルにダブルブッキングがあって、変更の末、わたしが予約したホテルと同じ
になってしまった。しまったというか、別にみんなと同じでもかまわないけど、わざわざ別手配にしたのに、なん
かくやしいじゃないですか!あーあ。
- 2006/10/29(日)
静養。散歩少々。
NC全国マネージ、21:30-23:00。
更新休みます。
- 2006/10/28(土)
NC練習、17:45-21:00。
朝、NCのマネージでM川さん宅へ。うちから近いといえば近いのだけれど、自転車がないとやはりしんどい距離。
きのうルイガノ号がパンクしてしまったので、鈴鹿以来、輪行状態(分解)のままだったモールトンを組み立てる。
組み立てに際して、気になるのはシートポストの高さあわせと、ハンドルのアライメントあわせの2つ。どちらも
分解時には取り外し、あるいは回転させるため、この作業がいるのだけれど、サインペンなどで位置を記していて
もなかなか一発で思うようには決まらないのが悩ましい。いっそ、型枠だとか治具を自分で作ってしまいたくなる
が、ほかのモールトンオーナー(に限らず、折り畳み式のユーザー)の皆さんはどうしているのだろう?と思う。
不眠改善のために、病院で診察を受ける。待ち時間1時間半。ほえー。待合室にあった「家栽の人」を読む。じつ
は初めて読んだ。妙に落ち着きを与えてくれます、この漫画。病院にはぴったりなのかもしれない。
昨日から喉の調子が悪い。高い音程のピッチがどうしてもさがってしまう。あまり声を出さす、どうしても必要な
部分だけ歌うようにする。しかし、ベースは人数が少ないから、どうしても出さざるを得ないんだよなぁ...。なん
でみんな、関西コンクール後の練習には来ないんだよぉ、ってわたし先週休みましたね。というか、あまり歌えて
ない人ほど来ないってことです。どうなってるんだみんな!
しんどい、疲れた。あしたは体と喉を休めよう。。。
- 2006/10/27(金)
BK練習、18:30-21:00。
BK宴会、21:30-23:00(途中退席)。
NCマネージ、24:00-26:30。
NCの用事で少々予定が狂ってしまい、夜中に大宮寺ノ内のNC団員宅へ自転車で急行(>迷惑かけました)。と、
その道中、明らかに自転車の可動範囲から「ペタン、ペタン」という異音がするのだ。さてはタイヤに何か張り
ついてしまったかと思ったのだが、到着してから調べてみるとびっくり。後輪タイヤに画鋲が突き刺さっていた。
さっきの音は画鋲が路面に接触する音だったのだな。それにしても、気づいたはいいけれどおかげで空気がほとんど
抜けてしまい完全なパンク状態。帰り道は下り坂で楽なはずなのに、べこんべこんになった後輪を必死で駆動させて
20分ほどの道のりを帰ったのだった。いい運動?になったか。すれちがう人はあまりのべこべこ、べたんべたんとい
う音に驚いていたような気もするが。
- 2006/10/26(木)
ネットのニュースによると、横浜の山下公園に係留されている「氷川丸」と、その近くにある「マリンタワー」
の運営会社が今年中に解散することが決まり、その二つの展示も12月25日で終了することになったそうなのだ。
青天の霹靂ってほどではないけれど、ちょっと残念。氷川丸は日本全国でも数少ない船の内部を見学できる施設
だっただけに、艦船ファン(でも船酔いする)のわたしにとっては貴重な存在なのだ。なんでも日本郵船に譲渡
されるそうだけれど、その後の身の振り方については書いていなかったので、行く末が気がかり。舳先ぎりぎり
まで立つことができるので、よくカップルが「タイタニックごっこ」をやっていたりしたので、結婚式場とか、
そういう施設になると横浜っぽくていいかも。実際に氷川丸ではそういう企画をやっていた。わたし自身は、
カップルがはけたあとに一人タイタニックごっこ(?)をやってみたけれど、あれはすごく怖いです。真下には
10m以上下に海面があるだけだから、高所恐怖症にはたまらんです。
船の見学というと、あとは船の科学館にある南極観測船「宗谷」、名古屋港にある同じく南極観測船「ふじ」が
あるけれど、豪華さという点ではやはり氷川丸が面白いかなぁ。あ、そうそう現役の南極観測船「しらせ」は、
2007年に退役予定らしい。ぜひとも、先代の二艦に続いて、どこかの港で見学展示を行って欲しいもの。その暁
には、どこであろうと飛んでいって、乗艦コンプリートを目指すのだ。
- 2006/10/25(水)
きょう買った本
・「だから失敗は起こる」(NHK知るを楽しむ-この人この世界テキスト)、畑村洋太郎著、NHK刊。683円。
NHKのことをことさら褒めたり、批判したりするつもりはないとはじめに断っておくが、NHKの良いと
ころは、頻繁に再放送をすることだと思う。この点、民放はあまり積極的ではないと思う。つい先日、フジ
テレビが古畑任三郎vsSMAPをゴールデンに再放送したけれど、あれは画期的なことで、もっとやってほし
いなぁと思う(フジ曰く、再放送って呼ばないらしいけれど)。その決断にいたったのは、その番組に対す
る視聴者の需要があるということだと思う。NHKは、そういう声に応えて放送しているわけではないと思う
けれどね。でも、編成としては正しいと思うのですよ。
で、わたしはどういうわけかこの再放送で、かつて見逃した良い番組を観ることができたということが多い。
今回買ったテキストの「だから失敗は起こる」もその一つ。失敗学という、失敗を生かして真の科学的理解
を得るという趣旨で、著者の畑村洋太郎氏が講義するもの。回転ドア事故、羽越線脱線事故、JCO臨界事故、
そして福知山線事故、それら具体的な事故の調査を通じて、なぜ事故=失敗が起こったのか?を毎回解明して
いくため、その失敗から得るものというが机上の論理ではなく、自分たちの身の回りにすぐにでもいかせそう
なそんな気にさせてくれるのだ。だから畑村氏は大学の教授だけれども、「現場をよく見ている人」という感
じがする。
大部分を見逃していたから、せめてテキストでも読もうと思って買ってきた。放映されたのは8、9月だけれ
ど、再々放送が平日の午前中にやっているらしい(あ、録画すればいいのか)ので今でもテキストが手に入る。
これも再放送のおかげ。
その他
・「成恵の世界」9巻、丸川トモヒロ著、角川書店刊。540円。待望の新刊デス!
・「げんしけん」7巻、8巻、木尾士目著、講談社刊。各514円。8巻の帯の惹句、ちょっと感動的ですらある。
『オタクだから、恋をした。』
『この趣味からは逃げられない。それでも人は人を好きになる。』
『そしてたしかに、ボクらの青春は、ここにある。』
中身はもっともっとよかった。
- 2006/10/24(火)
用事があって実家へ寄る。来月、母がオーストラリアのアデレードへ行くのだが、国際線でシドニー空港
についたあと、国内線へ乗り換えるためのルート?がよくわからないというので、かわりにインターネット
で調べることになった。自分で調べているときにWindowsの具合がおかしくなったらしく、うまくいかない
というのだ。不具合はたいしたことなく、簡単に解消。下手にいじって、もっとおかしくなると困るからと
いうのが母の弁だが、母くらいの年代の人間にこういうことを思わせるPCという機械は、つくづく未発達
な工業製品だなーと思う。
シドニー空港を検索すると、なんと「シドニー空港」そのものの日本語サイトを発見。いやー、さすがオー
ストラリア、日本とのつながりが深い。ほかのサイトの情報も含めて、乗り換え方法はなんとなくわかった
ので、あとはその辺にいるであろう日本人ビジネスマンを頼るように言っておく。
ああ、でもいいなぁオーストラリア。父と妹はそれぞれ1回、母などはこれで3回目(アデレードは初)で
ある。なのに、わたしは0回...。
- 2006/10/23(月)
21日分を追記。
きょうは、もちろん筋肉痛が来ました。しかし、腕、肩、腰、ふとももなど予想された箇所はほとんど
痛みがなく、全身の疲労度も普段のNCの練習に比べるとまし。たぶん、きのうチームメイトの人にも
らって飲んだBCAAアミノ酸粉末のおかげかと。「つぎの日の疲労がずいぶん違いますよ」と言われ
たのだけど、まさしくその通りだった。しかし、アミノ酸にどうしようもなかったところが一カ所。
前脛骨筋(脛の横、外側の筋肉)が痛いのなんのって、歩くのが嫌になるくらい。この筋肉は、足先を
反らせるときに使う筋肉、つまり自転車をこぐとき、踏み込みから頂点へ戻すときに使う。普通はこの
戻す作業は反対側の足の踏み込みがあるので負担は少ないのだけれど、今回はピンディングペダルだっ
たのだ。両足とも踏み戻し(引き足)を絶えず行っていたことになるから、酷使もいいところ。
ただピンディングペダルを使うだけなら、普通はこんなにひどくはないはず。やはり鈴鹿のコースの
すさまじさが一番の原因だろうな。22日の追記をするときに詳しく書くけれど、第一コーナーという
コース最低地点からシケインというポイントまでの1km、ずっと登りなのです。その高低差35m。1kmで
35mとはつまり勾配35パーミル。これは日本の鉄道では「急勾配」と定義され、これ以上の勾配では
登山鉄道の装備が必要になる。それくらいきついんです。え、あんまりイメージわかない?
知恩院前の坂道で特訓していたけれど、あれくらいでは全然駄目だということを思い知らされたわけ
だが、しかし、前脛骨筋なんて、普段どうやって鍛えればいいのやら。
- 2006/10/22(日)
鈴鹿8時間エンデューロ参戦(カテゴリー:4時間耐久ミニ)。
チーム成績:21周回(1周は5.824km。カテゴリートップから-6Laps)。平均29.3km/h。28位。
山D個人データ:5周回。最高48.1km/h。平均25.8km/h。走行時間1'06'47。走行距離28.82km。
後日、詳細記述予定。
- 2006/10/21(土)
18:00、鈴鹿のホテルに到着。駅に着いた時点ですでに日が沈みかけていたのだが、暗くなるまえに駅前の
道路の隅っこ(他にスペースがなかった...)でモールトンの組み立てを完了した。駅から鈴鹿市内までの
道のりはほとんど街灯がなく、日が暮れてから到着していたらかなり危険だったかも(そもそも組み立て自
体できなかったと思われる)。
23日:追記
京都から鈴鹿までは、一般に名古屋を経由するルートを思い浮かべる方が多いと思うが、よくよく調べて
みると、もうひとつのルートがあることに気づくと思う。鈴鹿市にあるJRの駅は加佐登駅だが、この駅
はJRの関西本線の駅。関西本線というのは大阪から名古屋までをほぼ真一文字に突っ切っている路線で、
京都からだと奈良線で木津まで下がるか、草津まで行き草津線(草津~柘植)で柘植まで下がることで接続
できる。草津線を経由した場合、運賃は1450円。それに対して、名古屋経由で逆方向から関西本線に乗っ
た場合は3260円。名古屋までは新幹線に乗る場合、特急券2410円が余分に必要になる。では時間はどうか
というと、時間帯によるが草津ルートの場合、最短1時間51分。名古屋ルート(新幹線利用)の場合、最短
1時間53分であり、違いがほとんどないのだ。ただ、乗り換え回数は草津ルート3、名古屋ルート1という
違いがある。
乗り換えが多いということはモールトンを運ぶ負担が多いということであり、簡単にはすませられない
問題がある。なお、名古屋ルートで名古屋から名鉄を使う(鈴鹿の最寄り駅は平田町)手もあるが、
JR名古屋と名鉄名古屋は、輪行には無視できない距離がある。1回の乗り換えでも、その距離が長い
と意味がない。
で、結局、行きは元気だろうということ、JR在来線同士の乗り換えは接続の関係上、同じホームか隣の
ホームで行われることが多い(対して、新幹線と在来線は離れているのが普通)ということから草津ルート
を選択した。しかし、ここでもうひとつ考えておくべきことがあったのだ。
当日、13時に家を出発、14時の琵琶湖線に乗る予定だった。途中、ご飯を食べる時間+モールトンの分解
の時間が必要だった。しかし、ちょっと悠長にココ一でカレーを食べている間に13時半になり、京都駅到着
が13時40分になってしまった。残り20分だが、それはホームまでの時間込み。輪行袋を抱えての移動だから
すたすたと歩けない。分解に残された時間は15分弱。かなりあせって、分解をはじめた。モールトンの分解
そのものは簡単で、工具がいる(六角レンチ)にしても、時間はかからない。時間がかかるのは輪行袋に固
定し、詰める作業なのだ。これがかなり面倒くさい。
結局、ホームについたのは14:05だった。乗り遅れたわけで、つぎの電車に乗って草津へ。ここで考えて
おくべきだったのは草津線のダイヤだった。関西本線の本数が少ないことは経験上知っていたが、草津線
も同様だということをすっかり忘れていたのだ。草津に着いた時点でつぎの電車は15分後、それくらいな
ら大丈夫と思っていたら、なんと途中の貴生川までしかいかないのだ。終点、柘植まで行く電車は53分後!
一時間遅く京都を出るのと変わらない。草津で待っているのも退屈なので、とりあえず貴生川まで乗る。
すると、貴生川からは再び草津に折り返す関係上、柘植行きの電車とは違うちょっと離れたホームに到着
してしまい、予期せぬ移動が発生。だまって草津で待ってれば、この移動はなかったわけで、ちょっと後悔。
貴生川で30分ほど待ってから柘植行きの電車乗った。
柘植からは関西本線にスイッチ。これは同じホームで助かる。ただし、途中の亀山までしかいかない。亀山
からは名古屋行きにスイッチ。ひとつ向こうのホームへ移動。亀山から二駅で加佐登到着である。草津線で
のロスのため、予定より1時間遅れでの到着。夕日が沈むまであとわずかであった。
電車のルートとは時間によって姿を変える生き物みたいなもの。都市部と違って、1分の遅れが命とり(その
日のうちに到着できなくなるなど)になるということを改めて思い知らされた移動であった。
- 2006/10/20(金)
BK練習、18:30-21:00。
友人らと会食、21:30-24:00。
少々、お酒も頂きました。酒で料理のうまさが引き立つって感覚、ひさしぶりだった。三種類飲んだけれど、
きょうは銘柄をひかえてくるの、忘れてしまった。幸せなひととき。
きょうの練習で、指揮者が作曲家と演奏家の違いというか、音楽上の有利?はどちらにあるかということを
話したのだけれど、その話を聞いて思い出した言葉がある。
『優れた画家が、美を描いた事はない。
優れた詩人が、美を歌つたことはない。
それは描くものではなく、歌い得るものでもない。
美とは、それを観た者の発見である。
創作である。』(青山二郎)
青山二郎は稀代の目利きとして知られ、小林秀雄、白州正子の骨董の師匠であった人物。
この言葉を目にしたときは、衝撃だった。「ああ、そうか、それでいいんだ」と思った。
音楽でもむろん同じだと思う。われわれ歌い手がなければ音楽はない。そして、観客が
いなければ、やはり音楽はない。われわれは楽譜を見て、発見し、創作しないといけないのだ。
そうでなければ、そこに美はない。(観客とて同じこと。)
指揮者の言いたかったことは、そういうことなのだろうな。
明日は、午後から鈴鹿へ。第7回鈴鹿8時間エンデューロ(耐久)大会に参戦するため。
8耐といっても、これは自転車の話。私が参加するのはモールトンやBD-1といった小径車の部門なので、
4時間耐久で、しかも4人でのチーム戦となる。大会の開催は日曜日なのだけど、レースの準備のために
朝4:15にはホテルを出ないといけないので、明日から鈴鹿入りする。車でも持っていれば、NC練習終わっ
てから、って考えるところだけれど、輪行する身ゆえ(+体力面)、明日の練習は休ませてもらうことに
した。ごめん!みんな。
がんばります。
molto vivace e cantabile!
- 2006/10/19(木)
最近、朝早く起きようと思って早く寝るのだが、そうすると夜中に目が覚めてしまい、そのままなかなか寝付く
ことができず、結局浅い眠りのまま朝を迎えるという、なんとも最悪なパターンが続いている。ビジネス雑誌
などでは、最近盛んに朝型になることをすすめる記事が目立つのだけれど、どうもわたしの場合、体質的?に
朝型には向いていないと感じる今日このごろ。
ただ、12時を回ってから寝るのと、11時以降12時前に寝るのとでは、結構次の日の朝の調子が違うので、この
あたりの微妙なバランスには注意したいと思っている。寝る前の「少しだけの読書」は特に危険だ。歯止めが
効かない性格なんである。
睡眠時間が短くてもよく眠ったーと思えるときがある。そういうときは眠りの密度が濃いのだろう。そういう
状態を恒常的に実現できると、日々健康にすごせるんだろうけど、どうしたらいいのか解が見つかっていない。
眠りの達人になること、私の願望の一つ。
- 2006/10/18(水)
きょう買った本。
・「村田エフェンディ滞土録」、梨木香歩著、角川書店刊。1400円。
・「のだめカンタービレ」16巻、二ノ宮知子著、講談社刊。390円。
・「げんしけん」6巻、木尾士目著、講談社刊。505円。
後日、補足予定。きのうの後遺症で、しんどいので寝ます(またかーって言わないで下サイ)。
- 2006/10/17(火)
市販の頭痛薬は高いですね。健康保険がきいてくれへんものかと思いつつ、今日も薬局に向かう山D。
夕食後、少し横になっていたら、とても怖い夢(デパートの屋上から、地上への脱出。山Dは高いところ
が苦手)を見てしまう。頭痛は取れたけれど、しばらく緊張感がおさまらず。痛さを取るのに、夢とはいえ
こんな怖い目に遭うなんて、なんとなく理不尽だなぁ。
- 2006/10/16(月)
OS Xのアップデートをしたら、Harbotに出てくる全部の文字が文字化けしてしまいまった。ほげー。
Flash Playerの問題かもしれないと思って、最新版にしたけれども解決せず。うーん。というわけで
今日知ってる人で誰が来たのかをピカードに聞いても、人数とアルファベットの名前の人しかわからな
いのだった(半角アルファベットはなぜか化けない)。
ひさしぶりに近所のドラッグストアで米を買ってくる(なぜか色々売っている)。ここ一月ほどパン食
だったのだけれど、パンでは夕飯にならないのである。当たり前だけど。買ってきたばかりの米の封を
切って、どばーっとおひつに注ぐのは気持ちいい。今日はカレー。米買った記念に300円のレトルトを
買った。
明日の朝は、これ↓で食べるぞー。

- 2006/10/15(日)

来週末の準備、その2デス。お世話になっている自転車屋さんのチームジャージ。

襟元にネームや好きな言葉を入れられるとのことだったので、こんなの入れてみた。
"molto vivace e cantabile"(きわめて快活に、そして歌うように)
こういう心持ちで自転車に乗っていられるといいなぁと思って。
もちろん、これは音楽用語(イタリア語)なんだけれど、自転車のコンポーネント(ギアやブレーキのセット)
の世界ではイタリアのカンパニョーロというメーカーが有名(ライバルは日本のシマノ)で、自転車とイタリア
っていうのはわりとつながりがあるのです。だから、違和感はないと思うのだけれど。どうでしょ?
きょうは、モールトンに乗って下鴨神社経由で、北白川のけいぶん社へ。BKの宴会のときにも話題になったのだ
けれど、最新のLマガジンの表紙にけいぶん社が取り上げられていて、ひさしぶりに覗いてみたくなった。で、
着いてみてびっくり。まず、店の前に自転車がずらーりと並んでいてどこかの下宿屋か定職屋みたいな様子。し
かも、いつもは誰も座っていない外の鉄製のベンチに人が座っている。まるで、Lマガジンの表紙そのままの構図。
いつもこんなに人いないよねーって、宴会では話していたのに。入ってみると自転車の数でもわかっていたのだ
けれど、いつもの2倍くらいのお客さん。多すぎて狭い通路を歩くのが大変なくらい。なんだかちょっとざわつい
てもいる。こんな状態のけいぶん社、初めて見た。やっぱり、Lマガジンの影響なんだろうけど、それにしても
雑誌の威力というか、恐ろしさというべきか。すごいなぁ。
けいぶん社の思惑はわからないけれど、「知る人ぞ知る」というひっそりした雰囲気、でも固定のお客さんは
ちゃんといるというのが好きだったんだけれど、こんなに人がいると落ち着かない。なので、ざっと一回りし
てから、ろくに立ち読みもせずに出てきてしまった。なんだかなぁ、ほんとはじっくり時間をつぶすつもりだ
ったんだけれど。ほとぼりがさめてから来るしかないね。だって、外に出た瞬間、目にしたのはけいぶん社の
外観(アンティークな雰囲気の看板がある)を携帯カメラで撮りまくる人たち(3~4人居た)だもの。ここ
は観光地じゃないぞお。
なんとなく、他の本屋に寄る気にもなれず、まっすぐうちに帰ってきてしまった。
で、家で文庫本を読んでたわけデス。「偶然の祝福」を読了。
ああ、この読書中の感覚、読後感はなかなかひとに伝えづらいものがある。
その中の一編、きのうNC帰りの京阪電車で読んだ「キリコさんの失敗」は、ちょっとこころが静かに震える
ようなものがあって、ああいう感慨はこのところ久しくなかったものだったな。とてもいい心持ちです。今。
- 2006/10/14(土)
NC練習、17:00-21:00。
NC宴会、21:30-22:45。
以前、話をしていたピンディングペダルをモールトンに装着したので、その写真を公開。
 
(左)ピンディングペダル、(右)ピンディングシューズ
ごらんのように通常のペダルに比べるとかなり小さい。このペダル自体は、仕上げがとても美しく、モールトンに
装着しても違和感がない。シューズはナイキ製。一見するとまったく普通のスニーカーにしか見えない。ちなみに
近年の自転車人口の増加にともない、アディダスやナイキといったシューズメーカーが積極的にサイクリング市場
に参入している。しかし、流通ルートは自転車専門店に限られているため、直営店に行っても扱っていないことが
ほとんど。心斎橋のアディダス直営店に問い合わせたところ「自転車専用シューズというのはありません」と回答
されたくらい。自分のところの商品群くらい把握しておいて欲しいなあ。結局、京都市内では有名な「コセキサイ
クリングセンター」(七本松今出川上ル)で、ナイキ2007年モデルを購入した。このお店は親切丁寧で、パーツや
アパレルも豊富なのでおすすめです。
 
(左)シューズの裏側(右)ペダルにシューズを固定したところ
普通のスニーカーと違うのは、ソールがくり抜かれてペダルに装着するための金具(クリート)がついている
ところ。ついているというか、買った直後はソールはゴムに覆われているので、切り取り溝にそってナイフを
入れて自分で切り取るのだけれど。そして、ペダルに付属するクリートを自分のポジションにあわせて取り付
けるのである。このクリートを、ペダルの金具に引っかけて、踏み込むと「ぱちん」と音がしてペダルに固定
される。機構としてはスキーのブーツの固定と同じ。はずすときは靴をねじれば良い。このはずす作業に慣れ
ないと、当然ペダルに足が固定されたままなので、自転車ごと横転する。まぁ、すぐ慣れるんだけれど、こけ
かけると、本当に怖いです。というわけで、頻繁に足をつくような街乗りには向いていないのだ。

こんな風にペダルと靴(足)が一体になる。
さて、ピンディングペダルをつけてみての感想だけれど、最初は劇的に何かが変わったという感じはしなかっ
たのだけれど、しばらく走っているうちに気づくことがあった。ひとつは高速で走っているときにペダルから
足が浮くことがないので、とても安心感があるし、文字通り自転車との一体感が増す。当然、ペダリングが安
定するのでロスが少なくなる。そして、サイクルメーターを見てわかったのが、平均時速があきらかに上がっ
ているということ。少なくとも2~4km/hは上がっている。これが、引き足(踏み込みから戻す動作)もペダル
の回転に使えているということなんだろう。街中ではなかなか本気でスピードを出せないのだけれど、高速に
なればなるほど効果は高いと思う。
さて、これで準備がだいたい整った。来週の週末が楽しみ。
何の準備かは、また後日。
- 2006/10/13(金)
BK練習、18:30-21:15。
BK宴会、21:30-23:30。
先週のコンクールから、リップクリームを再び使うようになった。前日の練習で歌っていると、知らないうち
にくちびるが切れていたのだ。気候はどんどん乾燥しはじめていたのに、まるで気がつかなかったというわけ
で、時の流れというか季節の移り変わりの早さを身をもって知った。全国コンクールまであと一月ちょっと。
そのときにはもう、コートを着て、セーターを着ているのかと思うと、なんだか信じがたい。
- 2006/10/12(木)
ヨーロッパのさる都市で、外壁、窓などがすべて何らかの形で覆われて、その本当の姿を見ることができない
建物の調査をしている夢を見た。建物は10ほどあり、公共施設や教会などらしい。どこかのホールで、それら
施設の内覧会(?)のようなものが行われているのを見学したりもした。場面変わって、街を見下ろすワイン
ディングロードにいる。一年一回だけそれらの覆いが取り外され、真の姿を見ることができるというので、写真
を撮るポイントを探して歩いているのだ。道を歩いて視界が開けると、海に面して湾沿いに発達した、美しい
夕暮れ直前の街が見えた。旧市街特有の茶系統の色屋根のなかに、きらきら光る濃紺色がみえる。たぶん、覆
いが外されたの建物が光っているのだろう。
前日、すこし「家守綺譚」を読み返していて、そのなかにトルコの話があって、トルコがイスラムに制圧され
たとき、それまでのキリスト教会はすべてモスクになってしまったのだが、その際、壁のキリストやマリアの
壁画はすべて塗り込められてしまったそうである。本文中では、主人公の友人で考古学者の男が、できるなら
壁をはがして、かつての壁画を見て見たいと手紙に書いて主人公に寄越すのであるが、主人公はある出来事を
体験することで、塗り込められたことによって存外マリア様の絵は守られているのかもしれない、と思うよう
になるのだった。夢を見たのはたぶん、この話のせいだろうな。でも街はスパニッシュ様式にみえたんだけど。
もうひとつ、続きで見た夢。こちら側にBKメンバー、向こうにVineのメンバーがいて、練習しようとしている。
BKのメンバーが足りないので、向こうにいる掛け持ちメンバーに帰ってきて欲しいなぁと思っていると、指揮者
が一人だけ帰すという。そして、指揮者とBKの技術庶務とが相談を始めるところで夢が終わった。
これはなんでだろう。昨日補習したのは男声だけだったんだけどな。返して欲しいって思ったのは女声なのに。
- 2006/10/11(水)
BK男声補習@おうき会館、18:30-21:00。
BK補習食事会@花いちりん、21:15-22:00。
普段のBK練習では、男声についてのフォローはあまりないため、パート内バランスを見る目的と、最近入団した
人向けの補習を目的として行ってみた。うーん、日程優先(水曜日)で決めてしまったため、参加はわたし含め
て5人。新人さんはいずれも都合がつかず。古参がうまいわけではないので、集まったメンバーで音色と和音を
確認する。大人数での練習ではわかりにくい個人の声をいかにあわせていくか?という過程がよくわかるのと、
メンバーで練習方法を相談したりして作っていく雰囲気が好きだ。普段の練習では、やはり指揮者との対峙、
他パートの対峙があるし、人数が増えると声をあげにくいこともあるから。基本的にパート練習はしない合唱団
だけれども、音楽的にも、精神的にも結束を深めるためには、自主的なパート練習は必要だなーと感じるこの頃
である。創団8年目にして、そんなことに気づくなよっていうご意見はもっともですが。今からでも、そういう
風土を根付かせることができたらなぁと個人的には思っている。
珍しく自転車。背広を着ていても、きょうは寒い。
帰宅途中、ちょっとおなかが痛くなるのだった。
以前紹介した、書籍管理ソフトDelicious Libraryについて、バグレポートをソフト会社に昨日送った。ウィ
ジェット内(別画面で呼び出すことのできるよく使うツール群)では、タイトルなどの部分検索が可能なのだが、
メイン画面の検索ではタイトルの先頭との完全一致でしか検索ができないのだ。たとえば、タイトルに「山」が
含まれる本を検索しようとすると、ウィジェットなら「日本の百名山」が検索できるのに、メインだと検索でき
ない。「山Dの電波暗室」や「山の上ホテルの歴史」のように「山」で始まらないと駄目なのだ。
このソフトはいくつかの言語にローカライズされているため、バグレポートもメニューで選んでに日本語で送る
ことができるのだが、果たしてレポートに関して日本語で送っても対応してもらえるかどうかは自信がなかった。
ところが昨日の今日で、このレポートに対して返信があった。返信内容は英語だったけれども、きちんと日本語
で送った内容をふまえての返信だったのには驚いた。返信内容は「そのバグは既知のバグであるが、現在のとこ
ろ原因がわからないでいる」というもの。内容には不満というか、改善されるまで時間がかかりそうなので、残念
ではあったが、対応の早さと、言語を問わないサポート力には大いに満足することができた。普通、現地法人で
もない限り、なかなかここまでできないと思うのだが。調べたところサポートはLucas NewmanとMike Leeの
二人だけ。やるな、Delicious Monster社。
- 2006/10/10(火)
夜、近所のマッサージ屋に久しぶりに行く。このところ肩こりの症状はなかったので行ってなかったのだけれど、
やはり昨日、一昨日の疲れが肩や首に来ていたので、気づいたうちにほぐしてもらおうと思って。担当は店長
さん。第一声が「なんか焼けはりましたね?なんか白いイメージがあって(笑)」。うーん確かにこの夏は、
モールトンであちこち走り回っていたから、いつもの夏に比べるとそうかも。しかし、月に1~2回くらいしか
行かないお店の人、しかも女性に色白い(ひ弱?)って認識されてたのはちょっとショックかもしれぬ。
ともかく、これで肩と首がだいぶ楽になった。肩のコリ、自分でここが痛いって思っている以外の部分の深い
ところや全然思いもよろない部分がこっていることがわかって、やっぱり人に診てもらうというのは必要なこ
となんだと、改めて思ったのだった。
「偶然の祝福」を読んでいて、突然万年筆で何か書きたくなる。しかし、書きたくなっても何か書くモノなど
特にないので困ってしまう。こういうとき、自分の名前、住所くらいを書くともう手詰まりである。暗室の文章
以外に本当にプライベートな日記でもつけていれば別だけれど、そういうものはないし。結局、暗室のネタに
なるかもと思って、万年筆に関して思ったことをその辺にあった紙に書き付けてみる。んー、やっぱり字が下手
だ、私は。結局、書いた内容は没。さて、次回また「書きたい病」が発症したらどうしようか考えておくべきだ
ろうな。やはり、劇中の主人公のように小説やエッセイなどの好きな文を写し取ってみるのがいいな。できれば
このごろ少なくなった縦書きで。本のなかには、しおりが二つ付いているものがあるけれど、一つはどこまで読
んだかを知るために使うのだけれど、もう一つは印象に残った文章のページに挟むことが多い。読み終わってい
るなら、二カ所に挟めるわけだ。そうやって記憶に残しておいた文章を、できれば原稿用紙に書いてみることに
しよう。何か発見があるかもしれない。
- 2006/10/9(月)
関西合唱コンクール、NCにて出演(シード演奏)。
12:30-16:00、練習。
17:40ごろ、本番。緊張はない。ただ、すごい演奏をするという気持ちだけ。すごいっていうのは、
音量とか迫力じゃない。ふつう、コンクールでは聞けない演奏ってこと。こんな演奏があってもいいんだ
って、お客さんに思ってもらうことができる演奏。そのために、ここにいる。
こころなしか、聞こえにくいはずに舞台上の音がよく聞こえる気がする。混声と違って男声ではやはり、
音程が近いせいかもしれない。とか思っていたら、和音進行がシビアの箇所で、崩れかかる。うーん、
いかんいかん。自分で自分をはったおしたい気分になるが、とりあえず棚上げ。
演奏終了。全国に向けての課題がいろいろとみえた。
審査発表、全国へはYKではなく、Vineが行くことになった。そうか。ちょっと心がゆるむ。残念なのは
残念なのだけれど。帰り、Hさんの車にて送ってもらう。思わず、次回のYK練習は行けません、って言
いそうになって、言いよどむ。そうだ、もうわたしは練習にはいかなくっていいのだった。一抹のさび
しさのような、あるいは逆の安堵感のような、入り混じった気持ち。いろんな気持ちが本当の気持ちだ
と長嶋有のエッセイにあった。だから、たぶん、どっちの気持ちも正しいんだろうな。
降り際、同乗していた友人に文庫本をもらう。
「偶然の祝福」、小川洋子著、角川文庫。
帰宅後、少し読み始める。小川洋子の視点には、単純な観察眼の鋭さというよりか、フェティシズムな
雰囲気が常に漂う。面白いことに、そこにはエロティックな香りが一切漂っていない。純粋なフェティ
シズムっていうのか、静物画を描くような冷静な視線だけがそこにある。ほっとひといき、という今の
こころもちにそれが、不思議とぴったりくるのだった。
ありがとう。ゆっくり、読みます。
- 2006/10/8(日)
関西合唱コンクール、YKにて出演。
伊丹ホールは歌っていて手応えがわかりにくいホール。もっているものを出し切れたかどうか、ちょっと
わからないまま演奏は終了。課題曲は手応えがあった気はするけれど、自由曲では音量の加減がわからず、
もしかしたら大きすぎたような気もする。終演後、聞きに来ていたBKメンバーにやはり男声の音量を指摘
されてしまった。しかし、課題曲は圧倒的にうまく、自由曲も遜色ないとの評価。この二人のメンバーは
音楽についてかなり客観的かつシビアな判断ができる人たちなので、信頼してもいいと思えた。そうする
とちょっと気分的に楽になった。
午後、昼食後いったんホールへ。このままAグループを聞き続けるかどうか迷う。もっとも聞きたいのは
17時すぎのアンサンブルVineの演奏だが、4時間近くあるのだ。夜はYKの打ち上げもあるし、とにかく
どこかで横になりたいなーと思い、思い切って梅田のホテルを予約した。打ち上げ後に京都に帰ってから、
明日また昼には伊丹にNCの練習・シード演奏に戻ってくるのはいかにもしんどい。実際、しんどいのは
昨年経験済みだったから。梅田まで片道30分弱。チェックインして、しばし休憩。いまごろ練習している
であろうVineメンバーには悪いなと思いつつ。ちなみに梅田のホテルは、阪急電車に路線に沿っているた
めに、当然ながら、窓からは阪急電車が見えるはずだった。しかし、通された部屋は反対側であった。ち
ょっと落胆する。電車側は音がうるさいのかもしれない。だから基本的に反対側からうめていくというル
ールでもあるのかもしれないなと思ったが、世の中には電車が走る風景が見える方が良いという人もいる
んです。
17時にホールに戻り、何団体か聞いてからVineの演奏。なんというか、醸し出す空気が違うのだ。コンク
ールで発表しているというのではなくて、音楽を表現しているということがまず第一にあって、それが皆
の方から客席にちゃんと届いている気がした。そんな演奏する団体は、はっきりいってほかに無いと言い
切れる。つぎにどんな音が鳴るんだろう?どんな言葉が彼女の口から発せられるんだろう?どんな表情で
彼女は歌いかけてくるんだろう?ひとりの人格のように、音楽が感じられた。わくわく、どきどきする。
楽しい!楽しい!すごく嬉しくなってくる。聞きたかったのはこんな歌。歌っているみんなも、とても楽
しそうだ。いま、ここにいるひとたちはみんなひとつの音楽をたしかに共有している。
コンクールなので、結果が出る。YKは二位金賞!やったね。Vineも二位金賞。ということは、どちらか
一方が全国大会に行くということ。もやっとした、複雑な気分。YKの一員としてみんなで熊本に行きたい
気もするし、観客としてもう一度Vineと音楽を共有したいという気もする。どちらも、正直な気持ち。
全国行きの結果はつぎの日にわかる。
21:15から23:50まで十三にて、YK打ち上げに参加。これまであまり話したことのないメンバー(主に女声)
と話をすることができた。わたしは季節団員なんだけれど、皆さんわりと知っていてくださっていたのが、
うれしかったり。悩み相談(?)とか、ちょっとシリアスな話もできたのはよかったかな。
24:00、ホテルに帰り、風呂。就寝。
- 2006/10/7(土)
YK練習、13:00-17:00。
NC練習、17:30-21:00。
関西コンクール前日練習。さすがに疲れた。
NC練習後、いつもHさんの車で京都に帰るのだけれど、そのとき必ずNHK-FMで放送している吉田秀和
のクラシック番組がBGMになっている。で、最近気づいたのだけれど、少なくともこの二ヶ月くらいの間、
必ずといっていいほど、リヒャルト・シュトラウスの曲がかかっている。クラシック好きの人ならどうかし
らないが、マイナー過ぎるのではないだろうか。ほとんど聞いたことがない曲ばかり。合唱をやっていると、
彼の歌曲集にはよく出会うのだけれど、もし音楽に携わっていなければ、その名を知ることはなかっただろう
と思う。つまり、普通一般の人には非常に縁のない存在なわけだ。
音楽家の知名度というのは、世間一般にどの程度のものなんだろうか。そういう統計調査とかあったら見て
みたい。Hさんの予想では、ワーグナーを知っている人はいてもマーラーを知らない人は結構いるのでは?
とのこと。うーん、映画「ベニスに死す」くらいしかマーラーの曲は一般に露出しないものな。それも古い。
TVCMに曲が使われると親しみやすさがだいぶ違うのだろうけど。
あしたはとても早起きなので、今日はそろそろ休みます。
おやすみなさい。あしたはがんばろう。
- 2006/10/6(金)
BK練習、18:30-21:00。
BK宴会、21:30-24:00。
ふるふるふるむーん。
- 2006/10/5(木)
朝、起床してから3時間ほど左の耳が耳鳴り。はじめてなったのだけれど、ずーっと単一周波数のキーン
という音が、同じ音量で聞こえているのだ。ひょっとして、と思って耳を覆ってみるけれどやっぱり聞こ
えたから、やっぱり外界ではなく、内側で感じているものなんだろう。痛みがあるわけでもないし、他の
音が聞こえないほどではないから良かったけれど、両耳だったらさすがにしんどかっただろうなぁ。時間
が経つと、音量が次第に小さくなり、やがて聞こえなくなった。原因は不明。予想としては、昨日飲んだ
頭痛薬が三半規管に過剰に働いたのではないかと思う。昨日、仕事中に1回、夕食後に1回、就寝前に1
回飲んだから。一応、1日3回が限度と箱には書いてあるけど、これからは注意した方がいいかも。以前
の頭痛薬はそういうことはなかったのだけれど、同じ頭痛薬でも成分が違う(頭痛の止め方が違う)とい
うことの証左だろう。あー、やっぱり前の頭痛薬(生産中止)がよかったよ...。どこかの薬局にデッドス
トックがないかなあ。
本屋に行くと、「家守綺譚」(梨木香歩著、新潮社刊)が文庫になっていた。ぱっと見ると、うっかり見逃し
てしまいそうな淡い装丁。うーん、地味。ちょっと手にとってもらいにくいかもという気がする。ハード
カバーの時と同じ装丁の方がよかったかもしれない。というわけで、中身は同じかもしれないけれど、
文庫とハードカバーの両方があったらハードカバーがお薦め。この本は雰囲気から入るといっそう楽しめ
ると思うから。古本なら文庫と同じ程度まで下がっているはず。
ところで「対岸の彼女」(角田光代著、文藝春秋刊)は、いつになったら文庫になるんだろう。こちらは
文庫で持ち歩いて、通勤時に再読したい。
- 2006/10/4(水)
仕事で半期ごとのプロジェクトの成果、下期の計画を発表するミーティング。結構長時間にわたって
パワーポイント資料を見つづけることになるので、目が疲れるのだった。でも、ぎりぎり頭痛になら
ない中途半端さ!こういうときに頭痛薬を飲んでもあまり効かないので困るのだった。この感覚、目
が悪い人とか、頭痛持ちの人ならわかってくれるかな...。あしたの朝、時間差で頭痛が来るような
気がする。
ひさしぶりにスタンドで食事。向かいに50代とおぼしきおじさん二人組がいたのだけれど、片方の
おじさんが「いかに源氏物語はすごいか」という熱弁をふるっていた。服飾デザインに興味がある
様子。話の内容からすると、薫と匂宮のことも話していたので、全段読みきったらしい。すごい。
それから話はルイ14世の時代うんぬんになり、平安時代かそのときのフランスに生まれたかったな
ぁなんてことも話していた。もう一方のおじさんは、その時代のフランスの修道院のワイン、チーズ
の生産について語りはじめた。うーん、スタンドでこんなにインテリゲンチャな会話を聞くことにな
ろうとは思わなかった。やっぱり、ここは面白い場所だわ。
50代くらいの人の会話って、住宅ローンとか、教育とか、政治・野球の話しかないものって思って
いたし、現に会社の食堂で聞こえてくるのはそんな話しかない。歴史とか文学、芸術を語るような
ことって社会人になる前は、普通にあるんだろうって思ってたけれど、実際は全然そんなことはない。
大人はじつは大人ではない、社会人は社会人じゃないってことに、就職してすぐのころ気づいて、
幻滅したことがあったっけ。そんな風に感じる自分は青いなぁって思うけれど。
何が大人で、何が社会人って規定するのはおかしいけれど、なにか教養を感じさせる会話っていう
のは必要なんじゃないかって思うことがある。むろん、見せかけじゃなくて、スタンドのおじさん
のように本当に興味を持ってるのがわかる会話。そういう会話には、語彙やレトリックなんかの国語
表現や、プレゼンテーションの基本、話の構成力、論理力が、普通のものに比べて多い気がするのだ。
で、それを見て、聞いて育つ子供っていうのは、何かこう、いろいろなものの土台が備わるような気
がするわけです。未分化だけれど、どんな進路にも進むことができる核のようなもの。そういうこと
が社会がする教育ってものなんじゃないかって漠然と思うのだ。ちょっとうまく整理できていないけ
れど。
どうかな。
- 2006/10/3(火)

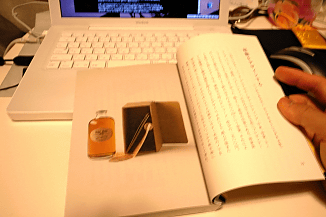
「クジラは潮を吹いていた。」、佐藤卓著、トランスアート刊。2400円。
グラフィックデザイナー佐藤卓を知らなくても、ニッカ・ピュアモルトや、ロッテ・クールミントガム、
大正製薬・ゼナ、明治・おいしい牛乳のデザインを見たことがないという人はいないだろう。NHK教育
の意欲作「にほんごであそぼ」を知らないお母さん方もいないと思う。それらのデザイン、ディレクション
を手がけたのが誰あろうこの本の著者、佐藤卓その人である。氏が独立してから20年余りの間に手がけた
デザインを一点一点、自身によって解説している。見開きの右に文章、左に写真で、4ページ構成という
シンプルなもの。まず、この本そのもののデザインにひかれる。文字のレイアウトがなんとも美しく、
読む気をそそるうえに、優美な上品さをたたえている。深沢直人の「デザインの輪郭」の装丁と同じもの
をこの本に感じた。だから、買った。そして、その文章を読んでみて正解だったと思った。
先に挙げたプロダクトは、いずれも有名でどの仕事も成功しているかのように見えるけれど、よく見れば
なかには、商品として失敗したもの、そして消えていったものも混じっている。それを語った言葉に、や
はり深沢直人と共通する言葉があった。「デザインの決定において民主主義はあり得ない」(深沢直人は
同じことを「共同でデザインする」ということはあり得ない、と言っている)。それはつまり、多くの人
の意見を取り入れることは良いことかもしれないが、結局それでできるものは「普通」のものになってし
まうということなのだ。モノにこめられた思いが、消費者に届かずに消えてしまうのだ(思いをこめる、
ことと自己主張は異なる。それをはきちがえても、やはりモノは残らずに、消えてしまう)。
と、まぁこれは佐藤氏ほどの熟練のプロの仕事であって、われわれ素人では一人でデザインをし通すとい
うことまでは、なかなか到達できない。たくさんの人の助言助力がいる。でも、それでも、何かをデザイン
することを志すならば、その助言を生かすにしても、使わないにしても、決定するのは自分でなければなら
ないと思う。そして、決定したことに責任を持つ。それが、デザインをするという行為なのだと思う。
本を読んだあと、BKの演奏会チラシに載せる地図をデザインしながら、そんなことを考えた。
ところで、表題になっている「クジラは潮を~」は一体、なんのことを指していると思いますか?ヒントは、
旧クールミントガム。答えは、本を読んで確かめてみてください。そこにこめられた著者の意図も。
ちなみに、わたしの使っている携帯電話P701iDは、じつは佐藤卓デザインだった。
本を読むまで知らなかったヨ。
- 2006/10/2(月)
今朝、ショックなニュースが飛び込んできた。コミックマーケット準備会代表、米沢嘉博氏死去。
享年53歳。なんで?どうして?一瞬理解できなかった。そのときになって初めて、わたしは代表が
9月30日付けで代表を退任していたことを準備会のHPの告知で知った。告知の内容は、7月から
入院していること、予断を許さない状況であること、さらにコミックマーケット71への参加は難し
いという悲壮なものだった。その矢先の、10月1日の死去。突然すぎる。
1975年、今から31年前、コミックマーケットの創設に関わり、1980年から代表。一般、サークル
参加併せて夏の三日間で約45万人の参加、日本でも最大規模の東京ビッグサイト全館での開催、
そんな信じられないほど大きくなったコミックマーケットを、文字通り体を張って支えていた人
だったのだ。同人誌というものによって、わたしたちに表現をするための場を与えつづけてくれ
ていた。いや、正確には、その理念からするなら、すべての参加者とともに、コミケをつくって
いた、われわれのもっとも大きな同人の一人だった。直接知らなくとも、コミケに参加するすべ
ての参加者にとって、そしてこれから参加するひとたちにとって、とてつもなく大事な精神的な
支柱を失ってしまった。ただただ、悲しくて、残念でならない。
正直、これからのコミケはやっていけるんだろうか、もうあんなイベントはできないんじゃないか、
そんな思いが脳裏をよぎった。しかし、告知には続きがあり、準備会メンバー3人による共同代表
就任の話が決まっていた。「これまでと変わらない形で続けてほしい」というのが、米沢代表の要望
であると書かれていた。共同代表となった筆谷氏(フデタニンと呼ぶ方がしっくりくる)の言葉を
借りるなら、それは「全てを受け入れ、誰も拒まない」表現の場であろうと思う。
「コミック」マーケットとはいうが、そこにあるのはもちろん漫画・アニメだけではないことは、
皆さんご存じだろう。ゲーム、評論、旅行記、メカ、ミリタリー、コスプレ、詩、短歌、俳句、
写真に至るまで、とにかくとどまることのない範疇の同人誌、それにまつわる表現物がここにある。
現に、わたしの創ってきた本は「近代建築の写真集」だ。卑下するつもりはないけれど、そういう
同人誌があってもいい、そういう表現があってもいいと教えてくれたのはコミケなのだ。コミケし
かなかった。
だから、米沢代表が亡くなっても、新しい代表と一緒に、ほかの一般・サークル参加者と一緒に、
この場を守らないといけない、続けていかなきゃならない。いま、本を創りたい!って思ってい
るであろう新しい人たちが路頭に迷うことがないように。そして、何より、本を創りつづけて、
買い続けている数多くの同人と、わたし自身のためにも。
具体的にどうするかって?決まっている。いままで同じように、全身全霊、全力を傾けて新刊を創る。
そして、コミケで売る。お気に入りのサークルの本を買う。それだけ。それが、何よりの弔いになる
と信じている。そうだろう?米やん、イワエモン。
奇しくも、今日コミックマーケット71の受付確認ハガキが届いた。
(注:申し込みが受理されたという通知。当落が決まるのは一月先のこと。)
ありがとう、おつかれさま。
ご冥福をお祈りします。
- 2006/10/1(日)
法事のため、YK練習欠席。
あさ、運動会のスタートピストルの音で目が覚める。うちの裏は中学校のグラウンドなのだ。
雨がもう降るってわかっているのにやっちゃうんだもんなぁ。来週は連休だから順延しにく
いのかもしれない。とにかく寝てられないので起きました。いや、二度寝しそうだったから
起こしてもらってよかった。20年前は運動会は普通に平日開催だったと思うのだけれど、や
っぱり、その間に働く親が増えたってことと、運動会に来たいと思う親が増えたってことが
休日開催につながっているんだろうな。しかし、小学生はともかく、中学生にもなると思春
期だから親が学校に来るのは嫌じゃないんだろうか。子供の側の意識も変わっているんだろ
うか。共働き家庭に育つと(学校行事には来られない)、どうも親が来てうれしいって感情
がピンと来ない...。
実家での法要の後、寺の墓へ移動し再び法要。
この前の墓参りのときに気づいたのだけれど、山の墓のほうが、お寺が用意(400円)して
いる「しきび」(木蓮科の常緑樹。葉を切り取って束ね墓に供える。しきみともいう)が、
生き生きとして、とてもきれいなのだ。親に聞いてみると、山の墓のものは寺の敷地内で
栽培しているものだかららしい。寺町の墓にあるのは、街中だからおそらく仕入れてきた
ものだろうけど、捨てる直前の野菜みたいに艶がなくて、ぼろぼろに近いんだもの。同じ
値段とは思えなかったなぁ。
例のごとく、実家で犬と遊ぶ。きょうは親戚もいたので、いつもより楽しそうであった。
- 2006/9/30(土)
体調不良のため、NC練習休み。
倦怠と発熱。それと腰痛が来たのは伏兵だった。テーピングで対応。そういえば、先週同期の
結婚式に行ったときに「山ちゃんはー、よう腰痛で練習休んでたなぁ~」と、その同期に言わ
れたことを思い出した。そうなのだ。土曜日の練習は新町校舎内にある新町別館で行われるの
だが、土曜日は授業がなかったので自宅から自転車で練習に通っていた。その途中に急にくる
のである、ずきーんと。もうそうなるとサドルに座っていられなくて、新町まで15分くらいの
距離なのだが、とても行けそうにない。自宅までならなんとか引き返せるかという、文字通り
腰砕けの状態で、近くの公衆電話(まだ携帯電話はなかった)に駆け寄り、クラブBOXに欠
席の電話をかけたことがある。クラブを欠席するには理由が必要で、筆頭は授業、研究室、マ
ネージだったが、「腰痛」というのはかなり異色なカテゴリーだったらしい。まぁ、まっすぐ
立てないんだから、3時間立ちっぱなしの合唱練習なんて無理なわけで十分理由に値すると思
うんだけど。
午前中、「せやねん」を見ていてふと思う。「テロップの使い方、うまいなぁ」と。これは昔
書いたかもしれないけど、TV番組で出演者の台詞をそのまま文字にして映し出すことが10年
ほど前から始まって、いまもほとんどのバラエティで採用されていると思う。あれは、いったい
どういう目的なのかって考えると、ようは出演者の滑舌が悪かったり、早口や小声で聞き取れな
いから、それを補助しているのが主目的だと思う。二次的には、誇張表現。TVタレントが、聞
き取れないような言葉を発しているという時点でおかしいし、それだけ番組が私的なものになっ
ている、制作者側の主体のなさ(出演者にしゃべらせるだけの構成)などいろいろな問題をこの
テロップの多用から指摘することができると思う。一方でMBSの「せやねん」や、ABCの
「探偵ナイトスクープ」は、テロップを台詞のために使っていない。
テロップが使われるのは、主に出演者へのつっこみや、制作者のひとりごと、出演陣がしゃべら
なかった内容のフォローなど。この「つっこみ」でわかるように、この手法は在京キー局ではな
く、在阪TV局のものなのだ。出演者の台詞のテロップは、台詞が聞き取れる場合、同じ内容な
ので見ていて冗長に感じてしまう。それに対して、後者のテロップは、それ自体がもうひとりの
出演者(制作者の意図、視聴者の代弁)となる情報なので、「見て」面白いと感じることができ
る。この差は、じつに大きい。在京のTV制作者は、そのことに気づいているのだろうか?それ
とも、東と西ではやはり視聴者が求めるものが違うのか(とはいっても、キー局の番組は全国放
送されるのだけれど。全国放送でも東中心の嗜好?指向?思考?ということかなぁ)。
出演者の台詞を再現するテロップでも、HTB(北海道テレビ)の「水曜どうでしょう」などは
その演出手法(フォント、表示のタイミングなど)によって、「面白い」ものになっており、
一概に批判されるべきものではないとは思う。それと、この台詞テロップ、音声を消した状態で
も番組の内容がわかる、というメリットは確かにある。たぶん制作者の意図した結果ではないの
だろうけど、夜中にザッピングするとき、うるさい音声をきかなくてもいいのは便利だ。では、
聴覚障害を持っている人は、この台詞テロップについてはどう考えているのだろうか?というこ
とが気になった。内容のほとんどを網羅する番組もあり、そういうものを見る場合は内容がわか
るだろうから、良いのかな?という気もする。でも、ナレーションの内容がテロップに出ること
はないし、中途半端だと逆にストレスになるのではないかとも思う。見たことはないが、時々
「文字放送」という表示がある番組があり、あれはデコーダーをつければスーパーで番組内容
が表示される仕組みだったと思う。そういうものがあるから、不要なのか、あるいは文字放送
の番組は少なくて(実際はどうか知らない)、やはり台詞テロップはあったほうがいいのか、
どっちなんだろう。
「夜のピクニック」読了。あ、「海辺のカフカ」より先に全部読んじゃった。よかったです。
非常に嫌みがない青春小説。キャラクターがとても魅力的ですな。ただ、自分の高校時代をふり
かえると、ここまで思慮深くいられたかなって、思ってしまうのは確か。それだけガキだったと
いうことかもしれないけれど。そのことがリアリティがないっていうんじゃなくて、逆にこんな
風にありたかった、って思わせるところが素敵なのだと思う。再読したい一冊。
調子にのって書きすぎました。ちょっと横になります。。。
- 2006/9/29(金)
不整脈自体は、昨日20時におさまる。5時間程度ですんでよかった。
とはいえ、そこから安眠できるかというとそうではないのだ。循環器系に負担がかかるのと、
正常に酸素を供給できなくなるので、必ず筋肉痛のような症状になる。だから、たぶん眠れた
のはAM4:00くらい。
で、きょうは体調不良のため、BK練習休み。
いつもなら、あっという間にすぎてしまう2時間半の練習時間も、うちにいて休んでいると
とてつもなく長く感じる。みんな、いまごろどうしてるんだろうか。きょうの新曲は、どん
な感じだったんだろうか。眠ることも、歌うこともできず、中途半端な時間がすぎていく。
ところで、最近写真を掲載していなのだが、理由があって、プロバイダーからわりあてられ
たファイル容量がもう1Mbyteを切っているから。こうやってテキストだけならしばらくは
保つのだけれど一枚でも大きな写真を載せるともうアウト。昔掲載した写真を削るにしても、
過去ログがきちんと参照できなくなるのはいやなので、契約を変更して増量することを検討中。
そろそろ横になります。あしたは、元気になりたい。。。
- 2006/9/28(木)
不整脈(心房細動)発作。午後になったので、回復は12時間後くらいの夜中か。
おそらく、後遺症で明日は伏せっていることになりそうです。
更新休みます。すいません。
- 2006/9/27(水)
考えてみると、最近スタンドに行ってない。ちょっと節制してたもので、足が遠のいてしまった。
食欲の秋であるから、そろそろ復帰してもよいかなと思う。
夜、窓を開け放つと虫の音が聞こえるのだけれど、いったいどこで鳴いているのだろうと不思議になる。
わたしの住んでいる界隈は、マンションのほかは呉服屋などのビルがほとんどで、まずもって公園など
の自然がない。山縁でも川縁でもない、街のど真ん中。通り一本を隔てたところにあるのは烏丸通りと
いう基幹道路なのだ。それでも、実家にいるときくらいか、それ以上の虫の音である。ベランダから
耳を傾けると、どうも向かいに見えるほんの少しの民家の庭から聞こえてくるものらしい。そうだ、
京都には緑は少ないけれど、町屋にはかならず小さいながらも中庭があるのだ。街の虫はそのわずかな
スペースをちゃんと見つけて居住しているわけだ。たくましいものだなぁ。こうして、町屋が残ってい
るうちは、マンション住まいでも虫の音が楽しめる。ありがたいことだけれど、ここに越してきてから
近隣のマンション開発が著しい。全部が全部町屋を壊しているわけじゃないが、そのうち虫の音が聞こ
えなくなるんじゃないかと心配になるのだった。
まぁ、今は何も考えずに部屋の灯りを豆電球のひとつにして、ぼーっとしながら、耳を澄ませてみよう
と思う。このまま、寝てしまってもいいさ。
- 2006/9/26(火)
BKマネージ少々。iTunesで、MIDIファイルをCDに音源として焼こうとすると、なぜかプレイリスト
から自動的に外されてしまう。うーん、読み込みはできるし、演奏もできるのになぁ。なんでだろう?
と考えて、調べたところメニューの「詳細」を開くと「選択項目をAACに変換」という項目があった。
これだ!環境設定を変えればMP3にもできるみたい。変換してからだと、ばっちり音楽CDとして焼けて
一安心。ただし、プレイリストで選択して変換すると、変換後のファイルは「最近追加した曲」にできる
ので注意が必要。プレイリストのファイルはMIDIのままなので、一度リストを削除して入れ替えないとい
けない。そのことに気づかずにCDーRを一枚無駄にしてしまった。
それにしても、MIDIファイルのAAC,MP3変換はWin時代は、ソフトをあれこれ探してと結構めんどうな作
業だったのにiTunes単独でできてしまうのはありがたいこと。CDも簡単に焼けるし、これぞシームレス
環境だと思う。そもそも一度もマニュアルを見ずにできてしまうところが、よく練られているなと感じる。
モールトンにピンディングペダルをつけることを検討する。ピンディングペダルっていうのは、専用のシュ
ーズと対で使うもので、靴とペダルを固定することができるもの。これによって、通常は踏み込みの時しか
ペダルにエネルギーを加えられないところが、「引き足」つまり、ペダルを頂点に戻すときにもエネルギー
を加えることができるようになるため、効率がぐんとアップするのだ。登坂や、長いツーリングのときには
重宝するらしい。欠点は、靴が固定されるため頻繁に停車するような街乗りには向かないこと。外すのにコツ
がいるから、慣れないとこけてしまう。ペダル自体は、普通簡単に取り替えられないので、街乗りかツーリン
グか?の二者択一になってしまうのだけれど、わたしが使っているペダルはちょっと違うのだ。輪行用に、工
具なしで取り外せるペダルで、同じようにピンディングタイプのものも装着可能。だから、使いたいときに気
軽に付け替えることができる(そうでなければ、ピンディングにするのには躊躇するところ)。
しかし、ちょっと問題。ピンディングシューズ自体、かなり特殊な靴なので自転車専門店でも、結構大きな
ところに行かないと手に入らない...。ペダルの方は、モールトンを買ったお店に在庫があるんだけれど。
靴だけは、履いてみないと相性がわからないので通販は避けたいのだ。近畿圏で近場の店を探さないとなぁ。
(自転車をこれから始める人は、ヘルメットも絶対、実際に試着することをお薦めします。頭の形はまさに
千差万別。メーカーによっては、一番大きなサイズでもちゃんと頭が入らないこともあるのです。わたしが
そうで、第一希望のメーカーのは見事に入りませんでした(泣))
今日は、ちょっとマニアックな話題ばかりで、ごめんなさい。
- 2006/9/25(月)
雑誌「Pen」10/1号の特集は「オランダの旅へ」、オランダデザインを巡る旅である。オランダというと
ディック・ブルーナ(ユトレヒト在住)が有名だけれど、首都アムステルダムの建築、都市計画もかなり
魅力的だということに気づかされる。ヨーロッパのなかでも、なんというかとりわけ上品で明るい自由奔放
さ?のようなものが、プロダクトデザインや、グラフィックデザインからも感じられた。オランダは大部分
が干拓によってできた平地。ゆえに自転車王国なのはよく聞く話で、この特集にあるようにサイクリングコ
ースを走りながら、建築散歩をしてみたいなーと思う。
で、Google Earthを使って、特集地図と見比べながらアムステルダムの街を覗いてみた。衛星写真だから
文字通り、空から覗いている気持ちになる。おお、これぞ計画都市というべきか。運河が同心円(正確には
多角形)状に張り巡らされ、まさしく水辺の街という趣。中央駅自体も、本当に島というか埋立地の上にあ
るのがよくわかる。ん、これはなんだろう?駅の東南東に広がる台形の土地の部分がモザイクで覆われてい
るではないか。この部分だけ映像がないのか、いやそんなはずはない。たぶん、意図的に隠されているのだ。
当然、なんなのか気になる。Google Mapで調べてみても、土地の部分が台形にぽっかりあいているだけで、
説明が一切ない。オランダの観光地図をネットで探しても、その部分を説明したものはない。だいたい、
その近辺は再開発地区らしく、一般的な観光スポットではないのだ(Penの特集的にはスポット目白押し)。
あからさまに怪しい場所だけど、考えられるのは王室関係か、軍関係、原子力発電所くらいだろうか。ネット
で見たニュースでは、オランダをはじめとするいくつかの国は重要施設の衛星写真を非公開にするよう、Google
に申し入れ(というか抗議)しているらしく、モザイクはそのためのようだ。日本なんか、皇居をはじめと
してあちこち見放題なんだけれど(米国も)。大丈夫なんだろうか、そんなに見せちゃってと心配になる。
ところで、ヨーロッパで行きたい都市がほかにふたつある。ひとつはポルトガルのリスボン。もうひとつは、
スペインはバルセロナ。リスボンには、有名な黄色いトラム(路面電車)が走っているからということと、
ポルトガルというヨーロッパの西の果てを見てみたいという思いがある。日本に鉄砲を伝えたのは彼の地な
のだ。バルセロナに行きたいのは、言わずとしれたガウディのサグラダファミリア聖堂をこの目で見たいから。
1882年の着工から、120余年。未だ完成せず、なおも建築中。こんな建物がほかにあるだろうか。ガウディ
のフニクラ(糸の両端を固定し、つり下げたときにできる形を上下逆にしたもの。力学的に安定した形)を
具現化したこの建築を、自分の目で確かめたい。複雑怪奇に見える、あの装飾を、なぜこんなにも美しいと
思うのか。その答えが知りたい。目の前にすれば、わかるかもしれない。そんな風に思っている。
夜、トレーニング。30分、約9km。だんだん登坂能力が上がってきたみたい。
帰り道、御池通に面したイタリアード本社ビルを、ツーリストらしき欧米人男性がずーっと、視点を変えて、
距離を変えては眺めていた。ちょっと変だったけど、建築好きなのか?
- 2006/9/24(日)
6:40、起床。
7:00、朝食。
7:30、チェックアウト。駅へ向かう。
8:11、長野発。ワイドビューしなの乗車。
11:06、名古屋着。酔った。
11:17、名古屋発。新幹線のぞみ乗車。新幹線の直進性の高さを体感する。
11:53、京都着。
12:05、近鉄京都発。奈良行き特急乗車。車内で昼食とドーピング。
12:42、近鉄奈良着。
13:00-16:45、YK合宿@奈良YH参加。
18:00、帰宅。帰りの車、くしくも全員BKメンバー。わいわい話したせいか、酔わず。体調そこそこ回復。
じつは練習開始時、立てなかった。ドーピングのおかげで、2クール目から立ち直る。
しかし、あれだ。長野に行ったというのに、善光寺に行っていないというのは、いかがなものか。
夕食後、ねむねむ。早めに眠ります。
おやすみなさい。
- 2006/9/23(土)
長野県にてグリー同期の結婚式に参列。
7:22、京都発。新幹線ひかり乗車。
8:15、名古屋着。ホームできしめんを食べる。
9:00、名古屋発。ワイドビューしなの乗車。中央線で長野へ。
11:58、長野着。姨捨はやはり絶景。が、そこから篠ノ井のあたりまでのカーブの連続で酔う。
12:25、ホテル着。徒歩15分は結構遠かった。渡された地図がわかりにくい。
13:00-15:30、披露宴。同期でカレッジソング、斉太郎節を歌うことに。10年ぶりに歌う者多数。
歌詞を覚えていないというので、カタカナで歌詞を書いてやる。けっこうめんどくさい。書いたら
書いたで、カタカナだと読みづらいという。えーい、だったらと英語で書く。めんどくさい。料理
が食べられないじゃないかー。演奏、新郎がいきなり4番を歌ってしまい、終わりそうになる。とほほ。
16:30-18:30、二次会。新郎が司会者にかわってマイクをにぎりっぱなしで、進行までしてしまう。
ああ、本当にうれしいんだな奴は。うらやましいことだ。
18:30-21:30、三次会欠席。ホテルにもどり入浴。YKの曲を暗譜する。
21:30-24:00、四次会に呼び出される。ホテルのバーで歓談。同期ってやっぱりいいなと再認識。
唯一しらふのため、会計をするわたし。BKの宴会と立場が変わらん。
24:00、就寝。
- 2006/9/22(金)
BK練習、18:30-21:00。
BK宴会、21:30-23:00(途中退席)。
練習場(教会)に向かう途中のバスから見える夕焼けがとてもきれいで、思わず友人にメール。
心動かされるものは、自分だけで感じるんじゃなくて、誰かと分かち合いたいと思うのだ。
夕方だと背広上下は、やや暑かった。帰宅時はちょうどいい感じだったけれど。いまの季節が
いちばん服装に困る。
練習後、教会の長椅子を動かしているときに右上腕部+脇腹がつってしまって5分ほど悶絶。
普段、あまりつかわないところだからなぁ。それにしても、ちょっと情けない。
そういえば、今日で京都シネマでの「時をかける少女」の上映が終了。結局、東京で1回、京都で2回
見たのだった。何度見ても、いいものはいいです。映画本編以外で印象に残ったのは、東京と京都では
笑いが起きるポイントが違ったこと。それから、最後に見に行ったときは、あまり笑いがなくて、どう
もリピーターが多くを占めていたようだということ。最近の映画では、洋画でもそんな現象はあまりな
いと思う。それだけ、見る人の心に響く映画なのだ。DVD化、レンタル開始の際は、是非皆さんご覧く
ださいませ。
明日早いので、きょうは早く寝ます。
おやすみなさい。
- 2006/9/21(木)
昨日の晩のタモリ倶楽部で「鉄道マージャン」なるものをやっていた。企画したのは、鉄子にも
登場したホリプロの南田マネージャー。もちろん、セットであの鉄道アイドル豊岡真澄も登場。
いやー、実物をはじめて見ましたが、とても親しみやすい感じ。こんな子が「EF63の運転免許を
とりましたっ!」(注)なんて言っちゃうんだから、世の中捨てたもんじゃないですなー。マー
ジャンの方は、通常の牌ではなく数字が含まれる駅名が貼付けてあるというもの。たとえば二条
城前とか、麻布十番だとか、三軒茶屋など。マージャンと違うのは、十も使って良いことと三つ
の牌の種類がないこと。で、どうやってやるかというと同じ数字でそろえたり、連番にするとこ
ろは同じなのだけれど、役が違う。駅名をJRでそろえる、私鉄でそろえる、同じ線でそろえると
いうような鉄道に因んだ役作りをしないといけないらしい。といっても、役を決めるのは南田さ
んなので、上がるたびに「判定」するという珍妙なことに。だからただの平和の方が役満よりも
点数が高かったりする。鉄道なだけにしゃべっているのは終始南田さんとタモリで、あとの二人
がだまりがちだったところが笑えた。あんなマージャンだったら、わたしでも勝てそうだなぁと
思って見ていた(ちゃんとしたマージャンをやった経験なし。たぶんカモられる体質)。
注:「碓氷峠鉄道文化むら」にて、座学と実地の講習(本当に機関車を運転する!)を受けると
取得できる。敷居が高いので、よほどのマニアでないと挑戦しようと思わない。
夜がめっきり寒くなってしまって、コンビニの帰りに自転車で風を切りながら走っていると、
ふと、とてつもなく心細く、寂しいような錯覚に陥ることがある。日の暮れた見知らぬ街で、方向
がわからずにうろうろしているときのような、キャンプに来て山のなかでひとり置き去りにされて
しまったような、そんな感じと似ている気がする。こういうのを人恋しいというんだろうな。そし
てそれが秋っていう季節なんだ。いつもは、そんなことに気づく間もなく秋になり、冬になってい
たけれど、今年はなんだか、ゆっくりとじんわりと夏から秋に変わっていったから、そんなふうに
思うのかもしれない。こんな風に秋を感じたことは、これまであまりなかったなー。
長袖の服、ひっぱり出してこないといけない。
- 2006/9/20(水)
午後一、墓参りに行く。家の近くからバス一本で行けるのだけれど、今回は自転車で行くことにした。
行きは始発だから問題ないのだが、帰りが問題。一時間に一本しかないのだ。なにしろ山の中なもんで、
タクシーに乗ろうにも電話で呼ばなければ来ないのだ。京都市内にもそんな場所はあるのですョ。
それで、往復所要時間は1時間34分。往復走行距離は23.8kmと、思ったよりも近いものだった。
行きはずっと登りだけれど。寺につくと、彼岸の入りとはいえ平日なのに結構な数の人がやってきていた。
着いたとき、ちょうど施餓鬼法要が始まるところだったけれど、一時間近くかかる行事なので今回は遠慮
させてもらう。「お塔婆」自体は後日、母親が参ったときに書いてもらうだろうから受付はせず、直接墓
に向かった。
おもりものは、コンビニで買ったどら焼きと、大福。来る途中でお餅屋さんをいくつも見つけて、そこで
買い直そうかと思ったのだけれど、結局持って帰らないといけないのでやめた。お参りに来ている人を見
て果物がないことに気づいた。だめだね、いつも親に任せっきりだとこういう細かいことを忘れてしまう。
でも、飲み物だけはいいのを買ったつもり。アサヒのプライムタイムという青い缶のビールだ。「とても
おいしいらしいから、三人(祖父、祖母、父)で飲んでくれよう」と言う。父は酒に強いわけではなかっ
たが、外で宴会があればビールは飲んだし、ほろ酔い加減くらいにはよくなっていた。わたしは、未だに
ビールは飲めないし、まして酔っぱらうこともない。こと酒に関しては劣性遺伝子ばかり引き継いだみた
いだ。
帰り、烏丸を南下せずに寺町まで行く。こちらには母方の寺がある。母方の祖父母はわたしが生まれる前
に亡くなっていたので、祖父母との縁はここの墓にしかない。だから、子供のころ母に連れられてこの墓に
参るのは「よそ行き」であり、特別で大事な行事だったように思う。母方は三姉妹なので、この墓を継ぐ者
はいない。京都にいる限りは、母に続いて、孫であるわたしや妹が守っていこうと思っている。
きのう、iTunesをver7にした後、storeのポイントが300円残っていたので、Every Little Thingの
「スイミー」を買ってみた。あ、別にわたしはELTのファンとかではないのです、え、そんなのはわかって
るって?たまたまチャートの上位にあって、視聴してみたらとても良い感じの曲だったので。で、ファンで
はないけれど、ELTを知らないわけじゃないので、持田香織の歌い方がえらく変わっていたのには驚いた。
どうもそのことで、ファンの間でも賛否両論があるようでiTunesの評価はあまり高くない。わたしが思う
に、昔の透明で伸びやかな歌い方は、どうも彼ら自身の曲や歌詞を受け止めるには幼い感じがして、その
せいもあってそんなに積極的にELTを聞こうとはしなかったようなところがある。でも、今の歌い方は、
たとえそれがYUKIやCHARAみたい、と批判されようとも、彼女の地の声と今の歌にはとてもしっくり来て
いるように思うのだ。スイミーが収録されているアルバムCrispy Parkを全部試聴してみて、ほかの曲も
買いたいなと、ファンでもないわたしに思わせるものがあった。グループとして良い方向にすすんだんじゃ
ないかなと素人目にはうつるのだけれど、どうでしょう。ところで、「スイミー」ってどういう意味なんだ
ろうか。「♪よっく食べる~、スイミー」(金魚の餌のCMソング)しか思い浮かばない。。。
夜、TVを見ていると、バラエティー番組に石原さとみと田畑智子がゲスト出演していた。舞台の宣伝らしい。
しかし、トークコーナーにも関わらず、話題はすべて石原さとみに集中!おいおい、それっておかしいじゃ
ないか、なぜ田畑智子の話をしない。というか、もっと田畑智子を映しなさい。彼女の方がきれいでかわい
いじゃないか、くそ~。というわけでわたしの主観と世間様(TV)はどうも相容れないみたいです。
- 2006/9/19(火)
わたしは普段iPod shuffleで音楽を聴いているのだけれど、これはWinマシンのときから使っていたもの
なので、その初期セットアップはWindowsXPで行っている。そのためか、MacBookに移行してからiPodをUSB
端子に差しても無効なデバイスとして認識されて、iTunesによる音楽の入れ替えができないという問題が
あった。おそらく初期化か何かすればいいのだろうけれど、面倒である。この面倒というのは、わたし個人の
性格によるものが大きいけれど、あながち間違った感情ではないのじゃないかと思う(正当化?)。という
のも、PCを仲介して使う電子機器、つまり大きなくくりで見るとコンピュータの一種として、同じ規格の
接続端子を用いながら、それが一方では使えて、一方では使えないというのはインターフェースのあり方と
しては問題なのではないかと思うからだ。なかには、そういう困難を技術的に解決することに喜びや、使命感
を感じるひと(メーカーの技術者ではなくて)もいるかもしれないが、こういった音楽機器を使う大多数の
ユーザーはPCの技術的なことには興味がなく、ただ音楽を聴くために使っているのだ。
個々人が技術的な興味を持つことを否定するわけではないが(むしろ、わたしはそちらの部類の人間)、
PCという、ある意味敷居の高いものの存在を感じさせることなく、機能を提供する裏方のみ役割を十分に
果たすもの、それが一般ユーザーにはもっとも必要とされる。機器を使うために、別の機器(PC)の使い
方を考えなければいけない、それはインターフェースではないだろう。人間と機器が一対一に対応するため
のもの、それが真だと思う。そして、そのことをよくわかっているのがAppleというメーカーなのだ。Apple
はMacという「ハード」と同時に、MacOSという「ソフト」を作っている。OSとはつまりはインターフェース
に他ならない。同じ携帯音楽機器を作っているSONYや、Panasonicは言ってみれば「ハード」のメーカーで
あり、ことPCを媒介とするインターフェースに関してはそれほど長じているわけではない。これらメーカー
製のバンドルソフトが決して使いやすいものではないことは、わたしに限らず多くのひとが経験していること
だと思う。
だからこそ、この問題を解決するのはApple自身でなければならない。インターフェースの研究に力を入れて
きたメーカーとして、WindowsからMacに移行したくらいでiPodが使えなくなるなんてことはあってはならな
いはずだ。ユーザーの、人間の手をわずらわすようなことは、すなわち敗北なのだ。Windowsユーザーの取り
込み戦略上からみても、都合のいいことではないだろうし。
なんてことは後付で考えたことで、この問題は今日あっさり解決された。発表されたiTunesのver7をダウン
ロードしたところ、あっさりiPodを認識のうえ、新しいセットアップファイルが自動的にダウンロードされ、
初期化まで完了。もちろん中身の音楽ファイルはそのままに。これまで通り、音楽ファイルの入れ替えが可能に
なった。不備のあったインターフェースがきちんと改善されたということだ。このことは、iPodを認識しなかっ
たことに対する不満を上回る、一種の感動というか感心をわたしのなかに生んだ。やるなApple、そうでなくっちゃ、
という感情。こういうことの積み重ねが、MacやAppleに対する信頼を高めていくのだろうな。
今、Windowsマシンを使っている人で、もしWindowsでなければできないことをやっているのでなければ、
次のマシンはMacにした方が良いと思う。見た目のかっこよさとか、流行とか、そんなことは全然関係ない。
大切なのは、インターフェース。ストレスなく機械・機器とつきあえるためのインターフェースがMacには
確実にある。
明日は休みをとって、彼岸の墓参りに行く予定。この週末は、忙しくていけそうにないから。
この10月には三回忌だ。早い。
今日のトレーニング:30分、約9km走行。
- 2006/9/18(月)
NC合宿。
午前、奈良YH。午後、奈良青少年会館YH。
7:00、起床。
9:00-12:00、練習。
13:00-16:00、練習。
起床、何かを考えるまえにまず食堂へ。覚醒しないまま、結構なボリュームの朝食。きょう一日の練習に
耐えられる気力残量を自らに問う。血糖値が上がったせいか、起床後よりまし。でも、ぎりぎりのライン
か。練習開始前にオロナミンCを飲んでみる。ちょっとすっきり。
セカンドの一部のメンバーは5:30から隣接する野球場のスタンドで早朝練習をしていたらしい。朝に強い
人がうらやましいなー。
今年は曲に関するプレッシャーが例年の3分の1、昨年の同時期の合宿における10分の1程度であった
ためか、過剰に疲労することはなく練習を終えることができた。なので、この睡眠不足がなければ、もっ
とアグレッシブにできたかもしれず、それだけが残念。ただ、わたしは自分自身で歯止めをかけるのが苦
手なので、かえって今日くらいのテンションの方がよかったような気もする。
とにかく寝不足にはかわりないので、きょうは早く寝ることにしよう。
あした起きられるか(たいがい、起きられない...)。
- 2006/9/17(日)
NC合宿@奈良YH。
15:00-18:00、練習。
19:00-21:00、練習。
21:50-24:15、懇親会参加。
24:15-25:00、読書。
25:00、就寝。
YHの好きなところは、多くがカーテン付きの二段ベッドである点。カーテンを閉じるとそこは狭いな
がらも一人きりの空間。この狭さ加減が秘密めいて、ちょうどいい。寝台列車に乗っている気分。しか
しいいことばかりでもなかったのだ。
取り立てて部屋が寒いわけでもなかったのに、懇親会でお茶を飲み過ぎたせいか、就寝後一時間の間に
3回もトイレに行くはめに。そんなこんなで寝付けないうちに相部屋のメンバーが帰還し、わたしより
さきに寝始めたのであった。けっきょく、なかなか眠れず。寝不足のまま翌朝を迎えるのだった。耳せ
んしてたのになぁ。
- 2006/9/16(土)
NC練習はお休み。
YK練習、18:00-21:00。
朝、ご飯を炊いていなかったので、久しぶりにトーストでも食べるかと思い、コンビニへ買いに行く。
コンビニで弁当を買うと、あのお決まりの台詞「お弁当温めますか?」を言われるのだろうが、普通の
買い物の場合はむろん何も言われない。そうすると、いつもは家で温めるからそんなこと聞かんでもえ
えのになぁ、返答するのが面倒だなぁと思うだけれど、かえって何も言われないことに物足りなさを感
じるときがある。で、頭の中で目の前の店員が「トースト焼きますか?」っていったら面白いだろうな
ぁなどと考えてみるのだった。
皆さんは文章を書くとき、あるいは何か作業をするとき「ながら作業」ができるタイプだろうか。たと
えば音楽を聴きながら何かをするということはわりと多いのかもしれない。わたしはだめなのだ。音楽
を聞きながら文章を書いたり、マネージをしたりができない。これはTVでもだめ。気が散りやすい性
質というか、ひとつのことしかいちどきにできない不器用さというか、その別のものに思考がひっぱら
れてしまうのだ。より感覚に訴えてくる方に。音楽だと、ビートの遅いものなら大丈夫か?と思うのだ
が、それはそれでゆったりと音楽に聞き入ってしまうようだ。いま書きながら試しにネットラジオをつ
けて実験してみてわかった。
だから、ほかのひとが音楽を聴きながら、TVを見ながら勉強したり、文章を書いたりしているのをみ
ると、なんでそんなことができるの?と感心するのと同時に、そのことにどんな作用や効果があるのか
を聞いてみたくなる。より集中できたり、効率が上がったりするのだろうか。外界の音を遮断する目的
があるとすると、その音楽自体はどうやって感覚のなかでフィルタリングするのか興味深い。外界音の
ほうが、ある意味日常にあふれている音で聞き慣れているがゆえに、自動的にフィルタリングされやす
い気がするのだけれど。しかも外界音は意味をもっていないが、音楽は意味を持っている分だけ感化し
やすい、つまり集中力を阻害しやすいのではないだろうか。うーん、実は効果があるような気がするの
は心理的なもので、じつは何も聞かない状態のほうが効率はいいということはないだろうか?誰かそう
いう研究をしている人いないのかな、と思う。
- 2006/9/15(金)
BK練習、18:30-21:00。
BK宴会、21:30-23:00。
最近、通販でものを買うときに通常の宅配便ではなくて、小さいモノや薄い書籍の類はメール便を
利用することができるので便利だ。送料が安くなるし、何より不在の場合でもポストに投函される
から受け取りが確実にできる。きょうも頼んでいた本が送られてきていた。実家にいるときは、う
けとりを気にする必要は当然なかったのだけれど、ひとり暮らしになると結構めんどくさい。そし
て逆にひとりぐらしするようになってからの方が通販することが増えたように思う。一番いいのは、
日中は職場に配送してもらうことなんだけれど、さすがにちょっとできないのだった。各戸に専用
の宅配用ポストがあるマンションに住みたいものだ(共用のはあるが、仕組みが簡単なので占有さ
れているケースが多いのです)。あるいは、通勤途中の駅などに宅配受け取り用ロッカーを業者が
設置したりしないだろうか。住所に「阪急烏丸駅○番ロッカー気付」とかけばOKなような。
- 2006/9/14(木)
事情でPCに向かうことができなかったので、二日続けて更新休ませてもらいました。
すいません。ちょいときつめの頭痛もあったので。グランドール(頭痛薬)が製造中止になってから、
自分にあった頭痛薬がなくて、ちょっと困っている。ちょっとどころか、かなり切実。
- 2006/9/13(水)
やたら眠たくなってしまって、更新する時間のまえに寝てしまいました。
ごめんなさい。
- 2006/9/12(火)
メガネの左のつるが内側にねじれてしまって、耳にひっかける部分が耳の後ろの骨に当たって痛い、という
夢を見た。手で外側にねじり直すのだけれどうまくいかないのだ。メガネを変えたいという願望か?
つづけて、先斗町よりも狭い迷路のような通路をぐるぐる回って、食事できる店を探すという夢を見る。こ
ちらは昨日録画で見た名探偵コナンスペシャルの影響かも。四国の金比羅座という日本最古の芝居小屋が舞
台だったのだけれど、劇中でも紹介されていたが表舞台は芝居のための仕掛けが多数あり、裏舞台は輪をか
けて入り組んた通路構造になっているのだ。ストーリーを見ながら「あー、見学(探検)したい」といつも
の癖で考えていた。食事が絡んだのは、さぬきうどんを食べるシーンがあったからだな。
YKのコンクール曲のラテン語訳をやってみたのだが、最後の一節がどうしてもわからず。NCのM川さんに
教えてもらう。psaliteと、psalmiという「詩編」と関係がありそうな単語が二つでてくるのだけれど、
活用されているようでネットの辞書では判明せず。同様の歌詞も見つからなかったため。psalmiは「詩編の」
という意味。これはなっとく。で、もう一方psaliteは、psalmiの基本形psalmusから来たpsalloという
動詞の命令形(書いていて、こんがらがりそうになった)で「竪琴や楽器を用いて賛美する」だそうだ。
なので、歌詞にある”psalite in cithara”の"in cithara"つまり、「竪琴で」は冗長表現ということ
になるらしい。でも、逆にこのcitharaがあるから、「竪琴で賛美する、かな?」と予想できたので、なか
ったら本当にちんぷんかんぷんだったろうと思う。
ということで、似た単語でも意味はかなり違うことがわかった(M川さん、ありがとう)。属格の名詞と、
動詞だから当然だけれど。やっぱり類推だけでは限界があるなぁと感じた次第。欧州系の言語は格変化する
ものがほとんどで、これがわからないと辞書すらひけない。学部時代にやったドイツ語でも苦労したし、NC
でスロヴァキア語の曲を訳したときもそうだった。スロヴァキア語→日本語の辞書というのは図書館になくて、
結局スロヴァキア語→英語の辞書を使ったのだけれど、判明したのはごく一部だった。結局、CDの解説につい
ていた英語の歌詞を団員が見つけて、そこから和訳ということになったと思う。まぁ、そういうものを見つけ
てくることも含めて、対訳、逐語訳というものはセンスのいる作業だなぁと、あのとき自分でやってみて思っ
たのだけれど、今回はセンス+語学基礎力が必要なんだと改めて思った次第。
夜、40分、10kmほどモールトンで走る。トレーニングのつもり。風が涼しいので外気による汗をかかないの
はありがたい。これで合唱に必要でわたしにないもの、持久力や背筋が鍛えられるはず。いままで毎年4月ご
ろ(演奏会前)と、9月ごろ(コンクール前)に筋トレ願望が目覚めていたけれど続かなかった。今回は季節
もいいし、なによりモールトンという相棒がいる。無理はせず、でもちょっとがんばってみようかなと思う。
- 2006/9/11(月)
いつ眠ったかはわからないけれど、とりあえず少しだけ眠れたみたいです。例のごとく変な夢を見たような
記憶。どこでも、どんなに明るくても、どんなにうるさくても、そしていつであろうとも、随時眠りにつく
ことのできる人をわたしは尊敬している。家族のなかで寝るのが苦手なのはわたしだけだったから余計にね。
ああすごいなーって素直に思うのです。宴会の帰りの電車で、さっきまで話をしていた友人が、あいづちを
打つともう寝ていたときにはえらく驚いたけれど。のびた級だった。
「ニシノユキヒコ~」の次に読む本を買ってきた。
・「ハチミツとクローバー」第10巻(完結)、羽海野チカ著、クイーンズコミックス。集英社刊、400円。
いちばんの、あるべきところに収束したというべきなんだろうか。不覚にも涙ぐみそうになってしまった
(我慢した)。
・「夜のピクニック」、恩田陸著、新潮文庫。629円。
ある高校で行われるイベント「歩行祭」。全校生徒が一晩かけて80km歩くというもの。その道行きに凝縮
された永遠の青春。第2回本屋大賞受賞作。映画化されたということを本屋のポスターで見ていて、じゃあ
そろそろ読みたいなぁと思っていたら、ちょうどそれにあわせて文庫化されたみたい。
「歩行祭」(実在する)こそなかったけれど、思い返せばそれなり青春を燃焼させることはあったなーとい
うことに、いまさらながら気づいた。つらいこと、しんどいことばかりじゃなかったんだ高校時代。
・「海辺のカフカ」上巻、村上春樹著、新潮文庫。705円。
まったく予期してなかったのだけれど、ぱっと目にその表紙が飛び込んできて、気づいたときには手にとっ
ていた。本を買うときってそういうことがあるもの。いまはちょうど村上春樹文体と波長があっているよう
な気がするので、天の導きか(?)。まずは、こちらから読むつもり。
きょうは、ちゃんと眠りたいな。
- 2006/9/10(日)
YK練習、13:00-17:00。
最近は、NCでも4時間練習が定着してきている(最初1時間は基礎練習)けれど、YKの練習と比べると、
どうも全体の密度が微妙に異なるような気がする。うまく言えない。もし、YKが土曜日の晩に、NCが日曜
日にあったとしたら感じ方がまた変わるのではないかと思う。んー、そうか。普段の練習がない日曜日の
午後と違う過ごし方をしているからだ。規則正しく、有意義で中身の詰まった休日の4時間というのはあま
り、わたしの場合ないものだから。きょうは帰宅後、頭痛はなし。YKの練習に体が馴染んできたのだ。
帰宅途中の阪急で「ニシノユキヒコの恋と冒険」(川上弘美著、新潮文庫。438円)を読了。川上弘美の
近作のなかでは筆頭にあがる傑作であると思う。主人公ニシノユキヒコと交情のあった十人の女性によっ
て語られる彼の生き様は、切ないというよりも、どこか滑稽にさえ映る。でも決して馬鹿にすることので
きない真剣さも含まれているようで、そこがなんとなくやっかいだ。小説のなかで描かれる感情というも
のはストーリーの進行上、必要に迫られた感情ではないか?と後になって思い返す(読んでいるときは気
づかないもの)ことがあるけれど、この連作集に登場する女性のそれは、とらえどころがなくて、どんな
ことを考えているの時々わからなくなる(とわたしは時々思う)、そんな現実の生に近いものをそのまま
転写したかのような、機微にあふれる通り一辺倒でない感情(表現)なのだ(いや、正確にはそんな気が
するだけなんだけれど)。その描写にときどき、はっとさせられたりどきっとする。こころのありようは、
じつは難解な比喩表現で表されるほど複雑ではない。普通の言葉で、修辞もなくあらわすことのできるも
の。でも、ただそれが幾重にも重なったり、相反する気持ちが同時に存在することがあるから、複雑にみ
えるんだ。この小説を読んでいると、そんな気がした。
追記:
参った。何が原因がわからないけれど目がさえて眠れない。体は適度に疲れているはずだし、床につく
前には眠気もあったはずなのに。きょうは、練習に行く前はどういうわけか眠くて仕方がなくて、絶対
早く寝ることになるだろうなぁと思っていたのだけど。昼前に飲んだ栄養ドリンクがまずかったのか?
しかし、今までもよく飲んでいたものだし、眠れなくなったことはなかったのだけれど。第一夜中まで
効力があるのか。たしかに、一日心臓の動きは活発だったような気はするが。うーん、食べあわせとか、
今飲んでいる漢方薬との組み合わせが悪かったのか??とにかく困った。眠りたいよ。。。助けてくれー。
- 2006/9/9(土)
NC練習、17:30-20:45。
午後一、実家に帰り犬と遊ぶ。というか犬に遊ばれている気がしないでもない。いつも、わたしが実家に
帰ると犬と遊んでいる話しか書かないけれど、母親とも話しをすることはあるのだ。たいがい、日本画か
陶器のことなので、ここでは詳しく書いていないだけ。周りにはそういう話ができる人がいないので、じ
つにつまらん、と最近よくこぼしている母である。実用にならないか、お金にならないことには目を向け
ないひとが増えているのは、なにも若い世代だけの傾向ではないらしい。美はきどったものではなくて、
市井の生活の中のそこかしこにある。そういうものにセンシティブであること、そのことを幸せだと感じ
られるようになりたいと、いつも思っている。道はなかなか遠くて、日々修行。
残暑が厳しいのだけれど、そのことは我が家のお茶の消費量からも察することができる。麦茶パックが
切れてから、番茶を沸かすようになったのだけれど、これがだいたい一日でなくなってしまう。だいた
い1リットルくらいだろうか。二番煎じまでは飲むことにしているので、二日に一回はお茶っぱを新調
せねばならないし、お湯などは毎日沸かしている始末である。お茶は安いものだからいいにしても、光
熱費が馬鹿にならないような気がする。それでもまぁ、コンビニで買うようりかは安いんだろうな。
いつも買っている弁当屋の包み紙には、何かしら文章が書かれている。5月くらいだと「若鮎の踊る季
節」とかそんなのだ。きょう見てみると「真っ赤なトマトが美味しい」と書かれていた。そうなのだ。
この残暑を乗り切るには夏野菜を食べて、体を冷やすのがいいのだ。中国医学では食物に温と冷がある
といい、旬の野菜を食べることは実は理にかなったこととされている。日本でも当然そうだろう。で、
トマトに話を戻すと、期間限定でCoco一番屋にトマトとアスパラのカレーが登場し、これが最近のお気
に入りなのである。アスパラが歯ごたえを提供するのみの役割なのが残念なのだが、カレーに半ば溶け
かかったトマトの方は、とんでもなくマッチしているのですよ。辛さのなかに、ほのかな甘さと酸っぱ
さを混ぜ込んでいて、これが美味しいのです!思い出すだけで唾が出てきそう。あんまりに鮮烈なので
続けては食べられない。できればインターバルは一週間くらいはおきたいと思う。あー、でももうすぐ
限定期間が終わっちゃうな...。秋本番になれば、また限定の肉じゃがカレー(これも大好き)が出て
くるだろうから、それまでは我慢我慢なのだ。
- 2006/9/8(金)
BK練習、18:30-21:00。
BK宴会、21:30-23:00。
BK宴会の帰り、少々暑かったのでこのまま歩いて帰るのはしんどいかもなぁーと思い、途中でタクシーに
乗車。わたしとしては珍しい。そのタクシーの車内で、運転手の趣味なのかハワイアンが流れていた。
いままで意識して聞いたことはなかったのだけれど、なんというかこの音楽は本当に楽天的というか、
あっけらかんとしているというか、こころに波風を立てず、表面をすーっとなでていく風のように、過度
に心を癒すような効力もなければ、もちろん悲しみに誘うようなものでもない。天気のいい午後の波打ち
際や、あるいは夕日の浜辺で、頭を空にしてただ目の前の景色と、波の音をあるがままに感じるときに、
ともにある音楽、そういう感じがした。平たくいえば、小難しい考えでかちこちになりそうな頭をくにゃ
っと、一瞬でときほぐしてしまう音楽なんだな。今日、練習したLauridsenや、Kreekの美しい旋律すら
忘れてしまいそうになる。美しい音楽を奏でることは、そんなに簡単なことでも楽なことではないもの。
だから、ときには何も考えずに、ただ流れてくる音楽に身を任せて、ふわふわと流れていってしまいたい、
そんなふうに思うときがある。そういうときがあってもいいと思う。タクシーを下車してから、そんな風
に思った。
- 2006/9/7(木)
どうやったらフランスパンをきれいに食べられるのか?ということについて考えていた。食後、フランス
パンを食べながら(デザート)。
まず食べ始めの千切る段階でパンくずが大量に落下する。そして口にしている間も外壁(?)の固い部分
がポロポロと削りとられてこれまた落ちていく。この部分は床に落ちれば掃除がやっかいなことは皆さん
経験おありだろう。かといって、口もとにビニールや、パンが入っている紙袋を添えながら食べるのはな
んとなく不格好だし、なによりパンを味わうことよりも、屑が周りに落下しないようにすることに気が奪
われてしまうと思うのだ。それではフランスパンを食べる意味がないじゃないか(おおげさ)。
はて、さてと思案して考えたのが、テーブルいっぱいに新聞紙を広げることだ。こうすればあとの掃除の
ことを考えずに、もりもり食べられるじゃないですか。さっそく、実行。で、あっと気づいたわけです。
普通はどうするかということに。千切って皿の上で食べればいいんじゃないか、レストランでライスかパン
かで、パンを選んだときに出てくるあのフランスパンのように!
あまりに当たり前のことに気づいていなかったというか、パンをそうやって食べてないわたしの常識のな
さに愕然としてしまったのであるが、いやいや、考えなおしてみると、フランスパンを一人で全部食べきろ
うとするスタイルの場合、皿に盛るのは無理があるわけで、そこに普通の発想を求めてはいけないのではな
いかと。無理矢理正当化してしまったけれど。フランスパンを千切っては食べ、千切っては食べするスタイ
ルの確立に明日も挑みつづけていくことにしよう。
え、行儀が悪い?そうですね、人前では注意します。
- 2006/9/6(水)
MacBookで使っているソフトの話をしよう。MacBookにはiSightという小型のカメラがついており、
これを使って顔写真を撮影したり、互いの顔見ながらチャットできたりするのだが、実際のところ
ほかにあまり用途がなかったりする。で、これはもったいないなー、何か有効利用しているソフトは
ないかと思って先月号のMacPeopleを読んでいて見つけたのが、"Delicious Library"というソフト。
このソフトは書籍や、DVD、ゲームについているISBNコードを読み取って検索し、タイトルや著者、
値段などの情報を得て、それらをデータベース化できるというもの。いってみれば蔵書録作成ソフト
なのだ。で、そのISBNコードの読み取りに、iSightを使うのである。
ソフトを立ち上げるとカメラ画面が表示され、ここに本の裏側についているあのバーコードをかざ
すと「ピッ」という、レジでおなじみのあの認識音が鳴って、読み取り→検索が瞬時に始まる。こ
のソフトの面白いところは、得られるのは文字情報だけではなくて、なんとAmazoneにアップされ
ている本の表紙写真を入手して、あたかも本物の本棚に本が並んでいるかのように画像表示してく
れるというところ。この画像、かなり解像度が高くて、縦400dotくらいの大きさでもジャギーが
見えないので、本当に画面のなかに本が縮小して収まっているかのように見える。
このカメラで本を読み取り→画像表示が、一度やり出すと面白くって仕方がない。手当たり次第に
手許にある本をカメラにかざしていく。バーコードの下地の色によって、多少読み取りにくいもの
があるが、そういうものはISBNを手入力すれば検索できる。
米国製のソフトだけれど、日本語にローカライズされおり、そのため日本の本の情報はAmazone.jp
に取得しにいく。もちろん、ISBNコードを使うということは、外国書籍でも区別なくよみとれると
いうことだ。うちには、洋書はほとんどないのだけれど、試しに音響学の教科書だった"The Theory
of Sound"(J.W.S.RALEIGH)と、写真集"Tokyo and my Daughter"(ホンマタカシ)をかざし
てみると、見事どちらも表紙写真付きで情報が得られた。それから、もうひとつ昔ベルリンの本屋で
買った数学の公式集(ドイツ語が読めなくても役にたつので買った)、これにはバーコードはなかっ
たのでISBNコードを打ちこんだところ、表紙こそでなかったがちゃんと書名ほかのデータが表示され
た。これにはなんとなく、びっくりするというか、感動すらおぼえた。11年前に外国で買った本だと
いうのに、その情報が今も、そして日本で引き出せるということに。ちなみに、現在この本の価格は
10ユーロと表示。本を裏返すと値札があって、そこにはDM14.80とある。現在1ユーロは約150円。
なので日本円にして約1500円。本を買った1995年の為替レートを調べると、1ドイツマルクは約65.6
円だった。なので、当時は日本円にして約970円だったことになる。この10年で1.5倍!これはユーロ
統一による影響なのだろうか?当時のドイツはほかのヨーロッパの国に比べると、日常生活品なんかは
安く感じられた(スイスなどは日本より高かった)のだけれど、今はやっぱり状況が違うのだろうな。
ISBNコードがいつからつけられているのかはわからないが、古い本の場合、たいがいついていない。
あるいはついていても、検索できないものがあった。その代表例がわたしのもっている聖書。1985年
に発行された日本聖書協会の旧約聖書(1955年改訳)と新約聖書(1954年改訳)である。中表紙を
開いたところにきちんとコードが書かれているが、4つ書かれているコードのいずれも検索不能であ
った(なぜ4つも書かれているのかという点も不思議)。この聖書は現行の新共同訳ではない、いわ
ば絶版書であるからだろうか?蛇足であるが、同じ1985年発行の日本基督教団出版局の讃美歌には
ISBNコードは振られていなかった(取次番号らしきものはあり)。
それから、雑誌の場合は書籍扱いの雑誌以外は雑誌コードと呼ばれるコードらしく、検索できるもの
とできないものがあった。MacPeopleは検索できたが、東京人は検索できず。もしかしたら、雑誌の
場合はなんらかのルールのがあるのではないだろうかと思う。試した東京人のバックナンバーは2004
年のものだったから、たとえば一年以内のみ有効とかそういうルール。このあたりは検証が必要だと
思う。
最後に、雑誌に関して気づいたというか、困ったのが「広告批評」である。デザイン状のこだわりな
のか、まずバーコードがない。それから雑誌コードそのものが、どこを探してもないのだ。あるのは
値段だけ。これ、よくよく考えると書店のレジでどうやって会計してるんだろう。やっぱり手打ちな
んだろうか?最近買っていないので覚えていないのだけど...。
ま、いろいろ探求はあるのだが、これから本を買ったらどんどん使っていこうと思っている。
これさえあれば、買ったまま読み忘れる本とか、二回同じ本を買う(!)というミスがなくなるはず!
補足:Delicious Library、残念ながらMac版のみでWindows版はないようです。
画面イメージだけでも参考に。→http://www.delicious-monster.com/
蛇足の蛇足:千原英喜のレクイエムも検索OKのうえ、画像もあり。なんとなくうれしい。そういえ
ば、楽譜も出版物だから検索できて当然なのか。外国のものだと流通経路が違う気はするけれど。
- 2006/9/5(火)
友人であるTAM氏が遅い夏季休暇を取って東北地方に旅行しているのである。夏の盛りに休みが取れ
ないことは、それはそれでしんどいのであろうが、暑さがやんだころのちょっとだけ夏が残っている
時期に旅行にいけるということは、それはそれでうらやましい。彼は今戦場、もとい船上の人(フェ
リーで移動中)のようだ。
で、そのことを思いやって、この11月に熊本に行く方法について考えないといけないということに
気づいた。まだ先だけれど、忙しくなる前に素案くらい作っておこうと思う。過去のコンクール全国
大会をここでふりかえってみよう。
1999年 広島 往路:自動車、復路:山陽新幹線
実は津に続いてもっともアクセスが楽だった。行きはメンバーの車だったが、中国道を使
うことで、さしたる渋滞もストレスもなく到着。広島市内の交通の利便性も良かった。
2000年 札幌 往路:トワイライトエキスプレス、復路:飛行機
せっかくだからということで奮発したトワイライトエキスプレス。日本海側を進む寝台列車
であるが、北陸を走る列車特有のことなのか、暖房がきつくて(個室だったのに制御不可)
よく眠れず。眠ったのは道内に入ってからの2時間程度であった。
2001年 郡山 往復:東海道新幹線+東北新幹線
東北新幹線の、それも下りはどこか落ち着いた感じがして好きなのだ。JR東日本のショッピ
ング雑誌が背もたれに入っているのが良い。帰りの東京までの新幹線内で打ち上げをやった
のだが、真ん中の席だったのと満員のせいか、めずらしく新幹線で酔った。
2002年 大津 往路:JR、復路:京津線
京都から京津線一本で移動可能であったが、琵琶湖畔の某大学の研修センターにて前日合宿。
合宿所から貸し切りバスで会場に乗り込むという、なんだか隣接県からの参加とは思えない移
動だった。
2003年 津 往復:自動車
どう考えても、有効な公共交通機関が思いつかなかった(近鉄があるっていう認識が希薄)
ため、メンバーの車で往復を移動。移動時間は過去最短であったと思う。打ち上げが終わっ
てから、翌日の夜中1時ごろには京都に到着していたはず。
2004年 松山 往路:飛行機、復路:特急+新幹線
往路、空港から市内までの遠さに辟易。飛行機を使った場合、必ずついて回る問題。タクシー
に分乗するべきだった(翌年実行)。復路は、列車で。やはり鉄道がいいね、うん。
2005年 新潟 往路:飛行機、復路:上越新幹線+東海道新幹線
北陸線経由では疲れることが明白だったため、やむをえず飛行機。しかし、復路は上越新幹線
の本数が少ないため、移動に半日を費やしてしまう。市内の移動はほぼタクシーに限られ、
過去もっとも交通費を使った年だったかもしれない。
で、以上をふまえて熊本をどうするか?選択肢は4つほどあると思う。
(1)往復:飛行機(約3時間、空港までの移動時間含む)
(2)往復:山陽新幹線+リレーつばめor有明(約4時間半)
(3)往路:大阪南港~大分・別府+九州横断特急(約15時間) 復路:(2)or(1)
(4)往路:大阪南港~新門司+リレーつばめ(門司港~)(約14時間半) 復路:(2)or(1)
ポイントはフェリー(瀬戸内航路)を入れたこと。もうひとつは、九州といえば鉄道。リレーつばめ号
に使われている787系に一度乗ってみたいなぁと思って。
時間的にはもちろん飛行機なのだが、飛行機がいやなのは空港からのアクセス。熊本空港も例外ではな
くて、リムジンバスで50分もかかるという。飛行機で酔わなくても、このバスで酔う可能性が高い。
となると、2~4。どうせ熊本まで行くならば、その途中で旅気分を味わいたいので時間的に可能なら
ばフェリーに乗りたいのが本音。だから、復路は2を選択して、往路は3か4になる。3の九州横断特
急は博多を経由せずに山を越えて文字通り九州の中央部を横断する風光明媚(という話)な路線。往路
で787系に乗るならば、行きはこっちかなぁ。
どちらにしても、前後のスケジュールによるので決定はできないのだけれど。最悪でも、熊本市電には
乗れるはずだー。
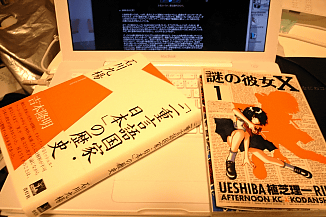
今日買った本
「『二重言語国家・日本』の歴史」、石川九楊著、青灯社刊。2200円。
二重言語とは、おわかりの通り漢語と和語の二つの言葉を指す。日本語の特異性ということは、一般的
によく語られることであるが、その一因は疑うべくもなく、この二重性にある。複数の言語を使う国家
がほかにないわけではないが、その多くは植民地として征服者によって強制された言語と、母国語とい
う構図であろうと思う。それに対して、他国によって明白に言語を強制された経験がないにも関わらず、
外来の国語と和語がほとんど同一の言語として使われるに至ったのはなぜか。そのことついて、われわ
れは歴史の時間でならうこともなく、国語の時間に習ったこともない。最近、国語の復権?ともいうか
国家と国語教育、英語教育の是非などの議論が盛んになってきているけれども、国家や国語を語るなら
ば、そのアインデンティは何か?ということにまで思いを巡らせる必要があるのではないかと思う。
書家たる著者が、その専門である書を手がかりに無文字の時代にまで遡って、日本の言葉と歴史につい
て考察を行っている。京都精華大学・文字文明研究所での講義録をまとめたもので、著者の類書のなか
では読みやすくわかりやすいと感じて購入(前からしょっちゅう立ち読みをしていた...)。
「謎の彼女X」1巻、植芝理一著、アフタヌーンKC、講談社刊。562円。
変な漫画(ほめ言葉)。パンツにハサミを差している女の子って、そうそういない(いや、全くいない)。
続きが楽しみな漫画がひとつ増えました。お薦め。
微熱が続いている。37度前後。外気は涼しいはずなのに窓を開け放っても部屋が暑く感じる。
現在、37度5分。自分で測ってて驚いた。きょうは、風呂には入らないほうがいいかな。
おやすみなさい。
- 2006/9/4(月)
入浴剤を買ってきた。つまり、風呂に入って湯船につかるということ。夏場はずっとシャワーだった
のだけれど、ようやく湯船が恋しい塩梅の気候になってきたので。種類はいろいろ試したけれど、や
っぱり好みなのは「バスロマン~スキンケア」。セラミド配合で乾燥肌に優しい、という成分よりも
白濁になる点が気に入っている。
さて、その風呂に入っているときにあることに気づいた。すごくどうでもいいことだ。たまたま、湯
船に折りたたみ式のブラシ(どっかのホテルのアメニティ)を持ちこんで遊んでいたのである。いや、
髪を洗ったあとにとくために持ち込んでいて、用がすんでから湯面をたたいてばしゃばしゃしていた
のだ。特に意味のある行為ではないし、大人のすることでもない。
で、そのとき鋭く湯面を叩くようにブラシを前方に振り出すと、ひゅんとお湯が前方に飛んでいくじゃ
ありませんか。お?っと思って二度三度繰り返すと、偶然じゃなく確実に、それもかなり勢いのある湯
が発射されるではないか。おー、面白い(面白くない?)。で、すごいのは単に飛んでいくということ
だけじゃなくて、やたら低い弾道を描くということ。仰角にして1~2度くらいしかないので、水面を
走るよう飛んでいくのがわかる。これなら相手のレーダーにも映ることなく攻撃が可能だ!相手ってな
んだとお思いでしょうが、もちろん仮想敵。この新しい水鉄砲で対戦する相手のことである。弾道が低
いということは、浴槽のふちぎりぎりまで水面がある場合、浴槽を飛び出してから俯角(水平方向より
下向きの角度。反対は仰角)への攻撃が可能ということである。
その後の研究(ばしゃばしゃ遊んでいるとも言う)によって、すなっぷのきかせ方や、振り出し方によ
って、仰角・俯角は変幻自在、弾の質量もコントロールできるようになった。一応、原理らしきものも
考察。ただ単純な平板な板を打ち付けても湯はこれほど飛んでいかない。秘密は、ブラシの形状にある。
ブラシの背面は本体側に向かって窪んだ形になっていて、いわば半円筒形にくりぬかれているようなも
の。さらに柄の部分にもくぼみがある。湯面に振り下ろした際、この窪みにたまった湯が、前方に移動
し、半円形のトンネルに沿って進むことで左右に拡散することなく、前へのエネルギーを保ったまま射
出されるのであろう。
せっかく得られた成果であるが、銭湯やプールなど広い空間での実戦に使うことは、おそらく衛生上の
問題から禁止されることは明白。むむ、残念である。どこか、広い浴室のついた旅館やホテルに滞在し
たときにでも試すしかないなぁ。そのとき、このブラシを持っているとは限らないが。ああ、そうだブ
ラシの形状も研究しておくべきだろう。
.....こんな風に、非常にどうでもいいことを考えながら風呂に入っているわたしである。
- 2006/9/3(日)
YK練習、13:00-17:00。YKに来ると、いつも以上にどうしたらもっといい音が出せるかを
考えられるような気がする。音楽の基本的な土台のことをいちいち気にする必要がないから、
そのうえに建てる家のことに集中できる、そんな感じかな。
帰宅後、まぶしいので部屋の明かりを消してみると、いつものように南の窓から京都タワー
が見えて、ほっと安心する。と、視点を動かすと、ちょうど南西の空に月が出ていた。なん
となくうれしい。外で空を眺めて見る月よりも、窓に切り取られた空に浮かぶ月の方が特別
な景色のような気がするからだ。窓っていうのは、不思議だな。
中くらいの頭痛あり。ひどくならないうちに休みます。
- 2006/9/2(土)
午前中、医者へ。
午後一、鍵盤でNC自由曲の和音を確認。先週、こんな音は鳴ってなかったよ。反省。
午後、五条坂のあたりまで、軽くモールトンを走らせてみる。坂道に慣れないと。
NC練習、18:00-21:00。

未来人風。
パタリロに出てくるタイムパトロールのメンバーは、こういう感じのサングラスをかけていたように思う。
わたしはメガネ着用者なので、当然メガネのうえからかけているのだが、写真を見る限りはわからないで
しょう。両目全体を覆うタイプだからできることで、通常は度付きか、クリップオンするタイプを使うみ
たいだ。自転車に乗るとき以外は使わないので度付きはもったいないし、クリップオンはいいデザインの
ものがない。オーバーサングラスというメガネのうえからかけることを想定したモノもあるけれど、いっ
てみれば、スキーのゴーグルみたいなもので、これもかっこいいものはない。サングラスメーカーは、こ
のあたり一考してほしいものだと思う。ちなみに、こういうかけ方はイレギュラーなので店員に止められ
るかと思ったが、意外と理解を示してくれた。そういうお客さんがいるんだろうな。
で、きょうは日差しがきついので使ってみたが、効果てきめん。まぶしい反射をすべてカットしてくれる
ので視界が一気に開けた感じ。輪郭すべてがくっきりみえるせいか、遠近感が希薄に感じる。直射光によ
る目の疲れはなくなったけれど、逆に見え過ぎちゃって困るのというか、情報量が増えて疲れるんじゃな
いかと危惧するくらい。慣れれば、大丈夫かな。もっと真夏の、それも軽井沢に行く前に買えば良かった。
- 2006/9/1(金)
BK練習、18:30-21:00。
BK宴会、21:30-23:30。
確か、昨日までは日中の空には少し入道雲が見られたのだけれど、今日会社から練習場に向かう空は、
完全に秋の、そう、すじ状の薄くて長い雲が視界いっぱいに広がった空になっていた。きょうから9月。
暦のうえでも、秋なんだねぇ。
秋の行楽、なんてものとはほど遠い世界に身を投じて、はや何年か。でも時間と体力とお金と、根性を
費やすに足る日々をすごさなければ、「秋の行楽」なんていう普通の世界に負けてしまう!それは悲し
いさ。一緒にやっててよかった、聞いてもらえて良かった、そういう合唱ができますように。歌と人を
きちんと愛することができますように。殺伐とした気持ちや、投げやりな気持ちになりませんように。
秋のはじまりに、切に願い、祈る。
- 2006/8/31(木)
早めに帰宅。少しだけレクイエム練習。
更新休みます。
- 2006/8/30(水)
日も沈んだのにどうにも暑いなぁと思っていたら、熱がありました。
くすり飲んで寝ます。更新やすみます。ごめんなさい。
- 2006/8/29(火)
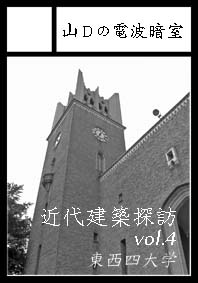
コミックマーケット71申し込み用短冊(実際はグレースケールではなく二値化してます)。
申し込みは終わっていたのだけれど、短冊だけまだできていなかったのだ。締め切りは明日の昼なので、
急いで作成。次回は、どんな体裁にするかはまだ検討できていないのだけれど、テーマは学校建築でい
こうかなと思っている。vol.1やvol.3のようなレイアウト主体の写真集は、外観、内装を織り交ぜて
結構な枚数の素材がいるのだけれど、これがじつはなかなか揃わない。ましてや同じテーマで固めると
なるとなおさらで、少々困っている。学校建築の場合でも同じだが、たいていは複数の建物があるので
枚数的にはいけると思う。問題はそれをどういう切り口で見せるか?ということ。vol.2のように文字
が多めになるか、vol.3で実験した地図との組み合わせで見せるガイドブック的なものになるか、どち
らかかなぁ。皆さんの意見をお待ちしています。
あすは健康診断なので、健康的に早めに寝ることを決意。健康関連でのじぶんのトピックスをあげてみよう。
○頭痛薬をアスピリンからバファリンに変更。アスピリンは成分はグランドールに似ているのに、あまり効
かない。バファリンは買ってはきたがまだ飲んでいないので効果わからず。
○魚をあまり食べていない。近所の弁当屋のメニューから「日本海弁当」が消えて以来、魚を食べる機会が
とんと減ってしまった。今日はひさしぶりに焼鮭を総菜屋で買ってきた。焼塩鯖食べたかった(売り切れ)。
○体重65~66kgを維持。少なからず、自転車で運動しているのが効いているのかもしれない。
○最近、肩こりの症状はみられず、マッサージ屋にもいっていない。油断大敵?
○集中力低下。魚が少ない食生活と関係ありか。野菜も減っているっぽい。要注意。
その他
○洗濯用洗剤を粉状から、液体に変えてみた。一度使ってみたかったのだ。健康とは関係ないな、これ。
○麦茶パック枯渇。コンビニにも売っていない。夏の終わりを意味するのだろう。これも雑感。
○とりあえず、秋が来るまでの間、夏の名残の大きくて高い雲を、日々写真に納めている。
おやすみなさい。
明日の朝、検尿採るのを忘れない>自分へ暗示。
- 2006/8/28(月)
昨日掲載した写真に違和感を覚えたひとは結構いたんじゃないだろうか。なにしろ、わたし自身見直して
みて違和感どころか、とても落ち着かない気持ちになってしまった。この写真はLUMIX-LC5で撮ったもの
だけれど、最近載せている写真はGR-Digitalで撮っている。その画質の違い、ではもちろんなくて、気
づいている人もいると思うけれど、縦横比が違うのだ。通常のデジカメは画像として画面に映すことを主
体に設計されているから、自ずとPCの画面と同じ縦横比である4:3を採用している。ところがGR-Digital
は玄人好みのカメラであるがゆえに、モードとして縦横比3:2での撮影が可能となっている。3:2と
いうのは、デジカメじゃない、35mmフィルムの写真の縦横比なのだ。4:3に比べると少しだけ横長に
なっているのだ。この3:2の縦横比に慣れてしまった目には、4:3の画像はどうにも縦が長すぎるよ
うな気がしてしょうがなくなってしまう。
しかし、GR-Digitalを使いはじめるまでは、LUMIX-LC5の写真を載せていたのに、そのときに違和感
を感じなかったのはなぜだろう。そのころは、デジカメと並行してフィルムカメラもよく使っていたから
3:2には当然馴染んでいたはずなのだ。
こたえは、日常使うPCがMacBookに変わったことと多いに関係があると思う。MacBookの画面の縦横比は
16:10と、これまた横長なのだ(ちなみに最近のTVは全部16:9)。横長画面は何かと作業がしや
すいということは、この前の本の編集作業でわかっていたが、そのあたりの機能性は置いておいて、単純
に横長の画面のなかにある4:3はとても目立つのだ。その縦の長さが。
最近では仕事で使っている4:3の液晶モニターの縦の長さ、というよりも横の狭さが気になって仕方が
ない。解像度は1280x1024と十分な広さがあるにも関わらずだ。仕事でPCを使っている時間のほうが長い
はずなのに、やはりそれだけMacBookに情が移ってきている(?)というべきか、主体がどちらにあるか
ということなんだろう。
で、話戻って昨日の写真。4:3から縦を若干切り取って3:2にしてみた。写真屋でデジカメプリント
をするときも、じつは上下が切り取られて3:2になっているのだ。手にとってみることのできるプリン
トが、もし4:3で渡されていたら、画面で感じるよりももっと大きな違和感があるだろうな。

どうだろうか、なんだかしっくりきませんか。16:10のモニターだとやっぱりこちらの方がいいな。
最近のほかのデジカメはどうなんだろう?3:2のモードは備えていないのかな。もし、あるならば、
ぜひ3:2で撮影することをお勧めしたい。きっと、違う視点や構図が目のまえにひらけてくるはずだ。
(画像が少し小さい分だけ、フルサイズの4:3よりもファイルサイズも小さくなって容量的にもお得)
- 2006/8/27(日)

夕立と入道雲(昨日撮影)
昨日、今日と激しい夕立。今日は市内全域で雨模様だったけれど、昨日のはなんだか局地的で、うちの
あたりは土砂降りなのに、東の空は晴れていた。写真の手前、よく見ると大粒の雨が斜めに横切ってい
るのだ。
夕方、TVをつけると「夏長崎から」が放映されていた。あー、もっと早くきづいておけばなぁ。ちょう
ど「道化師のソネット」がはじまったところ。サビの部分でさださんは、会場のみんなに歌うように促
した。ふつう、こんな風に会場のひとが歌う声は聞こえないはずなのに、はっきり歌詞がわかるくらい
聞こえたのに驚かされる。あつまった人みんな、老若男女問わず歌っている姿が画面に映った。それだ
け、このコンサートが、さだまさしの歌が愛されているんだなと思った。
『わらってよ、きみのために』
『わらってよ、ぼくのために』
(さだまさし詞・曲「道化師のソネット」より)
調べてみたらNHK FMで9/10の23:00-25:00まで、放送があるみたい。見逃した方、聞いてみてくだ
さい。わたしも聞きます(終わりの20分くらいしか見られなかったので)。
夕飯はスタンド。日曜の夜の外食はわたしとしては珍しい。食後に寺町通りに抜けて、北上する。そう、
確かこのあたりにできたはず。新しい本屋さん。「東京 RANDOM WALK」という。神田神保町に行くた
びに行っていた書店なのだけれど、この夏に京都にできたのだ。かわりにというか、その神保町の店の
方は無期限の休店になったらしい(赤坂や青山にも店はある)。しょんぼり。寺町店は洋書が中心で、
セレクト系の神田店とは雰囲気が異なるらしいと聞いていたのだけれど、どんなものか。
一階は外国人向けの日本や京都を紹介する本が中心。ああ、やっぱり見るものないかなぁと思って奥に
進むと、写真集、デザイン、広告関係については洋書よりも和書の方が多いみたい。なんだか見慣れた
感じがしてくる。結構、うちにある本が置いてあることに気づく。つまり、わたしの趣味に合致してい
るということか。
くるっとまわって、途中から日本の紹介本コーナーに戻るのだけれど、よく見るとおもしろい本もある。
漢字を教える本は特に興味深い。意味が英語に訳されているだけでなくて、イラストが添えられている。
それも名詞だけでなく、動詞にも。あとは、日本の風呂の入り方、楽しみ方を図入りで教えるものなん
てのもあった。企画したのは、日本の出版社なのか外国の出版社なのか、どっちなんだろう。
もうひとつ、小説コーナーで見つけたのが「TRAIN MAN」。なんと、電車男が英訳されているじゃない
か。中身の掲示板風の文字組まで同じになっている。かなり驚き。だって、村上春樹とか、村上龍のペ
ーパーバックが本棚の大部分をでーんと占めている、その片隅に電車男が紛れ込んでいるんだもの。ち
なみに「ねじ巻き鳥クロニクル」は合冊されていて辞書並みの厚さで1800円。新潮文庫の上中下を買う
より、ほんのちょっと高いだけ。洋書も安くなったなぁ。「TRAIN MAN」は調べ忘れました。
きょうは、早く寝ます。
おやすみなさい。
- 2006/8/26(土)
ことえり(Mac標準の日本語FEP)の操作が慣れないのと、変換精度の悪さに辟易してきたので、本日
ついにATOK2006 for Macを導入。ひとつたくさん文章を書いて、使い勝手の良さを試してやろうと
思ったのであるが、音源の編集やらなにやらやっているうちに疲れてしまって、いまは言葉がうまく
浮かんでこない状態。ありていに言うと眠たい。
きょうは、18:00-21:00にNC練習があっただけで、とりたてて疲れるようなことはなにもしていない
はずなのだけれど。ただ、単純に音楽を聴くのに比べると、編集作業は聞き所というか、観点が違うか
ら、久しぶりだったこともあって、脳が緊張したのかもしれない。作業は今回はじめてMacだけで行っ
たからということもある。しかし、Windowsでやっていたときに比べるとやはり、格段に初期作業の負
担は軽減されていると感じる。どうやってやるんだろう?と首をひねることが全くなく、こうすればで
きるだろうと行った操作で、ほぼそのままOKということがほとんどだったので。
この調子でほかの作業も全部Macでできればいいのだが、ExcelとWordだけはどうにもならない。なん
であんなに高いんだろうねぇ…。わたしはWindows版の正式ユーザーなんだから、ちょっとは安くして
欲しいな。
もう遅いです。おやすみなさい。
- 2006/8/25(金)
BK練習、18:30-20:45。
BK公式大宴会、21:00-25:00。
少し、幸せ。うまい棒を二本、食べてから寝るー。
- 2006/8/24(木)
帰宅するとポストに「良縁ニュース」なるものが入っていた。お見合い斡旋のチラシであるらしい。
なかを見ると、男女別に年齢、学歴、職業、趣味、身長、体重、希望(?)などが、さながら新聞の
三行広告のごとく、ずらっと並んでいた。見ているとなかなか面白い。女性の希望の欄、医師希望と
いう人が多いように見える。わざわざ父は医師ですとか、書いているひともいる。つづいて多いのが
「人物本位」。具体的になんなんだろうか、人物本位って。趣味は、もう判で押したように同じなの
に苦笑する。曰く、「読書」「旅行」「音楽鑑賞」「映画鑑賞」。これで判断しろっていうのか?え
らく難しいどころか、何もわからないと同じじゃないか。村上春樹が好きとか、近代建築巡りをして
ますとか、男声合唱のファンですとか、時かけ大好きとか、そういうのじゃないければ、「情報」
じゃないと思うんだけれど。編集方針なのか、世の中当たり障りのないことが好きな人が多いのか。
男性の方はわりとバリエーションがある。「自社ビルで近々開業、生活安定します」とか、えらく具
体的であるな。意味不明なのが「結婚決まり次第、年収上がります」。それでも「人物本位」は、割
と見受けられる。そうそう、女性になくて、男性にある項目「年収」。なんだかなぁ。こうやって、
シビアな条件ばかり見ていると、なんだか切なくなるなー。話のネタとしてはいいけれど、なにか
こう求人広告と変わらないような気がしてきて(「求人」ではあるんだろうけど)。ひとしきり見た
あとで、ゴミ箱に捨てた。
軽井沢、三日目の日記を追記。
「下北サンデーズ」、面白い。上戸彩がきらきらしてますなー。もうちょっと早くから見ておけば
よかった。
おやすみなさい。
- 2006/8/23(水)

今日は、雲ひとつない天気。日中はまだまだ夏。でも、夕焼け空には、時折秋の気配が見えるのだった。
夏コミも、軽井沢も終わったからだろうか。来週からはコンクールの練習が本格化する。合唱暦は秋に
入った。
就業後、駅前から会社までの通勤路の清掃に行く。当番なのである。30分ほどだが、日が暮れるまえ
なのでじんわりと汗をかく。拾うゴミの9割がタバコの吸い殻。いくらいっても、通勤路に捨てる輩が
絶えない。正直、同じ会社の人間として恥ずかしい。そもそも、喫煙者全員が毎日清掃当番をやりゃい
いのだ。理不尽極まりない。いったん居室に戻り一時間ほど仕事をしてから、帰宅の途につく。途中、
新しい吸い殻が捨ててあるを発見して、むなしくなる。くそ~。吸い殻捨てたやつは懲戒だ!
スタンドに夕食に行くと、21~25は休みと。ショック。大丸裏の大正軒にラーメンを食べにいったら、
M川さんが途中でやってきた。ここで会うのは二回目か。
帰宅後、軽井沢二日目の日記を追記。
- 2006/8/22(火)
夏コミで買ってきた本を段ボールからひっぱりだす。一部の直接持ち帰った本以外は、軽井沢
の準備なんかもあって、今日までほったらかしにしていたのだ。
こうやって眺めてみると、いろいろな版型の本が入り交じっていることがわかる。本のつくり
にしても、オフセットだったり、コピー本だったり、カラープリンター出力だったり様々。絵
だけの本、創作漫画、エッセイ、旅行記。ジャンルも形も様々な本を見ていると、内容を読む
前から、それだけで嬉しくなってきてしまう。市販の本にはない、本の可能性っていうんだろ
か、そういうものを感じるのだ。本っていう媒体でこんなことができるんだとか、市販の本で
は絶対存在しないだろうなーと思うものが、いまの手の中にある。それは、所有の喜びを引き
起こす。自分で探して、見つけて、手に入れる。自分と、ほんの少ししかない同じ本を持つ仲
間と、そして作者だけが共有することのできる世界。少なくて、小さいがゆえに輝くものを手
にする喜び。そういうものを知ってしまったら、もうここから抜けでることはできないのだ。
だから、新しい輝きを求めて、毎回コミケに出かけていく。
と、いうわけでいろいろ本を読みふけっていたら、軽井沢日記を書く時間がなくなってしまい
ました。覚えているうちに、全部かけるかなぁ。頭の片隅で推敲はしているのだけれど、書き
起こすのがめんどくさくならないうちに手をつけないと、とは思っている。
- 2006/8/21(月)
フェスティバル一日目の暗室を追記。
きょうはやたら眠かったのと、筋肉痛が来た。
フェスティバル期間中、実は睡眠時間をあまりとれてなかったので、その反動かも。
筋肉痛はモールトンを運んだせいかな?ほとんど新幹線だったから移動距離は少なかったはず
なんだけれど。
きょうは、一日目の追記のみで許してくださいませ。
おやすみなさい。
覚書き:三日目の合唱の中のピアノ講座、課題曲Gott ist mein Hirt.について書くこと。
二日目の夜話「グリーという概念」の思想(?)+橋本先生の発声講座について書くこと。
- 2006/8/20(日)
軽井沢合唱フェスティバル第三日目参加。
軽井沢から無事、帰ってきました。
心地よい疲れ。合唱フェスティバルの詳細は、明日書きます。
ひとつだけ思ったことを。東京のいい所のひとつは、軽井沢や箱根といった文化の薫りがする
避暑地がとても身近にあるということ。近いけれど地続きじゃなくて、完全に別世界の場所で
あることがうらやましい。京都にいると、関西の他の府県は全部、どこかでつながっている感
じがして、旅をしている気にあまりなれない。
軽井沢から、わずか1時間弱で東京についてしまったときに、そんなことを思ったのだった。
追記:
7:30起床。寝不足。K君は二日酔いらしく、一人で食事へ。あれ、みんな結構起きてるな。
9:00、チェックアウトしてから、新軽井沢会館へ。9:20からの朝の発声には出ずに、モール
トンを分解する。ほんとは少しでも駅に近いところでやりたいのだが、30分のロスがあるこ
とを考えると全行事が終わってからより、いまの方がいい。指定席ではないけれど、早い電車
にはなるべく乗りたい。皆が撤収するのを見送れば、必然出るのは最後になる。二回目の分解
はスムーズだけれど、やっぱり30分かかった。
10:00-12:15、「合唱のなかのピアノ」を受講。講師は浅井先生。合唱伴奏のための講座で、
3人のピアニストがそれぞれ指導を受ける。合唱は「さやか」のメンバー、指揮は松下耕。
ピアノパートだけで演奏することと、合唱と演奏することの違い、難しさを目の当たりにする。
そして同時に、合唱とピアノ、主と従の関係ではもちろんなく、音色の違うパート同士だとい
うことに気づかされる。
浅井先生の言葉は、合唱と一緒にピアノをやってきた人ならではの素直で、深みのある言葉。
「合唱とピアノは決して交わらない、でも共に並んで流れている」。
なかでも、一番感銘を受けたのは「言葉が、単語の意味がわからなければピアノは弾けない」。
シューベルトのGott ist mein Hirt(神は我が羊飼い)の、”seinen Namen”(あなたの
名前、つまり「神の御名」)の部分を練習していたときだ。音符ひとつひとつに単語がふられ
ているわけで、その単語ごとに音楽の表情は当然変わらないといけない。「神の御名」の音を
弾くならば、それにふさわしい音色、テンションがなければならないということを語られた。
それはもちろん、合唱でも同じことなのだ。ましてや、歌詞そのものを歌う合唱を歌う人間
がそのことをわかっていなくて、どうしよう。頭を揺さぶられた気がした。よく、歌詞の意味
をしっかりと、とはいうければ、場面場面で、小節ごとに、音符ごとにどんな音楽をつくらな
いといけないかということまでは、考えが及んでいなかったと思う。恥ずかしいことだ。
12:45-13:30、クロージング。もうひとつの講習会、ヤン先生のポーランドの合唱曲の演奏会
と、ピアノ講座の3人の演奏がつづく。押しているせいか、ちょっとあわただしい。
外にいったん集まって、連絡。おせわになったアテンドの方にお礼をしてから、新軽井沢会館
にて昼食。そして、集金。そう、これが一番大事なわたしの仕事。だから、帰るのが最後なの
ですよ。
で、集金しつつ弁当を食べて、食べた人から帰っていく。また、熊本でが挨拶がわり。ここで
問題が。お金は問題なし。でも、弁当が大量に余ってしまった。10個近くも。なぜか?遅れ
て来るひとの把握はわりとしっかりやっていたのだけれど、早く帰るひとが、何時に帰るかま
ではとても把握しきれるものじゃなくて、ともかく最後までいることを前提に弁当を頼んでい
たからだ。しっかし、ここまで余るのは予想外。若手+自主的な方(お腹すいている人)に頼
んで5個は消化。さらにあまった分は、車で帰る若手に「夕飯に食え」といって押し付けた。
ビニール袋を調達してきて、持ち運びしやすい状態で。一日二食も中華丼を食べたかなかった
とは思うが許せ。恨むなら、やはり弁当を残していった指揮者をうらんでくれ。
皆を送りだしてから、アテンドの方に挨拶をして新軽井沢会館を出た。そーいえば、去年も
一番最後だったっけか。14:58発(だったと思う)の新幹線で軽井沢を後にした。
京都、19:00頃着。八条口で再びモールトンを組み立て。もったまま地下鉄なり、タクシー
乗り場に行くよりも、組み立てて乗って変える方が楽だったからさ。京都はやっぱり暑いな
あ、同じ30分でも軽井沢とはやっぱり違うことを実感。
19:40ごろ帰宅。これで、わたしの夏はおしまい。
- 2006/8/19(土)
軽井沢合唱フェスティバル第二日目参加。
7:00、起床。7:30から食事だと思っていたら8:00からだった。もうちょっと寝とけばよかっ
たー!
9:20、朝の発声。つづけて公開個人発声講座。ここで講師から印象的な言葉が。合唱をやって
いる人は口や顔を動かしすぎる、しゃべろうとしすぎる。だから一般の人から見ると、とても
気味悪がられる、こわい感じがする。という内容。いままで、誰もこうもはっきりと合唱が一
般的なものにならない理由を述べた人はいなかった。嫌がられるだろうと思う、特に連盟の行
事では。でも、ここは連盟とは違う合唱の場。いままでなかったのは、連盟以外の場がなかっ
たからだけれど、いまはそうでもない。東京カンタートや、この合唱フェスティバルがある。
媚びる必要はむろんないのだが、合唱や歌うことを日常に根付かせるには、「合唱の常識」を
疑ってかかる必要があるんじゃないだろうかと思う。これは一応、この日の夜の伏線。
午後、NC練習開始。途中、昼食休憩10分。10分で食えー、といったら皆10分で食べるもんな。
この集中力は素晴らしい(?)と思ったり、思わなかったり。まぁ、われわれには時間がない
んだから仕方がない。賞味1時間40分の練習。全員がそろったのは一時間程度。今日来て、
今日帰る人が6人もいるのだ。
14:30~18:00、招待合唱団演奏会。NC出演。小田原少年少女合唱隊の演出が群を抜いて素晴
らしい。30分のステージに、二度も早着替えがあるのだ!NCの即興演出は完全に素人だなーと
悔しさが込み上げてくる。歌声の精緻さでもかなうはずもない。だったらいっちょやってやろ
うじゃないか。男声合唱団の根性、大人の声をお客さんには聞いてもらうぜー!と拳を握る。
18:15、集合。15分で夕飯を食えーといったら(以下略)。前回のフェスティバルでも感じて
今回も改善されていないことは、スケジュールの余裕のなさだろう。具体的には食事の時間が
参加合唱団に限らず、一般のお客さんにおいても十分に確保されているとは言いがたい点が問
題。いい音楽を楽しむには、いい食事時間が必要なことは、海外コンクール経験の多いであろ
う耕友会の方々なら、じゅうぶん承知のことだと思うのだけれど。ホールに隣接したレストラ
ン施設がないという施設上の問題はあるが、なんとかクリアする方法を考えてもらいたい。こ
れは後日、行われるであろう参加団体へのアンケートで進言することにする。
18:40-20:00、耕友会コンサート。いつも思うのだけれど、耕友会の演奏は個人個人に揺るぎ
がないところが素晴らしい。どの部分、どの声部を切り取っても、きちんと合唱として成り立っ
ている。誰かに頼らない、もちろん指揮者にも。こういう力強さを、BKやYK、むろんNCが身に
つければ、いまよりもっとすごい音楽ができるはず。がんばらんとなー。で、ひとつだけこの
コンサートに注文をつけるならば、松下耕作曲以外の曲を聞きたいということだろうか。同じ
作曲家の曲だけで、ステージを構成するのは、聞いている方としては若干つらい。巧いのだか
ら、もっと幅の広い音楽を聞かせて欲しいと思うのだ。招待合唱団の演奏において、5団体中
3団体は、一曲以上松下耕の曲を入れている。これでは、意図するところではないにしろ、翼
賛のフェスティバルに、なりかねないのではないだろうか?偉そうなこと言ってますが。やや
本気で心配するところ(氏の音楽性を否定するものでは決してない)。
20:00-22:00、交流会。
22:00、二次会には出ずに食料を買い込んで、ペンションに戻る。幾人かで集まって、個別二
次会を開催。そこで、「グリーという概念」を本にする、という企画が持ち上がる。発端は、
Dグリや、Wグリにかつて存在した不条理なオキテや、概念を語り合っているうちに、合唱とは
どういうものなのか、グリーってなんなんだということを一般の人にしってもらうには、本を
つくるのが良かろうということから。それも岩波文庫に限定。岩波には関屋晋著の「コーラス
は楽しい」という本があるのだが、このタイトルを見て、誰が手に取るのか?読んでみて本当
に合唱は楽しいと思うのか?という反発から決まった。今日の発声講座から想起された「合唱
の常識を疑う」ことがテーマでもある。
合唱における倍音に関する定義は音響学上は誤っていること、「ウの口で、イ」というUウムラ
ウトの指導法の間違いなど、アカデミックに迫る内容になっている。大部分は、今回初参加の
Wグリー出身のI畑氏の主導によるものだが。だいたい7章くらいまでの構想が決まり、推薦文
は誰がいいという話に。小泉純一郎、パウエル元国務長官、カルロスゴーンなど、一般受け?
を狙いに行く。結果、Wグリー出身(中退)の筑紫哲也はどうだろうという意見でまとまった。
別冊として「グリー漫画」(略して「ぐりまん」)も発案される。発案者はT橋の奥さんのHさん。
普通の人はそんなこと考えつきませんよ!さすがHさんだ、と感心する。
宿の門限は23時にも関わらず、指揮者、チェアマンをはじめ半分以上の団員が帰ってこない。
25:30過ぎになって、ぱらぱらと宿に到着する面々。宿の人に怒られるんじゃないかと、内心
ひやひやする。二次会では大地讃賞を歌ったらしい。ペンション二次会組から「大地を讃えす
ぎ」という意見が出た(笑)。
26:00ごろ就寝。しかし、同部屋のK君とSは帰ってない。
26:30、二人とも到着。すぐに、Sは荷物をまとめて、別の団員の車で軽井沢を離れた。
そう、NCは集まって、そして三々五々散っていく。皆が仕事を、家庭を持つがゆえに。
じつは、こういった団員の状況をちゃんと把握できていなかったがために、翌日ちょっと
だけ困った事態になるのだった。
- 2006/8/18(金)
軽井沢合唱フェスティバル第一日目参加。
10:20軽井沢到着。さっそく駅前でモールトンを組み立てる。今回軽井沢に行くことになった
とき、去年参加したとき、講習を受けなかった(それはどうかと思うが、まあ)BKの団員から
サイクリングが気持ちがいいということを聞いていたので輪行(自転車を袋にいれて手荷物と
して公共交通機関で運ぶこと)することにしたのだ。
フェスティバルの開始は17:00だから、十分時間がある。気になっていたのは天気だが、台風
の影響は信州までは及ばないようで、出発直前の天気予報では曇りだったが、見事な晴天。
雨なら持っていくのを止めるところだが、くもりならと思って持ってきて正解だった。わたし
はこういう賭けにはあまり勝ったことがないので、軽井沢の空を見たときはやったー!と思っ
たね。
組み立て中も、ちらほら輪行らしき人をみかける。モールトンいいですね、と声をかけてくれ
る人もいた。自転車乗り同士にはなんとなく連帯感があるなーということと、やっぱり軽井沢
は自転車が似合うなーと感じた。で、今回はじめて分解と組み立てをやったのだけれど、組み
立てに30分くらいかかってしまった。気温は25℃とはいえ、日差しは京都並みに厳しいので、
日陰でも結構汗をかいて、走る前から疲れてしまう。外したサドルの高さ位置あわせは、印を
つけていたのでよかったが、ハンドル(輪行時に90度回転させる)の位置あわせに四苦八苦。
あとは、前後ディレーラーのケーブル分割の接続は、ハンドルを元に戻さないとケーブル長が
足りないということも、やってみて初めてわかったことだった。
で、例によって地図を確認しないまま適当に走りはじめた。まずは、マネージ。宿泊予定の宿
を実地確認する。片方の宿は昨年BKで宿泊済みなので、記憶と事前の調査を頼りにする。確か
駅前の道を北上して6つ目の信号...。途中で、もう一方の宿も発見。見覚えのある昨年の
宿もすぐに見つかり、任務終了。宿には事務局の人が連れて行ってくれるが、片方はわたしが
引率しないといけないかもしれないと思っていたが、これだけ近いなら必要なかったかも。
さて、そこから旧軽井沢方面へ走る。ここからは自由時間。宿泊場所のある場所からして、も
う木陰のなかでひんやりとした風が吹いている。適当に道を選びながら、本当にあてもなくモ
ールトンを走らせはじめた。走っていてすぐに気づいたのは、道があまりよくないということ。
国道133号線と、国道18号線という主要道路以外のアスファルトは、ことごとくひび割れ
ていて、自転車、それもモールトンやロードのように細いタイヤにとっては走りにくい(とい
うか、危ない)ことこのうえない。これって、それだけ別荘地へ移動する車が多いということ
なのか、単純に財政難なのかどちらなのだろう?木立のなかでは、あまり車とすれ違わなかっ
たので後者だろうか。
標識を頼りに、旧三笠ホテルに向かう。重要文化財に指定されている洋館である。一応、事前
にチェックしていた。駅前から、やや軽めの坂を15分ほど北上すると、峠付近に建物が見えて
きた。しばし、休憩。こんなところ、車か自転車、バスでしかとても来れないなぁ。徒歩では
遠すぎるし、夜になったら真っ暗だ。そうそう、話は前後するが軽井沢の町の夜の暗さは、
徹底していて、明かりがほとんど見えない。街灯がほとんど見当たらないのは、条例か何かで
景観保全しているのかもしれない。夜間9時以降の騒音は厳しく取り締まられているのは去年
知ったが。
避暑地らしく、軽やかな造りでどちらかというと山荘に近いと思う。疲れていたせいか、写真
は控えめ。テラスや、窓際の明かりをみて、ああここは高地なんだなぁと感じて、ここでゆっ
くり滞在するイメージを広げるにとどまった。中で、椅子にでもすわれれば良かったのだけれ
どあいにく、現役のホテルではなかったから仕方がない。
帰りは下り坂。疲れも吹き飛ぶ気持ちいい風。ああーこれだー、この風は京都には絶対吹かな
い風。軽井沢に来ないと感じられない風だー。持ち運び続けるには決して軽くはないモールト
ンを持ってきてよかったと思える瞬間だった(レンタサイクルは、沢山あるけれどママチャリ
だからスピードは出ない)。
ひとしきり走って、昼過ぎに会場である軽井沢大賀ホールに向かう。事務局の担当者と事前打
ち合わせするため。一時間ほど。指揮者はすでに現地入りして、オープニング前の講習会を見
学しているらしい。打ち合わせ場所でしばし休憩。
16:30、NC集合。と、突然の夕立。そういえば去年もそうだったなー。やむとわかっている雨
を待つ時間はちょっと好き。
17:00、オープニング。ひきつづいて講習会、アンサンブルコンテストと立て続けに行事がす
すむ。21:20-21:45、ほんの少しだけ無理をいって新軽井沢会館を借りて練習。メンバーの
そろいにくいNCにとっては、どうしても必要だった。ほんとは21:00から使えたのだけれど、
諸般の事情で短く。指揮者の考えてることはよくわかりませぬ。プンスカ。
22:00、宿に到着。そうそう、モールトンは三日目まで分解せずにそのまま乗っていた。宿か
ら会場までは徒歩10分くらいかかるのだが、自転車だと3分くらいで、マネージをするのに皆
より早く移動する必要がある場合など、ほんとに役にたってくれた。宿では屋根のあるところ
に置かせてもらえたのは助かったと思う。
同部屋のK君とSと3人で小規模宴会。SがPowerBookG4ユーザーと判明(持参していた)。
ブログやHPはやっていないが、毎日日記をつけているとこのこと。ユーザーインターフェース
の良さについて語りあう。ああ、MacBook持ってくればよかったなぁ。今回はモールトンがや
や重かったのであきらめたのだった。リュック1つ、カバン1つ、モールトンでは身動きがと
りにくいことも理由だったが、よく考えるとわたしのリュックはちと小さいのではないかと思
い至った。リュックにいれられれば、それほど負担にはならなかったはずだし、荷物をひとつ
にまとめられたかもしれない。最近の旅行における課題だ。
交代で風呂に入り、1:00就寝。
- 2006/8/17(木)
午後、なじみの時計屋に新しく入荷したアンティーク時計をみせてもらいに行く。
歓談中、東京からきたご夫婦が来店。以前、来たときに見た時計を買いにこられたのだ。
わたしも客なのに、半分店員のような感じで店主と4人で会話。わりと普通に話している
つもりだったのに、その奥さんに「3人で時計の話をしていると楽しそうね」と言われる。
旦那さんは現行品の時計(40万円くらい)と、目当てのアンティークの時計を交換する
つもりだった。店主が何度も奥さんにいいですね?と確認すると、「欲しいっていってる
んだから仕方ないですよ」と。なんだか、とてもいい関係だなぁと思った。
夕方~夜、軽井沢マネージ最終準備。
行ってきます。
- 2006/8/16(水)
午前中、軽井沢マネージ。PCに向かったついでに、冬コミの申し込みをする。日程は12月29、30、
31日。よもや大晦日まで祭りをくりひろげるとは思ってもみなかった。みんな、31日が終わってから
正月になるまでに帰宅できるのか??最終日当日そのまま帰宅するのは久しぶりのことなので、よく
よく撤退シーケンスを練っておかねばならない。前日の夜のうちに宅急便を出すとか、持ち帰り荷物
を駅ロッカーに預けるとか、そんな程度だけれど。大晦日ということで次次回のマンレポには自虐ネ
タ多数ありと予想。
午後、クルートにて食事。そのまま、烏丸今出川へ。15:00-17:00、NCコンクール用マネージ。発送
用ラベルを見ていてきづくことが二つ。この人誰だっけ?という人がたくさんいること(大抵は練習
見学に来た学生だったり)、もうひとつは在関西メンバーで最近練習に来ない人が多いなということ。
軽井沢の練習だけやっていると思われているような気がする。とんでもない。軽井沢の練習は全体の
三分の一くらいで、残りはコンクールの選曲をしたり、課題曲の練習、それから発声練習にあててい
るのだ。9月になってから練習来始めたって、もう課題曲の音取り練習なんかやらないよ?3ヶ月前
に終わってるんだから。練習来ていなくて、コンクールに乗るつもりの人は、そのことわかっていて
自分で練習しているんだろうな(ってことはまずない)。今年の秋もまた、そういう人たちに引きず
られた練習をするかと思うと、ちょっと憂鬱になる。京都補習とか大阪補習とか、パートオーディシ
ョンとか絶対やるもんか。もうしんどい、疲れた。
17:20、自転車で実家に帰る。20:00ごろ、家の前で送り火。むかしは大文字があっても、各家庭で
送り火をしていたらしい。22:00ごろ、帰宅。夕食のまえくらいから、調子が悪く、頭痛と気分が悪
かったため、帰宅してすぐ就寝。更新、やすませてもらいました。ごめんなさい。
以上、8/17日朝記す。
- 2006/8/15(火)

東京はどこへ行ってもクレーンが建っている。巨大なクレーンには、日常にはありえない大質量感
が漂うせいか、大変フォトジェニックだ。みかけるとついつい撮ってしまう。
きょうは、午後一番に安藤忠雄が手がけた表参道ヒルズへ。まぁ、予想はしていたことだけれど、
建築はとてもいい。地上部分は3階までしかないにもかかわらず、中に入ると6階分、つまり地下
3階までの大吹き抜け空間が広がり、表から見たときとのギャップに驚かされる。そして、そのす
べてのフロアが、スロープによって一筆書きで移動できるということに、またまた驚く。奇をてら
った設計ではない。限られたスペースにひと続きの長いプロムナードを折り畳んで、それをひとつ
の建物にまとめてしまうという一次元→二次元変換を合理的に行った結果である。上下階は階段と
エレベータ、エスカレータでつなぐという常識をこれまで誰も疑わなかったのは不思議である。
安藤忠雄はやはり凄い。で、「建築は」と断ったのは、テナントが面白くないから。このビルのオ
ーナーは「ヒルズ」の名前でわかるように森ビルである。だから、テナントの多くは六本木ヒルズ
の縮小版という感じがした。スロープを歩いてみても、あまり気軽に立ち寄れる感じがしない。少
なくとも男性客には退屈至極。敷居を下げるべき、とは安易には言わないけれど、バリエーション
が少ないとリピーターがつかないのではないだろうか。一番賑わっていたのが、地下3階にある文
房具店と、京商(ラジコンメーカー)のオフィシャルショップであるように見えたのは気のせいで
はないと思うのだが。個人的には本屋を誘致しなかったのは疑問。大型書店ではなく、個性のある
セレクトショップ系書店、古書店ならば表参道の立地とマッチしただろうに。
その後、渋谷から東急東横線にのり中目黒へ。途中経由とはいえ、渋谷はなるべくなら行きたくな
い街である。新宿の方がまだまし。いや、100倍はいい。中目黒には古書店「ユトレヒト」に行く
ため降り立った。が、前日地図をネットでちょろっとみて、うろ覚えのままだったため、見事に迷
った。地図を残したMacを東京駅のコインロッカーに朝入れてきたのが悔やまれる。というか、自
分の記憶力を過信しすぎなんだな。それはともかくとして、外出先のPC運用で一番困るのがプリン
トアウトがなかなかできないということだ。いつでもどこでも、PCは持ち運べる時代になったけれ
ど、紙媒体の携行のしやすさ、視認のしやすさ、共有のしやすさは揺るぎのないものがある。コン
ビニに複合機を置いて、無線LAN接続で最寄りの店でプリントアウトができるようなサービスができ
ないものだろうかと思う。結局、友人の何人かに電話をかけて、店の電話番号を調べてもらうこと
にした(仕事中の対応、ごめんなさい。そしてありがとう>TAM師)。
そこまでして行くことにこだわったのは、その店が予約制だったから。15:00からの回をとってい
たので、たどりつかないわけにはいかない。しかし、なんだって予約制?。その答えは着いてみて
わかった。マンションの一室、わずか三畳ほどのスペースの3面に棚が置かれていたからだ。三人
も入ればぎゅぎゅうで、閲覧どころじゃない。二人が限度である。
ここではドイツの活版印刷工房から送られてくる紙モノのハギレセットと、ほか3冊の古書、新刊書
を買った。迷ったせいと、時間制約(今日は帰る日だった)で、自分のなかであわただしくなってし
まって、いまいち古本屋で味わう高揚感がないまま去ったのだけれど、帰宅して買った本を眺めると
なかなかどうして、いい本とめぐりあってるじゃあないか、と思えてきた。たどりつくのに迷っても、
一度行った場所は忘れないのがわたしの取り柄。つぎからは、もっとゆったりとした気持ちで臨める
はずだ。
16:46、東京発。
携帯電話に連絡あり。今週末の軽井沢行きのマネージ。メールのやり取りでは間に合わず、ついに
電話で直接。事務局もせっぱつまってきた様子が電話の向こうに感じられた。でもねぇ、新幹線に
乗りながらはちょっと無理があったなぁ。2回くらい途切れてしまったし。車中でわからない件は、
在阪のメンバーに頼んで、なんとか終了。30~40分くらいかかった。
やっぱり休暇中は連絡の取れないところか、携帯やPCに出ない、使わないようにしないといけない。
休暇にならないもの。昨日の夜と今朝も実はホテルでマネージをしていたし。ちょっと愚痴っぽく
なってしまった。お許しを。
20時頃、帰宅。
- 2006/8/14(月)
朝起きると、東京では大規模な停電が起きていた!。しかし、わたしは無事。よかったよかった。
(誰からも安否を気遣うような連絡が入らなかったので、自分で言ってしまう。)
昼くらいに親から電話があったのだが、「そうめん茹でたし、うち(実家)帰ってくるかー」だった。
まだ東京にいるっちゅーねん、と返事。そもそも停電があったことすら知っているかどうか怪しい。
どうなんだろう?大事には至らなかったものの、かなりの社会インフラが停止していたし、一国の首都
なのに、あまり騒がれなかったのは不思議。まぁ、パニック状態になるよりかは冷静な方がいいのだけ
れど、当然。システム関連の仕事に就いている人はそれどころじゃなかっただろうなぁ。京都で同じこ
とが起きたら他人事ではないんだけどさ。
午前中、東京都庭園美術館。あまりの「アールデコ祭り」加減に、心のなかで一人浮かれてしまう。
昼、新宿で友人と昼食。トマトのカレー。さくらやホビー館に案内してもらう。ええとこやー。
午後、テアトル新宿にて映画「時をかける少女」を見る。これから10年さきまで、この映画をこえ
えるアニメーションは出てこないかもしれない。もう一度みたい、なんどでも見たい。「思い出さ
くても大丈夫なように」(奥華子)。走る、走る、飛ぶ、転ぶ。なんども転ぶ、そんなヒロイン真琴
の、前に進むことをあきらめない姿が、胸を打つ。世界のために未来を変える、なんて大層な話はこ
こにはなくて、自分の大切な感情のために未来を選択する。青春だな。憧れてしまう。

夕方、ホテルから見える川と、その先の高層ビル群をぼけーっと眺める。川というか、運河の景色が
好きなのである。同じホテルの反対側はオーシャンビューなのだけれど、ことここに限っては川側の
方をいつも選択する。海側はなぜか料金高いのですよ。経済的には助かるけれど、差別するんじゃな
いと言いたい。あまり一般的な意見ではないか。
あしたは、どこへ行こう。
- 2006/8/13(日)

コミックマーケット70@東京ビッグサイト、第三日目。
一般参加。
全参加者の皆さんお疲れさまでした。今日はゆっくりやすむぞお。
と思ってたけれど、ちょびっとだけNCマネージ。いろんなことから逃れられない運命なのか...。
- 2006/8/12(土)
コミックマーケット70@東京ビッグサイト、第二日目。
サークル参加。西れ04b「山Dの電波暗室」。
サークルにお越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。
それから差しいれをいただきました方、ありがとうござます。
帰宅してからいただこうと思います。うちのサークルで差しいれをいただけるなんて。
スケブ書いてくださいって言われても書けない(当たり前だ)のに、申し訳ないです。
既刊の2冊は完売いたしました。再版の予定はありません(弱小個人サークルなので、すいません)。
新刊在庫は100冊ほどありますので、次回も続けて頒布します。
売り子を交代で努めていただいたS雄さん、T氏、H本の三氏に感謝。
その日の行動記録。
7:00、友人に「こことここの書体の大きさが一致してないー!」と、こっぴどく叱られる夢で起床。
8:30、ビッグサイト到着。
10:00、開場。ほとんど人が途切れない立地のおかげで、好調。
14:25、売り子を三氏に任せて、ビッグサイトを出発。
14:30、暴風雷雨。一歩踏み出したところで傘が折れる。「失うものは何もない」精神で、雨中吶喊。
14:40、りんかい線国際展示場駅到着。全身シャワー状態。
15:00、大井町着。落雷により山の手線停止。京浜東北線は動いていたので助かる。一瞬あきらめかけた。
15:20、東京着。
15:46、東京発。ホームで買った新聞紙を丸めて靴に放り込む。服は自然乾燥。
18:19、新大阪着。
18:30、大阪着。
18:40、大阪城公園駅着。
18:50、淀川混声合唱団第18回演奏会@いずみホールを、第三ステージから聞く。
19:45、終演。
20:15、いずみホールを出立。
20:46、新大阪発。
23:19、品川着。
23:30、大井町着。大浴場は24:00までだったので、なんとか風呂には入ることができた。
24:10、就寝。
翌4:50、起床。
演奏会の第4ステージ、シャガールと木の葉(作詩:谷川俊太郎、作曲:北川昇)の初演、これを
聞くことができて本当によかった。羽毛布団にくるまれて、眠っているかのような安らかな気持ち
になれた。(雨にうたれたせいか、ちょっと熱っぽかったからかも。)
- 2006/8/11(金)
コミックマーケット70@東京ビッグサイト、第一日目。
一般参加。
一日目終了。ホテルの無線LANスポットから更新。ビッグサイトから帰着後、NCマネージ。
軽井沢合唱フェスティバルの担当者から電話があったのだ。担当者はどういうわけか、現在海外に
いらっしゃる。日本語環境のPCがないためメールはローマ字!。今日は、そのPCの調子も悪くて、
直接電話で話すことになった。しかし、先方もわたしが東京にいるとは思ってないだろうなぁ。
正直、こんなところに来てまでマネージするとは思わなかったヨ。技術の進歩も善し悪しだ。
あしたは、サークル参加の日。長丁場の一日、頑張ります。
あす演奏会があるYKのみんな、がんばれー。
- 2006/8/10(木)
最終日にありがちなトラブルに巻き込まれることなく、なんとか帰宅。実は昨日、コンセント
が抜けてサーバーが落ちるという(正確には無停電電源の電池が切れるまで駆動してから)、
えらくマヌーなミスが発生していたのだった。あんな場所のコンセントが抜けるなんて通常あ
りえないのだけれど、ありえないことが起きるからトラブルなんだ。抜けにくい工夫と、あと
とどめに"DO NOT REMOVE!"というでっかいタグを括りつけてから帰宅した。ともかく、夏季
休暇中に発生しなくてよかった。
それでは、行ってきます。
追伸:MacBookを持っていくので、メールチェックと若干の更新は可能かも。
- 2006/8/9(水)
手伝ってくれた友人に新刊を手渡す。目を丸くしたり、じーっと見つめたり、ちょっと離して
見てみたり、読んでいる姿を観察すると面白い。ひとしきり話をして、別れたあとに気づいた。
できあがった本の感想、ちゃんと聞いていなかったよ。メールで画像や文章をやり取りしてい
たので内容は知ってもらっているけれど、「本」としてどうなのかは、やっぱり「手にとれる
形」でないと、実感としてわかないものだろうから。
夏コミ直前、あたふたと落ち着かない。あれもしないと、これもしないと、って思っていると
すぐ時間が過ぎて、気がつくと何も進んでいない。とりあえず必要な荷物を全部、ベッドの上
にずらっと並べてみる。旅行の準備をするときのわたしのやり方なのだけれど、ひとによって
違ったりするのだろうか。ちなみに映画「恋愛小説家」で、ボルチモアに旅行することになっ
たシーンで、ジャック・ニコルソンは、わたしと同じやり方をしていて、ヘレン・ハントの方
は旅行カバンを取り出して、片っ端からほうりこんだあげく、「旅行って何をもってたらいい
の?」と途方に暮れていた。男と女でも違うんだろうな。
「あたふた」を落ち着かせるために、ネットラジオのHAPPYDAYを聞く。ピアノのインスト中
心の選曲なので、いつまでもとぎれることなく聞いてしまう。ネットラジオを屋外で移動しな
ながら聞けたらいいのに、と思う。次世代のネット接続であるWiMAXが実用化されれば、そん
なことも可能になるんだろう。もちろん、新しいiPodで聞くわけだ。
- 2006/8/8(火)
新刊、印刷できました。入稿してからできるまでの間はやっぱりすごく不安。
ところで、ひとつ気づいたことがある。今回、紙が薄い。じつは前回の紙がどんなだったかを忘れ
てコート110kgで注文したのだけれど、どうもコート130kgだったみたい。紙の重さが変わっても
印刷+紙代は同じなので、頒価はそのままにさせていただきたく。すいません。印刷クォリティー
は変わらないので、ご安心を。ばっちりです。m(__)m
既刊のvol.1とvol.2は、それぞれ在庫100冊を持っていく予定。完売すると嬉しいなぁ。
そもそも本の在庫って重い。今回、どうあっても新刊と既刊を運ぶのは無理だと思ったので、急遽
東京在住の友人に連絡して、既刊のみ宅配便で送らせてもらうことにした。去年、無理して運んで
ひどい腰痛になったから、その轍は踏むまい。腰痛の原因は、キャリアの持ち手が短くて、腰を屈
めぎみだったことも原因だろうと思う。今回は引きひもをつけてみる。
考えてみるに、新幹線直結で移動できるわたしなんかは、まだいい方なのだろう。飛行機で来る人
とか、途中まで在来線の人とかは、本を持っての移動は大変だろうな。バリアフリーじゃないとこ
ろは都心でもまだ多いのに。東京の友人宅なんて、大使館が密集する地域の駅なのに、エレベータ
もエスカレータもないもの。ひきとったあと、ホテルまで持って帰るのどうしよう。
出発まであと二日。サークルチェック終わってない。
新幹線のなかでやろう。
あ、そうそう、今日の夕焼けは台風のせいか、劇的なまでにきれいでしたな。最初は、黄色のフィ
ルターをかけたかのような空、そしてだんだんセピアになって、西の空には本当に真っ赤に縁取ら
れた巨大な雲。。。きれーやった。で、そんな時に限って、デジカメにSDカードを差し忘れてるわ
けです。ショック!いいや、記憶に刻んだから。
- 2006/8/7(月)
さだまさしが毎年、原爆忌に開催していた「夏・長崎から」が20回目の今年でラストであると、
ニュースで流れていた。来年は広島で、本当のラストをやるという。中学生のころ、このコンサ
ートをFMラジオで聞き、録音したことを憶えている。平和コンサートであるという主旨、さださ
んの事務所が費用を負担する無料コンサートということは、何も知らなかったけれど、昔はお金
を貯めていつか長崎へコンサートを聞きにいきたいなと思っていた。あのとき録音した曲は、
「しあわせについて」。何度もくりかえして聞くうちに、覚えてしまった。何も知らない中学生
にも、切ない歌だとわかって、聞くたびに胸に沁みた。曲を語りあえるような同級生がいるはず
もなく、ひとり”老けていた”中学時代であった。
夏コミ後の予定を考えてみた。あけて月曜日は美術館/博物館が軒並みアウトなので行き場がな
いのは毎年同じ。今年は唯一、東京都庭園美術館が開いていた。しかも、展示は旧朝香宮邸のア
ールデコ、つまり建物自体が展示なのだ。場所限定で館内の写真撮影も可とあってはいかないわ
けには行かない。場所は目黒。
あとは、代官山にある古書店、ユトレヒトとハックネットへ行ってみようと思う。「古本道場」
で紹介されていたのを読んで、神田とは違うところに行ってみたくなったのだ。
最後は新宿。テアトル新宿で「時をかける少女」を見よう。19:10の最終回なら見れないことは
ないと思いたい。ちなみに8/8,8/18,8/28は、「メガネ女子胸キュン祭り」だそうで、メガネ
女子は非売品のポストカードがもらえるらしい(「8」の字をメガネに見立てている)。主人公
の真琴はメガネかけていないけれどいいのか?変な映画館。
目黒、代官山、新宿。あまりわたしには似つかわしくない場所かも。
つぎの日は、神田に寄ってから帰るとしよう(そういえば、去年も神田から帰ったなぁ)。
追伸:時をかける少女、京都でも京都シネマで8/19から上映するとのこと。
- 2006/8/6(日)
一ヶ月ぶりくらいにモールトンで走行。五条から西京極、サイクリングロードで嵐山。丸太町通り、
下立売沿いに烏丸まで。約24km程度。目的はただ、モールトンで走ること、汗をかくこと。この夏
の最高気温(38℃)の日に、そんなことして大丈夫なの?虚弱体質なのに。と思った方、心配無用。
しんどくなかったです。秘密はたぶんヘルメット。自転車用のヘルメットは、軽量化と蒸れ防止のた
めに、多くのエアインテーク、つまり空気穴が空いているのだ。このため、ただ普通に歩くだけでも
空気が風となって頭に吹き付けるようになっており、自転車で走行すれば、その効果は絶大。おかげ
で気持ちよく走れたのだった。しかし、夏場の走行にはもうひとつ問題があって、そちらは未解決の
まま。路面がまぶしいので目がかすむ。ようはサングラスがあればいいのだけれど、眼鏡装着の身と
してはなかなか選択できるアイテムがない。あと、友人に「山Dさんには、サングラスは似合わない」
と明言されている点も問題。まぁ、認めましょう。でも、すでにヘルメットかぶってる姿が似合って
いるとは思えない(頭が大きいから)ので、サングラスをかけてもあまり変わらないと思うんだけれ
どね。どうでしょう。
帰宅途中に、時計屋(アンティーク専門)に寄って、いろいろ見せてもらう。


(注:店の時計。買ったわけではないです)
昨日のNCの練習参加のときにも注意して見ていたのだが、やっぱり普段時計をしない人が増えてい
る。ベースの参加者6人中、わたし以外で時計をしていた人はいなかったように思う。仕事のとき
もしていないかどうかは、もちろん不明だけれど、社会人として人と接する機会がある人は、時計
をはめておくべきではないかなと思う。ビジネスマナーとまでは言わないけれど、初対面の人を推
し量るとき、もっとも見られているのは「靴」と「時計」の2つであると、プレゼン研修の講師も
言っていたし、事実わたしは必ず時計を見る。(講師の時計はショパールだった。お洒落だ!)
誤解のないように言っておくと、高い時計か安物の時計か?ということが問題ではない。その人の
人となりが、即座にわかるわけでもない。ただ、その場に臨むときの姿勢というものを判断する材
料にはなる。人と会うということは、その人と自分とが時間を共有するということであり、同時に
相手の時間をもらっていることにもなる。「貴重なお時間をいただき...」というのは挨拶の常套
句であるけれど、本当にそう思っているならば、それを目に見える形であらわす必要があると思う。
時計を身につけて、時計を見て時間を知るということだ。相手はきちんと見ている。時計をしてい
ない人がそれを言っても、どこかそらぞらしい。たとえ部屋に置き時計があったとしてもだ。
まぁ、本音をいえば、こんなビジネスのためにという外的要因ではなくて、もっと内面的な要因
つまり、その時計が好きだから身につける、というような人が増えてほしいと思っている。時計
好きなわたしとしては、個人個人が選んではめた、いろいろな時計が見たいから。
- 2006/8/5(土)
「時をかける少女」見れず、無念。
14:35の上映を見るために、1時間20分くらい前に梅田の劇場にいったのである。ところがその時点
で残席わずかの表示。どれくらいかなぁとおもっていたら残り1席!しかもわたしの右隣の男性に優
先権がある状態であった。次回の上映は17:00前なので、4時間近くも大阪で時間をつぶさなければ
ならない。それになにより、NCの練習に行けなくなってしまう。断れ~断れ~と念を送り続けた結果、
男性は次回上映に変更した。すごいぞ、わたしの念。ちょっと小躍りしたい。
ところが、ほどなくその男性が翻意した理由が判明する。「最前列のお席で、しかも、たいへんみづ
らくなっております」と係員はのたまったのだ。最前列くらいの覚悟はあったのだけれど、たいへん
みづらいと言われてしまっては見る気が萎えた。だいたいそんな席を販売するなんてどうかと思うぞ。
結局、断って劇場を出た。ああ、なんでそんなに人気があるに、こんなに上映館が少ないんだ。配給
元よ、なんとかしてくれ。(京都では上映なし)
しかたがないので、夏コミで東京へ行ったときに見ることに決めた。
(自分のホームグラウンドじゃない都市で映画を見るのは、それはそれでオツなものです。経験あり)
予定していた二時間がぽっかり空いてしまったので、ひとまず劇場の階上にあるロフトへ。その後、
大阪駅前のBook 1stを散策。いい書店ですね、ここは。
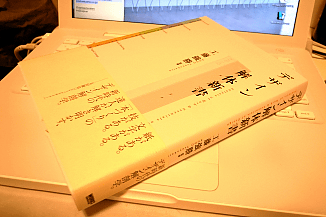
「デザイン解体新書」、工藤強勝監修、ワークスコーポレーション刊。2500円。
ずっと探していた本を発見。新刊原稿を始める2ヶ月くらい前に一度、京都のジュンク堂で手に取って
いたのだが、以後さがしてもさがしても見つからず。本当は原稿を始める前に読みたかった本。一見、
デザインの哲学書のようなタイトルとデザインだけれども、中身はエディトリアル・デザインの実践的
な指南書である。雑誌や、本の誌面デザイン(主にレイアウト)の教科書的な本はたくさんあるのだが、
それらの本には共通して不満なところがある。実際のプロが作成した誌面を掲載して、それに対して、
こういう絵作りをしなさいとか、ここがポイントと書かれてはいるけれど、どれもが観念的すぎて、
単なるレイアウトの見本集になってしまっているのだ。「見て感じろ」というのなら、わざわざそんな本を
買う必要はない。欲しいのは、デザインをするための感性じゃない。デザインをするための「ルール」
なのだ。プロの世界には暗黙のルールがある。それは例えば、文字と文字の間隔はこうあれかし、写真
と文章はこう組み合わせるべし、書体はこう使い分けるべし、といったものだ。デザイナーの感性によ
るものと思われている部分の多くは実はノウハウであり、ルールなのだ(感性が不要なわけではない)。
この本にも実際の誌面は登場する。しかし、その前にそのデザインがどういう指示(ルール)のもとに
作成されたのかが、必ず記されている。例えば、同じ等級、同じ字面の漢字とひらがなを並べるとバラ
ンスが悪い。だから、縦横比が10:9に設計された「小がな」を使う(これは縦組の場合)、といった具
合。このような事例が、具体的な誌面や文字組み、ときには比較によって示されているのだ。なぜ、こ
のようにレイアウトされているのか、なぜその誌面を見たときにきれいだと感ずるのか、そういうこと
をまさしく解体して説明しているのは、この本以外にはこれまでなかったように思う。
ところで、さきほど感性が不要ではないといったのは理由がある。いくらノウハウがあっても、二つの
事例を比較しているとき、どちらがより美しく、または読みやすく設計されているかということは、
本人が感じとるしかないからだ。この本のデザイン指示の多くも「見た目で調節する」という、いって
みればあいまいな記述が結構多くある。数値で指定しきれない部分だ。それは骨格はノウハウでつくり、
最終的な仕上げは個人の感性に依存するということを意味すると思う。骨格がしっかりしていればこそ
感性を発揮する部分もあろういうもので、特に時間の区切りがある仕事には、骨格に費やせる時間は限
られているのだ。その部分「暗黙のルール」があきらかになっていれば、はじめから高い位置でスター
トできるのはないだろうか。
わたしは、デザインを生業とするプロではないけれども、デザインしたものを多くの人にみてもらうと
いう立場はプロと変わりがない。規模が大きいか、小さいかの違いだけだ。だからこそ、読んでもらう
人、見てもらう人には「良い本だなー」「選んでよかったなー」と思ってもらえるデザインをしたいと
思うのだ。自分自身が、その本を身銭を切って所有したくなるものなのか?本を作っている最中は常に
そのことを考えている。
だから、今回は間に合わなかったけれども、今の自分の段階をひとつ乗り越えるためにも、この本を読
んで勉強しようと思うのだ。
いつになくまじめに語ってしまったけれど、文字校正のルールなんかは、これはこれで全く知らないの
で、デザインとは別に勉強しないといけないなぁ。
YK見学、17:00-17:30。(頑張って、YKのみんな)
NC練習、17:30-21:15。
- 2006/8/4(金)
BK練習@おうき会館、19:00-21:00。
BK宴会@花いちりん、21:30-23:00。
あしたは、練習前に「時をかける少女」を見に行くぞ。
楽しみ。
- 2006/8/3(木)
入稿しました。5日後に上がってくる予定。かなり余裕を持って始めたはずなのに、結果的には
いつも通りのぎりぎりになってしまった。後半の怒濤の進行のなか、連日手伝ってくれた友人に
感謝。
あとは当日用のペーパーとか、今回は壁なので大判のポスターなんか用意できたらいいのだけれ
ど。。。あと少しだけ頑張ってみようかな。
というわけで、夏コミ新刊出ます!
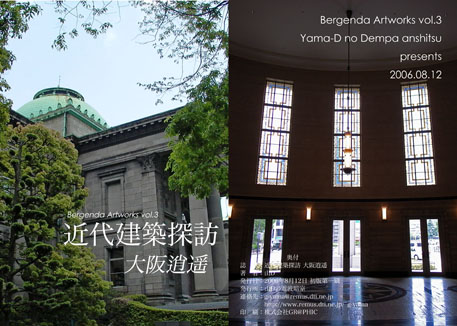
「近代建築探訪 大阪逍遥」、B5版フルカラー16ページ。頒価500円。
8月12日土曜日、西地区「れ」04b、「山Dの電波暗室」にてお待ちしています。
既刊「近代建築探訪 東京・横浜篇1」「近代建築探訪 京都断章」も、まだあります。
東京、京都、大阪の三点セットで是非どうぞ。
- 2006/8/2(水)
まだ原稿も終えてないのに、終わったも同然な気持ちになってしまい、本屋に寄って雑誌1冊
(Mac People9月号)と、漫画二冊(HELLSING8巻、GUNSLINGER GIRL7巻)を買ってし
まった。せっかちなのである。新潮文庫の新刊に、川上弘美の本が出ていたので買おうか買わ
ないか迷う。この前買った短編集がまだ読了していないから、という理由で今日はやめておい
た。でも、東京行きや軽井沢行きのときに、持っていくのなら文庫本の方がいいかもなぁと、
すでに買うための言い訳を考えだしているのだった。じつは、旅行用にということでは、すで
に伊藤たかみ(祝!芥川賞受賞)著の「ミカ!」を買っている。どちらかを滞在用、あるいは
往路用、復路用に設定しよう...。
あとどれだけ作業すればいいのか予測がつかないのに、気の大きいままスタンドで食事をし、
その足でユニクロに服を買いにいくことにした。夏コミ用ということで。ズボンと、ポロシャ
ツを選んでいたのだが、ハタと気づく。「サイズわからん!」
ふだん滅多に服を買わないわたしは、自分の服のサイズを把握していない。MだったかLだった
かそれくらいのレベルもわかっていないのだ。日常生活の優先順位の低さがうかがいしれます
な。そんな状態なので、ポロシャツは家に帰って去年かったサイズを調べることにする。ズボ
ンなんか、cm単位なのでこれはもうお手上げ。デパートだったら腰回りを測ってくれるわけだ
けれど、ユニクロではどうか。言えば測ってくれるかもしれないが、店員に声をかけるのは、
かけられるよりも苦手なのであった。かくして、週末に再度訪れる決意をして去った。
ポロシャツのサイズはL、腰回りは84cmくらいと判明。鉄のメジャーで測ったから、誤差がある
だろうなぁ。ちなみに、去年はどうやってLサイズにしたかというと、勘。帰宅してから着込ん
だらちょうどだったので、当たったわけだ。じつは、きょう「Mでいいかなぁ」とちょっと思っ
ていたので、買っていたら外すところだったのだ。あぶないあぶない。
あとはポロシャツの上と、ズボンをどういう風にあわせるのが良いか考えてみる。
...自分にあってるのか、あってないのかよくわからぬ。
求む、スタイリスト。テーマは夏コミ&軽井沢カジュアル。
テーマが相反しすぎているか。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 100%(決定稿)
序、中表紙 100%(決定稿)
建築その1 100%(決定稿)
建築その2 100%(決定稿)
建築その3 100%(決定稿)
建築その4 100%(決定稿)
建築その5 100%(決定稿)
解説 100%(決定稿)
丁合い完了。完パケCD作成完了。
- 2006/8/1(火)

午後7時15分。帰宅途中。
夏の雲が好き。夏の夕焼けが好き。
昔は秋の方が好きだったはずなのに、いつのころからか夏が好きになっていた。
それだけ、自分が活動的になってきたということなんだろうかなー。
入稿が終わったらしないといけないことを忘れていた。サークルチェック。
まったくやってないのだった。うーん。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 100%(決定稿)
序、中表紙 99%(序文第三版作成→校正完了)
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 100%(仮決定稿)
建築その5 100%(仮決定稿)
解説 99%(校正完了)
入稿予定日修正→8月3日(木)
- 2006/7/31(月)
MacBookで文章を書くとき、あるシェアウェアのエディターを使っている。こうやって暗室
のようなhtml文章を作成する分には、標準のテキストエディットとはほとんど大差がないの
だけれど、今回の夏コミ原稿を書いているときに便利な機能?を発見した。新規作成すると
きにテンプレートとして「原稿用紙20字×20行」というものがある。これをひらくと、画面
に文字通り、原稿用紙のマス目が表示されるのだ、それもちゃんと茶色の。1マスは1cm角
くらいの大きさで、ちゃんと1文字に対して1マスが使われる。その分、フォントは24ポイ
ントくらいになるのだけれど、これが手書き原稿の大きさと同じくらいで、実はとても見や
すいのだ。そして、そのせいか、かなりさくさく書ける。ちょっと乗ってくると、400字が
あっという間に埋まってしまう。そう、この「文字が埋まる」という感覚が気持ちいい。
限りなく広い、無地の地平のようなエディターに文章を書いていると、どこからが始まりで、
どこが終わりなのかが、ときどきわからなくなる。メールを書くときも似たような感じにな
る。自分は、いまどれくらいの分量を書いたのか。多いのか少ないのかの判断が狂う。それ
はとりもなおさず基準がないからだ。原稿用紙のような。
「紙幅がつきる」という言い回しがある。それは限られた文字数におさめなければならない
ということを物語っている。その言葉は、原稿用紙に直筆で文章を書かなくなった現代にな
ってもなくなることがない。文字数の制限からは、決して逃れられないからだ。物を書く
人間と、それを編集する人間は。
なにが言いたいかというと、せっかく文字数が一発でわかるような機能を手に入れたのなら
ば、それを有効に使わないといけないということだ。レイアウトしてみたら、文字が収まり
きらなくて、もう一度そのレイアウトにあった文章を練り直さなければならない、という愚
をおかさずにすむように。まさしく、昨日のわたしがそうだったのでした。
もう少し、あともう少しだ。
原稿終わったら、モールトンに乗って、どこかに写真をとりにいきたいなぁ。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 100%(決定稿)
序、中表紙 95%(中表紙レイアウト完了。序文第二版作成。校正依頼中。)
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 100%(仮決定稿)
建築その5 100%(仮決定稿)
解説 95%(レイアウト完了。校正依頼中。)
追記:小池真理子著「恋」、読了。半分を過ぎてからは一気読みに近かった。
哀しい終わり方でなくてよかった。人の営みは時に不可解で、理解しがたい
こともたくさんある。だから単純化して、類型化する。でも、ひとつひとつ
の感情を丹念にひも解くことで、その人にしかわからないはずの感情に、次第
に近づき、そして共感を覚えていくことができる。理解することは難しくても
共感ならできる。そのことをとてもよく著した小説だった。この小説の「官能」
は重要な要素だけれども、ある意味目くらましだったのかもしれないなと思う。
あらすじに書かれた文言「その奥底に漂う静謐な熱情」は、とても的確な表現
だなぁと、読了してから思った。
- 2006/7/30(日)

四条通り、午後7時半。
全然、体調が戻っていない。何かに中ったとしか考えられないナァ。かなりまいってます。
午前中はごまかし、ごまかし自宅で作業。午後になって、やや回復。
13:00-17:00、カフェベローチェにて原稿作成。
17:15-18:00、バッテリー切れのため自宅にて原稿作成。
18:00-20:00、夕食、休憩。
20:00-22:00、カフェベローチェにて、原稿作成。レイアウト作業。
22:15-22:30、自宅。洗濯物を干す。ご飯を炊く。
22:30-24:00、自宅にてレイアウト作業。
あと少し。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 100%(決定稿)
序、中表紙 75%(序文校正→修正中)
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 100%(仮決定稿)
建築その5 100%(仮決定稿)
解説 95%(レイアウト完了)
- 2006/7/29(日)
お腹の調子がよろしくないので、弱冷車に乗って、阪急宝塚線清荒神駅へ。
10:00-11:30、14:00-17:00、第22回宝塚国際室内合唱コンクール(@宝塚ベガ・ホール)を聞く。
フォークロア部門、石川のLa Musica、東京の菊華アンサンブル、大阪の畷ユースアンサンブル ミュスカが、
私的な三賞。実際の結果はしりませぬ。この三団体は皆、顔がよかった。実際聞いているほうも、幸せ気分。
畷は、ひいき目入ってるかもしれないけれど、やわらかい空気が心地よかった。ソプラノからアルトまです
べてのパートが同じ息の流れ、速度を共有しているのがわかる。そこがメンバーが似通っている、コール・
シェリーとの違いかな。なんだか、ほっとした気持ちをもらいました。一瞬、胸にズキュンとくるところも
あったし。
11:30-12:00、昼食。商店街のいつもの中華屋でやきめし。おなかはすく、さりとて食欲は微妙という状態
だったので。やきめしください、って頼んだのに、「チャーハン一丁」とオーダー。メニューにはやきめし
しかない。
12:00-13:30、隣接する図書館で原稿下書き。
13:30-14:00、ペンディングしていた「恋」の読書を再開。この間に文庫本4冊読んだ。長かった。
17:00-19:00、お腹の調子戻らず、微熱が続くため、NC練習を休み、帰宅する。
20:00-21:30、練習は休んだけれど、NCマネージはあるのだった。
原稿は、いよいよ明日が正念場。きょうは正露丸飲んで寝ます。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 100%(決定稿)
序、中表紙 75%(序文校正→修正中)
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 100%(仮決定稿)
建築その5 100%(仮決定稿)
解説 75%(下書き作成、レイアウト検討)
- 2006/7/28(金)
BK練習、間に合わず。
BK宴会、21:30-22:30。途中退出。
NCマネージ、23:00-25:15。
大人数の部屋割りって、なんてめんどくさいんだろう。
NCのメンバーなんか、寺だとか合宿所の大部屋に、全員雑魚寝でも一行に構わないのに。
なんだったらテントを張って、キャンプでもいい。たくましいから。
体調不良(腹痛、微熱)。
起きたら直ってますように。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 100%(決定稿)
序、中表紙 75%(序文校正→修正中)
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 100%(仮決定稿)
建築その5 100%(仮決定稿)
解説 50%(参考文献調査)
- 2006/7/27(木)
体調不良、あまり改善せず。悪いことは重なるもので、一昨日のレビューを開発部門に対して行ったと
ころ、かなり冷ややかな反応。その場にはこの前説明した工場部門のメンバーも出席していたのに、援
護射撃いっさいなし。四面楚歌状態となってしまった。手回しがぬるかったといえば、それまでなんだ
けれど、悪ければ開発中止という状況も想定されるまでに急転直下したのには、立ちくらみを起こしそ
うであった。正直、気持ちが萎えた。夏休みまでに、説得する計画とスケジュールを立てて、帰宅。
原稿の序文を書く。昨日の遅れを取り戻すには、いたらず。序文だけに、いろいろと試行錯誤。解説の
ほうが、まだスピードはあがるかな。でも、これでなんとなく芯が定まったような気がする。
きょうは、早めに休みます。
きのうよく眠れなかったので。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 100%(決定稿)
序、中表紙 50%(序文作成)
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 100%(仮決定稿)
建築その5 100%(仮決定稿)
解説 50%(参考文献調査)
- 2006/7/26(水)
・体調崩著。
・頭痛頻発。
・意識朦朧。
・原稿未完。
・安眠不可。
・老天爺。
- 2006/7/25(火)
懸案であった仕事のレビューが完了し、ほっとひといき。わたしのいる拠点と北陸にある三拠点を
結んでのTV会議であったが、正直なところ、各地に出張して直に説明をしたかった。というのも、
TV会議は、従来のものより画質が良くなって、応答速度も早くなっているのだが、それでもはっき
りと相手の表情がみえるほどではない。TV画面を分割していればなおさらだ。(個人個人ではなく、
各地のTV会議室のカメラでとらえるから。)そして、こちらのPCの画面を相手方に映して、資料を共
有する機能があるのだけれど、これのせいで誰も説明者である私の顔姿を見ることがない。わたし自身
もカメラに向かってではなく、資料を前に移して、マイクに向かってしゃべる。張り合いのないこと
はなはだしい。プレゼン中の相手との距離がまるで測れないのだ。しゃべるスピードも、間の取り方
も相手がみえてこそできることで、途中から「自分は本当にいまプレゼンをやっているのか」と疑問
がわいてきた。画面に向かって、練習しているのじゃないかしらんとまで思えた。
わたしがいる会議室にも、参加者はいるが、彼らと顔をあわしながらプレゼンをすると、カメラから
目が離れるので、ほかの拠点からはそっぽを向いて話しているようにみえるはずだ。やれやれ。
出張経費の削減という大きな問題はあるけれども、ひとに使ってもらうシステムの説明は、やっぱり
そのひとたちに直にしたいし、反応がみたい。終わったあとの質問や雑談で、なにかヒントをもらえ
たりすることもある。これは仕事とは直接関係ないが、拠点から拠点へ電車で移動し、各地で宿泊す
るということ自体に、日頃の仕事を少し忘れさせてくれるものがあって、仕事だけど仕事じゃない、
仕事じゃないけど完全なプライベートでもない、そんなどっちつかずの時間がなんとなく好きである
ということもある。もう二年近く、北陸には出張していない。出張するたびに、トラブルに巻きこま
れて、ホテルへ帰るのが深夜続きなんてこともざらだったけれど、それでも仕事を終えたあとの充足
感は、いま感じているものよりもずっと大きかった(充足感と仕事の出来映えが比例するかどうかは
別の話)。
とはいえ、ひとつ終わった。ささやかな充足には、ささやかな祝いで対応したい。そう、思って今日
はフンパツして、サイコロステーキ定食(890円)を食べたのだった。
これでお酒が飲めればなー。気持ちいいんだろうなあ。
長野にいる同期から、結婚するから9月に長野に来てくれーという電話。軽井沢でも一緒に歌う予定。
ふだんこちらにいる同期や友人とは、あまり話さないような話題をお互い話す。なんだか、気分が落
ち着く。近くにいる友もありがたいけれど、遠くにいる友もやはり同じようにありがたいものだなー
と思った。ふだんはわすれがちなことだけど。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 100%(決定稿)
序、中表紙 0%
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 100%(仮決定稿)
建築その5 100%(仮決定稿)
解説 50%(参考文献調査)
- 2006/7/24(月)
研修続きはやっぱりきつかった。終わってからふらふらと二時間残業後、帰宅。駅の階段で最後の
一段に気づかないくらい、ぽわーんとしていた。それから、みどりの窓口に並ぶ人の列が通路を遮
っているのをみて、「ダメな列だー」と思う。列は自分たち自身で、有機的に変化しなければなら
ないのだ。通路を塞ぎそうだと思ったら、直角に折れるとかしないと。あるいは、駅員が出て、
そのように並ばせないといけない。あんな列はコミケでは許されないのだ。いや、一般社会でも
そうだろう?みんな、列にならぶことに無自覚すぎる。
頭が痛い。井村屋のあずきバーを食べてから、早々に寝よう。
さいきん、多いな。頭痛。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 75%(修正中)
序、中表紙 0%
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 100%(仮決定稿)
建築その5 90%(2案検討中)
解説 25%(解説地図作成)
- 2006/7/23(日)
一時間ほど本屋に出かけた以外は、部屋で原稿作業をするか読書をしてすごす。ここのところ、
雨のせいでまったくモールトンに乗っていない。ややフラストレーションがたまっているかも。
30分くらいでいいから、すぱーっと走ってきて、それから原稿をやりたいなぁ。軽井沢、荷物
の問題がなければ、分解してモールトンを持っていきたいのだけど、どうだろう。乗っている時
間がないかな?
あすは仕事で金、土とは別の研修。それが終わってから資料作り。火曜日はレビュー。なので、
原稿作業的にはややきつい状況。月、火とは解説の資料を収集して、水曜日に前みたいに喫茶店
にこもって文章をかきあげる。木曜日に解説レイアウト、金曜日に校正依頼。最終、火曜日の晩
に入稿。よし、このスケジュールで行こう。やっぱり今回もぎりぎりになるのだった。MacBook
がなければ、落ちてたなぁ...。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 50%(仮組み完了)
序、中表紙 0%
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 100%(仮決定稿)
建築その5 90%(2案検討中)
解説 25%(解説地図作成)
- 2006/7/22(土)
プレゼン強化研修2日目、9:00-17:30。
NC練習、18:45-21:15。
ファイナルのプレゼンテーション実習で、講師の方に「Mr.プレゼンテーション」と呼ばれる。
たしかに、一生懸命やったけれど、ちょっとこそばゆい。そんなにプレゼンがうまいのならば、
このコミュニケーション下手をなんとかできそうなものだけれど。BK宴会を仕切るときや、NC
マネージをやるときなど、ひとの前に立つときのわたしは、そうとう無理をして、自分の地を塗
り込めて、こわいのをがまんしている。わからぬよう内面を鼓舞し、気を張りつめている。だか
ら、ときどきとても疲れる。でも、それは嫌々やっているのではなくて、誰かが何かしないと、
前に進まないということがわかっているとき、自然とそうするようになってしまっていたのだ。
損な性格をしているなぁと思う。普段はとても無愛想な人間なのです。
朝から、疲れた。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 0%
序、中表紙 0%
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 100%(仮決定稿)
建築その5 50%(仮組み完了)
解説 0%
- 2006/7/21(金)
きょうは仕事で、プレゼンテーション強化技術という研修を受講していた。明日も続きがあるのだが、
どういうわけか、自己研修扱いとなっており、休日出勤扱いとはならない。納得いかん。そもそも、
わたしは代理で、きのう突然当初受講する人がいけなくなったから行かないかと言われて、断れるは
ずもなく、行くことになってしまった。であるが、きょう受講してみて、これは得をしたと思うよう
になった。つまり、当初行くはずだった人は受けられないことで、損をしているはずだ。ひとの不幸
?を喜ぶつもりではないけれど。これまで自己流でこなしていた、プレゼンや講師、技術発表という
ものについて、限界のようなものを感じていたのだが、体系的な専門技術を得ることがこれほどまで
意識を変えることになるとは思ってもみなかった。わたしが入社した当時は、このような研修は、
内部で、それも「内部の自己流」で行われていた。会社の規模が大きいから、それがベストだと人事
も思っていたかもしれない。でも、それは誤りで、餅は餅屋、プロから学ぶほうがずっと身につくし、
無駄がないということが、はっきりしてきたように思う。今日の研修のように。5年ほど前から、
外部委託の研修の体系化が進められてきていたようだけれど、もっと早くにこういう研修を自分から
うけていればなーと、しょうしょう後悔もしたのだった。
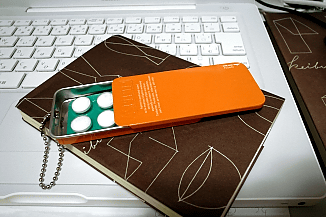
バイエル・アスピリンと、付属のピルケース。
9-17の研修後、通常の業務。研修の途中から頭痛があったため、途中で切り上げて帰宅。BK練習も、
BK宴会も出席は無理な状態だった。近所の薬局で、頭痛薬を購入。そう、以前愛用していて、10箱を
まとめがいしていた頭痛薬は、1ヶ月前ほどに切れてしまっていた。もう二度と手に入らないのは確定
していたから、新しい定番を見つけないといけなかった。
成分が似ていることから、バイエルのアスピリンを手に取ったところ、写真のようなピルケースがつい
ていたのだった。丸薬のようなものならともかく、頭痛薬のように水に溶けやすい成分の薬は、そのま
ま別の容器に移して携帯するということが難しい。わたしは前の薬は箱ごと持ち歩くか、薬の入った
プラスチックシートの状態で携帯していた。前者の場合は、箱なのでかさばるのが不便で、後者の場合
は知らない間に薬が押し出されてしまう、ということがままあった。
このピルケースは、平べったい。なぜなら、プラスチックシートごと格納することを前提にしているか
らだ。これならば、安全にそしてかさばることなく持ち歩ける。頭痛持ち人間の行動(常に携帯)と
それに伴う問題点をきっちりおさえたことに、いたく感心した。そんなことくらいで感心するなって?
いや、製薬業界ではあまりこういう販促品(?)というものはなかったものだから(薬事法の問題か)
余計に。
この文章を書いているということは、薬が効いているということの証例になるのだろう。まぁ、それで
もしばらく寝てました。明日の研修の課題をやらないといけないので、頭痛がなおっていなくても、ど
のみち起きなければいけなかったんだけども。
明日も早いので、このへんで。
おやすみなさい。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 0%
序、中表紙 0%
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 100%(仮決定稿)
建築その5 0%
解説 0%
- 2006/7/20(木)

『大仏、昼間見るよりも、なんだかいい男』(「ラジオの夏」より)
短編集「ざらざら」、川上弘美著、マガジンハウス刊。1300円。
疲れているときは、やはり本屋に行くものだ。川上弘美最新刊が発売されていた。わたしは短編の中途半端
な長さが苦手で、小説を読むのなら中編以上がいいと思っている。この短編集は一編あたり10ページ程度
で、短編というよりも、掌編に近い感覚なので、短編は苦手だが掌編は好きなわたしには、ちょうどよかっ
た。川上弘美の文章はこれくらいのページ数がもっとも光り輝くような気がしないでもない。
アップルから3000円のクーポンがメールで届く。3000円かぁ、と思ったけれど、さがせばあるもので、
アップルストアで3600円くらいのインナーケースを見つけた。持ち運びするときに欲しかったのだ。今年
の夏に、東京に持っていくのにちょうどいい。で、会計しようと思ったら、「31500円以上のお買い物で
3000円クーポンは有効です」と出た。たしかにメールにもそう書いてある。でも、これってクーポンの
権利が発生したのは、わたしがすでに31500円以上の買い物、つまりMacBookを買ったから生じたという
ようにも、読み取れる。20万円近い買い物したんだから、ポンと3000円の権利くれったていいのに。残念。
インナーケースは、よさそうなのでそのうち、自前で買うかもしれない。これって、なんだか思うツボだ。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 0%
序、中表紙 0%
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 85%(修正案を2案作成。検討中。)
建築その5 0%
解説 0%
- 2006/7/19(水)
右太ももの付け根、股関節のあたりが歩くと痛い。今朝、会社に行くときに気がついた。冷房があたった
せいとは考えにくいので、PC作業中のあぐらの組み方が悪かったのか。あ、そうかアルティの声楽アンサ
ンブルで、ほぼ二日間ともずっと足を組んでいたせいもあるかもしれない。
股関節が痛いと歩くたびに、身体が沈むような形になって大層歩きづらい。しかも結構痛い。わたしの母親
は戦争中のケガ?が原因らしく、股関節に異常があって、歩くときは杖をついている(身体障害者手帳を持
っている)。これは、杖がなければ本当に歩きにくいということがよくわかる。いままで、こんな箇所を痛
めたことがなかったので、つらさがわかっていなかった。今度会ったら、これまでの何十年、親身になって
いたわってこなかったことをわびなければならないと思った。
23:00-24:00、NCマネージ。この夏、軽井沢の合唱フェスティバルに参加するのだけれど、未だに全員の
参加/宿泊状況が完全に把握できない。事務局には迷惑をかけ通し。オンステ表明を尊重する指揮者との
板挟み。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 0%
序、中表紙 0%
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 75%(仮組み完了→細部修正を検討。)
建築その5 0%
解説 0%
- 2006/7/18(火)
先週末から、職場のわたしの席の右斜め後ろに扇風機がおかれるようになった。ことあるごとに、居室の
温度分布不均衡、つまり暑いということを部長や課長、健康管理室に訴え続けていたのだが、根負けして
くれたのか、それともあまりにもわたしの体調不良が目に余るのか、哀れんでもらったのか、とにかく、
感謝感謝なのである。まあ、居室全体の対流をうながすためのものなので、わたしのためだけじゃないの
だけれどね。それでも、かなりすごしやすくなったのは事実。扇風機のそばには寒暖計も取り付けられた。
あきらめないでいてよかった。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 0%
序、中表紙 0%
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 50%(仮組み完了)
建築その5 0%
解説 0%
- 2006/7/17(月)
アルティ声楽アンサンブルフェスティバル2006、二日目を聞きに京都府立府民ホールアルティへ。
合唱指揮者長谷川冴子を講師に招いたワークショップ「純正調の響き」でスタート。その後、5団体
による演奏。ワークショップは◎。純正調の全音には二種類ある、そして半音はどちらの全音の半分
よりも幅が広い!この2つだけはなんとか記憶。歌いながら意識できるかなぁ。演奏会については、
4団体目、合唱団Vivoのソプラノ!ほんと素晴らしいよ、ということだけ記憶にとどめた。
終了後、なんだか雨の中を歩きたくなって、アルティから自宅までひたすら烏丸を歩き続けた。こう
いう感じの雨は好きだ。土砂降りの後の、しとしと雨。少し涼しい。途中、大垣書店で休憩。ハチミ
ツとクローバー9巻を購入。帰宅後、読み始めることしばし。
-「持つ者」と「持たざる者」、「愛される者」と「愛されない者」。
こ、こんな重いテーマ突きつけないでくれーと言いたくなる。まったく。それでも読んじゃうんだな。
今回は真山だけ幸せそう。
さいきん、左肩が痛い。重いというか。これはたぶん冷えているのだと思う。山Dは寝るときに、一時
間の終了タイマーと、起床時間の一時間前の入りタイマーを、エアコンに設定する。部屋にいるときは
そうでもないのだけれど、寝ているときは、どうも左に風があたるようで、その二時間でどうもやられ
てしまったのだと思う。最近、急に暑くなって、かなりエアコンに頼るようになったからなぁ。シャワー
を浴びて、温めるのだけどあまりよくならない。つらいというほどでもないけれど、すっきりしない痛
さだ。あ、そうか、ときづいた。女の人が冷え性で肩が痛いっていうのは、こういう感覚なんだ。いま
まで、電車の弱冷車の存在を、単に女の人は冷えに弱いからっと頭で考えてたのだけれど、電車の強力
な冷房で、一発で肩がこんなふうになってしまうのだとしたら、そりゃつらかろう。それを考えての弱
冷車なんだな、たぶん。ようやく、現実に認識が追いついた(?)ような気がした。
あまり、予定は立ててないけれど、7月末には校了して入稿したい。
今回は夏コミ前日まで仕事で、直前は身動きがとれないから。
がんばれ、山D。手綱をゆるめるんじゃない。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 0%
序、中表紙 0%
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 100%(仮決定稿)
建築その4 0%
建築その5 0%
解説 0%
- 2006/7/16(日)
原稿作業で、集中力を全開。さきほど、ようやく三つ目の仮組みが終了して、放心状態。なので、
きょうのところはさくっと書きます。もへー。
アルティ声楽アンサンブルフェスティバル2006を聞きに京都府立府民ホールアルティへ。ちなみに、
わたしは京都市民であると同時に、京都府民であるけれど、普段の生活で府から何か恩恵を受けてい
ると感じることはほとんどない。たいがいの文化施設は市か国のものだからだ。そのなかでも、唯一
ありがたいなと思うのはアルティという日本でも希有のすばらしいホールの存在だ。このホールがあ
れば、ほかには恩恵なんてなくてもいいとさえ思える。
作曲家/合唱指揮者の松下耕のワークショップで開幕。5団体の演奏がそれに続く。そのうち4団体
を聞いたのだけれど、まずひとつ思ったのはBKのソプラノは全員、身銭を切って、時間をつくって、
これらの演奏を聞きにくるべきであると思った。3団体が女声合唱であったからだ。小人数のアンサ
ンブルにおける個々人の役割の高さは当然なのだけれど、それに負けない集中力と自信が、舞台にた
つときの3団体それぞれの出演者にはあったと思う。もちろん、出演者の皆さんの内面を透視できる
わけではないのだけれど、空間に紡ぎだされる音楽の強さというものはまぎれもない現実で、それを
支えているのが、先の2つの要素であると思ったのだ。すばらしい音楽はときとして、目にみえる、
そんな気がする。それを見てほしかった。BKのソプラノに足りないものが、全部ここにある。
招待団体である東京レディースコンソート”さやか”の演奏と、三番目に演奏したコールシェリーの演
奏について書こう。さやかの演奏は、洗練の極みだった。あざやかな緑のドレスをまとって入場した
ときから、見るものを自分たちの舞台にひきこんでしまう魅力をもう発揮していた。音楽はかぎりな
く、まっすぐ伸び上がり、変幻自在、それでも芯は決して失わない強さ。強靭な下半身をそこに感じ
ることができた。音楽の解像度もかぎりなく高く、ダイレクトに伝わってくる。演奏後のおじぎ、
パートチェンジや、舞台上の移動における所作には一分の無駄もなく、それが嫌みに感じない。ああ
こんなに徹頭徹尾エンターテイメントな音楽はほかにはないだろうな。すごい、そして楽しい。
しかし、そんなさやかにも感じることのなかった演奏をしたのが、シェリーだった。さやかに比べれ
ばなにもかもが違う。だからといって、その音楽が良くないというわけではない。まったく方向性が
違う音楽をシェリーは見せてくれたのだ。さやかになくて、シェリーにあったもの。それは「包み込
んでくれるもの」だと思うのだ。あたたかく、会場全体をわたしたち聴衆ごと包み込んでしまう大気
のような音楽。ときに母性すら感じる。それはたぶんに情緒的で、洗練されているとはいえないかも
しれない。でも、シェリーの歌声を聞いたときにまっさきに感じるのは彼女たちの息なのだ。生きて
いることを認識させてくれる優しい息づかい。それを練り上げて、強靭にして硬化させてたものが、
さやかの音楽かもしれない。でも、シェリーはあるがままの息で、音楽を満たしていく。ソプラノの、
メゾの、アルトのみんなの息がまじりあい、つながりあってひとつの大きな大きな大気を作り出す。
そういう音楽なのだ、彼女たちの、シェリーの音楽は。それはわたしたちに、すばらしい音楽が難し
くて、近寄りがたい、手の届かない存在などではなく、足下から2m先のところにあるんだというこ
とを教えてくれる。(それがどれだけの試練でもたらされたか、決して楽ではない道筋のさきにある
ものだってこと、それはちゃんとわかっているつもり。でも、いまはこういう風に考えさせてほしい。
>シェリーの友人へ)
とはいえ、2年前の結成のときには、こうはいかなかった。時を経て、合唱団は成長していくものな
のだな、とも思った。今日は、田の草取り歌が、いちばん良かったかな。松下耕編曲のアリランには、
すこし手こずったかんじ。これからも「はにかみ」つつも、いい音楽を聞かせてほしいと思う。
個人的には変な緊張をしつつも、いい音楽を聞くことができて、とてもしあわせだった。ありがとう。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 0%
序、中表紙 0%
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 50%(仮組み終了)
建築その4 0%
建築その5 0%
解説 0%
ぜんぜん、「さくっと」じゃないな...。
あたまをやすめないと。眠ります。
おやすみなさい。
- 2006/7/15(土)
NCマネージ12:00-13:00、15:00-15:45。
撮影(大阪肥後橋)16:30-17:30。
NC練習18:00-21:15。
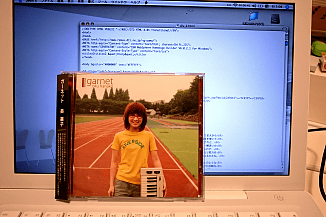
「あなたと過ごした日々を この胸に焼き付けよう 思い出さなくても大丈夫なように」
ガーネット/奥華子。ポニーキャニオン。映画「時をかける少女」主題歌。
この歌を聞いていると、女性って、たとえそれが高校生のころだったとしても、やっぱりとても現実
的なのだろうなと思ってしまった。創作された歌の世界であっても、それは変わらない。なんとなく
そんな気がした。自分の現実にはなかった青い空と白い雲。なにもかも輝いているはずの夏を夢想し
ながら、阪急電車に揺られていた。ガーネットの石言葉(?)は、「友愛」だそうだ。
コミックマーケット70カタログ(別名、読む凶器。厚さ3.2cm)も、買ってきた。わたしの配置は
西館の「れ」で、これは壁なのだ。壁になるということは、ほかの関連サークルと切り離されてしま
う可能性が高いので、ちょっと落胆というか、隣にどんなサークルさんが来るかによって、売れ行き
なんかも左右されてしまうし、一日を楽しくすごせるか不安だった。まずは、自分のサークルカット
を見て、ちゃんと印刷されていることを確認。すこし、濃いめに出ているなぁ。そして、左右のサー
クルさんを見る。おおー、「れ」は壁といっても一列に写真系のサークルを並べたゾーンだった!こ
れはなかなかいいなー。しかも同じ「れ」の4番のa(同じ番号にaとbが割り振られ、わたしはb)
のサークルは近代建築がテーマらしいぞ。「ヴォーリズ建築を巡って」と書いてあるから間違いない。
やったよ、お仲間だよ。近代建築探訪の京都断章の表紙、中表紙はヴォーリズ建築なんだよぉ。
あしたは、合唱の演奏会に行く予定。個人的な事情で、かなり複雑な気分。演奏を楽しめるかどうか、
不安。
予約しておいた「どうでしょう」の新作を見る。
寝ます。藤村Dのように、うなされたりしないだろうか...。
- 2006/7/14(金)
BK練習20:40~21:00。
BK宴会21:30~23:00。
仕事で遅くなって、かなりばて気味で練習場に到着。教会の中は、外よりも熱くて、歌うまえから
ダウンしてしまった。力が入らないので、一番後ろの席の陰に隠れて、横になって皆の音を聞いて
いた。ああ、こうやっていると床を通して、全身でみんなの声を感じる。しんどいのだけれど、
ちょっと気持ちいいかもしれない。このまま、眠るように意識を失ったら幸せかも、と一瞬思いか
けて、遮られる。いまやっている曲の最後、H-durのハモリがいまいちだったから。おもわず、
横になりながら一緒に声を出してしまう。寝ながら、しっかりした声を出すのって、かなり筋力を
使うことがわかって、すぐに止めてしまったけれど、元気なときなら、トレーニングになるのかな。
あー疲れた、頭の奥のほうの集中力をつかさどっているであろう部分から、集中力のもとのような
物質が絶えずもれているみたいな感じで、こうやって文章書いてるのもつらいし、なんだか些細な
ことでいらいらすることもあった。熱疲労なんだろうか。相変わらず、職場は暑いのだ。
きょうは、涼しくして寝ます。
気持ちよく起きれますように。
- 2006/7/13(木)
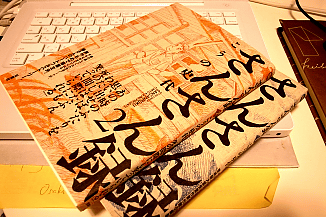
「あの時のふたりを思い出せば、わたしはたぶん死の間際にも笑っていられる。」
『さんさん録』第2巻(完結)、こうの史代著、双葉社刊。724円。
疲れているときに限って、本屋に行くと、思いがけなく新刊が出ているもので、そんなときは
素直に嬉しい。原稿をやる前に、読んでおこうとおもって、読み終えたら、すこしぼーっとし
てしまって、なんとなく余韻にひたっていたくて今日は原稿をやるのをやめた。家族とか、
親子とか、夫婦とか、孫。そして日々の生活と仕事。そういうものが、丁寧に描かれていて、
一見普通なのに、ときどき優しく、あるいは哀しい、するどい言葉がふいにとびこんでくる。
それがなぜだか胸をうつ。まるでわがことのように思われて。ちっとも違うのにねぇ。感情移
入しやすいのは認めるけれども。
ベランダに行って、蚊取り線香に火をつける。あ、これでマッチが切れてしまった。どっかで
もらってこないといけないな。そう思いながら、椅子にすわってすぅーっと息を吐いた。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 0%
序、中表紙 0%
建築その1 100%(仮決定稿)
建築その2 100%(仮決定稿)
建築その3 0%
建築その4 0%
建築その5 0%
解説 0%
- 2006/7/12(水)

もうすぐ、祇園祭も本番。
わたし自身には、この祭で何か印象に残る思い出とか、よきエピソードといったものは皆無で、
それがなんだか寂しく感じる。子供のころ、親に連れられて見物に行く途中、バスで酔った(ま
たかよ!とお思いでしょう。お許しください。)とかそんなのならたくさんある。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 0%
序、中表紙 0%
建築その1 100%
建築その2 50%(仮組み終了)
建築その3 0%
建築その4 0%
建築その5 0%
解説 0%
- 2006/7/11(火)
ただいまPhotoshop Elements 4.0をダウンロードインストール中。あと30分くらいかかる見込み。
その間に、昨日の答えをあわせをしよう。
問1:新潮文庫にあって、岩波文庫、角川文庫、講談社文庫、ハヤカワ文庫、文春文庫にないものは何か。
解答:ひものしおり(スピン)。
これは割と簡単だったのではないだろうか。宣伝や、名言、うんちくが書かれた紙のしおりがほとんどの
なか、新潮文庫にだけは茶色のしおりが装丁にのり付けされている。しおりとしての機能だけみれば、ど
ちらでも良いのだけれど、読んでいる最中、つまりしおりが必要でないときのしおりの有り様についてみ
れば、それは断然ひもの方がいいに決まっている。紙のしおりは、本のどのページに挟んでいても、その
わずかな固さが本を開くときの「つっかえ」になってしまうからだ。だからわたしは、読み始めると同時
にあの固い紙のしおりは、抜き取ってどこかにやってしまう。かわりに挟むのはたいがいレシートだ。紙
のしなりと一緒に曲がるので違和感がないから。
問2:岩波文庫、角川文庫、講談社文庫にあって、新潮文庫、ハヤカワ文庫、文春文庫にないものは何か。
解答:「文庫発刊に際しての言葉」が掲載されているかどうか。
こちらは、よほど本を最後まで丹念に、それこそ奥付まで読むような人でないと気づかないかもしれない。
この文庫をなぜ、わたし、われわれは発刊するのか、そういった所信表明みたいなものであり、文庫にとっ
てみれば、企業理念に準ずるものかもしれない。いらないといえば、いらないものかもしれない。文章はな
い、でも文庫におさめられた書を見てほしい、というスタンスの出版社もあるはずだ。ただ、発刊に際して
の心意気というものが垣間見えるそれら所信表明は、出版社のパーソナルというものを表しているようで、
とても興味深い。
なかでも、角川書店創設者の角川源義による「角川文庫発刊に際して」は、声に出して読みたい日本語に
所収されていてもおかしくないくらいの名文であろうと思う。お手元に角川文庫、あるいはスニーカー文庫
(スニーカー文庫は、名称上は独立した文庫だが、分類上は角川文庫の一部なのだ)をお持ちの方は本の後
ろを開いてぜひ、その文章を味わってみてほしい。
さて、問には含めなかったのだけど、もうひとつ、そのような文章を掲載している文庫がある。電撃文庫と
いって、主にライトノベルを扱った文庫である。ライトノベルになんで、そんなご大層なものが?と初めて
目にしたとき、とても驚いたのだけれど、その文章に込められた心意気には、なぜだか一読書人として、と
ても心をうつ、熱いものを感じてしまった。その文章を書いたのは角川歴彦。角川源義の次男である。兄は
いわずとしれた角川春樹。映像分野に傾倒する兄と袂をわかち、メディアワークスという出版社を創設。電
撃文庫を発刊した人物である。のちに、兄の逮捕後に、請われる形で角川書店に復帰した。独立したばかり
で、その勢いもあったのだろうけれど、その文章には父譲りの書店員としての誇りと使命があるよに思われる。
(さらに後、兄・春樹が発刊したハルキ文庫には、発刊に際しての文章は記されていない。)
余談になるけれど、メディアワークスはその後、角川グループの一員となって現在も存続している。ライト
ノベル分野では、本家角川書店のスニーカー文庫とは真っ向からぶつかっている。いいんだろうかと、ちょ
っと心配。(「凉宮ハルヒ」シリーズは、当然電撃文庫だろうと当初思っていたので、スニーカーと聞いて
意外だった。)
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 0%
序、中表紙 0%
建築その1 75%(仮組み第2案作成)
建築その2 0%
建築その3 0%
建築その4 0%
建築その5 0%
解説 0%
- 2006/7/10(月)
原稿開始。Photoshop Elementsでの作業に特に問題なし。勘を取り戻すのにやや時間がかかりそう。
そうそう、作業以外に二つ問題がある。1つはElementsはCMYKモードを扱えないこと。いつもはRGB
モード、つまり画像表示用のモードで作成してからCMYK、つまり印刷用のモードに変換していた。その
変換ができないのだ。これはちょっとしたことなんだけれど、家庭用プリンターでの印刷ではなくて、
業務用オフセット印刷をする場合には、不可欠なことなのだ。ふむー、変換のためだけにキンコーズに
行かねばならない。
もうひとつは、試用期間があと5日しかないということだ。当初のもくろみでは、インストールをぎり
ぎりまで遅らせること、期間限定ということで自分を追い込むことというのを考えていたのだけれど、
MacBookでの動作の様子がわからないと不安なため、かなり早めにインストールしてしまった。それゆ
え。自分を追い込むという状況は、すでに日数的な問題、仕事との集中力のバランスなどで、果たされ
つつある。なので、普通に購入してもいいだろう。ただし、現在の最新はElements4。重くなっていな
いといいのだけれど。しかし、意思の弱いことだなぁ。
夏コミ新刊原稿、進捗率
表紙、裏表紙 0%
序、中表紙 0%
建築その1 50%(仮組み終了)
建築その2 0%
建築その3 0%
建築その4 0%
建築その5 0%
解説 0%
クイズ
1 新潮文庫にあって、岩波文庫、角川文庫、講談社文庫、ハヤカワ文庫、文春文庫にないものは何か。
2 岩波文庫、角川文庫、講談社文庫にあって、新潮文庫、ハヤカワ文庫、文春文庫にないものは何か。
(注:トンチ問題ではない。)
こたえは明日。ほんとは今日書くつもりの話だったのだけれど、疲れてしまったので。
では、ごきげんよう。
- 2006/7/9(日)

リハビリを兼ねて、近場へでかける。少し、汗をかいておきたかったというのもあるけれど、ずっと
心のなかで、軽い懸案事項になっていたことを済ませたかったからだ。深刻なことではなくて、ただ
「北野天満宮に初詣していなかった」だけのこと。わが家のならいとして、毎年上賀茂神社に参った
あとは北野の天神さんにお参りすることになっている。べつに信心から来ることではなくて、今年も
よろしくお願いしますというお年賀みたいなものだ。相手は神様だけれど。
行くと、だいたいこの牛の頭を撫でて帰る。頭を撫でて、それから自分の頭を撫でると、天神さんの
知恵をもらえるという、おまじない。頭だけでなくて、目が悪ければ、目を撫でるし、鼻づまりなら
鼻を撫でるといった具合に、あらゆる願いに応じたオールマイティーなのだ。わたしはだいたい、頭
と目。眼鏡はかけていたい(笑)けれど、まぁこれ以上悪くならないように。子供のころは2.0にな
りたいとか、わりと切実に考えていた時期もあったなぁ。

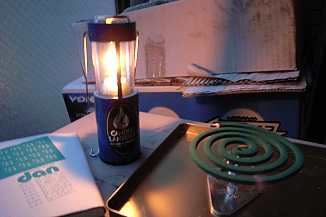
話は前後するけれども、途中で登山用品店に寄って、アルミでできた水筒と、キャンドルランタンを
買ってきた。前に話していたように、ベランダで本を読むため。水筒は...思わず。わたしは別段
アウトドア派ではないのだけれど、登山用品というのは、物欲を刺激するものがある。だいたいが単
一の用途に用いるもので、いかにも「道具」という名前がふさわしい質感をもっているからだ。多機
能を誇るスイスアーミーナイフでさえも、ある意味、道具として確立した存在感がある。というわけ
で店内でランタンをみつけたあとも、わけもなくわくわくして、うろうろしてしまった。途中、ひさ
しのあるベージュの帽子を見つけたので、自転車用にどうかなと思ってかぶって見たのだけれど、鏡
にうつるのは、どことなく旧日本軍兵士のような古風な顔立ちをした男だった。これは!絶対似合っ
ってない。ということで断念。
で、そのあとで見つけたのが上の水筒。持ってみてすごく軽いし、ふたの開け閉めの感覚がとても
スムーズで使いやすそうだった。なにより、色がよかった(ほかにも色の種類、サイズ違いあり)。
モールトンのボトルケージに差したら、ぴったりくるだろうなーという考えもあって、購入。その足
で、下御霊神社に行って水を汲んでみたのが上の写真。LAKENというメーカーなのだけれど、漠然と
ドイツの会社かなとおもっていたら、Made in Spainだった。スペイン製のモノを所有するのははじ
めてのような気がする。ところで、ラーケンと聞くと国際ダイヤモンド輸出機構のNo.2、デュラン・ド・
ラーケン伯爵を思い出してしまうのはわたしだけだろうか...。
帰宅後、暗くなってから香取線香をたいて、ランタンに火を灯した。本を読むにはやや暗いけれど、
なんとなくそこにあるだけで、気持ちが落ち着く。しばらく今日買ってきた文庫本を読んだ。この本
については、読了してから紹介しようと思う。
あ、そうだ水筒も、ランタンも軽井沢にもっていこう。。。
- 2006/7/8(土)
NC練習休みました。申し訳ない。マネージはF栄に引き継いでもらった。
背中に凝りがのしかかっていて、だるくてしかたがない。なんとか近くのマッサージ屋まで行って、
ほぐしてもらう。「右側、動きませんね...」、そうなんです。
凝りはましになったものの、目の奥がじーんとするのは原因が別のようなので、直らない。目がつ
かれているわけではないようだ。
近所の薬屋で売っている米を買ってくる。実家で食べていたものと同じ米が、どういう流通経路を
たどってか、ここにある。個人商店のブレンド米なのになぁ。ここ何ヶ月か、この米を食べていな
かったのである。ひとつは実家に帰ったときに別の米(無洗米)を持たされて、それを主食にして
いたこと。もうひとつは、その米が切れたあと、重い米を買いにいくのが面倒で、いざというとき
のための保存米を食べていたことが原因。いや、正確には保存米はあまりおいしくないので、一時
期、朝食はほとんどパンのなっていたのだ。
健康体にもどるためにも、うまい米のパワーが必要だと感じて、買ってきた。さっそく炊いてみる。
48分後、台所にいくと、炊飯器から炊きあがりの湯気がたっていた。んー、匂いが全然ちがう。
これだけで脳内的には十分かもしれない。食べてみたら、涙が出るほどまではいかなかったが、と
ても満たされた気持ちになった。あー、食生活の品質維持はやっぱり大事なんだな。肉体的にも精
神的にも。
建築探訪vol.3の写真のセレクトを始める。取り上げる建物は決まったけれど、二三枚おさえてお
きたいアングルの写真がないことに気づく。撮っていたつもりだったんだけれど。構成を考えると、
どうしても必要になる。改めて、撮りにいくか。きょう行けたらよかったんだけど、遭難しそうだ
ったしな。全体をみて、おおざっぱなレイアウトをイメージだけする。手を動かして配置するには
それなりの集中力がいるのだ。それでも、さきにおおまかなイメージあるのとないのでは、作業へ
の没入までの早さが違うのである。
適当なところで切り上げる。TVをつけていたけれど、集中できないので消す。
いまは「わたしを離さないで」を読んでいる。本は別腹なのだろう。
調子が戻るには、まだまだかかりそう...
追記:「わたしを離さないで」を読了した。今日だけで半分以上、170ページ読んでしまった。
その、とても抑制された語り口ゆえに、感情の細かな、観測不能ではないかと思われるような、
わずかな起伏まで読み手に伝わってくるようだった。正直なところ、読了の感想を大きな声で
伝えるのは難しい。読み手の感情もやはり、抑制された語りを踏襲してしまうようだ。ほんとう
ならば、おだやかでいられるはずもないことも、われわれはこの作品の世界のように、穏やかに、
いや、あまり考えないように受け止めてしまっているのだろうか。キャシーが最後に語った、
一度だけ許した甘えは、そのことに対する唯一の反抗であったかのように思える。人間らしい
感情の吐露を、時に甘えと、ときに羞恥と考えてしまうことがあるけれど、それは必要なこと
なんじゃないかなと思う。いろいろ悩んでしまうとき、あとさき考えずにさらけだしてしまい
たい。そういうことがないと、人間ではいられない。そう、強く思った。後半の感想は、なん
だか自己弁護のような気がしないでもない...。ま、いいか。
- 2006/7/7(金)
頭痛と断続的な発熱のため、さっきまで寝ていました。
BK練習休みました。ごめんなさい。
部屋に誰もいなくても「助けて」って叫んでしまうのはなぜなんだろう。
声を出すのも、つらいのに。
小康状態のうちに、七夕の願いを書いて、ベランダにつり下げた。
二年前に書いた短冊は色あせて、赤い色が真っ白になってしまっていた。
同じ短冊の消えかけてしまった二年前の文字の上に、また同じ願い事を書いた。
もう一度眠ります。
- 2006/7/6(木)
NCの練習が水曜日に変更になる、という夢を見た。Macintosh SE/30(?)にそのことを記録するわたし。
練習後、なぜかBKの友人と一緒に帰宅する。NCの練習じゃなかったのか?帰宅するために車に乗ることに。
乗ったのは大型の乗り合いダンプカーという設定。荷台は人がいっぱいだったので、運転席の後ろに座る
ことに決めて、いざ乗り込むと、意外にも奥行きが5mくらいあった。友人は中央列の真ん中に、わたし
は最後尾左奥に陣取るのだった。
祇園囃子の練習があちこちの鉾町から聞こえている。ここいらもあと10日もすると歩けなくなる。
22時ごろ帰宅。昨日、録画した「どうでしょう」を見る。
番組終了後に、KBS京都からお知らせ。
7月15日、19:00~
7月16日、19:55~
なんと二夜連続で、2005年どうでしょう新作「ジャングルリベンジ」全7夜を一挙放送!
やったね。しかしこれから急いで、DVDレコーダーの空きを増やしていかないといけない。
あと30分しか録画できないのだった。貯め込みすぎ。
疲れた。もう寝ます。
- 2006/7/5(水)

会社近くの本屋を出たあと、空を見上げたらこんなだった。夕焼けの赤と夜の青が、梅雨雲のわずかな
すきまをすみ分けるかのように、くっきりとわかれていた。一瞬、昔ジャンプで連載していた「ドラゴ
ンクエスト-ダイの大冒険」を思い出した。物語の後半くらいに、ダイの仲間の魔法使い(名前忘れた)
が、ある技の修行をする。それは確か右手で火炎系の魔法を、左手で氷雪系の魔法というように、相反
する属性の魔法を同時に現出させるというものだった(実は、その技自体は、本当の技を出すための前
段階だったという続きがある)。あの話を見て以来、どうも、ふたつの相反するものの同時存在という
構図を見ると必ず、きょうのように「ドラゴンクエスト」を思い出してしまうのだった。いったい何の
因果か。困ったもの。まぁ、きれいな空だったからいいさ。

「人はなぜツール・ド・フランスに魅せられるのか」、土肥志穂著、楓書店、東邦出版刊。1500円。
さきほど出てきた本屋で買ってきた。気づいてみれば、今年ももうツールが始まっていたのだった。
ツールを特集する雑誌は多いのだけれど、「ツールの世界観や観戦のポイント」を教えてくれる本と
いうものはなかったような気がする。しかし、この本は単なるガイドブックではなくて、基本的にレース
の再現ドラマを軸にして、さまざまなエピソードが語られる形式になっている。すこし立ち読みした
だけで、映像が頭に浮かぶような、とても良質なルポルタージュであるということがわかった。写真
もきれいなものが多く、装丁・本文デザインも好み(←またそれか!)だったので買いました。しか
し残念なことに、わたしにはツールを見る手段がないのだった。たしかCSでは見れるんだが。フジテ
レビかNHK、頼むからもう一度地上波でツールの番組を放映してはくれまいか。
あれ、本屋に入るとき坪内祐三の「極私的東京名所案内」を買うつもりだったはずなんだけど…。
(売ってなかったんだからしょうがない。)
ちなみに、写真下の本は「年上の彼女」第4巻(甘詰留太著、JETS COMICS。505円。)デス。
ちょっと、写真に出すがアレな絵だったもので、隠してしまいました。これから読みます。
- 2006/7/4(火)
きのうはあれから、うっかり「わたしを離さないで」のつづきを読み始めてしまい、きりのいいところ
まで読んだあげく、ちょうどはじまった「凉宮ハルヒの憂鬱」最終回をリアルタイムに見てしまった。
というわけで寝不足だったのだけれど、外界の情報がうまくはいってこないせいか、逆に集中して仕事
ができたような気がする。ものは考えよう。
さて、帰宅後懸案だったMacBookとレッツノートのファイル共有に再度挑戦した。もう無線LANはすっぱ
りとあきらめて、クロスケーブルで直接つなぐ方法をとった。まず、Mac側でWindows共有を設定。これ
でレッツノート側からプライベートIPを入力すれば、直接見れるはず...やっぱり見えない。Windows
はやっぱりアホだ。(自分の無知は棚にあげておこう)
つづいてMac側からアクセスする方法をホームページを見て試してみた。
1 Windows側の共有したいフォルダでネットワークの共有設定を行う。
2 Mac側のアプリケーション→ユーティリティ→ディレクトリアクセスを起動。
3 SMB/CIFSの設定を開き、ワークグループ名をWindowsのワークグループ名にする。("MSHOME"など)
4 ファインダー→移動→サーバーへ接続を起動。
5 サーバーアドレスに"smb://Windowsのコンピュータ名/共有フォルダ名"を入力し、「接続」を押す。
この設定は約5分くらい。で、接続を押すとあっさりと共有フォルダがマウントされてしまった。非常に
あっけなかった。さっそくiTunesのファイルをコピー。877MBもあったのだな。ケーブルを直接つないで
いるので、実にスムーズに終了。Mac側のフォルダと置き換えるだけで、ちゃんと認識できました。
およそネットワークの設定ほど、素人に難解なものはなくて、ネットのあちこちで苦闘している方のページ
を見て、参考にさせてもらったのだけれど、Macのネットワーク設定は本当に楽だと今回も感じた。ちょっ
と、そこの奥さん!これからはやっぱりMacですよ、OS Xですよ、と売り込みがしたくなるね、まったく。
- 2006/7/3(月)
水無月を食べている。すでに二個食べたのだが、まだ一個ある。そもそも6/30に食べないといけないの
に忘れていて、昨日買ったのだが、そのままさっきまで冷蔵庫に入れて食べるのを忘れていた。冷蔵庫
の扉が透明であれば、こんなこともなかろうなと考えるのだった。
東京在住の友人H本が、なぜか早すぎる夏休みをとって帰省していたので、K岡とともにご飯を食べにい
った。
本日のお酒:山三正宗(純米大吟醸)。フルーティーな香りというので、飲んでみたのだけれど、どう
も想像していたのと違って、するどい口当たり。辛くはないのだけれど。あとから口の奥のほうで、ふわ
あっと、香りがふくらんでいくような感じがして、そこで初めてフルーティーな感じがした。もっと、
とろ味のある、丸い口当たりのお酒のほうがいいな。二口だけ飲む。その後は、H本、K岡は焼酎モード
に入ってしまったため、打ち止め(わたしは一人で一杯飲めないので、ひとのやつを少しもらう飲み方
しかできないのだ)。
H本との話のなかで、どっか旅行にでもいけばいいのにというと、いきたいと思っているところがある
という。ブラジルだそうだ。目的は?と聞くと、「マイルを4万マイル貯めるため」という返答。なん
のことか、さっぱりなので、くわしく聞くともっとわけがわからなくなった。彼が示したルートはこう
だ。
成田→バンコク(1泊)by PEX→バンコク→成田(トランジット)by C→サンパウロ by C
直接サンパウロへいけばいいものの、わざわざバンコクにいくというところが変すぎる。くわしく聞く
と、この方法でいけば4マイル弱が手に入るのだそうだ。PEXというのは格安航空券のことで、Cはなん
とビジネスクラスだ。わざわざビジネスクラスにするのにも理由があって、マイレージが125%になるか
ららしい。バンコクに行くのはマイレージを稼ぐためと、バンコクの航空券ならば、ビジネスクラスでも
正規のエコノミークラスなみの値段ですむかららしい。
ところでなぜ4万マイルか。かれはすでに1万マイルもっているのだが、一年以内に5万マイルを達成
すると、マイレージのクラスが上流クラスになるからという理由。上流クラス発行のカードに入会する
と、生涯上流クラスの権利が得られるらしい。なんだかよくわからない。上流クラスに到達するには、
もうひとつ手段があり、これも一年以内に50回搭乗することだという。そんなの無理だと思うでしょ。
でも彼によると、東京-大島間を一日に5往復すれば、10回搭乗。これを5日間繰り返せばいいとい
う。こういう、マイル獲得に血道をあげるひとびとを、マイルオタク、通称「修行僧」というらしい。
当初は、上流クラス権利の獲得目的がいつのまにか、最適ルートを選定したり、マイルを獲得すること
自体が目的になってしまうのだ。
ちなみに、ブラジルに行かなくても4万マイルを稼ぐ方法はある。羽田-那覇、6日間。これは、一日
に三往復を6日間繰り返すのだそうだ。あまりにも不毛なため、ブラジル経路を考えだしたという。K
岡とわたしはひたすら笑いころげて、あきれかえっていたのだが、H本にいわせれば鉄道オタクとて同
じものだという。経路や時刻、運賃の組み合わせを考え抜き、ルートを選定し、ひたすら鉄道にのりま
くる。いわれてみれば、そんなものかも。一日中、乗っていても確かに苦にはならないし。航空の世界
では、チケットの料金体系は複雑極まりないため、より難易度や組み合わせの複雑さが上がり、高度に
なっているだけだと。ふむ、そうか。なんだか納得してしまう私、ついていけないという顔のK岡であ
った。
きょうは、お酒はあまり回っていない模様。好みではなかったけれど、体質的にはOKだった様子。
でも、ちょっと眠たくなってきたな。無理せず、寝ます。
おやすみなさい。ふつかよいしませんように。
- 2006/7/2(日)
諸事情が重なり、わたしは今日も長岡京文化会館にいるのだった。花園大学混声合唱団+京都府立大学
合唱団のジョイントコンサートにやってきたのである。座った席は昨日と同じ...ではなく、気分を
変えるためにひとつ隣の席に座った。
きょうの演奏会は、両方の団とも単独のステージで、かなりのびのびと力強い歌をうたっていたのが印
象的だった。技術的な面の違いというよりも、純粋に選曲がよかったのだと思う。団の歌声や、大学生
としての彼らにぴたっとはまる素直なものだったからだろう(花混:飛行機よ、府大:旅のかなたに)。
あ、でも府大の女声は格別うまかったです。いきいきとしていた。大学混声合唱団の鬼門はやはり男声
の発声であるということもつくづく感じた。声が幼すぎるのだな。ボイストレーナーの有無や能力が、
あるいはメソッドに則った発声練習の有無が、歌の充実度に影響を与えると思う。
合同は、企画ステージで宇宙の旅というテーマで選曲。今年の京都合唱祭の大学合同でも感じたことな
のだけど、こういう企画における「演技」は、どうしても見たり、聞くのが苦手。発想が子供っぽく思
われてしまって。合唱自体はとてもいいんだけどね。合同演奏は昨日の演奏会のように、ストイックで
スケールの大きいものが良いな。もしくは、早稲田大学グリークラブの企画ステージなみに、おそろし
くまじめに、おそろしくレベルが高く、おそろしくバカバカしいものであってくれたら。
同時刻に京都市内で行われていた「佛教大学混声合唱団サマーコンサート」はどんな様子だったんだろ
うか。両方聞きたかったな...。
- 2006/7/1(土)
今日はNC練習なし。
昨晩は、チケット案を2つ作り、実行委員長とチケット/パンフ担当にメール。午後、修正提案のメール
を受信。えー、だめなの?と一瞬思ったのであるが、改めて見ると、ちぐはぐな部分がないでもない。
しゃーないなーと思いながら、修正案にそったものを再作成。比べてみる。やや、こっちの方がいいん
じゃないのか?うむむ。やはり、やる気はあっても寝ぼけながらのデザインと、覚醒した状態+他者の
視点では、できばえに差が生じるのは理の当然か。外出から帰宅すると、修正デザインいいんじゃない
というメールが両者から届いており、ほっとする。デザイナーの心境を少し垣間みた気がした。
外出して向かったのは、京都大学音楽研究会ハイマート合唱団、同志社混声合唱団こまくさ、ジョイン
トコンサート@長岡京記念文化会館(しかし、長い演奏会名だ)。
結論から言ってしまうと、合同ステージのJohn Ratter作曲の「Magnificat」の演奏には目をみはる
ものがあった。合唱とソロ(小梶史絵)の二重唱となるEt misericordiaには、深い感嘆のためいき
をついた。なんという慈愛、美しさ。おおげさじゃなくて。途切れることのない、あっという間の7曲。
ところが、演奏終了後の指揮者の挨拶で初めて、演奏時間が40分もあったことに気づいた。時計を見て
びっくりである。それほど引き込まれていたのか。この合同ステージを聞くまえに、帰ってしまわない
で良かった、1000円払ってよかったなぁと思った。
合同の前に、途中で帰りたくなったのは事実だ。1ステ、2ステはそれぞれの団の単独演奏。どこかが
取り立てて悪いわけではないのだけれど、特筆すべき何かがあるわけではなかった。また、開演前から
演奏中、幕間に至るまで、たえず客席がざわついていたことで、なんとなく落ち着かなかった。OBOGと
父兄が大多数のようで、音楽を聞きに来たというよりか、娘・息子・後輩・友人の「発表披露」を見に
来たという雰囲気が濃厚に感じられて、それがなんとなく、肌にあわないなと感じてしまった。だから
あまり真剣に聞けず、途中何回か寝てしまった。
もし、彼彼女らに足りないものがあったとしたら、それはお客さんを引き込む力である。あまり音楽に
興味のない親や、友人が来るかもしれない。そういう人たちに、自分たち頑張ったよ~というメッセー
ジを伝えるだけでは、足りないのだ。それは自己満足だし、閉じた世界でしかない。そういう人たちの
集中力をぐいっと束ねてしまうメッセージ=音楽を伝えないとだめなんだ。単純に彼彼女らの音楽を聞
くために来た、わたしのような少数のひとたちに満足してもらうには、発表披露から突き抜けないとい
けないのだ。その違いは何かということを、両団の学生たちは合同演奏をすることで、肌で感じ取った
はずだと、思っている。それはできないことではなくて、自分たちにもちゃんとできるんだということ
を実感したと思うのだ。だから、つぎの演奏の機会には、単独のステージだけでちゃんと、お客さんと
自分たちとが満足できる演奏をして欲しいものだなぁと、帰りの阪急電車のなかで合同の余韻にひたり
ながら、ふつらふつら考えたのだった。
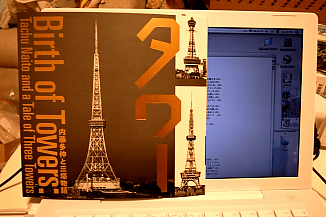
「タワー 内藤多仲と三塔物語」(INAXギャラリーパンフレット)、INAX出版。1500円。
名古屋テレビ塔、大阪通天閣(二代目)、そして東京タワー。これら3つのタワーを設計した人物、
-早稲田大学教授、内藤多仲のことは、この本ではじめてしった。わたしは、近代建築が好きだけれ
ども、同時に構造建築も好きなのだ。意匠のない潔さ、いや構造そのものが意匠とすら思える、力学
という理論に鉄壁なまでに支えられた、その姿にシビレルのである。わたしは工学部出身であるが、
電気系だったため、力学の授業は一年次のみで、機械系の人のように堪え難き苦しみを与えられたわ
けではなく、だから無責任にこんなことが言えるのだが。理論に支えられたものは、なぜかそこにあ
るだけで美しさを認めざるをえなかったりする、というとおおげさか。
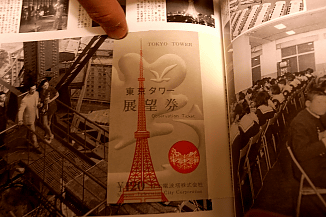

付録:開業当時の東京タワー展望券(表と裏)
内藤多仲は戦後だけでも、上記のタワーのほか札幌TV塔、別府TV塔、博多タワーの設計を行っている
のだが、戦前にすでに60以上のアンテナ塔を手がけていたというから、すごい。もうひとつこの本
でわかったことがある。それは、著名な近代建築の多くで、構造設計を手がけていたということだ。
早稲田大学大隈記念講堂、明治生命館、大丸京都店、それからあの千住にあったという「おばけ煙突」
まで多種・多岐にわたっている。すごい、すごいよ!と、読み進めるたびにびっくり、またびっくり
の連続である。氏の業績をこれまで知らなかったのは、一建築ファンとしては勉強不足の至り。反省し
ないといけないなぁ。
図版、写真多数。構成も◎。読み物としても、資料的にもこれだけのものは、なかなかないだろう。
構造建築、塔好きのひとにおすすめ(いるのか「塔好き」のひとって)。
なお、装丁は祖父江慎。さすが、いい仕事。
- 2006/6/30(金)
BK練習、18:40-21:00。
BK宴会、21:30-23:50。
きょうはMacBookを外に持ち出してみた。宴会中にPhotoshop Ele.でこの夏、BKが賛助出演する
演奏会のチケットを作るのだ。意外と外でも作業ができる。やっぱり、皆でイメージを共有しなが
ら修正を加えていけるのは良いなノート型マシンの利点。Windowsでもできることのはずなのにね。
どうしてだか、Macだからできる、という錯覚を覚えるのだった。でもマウスがないとミスクリック
が多くて、レイアウト作業にはやや苦戦。持ってはいっていたのだが、鉄板の手前の狭いスペース
では使えず。途中、鉄板の熱(お好み焼き屋に行ったのだ)で本体が溶けるんじゃないかと心配し
たのだけれど、大丈夫だった。鉄板からの輻射熱並みに実はMacBookは発熱するので、熱には強い
のかもしれない。ひざのうえに載せて作業していると、低温火傷が心配になるときがあるくらいだ。
MacBook自体は2.3kgと重いのだけれど、ふたを閉じると出っ張りがなく、薄いため鞄に入れても
容積をとらない。だから、わりと持ち運びがしやすいような気がする。そろそろ夏コミ原稿の作業
をしないといけないのだけど、どこかの喫茶店にでもいってお茶を飲みながら、などというあまり
似つかわしくないことをやってみたくなった。あっ、そうそうアップル的には「重さ」ではなくて、
「軽さ、わずか2.3kg」と表現するのが正しいみたい(笑)。(iBookG4のチラシ参照)
(わたしのWinマシン、Let'sノートは5年くらい前から、すでに990gなんだけど...。)
なんだかまとまりのない感じで申し訳ない。ふらふらしてきたので、眠ります。
- 2006/6/29(木)
朝から、レビュー(設計に問題がないか、よってたかってチェックを入れること)づくしで疲労。
午後は二時間ほど、わたしがレビューされる側に回る。しゃべりっぱなしのため、声が嗄れそうに
なる。プロジェクターを見やすくするため、部屋が暗く、逆に画面が明るすぎて見づらい。ちょっと
酔う。その昔、「E.T.」を今は亡き松竹映画館に見に行ったとき、酔ったのを思い出す。上映終了
後、人通りの絶えた新京極通りで、電柱につかまって吐き気にたえていた。なぜ、途中で抜けて帰
ろうとしなかったのか不明。字幕スーパーを暗いところで必死に目をこらして読んでいて、疲れて
しまったのかもしれない。子どものころから成長のないわたし。
すこし前から、暗室はMacで書いて、MacからFTPで送るようにしている。同時にメールもOS Xに
付属のメーラーで受信するようにした。NCのマネージや、BKのマネージで書類や写真のやり取り
が増えたからだ。本当は、メールの移行は十分に吟味するつもりだったが、急いでいたので付属
のものを仕方なくつかった。しかし、これが案外いいのである。インターフェースがOSとマッチ
しているのは当然だけれど、迷惑メールの自動フィルタリング機能や、アドレスの登録のしやす
さといった、ちょっとしたところが小気味いい感じで使いやすい。
しかし、特筆すべき点は別にある。メールの着信音が良いのだ。「ポン」という音。それは間違
いなく、飛行機のシートベルト着用サインの点灯時に鳴る、あの「ポン」音なのだ。この音は、
まわりがどんなにうるさくても、確実に耳に届くのに、それを聞いたことで不快な感じがしない、
いやむしろ快感?すらもたらすという不思議な音なのだ。すくなくとも私にとっては。だから、
「ポン」っと鳴って、メールを開くのが最近楽しい。心待ちにしているといってもいい。開いた
メールが楽しければ、より楽しく、嬉しければ、より嬉しい。そして、それがフィルタリングで
きなかった迷惑メールであったとしても、まぁいいかとすら思ってしまう。なんともまあ、あり
がたいというか、不可思議というか。この音、誰が考えたんでしょうね...。
- 2006/6/28(水)

「わたしを離さないで」、カズオ・イシグロ著、土屋政雄訳。早川書房刊、1800円。
日本人の名前なのに、なんで「訳」ってついているのかといぶかしんでいたのだが、著者は長崎生
まれの、英国育ちの日系英国人。本書は、英米で刊行されたので原著は英語なのだった。それどこ
ろか、英国最高のブッカー賞まで過去に受賞しているとのこと。全然知りませんでした。この本も
受賞歴多数のベストセラーらしいし。それにしては、日本での一般的知名度は全くないのが不思議。
マスコミで取り上げられる「海外に誇れる日本人」や、「海外で成功した日本人」だとか言うのに
は、たぶん登場しないのでしょうね。いや、それでいいのだと思うけれど。いまやマスコミがとり
上げるのは「お金持ちになったひと」だけだ。
さて、どうしてこの本を知ったか。本屋で直接見つけたわけではない。だって、およそ海外文学の
書棚というものは、ジュンク堂の例を見るまでもなく、いちばーん奥まったところの、レジからは
まったく見えないところにあるのだもの。高校の図書室の世界地理・歴史のコーナー並みにひと気
がないときてる。売れないのでしょうな、あまり。で、なにで知ったかだけれど、ずばり「本の雑
誌」の「新刊めったくたガイド」。つまり書評です。このコーナーは複数の評者が受け持ってるの
だけれど、一応ジャンル分けのようなすみ分けがされている。それにも関わらず、この本は二人の
著者に同時に取り上げられていたので、興味が湧いたのだ(ふつうの雑誌だったら、かぶったら
書き直させたりするのだろうけど、本の雑誌はそういうところは気にしない風である。もうひとつ
「蜂の巣にキス」(ジョナサン・キャロル著、創元推理文庫)という本も、複数著者推薦だし)。
ところで、推薦されていたからといって、すぐ買うものでもないので、ちょっと立ち読みしてみる。
お?内容に深く立ち入らないうちに、これは読みやすいなと感じた。なぜだろう。そう、翻訳モノ
独特の、奇妙な文章のひっかかりがまったくないのだ。著者が日系人であるから、その英語が日本
人にとって自然で、だから翻訳も自然、なんてことはあるわけはない。英語は英語である。これは
訳者がすごいのである(まだ、全部読んだわけではないので、著者の力量はわたしには量れない)。
この本を手に取る前に、「シンギュラリティ・スカイ」(ハヤカワ文庫SF)というこれまた英国の
本の訳書を手にとってみたのだけれど、最初の二行くらいでリタイアしてしまいました。とっつき
にくいことこのうえない。元の文章がもつSF的文章のせいもあるのだと思うのだけれど、やっぱり
読む気にさせる翻訳というもの、翻訳の差というものは厳としてあるのだろうと思った。
というわけで、冒頭の読みやすさ、没入できそうな雰囲気、あらすじに見るSF的要素、などから判
断して買ってきたわけです。ああ、なんだか読むのがとても楽しみだー。
ところで、海外文学書って、単価が高いせいか、装丁がよいものが多いなというのが、書棚を眺め
て感じた印象。どうでしょう?
業務連絡:凉宮ハルヒ(小説)、はじめました。
- 2006/6/27(火)
暑いだろう、と無意識にエアコンをつけて、冷房にしたり、除湿にしたりしていたのだけれど、
窓を開けて、換気扇で風を通したら、外は意外と涼しかった。未だにベランダに椅子をおきっぱ
なしにしているので、明かりがあったら本でも読んですごすのだけれど。なにしろ室内から漏れ
る光では少々暗いのだ。キャンプ用品の店に行ってランタンでも買ってこようかな。しかし、虫
が集まってきそうなのが心配ではある。
今日のところは、室内で「BLOOD ALONE」3巻(高野真之著、メディアワークス刊)を読んだ。
- 2006/6/26(月)
なんとなく気分が浮かないときに降る雨は、憂鬱であるが、静寂をもたらしてくれるものでもある。
こういうときは、同じような雰囲気を持つ小説だとか、音楽を自分に取り入れるのが良いという。
まえにも紹介した同質の原理。
なので、映画「トニー滝谷」をDVDで見た。二、三回目かな。BGMはすべて坂本龍一のピアノだ。
この前、原作(村上春樹。文春文庫「レキシントンの幽霊」所収)を少し立ち読みしたら、小説のもつ
雰囲気や文体が、ほんとうにそのまま再現されているのだとわかって、少し感動した。原作を先に読ん
でいたら、感じ方は違ったかもしれない。でも、映画にあって、小説にないものがある。宮沢りえの魅
力。吉永小百合と同年代のサユリストたちも、こんな風に感じていたのだろうか。宮沢りえと同い年の
わたし。
- 2006/6/25(日)
第55回東西四大学合唱演奏会@京都コンサートホールを聞きにいってきた。
開演から、終演まで、3時間15分という長さ。というわけで聞くほうも、かなり疲れた。
だから、いまからあまり、まとまったことは書けないと思う。簡単に記す。
実をいうとあまり期待せずに聞きにいったのだが、予想を覆す、とてもいい演奏会だった。
慶応:ジプシーの歌。この発声は、もはや伝統芸能。でも力強さがある。
関学:ドイツロマン派歌曲集。人数の少なさをカバーするために、響きをそろえて、徹底的に研ぎすます
方向に転換したようだ。これまでと全く違うスタイル。このまま、進めばもっとよくなる。期待度大。
とても良かった。
早稲田:季節へのまなざし。バカだなぁ。何も考えてない。でも、微笑ましく感じる。バカな子ほど可愛い。
同志社:丁寧さがわかる。でも個々人の芯が細すぎで、あれ以上声がのびないのが残念だった。響きをそろ
える、声を聞き合うという方向性は関学と同じ。あとは、同志社らしい何かを加えてほしい。
合同:男声合唱とパーカッションのための「響宴の歌」。信長貴富作曲、委嘱初演。大地から音楽がなりひ
びいたり、森のなかから聞こえてくる音楽であったり、とても壮大で、でも懐の深いものを感じさせる曲だっ
た。パーカッショニストだけでなく、学生もリコーダー、ギター、その他の楽器で演奏。こんなに一生懸命に
音楽がやれるんだ。ひところの無気力であったり、逆に悲壮感のあるような顔つきは演奏にはまったくなく、
ただ、ひたすらに音楽を作り出すことに真剣で夢中な姿を見ることができて、ちょっと安心した。合同に限ら
ず、演奏会全体を通して思ったことでもある。
こんなところかな。
おやすみなさい。
- 2006/6/24(土)
NC練習、17:00-21:00。集中しすぎて、終わったあとどっと疲れた。NCはやっぱり、体力勝負のとこ
ろがある。
練習前14:30~15:30、御堂筋線本町駅から歩いて5分の備後町にある綿業会館を訪れた。今日は月に
1回だけある見学会の日なのだ。昨日、BKの練習から帰宅してから、事前予約が必要なことを知り、
あわてて、きょうの9:00ごろに電話。すげなく断られるかと思ったら、さすが会員制の倶楽部、非常
に丁寧な応対で見学予約を受け付けてもらうことができた。
今日の見学者はなんと38人!クラスの社会見学のようだ。ほとんどが中高年の団体で、個人参加者
がちらほら。しかし、わたしのように建築好き!のオーラを出しているひとはおらず。しかし、これ
ほど人数がいるとは予想外だった。
見学は倶楽部の職員のひとに案内してもらう形ですすむ。写真撮影は自由。団体さんはばちばちフラ
ッシュたきまくるのだが、それもOKのようだ。ただ、撮影した写真を個人的に使用する場合でも、
同人誌に使用することはだめとのこと(一応お伺いをたててみた)。つまり、対価を支払ってもらう
ものに使うのは商業出版でなくても控えなければならない。ああ、聞かなければよかった。でも聞い
ちゃったからには本には載せられない、道義上。でも載せたい。考えました!無料ならいいと言われ
たから、綿業会館だけ別冊にして無料配布にする。形態は二つ折りかな。そうまでしても、これはみ
んなに見てもらいたい。これまで、いろんな建築を見てきたけれど、目を見開いて、思わずため息が
もれ出るような経験をしたのは初めてなのだ。ホームページで公開するだけじゃ物足りない、印刷し
たもので見せたい。本当なら、ここへ来て実際に見てもらいたい、そう思う。

綿業会館(日本綿業倶楽部)。昭和6年竣工。設計:渡辺節、村野藤吾。重要文化財。

ホール。イタリアルネッサンス様式。

談話室。部屋はジャコビアン様式。「喫煙室」を兼ねていた思われ、壁のタイルはイスラム様式か。

会議室。別名、鏡の間。アンピール様式。
見学会は、毎月第四土曜日、14:30から一時間程度。一人500円。要予約。
電話:06-6231-4881。
見学会に参加せずとも中を見る方法がひとつある。倶楽部の会員になればいい。もともと紡績関係者の
ための倶楽部であったが、最近では他業種の人間も入会可能とのこと。入会金12万円。月会費5000円。
安いか高いか?
- 2006/6/23(金)
BK練習、18:45-21:00。
BK宴会、21:30-24:30。前半は少しマネ会。うまくいくといいな。きょうは楽しかった。
宴会の帰り、ひとりになった後、ときどき大通りを外れて、町中の通りをいろいろ渡り歩きながら帰る。
もう遅いな、と思っていてもまだまだ営業しているお店があったりするのだけれど、あれ、みょうに人気
がないのに、明るいなと思うところがある。そう、お店の営業時間を終えたあと、ディスプレイや、玄関
のところだけ明かりをつけたままにしているのだ。たぶん、営業時間とはまったく違う姿、形がそこには
ある。さびしげなんだけれど、ひきよせられる。本来の姿ではない、みられることを意識していないはず
の建物や、窓という根源的な要素だけの存在。それを観察するわたし。そういう一対一の関係が静かな夜
にぽつんと存在することが、なんとなく不思議で、どこか別の世界に迷い込んだような錯覚をおぼえる。
そばには引き戻してくれるひともいない。いつまでも、ひとりでふらふら歩いていたくなる。
- 2006/6/22(木)
BKの仕事をまた少々。
さいきん、気になる歌手がいる。奥華子という。名前だけしっていたのだけれど、一週間ほどまえ
に初めて歌声を聞いて、一瞬で引き込まれてしまった。この夏公開される「時をかける少女」の
主題歌を歌っていて、TVCMでサビが少しだけ流れるのだ。ほんの10秒たらず。ちょっとの時間な
のに、その声を何度も聞きたくなる。まっすぐに届く歌が、映画の雰囲気とあいまって、少しぐっ
と来てしまう。17歳の戻らない夏の日というか。じぶんの17歳のころの夏なんてのは、さわ
やかでも、ロマンチックでもなくて、ただ艱難辛苦の日々だっただけに余計とあこがれてしまう。
(あのとき、合唱を止めなかったのはなんでなんだろうな。)あ、奥華子は17歳じゃないので
すよ。赤い眼鏡が似合う28歳。
http://www.kadokawa.co.jp/tokikake/index.php?cnts=info#20060404
予告編あり。TVCMより、長く主題歌が聞けます。
- 2006/6/21(水)
BKの仕事を少々やっていました。
ここしばらく、Macを触っていて思うことは、ショートカットキーを覚えたくなるということだ。
M川さんに、「マウスはいらない」といわれて半信半疑だったのだけれど、ひざのうえにおいて
文章をうつときなんかはマウスが使いづらいので、余計にそう感じる。タッチパッドで移動する
には画面が広いのだ。ショートカット自体はWindowsにもあるのだけれど、なぜかほとんどつ
かったことがない。この違いは何かと考えて、単純にMacBookのキーボードの感覚が心地良いか
らだということに気づいた。押しやすさもあるのだけれど、表面のつや消し加工のせいか、適度
に指先をうけとめてくれる摩擦があって、それがいいのだと思う。
長嶋有の「いろんな気持ちがほんとの気持ち」を読み返している。軽妙で、みょうに納得させら
れる文章がやっぱりいい。さらりと、ものごとの本質に切り込んで、でもそれが重くならないの
がいい。誰も持っていない視線がでてきて、「負けた!」って思わされるところがいい。
いちばん気に入っている文章は冒頭二つ目の「褒め負ける」。褒めよう、褒めようとおもって、
躊躇した瞬間に別の誰かに「差されてしまう」のだ。わたしも、ときどきあるので、その気持ち
がよくわかる。どうして、褒めたいのか。長嶋有は決意を述べるように、こう書いている。
「いつかこの世の『よさ』のすべてを習得しよう。そうしたら、いの一番に褒める。一杯奢っ
てもらう必要はない。喜んでもらいたいだけなんだ。」
はじめて読んだときも、読み返したときも、うん、そうだって、こころのなかであいづちを打
つ自分がいた。長嶋有とは長い友になれそうな、そんな気がした。
- 2006/6/20(火)
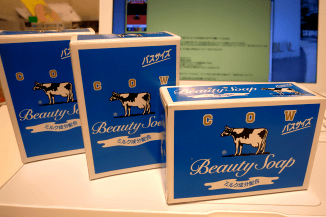

牛乳石鹸、青箱。
石けんが切れてしまったので、近所の薬局に買いにいった。で、ふと思ったのであるが、石けん
なんぞを店で買うのがこれが初めてではないのか。だいたい、実家にいるときは石けんというも
のは洗面所の下の扉をあけるとうずたかく積まれていて、それどころか旅館やらビジネスホテル
でもらってきたアメニテり、ってえい、ことえりで小さい「い」はどうやったらでるんだ!わか
らんので、「り」は小さい「い」と思ってください。で、それはともかく、アメニテりまでたく
さんあって、買う必要がなかった。親にしても、中元やら歳暮やらでもらったストックがあった
ので買ってきたというのは目にしたことがない。いや、知らないだけで密かに買ってきていたの
だろうか。
ともかく、こちらに引っ越すときも、実家からいくつか持ってきたのである。それが今回、いつ
のまにやらなくなった。わたしはハンドソープや、ボデリソープ(「り」は「い」)ではなく、
石けん派なので、わりと使っていたのだな。石けんの何が好きかというと、ひとつは箱やつつみ
を開けるときが大層楽しいところだ。新品の形、色、におい。新品だけがもっている感触。それ
ともうひとつは、減っていくところだ。シャンプーのように量が減るというのではなくて、形が
減じていくありさまが好きというか、磨かれて磨かれて、やがて消滅するところがなんとなく。
途中、分割してしまっても、ひとつに合体させて、磨いて磨いて整形して、またひとつにして、
それが減っていく行く末をみる。タオルにこすられて、こすられてエッジがたってくるのもいい
なと思う。すぐに泡立たなくても、ちょっと気を抜くと手からすり落ちても、石けんがいい。そ
れは、目に見えて、触れることのできる形を持ったもので、時間とともに変わるというところが
いいのだと思う。
すりすり。今日も、うちの石けんは減っていく。
訂正:ラジオのURL間違ってました。ごめんなさい。http://sinpo55555.com/mrx-8000.html
- 2006/6/19(月)
割と遅く会社を出る。金曜日に引き続き、少々込み入った仕事をしていたので、頭が疲
れた。クールダウンのため本屋に向かう。きのう言っていた漫画は、ヒロインの名前が
間違っていたらしく、主人公の名前だけで検索すると見つかった。名前だけはみたこと
がある。さてあるかなぁとおもって棚を見ると、なんと最新刊は19巻!これはつらい。
で、一巻だけ立ち読みができたので読んでみたところ、きのう見たのと絵柄が違う。そ
れはそーだ、連載開始が90年代と古いし、長い漫画はたいがいそう。そして、裏表紙の
あらすじを見て、びっくり。なんと、主人公だと思っていたメガネの男は主人公ではな
かったのだ。それどころか登場したのはつい1~2巻前。ヒロインも登場は10巻をす
ぎたあたりで、途中で一度話がリセットされた様子。うーん、どうしよう。漫画を読み
はじめるとき、4~5巻の既刊ならだいたいすぐに追いつくのだけれど、10巻をこえ
てからは「新規参入」しにくいとわたしの場合感じる。あきらめるか、それともリセッ
ト後から読むか。それでも半分だしなぁ。

ラジオ受信機、mrx-8000.
インターネットラジオをiTunesのように受信できるフリーウェアを見つけた。むかしの
受信機をイメージした画面は、イメージだけではなくて動作も凝っている。インターネ
ットなので、チューニングという概念は存在しないのだけれど、それを擬似的に再現し
ていて、チューニングのつまみをマウスでまわしていくと、放送局がない部分ではザー
ザーとしたノイズ、そして近づいてくると、キュイーンというあの独特の音が鳴り出し、
だんだんと音楽や声に変調がかかったものになる。そして、完全に同調できると、赤い
ランプがつくのだ。上下に動く操作ボタンもいい。動かすと、ややこもった低めのカチ
という音がする。これは昔の単コンオーディオのトグルスイッチの音を見事なまでに再
現している。手でつまんで動かしたときの感覚までよみがえってくるようだ。かつて、
祖父のうちにあったオーディオのスイッチを、意味もわからず、その感触と音を味わい
たいがために、なんども上げ下げを繰り返した記憶。上質なインターフェースというも
のは、何年も何十年も人間の記憶に深く刻まれる、そんな気がする。そしてそれはたぶ
ん普遍的なものなんだろうな。
アナログのレベルメーターがその代表かもしれない。もちろん、この「ラジオ」にも
装備されている。最近発売されたSONYの最高級ICレコーダーにも、左右独立のアナロ
グレベルメーターがついていた。なつかしい、という感覚だけで搭載されたのではなく
て、それが合理的だったからではないだろうか、インターフェースとして。
ところで、ラジオだとか、アナログメーターなどについて、わたしは思いいれは強いの
だけれど、それがほかの人にとってどうか、世間的にどうかというと、それはうーむな
ところだ。まえに宴会の席で友人に熱っぽくラジオCMのことを語ろうとしたところ、
「山Dさん、わたしらはラジオ世代ちゃうねんで」と一蹴されたことがある。そーかー
世代が違うのかー、そーかー...とちょっとショックを受けた。でも、大丈夫。たぶん。
歴史は繰り返すし、よのなかのいろいろなモノは巡る。そのうちにまた、ラジオの時間
はくると思う。現にポッドキャストというものがでてきた。形は変わったけれど、本質
は一緒だろう。放送を聞くという行為は、人間側のインターフェースが変わらないかぎ
りこれからもつづくのさ。
あ、ちなみにこのソフトはMac OS X, 10.4以降に対応。Windowsでは動きません。
ホームページ→http://sinpo55555.com/mrx-8000.html
- 2006/6/18(日)
京阪に乗って北浜、淀屋橋へ向かう。途中、隣の席になったひとが漫画を読み始めた。
ちょっとのぞき見ると、主人公は男だが、ヒロインの女の子がかわいい。メガネかけて
るし(男もかけている)。だんだん、ああこの漫画読みたいなぁと思い始めたのだが、
絵柄は見たことがないもので、作者がわからない。そのひとはカバーをかけていたので
タイトルも不明。隠されれば、隠される(いや、別に隠すつもりないのだろうが)ほど
読みたくなる。ラブコメ的な展開となるとなおさらだ!で、ちょろちょろと覗き見なが
らなんとか得た情報は、主人公の苗字と、ヒロインの名前(たぶん)。これをネットで
検索するのである。なお、読みたいと思っているので、ストーリーはなるべく見ないよ
うに注意を要した。帰宅後、すぐわかると思ったのだが、まったくひっかからず、現在
なお捜索中。なかなか手ごわい。なんとしても見つけてやる。
で、北浜、淀屋橋に向かっているのは二つ理由がある。ひとつめの理由は、これだ。

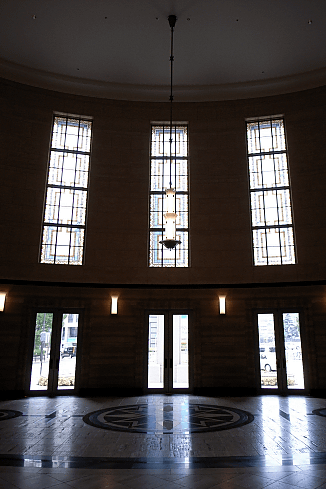
大阪証券取引所
この夏に出す予定の写真集は大阪の近代西洋建築がテーマ。中ノ島、淀屋橋、北浜の
近辺にはいまも数多くの貴重な建築が残っているのである。以前、一度のこの界隈は
撮影に来ているのだけれど、選択肢となる写真は増やしておきたいなと思って、再訪。
大阪証券取引所を皮切りに、定番の中央公会堂、大阪府立図書館、三井住友本店など
をはじめ、小規模な店舗なども切り取っていく。気がつけば、1時間半近くたって、
汗だくになっていた。もう、6月。全力でうごくとかなり体力を使う。で、そろそろ
つぎの場所に移動しないといけなかった。
御堂筋線でなんばへ。そして、南海電鉄高野線に。南海電車に乗る理由といえばただ
ひとつ。毎年恒例の大阪府合唱祭に行くためである。しかし、ことしはNCは出演し
ないため、聞きに行くのだ。YKの演奏を。いつもなら指揮者のI氏が指揮するので
あるが、氏が用事のため、今回ははじめて、いつも練習指揮をしている友人のNaが指
揮をすることになった。Naの本番指揮を見るのは初めてなのだ。わくわくする。
場所は大阪狭山氏駅近くのSAYAKAホール。いつもの貝塚に較べて多少近いのであるが、
京都の人間にしてみれば、「遠い」のにかわりはない。YKの演奏の10団体くらい
前から聞き始める。その間、正直かなりつらい演奏が多くて、逃げ出したくなるとき
もあったのだが、くわしくは書かない。YKの演奏を聞くという目的がなければ絶対
来年もう一度聞きたいとは思わないかもしれない。一生懸命やっているとか、それだ
けではだめで、やっぱり合唱も音楽の一つである以上、音楽として成り立っていない
といけない。聴衆に聞かせるための音楽、ともにうたう音楽でないといけない。でも、
何か「合唱だから」という甘えのようなものを感じさせる演奏や、自己実現のためだ
けの演奏が多くて、それがとてもイヤだった。
そんななか、YKの直前に演奏した岸和田市立桜台中学校の合唱部の演奏は、文字通
りわたしの頭をスキッとさせてくれる、とても気持ちのいい合唱だった。先生ではな
く学生指揮者の女の子が前に立つ。演奏がはじまる、その瞬間、すぅーっとその場に
音楽の波のようなものが形成されて、ステージから客席に流れ出すのを感じた。これ
は違う、これまでのどんな大人の団にもなかった、演奏が少しはうまかった団体にも
なかったもの。その場にいる彼・彼女らと、指揮者の彼女が一体になって、音楽をつ
くりだそうとしているのがわかった。発声だとか、声量だとか、和音だとか、それら
はとても重要で、未熟な部分はあるけれど、でもそういうことはどうでもよくて、
ひとに伝わる音楽っていうのは、これだーっていうことを教えてくれた、そんな気が
する合唱だった。それはその場にいたお客さんみんなそうだったと思う、ほぼ全員が
退場するまで拍手が続いていたから。
さて、つぎはYKの番だ、Naの指揮だ。緊張する。でもみんなは割りといい顔をして
いる。どうだろう。はじまった。
ああ、中学生にはできない、より高度な大人の演奏をYKはちゃんとやってくれる。
音楽の流れも悪くない。なにより、Naの指揮がかっこいい。音楽に対して、とても
的確にYKの音楽性を引き出すための指揮をしている。それは練習のための指揮で
はなくて、指揮者Naとしての指揮と音楽が見えてくるものだった。ああ、この場所
にいて、聞けてよかったと思えた。
演奏全体を見るならば、体全体の表情が固かったり、アルトだけが少し遅れたりと
微妙なところもあったのだけれど、ひいき目を承知でいうなら、そういう部分をあ
げつらうことの意味のなさを教えてくれる演奏だった。合唱の楽しさ、音楽の楽し
さを十分表現したものだったと思う。課題がまったくないわけではないけどね。8
月にある定期演奏会ではもっとよくなるはずだ。あとはNaの指揮にもっと呼応して
ほしかったかな。でもNaも緊張してたしね。YKの皆さん、Naお疲れさまでした。
というわけで、こんなに気持ちよく会場をあとにした大阪府合唱祭は初めてのよう
な気がする。時間にして10分もない演奏が、往復の時間を忘れさせてくれる。やっ
ぱり音楽ってすごいや、合唱っていいな、と思えた時だった。そんな恥ずかしいこ
と言うなって?いや、言うぞ今日は。
その後、梅田まで戻り、串カツ屋で飲んだ。途中、道に迷ったり、見知らぬ中古カ
メラ屋によったりもした。久しぶりに食べた「こんにゃく」の串はとろけるような
味わいで、ほんとうにおいしかった。今日の締めくくりには最適だった。
阪急電車で帰京。23:00、帰宅。
では、もう寝ます。おやすみなさい。
24:05記す。
- 2006/6/17(土)
AirMacExpressを買ってくる。Macからはほんの少しの設定だけで、いとも簡単に
インターネット接続できた。AirMac本体にアンプをつないで、iTunesでラジオを
選択し、BGMにJAZZを流しながらネットを見て回るなんてことが可能になった。
(なぜJAZZかって?大人のミュージックだからだ!)
で、本題のWindowsマシンからの接続なのだが、未だ構築できず...。ネットで
さがした記事を参考にしているのだが、確固たる手順というものがわからない。
Let's noteの無線LANカードは、AirMacの存在は認識し、「接続」はしているみ
たいなのだ。しかし、TCP/IP接続ができない。つまりインターネット接続ができ
ないのだ。Mac側で接続共有を開始しても、だめ。インターネットにつなげない
だけなら、それはそれでいい。Mac側でなんとかなる。でもファイル共有ができ
ないと、大きな問題がある。Let's noteで構築したiTunesのライブラリをMac側
にもっていけないからだ。本を作るための写真はMOで移動できるものの、ライブ
ラリ程の大きさになると無理だ。DVDに焼いて、もっていくなんて屈辱的なので
最後の最後までとっておく。
しかし、きょうはここまでにしておこうと思う。このまま、解をさがしつづける
と精魂尽き果てるのは目に見えている。Windowsってやつは...ほんとたまらん。
- 2006/6/16(金)
BK練習、19:00-21:00。
BK宴会、21:30-23:00。
見学者がなんと5人も。合唱祭を聞いて、という人はやはり多いのだなぁ。
練習は新曲。仕事で消耗していたので、あまり果敢に攻められなかったのが
残念だった。いい曲。疲れた。
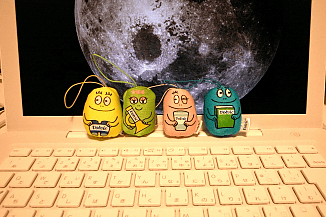
Volvic、バーバパパシリーズ。
集めるつもりはないのだけれど、Volvicを買うとついてくるので自然と。なかに
細かいビーズが入っているようで、指で押すとむにむにした感触。にぎにぎして
手のストレスをとるのに使っている。機能とバーバパパの特徴(のび縮み)が見
事に融合しているのであった。というか、バーバパパのアニメーション、ここ20
年くらい見たことがないのだけれど、あの「バーバー(ちょっとためて)トリップ!」
の効果音(?)が入る変身シーン、実は20代の人は見たことがないのではないだろうか。
うーむ。
- 2006/6/15(木)
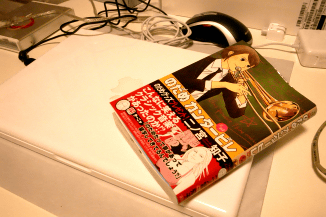
のだめカンタービレ15巻。二ノ宮知子著、講談社刊。390円。
今回は、のだめに甘い千秋。心境の変化か?
きょうみた夢はかなり変だった。友人と英国に行くことになったのであるが、旅の手配は
個々人でやるというので、つれていかれたのが西洋建築の屋敷のなかにある広い講堂のよ
うなところ。見ると壁のあちこちに紙やらなんやらが張ってある。よく見ると、どれも
旅行の手配を個人で請け負う人たちの宣伝用紙なのだ。飛行機の写真が印刷されているも
のがあり、これはその飛行機会社の往復のチケットのみ手配という意味らしい。あるもの
は、手書きの絵と文字がびっしり書かれている。どうやら観光パックの案内のようだ。わ
たしはここで一時間以内(だったと思う)に手配を終えないといけないので、かなりあせ
りながら探している...というところまでおぼえている。
最近、肩こりがひどくて寝不足気味なので、きょうはこのへんで。
おやすみなさい。って何時に書いているかわからないよね。
23:45です。
- 2006/6/14(水)
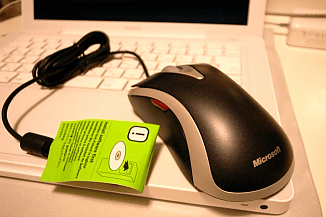
Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
マウス買ってきました。ってなんでマイクロソフトマウスやねん!ってつっこまれるのは
覚悟のうえなのだ。はじめはアップルのマイティマウスを買うつもりだったのだけれど、
どうもアップルストアの書き込みを見ていると共通しているのが、「三週間たつと下スク
ロールができなくなる」というもの。スクロールスイッチにゴミが溜まりやすい構造みた
いだ。割とお高いものなので、これはパス。で、昔から愛用しているマイクロソフトマウス
を選んだ。いわゆるなすびマウスという独特の形なのだけれど、手にフィットして握りや
すいので好きなのだ。まだマウスが1万円くらいしたころから使っている。これは2940円。
いろいろ種類があるなかで、こいつを選んだのはスクロールボタンの感触だろうか。ほか
のタイプが、スクロール単位ごとにカチカチと音がするのに対して、こいつは音がしない
し、カチカチ感もない。どちらかというとぬめっとして粘性が高い。なので、ゆびの動き
に追従しやすい。アナログ的というか。カチカチはデジタルなので、自分の思ったところ
で停止しない(カチの単位で動くから)のが癪なのである。カウント数からいったら、わ
ずかな差なのだけれど、インターフェースは自分の感覚にあわないとストレスが溜まる。
だから、こだわりは重要なのだ。インターフェースに自分の感覚をあわせるのが一番よく
ない。
さて、帰宅して最初にやったのがOSの再インストール。これはバンドルソフトなどの使わ
ないソフトをインストールしないことでHDDの容量を増やすために必須の作業。実用容量
74Gbyteで、そのままインストールすると、53Gbyteしか空き容量がない。しかし、削りに
削って、68Gbyteまで増やすことができた。ただし、バンドルソフトのうち、Officeだけ
はインストール(30日のトライアル版)。これはフォントが目的。MSPゴシックとかは割
りと使いでのあるフォントなので必要。雑誌の記事によると、トライアルが過ぎても、
フォントはそのまま残るそうなのだ。
それからようやくPhotoshop Elementsをインストール。さて、速度はどうか...全然問題
ないレベルだなぁ。800万画素のデジカメのファイルを扱っててもストレスはまったくな
い。メモリのおかげかな。Elementsの使い勝手はすこぶる良好。ワイドスクリーンという
環境がうまく効いている点もある。横幅が広いので、画像とそれ以外のツールウィンドウ
が重ならずにすむのだ。4:3の画面だとこうはいかない。Macを買った最大の目的は果たせ
そうだ。
週末は、AirMacExpressを導入して、無線LAN化計画を発動する予定。Winマシンである、
レッツノートR1には11bの無線LANが内蔵されているのだ。11gと11bは混在可能なので、
MacBookとの共存を図る。というか、ケーブルつなぎかえるのがめんどくさいだけなん
だけれど。iTuneの音楽をリモートでスピーカーにつなげる機能も魅力的。
わりとここまでストレスフリーに使えている。
PCはこうあるべきだ。うん。やっぱり。
- 2006/6/13(火)

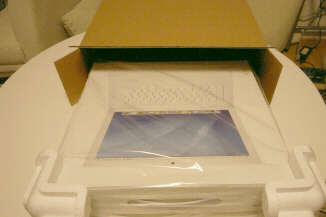
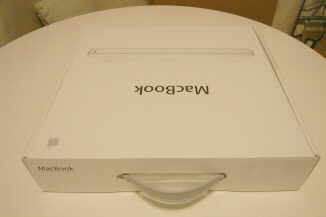
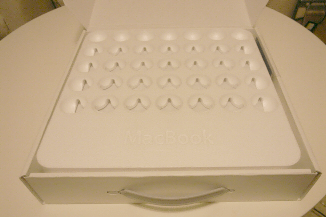

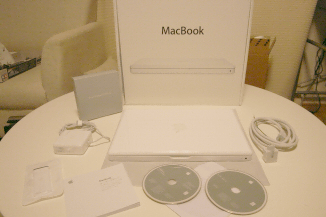
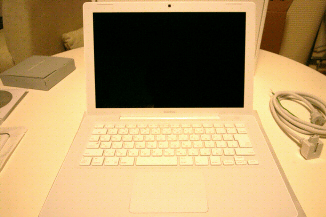
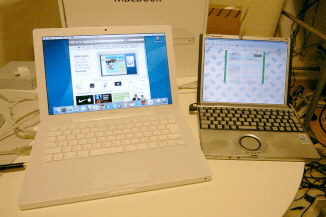
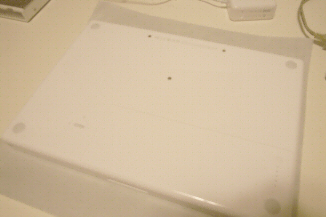

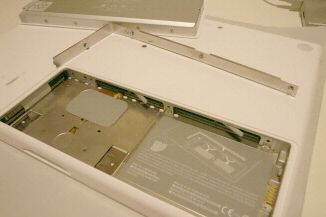
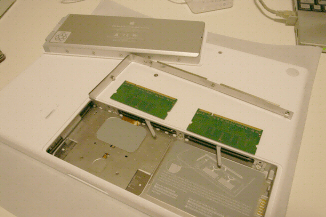

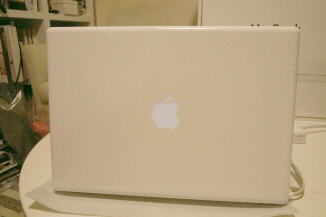
MacBook来た。
フレッツのアカウントと、パスワードを入力しただけでインターネットに直結したのに
はたまげた。ああ、これがPCのあるべき姿なんだね....と、ちょっとうっとり。Winで
使っていたMOをUSB接続しても、即画像ファイルが読みこめた。Windowsフォーマットの
MOディスクを直接見れるわけだ...これは、かなりすごい!いい。すごくいい。
あしたマウス買ってこよう。
- 2006/6/12(月)
きょうアップルストアで注文状況を確認したところ、6/10に出荷完了、6/15到着予定に
変更されていた。早くなる分には構わないけれど、見積もりの精度がアバウトだなぁ。
この分だと明日あたり到着しそうな気がする。
雑誌を読んでいてはじめて知ったのだけれど、MacOS XはUNIXのソフトウェアがコマン
ドラインベースだろうが、ウィンドウベースだろうが動いてしまうのだ。Windowsでも
リモート接続すれば、動かせるソフトはあるけれど、あくまでそれはターミナルとし
ての役目でしかなくて、Windows単体では意味をなさない。このことは仕事でUNIXを使
っている者にとっては、正直びっくりなことだ。だって、マシンのパワーを問題にしな
ければ、UNIX業界の巨人Sunがなしえなかったワークステーションのダウンサイジング
をOSレベルで実現したということだからだ。ひらたくいうと、ノート型UNIXマシンに
なるのだ、MacBookは。インテルマックでSolarisを起動することもできる(ほかなら
ぬSunの技術者が実現)というけれど、ソフトを使うだけのエンドユーザーにしてみれば、
そのことにあまり意味はないように感じる。(厳密にはSunRay環境というダウンサイジ
ングはあるにはあるけれど、ノートPCのような個人用途向けでははないし。)
BootCampによってWindowsXPが動いてしまう現在、WindowsPCを新たに買う意味が薄れ
てきている。動作速度の問題は早晩解決しそうだし、つきすすめて考えれば、雑誌に
もあったけれど、WindowsアプリをWindows環境で動かすのではなくて、「MacOS上で
ウィンドウズアプリケーションを直接動かす」(MacPeople7月号、海の向こうで胸騒
ぎII、飯吉透著、より引用)時代はほんというにすぐにやってきそうな雰囲気である。
Windowsユーザーは、たかがMacOSと侮っていてはいけないのかもしれないな。OS Xは
MacOSであって、MacOSではない(NeXTSTEPの後継)のだから。次期Windowsに対して、
確たる希望や、期待が持てないのに対して、OS Xには夢を見れる、そんな気がする。
PCとかOSとかに興味のないひと、ごめんなさい。ちょっとつっぱしってしまった。
- 2006/6/11(日)
きょうは、モールトンでツーリングに行って来た。ツーリングというからには、ひとり
ではなくて、総勢16人。わたしがモールトンを組み立ててもらったお店は、西京極にあ
るMoku2+4という小径車専門の自転車屋さん。モールトンはもちろん、BD-1、ブロンプ
トンなどのさまざまな車種を扱っているのだが、小径専門というのは全国的にも珍しく
その筋では有名なお店なのだ。モールトンに関しては、オリジナルのパーツを作成したり、
カスタムチューニングの事例が豊富で、日本の代理店だけでなくて、モールトン社や、
パシュレイ社(モールトンのライセンス生産社)にも名を知られている。
そのMoku2+4のお客さんたちとのツーリングなのだが、きょうはゲストが居た。モール
トン社で開発を担当しており、モールトン産みの親であるアレックスモールトン博士の
甥である、ショーンモールトンさん、そしてガールフレンドのカレンさんだ。二週間ほ
どバカンスに来たとのこと。なので、今日は定番観光コースをめぐる。
さて、山Dはこれらのメンバーとは、店長を除いて全員初対面。モールトン暦も浅いの
でなんとなく気弱。うまく打ち解けられるか、不安なまま出発となった。
10:30にMokuに集合。以下のコースをたどる。
Moku出発→堀川通→御池通→寺町通→鴨川沿い(西側)→紫明通→昼食。
→今宮神社(あぶり餅)→金閣寺→竜安寺→嵐山(休憩)→Moku解散。

今宮神社にて。モールトンだらけ。あぶりもちを食べました。
(モールトンのほかにも、BD-1が4台参加。モールトンは、AM,APB,BSM,パイロンと多彩。)
ツーリングというと、一直線に走るイメージがあると思うのだけれど、広い通りを走る
ときは、ときに並んだり、ときに前後にわずかにずれて重なりあうこともあって、結構
走りながら、会話できるのだ。最初は不安だったが、思い切っていろいろな人の隣で、
しゃべることにする。逆に、常連さんのほうから、話かけてくれたりして、モールトン
や自転車、ツーリングのことを軸に話しがすすんだ。なんだ、気にすることはなかった、
みんな同じ自転車のオーナーなんだし。気さくな人が多いのだ。合唱をやっていること
なんかも話すことができた。今日のためにと思って、NCの名札をかけていったのも、
目だってよかったみたい。昼食をとるころには打ち解けることができた。
誰しも、はじめてコミュニティに参加するのは不安があるはずだ。それを乗り越えるに
は自分から乗り越えるのと、山の上から手を伸ばしてくれるひとの両方が必要なんだな
と、この過程で感じた。特にモールトンの世界というのは、マシンのメカニカルなスペ
ックや、値段の高さが取り上げられることが多いけれど、じつはこういう「輪」が自然
に存在するという「風土の良さ」こそが魅力なんじゃないだろうか。自転車界では珍し
くオーナーズミーティングが世界や日本全国で開かれているのは、その証だろう。
このことを別のコミュニティに敷衍して考えてしまうのは、どうしても仕方がないこと。
たとえば、それはBKに対してであったりする。BKの風土って、こんなに入りやすく
はないよね?

金閣寺。ベタですが、やっぱり観光地になっているだけの見所があります。

おみくじマシーン。英語、ハングル、中文、各種そろいぶみ。

龍安寺。石庭の前はいもあらい状態。平日の午後とか、人気のないときに再訪したい。
石庭以外に、池の周りを回遊する庭園の緑が素晴らしい。秋はそざかしきれいなことだろうな。
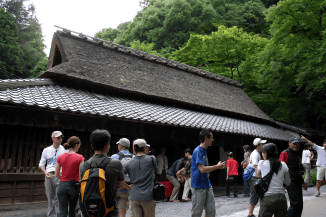
きぬかけの道を通って、嵐山・清滝方面へ。嵯峨野は鳥居本、愛宕山の神域の鳥居のすぐそば
にある、平野屋で休憩。ひんやりした空気と、山の緑の良いにおいに、ショーンさんも、カレン
さんも、やたらスメルグッド、とかプリティグッドと言っておりました。
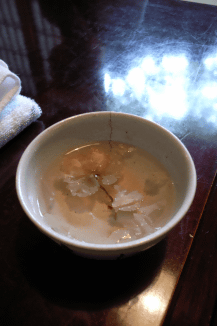 
さくら湯。しんこ餅とお抹茶を頂く。あー極楽。右は店の人が鮎をすくっているところ。

平野屋から引き返し、野宮神社(ののみやじんじゃ)を経て、TVによく登場する竹の回廊へ。
わたし、恥ずかしながらはじめて通りました。そして、ついに最終目的地の嵐山へ。ああ、この
山、この水の流れ。圧倒される気持ちよさ、開放感。

夕日を浴びるモールトン。
嵐山からは、サイクリングロードを通って西京極へ。ここぞとばかりに30km/h近いスピードで
飛ばすみんな。市内ではだいたい15~6km/hというスローペースだったので。
Mokuに着いたのは18:30でした。
総走行距離、41km。走行時間2時間46分。最高速度35.7km/h。平均速度14.7km/h。
ああ、よく走った。よく食べた。よく見た。ありきたりなコースと思ってあなどっていたのだ
けれど、ほとんどがはじめて走る道ばかりで、烏丸再発見の旅にも通ずることだけど、わたし
はまだ京都の全部をしっているわけじゃないのだと強く思った次第。
ツーリングが、たくさんの人と走ることが、こんなに楽しいとは思っていなかった。
よい一日でありました。
分野は違うけれども、NCでも、BKでも、こんな楽しいことはない!って思えるようになら
ないと、そういう風土になっていかないとダメだ。頑張ろう。
- 2006/6/10(土)
NC練習、18:00-21:00。帰宅したら結構疲れてた。
練習直前まで梅田のヨドバシカメラ店頭でMacの習熟訓練をする。そういうえば原稿作業する
のにマウスがいるなと思うが、まだ買わない。なぜなら、到着予定は20日。アップルストア
の出荷は14日で、これも意外と遅いのだけれど、なぜ到着に6日もかかるのだろう。シンガポ
ールあたりから空輸するにしたって、ちょっと遅いなぁ。かつて、TIMBUK2(自転車用の鞄)
を注文してから到着までの5日間と、どうしても比較してしまう。同じオーダーメードでこの
違い。20GByteの上乗せで、プラス12日はちょっと予想外だった(HDD、60Gのままなら即納の
店があったので)。

そういうわけで、メモリだけ先に着いてしまった。DDR2-667,1Gbyte×2。
まぁ、待つのは得意。その間に写真を整理するか。
今日のモールトン

後輪のチューブ交換中。

うちの近く、五条天神宮にて狛犬と。
モールトンは後ろ姿の方がフォトジェニックだと思う。
- 2006/6/9(金)
すいません、体が超絶にだるくて寝てしまいました。職場の空調がやけに暑くて、そのせい
かと思っていたのだけれど、帰宅しても症状がかわらず。眩暈もある。半年にいっぺんくら
いおこる症状に似ているので、たぶんそれだろうと結論づけて、無理せず寝ることに。しか
しあんまり眠れず。途中、リストラされてホテルを改造した工場で働かされるという悪夢を
見てしまう。異星人が攻めてくるとか、怪物に襲われるとか、そういうものよりも、ちょっ
とリアルが混じった夢のほうが怖いことこの上ない。
起床後、症状改善見られず。あう。(6/10、昼記す)
- 2006/6/8(木)
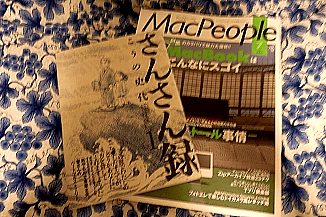
「MacPeople」7月号、ASCII刊。780円。
とうとう、わたしもマッキンな人(寺島令子著、「墜落日誌」参照)になることが決定し
たので、情報誌を買ってみた。Windows系の雑誌に比べると、そこはかとなく文系の
香りが漂っているように感じるのはなぜだろう。
「さんさん録」、こうの史代著、双葉社刊。742円。
『この世でわたしの愛したすべてが、どうかあなたに力を貸してくれますように』。
同じ著者の作品「長い道」は、道と荘介の二人の話だったけれど、さんさん録は亡き妻
と、息子夫婦と孫、そして妻の遺した生活ノートの話。どこかつながっているような気
がする。読んだときのこの感じはなんていうんだろう。切ない?しみじみ?あたたか?
違うなぁと思っていたら、裏表紙の解説に答えを見つけた。そう「ほろ苦くも面白い」だ。
梅雨だなぁ。明日、何をしてすごそうか。
- 2006/6/7(水)
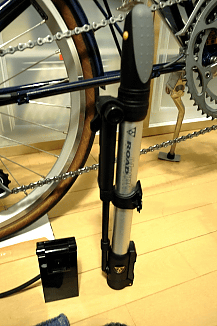 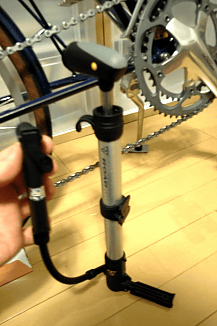
Topeak社製ROAD MORPH.(空気入れ)(左)収納時、(右)展開時
携帯用の空気入れを買ってきた。え、いままで持ってなかったの?と不思議がられそう
である。モールトンのタイヤのバルブは、仏式なのだけれど、うちにあるのはほとんど
の一般家庭にあるのと同じ英式バルブ用のもの。ルイガノ号を買ったときに専用の空気
入れを買わないとなぁと思って、タイヤを見るとなんとスポーツ車なのに、英式バルブ
がついていて、ずいぶんがっくりきたのだけれど、そんなわけで仏式を買うのは初めて
なのだ。もうひとつ、米式というのもある。高圧をいれる場合は、仏式が主流のよう。
さて、空気入れを買ってきたのは、どうやら後輪がスローパンク(少しずつ空気が抜け
るパンク。極小さな穴が開いている)しているみたいで、走行中に尻が振れるようにな
ったからだ。気づいてから2~3日でかなり減圧。このままでは修理に持っていくことも
できないので、とりあえず空気を入れてみる。ロード系のタイヤの圧力は8~9気圧必要
なのだけれど、これがまた予想以上にきつい。6気圧くらいまではわりと簡単に入った
のだが、そこから先がなかなかすすまない。ちなみにこの空気入れには圧力計がついて
いるので、それでチェックする。普通のMTBのタイヤだと3.5気圧だというから、倍以上
だ。携帯式のなかには、片手で持って、片手で空気を送り込むものがあるが、あんなの
では到底8気圧は入らない。展開時の写真を見てもらうとわかるが、コイツは床に立てて
体重を掛けられるので、まだまし。店で薦められたのが、このタイプなのもうなづける。
なんとか、120PSI近くまで入れる。あ、そうそう圧力の単位は、このPSIというポンド
と、kPa(キロパスカル)、kgf(キログラム=1気圧)の三種類があるそうで、国際標準
単位系ではkPaが標準。欧米では例によって標準単位系なんか無視していまだにポンド
を使っているわけで、このTopeak社(米国)のゲージも当然PSI表示なのだ。この例に限
らないが、傾向として日本は、律儀にISOに準拠しようとする。逆にまったく守らないの
は英国と米国。日本にも尺貫法は残っているけれど、商取引では禁止ではなかったかし
らん。尺貫法と同じように、なじみの単位系というのがあるのは理解できるのだけれど、
こと国際的に利用される商品やゲージに標準単位系を使わないのは理解に苦しむ。
で、120PSIというのは約8.5気圧。耳をすませてみても、空気が漏れるような音は聞こえ
ない。単にバルブが緩んでいただけとか?あるいは漏れ音が聞こえないくらいだからこそ
スローパンクなのか。とりあえず、これでしばらく放置して、週末まで様子を見るつもり。
Macの件、その後、有識者3人の意見を参考にさせてもらった結果、MacBookを買うことに
決定。もう、注文した。アップルストアで、2.0GHzモデルのHDDを60→80GBにアップ。
メモリは純正の場合、512→2GBにすると約6万円の追加とばか高いので、通販で別途購入
して自分で差し替えることにした。この場合半額以下になる。なぜ、こういう買い方を
したかというと、メモリ増設はショップオリジナルモデルで存在するものの、HDDについ
てはアップルストア以外ではアップする選択肢がなかったからだ。HDDの追加費用が6000円
と安かったのも理由。
で、ソフトの方はどうするかというと、Photoshop Elements(トライアル版)を使うこと
にした。GR-Digitalを買ったときについてきたもので、Win/Mac両方ついていたのだ。昨日
WinPC(ノート)にインストールして確かめたところ、わたしが本を作るときに使う機能は
すべてElementsで網羅できていることがわかった。ならば、当面はこれで十分だ。来年の
ネイティブ対応のAdobe CS3をゆっくり待てばいい。
一つだけ問題がある。トライアル版なので、30日しか使えない。だからインストール後、
30日以内に本を完成させないといけない!って、そんなせこいことしなくても、1万円程度
のソフトなんだから買えばいいのにって思うかもしれないが、これはあれだ。自分に課す
ハードルなのだ。キンコーズにおける時間との闘いを過去に押しやった今、本を作ること
に対する緊張感が薄れてしまうことを何より懸念している。一定以上のクオリティのもの
を出すのは当選した者の義務だと思うし、自分が納得できない同人誌なんてありえない。
制限のあるなかにこそ、創意工夫が生まれて、高い水準のものができるのは、世の中の
真理だろう。時間があれば、いいものができるというのは、多くのひとが気づいている
ように幻想だと思う。
まぁ、理想です。とりあえず完成目標を本番一週間前の8月第一週と定めて、逆算して
7月第一週にPhotoshopでの作業を開始する。つまり、それまでの約1ヶ月で企画と写真
のセレクション、台割を決定する必要があるということ。Macへのデータ移行や習熟の
時間も考えると、かならずしも十分ではないかも。
ということで、体制は整いつつある。本作り頑張るぞー!
(本業の仕事も頑張らねばならぬ、印刷代確保のために。←本末転倒)
- 2006/6/6(火)
さくじつの演奏は大層よかったそうなのである。ならば、無理をしてでも行くべきで
あったと後悔したのであるが、果たしてそれはそれで正しいことなのかと思う。心理
学の用語で同質の原理というのがあるそうだ。楽しいときには、楽しい音楽を聞くの
がいいし、悲しいときには悲しい音楽を聞くほうが、心の理にかなっているというこ
とらしい。つまり、悲しいときに楽しい音楽を無理に聴くのはギャップがありすぎて
かえって負担になるのだという。
きのうは楽しくも悲しくもなく、単純にしんどい状態だったのだが、青いメッセージ
はどちらかというと、切なさとか物悲しさを超越したところにある、力強さのある曲
だから、同質であるとはいえない。かといって対極にあったわけでもないから、やっ
ぱり聞きにいけばよかった。健康管理の不徹底は、ときに不利益をもたらすものだと
思い知る。
で、きのうはどうしたかというと、本を買って帰った。
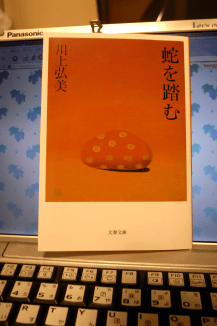
「蛇を踏む」、川上弘美著、文春文庫。390円。(第115回芥川賞受賞作)
きのうの心理状態としては、この物語のようにとらえどころのないものと同質の感覚
だったのだろう。冒頭の文章を読んで、すぐさま買うと決めていたことからも、たぶ
ん正しい。
『藪で、蛇を踏んだ。「踏まれたので仕方ありません」と声がして、蛇は女になった。
「あなたのお母さんよ」と、部屋で料理を作って待っていた...。』(あらすじより)
きょうの夜になってようやく、思考がはっきりしてくる。やはり甚だしく夜型人間なのだ。
最近、思考しているとき、頭のなかでは断片的な独白ではなくて、暗室に書いているよう
な文章がつむがれていることに気がついた。一度出力された文章を推敲し、手直しし、
また出力する。そんなことの繰り返しである。暗室を書く行為が日常に深く直結してい
るということだろうか。
Macの件であるが、現状ならiMac G5が良いんじゃないかとM川さんに薦められたこ
ともあり、ずいぶんと探してはいるのだが、遅すぎたようで、判で押したように店頭在
庫はありませんという答えが店からは帰ってくる。iBOOK G4の在庫がソフマップにあっ
て、ずいぶんすすめられたのだが、液晶が見劣りすること、Photoshopの作業がつらいの
ではないのか?ということで保留中である。1Gのメモリを積んでもかなり安いのは魅力
であるが、写真中心の作業だとMacBookや、iMacの液晶の方がやり易い。このままだと
IntelMacの可能性が濃厚となってきた。ほかのMacユーザーにも聞いてみる。
エキスパートに聞いてみた意見と、わたしの使い方からして、MacBook,2.0GHz,1GB,80G
という線が現実的。この夏に出る、第二世代IntelCoreの性能がいいらしいので、待て
るなら待ったほうがいいが、機会損失を考えるならベターとの見解。まぁ、結局はそこ
が一番重要なのかもしれない。いま使えるということを優先させるべきなんだろうな。
いわゆるプライスレスというやつだ。
- 2006/6/5(月)
関混連、合同演奏「青いメッセージ<混声版>」を聞きにいくつもりだったのだが、
どうにも体調が思わしくないため、大阪まで行く気力が出ずに断念。
更新、休みます。すいません。
最近生活リズムが狂いがち。
- 2006/6/4(日)
第43回京都合唱祭。BKにて出演。
いつまでも成熟できない合唱団から、脱却するにはどうしたらいいのか。思い悩む。
かれこれ、もう8年目なのだ。
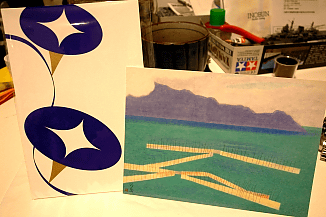
BK練習前のぶらぶらしている時に、京都便利堂の前を通りかかった。以前、さがして
いて見つからなかったので入ってみる。便利堂は美術館や、美術展で販売される図録や、
絵葉書の作成を請け負っている会社で、そのギャラリーがここ、三条富小路上がったと
ころにある。日本各地の美術館所蔵の作品の絵葉書が壁一面に展示されて、そのどれもが
80~100円という値段で買うことができるのだが、あまりその存在は知られていないように
思える。誰も、いままでああいうところで販売されている絵葉書は、誰が、どうやって、
作っているのかなんて考えもしなかったからかもしれない。よく考えてみれば、絵画複製
というのは、相応の技術が必要なことなのだ。
壁に貼るつもりで、夏向けの絵柄のものを選んでみたのだけれど、いかがでしょう。
左の朝顔は便利堂オリジナルブランド、文房伯爵の一枚。朝顔、なんとなく好きなのだ。
英語名が、"morning glory"っていうところも好きな理由。朝が弱い身としてはあこがれ
なのかもしれないなぁ。右は小野竹喬の「湖」という作品。これ、やっぱり琵琶湖なん
だろうか。淡いエメラルドグリーンが目に優しく感じて選んだ。
便利堂を出たあと、練習開始まですることもなかったので、練習場近くの下御霊神社に
行って、境内で本を読む。ときどき寝る。ここの井戸水は名水としてしられているから、
ポリタンクを持ったひとがよくやってくる。水を汲む音は、それだけで涼しい。公園の
少ない京都は、お寺や神社がその代わりになって、都市の清涼を担っているような気が
するのだった。
- 2006/6/3(土)
NC練習、18:20~21:00。参加16人。今日はバリトンいました。

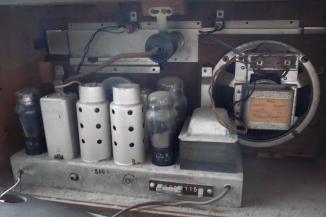
真空管ラジオ、日本ビクター製。
墓参りの帰りに実家に寄る。祖父が亡くなってから家に引き取られたラジオが目に留まる。
10年近く前から、こうして置いてあったように思うのだが、ほとんど気にしたことがなか
ったのは、この部屋が父の領域であったからにほかならない。いつか、修理するつもりだ
ったのだろうか。電源ケーブルがとけかかっている。真空管に経年劣化があるのかどうか
わからないのだけれど、配線系統のチェックとケーブルの交換ができれば、動くような気
がする。しかし、ラジオを聞くのにいったいどれくらい電力を食うのか、考えると恐ろし
い。それでも、これで放送を聞きたいと思うのは、単なるノスタルジックではなくて、男
という人種は、原始以来、エンジニアであり、メカニックだからだ。祖父も、父も、わた
しも、その血脈を受け継いでいるのは確かなようだ。

阪急桂駅。f3.5,1/200s、ISO64。
それがどうしたと言われると困るのだが、何か連なっていたり、並んでいる無機物が好き
みたいである。そういうものが視界に入ると、無意識にカメラを向けていることがある。
理由を考えたことはない。
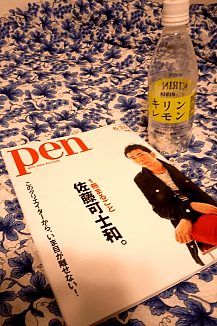
Pen、6/15号、特集『1冊まるごと佐藤可士和。』、阪急コミニュケーションズ刊。500円。
ホンダステップワゴン、スマップのキャンペーン(赤・青・黄の色の組み合わせ)、
キリン極生、最近ではFOMA N702iD。佐藤可士和の名前は知らなくても、彼が生み出した
ものは、誰しも見たことがあると思う。工業デザイナーでもなく、グラフィックデザイナー
でもない。アートディレクターである。最近、わたしは風呂あがりにキリンレモンをよく飲
むのであるが、それは氏が、そのリニューアルをやったと聞いて、実物を見ていっぺんで気
にいってしまったからだ。案外ミーハーな理由ですな。過去の作品のほか、現在進行形の作
品が多数掲載。特に明治学院大学のブランディングは格別。やっぱりタイポグラフィーって
良いなぁ。
ところで佐藤可士和は(というか写真に写っているときか)、目がこわい。だいたいどの
雑誌の特集でも同じ目つきでこちらを睨んでいるように見える。が、この特集のなかで例外
的に笑っている写真があって、少々驚いた。といっても半笑いなんだけど。
家電製品であるとか、大衆薬など、氏のイメージとは違う、日常の手垢がついた分野のディ
レクションを一度やってみてほしいものだ。どんなものができるのか見てみたい。
- 2006/6/2(金)
BK練習、18:40-21:00。
BK宴会、21:30-24:30。
知っている人が多いかもしれないが、調べ物をするときにとても便利なものがある。
ネット上に構築されたフリーの百科事典ウィキペディアである。(http://ja.wikipedia.org/wiki/)
執筆は誰でも自由。ただし、ルールと、ガイドにしたがうことが条件である。特定
の専門家が集まって書いた出版社の百科事典と遜色のない、秀逸な記事が数多く存
在し、信頼性はじゅうぶんあると感じる。
闇雲にネット全体に検索をかけるよりも、ずっと確実に知りたいことがわかるので、
わりとよく使っている。が、注意しないといけないことがひとつある。抜けられな
くなるのだ。キーワードの連鎖から。かつてのCD-ROMの百科事典と同じで、
説明文中に関連するキーワードがハイパーリンクとして埋め込まれているため、読
み終わると、すぐにその記事が読みたくなってしまう。そうすると、また次の記事、
その次と、最初の調べ物だけで終わらなくなってしまうのだ。
今日も、会社の昼休みに突然思いついて、「騎士団」→「テンプル騎士団」→「聖
ヨハネ騎士団」→「マルタ騎士団」...と、休みをめいっぱい使って、記事を読みあ
さってしまった。知ってましたか?マルタ騎士団っていうのは、現代に、まだ存在
する団体なのですよ。
ネット上にあるだけに、アニメ・吹き替え好きの執筆者が多いのか、日本の声優の
ほとんどを記事として網羅しているという特徴がある。そのことを指して記事に偏
りがあるとする向きもあるが、まぁともかく、いったん声優のページを開くと泥沼
にはまってしまう。つまり、その声優の過去の出演作品、吹き替えがリストになっ
ているため、まずそのリンクに飛ぶ。すると、出演者のリストがあって、そこから
別の声優に飛ぶ。また戻るか、その声優さんから、別の作品に飛ぶ...。ときには、
声優同士の交友関係、血縁関係も書かれているため、飛び先には限りがないのだ。
ひとの経歴を読むというのは面白い。普通の百科事典には絶対に載らないような、
現代に生きる、同時代のひとたちのことがわかるというのは、この事典ならでは。
まぁ、これは声優に限りませんが、わたしの趣味の範疇ということで。記事のなか
では、どういった役柄が多いのかということで、あああの人だなとわかるものも
あるが、やはり声の特徴が書かれていると、名前と声がすぐに結びつく。
声の特徴は、書く人によっていろいろな工夫がされていて、ときには単に渋い系
とか手抜きのものもあるが、「理知的な悪役声」「アメリカ人よりアメリカン」
というだけで「ああ、納得」というものもあり、読んでいて楽しい部分である。
(とりみき?が書いた吹き替え声優事典の「声の描写」には残念ながらおよぶべ
くもない。声という伝えにくい特徴をあれほど、写実した例はほかにみあたらず、
ほぼ99%の声優の声を想像、頭のなかで一致させることができるほど。)
で、こうやって書いている間にも、検索をはじめたらやめられなって、なんども
中断してしまった。もう一時間くらい、書いているような気がする。
ウィキペディアはお勧めですが、中毒症状にはご注意ください。
おやすみなさい。
- 2006/6/1(木)
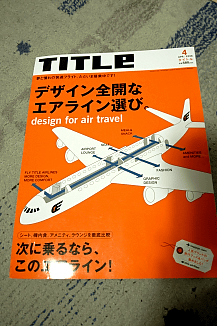
雑誌「タイトル」4月号、特集デザイン全開なエアライン選び。文藝春秋刊。580円。
こんなスタイリッシュな雑誌をなぜ文藝春秋が...。編集しているのはデザイン事務所
アトモスフィアというところなのだけど。
さて、雑誌の8割以上がエアラインに関しての特集。ひらくと出てくる出てくる、公共
交通機関のなかで、これほど多岐にわたるデザイン領域を有して、かつそのどこにも
デザイン行き届いている例はほかにないということ実感させられる。機体や、乗務員
の制服は言うに及ばす、シート、チケット、空港、ラウンジ、機内食、広告、CI...。
しかし、その中でも最たるものは空港建築ではないのかなと、わたしは思う。建築好き
というひいき目を差し引いても、その場所が持つ高揚感や、非日常性の高さは、駅や、
港を大きく引き離していて、デザインのふるいがいがわるわけだ。そもそも、空港建築
というもの自体、歴史的建造物の多い駅に対して、いきなり現代建築として始まったわ
けで、その分発想の自由度が高いはずと思う。立地上、周囲の景観への影響も少ないし。
空港には旅行の際のわずかな時間しか滞在しない、というのが一般的なのかもしれない
が、これほど見学しがいがあるものはない。だから飛行機に乗らなくても、おとずれた
っていいと思う。事実、国内の空港、羽田や、中部国際空港、神戸空港などの新規、
リニューアル空港では、旅行しない人をひきつけるかのような店舗が増えている。空港
に買い物にいったり、食事をしにいくのだ。かくいうわたしは、羽田第二ターミナルが
完成したとき、同時にリニューアルになった「羽田エクセルホテル東急」に泊まりに行
った。行きは京急、帰りは東京モノレールというふうに鉄道に乗るという目的もセット
にして。「ああ、あしたは朝一番に出発しないといけないけれど、ぎりぎりまで寝てて
も安心だよ~」という擬似旅行気分をたっぷり味わったものだ。すべての飛行機が飛び
立ったあとの人気のなくなった空港も新鮮だった。
ところで、記事によると、航空会社にもよるけれど『犬猫連れの搭乗が可能だって知っ
てました?』。わたし、知りませんでした。そこには、かばんからちょこんと顔を出し
て窓の外を眺めている黒猫の姿が写っていて、ああほんとなんだ!すごいなぁとみょう
に感心してしまった。(じつは、空港建築の写真よりも、この写真の方にひかれて買っ
てしまった。)
うちの実家の犬はどうだろう、わたしに似て乗り物酔いする性質だから、一緒に旅行す
るのは無理かなぁ。
- 2006/5/31(水)

黒い画用紙につめの先でつけたような、細くて小さな輪郭から、わずかに漏れ出でる淡く、
ぼうとした明かり。そういう月がわたしは好きなのだ。

こんな月夜は、ふらふらと歩いてみたくなりませんか?
お知らせ:
コミックマーケット70、当選しました。二日目(土)西れ-04b「山Dの電波暗室」です。
きのうの晩、コミケット準備会の当選検索でわかっていたのだけれど、やっぱり封筒が届く
まではどことなく不安であった。これで、腹は決まった。『近代建築探訪vol.3』の製作を
開始する!Macも買う。しかし、PhotoshopのIntel版対応は来年。うーん、悩みどころ。
今年はキンコーズから脱却したいのだけれどなー。
- 2006/5/30(火)
はじめに、訂正。土曜日の暗室で「龍池」と「柳池」、どちらも「りゅうち」と書いたの
だが、ただしくは前者は「たついけ」であった(M川さん、ご指摘ありがとうございます)。
両者はまったく別の「学区」。思い込みの疑問のままではなく、きちんと調べるべきでした。
ごめんなさい。
きのう、亡くなった父の夢をみた。じつは昨日だけではなく、この何ヶ月かに結構な回数
を見ている。夢のなかで、父に語りかけられるということはなくて、ふつうに父がいる日
常であったり、出来事の夢である。これは...ちょっと気になって、母に電話したところ、
母もそうなのだと言う。それで先週、妹を連れて墓参りにいったそうだ。「あんたもさそ
たらよかったな。気にしてたんや」。そう、わたしは正月は腰痛で、お彼岸はNCのさく
らコンサートやらなにやらで、ずいぶんと墓に参っていないのだった。きっと、そういう
ことなのだろう。日曜日に思い立って、ゆかりのある上賀茂神社に行ったのも偶然ではな
いのかもしれない。
きっと、父が聞いたら言下に否定するに違いない。父はどちらかというと、この手の話は
頑として信じないたちであったからだ。対して、母や母方の家系というのは、むしろそう
いうことにするどいか、するどすぎるきらいがあって、子どものころはどちらを信じたら
いいのやら迷ったものだ。いまも、こういうことがあるくらいだから、母方の血が出てい
るのかな?とも思うし、深層心理にある不義理の心が夢に現れたともとれる。ニュートラ
ルのあたりをふらふらしているわけだ。
ともかく、どちらにしろ、最近実家にも帰っていないので、親不孝であることに変わりは
ないだろう。
だから、この週末は墓参りに行くと決めた。
- 2006/5/29(月)
最近、「長い長い散歩」「チーズスィートホーム」「ぷーねこ」といった猫を物語の主役
に据えた漫画が相次いで刊行されているが、ある意味ではこの漫画はその分野の草分け?
になるのかもしれない。でも、万人にはお勧めできないかも。なぜなら、
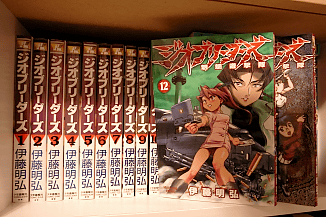
今日買ってきた本:
「ジオブリーダーズ 魍魎遊撃隊」第12巻、伊藤明弘著、少年画報社刊。514円。
猫といっても、『動く磁気情報である"化け猫"』という存在だから。第1巻が刊行された
のが平成7年であるから、かれこれ11年の連載になる。月刊誌の連載であるから、だいたい
単行本が出るのに1年弱かかる。11巻が刊行されたのはちょうど1年前。なもんで、12巻
を読み始めてすぐに、内容についていけないことを察知し、11巻から読み直すことにはめ
になってしまった。1年前に読んだ漫画のストーリーを覚えている人がいたら手を挙げて
ほしいものだ。尊敬します。
11巻を読むのに35分。12巻読了に1時間。ふぅ~。読み終えたあとで、こんなに頭がぱん
ぱんになって、酸素不足でランナーズハイみたいになる漫画は、ほかにF.S.S.くらいな
ものです。似ても似つかない両者だけれども、F.S.S.が読めるひとはジオブリーダーズ
も読めると思うな。漫画として描かれているのは、ほんの一部に過ぎず、その世界の大
半は見えないところにある。ふつうの漫画だって設定というものがあって、描かれてい
るのは一部なのだと思うけれど、でも読んでいる分には、そういうふうに思えない。見
えている世界、目の前にある世界が、世界のすべてみたいに思えてしまう。でも、この
ふたつの漫画は(ああ、あと攻撃殻機動隊1・2もそうだなぁ)、「見えていない世
界の大きさ」に圧倒されてしまう。矛盾した言い方だが、全体を知らなくても、その縁
を見るだけでそれがとてつもなく大きなものだ、というくらいは感じることができるよ
うなものだ。
その圧倒を面白い!って思えたら、この漫画は読めます。たぶん。
ものごとをすべて、つまびらかにして、理解しないと気がすまなくて、理解しよう、
理解しようとすると、この漫画は読めない。たぶん。
ああ、あと「ねじまき鳥」を読んで面白いなぁ、って思ったひとなら大丈夫かな。
そういえば、....「猫村さん」って漫画もあったなぁ。
- 2006/5/28(日)
烏丸近辺再発見の旅、その1
 
本家尾張屋。せいろ大盛(890円)、もちろんそば湯もあります。
車屋町通二条下ルにある、老舗の蕎麦屋さん。以前紹介した晦日庵河道屋と並んで有名。
いっけん、料亭のようで敷居が高そうであるが、別にそんなことはなし。普通に入って
構わない。あ、車屋町通っていうのは、烏丸通の一筋東の通り。中に入ると、外見とは
異なって、一階、二階ともに椅子席であった。ただ、一階右手に三畳ほどの小座敷があ
って、ここは靴を脱いであがる。低めの長机が二席あり、雰囲気を味わいたいなら、ここ
がいいと思う。座席バリエーションや、店の中の雰囲気なら、晦日庵の方が好みかなぁ。
そばは、淡白な味わい。しかし、せいろだけってのは通すぎたかも。天ぷら頼めばよか
ったな。
 
(左)真鍮の輝き。(右)ELITE社のCUSSI,INOX。ステンレス製で48gと軽いです。
昨晩、ツーリング用にベルとボトルケージをつけたのだけれど、今日は雨だろうなと
あきらめていた。しかし、くもり空ではあるけれど、とこどころ明るいという天気な
ので、遠出はせずともモールトンで出かけることに。少しでも乗ってサドルをやわら
かくしないとね。
 
上賀茂神社境内、(左)御手洗川(右)ならの小川。
賀茂川を北上して、向かったのは上賀茂神社。山Dのルーツたる神社であり、毎年初
詣に訪れる場所なのだが、今年の正月は腰を痛めていたせいで、これが実に約半年遅
れの初詣となる。社殿に入るとき、別雷(わけいかづち)の神様ごめんなさいと謝っ
ておく。
きょうは境内で、かみがも手作り市というフリーマーケットのような催しが開催され
ていた。上賀茂神社でこういうイベントが行われているのを初めてみたけれど、毎月
第四日曜日開催としてあったから、いつのまにか定着していた様子。なかには、簡易
ベッドをもちこんでの足つぼマッサージや、整体などの店もあり、ややびっくり。
豆知識コーナー。百人一首に「かぜそよぐ ならの小川の ゆうぐれは みそぎぞ夏
のしるしなりける」という歌がある。ここに登場する「ならの小川」というのは、子
どものころ、ずっと奈良にあるとおもっていたのだけれど、実は上賀茂神社の境内を
流れている川のことなのだ。わたし、かなり大人になってから知りました。みそぎと
いうのは、6月30日に行われる夏越祓(なごしのはらえ)の儀式ことを指している
らしい。
歌によまれたとおり、ここはかぜの通り道。大変涼しいのですよ。

明神川にて。
ならの小川が、神社の外に出ると、明神川と名前をかえて町のなかに流れていく。
このあたりは、神官達が居住していた地域。水辺を走るのは気持ちがいい。
本日の走行距離、20.9km。軽めのつもりが以外と走ってました。
超不定期連載「わたしの好きな活字」
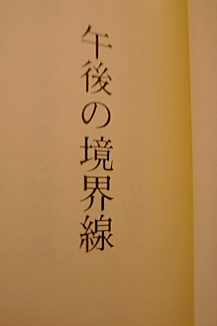
「早稲田古本屋日録」の各エッセイの表題に使われている活字。明朝の一種だと思う
のだけれど、切り絵文字というか、陰影のはっきりしたところが好き。どことなく、
「和」を感じさせる。正式な書体名が知りたい。
- 2006/5/27(土)
NC練習、18:00~21:00。
参加人数18人。トップ7人、セカンド7人、ベース4人。
つまり、バリトン0人。これは「合唱崩壊」の危機ですよ。
昼食を、M川さんご推薦の洋食屋「クルート」(烏丸二条西入ル)で食べる。
ミックスランチ750円。これは~、スタンドにつづく定番として、毎週土曜日には食べに来ないと
いけなくなった。洋食とは、かくありなんというものを思い出させてくれる。おいしい!店内に
ヨゼフ・チャペック(カレル・チャペックの兄)デザインのポスターや、昔の調味料の雑誌広告
といった「紙モノ」が飾られているのも、わたし的にはポイント高し。
その帰り道、烏丸通りの一本西の縦の通りである両替町通りを下る。と、そこにあらわれたのが、
小学校と思われる西洋建築だった。

 
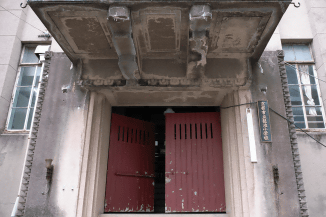
ここは旧京都市立龍池小学校。どうやらかなり前から廃校になっていた様子。烏丸御池を上がる
と左手にグラウンドが見えるので、学校があることは知っていたのだが、それが歴史的建造物で
あるということはまったくしらなかった。グラウンド側の壁が高いため、建物がうかがいしれな
かったというのが理由。現在、この敷地は京都精華大学の所有となっており、国際漫画ミュージ
アムという施設に生まれ変わるらしい。建築事態の行く末が気になったのだが、5月1日に着工
とされているのにもかかわらず、写真のように外観はそのままであり、補修して活用ということ
になるのではないだろうか。ところで、烏丸通を挟んで東にしばらく行くと、御池通り沿いに
「京都市立柳池中学校」があるのだが、同じ「りゅうち」でありながら、漢字表記が異なってい
るのが謎である。(5/30訂正、「龍池」は、「たついけ」と読むそうです。すいません。)
京都のことを知っているつもりでも、じつはこんな近くにこんな場所があることを今日の今日ま
でしらなかったことに、若干ショックを受けた。知っているつもり、というのは知らないのと同
じであるなぁと反省し、烏丸界隈についてはもっと詳細に自分のなかでマッピングをしなければ
と、思い立った。
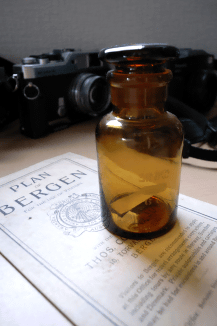
茶色の小瓶。350円。
クルートの近くの雑貨屋、「Monterosa」で購入。この店も今日はじめて発見した。ランタンや、
試験管、青ガラスの瓶など、ガラス製品の扱いが多い。なかでも気に入ったのが、この茶色の瓶。
クラフト・エヴィング商会の本にでてきそうな薬瓶である。何かを入れておくためというより、
その存在自体の魅力にやられて買うことに。その普遍的な形は、デザインされたというよりも、
はじめからその形として存在して、ある日そこに見出されたというような感じがする。淘汰され
ないものというのは、すべからくそうである気がする。
- 2006/5/26(金)
BK練習、18:30~21:00。
BK宴会、21:30~23:45。
「ハチクロとか読んでんのに、なんで女の子の気持ちがわからへんの?」と、なかなか
するどい質問をされてしまう。別に修羅場にいあわせたわけではなくて、飲み会の話題
としてふられた話だったのだけれど、わたしはそーゆーふうに見られているのだとする
とちょと由々しき問題である。しかし、どういうふうに反省したり、行動にうつせばい
いのか、困る。少なくとも、ハチクロを例に出されると。
ハチクロにはわたしとおなじ苗字の登場人物がいる。女性なんですが。で、その女性を
仮に山Dとすると、山Dの作中の状況とか、モノローグの思いというのが、じぶんの状
況と重ね合うところが少なからずあって、そのことは実は男性だからとか女性だからと
関係のないところであったりするのだ。基本的に、ハチクロに登場する人たちの気持ち、
思いというのは、ある立場にあるひとには、誰にでも共通にあることで、その人物が男
だから男性特有の気持ち、女性だから女性特有の気持ちというものでもないのですよ。
とまぁ、いいわけしておきます。
ごめんなさいねー、BK以外の読者の方。ちなみに、ハチクロの山Dみたいに、商店街
の二代目異性にもてまくり、というところだけは全然違うので。
*****
きのう、ゲームを買ってきた。主人公の名前を好きな名前に変えられるタイプだ。RPG
やアドベンチャーゲームに多いのだけれど、こういう場合、皆さんはどういう名前をつけ
るだろうか。こういう名前と常に同じ名前に決めているひと、ぶなんに自分の名前を使う
ケースいろいろあるだろう。わたしの場合、山Dの山をとって、山ちゃんであるとか、昔は
Glee山田という名前をよくつけていた。姓名の両方をつけられる場合は、山ちゃん山ちゃん
とする。こうすると、作中の人物に声を掛けられるとき面白い。「山ちゃん」は呼び捨てケ
ース、「山ちゃんさん」は丁寧よびケースである。ただし「山ちゃん」が苗字呼び捨てケース
か、名前呼び捨てケースなのかは判断できないが、「山ちゃん」と呼ばれるのはわりと気にい
っているのであまり気にしないのだった。本名で入力していて、いきなり下の名前で呼ばれ
たらびっくりするので、本名を入力したことはほとんどない。しかし、ゲームの例だと苗字
か名前のどちらかのバリエーションしかないのだが、現実世界、特に合唱団では敬称とかな
しに、フルネームで呼ばれることが多いのはいまもって謎である。イヤではなく、とても不
思議な響きがするものだ、といつも感じているのだった。
で、今回つけたのはいつもとちょっと違う。その名も「山D十兵衛」。ゲームを始める直前
に「柳生十兵衛、七番勝負」という時代劇を見ていたもので。このドラマはぜひ再放送があ
ったら見ていただきたい。殺陣がはんぱじゃなくすごい。鬼気迫るものがある。見とれてし
まい、息を呑む。
というわけでゲーム中では「十兵衛さん」とか、「十兵衛ちゃん」とか呼ばれたりする予定。
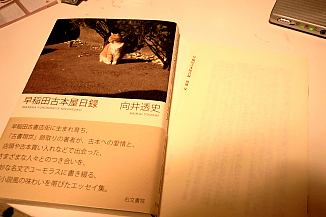
「早稲田古本屋日録」、向井透史著、右京文院刊。1500円。
早稲田古書街の「古書現世」の跡取りが書いたエッセイ。自分の店の通販用目録に連載して
いたものが半分、ブログの内容を元に書き下ろしたものが半分。とてもきっちりとして、
媚のない、飾り気はないけれど、淡白ではない。芯が通っているように感じる。その文章の
視点は個であり、孤であるような気がする。古書店の帳場に座っている気分がそのまま読者
に伝わってくる。たくさんのお客さんと交流するのだけれど、仕事場にいるのは独り。独り
で考え、独りで決める。寄り合いで一緒に仕事をしていても、その姿勢は保たれつづける。
そういうところが、共感できる。でも、真実独りなわけじゃない。この本には栞がついてい
る。写真の右側にうつっているのがそうだ。「別冊栞」という聞きなれないもの。著者と交流
のある古書店の店主や、文筆業、店のファンといったひとたち6人が書いた、推薦状みたい
なもの。それらを読んでいると著者への共感が一層深いものになる。そういうひとが周りに
いる、そしてこういうエッセイが書けるって、素晴らしいことだ。
早稲田古書店街にはちゃんと行ったことがない。表紙にうつっている猫はここにいるのだろ
うか。また、ひとつ行ってみたいところが増えた。

週末はあまり天気がよくなさそうである。モールトンが寂しげに見える。うしろに誰かを乗
せて走るような自転車ではないけれど、誰かと一緒に走りたくなる自転車ではある。
なんだか、つらつらと書いてしまった。
おやすみなさい。
- 2006/5/25(木)
さきに書いたとおり、わたしのモールトンの色はUltra Marineという青だ。この色の名前は
店のひとが勝手に命名したわけではなく、ちゃんとグラフィック関係の共通の色の名前とし
て決まっているものだ。ウェブで検索した色の名前のページにはほかにもさまざまな名称が
並んでいるのだけれど、思いついてひとつの色の名前があるか調べてみた。
・・・瑪瑙色だ。
思ったとおり、そういう名前はなかった。なぜなら、その色の名前はおそらく単色ではない
からだ。瑪瑙と聞いて思い浮かべるのは、緑と白の縞模様。だから、その色が差すものも、
おそらく単純な色じゃなくて、混ざり合い、時々によって変化するものに違いない。
瑪瑙色が差すものは、海だ。英国、コーンウォール、セントアイヴス。
行ったことはない。しかし、いつか行ってみたいとかなり昔から思っていた。
ときどき、ふと思い出しては、想像するのだけれど、うまく思い浮かべられない。
その名前が、登場するのは浦沢直樹の漫画「マスターキートン」第7巻、『瑪瑙色の時間』
の回である。モールトンは、英国の自転車。そして、Ultra Marineという言葉から、急に思
いだした。キートン先生は少年の頃、両親の離婚にともなって、祖母の住むコーンウォール
に母と一緒に移り住んできた。そのときに知り合ったバスの運転手クリスに誘われた秘密の
場所から見た海の色。それが「瑪瑙色」なのだ。カラーではなくモノクロだったので、その
回を読んだ当時も、そして今も、自分がいままで見た海の色から想像するしかない。架空の
話だから、本当は瑪瑙色なんてものじゃないのかもしれない。
でも行って、確かめてみたい。できることなら、モールトンを携えて(モールトンは折り畳
みではないが、トラスフレームの中央から2つに分割することができる)。マスターキートン
の世界とは、なんだかそういう気持ちにさせるものがある。
いつか、叶えられるかなぁ。
- 2006/5/24(水)
スタンドのメニューは、飲み屋でよくあるように黒いカマボコ板に白い墨で書かれたものが、
店の両側の壁にそってずらっと、かけてある。だから単品を注文するときは、うーんと言いな
がら店内をぐるりと見まわすことになる。今日、座った席のまえを見ると「くらげのうた」と
書かれた札が目についた。なんや、合唱曲にありそうやなぁなどと思って、よく見るとそれは
「くらげのうに」。「に」の縦棒に横線が見えると「た」になる。さいきん、目が疲れている
よーだ。ところで、もともとのメニューの「くらげのうに」ってなんなんだろう。「かにのみ
そ」とか、そういう類のものか。くらげもそうだけど、うにはあまり美味しいとか、食べたい
とか思わない舌を持っているので、頼んでみよう!とか思ったりはしなかった。たぶん、酒の
肴にちょうどいい(推測)ものなんだろうと結論づけた。
帰宅後、「くらげのうた」ってあるかな?と思って検索してみたら、14件ヒット。よくよーく
見ると、「男声合唱とピアノのための感傷的な二つの奏鳴曲」の第一曲目が「くらげのうた」
だったことに気づく。そうだ、わたしは少なくとも男声で2回、混声で1回、この曲を聞いた
ことがある!”合唱曲にありそうやなぁ”どころじゃない。まったくもう。あまり、ポピュラー
な日本の合唱曲というものを聞いたり、歌いなれていないので、頭のなかで合唱の記憶野に
分類されていなかったものらしい。合唱という栞の断片だけがインデックスとして残っていたの
だと思う(いいわけ)。
で、もう一方の「くらげのうに」は2件しかヒットせず。合唱曲よりもマイナーな存在なのか。
ひっかかったのはいずれも「くらげのうに和え」だった。なるほど、和えてあるわけか。納得。
- 2006/5/23(火)
この時期って、例年こんなにすごしやすかったっけ?と思うほど、京都はいますごしやすい
気候になっている。日中はともかく、夕方にもなると非常に涼しい風が吹いているからだ。
雨が降っても、じとーっとするほどの湿気にはならず、わりとすぐにからっとした感じに戻
るような気がする。梅雨の時期もこうだったらいいのに。
帰宅時、どうも時折、左足の裏にチクリ、チクリと刺すような痛みがある。何か靴に入って
るのかと思って、何度もひっくり返すのだけれど何も出ず。でも歩きだすと、「何か」を踏
んでいるような感覚がある。で、ときどきチクッとくる。結構痛い。いつくるかわからない
ので歩くのが億劫になる。いったいなんなんだ。
家に着いて、靴下を脱いでみても何も発見できない。直後、素足になるとまた痛みが走る。
ということは、なにかが刺さった痛みではなくて、内側から来るものなのか。それにしては
激しすぎないか。やっぱり磨り減った靴のせいか?と考える。
で、念のため、足の裏を見たがなにもついてない...?ん、痛みがあったかしょがなにやら
黒くなっている。よく見ると、なにか刺さっていた。ピンセットでつまみあげたそれは、
1.5mmほどの銅線だった。こんな小さなものでも、刺さるとなると、歩けないほどの痛みを
与えてくれるのだからおそろしい。それにしもてなんで、こんなものが。
思い当たらないでもなかった。昨日、砲弾ライトの中身を修理していたのだ。結構雑に配線
していたのと、詰め物などしていなかったので、走行中になかで回路が暴れて、配線が切れ
たのだ。修理は半田が足りなかったので、うまくいかず、持ち越しになったのだけれど、
たぶんそのときに使った銅線の切れ端だ。新聞紙を引かずに床でやっていたからなぁ。
教訓、工作をやるときは机のうえで、やりましょう。
みなさんも注意。って、工作なんかしないですか。
- 2006/5/22(月)
えー、あー、かなり足腰に来ております。階段の下りがツライデス。
二日連続はよくなかった。うれしさのあまりつい。反省。
実は、長距離走行以外にも原因はある。それがコレ↓。

革サドル(BROOKS社製、チームプロ)。
実物を見るまで、何か土台になる部分に革が貼り付けてあるのかな?なんて思っていたので
あるが(初心者ゆえの無知と笑ってください)、本当に革だけなのだ。一枚の革を折り曲げ
て二本のレールに取り付けてあるだけ。これが固いのだ、ほんとに。大の大人が座っても、
へこみもしない。板のうえにすわってるみたいに固い。慣れると快適そのもののクッション
性を発揮するらしいのだけれど、だいたい1~3ヶ月はかかるという代物。
メンテナンスにはサドルオイルというものが必要なのだが、しばらくは要らないだろうと思
って、買っていなかった。が、調べてみると新品をやわらかくするのにも使えるらしい。ど
うせ必要になるものだし、明日仕事が早く終わったら買いに行こうと思う。
革サドルの自転車をほとんどみかけない理由がわかった気がする。時間をかけて馴染ませて
いくっていうこと自体が、実用じゃなくて趣味の領域なのだもの。モールトン、納車された
からといって、終わりじゃない。ここから「自分のもの」にしていくまで完成じゃないのだ
ということを実感したのでありました。
- 2006/5/21(日)

Alex Moulton APB-8 Ultra Marine, Made in England.
Powered by MokuTune(Moku2+4). Launched STARDATE 2006.05.21
自転車をもう一台買いました。というか、正確に言うと今日が納車の日だったのである。購入を
決めたのは4ヶ月前で、組み立てと調整にそれだけかかったということになる。自転車の名前は
アレックス・モールトン、型式をAPB-8という。モールトン(通称)がどういう自転車で、
どういう経緯を経て、購入にいたったのかについては、今後、おいおい紹介していくことにした
い。
さて、ここで読者の皆さんに謝らないといけないことがある。約3ヶ月前に、わたしはオーク
ションで砲弾型ライトを落札したが、そのときの「このライトに似合う自転車をさがさないと
いけないなぁ」と暗室に書いた。これはまったく韜晦もいいところで、真実はすでに購入が決
まっていたモールトンに似合うライトを探していたのである。ごめんなさい。どうして、皆さ
んをたばかったかと言うと、モールトンを買うということを、完成するまでだまっておきたか
ったという、ただそれだけなのだ。でも、ライトを落札したということは話のネタとして、書
いておきたかったので、一種布石のような形をとった。どうかお許しを。あとは、自転車を二
台所有するということを、理解してもらえるかどうか自信がなくて、友人・知人に「もう、そ
んな無駄遣いして~」と怒られる(?)のが怖かったのかもしれないな。
で、所有自転車の基本的な運用方針を次のように定めた。
・ルイガノ(現役就航中)→街乗り、トレーニング。
・モールトン→長距離ツーリング、輪行。
なお、昨日の北山行きで、ルイガノ号はだいぶ汚れがついたので、今日はメンテナンス。洗浄
と注油を行っている。泥汚れってのは、なかなかやっかいだ。
 
(左)砲弾型ライトはこんなふうに装着。(右)処女航海は哲学の道へ。
で、話戻ってライトのことだが、通常モールトンはこのタイプのライトを装着するようには
できていない。そのため、自転車屋さんと相談して、特注でライトステー(取り付け台座)
を作成、本体のフロントフォークにロウ付けすることになった。実現してくれた店長に感謝
である。このステーは、全国のモールトニア(モールトン乗り)にも少しは自慢していいと
思う。
西京極の自転車屋Moku2+4(お店の紹介は、モールトンの解説の時に)でモールトンを受け
取ったあと、いったん帰宅。昼食をとってから、白川通今出川へ。ここは、あの有名な
「哲学の道」の起点なのだ。ここから10分ほど歩けば、銀閣寺にいたるということもあ
って、なかなかひとが多い。ただ、哲学の道を歩くひとはそれほどでもなく、ゆったりと
走ることができた。終点の熊野若王子神社にたどり着くと、こんどは鹿ケ谷通りを北上し
てUターン、法然院へ向かった。きょうはとにかく暑くて、途中の木陰で休んだものの、
本格的に休憩するには、ひとがまばらなほうがいいと考えてのこと。
 
(左)法然院三門。午後4時閉山。(右)本堂にて。
法然院は、哲学の道よりも山側にあり、この坂を上るのは歩いてでもなかなかしんどい。
しかし、いったん入山すると、ひんやりとした空気に疲れがほぐされる。境内のほとんど
が木立のなかに存在するため、体感温度は2~3℃低く感じる。本堂の廊下に座って、
30分ほど読書。ケラの鳴き声と、ししおどしの音以外は聞こえない。まったくの無音では
ないのがかえって心地よかった。
本日の走行距離は約20kmであった。

室内に置いてみた。
玄関にはルイガノ号があるので、実際のところここに置いておくしかないのだ。ところで、
この塗装は、Ultra Marineというのだが、写真でもわかるとおり、日の光を浴びるとライ
トな青色で軽やかな感じがする。それに対して、屋内ではこの通り、Navyのように深みの
ある色合いに変化するのだ。うーん、この色の選択は正解だった。青~紺色が好きなので
ある。
きょうはここまで。
おやすみなさい。
- 2006/5/20(土)

四条寺町下ル「あいば」にて。Aランチ。
昼食の後、大阪へ行くか、京都の北山へ行くかを10分ほど考えた。大阪ならNMAO、
国立国際美術館が目的。全国でも珍しい、全室地下にある美術館で、1~2年前に開館し
たばかり。一度いってみたいと思っていた。主に建築見学が目的。北山なら狐坂に行こう
と。狐坂とは京都屈指の難所で、急勾配のヘアピンカーブが特徴の道路。北山(松ヶ崎)
と、京都国際会議場やプリンスホテルがある宝ヶ池・岩倉を結んでいる。その坂に4月、
急勾配のない自動車道路が開通した。以前、地下鉄が国際会議場まで開通するまでは、こ
の坂を市バスが運行していたのだが、冬場になると雪のため坂を上れないことがあるほど
で、乗用車でもかなりきつい坂だったのだ。で、旧道のほうは、自転車・人道路としてそ
のまま残されるという話を聞いた。急勾配ではあるが、木立のなかを抜けるワインディン
グロードはかなり気持ちがいい。
この前振りの文字数の違いからも、おわかりの通り、行き先は狐坂に決定。だってこんな
気持ちよく晴れていたらねぇ。地下に行くのはもったいない。
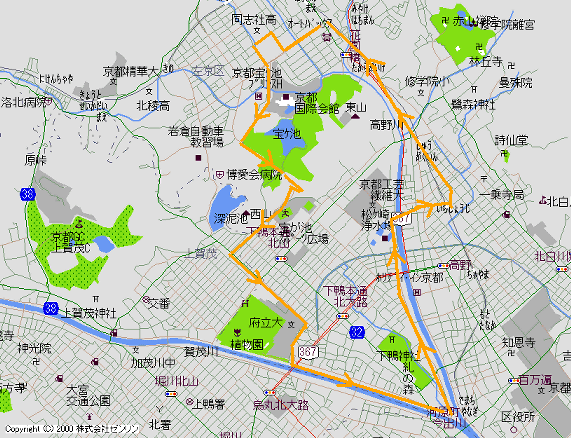
本日のコース。走行距離24.5km。走行時間1時間44分。
(地図上では出町柳~寺町のコースは含まれていない)
四条から御池まで北上し、そこから鴨川河川敷へ。そこから北上し、賀茂川と高野川の
合流地点である出町柳に到達(ふたつの川があわさって"鴨川"となります)。そこから
は高野川の左岸沿いに北上(地図では左上が北)。途中、京都工芸繊維大学近くの電器
店にて休憩。え、なんで電器店で休憩かというと、ここは8年前に一ヶ月半の間、販売
実習でお世話になったところなのだ。いまでもつきあいがある。販売実習とはいっても
営業活動をするのではなく、主な仕事はエアコンの取り付けや、家電販売後の設置とい
う「街の電器屋さん」の仕事そのもの。体の弱い山Dは7月1日、エアコンの取り付け
中にお客さんのお宅で、熱中症で倒れてしまったという苦い経験が。
いやはや、やっぱり現場に来ると良いことも悪いことも「お客さんの声」がびしばしと
飛んでくるのが実感できる。この声がどれだけメーカーに伝わっているのかは測りかね
るが、ものをつくってうる商売をやっている以上、ここから離れたらだめなんだなぁと
改めて思った次第。実習の話などを会長(社長の奥さん)と話していると、最近は実習
生は女性の方が良い、根性があるから、ということを聞いた。エアコンの取り付けが多
いので、女性はどうしても敬遠されがちということを昔は聞いたものだけれど、意外で
した。
一時間ほどの休憩の後、すぐ近くの恵文社一乗寺店へ。
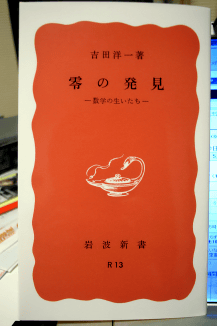
「零の発見-数学の生いたち-」、吉田洋一著、岩波新書。700円。
こういう本を「発掘」できるのも、恵文社ならではであると思う。この本はすごいのだ。
奥付にある2006年現在の刷数は、なんと98刷!はしがきにある日付が昭和14年。「改版
に際して」が昭和31年、「再改版に際して」が昭和53年の日付。67年も読み継がれてい
ることになる。
『この書物では数式をかかげることを極度に避けておいた。数式に対する一般人の恐怖
は病的ともいうべきものがある。数式に出会いさえすれば、それが何であるか見きわめ
もせずに、ただ敬遠することを考える。』(はしがきより)
じつに67年が経過した現在、大戦をはさんでも、その状況には今も変わりがないという
現実は、なんだかとても悲しい。日本は本当に科学立国、経済立国なんだろうかと思わ
ざるを得ない。文部省は、小学生の算数(と国語)の時間を増やすべきじゃないですか。
かつて審議官の奥さんが「二次方程式なんて、生活するのになんの役にも立たないのじ
ゃないの」と審議官に意見した、という話を聞いたことがある。だいぶ以前に暗室でも
書いたことだけれども、二次方程式を使わないではわれわれは一歩だって歩けないし、
生活できないのだ。そんな大事なことを教えずに済ませようっていうのは、ある意味で
は国家に対する反逆だといってもいいと思うのだけれど。祖国を滅ぼしかねない。
大事なのは、引用の後半。「何であるか見きわめもせずに」という人を増やさないこと。
そのためには、なかったことにするのではなくて、そのためにきちんと時間を費やすこ
とだ。この問題は数学だけにとどまらないはず。
滞在、約1時間。お、もう5時じゃないですか。でも、日はまだ高い。修学院を抜け、
さらに北上。宝ヶ池通りに入る。

母校付近から見える比叡山。緑がほんとに濃い。空もだんだん高くなってきた。
宝ヶ池通りを西へ進むとやがて、わたしの母校が見えてくる。きょうは高校総体がグランド
のあちこちで行われていたようだ。あたりを一周、新設された小学校の建物を発見した。
これはまた、社会情勢を顕著に反映しているというべきか。建物の周囲がぐるっと、塀と
金網で完全に囲まれて、あちこちに監視カメラが設置されているのがわかる。川沿いの道
側もきちんと金網でガード。敷地内を公道が通り、正門もなければ、塀らしい塀もなく、
川沿いの道からは犬の散歩に地元住民が訪れるという破天荒な高校とはえらい違いである。
さて、そこからは駅伝での折り返し地点となっている京都国際会議場の正門道路に進入し
て一路、狐坂を目指す。このあたりは非常に舗装がきれいに保たれているので快適この上
ない。長いトンネルを抜けるとすぐに道路は下降し始める。おっ、あれが新設道路か。
旧道の手前50m付近から右カーブとなり、かつて空中だったところに高架道路があらわれ
ている。かつての木立はなく、かなり見晴らしが良さそうだ。

で、こちらが旧道。奥にかつての難所を示す「急カーブ」の文字が。
あー、これはまた、すごいことに。自転車道はまだ整備されていなかったようで、旧道は
土砂だらけ。一応道路の端っこを走行することはできたのだが、泥水だらけで大変なこと
に。しかも道の途中からは、未整備の部分が進入禁止となっており、道でもなんでもない
ところに仮の脱出路が形成されている。これ、絶対下れても上れないぞ、という勾配。
下りおえると、宝ヶ池運動公園の横にでて、新道と併走する形になった。
というわけで、当初の目的であった狐坂サイクリングは中途半端なまま終了。これはまた
自転車道が開通するのを待たねばならんなぁ。
その後は、京都コンサートホールまで西進し、そこから南下。京都府立大学沿いに植物園
入り口へ抜けて、川にもどってきた。こちらは、賀茂川である。賀茂川右岸をそのまま南
下する。ここは舗装道路ではないので、ロードレーサーの場合は難があるだろう。左岸の
土手を走る自動車道路を走るのが良い。ただし、交通量が多いし、片側一車線。と、気が
つくといつの間にか、行き止まりにつっこんでいた。そう、出町柳の合流地点に着いてい
たのだった。中州ではたくさんの人がピクニックに興じていた。ああ、夕方だねぇ。

夕暮れの賀茂川(合流地点のすぐ手前)
今回のコースは、数少ない京都の自然を身近に感じながら走れるので、なかなかお勧め。
京都にはレンタサイクルも多いので、ぜひスポーツ車を借りて、チャレンジしてみてく
ださい。
余談:木津川66kmサイクリングのおかげか、今回はほとんど疲労を感じていない。この
調子で身体能力を鍛えるのだぁ。
- 2006/5/19(金)
BK練習、18:30~21:00。
あしたはNCの練習がない。珍しい。こういうときは少し夜更かしをして、映画でもみたくなる。
深夜に上映が終了して、それからちょっとラーメンでも食べる。そういうのがいいのだけれど、
よほどの話題作のロードショーでもない限り、深夜興行は通常はやっていない。採算がとれない
のは明白だからなぁ。
で、代わりに自宅でDVDでも見ることにする。こういうときに見るDVDは実は、だいたい決
まっている。徹底的にシリアスで、淡々とした描写のもの。こころをかき乱さないから。
「機動警察パトレイバー2」(監督:押井守)
「イノセンス」(監督:押井守)
「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」(監督:富野由悠季)
「ショーシャンクの空に」(主演:ティムロビンス、モーガンフリーマン、監督:フランクダラボン)
「スパイゲーム」(主演:ロバートレッドフォード、ブラッドピッド、監督:リドリースコット)
「スニーカーズ」(主演:ロバートレッドフォード、監督:フィルAロビンス)
「ピースメーカー」(主演:ジョージクルーニー、ニコールキッドマン、監督:ミミレダー)
(持っていれば「LAコンフィデンシャル」も候補に上がると思う)
だいたい以上をローテーションしている。これらの映画は午前中に見るものじゃない。またゴー
ルデンタイムに見るものでもない。断然深夜に見るに限る。できるだけ暗くて、そして静かな時
間。現実と夢の境界がなんとなくあいまいになるとき。そんなときにDIVEしたくなる、そう
いう世界を持っている気がする。なんとなくわかってもらえるだろうか。
では、おやすみなさい。
じゃない、何か見るんだった。
- 2006/5/18(木)
大丸の地下食品売り場は、たいていの百貨店がそうであるように、閉店一時間前、つまり大丸
の場合は午後7時になるとタイムサービスが始まる。200円引きとか、3割引きというよう
な値段で弁当が買えるので、阪急烏丸に着いた時刻によっては買いに行くことがある。
目当ての弁当は、惣菜屋の野菜中心弁当で670円のものが、たいがい600円以下で買える。
しかし、この弁当は人気があるのか7時半ごろにいくとすでに売り切れている確率が高いので
見つけられたらラッキーぐらいに考えないといけない。そこで次点にあがるのが、中華惣菜屋
のチャーハン+焼きそば弁当であるとか、チャーハン+から揚げなどの、割と高カロリー系の
弁当である。(なのであまり続けては食べない)
この中華惣菜屋がなかなか曲者なのだ。タイムサービス時は3割引きが基本であるらしいのだ
が、あるとき、わたしが弁当を差し出すと「いまから5割引にします」と店員がのたまった!
「え、なんで?、僕だけ特別か?」と一瞬つごうのいいことを考えたのであるが、店員は確か
「いまから」といった。時計を見ると午後7時55分ちょうど。閉店5分前だ。なるほど、
時間が進めば進むほど売り切る必要度が高まってくるわけだ。
で、翌日、半額になるのなら、おかずをもう一品追加したり、朝食のフランスパンが買えるな
と思い、またしても大丸に赴いた。先にパンを買い、野菜の惣菜を買ったりして時間の経過を
待つ。あと5分くらい。一度、前を通りめぼしい弁当が残っているのを確認。よし。マージン
をとって7時56分くらいにおもむろに列に並んで、弁当を差し出した。
ところがである。通常通り3割引にしかならなかったのである。え、どういうことですか?と
聞き返したかったが、売り手市場(当たり前だ)である以上ルールを決めるのは店である。
瞬間的に落胆したあと、あきらめて支払いをする。すると、わたしの2人後ろの客に対して
店員が歩みより「もっとお安くなります」とペンをとって、ふたになにか書いている!それ
がもともと値引き率が低いものだったのか、それとも前日のわたしのように、その客から5
割引になったのかは不明だが、納得のいかないもやもやした気分になったのは確かだ。まぁ
十分安い値段に買えてるから文句をいうべきではないのかも。
冷静になって考えると、その日、その時々によって売りのペースは違うはずなのだ。あるい
は曜日ごと、季節ごとに顕著な傾向というものがあるのかもしれない。だから、タイムサー
ビスの内容もいちいち変化して当然なのだろう。一律にやって損を出したら、意味がない。
5割引になったときは、よほど売れ残りが多かったと見るべきだろう。
こうなると、定点観測でもやって、最適なタイミングを割り出すなどしないと、つねに最低
価格で手に入れることは難しいということになる。チラシを分析して、1円でも安いところ
で買うという主婦の気持ちを金銭的な面からは、なかなか理解しがたいのであるが、戦略を
練り、戦術を駆使して店側と駆け引きをするという知略の面に関しては、この一件を持って
理解できるような気がした。
で、きょうしばらくぶりに弁当を買いにいったのだが、なんと今日は通常のタイムサービス
は2割と、低率であった。7時25分くらいだったので、もしやと思い、そこらへんをぐる
ぐるまわって35分くらいにいっても、2割引のままだった。45分まで待てば…!と一瞬
考えかけたが、早く帰宅してご飯を食べることの方が重要だろうと思いなおして、不本意な
がら2割引きで購入したのだった。
いつか、また5割引を勝ち取る日が来るさ...。
- 2006/5/17(水)
ポスター三枚とも落ちた...。やっぱり大きい紙は伸縮するからダメみたい。伸縮方向に二点
支持ではなく、水平方向に多点支持するしかなさそうだ。一点支持のポストカードはほとんど
落下していないのは伸縮に影響されていないからだろう。落ちたものは、アヴァンギャルド展
ポスター落下による風圧によるもの。夜中に頭のうえに落下してきたときは何事かと。
スタンド帰り、本屋に寄るも何も買わず。ちょっと、一度読んだ本を読みなおしてみたいと思
ったからだ。読了直後のねじまき鳥を除くと、ここ数ヶ月のうち読んだもののなかで、そうい
う本は三冊ある。いずれも小説ではない。
川上弘美の「此処彼処」、長嶋有の「いろんな気持ちが本当の気持ち」、そして深沢直人の
「デザインの輪郭」である。特に「デザインの輪郭」は読むだけで第六感が静かに刺激され
るように思うので、疲れているときなど逆に読み返したくなる。(三冊とも暗室で紹介済み)
ほんとは、広告批評の4月号と5月号を買うかどうか迷ったのである。4月号は新しい携帯
電話のデザインについて、佐藤可士和と深沢直人のインタビューが掲載されていて、5月号
はラジオCM大賞の発表が載っている。どちらも読みたい。しかし、月刊誌二冊はなかなか
読む時間がないので、積読になる可能性が高いのだな。しかし、逆にこのままほおっておく
と、つぎの号が出てしまうというジレンマがある。月刊誌や、週刊誌レベルでの情報量とい
うのはなかなか侮れない。すみからすみまで全て読みきったとしたら、どれくらいのものに
なるか。まぁ、その月々によって情報の「質量」というものには、かなりの増減があるわけ
で、それがわたしが毎月同じ雑誌を買うとは限らない理由になっているのだけれど。今回は
割と異例(きょうは買ってないけど)。
じつは本は買わなかったというのは正確ではなくて、「注文していた本」は一冊買ったのだ
けれど、まぁこれはカウントしないということで許してもらいたい。きょう買おうとした本
はなかったということで。屁理屈だけど。
なにごとも、我慢すれば、その分よろこびは増えるもの。
でしょでしょ?
- 2006/5/16(火)
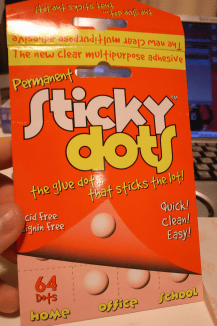
毒々しいデザインは、MADE IN UK。さすがパンクの国。297円、64個入り。
会社で使う用紙を探しに文房具屋に入ったら、いいものを見つけた。以前、ポスターを貼る
のにいいものはないか?という話をしたことがあるが、まさにうってつけ。粘着力のあるゲ
ル素材製、ドットタイプの接着剤である。これなら、凹凸のある壁紙にでも貼り付けられる!
というわけで、帰宅するなりさっそく試してみた。かなりの粘着で、剥がすときにポスター
の方を傷めそうなくらいであるが、こすってやると"だま"になるのでスライドさせるとうま
くはがすことができそうだ。
本格的に作業を開始。一時間後↓

配置を考えながらやったら、結構疲れました。
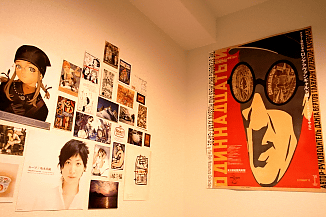
ロシアアヴァンギャルド展の巨大ポスターもばっちり。
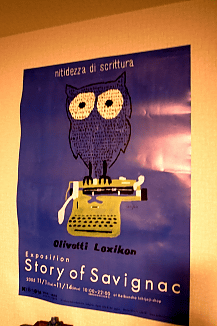 
南側面にペタ、玄関にもペタ。
わたしの悪いくせなのだけれど、一度何かをやりだすと止まらない。中途半端がいやなのだ
な、いい加減なわりに。もう体がくたくたになるまで、汗が出るまで、掃除でも食器洗いで
もやってしまう。そういうわけで、ある程度の形になるまで、貼りまくってしまった。しか
しこれは、形になるとなかなか楽しい作業。これからは一気にやらず、ちょろちょろと暇を
見つけてやっていこうと思う。
- 2006/5/15(月)
きょうの日経産業新聞に、国内眼鏡フレーム大手のシャルマンがフレームデザインの国際
コンペを実施したとの記事があった。メガネと聞いて、見逃すわけにはいかない。
「メガネはない方がいい-なければならない人のためにあるべきメガネ」というテーマで
募集したとのこと。このテーマについては、いろいろ意見のあるひとが、わたしの周りに
いそうではあるが、ファッションとしてのメガネが消費を牽引するなかで、装飾性のみを
追求していくと、メガネが持つ本来必要な機能を果たせなくなるのでは?という危惧が主
催者にあったのではないかと推測する。道具としてのデザインを見直すという視点はたし
かに必要だと思う。審査を務めたのが、工業デザイナーの深沢直人であるというところに
も、主催者の深謀がうかがえる。単純な道具であるゆえに、装飾性を排した、いや装飾性
があっても、このテーマに沿ったものをデザインするのは、相当難しかったに違いない。
グランプリは、ロシアの人、準グランプリは台湾の人。応募総数は771点だったという。
記事にはグランプリのメガネの写真が掲載されていたが、やはりシンプルな形状だった。
つるの部分が丸い箸のように、先に行くほど径が細くなっている様子。耳に負担がかから
ないようにというデザイン意図なのだろうか。ぜひかけてみたい。それから他のデザイン
も見てみたいのだが、どういうわけか、ネット上にはこの件に関するニュースリリースが
まったくないのだ。デザインのコンペを紹介するポータルサイトでは、一次審査完了の告
知はあるものの、今回の受賞の速報などはない。検索範囲を海外に広めれば見つかるのだ
ろうか。いまのところ、新聞が一番の速報みたいである。いまどき珍しい。
メガネのデザインについて、すこしだけ思うことがある。外観設計のことではなくて、
レンズをつけたときの設計についてだ。メガネを替えるとき、同じ度数のレンズをはめて
も、焦点距離や見え方の関係からか、しばらくは慣れないということがあると思う。わた
しの場合、かなりの頭痛が伴うので一度慣れるとなかなか替えたくなくなってしまう。去
年の夏に買った銀縁のメガネは、外観形状がほとんど同じにもかかわらず、未だにきちん
と一日かけられずにいる。これって、なんとかならないのだろうか。わたしのメガネは当
然伊達ではなく、「なければならない」のである。もし、今のメガネが壊れたら、銀縁を
かけないといけないが、これで仕事をする自信がない。どんな外観デザインであっても、
かけたときの眼とのフィット感が統一される、そんな共通フォーマットができないだろう
か。やっぱりオーダーメードでないと無理なのか?
もうひとつだけ、ちょっと未来的な希望になるのだけれど、メガネを選ぶとき、本人のみ
がその装着した様子を目にすることができない状況っていうのはなんとかならないものか。
つまり、フレームのボタンをピッピッと調整すると、レンズの度が自在に変化すればいい。
実現すれば、もっとメガネを選ぶ楽しみが増えると思うのだけれどな。どうだろう。
- 2006/5/14(日)
思い立って、サイクリングに出かける。目的地は一度行ってみたかった木津川の流れ橋。
往復走行距離約66km、往復走行時間約3時間50分(なお、出発は10時半、帰宅は16時半)。
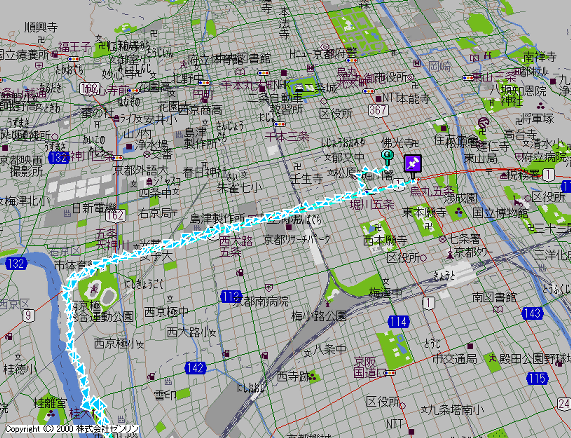
五条通を西進して、桂川へ。ここから桂川サイクリングロードに乗る。幅が3m程度の狭い道
であるが、自転車+歩行者専用道のため、自動車や信号を気にする必要がない。それと、
鉄道や道路の高架をくぐるとき以外は、まったくアップダウンがないのがよい。と、ここま
では事前に調べていた情報。実際はけっこう大きな問題点があった。
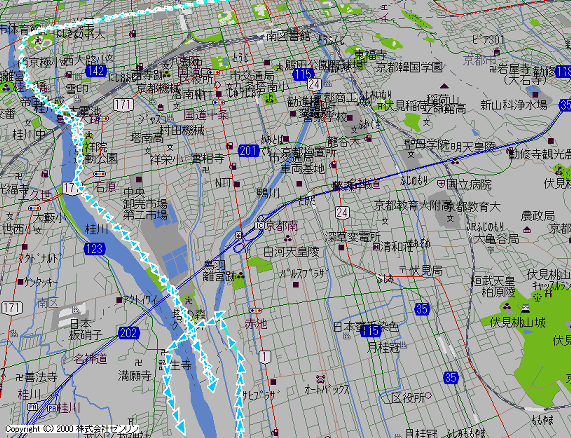
というのはルートが非常にわかりにくい箇所がいくつかあるのだ。わたしは到着までに3回
も迷ってしまった。一度目はまっすぐ走っていたら、いつのまにか舗装がなくなり、獣道の
ようなところになり、気づいたら、脱出不可能な中洲に到達していた。じつは、途中でスイ
ッチバックして、橋を一本わたらなくてはならなかったのだが、標識もルートマップもまっ
たくないのだ。ここははじめてきた人は絶対迷う。リピーターっぽい人の後を付いていくの
がいちばんよい。
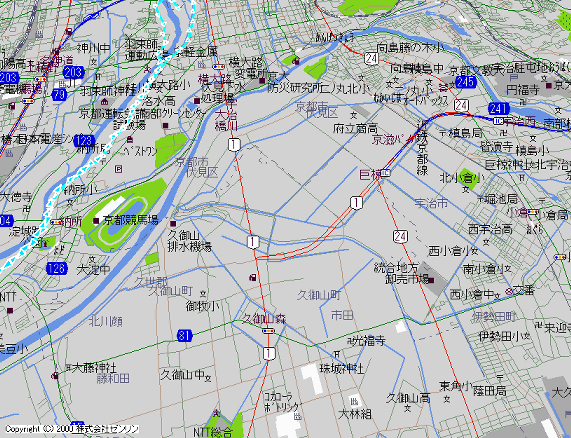
二度目は、いったん道路と交差するポイントがあり、やはりそこもまっすぐ進むと、舗装が
なくなっていた。というか、ちょうどそのとき、河川の水防訓練がおこなわれていて、途中
で通行止めになっていたのでやむをえず引き換えしたのだが、そこからさき、まったくどう
すすんでいいのかわからなくなってしまった。正解は、道路沿いに左折し、100mほど進
んでから、えらく細くなった鴨川沿いに進む。そこで再びサイクリングロードが姿をあらわす。
けっきょくその時点は正解がわからず、いったん桂川を離れて、住宅街を通っているうちに
自転車が多く渡る橋を発見したことで、ルートに戻れた。そこではじめて非常にアバウトな
地図を発見し、正解のルートも把握したのだった。(復路はそのルートを通った)
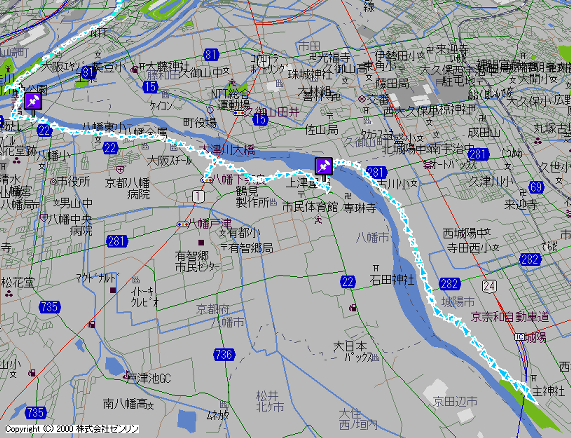
三度目は、桂川、宇治川、木津川の合流地点。ここで、急にぷっつりとサイクリングロード
が途絶えてしまった。川が複雑に入り組んでいるせいか、方向感覚も狂ってしまい、ここで
あきらめようかと思ったくらいだ。最終的には、「ながれ橋」という自動車用の標識をみつ
けて、そちらに向かったところ、唐突にサイクリングロードが復活したのだった。
途中で国道一号線との交差点の近くで、ファミレスを見つけ昼食。そこからは道なりに20分ほ
どで、無事流れ橋に到着。ああ、よかった。しかし、ここからまた帰るのかぁ...。

流れ橋。時代劇のロケによく使うらしいが、橋板を固定する鉄のケーブルは特撮処理でもし
ているのだろうか?それにしても、この高さの橋が流されるほど増水する状態だとするとあ
たり一面はすごいことになっているのだろうな。想像すると少々恐ろしい。
ただ帰るのは面白くないとおもって、流れ橋を渡ったあと、どこかの橋で対岸にもどるつも
りでしばらく走る。しかし、木津川の幅はどんどん広くなり、対岸の自転車道もみえなくな
る。いつまでたっても橋はない。やっとみつけたと思った京奈和自動車道も、土手からの進入
道がみつからず、結局引き返すことに。この行程がけっこうつらかった。あとで地図を見ると、
わたれる橋は10km近く先だったみたいだ。
帰りはルートを把握しているためわりと順調に進んだ。ただ、五条通まであと1kmくらいの
地点から、向かい風になり、そのせいかかなり足取りが遅くなる。巡行速度が25km/hだった
のが、12-13km/hまで落ちる。街中なら、これくらいのスピードが普通だけれど、なぜだか
こいでもこいでもちっとも進まなくなったような気がして、精神的にここが一番つらかった
と思う。ここでスタミナ切れにならなくてよかった。
五条についてからは、西京極にある顔見知りの自転車店で少し休憩させてもらい、復活。
あとは一路、烏丸五条までの帰途についた次第。
こんなに運動したのはひさしぶりだなぁ。
きょうは、よく眠れることでしょう。
おまけ:不定期掲載「わたしの好きな場所」

京阪電鉄、木津川橋梁。
きょうの行程ですぐ近くを通ったので撮影。京都方面から京都競馬場のあたりを過ぎて、
八幡市駅に入る直前に、すごいRのカーブがある。その出口に位置するのがこの赤いトラ
スト橋。列車の最後尾から見る、先頭車両が弧を描きながら鉄橋に突入していくさまが好
きなのである。みなさんも京阪電車に乗ったら是非、淀屋橋行き進行方向の左側の座席に
座って、車窓を眺めて欲しい。共感してくれるひと、いるだろうか。
- 2006/5/13(土)
 
「鉄道むすめ vol.2」。警視庁鉄道警察隊所属、門田さくら。
(撮影:阪急電鉄京都線にて)
CDを買いに行ったら、レジの前にこんなものが並んでいたので、ピクっと反応してしまいました。
『「鉄道むすめ」は、オリジナルキャラクター達が実際の鉄道事業者の現場で活躍する制服を着た
コレクションフィギュアです。』という説明が。ほかに、東武鉄道、鉄道整備、小田急電鉄、三陸
鉄道の"鉄道むすめ"がいるみたい。しかし、こんなニッチなフィギュアがあるなんて驚きである。
企画したひとはえらいなぁ。なぜニッチになってしまうかというと、鉄道というものに携わる女性
が少ないからにほかならないのだけれど。最近ようやく女性の運転士や、車掌を普通に見るように
なってきたので、フィギュアとして異質とはいえないと思う。東ヨーロッパやロシアなんかだと、
女性の鉄道職員はわりと普通なのだけれどね。でも、たいがいはおばさんで、このフィギュアみた
いに若い子がいないのはなぜだろう。やっぱり男性優位で、かつ人気のない職業なのか。日本では
今後、"鉄道むすめ"が隆盛することを望みたいなぁ。
ちなみに、国鉄時代は鉄道警察というのは、国鉄に所属する警察権を持った公安官だったそうで、
分割民営化後に各地方の都道府県警に引き継がれたとのこと。付属しているカードに書いてありま
した。芸が細かい。鉄道警察っていうと、「さすらい刑事旅情編」(宇津井健や、三浦洋一が出演)
を思い出すのだけれど、見てた人はいるだろうか。NC練習帰宅後に、TVをつけたら土曜ワイド
劇場でもちょうど鉄道捜査官のドラマをやっていて、じつは鉄道警察って意外と世間的な認知は高
いのではないのかと思うのであった。そんなわけないか。(沢口靖子主演。いつまでたっても若い。)

「冒険でしょでしょ?」、歌:平野綾。「ハレ晴レユカイ」、歌:平野綾、茅原実里、後藤邑子。
買いに行ったCD2枚。TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」、OP&EDテーマ曲。
それぞれ、「答えはいつも私の胸に...」、「明日また会うとき、笑いながらハミング」という
フレーズが気にいっている。主演声優が歌う主題歌らしい主題歌で、かつ歌がうまいと
いうのは久しぶり。聞いていてとても楽しい、嬉しい。良いデス!
NC練習、17:15~21:00。
「演奏会後の練習がいちばん大事」とは、われらがBOSS(NCの役職)のセリフ。しかし、きょう
集まったのは20人弱。ベースは4人。演奏会のオンステ、ベースは22人も居たのに!男声合唱団
は立ち止まったら終わり。サメみたいにつねに走ってなけりゃ続けられない。止まったまま死ぬか、
走りながら死ぬか。宿命みたいなもんだ。ほんとは死にたくないけどさ。
- 2006/5/12(金)

明日の昼食。
今シーズンはじめての冷やし中華を買う。初夏~夏にかけてのわたしの昼食の定番。これが店に
並び始めると夏だなぁと思う。しかし、なんですね。今年は春というものがほとんどなかったの
が残念でならない。桜が満開のときですら、肌寒い日と雨つづきで、はっきりとした春の日差し
をこの身に受けて、手をかざしながら「あぁ、眠たいなぁ」なんていいながら、芝生に寝転がる、
そんな気持ちのいい日が一日としてなかったものな。ちなみに身近に芝生なんぞないのであるけ
れど、ものの例え。京都には公園が少ないのだ。
BK練習の帰り、コンビニに寄ると、小林明子の「恋に落ちて」を外国人歌手がカバーしたもの
がかかっていた。もともと、2番の歌詞が英語なのでほとんど違和感がないし、あのメロディは
どんな言語で聞いても、せつない明るさが胸に響く。わたしは当時小学6年生だったけれど、カ
ラオケボックスなんてなかった時代、この曲だけはどういうわけかフルコーラスを歌うことがで
きた。あいまいながら、ちゃんと英語のところも。いまから思い返すとなんでだろうと思う。も
ともとはドラマ「金曜日の妻たちへ」の主題歌なのだけれど、小学生が見ているはずもなく、お
そらくは歌番組で何度か聞いただけだったはずだ。ほれ込んでいたんだと思う、小林明子の歌と
歌声に。だから、ほんのわずかな断片を余さず、憶えこんだ。聞くことができたそのときに逃さ
ずに自分のなかにしまいこんだ。そういうことだったんではないか。
いま、あのときのような純粋さをもって、憶えたくて、歌いたくて仕方がない歌が、果たして自
分にはあるのかな、ふとそう思った、深夜のコンビニであった。
- 2006/5/11(木)
わたしの夕食の典型が、近所の弁当屋でおかずのみ(つまり、ごはんぬき)を買い、家で炊いた
米を食べるというものだということは、以前話したことがあるかもしれない。最近、おかずのみ
買ってくるというスタイルは変えずに、あることをやっている。買ってきた弁当の容器の、ごは
んが入るべきところに、じぶんでご飯をつめるのである。一見すると、普通の弁当を買ってきた
かのように見えるが、これはご飯がない分100円引きの弁当なのだ。
どうして、そんなことをするのか。少し前まで、ごはんぬきの弁当を買うと、同じ容器をつかっ
ていたとしても、容器全体におかずを配置してくれた。つまり、ごはんスペースにおかずをつめ
てくれたわけだ。多少不自然ではあるが、立派なおかずのみとして独立した弁当だったのだ。と
ころが、最近になってこれが面倒になったのか、ごはんスペースがどーんと空いた状態で渡され
るようになってしまった。もともと、ごはんがない分だけ軽かったのであるが、おかずスペース
にだけおかずが偏っている分、持ち運びのバランスが悪くなってしまった。これがひとつの難点。
そして、もうひとつが重要で、ふたをあけたときに大層、貧相に見えるのだ。弁当が。どれだけ
ぎっしりおかずがあったとしても、ごはんという中心がない弁当の喪失感は想像以上に大きかっ
たのである。え、これがわたしの夕食なのか...となんだか悲しくなるくらいだ。そう、弁当は
ごはんとおかずがあって、はじめて弁当足りえるのだということを、恥ずかしながらそのとき
初めて実感したのである。
以来、まっさらの未使用のご飯スペースに、じぶんのうちで炊いた米をスペースいっぱいにつめ
るようになった。自分で入れてみると、食べたときの実感以上に量が多いのだということがわか
る。もうひとつ、わかったことがある。弁当屋は、ごはんを入れるのがうまいということだ。わ
たしがいれた弁当は、どうみても「あとからいれました」というようにしか見えない。まぁ、実
際そうなのだから、そう思えて当然なのだけれど、弁当屋の場合も条件は同じ。なのに、そこに
はじめからご飯が存在していたかのように見えるというのが、すごい。あれは何かコツがあるの
だろうな。ときどき、米を切らしたときに買う、「ご飯入り」の弁当をよく観察して、その手法
をつかみとってみたいものだと思っている。
- 2006/5/10(水)
スタンドで夕食。日替わり定食は肉が多いので、帰宅後はたいてい「一日分の野菜」を飲んで
バランスをとるようにしているのだった。それにしても、ご飯もおかずも量が多い。なので水
曜日の昼食は控えめにしているのだけれど、それでもぐぐっとくる。一度、定食ではなくて、
ほかのお客さんがそうしているように単品で頼んでみようかと思う。ビールとかお酒飲まない
のに単品は変だろうかネ?ああ、サイダーがあるんだった。それで行こう。定食から単品、な
んとなくちょっと経験値が上がった気分(←なんの経験値だ)。
- 2006/5/9(火)
大丸でフランスパン(の半分サイズ。バタールという名前)を買うと、いつも「フランスパンの
保存袋をお付けしますね」と有無を言わさず、巻物状態に畳んだ袋を渡される。食べ残したパン
が湿気を吸わないようにするためらしいのだけれど、大丸でパンを買うようになってから、つま
り2年前にそういうものがあることをはじめて知った。しかし、その前後で何か変わったかとい
うと何も変わらないのだった。なぜなら、わたしは買ったフランスパンはほぼその日に完食して
しまうので、保存の必要がないのだ。というわけで、巻物状態から展開したことがなかったのだ
けれど、どんなんやろと思って開いてみたら、ロゴの入った単なる透明なビニールの袋で、長さ
も想像していた細長いものではなく、通常のフランスパンの半分くらいのものだった。細長いも
のだったら、「使い道に困るなぁ」と思っていたのに、いざなんでもない長さでしかないことが
わかった途端「つまらん」と思ってしまった。身勝手なものである。しかし、これ、わざわざつ
けるほどのものなんだろうか?何か特殊なビニールなのか?使っている人教えて欲しい。
PCが死んでしまってから久しく使っていなかったPC用の椅子をベランダに出してみた、昨日。
気温がぐんぐんあがっていくのと比例して、ベランダの風がたいそう気持ちがよいので夕涼みを
してみたかったのだ。独り用の縁側というべきか。うちのベランダは無駄に広いのでなかなか快適
である。きのうは柿の種をつまみに一杯(水)飲んだ。頭痛かったけど。座っていると空と雲ばか
りしか見えないのだけれど、たまには星が見えることもあるだろう。そういうわけで、椅子はだし
っぱなしにしている。きょうは湯上りにフランスパンを食べるつもりだ。
...って上がってみたら、雨降ってるじゃないか!
- 2006/5/8(月)
あたた、一日経ってから首肩に痛みが。どうして、こうも頭痛体質なのか。
コーラスワークショップ、練習、演奏会の連荘は、やはり後遺症が大きい。
「男声合唱を続けるには無理をしなければならない」と、打ち上げで指揮者は言ったが、
このGW期間中の東京カンタート当日キャンセルをきっかけに、自信がなくなってきた。
NCにおいて、歌でもマネージでも、20代の若手が台頭してくれないと、いつまでも引っ
張っていくのはしんどい、というようなことをNCのBM(バンケットマネージャー)と
話したのであるが、待っているだけでは今はダメなんだろう。なんとか育成していかない
といけないのだけれど、簡単じゃないのだなぁ。両方のスキルにもっとも必要なことは、
「全体最適」を理解する、ということで、これは社会人として数年やっていかないと身に
つかないことだけに、ジレンマだ。全体最適を「自分が犠牲になるのはヤダ」って思われ
たらもう成り立たない。もへ~。
頭痛いので、きょうはこのへんで。
- 2006/5/7(日)
休養のため、メモだけ。
メモ
・「ねじまき鳥クロニクル」読了。この本は時間をおいて、読み返してみたい。
・今日買った本:"The Catcher in the Rye",J.D.Salinger,村上春樹訳。白水社刊。820円。
続けて何か読みたかったので「ダンス・ダンス・ダンス」にしようと思ったのだけれど、
講談社文庫の活字、正確には紙と活字のコントラストが、わたしはどうも苦手で、特に
疲れているときは目が受け付けないために、断念。蔵書のなかでも、講談社文庫は驚く
ほど少ない。村上春樹訳ということで、ねじまき鳥読了直後のいまなら「親和性」があ
るし、聞いたことはあるが読んだことがない「ライ麦畑でつかまえて」を読んでみたか
ったこともあり、購入。ペーパーバックエディションなので、手に馴染む。
・帰宅後、猛烈に眠くなり、体から力が抜ける。なにもせず、横になる。明日起きられるかなぁ。
- 2006/5/6(土)
なにわコラリアーズ第12回演奏会@兵庫県立芸術文化センター。
10:30-23:15。
終わりました。ご来場いただきました皆さんに感謝を。
かげにひなたに応援・協力していただいた皆さんに感謝を。
そして、支えてくれた友人に感謝を。
わたしは、みんながいるから歌っていられる。
ありがとう。
- 2006/5/5(金)
NC練習、15:00-20:00。
はっきりいってしんどい。練習は楽しかったけどさ。
帰宅後、オーダーを作成。トップ、セカンドは各パートの自治に任せた。ベースは作成済み。
どういうわけかバリトンのオーダーは作ってくれる人がいないので、わたしが作成。なぜだ...。
マネージャーはホール入りが早いので、もう寝ます。
おやすみなさい。
- 2006/5/4(木)
全日本合唱連盟コーラスワークショップ@いたみホール。
スペシャルコンサートにNCで出演。(12:00-21:00、伊丹滞在)
「楽譜は時間を空間化するための手段であった」「そのため、最適な和声の組み合わせが研究可能
となった」という皆川達夫の講演は、聞き応えのあるものだった。やはり氏は研究者だ。論の展開
に納得性がある。ただし、聞く側にも抽象的な概念の理解力が必要。ただ合唱で歌うだけならば、
論は必要のないこと。しかし、合唱をより深く知ろうとし、考えるならば、避けては通れない。
アカデミズムは合唱に必要であるなぁと思った一時間だった。
演奏のとき、わたしは目が悪いので席にいる友人・知人を見つけることがほとんどできない。それ
でもさがしたくなることがある。歌を歌うとき、どうしても歌いかけたいからだ。演奏の全体はそ
の場に来てくれたお客さんみんなに向けてのものかもしれないが、個々人の歌はいつも誰かのため
にあると思う。でないとウソのような気がする。
誰かの心に届いているのかどうかは、結局のところわかりようもないのだけれど、それでも歌を歌
いながら、「ああ、歌が搬送波で、歌にこめた気持ちを変調して飛ばせたらすごいなぁ」などと、
考えたりする(←ちょっと変だ)。それができたら、もし演奏会場にその誰かがいなかったとして
も届くんじゃないだろうか、とも思う。人間ラジオ。
もし、その人が受信帯域に合うアンテナをもっていなかったら、受信できないわけだけれど。
(え、言っていることが工学チック過ぎますか?比喩です。比喩。)
きょうも疲れました。寝ます。
- 2006/5/3(水)
「フンデルトバッサー展~人と自然:ある芸術家の理想と挑戦」(京都国立近代美術館)を観覧。
わたしは彼のことをずっと建築家だと認識していたのだが、実は活動的なエコロジストであり、
芸術家(画家)であったことを本展覧会ではじめて知った。彼のことを知ったのは、ある日実家
で親から「あんたの好きそうなんのってるでー」と雑誌のページを引きちぎったものを渡された
ときだった(余談だが、うちの母は必要な情報は何でも引きちぎって携帯する)。そこには大阪
の舞洲の大阪市清掃局のなんともカラフルで植物的な造形の、およそ清掃局とは思えない建物が
紹介されていた。それが、フンデルトバッサーのデザインによるものだった。絵画や模型、空想
の世界にしかありえないだろうと思う色彩と造形を、「現出」させてしまっているそのことに、
そしてそれが日本にあることにえらく驚いた。その後、書店でたしかタッシェンの本で6000円く
らいする、彼の建築プロジェクトをまとめた本を見て、ますます「建築家」としてのイメージが
深くなった。
しかし、今回の展覧会、ポスターやチラシでは「建築」に焦点を当てると書いてありながら、
約半分以上を占めるのが、彼の独特の絵画(ほとんどが版画)なのだった。抽象画とは違う。
鮮烈な色彩と、およそ題名からは判別しがたい内容でありながら、それは抽象画とは異なり、
作者の強烈なメッセージ性をダイレクトに伝えてくるような印象を受けた。
それはそれで新しい発見であったのだが、あの独特の建築と、この絵画が、そして彼が目指し
たエコロジストとしての理想が、どのように結びつくのか、どのような過程でそれらが醸成さ
れていったのかということは、この展覧会から読み解くことができなかった。おおまかに4つ
のパートに分かれているものの、なぜ彼がこれほどの版画を作成したのか、それがなぜ日本の
彫氏、摺氏との共同作業だったのか、などさまざまな重要と思われるポイントの説明がすっぽ
り抜けている感じがした。確かにそれぞれの作品のテーマは、人間と自然、社会とのかかわり
を示すものだったが、もう少しキーワードをちりばめたり、彼の足跡をたどるための手がかり
のある構成が必要だったのではないかと思う。彼の青年期の作品が展示はそういう意味ではむ
しろなかったほうがよかったのではないか。
要所、要所にある建築模型によって、なんとか興味をひきとどめられてはいたが、これらと絵
画との関連性がもっと明示的であったなら、彼の作品への理解と興味も高められたのではない
かと思う。フンデルトバッサーのことをよく知る研究者にとっては、これでよかったのかもし
れないが、もう一工夫が欲しい展覧会であった。
図録は買わず。昔みたタッシェンの本も売られており、こちらのほうが興味をそそられる。
いつか買おう買おうと思っていたのだけれど、持ち合わせもなかったし何しろでかい本なの
で今回も見送った。
会期は5/21まで。
不定期掲載「わたしの好きな場所」

<その1>古今烏丸(ここんからすま)、階段室。
タイル張りの階段と踊り場は、とても丁寧な手仕事の良さを感じさせる。目立たない部分
だけれども、そこに居るひとがもっともよく使う部分。こういう場所で手を抜くか、抜か
ないかという点が、その建築の全体のよしあしに関わってくると、わたしは思う。
- 2006/5/2(火)
きょう、さる所で500円の買い物をしたとき、「はい5億円」と言われた。これまで生き
ていて、こんな漫画のようなシーンに出くわしたのは、むろんはじめてで、夢にもよらな
かったので多いに面食らったわけであるが、こういうことは「大阪のおばちゃん」ではな
くてもゆうんやなーと妙に感心もした。
しかし、違和感があった点がひとつあり、500円の場合、「500万円」というように本来の
価格情報を判別しやすいようにするのが”普通”であろうと思われるのだが、なぜ「5億
円」なのか。
500円に対して、500万円は10の4乗倍だな。それに対して、5億円は10の6乗倍だ。このあた
りにヒントがあるのかもしれない。日本の数の数え方において、万以上の単位で普通用い
られるのは億と兆であるが、万→億→兆は10の4乗で変化する。このことは日本人の一般的
感覚として染み付いていることは言うまでもない。ところが、この感覚を無視するかのよ
うに、会計報告など、アラビア数字だけ数字を表すとき、500万や5億はどのように点
をうつだろうか。5,000,000(500万円)であり、500,000,000(5億円)だ。これはあきら
かに英語圏の単位変化に則っているからだ。10の三乗を基本に単位が推移する。1thousand
のつぎは、1millionなのだ。だから、一般的な生活を送っているひとにとって、この点の
うちかたは言語体系に対して、違和感を生じさせ、数字の可読判別性を多いに阻害してい
ており、会計数値の点うちは4桁単位にすべきだ、という主張がある。このあたりのことは
本多勝一著、「日本語の作文技術」(朝日文庫)にくわしく述べられている。
まぁ、その主張に関しては、多いに同調すべき点はあるが、自然科学で主として用いられる
主流のMKS単位系(kキロ,Mメガ,Gギガとかね)などは10の三乗が基本なので、お金の数
字のあらわしかただけ点うちのルールを変えると混乱が起きるだろう。あ、さてそれはさ
ておき、普段の生活で数字の考え方としてはすぐには10の6乗、つまり10の3乗系統の思考
というものはなかなか日本人は出てこないものなのだ。それがすんなり「5億円」となる
のは、よほど金融や税制などで職業柄目にしているひとか、企業で予算策定などをこなし
ている人だけではないかと思う。
その言葉を発した場所のそのひとは、そういう人なのだろうか。一般的には想像しにくい
のであるが、まぁ考えてみれば、イメージとしては遠くあるべきだが、実際上は気にしな
ければ立ち行かないものなのであろう。(別にそのことを揶揄するつもりはまったくない
のだけれどね。)
その場所とは「お寺」であり、そのひとは「お坊さん」であった。
健康祈願、病気(?)治癒祈願に行ったのでした。
- 2006/5/1(月)
evian飲んで、土佐煮弁当を食べて養生中。
更新休みます。
- 2006/4/30(日)
東京カンタート@すみだトリフォニーホール。YKの一員として参加。
の予定であったが、著しい体調不良に見舞われ、やむなく参加を断念。
YKメンバーの皆さんには、迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。
当日は名古屋で途中下車。あのタイミングで、休むように諭すメールがなければ、
降りるタイミングを逸して東京まで行き、ひどいことになっていたことは想像に
難くなく、げに友人の忠告はありがたきかな、とあとで思った次第。
遠足の当日に熱を出してしまった子どもの気持ちがよくわかりました。それから、
熱くて苦しいときは、アイスノンや冷えピタよりも、床に直接寝転がる方が気持
ちいいことも(もう味わいたくないッ!)。
- 2006/4/29(土)
YK練習、12:00~17:00。
NC練習、17:30~21:30。
YK練習では東京カンタート以外の曲も練習に参加。誇張ではなく、心が洗われる。もっと歌って
いたいと思った。合唱部分だけでなく、ピアノ部分の作曲のすごさに改めて感心する。そして、こ
の曲はYKの歌声にとてもあっていると思う。この曲をはじめて聞いた東京の団体とはまったく違
った、YKにしかできない、情緒的な温かみをました演奏ができるはず。いまのままでは程遠いけ
れど。あとはみんながどれだけ、この曲を愛することができるか(どれだけ真剣になれるか)なん
だろうな。
ああ、足が痛い。
- 2006/4/28(金)
BK練習、18:45~21:00。N山さん襲来。驚く。こうやって、金曜日の晩の京都にひょっこり
帰ってきてくれるひとがいるって、じつはBKの良さなのかもしれないなと思う。
BK宴会、21:30~25:15。
いろつきチューハイで盛り上がる。

「よつばと!」5巻、あずまきよひこ著、メディアワークス刊。600円。
昨日、買ったのだけれど読んでいない。このまえ買った川上弘美の新刊も読んでいない。どちらも
東京に持っていって、カンタートが終わってからホテルでゆっくり読むのだ。もちろん、ねじまき
鳥も一緒。こんなにいっぺんには読めない、とわかっていても旅行にでかけるときは、何冊か本を
もって行ってしまう。それでもって、現地でも必ず最低一冊は買うのだ。そこでないと買えない本
ではなくて、京都でも買える本なのだけれど、その土地で、その場所で、旅先で見つけたというこ
とは京都では味わうことができない。あたりまえだけど。本を持っていくのも、日常とは違う読書
がしたいのだと思う、多分。もっとも日常的なことだからこそ、すこしの違いがとても大きな違い
になる。
東京カンタートでYKが歌うとき、いつもと同じだとダメなんじゃないかなって思う。平常心は必
要で、自分達の音楽を変えることはできないし、その必要はないと思うのだけれど、でも、やっぱ
りいつもと違う気持ちというのがあればいいと思う。いい意味での「張り」みたいなものをもつこ
とで、音楽をいい方向にアレンジできればいいのになと思う。音楽というものが読書みたいに日常
化すれば、ちょっとの違いが大きな違いになるんだろうか。
- 2006/4/27(木)
NCマネージでちょっとしたデリバリー。御池通を東へ、そして帰りは押小路を西へ。今日わか
った。御池通りは歩道のほうが路面抵抗が少なくて、自転車が走りやすい。つるっとした大きめ
めの磨き石が使われているのだ。しかし、自転車専用レーンがないので、それほどスピードは出
せない。最近の流れとして、自転車も車道を走るというルールが浸透してきているのか、歩道の
一部をわざわざ自転車用にすることはないのかもしれない。法律上の扱いが自転車はあいまいな
ので、地域によって解釈が異なるし、同じ京都市内でも堀川にはレーンがあったように思う(堀
川通はレーンを作ったと思ったら、すぐに掘り返して工事をする代表的な道路なので、まともに
レーンを走れることは少ない)。京都議定書を本気で遵守しようと思うのだったら、冷房の温度
を28℃(いまからげんなりする)にするなんていう身体に悪そうなことはやめて、自転車が走り
やすい空間を作って、車に頼りすぎる社会構造から脱却するほうが、よっぽど健康にもいいし、
効果が高いのではないだろうか。自転車に乗っているひとからは、税金がとれない。自動車から
はとれる。だから積極的に自転車への振り替えは進められないのだろうか。しかるべき自転車道
や駐輪場があるなら、自転車から税金とってもいいと思うのだけどな。
そう自転車のための環境が欲しい。自転車に保険がほとんどないのは、盗難率が高いからだけど、
盗難される土台というのは都市環境によると思う。しかるべき駐輪スペースがあれば都市の景観
を粗雑にしてしまう野放図な駐輪状態はなくなり、盗難する機会自体が失われる。このことは
JR山陰線の二条駅、円町駅、花園駅に有料駐輪場ができたときに劇的に改善された(と利用者
であったわたしの目にはうつった)ことから、有効な施策であることはあきらかだと思う。盗難
が減れば、保険ができるかもしれない。そうすれば、所有しやすくなる。そして、いい自転車が
欲しいと思うし、いい自転車だったら、それを大切に扱う風潮が生まれるのではないかと思う。
ひいてはそれが都市の景観を美しくすることにつながる。
自転車雑誌を眺めていると、季節を問わず京都の街を自転車で走ろう、という特集がある。実際
にまえにも書いたように、自転車向けの大きさなのだ。しかし、他府県のひとがひかれるのは、
京都の既存の観光資源であって、自転車の走りやすさにではない。これはもったいない。せっか
く自転車に向いた資質をもつのだから、それを高めるようにすれば、自転車に乗るために京都に
くるなんてことが起きるかもしれない。それは新しい観光資源なのだ。進取の精神を発揮してな
んとかならないものだろうかなぁ。
- 2006/4/26(水)
夕食、スタンドにて。満席。スタンドの店内は空気の流れがよいのか、つねに空気がきれいな
感じがする。隣と、向かいにタバコを吸っている人がいたが、煙のにおいがあまりしないので
気にならない。また空調も適切で、暑いとか、寒いと感じだことがない。食事をするにはいい
環境だと思う。まぶしくない照明もわたしにはありがたい。
帰宅後、トレーニング。8.3km、30分。前回とほぼ同じコースだが、二条まで上がらず、御池
で西進するコース。御池通りの車道の舗装は意外と走りにくいと感じる。横風を受けていたか
らかもしれない。逆に走りやすいのが堀川通の南行き。西本願寺前のあたりはスピードも乗っ
て最高に気持ちがよい。それにしても、四月も終わりだというのに、夜のこの寒さはどうした
ことだろう。春物の背広では寒い(注:トレーニング時は平服着てます)。
トレーニング後、NCマネージ少々。
TVアニメーション「涼宮ハルヒの憂鬱」を見る。きのう二回見て、今日一回。たかだか25分
弱の時間のなかに、圧倒されるほどの動きと、演技と、演出がこめられていることに、ただた
だ敬服し、感心し、たくさん笑って、ちょっとほっこりする。世の人は、安直にTVアニメは
どれもかわいい女の子がでてきて、それで終わりだと思っていないだろうか。広告だけを見る
とそう思っても仕方がないかも。でも、でもだ。同じかわいい(にもいろいろあるが)という
のが、動きになったとき、圧倒的な差を生じるときがある。作品によって。絵が動いている、
くらいにしか思えないものはアニメとしては論外なのだ。そういうものは、その絵が好きなひ
と以外にはまったく支持されない。感情移入できるしぐさをともなった人物と感じられなけれ
ば、いくら壮大な設定があったり、重厚なストーリーがあっても、面白くない。そういうもの
をオタクは支持しない。あらすじにして、一行にしかならないストーリーでも、25分間まった
く退屈せずに見続けることができる、そういうアニメをわたしたちは見たいのだ。断じて、か
わいい女の子を眺めるためだけに、なんでもかんでもみているわけではない。それはみんなが
見ているTVドラマでも同じことだろう?きれいな女優をみるためだけに、ドラマを見てはい
ないはずなのだ。類型化し、型におとしこんだ理解をしてはいないだろうか。アニメを見る人
のことを。(そのほうが楽なんだろうけど。違うものがあるということは複雑さを増す。なる
べく簡単なほうがいいと思うのは摂理かもしれない。でもその思考には発展がないと思う。)
ことはアニメに限らない。
- 2006/4/25(火)
給料日。定時規制日なので早く帰れる。NCマネージで、いささか寝不足なので助かる。
きのうは、別にあることを少しやっていた。3月の結婚式の写真をデータで欲しいと、
新郎新婦に言われていたので、CDに焼こうとしたのである。
マーフィーの法則に「失敗する可能性のあるものは失敗する」というのがある。少し以前
からまたCD-R焼けない病が再発しており(わたしがそういう病気にかかったみたいだ)、
こんかいは音楽じゃなくてデータだから大丈夫かなと思ったら、甘かった。100%失敗する。
こうなったら、SDカードでデータを渡して友人に焼いてもらおうかと考えたのだけれど、
そういえば会社のPCなら焼けるかもと思って、会社にデータを持っていった。メディアは
SDとPCカードアダプター。が、デスクトップにはUSB端子はあったが、SDもPCも
カードスロットはなかったのである。個人で使えるノートPCはあるにはあるのだが、担当
者にことわらないといけないので私用には使いにくい。さて。
で、ひらめいた!DVDレコーダーを使うのだ。CDがダメならDVD。うちのDVDレコ
ーダーにはSDスロットがある。これならPCを介さずに済む。
予想がつくと思うが、これもだめだった。SDから焼けるのはDVD-RAMで、DVD-
Rには焼けない仕様だった。DVD-RAMはメディアが高いし、対応するPCも多いとは
いえない。新郎新婦にはDVDでもOKとの内諾をとっていたが、RAMは読めるかどうか
微妙な線。困った。
あきらめて、初心に返る。だめもとで、PCでDVD-Rを焼いてみるのだ。だめもと、と
はいったが、内心ちょっと期待もあった。このドライブはCDはともかくDVD-RAMの
書き込みで不具合が出たことはない。Rでもいける可能性にかけることにしたのだ。結果、
何の問題もなく、すんなりクリア。じつにあっけなかった。しかしなぁ、なんでやねん!と
おもわずにはいられぬ。とにかくこれで任務を遂行できた。
今後、データはDVDに焼く方針とするにしても、音楽についてはCDでないとだめなこと
は変わらない。NCの演奏会のCD作りが、このままではできないのは確かである。ふーむ
な状況。
きょうはたぶん、早めに寝ます。
たぶんね。
- 2006/4/24(月)
なにコラマネージのため、更新休みます。すいません、ばたばたしてます。
本日の本。
・川上弘美最新刊、「夜の公園」、中央公論社刊。1400円。
・雑誌「pen」、特集『自転車のある美しい暮らし』。500円。
覚書。
・よつばと5巻の発売は、27日。
ねじまき鳥近況。
・第3部を5分の2くらい読んだ。ナツメグとシナモン登場。笠原メイの手紙が好き。
- 2006/4/23(日)
高島屋でシャツとズボンを買う。この前、服を買ったのは11月のコンクール前。そのまえは、昨年
のカンタート前。なぜだか、合唱の「こよみ」とリンクしている。自分のセンスはあまり信用でき
ないので、店員さんにあわせてもらった。というか、じぶんの目だけで考えていると、同じ傾向の
服に偏ってしまう(あまり買わないのに)ので、あえて人の目に頼ってみるのだ。想像の外にある
自分の格好は、やっぱり新鮮である。持っている服と合いそうかどうかだけは気にしたが。なにせ
これからしばらくは買わないのだから、着まわしは重要である。しかしなぁ、新鮮ではあるけれど
つくづく普通の服が似合わない、のだなわたしは。選んでもらってるにも関わらず。その点、背広
は楽だ。背広というのは記号のようなもので、すでに外見が規定されているから。まぁ、背広にも
センスが必要なのは認めるが、普段着と背広なら、わたしは背広のほうがましな格好に見えるよう
な気がする。通勤で、背広禁止っていわれたら困るだろうな。
- 2006/4/22(土)
NC練習、15:00-21:15。
4/30に東京カンタートにYKメンバーとして出演するため、東京へ行く。日曜日である。翌日は
月曜日だ。当然だな。でもこれはとても重要なことなのだ。なにかの用事のついで、それはつま
りほとんどが合唱関係であったり、コミケ関係であるわけだが、それは日曜日に終了する場合が
多い。翌日、休みがとれればそのまま逗留して、東京を散策する。しかし、月曜日というのはわ
たしが主に回りたいと思う美術館、博物館の全国的に共通の休館日なのだ。このことには長年な
やまされ続けている。主目的のついでであるから、仕方のないこととはいえ、せっかく滞在して
いるのに行き場がないのはもったいない。月曜日が休みでない施設をあらかじめさがすのである
けれど、これがなかなか興味を引かれるところはないものなのだ。結局のところ、神保町へいっ
たり(神田の古書店はむしろ日祝に規則正しく休む)、丸善丸の内OAZO本店に落ち着くこと
になってしまう。嫌いでないとはいえ、たまには違うところに行ってみたくなる。
しかし、今回は例外的に月曜日が休みのところが開館するため、そこへ行く。場所は秋葉原、
神田万世橋。名を「交通博物館」という。5月14日に閉館するため、4月24日の休みを最後
に連日開館する。もし、規則どおり月曜日休館であったなら、博物館最後の姿を目にすることが
できなかった。いまは、平日休日を問わず、ときには入場制限がかかるほどであるという。それ
だけ、この場所に思いいれのあるひとが多いのだろう。わたし自身は、3回か4回かしか行った
ことはないのだけれど(京都在住の人間としては多いのかな?)、数ある美術館・博物館のなか
で、一番わくわくする場所であると思う。だから、この場所がなくなるのは寂しいし、記憶にと
どめておかないといけないなと思うのだ。そして、わくわくする感じもアップデートして、記憶
するのだ。
あ、主目的はあくまで東京カンタートなので、それを忘れてはいけない。
楽しんで、歌います。
- 2006/4/21(金)
BK練習、18:40-21:00。
BK宴会、21:30-23:00。

夜のショールーム。
BKからの帰宅途中、烏丸御池の角にショールームがある。ひとけのないバスタブはまるで
チェックインした直後のホテルのそれのように、ひっそりとして、誰かが使った気配もまる
で見せずに、静けさそのものをあたりに放っているようだ。その奥に見える便座もしかり。
もうれつに店に入って、靴のままつかりたくなる。
ショールームが好きなのだ。子どものころは、どちらかというと親に連れられてモデルハウ
スをよく見て回って、ショールームにいった記憶があまりない。小学生のころか、京橋にあ
るツイン21のナショナルの電気館?かどこかに遊びにいって、そのつづきで階下にあるシ
ョールームにいったのが一番古い記憶かもしれない。とにかく感動した。モデルハウスでは
「こんな家に住めたらなぁ」とは思ったけれど、感動まではしなかったのだ。なぜだろう。
ショールームというのはたいがいはビルの1フロアのなかにある。そこはあきらかにひとが
生活をする場ではないし、われわれは靴のまま歩く。そこに突如として、キッチンがあらわ
れる。その先にはまたキッチンがある。角を曲がるとバスタブがあって、トイレがある。限
られた空間のなかに、ひじょうに高密度に住空間の見本が配置され、そのどれもがその当時
の最先端なのだ。まるで「ホテルみたいだ!」と思ったのだと思う。そうホテル。日常には
こんな場所はありえないし、なにより靴のままでいるということが、その気分を補強したの
だろう。
モデルハウスはこれからそこで暮らす家族の生活を模している「日常」なのに対し、ショー
ルームはおなじ日常を形作るための素材の展示でありながら、その空間の特異さゆえに「非
日常」をつくりだしている、そんな気がするのだ。だから、ショールームに行くということ
は一種の旅行であり、リクリエーションみたいなものなのだな、わたしにとって。
汐留の再開発が行われたとき、松下電工(現在は、松下電工+電器)の大規模なショールー
ムが開館した。階上には電工の美術館があり、そこへ立ち寄ったついでに入ってみた。が、
あまり楽しめなかった。だって、あからさまに冷やかしでもなく、本当にリフォームだとか
家を建てる目的でもなく、そこに遊びに来ているだけの男性、それもひとりとなれば、怪し
いことこのうえないじゃないか。そういう心理があって、そそくさと立ち去ってしまった。
いや、あれはざんねんだった。意気地なしなのである。
誰か、一緒にショールーム行きませんか。
ホームルームじゃないですよ。
- 2006/4/20(木)
阪急電車の車中から、烏丸の改札を出て地上に降り立ち、キンコーズ四条烏丸店にいきつくま
での間、わたしは一心不乱に「いろんな気持ちが本当の気持ち」を読んでいた。歩きながら本
を読んだのは角田光代の「対岸の彼女」以来だ。長嶋有はとにかく発想が豊かだ。それでいて
文章はとてもストレートだ。さくさく読めるのに、読み返したくなる文章だ。キンコーズにい
きつくまで、と書いたけれど、実際は5歩くらい手前でやめた。顔が相当ゆるんでいて、にや
にやしていたので、クールダウンする必要があったのだ。ニヤニヤしながらコピー屋に入って
いくひとはあまりいない。
そういうニヤニヤさせる文もあるかと思いきや、至言だなと思う文に出くわすこともある。少
し引用したい。
『少なくとも、さも賢い選択をしているかのように「読書は図書館で借りてすませます」と人
前で得意気にいうのはやめたほうがいい。お金のない学生ならいざ知らず、大の大人がまった
く身銭も切らずに世界を知ろうとするなんて、いけないことではないが、はしたないことに思
える。』(「作家の好きな言葉」より)
ハリーポッターの第一巻が発売された直後、ひとつの図書館で、何十冊というハリポタが購入
されたという話を聞いたことがある。読みたいという要望が殺到したからだという。ニュース
になったのは版元がかなり怒っていたからだったと思う。たしかに税金を払っている人なら、
要望してそれを読む権利はあるのだろうけど、何かすっきりしないものをそのとき感じていた。
そのすっきりしない何かを、これほどうまく言いあてた文はなかった。溜飲が下がったとでも
いうべき気持ちになった。
身銭を切って得る何か。それは鋭敏な感覚であり、世界をよりよく知ろうとうするための原動
力だと思う。自分自身がその対価を支払わないでどうするんだ。
さて、この引用された文のタイトルは「作家の好きな言葉」。では、それは何かというと、
「増刷」だそうである。増刷...。なんだかあまりに即物的な響きに思えるだろうけれど、本
を作ったことのある人なら、その響きのもつ、晴れがましさやよろこびはわかってもらえると
思う。だからって、サイン会で「増刷したい」って書いてしまう長嶋有はちょっと変だ。
- 2006/4/19(水)
三週間ぶりにスタンドで夕食。ひさしぶりにかぐとんかつのソース(ただのソース)の匂いが
あまりにも濃厚で、充血して張り付いた脳と頭蓋骨にすこーんと隙間をあけるような爽快感を
得た。あまりに気持ちよかったので、食べるまえに二度三度とくんくんと匂いをあじわってい
たものだから、はたから見るとちょっと怪しかったのではないだろうか。アルバイトの店員が
いかがわしげな眼で見ていたような気もする。まぁ、気にしない。匂いという感覚をどうやっ
て人間は感知しているのか、6~7年前だったか旅先のビジネスホテルでつけたTV、NHK
スペシャルだったか、BBCのドキュメントだったかでその研究をとりあげていた。番組をみ
るかぎり、その時点ではほとんど解明されていないも同然で、仮説がいくつかあるにすぎない
状態だった。視覚や聴覚の科学的説明がニュートン力学なら、嗅覚のそれは量子物理学のよう
なもので、数式ではイメージできず、例え話をどれだけ理解できるかが、「ああ、なるほど」
と思えるかどうかの分岐点のような印象を受けた。そんなだから、当時番組の内容を手帳にメ
モした記憶がある。あの手帳はいずこへ?以降、思い出すこともなく、ひとに話すこともなく
すぎたが、あの番組はもう一度みてみたい。よくできていた。
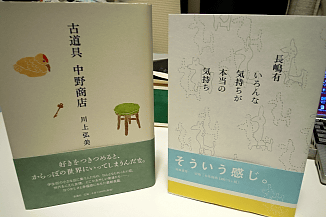
「いろんな気持ちが本当の気持ち」、長嶋有、筑摩書房刊。1300円。
本当はべつの本を買おうと思っていた。ある本屋でみつけたその本は、本の端がかなりの頁に
わたって折れ曲がっていたので、隣の本屋まで行ってさがそうと思ったのだ。そんなとき、隣
の本屋で見つけたのがこのエッセイ集だ。著者の長嶋有の小説は読んだことがないのだけれど
あることでずっと頭に残っていた。この前読んだ川上弘美のエッセイで、長嶋くんに北海道土
産を買う(長嶋有は北海道出身なのに)という件があったのだ。作家友達であるらしい。それ
で棚に並んだ本のなかで目がとまった。で、取り出してみると装丁がすごくいい。活字の型押
しのタイトルがいい雰囲気だ。こころなしか川上弘美の本に通じるなにかを感じる。中身を読
むまえから、川上弘美の友達だったら、どこかしら連なるなにか、おなじ空気をにおわせる何
かがあるんじゃないかと思った。作家であるから、文体は当然違うのだけれど、見ているもの
が近かったり、感じ方の振れ具合が同じくらいだったりするのじゃないかということだ。だか
ら、中身を読む前に買うことにした。それでちょっと中身を読んでみて、ああそれでいい、と
やっぱり思えた。
買うとき、カバーは入りませんと言った。その店のブックカバーはあまり好きではないからだ。
どうせなら、気に入りのものをかけたい。では、その気に入りのカバーはどうするのかという
と、すでに読んだ本から取ってくる。カバーのリユース、いやいやそんなものじゃない、継承
である。
帰宅してから、川上弘美の「古道具中野商店」のカバーをとり、「いろんな気持ちが本当の気
持ち」にあわせて折って、かけた。こうやって、このカバーはこれからも、いろいろな本に伝
えられていくのだろうと思う。伝承したいと思う本があらわれた時に。その事実はわたしにし
かわからないというのが、なんとなく愉悦である。(そんなところに楽しみを見出すのは変か?)
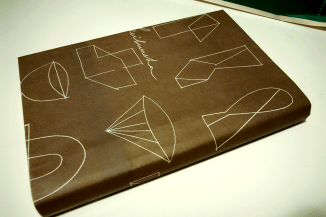
- 2006/4/18(火)
やはり、ちょっと長めの夢を見た。どこか西洋の都市の一角のわりと近代的なアパルトメント
で目を覚ますわたし。会社には出かけず、街にでると、その界隈は美術館や商業施設が集中す
る区域のようだ。美術館近辺のデザインはフンデルトバッサーであったり、ガウディであった
り、曲線や生物的なイメージのものが多い。美術館のまえでは、日本語の解説が流れていた。
歩いていると、駅構内へ通ずる上り階段を見つけた。そこで、夢の世界ではない、現実の世界
のわたしは思った。「この階段を上るとまだ工事中だったはず」。過去形。そう、なぜだか、
わたしはこの夢のなかの世界に来たことがある!と、思っている。正確なところはなにしろ夢
のことなのであいまいだが、こんな風に、夢のなかの舞台が一回こっきりではなく、複数の夜
に登場することがよくあるのだ。連続ではなく、何ヶ月か、何年かぶりにひょっこりあらわれ
る「続き」の世界。それはもしかしたら、それぞれが現実世界の何かと結びついているのかも
しれないけれど、登場するきっかけというものがまるでわからないので、意図的に見ることが
できない。可能だったら、その架空の街をすみずみまで探検してやるのにと思うのだが。。
きょうは、マッサージに行ったので、また短編にもどるだろうか。
***
部屋のなかがわりと殺風景になっている。原因は壁にポスターが張れないからだ。正確には
張っていてもはがれてしまう。ピンナップ程度のものなら、セロハンテープかなにかでとめ
ておけるのだが、大判のポスターになると、紙が重くてとてもささえきれない。仮にガムテ
ープを使ったとしても、やはり落ちてくる。原因はふたつある。ひとつは大きなポスターは
空気中の水分を吸って伸び縮みするため、留め位置が固定しないのだ。これは実家にいると
きはまるで気がつかなかったのだけれど、部屋と浴室が近いワンルームでは湿度の上下がわ
りと極端だからかもしれない。
もうひとつは壁紙だ。汚れを防ぐためか、表面に細かい模様がついていて、このせいでどん
な強固なテープを貼り付けても、貼り付け面積が十分に確保できないのだ。面ではなくて、
線の集合体にはりつけているようなものだ。だから、粘着力が弱い。この問題だけはいかん
ともしがたい。貼り付け強度を確保するためにやたら、テープを使うことになる。大判ポス
ターの場合、かなりめんどうで、やっかいな作業になる。それもはがれやすいことにはかわ
りないので、何日か経つとつけかえる必要が出てくる。
というわけで、部屋に潤いを与えるためにも、なにか良い方法がないものか検討中なので
ある。
- 2006/4/17(月)
最近、寝る前に温めた牛乳(砂糖入り)を飲んでいる。それまではずっと番茶を飲んでいた
のだが、少しでも睡眠を深いものにしたいと思ってのことである。よくお茶にはカフェイン
が含まれているので就寝前に飲むのはよくないと聞くのだが、あまり信じてはいなかった。
目がさえて困るというような感じがしなかったからだ。どちらかというと、利尿作用の方が
安眠の妨げになっているかなという気はしていた。
牛乳に変えてからは、こころなしか目覚めのあと、覚醒までの時間が短縮されたような気が
する。よく眠れているということなのかもしれない。そのわりには夢は見ているのが不思議
であるけれど。この前見たのは、卒業した大学のなかにある情報センターで調べ物をしてい
る夢であった。あまりに高層のため携帯電話がつながらないのである。そこへ、職員のひと
から構内電話がかかってくる。伝言を預かっているという。聞くと、友人から、山Dさん今
日は飲みに行くかー、という誘いの内容であった。夢はそこで終わりであった。どうやら夢
は短編化しているようだ。
しかし、今日は牛乳を飲み終わってから所用があって、コンビニまで出かけたため、帰宅し
てからどうにも喉がかわいてしまい、とうとう番茶に手を出してしまった。もう三杯目に手
がかかろうとしている。しまったと思うがもうやめられない。これから気候が暖かくなって
くると摂取する水分は増えるだろうが、全部牛乳でまかなうのは難しい。大量の番茶、麦茶
で対応するしかないなぁ、安眠と水分欲求、均衡点を探らねばならぬ。
きょうの夢は、長いか短いか?
- 2006/4/16(日)
YK練習、13:00~17:00。東京カンタートの曲を中心に。季節団員なのだ、わたしは。
Ensemble Vine練習見学、18:30~21:00。ちょっとしたお手伝いをしている関係。
午前中、出発する10分前に財布がないことに気づく。札入れではなく、小銭入れの方だ。ただ、小銭
が入っているだけなら、あとで探しておこうと思うのだが、一緒に鍵を入れていたからあわてた。会
社のロッカーの鍵と、机の鍵なのだ。その鍵を無くした場合、セキュリティ上大きな事故につながる
可能性はないが(理由は説明できません)、神経過敏なこのごろ、事故報告を出さないといけないと
も限らない。作業着に着替えられなくても、机の鍵が開かなくても仕事はできるのだけれど、前者の
内容が頭をよぎってしまい、ちょっと必死に探した。昨日、帰りにコンビニ寄ったときに置き忘れた
のか?いやあの時は札を出して、おつりを受け取ったから、そのおつりをしまったはずだ。はずって
いうのは、そういう瑣末なルーチンまでは記憶に残っていないから推測。帰宅してから、一時的に寝
床のうえに放り出したのか?どこかに紛れ込んでいるかと思って、かけぶどんをめくりあげてみたが
ない。
あとひとつ、ありそうなところ...。ズボンのポケットだ。昨日脱いでからクローゼットにかけた。
いちばん確率が高いかもしれないが.........
ない。
タイムリミットを過ぎてしまった。どうしよう。やはりコンビニかもしれないと思い、出かけるこ
とにする。しかし、もう一度だけと思い、あるところを探す。
みつかった。
ものを失くしたときに思い出すべきこと「一度探したところを、もう一度さがす」。そう、人間の
行動心理として一度探したところは、二回探そうとしないものだ。これはどちらかというと、かく
れんぼの極意なのだけれど、その逆のことをすれば、何か隠れているものを見つけることができる
はず。
小銭入れはクローゼットの奥、服が積まれた奥で見つかった。ズボンのポケットに入れられたまま
ポールに吊り下げられたときに、ポケットから落ちてしまったのだ。みつかってしまえば、単純な
ことなのだけれど、人間の行動の範囲の外で自然に起きる現象は、まさに思考の範囲の外にあって
それゆえに見つけることが難しい。
ときには思考に頼らず、探し物の原理原則のように、とりあえず何かしたがって行動してみるとい
うことも、必要なのかもしれない。スポーツの素振りのように、発声練習における音感練習のよう
に。ちょっとニュアンスが違うか。まぁ、その原理原則を確立する、見つけることが難しいのだけ
れど。
- 2006/4/15(土)
NC練習15:30~21:15。
これから演奏会まで毎週、練習が続くのだけれど、普通に6時間練習だったりする。つまり合宿と
同じ時間を毎回歌うわけだ。ただ、コンクールの練習とは違うのは、何より楽しい。真剣さや集中
力はそれほど違いはないけれど、楽しいかどうかだけで疲労の度合いがだいぶ異なる。何より、部
屋の散らかり具合が変わる。去年のコンクールのころは、関西も全国もやさぐれ度がMAXで、か
たづけるために力を割く気持ちになれなかったから、デフレスパイラルみたいなものだった。
このまま、演奏会が終わるまで、きれいな部屋であることを目指すのだ。
体調は一進一退で気は抜けないけれど。(特に目肩腰。)
- 2006/4/14(金)
BK練習、18:30~21:00。
車のナンバープレートで、黄色地に黒字は軽自動車だが、黒地に黄色字のものがある。これは
営業用の軽自動車を表している。普通自動車の営業用である、いわゆるグリーンナンバーに比
べると街中でみかける機会は非常に少ない。主に小規模の宅配業者なんかが使っているくらい
だろうと思う。
その希少性?に目をつけたのか、小学生のころに友達に「黒に黄色の自動車を一日に五台みか
けたら良いことがある」と言われた。ただみかけるだけではダメなんだそうである。曰く、
「みかけたら、♪くろときいろ、くろときいろ、一台目、ぱんぱん。♪くろときいろ、くろと
きいろ、あと四台、ぱんぱん、って歌わなあかん」(ぱんぱんは効果音。みかけるたびに二台、
三台と前半の歌詞はインクリメント、後半はデクリメントする)。
その話は以後、その友達からしか聞いたことはなかったが、以来「くろときいろ」の自動車
をみかけると反射的に歌うくせが残った。実際に一台に五台みかけたときも、何度かあったの
で必ずしも実現不可能なことではなかった。良いことがあったかどうかはざんねんながら覚え
ていない。
急にそんなことを思い出したのは、最近あることが通勤路で起こり始めたからだ。みなさんは、
車を運ぶ車を知っているだろうか。自動車工場でできた新車を一度に8台近く、二段重ねにし
て運ぶ大型のトレーラーのような車だ。あの車を街中でみかけることはほとんどないと思う。
そういう意味では、「くろときいろ」よりも、見つけたときのご利益は高いはず。一台見るだ
けでも十分なくらいだ。一生のうち、両手で余るくらい見れれば良いほうだと思っていた。そ
のときがくるまでは。
通勤路の駐車場で急に工事が始まったのが去年の冬で、今年の春に広大な敷地ができた。いっ
たいなんなんだと思っていると、ぴっかぴかのダイハツの軽自動車がずらっと並び始めたので
ある。どうやら、完成車を一次保管する「車場」と呼ばれるものらしい。そして、その車を運
んで来るのが、あの車を運ぶ車なのだ。朝、会社に向かっているとあの巨体が立て続けに三台
も横を通りすぎていったりする。圧倒される。空きがあると、思わず飛び乗りたくなることも
ある。夕方にはまた二台ほど連なって走っているのを駅に向かって歩いているときにみかける。
二日もあれば、一生かかってみれるかという数をクリアしてしまうわけだ。
で、最近考えた。「あれってなんていう名前だっけ?」。子どものころは確実にその名前をし
っていた。たしかすごく珍しくて、格好いい名前だった記憶がある。車を運ぶから、キャリア
カーかな?と大人のわたしは考えたのだが、記憶にある子どものわたしがそれを否定する。さ
てどうしたものか。意味がわからない言葉は辞書を引けば良い、名前がわからないモノの名前
を知るにはどうすればいい。あるいは、むかしはどうしていたか。そう、図鑑だ。いまではま
るで見なくなってしまった図鑑をさがそう。
わたしは、一目散に本屋に向かった。え、毎日向かっているじゃないかって。まぁそうですけ
ど。それはともかく、雑誌のコーナーも、文庫本のコーナーも、漫画のコーナーも見向きもせ
ずに図鑑のコーナーに向かった。ちゃんとあるんだ、図鑑コーナーが。あったありました。乗
り物図鑑、そして「働く車」のページ。
答え「カーキャリア」。
あれ??そんなんでいいのか、なんかこうもっと専門的な名前じゃなかったのか...うーん。
どうも納得できないなぁ....という結果に。期待が大きかっただけに、このあまりに普通な
結果はどうしたことか。推測すると小学生のころは英語を知らなかったわけで、カーはとも
かく、「キャリア」というのは珍しい響きをもって聞こえていたのではないだろうか。英語
を使うことが普通の現代から比べると、当時は社会的にもまだまだ英語は「外来語」の時代
だったように思う。
ところで、図鑑っていうけれども、最近のはほとんどが写真なんだな、モノの紹介が。図説
の部分だけが、文字通り図で。写真製版の値段がそれだけ下がったということなのか、ちょ
っぴりざんねん。図独特の質感というか、フリーハンドの味わいが好きなのだ。と思って、
他の虫図鑑とか、動物図鑑、鳥図鑑を取り出して眺めると、あ、こちらは昔ながらの図の方
が多いくらいだ。そうか、乗り物は動かない写真が撮れるが、虫や鳥は動いていない写真は
撮るのが大変だ。本の構成上、思った構図の写真を得ようとうすればなおさらだ。図の方が
つごうが良いに違いない。
乗り物図鑑、欲しかったのだけれど、その気持ちは抑えて、友人知人に子どもができたなら
誕生祝いにでも贈ってみたいなと思う。誕生祝いだと早すぎるか。でも鉄のエリート教育は
生まれてすぐの方がいいのかも。(←鉄に限定しまうのはどうか。)
- 2006/4/13(木)
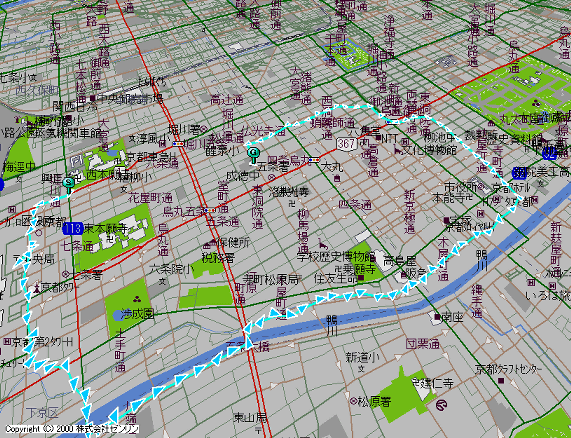
走行距離9.8km、走行時間約30分。
そろそろ自転車のシーズン。風がふけば肌寒いけれど、上着一枚あればいいくらい
だし、暑くて汗だくになることもない。ということで思い立って、帰宅後にトレー
ニングに出かけた。毎日でなくとも、週に2~3回、30分程度の走行が目標。まあ、
これくらいなら続けられそうかな。
自宅を出て、五条→堀川と走行。途中からGPSが電波を拾いはじめた。上の地図
で言うとSと書かれた印がそう。そこから、塩小路まで下がり、塩小路から京都駅
前をつっきって、再び七条へ戻り、川端通りへ。そのまま川端を五条まで北上。
五条からは木屋町に移動して、二条まで延々とつづく夜桜の下を疾走。気持ちのい
いことといったらない。特に四条までの間は、あまり知られていないのかひとも車
も少なく、ほろ酔い加減で歩きたいなぁと思わせる。でも、週末には散ってしまっ
ているか、ぎりぎり残っているかというところだ。
二条で高瀬川が途切れ、桜もそこでお終い。二条通を西進し、烏丸へ。御所(地図
上で右ナナメ上の緑の四角がそう)の南のこの界隈は、夜になると人通りがまった
くなく、自転車散歩にはもってこい。途中、薄明かりの喫茶店やレストランがぽつ
り、ぽつりとあらわれるので、寂しげというわけでもないのが好みである。
烏丸を御池へ、そして再び西に行き、今度は新町やら、西洞院を下っていく。もっ
ともスピードが出て、27~8km/hくらいになる。夜道はスピードが出ているようでも
知らず知らずとセーブしているものだ、という話を聞いたことがある。昼間はこの
あたりは車の行き来が多いので、これ以上出ることはないと思うけれど。
一気に高辻まで下がり、そのまま高辻を東へ。成徳中学の裏のわが家に到着。地図
でいうと、Gの印のところだ。京都の市街地の南東部分を全部囲うような感じにな
っている。これで9.8kmだから、意外と京都って狭いものです。逆にこれだけのス
ケールしかないから、そこにぴったりくるのはやっぱり自転車なのだな。改めて、
実感した。
さて、風呂に入って、今日買ってきたJTB時刻表5月号増刊「鉄道の旅が好き」、
特集さようなら交通博物館(JTBパブリッシング刊。900円)を読もう。
なんて健康的なんだろう。
(この調子で頑張れ山D!)
- 2006/4/12(水)
散髪行けず...帰ろうと思ったら、残業。突発で緊急の残業。水曜なのに。
スタンド、行けず。水曜なのに。
なのに...
のに..
noni.
no
n
「ねじまき鳥クロニクル第2部予言する鳥編」読了。目録の、村上春樹の次に並んでいたのは、
なんと、チェーホフ、ディケンズ、ドストエフスキー。不思議と、おかしな気がしない。むしろ
絶妙の配置とすら思える。ふつうに考えるなら、世界の文豪、日本の文豪といったくくりにある
方が自然なのだが、そういったもののなかに並んでいたならいかに文豪達の作品とはいえ、うず
もれてしまう。それがどうだろう、「村上朝日堂はいほー!」の隣にチェーホフのかもめが並ぶ
と、あらふしぎ。え、これってどんなんやろうと読みたくなってしまうではないか。村上ワール
ドの隣に来る本を見つけ出し、なおかつ読む気にさせる、すごいぞ新潮文庫編集部。
それらのあらすじに並ぶ文字は、「錯綜」「絶望」「忍耐」「逆境」「地獄」「凄惨」。
これらに魅かれるってのは何か問題あるのか。それともその先にある反対のものを求めていると
ということなのか。うーん、どっちだ。ねじまき鳥はどっちへ進んでいるんだ。
などと考えつつ、第3部鳥刺し男編に突入した。
- 2006/4/11(火)
朝、どうにも髪の毛がうざったくなって、もみ上げの部分だけ鋏で切り落とした。あとを髭剃り
で処理して一応体裁は整えておいたので、見た目は変ではなかったと思う。帰宅して風呂に入っ
たとき鏡をよく見ると、切り残した二束くらいがぴょんともみ上げから所在なく飛び出しており
かなり珍妙であった。こんなんで往来を通勤して、仕事してたのかと思うと、おそろしい。営業
職なら切腹ものだろう。アホ毛(あるいはアンテナ)を再び切り落とすと、耳の外には髪の毛が
かかっているのに、頬との間に隙間があるという不思議な状態。これがエアーインテークという
ものか...とちょっと感心したのち、やっぱり明日散髪屋に行こうと決意したのだった。
前にも同じことをしていたような。進歩がないなぁ。
皆さんも、髪の毛はひとに任せたほうがいいですよ。
- 2006/4/10(月)
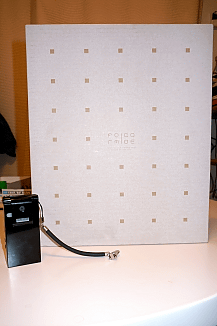
村田蓮爾第3画集「formcode」。
大きすぎて、鞄に入らず。両手に抱えて持ち帰りました。↑の写真は携帯電話との比較。
第2画集と同じく、単なる画集の域を超えていて、ひとつの本としてみても、これだけ充実して
いて、「読みごたえ」のあるものはなかなかないと思う。全体の半分が画集、それに巨大ポス
ター、ブックレット2冊のほか、全体で見ると8~9部構成となっている。本という媒体、紙
という媒体の多様性は、村田氏の活動の全体を投影するのにとても適していると感ずる。
その内容は、とてもじゃないけれどここで紹介しきれるものでもないし、うまく伝えることも
できないと思う。本屋で立ち読みすることができない本なので、できれば完売する前に買って
見て、世界に触れて欲しい。というか、知人友人の皆さんには無理やりにでも見せたい~。
あ、F.F.S XIIもちゃんと買いましたよ。
諸般の事情により、画集もF.F.S.もきちんと読む余裕がないのが悲しい。
- 2006/4/9(日)
NC合宿@新大阪ユースホステル。第二日目。
08:30~10:00 自習
10:00~12:00 練習Ⅲ
13:00~17:00 練習Ⅳ
17:43新大阪発、17:58京都着。
移動による体の負担をなるべく無くしたかったので、「新幹線」に乗りました。一区間だけの
乗車というのは、なんだかかりそめの旅人のようで、なんとなく心情的には肩身が狭く感じる。
だからというわけではないけれど、最前列に座る。目の前が壁の座席は、普段東京へ行くとき
などは、絶対座らないような場所だけれど、座ってみると意外に居心地がよいものだった。たぶ
ん適度な圧迫感が個室のような雰囲気を作り出していたのだと思う。窓の風景を眺めていても、
どこか隠し部屋から、こっそりと外界をうかがっているような雰囲気がして、新鮮だった。
ああ、楽だ。18:30には自宅につく。家の裏にある中学校に知事選の選挙にいってから、ようやく
ひといきつく。と、急激に疲れに襲われる。列車のなかで寝ると確実にねすごすので、眠るまい
眠るまいとしていたことで張っていた気力が一気に抜けたような感じだった。
相変わらずのしんどさだが、最後に練習したアンコールのための曲を思い出すと、元気なれる気
がする。ありふれて、はずかしいような言葉が、ときとしてすごい力を人に与えてくれることが
ある。そういうことを実感できる瞬間があると知っているから、合唱を続けていられるのかもし
れない。(むろん、歌のなかだけで終わって欲しくはない言葉なのだけれど、現実は厳しい。)
肩こりがひどくなってきた。
頭痛薬を飲んで、休みます。
- 2006/4/8(土)
NC合宿@新大阪ユースホステル。第一日目。
14:00~18:00 練習Ⅰ
19:00~21:00 練習Ⅱ
忘れられたかに見えた砲弾型ライト計画は実は密かに進行していた...。
その真実とは!(合宿とは全然関係のない話だ)

真実の断片1

真実の断片2
つづく(...のか?)。
- 2006/4/7(金)
BK練習の帰り、御池にあるホテルの前を通ると「歓迎」の看板が目についた。
「桜の京都七大名所めぐり」様
「オークツアー桜の京都の旅」様
「京の名椿と桜」様
「桜咲く!関西桜スペシャル3日間」様
...最後のって、ほんとうにツアーの名前なのか。TV東京のいい旅夢気分の企画名みたいだ。
くすっと笑ってしまった。集合場所で添乗員が「桜咲く!桜咲くの皆さん、出発で~す」と連呼
している姿を想像してしまう。しかし、3日間も花見を続けるツアーって、すごい。いやよく考
えると、桜を見るために京都に来るツアーがこのホテルだけ4件もあるということも十分すごい。
ふだん暮らしていると、身近な範囲、たとえば家の近くの仏光寺の桜、BKの練習帰りの鴨川の
桜、BKお花見定番(?)の御所の桜くらいしか目につかないのだけれど、他府県から人を呼び
よせるほどの桜が、ツアーのひとが押しかけてもまだ余る(仏光寺の桜などは名所であるけれど、
観光バスが来てるというわけではない)ほどの見所が、この狭い京都にあるっていうことを、こ
の「歓迎」に書かれたツアーに教えられたような気がする。
しかし、お花見に絶好と思える明日、あさってはNCの合宿なんだな、これが。
日曜の練習が終わってから、どこかにひっそりと咲く夜桜でも見に行きますかね。
- 2006/4/6(木)
昨日の録音の編集作業。昨日やらなくて正解だった。しばらくやっていなくて感覚がつかめ
なかったかせいか、二時間もかかってしまった。曲は11曲だけど、2テイクとった曲があ
ため録音時間は一時間(曲の総演奏時間は30分)。過去もだいたい、録音時間の二倍の作業
時間を見込んでいたはずだ。
ノートPCのHDDとメモリでは安定性にかけるので、ほんとはデスクトップで作業がした
いところなんだけれど。はやくインテルマックを買うべきなのだろうか?。フォトショップ
はロゼッタで動かせばいいという気がする。どうせあまりエフェクトは使わないので、影響
は少ないように思う。そろそろマック系の雑誌を一度買ってみることにする。
疲れた。新年度は、長時間の運営方針がやたら多くて、拘束時間が長いのが困りもの。上部
組織とは別に下部組織の説明会もあるのだから、重複する部分ははじめからどちらかのみで
やるか、省いてくれればいいのにと思う。全部出ていると、仕事にならない。ひとはえらく
なると、昔感じていたことを忘れてしまうのか、それとも新しい何かをそこに感じ取るよう
になってしまうのだろうか。無駄だとはいわないけれど、無駄が容易に潜みそうな気はする。
眠ります。きょうはほとんど独り言で申し訳ない。
- 2006/4/5(水)

SONY TCD-D100+SONY ECM-MS907×2
依頼をうけて、今日、Ensemble Vineの練習を録音しにいった。そのときの機材がこれ。
DATレコーダーとマイク2本。なぜマイクが2本あるのか。LとR独立?いや1本でステレオ
録音できるマイクです、これは。1本は昔から使っているもの、1本は今日買ったものなのだ。
きのう、テープを買って帰って、家で録音ができるかのチェックをやっていた。テープをいれて、
マイクのまわりをぐるっと回って、「マイクの右にいます」「左にいます」とテストをしたのだ。
で、再生してみると雑音が入っている。それどころか、そのうちに右音声しか入らなくなってし
まったので、あわてた。マイクのケーブルが断線したものらしい。向きを変えたり、古典的な方法
だがぶったたいたりすると、調子がよくなったりしたが、やはりだめ。こんな調子では大事な録音
ができない。
時間があれば、修理にだせるような故障だが、録音は明日。背に腹は代えられず、今日仕事帰りに
寺町に寄って、同じマイクを買った。すこしは安くなってるかなぁと期待したのだけど、昔買った
ときと同じ値段でショック。これからも使うし、前のは十分もととったし、と自分を慰めながら、
録音現場に向かった。
指定された時間の15分前に着き、外で再度録音チェック...。あれ??、やっぱり右しかとれない。
ショック大!マイクではなく本体に問題があったのか!あと10分では代替も用意できない。くそぉ
と思ったわたしは、やはり本体を殴りつけたり、ふったりして、なんとか解決をこころみる。と殴り
どころが悪かったのか、キュルキュルと異音を発して、テープが停止してしまった。万事休す。
ふたを開けてみると、案の定テープが絡まっていた。DATデッキにはよくあることだが、替えのテ
ープがないから、慎重に取り出す...。と、そのとき、閃いた。原因はマイクでも、本体でもない。
テープが絡まって記録面がぐちゃぐちゃになったから、LRが正常に録音できなかった。おそらく、
テープが折れて、R側に偏ったのだ。昨日、チェックをするとき、テープの先頭の方でなんども巻き
戻していたから、なんどやってもだめだったのだ。では、そもそもテープが絡まった原因は何か。そ
れもわかった。電池切れだ。
昨日も、今日もACアダプターではなく、アルカリ電池で駆動していたのだが、前に使ったときの
電池が切れかけていたのだ。電池がない=駆動力がないである。駆動力がない場合には、テープの
絡みが発生し易い。
その後、きょうのために買っておいた新しい電池でテストしたところ、なんの問題もなく録音でき
たのであった。
そういうわけで手元にマイクが2本あるのだ。これ、どうしようか。
誰か9掛けくらいで買ってください。箱は捨てたけど、保証書つき。
いいマイクですよ。
補足:むろん練習の録音はきちんとできました。歌い手でもなく、純粋な聞き手でもない、録音の
仕事はなかなか楽しいもの。でも、終わったあと、手のひらにびっしょり汗をかいていたのは、
風邪をひいていたからというよりも、歌っている皆と同じように緊張していたのかもしれないな。
きょうは編集はせずに、きちんと寝て、風邪を治します。
おやすみなさい。
- 2006/4/4(火)
風邪ひきました。
どれくらいの症状かと言うと、寺町電計社で領収書だけもらって、商品(DATテープ)を
もってかえるのを忘れたくらい(お店の人に引き止められた)。
- 2006/4/3(月)
すいませんが、更新休みます。
- 2006/4/2(日)
数日前にお茶葉が切れたので、昼過ぎに高島屋に買いにいくことにした。雨であったけれ
どなんとなく、外に出てみたい気分だった。

途中、寺町にある「あいば」という喫茶・バー・定食屋で、ランチを食べる。学生街にあ
るような感じの、でもやや落ち着いた店内では、食後に本を読んでいる人が多かった。こ
こはおすすめしたい。味はちょっと濃かった。食べている途中に大雨になったので、30分
ほど文庫本を読んですごす。あああ、これはかなり贅沢な時間なのでは?
高島屋地下食品売り場で柳桜園の刈番茶を買う。これでだいたい1年くらいは保つはず。
そのあと、気が向いて、館内を散策することにした。主に、雑貨のフロアをぐるぐるまわ
って、陶器のコーナーによったり、美術品展示のコーナーで版画を冷やかしたりした。デ
パートが日本に誕生したとき、これを「百貨店」と翻訳した明治の人はほんとうにえらい
ものだ。デパートにあるものは、デパートでなくても買える、だからデパートにいかなく
でもいい、とちょっと前まではそう思っていたのだけれど、それは本当ではないだろう。
買わなくても、歩いているだけでも楽しい場所だったのだな。子どものころ、各デパート
のおもちゃ売り場の階を覚えていたことをふと思い出した。
寺町通側からでて、ふと目についた火除天満宮にお参りする。ここはなかなか面白い場所
なのだが、参ったのははじめてだ。

カメラのナニワが入っているビルの一階のわきに、ひっそりと鳥居が立つ。
すぐ横はライブハウス(だと思う)の入り口という、不思議な空間。

なんとビル側面の軒下(!)に、参道が続いているのだ。

その先に突如現れる、お社。境内は小さくてひっそりとしている。でも、奥の方には
きちんとした社殿がそびえる。小さくても、天神さんなのである。
京都にはこんな風に、えっと思うようなところに突然寺社仏閣が建っていたりする。
この寺町通を上がると、四条寺町と新京極通りの間に「林万昌堂」という甘栗屋さん
があるのだけれど、店舗に入って、右側に進んでいくと知らないうちに外に出ていて、
「染殿地蔵院」という安産のお寺に行き着くのである。新京極側からも入れるのだけ
れど、こちらも入り口は狭くて、普通に歩いていると絶対見過ごしてしまう。こちら
のほうが迷宮度はかなり高し。
メジャーな京都観光は飽きたという人にお勧めします。
昨日の補足:
0,0→1
0,1→1
1,0→1
1,1→0
0,0をOK(1)とするならば、組み合わせと結果は上記のようになり、これは論理積
=ANDを反転した形になるので、NAND(論理積の負論理)という。アンケートでは、
両方選択は不可だったが、両方選択しないことは可だったので、じつはNANDが正しい。
- 2006/4/1(土)
今日、あることで、ひとつ失敗したことに気づかされた。まったく、そのように意識してい
なかったので、これはショックだった。確かに自分が悪い。ことの顛末を説明する前に、
言葉の定義からはじめよう。正確には、すでに定義済みのことを説明する。
みなさんは「論理和」という言葉を知っているだろうか。多少なりとも、情報工学を勉強し
たひとならともかく、普通のひとは知らないし、知っているべき言葉でもないだろうが、
その概念というものは、生活のなかで使っている。
スイッチが二つある電灯を想像して欲しい。この電灯はスイッチの組み合わせによって、
ついたり・消えたりするものだと思ってもらいたい。スイッチをONすることを1、OFF
することを0で表してみる。そして、電灯がつくことをやはり1で、消えることを0で表し
てみよう。
スイッチはふたつあるから、ON、OFFの組み合わせは
0,0
0,1
1,0
1,1
の4種類あることがわかる。さて、この4種類の組み合わせに対して、
0,0→0
0,1→1
1,0→1
1,1→1
という結果になること、つまり「どちらかのスイッチがONだったら電灯がつく」場合、
この結果を「論理和」という。ここでいう1、0というのは、「ある」か「ない」かという
ふうに言い換えることもできる。
さて、0,1の組み合わせに対する結果は、上記だけではないはずだ。こんな場合もあるだ
ろう。
0,0→0
0,1→0
1,0→0
1,1→1
これはつまり、「両方のスイッチがONのときだけ電灯がつく」状態だ。このような結果を
「論理積」という。
そして、もうひとつ名前のついている結果の組み合わせがあるのだ。
0,0→0
0,1→1
1,0→1
1,1→0
これはなんと説明したらいいんだろうか?そう「どちらか一方だけがONのとき電灯がつく」
という状態だ。この結果を「排他的論理和」という。
この排他的論理和というのは、身近な考えでいうと二つの選択肢AとBがあったとき、Aを
選択して(1)、Bを選択しない(0)、もしくはその逆はOK(1)だけれど、どっちも
選択しないとか、両方選択するというのはNG(0)であるということを意味する。これっ
てもっとわかりやすい言葉があったはずだ。そうだ、「二者択一」のことだ。
(まぁ、二者択一は必ず選ぶことが前提になっている言葉だから、どちらも選択しないとい
う場合、ほかにわかりやすい言葉があるかというとなさそうな気がする)
さて、長い前置きがあったところで、何を失敗したかの話である。NCであるアンケートを
行ったのだ。NCはこの夏行われる「軽井沢合唱フェスティバル」という催しに参加するこ
とが決まっているのだが、出席人数を知るため、交流会の参加の可否をたずねたのである。
交流会に出る場合、夕食は交流会で出される軽食がその代わりとなり、このときホテルの
夕食はとれない。もし交流会に出ないのなら、ホテルで夕食をとることになる。つまり、
交流会の参加と、ホテルの夕食は「二者択一」なのである。
アンケートを作る際に、「この二つは二者択一」と書けばよかったのに、わたしは「この二
つは排他選択」と書いてしまったのである。「排他選択」とは一般的に定義されている言葉
ではないかもしれないが、ようは「排他的に選択する」=「排他的論理和」という意図でか
いた。
ところが!この「排他選択」の意味がわからない!という人がいたのだ。すくなからず。
言わんとしていることはなんとなくわかるが、言葉として「排他選択」ということが理解
できないと言われたのだ。そのとき、自分が犯したミスに気がついた。
わたしは知らず知らずのうちに、普段仕事で使っていたり、学生のときに身につけた学問
体系の専門用語で思考していたのである。(「論理和」や「排他的論理和」というものは、
情報工学(数学の一部として習うこともある)の言葉なのである。情報系の学部でなくて
も、電気工学系の人間においても必須の言葉であり、概念である。)
そのことが悪いというのではないが、専門用語は同じ概念を共有できるコミュニティでしか
正しく理解されない。だから、一般的な場においては、その言葉によって思考された概念は
誤解されうるということに気づいていないといけなかったのだ。言葉を理解するには想像力
が必要であるけれど、その言葉が想像の及ばない専門領域にあったとき、想像のしようがな
いからだ。
「二者択一」の代わりに、わざわざ「排他選択」と書いたのではない。このような選択にお
いては、それは「排他的」だなぁと普通に思ったのである。先に書いたように、どちらも選
ばないこともありうるから、二者択一とは違うと考えたのかもしれない。
しかし「排他的」とは辞書で引くと「自分や仲間以外の者を排斥する傾向のあるさま」とな
っていて、転じて「どちらか一方」という意味は載っていない。一般的には通用しない使い
方なのである。そのことにまで、考えをめぐらすべきであったのかもしれない。ひとに何か
をたずねるのであるから、見慣れない言葉、わかりにくい言葉はないかと点検すべきだった
のかもしれない。
落ち込んでいる、というのではないが、とにかく最初に書いたように、ショックな出来事で
あった。言葉というものは、どの程度浸透すれば、一般的といえるのか。そういうことを考
えさせられる契機にもなった。少なくとも、情報工学系の言葉は通用しないんだ、というこ
とがわかったので、それを収穫とする。
- 2006/3/31(金)
【今日買った本】
「マリア様がみてる くもりガラスの向こう側」、今野緒雪著。コバルト文庫。419円。
本買いすぎ!といわれても仕方がないありさま。言い訳のしようもございません。
でも、ちゃんと全部読んでる。ただ、「マリみて」と「ねじまき鳥」を並行して読むのは
難しいので、「ねじまき鳥」第2部は、2章まで読んだところで一時停止している。マリ
みて集中モード。
文庫本には二種類あると思う。一気に読んでしまって、余韻を味わうタイプと、一気によ
んでしまうのがもったいなくて、すこしづつ浸透させるように読み進めて、感想を蓄積さ
せていくタイプ。この見極めはかなり重要である。どちらが良いとか、好きというのはな
くて、いまどちらを読むべきかを考えるところに醍醐味があると思っている。買ってから
少し寝かしたり、通勤電車限定にしたりと、その戦略は多彩なのだ。
ただ、私の場合、通勤(行き)のときは、本は読まない。仕事の前に読んでしまうと、本
の楽しさが半減するような気がして。余韻に浸る間もなく、混雑した改札を抜けて、ひと
で溢れかえる狭い道を進んでいかなくてはならない。そんなことを気にしながら本を読む
のは嫌なのだ。「現実」との切り替えがドラスティックすぎるのだ。朝は。本はゆるやか
に読みたい。旅の空で、伏せては景色を見、上げては読み、旅の空で読了したい。
- 2006/3/30(木)
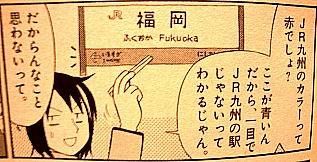
菊池さん、もう立派なテツですね。「鉄子の旅」第5巻p19より。
(まんが:菊池直恵、旅の案内人:横見浩彦。小学館。562円。)
新しいシャンプーとリンスで髪を洗っていたときに思った。「社会見学に行きたいなぁ」。
小学生のとき、一番思い出深いのはただの遠足よりも、社会見学だった。おぼえているのは
明治製菓でカールとチョコレートの、サントリーでビールの製造現場を見たこと。明治では
お土産にカールをもらい、サントリーではなぜか甘酒をもらった(お察しの通り、わたしは
飲まずに友達にゆずった)。どちらも、見学設備を完備した子供心にも立派だーと思える、
工場であった。いまでも、小学生は社会見学に行くのだろうか?
ところで、シャンプーとリンスを見て思ったのは、シャンプーとリンスに両方に香りがつい
ている必要があるのかな、ということだった。シャンプーは単体で使うことがあるにしても、
リンスはたいがいシャンプーとセットで使う。ほかのひとのことはわからないけど、一般的
にそうですよね?で、リンスはシャンプーのあとに使うから、リンスに香りがなくても、
シャンプーの残り香で十分じゃないのか、いや両方に香りがあるのはむしろ、香りが混ざり
合って、本来意図した香りがでないのではないのか。そんなことを考えたのである。
もしかしたら、両方が混ざることを前提に作られているのか、それとも、時間差によって香
りの二重構造ができるのか。考えだすときりがないけれど、そんなことは専門家でないとわ
からないことだろう。
そんな質問を専門家に聞くには?→社会見学がぴったり!という発想で「行きたいなぁ」と
思った次第。『せやねん』でかつみ・さゆりがやってる”メチャ売れ”のコーナーみたいな
のが理想かなぁ。
- 2006/3/29(水)
風は冷たい、でも今日少しだけのぞいた日差しのなかを通る風は、やはり春の匂いが感じられ
て、ああ新しい季節なんだと思わずにはいられなかった。という感慨も、帰宅するときの木枯
らしのような冬の風に吹き飛んでしまった。いったいどういう気候なんだ...。
スタンドで夕食。後、ジュンク堂でひとしきり過ごす。本屋にいるときが一番幸せなのかもし
れない。
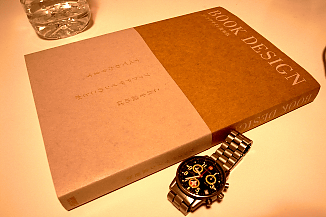
「ブックデザイン復刻版」、ワークスコーポレーション刊。2500円。
DTP WORLDという雑誌の別冊、BOOK DESIGN vol.1とvol.2を再編集し、合冊したもの。ブックデ
ザインとは、単純に言えば、本の装丁のことであるが、装丁にとどまらず、本文構成やレイアウト
にまで含む場合がある。これまでも何度か、装丁にかかわる話をしてきたが、この本のもととな
った本の存在はしらなかった。
装丁に関する本というものは結構出版されているのだが、羅列的、網羅的な本が多く、いまいち
読み応えにかけるというか、同じ構成だと、よほど文章が面白くなければ飽きてしまうため、買
ったことがなかった。しかし、この本は、もともとがムック的なもので、読ませる見せるという
点では、他の本にはない面白さ、値段に見合った時間を提供してくれるように思えた。中身を見
てみよう。
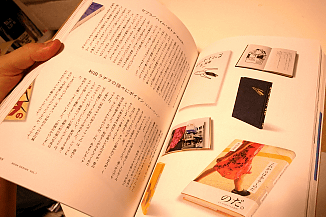
特集がいくつかあり、「五感、触感を刺激する本」では、紙質、判形、デザインに凝った本たち
を、カタログ的に紹介。見ていて楽しい。そして二人の装丁家を取り上げた特集「池田進吾のブ
ックデザイン」と「大久保明子のブックデザイン」が、この本の中核を成している。以前紹介し
た南伸坊の「装丁」という本もそうだったが、デザインした本に、それぞれコメントが書かれて
いるというスタイル。コメントといっても文字数は多く、ひとつひとつの作品に対する思い入れ、
経緯なんかが細かく丁寧に語られているのがいい。そして、もうひとつ、「装丁」になかったも
のがあって、それはその本の著者自身によるコメント。本が読んでもらえるかどうかというのは、
実は装丁によるところがとても大きい、だから著者がどういう風にその本を思っているかという
のはとても興味深い。だって、原稿用紙やワープロのテキストだけでは、それは作品かもしれな
いけど、「本」じゃない。「本」をつくるのは、著者が大本だけれど、著者だけでは成り立たな
いってことを思い知ることできる。
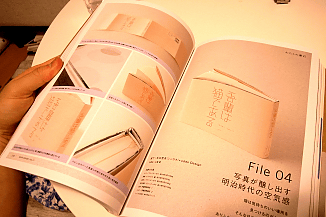
もうひとつ紹介したいのが「わたしの漱石」という企画。4人のデザイナーが、「我輩は猫であ
る」のブックデザインをするというもの。「猫」、皆さんはどういう形態で読まれただろうか。
わたしにとっての「猫」は、岩波文庫なのだ。白い表紙にあらすじ兼解説があり、背表紙が緑色
のアレです。現代作家の小説ならば新潮文庫なのだろうけど、「猫」はもはや古典であるから、
古典といえば、岩波なのだ。字が異常に細かいところと、独特の活字が好き。で、そういう長年
の固定されたイメージからすると、ほんとうに此処でデザインされた四冊は目からうろこである。
四冊とも欲しい、そうおもわせる。装丁はもちろん、本文をどのように組むかまでデザインされ
ていて、なかには横書きのものもあるし、各ページごとに写真をいれていたりする。同じ作品に
対していろいろなアプローチがあるという点では、なんだか合唱の課題曲のようだけれど、ここ
まで変化のあるものは、合唱ではなかなかやれないだろうなぁ。
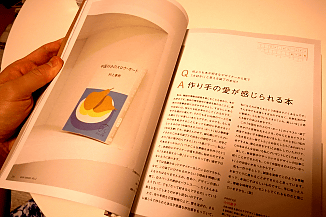
さて、立ち読みしていて、買おうかなぁどうしよっかなーと思っているとき、ふいに背中を押す
ものに出くわすことがある。この本は半ば買うつもりであったけれど、そんなふうに「ふい」を
つかれたのが、うえの写真の記事だった。
「タテヨコナナメ装丁談義」と題されたエッセイ数編。そのなかのひとつ。『Q何よりも本好き
のデザイナーから見て「大好き!」と思える装丁の本は?」という問いに対して、その回答は、
『A作り手の愛が感じられる本』。そして、その本として紹介されていたのは村上春樹「中国行
きのスローボート」だったのだ。本好きのそのグラフィックデザイナーは、この本の装丁を見て、
デザイナーの道を志し、プロになり、後に装丁とイラストを手がけた安西水丸氏に会う機会をえ
たという忘れえぬ本だった。
わたしが「ふい」をつかれたのは、最近村上春樹の本を読んでいるからというのもあるけれど、
もっと単純に「中国行きのスローボート」を持っていたからだ。そして、デザイナー氏と同じよ
うに、思い出のある大事な本だったからだ。
同じ本に対して、なんらかの思いをもっている人がほかにもいる、ということを知るのは、なん
だかうれしく思うのと同時に、自分ひとりのひそやかな秘密ではない(わたしだけがしっている
みたいな感覚か?)ということをも知らされることでもあり、少々複雑な思いがしないでもない。
でも、まぁこうやって紹介されているのを見るのは、悪くない。いや、良い。じぶんの思いをこ
こに書くことはしないけれど。
ちなみに、写真のものは、中公文庫版でデザイナー氏が見たのもこれ。わたしがもっているのは
ハードカバーだが、装丁のイラストはまったく同じもので、タイトルデザインも同じである。だ
から一瞬、文庫版とは気がつかなかったのだけれど、よく見ると違うポイントが一箇所だけある。
わかるだろうか。少し大きな本屋さんに行って、ハードカバーと文庫の両方を見比べてください。
さて、いま迷っている。ひさしぶりに「中国行きのスローボート」を読み返すか、それとも今日
買ってきたもう一冊の本、「ねじまき鳥クロニクル 第2部予言する鳥編」を読むかについて。
どうしよっかなぁ。
- 2006/3/28(火)
携帯電話に人工呼吸している夢を見た。正確には中に入った水?を吹き出そうとしていたよう
である。努力の甲斐なく、その電話では連絡が取れないことがわかるというところで、つぎの
夢に移ったと思う。たぶん。というように変な夢を見続けたせいか、ほとんど休んだ気がしな
いのだった。そろそろまたマッサージに行かないといけないなぁ。
ずっと前から挑戦していて、成し遂げられないことがある。会社のトイレにあるトイレットペ
ーパーは、Pulptexというメーカー製のガードにくるまれており、そこにはペーパーが二巻格納
されている。右側のペーパーを使い終わると、左のペーパーを心棒に沿ってスライドさせると
いう仕組みになっている。同じものを見たことがある人もいると思う。左側は閉じられていて、
右側だけが開放されている。しかし、右側は芯の近くまでガードが張り出しているため、芯の
状態になるまでガードの外に取り出すことができず、また逆に外から新たなペーパーを差し込
むことができない。ここで、当然な疑問が浮かぶ。いったいどうやって、ペーパーを交換すれ
ばよいのか?
どこかを押したり、引いたりすればガードがパカッと開くなり、左右どちらかへスライドする
だろうと、トイレにこもるたびに、あちこちいじったり、上からみたり、下から見たり観察し
ているのだが、一向に手がかりがつかめない。簡単に取り外せるようなら、いたずらされてし
まう(わたしがそうなのか??)だろうし、どこかに工夫があると睨んでいる。もしかしたら
特別な冶具が必要なのかもしれない。ひとつだけ手がかりがあるとすれば、清掃の人が交換し
ているときの音である。かなり豪快な「ガチャン、ガチャン!」という音をさせて、開放?し
ているので、もしかしたら力任せにやるのがいいのかもしれない。
とはいっても、プラスチック製なので壊してしまうとことだ。ましてや、ケガなんかしてしま
ったら、理由を説明しにくい。なんでそんなことやったんだといわれても、なにか仕掛けがあ
れば解明したくなるのは、人としての道理じゃないですか、なんて言い訳は通用しないであろ
うし。
交換しているところを見れば、仕掛けがわかるじゃないかとお思いだろうが、それは面白くな
い。知恵の輪と同じで、自分で解を見つけるから楽しいし、達成感がある。そんなところに力
をそそがなくても、仕事をして達成感を得ればいいという気がしないでもないが、頭の体操、
息抜きということで許してください。これならニンテンドウDSがなくてもできるし、電源も
不要。
さあ、君もチャレンジ。
- 2006/3/27(月)
仕事、期末のため、技術資料2本を片付ける。文章仕事はプログラミング以上に目と頭と集中力
を使うのか、きょくたんに疲労。目の周りにおもりをつけているみたい。目薬と頭痛薬を併用中。
【今日買った本】
「新世紀エヴァンゲリオン10巻」、貞本義行著、角川書店。540円。
いつのまにやら、連載11年。早いものだ...。
【今日予約した本】
村田蓮爾第3画集「formcode」、ワニマガジン社。9975円。
意外と遅れずに発売される模様。というか、ほんとは3/25発売のはず。恵文社で予約すると、
4/8のサイン会(なんと、村田蓮爾が長岡京にやってくる!前代未聞)に参加できるのだけれ
ど、その日はNCの合宿なのだった...。16:00から代わりに行ってくれる人募集。
【今日発売日を知った本】
「F.S.S. XII巻」、永野護著、角川書店。4月10日発売。
3年ぶりの新刊。こちらは連載20年。こうなったらどこまでもついていく所存。
あしたは一時間遅く出社しても構わないので、早く寝て疲れをとりまする。
あしたはあしたでハードな予定。
- 2006/3/26(日)
旧の携帯電話を充電する。きのうの食事の話のなかで、すこし話題になって、気になったからだ。
携帯電話を替えるにあたって気になっていたことに、過去のメールは新しい携帯電話には引き継ぐ
ことができないということがあった。少なくない記憶がそこにはつまっていて、それをときどきは見
返してみる、ということは皆がやっていることなのだと昨日知った。文面だけでなくて、写メール
のアドレスなんかもある。少し前、違うキャリア同士の写真の交換は、サーバーのアドレスを参照
することでやっていた、それである。一応期限がついているのだけれど、実は何年かたっても見れ
るものもあった。これなんかはURLを写し取ればいいのだけど、メールそのものが消えてしまった
らどうしようもない。そう、ほおっておけばいつかメモリーが消えてしまう。
じつは、買い換えてからしばらくは旧の方も充電していたのだけれど、あっという間に電池が切れ
るので、いつしかやめてしまっていた。よく考えると、旧の方は「圏外」扱いになっているため、
常に電波を受信する状態になっていたのだ。だから消耗が激しかった。充電が終わったらOFFに
しておかないと。
きょう、充電をはじめたときなかなか電源がオンにならず、ああもうだめなのかなとあきらめかけ
たのだけれど、1分ほどすると見事よみがえった。二~三週間は切れていたはずなのに、えらいこ
とだ。
ところで新しい携帯電話はF○MAなのだが、電波の入りがやはり弱いせいか、M○VAに比べる
と電池の減りが極端に早い。いくら機種そのものの待ち受け時間が長くなっても、受信感度が悪い
場所での電力消費は抑えようがない。携帯電話メーカーに過酷な要求を出すのなら、キャリアはそ
の責務として、受信地域の拡大にもっと積極的に努めるべきだと思うのだけれど。高周波なので、
直進性が高いから仕方がない?(←フィクション。でも言いそう。)そんなこと一般消費者には関
係ない話なんだけどなぁ...。
- 2006/3/25(土)
NCさくらコンサート@城陽市文化パルク。
13:00~17:30、準備・リハーサル。
18:30~20:00、コンサート。
20:30~22:30、友人と食事・歓談。
ひとつきぶりのコンサート。長丁場でした。お客さんひとりひとりを出口で見送ったというのは
初めての経験かもしれない。演奏を終えて、袖にひっこんだままというのは何か、CDでいうな
ら、演奏の部分だけが収録されているような気がする。こうやって、直にお客さんと交流を持つ
のは、演奏のあとに拍手まで収録されているライブCDみたいなもので、なんていうんだろう、
血が通っているような、そんな気がする。わたしは後者の方が好きだ。CDでも演奏会でも。
といっても最近は、マネージの後片付けが多くて、艦を最後に出るのは艦長の役目とでもいうか
マネージのチーフとして、最後にホールを出ることが続いていて、会場を出るお客さんはもちろ
ん、楽屋口待ちのお客さんや友人すら帰ったあとということが多かった。だから、きょうみたい
にあとのことを心配せず、皆と一緒に見送りができたのは、とても嬉しいことだった。
ああ、しかし食事をしているときは全然気づかなかったのだけれど、こうやって帰宅すると、
疲れていたんだなぁと気づく。えらく眠いよ。

ソフトフランス練乳パン+もちもちくるみパン
最近気に入っている、朝食の組み合わせ。フランスパン生地で噛み応えを、もちもちパンで、
もちもち感覚を堪能できる(もちもちという言葉以外で表現できない。それがもちもち)ベス
トコンビといえよう。
明日の朝を楽しみにしつつ、きょうは休むことにする。
おやすみなさい。
- 2006/3/24(金)
「ねじまき鳥」を買った際、「LOVE書店!」というフリーペーパーをもらった。本屋大賞実
行委員会が発行する情報誌で、表紙は上野樹里(いやぁ、女性はほんとうに髪形が変わると別人
のようですね)。
特集の「小川洋子と甲子園を探検」のほか、けっこう読ませる内容。その最後の方に、2006年本
本大賞ノミネート11作品の紹介と、書店員の推薦文の一部が載っていた。じつは、何週間か前
にノミネート作品一覧をネットのニュースで見かけていたのだが、ここでもう一度見返して、改
めて「面白くないなぁ」と思った。そして、第3回目にして、本屋大賞はちょっと違う方向へ向
かいつつあるように思えて、その将来を(勝手に)危惧しはじめた。
ノミネート作品と作者を挙げてみよう。
・「県庁の星」、桂望実(小学館)。
・「告白」、町田康(中央公論社)。
・「サウスバウンド」、奥田秀朗(角川書店)。
・「さくら」、西加奈子(小学館)。
・「死神の精度」、伊坂幸太郎(文藝春秋)。
・「その日のまえに」、重松清(文藝春秋)。
・「東京タワー オカンとボクと時々、オトン」、リリーフランキー(扶桑社)。
・「ナラタージュ」、島本理生(角川書店)。
・「ベルカ、吠えないのか?」、古川日出男(文藝春秋)。
・「魔王」、伊坂幸太郎(講談社)。
・「容疑者Xの献身」、東野圭吾(文藝春秋)。
以上、11作品。なお、わたしは上記のどれもまだ読んでいないので、以下に書くことは、本の
内容から考えたことではないことを断っておきます。
さて、ノミネートを見て、なぜ「面白くない」と思ったのかだが、このリストを見ただけで一目
瞭然のことがあると思う。本屋大賞はそもそも、本を売る現場からの「この本を読んでほしい」
「この本は(売れてないけどイイ本だ)だから、もっと売れていいはずだ!」という、出版業界
や一般読者に向けたメッセージだったはず。つまり、この大賞がきっかけで本や、作家が多くの
人に知られるになればいいという目論見が含まれていた(予想)。ところがだ、このリストを見
てわかるとおり、大半が「すでに売れている本」なのである。
「県庁の星」は映画化されており、内容が単純ありきたりのサクセスストーリーで(あらすじか
らしてわかる)、いまさらどうして、本屋大賞に入ってくるのか理解に苦しむ。本好きのひとが
わざわざ読む本でもないだろうし、本を読まないひとがこの本を読んで、さらに別の本への世界
が開かれるかといったら、疑問だろう。ペーパーに載っていたある書店員の推薦文もひどい!
それから、「東京タワー」。これは内容的にはあちこちで褒められているようなので、ひどい本
というわけではないだろうけど、どちらかというと世間的には「タレント告白本」と同系列の扱
いで、しかも泣かせる話だというから、なにもしなくても売れている。どこの本屋に言っても平
積だし。リリーフランキー氏が、作家としてコンスタントに活動を続け、小説を出し続けている
なかでの、ノミネートなならば個人的には納得もいくのだけれど、これを大賞にしてしまったら、
なんだか白けてしまう。
この2冊を推薦した書店員は、ミーハーすぎる。単に「感動したから」「おもしろかったから」
という理由で推薦するのなら「書店員が選ぶ」という意味がなく、あまりに見識が低すぎる。
つぎに、町田康、奥田秀朗、重松清、東野圭吾の4人の作品についても、すでに売れていること
に変わりはないが、事情が若干異なる。町田康は、芥川賞、そのほかの3人は、すでに直木賞を
受賞している。芥川・直木賞に権威を見るかはともかく、売れる本という意味では出版社にとっ
てはこのうえなく重要な「記号」であろう。そういう人たちに、本屋大賞をあげちゃっていいの
かと思うのだ。もっと、若かったり、中堅で、1~2の賞は取っていて、実力はあるけれど、知
名度はまだまだって人の作品を見つけ出すべきじゃないの?って思うのだ(奥田秀朗は知名度低
いかも)。
さて、伊坂幸太郎は二冊ノミネートされている。これは票が割れてしまうであろうということと、
最近出版点数が多く、過去の本屋大賞でもノミネートが多いので、知名度が上がっていて、そう
いう、やや常連化したところが、個人的に面白みに欠けるなと思わせる。つまり、本屋大賞を受
賞したとしても、東野圭吾が直木賞をもらったみたいなもので、「いまさら」感が漂うのだ。
残るは「さくら」「ナラタージュ」「ベルカ、吠えないのか?」である。この三作品くらいでは
ないだろうか、本屋大賞のノミネートとして「面白い!」と思わせてくれるのは。知名度、これ
からの期待度という点から見て。「さくら」の西加奈子以外のふたりは、そこそこの受賞歴があ
るのに、一般への浸透度は低いし。(といっても、古川日出男は推理作家協会賞とSF大賞まで
とっている)
と、「本屋大賞らしい」本や、作家がこれだけしかいないというのが、面白くないなあと思った
理由である。もっと他にあったんじゃないだろうか。どうも、今回のノミネートは書店員の本に
対する愛情とか、作家への思い入れが前回に比べて薄れてしまっているように感じる。「本を読
まない一般人」的な視点に毒されているというべきか。まったくの無冠で、知名度もなかった
恩田陸を「夜のピクニック」の大賞で、売れっ子に押し上げた本屋大賞と書店員はどこにいった
んだ、とざんねんに思う。たった一年前なのに。
もし、この傾向が来年度も続くようならば、早晩本屋大賞は、書店の売り上げトップ10などの
ランキングとまったく同じ本が並ぶことになってしまうような気がする。
わたしが本屋大賞に求めているもの、それはすでにもう、ある書店員さんが記しているので、そ
の文を引用しておきたい。昨年の本屋大賞第3位の「家守綺譚」(梨木香歩、新潮社)の推薦文
である。
『私は本屋大賞の一位に恋愛小説を据えたくはない。なぜなら恋愛小説は、世代、性別、嗜好が
かなりはっきりと分かれてしまうものだからだ。そしてさらに言うならば、あまり悲しみややる
せなさに満ちた作品も据えたくはない。もちろん、そのどちらも否定するつもりでもない。ただ
私にとっての理想の本屋大賞受賞作とは「世代と性別を問わず、おすすめできる作品」だという
ことだ。』(山口由美子さん/優文堂SBS店)(本の雑誌増刊本屋大賞2005、P23より引用)
- 2006/3/23(木)
今日のお酒:司牡丹船中八策。辛い。あまり、わたしにあっていなかったようだ。あとになって
きいてきた。飲んでいる(ふたくちくらい)最中は気がつかなかった。めがかすむ。やはり、ア
ドバイスなしにのもうとしてはいけないな。
すいませんが、今日の更新は休みます。
- 2006/3/22(水)
夕方から雨。
きょうは二つある仕事のうちの片方で詰まってしまい、うーん、うーんとうなりながら考えてい
たら定時になってしまった。考えた甲斐はあって、解決はしたのであるが、もう片方の仕事がま
ったく進まなかったのが気がかりであった。残業したかったのであるが、今日は定時規制日なの
でいたしかたない。真剣に仕事をしているときの一日とはえらく短い。
昨日、「老ヴォールの惑星」を読了したので、次なる通勤用の本を探す。ちなみに、残り二編の
「幸せになる箱庭」「漂った男」、いずれも日常では考え得ない状況下を描いたもので、想像力
と、思考力をかき立てられる名品だった。日常を生きるということの意味をこれほど深く掘り下
げることができるものなのか。読みながら何度も、うなってしまった。SFを読まないひとにこ
そ薦めたい。
さて話戻って、次の本のこと。以前話した「村上ラヂオ」を読み始めたころに、気になることが
あって、その解決のため村上朝日堂を順次読んでいく計画を立てた。これでは、なんのことかわ
からないだろうが、説明するほどのことでもないので、聞き流してください。とにかく、村上朝
日堂を読むことにして、きょうは「いかにして鍛えられたか」を手に取ったのである。これで、
ミッションコンプリートかと思われたのだが、どうもわたしのなかの本の虫センサーが、ささや
くのだ。いまは、小説モードであると。
ながらくエッセイモードが続いていたのであるが、「老ヴォール」の圧倒的な力のせいか、小説
モードに完全に切り替わったようなのだ。「いかにして鍛えられたか」は、ちょっと立ち読みし
ただけで、面白いのがわかる。しかし、いまはどうしても、長くて連続したものが読みたい、と
本の虫が告げている。じゃあ、どうすりゃいいのよと独りで会話していて気がついた。村上春樹
の小説を読めばいい。目の前にあったのが、「ねじまき鳥クロニクル」だった。
なぜ、この小説だったかというと、ひとつは”クロニクル”という言葉がなんとなく昔から好き
であったからという単純な理由。この単語が発する、音韻が気に入っている。エンサイクロペデ
ィアという言葉も好きなので、cl音に魅かれる傾向があるのかもしれない。もうひとつは、裏表
紙のあらすじが気になったからだ。この本は第一部、第二部、第三部の三冊に分かれている(た
しかハードカバーのときもそうだった)のだが、そのすべてのあらすじが、本文の引用なのだ。
つまり、あらすじじゃない。タイトルしか知らず、一応どんな話か確かめてみたいと思って、第
一部を見たら、そんなありさまで、まったく内容がわからない。わからないけれど、なにやら、
不可思議な世界でおもしろそうである。じゃあ、第二部ならちょっとは載っているか?と思って
慎重に裏表紙をめくった。慎重なのには理由がある。分冊されている小説のあらすじは、その巻
の内容に即したものになる。だから、最悪前の巻の筋がわかってしまうという危険を秘めている
のである。これにはよくよく注意せねばならないし、編集者もそこのところは注意して欲しいの
である。ともかく、結果は第二部も「本文より」なのだった。
第三部は、すばやくめくったが予想通り、引用だった。あらすじを書くところが三箇所もあるの
に、どれひとつとしてあらすじでない。つまりこれは、あらすじを書くことができないのか、あ
らすじを書くことに意味がないのかどちらかであろうと想像した。これはもう読んで確かめるし
かないなと思った。第一部のはじまりを少し読んでみると、「僕」がスパゲティをゆでていると
きに見知らぬ女から電話がかかってくる。女は「10分間、時間を欲しいの」といった。-これ
は一種のSFではないかという感触がした。だから、読むことに抵抗をもたなかった。たぶん、
読みすすめていけるだろう。
新潮文庫を読み始めるときの作法。しおり紐がはさまっているページを開き、内容は見ないよう
にさっと、紐を抜いて、見返しに挟み込む。阪急電車のなかで、いつものように儀式を済ませて
から、読み始めた。そういうわけで、しばらくは「ねじまき鳥」にかかりきりになってしまいそ
うで、だから「村上朝日堂」計画は遅れる見込みなのだった。
予告:今年度の本屋大賞ノミネートについて、あれこれ考えてみた。
きょう書くつもりが、前半が長くなったので延期。
大和建造進捗:後部艦橋完成、って全然進んでねぇ。
- 2006/3/21(火)
彼岸の中日だというのに、この気候。いったい春はいつ来るのだろうな...。
腰のこと(テーピングとバンテリンで対策中)もあるので、あまり出歩く気にもなれず、部屋の
なかでできることを探した結果、こういうものを買ってきた。
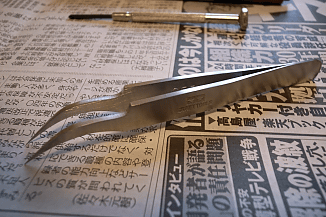
精密ピンセット(つる首タイプ)。1260円。
店に売っていたものでは、一番高いもの。その次はこの半額。見た目で高いほうを選んだ。外見
で判断することの理由は明らかである。高いほうが明らかに「仕上げ」がいいからだ。こういっ
た単一機能の「道具」の場合、構造のシンプルさゆえに、そのグレードというものは、どれだけ
手間暇かかっているかということで決まる。手間暇かかっているものは、使い勝手もそれだけよ
い。そして、手間暇の度合いというものは、細部に宿っているのだ。外形的には一見同じように
見えても、エッジ、R、表面の加工、それらわずかな外見の違いが、使いやすさを決定的に変え
てしまう。人間の感覚が道具に求めるのは、相当シビアなものなのだ。
さて、この道具、いや工具といったほうがいいか、を使って何を作るかというと、以前予告して
いたとおり、コレです。
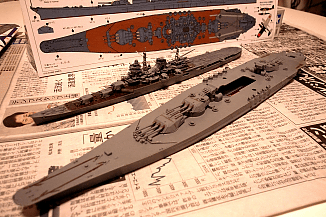
1/700、日本戦艦大和(やまと)。TAMIYA製。2160円。
近頃は、大和を「だいわ」なんて読まれかねないので、一応ルビを振っておいた。そういえば、
うちの妹はむかし、「日本武尊」を「にほんぶそん」と読んだことがある。古事記でも読まない
と出てこないから仕方ないといえば仕方ないのかなぁ。
で、戦艦の大和であるが、でかい。全長37cmもある。隣に「最上」を並べると、彼我の差は
一目瞭然。だいたい、最上の主砲よりも、大和の副砲の方が大きいじゃないですか。あと気がつ
いたのは、全長に対して、全幅が長めなのだということ。最上のバランスで見るなら、大和はも
っとほっそりしていていいはずだが、解説書によると安定性を考慮してこのようなバランスで
建造されたらしい。こういうことは、模型だからこそわかることか。
今日の建造時間は約4時間。写真の状態になるまで4時間。たいして進んでないように見えるの
に。この後の艦橋まわりの組み立てがどれくらいかかるのか想像もつかない。集中力を分散させ
つつ、気長に取り組む予定。艦船模型はあせっちゃだめということが、前回でわかったから。
ちなみに、ピンセットはどういうとき使うかというと、こういう部品をつかむときに。
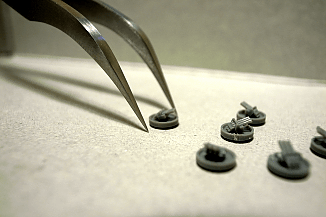
写真に写っているのは、機関砲座。ちなみにこれでもまだ大きい方で、この砲座自体2つの部品
からできているのだ。こんなのを相手にしているのだから、気長にもなる。
- 2006/3/20(月)
最近、わたしの部屋はややきれいである。細部を見ると整理されていないものが目についたり
するが、整理と整頓を切り離すことにした。どちらもできていないよりか、どちらかでもでき
ていたほうが、生理的にも精神的にも健康な状態を保てると発見したからである。整理とは分
類することであるが、わたしは大くくりな分類が苦手である。捨てるもの、捨てないものとい
う二元論に行き着かないのである。捨ててもいいものに近いものから、捨ててはいけないもの
の間に、何千何百という区分けをつくってしまうのだ。捨てる、捨てないは喩えで、捨てない
と生ゴミまでとっておくことになってしまうが。とにかく、分類が細密すぎて結局整理になら
ないというのが、結論である。
では、整頓とは何か。ものごとを整えるのだ。整えるというのをわたくしのなかでとらえなお
すと、1ものの方向が定まっている、2格納する場所が限定されている状態、ということにな
った。なので、本は部屋のなかに積み上げても良いが、方向をそろえて、個々が直角に並ぶよ
うにした。書類もそう。つぎに、部屋のちゃぶ台のうえにはPCと、やかんと湯呑み意外のも
のは常駐させないことにした。つまり、それ以外のものは、格納場所を決め、使ったら必ずも
どすことにした。ちょっとめんどくさいこともあるが、徹底することにした。
いまのところ効果は絶大といっていい。自分がこれほど我慢強いとは思わなかったが、もとに
もどす行為を続けていると当たり前だが、ちゃぶ台の上にモノがたまらなくなった。つねにき
れいな表面を見せているちゃぶ台が部屋の真ん中にあることは、とても気持ちがいい。洗濯物
をたたむのに、スペースを確保する必要はないし、キーボードをひざのうえに乗せなくても、
よくなった。そう、PCでいうならば、ちゃぶ台はテンポラリスペースで、どれか特定のもの
の格納場所ではなくなったのだ。こういう場所が、一家に一箇所は必要なのだと思い知った。
逆に考えると、そのスペースをつくり出すことができれば、おのずと日々の整頓が進むのだ。
整頓されている、という基準は自分のなかにしかないが、少なくともお客さんを呼んで、食事
をしたり、酒を酌み交わす程度のスペースは確保できていると思うので、この状態はキープし
たいなと思っている。
- 2006/3/19(日)
昨夜より腰が痛い(またか!)。
動けないので、蟲師最終話「筆の海」を都合3回繰り返して見る。屈指の名作であると思う。
蟲師のギンコと、「筆記者」淡幽の会話における両者の交感は、見るものの心にゆっくりと、
深くしみこんでいく。全篇が「声の力」と「会話の力」に満ちていた。それは原作の漫画には
決して現れえないもの。アニメーションというものの本領が、これほど発揮されているのを、
近年見たことがなかった。
短い言葉のなかで、意思を通い合わせ、相手を思い遣ること。
その美しさが、わたしのこころを静かに灼く。
現実の世界で、それを求め得ようとするのは、難しいことなのだろうか。
...難しいことなのだろうな。やっぱり。
- 2006/3/18(土)

Onちゃんと、くまちゃん(二次会でもらった)。
しあわせな二人を見ていると、オブザーバーであるじぶんまでも幸せになれるような気がした。
ほんとうにあたたかなものに包まれていた一日。ときを忘れるほどに。
だから、きょうは時計のねじを巻いていない。
Iくん、Yさん、おめでとう。
いつまでも、幸せに。
- 2006/3/17(金)
BK練習。ひさしぶりに全参加。18:30~21:00。
発声2時間はさすがに疲れた。
最近、ちょっと種類の違う仕事をはじめて、慣れないせいもあり、頭が常にフル回転状態にある。
これまではわりと、自分ひとりで完結するか、何人かで仕事をするにしても、分担がはっきりわか
れており、やはりひとりでコントロールが効くものだった。現在の仕事は、自分だけができていて
もダメで、ほかの人との組み合わせが複雑になっており、それゆえ「抜け」がないか、とても気を
使う。というか、古参のメンバーはどちらかというと、自分のところしか見ていないようなところ
があって、新参のわたしからみると、よくこれで回ってたナァと思うことしきりである。きょうな
ども、デバッグ(プログラムを直すこと)をしていて、自分の修正よりも、ほかの部分の修正のほ
うが多く、コーディングしたひとりひとり(3人)に修正内容を説明しにいった。わたしより、く
わしいんだから、なんとかしてほしい。この先心配だ...。
というわけで、いまはあまり頭が働きませぬ。ぐちってしまった。すいません。

準備万端。
うそ。こんなにカメラは持って行かない。でも、このカメラならこんなシーンが撮れるな、この
レンズならこういうシチュエーションにぴったりだ、というのがあって、どれを使うのがよいの
か迷ってしまう。でも、最終的に必要なことは、ただ、しあわせな写真を撮ってあげたい、とい
う思いだけなのだろう。明日は、BK団員どうしの結婚式。
腕時計のねじは巻いた。あとは、靴を磨くだけ。
よき日であることを祈って。
おやすみなさい。
- 2006/3/16(木)
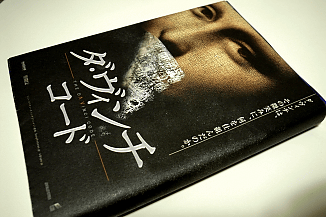
いま読んでいる本。ダヴィンチコードを読んでいる、ように見えるだろうが実は違う。これは
ブックカバーなのだ。映画の宣伝なのであるが、同時に角川文庫の宣伝にもなっているという
巧妙なしかけ。他社の文庫本を軒並み角川文庫のようにみせてしまうのはかなり凶悪である。
実際、この本を読んでいると、電車のなかでも、スタンドでも、定食屋でも、近くにいる人が
じーっと見ているのがわかる。ああ、わたしはそんなベストセラー本なんか読んでないのだー
という叫びは通じようもないのがくやしいところである。なお、このカバーの許せないところ
はもうひとつあって、3mmほど丈が短いのだ。
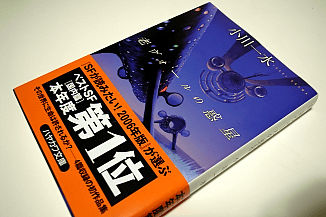
「老ヴォールの惑星」、小川一水著、ハヤカワJA。720円。
で、こちらがじっさいに読んでいる本。お察しのとおり、SFである。「第六大陸」で星雲賞
を受賞した小川一水の作品集。4本の中編が収められている。そもそもわたしは、短編や中編
が苦手というか、敬遠している。連作短編のように、全体を通じてみたときにひとつのストー
リーとしてつながっているものはすごく安心するのだけれど、短編は短いゆえに状況説明や、
人物描写、背景描写が十分でないまま終わるか、もうすこし読みたい、と食い足りなさを残し
たまま終わるものが多い。ゆえに、たくさんの短編が収められていても、個々の短編でのもの
たりなさが積み上げられるだけで、一冊の本として満足できないのである。
だから、この本もいくら読ませる作家である小川一水とはいえ、躊躇した。しかし、気になっ
たのは、帯のベストSF1位の文字。単なる1位ではなく、多くのほかの長編をおさえて、
中編の作品集が1位となるのは、かなり異例のことであると思わざるを得ない。それだけの力
を秘めているということなのか、あるいは一部の作品だけが面白くてそれが評価されたのか。
期待半分で、購入し、読み始めた。
いまこれを書いている時点で、「ギャルナフカの迷宮」と表題作「老ヴォールの惑星」を読み
終えているが、わたしの心配はまったくの杞憂だった。「ギャルナフカの迷宮」を読み終えた
だけで、わたしはほかの文庫小説一冊分を読んだ以上の充足を得た。十分な読み応えがあった。
「老ヴォールの惑星」にしてもそうだった。単にそれだけではなく、小川一水の小説らしく、
未来があって、希望があるエンディングは、読むものを幸せにする。泣かせたり、せつなくさ
せたりする小説は世のなかに溢れているけれど、そんな気持ちにさせる小説は実は少ないし、
まさかそれがSFの世界にあるなんて(←偏見)、誰も思わないだろう。でも、それはここに
ある。これは私見だけれども、作者は私より年下であるが家族持ちであり、そのことが何かし
ら作品に影響を与えているように思われる。ふたつの作品を読んで思ったのは、わたしもい
つかは家族を持ちたいなぁ、という漠然とした、でもいままでよりも、けっこう確かな思いだ
たような気がする。この本を読んでもらえれば、わかると思う。
残り二編が楽しみだ。
ゆっくり読もう。
- 2006/3/15(水)
夜、だいたい決まった時刻に時計のねじを巻く。
この行為はじつはとてもすごいことのように思える。哲学的な意味ではなくて、身体的な話だ。
ねじを巻くにはリューズを右手の人差し指と親指で挟み込む。それはつまむという動作ではな
い。正確に描写すると、親指の腹をリューズの上面にあて、人差し指の右のわき腹、つまり腹
を正面に向けたときの右側面をリューズの下面にあてている。そして、親指は奥へ、人差し指
は手前にひく。このことで、リューズは時計回りに回転させられる。すごいことというのは、
それぞれの指が連携して、違う方向に同時に動かすことができるということだ。
ロボット用、あるいは義手の研究というものはずいぶん進んでいると思うのだが、つかんだり
つまんだりという動きは、ある程度できても、この「指だけによるねじりの運動」というもの
はまだできないのではないだろうか。つかんで、手首を回転させるということで、ねじりは人工
的にできると思うが、指先のみでの実現は、ちょっと考えただけでも難しいことがわかる。指
と指とを連携をさせるための制御、機械上の動作範囲、それらの三次元上での組み合わせ。人
間の親指と人差し指付近の筋肉と骨の構造を見れば、それがいかに複雑であるかを思い知らさ
れる。
そんな、すごいなぁと思う動作も、意識して使うのは、時計のねじを巻くときだけかもしれな
い。そのねじ巻き行為自体もクォーツや自動巻きの浸透で、一部の好事家だけのものとなって
しまったのは、もう何十年も前のことだ。自動車に乗り始めると、体をあまり使わなくなって
体力や運動能力が低下するなんていうが、それほど具体的でなくても、わたしたちは日常のな
かで知らず知らずのうちに、「ねじ巻き」のような複雑な身体動作をしなくなり、忘れてしま
っているのではないだろうか。それはとてももったいないような気がするのだが、どういう動
作が失われてしまったのかは、忘れてしまっている(であろう)から、わからない。ざんねん
である。
ところで、ねじ巻きを毎日続けていると、指先が刺激されて、脳が活性化される!そんな研究
が「あるある大事典II」などで、報告されたら、そのつぎの日から手巻き腕時計の大ブームが
起きたりして、機械式時計が息を吹き返す、なんてことにはなったりしないだろうか。もしか
したら、クォーツに、フェイクのねじ巻き機構がついたりするのではないか?!
ないだろうなぁ。
- 2006/3/14(火)
会社の帰りに合唱楽譜の専門店パナムジカへ行く。じつは会社から阪急の駅へ向かう途中に
あるのだ。といっても、来たのは2回目だったりする。
はじめて来たとき、ちょっと予想外であった。10万冊近い在庫を持つ楽譜屋と聞いていた
わたしのなかには、なぜか古本屋+レコード屋+骨董屋の集合体のような店舗を想像してい
たのだ。店に入り、カウンターの親父さんに「○○の楽譜」というと、棚に収まりきらず山
積みされた楽譜のなかから、すっと目的のものを取り出す、そういうイメージだった。
実際は、マンションの一室のようなこぎれいな部屋の三方に棚があり、部屋の真ん中には閲
覧するためのテーブルと、椅子。そして驚くべきことにレジの類がなく、奥の事務所に続く
扉があるのみだった。ちょっと、拍子抜けだったのを憶えている。そして、もうひとつ思っ
たのは、思っていた以上に小さいということだった。店頭に出ているものが在庫のすべてで
はないのはもちろんではあるが、楽譜の山を想像していた頭にはかなり意外な光景だった。
しかし、いまこうやってもう一度訪れてみてわかったのは、楽譜というものはもともと一つ
ひとつが薄いのだ。オーケストラのスコアならともかく、合唱の楽譜ともなれば、小さいし
薄い。ここにあるコンパクトな棚3つをよくよく見てみれば、それだけですごい数の曲があ
るのだ。
そして、もうひとつ思ったことがある。楽譜というもののすごさというか、単純なことなの
だけれど、ここにある棚の曲を全部演奏したら、いったいどれくらいの時間がかかるのか、
どれくらいの喜怒哀楽が表現されるのかを考えてみると、これはすごいことになるなと。そ
れがぎゅっと、折り畳まれたのがここにある楽譜たちなのだ。音符という符号によって、
「符号化」されたデジタル情報、それが楽譜。情報の高密度パッケージとして、これほど
すごい「本」があるだろうか。そう考えると、下手なビジネス新書一冊の情報量をはるか
にしのいでしまうこともあるだろう。情報に付随してえられる情動も含めるならば。
符号化されたものは、復号しなければアナログ信号にならない。復号するということ、それ
はすなわち、楽譜を読むということ。復号技術のよしあしによって、再現される信号のよし
あしは決まる。わたしたちは、楽譜からどれくらいの情報を復号できているんだろうか。ふ
とそんなことを思ったりした。
頼まれていた楽譜を購入して、店をあとにした。
- 2006/3/13(月)
寒いですな。朝、家で一回、会社で3回ほど、トイレにこもってしまった。気候の変化を敏
感に感じ取っているわけですな、わたしのお腹は。
ところで「蟲師」という漫画をご存知だろうか。アフタヌーンで連載されているが、最近ア
ニメ化されて、関西では8ch、つまり関西テレビで土曜の深夜に放映されている。わたし
自身は、漫画は少し立ち読みした程度、アニメは前回はちょろっと見た程度(眠くて寝た)
で、今日やっと、録画していたものをきちんと見た(「天辺の糸」)。
蟲(むし)とは、陰から生まれたもので、陰と陽の間に存在するもの。動物でも植物でもな
く、生命の原生体と、本編などでは説明されている。これではなんのことかわからないと思
う。乱暴な言い方をすると、虫の妖怪みたいなものです。だから、目には見えない。でも、
見えるひとがいる。正確にはいたというべきか。陰陽道や呪術の世界ではわりと出てくる。
そして、蟲師とは蟲と人間とが出合っておきる厄介ごとを解決するのを生業にしている職業
で、これはそういうお話。
こうやって聞くと、なにか「帝都物語」だとか、「陰陽師」みたいな世界なの?と思ってし
まわないだろうか。妖しげで、おどろおどろしい。しかし、この「蟲師」という作品はまっ
たくの別物だった。例えて言うならば、「大人のためのまんが日本昔話」。そう、ああいう
山々と川、森、に囲まれた日本の里が舞台で、その語り口もとても穏やかだ。蟲は必ずしも
人間とは相容れない存在で、その事象に触れることはやっぱり怖いことなのだけど、ふしぎ
とそういうものを受け入れることのできる土壌が、むかしの日本、100年くらい前までは
あったのだ。そして、いまのわれわれも、そのことがなんとなくわかる。この作品を見てい
ると、そういうふうに思わされる。
となりのトトロに出てきた、まっくろくろすけ、あれもまた「蟲」の一種みたいなものだろ
うと思う。異界ではなく、隣あった世界、あるいは同じ世界のなかにある位相の違う世界。
それが蟲の棲む世界で、そういう認識は何も「蟲師」に限ったことではなく、ジブリ作品の
ようなメジャーなもののなかにも、ちゃんとあったりする。
今の日本の社会のなかで、そういう世界が一般的でないのは、明治維新による文明開化で
一度滅ぼされ、わずかに残ったものも、戦後の米軍占領とそれに続く復興で完全に駆逐さ
れたからだと思う。その断絶は、なにも「蟲」に限らないのだけれど、日本の文化という
ものを語り、理解するうえで、正史に残らない、そういう民俗学的な部分も知っていたほ
うがいいんじゃないかと思う。アインデンティティなんだから。
さて、この「蟲」という字、えらく苦労して表示させたんじゃない?と思っているひとが
多いんじゃなかろうか。ためしに手元のPCで「むし」で変換させてみてください。なん
の苦労もなく、あっけないほど簡単に目にすることができるはず。これはつまり、活字の
の世界には細々とでも「蟲」の世界がちゃんと残ってる、それを伝えようとする文化があ
るってことなのかもしれない。世のなかの目を盗んで、ひそやかに残された秘密を見つけ
てしまったような気がして、すこしどきどきした。
- 2006/3/12(日)
神戸空港(という認識)にいる夢を見た。搭乗案内があったので、ゲートに行く。ゲートを
くぐると、そこにはなぜか大きな段差の石段がつづいていた。ふもとまで。搭乗まであと10
分しかない。はるか眼下のふもとまで、猛烈ないきおいでわたしは下りはじめた。ほかの乗
客も同様に、駆け下りている。ふもとの飛行場にたどり着いたとき、飛行機は出たあとであ
るらしかった。ローカル鉄道の待合室のようなところに入ったが、文句を言おうにも窓口に
は誰もいないのだった。
目が覚めると、雨。寒い。これはサイクリングには行けないなぁとぼんやり考える。きのう
の気候から、ばくぜんと行き先は決めずに予定していたのだった。
それで、午後から映画を見に行くことにする。映画は15時からだったので、モスバーガー
によることにした。あさは、フランスパン風コンビニパン、昼はごはん一杯だったものだか
ら。並ぶまえに、なんとなくトレイにしく紙が目に入った。おっ、なかなかいいじゃないで
すか。モスバーガーのトレイ敷きは、新商品がないときは、コーヒー豆や、カップだとかを
モチーフにしたイラストレーションに、数行の詩がそえられているものが使われている。こ
のシリーズを気に入っていて、過去二点ほどわざわざ持ち帰ってコレクションしている。紙
モノ好きの性というべきなんだろうなぁ。(どんなのか見たい人は、わたしのうちのトイレ
に来てください。座ったときにみえるように貼ってあるので。)
で、今回はトマトがモチーフだった。よし、持ってかえろうと思ったのだが、カウンターを
よく見ると、ことはそう簡単ではなかったのである!向かって左のカウンター、これは目的
のブツであるのでよし。ところが、右のカウンターでは、新発売のカツカレーバーガーのあ
られもない広告(いや単にバーガーの写真が載っているだけなんだけど)バージョンを敷い
ていたのである。列は一列並びで、どちらのカウンターに向かうかの選択権はない。心のな
かで一心に「左、左、左」と唱え続ける。ついにわたしの番、両方のカウンターがうまって
いる状態。そして、両方とも飲み物セット後の、待ちであるから、勝負は五分五分だ...。
この手の勝負事(?)には弱いため、みごとに右を引き当ててしまう。右の店員、手際がよ
すぎるんだよ!と責任転嫁しつつも、瞬時に次のことを考えていた。店員がさっと敷いたカ
ツバージョンを、「トマトのやつに替えてくれませんか?」とお願いしてみたらどうだろう
かということ。いまいうべきか、いやいわないほうがいいか、悩む。店は混雑しているし、
そういうときに、通常の対応にないことを依頼しても、「は?」と聞き返されるだけだろう。
そこから理由を説明して、理解してもらうのがめんどくさくなって、結局最後の手段を使う
ことにした。誰か別のひとが食べ終わったトレイから、回収するのだ。
しかし、結果これも失敗した。またしても店員の手際がよすぎるのか、わたしが返却口にも
っていったときには、ひとつもトレイはなく、すべて片付けられていた。さすがに、待って
いるのはどうか(わたしはこれでも人目を気にするほうだ!?)と思い、撤退やむなしと相
なった。
モスバーガーに来るのはじぶんのなかでいろいろと条件がそろったときなので、次にくると
きは、もう違うやつなんだろうなぁと、落胆しつつ、店をあとにした。映画はなかなかよか
ったので、見終わったころにはすっかりそんなことは忘れてしまっていたのだが。
きょうの映画:「機動戦士ZガンダムIII 星の鼓動は愛」
- 2006/3/11(土)
Javier Bustoという作曲家のAve Mariaという曲をご存知だろうか。合唱をやっている方ならば、
耳にされたことがあると思う。この曲を知っている多くの人がそうであるように、わたしもこの
曲が好きだ。そして、この曲のどこが一番好きかと問われたなら、前奏部だと即答する。合唱曲
なのに、どうしてと思うだろう。もちろん、合唱部がいいから好きといえるのだけれど、この曲
の前奏、わずか6小節は特別なのだ。第一小節のGDHの和音が奏でられた瞬間に、心の奥底
にある誰にも見せたことのない情感のひだに、そっと手を触れられたような気持ちになる。
少し、おどろいていると二小節、三小節とつづく和音によって、心がざわつきはじめ、四小節
のD→Cの下降音階によって、せきが切れたように、「そこ」から熱くて温かい「何か」が血管に
流れ出すのを感じる。涙が出そうになる。本当に。
そして、前奏を聞いた後には、歌い手であるわたしからは、あとはもう何もしなくても、自動的
に音楽がつむぎだされていく。だから、特別。ロマンチックすぎますか?でもね、わたしにとっ
てはぜんぶ、ほんとうのことで、こういうふうにしかかけないし、自分で茶化すこともできない
のだ。
だから、この曲を同じ合唱団の仲間同士の結婚式で歌うと知ったときは、それはもう嬉しかった。
本音をいうならば、あるかどうかわからない自分のときにですね、聞きたいものだなぁなどと思
ったりもしたのであるけれど。こういうことは、わりとよくあって、良い曲だなぁと思うものは、
たいがい結婚式で歌うことになる。You'll never walk aloneなんかもそうだし、歌ってはいない
が、深い眠りにつつまれて、もそうだった。いまNCで練習している男声版の「夢見たものは」
も早晩、やることになるような気がする。もともと、作曲者の木下牧子が懇意にしていた編集者
の慶事のために書いたものだというし。
今日NCの曲を予習するまえに、鍵盤で前奏部だけ練習してみた。もともとはオルガン伴奏。
けれど、これをピアノでやると、小さな多面体のガラスを散らしたようなキラキラとした光が、
こぼれでるように音が鳴る。
まぁ、その、うまく弾ければという条件つきであるが。鍵盤って難しい。
- 2006/3/10(金)
BK練習参加、19:00~21:00。
ときどき、酔っ払えたらええのにな、っておもうときがある。
- 2006/3/9(木)
頭痛、肩こりのため、更新やすみます。あう。
きのう、水道局の連絡先を電話帳で必死で探すが見つからないという夢をみた。
- 2006/3/8(水)
文庫本の、本文を読み終えたあとの楽しみは「あとがき」である。ときどき先に読んでしまう
こともある。その次は、あれば解説を読む。うまい!とか、なるほど!とうならされるような
解説に出会うことはあまりない。そして最後の楽しみは「奥付」である。ウソです。いくら本
好きでも、ありふれた文庫本の奥付を見て興味をそそられる、ということはほとんどないはず
だ。完全に否定するわけでもないけど。
最後の楽しみは「目録」である。同じ著者の、同じ文庫のほかの本の紹介が3行ほどの文で書
かれている、あれのこと(呼びようがないので目録とした)。今日、その目録を見ていて思っ
たのは、「著作リストが切れたその次、あるいはそれ以降にはどんな本が並ぶのか?」という
ことである。
たとえば、手元にあったものを例にとると、伊丹十三のエッセイの場合、彼のエッセイの次に
あったのは、開高健で、そのつぎは山口瞳である。大人の男のエッセイと聞いて思い浮かぶで
あろう作家の本が並んでいる。それから、つぎは藤原正彦のエッセイの場合、斎藤孝、桜井よ
しこ、柳田邦男、佐野眞一である。斎藤孝はこの本の解説を書いているし、国語のエッセイな
ので、そのつながり。桜井よしこは、藤原氏と同様、日本社会の危機を訴える著作を多く書い
ている。柳田、佐野の両氏の著作のうち、ここでは読書や、本そのものに関するものが選ばれ
ている。これもまた、この本の中核をなす読書、国語に通じている。あ、そうそう最後は、
新田次郎だった。いわずと知れた、藤原氏の父親である。
すでにおわかりだと思うが、目録にはその本と関連のあるであろう著作が選択され、並べられ
ている。つぎの文庫を買ってもらうときの手がかりにしてもらうべく、編集者が知恵をしぼっ
ているに違いない。その文庫に著作がその本一冊しかないばあいでも、関連テーマ、たとえば
恋愛小説や、歴史小説といったものは、目録の選択は難しくはないだろう。
しかし、なかにはどういうジャンルに属し、どういうテーマで扱っていいか、図りかねる場合
もあるに違いない。
きょう読み終えた「村上ラヂオ」の著者、村上春樹の著作は、その代表例ではないだろうか。
村上春樹の著作は、文庫にも多く、目録のほとんどは自作で埋め尽くされている。しかし、
その後、三ページもあるにもかかわらず、残りの目録はすべて「新刊書案内」というくくりに
なっている。これはひとえに、村上春樹と関連する著作を、同じ文庫のなかから選択すること
ができなかった、もしくは、ほかの著作を関連させる意味がない、ということを意味するのだ
ろう。
そう、村上春樹は村上春樹ひとりで、村上ワールドをつくっている。だから、それ以外のもの
は何を持ってきても、しっくりくるはずがないのだ。だから、わざわざ「新刊書案内」という
べつの区切りを持ち出して、「別」であることを表したのだろう。それと、村上ファンは、
シリアルに村上春樹を買い続ける傾向があるので、たとえ苦心して関連書籍を選択しても興味
を持ってもらえないかも、そんな心理があるのかもしれない。あー、ことわっておくと、べつ
に村上春樹や、そのファンを揶揄したり、皮肉ったりしてるわけではないですよ。こういう世
界をつくりだしてしまう人がいるのだという例であって。
若い作家のなかには、村上ワールドを模倣しようとして、それっぽい小説を書いているひとが
多いから、本屋大賞のなかに「村上部門」というのをつくったらどうか?と、大森望と豊崎由
美が以前語っていたが、まぁこれはなかなかうなずける話で、そういう若い作家を皮肉って、
こきおろしている点は痛快である。そして、そういう喩えにされちゃう村上春樹という作家は
やっぱり、ある種の孤高(←村上春樹自身は首をかしげるかも)というか、際立った存在なの
だろうと思うのである。
というわけで、目録に注目すると、なにやら見えてくるものがあるやもしれませぬ。
みなさんも手元の文庫本をごらんあれ。
- 2006/3/7(火)
ねんざした。たぶん。
きのうの帰宅途中からどうも左足首が張って、歩くたびに痛みが走っていた。昨日、日曜日に
しょうしょう歩いて疲れたのだろうくらいに思っていたのだけれど、きょうになっても痛みが
ひかない。歩けないことはないが、この感覚は一昨年の夏に、横浜で歩きすぎて、歩行困難に
なったときと同じであることに気づいた。これを我慢して歩いていると、そのうちあの激痛に
変わってしまうのであろう。足首なんて、あまり鍛えることがないので、「くせ」がついてし
まっているか、靴が磨り減っているのかもしれない。
ともかく、帰宅後に湿布とテーピングをしている。これでずいぶんましに...と思って、ちょと
歩いたのだけれど、あまり変わらない。一昨年は、激痛のまま3日間のコミケを耐え抜いて、
三日目の午後には、痛みがとれていたのだが、あれは脳内麻薬でもでていたに違いない。とい
うことなので、どれくらいで治るかがわからない。歩くのが好きなわたしとしては、なかなか
つらい状況なのだった。
ラーメン屋でも、持込みというのはいけないものなのだろうか。きょうは、いつもと違うもの
が食べたいと思って、四条東洞院を上がったところにあるラーメン屋におもむいた。まえに一
度きたことがある。ラーメンとチャーハンのセットに、半熟卵をトッピングした。卵は100円。
と、まえを見るとこの前は気がつかなかったが、ほかのものもトッピングできるらしい。曰く、
「メンマ」「キムチ」「有明海苔」。
有明海苔...3枚で100円。ラーメンに海苔はおいしい。しかし、3枚だ。良い海苔なのかも
しれない。しかし、100円は高いのではないか。と、みょうに気になってしまった。だって
家に帰れば、山本山の焼き海苔がある。それを持ち歩けば、100円払わなくてもおいしい
ラーメンが食べられるのではないだろうか。たとえば、そう手帳とかにはさんでおいて、ラーメン
が運ばれてきたら、さっと取り出すのである。半熟卵をタッパーにつめて、持ち歩くのは難しい
だろうが、海苔ならかさばらない。名刺入れにも入るかもしれない。読みかけの文庫本から何気
なく取り出したしおり、かと思いきや、じつは海苔だったというのも意表がつけてイイ。
とまぁ、そんなことを考えながらラーメンを食べた。
ところで、トッピングにもあるメンマ。最近まで食べたことがなかった。ああ、やっぱりねと
そこのあなた、いまちょっと思ったでしょう。嫌いというほどではないが、あまりすすんでた
べたいと思わなくて、子どものころからずっと残していた。最近になって、勇気をだして食べ
てみたところ、まぁその食べられるナァということを発見したのである。自力で克服したもの
の第二号。第一号は、グリンピース。これはスタンドの定食にいつもいつもついてくる、卵と
和えたものに限ります。単体ではまだすこし苦手。毎週出てくるので、残しちゃまずいと思っ
て食べ続けているうちに大丈夫になった。でも、まぁ一番最初に全部食べてしまうのだけど。
自力じゃないものは、どうやって克服したかというと他力。たいがい、「これ食べられへん」と
いうと、友人に「食べてみ」といわれるので、チャレンジしているうちになんとかかんとか。
こうやって書いていると、こと食生活に関して、わたしは給食の食べられない小学生並だとい
うことに気づかされますな。しかし、考えてみると、わけもわからずとにかく何でも食べられ
るよりか、こうやって大人になってから、少しずつ「味覚」を見つけていく、あるいは取り戻
していくことの方が、じつは「味」に対する喜びが深いのではないだろうか。
(負け惜しみ?)(そうかも。)
- 2006/3/6(月)
帰宅途中に本屋で、文庫本を買った。カバーをつけてもらったところ、どうにも違和感が
ある。本のサイズより、7mmばかし長いのだ。つけている当人もじゃっかんの戸惑いがある
ように見えたが、結局そのまま渡され、そのまま受け取ってしまった。こういうものに頓着
しないひともいると思うが、わたしはひじょうに気にするほう。丈のあってない洋服をきて
いるみたいで気持ち悪いのです。あと、かばんやポケットに入れておくと、長い部分がぐしゃ
と折れてしまうのがイヤ。だいいち、読みにくい。手が文庫本のサイズというものを覚えてい
るから、それにあわないものを自然と拒絶してしまうのだな。
というわけで、店を出てそうそうに、カバーをはずして、宙にもったまま目分量で折った。
これはなかなか難しい。真ん中のあたりが短く折れてしまったりするのだ。そうなっては、
またストレスが溜まるので、途中でそのへんのガラスの壁にカバーを押し当てて、きっちり
折ってみた。といっても文庫本にあわせて折るのではなく、あくまで目分量。あまり正確さ
を求める性質ではないのだ。けっこういい加減にできている。
おかげで、そこそこしっくりくる長さに収まって、ひと安心。
ところが、この文章を書いているとき、ふと目を左にやると同じ店で買った文庫本があり、
そのカバーはやはり7mm長かったうえに、伸びている部分がぐちゃっとつぶれていた。どう
も、じぶんのなかで、長くてもいいときと、そうでないときがあるようだ。でも、まあ基本
的には、ぴったり収まっているほうが好きです。
買った本は「村上ラヂオ」、村上春樹 文、大橋歩 画、新潮文庫。
村上春樹のエッセイを読んでいると、あたまのなかに文章のネタがつぎつぎと浮かんでくる
のが不思議だ。きょうなどは、家に帰るまでに3つくらい、起承転結ができたほどである。
村上的思考パターンというか、あれこれ考え過ぎないと逆に、あれこれ思う浮かぶような気
がするのであった。まぁ、とうぜんながら村上さんの文章にはかなわなくて、嫉妬してしま
うのであるけれど。
- 2006/3/5(日)
春の陽気のなか、五条→二条を歩いてみる。BK練習の帰りよりも短いはずなのだけれど、
やはり昼と夜とではコンディションが違うためか、あとになってから疲れが著しく、夜にい
たるまでずっと眠気におそわれている。
今回歩いたのは天神川通という市内でもマイナーな通り。川沿いの、ほんとに自動車専用と
いった道で、散策向けとはいえないが、春になれば川沿いの桜がきれいなはずだ。
こうやって、一本の通りを南北、あるいは東西に歩くという試みは、思いついたら実行し、
なにかのついでに実行し、また忘れたころにやりたくなる。平安建都1200年を記念して
出版された「京都の大路小路」という市内の通り図鑑があり、その本を読んで以来のことだ
と思う。
この本の東京版というものは出ないものだろうか?と東京で町歩きをすると時々思う。土地
土地の地名というものはインプットされても、そのあいだをつなぐのは旅行者のじぶんにと
っては、地下鉄や山手線といった、道を無視して走る乗り物である。だから、地理的な位置
関係というものの把握がいまいちできずにいる。別にそれを知る必要があるかといわれると
そうではないが、頭のなかにばらばらに存在するピースとピースをつなげたい、という欲求
があるのだ。京都と違って、東京の道は曲がりくねっている(というイメージ)ので、その
作業がなかなか難しい。
そんなの、都区内の地図を見れば一発解決なのであるが、いきなり全体を見るというのは
面白くないし、求めるものは得られないような気がする。人体デッサンをするとき、その
外面だけを見て描くのと、筋肉や骨格を知って描くのとでは得られるものが違うと思うが、
それと似ていると思う。
「東京人」の読者アンケートに、連載企画の提案として書いてみようかナ。
- 2006/3/4(土)
NCマネ会、14:30~17:00。
NC練習、17:00~21:00。
きょうは、飲まずに帰る。
京橋の駅で人が少ないなぁと思ったら、今日は終電ではなかったのだな。
- 2006/3/3(金)
ひなまつりですなぁ。小学生のときは、ひし形の三色ゼリーっていうのが、給食に
でたのだが、ほかの地域でも出たのだろうか。六年生のとき、ちょうど今日、この
日が中学受験にあたっていて、食べられず悔やしい思いをしたことを憶えている。
なにせ、一生のうちで最高6回しか食べられないのだから、悔しくないはずがない。
同じ中学校を受けた同級生は、わざわざゼリーを食べるために、受験が終わってか
ら学校に戻ったらしい。小学生の行動力はときにおそろしい。
家では、ひなあられとちらし寿司。一部のひとは予測がつくと思うが、わたしは
散らし寿司は食べなかった。酢めしが苦手だったのだ。あられはチョコレートで
コーティングされたものを狙って食べてばかりいたので、妹とケンカになったこ
とがあったような、なかったような。
どうも、食べ物のことしか思い出さないというのは、じぶんが男だからだろうか。
かといって、端午の節句に思い出があるかというとあまりない。チマキ、嫌いだっ
たし、こいのぼりも、よろいもなかったから。金色の風車がついたポール、真鯉、
緋鯉が風におよぐ姿、隣家の庭をぼんやり眺めていた。いまは、どうでもいいこと
だけれど、子どものころの、なんというか、くやしさというか、さびしさというも
のは、大人の想像を超えていたように思う。
ひなかざりはあったんだよなぁ。京都だけは内裏様とお雛様の位置がちがうんやで
とか教えられたナァ。
うまくまとまらないので、もう寝ます。
- 2006/3/2(木)
砲弾型ランプ、単体点灯計画を実行に移した。どうでしょう↓。
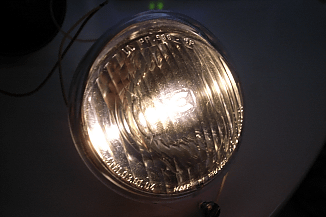
こんな感じ。正面から見るとまぶしいほど。(博士、成功です!)
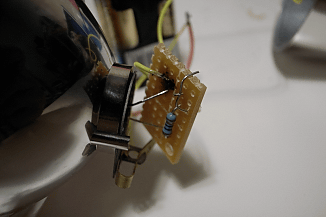
しかし、実はLEDなのだ。白色LEDはいやだったので、あえて電球色で擬態。
抵抗をつないだだけなので、ひじょうにお手軽。(拍手のうず)
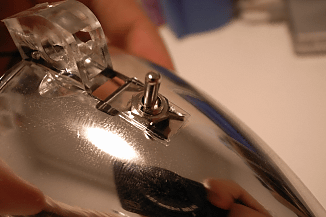
ひとつだけこだわった点、スイッチ。トグルスイッチを選択。砲弾の外観と違和感
なくマッチしたので狙い通り。(諸君、よくやってくれた。)

おおきな問題点。単三乾電池4本は、どうあっても砲弾内部に格納できないのだった。
引っ越してみたら、玄関からソファが入らなかったヨ、みたいな感じ。
(われわれの計算は正しかったはずだっ・・・Warum!)
というわけで、つづく。
- 2006/3/1(水)
うち以外で、本を読み始める場所というのはどこが多いだろう。そう、その本をはじめて
読むときのことだ。本屋で立ち読みする分は、回数も記憶もリセットする(これは高度な
技なのだ!)。それは多分電車のなかではないかと思うのだ。夕方の梅田行きの阪急電車
だったり、夜中の京阪電車であったり、昼下がりの東海道新幹線であったりする。
では、本を読み終えるのはどこが多いだろうか。じつはやっぱり電車のなかなんじゃない
のか。読みおえて、ふと見上げると、そこは夏の晴れた日本海であったり、吹雪の東北本
線であったり、明け方のオリエント急行であったりすると、とても心地がいいはずだ。
物語の始まりにはあまりこだわりがなく、終わりに過剰な期待がこめられているような
気がしないでもない。ほんとうは、旅のなかに読書がくみこまれている、という状況が
好きなだけだろう。
きょう、阪急に乗っている途中で、これは途中で読み終わってしまう、と途中で本をし
まった。電車のなかで終わるのがいやなのではなく、河原町につくかつかないかという
タイミングが問題だった。読み終わったあとも、電車は走っていて欲しい。本をとじた
瞬間に静止した心と、動き続ける外界の対比というのを無意識に欲しているのだ。わた
しはこうみえても、センチメンタルにできている。
というわけで、ラストはスタンドで定食を待っているときの待ち時間か、食べおえた後
の一服(むろん読書のことだ)のときだろうと予測した。飲み屋で読み終えるというの
も、なかなか新鮮だと思う。がやがやした<動>の店内と、<静>のじぶんの対比は
ここにもある。
が、結果はマッサージ屋で、マッサージを受けたあと、テーブルに腰掛けてお冷を出し
てもらっているときだった。これは予想外。でも、ここは本を読むのにとても良い空間
であると発見した。いや、読みおえるにもいい空間だった。町屋のなかの薄明かりがな
にか、山奥のバンガローにキャンプに来たような静けさで、それがここちよかった。
静止×静止、という式もありなのだと気づいた。それを調和というのだろう。
「此処彼処」、川上弘美著、読了。
- 2006/2/28(火)
最近、あまりよく眠れない。夜中か、明け方に目が覚める。たいがい夢を見ている。
この前などは、なんの夢かは忘れたが、右手でこぶしを握って、前につきだして、おっ
しゃーと力んだところで目が覚めた。ところが、気がつくと現実でも右手を突き出して
いたのには、ちょっとびっくりした。馬鹿だなぁなと思った。目がさめた時間が、夜中
二時とか三時だと、ああまだゆっくり寝れると一安心なのだが、これが5時半とかだと
じつに中途半端で、落胆することしきりである。目覚めて、その日のはじめに落胆する
のはきっと精神衛生上よくないことであろう。
きのうは、NCの指揮者が登場し、せかされて乗合馬車のような狭い車両に乗せられる
という夢だった。どこの始発かはわからないが、京都行きで、終点は高雄の方である。
高雄というのは京都の西の端である。だから、寝過ごすわけにはいかない、指揮者を起
こさないといけないなぁ、などと思っていたところで目が覚めた。あまり気持ちのいい
夢とはいえません。インフルエンザのときは、同じ合唱の夢でも、けっこうこころとき
めくようなのを見たのであるが、ああいう夢を狙ってみれるようになれば、毎日さぞ楽
しいことであろう。
まぁ、あまり眠れないにしては、起きている間はわりと心穏やかにすごしている今日こ
のごろ。(体はしんどい)
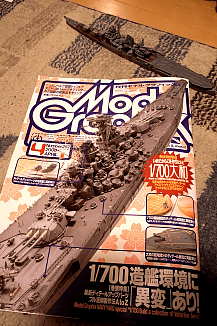
月刊モデルグラフィックス、4月号。特集『1/700造艦環境に「異変」あり』。
「環境」と変換しようとしたら、候補のトップが「艦橋」だった。そんなわけで、また
また艦船模型を作りたいなと思い始めている。ちょうど作例もバーンと載っていること
だし、ここはやはり大和でしょうか。1/700の大和はなんと全長36.7cm。この前つくった
最上が28cmであるから、相当大きい。
そう思ったところで、まずはピンセットを買っておくべきだと気づいた。1/700の模型を
ピンセットなしで作るのはかなり無謀であると、記事にもあるし、最上を作ったときに
実感した。道具は大事。
あ、そうそう尾道の大和のセット、GWまで見学期間が延長されたらしい。とはいっても、
4月は忙しくなるので、ひまを見つけて3月のうちに見に行っておきたいものだ。
- 2006/2/27(月)
朝、クリームパン、昼、カツサンドとチョコクロワッサンというように、今日になっても
食欲はいまいちである。おなかもややゆるい。夜になって、さすがにパンばかりだったせ
いか、やや食欲が復活し、定食屋で生姜焼きとから揚げのセットを食べる。あまりすっき
りしない。野菜で整腸する必要があるのかもしれない。伊藤園の「一日分の野菜」を復活
させてみようと思う。
きのう、実家に帰ったら部屋でこんなものを見つけた。
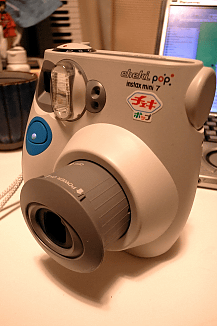
富士フイルムのチェキ。
買ったのではなくて、当てた。数年前、グリーの同期の結婚式で行われたジャンケン大会で、
日頃、発揮されない運をうっかりつかってしまい、三位だかに入賞したときの賞品がこれな
のだ。自宅に帰ってから、フィルムをセットし、ためしに目の前のPCを撮ってみたら、お
お、ちゃんと写真が出てきた。なかなか鮮明である。どれどれ、こんどは何か別のものを撮
ろうと思ったら、そこでフィルムは切れた。一枚きりのお試しフィルムだったのだ。以来、
数年間、フィルムを買ってくることもなく置き去りにされていたのである。
ちょうど3月のなかごろに、これを使うのにぴったりの用件があるので持ち帰ってきた。
レンズの部分をひっぱるとスイッチが入り、空シャッターを切るとちゃんと動く。しかし
まあすごい音がするのだ。撮ったフィルムを排出するためのモーター音だと思うのだけれ
どゴミ収集車の圧縮機なみの騒音である。おそらくパーティーとか、コンパ会場のような
大きな音が許容される空間での使用を想定して、静音にはこだわらず価格を下げた設計に
なっているのだと思う。
あと驚いたのが、単三のアルカリ乾電池を4本も使っている点。普通のカメラではこんな
に電池はいらない。さきほどのモーターにえらくパワーがかかってるようだ。あと、フラ
ッシュはオートマチックなのだが、室内だとほぼ100%光るみたいなので、そのために
容量がいるのだと思う。電池はちょうどグリップの中に納まるため、持ったときのバラン
スがいい。ということはぶれにくいということになる。レンズとスイッチの兼用といい、
静音思想の省略、電池の格納など、随所に細かな設計の妙技がみられる。インスタントな
カメラだといって、なかなかあなどれないのだった。
- 2006/2/26(日)
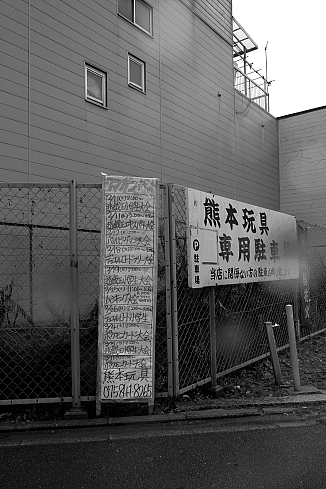
小学生達に「クマガン」と呼ばれているらしい熊本玩具店。雨の街角にて。
わたしが小学生のころというのは、こういう玩具店主催のイベントというのは
なかった。ガンプラ+ファミコンが主体で、それらはどちらかというと各々の
自宅で完結しての遊びだったからだ。その後のミニ四駆や、昨今のカードゲーム
というのは、一人で遊ぶことにあまり意味がなく、どうしても場が必要なもの。
そういうことからすると、わたしの世代よりも、若い世代の方が遊びのなかで
「社会性」を身につけやすかった(現在も進行形)のではないかと思う。非常
に適当な想像だが。ひと見知りをする自分としては、遅れて生まれなくてよか
ったなんて、思ってしまうのだった。(そこで得られる社会性がどの程度のも
のなのかというのは、ここでは深く考えていない。)
木、金、土と外食で、きちんとしたものを食べていなかったせいか、どうも
お腹はすくのに、食欲がないという状況になる。しかたなく、大丸で野菜の
おかずがたくさん入った弁当を買ってきて食べる。大丸によると、いつもな
らフランスパンを買うところだが、やはり「胃乗り」しなくて、かわりにク
リームパンと、デンマークパンを買う。明日の朝ごはんの予定。
そういえば、226事件の日であった。雪、降るかと思ったけども...。
- 2006/2/25(土)
YMCAチャリティーコンサート@京都コンサートホール、小ホール。
コールシェリー&スピリタスの一員として参加。シェリーは京都を中心に不定期に
活動する女声合唱団。スピリタスはNCからの選抜(ということになっている)
メンバー。シェリー2ステージ、スピリタス2ステージ、合同1ステージの本格的
な演奏会だった。
きのうの衰弱が思ったよりひどく、ぎりぎりまで横になっていたのだが、オーダー
を作らねばならなかったので起きた。集合は14:15。NCメンバーのことだか
ら誰も来てないだろうと思って、14:00にホールについたら9割近く来ていて、
しかも楽屋で練習までしていたので、びっくりした。わたしはこの演奏会のNC側の
マネージ統括だったので、ちょっと肩身が狭い。まぁ、団としてはいい傾向です。
15:20、ホールリハ。シェリーのリハを少し聞く。全員一列に並んで、最初の
一音だけ歌う、というところしか聞けなかったのだけれど、その一音がとても清冽
で力強くて。もう、それだけで気持ちがよくて、がんばろうという気持ちにさせて
くれたのだった。ありがとう、シェリーのみんな。
合同リハを経て、NCリハ。オーダー表(事前に二種類作るように言われていた)
を指揮者に渡すと、すげなく「いらん」と言われる。ホールの響きから、もっとも
単純なベタ無し二列オーダーが最適だったためらしい。いつものことなのでめげない。
18:00~20:00、演奏会。
20:45~23:00、合同打ち上げ。
お客さんにとても喜んでもらえていたのが、ステージ上からわかった。
やっぱり、コンクールじゃなくて、演奏会がいいなぁと思えた。
どんな演奏でも、もちろんくたくたになるまで全身全霊をかけるのだけれど、
へとへとで歩けないくらい、集中するのだけれど、歌いかけてこたえてくれ
る人がいるというだけで、あとの疲れが心地よいものに変わったりするのだ。
あーでも、シェリーとはもっと近くで歌いたかったな。
お客さんを取り囲んでの演奏だったので、遠かったよ...。
- 2006/2/24(金)
会社後輩送別会。
氷過食下痢。厠駆込。
寝不足脱水。要休眠。
了
- 2006/2/23(木)
木曜の晩にお酒を飲むのはなんとなく、週末でもない平日でもない、どこか微妙な
緊張感と弛緩のあいだというような空気があって、それはとても居心地のよいもの
なんだなぁということを今日、発見した。
今日のお酒:黒牛、というのが美味しかった。例によって一口だけなんだけれども。
明日、起きられるかな。
- 2006/2/22(水)
オークションで落札したのは、これ。
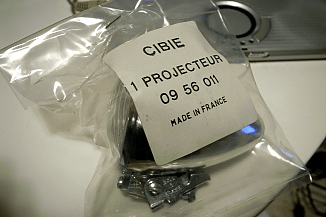
確かにフランス製。CIBIEというメーカー。
PROJECTEURとある。なんでしょうか。
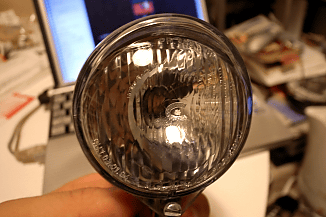
自転車のランプなのでした。(電球なし)
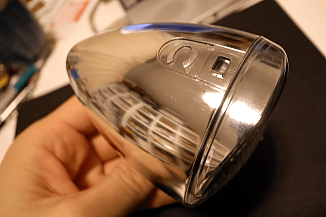
いわゆる砲弾型。「ひさし」がついているの良いアクセント。

つややかなメタリック、そして煽情的なまでの腰のライン。惚れぼれ。
実は、プラスティックにメッキをほどこしたもの。なので、とても軽い。
そんなの買ってどうするのと言われそうであるが、当面の目標は電球を備えつけ
たうえ、内部に細工をして、単体で光らせること。これは通常はダイナモといっ
て、ママチャリによくついている前輪の回転によって発電する装置からの電力供給
によって光らせるのであるが、ご存知のとおり、ダイナモをつけると車輪が重くな
ってしまう(最近ではホイールに内臓する「ハブダイナモ」というものがあり、こ
れは重さを感じない)。
単体で光らせることができれば、ダイナモなしにどんな自転車にも取り付け可能。
それどころか、懐中電灯がわりにも使えるはず。ちょっと無理があるけど。
デザインが非常にクラシカルなので、いまのっているスポーツタイプのルイガノ号
には当然似合わない。となると、このデザインにぴったりくる自転車をみつけない
といけないわけである。そうなると、こんどはなんで二台も自転車がいるの?とい
われそうであるが、フィルムカメラ3台、アンティーク腕時計を3本もっている人
に聞く質問ではありませぬ。男というものはすべからく、金属係数の高い「器械」
を所持したがるものなのです(ご婦人にはなかなかわかってもらえない)。
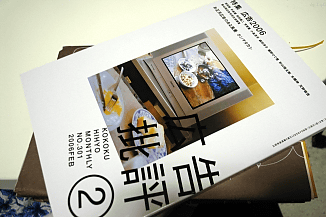
今日買った本。広告批評2月号。特集、広告2006。
今月のベスト5に、資生堂の元旦広告が入っていた。やはりというべきか。
12人のモデル・女優の大集合写真。それは人間の本能に訴えかけてくる何か
があった。美しいものを目にしていたいという願望。ずっと美しくあってほし
いという願い。キャッチコピーは「一瞬も一生も美しく」だった。
あの広告、とっときゃよかったなぁ。
- 2006/2/21(火)
カーリング、負けてしまいました。残念。
スポーツ中継で、多数の選手が同時に競技を行う、たとえばクロスカントリーなどの場合
どれがどの選手なのか、というのは、みなさん見ていて瞬時にわかるだろうか。顔が見え
る競技で、この人と決めて見るならともかく、全身を覆うユニホーム、サングラス、そし
てはじめてみる選手達という条件。そういうとき判別に役立つのがゼッケン番号だと思う
が、それにしても、どの番号がなんという名前の選手で、どこの国の選手だということ把
握していないといけない。手元にリストがあったとしても難しい。
オリンピックの中継を見ていると、アナウンサーはその難しいことをリアルタイムに、そ
してあらゆる場面でやってのけ、把握するだけでなく放送で伝えている。それだけではな
く選手個人の戦歴や、特徴まで非常にくわしく、しかも当たり前のように。これはじつは
とてもすごいことなのではないだろうか。なにか、秘訣とか特訓があるのだろう。
むかしから、野球選手の背番号などが全然覚えられない私にとっては、魔法のように思え
るのだった。(野球をはじめとするスポーツ競技に通常はあまり興味がないからか?)
- 2006/2/20(月)
このオリンピックを通じて、実はもっとも注目されている競技は女子カーリングではない
だろうか。ほとんどが一発勝負の競技が多い中、予選がリーグ戦のためほぼ毎日放映され
ているため、競技のルールがわかっただけでなく、非常に戦略性の高い「ゲーム」である
ことがだんだんとわかってきた、というのはわたしだけではないはずだ。選手の名前も覚
えてしまった。スキップ(キャプテン)小野寺選手、林選手、本橋選手、目黒選手。そう
なると応援にも熱が入る。小野寺選手の胸のすくようなショットには本当に驚かされるし、
すごいと思う。自力での決勝進出はなくなったけれども、がんばれー!
ひとつだけ気になることがある。本橋選手が石を投げるとき、アナウンサーが必ず「出る
か、マリリンショット…」というのはなぜだ。
ネットオークション、終了直前になってさらわれる。しかし、同じ商品が即決で出ていた
のを発見し、結果的に先の落札価格の6割程度で落札できた。あるようでなかなか手にい
れにくい物だけに手に入ってよかった。さて、オークションクイズ第二弾。なにを落札し
たのでしょうか。
ヒント1:自転車のパーツ。
ヒント2:フランス製。生産中止品。
ヒント3:落札価格1260円。
思いたって親に電話。身体の調子が悪いらしい。確定申告を頑張りすぎたとのこと。
世間的にみれば、すでに高齢と呼ばれる年齢だけに、インフルエンザでなくてよかった。
- 2006/2/19(日)
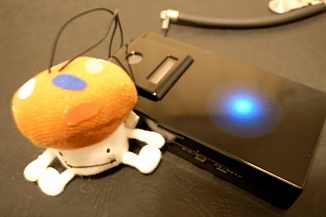
P701iD with ドコモダケ
携帯をP504iから機種変更した。3年くらい使っていたと思う。メモリの一部がビット不良
を起こしているようで、メールの送受信が正しく行われているか不安になってきたためだ
(送信後のメールが一文字置きにしか表示されない現象あり)。
P701iDは羊羹というか、モノリスというか、飾り気がないところが気に入って選んだ。
角にRがあってマット仕上げのものと、スクウェアのままでグロス仕上げの二種類がある
のだけど、グロスの方を選択。Rがあるタイプだと、どことなく地味にうつる。この組み
合わせは逆の方がよかったんじゃないかと思う。
さて、中身はさすがに3年も経つと、いや504iが出たのはもっと前だけど、インターフェー
スがかなり変わっていて、指先がまったく追従しない。困ったのが文字入力。普通の文字変
換は直感でわかるものの、半角記号、顔文字、改行のやり方がまったくわからなくて四苦八
苦する。特に違和感をおぼえたのが、拗音の入力。P504iでは同じボタンで「つ」のあとに
「っ」、「ゆ」のあとに「ゅ」できたものが、P701iDだと「つ」のあとに「大小」きりかえ
ボタンを押さないといけない。同じツーストロークでも、指位置が変わるのでやりにくくっ
てしかたがない。慣れるまで時間がかかりそう。PCのキーボードと違って、インターフェ
ースの共通化、あるいはカスタマイズができないというのは、携帯がユビキタス社会の統一
端末になり切れない最大の理由じゃないだろうか。(このP504i→P701iDの変化というのは、
P社とN社の共同開発ゆえのことだけれど。)
あ、そうそう、カメラがついてた。
今のところ自分の顔しかとっていない。
何か面白い使い道はないものか?
- 2006/2/18(土)
NC練習、17:00~21:00。
疲れた。途中で二度ほどあたまがくらっと来て、ふらつく。
BKの倍近い練習時間というのもあるが、無駄にエネルギーを消費しているような気が
しないでもない...。

OsakaPitapaのイメージキャラクター「ぴたポン」
Pitapaとは関西私鉄共通で使用できるICクレジットカードによる後払い式の
運賃精算システムの総称である。JR東日本のSuica、JR西日本のICOCA
に対抗するICカードの第三勢力なのだ。対抗するといっても、このたび、あ、いや正確
な日付はしらないのだが、とにかく最近になってPitapaとICOCAは相互利用が
できるようになった。つまりJRと私鉄がシームレスでつながったことになる。これは
喜ばしい。
さて、そのPitapaにOSAKAがつくと何が違うのかというと、実は機能的な違い
はPitapaと互換なのでほとんど違いはないようだ。ただ、大阪市営地下鉄・バスが
発行するカード(実際にはクレジット会社が発行)だけがなぜか、独立してOSAKAを
冠している。最大の違いはなんと本家Pitapaでも存在しないイメージキャラクター
をつくってしまったことだろう。それが、このぴたポン。
いやーいいです、ぴたポン。ぐっと来ます。
これまで関西圏のカードシステムは、ことキャラクターに関してはSUICAのペンギン
に対して、するっとKANSAIのするっとちゃん、ICOCAのイコカモノハシと、
インパクトでは勝るものの、「愛される」キャラクターとしては完敗状態であったといえ
る。それが、このぴたポンを見よ!ペンギンと対等に戦える資質を備えているのではない
だろうか(私見)。大阪市交通局の大手柄といっていい。まぁ、デザインしたのはアランジ
アロンゾなんだけどネ。
せっかくの、ぴたポンなんだから、ぜひともカードのデザインにも登場して欲しい。もし
でたら、OsakaPitapaカード作ろうかなと思う。
(加入グッズなんかあるとうれしいなぁ。)
もうひとつ、夏コミにぴたポンサークルができないか期待している。ペンギンや、イコカモ
ノハシ、するっとちゃんをフィーチャーした鉄サークルはすでに存在するだけに、可能性は
あるはずだ!
おまけ情報1:ぴたポンの好物は「たぬきそば」らしい。
おまけ情報2:関西では「たぬき」というと「あんかけ」のことなので注意。
- 2006/2/17(金)
BK練習。
にごりざけ、注意。
映画、レッド・バイオリン。こういう映画は好き。英語、イタリア語、ドイツ語...。
普段ハリウッド映画で聞こえる、くずれてただれてしまったような米語にはない音楽的
な響き。眠いので、最後まで見れないのがざんねん。眠ります。
- 2006/2/16(木)
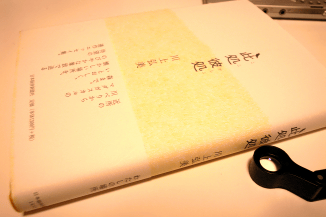
「此処彼処(ここかしこ)」、川上弘美著、日本経済新聞社刊。1300円。
病み上がりの記念に、なにか読みたいと思って、本を探す。雑誌は適当なのがない。小説
は、いまの集中力からすると重すぎる。何より今日は疲れている。今朝まではわりと調子
はよかったはずなのだけれど、どういうわけか職場の室温が28.5℃(寒暖計で測った)
もあり、その暑さにあてられてしまった。
そんなじょうたいでも、すうーっとその世界に入っていけるのが川上弘美の本である。よみ
はじめるのに抵抗がない。読みすすめるのに抵抗もない。でも、しっかりその軌跡はあたま
のかたすみにのこっている。まぁ、そういう抽象的な面ばかりをいってもつまらない。なに
より川上弘美のエッセイ、そうこの本は連作エッセイだ、を読むと彼女はよくひとりで、徘
徊というか、散歩をしていることが多く、そのほとんどがえもいわれないさびしさに満ちて
いるのが好きなのだ。みじめな感じではなくて、つっぱっている感じでもなくて、喫茶店で
コーヒーを頼んで、文庫本を読んでいるような、そういうおちついたさびしさ。そういう
心境はわたしのこころを不安にさせない。物語や、エッセイに登場する人物に感情移入し
ては、一行、一文ごとに、じぶんのこころをかき乱し、落ち着きすることがよくある。そう
いうのは困る。本をなかなか読みすすめられないから。この前、読んでいた井上靖の「氷壁」
がそうだった(じつはまだ読了していない)。
川上弘美の文章は、どこか透徹していて、淡淡としていて、こころをかきみださない。
でも、すこし「くすぐりわらい」がある。ふつうの視点じゃない。ふつうじゃないことが、
たのしい。ふつうの、へいせいなこころのありようというのは、じつはこのひとのほうで、
よのなかのほうがじつは、へんなんじゃないかな?とおもったりする。
まぁ、そういうわけで、さびしくもこころおだやかに、ひそひそわらい、どくしょをするよ
ふけなのである。
ひらがなだらけ。
- 2006/2/15(水)
惣菜屋で買ってきたおかずを、皿に盛り付けるのは意外と難しいものがある。買って来た
ままの容器を食卓に上らせることは、もちろん無粋であるが、容器から取り出して皿に移
しかえただけというのもまた、それと変わらないほど無粋であるし、うつくしくない。ポ
テトサラダのような塑性が高いものはとくに容器のふたの形がそのままのこって、K2
北壁のような斜面になっていることがある。アイスクリームならともかく、ポテトサラダ
ではそれだけで食欲が半減する。
たとえ自炊した料理でなくても、おいしく食べたいという欲求は変わらない。おいしそう
に見えるということが重要なのだ。目や匂いといった要素は味覚をより引き立たせるので
ある。もし、ひとりで食べるのでなければ、おいしく食べて欲しいと思う、もてなしの心
であるとか、親愛の心がそうさせるだろう。
こういうこころのうえにある、盛り付けという所作は自然と身につくという類のものでは
ないだろうと思っている。教えられるわけでもないと思う。いってみれば、誰かから得る
のだと思う。親が教えるという場合があるかもしれないが、それは教えるというより、受
け継がれるものという気がする。師匠がいるならば、それは盗むもの。これも言い換えれ
ば継承か。継承されるのは、かたちであり、こころ。なにも格式ばったものではなくて、
それは日常のなかにある小さな美意識の連続にすぎない。盛り付けに限らず、小さなもの
の集積が質の高い豊かな日常を生み出し、つなげていく。ことわっておくと、質の高いこ
とと高価なことは必ずしも関連しない。
だから、惣菜屋のおかずの盛り付けにだって、心血を注ぐとまではいかないでも、気をつ
かう程度の配慮はあっていいのだ。わたしに、もし子どもがいたならば、食事を準備する
姿を、たとえサッポロ一番塩ラーメンをつくるにしても、見せるに違いない(そこにどん
な所作があるのかはわからないが)。見て、何か感じ取ることがあってほしいと思う。
それが反面教師になる可能性がないとは言い切れないけれど。
おなじことは自分の書棚をみてもときどき感じることがある。盛り付けの所作の話とは少
し違うのだけれど、じぶんが読み集めた本を見て読んで、そこから何かを感じて受け取っ
て、それをまた誰かにつないではくれないだろうかと。所作が普遍的な価値であるならば、
まったく個人的な価値なのだけれど。
もし、本をうっぱらってしまうことになっても、一括でブックオフにおろすのではなくて
ジャンルごとにこれは、○○書店、これは書肆△△とわけてほしいなぁ、というところま
で妄想するのだった。
後半、ほとんどドリームだなぁ。
インフルエンザ、治ったと思います。薬も飲みきったので、ひとにうつす心配もなし。
あしたから、社会復帰いたします。
- 2006/2/14(火)
食料が切れたので、3日ぶりに外に出た。歩いて5分のコンビニへ。身体の重さは
感じられないので、快方に向かっている様子。ただ、帰宅するとかなり熱くなる。
ひさしぶりに動かしたせいもあると思うが、恒常性がまだうまくとりもどせていない。
もうすこしかな。
漢方薬、「片仔こう(「黄」に病だれ)」を飲む。わが家における体調を崩したとき、
病中病後の最終奥義ともいうべきモノ。めったなことでは服用が許されない。逆に飲ん
でいいときはよっぽどのときということ(実家から離れてるので、自分で決めて良い
のだけれど)。
医者の薬(菌の増殖を抑えるためのもの)とともに飲んで3日目。通常は一回飲むだけ
で劇的に回復するところであるが、さすがにインフルエンザ相手ではそんなに簡単には
いかないみたい。
あと一日だけ休みます。
- 2006/2/13(月)
疲労のピークなのか、終日かなりしんどい。
会社は連絡して休ませてもらった(ただし、欠勤扱い)。
このぶんでは、あと二日くらいはダメかも。
とても起きていられないので、ただいま19:00ですが眠ります。
肩こり緩和にバンテリンを塗りました。おととしの夏コミ前日に捻挫したときの余り。
やな夢見ないように。
- 2006/2/12(日)
熱は下がった?と思うのだが、寝ているとやたら汗をかくので、まだまだなんだろう。
きのうから4回ほど着替えている。
昼からは少し起きていても大丈夫になった。ただし、ちょっと動くとすぐにしんどくなる。
TVをつけると東京国際マラソンをやっていた。と、その際のCMに注目。このマラソン
は「東京メトロ」がスポンサード。で、CMも東京メトロ。地下鉄のCM自体見ることが
はじめてだったが、これがなかなか良いのです。いろいろなバージョンがあるのだけれど
たとえば、『銀座で振られて』→『浅草で立ち直る(あんみつをたべる)』(銀座線)
というように、路線+駅ごとのシチュエーションがコント仕立てでまとめられているのだ。
で、駅しか出てこないかというと、ちゃんと車両も登場。地上の風景の上空を透明な軌道?
に沿って軽やかに走る列車。まるで70年代的未来鉄道!街と街をつなぐのが東京メトロとい
うイメージなのだろう。「地下」という固定観念で考えていたらこんな映像は思いもつかな
ない。グッド!
もうひとつ気に入った点はBGM。ミュージカル「南太平洋」のナンバー、"Happy Talk"。
この曲は昔、グリー時代に歌ったのもので、よく覚えている。軽快で、ほがらかで、歩き
出したくなる、ミュージカル映画全盛期のアメリカらしい色彩にあふれている。これもま
たCMのキャッチコピー「東京ポジティブで行こう」にぴったりだなぁと感じた。
普段、東京地区でこのCMが流れているのかどうかわからないが、だとすると、全国放送
で地区限定のCMが見られるのはすごく珍しいこと。しかし、東京メトロも思い切ったこ
とをするものだ。東京の地名にはブランドがある。だからこそできる技かもしれないが。
その心意気とCMの良さを応援したいと思う。
あ、そんなこんなでまたしても活動限界が近い模様。夕方からすこし熱が出てきた。
きょうはここまで。この調子だと、あしたもたぶん寝ています。
- 2006/2/11(土)
あけがた寒気に襲われる。
早朝、舌下で38.5℃。これはやばい!と思い、家の近くのクリニックに行く。診療時間の
9時になっても、扉が開かない。それから5分くらい待つも変化無し。タクシーにのって
四条大宮の診療所に行く、9時は過ぎていたのに、ここも閉まっている。そこで、はたと
気づく。きょうは、ただの土曜日ではなくて、祝日と重なっていたのだ。「病気に休みは
ないんじゃー」と悪態をついて、休日に空いている病院を親に聞く。インフルエンザだっ
たら、発症からの何時間が勝負だ。身体が動くうちに病院に駆け込まないとまずい。
京都府庁前の第二日赤、救急外来に行く。受付には「ただの風邪なら平日来い」というよ
うなことが書いてあり、ヒドイなと思う。熱のせいでいくぶんナーバスになっているなと
感ずる。「風邪、いやインフルエンザ」と告げる。確証はなかったけれど、追い返された
ら死んでしまう。
問診を受ける。熱は腋下で37.4℃。舌下とえらく違うなぁ。いろいろな症状があるか聞か
れるが、ことごとくあてはまらない。食欲もあったというか、何か食べないとまずいと思
って、パンとアクエリアスはのんできた。病人にしては冷静すぎる?ようで、センセイの
眼に疑問の色が...。一応、検査。鼻の奥の粘膜をごしごしとやられる。「すごく痛いで
すヨ~、5秒くらいやりますよ~」、センセイと助手のひとの目が一瞬キラリンと光った
ような気がした。実際はそれほどでもなかった。もっと刺すような痛みがあるのかと。
15分待つ。かなり朦朧となる。
インフルエンザA型と判明。予想はしていたが、やはりそうか。薬をもらって、タクシー
で帰宅する。途中、コンビニで食料を仕入れておく。
10~19:30、眠る。途中、頭痛のため何度か起きる。水分補給は随時する。かなり
しんどい。熱よりも、首・肩の凝りによる頭痛がつらい。
19:30、目覚める。やや小康状態。といっても、熱は腋下で37.4℃。すこしふらつく。
とにかく、あるものを食べて夕食にし、薬を飲む。病気のとき、食事を取らないと、病気で
ふらついているうえ、栄養が足りなくてふらつくことがあるので、無理でも食べる。今回、
口にいれやすいものしか食べてないとはいえ、食欲があることはさいわいであると思う。
いまの間にかけるだけ書いておこうと思い、記す。もうろうとしているが、指先だけはな
んとかちゃんと動く。
活動限界が近づいてきたようなので、ここまでにする。ふたたび、眠る。
- 2006/2/10(金)
くしゃみと鼻水が止まらず。
BK練習、見学者の対応のみ。ほとんど歌わずに楽譜を見るのみ。
BK宴会、途中退席。
- 2006/2/9(木)
ここのところ、仕事を終えて居室から屋外へ出たときの寒さといったら、ない。もう許して
くださいと誰に言うのか呟いてしまう。いくら12月、1月が平年より寒さが厳しかったと
いっても、やいやい本場2月の寒さには勝てんだろう、べらぼうめ、ガハハ!なぐご、いね
ーがーとか言う声もときどき聞こえる。。まぁ、更衣室に着くまでのしんぼうなのだけれど
しんぼうならんときもある。それは米を研ぐとき。骨身にしみるという言葉があるけれど、
物理的な事象だけでいえば、まさにそれにあたる。
きょうの晩御飯はカレー。レトルトカレー。辛口。いつもいつも中辛を食べていると飽きて
しまったということと、この前、それしかなかったという理由でククレカレーの甘口を食べ
たところ、こんなのカレーじゃないという甘さだったので、その反動であろうと思う。普段
は絶対に選ばない(ほんとに辛かったたら食べられないという弱気な理由で)。
結果、鼻の通りがかなりいい。やっぱり辛い方が、香辛料が効いているのか?ちょっと元気
になりましたよ!これから10回に1回くらいは辛口にすべきだろうか。
ああ、しかし。カレーのとき、わたしは調子にのってご飯を盛りすぎる傾向にあるようだ。
明日の朝食には少々足りぬ量しか米が残っていない。つまり、新たに研がねばならぬという
こと。カレー屋でよく使っている、ホースをつなぐと水流で自動的に米を研いでくれる器械
が切実に欲しいと思う今日この頃。5~10万円くらいするのかな、あれ。
- 2006/2/8(水)

C70のサークルカット。後ろの建物は旧住友銀行本店(現、三井住友銀行本店営業部)。
大阪の中ノ島に現存。現役の銀行のなかでは、群を抜く品格を漂わせている。その正面の
オーダーは一度見たら忘れられない。ちなみに写真は正面ではなく、裏側のもの。正面と
同じオーダーなので、ゆっくり全体を見るならこちらの方がよい。警備員に怪しまれない
よう注意がいりますが。
あ、誌名に「近代」が抜けてた...。
阪急に乗ると、「+神戸」と描かれたポスターが掲示されていた。そうかぁ、神戸空港開業
なんだなぁと思ってよく見ると、右下には飛行機の尾翼、そしてANAの文字。そう、この
ポスターは空港会社ではなくて、ANAの広告なのだ。思えば、羽田空港第二旅客ターミナル
の開業時もANAが宣伝をうっていた。まぁ、自社専用ターミナルに近いのだから当然にして
も、今回の神戸空港はそうでもないはずだろう。それが、このポスターを見たならば、まるで
ANAのための空港かのように思える。文言としては当然そのようなことは書いていないにも
かかわらずだ。正直、うまいと思った。羽田の件とあわせ技一本といってもいい。
宮里藍を起用したマイルキャンペーンに終始するJALとは段違いのセンス、戦略を感じる。
かたや増収増益(ANA)、かたや減収減益(JAL)と、営業面でもくっきり分かれたよう
で、さもありなんというべきか。
広告は企業の姿を照らしだす。
侮ってはいけないと思う。
- 2006/2/7(火)
引越し記念日(二周年)。コーヒーゼリー、買ってくるのを忘れた。
あした、スタンドで祝うことにしよう。
きのうの急激な不調の原因は不明。結局、今日は午後定時ごろまで不調ではあったが、熱はなく
インフルエンザというわけではなかった。ひと安心。ただ、のどの痛みは残っているので、不調
そのものとは無関係に風邪をぶり返している可能性はある。
原因として推測されるのが、血糖値の急激な下降がある。夕方、少しこばらがすいたので、脳に
糖分を補給するつもりもあってチョコレートを食べたのであるが、これによって血糖値が急上昇
したのではないだろうか。その結果、インシュリンが急激に増加し、血糖値を下げる方向に働い
たが、こんどは逆に下降が急激すぎたため、不調を引き起こした。めまいのような症状を伴うか
どうかは定かではないが、熱がなかったことから、そうなのではないかと思っている。ただ、普
段もときどきチョコレートを食べるが、このような症状が出たことはないので、やはりなんらか
体内バランス等が崩れていたのではないか、のどの痛みの原因が、その原因にもなっているので
はないだろうかと思う。
昨日は、山岳地帯を走るハイウェイをカブのようなバイクで猛スピードで下っていくのを俯瞰で
眺めるという夢をみた。ああ、こんなスピードではすべる~、こわいーという感情はあるが、視
点が俯瞰のままなので、なんだかゲームをやっているかのようだった。
そのつぎに、YKの練習に行くという夢を見た。練習場はどこかの洋品店の二階である。一階の
洋品店につくと、白に黒ぶちの小さな猫と、茶色の大きな猫がいた。店主らしき年配の女性にわ
たしは小さな猫を指して「あれが○○ですか?」と、猫の名前を尋ねていた。どうやらその猫の
ことは知っているが会うのは初めてだったようだ。その小さな猫はぱーっとわたしの前方へ走り
去ったが、茶色の猫(これが大きい)が悠然と、どれ案内してやろうかといいたげな表情でこち
らを見ながら、奥の二階へ続く階段まで併走してくれた。いや、階段を上りきるまで一緒だった。
二階につくとまだ二人ほどしか来ておらず、窓から下の道を眺めていた。
よくわからないが、妙にストーリー性のある夢であった。
帰宅後、夏コミの申し込みを行う。今回からオンライン申し込みが可能。いやぁー、あの紙に書
いていたときの緊張感がまったくなくて非常に楽。写し間違えはないかとか、短冊を切り離すな
どのデリケートな作業がないで助かる。なによりカード決済なので、郵便局にいかなくていい!
これが一番のメリットだと思う。サークルカットのアップロードの手前で仮保存する。カットは
テンプレートが用意されているので、明日キンコーズで作成予定。
しかし、ここまで楽になると、「書類不備」は確実に減るのではないだろうか。と思ったのだが
ここまで楽だったのは、これまで二回書類を書いてきたからで、入力している内容は書類の場合
と同じなのだ。活動概要や、ジャンルコード、販売実績、申込書番号、初申し込み時期、前回受
付番号、前々回受付番号...こういったコミケ独特の項目の記述ルールをわかっているから、
入力がスムーズだったわけで、もしはじめて申し込むという場合は、やはりかなり戸惑うと思う。
画面には特にヘルプはなさそうだったし、申込書の入力例をじっくり読むしかない。まぁ、なく
なるとすれば、写し間違いは起こりようがないだろうなぁ。書類のときは住所なんか7箇所くら
いかかないといけなかったのだ...。
夏に出す新刊はタイトルだけ決めた。「建築探訪 大阪逍遥」である。どのような形式にするか
はまだアイデアがない。大阪で撮った写真は多いが室内写真は少ないため、東京篇のような構成
は難しいと思う。しかし、大阪は京都ほど慣れ親しんでいるわけではないから、京都断章のよう
な文章は書きにくい。むしろ、東京のほうが文章は書きやすいかもしれない。どうするか...。
もし、前回、前々回と本を買っていただいた方がいらっしゃったら、次回はどんなものがいい
か、希望を聞かせていただきたく思う。トップページのメールアドレスまでご意見ください。
場合によっては大阪ではなく、東京篇にもどるか、名古屋篇、門司・下関篇も候補にあがるこ
とになるかもしれないなぁ。
- 2006/2/6(月)
夕方から、のどの調子が悪いナァと思っていたのですが、夜になって急に気分が悪くなって
きました。頭も痛いので薬を飲みましたが効きませぬ。めまい...
- 2006/2/5(日)

子どものころから、懐中電灯が好きだ。アウトドア志向があったとか、川口浩探検隊に影響
されたとかいうのではない。わたしはどちらかというとインドア派であった。あ、探検隊に
影響されなかったというのは正確ではないな。わたしにはインドア探検趣味と、秘密基地造営
趣味があったのだ。昼なお暗きは、何もジャングルの密林や、巨大洞窟だけではなくて、一般
家庭の物置や、押入れもそうであった。そういった内なる暗闇を求めて、わたしは日夜道なき
道、地図なき土地を、相棒たる懐中電灯を手に歩き回っていた。
未知の空間を発見すると、そこに定住し、さっそく基地の建設に取り掛かった。そんな際、
太陽が届かない場所に光をもたらしてくれるのが、やはり懐中電灯であった。秘密基地では
もっぱら保存食(地蔵盆で得たお菓子のたくわえ)を食べ、読書(まんが)に励んでいた。
自宅、親戚のうちを探検しつくすと、寝るときに布団をかぶって、うつぶせになって基地気
分をかもしだしていた。そこでもやはり本を読んでいたように思う。目が悪くなったのと、
暗いところが好きになったのはこの影響かもしれない。
そんな生活も中断されることが多々あった。原因は電池切れ。小遣いをもらっていなかった
ため電池を買うことはできない。ならば、と家にある使えそうな電池を可能な限り調達した。
TVのリモコン、電動ロボット、ほかの懐中電灯、etc。そんなわけで家にある光源は言うに
及ばず、祖父母宅にある懐中電灯や、電池はことごとくわたしの趣味に費やされた。結果、
「おまえのおかげで、いつも使いたいときに電池がない!」と父親によく叱られた。ならば、
電池を買う小遣いをくれ、と言うような勇気はなかったし、思いもつかなかった。親という
ものの存在は絶対だったのだ。
さて、きょうは半日をゆったりとすごした。炊事をし、洗濯をし、トイレ掃除、床掃除。でか
けたのは思い立って、懐中電灯の電球を買いにいったときだけだ。写真の懐中電灯はマグライト
というアメリカ製のライト。アルミ合金を削りだしたボディは耐久性にとみ、かつシンプルで
美しい。おおざっぱなアメリカ人が作っているとはとても思えないほど、クラフトマンシップ
を感じさせるつくりだ。1994年に購入して以来、電球、電池切れ以外の理由で点灯できなかっ
たことは一度もない。信頼がおける(通常の懐中電灯は接点や、点灯回路の故障がけっこうあ
るものだ)。
が、そんなマグライトにも弱点はあって、電球が専用品なのだ。電池のようにコンビニで購入
というわけにはいかず、一度切らしてしまうと、入手がめんどくさい。まぁ、東急ハンズや、
ロフトのような大型雑貨店にいけば手に入るのだけれど。きょうは、ロフトに行ったのだが
欠品中であった。電球を買う目的だけででかけたので、かなり落胆。結局、そのあと御池に
ある登山専門店で見つけた。アウトドア専門店ならば、マグライトは100%扱っているのを思い
出したのだった。
LEDではない、豆球のあかりはやはり落ち着く。いや、落ち着くのが目的ではないのだけれ
ど、暗い場所を照らすとき、なんとなくそこに温かみや、安心感を求めてしまうのは自然な情
動ではないのかな?と思うわけで、そういう意味で多種多様なLEDライトが登場するなか、
もはや老舗といっていいマグライトがいまも生き残っているのは、とても自然なことなのかも
しれないと思う。
- 2006/2/4(土)
大阪駅前のBook1stで、「南方熊楠英文論文考」を探すが店頭在庫切れであった。南方熊楠に
関する本は民俗学のコーナーに集められている。他の書店でも同じような扱いなのかもしれ
ない。分類としては間違ってはいないような気もするが、すくなくとも熊楠の英文論文は、
自然科学誌「Nature」に掲載されたものであるから、せめて理数、博物のコーナーにおくべ
きではないかなと思う。「あやしげなもの」「じみなもの」「ひのあたらぬもの」「まつろ
わぬもの」、民俗学はそういうものを扱ってきた。つまりはマイナーだ。西洋近代科学では
解明・理解できぬものとして、追いやられたものたちだ。現代の、世間一般における熊楠に
対する理解も、そういうものに含まれているのかもしれない。すこし悲しい思いがした
(民俗学を軽んじているわけではないが)。
やや衝動的に「ユリイカ臨時増刊、総特集 白洲正子」を買う。ユリイカの増刊は、本誌と
違って手触りがよいのが好き。
- 2006/2/3(金)
みなさん、豆まきしましたか。
うちはマンションで、しかも入り口が屋内にあるタイプなので、入り口では小声で二粒ほど
だけ廊下にまいて、かわりにベランダはたっぷり十粒、トイレ、風呂は掃除のことを考えて
やはり二粒。そして、歳の数だけ食べるわけだが、これが「結構多いなぁ」と思うような量
で、精神的なものにくらべて、物理的なものに変換されると、問答無用なのだなと思い知る
のだった。
香を焚く。すぅーっとまっすぐに、のびやかに立ち上り、途中で分かれ、また絡み合い、
螺旋を描き、宙に拡散し、消えていく煙を見ると、なんだか人の声みたいで、合唱みたい
だと思った。
福が来ますように。
- 2006/2/2(木)
さいきんのわたしの脳内ヘビーローテーションはnirgilisの「sakura」である。
じぶんにとっていい曲かどうかは大体はじめて聞いた瞬間に決まる。
何回も聞いているうちによくなってくるということはまずない。
この曲はわたしにあっていると感ずる。
「sakura」は日曜日の朝7:00から放映している「交響詩篇エウレカセブン」の新オープ
ニングテーマである。なぜ、脳内かというと、また発売されていないからだ。新オープニン
グが放映されたのは、先週だからいたしかたないと思わないでもないが、発売日は3月1日
とあと一ヶ月もまたねばならない。これはちょっとひどいですよ。というか、最近のアニメ
のテーマ曲はだいたいこんな感じ。
レコード会社の戦略としては、曲をある程度浸透させてから売り出したいというところなの
かもしれないが、わたしにとってみれば気に入った曲は時間が経てば経つほど新鮮度がおち
ていくので、レコード会社が想定する「視聴者の期待感」はだいぶ薄らいでしまう。曲その
ものに対する評価がそれで変わるわけではないけれど、この聞きたい聞きたい感が旬なうち
でないと「フィーバー!」とはならないのである。
ところで、ふと思ったのだが、元からアニメ向けに作られた曲はともかく、こういうタイア
ップ式の曲の場合、当然ながらアニメのオープニングなり、エンディングの尺とはあわない。
そうすると、尺にあわせたバージョンが作られるわけだが、これがなかなか曲者である。
よくよく聞くと、歌詞の意味が全然通っていなかったり、サビにいたるメロディが唐突だっ
たりと、尺には収まってるけれど曲としてどうなのと思うことがある。なかにはまったくそ
のことに気づかないものがあって、CDを買ってみて愕然とすることもある。すごいのは、
一番の歌詞と二番の歌詞が混合してたりするのだ。
で、なにをいいたいのかというと、その尺の短いバージョンというのは、歌い手にとっては
どういう位置づけなのかということだ。自分たちの思いが完全には曲に乗らないで、解釈さ
れうることもあるわけで、あまりいい印象がないのではないかというのが想像。逆に考えて
みて尺にあわせるための「編集」であるとか、音楽の骨格を組み替えることにあえて挑戦す
るような歌い手もいるんじゃないかとも思う。その尺あわせが、歌い手、製作サイドのどこ
から生ずるかによっても変わるのだろうな。
歌と絵がシンクロしたオープニング、エンディングは見ていて気持ちがいい。そういうもの
はたとえ尺が短いバージョンでも、わたしとしてはちゃんと評価したいと思う。
仕事でえらいことをやらかしてしまって、きのう、きょうと精神力と集中力をかなり使い果
たしてしまう。けがの功名的な部分があったのが不幸中のさいわい。だいじにはいたらなか
ったのもさいわい。あした起きられれば、もっとさいわい。できることならぐったり寝てタ
イ。目ぇーがイタイ。おやすみなさい。
- 2006/2/1(水)
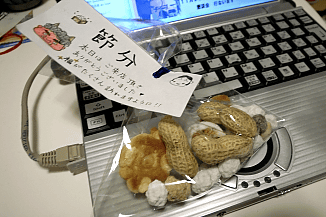
マッサージに行ったら、帰りに節分の豆をくれた。ふつうの福豆に落花生に、五色豆の白いのや
ら緑のと、いろいろ入っている。これは鬼に投げつけるにはもったいない。歳の数には足りない
けれど、ありがたく食べる用にいただきましょう。外にまく用のもの、金曜のBK練習のまえに
買っておかないといけないな。
- 2006/1/31(火)
友人にふとんをひっぺがされそうになるのを、内側から必死で引きとどめて苦悶している、とい
う夢を見る。目が覚めると、かけぶとんがいまにも自重で左側面に落下しようとしていた。あー
なるほど。物理的な干渉というものは、じつは夢に反映されやすいのかも。経験上、匂いが反映
される確率は高い。
職場が暑い。まえの居室でもおんなじことをいっていたような気がするが、今回はわたしだけ
ではなくて、ほぼ全員が口にしているから信憑性は高いだろう。暑くなったのは昨日からで、
まず上着は着ていられない(これはわたしだけ)ので、常時Yシャツでいる。ウォームビス推奨
と居室のドアにいつの間にか貼ってあり(そのような通達はなぜか見たことがない...)、その
貼り紙によると、暖房温度は20℃が推奨されている。
ところが、隣のグループの部長が、寒暖計を取り出し(どこから調達してきたのか?)計測した
ところ「ほら25℃やで」。
今日になっても改善されていなかったので、空調の故障かもしれない。それにしても、よく考え
ると、夏場の設定温度は28℃であるから、夏はこれよりもさらに暑いということなのだ。外気
温との相対的な関係で体感温度は変わるにしても、いまから夏の暑さが思い起こされて、ちょっ
と気持ちが萎えるのだった。
あすはいつもより早いので、もう寝ます。
って読んでいるひとには何時に書いているかわからんのだよな。
- 2006/1/30(月)
仕事のプログラムがなんとか形になった安堵感か、ちょっと無理をしたせいか、たぶん両方で
かなり疲れてまふ。
この前の冬コミの入稿前後に、これはもう新しいマシンを買って...という話を書いたと思うの
だが、どうせならこれを機にMacを導入してはどうだろうと考えている。わたしはべつにMacが
嫌いではないし、むしろ高校生のころなどは、本気でMacを買うことすら検討していたのだ。
まだジョブスが復帰するまえ(彼はNextCubeという高価な「椅子」兼Workstationなんか作って
いた)で、最高機種がQuadoraだったと思う。一方のPCはというと、IBM互換機がはじめて登場し
たくらいで、OSはMS-DOS。MacのGUIに比べると、見劣りがするなんてものじゃなかった。
まぁ、高校生が使ったり遊んだりする安価なソフトも、プログラミング環境もMacにはなかった
から大学生になってPC(EPSON互換機)を買ったことは当然で、正解だったのだけれど、
あのときわけもわからずMacに傾きかけたのは、身の回りでメジャーじゃないもがいい!という
玄人志向を当時から持ちあわせていたということだろうか。当時のAppleは今年つぶれる!とい
う噂が毎年絶えないくらい先行き不透明な会社だった。いまの勢いからすると信じられないと
思うが。
ひるがえって現在のAppleはなかなか隆盛であるし、この余勢を駆ってMac本体も売ろうという気
まんまんである。なにより、IntelのCPUを搭載したことはその証拠だろう。いま現在の
PCの利用目的はインターネットが主であるし、今回の目的がPhotoshopでの作業というならば、
なおさらWindowsマシンである必要性がない。最近はPCゲームもやらないし、ネットでフリーソ
フトを取ってくることもない。だったらいいんじゃないかと。それと昔から、Photoshopや
Illustratorなどを使うデザイン系の職業のひとはなぜか100%Macであることが不思議で、なぜそう
なのか?ということを自分で使って確かめてみたいと思うのだ。
噂では新Macのパワーがあれば、Windowsをエミュレートするのは容易いのではないかという話も
ある。とりあえず、夏のボーナスまで時間があるのでしばらくこの考えは寝かせておく。まずは、
来週から始まる夏コミ申し込みに向けて、サークルカットを作ることに専念しよう。ってたぶん
キンコーズで一時間くらいでつくっちゃうんだろうけど。
- 2006/1/29(日)
晴天、天候も暖かく穏やか。だが、用心のため風を切る自転車は避け、徒歩で買い物にでかける。
二時間ほどで帰宅。うろうろしながら、写真でも撮ろうかと考えるが、「この気候に惑わされては
いけない」と心がささやくので、おとなしく帰宅。やや過剰かと思うが、のどもとすぎれば...の
ことわざ的生活を改めないと、この冬は乗り切れないと考えて自制気味なのだった。
ベッドメーキングをする。週に一度くらい。
わたしは特に寝相が悪いという自覚もないし、合宿などの集団生活でも指摘されたことはないのだ
けれど、起きたときのベッド(ベッドの上にマットレス、その上にふとん敷)の状態をみると、あ
る特徴的な動きをしていることがわかる。ベッドのマットレスに対して、しきぶとんが足元方向と、
左方向に大きくシフトしているのだ。ベッドの頭方向と右側面に壁があるので、それから逃れようと
しているかというと、そうではないみたい。一時期、頭の方向を逆、つまり足元と左側面を壁にして
寝ていたことがあるが、このときはまったくシフトがなかったからだ。
いったい、どういう運動をするとこのようなことになるのか不明であるが、とにかく毎日これがつづ
くと、頭方向15cm、右側面に5cmくらいの隙間が生じてしまう。この隙間が問題で、枕が沈み
んでしまうのだ。それからベッドの長さは190cmくらいしかないので、必然的に寝るスペースが短く
なっていく。足元の布団は完全にベッドからはみ出しているから。
変な夢を見たり、起床時に頭痛があったりするのは、じつはこの状態で寝ようとして、無理な姿勢
になっているのが原因ではなかろうか。ならば、なんとか改善方法を考えねばならない。とりあえ
ずふとんとマットレス面の摩擦抵抗をあげる手段を検討してみよう、と今日思った。ずれを修正す
るのは結構手間がかかるのだ。
同時に「いったい何日かけると、寝ている間にベッドから落ちるか実験してみよう!」という提案が
頭のなかで可決されないよう、食い止める必要もあるのだった。
おや、こんな時間。では、おやすみなさい。
- 2006/1/28(土)
NC練習に行くとき、烏丸通りから四条通りを西に向かって進む。ところが帰って来るときもまた、
四条通りを西に進んで帰ってくる。それはまるで、8時間で地球を一周してきたかのような錯覚を
おぼえる...というのはウソだが、どこか不思議な感覚になるのは確かだ。
なんのことはない、行きは大阪梅田へ阪急電車で向かい、帰りは大阪淀屋橋から京阪電車で帰って
くるだけのことで、長方形に近い輪を描いて循環するのだから、同じ方向に進むことになる。
ある二点間を移動するとき、単に往復するのはつまらない。それは真上に放り上げたボールがその
まま落ちてくるのと同じ、位置エネルギーと運動エネルギーが交換されるだけで何も変わらない。
円を描いて循環することも、同じところに戻ってくるという意味では、往復運動と変わりはないけ
れど、より長く、そして常に前に動き続けることができるから、その過程が違う。有限の時間と、
かえるべき場所という制限のなかで、精一杯欲張りに生きるための手段なのだ。
...最終の京阪特急に乗ると、ときどきこういうどーでもいいことを思索して、あたまのなかがぐる
ぐる、ぐるぐると回ってしまうよーだ。
寝ます。変な夢、見ませんように。
- 2006/1/27(金)
いま、アレックスモールトンという自転車のことが少し気になっている。以前、BD-1という
折り畳み可能な小径の自転車を紹介したが、モールトンはおなじく小径の自転車でありながら、
その思想とか形といったものがまるで違う。特長的なのは、まず形でトラス構造(鉄橋とかの三
角形の骨組み)で車体の前部と後部がつながれている。はじめて見ると、一瞬こんな細いフレー
ムで大丈夫なのと思い、そのうちだんだんと、そのシンプルゆえの優美さのようなものにひきこ
まれ、おそらくずっとフレームだけを眺めていても飽きないといった状態になる。
つぎにその思想性。普通、小径の自転車というのは折り畳みによる携行性、省スペースなどを目
的として「小径」に設計されるが、モールトンの場合、「走り」を追究した結果、小径となった
というのである。それを裏付けるかのように、80km/h以上のスピード記録が存在する。車輪
が大きいとスピードが速いというのは理論的には正しくないそうなのだ。そう、自転車の設計
のなかに、数々の理論が埋め込まれたのがモールトンだともいえる。
おわかりかと思うが、こういう「玄人好み」的なものにわたしは弱い。なにか、確かなものに裏
打ちされていながら、一般的な知名度が高くない。それは流行に流されず、確固たる信条を持っ
ている証拠だし、またそれを支持する”熱い”ユーザーが存在することを暗にうかがわせる。そ
ういうものを同じように支持したくなる衝動に駆られる。そこに一種の優越感というか、わたし
だけが知っている感がないとは言い切れないけれども、そういう矮小な感覚が多少入りこんだと
しても、それをはるかに超えるオーナーシップというか、モノを愛し、モノとともにある精神が
自分の人生をゆたかにしてくれるように思うのだ。時計やカメラにおいても同じ境地に立ち入る
ときがある。
多少どころか、かなりお高いものであるが、ハードルが高くなければ面白くない。その高みへ
行き着くための「勇気」もまた、精神を強めてくれるはずだ(←何かの修行か?)。
BK練習18:45~21:00参加。
BK宴会21:30~23:30参加。
宴会参加者は、全員男、そして全員ベース。
「志は高く、ピッチ音階は低く」が合言葉。
- 2006/1/26(木)
BKの練習CDを焼いていたのだけれど、なんと歩留り100%。ヤッタネ!って、なんでそん
なことで喜ぶかというと、実は以前焼いたときは65%という低歩留りを喫していたからなのだ。
ライティングソフトのせいかなと思って、ソフトのバージョンアップをしたり、できるだけ単機能
のフリーソフトをさがしてきたり、ネット接続は完全に切ってから、など地道な改善をしてこの
数字で、ドライブを買ってきた当初は50%をきっていた。
それが、きょうはネットはつなぎっぱなしで、常駐ソフトもすべてそのままの状態だったから、
これで原因がはっきりした。SETIのための計算ソフトとの相性が悪かったに違いない。
SETI計算ソフトとは、電波望遠鏡で拾った外宇宙からの信号をフーリエ変換するためのもの
で、スクリーンセーバー状態で起動する。1年以上前から使っていたのだが、最近計算結果のア
ップロードがうまくできなくなり、仕方がないのでアンインストールしたばかりだった。失敗続
きのCD焼きのときは、常駐を外していたのだが...。使っているDLLか何かが問題だったのか。
最新のSETIソフトを導入して検証する必要がある(ぬれぎぬという可能性もある)。
さて、そもそもSETIって何で、なんでそんなことやってるの、家に電波望遠鏡があるの?とい
う質問がきこえてきそうであるが、今日はもう寝る時間。このつづきはいつか。気になるひとは、
自分で調べてみてください。面白いですよ(手抜き)。
- 2006/1/25(水)
会社につくと、全社にある通達が出ていた。なんと「インフルエンザの予防徹底」という内容。
入社して何年にもなるが、こんなのは初めてでおどろいた。なかみは、うがい・手洗いの励行、
湿度を保つなど基本的なことが多かったが、なぜそれが有効なのかまで説明されていて、説得力
があり、この種の通達としては読みごたえがあった。それから、熱が下がって治りかけのときも
感染力があるので、しばらくは出社しないことなど、かなり具体的な指示まであって、社内での
流行に対して、かなりの警戒があることをうかがわせる。
いまのところ、職場ではっきりとインフルエンザで休んでいるという人はいないが、この週明け
から風邪引きの人が目立っている。なにせ、課長・部長そろってマスクをしているのだから、こ
れは注意すべきだろうか。通達の内容が気になって、帰宅後のうがい・手洗いは言うに及ばず、
先週の風邪引きに引き続いて加湿器を稼動させることにした。なにせわたしにはあとがない。
有給休暇がもうないのだ。つぎに休むと欠勤になってしまう!残り二ヶ月弱、一に健康、二に健康
をスローガンに生きていかねばならぬ。
帰宅途中、いままで気づかなかった場所に神社を見つけた。おりもおりだし、じぶん、家族、友人
の健康を祈願した。魔除け、火除けの神さんだった。5円分としては欲張りすぎたかもしれない。
普段、あまり祈るということをしてこなかったのだけれど、今年はなんとなくそういう気分なのだ
った。誰かに頼りたいっていう願望のあらわれなんだろうかネ。
あ、そうそうきょうは、給料日なのでした。
明細が電子化されてからは、給料日のうきうき感も薄れてしまって、豪気にお金を使うっていう
こともなくなってしまったような気がする。その祭りのような高揚感がつぎの一ヶ月への精気を
高めていたのだと、あとになって気づくのだった。たとえ振込みでも、明細だけは上司からの手
渡しだった。これが、もっと前、現金手渡しのころはいったいどんなだったのか、想像以上のも
のだったに違いない。年に一回くらいは、現金支給を復活させて、その気分を味あわせてもらい
たいものだ。
- 2006/1/24(火)
祝!H2A打ち上げ成功、「だいち」軌道投入成功。
山Dの電波暗室はJAXAを勝手に応援しています。
会社の居室が移動になった。昨日から。
よくなった点
・食堂に近くなり、売れきれの心配がなくなった。
・更衣室に近くなった。
・空調の不均衡がなくなり、二酸化炭素濃度が下がった(酸欠にならない)。
悪くなった点
・窓がないので、四季、気候、天気が一切わからない。情趣もへったくれもない。春に桜が見えん。
・どういうわけか、照明が天井直付け。そのため、直射光しかない。つまり、眩しい。モニターを見
てプログラミングする身としてはかなりつらい。私設パーティションでやや減光。
・トイレの冷え込みが激しい(床がタイル)。
という具合。完璧な職場というものはなかなかないものだなぁ。

「ズッコケ中年三人組」、那須正幹著、ポプラ社刊。1000円。
10代~30代にとっては説明不要の児童文学のロングセラー、ズッコケ三人組シリーズ。
小学生のときの読書というと、わたしの場合ズッコケか、ルパンだった(ホームズは当時の
小学生の目からすると、途方もなく地味に映ったのだ。高学年になると、赤川次郎とか、
西村京太郎をよく読んでいた←小学生っぽくない。)
第一巻は1978年の刊行。そして、最終巻の50巻が出たのが2004年。1978年に
12歳だったズッコケ三人組がそのまま歳を重ねると、今年40歳になる。つまり立派な中年
なのだった。最終巻のあとの反響があまりにも大きかったため、ファンサービス的に今回の本
となったとのこと。自分ではずいぶん熱心なファンだったつもりだけれど、この本の裏表紙に
50巻全部の表紙が掲載されていて、最後に読んだ巻をさがすと、たかだか13巻目までだっ
た。いいかえれば、37巻の間にわたしは大人になっていた。
それでも20余年の時を経て、店頭に並んだこの本を見たとき、手に取らずにはいられなかった。
小学生の長くて、短い時間のなかで、ズッコケを読んだことは、わたしの読書体験のなかで色濃
く残っている。自分が体験できないことをあたかもその場にいあわせたかのように想像し、とき
にその想像は時空を超える。読書の楽しさというものをしらずしらず教えてもらった。そんな気
がする。
こども世界文学全集は読まなかったけれど、ズッコケは読んだ。
それでいいと思っている。
- 2006/1/23(月)
今日は、22日に行って来た金沢21世紀美術館の印象について写真を中心に話してみたい。

この美術館はその形が円であり、そして基本的に平屋建て(地下1Fあり)であることが
特長となっている。美術館のコンセプトは、誰もが入りやすくて、交流しやすいというこ
とであるらしく、実際これほど開放的な美術館は少ないと思った。内部は11室の展示室
と市民ギャラリー、や長期展示ルームなどに細分化されて、それぞれを回廊が結んでいる。
この構成のため、内部を二分して別々の企画展を並存させることもあるようだ。写真にみ
える四角い建物は、それぞれの展示室である。最大で12m近い高さがあり、国内ではこ
れほどの規模のものはほかにはないのではないだろうか。今回の企画展で内部を歩いて思
ったのは、外観から想像できる規模よりも、体感的にはずっと広いということがあった。
それは、この高い空間と、回廊を行き来するということによってもたらされるものである
と思う。

近年開館される美術館がそうであるように、金・土に限っては20時まで開館している。
場所は、百万石通と本多通りの角にあって、市内の中心部、香林坊、片町から歩いて5分
という立地にあるため、ほんとうに気軽に仕事帰りに寄っていける場所だといえる。都市
の中心部にこのような郊外的かつ、都市的な美術館があることはほんとうにうらやましい
と思う。

外周はすべてガラス張りのため、ひじょうに明るい。これは想像であるが、雪による光の
反射も考慮されていたのではないだろうか。冬がもっとも明るいというのは、北陸金沢の
町ならではと思う。

外周部分は基本的に誰でも無料で入館できるスペースであり、椅子などの休憩スペースが
多数設置されている。
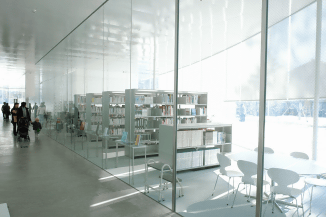
施設のひとつ、ライブラリ。国内外の美術雑誌、パンフレットの閲覧ができる。この隣に
は、開館中に利用できる託児所が併設されている(有料)。誰もが入りやすい、というコ
ンセプトがきちんと貫かれているのだ。

レクチャールーム。こうやって、四方をガラス張りにし、半地下+段差にするだけで、
「この部屋に入ってみたい」と思わせる設計はさすがであるとしかいいようがない。
別室であるが、会議室も完全なガラス張りで、会議の様子が外から丸見えだった。
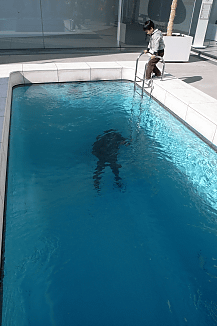
さて、この美術館のもはや名所といってもいいのがこちら。中庭のプール。
これも現代美術の展示作品のひとつなのだ。水中を「泳ぐ」ひとを見ると、
おもわず水面をのぞきこんでしまう。こどもたちに大人気。
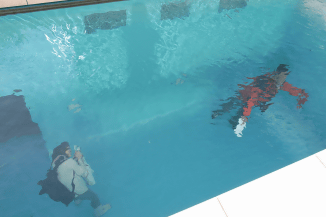
水中でカメラだって構えちゃいます。
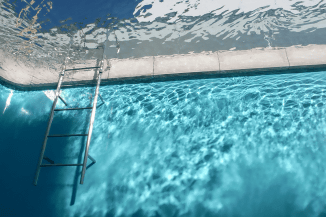
わたしもざぶーん、ともぐります。ぶくぶくぶく。
  
作品ではないが、これが一押し。油圧式エレベータ。巨大なシリンダーで昇降するのだ。
これが何を意味するかというと、四方はもちろん、天井まで視界が開けているということ。
いやーすごい、この感覚は。一緒に乗りあわせたひとが「宙に浮かんでるみたい」ともらし
ていたが、ほんとうにそう。例えるならあれです。天空の城ラピュタの釜の部分の内部で、
ムスカとシータが移動に使っていた石のエレベータ。前後左右には動きませんが。
というわけで駆け足で紹介。ここにあげた部分を見るためだけでも行く価値はあると思う。
であるが、やはり美術館の本質は企画展。次回は、今回見てきた「もうひとつの楽園」に
ついてお話したい。
- 2006/1/22(日)

みんなおはよう。安田さんOnちゃんです。きょうのかなざわはすっごく晴れてるよ。
さんぽのとちゅうで、「ぶどうの木」っていうお店をみつけました。山DがはいってるBK
って合唱団とおんなじ名前だね。「木」と「樹」だけ違うって。お店は11時からみたい。
山Dはいちどきたことがあるって。でも入ったことないんだって。またこんど来たいなぁ。
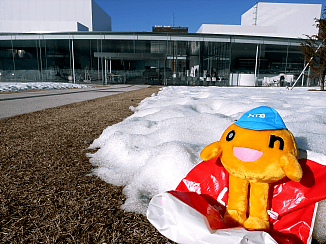
歩いて5ふん。金沢21世紀美術館にきたよ。この美術館は2004ねんの10月にできたば
かりなんだよ。たてものぜんたいがまん丸なんだって。
・・・くわしい紹介は、あした追記するって、山Dが言ってる。

12じ52ふん発のサンダーバードにのって、京都へかえりました。
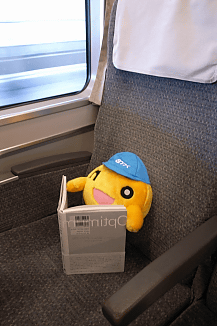
山D、美術館で本をかったみたい。本が好きなんだねぇ。
「デザインの原形」
企画・構成:深沢直人+原研哉+佐藤卓、制作:日本デザインコミッティー。
六曜社刊。2500円。
きょうは疲れたから、お風呂に入って寝るそうです。
おやすみなさい。
- 2006/1/21(土)
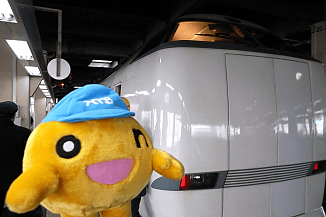
ぼく安田さんOnちゃん。HTB(北海道テレビ)のマスコットキャラクターだよ。
きょうは山Dがどっかにでかけるっていうから、ついていくことにしました。電車にのるみたい。

「冬の湖西線から眺める琵琶湖はきれいやー」と山Dがいってました。
それにしても、なんで写真をとるときにこそこそするんだろう。
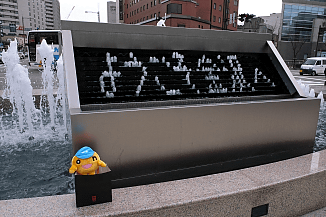
じゃーん、なんとかなざわえきにつきました。なにしにきたのかな?
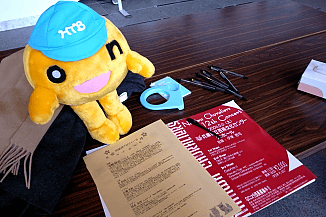
山Dがやってきたのは「金沢観光会館」っていうところ。でも、ここって、ほーるみたいだよ。
で、着くなりなにか作業をはじめちゃった。ぼくも手伝ったけど、「ひるごはんたべる時間なか
ったからお腹すいた...」って弱音をはいてたよ。
1じかん30ふんくらいやってたみたい。さぎょうしながら、あちこちにでんわしてたとおも
ったら、おわってすぐにべつのさぎょうをするためにまた移動するんだって。
「NCで問題発覚...」とか言ってた。
えきまえのほてるから「がくふ」をとってきて、コンビニでコピーして、ファックスを送るん
だって。おわったら夕方だったよ。おおずもうがはじまるじかん。
「なにか食べないと僕は死にます...」って山Dが言ってた。

もういっかい観光会館にもどってきたよ。あ、山Dはこの演奏会をききにきたんだね。
イトウってひとがが指揮をするって教えてくれた。さっきやってたのはチラシバサミ
っていうみたい。

えんそうかいってはじめてなので、どきどき。
19じ半ごろにおわったよ。すごくすてきなうただったよ。
「清冽な強さっていうんかなぁ。おごってるわけでもないし、しゃかりきでもない。弱声も強
声も、ぜんぜん乱れない。ひとのこころのまよいとか、そんなものをさーと吹き流してくれる
風みたいやった。おそれず、ひるまず、どんな音も響きだしからしっかりと、はっきりと。き
いてて、たるむようなところがないねんな。うたいかたもとても自然。まじめなんやなぁ。固
さのないまじめさかな。音楽的なことを追究したら、固くなってうたったりできひんかったん
やと思う。組曲をどの曲も退屈せずに聞けたのって、はじめてかも。関西の大学合唱団の演奏
会に行くと『価値の多様化による学生合唱の弱体化が...』って、学生が自分たちで書いてしま
ってるけれど、そんなこと言ってる間にもっと練習したり、金沢までこの演奏を聞きにこなあ
かんと思う。あっ、そうそう。演奏開始のベルが、阪大の学歌になってたね。あれ、いつもジ
ョイントしてる阪大混声に敬意を表してのことなんやろね。礼儀ただしいなって思った。」
って、ながながと山Dにきかされたよ。
ぼくはアンコールの「やさしさにつつまれたなら」っていう歌がとてもきにいったよ。

えんそうかいのあとに、げんちのひととごはんをたべにいったよ。
「この牛筋煮込み、京都とおんなじ味付けや~。お酒ともすごくあうよ~」って山Dが感激
してた。山Dはおちょこの10分の1くらいだったら、お酒がのめるようになったんだって。
でも、とちゅうでちょっとやばかったから、ウーロン茶をたくさん飲んだとも言ってたよ。

10じはんにホテルにもどってきました。山Dはホテルのおくじょうにある露天風呂にいくんだ
って。ぼくはお酒がまわってきたみたい。きもちいいから、このままねますー。おやすみなさい。
いい演奏会だったなー。
- 2006/1/20(金)
BK練習、19:30~21:00参加。Eは出てるという実感はあるけど、Esになるとか
なり怪しくて、息がぼえっと出てるようにしか感じられない。ところが、全パートであわせる
と、不思議なことに音が目に見えてきた。和音のなかでのEsが空間にうかびあがったような
気がした。そのEsが土台にあるから、ほかのパートの音が際立つということを、和音の理論
ではなくて体感できた。自分の音をだそうだそうと思っていたときはなかなかわからなくて、
自分の声が聞こえなくなるときに、はじめて聞こえるということを今日ほど実感したことはな
かったかもしれない。つくづく、Kreekの曲はすごいなぁと思った次第。音楽としては、BK
の演奏は、まだたどたどしくて、弱々しいのだけれどね。
BK宴会、21:30~23:30ごろ参加。方言の話で盛り上がる。関西弁8拍子説、栃木
弁レチタチーボ説ほか、音楽的な解釈や想像がふくらむ。その場では話がなかったけれども、
関西以外のひとが関西に来ると、関西の言葉に侵食されてしまうケースが多いのはなぜなんだ
ろうかと思う。ほかの地区の方言に比べて、異常に高いと思う。友人とはじめて会ったころ、
関東出身だというのに、本当によどみのない、きれいで優しい関西弁をしゃべっていたことに
驚いて、そして感動したことをいまも憶えている。逆のことは絶対に自分にはできひんのやろ
なあと、すこしうらやましく思ったものだった。マザータングが土台にあるうえでの関西弁と
いうものは、面白いテーマかもしれない。
帰宅途中、マスクを買う。再度の風邪や、インフルエンザ予防のため。気づいたのだけれど、
マスクをして鼻で呼吸すると、眼鏡が曇りますな。それは盛大に曇ります。口で呼吸すると大
丈夫なのはわかっているけれど、普段口で呼吸することに慣れていないので、戸惑ってしまう。
え、普通は鼻呼吸?そうでもないんですよ。街中や電車で観察していると、逆に鼻呼吸できな
い人が増えているように思われるのだ。口が微妙に開きっぱなしという人が少なからずいる。
あなたも明日電車に乗ったら観察してみよう。
- 2006/1/19(木)
きのう、マッサージ屋にいったのだ。効果は絶大で、今朝の身体はつきものが落ちたかのよう
な軽やかさ。ぼわーっとした熱も今日はない。...であるが、集中力であるとか、頭の回転は
かなりいまいち。4行くらいでかけるフラグ立てのアルゴリズムが思い浮かばず、四苦八苦。
思い浮かぶなんてレベルじゃなくて、指先が勝手に描いてしまうようなものなのになぁ。定時
からやっていたデータベースの修正でポカミスをして、これまた修正に時間を費やす。簡単な
ミスほど、修正箇所は多く、めんどうなもの。救いは以前、同じようなミスをやったとき、
リカバー用のスクリプトを書いていたこと。ああ、あのときのわたし、よく面倒がらずにこの
スクリプトを書いていてくれた。しかし、しなくていい仕事をしてしまったのは変わりなく、
今日完成させるつもりのツールは進捗90%であった。がっくり。
帰宅後、血糖値をあげて脳を活性化させるべく、プッチンプリンを3個食べた。
きょうは、さっさと寝よう。
と思ったのだが、読んでいる小説がいいところなので、読みきってしまおうと思う。
意思が強いのか、弱いのかわからない自分だった。
...弱いんだろうナァ。
- 2006/1/18(水)

阪急河原町駅で見つけたAED、自動体外式除細動器。病院の待合所以外、街中で見るのは
初めてだ。愛知万博でも会場内に多数設置されたと聞くし、近年増えているようだ。しかし
実際にこれを一般の人が使うのは難しいという気がする。そもそも、除細動という言葉自体
になじみのあるひとは少ないだろうから。どういう症状のときに、どのように使うか、とい
うパンフレットなんかがあるとわかりやすいと思う。あと、教習所の応急処置講習のなかで
人工呼吸の実習があるけれど、あのときに一緒にやってはどうだろうかと思う。
そういえば、ここ1年以上細動発作は起きていない。よい傾向。
可能ならば、AEDのお世話にならず平穏にすごしたいなぁ。
36.7℃、平熱に近づいてきたので、ちょっと安心。
「東証、取引停止」のニュースには、ちょっとくらくらきましたが。
- 2006/1/17(火)
震災忌。11年経つと、やっぱり記憶が薄れてしまうのだな。
直接、あの現場にいたわけではないから。
ライブドア、やってくれた。日経平均株価が400円も下がるなんて予測もつかない。そもそも、
一企業の不祥事が株価にこれだけダメージを与えるっていうのはどういうことか。過去の企業の例
を見てもなかったことだ。それはつまり、誰もIT関連企業の株を、企業の本質的な価値を見て買
っているわけではないということだ。ライブドアの株価と同様、ほかのIT関連の株価も「なにか
あやしいのじゃないか」という不確かな推測が働いたからで、まじめに商売やってる企業にとって
みたらとばっちりもいいところ。これが平均株価20000円まで行くと言われている株価の実態なのか
もしれない。機関投資家が大勢を占めていた昔ならこんな動きはなかったような気がする。ちょっ
としたことに付和雷同する、個人投資家の動きは本当におそろしい。
急にこんなことを言い出したのは、わたしが、日経225銘柄の平均株価に連動する投資信託を買
っているからなのだ。1万9000円ほどプラスだったに、5000円のマイナスですよ!ううう。
きのうの夢:
なぜかわたしはF1カーをカートみたいな取っ手を持って、後ろから押して歩いている。運転の練
習をするためだ。再開発地区のようなだだっ広い道に出たところ、家族連れの男性に何をやってい
るのかと怪しまれる。いやいや、運転の練習をする場所を探しているのです、とこたえると、あち
らの方なら人気もないので、適しているのでは?と親切に教えてくれた。男性はどこか大店の旦那
のようで、茶色の羽織をはおっていた。染め抜きをみると、「やきそば、しょうゆ」と二列に縦書
き、そのうえに横書きで「ほし」とあった。老舗のしょうゆ屋であると理解する夢のなかのわたし。
その後、歩いていると何かのはずみで、バックで立体駐車場の出口から車が入ってしまった。あわ
てて、運転席に乗り込み、出口に向かおうとするが、エンジンが入らない。傾斜がついているため
勝手に進んだが、こんどはとまらない。ブレーキを探すが見つからず。出口の扉に激突するも、ダ
メージはなく、なんとか外に出られる。出口にいた、従業員とおぼしき女の子二人を説得して、
駐車代を払わずに済む。すると、お金を払っていないのにおつり?と思しき、エナメル地の丸い
硬貨のようなものをもらう。なんとなく受け取らないと、向こうのほうで、つじつまあわせがで
きないということを理解して、そのままもらっておく。
出てすぐのところに、メイド服のようなものを来た眼鏡の女の子に、今度は靴を検査される。壁に
はたくさんの靴の革のサンプルが用意されており、それをもとに比較するものらしい。安物なので
不可とされて、左手にある出口(なんの出口やら不明)から出ることを許されない。必死に、この
靴はハッシュパピーの靴だからいいじゃないかとよくわからない弁明をするわたし。その靴はいつ
ものアシックスペダラの革靴なのに、なんでウソついているのだろうと頭のなかで考えている。
と、そこで終わった。車の件はなんとなく想像がつくものの、それ以降の内容はなんなんだろう。
車にしたって、なぜF1か。不思議。
体調、変わらず。微熱。
もっと、健やかに、気持ちのいい夢をみて眠りたい。
- 2006/1/16(月)
今日は散文です。写真展の感想は風邪が治ったくらいになるかもしれませぬ。
相変わらず、37℃の微熱が続く。かんなで削るようにうすくうすく、しかし持続的にエネルギーが
熱となって削り取られていくので、けっこうしんどい。プログラムを書くときの集中力はなぜだか
増している。センサーをすべて駆動する余裕がないから、外界からの雑音が入らないからかも。
仕事をしている途中から左手の手首やひじの関節が痛くなってくる。左手だけなので、風邪の症状
というよりか、鎮痛剤の副作用のような気がする。市販の風邪薬や、病院の薬は眠くなるものが多
いので、週末以外は頭痛薬を解熱鎮痛剤として使っていた。それにくわえて、普通に頭が痛かった
りもしたので、ここ数日つづけてのみすぎたように思う。
さいきん、野菜が足りないなぁと思っていたら、きのうの夢のなかに野菜生活の缶を買い置きして
のんでいる夢を見た。
しんどくても本屋に行くと治るような気がして、ついつい帰りに立ち寄ってしまう。
今日は二冊買った。
「祖国とは国語」、藤原正彦著、新潮文庫。400円。
世の流れに対して、危惧を持ち、警鐘を鳴らす場合、センセーショナルで過激な物言いの方が、ふ
りむいてもらえる率は高いし、話題になる。でもそういう物言いは見て、聞いて気持ちのいいもの
ではあまりないし、ときに目をそむけたくなる。かといって、ものわかりのいい、どこまでも善人
的な物言いには力はないし、正論ばかりだと世に通じないばかりか、逆に敬遠される。難しいこと
なのだ。でも、藤原氏はあえてその難しいことをやろうとしている。その物言いは、わたしには品
格をもって怒っている、というように思われる。ぶつけるだけの怒りを書くような職業作家やエッ
セイストよりも、よほど世のなかに伝わるんではないだろうか。
「female(フィーメール)」、小池真理子、唯川恵、室井佑月、姫野カオルコ、乃南アサ著、
新潮文庫。362円。
この本は立ち読みで買おうと思ったのではなくて、はじめから買おうと思って買ったのである。
題名と、5人の作家による共著だということ、新潮社刊ということだけ知っていたのだけれど、
さて文庫コーナーに着いてみたはいいけれど、どこをさがしたらいいのか途方にくれた。文庫本
に限らないが、書店での本は著者別に並んでいるのが普通なのだ。図書館のように題名順に並ん
でいるところはまずない。なので、題名だけ知っていても探すのに役に立たなかった。しかも共
著というか、短編アンソロジーなので、どの著者のコーナーに入っているかもわからない。これ
は本当に困った。前に、見かけたときはたまたま平積みにされていたので、目に入ったのだけれ
ど、いったん文庫の棚に納まったら、端から端までみていくしかないのだった。
見つけたのは、小池真理子のコーナーだった。文庫の背の分類番号のところには「こ***」と
ある。著者が複数いる場合、先頭に記された著者分類になるよーだ。ところで、わたしはこの5
人の作家の本はいままで読んだことがない。だのに、この本を買ったのは同名映画の原作本であ
るから。去年、みなみ会館まで映画を見に行ったのだ。その映画の話を聞いたのは友人からであ
るが、友人は見逃していて、かわりに原作を読んだ。そして、ちかごろDVDが出たのを知った
ので、わたしはDVDを見ることをすすめ、かわりに友人には原作をすすめられたという次第。
本屋の入り口に「博士の愛した数式」の映画のチラシが置いてあった。そう、映画になったのだ。
1月21日公開。お決まりのように映画を先行してみた人の感想が書いてあったのだけれど、
よく見ると、いわゆる著名人、芸能人といったひとたちではなかった。10人すべてが、本屋の
店員さんだった。そう、原作は第一回本屋大賞受賞作。本屋さんが選んだ本なのだから、こうで
なくては、映画を作り、宣伝する人たちがそういう風に考えてくれたのはなんだかとてもうれし
いことだった。見に行かないといけない。
しんどいとか言っているわりには、たくさん書いてしまった...。
- 2006/1/15(日)
旧成人の日。午後から、京都国立近代美術館へ行く。企画展「ドイツ写真の現在」を見るためだ。
この展覧会のことは地下鉄の中吊り広告で知ったのだけれど、「ドイツ写真」と聞いてもピンとこ
かった。というのも、ドイツという国はライカや、ツァイスなどの非常に優秀なカメラを生み出し
た国ではあるけれども、こと写真家、それも世界的なとなるとほとんど輩出していないというのが
わたしのなかのイメージだった。しかし、これは少し不勉強であったみたいだ。
....すいません、ちょっとしんどくなってきたので、この続きはまた。
目が疲れたような感覚。やや熱っぽい。穴があくほど写真を見ていたわけではないのになぁ。
ひさしぶりの展覧会なので、疲れたのかも。
寝ます。
おぼえがき
夕食:冷奴、ハムカツ、ポテトサラダ、さんま、いわしフライ、キリンレモン、ウーロン茶。
- 2006/1/14(土)
NC練習、17:30~21:00。
きょうは林号に乗せてもらい帰宅。22:00を過ぎてから高速を出るとETCの場合、料金が
半額になるため、京都南までぎりぎりの攻防。具体的には時速50kmで走ったり、桂のPAに
入ってみたりなど。その甲斐あって、22時ちょうどにインター通過。無事500円の表示に、
全員(3人)で歓声をあげたのだった。
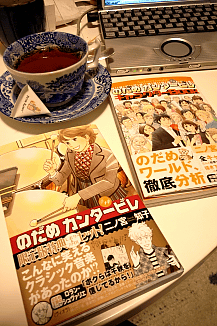
ぎゃぼ、のだめカンタービレ14巻&キャラクターブック。
これから一心不乱に読むのデス。
パーマをかけたのだめ(14巻表紙)、かわいいなぁ。
あしたは、京都近代美術館にでも行こう。
- 2006/1/13(金)
BK練習、19:00~21:00。
BK宴会、1時間のみ出席。
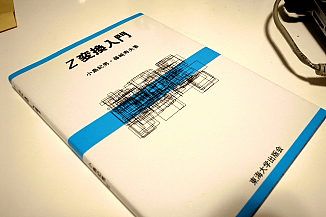
知り合いのM川さんのHPに「テイラー展開がなんの役に立つのか未だにわからない」という
ことが書いてあって、ちょっと気になった。わたしは工学部出身なのであるが、恥ずかしなが
ら、テイラー展開を具体的に何かに使ったことっていうのは確かにない。わたしは代数のなか
でも、級数というのが特に苦手だったせいもあり、いまでもテイラー展開とか、マクローリン
展開というものを聞くとさけて通っている。
しかし、テイラー展開はともかく、学生時代に勉強したことというのは、今になってみると、
「試験を受けなければならない」「単位をとらないといけない」というプレッシャーから解放
されている分、いくぶん興味をもって振り返ることができるような気がする。工学部だったと
いうことを忘れたくないっていう意識も多分にあると思う。
まえに少し書いたかもしれないが、純粋数学というのは嫌いで、どっちかというと、工学者の
立場からみたツール的な数学の方が好きである(得意とは限らない)。大学でも、そういった
ツール的な数学を教えてくれたのは数学の先生ではなく、工学部(わたしは電気)のセンセイ
方で、授業も興味をもって聞いていたのを憶えている。なにしろ、「なんの役に立つんやろ」
と考えてなくてもいいのが、ありがたかった。ツール的数学は、工学の世界をひろげてくれる
ルーペであり、また望遠鏡みたいなものだったので、好奇心と探究心さえ備えていれば、自然
とその有用性が理解できたのだ。
そういった数学の代表例が、ラプラス変換であり、Z変換だったと思う。電気回路の過渡応答
や、音響回路工学、電気信号処理には欠かせなかった。この本は、1996年4月28日にジュンク堂
で買ったもの。当時M1。なんでそんなに正確かというと、レシートが挟まってたから。むかし
から買った本に、そのままはさんだままにしておくことが多い。それはともかく、当時は勉強
せにゃーという気概でいっぱいだったのだなぁ。いま、これをいきなり読み返してみても、さっ
ぱりわからにゃい。まずはラプラス変換から思い出さないといけないのだ。
テイラー展開もふくめて、そういう場合はここ。
http://www.tohtech.ac.jp/~comms/nakagawa/taylorexp/taylor1.htm
- 2006/1/12(木)
風邪、微熱が続くが、薬のおかげかのどには来ないので助かる。身体の節々が痛いというこ
とは、治りかけのフェーズに入っているとみてよいか。念のため、夕食後に小児用ジキニン
をひとびん服用する。子どもは真似したらだめ(小児6回分にあたるので)。
BKで前回練習をはじめたKreekの4つのダビデ詩篇、Taaveti lauluの復習をする。何の気なし
にネットで検索したら、第8回Vox-Gaudiosa定期演奏会のプログラムが見つかる。...あれ、
ということは、この曲を聞いたのはVineの演奏を聞くよりも前ということだ。わたしはこの
演奏会を聞きにいっていたのだから。いまのいままで気づいていなかった。
>色調は控えめで大気のような絵画。すばらしかった。(2005/02の電波暗室より)
とは書いている。でも1/6に書いたような響きを感じたわけではなかったみたい。はじめての
歌声、よその土地での演奏会、ということもあって緊張していたり、歌声に圧倒されていたの
だと思うけれど、ひいきのひきたおしをするならば、わたしにとってはVineの歌声のほうが、
心地よかったということなんだろうかなぁ。Gauidiosaに比べれば、聞きなれている声だから
安心できたということもあるのかもしれない(聞く前はいつも緊張するのだけれど)。
かりにYKが歌ったら、やっぱり違うように感じるのだろう。
BKなら、どうなるのかなぁ。
VineとBKはときに混同されるし、重複メンバーも少なからずいるのだけれど、やっぱり違う
演奏になるだろうし、違うものでありたい。Vineと違って、わたしは歌うがわにいるわけだ
から。聞いてくれたひとが、ただきれい、美しいといってくれるだけでなくて、一緒に歌い
たいんですといってくれるような演奏ができれば、それはBKらしいっていえるような気が
する。
もう一度、復習してから寝ます。
いい夢みたい(きのうはかなり変な夢だった)。
- 2006/1/11(水)
○○かぜ内服液を飲んだ。
加湿器を投入。
腰の痛みが、ぶり返してきたのが気になる。
元気なときに調子に乗りすぎるのが原因なのだろうなぁ。
眠ります。
- 2006/1/10(火)
風邪引いたみたいです。
更新休みます。
- 2006/1/9(月・祝)
正午、自転車で出かける。新町を南下、七条新町のなか卯で昼食。ここのなか卯はちょっと
変わっていて、歴史的建造物の認定を受けている旧富士ラビット社の1階部分にあるのだ。
外観に配慮して、意匠や看板はやや控えめ。賛否はあると思うが、賑わいがあるほうが建物
にとっていいと思う。無粋な感じはしない。
昼食中、偶然にもMAD WORKSのTAM氏と出会う。ここは氏の勤務先に近い。やはり休日出勤で
あった。最近のアニメ情勢(?)について歓談。暖かくなるころに、尾道ツアーをしよう、
という話をして別れる。氏の手には、冬コミ発行の新刊の通販用封筒が握られていた。会社
のひとも、昼休みに氏が封筒を買ってきた理由はわからないだろうなぁ。
さて、そこから約5分、本日の目的地に到着した。
鉄道五大聖地のひとつ「梅小路蒸気機関車館」である!バーン(効果音)
※鉄道五大聖地
ほかの4つは、秋葉原「交通博物館」、青梅「青梅鉄道公園」、碓氷峠「碓氷峠鉄道文化む
ら」、弁天町「交通科学博物館」を指す。わたしがいま勝手に考えたのだが、大筋で間違っ
ていないはず。このうち聖地(秋葉原)のなかの聖地というべき「交通博物館」が、今年5
月に閉館してしまう。2007年、大宮に「鉄道博物館」として移転する計画であるが、「交通」
でなくなった点が惜しまれる。交通博物館は確かに鉄道中心だったが、自動車、船、飛行
機に関する展示もあったのだ。
さて、以下写真日記風に紹介。

蒸気機関車館の中心、国重要文化財にも指定された扇形倉庫と転車台。
 
なかにはもちろん、蒸気機関車が立ち並ぶ。動態保存(実際に動く)が基本。

「D511」(1/25sec,F2.4,ISO64、ノートリミング)

「C581」(1/50sec,F2.4,ISO64、BWモード、ノートリミング)
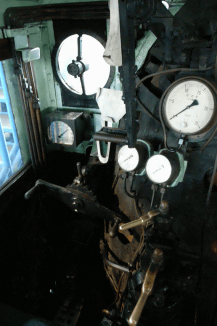 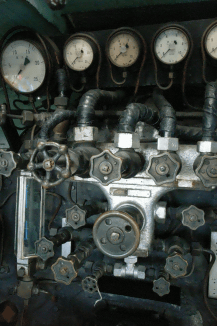
一部の車両は、運転席の見学ができるのだ。うーん、ビバ圧力計。
(むかしは、汽笛を鳴らすことができた)

日に5~6回、実際に走行するSLに乗車できる。この日は特急つばめを引いたC62。

乗車待ちの列。100%親子連れ。「鉄」の英才教育といえよう。
ちなみに乗るのはトロッコ車両。絵的にはいまいちだけれど、機関車を生で感じるにはそれで
いいのかも。

屋外展示施設兼、実用も兼ねている給水塔。
また、構造物を撮ってしまった...。

屋外展示施設、旧客車。台車を除くほとんどが木製の客車。デッキのドアは、走行中、手であ
けることができた。わたしが幼稚園入るか入らないかのころまでは、山陰線をDD51にひか
れて普通に走ってた。いまでは客車(モーター無し)という存在自体が珍しくなってしまった。
梅小路には子供のころ、親に何度も連れて行ってもらった。蒸気機関車というものに、ノスタル
ジックな特別な思い入れがあるわけではないのに、大人になってからも何度かおとずれているの
は、普段目にしている電車とはあきらかに違う、その巨体に魅せられたからだと思う。くろぐろ
とした鉄の塊でありながら、細部はギアと動輪、パイプが複雑に組み合わさった精密機械。その
ギャップ。手をふれるとひんやりするその身体も、一度うごきだせば、煙をはき、蒸気をふきだ
し、近づくだけでその熱を肌に直接感じることができる。人間の操縦に呼応して、生きているか
のようだ。ときおり、子どもが「こわいー」と泣き叫んでいるのも、生理的には当然の反応なの
かもしれない。
それにしても親子連れが多かった。鉄道はあいかわらず子供には人気なのだな。
それが、大人になっても好きだと、鉄とか言われてさげすまれるのは納得がいかないぞ。
みんなこどものころの純な心を思い出すのだー。
おまけ劇場
 山DはD51をみつけた。 山DはD51をみつけた。
 搭乗する(注:上ってはいけません)。 搭乗する(注:上ってはいけません)。
 釜炊きはきついなぁ。 釜炊きはきついなぁ。
 業務終了、下車。 業務終了、下車。
 破壊工作点検をしている山D。
<終劇>
こんな大人にならないよう注意。
- 2006/1/8(日)
訂正があるのだ。今日、用事があって実家に行ったときに判明したのだが、実家のT-FALのタイプ
はコレ↓だった。
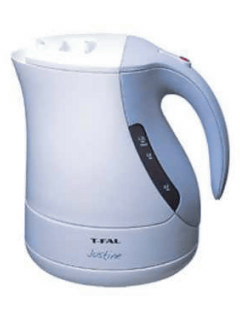
すっかり旧型だと思いこんでいたのだが、全然形違うなぁ。人間の観察力というのはこの程度のもの
であてにならないものです(個人的なことから一般的なことにすり替えてみた)。とはいえ、このタ
イプは水差しのような形状からして、全タイプのなかでもっとも持ちやすいのではないだろうか。取
っ手と重心軸の距離がかなり近い。
(しかしなぁ、旧タイプどこかで見たような気がするんだけどなぁ。)
構造建造物にひかれる今日この頃。こういうのばっかり撮ってるからポートレートがうまくならない
のかもしれない...。
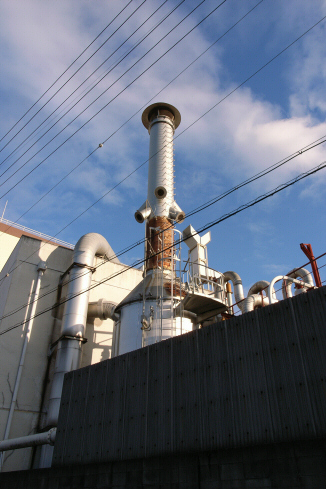
1/400sec,F5.0,ISO64、ノートリミング

1/60sec,F8.0,ISO64、ノートリミング

1/400sec,F5.6,ISO64、ノートリミング
あしたも、何か撮りにいく予定。
- 2006/1/7(土)
18:00~21:00、NC練習。次Tさん復活。どれだけ待ち望んでいたことか。ベースが正常
に鳴る。余計な音がない。パート内で音をあわせにいくという、久しくなかった感覚。安心して歌え
る。すばらしい。
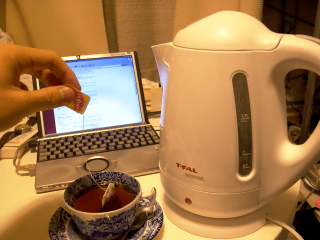
買ってきましたよ、電気やかん
じつは紅茶よりも先にカップヌードル食べるのにお湯を使ったのだけれど、見栄えを気にして紅茶で
撮影してしまった。
買ってきたのは1.7lタイプ。自宅で使うなら1lタイプで十分なのに、1.7lタイプを買ってしまったの
はそれなりの理由がある。1lタイプはなんとなく持ちにくかったからだ。どういうことか説明しよう。

これは実家でも使っている旧タイプ(1l)のもの。

そしてこれは、新タイプ(1l)。
パイロットランプの有無や、確認窓の位置・形状をのぞくとほとんど同じ形なのだけれど、ひとつだ
け大きな違いがある。わかってもらえるだろうか。そう、取っ手の形状が微妙に変わっている。新タ
イプの方がほんの少しだけ外側へ広がり、空きが大きくなっている。たったそれだけの違いなのに、
実家で旧タイプを手にしたときの持ち加減と、店頭で新タイプを持ったときの加減がまるでかわって
いたのである。「空き」を広げたことで、重心の軸が取っ手から離れてしまったこと。それとおそら
く重心の位置が従来よりも高くなっているのではないだろうか(水が入っていない状態での主観的な
比較)。この二点によって加減が変わってしまったと考えられる。
で、やや大きい(縦に長い)ものの1.7lタイプを持ってみると、旧型に近い持ち加減である。縦長の
分だけ重心が低いこと、縦型の形状にあわせて持ち手が1lタイプに比べて重心軸に近いであろうこと
が、その理由ではないかと思う(力学は大学の一回生時にならったきりなので、いい加減)。
こういうものは値段よりも使い勝手(=ストレスがない)を重視すべきである!と判断し、1.7lタイ
プを購入することになった次第。1000円高いのだけれど、ポイントを使ったのでダメージは軽微
で済んだ。
いやぁ、やっぱり沸くの早い。それと実家では気づかなかったのだけれど、沸いていく過程が実感で
きるので、待っている間に退屈しない。残量を確認する窓から、湯がぐつぐつ、ぼこぼこ煮え立つの
が見えるのだ。沸騰間際になると、それはもう激しいのなんのって。これは意外な発見で、けっこう
見ていて楽しいのだった。
あしたも使おう。
- 2006/1/6(金)
BK練習。新曲をやる。そのうちの一曲はVineがこの前のコンクールで演奏していたものだ。はじめ
て聞いたとき、心のなかのつらいことも、苦しいことも、一瞬にして洗い流されてしまう、いや浄化
されてしまうような感覚を味わって、どう感情を表現したらよいのか混乱して、ただ自然と涙がでて
きてしまったことを憶えている。音楽のもちうる力の大きさ、ある意味での恐ろしさを教えられた。
この曲には、立ち向かうことも、抗うこともできない。ただひれ伏して、あるがままを受け入れるし
かない。これこそが天の恩寵、無上の喜びというものかもしれないなと後で思った。いまでも思う。
曲が終わると、すぐに現世に返ってしまって、ぬぐいさられたはずのつらさも、苦しいことも、思い
だされてしまうのが、悲しいところである。俗人だからいたしかたない(と開き直って、つよがって
みる)
ぶどうだったら、どんな演奏ができるのか。それを楽しみに頑張る所存。
ベースらしい働きをしないとね。
今年の夏コミの件であるが、日程が8/11,12,13なので迷っていた。8/12は淀川混声合唱団の定期演
奏会なのだ。夏コミに参加する=よどこんの演奏が聞けない、ということになる。そのことを知っ
たとき、8/11の夜に大阪に戻り、12の演奏会後に再び東京へ行くというプランも考えたのだけれど、
わたしがサークル参加する場合のジャンルはメカミリ、つまり二日目の配置のため、12の少なくと
も10時から16時までは東京にいる。土曜日だから、開演時間は遅いかもしれないけれど、最短でも
20時着になりそうだし、物理的に無理な気がする。昼、もしくは夕方開催ならまず無理だなぁ。
よどこんのみんなの演奏が聞けないことは、本当につらい。でも、2006年の夏コミに参加すること
もわたしにとってはかけがえのないこと。まぁ、サークルが当選するかどうかはわからないんだけ
れど、きょうの時点では、夏コミに参加することを優先すると決めた。そして、ぎりぎりまで最大
限の努力と画策はしてみるつもり。欲張りかな?
- 2006/1/5(木)
正月に実家に帰ったときに、これほしいなぁと思うものがあった。T-FALというフランスの家電メー
カー(?)の電気ケトル。日本語にすると電気やかん。まぁ、だいぶ前から実家にはあったのだけれ
ど、保温機能のない湯沸し程度の認識しかなかったのだ。
元旦、母と妹が親戚のうちに遊びに行っているとき、父方の従兄弟が奥さんと挨拶に来ると連絡が
あった。来てからお茶を入れるのは時間がかかるし、よしあらかじめ湯を沸かそうと思っていると
電気やかんが目に入った。ふむ、せっかくやし試してみようと思い、水を注ぐ。お、台座部分から
とると軽い。湯沸しみたいに給水がめんどくさくない。では、と思って台座に置く。それだけでい
いみたいだ。で、お茶葉お茶葉と探していると「カチッ」という音がした。水曜どうでしょうで、
藤村Dが切れたときの音よりかはいくぶん固めの音。なんというか、コンロで湯をわかすのに比べ
て体感速度で10倍くらい早いのではないだろうか。かなり驚いた。
5分後に従兄弟夫婦がやってきたが、仏壇におまいりすませると、夕食どきだからというので、あっ
という間に帰ってしまい、お茶を出すどころではなかった。ひとりで食べるんだから、別によかっ
たんだけどなぁ。お年賀だけはもらってしまったし。
まぁ、ともかくそういうわけで、はからずも電気やかんの実力がわかったのである。
この品物で気に入った点と、自宅での有用性について述べよう。気に入った点は、沸いたときに、
カチッと、ボタンが戻る音がするだけという点。あ、さっき台に置くだけでいいと書いたが間違い
だった。この取っ手の近くにあるボタンを押し込む必要あり。で、このボタンがもとの位置に戻る。
ピーとか、ピッピ、とか電子音じゃないのがいいと思う。わたしは「気にしい」なので。電子部品
は使ってなさそうなので、構造が単純っぽい。たぶん壊れにくい(これは想像)のも○。
次に有用性についてだが、自宅にはやかんあるが、メインはお茶専用なのだ。つまり、湯を沸かす
にはなべを使うか、お茶を飲み干す必要がある。お茶を飲み干したとしても、そこからお茶葉をか
きだすのが大変めんどうくさいのである。前に友人にその話をしたところ、スーパーにいってお茶
葉袋を買いなさいと言われたのだが、未だに実現できていないのだった...。m(_ _)m
しかしだ、この電気やかんがあれば、心配無用。お茶が残っていても、なべを洗っていなくても、
カップラーメン用や、コーヒー紅茶用に湯をわかせる。それも早く。いらちで、ずぼらのわたしに
ぴったり。
という経緯があって、今日帰宅前に寺町に寄ってみた。ところが!なんと7000円近くするじゃ
ないですか!!いいとこ3500円くらいだろうと思ってたのに。電気やかんなのに、そんなする
なんて、湯沸し器の安いやつだったら買えるんではないのか...。これが世にいう付加価値で儲け
るというやつなんだなぁと、ちょっと感心した。(早いに特化して、それ以外のいらん機能をそぎ
おとすという逆の付加価値の方。iPod shuffleと似てる)。
とりあえず、ネットで世の価格動向を調べてから買うことにして、パンフだけもらって帰宅した。
安いところでも6000円くらいが相場のよう。あまり値崩れしないのも、こういう商品の特徴
だよなぁ、などと考えながら、とりあえず週末にヨドバシに行こうかと思っている。ポイント、
2000円くらい残ってたし。カメラのナニワなら8000円くらいポイントあるのになぁ。カメラ屋に
電気やかんは売ってないやろなぁ。
- 2006/1/4(水)
寝ていると壁のポスターが突然はがれてきたり、起きるとひどい頭痛であったりしたのだけれど、
直前に見た夢のおかげで、ちょっと幸せな気分になれた。これを今年の初夢と認定する。
午後、大学の同期と初詣。腰は寝返りがうてるようになり、出かけるには支障がないレベル。
夕食までの暇つぶしに寄ったLoftで手帳を買う。12ヶ月のカレンダーオンリーの薄いもの。たぶん
不精なわたしとしては、これくらいが精一杯。ついでにパーカーのシャープペンを新調する。削り
出しの金属ボディが美しい。これで万年筆、ボールペン、シャープペンと、まともな筆記具がそろ
った。
帰宅後、合唱の予定を書いてみた。何の行事もない月は、1月と9月のみ。それも2月、10月の行事
に備えた練習があるから、別に予定が空いているわけではないのだった。合間にコミケに向けた
本作りとサークル参加が入ることになる。あ、そうそう夏の申し込み締め切りを手帳に書いておか
ないと。今回からオンライン申し込みができるらしい。郵便局にいかなくても、クレジットで申し
こみができること、サークルカットを画像入稿できる点がありがたい。ただ、オンライン申し込み
でも申し込みセットの購入が必要な点は、ちょっとフェイントかも。間違えて買ってない人がいる
んじゃないだろうか?
あと、本作りまでに新しいデスクトップPCと、PhotoshopCSを買わないといけないな。今回の件で
キンコーズで作業するのはもう限界だと悟ったことだし。場合によっては、DTPソフトも欲しい
なぁ。Photoshopで文字組みするのはどう考えても無理がある。とりあえず、サークルカットまでは
キンコーズ製作だと思う(お金がない)。。。
今年も頑張ります。去年みたいに、つぶれないように。
追伸:夏の申し込みについては、実は少々悩んでいる。本も作りたいし、コミケにも行きたい。悩
んでも、もはやどうしようもないことなので、最終的には申し込むことになると思うのだけれど。
(この冬の在庫も売らないといけないし)。きちんと決めたら、報告します。
- 2006/1/3(火)
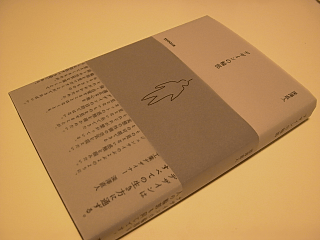
「デザインの輪郭」、深沢直人著、TOTO出版。1800円。
深沢直人は、工業デザイナーである。氏のデザインに対する姿勢というものは、ジャンルは違うが
グラフィックデザイナーの原研哉と通ずるところがあると思う。それはゆるがない哲学をもってい
る点である。工業デザインは文字通り、工業製品のかたち、つまり「輪郭」をつくるわけで、いわ
ば、世間的にもっとも「デザイン」と聞いて思い浮かべるであろう「デザイン」をする仕事なのだ。
それは、たぶんに個人の感受性であるとか、ひらめきであるとかによるところが大きいと思われて、
それがいったいどういう理由で、どのように生み出されるのか、ということについては、ほとんど
関心が払われていないように思う。それゆえに、工業デザインを考えようとすると、いったい何が
重要なのかということが、初心者にはわからない。工業デザインというものは、必然のデザインで
なければならないと私は思っている。プラスでも、マイナスでもない、0の位置にあるべきもの。
ものの形が本質ではなくて、その工業製品の機能が本質だからだと思うからだ。その本質をひきだ
すためのもの、人間とのインターフェースとなるもの、それがデザインであると思う。そう考える
と、そのものの機能を理解しているだけではデザインはできなくて、そのものがおかれる環境や、
使う人の五感、といったものまで意識しないといけないはずなのだ。それは実に難しいこと。
この本は、深沢直人がこれまで蓄積してきた、あるいはいま考えているそういった「デザイン」を
生み出すために必要な概念、言葉、感覚をひとつひとつ整理して、語ったものである。では、ここ
に語られた言葉は、すべてデザインを学ぶ人たちのためのものか?というと実はそうではない。
カバーに書かれていることば、それは「デザインはすべての生き方に通ずる」。ずいぶんと、たい
そうな物言いであるけれど、なにも人生の指南書というわけではない。「デザイン」を考えるとい
うことは、日常のひとつひとつのものごとをどう感じているか、人間の感覚をどれだけ自覚できて
いるかということゆきついてしまうのだ。そのプロセス?については、ぜひ本書を読んで感じ取っ
てもらいたいと思う。文章はあくまで平易なので、するすると理解できると思う。
最後に、この本を買うきっかけになった箇所を少し引用しておきたい。
『人間は、関係性の美を育んできた。礼儀とか、話し方とかにセンシティブであったことがスムー
ズなインタラクションを生み出してきた。それが破綻のない社会を生み出してきた。』
『今の問題は、精神論じゃない。センサーの欠如なんです。』
31章「情報と経験」より

明日の朝食予定。2種類のメロンパン。
サンライズという呼称はいまやほとんど使われなくなってしまいましたなぁ。わたしなどは、
メロンが好きではないので、あのパンの形を見ても「メロン」とは連想しにくいのだけれど。
本を買いに出たとき、京都宝塚劇場、スカラ座、京極東宝が1月29日に閉館するという告知を目に
する。えらく唐突な話で、しばし唖然とする。東宝系の映画、これからどこへ見にいけばいいの
でしょうか?わざわざ二条のTOHOシネマズまで行くのか...。街中にあってこそ映画館なのに。
あれ、閉館=建て直し→一階のBook1stもなくなるってことか?うーむ、心配。
- 2006/1/2(月)
・10:30頃、箱根駅伝を見る。
・11:30頃、嵯峨野に新しくできた(源泉が沸いた)天然温泉にいく。腰が少し楽になる。
・14:00頃、大学ラグビー、同志社が関東学院に負ける。勝てば決勝だった。残念。
・つづいて、早稲田対法政の試合を見る。早稲田強し。スクラムハーフの選手がすごい。
・17:00頃、自宅に帰る。
・台所を掃除する。ずっと立っているだけなら、楽なのだけれど。腰をかがめるのがしんどい。
- 2006/1/1(日)
みなさんあけましておめでとうございます。
本年も、よろしくお願いします。
<今年の目標>
・腹筋を鍛える。
・夏コミ新刊、建築探訪大阪篇を出す。
腰痛がひどいため、墓参り、初詣にもいかず、終日実家にてすごす。
|
|