|
電波暗室 2005/05
- 2005/05/31(火)
今日はとにかく朝から1、2時間単位でいろいろな仕事(仕様検討、資料作成、会議、ブレーンス
トーミング、上司面談など)をやっていたためか、えらく時間がすぎるのが早かった。わたしの職場
の場合、月末だからといった定期的な忙しさはないので、むしろ今日のように自分で忙しいペースを
作らないとついつい怠けそうになってしまう。
今日はビジネスっぽい話をしてみたい。今日あった2つの会議のうちのひとつのことだ。10:30に
開始して、終了したのは12:30。わたしはぷりぷり怒っていた。お腹がすいていたからだ。うちの
昼休みは12:15から13:00の45分間しかない。ちょっとでも出遅れると、あっというまに残り30分
とかになってしまう。それにたちが悪いのが食堂だ。10分遅れると、食べるものがなくなる可能性
がある。食堂の処理能力はときどきがくんと落ちることがあって100人以上が行列をつくってい
るのに、たべらるものが白米のみなんてことがなんどもあった。そうでなくても、めぼしいおかず
は売り切れが早い。だれかフライングしてるんじゃないかと思うくらいだ。
そんな状態なのに、15分も会議は押している。なぜか?誰も会議のやり方を知らないからにほかな
らない。会議を進行する側の役割、出席するものの役割、それを双方が把握していないと、時間を
守らず、結果の出ないしまりのない会議になってしまう。我慢しても意味がない。途中でよっぽど
席をたってでていこうかと思ったのであるが、今日はあるプロジェクトの初回会議だったので、
雰囲気が剣呑になることは避けねばならなかった。
会議を引き伸ばさないために大事なことはなんだろう。考えてみる。
1 主旨と目的をはっきりさせる。
2 時間をくぎって、時間がきたら次の議題に強制的にうつる。
3 感想を述べない。
4 進行担当は勝手にしゃべるひとをだまらせる。
5 終了間際に質問しない。
6 終了間際に「ほかに意見ありませんか」と聞かない。
くらいだろうか。このなかで特に注意がいるのは6ではないかと思う。常套句のように口にしそうに
なってしまう魔のキーワードであるが、これにはなんども煮え湯を飲まされてきた。つまりは成長し
てないんだけども。人間、こう聞かれると「あっ、じゃあ何か質問とか意見しないとまずいかな」な
どと悪気がなくても思ってしまうのである。話はじめると、聞いた手前途中でさえぎれないから、
よけいにまずい。これは5にもあるように、出席側も配慮しないといけない内容だと思う。
いいたいこと、議論すべきことをおいてまで時間を守らないといけないのか、というとそれは観点が
違うと思う。大切なことに時間を費やすために、よけいな部分をなくしていくのが会議の本質なのだ。
それを考えると、進行役が客観的に冷静に舵をとる必要がある。そのために発表者と進行役は
兼ねないほうがいい。集中できるように議事録も別のひとが書く。しかし、実際は3つを一人でやる
ことがほとんどなんだな。だから、おかしなことになってしまう。その会議のやり方はおかしいよっ
て言う第三者が必要だなーとつねづね思っているのだが、会議のやり方が研修プログラムに組まれ
たことはない。うまいひと、へたなひとの差が大きくなっていく。研修所に進言してみるか。
堅い話になってしまった。ちょっと考えをまとめておきたかった。
自分が楽をするためには、自分が苦労しないといけない。
そう感じる今日この頃。
- 2005/05/30(月)
今日から会社の制服を夏服にした。6/1の前後二週間は夏・冬どちらを着ても良いことになっている。
いつもならば、夏服OKの日から即座に変更していたのであるが、例年に比べてかなり遅い変更であ
る。これは皆さんご承知のように昼間はまだしも、夜などは半そででは肌寒いからで、どうも今年の
夏は寒いのではないかという予感がする。
で、とつぜんに上下とも夏服にしたら身体がついてこなかったのか、急に頭痛が襲ってきたり、お腹
の調子がかなりゆるくなったりと相変わらずの身体機能の弱さを露呈する結果となってしまった。夏
に涼しいかっこをするというのは実は考え物なのである。というのも、お腹を冷やすのは冬よりも夏
の方が多かったりするのだ。「汗をかく→布地が薄い→冷える→お腹イタイ」という図式が汗かきの
わたしのパターンなのである。だからといって夏服を着ないと「汗をかく→布地が厚い→蒸れる→
身体が熱くなる→しんどい」というパターンに陥ってしまうので、バランスが難しい。
私服の場合、この服は今日着るとしんどくなるとか、おなかいたくなるというのが経験的に判断でき
るのであるが、制服の場合は決めうちなので、どのタイミングで着るかのみの選択しかできないのが
やっかいである。わたしの職場は開発系なので、制服が夏・冬分かれているが、工場現場や、プロセ
ス系などの職場では、オールシーズン共用の防塵服なのだ。防塵だけに綿0%、通気性皆無。
新入社員のときの実習でプロセス系の現場に3週間いたのだが、かなり死にそうであった。そう思う
と、綿100%の服が着られるだけでも、ありがたいと思わなければならないのだろうな。
あ、さて、ここでお知らせです。
夏コミ、受かりました。9年目にして初のサークル参加。おめでとう、わたし。ぱちぱち。
日付:二日目 8/13(土)
位置:西1ホール、”ら”ブロック-24b
サークル名:「山Dの電波暗室」
ジャンル:建築写真
となってます。なんとしてもいい本をつくって、参加される皆さんに手にとってもらえるよう頑張ろ
うと思います。直近になりましたら、専用ページを作る予定です。週末にさっそく写真のセレクトを
しないといけないなぁ。
- 2005/05/29(日)

LOUIS GARNEAU LGS-FIVE
最近になって自転車のハンドルの動きがもうどうにもだめになってきたので、自転車を買うこと
に。で実家に帰るついでに近くの自転車専門店へ行き、あまり予備知識のないまま買ったのが
写真の自転車である。帰宅してから調べてみると、スイスのルイガノというメーカーの定番モデル
の20005年版らしく、この世界では割とポピュラーで人気のあるものらしい。
そもそもT字ハンドル、前傾姿勢の自転車に強い抵抗感があって、今回も街乗りできるママチャリ
とは違うデザインで、あまり前傾しないもの、というテーマで選びにいったのである。しかし、
買ってきたのはごらんの通り。理由のひとつは、あまり前傾しないタイプのなかで、良いデザイン
それも質感がよいものがなかったから。(ひとつだけあった候補は色あいが好きになれず。)で、
前傾にはまず目をつぶって、全体デザインでさきに選んでみた。でそのうえで試乗させてもらった
のがルイガノである。
結果、乗らず嫌いであるということが判明。おそるおそるの前傾姿勢ではなく、サドルを思い切り
あげた状態での姿勢は、むしろ安定感があり、運転もしやすかったのである。たぶん2分くらいし
か乗っていなかったが即決。価格は事前にBKのK岡に聞いていた価格帯の範囲で、乗りごごち
の良さに比べて、びっくりするような高価格でなかったのには驚いた。(給料日直後だったので
気が大きかったというのもある。)
もうひとつ驚いたのは整備してもらって受け取ったあとでパーツをチェックしていくと、変速機
やブレーキ周りなどの主要部品のほとんどがSHIMANO、つまり日本メーカー製であったこ
と。SHIMANOが世界に名だたる部品メーカーであることは、ほんの少しの知識としてあっ
たし、わたしのママチャリのブレーキもSHIMANOだったのでその優秀性はしっていたが、
海外メーカーにここまで信頼されているとは。海外の自転車競技・趣味人口は日本に比べると桁
違いであるから、そこでもまれたうえで、なおも主要部品で確固たる地位があるというのはすご
いことなんだろう。(なんかあまりにも素人くさすぎますか?)
さて、購入した足で実家へ寄って親に見せびらかしてみた。実は、この自転車には標準でサイク
ルコンピュータ(まああれです速度とか走行距離がわかるメーター)がついていて、それを説明
したところ、「あんたの好きそうなやつやなぁ」とのお言葉。そう、このルイガノを買った一因
にはこれがあるのだった。さすが見抜かれている。
その後、一度帰宅してからまだ日も高いので、ミニツーリングにでかける。ひさびさの変速機に
興奮する。自分の踏み込みがダイレクトに加速につながるのがこんなにも楽しいものとは思わな
かった。これを味わったら、もう別に買い物だとか、ちょっとそこまでとかの用事に気軽につか
えなくてもいい、自転車に乗るためだけにこいつで出かけてもいいとさえ思い始めた。それくら
いの感激があった。(ちなみに前3速×後8速)
あちらこちらと走り回り、ココへたどり着いた。
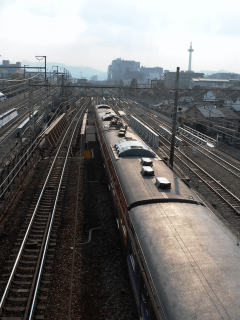
地上に出た京阪と、京都駅につづくJRが交差するポイントにかかる跨線橋である。いつも東京
がえりの新幹線や、北陸がえりのサンダーバードから見えてはいたが、実際に来たのははじめて
だった。西日がまぶしかったが、そんなことも気にならないくらい(私は西日が嫌い。夕焼けや
落日は好き。)わくわくする光景だった。わたしだけでなく、何組かの親子連れが一心にゆきか
う電車を眺めていた。橋の奥のほうに、スーパーはくとらしき車両が停止したままなのを見て、
おばあちゃんが孫にいつになったらうごくんやろね~と聞いていた。孫、こたえて曰く「う~ん、
三年後!」。おじいちゃん「もっとはよにうごくわ!(ちょっと怒ってる)」、などといったや
りとりが聞こえた。おじいちゃん、そんなに怒らんでもええのになぁ。
その後は、例のごとく鴨川河川敷を塩小路から今出川まで北上し、今出川経由、烏丸を南下して
帰宅した。本日の走行距離、22km。前傾姿勢で気になっていた肩凝りや、腰の痛みはまったくな
い。つくづく「乗らず嫌い」だったなぁ。(明日、とつぜん襲われないとも限らないけど)
ちゅうい:天気のいい日の河川敷を高速で走ると、大量の虫さんが顔中にぶち当たります。
- 2005/05/28(土)
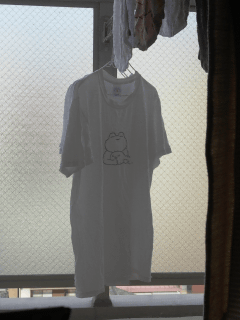
おだやかな午後。
洗濯したてのTシャツと、言葉のない会話をしてみる。
晴れてよかったねぇとか。
- 2005/05/27(金)

二条若狭屋、竹水ようかん。

竹節の底に専用きりをねじりながら押し込む。
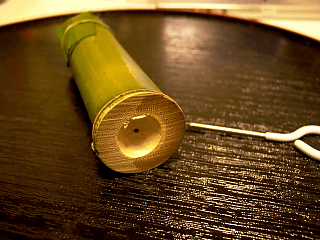
穴があく。

笹をとると中に水ようかんがつまってる。

底の穴から空気がはいり、中身がでてくる。

くちにくわえて、吸い出しながら食べる。(パピコみたいに)
もしゃもしゃ。
絶品です。
- 2005/05/26(木)
昨日の「どうでしょうリターンズ」の録画、野球中継で1時間以上遅れていたため、レコーダー
の自動録画延長でも追いきれず、まったく録れていないことが先ほど発覚...。野球は敵だ!!!
ふてねする。
- 2005/05/25(水)
ああ、気持ちよく目覚めたー!と自覚できるほど、気持ちのよい目覚めの日というのは、いった
いこれまでに何回くらいあっただろうと考えてみる。たぶん、これまでも何回か考えていて、前
に暗室に書いたり、誰かに話したこともあったかもしれない。
何週間か前の新聞に、汐留ロイヤルパークホテルに「快眠ルーム」(名前不正確)のような部屋
ができたという記事が載っていた。これは松下電工との協力事業で、電工が長年にわたって研究
してきた照明技術を駆使したものらしい。快眠にはとうぜん快適に目覚めることも含まれていて、
設定時刻になるとカーテンが自動でひらき、音楽がなり、照明がつくといった一連の流れが自動で、
しかも「気分よく目覚めるための設定」で行われるというのだ。通常の照明の波長には、覚醒をさ
またげる物質を脳内に誘発するものがあるらしく、ここの照明ではそれがフィルタリングされてい
るという。
一泊の料金は3万円と高い。ホテルのホームページを見に行けば、割引とかあるかな?と思って、
GW期間中の宿泊さがしのときに調べたが、発表と同じで3万円でFIXされていた。通常2万~
はするホテルなので、付加価値を考えると妥当なのかもしれないが、必ずしも快眠できるかわから
ないのだから、もの珍しさだけで+1万円はきついなぁと思う。ホテルの場合、通販とちがって
満足できなければ返品というシステムは使えないし。下手に「快眠できなかったら返金保証」なん
てあっても、ほんとに快適じゃなかった場合にそれを証明してみせることが面倒だ。そんなことを
考えること事態がなんか不快になりそうである。-結局のところ、もっと割り引いてくれたなら、
気軽に利用して、モニターしましょうって気分にもなるのにということだ。
松下電工としては、サービスでこんな部屋を作ったわけではなくて、「実験結果」が良好なら新規
開業のホテルにシステムを丸ごと売り込もうって計算があるはずなのだ。結果がよければ、ホテル
側にとっても付加価値を高めやすいだろうし。だったら、「被験者」は多いほうがいいと思うのだ
けれど。まぁ、試作の一号というのはだいたい採算を考えていないから設備費が高くついていると
いうのが値段設定の一因にあるのだろう(推測です)。
まわりくどくなってしまったが、私は快眠と快適な覚醒が欲しいと願っているのだ。
つまり、きょうも目覚めは×でした。なんでだろ?
ちなみに記憶している最良の目覚めは1993年6月の東西四大学合唱演奏会(東京人見記念講堂)、
翌日の朝である。あれから12年、つぎの最良はいつになるのやら。なんだかスパンからすると、
天体現象のよーだ。
- 2005/05/24(火)
睡眠と覚醒のリズムがこのところおかしくなっており、朝が非常につらい。午前中まともに仕事
できないため、必然的に遅くまで会社にいて、結果遅く寝るという悪循環に陥いりかけている。
というわけで、申し訳ありませんが、本日の暗室はおやすみさせてもらって、早めに眠ります。
- 2005/05/23(月)
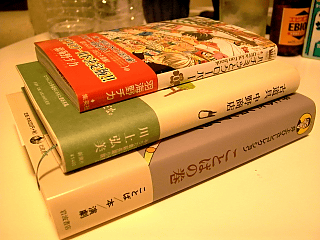
昨日買った本、今日買った本。
きのう「井上ひさしコレクション ことばの巻」、岩波書店刊、3200円。
きょう「古道具 中野商店」、川上弘美著、新潮社刊、1400円。
きょう「ハチミツとクローバーvol.0 official fan book」、羽海野チカ著、590円。
昨日買った本と、今日買った本に何か違いがあるとすれば、それは昨日読みたかったか、今日読み
たいと思ったかの違いでしかない。「古道具 中野商店」は、昨日ジュンク堂で手にとって、少し
読んででいたが、結局買わなかった。しかし、今日恵文社で読んでみて読み続けたくなった。
本との出合いというものは一期一会だ、みたいなことを前に書いたように思うが、どうにも「気分」
が乗らないときに出会ってしまうと、食指はうごいても、破談することが多い。時間を置くことが
必要なときもある。
時間を置いても置いても、なぜだか買わない本もある。昨日、ジュンク堂に入ったら、いつも立ち読
みするのに、なかなか買う気持ちにならないある本が、棚からなくなっていた。アラーキーこと、
荒木経惟の「目を磨け」という談話集だ。彼の語る一言、一言は直裁で、すぱっと頭に響いてくるの
で心地がいい。決して高い本ではないのに、いまだに買えないので自分でもひじょうに不思議に思っ
ている。もしかしたら、書店が注文しないかもしれない。もしかしたら、版元で絶版になっているか
もしれない。でも、またここか、あるいはどこか別の場所で会える。根拠はないが、そんな気がする。
そして、そのときも、気分がのらなければ買わないだろうと思う。
- 2005/05/22(日)
大丸で夕飯を買い求めたあと、その奥の和菓子コーナーをぶらり、ぐるりとまわってみる。そろそろ
夏のお菓子が出ている。水無月、あゆ(鮎の形をした菓子)、水ようかん、わらびもち。ウィンドウ
にかぶりつきそうになるのをじっと我慢して、気のないそぶりでひやかしていく。
デパートの地下の和菓子コーナーに行こうと思うとき、ほとんどが贈答目的だと思うが、こうやって
なんの気なしにのぞいて見れば、自分のおやつに欲しくなるものがたくさん見つかるのだなぁ。京都
の街中には和菓子を売る「おもちやさん」(おはぎとか売ってる)や「菓子司」(おもちやさんの
上級バージョン)がたくさんあるのだけれど、私の住んでいる近辺は呉服ゾーンで、和菓子はおろか
着物屋三以外の普通のお店も少ない。普段食べなれていたものが食べられるなくなるのはつらい。
こうやってデパートが近くにあると助かる。
さて、今日は試食した抹茶わらびもちがおいしかったので、食後のデザートにと思って買ってきた。
実はもうひとつ、のどから手が出るほど食べたいものがあったのだが、手持ちがなかったので、週末
にとっておくことにした。きょうは、このわらびもちでじゅうぶん満足できるはず。
...と思っていたのだが、夕飯を少し食べすぎた。
冷やしておけば、明日食べても大丈夫と、売り場のおばちゃんはいっていたから、明日にお預けとする。
- 2005/05/21(土)

いつもより念入りに掃除していたら、歯ブラシがたくさん見つかった。使用済み4本、未使用1本。
来歴は100%、ホテル・旅館のアメニティである。5本とも種類が違うので、それぞれ違う場所で
もらってきたものだとわかる。こんなにあっても使い道がない。日替わりで使ったりとか、未使用で
あれば泊まりの来客につかってもらうとか(そんな来客いやしない)、洗面所の水垢掃除に使うとか
考えられそうだが、積極的にやることではない。(最後のは昔祖母がよくやっていた)
こうやって持って帰ってきてしまうのは、やはり「このまま使い捨てるのはもったいない」という
精神が働くからであるが、そもそもそう思うくらいなら泊まりに行くときは自前の旅行セットをも
っていけばよいのだ。合宿のときに必ずもっていったように。
しかし、それができないのは単にずぼらであるからだけではなくて、何か別の理由がありそうだ。
それはおそらく、日常のものを「旅」にもちこみたくないという精神の表れではないかしらん。
毎日使っている歯ブラシであるとかデンターライオン、シックの二枚刃の髭剃り、ブラシ、櫛etc.
を持ち込んでしまうと、そこがまるで自分の部屋であるかのような錯覚を起こす。いつもと違うな
にかを求めているところに、いつもと同じものがあってはまずいのだ。
だから、わかっていながらあえて、旅先にあるものをわざわざ使ってしまう。そして、その旅を記
憶にとどめるかのように、それらを持ち帰るのだ。それにしても、ほかにもいろいろあるだろうに
なぜ歯ブラシだけがこんなに大量に手元にあるのかわからない。アメニティのなかでも、もっとも
差別化が図りにくいグッズだというのに。持ち帰ったとしても「~ホテルの歯ブラシ」なんてあと
でわかるはずもないのになぁ。(つまり、どこの記念だかわからない)
実用上でいうならば、「タオル」が一番持ち帰りたいモノだ。オリジナルのロゴや模様が多いからだ。
しかしながら、ホテルの場合はほとんど持ち帰り不可だ。温泉旅館などであると、温泉手ぬぐいなら
持って帰れるケースがあるようだ。かわいた状態ではおぼろげにしか見えない文字や絵が、
湯に濡れるとくっきりとあざやかにうかびあがる。あの独特の織りや布地には、なぜだか強くひか
れるものがあるんだな。
こんなことを書いていると温泉に行きたくなった。シーズンじゃないけどさ。
- 2005/05/20(金)
HPのプロフィールであるとか、あるいはもっとアナログな時代だと小中学校の文集などで、自分
の好きなこと、好きな食べ物などを書くのと同じくらいの確率で、嫌いなこと、苦手なことなどを
書かされることがなかっただろうか。(自由に書ける形式よりも、みんな同じフォーマットで質問
にこたえるタイプ。)(まぁ、HPは自分で選択できるけれど。)
わたしは非常に用心深いというか、うたぐり深い性格なのか、極力そういうところにはノーコメン
トを通してきた。素直にひとに弱みを見せられない、意地っ張りであったというよりも、かなり本
気で、「苦手なことは弱点。将来いつなんどき、その弱点が誰かの手に渡って、思いもよらぬ攻撃
をうけることになるまいか?」などと考えていた節がある。馬鹿だったナァなどといまだから思え
るのだけど、当時は真剣だったのだろう。変なところに考えが及ぶ人格は、そのころすでに形成さ
れていたといえる。
さて、今現在はわりとダメなものはダメと公言できるようになっているが、それは付き合う相手に
弱みを見せられるという信頼関係を築けているからこそできることで、人との付き合いを知らない
子供のときには当然それは無理な話なのだった。いや、それができる子供時代を送ったひとはとて
もうらやましく思う。
さて、ここでいちいち弱みを見せる必要はないけれど、子供のころ、本当に幼かったころに苦手だ
ったことならば、書いてもそれをもとに攻撃されることはないだろう。克服しているからな、当然。
と同時に、世間一般的にこどもの苦手なものというのは、共通しているのか、私の感じていたこと
は割と特殊だったのか、普通だったのか知りたいという思いもある。
わたしの親は、私をデパートに連れていくと大変疲れるので幼い頃はあまり連れて行きたくなかっ
たようである。なぜなら、常に「階段」でしか上下階の移動ができないからだ。そう、わたしの苦
手だったもの、それは「エレベーター」と「エスカレーター」。『なにが怖いネン!』とつっこみ
がくるのは当然と思う。解説しよう。
克服したのはエレベーターの方が早かったが、なにがだめだったかというと、マンションだとかの
ものではあまりないと思うが、デパートのものは階ごとに停止するときにやや上に上がってから、
ふわりと下にさがる感覚があってから停止する。あの浮遊感、重力がかかり、それが急に失われる
感覚が「気持ち悪かった」のである。そうだ、お察しのとおり私は乗り物酔いする性質でもあった。
いや、これはいまもそう。こどものころからGに弱かったのだなと思う。これはなんとか、あの
浮遊感に慣れれば、短い時間なので耐えることができるようになった。小学校入るくらいには大丈
夫だったのではないか。
問題は、エスカレーターである。これは「気持ち悪い」ではなく、直接的な怖さをともなっていた。
「動いているものに、飛び乗る」という行為ができなかったのだ。バランスをくずしてこけるんで
はないか、よしんばのれても降りるときに引きずり込まれるんではないか。そんな恐怖感が常にあ
ったと思う。そうだ、大縄跳びになかなか入ることのできない状態に近かったかもしれない。完全
に一人で乗れるようになったのは小学校の中学年に入るくらいではなかったか。それも一応乗れる
というレベルで、乗るとき、降りるときはそれこそ必死の覚悟を、各階に到着するたびにしていた
ように思う。完全に克服したときには、何の自慢にもならないが、妙に誇らしげであった。あの、
まぶしくらいの蛍光灯の光にあふれて、足元のすきまが緑色にひかって、手すりがオートマティック
に動く、未知の空間に恐れをいだきながら、じつはあこがれていたのだろう。
この2つ、わたしの世代の子供にとってはデパートの象徴のような乗り物で、一般的には憧れの的
ではなかっただろうか。わたしのように、両方ダメで、デパートにとってはむしろ裏街道的な
「階段」をこよなく愛すというのは、異端だったような気がする。みなさんはどうでしたか。
さて、いま現在は当然何の問題もないエスカレーターとエレベーターであるが、このうちの片方
で、ある条件が重なった場合、実はいまでも怖いのだ。平気な顔をして、内心はびくびくものな
ので、わたしと乗り合わせることになった人は、観察してみてください。必死で隠します。
- 2005/05/19(木)

YAMAHA CBX-K3 + Roland SC-88VL、私の音取り環境
BKで練習している曲、音が難しくなかなか前に進めない。これはやばい、と思い始めたので音取
り環境を組み立てる。なぜ、組み立てる?かというと、私はいわゆる音源をもっていないからなの
だ。これでも説明不足だ。「電源を入れて鍵盤を叩くと音が出るもの」をもっていないので、くみ
あわせてそれらしいものを作る必要があるのだ。
これがなかなか面倒で、材料がこれだけある。
・MIDIキーボード
・MIDI音源
・ヘッドフォン
・ACアダプター×2個
・MIDIケーブル×1本
キーボードとMIDI音源にそれぞれ独立にACアダプターをつなぎ、つぎにMIDIケーブルで
両者をつなぐ。そして、最後にヘッドフォンをMIDI音源につなぐ。まぁ、かいてみればそれほ
どでもなかった。が、普通のキーボードに比べると手順が多いのは確かである。アダプターをつな
ぐためのコンセントも2口、しかもACがつなげる場所をあけないといけない。
なぜ、普通のキーボードを買わず、こんなしちめんどくさいことをしているかというと、音の問題
なのだ。音質にこだわるとか、そういう高級な話ではなく、もっと基本的な部分。むかし、むかし
普通のキーボードを買ったのだが、ある音階が減衰していく途中で半音近く音が下がるという現象
があったのだ。合唱をやる者、音楽をやるものにとってこれは、ちょっとなぁと思われて、店に文
句をいったら、紆余曲折があったのち、「このレベルの音源ではこんなものなんです」といわれて
しまって、かなりショックを受けたのだった。結局、そのキーボードは返品して、その足でMIDI
キーボードを買いにいった。
当時、MIDI音源は持っていて、音をだすための装置としてはこれ以上ないくらい信頼できた。
だったらそれを徹底的に使おうと思ったのだ。だから、あとは入力装置としての鍵盤だけ買えば
よく、返品したキーボードよりも高いMIDIキーボードを買った。どんなものでもそうだと思う
が、あることに特化し、基本的な機能のみ搭載した道具というのは美しい。伴奏機能であるとか、
サンプル曲だとか、メトロノームだとか、UFOの音だとか、そんなものは音を奏でる(というか
音取りレベル)にはまったくいらないのだ。そんな機能にかかる費用があれば、鍵盤の質やつくり
が高級であったほうがどれだけ良いか。結果的にそういうものの方が故障も少ないし、長く使える。
当然、音を出す部分もないので、ヘッドフォンをつないだ。音割れするようなちゃちなスピーカー
なんかないほうがいい!かように、頑固で意地っぱりな精神のうえに成り立ったのが今のこの組み
たて環境なのだった。もう10年になるかなぁ。
なお、写真をみて鍵盤少ないから、ベースの音取れないんじゃないの?と思われたかたがいるかも
しれない。実際に44鍵盤しかないが、そこはそれMIDIですから、キーボードのボタン1つで
オクターブアップ、ダウンができるのだった。
さて、では音取りします。
- 2005/05/18(水)
『踏み固められた土を道だと呼ぶのならば 目をとじることでも愛かなあ?』
『語りかけてくる文字を小説と呼ぶのならば 届かない言葉は夢かなあ?』
(「ループ」lyrics:h's music&arrangement:h-wonderより)
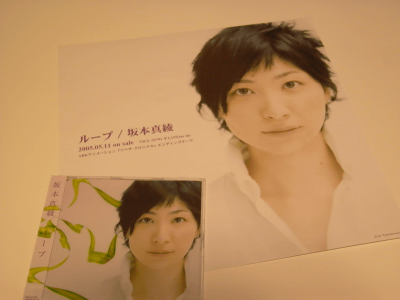
坂本真綾、Newシングル「ループ」。
すっかり大人(イイオンナ)になっちゃって...ねぇ、ホントに。
写真、いつもより大きめデス。
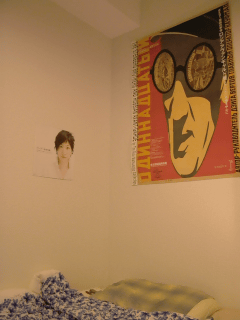
枕元に張ってみた。ちなみに天井には、写真とか張ってない。(遠くて見えないから)
右のポスターは2001年に東京都庭園美術館で開催された「ロシア・アヴァンギャルド展」のもの。
ステンベルグ兄弟の強烈なポスターに対抗できるポスターがなかなかなかったのだが、坂本真綾な
ら違和感なく十分だ!(信じることが重要)
新京極スタンドにて、日替わり定食。場所柄外国人のお客さんも多い。ちゃんと英文メニューが
用意されているうえ、おばちゃんの応対もなれたものだ。おばちゃんはすべて日本語で説明して
いるのだが、きちんと通じている様子。そんなところに、わたしの隣のカウンターに向かい合わ
せに座る形で、外国人の青年と30後半と思しき日本人男性の二人連れがやってきた。聞くとは
なしに会話をきいてしまうことになるのだが、これが面白い。
男性は標準語(関西弁はなかなか出てこないと本人が説明しているのを聞いた)で、外国人青年
は完全な関西弁なのだ。日本語だけきいてもかなりネイティブに聞こえる。なぜだろう?外国人
が日本語を少しでもしゃべると、うまいうまいとほめる傾向があるが、それが違和感なく聞こえ
るレベルになるまでには、やはり相当隔たりがあると思う。
この外国人青年は、話の内容を聞くと建築科の留学生のようなので、日本の生まれ・育ちではな
いようだ。ここではなぜ彼がネイティブに近くなったのかではなく、なぜネイティブらしく聞こ
えるかを考えてみよう。そのために、注意深く話しをききつづけてみる。
「....え、まじそれ?」
「ええなぁ~」
「・・・せやなぁ~」
そう、これだ「せやなぁ」。標準語でいうならば、「そうだね」ともいうべき言葉で、つかわれ
る場面は決まっている。あいづちをうつときだ。あいづちを現地の言葉でうてる。しかもその土
地のローカル言語でうてる。おそらく、これが違和感なく聞こえた正体なのだ。せやなぁに限ら
ず、「ええなぁ」も、「まじそれ?」も相手に返す言葉だ。こういう言葉は普通の文章、センテ
ンスとしては出てこない、生の言葉だ。生活のなかでしか聞こえない。だから、それが使える=
ネィティブらしさ、を生み出すのだろう。
この青年は、ほかにも「うちの兄貴」とか、「歳の上下」という概念のある日本語を普通に使っ
ていたので、相当な使い手と見られる。ここまでしゃべれる留学生というのは初めて見たナァ。
いろいろな人が入り乱れるこの酒場は、毎回面白い人間風景が楽しめるという点でも好きである。
いや、飲むのは相変わらず水なんだけどネ。
- 2005/05/17(火)
4月に冷泉通りに花見に行って以来、自転車の調子が悪いのである。具体的にはハンドルの回転
がおかしい。右に回すと、右に、左に回すと、左に、「勝手に回り続ける」のだ。すべりがよす
ぎるというのではなくて、明らかにばねか何かに引っ張られるような力が加わっている。自転車
というものは、つねに左右にハンドルを少しづつうごかすことでバランスが取れているから、ま
っすぐ進んでいてもハンドルは回転している。で、左右に変な力がかかるものだから、少し左に
振れたと思ったら、左に回り続けようとする力を振り切って右に回さないといけない。でないと
こけてしまう。で、右に切ったと思ったら、今度は右に回り続ける力に対抗して、左に回さない
といけないのだ。
これが思っている以上に疲れてしまう。ゲームセンターでドライビングゲームなどをやるととき
たま、ステアリングに加重がかかって実車走行のような体験ができるものがあるが、ちょうどあ
んな感じの、とても不自然な加重と戦わないとまっすぐ走れないのだ。それは疲れるはずなのだ。
普通自転車乗るときに、バランスをとるための左右の回転など意識しないが、今のマイ自転車は
そんな些細な挙動にも注意を払わねばならない。
なにが起こったのか定かではないのだが、どうもハンドルの回転部に入っているベアリングなり、
なんらかの回転機構がつぶれてしまったようだ。花見にいったとき、自転車を止めて写真をとっ
た際、ハンドルが右にぐいぃーと身体の方まで最大角度近くまで曲がったのだが、その瞬間に、
「ぎゅぃーん、ぎぎぎぃー」とえもいわれぬ大音響が鳴り響いたのだった。何がばねのようなも
のがはちきれるような音だ。いったい自転車のどこにそんな音を出す部品があるんや?!とえら
くびっくりしたのだが、どうやら回転部の中みたいだ。外見からはまったく、そんなところに
「工夫」とか「ヒミツ」があるようには思えないのだが、以降回転の具合がおかしくなったとこ
ろ見ると、重要な部品が入っていたようだ。なかなかあなどれない。
回転の具合は日増しに悪くなり、いまでは多分私以外のひとが運転したら簡単にこけてしまうこ
と請け合いである。これはもう、残念ながら買い替えの時期が迫っていると考えてよいかもしれ
ない。思い返せば、1996年5月4日に購入。買ってすぐに京都の鷹ヶ峯までサイクリングしたよう
な記憶がある。ただひたすら、佛大の横のあの坂を、汗をかきながら上った。あのとき考えてい
たことは、9年経ったいまも憶えている。若かったなぁ。
そんな、自転車のことが気になっていたのか、昨日もまたすこし変わった夢を見た。どこかは
しれない坂道にたたずんでいると、急に小学校時代の塾の友達が、自転車を届けにきてくれた。
街乗りの普通の自転車で、ハンドルに変速がついている。なんだか見たことがあるような。起き
てから気づいた。あれはNaの自転車だ。夢のなかでは変速は8段になっていた。見た目の機構上
どうやっても8段には見えないのだが、友人はそういい残していったので、ためしのりをしなが
らいろいろ試してみる。うまく切り替わらない。
そうこうしているうちに、どうやら学校らしき建物の前に出た。真新しい建物のなかから、男声
合唱が聞こえる。ああ、ここが淀工か!と理解。これも起きてから気づいたのだが、淀工はプロ
ジェクトXで最近見たからで、あのまあたらしい建物は、新設される「立命館小学校」の校舎だ。
ちょうど、昨日帰りがけに駅張りの広告で見たばかりだった。あの絵をみただけで、夢のなかで
即座に三次元に置き換わるとはなぁ。
で、そのあたりを走っていると淀工メンバーがパート別に近くの畑で練習していた。近くを通る
となぜか、鍵盤をたたいているのは私服の女の子ではないか。どうも各パートにひとり専属のよ
うだ。うらやましい!と思ったかどうかは憶えていない。残念ながら女の子の顔はよくみえない
まま、わたしは走り出していた。
しばらくすると、いつのまにか私は電車、それもおそらく地下鉄に乗っていた。おそらくという
のは、実際に電車に乗っている絵があるわけではなく、なぜか頭のなかいっぱいに路線図がひろ
がっていたからだ。どうやら私はどこかに帰りたいらしいのだが、気がつくと思っているところ
とはまったく違う方向へ行く電車に乗っていて、ああまた行き過ぎたとか考えているのだ。そん
なことを2回くらい繰り返していた。ひとつだけ駅名が登場して、それはなぜか「トヨタ」駅
であった。ここは愛知なのかナァなどと思っているうちに、夢終了。
最後の行き先不明で、2回乗り間違う電車というのは、どうも最近の体験のなかでむすびつく
ものがなく謎である。なにかの願望を示すようにも思えないし。日が暮れて、心さびしげで、
なかなか、帰りつかれない不安の心情が非常にリアルであった。
夢で感じている感情というのは現実で感じる感情と何か違いがあるのだろうか?悪夢は気分が
悪いし、恋するひとが出てくれば、おだやかで気持ちのいい気分になれる。どうせならば、夢
のなかでは気分よくいたいと思うのだが、現実にあじわっている以上の気持ちを感じることは
まれのようだ。「夢」なのにひどく「現実」的なこころのありよう。不思議である。
- 2005/05/16(月)
昨日というか、今朝、これまでになかった夢を見た。明らかに歴史的建造物とわかる建物を
私は外部から見学している。いままで見たことも聞いたこともない建物だ。外見上は西洋建築
の域を大きくはずれるものではない。建物中央部から左右に回廊状に建物が伸びていて、灰色
の石造り。ただし中央部のみ、石造りのうえにレンガで装飾がされている。ここがやや変であ
るが、装飾的にはなかなか良いと思える。と、そこに誰がしゃべっているのか、「これは典型
的な八卦様式です」というナレーションが聞こえてくる。いったい誰なんだ?
八卦というとあの占いで使うもので、算木を組み合わせたような模様。いわれてみればレンガ
の組み方が、似ていなくもない。ただ、「聞こえてきた」のに「八卦」と頭のなかで理解され
ているのがさすが夢というべきか。変わっているのはほかにもあって、建物をよくみると、
左右の翼部は中央部からまっすぐ伸びているのではなく、やや湾曲している。上からみると
おそらくS字状、もっと正確にいうなら積分記号∫のような感じである。
外を眺めていた私(主観映像なので私の姿は見えない)は建物のなかに入る。と予想通り、
左右に分かれて上部で一緒になる円形状の階段室となっていた。階段を上ると上から、やや
年輩の男性と、その男性に事務的なことを話している秘書的な女性がおりてきた。私はその
女性が話し終わるやいなや、男性に「この場所で保存されるんですか?」と質問していた。
どうもここは学校の敷地内で男性は学長らしいと理解している。
このあたりで夢は終わるのであるが、終わりかけに夢のなかでわたしは「ああ、こんな建物
は現実には見たことがない。とするとわたしの夢の産物か。とするとこの建物の設計図をな
んとしても「こちらに意識があるうち」にどこかに記しておきたいものだなぁと考えていた。
思い返してみるに、夢で見た建物は東京国立博物館の表慶館にやや似ているのだが、あれほど
ドームは大きくなかった。八卦様式なんて珍妙なものと、翼部の湾曲はいったいどこからでて
きたのかも謎だ。そもそもベース?らしき表慶館を目にしたのはおととしの秋ごろだったので
えらく前のことだ。西洋建築の写真を撮ることは確かに趣味であるが、こうやって建物、しか
もオリジナルを探訪するという夢を体験をしたことはちょっとおどろきだ。
この前の東京行きでは三信ビル以外に特に着目せず、古本修行をしていたのが、実はこころの
なかでは欲求不満だったのかなぁ。都心で内部見学できる有名どころは結構、行ってしまって
いて、まだ見ていないところは郊外に多い。そうなると建物単独だけを見に行くことはなかな
かつらくなっていて、今回はあえて古本一本に絞ったのだった。
オリジナルと思っていた変な建物は実は、まだ見ぬ素晴らしい西洋建築を探し続けたいという
願望のあらわれなのだろうな。一応、ライフワークのつもりなので、夏の軽井沢行きの際でも
新しい発見ができるよう、事前に建物情報を調べておこうと思う。
- 2005/05/15(日)

ぎゃぼ。いつの間にやらこんな数に。のだめカンタービレ12巻発売デス。
そろそろ読んで見マセンカ?
12巻発売との連動プレゼント、描きおろしマングースTシャツが欲しいけれど、そのためには
のだめが連載されているKiss11号を買わないといけない。いったいどんな雑誌なんだろうか。
私は漫画は単行本で読む派なので、掲載紙というものに関心を持ったことがあまりない。単行
本のほうが、そろえる喜びのようなものがあるからだ。それは一巻、一巻が丁寧に装丁されて
いて、そこに本編と共通した手仕事のよさみたいなを感じられるから。洋服の仕立てのような
もんだろうか。最近、漫画や小説を手にとると必ずといっていいほど、カバーの見返しや、
奥付のあたりをのぞいて、誰が装丁したのかを調べるくせがついた。
本は手にとってもえない限り、買われもしないし、読まれもしない。当たり前のことだな。だか
ら、手にとってもらえるための装丁というのはすごく重要なことなのだ。本の良さは「見栄え」
じゃない、なんてみんなわかってる。けど、良いなぁと思う本には大概良い装丁が寄り添ってい
るもの。気に入った本や漫画を思い返すとき、そこにはいつもカバーの絵や写真、そして指先で
感じる紙の肌触りがある。愛着っていうのはそういうところから生まれるのだと思っている。
- 2005/05/14(土)
NCマネージ@自宅、13:30~16:00。
NC練習、18:00~21:00。
NCマネージ@明治維新、21:00~23:00。
NC練習前に、どうしてもいっておきたい場所があった。デパートの北海道物産展に「水曜ど
うでしょう」を製作しているHTBのブースが出るのである。普通、物産展にTV局がブース
を構えることなどありえない。だって、売るものがないからだ。しかし、HTBにはそれがあ
る。数々のどうでしょうグッズ!DVDや、本をはじめとするどうでしょうグッズは普段はロ
ーソンを通じての限定販売か、北海道内の限られた店舗でしか買えない。なので、この物産展
にはなんとしても行かねばならないと思っていた。
で、体調が悪くてNCすら休もうかと思っていたのに、でかけることに。しかし、大阪につい
てからつまづいた。デパートについて、前をいくひとを追い抜き、エスカレータをかき分けて
進み催事場にたどり着くのだが、ナイデスヨ物産展。???そういうえば、店内のどこにも
案内がない。まさか、まさかと思って、隣のデパートへ。ああ、なんということか阪神百貨店
だと思っていたが実は阪急百貨店で開催だったのだ。公式HPの案内を見事に見間違えていた。
おかしい。疲れ目?
それにしても、なんだこの混雑は。阪神も阪急も地階を経由して移動したのだが、全然前に進め
ない。なんという人出。なんという行列。めまいがする。こんなところで日常的に買い物なんて
とてもできない。京都に住んでいて良かったとつくづく感じる。だいたい両方のデパートとも、
地階から上方階への連絡がすこぶる悪いのには、参った。阪急なんて直通のエスカレータが全然
見つけられないうえ、移動方向の案内板がわかりにくい。大阪の地下街の伝統芸能なのかもしれ
んなぁ、などと考えながらようやく、催事場へ。もう迷わない、ずんずん進む。あれ、なにやら
雰囲気が変だ...、と思ったら「女性下着フェア」へ頭半分くらい突っ込んでいた。もう!物産展
と下着フェアを同じ催事場でやらんでください。恥ずい。
気を取り直して、反対側の会場へ。....と思ったら、嫌な予感。そして的中。HTBのブースに
はなんと行列ができていた。50人以上はいるなぁ。前を見にいくと「入場制限」の文字。皆さ
ん、物産展で行列ができるのを見たことがありますか?僕はないです。前の方の看板には、「一
時間待ち」の文字がうっすら透けて見える。(今日はそれほどではない様子)最後尾にはデパー
トの係りらしき人が「最後尾」の看板をもって辛気くさそうにたたずんでいる。それはそうだ、
まさか北海道物産展で入場整理が必要だなんて思わないし、ましてやそれが北海道ローカルのT
V局のブースだというんだから、訳がわからないだろうなぁ。
かように、「水曜どうでしょう」の人気は関西でも絶大なのでした。2年前に北海道で放送が終
了した番組のグッズが行列の原因だって、あの係りの人に教えてあげたら絶句するだろうナ。
さて、普段なら50人くらいの行列はなんでもない私であるが、20分後に練習開始だったことと、
やはり体調悪くて快適な心持で買い物を楽しむ状況になかったため、あきらめて練習に向かった
のだった。残念だ。onちゃんグッズ欲しかった。
*どうでしょう公式HPはこちら
*京都では、毎週水曜日23:00からKBS京都で放送中。
帰宅後、郵便受けにこんなものが入っていた。
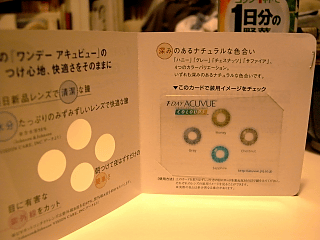
カラーコンタクトレンズの宣伝である。なかをあけると、ごらんのように透明なカードに瞳の
部分が印刷されている。片目にこれをあてて、鏡で見ればイメージがわきますよということら
しい。さっそく試してみるメガネの私。
色はハニー、グレー、チェスナッツ、サファイアの四色。メガネをはずすと確認できないので
メガネのレンズと目のすきまにカードを、ぐっぐっと差しこんで無理やり瞳の位置にもってく
る。うむうむ、なるほど。私というか、皆さんの多くは瞳のいろは茶色~黒であろう。そうで
すよね?(瞳の色って、個人差は大きいのだろうか。それとも人種ではだいたい同じなのか)
そうすると、この4色のうちハニー、グレー、チェスナッツは、本当の瞳の色である茶色に見
事に溶け込んでしまって、ほとんと目立たない。ハニー=金色などは、もっと目立って妖しい
雰囲気(銀河英雄伝説にヘテロクロミア?の人がいたっけか)がでるかと思ったのだが。装着
してはっきりわかるくらいにするには透明度を下げねばならず、そうするとコンタクトの役割
は当然果たせないから、バランスとして難しいのだろうな。
というか、これはあくまでチェックシート+メガネごし(無理やり)なのであてにはならない
のだけれど。そんななか、唯一サファイア、つまり青だけはかなり目立つことがわかった。
妖しいってなもんじゃない。吸血鬼に操られた人間みたいである。こんな瞳で見つめられた
ら、意思があるのやらないのやらわからず、怖いだろう。間違っても日本人が過去も現在も
根拠のない憧れをもって抱いている青い目の白人のイメージにはならない。だって素で青なの
と、茶色の上の青なんて全然別物だもん。ま、とにかくイメージチェンジするなら絶対、この
色であることには違いない。
しかし、このイメージというのもあまりあてにならない。私は目が細い。だからこのチェック
シートの虹彩の部分を、自分の瞳と合わせるには「とてもすごく」目を開かないといけないの
だった。目がぱっちりの状態なんて、あきらかに普段の自分と違うからなぁ。こんなに目をあ
けるのは上のFの音をとるときくらいかも。
漫画「ブラックジャック」で、瞳の色がキーポイントとなる話があるが、そのなかで「瞳の色
は薬物を使っても決して変えることができない」というセリフがあったと思う。現在の医療技
術でもやはりその点は変わっていないのだろうか。だとすれば、瞳の色というのは個人を同定
したり、その印象を決定付ける非常に重要なファクターなのだ。だから、普通はその色をコン
タクトで変えるなんて発想はヨーロッパや、アメリカのように様々な瞳の色が混在する場所で
は出てこないのじゃなかろうか。逆に、同じ人種が多く固まるような地域や、場所ではありな
のかもしれない。(100年前だとそういう地域で他者と異なるというのは、あまり良い印象
をもって迎えられなかったはずであるが)
映画「マイフェアレディ」のなかで、家出したヒロインのイライザを探すために、ヒギンズ教
授が警察に彼女の容貌を伝えるシーンがある(実際に電話しているのはピカリング大佐)。
そのときに伝えているのが「髪の毛の色」と「瞳の色」なのだ。このシーンを見たとき、髪の
色はともかく、瞳なんて黒に決まってるやんか、と子供のころ思ったもんだ。
さて、このカード、面白いのでとっておくことにする。
会う人会う人に試してもらおうっと。
- 2005/05/13(金)
紙モノの所感はなかなか受けた。ただ、「こんなん買って何するんやろと思うでしょ」と言っ
たら、皆が一様に「うんうん」という顔をしていたのはやや悲しかった。
BKの練習前に頼んでおいた写真のプリントを取りに行く。36枚で2000円。やっぱり高
いなぁ。でも、それだけの価値がモノクロには十分あるとプリントを見るたび思うのだ。鮮や
かな色はないけれども、それがかえって写っているひとの表情やこころを浮きだたせるような
気がする。より、被写体の心に近づいたプライベートな色合いが強くなる、そんな気もする。
そう、モノクロで撮るべきはやっぱり人なのだ。
今回、ULTRON、Summaron、Summicronの3玉で被写体をとらえたのだけれど、一番味があって
ずっと見つめていても、いっこうに見飽きることがなく、こころがざわざわする写真を写して
いたのはSummicronだった。ほとんどが屋内で撮影だったから、50mmという焦点距離、f2.0と
いう明るさが威力を発揮したのだとは思うけれど、やわらかさとシャープさをあわせもった
描写には、ちょっとうっとりして、くらくらしてしまった。被写体の魅力をこんなに引き出
すことができるんだなぁ、ほんとにすごい。こんな写真を見てしまったら、もうずっと撮り
続けずにはいられなくなる...。
お酒が回ってきたみたい、寝ます。クルクル~。
- 2005/05/12(木)
明日、急に所感が回ってきた。所感というのは、昼会で5分くらい前にたって話しをしたり、
ストレッチ体操をしたりする係りのことである。昼会とは文字通り、昼に行う朝会みたいなも
の。会社のローカル用語が多くて説明が長ったらしくなってしまった。
で、ネタは何にしようかと考えているところなのだ。前回は「第六大陸」と「プラネテス」
を題材に宇宙の話をしたのだが、話がSFすぎてとっぴだったのか、聞いているひとの半分
以上は、ぽかーんとしていたような気がする。こんかいは身近なところで古本屋の話、それ
も紙モノの話はどうだろうか。(全然、身近じゃない)実物を持っていって、これは戦後の
~で、こっちは戦前の~です、とやったらみんな面白がってくれるのじゃないかと思う。お
しむらくは、京都には紙モノを扱っているような古本屋さんが(たぶん)ないということ。
もし、誰か興味をもってくれたとしても、「東京までいけばありますよ」というのはちょと
厳しい。
さて、次回の所感までにやろうと思っていることがある。だいたい3ヶ月程度、つまり60
人くらいで一回りなのだが、その60人の所感分類をするのだ。シリーズネタ、とっぱつネ
タ、皆さん教えてくださいネタ、本ネタ、大河ドラマネタ、いろいろある。聞いていてもっ
ともあっけにとられるネタとして、「AはBでした。おわり」タイプがある。あんたそれで
も社会人かー!5分間みんなを楽しませるとか、笑わせるとかしろよーと怒りたくなるとき
があるが、以外とそういう所感をする人は多い。単純にAはBとだけいう人もいるが、いろ
いろ枝葉はついているが、結局は一本道のAはBというパターンもある。話のうまい人とい
うのは主題として「AはB」というテーマはあるが、それをそのまま話さない。CはDの話
をしながら、その背筋に「AはB」が隠されていたりする。そういうところも含めて、構造
分解を頭でしながら、どの系統が多いのか考えてみたいと思っている。
また、会社のモットーのようなもの(信条綱領という)を読み上げるのも係りの役目だが、
そのなかに「向上」という言葉がある。この言葉のアクセントが面白いくらいはっきりと、
2つに分かれる。こちらも、調べてみたい。可能ならば聞き取り調査して、出身地などと
関連があるかということも追究してみたい。通常の会話ではなく、皆の前で読み上げる場
合のアクセントというものは、じゃっかん違うのではないかと思っている。
このような日常のどうでもいいようなことを調べ、考える学問を考現学という。
(「図書室」で考現学の本を紹介したことがあるはず。参照してみてください)
- 2005/05/11(水)
水曜どうでしょう「合衆国横断3750マイル」終了。7日間で北米大陸横断。いやぁ、全8夜
ということは、約2ヶ月も見ていたんだねぇ。これを見ていると、どうしても思い出すのは、
アメリカ横断ウルトラクイズである。しかも、第15回だったか、飛行機を使わずに今回のどう
でしょうと同じようにすべて陸路で旅をした回があった。あのときの優勝者はたしか、立命館大
学クイズ研究会のひとで、うちから割合近くに住んでいたのだよ。あのときのウルトラクイズは
本当に見ごたえがあって、毎週木曜が楽しみだった。実家を探せば、ビデオテープがまだあるは
ずだ。保存版にするため、わざわざワープロ(パソじゃないよ)でラベルを作ったくらいの入れ
こみようだった。
大学生になったらぜったい出場する!と心に決めていたのだが、高校生のときに終わってしまっ
て非常に悲しかった。出場する前から、「もし成田まで勝ち残ったら大学の授業休まなあかんな
あ」などと、先走った妄想をしていただけに、残念、無念であった。
人間、一度は先行きのしれない、予定の立たない「旅」をしなければ!そんなことを思いはじめ
たころだったような気がする。ただ、大学では工学部、クラブはグリーとくれば、あてのない旅
などしようもなかったのは、自明である。
社会人ともなれば、あてのない旅はまったくできない。が、ちがう旅のスタイルを私は身につけ
つつある。観光地には行かない、なんて頑固なことは言わない。観光地にいってもいい。ただ、
そこに住んでいる人がいくようにふらりといく。ご飯を食べるのも、本屋に行くのも、まるでそ
この住人のような心持で行く。日が暮れたら、家に帰るようにホテルに帰るだけ。この感覚は、
一緒に旅しないとわかってもらえないかもしれない。ふだんの生活を旅先の都市で続ける。これ
である。そう、行き先は都市。文庫本、ひとつ持って。いや、やっぱり二つ欲しいな。で、現地
でもう一冊買う。
ああ、あまり暑くならないうちに、練習一回サボってどっか行きたいなぁ。
尾道再訪とか、路面電車の旅in高知とか。
私信:姐さんありがとう。
- 2005/05/10(火)
会社最寄り駅の駅前が再開発されている話は以前にもしたが、新たに駅から駅前ビルに向かう
歩道橋ができた。この歩道橋を歩いていると、いまは駅ビルに入った恵文社の仮店舗が見えた。
正確には、仮店舗だった場所だ。プレハブ2階だての店舗が、気がつくと更地になっているのが
よくわかった。
そこで感じたのは、更地というものはなぜ狭く見えるのだろう?ということ。かつての店舗面積
から想像する広さには見えないのだ。そういう経験は皆さんないだろうか。たとえば、新築の家
の基礎工事中であるとか、引越し先のマンションの部屋でも似た経験ができると思う。いま住ん
でいるマンションの部屋を不動産屋に見せてもらったとき、わたしは部屋の端っこにすわって
広さを見極めようとしたのだが、そのとき思ったのは「7.4畳って狭いなぁ」である。実家の部屋
が4.5畳にも満たないのに、なぜだかそんな風に感じた。
実際に越してきて、断然広いということを日に日に実感していった。それは部屋のなかにブック
タワーをひとつも作らなくても良いということから感じたわけではなく、本棚や机、ソファとい
った家具を買い揃えていくうちに感じたのである。家具がふえれば、その分だけ部屋が狭くなる
はずなのにである。これは不思議な錯覚だが、説明がつかないことでもないと思う。
何もない空間というのは天井と壁という、大枠しかないので大きさを比較するものがない。そう
いうところでは、人間の感覚というものははなはだ頼りないのだ。絶対的なスケール感覚を身に
つけている人はそうはいないだろうから、天井より低い家具を置いてみて初めて、視覚に対して
「奥行き感」ともいうべきものが与えられるのだろう。家具が増えることで、壁がうまっていく
し、手前に比較するものが増える。だから、高いものは奥に、低いものは手前に置くとさらに遠
近感が強調されて、逆に部屋が広く感じることすらあると思う。
これは引越しをしてみて、初めてわかったことだった。今、住んでいるところにどれくらいとど
まるかわからないが、これから何回かは引越しを繰り返すと思う。その部屋探しの際に、家具を
いくつか運んで広さを実感したいとは思うが当然無理だろうなぁ。立体投影装置のようなものが
実用化されれば、いいのだけれど。
いまわかった。新築のマンションなどでモデルルームを作るがあれには家具が全部ついている。
あれはなにも家具を置かないと殺風景だからとか、生活感がわかないからという理由だけでなく
て、部屋のスケールを正しく実感させるためにあるのだ。だって、何も置かなければ、ふつうは
「狭い」と感じるだろうから、それは売るほうとってはマイナスイメージだもの。(逆に、広い
と感じたら、それは実際の自分の生活様式からすると、広すぎるのだろう。それはそれで、快適
な生活とはよべないかもしれない。狭いほうがいいことだってあるのだ。)
まぁ、立体装置はないにしても、ダンボール一つ持っていって組み立てるだけで、本棚にみたて
たり、TVに見立てたりできるのではないかと思う。部屋をお探しの方(時期はずれか)試して
みてください。
- 2005/05/09(月)
一回休み。(会社を休んだわけではない)
NCマネージ、若干。
- 2005/05/08(日)
打ち上げで、飲めないのに、日本酒(Rさんからの団差し)をいつもより多く飲んだ。
飲まされたわけではなく、自分から飲んだ。
みんなの前で「飲まなきゃやってられん」と、マネージが理由みたいなことを言ったのであるが、
半分はほんとで、たぶん半分は自分でもわからない。
翌日、頭がいたかったり、気分が悪かったりしなかったのは多分、良いお酒だったからなのだろう。
ただ、もともとアルコールがダメな体質なので、身体がだるく、体温調節ができない感じ(冷や汗?)
が残っていた。何をする気もなかったので、食料を買いに出たり、ちょっとした用事をする以外は、
部屋で過ごした。
そんなわけで近頃荒れ放題になっていた部屋を掃除し、洗濯モノを干し、皿を洗い、ゴミを捨てた。
家事というのはいっぺんにやると疲れる。やっぱりこまめにやるべきだなぁと思うのであるが、つ
いこの前、東京から帰ってきた直後にもやっていたのに、3日も経たないうちにこの有様になるのを
考えると、毎日部屋を維持するエネルギーも相当なものではないのか?と思ったりもする。
身体を動かしているうちに、どんどん汗をかいてきた。かけばかくほど軽くなってくるようだ。
―そうか、こうやってアルコールが抜けていくのだな!(こんな経験初めてなのだ)
付記:5/3,5/4の写真追加。
- 2005/05/07(土)
なにわコラリアーズ第11回演奏会。
結局のところ、われわれは「このメンバーで歌いたい」「こいつと一緒に歌いたい」という、そん
な単純な原子だけで構成された存在で、だからこそマネージがめためたでも、音程と発声がぐらぐ
らでも歌うことをやめられずにいるのだ。なにもかもが溶け合った家族という存在ではない。個と
全体が対等に存在しうる場所だからこそ、そこにいられる。無条件に受け入れるほど甘くはないけ
れど、何かを否定するためにある場所ではない。だから、これからも全身を賭して歌う。一緒に歌
うため、そして誰かに聞いてもらうために。
... so lieb ich dich, Roeslein auf der Heiden.
帰宅後、録画していた映画「ナチュラル」(ロバートレッドフォード主演)を見る。中学時代から
好きな映画のひとつ。演奏会を終えて、好きな映画を見る幸せ。
- 2005/05/06(金)
NCマネージ13~16時。
NC練習18~21時。
NCマネージ23~26時。
練習のため、阪急で大阪に向かう。なぜか特急が来ない。快速急行、普通、快速急行。
3本目の快速急行が大阪先着らしいので、これに乗る。楽譜は見ないで、「古本道場」を読む。
「古本屋の棚の前で、十八歳の私は不安に震えていた。世のなかにはこんなに本がある。いつに
なったら読み終えるのか。それは知識の分厚い壁だった」。角田光代という人は、平易な言葉を
使いながらも、こころの動き、そのとき感じたことをじつにわかりやすく伝えることのできる人
だと感心する。小説に登場する人物たちが誰も平凡で普通の人でありながら、物語をすすめ、感
情移入できる人物として描かけているのは、こういった普段の心情をよく観察し、汲み取り、整
理できるからなのだろう。
梅田駅に到着。雨がふっていて暗いせいか、こころなしか駅がさびしげにうつる。いつも特急が
とまっているホームには、北千里行きの普通が止まっているし、いつもなら天井につるされてい
る商品広告もない。平日の17時前後なので、帰宅ラッシュも始まっていない。どこかぽっかりと
なにかが抜け落ちたような時空。ふいに、自分は知らない間に何十年も前の梅田駅に降り立って
しまったのではないか、という根拠のない空想が浮かぶ。走りつづける電車に乗っているうちに
いつのまにか、現在から過去へと移動する。雨の日には、なぜかそういう空想を時々する。おり
たつ先が未来であったことはなぜかない。これも雨のせいだろうか。
帰りの電車で、再び「古本道場」を読む。古本屋が運ぶ「可能性」や何かの縁というものをあら
ためて感じた。
- 2005/05/05(木)
NC練習13~17時。
帰宅後、5/2の暗室を追記。
練習も、マネージも大変ではあるが、心穏やかにすごす。
- 2005/05/04(水)

丸善にて、雑誌「Neutral No.2 特集美人のルーツ」、安野光雅のポスター本を購入。

品川の原美術館へ。建物もいい。
夕方、京都へ帰る。
(詳細後日追記)
- 2005/05/03(火)

三信ビルの健在を確認。
・総武線快速と、総武線普通の路線が違うことに初めて気づく。鉄好きとしては失格だなぁ。
・YK、東大島で練習。
・YK、東京カンタート出演。歌えてよかった。
・新橋にて、3人で打ち上げ。これまで接点のなかったメンバーと交流を深める。
 
丸ノ内ホテル宿泊。東京駅の全ホームが眺められる。うれしい。
(詳細後日追記)
- 2005/05/02(月)
新幹線に乗っていて、富士山が見えるとうれしいとか、すごいとか思う前に、いつもびっくり
する。いつもだ。なぜかというと、日常見慣れている山々とあまりにもありようが違うため、
現実離れしているというか、日常の生活の枠内から外れたジオラマのように感じてしまうのだ。
私が普段見慣れているのは京都の北山、東山、西山といったものだ。東山三十六峰というように、
山々が連なっている。これがベースなので、たとえば南アルプスなんかをみても、独立峰はあって
も山脈の一部として捉えれる。違うのは単に大きさだけだ。
ところが、富士山というのはなだらかな高原や、工業地帯の間から突然、にょきっと生えあがっ
ている。なんの前触れもなく現れるから、こちらとしては心の準備もなにもあったものではない
ので、ついつい、挨拶するのを忘れているうちに見えなくなってしまう。あれは確かに見るもの
に何かの信仰を抱かせるには十分な異様というか、威容があると思う。不思議な山だと思う。
ただ、いつも新幹線側からしかみていないので、いつか富士五湖を手前にしてそれぞれ眺めてみ
たいと思う。
11:30頃、飯田橋に到着。目的は、昼食をとるため。なぜ飯田橋かというと、神楽坂にコロッケの
おいしい定食屋があると、聞いていたからである。で、あるが肝心の店の場所や、名前をきいて
いなかったため、神楽坂を上がったり下がったりして汗だくになってしまった。今日はいい天気。
12時まえに携帯で店の画像を送ってもらい、それを頼りにひたすら神楽坂を歩く。
いままで、神楽坂上より向こうには行ったことがなかったので、かなり新鮮であると同時に、この
界隈の奥行きの広さを知る。昼食のことがなければゆっくり路地から路地を写真を撮って歩きたい。
途中で、音楽の友社のビルに遭遇。こんなところにあるんだねぇ。しかし、肝心の店はみつからず。
探し始めて約20分後、画像と同じ店を発見。あれ?定食屋じゃなくて居酒屋??ほんとにここがそ
うなのか確かめようにも、営業していない。しょっく。

証拠(?)写真、その1
それにしても、ここだったのか。地下鉄神楽坂駅を出てすぐ左。実は、話を聞いたとき、かってに
神楽坂=飯田橋から出発=飯田橋駅を出てすぐ、と勘違いしていたのだ。地下鉄ではわずか一駅だ
が歩くとそれなりの距離があるのだった。すぐ近くにいつもお世話になっている新潮社を発見。
記念に一枚撮る。

証拠(?)写真、その2
13:30頃、西荻窪到着。
さて、ついたは良いのだが、今回の目的の古書店三店はどこにあるのだろうか。だいたいの場所
しか調べてこなかったのである。当然、現実の町並みは地図のように単純ではなかった。まずも
って方向がわからない。こういうときは自分の勘というか嗅覚を頼りに歩く。およそこの嗅覚と
いうものは、迷っているときには働かないのが常なのと、相性の悪い街ではおそろしくあてにな
らない。ただ、西洋建築であるとか、今回の古書店がターゲットの場合、逆に自分でもこわいく
らいに目的地に行き着くことができる。
とてとてと歩いて10分。まだ見つからない。でも私好みの被写体が多く、ちっとも気にならな
い。古いような、新しいような、落ち着いたところだ。たぶん相性がいいのだ。そういえば、
中央線に乗っていて、新宿をすぎると急に街の背が低くなって、あちこちに神社の杜だったり、
家々の生垣といった緑が増えてきた。だんだん遠くなる新宿のビルを見ていると、なんだかあの
街は無理して、中央線沿線のほかの街から訣別していきがっているようで少し滑稽な感じがした。
さらに5分ほどして、目的地のひとつハートランド発見。全然迷っていない、すごい。やっぱり
相性がいいのか。さて、すぐには入らない。なぜかというと、もうひとつの目的地音羽館をさが
すため。自分のなかでは音羽館→ハートランド→ごごしまやというルートを描いてた。これは扱
っている本のジャンルから決めた。音羽館はオールラウンド、ハートランドは芸術・思想・哲学
で、ごごしまやは紙モノ、絵本など。音羽館で古本探索モードに入り、そのあと二つの専門分野
に沈んでいくという次第。
それから、さらに適当に街を歩いているともの5分も起たないうちに音羽館発見。
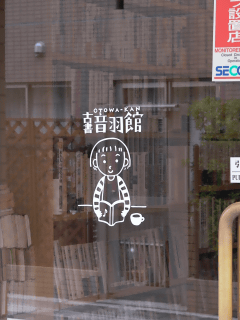
ますこっとのおとわちゃん
よし、ではここからスタート。まずは基本の均一台(すべて100円)をなめまわす。・・すご
いな、こんなにいい本ばっかりならんでていいのか?特に新書が100円というのはうれしいな。
均一台で4冊、選ぶ。さらに店内。狭いのによく整理されている。文庫の品揃えもいいけれど、
やはり新書が多いのがすばらしい。ああ、毎週来たい。いるだけで癒される。
というわけで、店内で2冊、計6冊を購入。
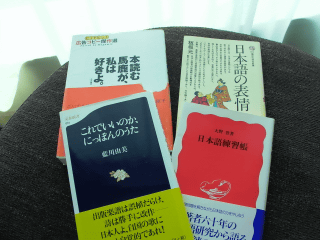 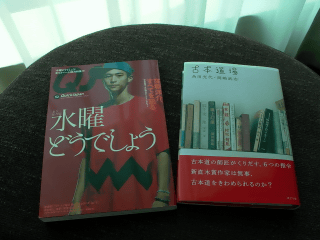
・「日本語練習帳」大野晋著、岩波新書。購入価格100円。
・「日本語の表情」坂元元著、講談社現代新書。購入価格100円。
・「これでいいのかにっぽんのうた」藍川由美著、文春新書。購入価格200円。
・広告コピー傑作選「本読む馬鹿が、私は好きよ。」メガミックス編、学陽書房刊。購入価格500円。
・QuickJapan vol.52 特集「永久保存版水曜どうでしょう」太田出版刊。購入価格100円。
・「古本道場」角田光代・岡崎武志著、ポプラ社。
狙ったわけではないのだけれど、日本語系の本が多くなった。QuickJapanは、「水曜どうでしょ
う」が特集だったので。それから、「古本道場」は古本ではなくて新刊書。古本道を学ぶ実践場
として、今回私が行った三店舗他が登場しているのだ。しかし、購入動機はそれだけではない。
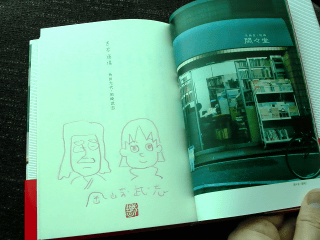
実はサイン本なのだ。岡崎武志さんの書くイラスト、角田さんそっくりだなぁ。ちなみに次の日、
YKメンバーのI田に「角田光代って知ってる?」って聞いたら「ああ、あのK1の?」って言わ
れた。いや「光代」はK1には出ないだろう。作家って、やっぱり知名度低いのかなぁと思う。
さて、小一時間ほどしてから、いよいよハートランドへ。まだまだ元気。棚という棚を探索探索。
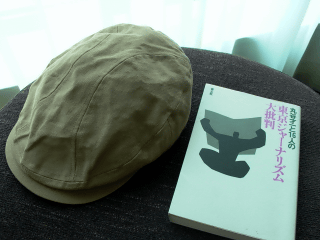
・「丸谷才一と16人の東京ジャーナリズム大批判」青土社刊。購入価格850円。
・帽子、2000円。
購入数こそ少ないが、東京ジャーナリズム大批判は掘り出しもの。かつて雑誌「東京人」で連載
されていたもので、毎回三人の鼎談形式で文明論的にジャーナリズムを論じるもの。読み物とし
て非常に面白い。朝日新聞からハヤカワポケットミステリ、文藝春秋からNHKと幅広く。批評
のない世界は堕落する、という言葉があるらしい。なかなか噛み応えのある言葉。古本屋で帽子
を買うってありなのか?と思う方もいるかもしれないが、この西荻という場所、このハートランド
という空間にいる限りは、ありなんじゃないだろうか、と思って購入した次第。なかなかいい帽子
にめぐりあう機会がなかったが、これは何か一期一会というか、欲しいと思ったのである。
さて、その後駅の反対側のごごしまやへ。ここはハートランドでもらった地図を見ていったので
すすーっと到着。紙モノを扱っているということで日月堂さんに紹介してもらったのであるが、
どんなものがあるかなぁ。
お、マッチラベル。これは日月堂でも時々ありますね。でも一枚一枚選べるな。それから昔の観
光地絵葉書が充実している←守備範囲外。ああ、これはいいエクスリブス。日本語でいうと蔵書
票です。よほどの本好きじゃないとこれは作らないと思うが、なかには芹沢銈介デザインのもの
がある。やはり高くて2500円くらいする。これにはちょっと迷う。
結局買ったのは以下のもの。いつも買っているものの系統に近い。
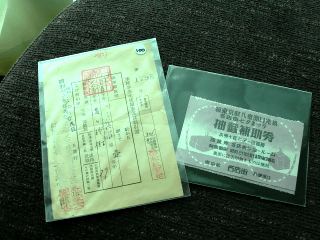 
・昭和廿六年の学割。紅陵大学政経学部の人のもの。100円
・昭和三十年、東京駅八重洲口完成、名店街七夕まつり抽選補助券(4枚)。200円
・大正時代の輸出向けマッチラベル。ロブスター(?)600円。鯛400円。
なかなかのしゅうかく!で、この買い物で面白かったのは、先に買っていた「古本道場」の中表
紙を見ると、なんと学割と同じ名前の人の大学の身分証明書と、日赤の診察券が載っているじゃ
ないですか。あとできづいたんだけども、これは確実にごごしまやで買ったものだヨ。紙モノの
回転が早いかどうかわからんけれど、もうちょっと早く、そう2月に東京に来たときに、西荻に
きてれば、角田さんとニアミスしてただろうか。
され、これでひとまず西荻古本散策は終了。で、もうひとつおまけの収穫物。
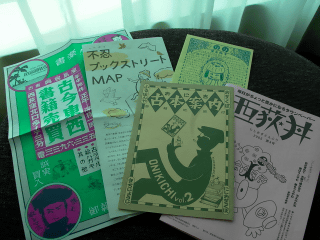
西荻オリジナルの情報ペーパー、チラシたち。地域のお店や有志で発行しているのである。
古本以外の散策情報も充実している。こういうものがたくさんあるということはそれだけ街に活
気があるということなんだろうな。それもオフセットのような上品すぎて敷居の高いものでもな
く、クーポンが入ってたりして、どこかぎらぎらしたものでもなく、手書きに近い感覚のものた
ち。そこからはこの街が好きという、とても素直で気持ちのいい精神が感じられてとても好まし
いと感ずるのだった。
よきかなよきかな。本を抱えて一路、浜松町のインターコンチネンタルに向かった。
- 2005/05/01(日)
雨。撮影済みフィルムを胸ポケットにいれて、実家に帰宅したところ、途中でフィルムがなくな
っていることに気づく。一時間以上さがすも見つからず。多大なる喪失感。写真を撮らせてくれ
た人たちに申し訳ない気持ちでいっぱいになる。書店に寄るも、そのことが気になり購入にいた
らず。自宅に帰宅後、しばらくして後、左の捲り上げた袖に違和感あり。手を入れるとフィルム
あり。いったい、どのようにして移動したのか見当もつかず。また、よく移動中にここから紛失
しなかったものだと驚く。胸ポケットと袖に極小ワームホールが開通したのであろうか。とりあ
えず、安堵する。
夜、NCマネージ。
|
|