|
電波暗室 2005/02
- 2005/02/28(月)
『丸谷才一、井上ひさしのあるところに和田誠あり。』とは私がいま考えた言葉であるが、
統計を取ってみたら、結構正しいのではなかろうかとひそかに思っている。
こんなことを言い出したのは、「文藝春秋特別版3月臨時増刊号 言葉の力 生かそう日本語の
底力」を読んでいるからである。昨日、京都駅の売店で購入し、往きの新幹線でずっと読んで
いた。帰りの新幹線でもずっと読んでいた。
どういう雑誌かというと、ちょうど表紙に惹句があるからそれを引用。
『読む、書く、離す、聞く」全篇書下ろし95人の言葉の使い方』…95人である。どこを開いても
国語、国語、文章、文章、日本語、日本語、漢字、漢字のオンパレード。で、むさぼるように読んで
いると書こうと思ったのだが、じっくり読んでいる。正確には、読んでは考え、考えては読んでいる
ので、時間がかかるのだ。わたしが普段考えていた言語観と同じものにいきあたっったときは「ふむ
ふむあなたもそう思います」かだし、新しく知る考えならは、その論理的考察をたどって「いやすご
い、納得である。私ならここをもっと補強しますが」と意見し、あるいはその人の文章の美しさ、
面白さそのものに拍手したくなることもある。
この本をきっかけに暗室を書くならば、一年中日本語や言語についての随想を書くことができると
思う。日本語という蒲焼のいい匂いがあれば、ごはん100杯は軽い。そういうきわめて示唆に富む
本なのだ。その一篇にくだんの丸谷才一と井上ひさしの特別対談「豊かな言語生活」がある。挿絵は
和田誠。
この二人が対談をやりだすと本当に聞いていて(読んでいて)あきることがない。一回の対談で何十
個という宝石のような「思考」と「論証」と「笑い」がこぼれ落ちてくるからだ。ここで全文引用し
たいくらいであるが、話題としては「小泉首相の言葉は犬並み?」「昭和天皇の言語能力」「議論が
苦手な日本人」「ものあわれの「もの」とは」「読んではいけない文章」「意味と語感」などなど。
このなかでどうしても一つだけ引用しておきたい言葉がある。よく、JPOPの歌詞のなかででてき
ていやだなぁと思うフレーズがある。引用したい考え、言葉はそんなフレーズに対する私の思いを補
強してくれる。いやなフレーズは「言葉はいらない」。以下引用。
『言葉は伝達のための道具だという考え方が戦後ずっと支配していた。ものを考えたり、感じたこと
をまとめたり、整理して物語にしたりというときの言葉の働きを無視した時代が長すぎた。』
(同書籍、P41の井上ひさしの発言より)
言語原理主義者(?)ではないけれど、わたしには「言葉」が必要だ。神は「光あれ」と言われたが
世の始まりである光のまえには、神の「言葉」があったわけだ。光さえも作れるこのすばらしいもの
を、もっと大事に守り育てないといけないと思う。どのページの誰の文書を読んでいても、共通して
思うことはそのことだった。
- 2005/02/27(日)
昨日書いた内容で、六連当日に遅刻覚悟するほどの忘れ物とは何かを書いていなかった。
実はステージコート一式である。演奏会当日に衣装忘れたらいかんよね(他人事風)。
さて、本日は6:35起床。本当は6:25,6:30にもアラーム(携帯のバイブレーション。振動音を感知して
起きる。)をセットしていたのだが、どちらかは完全に無意識、どちらかは夢の中で解除していた。
6:35も夢の出来事で誰かに突然何かを命じられて「えっ、何。何をいったい」という状態で目が覚め
た。正確にはおきてからもしばし、状況が把握できず。念をいれて3度のセットにして良かった。
今日は、室内合唱団Vox Gaudiosaの第8回定期演奏会。場所は東京は隅田川、築地に程近い
第一生命ホール。開演が14時なので、寝過ごすとあぶないところであった。わたしは下手をする
と昼まで寝る仕様になっているので。
京都駅で差し入れを買い、移動。10時に東京に到着ののち、予定の行動をとる。松下電工東京
本社ビルに併設された汐留ミュージアムへ向かう。ジョルジュ・ルオーの版画を見るためである。
ルオーというと、キリストの版画のイメージくらいしかもっていなかったのだが、明るい色彩で描
かれた「流れる星のサーカス」という散文詩の挿絵版画の展示はそのイメージが一面的でしかなか
ったことを教えてくれた。ほかにも、ボードレールの「悪の華」に題材をとったというモノクロの
版画が印象的であった。全部見ても30分くらいの小さなミュージアムであるが、ルオーの作品を
中心に意欲的に企画展をやっているようで、汐留の穴場かもしれない。すぐ隣にはNationalショー
ルームがあり、こちらも是非覗いてみたかったが、家族連れ(家を建てる、リフォームする人々)
が多く、独りだとあきらかに冷やかしもいいところなので、あきらめて退散した。
なんだか本来の目的を忘れそうになっているが、そんなことはない。しっかり逆算して行動してい
るのである。というわけで第二の目的地、秋葉原へ向かう。CDを買うためだ。ここではたと気づ
いたのであるが、目的地であるホールの最寄り駅は地下鉄大江戸線の勝どき駅なのだ。ということ
は先に秋葉原に行ってから、こちらに来て、その足で大江戸線汐留駅から勝どき駅へ向かえば効率
が良かったのである。ただでさえ地下鉄大江戸線には乗りなれていないうえに、そのどの駅も、
ほかの駅から大層距離が離れている。汐留駅の場合、JR新橋駅からたっぷり500mはあるの
だ。効率性も考えたくなるというもの。
まぁあきらめて、山手線で秋葉原へ。京都の人間がわざわざ秋葉原でCDを買うこともあるまいに
とひとはいうかもしれない。自分自身だってそう思うのだが、昨日NCの練習前に寄った大阪の店
でどこも欠品だったため止むをえずである。それにしてもしばらくこないうちに秋葉原の駅は大き
く変わった。あの電気街口へ向かう狭くて折れ曲がり、いつも東京方面と上野方面への客が正面か
ら押し合いへしあいする通路はなくなり、3階から1階へと直接おりる形式になっていた。これは
秋葉原史上大変な変化である。何せ、この街にくる人間の9割は登山客よろしくリュックを背負っ
ているから、(・・・・このままでは話が進まないので、2時間後にワープ)
13:40第一生命ホール入場。VoxGaudiosaはこの夏、京都で行われる世界合唱シンポジウムの招待
団体であり、シンポジウムと関連をもつ「コミュニティコンサート」で葡萄と共演することに
なっている合唱団である....ということくらいしか実は私は知らなかった。かつてコンクールに出
出場し、優秀な成績を収めているということも聞いてはいたが、肝心の「いったいどんな演奏をす
る団体なのか?」ということはまるで知らないままであった。東京の合唱団であるから、近くの合
唱関係者から、漏れ聞く程度の情報もないのである。「共演するというのにそんなことじゃいかん
やろ」そう思い、今回知人も誰もいない演奏会に足をはこんだ。
第一ステージ、「ルネサンスからバロックへ」が開演。第一声、ビビッタ。なんて力強く、意思の
ある声なのか。音の立ち上がりに寸分の狂いもない。第一小節の一拍目からそれは音楽だった。
最初の曲というプレッシャーのようなものすら感じさせない。この瞬間から演奏会なのだ。これは
考えてみれば当たり前のことなのだけど、しかし第2、第3とステージがすすむにつれて調子が上
がっていくという合唱の演奏会は多いのだ。聞くほうも、第1ステージならこんなもんかななどと
とんでもないことを考えてしまうことすらある。それはやっぱりよくないことなのだ。聞かせる方
と聞くほうの真剣な対峙がないと演奏会にはならないのだ。演奏が始まった時点から演奏会である
べきなのだ。
簡単に言ってしまったけれど、それは難しいことの証で、実際今回初めてそういう演奏を聴いたの
だった。今回の演奏会、一言でいえば「徹頭徹尾、揺るぎがない」ということだろうか。1ステの
間はただただ余裕なく、そんなことばかり考えてしまった。
第2ステージ、「古典派の魅力」。ソリストと室内オーケストラを迎えてのモーツァルト、ミサ
ブレビスニ短調と、主のあわれみを、の2曲を演奏。過去何度かこういったオーケストラとのア
ンサンブルを聞いたことがあるが、それぞれの演奏がよくてもバランスにかけることが多かった。
そういう意味では、このステージはオーケストラと合唱の音量のマッチングがこわいくらいとれて
いた。演奏にはまったく破綻などなく、調和のある、タイトルどおりの「古典派の魅力」を聞かせ
るものだった。これは本当にアマチュア合唱団の演奏会なのか...。ただただ驚くことのみ多くて
いっぱいいっぱいの状態が続いた。
第3ステージ、「バルトの祈り」はエストニアの作曲家C.Kreekの四つのダヴィデ詩篇という曲。
ここでやっと聞く側として落ち着きがでてきたので、しっかりきけた。それまでがちょっともっ
たいなかったのだが、東欧の宗教曲らしく穏やかで、飾りのない、でも豊穣な音の場が広がってい
たを感じることが出来たのは良かった。ここでも「揺るぎのなさ」は健在であるが、それにくわえ
て、パートの調和が際立っていた。ベースの通奏低音にはじまり、アルト、テナー、ソプラノが重
なっていくさまは、声という筆によって、あたかもそこに音楽の流れという絵画ができあがってい
くようで、それがすこしも不自然に感じないのだった。色調は控えめで大気のような絵画。すばら
しかった。
第4ステージ、「デブレッツェンより」。デブレッツェンとはハンガリー第2の都市で、このステ
ージはそこで開かれ、VoxGaudiosaが出場した「第21回バルトーク・ベーラ国際合唱コンクール」
のプログラムから選ばれたもの。ぶどうもやったことがあるBustoのAveMariaや、武満の翼といった
現代曲のステージである。このステージは皆暗譜で、表情もこれまでのちょっと固めのものから、
やわらかいものにかわっていったのが印象的であった。演奏そのものはもう何もいうまい。
こうやって、ステージ構成をみてお気づきかと思うが、多種多様である。時代も古典、中世、近代、
現代にわたる。普通の合唱団でひとつの演奏会でこれらを歌いこなすことができるものだろうか?
おそらく無理だ。ほかにこんな合唱団はない、と言い切れると思う。
それが可能なのはやはり個人個人の「揺るぎのない」発声であり、意思ゆえではないかと思うの
だ。それは葡萄がいままさに得ようとしている、得ようとしなければならないものだと感じだ。
頭の先から、しっぽの先まであんこでいっぱいの鯛焼き。それをどこまで細かく分割しても、
そこには細胞のひとつひとつにまで、力があふれている。それもきちんと制御された力だ。
それが基本にあるから、もっと高い次元での音楽を合唱をやっていける。高い音、低い音、跳躍
に振り回されていては、音楽の全体を見る余裕もできないのは当然かもしれない。それがいまの
葡萄の姿であろう。
さて、アンコールは、マンティヤルビのエルハンボと、コダーイのAdventi Enekであった。エルハン
ボはVineで演奏を聴いたことがあり、Adventi Enek(通称:ベニベニ)は葡萄でまさにいま練習し
ている曲である。頭のなかで比較しないわけにはいかなかった。
思ったのは、(完成度はさておくとして)「自分達は彼らとは違う音楽をするだろうな」ということ
だった。すごく当たり前のことなのだが、そこは葡萄ならこう演奏するなぁということを考えながら
聞いていた。エルハンボにしても、彼らは非常にスタイリッシュというか、都会的というか、その演
奏がとても「粋」なのである。表情ひとつとってもそうなのだ。これはやはり東京という土地がもた
らすところが少なからずあると思う。
それに対して、Vineや葡萄は「恥らい」「シャイ」の演奏をするであろうということ。
それは意識してそうなっているのではなく、消極性、自己主張の弱さから来るものであることは
否定できないけれど、同じように土地の性質、つまり京都という土地がもたらすものであるのではな
いかと思う。それは否定すべきものではなく、むしろ特質として生かすべきことなのだと考える。
彼らの音楽と対抗するような必要はまったくないが、同じ演奏会で共演するものとして、拮抗する
だけのものを作って見せねばならない。そのためには彼らと同じである必要はないのだ。音楽的な
意味において。しかし、合唱の基礎体力という面での差は歴然であるから、そこは埋める努力をし
ないといけない。そう思う。
素直にすばらしい演奏を聞かせてもらったことに今日は感謝しなければならないと思う。ただ一点、
自分のなかで、「震えがくるほどに、心にしみこむ音楽」を感じたかというと、すこし疑問が残る。
それが、力強さゆえの「声の硬さ」に起因するのか、あるいは「個人個人の隙のなさ」ゆえの弛緩
を許さない音場のせいなのかは、判然としない。ただ、これがはじめてのVoxGaudiosa体験なのだか
らこれからもっともっと彼らのいろいろな側面を聞いていけば良いのだと思う。何より、夏に一緒
に歌うのだから、その機会を楽しみに待っていよう。
- 2005/02/26(土)
H2Aロケット7号機、打ち上げ成功。
NC、郡山練習。そういえば、前回の郡山は寝坊して危うく皆においていかれるところだった。
普段、こういうイベントの際にほとんど遅刻しないのであるが、何年かに一回とてつもない遅刻
、寝坊をやらかすことがある。履歴を出してみよう。
1990年、京都私学理科研究会主催の屋久島ツアー最終日、寝坊して高速艇に乗り遅れそうになる。
1992年、同志社グリークラブEve祭コンサート当日、寝坊してリハに遅れる。(「アホか!」を食らう)
1993年、関西六大学合唱演奏会当日、忘れ物により遅刻覚悟。しかし、新大阪まで新幹線に乗るという
荒業により、遅刻は免れる。
2001年、水と緑の音楽祭出発当日、寝坊により集合時間に遅れる。(列車には間に合う)
このほかにも、忘れているだけで結構あるような気がするが、大きなものはこれくらいか。
遅刻、遅刻しかける要因の多くは、前日に準備をいろいろするあまり、寝るのが遅くなったり、準備に
疲れてしまうせいである。前もって準備するということが苦手なのだ。そのくせ、準備は入念に行おう
とする貧乏性であったりもする。やれることをやっておかないと後味が悪いという気持ちが強いのだと
思う。
この暗室にしても、風邪や頭痛、あるいはネタが思いつかずに苦しむときがよくある。そんなときでも
何か書かなきゃ、書かなければ、という気持ちでとりあえずのものができるまで、書き直しをくり返す
ことがある。その結果、状態を悪化させることがあったりして、正直馬鹿だなぁと時々思う。
ただ、まえはそんなふうな自分への義務感が多かったが、暗室一周年を迎えるころからか、毎日読んで
くれる人たちがHPに来てくれたときに、落胆することのないように頑張ろう、という気持ちが勝って
きたように思う。読んでもらえる文章を常にかけているかというとそうでもないけれど、読んでもらえ
ているということは日々の生活の励みにもなっているので、それに応えたいという気持ちがあるのは確
かだ。
当初の話からずれて、心情をつづってしまった。気がつくと、かなり遅い。今日は早起き、明日も早起
きなので、遅刻しないように気をつけなければ。
明日は、Vox Gaudiosa定期演奏会at東京。
おやすみなさい。
- 2005/02/25(金)
BK、なべ、酒、読書会、就寝。
ねむいよぉ。
- 2005/02/24(木)
なぜか、仕事でいらいらすること多し。つとめて平静でいようと考えている時点でストレスがたまっ
ている証拠なのだろう。並行してかかえている仕事が5〜6つあるというのはやっぱり問題なんだろ
なぁ。たまには休みたい。(年休が残り1日しかないので、簡単に休めないのだった...。)

H2Aロケット7号機、打ち上げ成功を祈念して、volvicロケットを作ってみた。
頑張れJAXA。(2月26日17:09打ち上げ予定)
冗談みたいだけれども、ペットボトルでロケットはつくれます。水噴射だけど。(写真のロケットは噴
噴射口が逆だが)ペットボトルに三分の一くらい水をいれて栓をし、栓を下に向ける。栓に穴をあけて
そこから空気入れで空気をいれていく。内部の圧力が限界に達したところで栓がはずれ、水を噴射し
ながらロケットとして飛翔するのだ。だいたい学校の校舎、3〜4階くらいまで飛ぶ。水しぶきをあ
げてすさまじい勢いで上昇するペットボトルを真近でみたときの興奮はいまも思い出せる。確か、
高校2年の秋冬、野外天文観測の夜だった。
このロケットの欠点は栓(ゴム)が臨界に達するまでロケットを支える役が必要ということ。臨界がき
たら上方にむけたまま手を離さないといけないのだが、当然もろに水しぶきを浴びる。本物のロケット
でいうならエンジンの真下に立っているようなもの。名誉の戦死(水浴死)といえなくもない。
いまは、水ロケット用のパーツが充実していて、ちゃんとした発射台キットが市販されているので、こ
んなことはないが、当時もっと真剣に発射台を研究するべきだったなぁと思う。当時はいかにして、二
段階水ロケットをつくるか?というのをよく考えていた。クラブなどではなく、予算とか使える器材が
なかったので、実現しなかったが。
ロケットを一緒に飛ばした友達は大学で気象を学び、気象予報会社に就職。何年か前に転職して、
名古屋の科学館の学芸員になった。もしかしたら、未来の航宙士たる小中学生たち相手にロケット
講座でも開いているかもしれないな。
- 2005/02/23(水)
夕方くらいから、急に右の肩甲骨のあたりが筋を違えたような感じになってくる。たいそう痛+気持
ち悪い。ストレッチなどしてなおそうとしたが効果なし。肩がこっているのだと思う。この位置とい
うのは体のなかでもっとも手が届きにくい場所だと思う。湿布なんかをはろうと思っても、絶対うま
くはれず、湿布の貼付面同士がくっついてぐちゃぐちゃになってしまうのが目に浮かぶ。あっ、いま
いいことを思いついた。
1、床に寝転がる。
2、痛い位置に湿布大の紙を床との間に滑り込ませる。
3、足、手、頭の位置にしるしをつける。
4、起きて、さきほどの紙の位置に湿布を置く。
5、印の位置にあうように再度寝転がる。
6、所望の場所に湿布が貼付される。
非常にしちめんどくさいので、却下。
自然に治癒することを期待して眠ることにする。
- 2005/02/22(火)
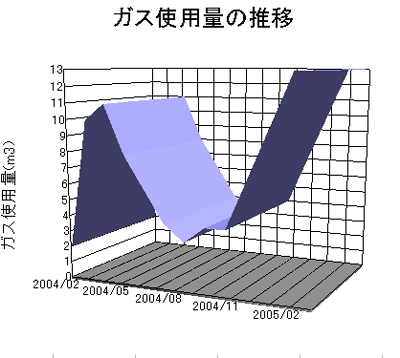
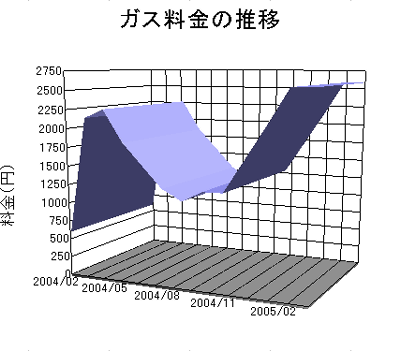
ガスについても1年分をまとめてみた。電気よりもさらにわかりやすい推移を示している。
冬場多くて、夏場少ない。これは夏はシャワー、冬は湯船という生活習慣の変化を如実にものが
たっている。うちの暖房は電気なのでまだ冬夏の格差は少ないと思うが、実家などはファンヒー
ターなので、差は激しいと思う。
電気と異なるのは、使用量の格差ほどに料金の格差がついていないことか。ガスは固定費である
基本料金が電気に比べて高いが、0〜20立方メートルまでは1立方あたりの値段はかわらない。
それに対し、電気は15kWhまでの最低料金は安いものの、15〜120kWhまでが、1kWh
あたり17.77円なのに対して、120kWh超〜300kWhまでが23.20円、それをこえ
ると、24.92円と使うほどに従量費が高くなる。(ガスは逆に基本料は上がるものの従量費は下
がる。)この違いが出たものと思われる。
固定費を取るか、従量をとるかというのは昔の通信料金のプランのようである。考えてみれば、通信
料金というのは電気・ガスに比べると原材料費がかからないわりには割高だと思う。設備投資の規模
にしても電気・ガスよりもはるかに低いはずだが。(香港なんか市内通話はただなのになぁ)
電話料金は、なぜか料金表をとっていないので、集計せず。たぶんあまり面白い傾向は出ないし。
- 2005/02/21(月)
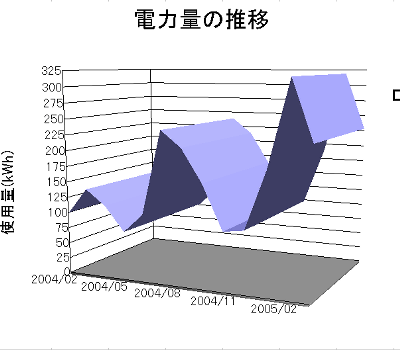
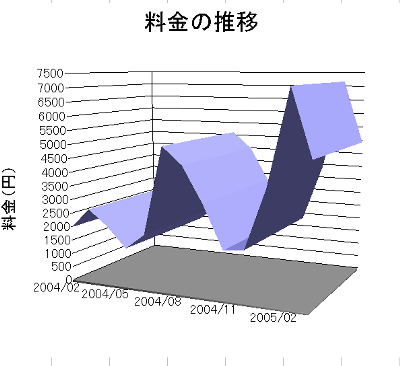
2月の電気料金の請求が来た。これでまる一年分なので、電力量とその料金を集計してみた。
従量制なので、電力量に料金が比例していることがわかるが、料金は段数によって若干変動する
ので、完全に同じというわけではない。そんなことより、こうやってみると夏場の電力よりも冬
のほうが多いというのはちょっと問題かも。眠るまえの電気カーペットの消し忘れが結構多かっ
たのが原因かもしれない。去年の冬場に比べると明らかに多いのは今年のほうが寒いということ
の証左だろうか。しかし、一月の7000円はちょっときつかった。注意せねば。
ガス料金についても後日集計してみたい。
- 2005/02/20(日)
部屋の電気を落とすと、真っ暗になるかと思いきや、実は鋭く輝く光がある。パソコンやオーディオ
それにTVやレコーダー、スイッチ付きのコンセント、ターミナルアダプター.....それらのパイロ
ットランプの赤や、緑のLEDの光なのだ。それらは寝静まった都市の門番のような赤い航空灯や
一晩中働き続ける信号のようにようで、真夜中の夜景を俯瞰しているような気分になる。
パイロットランプがついているということは、通電していて電力を消費していることの証なのだが、
寝床で眠りにつくまえにその灯りを見ていると、なんだか消してしまうのがもったいないように思わ
れて、ときどきつけたままにしている。
常夜灯のつもりではないけれど、一等星のようにくっきりした光達は夜中目が覚めたときの道しるべ
なのだ。・・・導く先がトイレとか台所だったりするのがちと、情緒にはかけるんだけど。
おやすみなさい。
- 2005/02/19(土)
私の部屋にはある二つのものがなかったのであるが、特に不便を感じていなかった。だがどうも
あったほうが良いのではないかという状況になってきたので、そのうちの安いほうを購入するこ
とにした。というか今日買ってきた。
買ってきたのはドライヤーで未だにないものは掃除機だ。そんなの標準装備だろ!と思うかもし
れないが、なくてもなんとかなってきたのだ、これが。ドライヤーがなくても念入りなタオリン
グ(そんな言葉ないか)で水分をとっておけば、自然乾燥するし、夏場や髪の短いときはそれす
ら不要だった。掃除機に関しては、まえにも書いたと思うが、クイックルとコロコロで十分なの
でこれも不要だった。
ところが水曜日にやらかしてしまった。バスクリンを浴槽にいれたあとあわててしまい、ふたを
しめきらないままで箱をでーんと洗面所に倒してしまったのだ。そう、大量の粉モノをこぼした
場合の対処方法としては掃除機が最良なのだが、うちにはなかった。これには結構困ってしまっ
た。とりあえずこぼれたバスクリンは乾燥したままで、まだ生きていたからなんとか箱にもどす
ためにうすくて丈夫な紙ですくいとる作業を繰り返した。9割くらいはすくえたが、あとすこし
はどうしようもない。ぞうきんでふき取ることにしたが、めんどくさいので放置している。
まぁ、とりあえずなくても対処できたので優先度は下がっている。これがホットカーペットの
じゅうたんのうえだったらと思うと、ちょっと考え直したかもしれないなぁ。
さて、ではドライヤーを買った理由だが、当然ながらタオリングによる乾燥には限界があって、
その後の自然乾燥に頼った場合、翌日にすくなからず頭痛を伴うケースが増えたためである。
わたしの頭皮防御構造も弱くなったものだ。もうひとつ。自然にかわいた場合には一つ問題が
あって、翌日の髪型がどうなるのか予測がつかないということだ。
あさ、はねはねの髪を水でぬらしてタオルをかぶって補正するのだが、横を向くとどうも後頭部
がおもしろいくらいに浮き上がっているのがわかる。まるでエアーインテークのようにである。
エアインテークとはジェットエンジンの吸気口のことなので、本来は前面にないとおかしい、
などとどうでもいいつっこみをしてしまいつつも、どうにもぴょんと跳ねた姿は珍妙である。
まぁそのあたりは無頓着なので、これまで気にしていなかったのだが、このまえ帰宅したとき、
玄関の靴入れについている鏡で自分の顔をみてちょっとへこんだ。仕事で疲れているとはいえ、
なんとも冴えない雰囲気を漂わせている。その元凶はなすがままののっぺりした髪型にあるよう
だった。もともとの顔のつくりは仕方がないが、髪型はなんとかなる部分だ。
清潔感とかそういうものは他人が見て不快感を与えないという面でも重要かもしれないが、自分
の姿を自分でみたときに、そこに活力があるか?感じ取れるかということでも重要なのだといま
さらながら気づいたのだ。そういう努力を自分でする、創りだしているという気持ちだけでも、
たとえ外見上がそれほど魅力的でなかったとしても、毎日仕事をして生活をしていくうえで気持
ちをプラスに持っていけるような気がする。
実家にいるとき、当然ドライヤーはあったのだが、生来のめんどくさがりのせいかあまり使って
いなかった。たしかにちゃんと使ったあとは、睡眠をとった翌日でも髪がしっかりきまっていて
無理に補正する必要もなかった。
ひとりで暮らし始めて一年少し経っているのに、社会人になってはウン年なのに、いまだに未熟
であることに気づかされる毎日なのだった。
ドライヤーは松下電工製で1850円。安い。
- 2005/02/18(金)
どうでしょうリターンズを見ていて最近思うのは、小中高で覚えた地理の知識というものをほと
んど忘れているなぁということ。あんなに必死になって覚えたのに、カルスト地形とかシラス
台地とか河岸段丘、牧ノ原台地なんて、問題として問われるとなかなか出てこない。しかし、こ
うやって番組で大泉洋と一緒にフィールドワークをするとみるみる知識が更新されていく。すごい。
なんだか地図帳をすみからすみまで見たくなってきた。地図帳というと、中学のときの地理の小試験
を思い出す。そのテストは007という名前なのだ。問題は常に7問あり、一問につき完答なら
100。部分正解で010。不正解で001とカウントされる。正解3点、部分正解1点、不正解
0点。つまり7問すべて不正解だとカウント007で0点。007の名前の由来である。
7問の問題はすべて口頭で出題される。たとえばこうだ。「中部山地の主な山の名前を北から順に
5つ答えよ」。試験のたびに地図帳の何ページから何ページという範囲のみ示される。われわれは
そこに記されたすべての地理情報を片っ端から頭に叩き込んでいくのである。なにしろどんな問題
が出るのかわからない。山河の名前、都市の名前、地理的形状.....とにかく地図帳さえ見ることが
できれば解決するのだが、それを頭のなかに再現できないことにはどうしようもない。名前をおぼえ
ても、「標高順」「緯度順」「経度順」などなどあらゆるソートができないといけないから、文字情
報としてではなく、視覚情報が必要なのだ。
このテスト、学期ごとの中間期末前に計5回行われ、その点数は成績の四分の一の重みを持っていた。
ひどい。そのうえ、実施されるのは8クラス中3クラスのみ。こんな理不尽あっていいものか!いつも
思っていたものだ。だいたい700とった人間がその先生(50過ぎ)の在任期間中に2人しかいない
のである。口頭だから過去問などないし、試験前はもう山かけに頼るしかない。「今回は川だろう」と
か、「いやいや鉄道だろう」とか。
まぁ、思い出せばつらいことはきりがない。
でも、あのテストで地理が嫌いなったということはない。テストはいやだったが地図帳は本来面白いも
のだ。こうやって、いまも大泉洋と一緒に勉強しなおしたいなぁとさえ思っている。あれほどの情報が
一枚の紙に、何十ページか足らずに本にすべて収まっている。これはすごいことだ。そのことにきづ
かせてくれただけでも、あの過酷な試験には感謝しないといけないのだ。すごく前向きに考えて。結構
無理矢理。
さて、こんな話をしても、「どうでしょう」をごらんでない方には一向にその趣がわからないと思う。
安心してください。DVDにして見せます。近くの方。
・・・・オーノー、ここまで書くのに無駄につぶした時間を含めて1時間半も経っている。
金曜日の晩、葡萄のあとはいつも、頭がぐるぐるしてこんな感じ。最近特にそう。助けて。
おまけ
琵琶湖の面積と周囲
669km2(ろくろっくび)もビックリの琵琶湖277km(ふひひ)
おぼえた?
- 2005/02/17(木)
昨日の、『本が好きなんです』という答えはあまり気が利いた答えではないと思い、なぜなんだろ
うかというのをもう一度考え直していた。
昼すぎ、会社のトイレに入って考えた結果は「本を読んでいると独りでもさびしくない」という少々
わびしくて、ひねくれたものだった。理論はこうである。娯楽のうち、ぱっと思いつくもの、映画を
見る、美術作品を見る、博物館の展示物を見るという行為はどれも1対多人数が可能なものである。
もちろん対峙している人間にとっては1対1なのだが、それが多人数で同時進行するのがこれらの行
為の共通点だと思う。そして、多人数であることがほぼ当たり前の世界である。そのなかで、独りで
いる状況というのは、余計に独りであることを意識させ、際立たせてしまうように思うのだ。
対して、本を読むという行為自体は、はじめから読者と本の一対一の関係しかない。まぁ、二人とか
三人で読むことも不可能ではないが、読むという行為自体は必然的に独りにならざるを得ないものの
ような気がする。映画などが向こうからの刺激に対して受動的であればよいのに対し、本を読むとい
う行為は、その字の通り読むという能動的な行為であり、自意識を積極的に働かせる必要がある。
与えられた文字を見るという行為ではなく、それを意味のある文章として感じ取るには他人の意思で
はなく、自分の意思が必要なのだ。その行為は独りきりのものだ。(広義に解釈すれば、映画だって
そうなのだけど。)もっと簡単に考えると、読みながら他人とおしゃべりするのは難しいということ
だといえる。だから独り。もともと独りきりであるから、そのなかで独りでいることの寂しさを感じ
ることは少ないと思う。
・・・・と一旦は思ったのだが、どうも違うなぁと思い始めた。さびしいから、どんどん本を買って
寂しさを紛らわしているのかといわれると違うのだ。本を探しいるとき、買っているときは楽しい
のだ。それは隙間を埋めるために無理して楽しんでいるわけではなくて、正の循環のようにもっと楽
しいことを求めるようなそんな感じでもある。
昨日、書皮友好協会の方にこの前買った「カバーおかけしますか?」の感想メールを書き、その返事
を頂いた。文面から、本屋が好きで本が好きでということが伝わってきた。そして、機会があれば会
に参加しませんか?とお誘いいただいた。みんなの好きな本と、私の好きな本の傾向が似ているとか。
また、昨日、今日と友人と本についてのやりとりをした。簡単な文面のメールだけど、お互い本のこ
とを伝え合った。
これらのことを通じて感じたのは、本は独りで読むものだけれど、読んだあとは独りではいられない
気持ちになるのだということ。この本のことを知ってもらいたい、読んでもらいたい、あの本はどん
な本なんだろう、たずねたい、教えて欲しい。そういう気持ちが生まれてくる。そう、本をつぎつぎ
買ってしまうのは、独りでいたい、独りでもさびしくないっていう気持ち、それ自体は少しはあるか
も知れないが、もっと大きな理由は、もっと積極的に人とかかわっていたいからなのかもしれない。
人とかかわりたいというのは寂しさゆえの行為なのかもしれないけれど、さびしくないからというこ
ととは気持ちの向き方が違うし、当然その結果も変わってくるだろう。
今日も本を読み、明日も読んで、思ったこと感じたことを伝えたい。聞きたい。
結論が出たところで、終劇。(チャラララ、ラーン←寅さんのエンディングのイメージで。)
- 2005/02/16(水)
本屋に寄ると文庫コーナーに「終戦のローレライ」が平積みされていた。だんだん気分が盛り上が
ってきたので、そろそろ自分的に買い注文をいれるときなのである。しかし、ここで待ったがか
かった。「文庫4冊セット+フィギュア(樋口真嗣監修、海洋堂製作)3月発売!」というなん
とも扇情的なポップが立っていたのだっ!ついに文庫本にまでフィギュアがつく時代になってし
まった。あきれるというより感動を憶えてしまう。ちなみにヒロイン(っているのか?)のフィギュ
アとかではなくて、もちろん潜水艦。それも2隻。男のロマン。
しかしなんですね、女性で乗り物(鉄道、艦船、飛行機などなど)に興味があるひとって、ほとん
どいないのはなぜなんだろうか。遺伝子に刻まれているとも思えないが。コミケでもメカミリのコ
ーナーには少なからず婦女子はいらっしゃるが、50:50ってことは決してない。
ところで先ほどのフィギュアつき文庫セットは1万セット発売だそうである。出版社の事情はよく
わからないが、映画とのタイアップとはいえ、バリバリ硬派な小説が4冊である。そんなに買う人
がいるのか心配になってしまう。フィギュアつきの漫画や、アニメDVDを買う人というのは、
かなりの確率で、フィギュアの道にも、アニメ・漫画の道にも通じているものだ。だから商品とし
て成り立つわけだが、小説好きとフィギュア好きの接点はあるにはあるけれど、かなり限定される
と思う。これが、映画「ローレライ」のDVDにフィギュアがつくというのならわかる。特撮好き
のひとは、模型、フィギュアの道に通じているから。
というわけで、多分店頭で「だぶつく」と思うので予約はしなかった。書店には珍しく内金2000円
というのもちょっと痛いし。
その後、文庫本を2冊買ってから店を後にした。
『近頃、本を買いすぎじゃないですか』というお便りを頂きました(ウソ)。
『本が好きなんです。』と答えておこう。(誰に?)
「どうでしょうリターンズ〜試験に出るどうでしょう第3回」を見て、「白いメリーさん」を少し
読んでから寝ることにする。明日早いけど大丈夫かなぁ。
- 2005/02/15(火)
昼休み、ネットで国立公文書館のHPを見る。1924年のテレグラフを探すためだ。
日月堂で手に入れた、Imperial Government Telegraphs。訳文は鉛筆書きで「孫氏北へタツ
至急話シ キメタシ」とある。発信は広東(Cantonと表記。この表記は正しいか?)で、
あて先は、「Kayano Nakanocho Azabu Tokio」となっている。当時、麻布区仲之町という地名が
存在することまでは確かめたが、「カヤノ」が何をさすのかがわからない。人名なのか、住所の
続きなのか。なによりも、このテレグラフの仕組みが不明である。民間人も使えるものだったの
かも定かではない。それともやはりこれは政府機関専用のものだったのか。
何を考えているかというと、1924年、北、孫というとどうしても、孫文のことがうかんでく
るのである。孫文は死去する1925年の前年の1924年に広東から北京へ向かっている。
もしかしたら、そのことを指す文書なのではないか・・・と、想像をたくましくしているわけ
である。で、当時のテレグラムで同様の文書、あるいは住所への通信がないかと思って、公文書
をあたってみることにした。検索の仕方が悪いのか、いまのところ似たものは見つかっていない。
もしかしたら好事家の偽造品?などと、またもや飛躍したりするが、価格が200円なので、セド
リの価格は推してしるべしであるし、紙の質、用紙についている「大日本帝国 電信」証紙などを
見ると、とても偽造には思えない。
まぁ、これが単なる広東の孫さんとの商談のやり取りであっても、当時の通信インフラを知ること
ができる貴重な資料であることには変わりはない。まぁ、貴重といっても、一部の人間以外は誰も
見向きもしないであろう単なる紙モノなんだけど・・・。これを面白いっ!て思ってくれる人、
あなたは友達デス。
- 2005/02/14(月)
この旅で、ひとつ自分的に変わったことがある。水を飲むようになった。
箱根で風呂上りに水分を補給したかったのだが、ランチを食べてから時間があまりたっていな
かったこともあって、あまり甘いものは飲む気がしなかった。そこで、まぁものはためしと思
って、自販機でvolvicというミネラルウォーターを買ったのである。
むかし、NCで酸素10倍ミネラルウォーターが2週間ほど流行ったことがあった。そのとき
にわたしもそれを飲んでみたのだが、どうも「水」だけを飲むと胃腸の調子や、口のなかのあ
と味がよろしくなく、文字通り「水があわない」感じでそれ以来避けていた。(食事と一緒に
飲むお冷は平気だったのでよくわからない。)
で、volvicを飲んでみたのだが、まず一杯目は風呂上りだからうまいに決まっている。問題は
そのあと続けて飲む気になるかだった。・・・おっ、お腹の調子もいいし、なにより後味がい
い。おいしいと感じる。そんな調子でごくごくやってしまった。そのあと、小田急で新宿まで
向かう車内でも、軽いお菓子とvolvicだけですごすことができた。これは自分的には事件だった。
翌日、神保町散策前に東京駅で二本目のvolvicを購入。これで大丈夫なら本物だろうと思った。
結果は見事、その日一日の水分をそれだけで補充することに成功。(あっ、昼に紅茶飲んだけど
それ以外ということで)
三日目の昼を食べた店はテーブルにはじめからミネラルウォーターがセットされていて、飲んだ
ら100円というシステムの小洒落た店だった。好き好んで入ったわけではなく、皇居北の丸の
あたりにはご飯を食べるところはおろか、コンビニすら一軒もないすごいところで、仕方なく入
ったのである。近隣の警視庁第一機動隊や、毎日新聞社の人はどこにご飯を食べに行っているの
か不思議だ。で、その水はSAN BENEDETTOという正体不明の水であった。
そこでも私は三日目もいけるか?と思い、その水にチャレンジした。うぬぬ、なんかやっぱり
volvicとは明らかに違う。さわやかさにかけるというか・・・でも、お腹の調子は良いようだ。
問題なしと判断。飲用を続行した。昼の分は余ったのでそのまま持ち帰り、帰りの新幹線でも
それ一本で通した。どうやら、ちゃんと「水」だけでもOKな身体になったようだ。
さて、いま書きながら調べてみた。SAN BENEDETTOはイタリア原産で、アルプスの水らしい。味が
違ったのは当然で、こちらは弱硬水で、volvicは軟水だった。それにしてもこんなに違うとはな
ぁ。酒が水で味が変わるというのもなんだか納得である。私は、いままで水にはあまりこだわり
などなかったのだが、これからはちょっと気をつけて、探究していきたいと思う。
ところでこのSAN BENEDETTOの宣伝のところに、「こだわりキムチの直送便」ってあるのはなんだ
ろう?
(追記:「キムチの直送便」が本業の会社が、ミネラルウォーターも扱っているのが真相のよう。
宇都宮の会社らしく、手作り餃子も扱っている。どんな会社なんだ、いったい。)
- 2005/02/13(日)
旅の終わり
丸の内OAZO、丸善(探検)。
丸の内OAZO、宇宙航空研究開発機構情報センター JAXA i(見学)。
東京国立近代美術館工芸館、「人間国宝の日常のうつわ−もう一つの富本憲吉」(鑑賞)。
東京国立近代美術館隣接、H2(昼食、特製ハンバーガー食す)。
東京国立近代美術館、「痕跡−戦後美術における身体と思考」(鑑賞)。
東京国立近代美術館、「河野鷹思のグラフィックデザイン 都会とユーモア」(鑑賞)。
皇居、竹橋〜桔梗門(お堀沿いを散策)。
夜、帰京。
入手したもの1
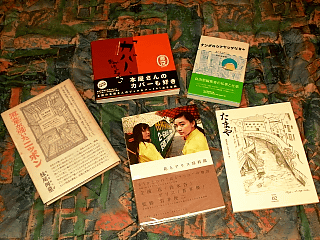
・「河童が覗いたニッポン」(『話の特集』社版)@ブックブラザー武内書店
・「カバーおかけしますか?本屋さんのブックカバー集」(出版ニュース社編)@書肆アクセス
・「たまや 02号」(詩歌、俳句、散文、写真の同人誌。山猫軒刊)@書肆アクセス
・「ナンダロウアヤシゲな日々 本の海で溺れて」(南駝楼綾繁著、無名舎出版刊)@書肆アクセス
・「花とアリス寫眞舘」(岩井俊二監修、扶桑社刊)@書泉グランデ
入手したもの2@日月堂
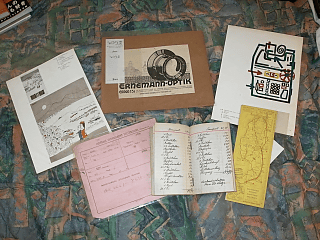
・ミラノ、LANEROSSI社?の企業カレンダー図版(1958年の広告年鑑より)
・olivetti社、Multisumma22の広告(広告年鑑より)
・ERNEMANN社のレンズの広告(雑誌切り取り)
・Imperial Government Telegraphs、広東より麻布。1924年2月5日の通信。
・SALINAS〜SAN JOSE〜SAN FRANCISC,OAKLANDへのルートマップ。戦前のもの。
・三井高陽、ドイツ滞在時?の出納帳(1927.11〜1928.4)
入手したもの3
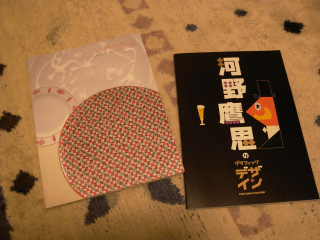
・「人間国宝の日常のうつわ−もう一つの富本憲吉」カタログ
・「河野鷹思のグラフィックデザイン 都会とユーモア」カタログ
- 2005/02/12(土)
旅の途中
神田神保町(書店巡り)。
神田カトリック教会(撮影)。
神田古書センター2F、ボンディ(昼食、野菜カレー食す)。
南青山、古書日月堂(紙モノ入手)。
六本木、森美術館「アーキラボ 建築・都市・アートの新たな実験展1950-2005」(鑑賞)。
大井町、アワーズイン阪急(入浴、宿泊)
- 2005/02/11(金)
旅立ち
箱根宮ノ下、富士屋ホテル(ランチ)。
箱根湯本、湯本富士屋ホテル(入浴)。
羽田空港第2旅客ターミナル(夜間撮影)。
羽田エクセル東急フライヤーズテーブル(夜食)。
羽田エクセル東急(宿泊)。
- 2005/02/10(木)
19時27分(店内時間)、「*&%$#」を買う。
19時43分(店内時間)、「空のオルゴール」を買う。
19時59分(店内時間)、「日本海弁当」を買う。
主時間は記録できない。でも客観時間はこうやっていつのまにか記録されている。
家計簿をつけるためにレシートを集めるのはなんだか面白くないけれど、文字のない記録をつける
ために集めるレシートは楽しいかもしれない。あのとき、このとき自分は何を考えながら、どこで
どんなものを買ったり、食べたりしたのか思い出しながら眺める日記みたいなもの。店名も商品名
も書いてなくて、時間と値段だけのレシートが実は一番面白いと思う。
- 2005/02/09(水)
反省や悔悟、欲望がくるくるして、定まらない。
前向きに生きたいと思っても、どちらが前なんやろか。
申し込み準備完了。明日投函する。協力してくれたS降、たむ氏に感謝。
コンビニに寄ったときにふらふらと「ボム」という雑誌を買ってしまった。小野真弓の特集だった
ので、つい。だいたい、成人男性で「ボム」を読んでいる人というのはどうもダメ人間なんじゃな
いかというイメージがあったのだが、とうとうその仲間入りをしてしまった。いや、ちがう。定期
的に買っているわけじゃないから、まだ大丈夫だと思いたい。それにしてもココの店は、他店にな
いくらい「ボム」がたくさん置いてある。需要があるということか....。気をつけよう。
「どうでしょうリターンズ」を見て寝ることにする。
- 2005/02/08(火)

実物は45mm×37mm。カタログ印刷時には63.8%縮小される。
計画通り、四条烏丸のキンコーズに行ってサークルカットを製作。所要時間30分、経費600円少々。
Photoshopのバージョンが7だったので、少し戸惑う。家で使っているのは4.0LEで、たしか5くらい
からインターフェースの大幅な変更があったのだ。サイズが非常に小さいのであまり凝ったことを
すると、きちんと印刷されない恐れがある。シンプルに、でもちょっと目を引く感じで作ってみた。
いかがでしょうか?
このセルフのPCコーナーは便利なのだけど、ひとつ問題があって、印刷しようとすると紙にサイズ
やファイル名を書いて、店員に渡さないと印刷できない決まりなのだ。今回のように何枚か刷って、
濃度などを調整したい場合にはめんどくさい。しかも、印刷されたものは店員から受け取るのだ。
これってある意味羞恥プレイだ。一応、今回はまじめな印刷物だが、恥ずかしい内容だったらどうす
るんですか。各スペースにプリンタを置いて、枚数だけカウントしてくれれば良いのに。
- 2005/02/07(月)

引越し一周年記念日。
ケーキ屋が空いている時間に帰れなかったので、コンビニで売っていたもののなかから、それなりに
祝祭的な雰囲気漂う(と思われる)コーヒーゼリーを買ってきた。ろうそくが売ってなかったので、
マッチを立てて火をつけた。でも、吹き消す前に消えてしまうのだった。
これからは毎年コーヒーゼリーで祝うと決めた。ものの3分もせずに食べ終わるのが悲しいけれど...。
サークルカットを作ろうとして、メインマシンでPhotoshopを立ち上げる。画像を配置して、文字を入
れようと思いタイプツールを立ち上げる.....?フォントがMSゴシックと、MSPゴシックしか選択
できない!そんな馬鹿な。Wordを立ち上げてみるとやはり同じでこの2つしか選べない。フォントその
ものは、フォントディレクトリにあるので消滅したわけではなく、なんらかのリンクが切れている様子。
OS自体、夏ごろからおかしかったので、直すのは無理っぽい。セーフモードの立ち上げ途中に突然
落ちるのだから直しようもないのだった。
くそー、こうなったら明日会社帰りにキンコーズに寄って作ってやる。
(会社で印刷せずに済むし。)
- 2005/02/06(日)
コミックマーケット68の申し込み準備をする。住所を9箇所近く書かねばならないのだが、私の
現住所名には通りの名前が入っているためすごく長く、これだけでもう大変。そのうえいくつかの
箇所は振り仮名をつけねばならず、注意していないと欄をはみ出しそうなのだ。
同封する「短冊」と呼ばれる書類は、用紙からカッターで切り取らねばならないのだが、切り取り
用の点線は残さずにきらないといけない決まり。同じ用紙にサークルカット(カタログに掲載され
る各サークルのアピールのこと。大多数が絵。)を描く欄があるがその欄のまわりは黒く縁取られ
ている。この黒ぶちの外がわに白い部分が残っているとアウト。
また、参加サークルを分類するためのコードを書かねばならないのだが、これがやっかいで、安易
に「その他」を選んでしまって、もし活動内容に書かれた内容と一致するコードが存在した場合に
はこれもアウト。私は今回、建築の写真集をだそうと思っているのだが、これなどはコードが存在
しない。しかし、コード609鉄道、旅行、メカミリの補足欄に「カメラ」とあるのが曲者だ。カ
メラという場合、カメラの機械的なことだけを指すのか、写真も含むのかが一切判断できないのだ。
たしか、冬コミで廃墟の写真集を出していたサークルはメカミリ・旅行の近辺に配置されていたは
ずなので、609として、活動内容に「建築写真」とかいてあれば、近くに配置してもらえるかも
しれない。まったくジャンルが異なるところに配置されてしまうと、手にとってみてもらえる機会
が極端に減ってしまうし、隣近所のサークルと会話もできないのでさびしいだろうと思う。
とりあえず、「その他」にして「カメラ」と判断されてアウトになるよりも、609を選んだほう
が得策と考えた。これ以外にもさまざまな書類上の注意があって、全部書くのに3時間くらいかか
ってしまった。(アンケートなどもあるので)
これまでアウトといっているのは「書類不備」扱いで、抽選の対象にならないことを指している。
そう、何万というサークルが申し込みを行うが、東京ビッグサイト全館を使用してもその数はまか
ないきれるものではなくて、そのためにジャンルごとに抽選が行われるのだ。全申し込みの5割か
ら7割が当選となる。そういうこともあって、ことさら書類の不備には厳しくなっている。
(サークルチケットを手に入れるための『ダミーサークル』排除の意味合いも強いと思われる。)
まあ、ここまで苦労したうえに仮に当選したならば、いい本を作らねばいけない、という気持ちに
ならないはずがないと思う。
さて、あとは一番重要なサークルカットのみ。絵は難しいので文字をPCでレイアウトしてプリン
トアウトするつもり。ここでも注意があってカットの左上の升目にはプリントなどを張り込んでは
いけないのだ。サークルの配置番号が印刷される箇所であるため。最後まで気を抜けないのであっ
た。
まずは明日、参加費用を郵便局で払い込む。夢への第一歩となるか。
いろいろ悩みはつきないけれど、頑張らねば。
そう、頑張ろう。
- 2005/02/05(土)
坂本真綾の2nd Album「DIVE」を聞きながら、阪急で大阪に向かう。このアルバムは1998年の発売
だから、わたしが会社に入った年と同じだ。彼女のほかのアルバムに比べて、どうも地味な感じが
して、ながらく聞いていなかったのをひっぱりだしてきた。とつぜん聞いてみたくなったのだ。
あらためて聞いてみると、しずかな曲調のものが多くて派手さもないけれど、きらきらひからない
けれど、しずかにしずかに銀の光を放っているように感じられた。それは低周波で体の奥まで届く
マッサージ器のように、かたくなった心をときほくしていくようだった。98年当時には思いもつ
かなかった。
最後の曲、「DIVE」を聞いてひとつ得心がいった。このアルバムの印象がこれまで薄れてしまって
いたのは、この曲の存在が自分にはあまりにも大きすぎたからだ。アルバム「DIVE」イコールこの
曲といっていいくらいの強烈な印象が当時あった。アルバムそのものに対する考えは変わったとし
ても、この曲のもつ強さというものはいまも変わらなかった。
ふつう、ポピュラーな曲の場合、歌詞は1〜2,3番あるだろう。そしてたとえば1,2番とある
場合、その歌詞の内容というのは同じテーマに対する違うアプローチであったり、言い換えであっ
たりすると思う。つまり1番と2番は並列なのだ。メッセージソングの場合、歌詞がつづきものにな
っていることもあるが、数は多くないし、1番から最低3番はあるだろう。
このDIVEの場合、歌詞は1番と2番しかありえない。3番はないのだ。そして1番が起承ならば、
2番は転結であり、1番だけ聞いても意味はなく、2番だけ聞いても意味はない。一分のすきもなく
そこで世界がはじまり、そこで終わる。ひとつの曲で完結した世界。その密度の高さは聞いてい
てふるえがくる。高揚し、沈静する。曲だけでもだめで、詞だけでもだめで、そこに歌があるか
らこんなにもこころ震わすのだと思う。この世界は、もしかしたらとても日常的なことで、世の
中の誰もが経験していることなのかもしれないけれど、こんなにも純粋で、哀しくて希望に満ち
ているのはなぜなんだろうか。
坂本真綾当時18歳の歌は、むかしもいまも私の精神安定剤。

練習前のひととき。やっぱり外は寒いよ〜。飲み終えてからなかに入ると、I東さんが窓際で
こちらを観察していた。いつから見てたんだろ・・・なかの席空いてるなら呼んでくださいヨ。
- 2005/02/04(金)
豆は売ってなかった。コーヒー牛乳と小倉マーガリンとハバネロを買って、とぼとぼ帰った。
自分の気持ちをどう表現したいのか、ときどきわからなくなる。寝る。
- 2005/02/03(木)
そういえば、今日は節分でしたか。すっかり失念。昨日の夜は、「明日はコンビニで豆でも買って
帰るか〜、鬼のお面がついているやつ」とか思っていたのであるが。2/7で引越し一周年なので、
約一年間の厄払いとこれからの福を招かねばなるまい。というわけで、明日は在庫処分でちょっと
安いはずの豆を買うと決めた。お面ついているやつがあればいいなぁ。
カセットコンロでお茶を沸かしてみた。ぐつぐつ、かたかた、かたかた。まるで雪深い北陸の待合
室にいるかのような気分に浸る。台所では聞き取れない音が部屋の真ん中に響く。と気がつくと、
いつのまにか理科実験室に移動していたりして、頭のなかは忙しい。こういう日常音を録音してみ
ると面白いかもしれない。コミケなどに行くと、鉄道のアナウンスや、走行音を録音したCDを売
っていたりするが、これがなかなか聞いていて楽しいのだ。それの日常生活版。
お茶が沸いたので飲む。こぽこぽっ、とお湯のみに注ぐ。これもいい音。
- 2005/02/02(水)
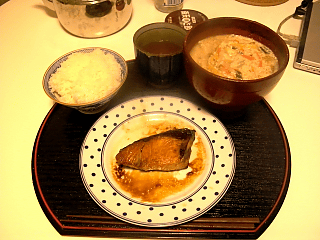
本日の食卓。ごはん、ぶり、かすじる、番茶。毎日こういう調子だといいのですが。
ぶりを食べるのにいい皿が家にはなく、やむをえず明るい系のものを選ぶ。なんだか、洋食っぽく
なってしまった。やはり、焼き魚には角皿で藍か、緑釉のものがいいと思う。実家からもらってく
るというのもいいが、そろそろ陶器を自分で選ぶという気持ちが出てきた。五条もわりあい近いの
で今度探しに行こうかと思う。
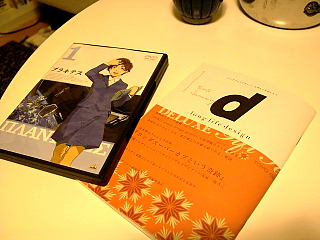
本日の買い物。雑誌「ディ・ロングライフデザイン1」、DVD「プラネテス1」。
プラネテス1巻をビーバーレコードで発見する。これまで5軒ほど探したが、なぜか1巻だけがな
いというところが多くて、やっとのことで手に入った。これは「R.O.D the TV」以来、久しぶりの
「何度見ても面白い」「どうしても人に見せたい」アニメーションである。雪野五月さんの演技が
とても良い、というのもR.O.Dとの共通点かもしれない。
東京人の三月号を買うつもりで行ったジュンク堂であったが、発売はまだであったので、いつもの
ごとく4階に行く。なぜか、建築のコーナーで発見したのが「ディ・ロングライフデザイン」であ
る。D&DEPARTMENT PROJECTのナガオカケンメイ氏の発行するデザイン誌。A5、48ページ。
A5サイズの雑誌というのは実はとても、読みやすい。両手にちょうどおさまるか、ややあまる大
きさというのは、視覚的にも心理的にも落ち着きをもたらすような気がする。・・本の話ですよ。
この雑誌は、雑誌というよりも「小冊子」のようである。製本も中綴じであるし。このことも含め
てのことだと思うが、編集後記でナガオカ氏は「デザインをしないようにしてデザインのよさを伝
える」ということをやりたいのだそうだ。D&DEPARTMENTのことをご存知の方はわかると思うのだが、
過去から現在、あるいは過去にロングセラーを誇ったモノ、グッドデザイン賞に選定されたがいま
はもうないもの、そういったものにこそ、「デザインの本質」があるというのが氏の考えのひとつ
であり、この本はその「本質」というものの姿を読み物の形でいろいろと紹介している。広告は3点
のみ。だから読んでいてうるさくない。その広告も本文の一部かのようだ。デザインを買わせるため
に「見る」「見させられる」雑誌ではなく、デザインのありようをゆっくり「読む」「識る」「考える」ための
小冊子だと思う。
雑誌「カメラジャーナル」の終刊以来、定期的に購読する雑誌がなかったのであるが、この本は毎月
読みたくなるような、そんな希望を感じさせる。まだ発刊されたばかり。うまく成長してほしいと思う。
追記:読み返してみて東京人は定期的に購読する雑誌じゃないの?と自己突っ込み。まぁ、買わない
ときもあるし、A5サイズの雑誌という意味で。広告批評もA5だが、これもいつも買うわけではない。
- 2005/02/01(火)
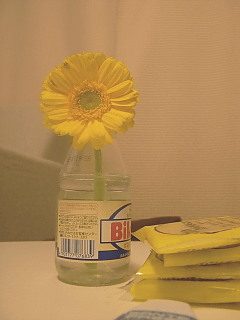
披露宴でもらった花を生けてみた。
私の花キューピットはいずこに?(ちょっと壊れている)
|
|