|
電波暗室 2003/06
- 2003/06/30(月) 「集まらない」
会社帰りにボディーソープを切らしていたことを思い出し、近所の薬局に寄る。勘定の際、
「スタンプカードはお持ちですか?」とたずねられる。そういえばこの店は500円ごとに
スタンプを押してくれるのだ。持ち合わせてないとわかると、レシートに代理スタンプを
押してくれた。これで後日、カードに押しなおしてくれるのだ。
実は、わたしはこの手のスタンプ式カードをコンプリートしたことが一度もないのだ。理由は
結構単純で、1.コンプリートするほど、その店で買い物をしない。2.コンプリートする前に必ず
といっていいほどカードを失くす。のどちらか。
そもそも私は、レシートからスタンプカード、定期、キャッシュカードをひとつの財布につめ
こみすぎる。使い切ったラガールカードまで入っている。一番多いのはレシートだ。なんと
なく昔から、ものが捨てられない性分のため、どんどんたまっていく。それを半期に一度、
だいたい盆と暮れに一気に整理するのだが、そのときに大概、スタンプカードも一緒に
どこかにやってしまう。←袋につめてどこかにおいておくだけ。あくまで捨てない。
ヨドバシカメラや、カメラのナニワのポイントなんかは、カードさえ持ってれば、向こうが覚え
てくれてるし、紙式のカードではなくプラ製なので、財布から駆除される心配がない。また、
コンプリート制ではないので、好きなときに使える。自然と買い物も多くなる。
ただ、紙製のスタンプカードの方が、店員さんが直に押すし、あと少しでたまる!という期待
感や、たまったときの達成感が強く得られるんではないかと思う。その分、お店にも感情移
入したりと、お店にとっては思いもよらないような副産物効果があるのかしれない。初期投資
のすくなさやメンテナンスのなさも個人商店なんかにはいいのかも。
スタンプ式とは違うが、全然たまらないのが、「和幸」(東京のとんかつ屋)の"10枚集めたら
ロースかつ定食一食無料"の券である。わたしは東京に行くと、初日の夜は必ず東京駅
八重洲地下街の「和幸」で食事をすると決めている。(ちなみに二日目は、JR大井町アトレ
6階にある、新宿さぼてん(とんかつ屋)に落ち着くことが多い。)それで、この券は一食に
つき一枚くれる。東京に行くのはだいたい年に3回〜4回なので、一食ずつ食べても10枚に
はならない。問題なのはこのサービス券の有効期限が1年しかないことだ。
したがって、スタンプ式と同じく、ほとんどが財布の厚みを増すのに一役買ってるだけで、
次の東京行きのころには、放出されてしまうのである。「和幸」に行くと、暇な店員が、
ひたすらレジのところで、「ポン、ポン」と有効期限はんこを押している。あれを見るたびに、
いつもくやしい思いをする。いい加減、10枚集めるのはやめて、「和幸」全店制覇という
無意味なコンプリートを目指そうかな?と思っている。八重洲、幕張、新宿京急店しかいっ
たことないので、制覇にはまだまだ時間がかかりそうだ。
- 2003/06/29(日) 「仏」
昨日夜、親戚の大伯父が亡くなった。正確には、母の従兄にあたる。一族の長兄で、母も
含めて、みな「お兄ちゃん」と呼び、とても存在感のある人だった。仕事があるので、通夜・
葬式と出られないので、今日家族と一緒に鳴滝のお宅へお別れに行った。
おばさんに挨拶をした後、お顔を見せてもらった。「ええ顔してるやろ。今日は若い人らが
ぎょうさん来てくれはって、よろこんだはる。」とおばさんはにこやかに言った。私は、おじさん
の顔を見て、無意識に「仏さんの顔してはる...。」といっていた。死んだひとの顔を見て、「仏
さん」というのは、自分でもなんだかおかしいと思った。
でも、本当に仏像だとか、仏画にえがかれている仏様のように、とても良いお顔だった。いま
まで、幾人もの親戚にお別れを言ってきたけれど、おじさんのような顔を見たのは初めてだっ
た。生前、仏様のような善行をつんだ、という人ではなく、よく仕事をし、よく遊んだ、とても
闊達で、でも厳しいような人だったと思う。
昨日の夜、一度来ていた母が、もう一度顔をのぞきこんで、「ほんまやわ。そう、仏さんになら
はったんやね。」と言った。昨日の夜は、まだ生きている感じがしたらしい。死というものは
とても怖いもので、悲しいものなんだけれど、なんだか仏様になった伯父さんに私は生きて
いくパワーをもらったような気がした。
その後、伯父さんの家族と会ったが、みな悲しみにくれるという風ではなく、あきらめという
ものもなく、本当にさわやかに、伯父さんを送ったという感じに見えた。そして、それが、不思
議だとかは、思わなかった。ごく当たり前にすがすがしく感じた。本当のところは、本当に近
い身内にしかわからないものがあると思うけれど、私は伯父さんが、みんなにもパワーを送
ってくれているように思えた。
その夜は大阪に大学合同のサマーコンサートを聞きに言った。夜、帰りの自転車で四条を
通ると、あちらこちらで祇園祭の準備がされていた。すこし、汗臭い体と、吹きぬける風に、
夏の香りをかいだ。もう夏なんだ、と思った。
- 2003/06/28(土) 「まずは歌っとく」
今日は、なにわコラリアーズの練習。雨のせいか?月末のせいか?集まりが悪く20人弱。
雨だから来ないって普通ありえないが、「なにコラ」ならありえるのではと思える。最近、
発声の時間が長くて、今日も45分くらいかけている。指揮者が新開発の発声練習をため
しているのだ。ここのところ長調の音階の後、短調に移行するのをやるようになった。
普通、発声練習というと長調でやることが多い。しかし、実際の曲は短調のものもあるので、
短調の音階練習をやらないのは逆におかしい。はじめてこの練習をやったとき、CM(コン
サートマスター)に指摘されたのは、短調の音階になると、長三度の音階がさがりきらない
ということだった。皆、「短調だとくらめ」というのが染み付いているのだ。さすがCM。
さて、今日は合唱コンクールの自由曲候補曲を音源CDを聴きつつ、練習。なかなか、いい
曲だ。問題は、課題曲の選定。指定されている曲は4曲あり、柴田南雄の「しょうがない」、
ヤナーチェクの「Ach vojna,vojna」、J.Dunstableの「Sancta Maria, non est
tibi similis」、
そして多田武彦の「水路」。
これまでは、水路の練習ばかりやっていた。ボイナ(ヤナーチェクの曲のこと)は演奏会で
やっていたし、「しょうがない」は詩が独特すぎるので敬遠されてきた。どこか独特かって
いうと、こんな詩なのだ。『あめだよくふるな〜、まきにひをくべろよ、いまなんじ?いちじ』
『だれもきやしないよ、おてんとさまもきやしない、なんじになった?にじ』。こんな調子で、
八時まで歌詞がつづく。
団内に熱心な「しょうがない」支持者がいて、ことあるごとに「じゃ、つぎはしょうがないやり
ましょ」と指揮者に言い続けてきたが、ことごとく却下されてきた。しかし、とうとう根負けした
のか、指揮者がやる気になった。とりあえず歌うだけ歌ってみたのだ。そうすると「いいじゃ
ん、この曲」と指揮者豹変。いや、実際やってみると、いい曲というか、合唱音楽の技巧の
極みみたいな曲で、ふざけているのか遊んでいるのか真面目なのか、すれすれの曲なの
だ。誰だ、こんな曲を課題曲にしたのは?
で、そのあと、「M1(Sancta Maria〜)もやりましょう」の声があがったが、「三声はイヤ」と
即却下。しかし、いつもならここで終わりだが、なおも食い下がると、まあいっぺんだけ、
ということになり、やってみた。「この曲、いいじゃん。」、指揮者再び豹変。今日は意外な
ことがよく起こる。
これで、全曲歌ったことになるが、さいごにこんな意見が出た。「F2のBusto、いいんちゃい
ます?」。FとはFemaleの略、つまり女声合唱用課題曲なのだ。しかし「そうやなオクターブ
さげたらいけるな」「課題曲のなかで一番いい曲かも」など、一同乗り気。指揮者も「F2歌っ
ていいか、(合唱連盟に)きいてみて」という始末。相変わらずどこまで本気かわからない。
意外と、男声が女声用課題曲を歌ってはいけないという規定はなかったりして。
(あとで調べてみよう。)
- 2003/06/27(金) 「糸」
ほぼ毎週金曜日、合唱団葡萄の樹の練習がある。18:30から21:00まで、京都市内の
教会を借りて練習している。団が創立された当時、金曜日とはいえ平日に練習にいける
だろうか?と心配していた。そのころはまだ新入社員で、仕事もそれほどなかったので
わりと問題なく練習に参加していたと思う。
その次の年くらいからメインで担当する仕事を持ち始めたので、とたんに忙しくなった。
金曜日は週末なので、どうせなら週末を気分良く、週明けに気持ちよく、という意識が強く
働いて、切りのいいところまで、あと少し少しと仕事を伸ばしていった。そうすると、気がつい
たらどう頑張っても練習に間に合わないということも多くなり、自然と足が遠のいてしまった。
気がつくと、12月の演奏会の曲を全然知らないまま、10月くらいになっていて、あわてて
練習に行くと、いつの間にか新しいメンバーがたくさん増えていて、自分がすごく浮いた
存在なように感じてしまった。そうすると、また何か行きにくくなり、なんとなく打ち解けられ
ない不安だけが残った。
しかし、年を経て仕事がさらに忙しくなると、逆に逃避というのではなく、無理にでも時間を
作って練習に行かないと、自分が枯れてしまう、と思い、金曜日は自分の定時日と決め、
職場でもアピールするようにして、早く帰れる雰囲気を醸成することに努めた。たとえ、5分
であっても練習に参加するようにした。たとえ練習が終わっても、宴会から参加することに
した。そうすると、今まであまり話しができなかった学生達や、後輩達と自然と話すように
なり、いつしかそれが心地の良いものになっていた。
大切なのは糸を絶やさないこと。どんなに細い糸であっても、それがつながっている限り
孤独ではないのだ、と思えるようになった。そういうことに気がつくのにずいぶんと時間が
かかってしまった。いまは、練習が終わって、あと1週間も会えないのかと思うとすごく
寂しいと感じるようになってしまった。その一週間の間に仕事はこんだけ進捗させんと
いかんなあとか考えてしまうのは、悲しい性である。
つぎの練習は来週の日曜日。一週間以上もあるじゃないですか!嗚呼。
あ、なにコラの曲の音とりせんと。
- 2003/06/26(木) 「ライフタイム」

最近、会社でノートに筆記する際、すべてボールペンで書いている。ボールペンは間違える
と当然消せないし、インクだまりができて手が汚れたり、とあまりいいことはない。原因は、
愛用のシャープペンシルがつぶれたからだ。安いのを売店で買ってくればいいのだが、生来
のめんどくさがり癖もあり、機会のないまま、はや数ヶ月。
愛用していたシャープペンシルは、アメリカの筆記具メーカー、「パーカー」社のもの。モンブ
ランやペリカンとならぶ、世界に名だたる有名筆記具メーカーである。万年筆は当然高いの
だが、ボールペンや、シャープペンシルは結構お手ごろな価格で手に入るので、中学時代
から使っている。今回つぶれたのは、1995年にフランクフルト空港で買った、おみやげ用
のブリスターパックのもので、たしか2000円くらいだった。モデル名インシグニア。
パーカーのものとしては、最低価格帯のものだ。つごう8年間くらい、学生・社会人と使いた
おした。なぜ、そのんなに長期間使っていたのかというと、単純に書きやすいからだ。道具
というのは常に進化するが、ある瞬間に究極の進化形態となって、以降定番化する。この
シャーペンはまさにそんな形だった。あとは、使いべりしない丈夫さ。そして、見ていて飽き
ない「単純」なフォルム。長くつきあえる道具というのは、概して単純美をそなえているよう
に思う。
さて、今回どうも内部の機構がつぶれたらしく、芯をいれてもまったく出てこない。細い針で、
芯先から清掃をなんどかやってみたが、だめなのである。こまったことに分解できるように
できていないので、仕方なくあきらめた。(100円シャーペンのメンテナンス性能の高さには
勝てなかった。)
ところが、いまごろになって思い出したのだが、このシャーペンを買ったとき、確か保証書が
ついていて、こんな言葉が書かれていたのだ。"Lifetime Gurantee"、つまり一生涯保証。
壊れたら、きちんと修理しますということなのだ(むろん有料だと思うが)。電化製品ではおよ
そ考えられないし、不可能に近いのだが、それでも一生涯保証すると明言してしまう根性が
スゴイ!(筆記具という単純な道具だから可能というのは、よこに置く。)
どうも、欧米の製品にはこういう保証が多いみたいだ。まえにドイツの双眼鏡メーカーのカタ
ログをみていたら、25年保証とか平然と書いてあった。日本ではどんな製品でも、たいがい
1年間保証であるのと、どうしても比べてしまうというものだ。
パーカー社に送れば、わたしのシャーペンも修理できると思うのだが、航空運賃の方がどう
考えてもシャーペン代金よりも高いと思うので、さすがにやめた。誰か海外に旅行する人に
新しいやつを買ってきてもらうほうが早いだろう。国内でも売ってると思うが、あのブリスター
パック式のやつになぜか心引かれるのだ。
さて、そんなこんなでボールペンをつかい続けているのだが、このボールペンも2001年に
家族にどこかのお土産としてもらった「パーカー」製なのだ。なんだかんだ文句をいっても、
書きやすいことこの上ないので、シャーペンに変わり活躍している。シャーペンに比べて、
壊れる箇所がないので、新しいパーカー製シャーペンを手に入れるまで使い続けると思う。
- 2003/06/25(水) 「食器」
毎日の昼食は会社の食堂で食べる。何せ工場と開発職場をあわせて何千の人間が集まる
から、それはもうでかい。で、当然ながら、セルフサービスである。ここで、常日頃、非常に気
になっていることがある。
食器がプラスティック製なのはまあ、100歩ゆずって許すとしても、どうしても許せないことが
ある。問題は片付けである。ユースホステルとかと同じように、シャワーでゆすいで、食べ残
しや食べかすを流してから、湯槽につける方式なのだが、あまりにも人が多くて、数が多い
ので、すぐに湯槽が満杯になる。で、どうなるかというと、食器洗い担当のおばちゃんが、
プラスティック製の”くわ”で、その山を切り崩すのである。そのときの音たるや、すさまじい。
「ガラガラ、ガシャガシャーン」と、ものすごい耳障りな音を発する。単にそれがうるさい、とい
うのはなくて、あまりにも食器がぞんざいに扱われるのがどうしても我慢ならないのだ。食器
の悲鳴なのだ。そして、毎日その音を聞いていると、「感性」が破壊されていくような気がする。
プラスティック製の食器にも、食堂のおばちゃんにも罪はないのはわかっているが、なにか、
ものづくりを行う会社にいる人間としては、こういうことを許容してはいけないのではないか?
という疑問がわいてくる。
おさないころから、陶磁器製の茶碗や、木の椀といった食器で食事をし、ときには割ったりし
て、親に怒られていると、いやでも食器そのものを大事に扱うようになる。そして、食事をする
ことは、同時にその食器を愛で、鑑賞し、感謝する時間でもあった。新しいお皿で食べる食事
にはいつでもわくわくするものだ。
大量の人間を短時間でさばき、効率よくやっていくことが必要な大食堂には、プラスティック
食器が合理的だし、多少乱暴に扱っても壊れないという利点は経営的にゆずれないだろう。
しかし、である。仕事の合間の休憩時間、食事は何よりの楽しみである。できれば、おいしく
気分よく味わいたい。そのためには、食器というものは重要な要素だと思う。
最近、湯槽につける人たちのマナーもおかしくなってきた。ゆっくり、お湯が飛び散らないよう
にそっとつけるひとはまれだ。たいがいは投げる。食器の山に。ひどい人はトレーから、すべ
らて、落とす。陶器の食器ならば、そんなことはしないだろうと思う。(するひともいるかも。)
そういう行為を見るにつけ、食事の片付けにとどまらない、その人間の「ものに対する」考え
方を見、その考えはメーカーにとって大切なものづくりに良くない影響を及ぼすんではないか
と、思う。また、そういう場面をみて、よい印象を受ける顧客はいないと思う。
大げさなことをかいてるなぁと、自分でも思うのだけど、企業の姿勢をつくるのは、従業員
ひとりひとりの常日ごろの行動なのだ。その行動の、生活の一部に社員食堂がある。
おろそかにしてはいけないと思う。
- 2003/06/24(火) 「雨」
今日も雨である。去年やおととしは確か空梅雨だったと思う。あまりこの時期に傘を差した
記憶がない。雨がふると近頃思い出すのは、おととしの夏、お盆のころだ。東京滞在中だっ
たときに、ニュースで見たのだが、多摩川だかどこかの上流のダムで、「降雨実験」をやっ
ったというものだ。
確かヨウ化銀を気化させて、大気中に拡散させると化学的に雨が降りやすくなるそうなのだ。
果たして、その実験30分後くらいに、ダム湖に雨が降ったのだという。実験を行った施設
は建坪6畳くらいで、実験というより、本格的な降雨装置という感じだった。
昔から、SFの世界では天気はすべて制御されていて、「あと5分で雨が止む」なんていう
台詞がよく出てくるが、制御とはいわないまでも、降雨をうながす装置が実在したことは、
驚きだった。
もうひとつ思い出すのが、草野心平の「雨」という詩である。この詩に曲をつけた多田武彦の
男声合唱曲を学生時代に歌ったことがあり、非常に印象に残っている。この詩はこんなふう
に始まる。
「志度平温泉、第五号の番傘に音を立てる 何千メートルの天の奥からならんでくる雨が
地上すれすれの番傘に音をたてる」(原詩がこの通りかは不明)。この志度平温泉とはい
ったいどこなのか?長い間疑問だった。院生時代、花巻の大沢温泉に旅行にでかけたとき、
その謎は解けた。志度平温泉は花巻温泉郷のひとつで、大沢温泉のすぐ隣にあったのだ。
バスの路線図に、大沢温泉向かう途中に、志度平温泉を見つけたときは、若干興奮した。
いったいどんな風情のある温泉なんだろう?とワクワクしながら、車窓を眺めていると、
飛び込んできたのは、「志度平グランドホテル」のでっかい建物のみ。どこにも番傘が似合
う風情などなかった。勝手に期待していた分、落胆も大きかった。むしろ、到着した大沢温
泉の方が、昔の湯治場そのままの木造家屋で、川沿いの露天風呂は混浴で、たっぷりの
雪と温泉の湯気が、温泉らしい情趣をかもし出していた。番傘があるかと思ったが、大沢温
泉にはなく、雨ではなく雪が降っていた。
歌の、詩の世界の情景を求めて、旅をする人は多いと思うが、実際に想像通りの、想像以上
の風景に出会えるのはどれくらいの確率だろうか。わたしはその後も、「斎太郎節」という
民謡に歌われた「松島の瑞願寺」をたずねたことがあるが、うたに詠まれるほど、すごい
名刹というわけでもなかった。(松島には感動したが。)
一度、歌の通りの情景というものに出会ってみたい。どなたか、これすごいよ!というもの
があったら、その歌と、場所を教えてください。
- 2003/06/23(月) 「げしげし」
新聞を見て気がついたのだが、昨日は夏至だったらしい。昼間の時間がもっとも長い日。
その記事によると、神戸マリンタワーや、道頓堀のグリコマーク、京都タワーなどの照明を
ダウンさせるというイベントが環境庁とNGOの主導であったそうだ。かならず、あるものが
ない風景、事前にしっていれば直接見てみたかった。
地球温暖化へに対するアピールと、東電の電力不足問題などもあり、省エネルギーへの
関心を高めることも目的という。しかし、真に省エネルギーに取り組むには夜間の電力消費
を抑えることには、あまり意味がないはずだ。必要なのは、ピーク電力の平滑化であり、
それはとりもなおさず、昼間時の、主として冷房電力の減少である。
電気はためることができない。夜作った電気を昼使うということはできないのだ。だから、
そのとき必要な分を常に供給し続けなければならない。ならば、昼間の時間を短くすれば
良いのではないか?という意見がある。サマータイム制だ。
サマータイム制には賛成・反対の両方の意見がある。環境効果・経済効果に関するデータ
の信頼性が焦点になっているようだ。実際のところ、どうなのだろうか。サマータイム制を
導入している国は結構多くある。それらの国で暮らしているひとはどう感じているのか。実際
に、経済効果はあったのか、環境効果はあったのか。導入されてからすでに何十年も経って
いるのならば、その当時の環境・経済データと比較することは無意味だろう。そういう意味で
この問題は検証不可能なように思う。
もし、わたしが強い意志の持ち主であったなら、「ひとりサマータイム」をやってみて、その
効果を算出してみたいものだ。幸い私の会社勤務はフレックス制なので、あさ早く出社し、
夕方早く帰ることも可能だ。しかし、会社というのはおかしなもので、定時より後に会議が
あったりする。ある計測機器が使える時間はあさ7時から22時までで、予約抽選制なので
自分の好きな時間に使えるとはかぎらない。個人レベルというはハードルが高そうだ。
ということを考えていたら、グループ会社では大量の電力を使うため、夏場はシフト勤務に
なるそうだ。土日休みを日月やすみ、月火休みにするのだ。これは週末電力の方が安い
からだ。休みがずれるので、家族や友人と遊んだりできないらしい。サマータイムとは
厳密には違うが、電力平均化には一役買っているのかもしれない。
最近の企業は、環境やエネルギー問題に積極的に取り組んでいる。ここらで、話題づくり
の意味もこめて、「会社サマータイム」の検証をやってみるというのは、いい提案だと思う
のだが、どうだろうか。
- 2003/06/22(日) 「大阪府合唱祭」
 
今日は朝から、大阪泉州の貝塚で行われた大阪府合唱祭に行ってきた。場所は貝塚
コスモホール。京都からここへいく場合のルートを記そう。私の場合こうだ。
阪急河原町→(特急45分)→阪急梅田→(徒歩5分)→地下鉄御堂筋線梅田→(10分)
→地下鉄御堂筋線なんば→(徒歩5分)→南海なんば→(急行30分)→南海貝塚→
(タクシー5分、水間鉄道5分、徒歩20分)→貝塚コスモホール。片道1160円。
ごらんの通り、ひじょーに遠いのだ。しかも懐直撃な交通費。車の場合は時間は短縮
されるが、有料道路を駆使(?)すると、片道3000円以上かかるらしい。
かように、不便なホールであっても、ゆずれない理由というものはあって、それはホール
代。格安らしいのだ。それからもっとも重要なのが、音響。良いホールっていうのは、私
の感覚からすると、自分の声が下に沈まずまっすぐ伸びていく感じがするところ。そして、
歌い手の声をダイレクトに客席へ届けるところ。風呂場音響だと何重にも反響しあって
しまうため、良い声も悪い声もごっちゃになってよくわからなくなる。良いホールはそれが
ない。けれどその分、歌い手の技量がシビアに問われる。
さて、自分の出演する団体の集合は15:20なのだが、ある団体の演奏が聞きたいので、
オープニング10:00から現地入りした。その団体は畷ジュニアハーモニー。ジュニア合唱
団というと、子供の"習い事"的な感じがして、音楽そのものよりも、子供のパフォーマンス
を見ている気がして、気恥ずかしくて見ていられない、と正直思っていた。
1、2年前、私の入っている合唱団の指揮者が、畷ジュニア(略称NJH)の指導を始めた、
と聞いたときも、「たいへんやなあ」としか思わなかった。実際、ジュニア合唱団の指導・運
営は相手が子供であることから、学校・保護者などの絡みもあって大変だったようだ。
だが、指揮者が着任してから各地の演奏会への参加や、上海での交流演奏会など、着実
に実績を重ねていくのを見ていると、これはひょっとしたら?と思いはじめ、ききにいく機会
を待っていた。そして、今日の日となった。
NJHの前には2団体のジュニア合唱団が演奏。子供らしい素直な発声で演奏そのものは
楽しめた。一団体はオペラ「森は生きている」の一幕を、衣装演技つきでやるなど、目でも
楽しませてくれたが、それ以上のものはなかった。素直に認められないのだ。なんかもやっ
として、これでいいのか?いやジュニアだからこれでいいのだ?いや違うの葛藤。
そして、NJHの出番。まず選曲からしてびっくりである。コダーイのケセンテである。だれも
ジュニア合唱団がこんな渋い選曲するとは思わないだろう。まず、不意打ち。演奏が始まる。
ショック2。あたまから和音が決まって、ホールがパンと鳴る。その後もハーモニーの美しさは
絶えない。パフォーマンスに頼らない「音楽性」をまとっていた。発声が素直な分、大人の
合唱団にはありえない、そう雲の上のような、常に明るい日差しが輝く和声だった。
他2曲はアリランと民謡風の中国のうた。こちらは難易度は下がるが、やはり決めるところは
決める、しめるというかっちりとした音楽作りがなされていた。パフォーマンスもあったのだ
が、もう、それも無条件で許してしまえるくらいに聞き入っていた。残念だったのは、パワー
不足。和音が決まっているだけに、声量の少なさが惜しかった。ここを読まれている方で、
お子さんがいらっしゃる方、ぜひNJHに入れてあげてください。いい合唱団です。これから
もっと伸びる要素を秘めてます。"習い事"で終わらない、音楽の世界への扉をぜひ。
で、自分の団体はどうだったのかというと、それはもう、きっちりくっきりやりました。ホールが
良かったので、気持ちよかったー。それから10年連続出場で表彰状と副賞として、商品券
いただきました。さすが実利的な大阪。ありがとうございます。
- 2003/06/21(土) 「楽器と縁のはなし」
 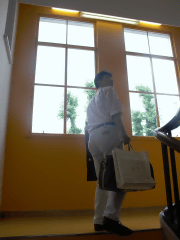
(リニューアルされた関西日仏学館)
今日は、学生時代の合唱団の同期の奥さんが、初のピアノリサイタルを開くというので、
その同期と、もうひとりの同期と、会場の関西日仏学館へ行った。京都に昔からあるのに、
行ったのは今日がはじめてである。どうせならリニューアルする前の姿を見ておきたかった。
建物の外観は同じらしいが、中は結構手をいれたようだ。写真↑のとおり、階段の踊り場
は、黄色の原色ペイントで、さすがフランスである(意味不明)。
なかに入ると、当たり前だがフランス語が飛び交い、掲示板なんかもカラフルかつシンプル
な広告や、告知が張られていて、日本じゃないみたい。掲示板をみてみると...「フランス在
住の娘が用事でしばらく日本滞在するので、受け入れ先を探している」といった下宿相談
から、「写真家○○の京都滞在中のアシスタント募集」まである。←芸術家志望のひとなん
かは、こういうところにチャンスがあったりするので、チェックしてみては?
さてリサイタルである。奥さんの名前は、中司麻希子(Makiko NAKATSUKASA)さん。2003年
フランス音楽コンクール・ピアノ部門で第1位を獲得したことが縁となって、今日のリサイタル
開催のはこびとなったらしい。同期と彼女は高校の同級生で、グリー時代にはよく演奏会に
きていたので、もうひとりの同期も、私も、ふたりの結婚前からの顔なじみだ。
プログラムはフォーレ、ドビュッシー、メシアン、ラヴェル、ブーレーズと、フランスもので構成。
ピアノのリサイタルというものを生で聴いたのは、記憶の限りでは自分史上はじめてだった
ので、とても新鮮だった。演奏はきびきびしたもので、その表現力の高さは、素人聞きにも
すごいものだとわかった。
実は、開演前に少しリハーサルを聞かせてもらった。会場の響きを確かめて、それにあわせ
て的確に演奏の仕方、つまり音の出し方をコントロールしていく姿は、さすがプロだった。どう
すれば、音が変わるのかということを、完全に理解しているのだろう。演奏するピアノは、
当然、演奏する場所場所によって違うから、そのピアノの特性を、すぐに聞き取って、感じと
って理解する技術も必要だろう。
私は、合唱をやっている。合唱の楽器は自分自身だ。私は彼女のように、「楽器」を理解して
演奏できているだろうか?この点には関しては、プロもアマチュアもないはずだ。自分自身の
ことを客観的に感じ取るのは難しいけれども、それがきちんとやれたとき、次のステップに
すすめるような気がする。
さて、演奏はすばらしいものだったので、演奏終了後には彼女や、夫である同期に、別の
演奏会のオファーがあったり、日仏学館の館長さんからも別件のお話があったみたいであ
る。観客のなかに、フランス人の作曲家の方もおり、曲を書くから演奏してほしいという話も
なされていた。このリサイタルが単なる点に終わらず、そこから新しいものが発展していく、
そういう過程というものが見えて、ひとごとながら何か嬉しさのようなものを感じた。
- 2003/06/20(金) 「あのころの私」
会社の行けがけに電車の窓から「うなぎ放題」と見えた。意味不明なので、よく見直すと
「(電話)つなぎ放題」だった。疲れているのか、自分。
今日は混声合唱団「葡萄の樹」の練習の日。練習後はほとんど毎回、飲み会がある。飲み
というよりかは、みんなで晩御飯を食べるようなものだ。だから、かけ声は「飲みいこー」で
はなく、「今日、飯るひと〜」となる。「飯る」とは葡萄用語で、ほかで聞いたことはない。
今日も、だいたいいつものメンバーで近所のお好み焼きへ。そこでの話したある話題が、
自分にとってはある意味ショックだった。今日の練習は指揮者が客演でいないため、副
指揮が練習したのだが、あるメンバーが、「いや〜学生のとき、○○さん(副指揮)尊敬し
てました〜。指揮者講習会のときも...」と話を始めた。
そうすると別のメンバー「あ〜そのとき一緒の班やったよね。あのときの写真あるよ〜」と
話が続いた。彼女達は学生時代は別団体だったし、歳も1〜2違う。ところが、結構昔から、
団や年齢の枠を越えて面識があるのだ。彼女らだけでなく、現役や卒業したての学生達も
団を超えての交流が盛んみたいなのだ。
そこで、私は聞かれたのだ。「山Dさんのときはどやった〜?」。
その場でも話したが、私の入っていた合唱団、同○社グリークラブ(男声合唱団)の人間達
は、よその団体への興味というのがまったくなかった。本当に視野になかったのだ。合唱
連盟の学生部会への行事など、ほとんど参加せず、ひたすら練習。よその団が情宣に来て
も、大概チケットは買わない。皆、平均よりかなり貧乏だったというのもあるが、練習がある
ので、ほとんど聞きにいけないのだ。だから、同じ学校のほかの合唱団に、友達などいよう
はずもなく、交流もなかった。
その場で、同じ団の後輩のIがこういった。「○グリのやつらは合唱が嫌いなんですよ。」。
じゃー何がすきなんという突っ込みに対して、「合唱は嫌いでグリーが好き」。う〜ん、極端
な言い方だけど、本質を言い当ててると思った。そして、同時になんて悲しい集団なのだろう
とも。
あのころは、授業・授業・グリー・実験レポート・グリー、の生活だった。グリー以外に音楽は
なかった。グリー以外に同じ音楽を志す仲間を持たなかった。そんなストイックさが、自分達
だけの、独自の音楽を形作っていたことも確かで、一概に否定するものではなく、くるしくは
あったけど、楽しかったのは確かだった。
しかし、今振り返って感じるのは、自分達はもっと外の世界の音楽を聴けばよかったんじゃ
ないか、そうしたらもっともっと、自分達の音楽を深められたんじゃないかという、後悔だ。
もっともっと、今社会人になっても付き合っていける、違う世界の、同じ志の仲間とめぐり
あえたんじゃないか?という後悔だ。
でも、すぐに思い直した。今、このとき、私はここにいて、いろいろな合唱の世界から来た、
同じ志の仲間たちと歌を歌い、ご飯をたべながら、笑いあっているじゃないか。遅ればせな
がら、新しい世界を感じている。未来から過去を見て、それを否定してはいけないのだ。
反省はしてもいいと思うけれど、今どうしているか、これからどうするかが重要なのだ。
酒はまったく飲めないけど、雰囲気に酔うことはある。私はいま少し酔ってるみたいだ。
こーゆーのが日常のしあわせとゆーのかなーと思う。
- 2003/06/19(木) 「閑話有題」(井上ひさし著「吉里吉里人」より)
いつだか、どこかの合唱の演奏会でパンフレットを見ていたら、全4ステージの中間にあたる
部分に、「閑話休題」とあり、ルビとして「インターミッション」と振られていた。ありきたりに、
休憩とか、インターミッションと表記するのに飽きて、ちょっと変わったところを狙った、という
ように見えた。
最近、この「閑話休題」をよく耳にするが、さきのルビと同じで、どうも意味を取り違えている
ケースが多い、というかほとんだ。インターミッションはそのものずばり、休憩であり、中断し
ている時間そのものを指す。しかし、閑話休題というのは、『閑話(どうでもいい話)を止めて、
本題にもどります』という接続詞的な言葉だ。だから、インターミッションが線であれば、閑話
休題は、点であり、両者はイコールではない。
「休題」とか「閑話」の語感のみが抽出され、「どうでもいい話」「休憩のときの話」のイメージで
使われているようだ。なぜ、このような誤用がまかり通るのか?と考えてみたが、答えは意外
と簡単だと思う。「国語辞典を引くのがめんどくさい」からではないだろうか。
私が会社に入るとき、研修までに必ず携帯用の英和辞典と、国語辞典を用意するようにい
われた。研修中、特に指導があったわけではなかったが、わからない言葉は必ず調べなさ
い、ということだったと思う。社会人にとって、公の場での発言は常に慎重であらねばならな
い。一言の間違いが明暗をわける。また、契約の文言に間違いがあってはならない。文書は
紙、もとい神なのだ。
擦り切れたレコードの上を走る針は、溝とは何の関係性もない「音」を流し続ける。言葉が音
になっては、コミニュケーションもとれず、思考すらままならなくなるのではないだろうか。いや
思考がないから、音になってしまうのか。我々はもっと真剣に日本語のことを勉強すべきだ。
「日本語ブーム」をブームで終わらせてはならないと思う。
「閑話有題」とは本筋とは関係ない話をこれからも続行します、という意味で、井上ひさし氏が
小説のなかで使った言葉です。辞書には載ってませんので悪しからず。
- 2003/06/18(水) 「マン・マシン・インターフェース」
今日の新聞に、日本学生科学賞ソリューション部門の記事が載っていた。日本学生科学賞
とは、科学分野研究の学生コンクールで、歴史と権威のある賞なのだ。毎回の受賞者のテ
ーマ選定や、その分析能力のすごさにはいつも驚かされる。
近年の受賞者を見ていて気づいたのだが、女子中学生・高校生の入賞や大賞が多いのだ。
いつだかの科学賞の募集新聞広告は、セーラー服を来た女子学生が、ロケットを背負って、
今まさに飛び立とうとしている写真が印象的だった。あのころから、いやもっと前から、科学
を目指す女性は増えているのだなーと感じた。
さて、その学生科学賞に昨年から新設されたのが、ソリューション部門。科学的分析というよ
りは、ある課題について解決方法を提案する能力が問われる。解決には主にコンピュータを
使う。その部門の昨年の大賞受賞者が、これまた大阪の女子高校生。テーマは、「携帯電話
の文字入力方法」。
「ももちゃんという友達の名前を打つのに、10回もキーをおさないといけない」というのが、
発想の原点だったという。そこで、携帯のダイヤルキーを使った方法を提案。データによると
30%近く押す回数が減らせるという。携帯電話メーカーはこぞって、いろいろな機能をつけて
いるが、一番のユーザーである高校生が自ら、「文字を入力する」という基本的なインター
フェースの問題に取り組んで、解決手法を示したことに、メーカーの技術者はやられた!と
思ったに違いない。(私もその一人だが。)
このような文字入力に代表される、人間と機械の間を取り持つもの、それがMMI、マン・
マシン・インターフェースだ。あなたや私の目の前にあるキーボードや、マウスがその代表例
だろう。文字入力に関しては、過去からいろいろと研究されてきた分野だけれども、誰もが
携帯端末を持つ時代が確実に近づいている今、この分野はさらなる研究の余地があるよう
に思う。
今、この世界でもっとも完成されている方式は、PalmOSに搭載されているGraffiti文字入力
ではないかなと思う。Graffitiというアルファベットを一筆書きで画面に記すと、機械がそれを
文字と認識するのだ。たとえば"A"なら"Λ"、といように大胆に省略されており、覚えるのは
簡単だ。日本語変換も簡単にできる。文字認識そのものは、ZAURSでも行われているが、
あちらは日本語(漢字・かな)を直接認識させるので、画数が多く高速入力には向かない。
アルファベットで入力し、後で変換する、というある意味、日本語入力にとっては手間と思わ
れる方法の方がずっと早いのは皮肉といえる。
しかし、携帯端末となると片手で端末を持ったまま文字入力をするというのが理想だろう。
そうなるとやはり「音声入力」というのが、一番の方法だ。でもこの方式は「文章を声に出して
読む」という、国語教育には理想(笑)だが、はた迷惑な欠点がある。考えても見て欲しい。
夜中に街を歩いていたら、前の方から、「文語調」で独り言をしゃべりながら近づいてくる人
がいたら、怖くないだろうか。(いや、普通に電話していても怖い。)
音声入力というのは、SF世界ではよく登場し(Star Trekとか、ナイトライダー)、ある種、少年
少女の憧れであったわけであるが、それを公共マナーに反しないように、品格をもって、また
恥ずかしさやテレもなく、使えるようになるには、機械の進化だけでなくて、人間そのもの
が進化していないと無理だろうという気がする。機械は道具だし、道具を使うのは人間。
なにごとも人間次第。
- 2003/06/17(火) 「コスパパン」
会社帰りはおなかがすく。すごくすく。うまい具合に通り道にコンビニがあるので、寄る。
私はこれと決めるとそれを一定期間食べ続ける傾向があり、今の旬は「小倉デーニッシュ」
(¥84)だ。ときおり「たまごチャーハンおにぎり」(¥105)と入れ替わる。(9対1くらい)
小倉デーニッシュは、私が毎日買うので、ほとんど必ず入荷される。が、ときたま人気があり
すぎてなくなることがあり、そういうときはどうするのかというと、「コスパパン」を購入する。
「コスパパン」は正式名称ではない。なんたらロールという名前で、大きな渦巻状の生地
に、白く固まった蜜が縦横にかけられている。値段は¥105。このパンはロングセラー商品
のようで(小倉デーニッシュもそう)、私が高校生のときもよく食べていた。
「コスパパン」の名前の由来は、食生活に関してなにかとこだわりのある友人が、「このパン
はコストパフォーマンス最大!」と力説しながらいつも食べていたので、別の友人が、略して
「コスパパン」と命名したことによる。エンゲル係数は高いが、総収入額の少ない高校生と
しては、わずか¥100(当時は消費税がなかった)ながら、同レベルのほかのパンにくらべ
て、総量の多い(ように見える)「コスパパン」は生命線だった。
ちなみに「コスパパン」を見出したその友人は、大学時代にも独創的な定食を編み出した。
「ごはん(大)+コロッケ(1個)=¥100」セットである。このメニューもまた、その値段のわり
には、午後の授業を乗り切るのにぎりぎりのカロリーを摂取するのに有効だった。また、なら
ばすともすぐに食べられるという長所もあった。短所はなぜだかワビシサが漂うことだろうか。
工学部だった我々は、毎日1〜4まで授業がつまっており、昼食は混みこみの時間帯に食べ
ざるを得なかった。ついでに高校生と同じくらいお金もなかったので、一石二鳥だったのであ
る。4回生になり、研究室に入って時間の余裕ができると、¥100セットを食べることも少なく
なったが、いついかなるときも初心を忘れないために、コロッケ(1個)は必ず食べていた。
(単にコロッケ好きだったともいう。)
さて、その友人も私もいつしか社会人になり、食へのこだわりもうすれたと思っていた。
ところが、昨年の暮れに久しぶり会ったとき、友人はまだあきらめていなかった。彼は、
週末になると卵をたくさん買いもとめ、毎日卵焼きとご飯だけ食べているのだという。
そのうちに、おなかの調子がおかしくなったというが、そのチャレンジ精神には感服した。
その意気に敬意を表して、わたしは秋葉原のメイド喫茶(店員さんがメイド服を着ていると
いう不思議空間。←いかがわしいところではない、と一応力説)へ彼を招待した。そこで、
彼が注文したのは「おでん+熱燗」セットだった。喫茶店におでんがあるのも驚きだったが、
そこでそれを注文してしまう友人はやはり只者ではないと思った。
- 2003/06/16(月) 「セキュリティ」
私の会社では出社時と退社時に門のところで、カードリーダーに身分証明書を通さなけれ
ばならない。建物のなかに入っても、違う階に移動するには必ずカードが必要になるのだ
が、出社・退社にまで強化されたのは今年になってからだ。どうも実際問題としてのセキュリ
ティの強化と、セキュリティに関する規格がISO規格にあがりそうなので、その準備もあるよ
うだ。
導入にあたって、ちょっとなあ、という問題があった。身分証明書が、クレジットカードと一体
になっているのだ。それまでは、クレジットのあるなしを選択できたのだが、VISAかJCBの
強制ときた。なにせ昼食の支払いまでできるカードなので、しょっちゅう出し入れする。だから
そんなものにクレジットなんてつけたくなかった私としては、同じ考えだった課長と一緒に、
官憲横暴!と訴えたのだが、見事に敗訴した。
会社の思惑として、おそらくあまりもうかっていないグループのカード会社に労せずして、会員
数を提供するということがあったと思う。やり方がせこいぜ、まったくもう。(一応私の想像な
ので、あまり本気にしないでください。)まあ、一応会社からの出張旅費の手当てなどの
清算にカードを使うという名分はあるのだが、それとてカード会社扱いなんだから。。。
新しくカードを作ることは、個人にとって、気づかないうちに、リスクを負わせることになる。
(どこで番号を控えられるかわかったものじゃない!)会社のセキュリティのために、個人の
セキュリティリスクをあげるということに、納得がいかなかった。
もうひとつ、気になった点があった。私のような不穏分子をごまかす(?)ためか、会社の信
用のせいか、なんとゴールドカード待遇なのだ。全員。ちょっとまて、である。全員、与信され
るのか?もし過去5年以内に自己破産している人がいたらその人はどうするの??もし、
全員が審査を通るなんてことになれば、それこそ某カード会社の「甘さ」がもろばれではな
いか。
案の定、カード発行後の通達文書には、「クレジットなしのカードの方の場合は...」という文言
があった。だったら最初からクレジットなしをオプションで用意しろと憤ったものだ。まあ、あま
り文句をいっても埒があかないだけで、自分の健康に悪いのでさっさと忘れることにした。
しかし、毎日毎日カードを通すたびに思うのだ。どうせクレジットカードなんだったら、出社
一回につき○○ポイントキャッシュバック!キャンペーンとかやってほしい。皆勤の方には、
抽選で海外旅行プレゼントとか。みんな喜んで会社に来るだろうになあ。
- 2003/06/15(日) 「日記らしい日記と新しい出会い」
今日は、今日起こったことを書く。ことの始まりは先週の日曜日である。母と妹が急に時計の
話をするので、なにごとかとおもいたずねると、今日アンティーク時計屋にいったのだという。
正確には、輸入もののアロマテラピーの容器とオイルを扱うショップらしい。
なんでもご主人が大の時計好きで、店を始めるにあたり、奥さんからコレクションの一部を売
りにだすように言われたらしいとか。とにかく、アロマの話よりも時計の話の方が長かったと
いう。なんでも、時計の話のできる人に会いたいとかで、裏書した名刺を渡されたのだ。
そういうわけで、今日その店を訪ねていった。一歩店に入ると、ユーカリオイルの匂いが漂
い、とても気持ちがいい。ご主人に挨拶すると、とても喜んでくださり、それから2時間に及ぶ
時計談義が始まった。(中略)
ご主人の方針は明確だった。この店で売っている時計はほとんどがご主人のコレクションの
一部。だから、ほんとうにその時計のことをわかって、きちんと使ってくれる人になら、自分が
購入した価格、そのままで譲りたいという。単に飾っておいたり、珍しいから、というので買わ
れるのは嫌なのだそうだ。
こう書くと、なんかこだわり頑固店主みたいだけど、いたって穏やかで、物腰のやわらかな方
だ。時計のことを話すとき、本当にうれしそうに話されるのが印象だった。本当に時計のこと
が好きなんだなと思った。
最後に、その場で気に入った時計をしばらく取りおきしてもらう話をして帰り支度。(その時計
はその場でご主人がはめていたもの!)土、日は私がいますから、また来て下さい、といわ
れ再会の約束をしてその場を辞した。
私は、これまでどこかのお店の常連になって、店の人と話をしたりというようなことは一度もな
かった。だから、時計の話ができたのはもちろん、今日のこの出会いそのものがとても嬉し
かった。趣味が取り持つ縁の不思議さを、合唱以外でも感じた一日だった。
- 2003/06/14(土) 「ラジオ・デイズ」

私は、極端な夜型である。そもそものはじまりは、小学5年生のとき、従兄に手伝ってもらっ
て作ったラジオにある。(写真中段。一番上は大きさ比較のための携帯。下段は高校以来
愛用のSONY・ICR-SW700。学校に行くときや旅行のときは、Panasonic・RF-H760を愛用。)
初めて自分のラジオを手に入れた私は、小学生にもかかわらず、毎日、深夜放送を聞くよう
になった。そう、毎日だ。KBS京都のハイヤング京都で、ツボイノリオ、みのやまさひこ、
越前屋俵太、平智之を聞いていた。中島みゆきのオールナイトニッポンまで聞くこともあった。
高校時代から、就職するまではコサキン(小堺一機・関根勤)の時代だった。コサキンは途中
で関西ネットがなくなり、仕方がないので、TBS954kHzを直接受信していた。とにかく、TV
での二人は、仮面であって、ラジオの姿こそ真のコサキンであることを知った。窒息しそうな
ほど笑った記憶というのは、このラジオ番組以外にはない。
しかし、私のラジオ黄金時代は、就職とともに終わった。と、同時に死ぬほど笑うということも
なくなってしまった。今は定期で聞いているラジオはない。時折、眠れないときに枕元でつけ
てみたりするだけだ。それも聞き入ると起きれなくなるので、途中で切ってしまう。
録音して、昼間きけばいいじゃないか、と思うこともある。でも深夜ラジオは、なにもかもが寝
静まった夜に、目をつぶり、耳だけに意識を集中して、ひそやかに聞く、ということ自体に楽し
みがあるように思うのだ。体は横たわっていても、意識はそこをとびだして、遠く放送局のDJ
とつながる感覚(たとえそれが録音放送であったとしてもだ!)。
もう一度、あの感覚を日々の生活のなかに呼び覚ましたい、と思うのはいけないことだろうか。
- 2003/06/13(金) 「京都は観光都市」
学生時代、合唱団のヴォイストレーナーの先生が、mとnとngの違いを説明するのに、よく
♪きょうとは〜かんこうと〜し、と節をつけて歌っていた。「かんこう」の「ん」は、n,m,ngの
どれか?と学生に質問するのだ。
なぜ、そんなことを急に思い出したかというと、バス停のローマ字表記が気になったからだ。
と、いってもn,mの使い分けができてない!とかそういう文句ではなく、もっと素朴なことだ。
そのバス停には「洛北高校」の漢字表記の下に、"Rakuhoku Koko"と書いてあった。また、
その下には、「下鴨神社」、"Shimogamo shrine"、「金閣寺」、"Kinkakuji"ともあった。
さらにバスに乗るとこういうアナウンスが。「次は京都市役所前〜、"next
stop is Kyoto shiyakusho mae".」。
京都は観光都市なので、外国の観光客に配慮して、英語を併記している案内が多い。市バ
スの停留所や、アナウンスがそうだ。しかし、その表記は外国の人が見て、役に立つのか?
と思うものが多い。なぜ、"high school"ではなく、"Koko"なのか。なぜ、"in
front of City Hall"
ではなく"shiyakusho mae"なのか?観光するひとにとって、重要な情報というのは「読み」より
も「意味」であるはずだ。
まあ、バスに乗ったとき外国人に"next stop is City Hall?"と聞かれよりも、"shiyakusho
mae?"と聞かれるほうが、こっちにとっては意味がよくわかる、ということもある。郷に入りて
は、郷に従えともいうし。しかし、それならそれで、表記を統一すればいいものだが、「京都
駅」は、"Kyoto Eki"ではなく、"Kyoto Station"だし、神社は全部最後に"shrine"がつい
ている。寺でも金閣寺は"Kinkakuji temple"という表記もあれば、"Kinkakuji"となっている場
合もあり統一性がない。
民間の発行する観光地図とかならともかく、世界に名だたる観光都市であれば、そういうとこ
ろはきちんと監修して、表記・発音の統一をはかるべきだろう。「意味」をとるか「音」をとるか
は、難しいところではある。けれど、少なくともアナウンスに関しては、先に日本語で読んでい
るのだから、わざわざ英語っぽい変なアクセントでその音を読み直す必要はないと思う。
海外で、日本人がよく行く観光地には、漢字かな混じりのきちんとしたパンフレット(たいがい
明朝体で、ちょっとぎこちない段組ではあるけれど)や、日本語の観光テープがあるところま
である。本気で観光都市たらんとするならば、もうちょっと頑張って欲しいものである。
- 2003/06/12(木) 「艶麗」
北野恒富展(滋賀県立美術館)に行ってきた。大正から昭和初期に大阪で活躍した、いわゆ
る美人画を多く描いた日本画家である。「いわゆる」と書いたのは美人画と聞いて、すぐに思
い出される上村松園の描く、楚々とした美人とはまったく異なる絵だからである。
恒富はまさに大阪の美人を描いた。大阪といっても戦前の浪速、船場がいきいきとしていた
情趣ゆたかな時代の大阪であり、今日のけばけばしさ、派手さのみを強調した大阪ではな
い。もっとも適切と思えるのは谷崎潤一郎の「細雪」の世界だ。
常になにかに抑制された京都画壇の美人画とは違い、その絵には色気があふれていた。
いや、こんな表現では足りないな。見ているうちに、なんとはなく、もわもわするというか、
むらむらするというか、でも単に英語でいうエロティシズムというのとも違う。
図録の解説の言葉をかりるなら、『艶麗』である。
それは「赤と黒の対比」の色彩のせいもあるし、女性たちの「動き」の豊穣さのせいもある。
昔の大阪の大らかさ、文化的な息遣いという背景のせいもあるだろう。"そんな当時のことは
知るはずもない現代の私"に、そういう風に思わせてしまう絵なのだ。
当時、「画壇の悪魔派」と呼ばれた理由もなんとなくわかる。日本画以外にも、スケッチブック
や小説の挿絵、そして高島屋の呉服セールや、サクラビールの宣伝ポスターも展示されてい
て、美人画だけでない、幅広さを知ることができた。
見に行くまでは、もっとこう繊細な人物のイメージがあったのだけど、会場に入ってすぐの
写真を見ると、恰幅の良い粋人といった感じで、大阪の商家のぼんちのようである。
そこに商人的な部分がやや薄く、品の良さが見て取れるのは、恒富が金沢で生まれ育った
という背景があるのかもしれない。
最後に、彼が描いた船場、道頓堀の美人たちの世界が、今日の大阪でまったく失われてしま
ったことは、なにかと「大阪の人とは違います」といいたがる京都人として、はりあいのない寂
しさを感じ、また残念に思うのだった。
- 2003/06/11(水) 「脳内麻薬分泌法」
会社の近くの駅前に、「けいぶんしゃ」という本屋がある。贔屓にしている本屋のひとつなの
だ。本屋を評価するうえで重要なのは、やはりほしい本があるか、読みたい本が並んでいる
か、それと本屋の人が本が好きか、ということだと思う。ほしい本があるか、ということを基準
にすると、大型書店が有利なように思えるがそうではない。小型書店はせまいから、ほんの
数は少なけれど、その分品揃えに工夫を凝らす必要がある。売れ筋の本や定番の本だけ置
かれていても、一度行けばあきる。売れ筋をおさえつつ、狭い範囲でスマッシュを狙うのだ。
大型書店では見逃してしまいそうな本を浮かび上がらせてくれる、それが小型書店のいい
ところ。
そういう点で、けいぶんしゃは私のツボにはまっている。高校時代の贔屓、北大路の大垣
書店にも似た空気がある。全然興味のない分野でも、あっこれおもしろそうだと、手にとって
立ち読みをすることが多い。というかそういう本のチョイスが実に巧みだと思う。これは2階の
漫画コーナーでも同じ。漫画コーナーでは、カバーを工夫して、お勧め漫画を1話だけ読める
ようにしてあったりする。そうすると、普段読まない週刊誌の連載漫画とかでも読めるので、
すすーっと手が伸びる。そして、「おっとこの先は買ってから読んでね!」とか書いてあるの
だ。全部立ち読みできるより、こっちの方が興味を引かれて買う確率が高いだろうと思う。
この本屋には必然的に会社帰りに寄ることになるのだが、すご〜く疲れていても、つい入りた
くなる。なぜかというと、本を見て回っているうちに、疲れがとれるのだ!これはかなり実感と
してあって、いつだか強烈な頭痛のあったとき、脳内麻薬が耳からあふれるくらい大量に
分泌されて、急激に痛みがとれていくの感じたことがある。
まあ、これはこの本屋に限った現象ではないんだけども、会社帰りというコンディションで、
品揃えのいい本屋が近くにあるのは助かる。ちなみに夜10時半までやっているので、会社
帰りに必ず開いているのもありがたい。(組合との協定で残業は10時までしかできない。)
ところが、駅前の再開発計画のおかげで、店が6月末で移転するという張り紙が!場所は
近くなので、それほど気にしなかったが、移転作業のためにお盆くらいまで休業するという!
困った、困りましたよ。どうしたらいいんでしょうね。(ほんとに困っている)
今日買った本:「ラーメンズつくるひとデコ」(そのうち図書室で紹介)
- 2003/06/10(火) 「ダイナミックレンジ」
今日は「時の記念日」ということを、朝刊で知り、昨日の時計ネタは今日書くべきだったなぁ、
と通勤途中に思う。時すでに遅しなので、別のネタを考える。どうもこのページは始まった
当初から日記ではなく、ましてや備忘録でもないな、と書きながら思う。
さて、私の勤めている会社では、毎日朝会、もしくは昼会(フレックス勤務の場合)がある。
当番のものが前に出て綱領(社訓みたいなもの)を読み上げ、全員で唱和の後、社歌(!)を
歌う。ちなみに、うちの部署でまともに歌っているのは私くらいしかいない。なので、休みを
とるとすぐにわかるようだ。
その後、当番の者が5分以内くらいで「所感」を語る。話題はひとによっていろいろで、最近
買った家電の話とか(シリーズ化している)、ダイエット法の話であるとか、リサイクルの話、
などさまざまだが、最後は大概、仕事のやり方とかに(無理やり)結び付けて終わるのが
セオリーである。なかには、「AはBです」「CはDでした」というような、起承転結の起の字にも
ならないような、ワンセンテンスの所感をする豪傑もいる。プレゼンテーション能力が非常に
疑われる。
この所感だが、会社の創業者が自分の上がり症を克服するためにはじめたといわれてい
る。確かに、部署単位で行うにしても、40〜50人を前に、それなりにまとまった話をするの
は、かなり緊張感を伴うので、知らずしらずのうちに鍛えられているのかも知れない。
このせいか、うちの社員は結婚式のスピーチがうまい、という社外の声もあるようだ。
どんなところで、役に立つのかわからないものである。
ところで、この所感で気になるのが、極端に話し声が小さい人が多いことだ。3mと離れて
いないところで聞いても、内容がまったく伝わらないくらいなのだ。そういう人が多いので、
だいぶ前にマイクが導入された。ところが、マイクがあるという安心感のせいか、よけいに
声が小さく、かつ、マイクの指向性を理解せずにあさっての方向にマイクをむけるものだか
ら、まったく聞えない。これが新入社員とかだったらまだしも、課長、部長クラスのひとでさえ、
そういうひとがいるのだから、困る。
思うに、どうもダイナミックレンジが極端に狭い人が増えているのではないだろうか。小さい
声から大きい声の範囲がせまいのだ。そして、それは「声や音を聞く能力の低下」をあらわ
しているように思える。自分の声が、どこまで届いているのか、客観的に感じ取る敏感さの
欠如といってもいい。
確かなことはわからないけれど、昨今の音量のメリハリのない音楽の氾濫は、耳に小さな
音をひろう労力を失わせているのではないだろうか。学校教育の過程で、クラシック音楽
などのダイナミックレンジの広い音楽を聴く(それも生で)ということは、聴覚を鍛える意味
でも必要な行為なのかも知れない。
- 2003/06/09(月) 「一生モノ」
かつての日本では、一眼レフカメラというものは、自動車と同じ耐久消費財であって、家族の
記念などの、ここぞというときにしか登場しないものだった。そういう意味でカメラは一生モノ
だった。そして、それは一生モノにふさわしい、存在感をはなっていたように思う。
現在の一眼レフカメラの、ものとしての魅力の減衰は、昨今のデジタルカメラの隆盛よりも
10年は前からはじまっていて、いまさらいうことではないかもしれない。が、デジタルカメラも
含めて、それらに「一生モノ」としての存在感は、現在大変希薄になっている。
自動車会社の広告に「モノより思い出」というコピーがあるけれど、その思い出をはぐくんだ
り、想起させるものは、ハード的なものですよ、だからいいものを買いましょうね、というような
逆説的なメッセージがこめられているように思う。しかし、自動車とて10年もすると買い替える
のが、当たり前の世の中になってしまった。そうすると、「一生モノ」は今、あるのだろうか?と
考えてしまう。
わたしにとっては、その答えは、「機械式時計」になると思う。80年代、日本のクォーツ時計
によって、スイスの機械式時計メーカーが壊滅的な打撃を受けたのは有名な話だ。しかし、
この10年で、機械式時計はみごとに復活した。といっても、ロレックスやオメガなどは、昔か
ら認知度が高いが、それ以外のブランドとなると、一部の好事家しかしらないかもしれない。
その中にメーカーではない、独立時計師とよばれる人たちが作る時計がある。なかには、
時計の心臓部、ムーブメントを一から手作りするひとがいる。年に10本の時計をつくるのが
やっとというその時計には、メーカーではなしえない、製作者の壮絶なる想いと愛がこめられ
ている。それらはまさに「一生モノ」の存在感を示しているし、実際にメンテナンスをつづけ
れば、一生どころか、三代以上動きつづけるのだ。
そういう時計はどれくらいの値段がするの?と思われるかたもいるだろう。すくなくとも、
車よりは安い。(高いのも当然ある)。わたしは車を買うお金があるなら、時計を買うだろう
と思う。独立時計師の時計が買えるかどうか別にしても、わたしはそういう「一生モノ」の
時計を買う計画を練っている。しかし、この計画は、(そういう日が来るかどうかは未定だが)
結婚するまでに遂行しなければならないのは言うまでもない。
今日、小中高と同級であった友達が訪ねてきた。10年はあっていなかった。
でも、あまり意識せずに普通に話せた。道具とはむろん、次元が違うけれども、これもまた
「一生モノ」を持つことの喜びであると思った。
- 2003/06/08(日) 「いきつけ」

お酒が好きな人には、それぞれいきつけのバーがあるだろう。コーヒーが好きな人にも、
それぞれ馴染みの喫茶店があるだろう。酒も飲まない(飲めない)、コーヒー(紅茶)を飲む
習慣を持たない私としては、そういう自宅や仕事場とは別の第3の空間ともいうべき、「自分
だけの穴倉」を持っている人をうらやましく思うことがある。
しかし、休日の昼間に、ぶらぶらと散歩していて、自分にもそういう店があるのだと気がつ
いた。新京極の誓願寺からほんの少し下がったあたりに、「更科」という、きしめんやさんが
ある。カツどんチェーン店や、お洒落なケーキショップのならびにあって、新京極の通りのな
かでは、かなり地味な外観である。
ここにくるようになったのは5〜6年前か。それほど回数多いわけでもないし、店の人が覚え
てくれているというわけでもない。でも来てしまうのは、京都ではなかなか食べられないきし
めん(600円)が食べられるのと、店の雰囲気だろう。一歩はいると、下は石張りで、すこし
ひんやりした感じ。表通りの新京極のにぎやかさが、扉一枚でぴたっと止んで、町屋のなか
にいるようで、おちつく。かといって、入りにくい雰囲気でもない。
こんな地味なお店なのに、お客さんはつねに6〜7割りをキープしている。客層も親子連れ
や、若いカップル、おじさん、おばさんとさまざま。たぶん、みんながちゃがちゃした喧騒を逃
れて、入ってくるんだろう。高回転率を目指すようなチェーン店でもないから、ゆっくりできる。
私の母親の娘時代からあるというのだから、そうとう長い。うつりかわりの激しい新京極で、
これからもずっと営業を続けてくれるとうれしい。
- 2003/06/07(土) 「路面電車で君と行こう」
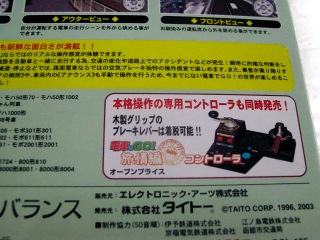
こどものころは、阪急電車の運転士になりたかった。西院から大阪梅田に向かう電車が、
地下線内から、外へ飛び出すとき、車内にぱぁーっと光りがあふれてくる瞬間が今でも好き
だ。通勤に一時期、JRを使っていたが、なんとなく陰気な感じのする車内がいやで、去年の
夏ごろから、阪急に変えた。会社から駅までJRより遠いのだが、その清潔で明るい雰囲気
の車内は、子供のころ受けた印象と少しも変わらない。今日も頑張ろう!という気になれる
のだ。
さて、昨日阪急電車ではないが、電車の運転をシミュレートできるゲームソフト、「電車でGO
旅情編」を買ってきた。いろいろシリーズがあって、新幹線とか、新快速とかもあるのだが、
今回は路面電車。伊予鉄道、江ノ島電鉄、函館市交通局、そしてご当地、京福電気鉄道の
4つの電車を楽しめる。
普通の電車と違って、なかなかにブレーキの操作が難しい。しかもキーボードでやるもの
だから、微妙な操作ができない。これはやはり上の写真にあるコントローラーが欲しくなる
というもの。
今日、合唱団の練習の行きがけに早速コントローラー(上の写真)を物色しにいった。
でも高いのだ。8700円もする。ゲーム本体より高い。でも欲しい。実物のデモもやって
いて、やはり専用だけあって雰囲気もでるし、運転しやすい。悩んだすえ、「給料日か
ボーナスで買おう」という消極的な結論に落ち着いたのだった。
運転台の真ん中に鉄道時計を置くとおぼしき"へこみ"があるのも見逃せないポイント。
このように、電車少年というものは、大人になってもあまり成長がないものです。
路面電車で君と、なんていっておきながら一人、男のロマンに酔ってしまうのでした。
そういえば、女性の運転士は日本で見たことがないなぁ。
- 2003/06/06(金) 「科学少年01くん」(by永野のりこ)
今日は、ある大手測定機器メーカー主催の技術フォーラムの日である。毎年、うちの
チームからも何人か出席する。このフォーラムに出席すると良いことが二つある。
ひとつは、フォーラム後にお食事会があること、もうひとつはお土産がもらえることである。
夕方、出席者のひとりA君がお土産を携えて、帰社したので、さっそく(勝手に)包装を解いて
みた。10x10x40cmくらいの大きな包装だ。なかから現れたのが、液体の詰まった円筒の
なかに、6つの小球体が浮かぶ不思議なオブジェ − 「ガリレオ温度計」だった。
くわしい原理は省くが、小球体それぞれに温度の札がとりつけられ、円筒のなかを浮かんだ
り、沈んだりすることで温度がわかる。これを見たA君は、「あちゃー今年はケチったなー。
こんなんもって帰ったら嫁はんにおこられるわ〜」と嘆いた。実は去年のお土産は当時話題
になった「電波時計」だったので、それと比べているのである。
元科学少年の私にしてみれば、全然狂わないただの時計よりも、こちらの方が数倍魅力的。
正確、高精度を至上とする測定機器メーカーの選んだお土産が、精密電子機器ではなく、
物理現象を応用した温度計であるとは、なんともおもしろく、ロマンチックだ。
情報系出身のA君にはそのあたりの心情は理解不能みたい。A君の奥さんが「こんなん
いらん」と言ったら、私がもらいうけることにしよう。
- 2003/06/05(木) 「日課」
会社の組合の事務所には、各種新聞と雑誌が置いてあり、昼食後は
そこで何か読むのが日課である。たいがい、週刊ダイヤモンドと
日経産業新聞を日替わりで読む。活字中毒症なのである。
実は、子供のころ、週刊ダイヤモンドと週刊宝石をライバル誌だと思っていた。
ちゃんと読むようになったのは会社に入ってからである。日経産業新聞の存在
には去年の夏ごろ気がついた。日経新聞よりも面白いのはなぜだろう。
ホテルなどに泊まると、「朝刊は何になさいますか」と聞かれることがある。
いつだか、「じゃあ日経産業新聞を。」というと、やはり扱ってなかった。
そういうマニアックな新聞を読むにはやはり身銭を切らねばならないのだ。
|
|