|
電波暗室 2004/07
- 2004/07/31(土)
待望のソファーが届く。おおー、やはりこの張り地で正解だった。イメージぴったり。ショールーム
に行って、相談に乗ってもらったのが良かった。良い機会なので、最近さぼっていた部屋の掃除
をする。ソファのだいたいの位置を決める。窓際、本棚のすぐ横。さっそくすわって本を読む。いつ
までも読んでいられる。本当に気持ちがいい。
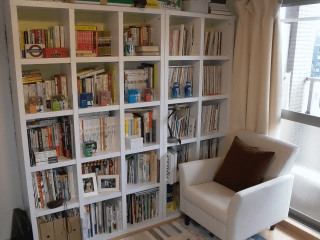

しかし、↑このダンボール、いったいどうしたものか。これより手前に入らなかったので、玄関で
梱包を解いて、なんとかソファは部屋にいれることができたのだ。この大きさになると解体も面倒
だ。しかし、解体しないことには通行ができない。一度箱に入って、出ないと一足ではまたげない
。。。箱に入って内側から蓋を閉めて、5分くらい考える。おぉーなんだか秘密基地みたいだゾ。
いっそこのまま置いておくか?
本日の査収物。
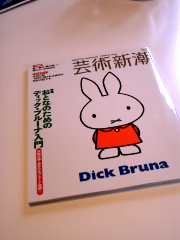
芸術新潮のバックナンバー2004/03号、ディック=ブルーナ特集。良い。
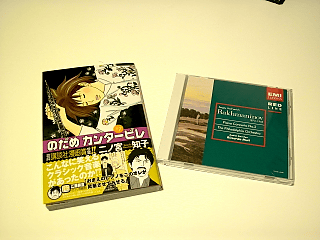
「のだめカンタービレ#7」&「ラフマニノフ、ピアノ協奏曲第2番」。すこぶる良い。
完全にのだめの影響受けている。わたしは普段クラシックは聞かないのに。
いまも、この文章を書きながら聞いている。今日もう三回目だ。
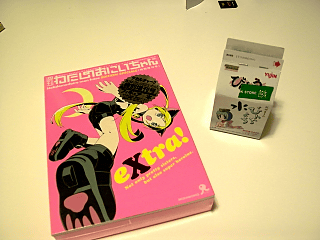
「週刊わたしのおにいちゃん、特別増刊号」&「びんちょうタン」。・・・すごく良い(?)
”デカルチャー!!”な一品。(意味不明)
- 2004/07/30(金)
BK夏休み中につき、金曜日だが練習なし。
夕飯でも食べようと、友人を誘う。「今日って、夜、大雨になるんちゃう?」。....そうだった、台風が
来ているのだった。私は、日常はその日の天気について、全く気にしないので、気象情報には大
変うといのだった。この時点で、雨だとか、風だとかそんなことは意識していなかった。
20時すぎ、会社を出るといやがおうにも、台風が来ていることを実感。しかし、雨はまったくふって
いないので、夕飯計画(Operation Dinner Out)にGOサインを出した。
あまり関係ないのだが、こういう「GOサイン」などはもともと軍事関係の言い回しだと思うが、帰宅
後に民主党の党大会のニュースを見ていると、ケリー候補が「大統領候補として着任いたしました
(敬礼)」と言っていたり、クリントン元大統領が「・・一兵卒として戦う・・・」、ヒラリー上院議員が「(
ケリー候補を)軍最高司令官(=大統領)にすべき」などなど、軍事にちなんだ、もしくは軍事そのも
のの用語を多用していたのが目に付いた。
アメリカの人たちが、普段こういう言い回しを日本人よりも多く使うとは考えにくいので、これはあき
らかに、民主党=国内政治というイメージではなくて、「軍事外交をやっていきます」というイメージ
を全面に出した「戦略」の一環なのだろうな...などと考える。(あまり深いことは考えてマセン)
話がそれてしまった。
店につく頃にも、風は強いものの、雨が降る気配がない。時折、ぽつっとくるものの、「雨の匂い」
がしない。これは大丈夫なんちゃうかなと思いながら食事をする。小芋のから揚げ、鴨ロースのさっ
ぱり風味、鮎の南蛮風味、みょうがの天ぷら、とりのから揚げ、そして、茄子の忘れ煮。ああ、茄子
の忘れ煮。こんなにおいしいものがあるなんて。
実家生活が長かったせいか、こうやって外で、友人と話をしながら、酒を飲み交わしながら、ゆっくり
料理を楽しむということがなかった。自分の生活も変わったな、と感じる。何より変わったのは、アル
コール類は基本的にダメなのだが、「酒の味の違いを感じてみたい」と思うようになったことだと思う。
少量口に含む程度でも、ひとつひとつ味がまったく違うことに気づかされて、「酒→匂い→頭痛」とい
う図式しか頭になかったことが嘘のようだ。酒ががぶがぶ飲めるようになったとか、飲めるようになり
たいというのではなくて、食事の一環として、「楽しめる」ようになれたら...と思うのだ。
今日は、酒によってあう料理、あわない料理がそれぞれ違うんだということに気づいて、新鮮な気持
ちだった。無理に飲ませたりせず、温かく見守ってくれる(生態を観察している...?)友人に、感謝する。
うどんで〆めて店を出ると、やはり雨はなく、風だけだった。
ふわふわと、ほっこりほこほこした気分で帰途についた。
- 2004/07/29(木)
最近、どうも私はやせたようなのだ。
健康管理室の言いつけにより、食事の制限を去年の秋くらいから課せられていたのだが、今年の
春の時点では、ぜんぜん変化がなかったのだった。ところが最近、どうもズボンがゆるくて落ちてく
るので、ベルトをきつめにしめることとが多くなっていた。で、この前体重を量ったら、もっとも増えて
いた時期よりも4〜5kg落ちていたのだった。
夏になって、特に食欲がなくなったというわけではなく、三度三度食べているのだが、ご飯を大から
小に変えて、もう半年くらいになり、会社帰りの間食も80%なくなっていた。20%はBKのまえとか
のはらごしらえ。はじめのころは、ごはん小だとすぐにおなかがすいて、夜までもたなかったが、
最近は、ぜんぜん平気になっている。
あと、朝なのだが、ちゃんと食べないとマズイ、と思ってひとりぐらしの初期の頃は、次の日用にソー
セージを買ってきたり、出しまきを買ってきたりしてたのだが、最近ではめんどくさくなってきて、お茶
一杯、ごはん一杯、ときどきふりかけをつける程度になっている。少々、食卓に色気がないのだが、
たまに旅行でホテルの朝ごはんなどを食べると、すごくうれしくなるので、このギャップはあればある
ほどいいのかもしれない。
無理に痩せようとは思っていなかったが、心臓への負担とかを考えるとやせた方がいいとはいわれ
ていたので、ちょっとだけ気にかけていた。時間をかければいつのまにかやせられるものだなぁと感
慨しきり。ただ、痩せただけでは、おなかはひっこんでも腹筋がつくわけではないから、こちらはちゃ
んと鍛えないといけないだろう。「息が続かない」という弱点を克服しないと、私の場合歌はうまくな
らないような気がするからだ。
四回生のとき、四連前の3ヶ月、必死で腹筋をしていたのが思いだされる。息が続くと、フレージング
や和声を気にする余裕がでてきて、とても歌いやすかった。あの時は、珍しくパーリーにほめられた。
音に対する感覚は今のほうがはるかに研ぎ澄まされている。だから、もっとうまくなってみたいと思っ
ている。
あぁ、今日はなんだか前向きだ。ナチュラルハイ?
あしたのあさがこわいデス。
- 2004/07/28(水)
会社の研修で、「適性試験」を受ける。二時間ぶっ通しの試験である。語彙力、読解力、論理力、
計算力に心理テストと、てんこ盛り。筆算を使った掛け算や、割り算などの計算をしたのは、いつ
以来だろう。意外と、子供ころに仕込まれたものは忘れていないもので、少し安心したが。
私は頭が切れるほうではないので、こういうものは基本的に苦手である。一度、試験中に集中力
が切れる瞬間を、自分自身客観的に見てしまったくらいだ。すぐに頭のスイッチを切り替えられたの
は、合唱の経験がなせる技?だろうか。わたしはスポーツはやっておらず、そういう切り替え方法
を習得した覚えはないから。音楽というものは、とどまらず流れるものなので、一箇所間違えたから
といって、そこで終わりにならないし、してはいけないのだ。(そして、聞いているひとにそれをさとら
せてはいけないものだ)
これから約4ヶ月、少々、いやかなり厳しい状態に置かれることになってしまった。秋〜冬にかけて
の合唱生活を考えると、体力的にも精神的も大丈夫かなぁというのが正直なところ。生きていくため
には、働かないといけないけれども、歌をうたわない生活は、それは生活なんだろうか。ただはたら
いて、生きて、何が残るんだろうか?などと考え始めると、「根性」出して、歌も仕事もやらないとい
けないと思うのだ。
昨日、「プロジェクトX」の総集編みたいなのを見てしまった。「プロジェクトX」のリーダー達は、死ぬ
ほど働いて、成果をだして、世の中に貢献した。そして、そこに人生の後悔はなかったとは思う。しか
し、これは働かせる側から見れば、非常に都合のいい教材であろうなぁと思う。死ぬほど働かない
と、感動できないんだ!と刷り込ませるための。死ぬほど働かせている人たちを、当時冷遇していた
としても、当人が感動していれば、すべてチャラみたいなところもある。
変にうがったものの見方をしてしまうのは、たぶん疲れているからだろうな。
おととい買ってきた、宮部みゆきの『理由』でも読んで、こころを鎮めよう。
- 2004/07/27(火)
作家の中島らも氏の訃報をwebで知る。なんだか実感がわかない。これは、ついこのあいだ、
亡くなった、漫画家の鈴木義司氏のときもそうだった。どちらも、ネットではじめて知ったのだ。
新聞に載っている訃報を見るとき、それはもう固まってしまって、覆せない、石に刻まれた言葉
のように冷徹な情報であることを、私に限らず誰もが実感していて、一瞬の躊躇はあるものの、
それを素直に受け入れざるを得ないということがあると思う。
それに対して、同じ文字情報であるのに、webのニュースの場合、同じソースの情報であっても、
なぜだか、にわかには受け入れがたいものを感じる。ネットの場合、第一報ののち、刻々と追加
の情報が入り、常に更新されてゆくという流動性がある。固まらないのだ。常に流れている時間
とともにやってきて、すぎていく。その分、ひとつひとつの情報の価値が相対的に低く感じられる。
現実感にとぼしくなる。そして、そこには、「このニュースは次の更新でひょっとしたら覆されるの
ではないか?」という期待が入り込む「隙」がある。
ネットがいい悪いの問題ではなく、読み手に想起させるものが、根本的に違うのだろうと思う。
紙と、ネットでは。
中島らも氏の小説を私は読んだことはないが、「明るい悩み相談室」の単行本は買って読んでい
た。おそろしく、まじめで理知的に見える文章なのに、おそろしくばかばかしい内容になっている
のが不思議でたまらなかった。掲載紙であった朝日新聞は大嫌いだけれども、そのなかにあった
からこそあんな輝きをはなっていたような気がする。らも氏に、そういうつもりがなかったとしても。
世の中には、真面目で、正直なことも必要だけれども、それと同じくらい、不真面目で、へそ曲がり
で、ばかばかしいことがないとバランスが取れないのだと思う。そういうものを生み出している人た
ちのひとりであった、らも氏がなくなったことを残念に思う....ってなんだかくそ真面目だ。
心底愛読しているファンのひとには、もっともっと痛烈な思いがあるのだろうな。
わたしにとって、らも氏はそういう対象ではなかったけれども、悲しむ気持ちは理解できると思う。
わたしにも大好きな作家さんがいるから。本が好きな人間やから。
その思いを、聞いてみたいと思う。
- 2004/07/26(月)
プールにでも行きたいなぁ。
昔、阪急長岡天神からバスで5分くらいのところに、「プラザ・ブルーレイク」という屋外型のレジ
ャープールがあったのだ。わたしが、中学生くらいのころまでは。市街地のどまんなかにあって、
交通の利便がよいので、子供のころ、ほんとによく親に連れて貰った。あのころ、長岡天神という
駅は、夏の聖地みたいに、わたしの目にはうつっていたと思う。流れるプールにつかっていると、
スライダーのすぐそばを阪急電車が走るのが見えた。
そのころから、ここはもうすぐつぶれるみたいな噂が、子供の耳にも入ってきていたのだが、
いまから15〜6年前につぶれたようだ。跡地はしばらくは、水のないプールという悲しい光景
だった。それからしばらくして、近くの病院の管理するガーデンみたいなのになったが、阪急電車
で大阪に向かうときに見えるその光景には、いまでも違和感を感じる。
- 2004/07/25(日)
宝塚フレンドシップコンサート当日。
不足はあったと思うけれども、演奏会でやった同じ曲については、演奏会よりも進化したものが
できたように思うので、それは良かったかなと思う。リハーサルのとき、一部ソロをやったのだ
が、演奏会のときよりもうまくできた。ホールとの相性がよかったのかもしれない。しかし、本番
では、別のひと。指揮者に今日だけもう一回やらせてくださいといえばよかったかも。。。
でも、今日の終わり、Vineの打ち上げ(なぜか参加させてもらった)帰り、友人に「リハのソロ、曲
の感じとあっていて良かったよ。」と言ってもらえた。もうそれだけで、十分すぎるくらい満足で、
うれしかった。
宝塚のベガ・ホールは、客席数が少ないので、演奏会出演団体は、リハーサルでしかほかの団体の
演奏を聴くことができなかった。今日ほど、本番での演奏が聴けないことがくやしかったことは
ない。それは、リハーサルで、Ensamble Vineの演奏を聞いてしまったから。身びいきというのを
さっぴいても、やはりVineの演奏はほかの団体と違うのだ。
技術的にうまいとか、発声がいいとか、アンサンブルがいいとかいう問題じゃなくて、あきらかに
そこから感じられる音楽が違う。ほんとうに優しくて、心穏やかな気持ちにさせてくれる。リハー
サルを聞いていた私は、本当に涙が出そうだった。ちょっと出てたかもしれない。一度は、NCの集合
のために、演奏途中で席をたったのだが、集合後、しばらくインターバルがあるとわかると、ホール
に文字通りかけもどり、最後尾でドアを背にして、最後の曲を聞いた。
全身をあたたかいものがつきぬけていくのを感じて、震えた。
あの瞬間、私は確かに「幸せ」だった。
- 2004/07/24(土)
宝塚フレンドシップコンサート、前日。宝塚ベガ・ホールにて、ステージリハーサル。
このホールは、小さい音でも本当によく拾ってくれるので歌いやすい。気持ちいい。
リハーサルは、練習不足、集中力不足。
別の場所にうつり、練習継続。
練習終了後、Ensamble Vineのメンバーと合流。その場で、双方のメンバー同士の結婚の報告。
「みんな、後に続くように。」というコメントをI東さんが発する。こういうことを言うのは珍
しい。I東さんも、この二人の結婚はよほどうれしいのだろうなぁ。
前夜祭(交流会)出席。実は、前夜、帰宅後からNCの第10回演奏会のCDを作成していたため
猛烈な寝不足だった。帰ろうかなとも思っていたのだが、明日はNCでは打ち上げはできない
だろうし、そうすると明日から当分会えない遠隔地メンバーもいるので、交流会のためという
よりも、みんなで飲むという目的で参加することにした。
とはいうものの、NCメンバーばかりで固まっているはずもなく。けっこうばらばらに散ってしまう。
交流会という名目なんだが、どうにも面識のないひととは話しづらい。しかもまわりは「合唱人」
っぽいひとたちばっかりだ!誰と話すわけでもなく、ひたすらお茶を飲み、食べ物を食べ、ひまな
時間は暗譜に努める。われながら、ばかだなぁとは思うけれども、ああいう雰囲気は苦手だ。
林号で京都まで送ってもらう。なんと交流会会場のある逆瀬川から京都までの所要時間は、いつもの
大阪の本町の練習場からの時間よりも、短いのだった。これにはちょっと驚き。高速道路のマジック
なんだろう。車乗らないので、ルートは全然わからなかった...。
- 2004/07/23(金)
新潟県新井での仕事に、やりのこしが発覚。一瞬「いまからまたきてください」とかいわれたら
どうしようという恐怖が頭をかけめぐる。ネットワークを介して、向こうのマシンにアクセスし
て直接プログラムを変更することで、なんとかなった。この仕事、段取りを考えていたときには
予想もしなかったことが頻発。まさか帰ってきてからも起きるとは。出張の疲れが取れぬまま、
さらに憔悴するのだった。
BK、前期最後の練習。これから8月下旬までおやすみ。練習場に扇風機以外の冷房がないため。
練習後の納涼会には20人近くが参加。最終メンバーが帰途に着いたのは午前1時近くで、いつ
もの宴会よりもロングだった(ノーカット特別編)。こういう宴会だと、普段来ないひととも
話しができるし、ああこういう人だったんだーという以外な面をしることができる。
この日、印象的な話題だったのは、「ありんこ」と「M川さんの自転車とその走行」である。
「ありんこ」というのは、腕とか足の毛が生えているところに、手をあててくるくるとさすって
やるとできる小さい毛玉のことをいうらしい。私が知らないというと、「ぱんきょーですよ!」
と何人かに言われてしまった。今日、参加していたメンバーのなかには「ありんこ」できそう
な人はいないらしい。こんな話題なのに、大盛り上がりしてたのが不思議。みんな若いよ!
「M川さんの自転車とその走行」は、そのまんまで、市内でM川さんの走りを目撃した人たちに
よるドキュメントで話がすすんだ。そのあまりの走行の激しさを表現しようとするあまり、なつ。
がビールグラスを床に落として割ってしまうというハプニングも。幸いけがもなく。でも、スカー
トにダメージをうけてしまった。(【豆知識】なつ。のスカート姿は、大変貴重なものとして知ら
れている)
解散後、毎度のことながら、不本意ながら、K岡と帰る。家の方向が同じなんだから仕方がない。
本人には悪いが、このときいつも、「ちっ!」とか思う。(本人はいたっていいやつ。)
もし、近い将来、katoponさんが京都に引っ越すなんてことになった場合は、出町とか、北方面に
誘導して、帰宅ルートが重ならないようにしよう、なんちて。(笑)
- 2004/07/22(木)
新潟県新井出張、第三日。
報告書を前夜のうちにしあげておいたので、朝一で帰る計画を練るも早々に頓挫。
交渉のすえ、昼前に仕事終了。信越線の駅についたのは電車がくる3分前だった。
(直江津からの連絡が悪いので、下手をすると帰着が2〜3時間ずれる)
京都着17:06。定時を回っていたので、連絡して直帰させてもらう。
帰宅すると電気代の請求が来ていた。
「239kWh、5113円」。がぼーん!
- 2004/07/21(水)
新潟県新井出張、第二日。
食欲や睡眠欲がなくなってくる。携帯の電池が切れかけているため、温存する。
この"つながり"を絶やすと、倒れてしまう。
(いかに助けられているかということを、遠い地で感じた。)
- 2004/07/20(火)
新潟県新井出張、第一日。
着くなりカウンターパンチをくらい、脳震盪気味。
22:00まで残業。ホテル予約するの忘れてた。。。
- 2004/07/19(月)
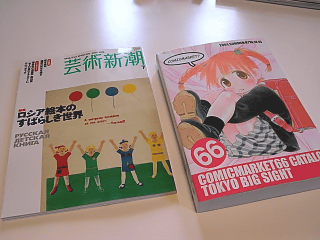
コミックマーケット66カタログ、芸術新潮7月号(特集「ロシア絵本のすばらしき世界」)の2冊を査収。
コミケカタログには、予約していないのに、予約特典がついていた。ここではとても見せられない...。
(カタログの表紙も、ちょっとアレだ。)
- 2004/07/18(日)
お昼すぎ、私は豊橋にいた。豊橋市公会堂を見学にいったのである。こっち方面にはなかなか
別件の用事などなく、この建物を見に行くためのみ。京都からだと約3時間くらいでつく。
 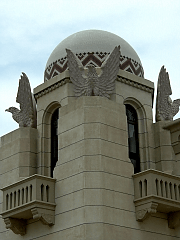
2つの塔屋に挟まれた大階段が特長的。 塔屋の上に鷲。
建物の屋上に出ることができず、階段室のドームと鷲を真近にとらえられなかったのが残念。
大ホールでは、市民出演による懐メロ歌謡ショーが催されていて、公会堂らしい使われ方をい
まも続けている建物。(昭和6年建築)
さて、これで帰ったのでは、少々物足りない。豊橋には路面電車があるので、今度はそっち方面
を攻めることにする。
 
見ていた限りでは5〜6種類以上の外観がある。 女性の運転士さんもいた。
さて、次の目的地、名古屋へ戻る。移動には名鉄特急を利用。JRよりも快適で安い。
(200円くらい割安)
以下に名古屋で移動の履歴(GPSで測定)を示してみよう。
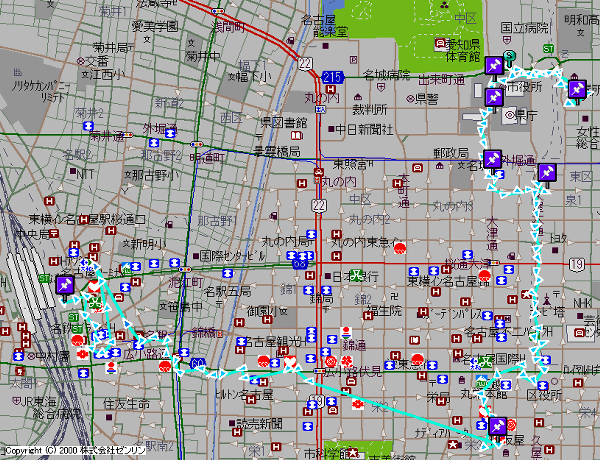
右上に位置する名古屋市市政資料館から出発し、名古屋市役所〜愛知県庁〜大津橋近くの洋館
〜ソファー専門店のショールームを経て、松坂屋で夕食〜名古屋駅までという行程。約8kmを歩く。
今回の名古屋入りの目的は二つ。ソファー専門店へ行くこと。名古屋市市政資料館へ行くこと。
7/13の生地サンプルは、ソファーのものだったのだ。生地サンプルでは全体のイメージがつかみ
にくいので、ならばと思い出かけたのである。もちろん座りごごちも気になっていた。

考えているのはこのタイプのひとり用。読書するのに使う。
インテリア・家具ショップなどと違い、ソファー製作工房の直接製作・販売なので、安い。お店の
ひとは、普段工房で働いているひとなので、対応は朴訥だけれども丁寧で、親しみやすい。この
手の商品は、ほかの工業製品と同じでアジア勢の低価格攻勢におされ気味らしい。しかし、品質
面からすると、国内産はアジア製の数段うえを行く。わたしも実際、ロ○トなどで、お洒落だけど安
いそれらの製品にふれてみたが、どれも座ってみると、すぐにいまいちとわかった。
さて、ここのソファーはどうか...と思って座ると、あぁぁこれ、これですよ。ホテルの客室で窓辺にお
かれている読書椅子の感覚そのまま。気持ちいい。やわらかすぎず、固すぎず。理想のホールデ
ィング。ちゃんと考えて作ってるなぁというのが伝わってくるソファー。もう迷うことなく。生地を用意
してもらって、比較検討。30分くらいで購入を決めていた。これから2週間かけて製作される。
これで夏期休暇は、ソファーで読書三昧だー!。
最近、わたしはモノを買いすぎとお思いですか?確かにそうかも。しかし、高いものは買っていない
のだ。高そうなものは買っているが、どれもちゃんと吟味して、市価に比べて安く、でも長く使えて、
しっかりしたものを選んでいるつもり。
さてさて、順番が前後するのだが、今日一番感動したのは、名古屋市政資料館、旧名古屋控訴院
である。まずは写真を。これはもう、語るべき言葉を持たない。
 
 
長年、近代建築を追いかけてきたけれど、こんなすごいものが、これほどいい状態で残っている
ものは、例を見たことがない。いままでまったく見逃してきたことが悔やまれる。もちろん、保存に
あたり、手が入っているのだが、その跡が極力見えないようになっている点は、この建物のソフト
的な部分(保存を手がけ、常設展示を手がけたひとたち)のすばらしさであると思う。
名古屋に行くことがあったら、是非見て、感じていただきたい。
*******
帰京するまえに、夕食を食べるため、松坂屋へ赴く。あの「ひつまぶし」を食べるためだ。ここには
本家本元の「あつた蓬莱軒」が入っているのは調査済みである。夕方6時半。歩きどおしで、疲れ
きっている....。あれ?なんだこの人たち。食堂フロアの休憩所と思しきところの腰掛けられる場所
という場所にすべて人が座っている。それもよく見ると一筆書き。も、もしや?
そう、ほどなくして、案内がかりのひとが、「前にお詰め合わせください」と声をかけると、それらの
ひとが全員動き出したのだ。つまり、ここにいる全員が蓬莱軒待ち。ざっと70〜80人。一時間半
待ちといわれる。待ち時間を聞いただけで諦めるひとも多かったが、わたしはコミケで鍛えた不屈
の忍耐力で持久戦に突入。約45分に勝利を収めた。というのも、家族づれが多いなか、ひとりで
待っていたので、席と席の穴埋め的に救済されたものらしい。20人くらいをすっ飛ばして案内され
た。あのとき、隣の人たちに、なにか声でもかけるべきだったのだろうが、さすがにそんな余裕は
なかった。
出てきたひつまぶしは、それはそれはおいしゅうございました。しかし、そのとき「ひつまぶし」本来の
うまさを私が堪能していたかどうかは、かなり疑わしい。そのときの私は、もう「おなかにはいれば」
なんでもOK状態にまで腹がすいており、空腹調味料が効きすぎていたといえるからだ。今度、食
べに行くときは、案内されるときにちょうどいい加減のすき具合になるよう、考えて並ばねばなるま
い。
そういうわけで、今回の豊橋・名古屋紀行は終了。帰りは、さすがに疲れていたので、大枚(?)
はたいて、新幹線に乗ってしまった。。。
- 2004/07/17(土)
今週はNC練習あり。冷房のない部屋なので、シャツが汗だく。乾かない冷えたシャツのせいで、
おなかの調子が変に。
気分転換に明日はどこかに日帰りで旅行に行くことにする。尾道あたりに海を見に行くか、近場で
建築写真を撮るかなど、プランを行く通りか立てる。プランをたてながらも、急に「しんどいしやめと
こ」とか、「映画でも見に行けばええ」とかいう考えがうかんできたりする。あきらかに仕事のしすぎ
による「後ろ向き思考」の発症である。これを打破するには、とにかく無理やりにでもでかけるしか
ない。朝、はやめに目覚ましをセットし、早めに就寝する。
- 2004/07/16(金)
BKのフランス語歌唱指導のある日。3連休前の定時退社日なのだが、仕事が相当せっぱつまって
いるので、関係各位に定時に退社されると非常に困るというジレンマな状況。頭のパンパン度も限
界に近い。こんなことを続けているとまた静養するはめになる。肉体よりも、頭に直接ダメージがくる
のがわかる。根性を発動させて仕事を終わらせる。連休明けは新潟に出張。新潟は豪雨のため、
あちこちで被害がでており、電車も運休がでている。果たして、出張できるのか。
練習後、飯る人間は6人。最小に近い。5人が自転車で、徒歩は私のみ。宴会場から、とぼとぼひと
りで帰る。
- 2004/07/15(木)
仕事が....きつきつ。わたしはシングルタスクの人間なので、あまり同時進行で仕事をすると頭が
パンクするのだった。(夜、寝ようとすると、勝手に仕事の段取りが思考されてしまうという困った
現象が起きる。←マジで寝付けない)
23時すぎに四条烏丸に帰着。人の多さにうんざりしていたところ、スピーカーから「歩行者は歩道
にもどってくださーい」という五条警察の婦警さんの声が繰り返し聞えた。歩行者天国が解除される
らしい。歩行者天国のことなどどうでもいいのだが、この婦警さんの声が実に良かった。スピーカー
映えする、きれいでキレがあるけど、やさしい良い声。あまり頭が回らないながらも、ぼーっと聞きほ
れてしまった。
あまりのひとの多さに、数時間前に近くを用事通った友人がメールをくれて、帰宅できるのかどうか
を心配してくれたのだが、遅い時間帯だったため店じまいする夜店がではじめ、そのせいか人通り
の少ない新町通りを南下して帰宅できた。
- 2004/07/14(水)
宵宵々山だから、そんなに混んでないだろうと思ったら、帰りの阪急京都線は人がいっぱい
だった。人が群れて、声高で騒々しいのは(誰でもそうだと思うが)、あまり好きではない。
駅を出て、50m先にある弁当屋に行こうとしたら、とにかく前に進めない。屋台に人が群がって
いる。彼らは、祗園祭を見に来たのではなくて、単に祭りの雰囲気を味わいにきた、もしくは仲間と
公然とたむろってわいわい騒ぐためにやってきたのであって、鉾そのものや、町内会やお店秘蔵の
物品・建物を見に来たわけではないのだろうな。屋台なんぞなければいいのに。
弁当を買い、いま来た方向に戻る。東西南には人が多くて進めない。わたしの住まいは、南...。
思ったより遠回りして、帰宅。明日、明後日は、この弁当屋にたどりつくのは不可能かもしれない。
祭りなのに、なんだか不機嫌である。
*******
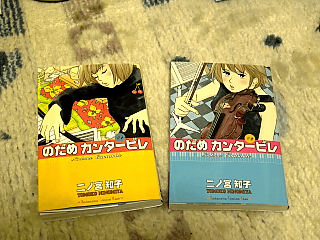
気がつくと増殖している「のだめ」。漫画そのものもいいけれど、装丁も好きだ。
- 2004/07/13(火)
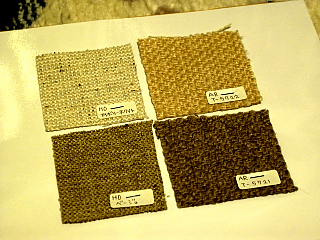
生地のサンプルが届く。まだ実現するかどうかわからないプロジェクトの検討のために
取り寄せたのだった。
仕事で疲れているので、あまり難しいことが考えられない。とにかくむにむにと生地を
さわって感触を確かめたり、すりすりとはだにつけて、風合をみる。
- 2004/07/12(月)
朝起きると、そんなに暑くない。ヤタ!昨日の工夫が功をそうした?と思って窓を開けると、
単に曇っていただけだった。涼しいのは喜ぶべきではなかったか...。なんだこの残念感は。
会社帰り、なんとなくSFちっくな設定の漫画が読みたいなァと思い、本屋に寄る。しかし、
店を出るとき手にしていたのは「のだめカンタービレ」だった。音楽がテーマの漫画というの
でなんとなく手をだすのが億劫だったのだが、「ハチミツとクローバー」と同じくらい、この店
は「のだめ」をプッシュしていたので、店を信用して買ってみた。
思えば、この店のお薦めで買った本は少なくない。小説の「マルドゥック・スクランブル」然り、
「成恵の世界」、「ハチミツとクローバー」、「鋼の錬金術師」etc...どれも今のようにメジャーに
なる前から(ここでいうメジャーとは一般の方の尺度とは異なるので注意!)、いち早く注目し
応援していたように思う。
自分にとって本や漫画というのは、自分の基準で選んで、買う場合が多かったのだけれども、
会社帰りにフラッと立ち寄れて、私のような人間にピシッとツボにはまった本を薦めてくれる
この本屋と本格的に出合ってから、読書の幅が広がったような気がする。漫画中心だが。
他人のアドバイスというのはなんにおいても必要なものなのだなぁと、いまさらながらに考える。
********
菊水鉾にはすでに提灯の灯りがともり、鉾の上での祗園囃子の練習が始まっていた。もうあと
幾日もしないうちに、宵山になり、巡行になる。宵山で人がごったがえすまえあたりに、夜静かに
鉾を見て回りたいなと思う。(宵山の日は新潟の新井に出張になりそうな状態だからというのも
ある。)
- 2004/07/11(日)
昨日から、今日にかけて、祇園祭の鉾建てが始まる。一応、名目上の梅雨もあけて、
夏だな〜という雰囲気である。
これから夏本番となると、つらいのが朝方の暑さである。私の部屋は南東にあるため、
なんの対策もないわけではなく、カーテンは二重で、ひとつは断熱性能のあるものを
使っている。朝カーテンをあけると、窓を開けているわけでもないのに、すさまじい熱波が
押し寄せてくる。それだけ、カーテンでしのいでいたのだ。しかし、ここしばらくの暑さは
想像を超えていた。
そこで、今日はもうひとつの防御壁をもうけることにした。「すだれ」の投入である。窓の
外にすだれを設置し、窓にあたる太陽を緩和できれば、もう1〜2度部屋の温度を下げる
ことができるかもしれない。
と思って、町中にでかけたのだが、すだれがどこに売っていない。まず、ロフトにいったの
だが、屋内しか扱っていないということ。で、荒物屋さんを探すしかないか、と思って、自転
車で東西南北いったりきたりしたのだが、荒物屋さん自体が見つからない。自転車の後輪
の空気がほとんどなくなっていて、自転車の移動がおっくうになりはじめてきたので、1時間
ほどで断念した。いきあたりばったりで買い物ができる環境がなくなりつつあるのだろうか?
仕方がないので、ダンボールとバスタオルで二重の防御壁をベランダに築いた。これで対応
できればいいのだが、なんだか味気ないというよりも、見た目的にあれだ。みているだけで、
涼しげな雰囲気をかもし出す「すだれ」はやはり偉大なものだと改めて思った。
- 2004/07/10(土)
 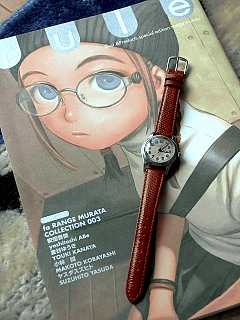
ボーナスでモノを買い物第2弾。アンティークの時計を買う。
OYSTER WATCH CO.のJUNIOR SPORTという時計。手巻き。1930年代製。
この時計の最大の特長は、OYSTERケースという防水機構である。削りだしのケースとねじ込み
式の裏蓋とリューズは、時計内部の気密を完全に保ち、製造から70年を経た現在もその性能は
健在である(といっても日常防水)。アンティークの時計は水・汗に弱いものだが、このケースに
限っては、夏場であっても全然問題がない。(時計の状態による)
むろん、選んだのはそれだけが理由ではなくて、その上品な盤面のデザインと、アンティーク特有
の飛び出したまるみのあるプラスチック風防、シンプルな円で構成されたケースのデザインなどが
あわさったときの、美しさ、というよりも愛らしさに魅かれたからだと思う。この時代の、Oyster社の
時計は、機械の信頼性もさることながら、そのデザインの良さがあって、すこし前から、一本欲しい
なと思っていたのだ。
さて、時計に詳しいかたはお分かりだと思うが、Oyster社とは後のR○○○X社なのだが、現在の
この会社にはOysterケースこそ受け継がれているが、品のよい、愛らしいデザインというものは、
すでになくなっていて、一部のお金持ち向けの俗っぽい時計ばかり作る会社に成り下がってしま
った。なんでもかんでも、「古き良き」ではなく、わたしは現行の機械式腕時計も好きだが、唯一、
この会社のものだけは、アンティークが良いと思う。
********
時計を買ってなんとなくうきうきした余勢をかって、NCの練習にでかける。本町の練習場(学校の
教室を借りている)につき、受付で名前をつげると、すこし怪訝な顔をされ、「きょうはNCさんは、
とられてませんよ」と返答された。そう、今日は練習休みなのだった。以前買った手帳がちっとも
いかされていない!
途方にくれた私。このままとんぼがえりするのもアホらしいが、すでに夕刻の大阪、それも本町
(ビジネス街)で、どこか遊べるような場所など、見当もつかない。で、なんとなく指揮者のI東さん
に、「間違えました」などとメールを打ったところ、「桜ノ宮アートよどこん」という名詞だけで構成
された返信があった。ああ、そういえばメンバーのひとから、客演指揮のC原先生の練習がある
ようなことは聞いていたが、土曜日だったのか。
ということで、行き場のない私は、ふらふらと本町から桜ノ宮に移動。実はけっこうめんどくさい
ルートだったりする。練習場にお邪魔したところ、そこには、ギラギラ照りつける太陽の音楽が
充満していた。そう、いまYKで練習していのはスペインの曲なのだった。楽譜をお借りし、後ろ
のほうで、正座して見学。ときどきこっそり声をだしてみたり。
スペイン語の曲というのは、どこか浪花節的なところがあり、情趣に訴えかけてくる旋律が多い。
そして、常に太陽が照り付けている感じがする。暑い、確かに暑いのだけれど、生命力がみなぎ
った結果の暑さであって、ひとを弱らせるものではなく。たとえるなら、夏に辛いカレーを食べて、
はふはふいってるようなものか。あんまりたとえになっていない気もするが、とにかくそんな感じ
だ。
休憩時間にBK,NC掛け持ちメンバーから「ご入団?」などといわれるが、まったくその気はなく
て、事故であることを強調する。YKが作り出す音楽は、自分としては内側からではなく外側から
客観的に見て、聞いて、楽しみたい。にしても、C原先生練習とはいえ、その音楽を内側からこっ
そりのぞかせてもらったことは、楽しい経験だった。2ヶ月後の本番が楽しみになってきた。
(問題点もいろいろと気づいてしまったのだけれど...。)
I東さんが、ちゃんとベースを歌っていたのも感心した。(和音をきめるときだけ。)
帰りは、林号で京都まで送ってもらったのだが、全然違和感はなく。いつもなら土曜はNC練習
で、その帰りはやはり送ってもらっているので、当然か。メンバーも8割はBK,NC組だったのだ。
- 2004/07/09(金)
昨日の後遺症で、気分・体調ともにすぐれず、午後にやっとのことで出社。日差しのもっともきつい
午後一に出社するなど、すすんでもう一度体調をくずしにいくようなものだったが、しかたない。
夕方の定例会議の開始が遅れ、BKの練習参加が不可能になる。それでも宴会にでれば、気分
も晴れるか?と思い、少々からだがきついのをおして、いきつけの焼き鳥やに向かう。入って、定位
置の奥のテーブルを見やると、知った顔がいない。真近で名前を呼ばれるので、見ると手前の6人
がけ席で細々と宴会をやっているのだった。しかも全員野郎だ。
「僕やったら即刻帰るな」とは、後日のI東氏の弁。(まぁ、普通そう思う)
なんだかんだで、結局12時手前まで宴会をしていたのだが、どうも最近、宴会の出席者が減少傾
向にあるような気がする。これはBKメンバーの気質によるところが大きいと思う。BKの皆は基本
的におとなしい人が多く、自律的にメンバーと交流を深めようという気持ちが淡白だ。(かつてはわた
しもそうだった。)いまでこそ定番の宴会も、結成1年くらいは一度もなかったくらいなのだ。
それが、定番化するにいたった原因は、一部の求心力というか、「手をあげさせる人たち」の出現に
あると考えられる。手をあげさせる人というのは、「今日、飯るひと〜」と第一声をあげて、場を宴会進
行に移行させるひとのことだ。いわば、彼らという磁石があり、いいかたが悪いがそれに引き寄せら
れるクリップや、ホチキスの芯が、BKメンバーの大半なのである。(誤解のないようにいうと、あくま
で宴会における主体的行動性のあるなしのことを指している。)
そして、磁石に吸い付けられた結果、それぞれが弱いながらも磁化されることで、まわりのメンバー
たちとの結びつきが生まれたといえる。過去に、何人かこれら「マグネタイザー」(そんな言葉ないと
思う)が出現して来たが、2004年度はそれらのひとびとが、同時的に練習参加率が下がってしまっ
たように思う。
そういうわけもあって、最近は私などが「飯行くひと〜」と声をあげるような機会も増えた。だが、先達
にくらべると、その技量はまだまだなのだった。なんとかコーディネートしようと、場を進行させている
と、「山Dさん今日は、はりきってますね」などと言われる始末で、真の推進者はそんなことを気取られ
てはいけないのだ。
- 2004/07/08(木)
仕事中。熱中症。帰宅。寝る。
- 2004/07/07(水)
子どものころ、短冊に願い事を書いて笹につるしていたのものだが、牽牛と織女の物語の舞台と
なる天の川をこの目でみたことはなかった。
天の川をまともに見たのは、高校2年のときだった。縄文杉を見るために屋久島に向かう途中の
瀬戸内航路。それまでの人生で、あれだけ圧倒的で、美しくて、目に焼きついて離れない光景とい
うものを見たことがなかった。衝撃だった。「本当に川やん!」と心のなかで突っ込んでいた。七夕
の伝説が生まれるわけわけやで、と思ったかもしれない。
空気の澄んだ地方にいるひとにとっては当たり前の光景も、京都の街中の一少年にとっては大した
威力をもっていた。それからというもの、私はあの光景を見たい一心で、旅行をするときに船に乗る
ようになった。船酔いするにもかかわらず。
ところが、一度は同じ瀬戸内航路、つぎは敦賀〜小樽、そして大阪〜足摺岬、仙台〜名古屋...。
いずれも雨、もしくは曇り。足摺岬のときは台風が近づいていたか。わたしはどうも雨のち晴れ男
らしく、旅行初日に雨に見舞われる傾向があるのだった。
だから、あの時以来、天の川をみたことがない。
*******
近年、七夕の日はほとんど雨だ。だって新暦の7月7日といえば、梅雨のまっただなかだ。だが、
今年は晴れている。なにか、願いごとを書いてみたくなった。どういうわけか、部屋に短冊が一枚
あった(電気屋さんのフェアーでもらった)ので、ボールペンでぐりぐり書く。こよりをつくるまえに、
目の前に輪ゴムを見つけたので、穴にとおして、ベランダにつるす。
明日の朝、風に吹かれて飛んでいったりしてなければいいが。
- 2004/07/06(火)
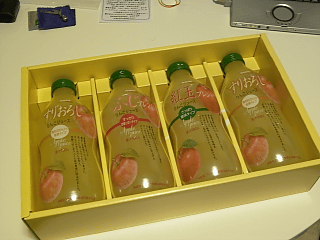
本日も何やら荷物到着。あけてみると、津軽完熟りんごジュースだった。差出人は中高時代の友人。
お中元なのだった。ちなみに友人は京都在住。京都在住といっても、会うのは正月前後の同窓会か
NCの演奏会に聞きにきてくれたときくらいか。奴は中高時代のわたしの百人一首の師匠であり、
鉄道趣味の師匠でもあり、駄洒落判定員でもあった。駄洒落判定員とは、わたしの発した駄洒落を
コンマ5秒くらいで判定する役割で、OKならなにもなし、NGならば速攻で頭突きをされる。こうして
文字通り私の駄洒落は鍛えられたのだった。ちなみに駄洒落の師匠は、生物の先生と、地学の先生
だった。
我が家は、父親あてには仲人をした部下の方などから、母親は鍼灸師なので、患者さんからお中元
が届く。定番というものがあって、いつもの同じものを贈ってくれる方がいて、子どものころはやはり
カルピスが届くのが楽しみだったと思う。
自分が社会人になったとき、お中元・お歳暮という贈答習慣をすることになるのかな?と漠然と思って
いたのだが、うちの会社は上司部下の間でそういう習慣というものは一切なく、ある意味しがらみが
ないところだった。技術職だからかもしれない。バレンタインデーやホワイトデーという風物詩も全く無
かったので、「ええとこや」と思ったおぼえがある。男女の人数比が違いすぎるので、自然にそうなっ
たということも考えられるが、とにかく人間関係がフランクな風土はあるような気がする。贈答習慣は
ときに格式ばったりして、壁をつくりかねない。
だからといって、お中元のような風習を否定するつもりはないのだが、周りにそういう風習がない場
合どういうきっかけで、自分はそれを始めることになるのだろうと思っていた。そこへ、旧い友からの
お中元が届き、気づいたのだ。そう、これは自然な発露なのだと。
お正月に年賀状を送るとき、いつのまにか、近況を書くように、遠く離れた(物理的にも、時間的にも)
友人と挨拶を交わしたくなる。「自分は元気でやってる、おまえはどーや?」という、夏の挨拶。だから
「送らねば」という精神で送るのではなくて、「送りたくなる」ものなのだ。この感覚というものは、子ど
もや学生時代にはなかなか理解できないものだと思う。社会に出て、歳を重ねてはじめてわかるも
のなのだろう。
いま、お中元を贈ってくれた友人以外に、夏の便りを送りたいひとは誰だろうか。ふと、考えてみる。
やはり、学生時代の恩師だろうと思う。卒業以来、一度も顔を見せていない。工学部の校舎は、京都
から少しばかり離れた奈良付近の山の中なので、なかなか足が向かないのだ。
この夏、なんとか機会を作って、お中元を届けに行きたいと思う。
- 2004/07/05(月)
7/3の追記で、「神戸線、宝塚線、北千里線をよこにむすぶルートがあると、それなりに便利と思う
のだが。」と書いたところ、大阪府のkatoponさんから、「それがまさしく大阪モノレールやないか!
(一部脚色しています)」というツッコミ、もといご指摘を頂きました。
はい、そうでした。蛍池で阪急宝塚線、千里中央で御堂筋線、山田で阪急千里線、南茨木で阪急
京都線、大日で谷町線、門真市で京阪に接続するという、神戸線をのぞく京阪神主要路線をすべ
て押さえたすごい路線だったのだ、大阪モノレールは。勉強不足でした。南茨木と大日くらいしか
モノレールには乗らないので、千里を通っているとはまさか思いもよらず。
********
さて、本日帰宅後、さる筋から荷物が届いた。

問い:これはなんでしょうか?
答えは、ヘッドフォンケーブル。ずいぶん以前の暗室で、Sennheiser社のHD580というヘッドフォンを
紹介したのだが、これはその専用交換ケーブル。純正のものではなくて、Stefan
AudioArt社というと
ころが出しているEquinox HD600/HD580という商品。
実は、もともとヘッドフォンについていたケーブルを足で踏んづけて、内部断線させたままだったので
換えのケーブルを探していた。ドイツのメーカーのヘッドフォンだけに、国内の普通のオーディオショッ
プでは純正のケーブルすら手に入りづらい代物。実は断線させたのは2回目で、前回は大阪の日本
橋を歩き回って、老舗の河口無線でようやく手に入れた。前回買ったとき、「在庫ないかもしれへん
し、次回からは電話で確認してな」と言われていたくらいなので、いつもあるとは限らない。
また、この純正ケーブル、実は4000円くらいすることもあり、かなり長い間断線したままにしておい
た。断線といっても、ケーブルのひねり具合などを調整するときちんと聞えることもあり、必要性が低
かったのも原因。しかし、だんだんその調整が効かなくなり、ついには右側が完全に断線。それから
は、ヘッドフォンステレオ用のインナータイプのものを使っていたのだが、いかんせんHD580ほどの
音は期待できず、だんだんあの音が恋しくなってきていた。
そこで、webで以前見つけていたAIRYというショップから通販で購入することにした。ここのショップは
国内では手に入りにくいアンプや、ヘッドフォンを専門に扱うところで、HPの各種解説が丁寧なのが
気に入っていた。昨日の夕方に注文し、今朝銀行振り込みし、今日の夜届くと言うハイスピード。
そんなわけで、これが今季のボーナスで買った初めての物品。あんまり普通の買い物じゃないなぁ。
さて、その性能なのだが、まずケーブル自体が編みこみのしなやかな被覆で覆われていて、実に
「納まり」が良く、丈夫だ。これは結構重要で、細すぎるケーブルは、あちこちで絡まったりしやすく、
耐久度が低いのだ。それから、音そのものだが、純正のものと同じ性質だが、やや音が豊かになる
ようになったように思う。この程度の言葉ならまだ、十分理解できるが、いかんせんオーディオ世界
というのは不思議な言語が用いられ、ニュアンスで製品の特長が説明されることが多い。感覚を共
有しづらい、味覚の世界と通ずるところがあるかもしれない。が、慣れてくると、そのいわんとするこ
とがだいたいわかるようになるし、はっきりと耳で感じ取れるようになる。この耳で感じ取れるという
のは、合唱でいうところの「耳がよい」とはやや違った方向性をもっている。ありていにいえば、オー
ディオ世界の住人が歌がうまいか、和音がわかるのかというと、「それはどうかな?」ということにな
る。
とりあえず、今のところ、自分的にはかなり気に入った音がでているので、満足。なお、どんなオー
ディオ機器でも同じなのだが、説明書には「まっとうなリスニングをする前に72時間、エージングを
しろ」というようなことが書いてある。ようは、慣らし運転をしろということ。生まれたての機械は赤ん
坊と同じ。手間ひまかけて調整が必要なように、たとえケーブルであっても、その手間は必要なの
だ。
え、理解しがたい?
- 2004/07/04(日)
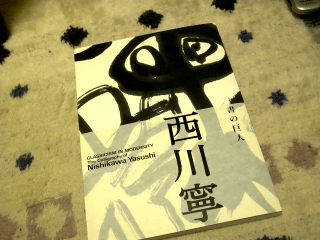 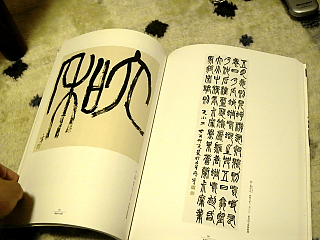
昔から、タイポグラフィーに興味があったのだが、その言葉を聞いてすぐに思い浮かぶのは英語のア
ルファベットであるのは否めなかった。しかし、最近、漢字オンリーのタイポグラフィーにも目が向くよ
うになってきた。それはつまり、「書」である。そのきっかけとなったは、2002年に東京国立博物館で
行われた「生誕100周年記念特別展 書の巨人"西川寧" 展」だと思う。
うちの玄関のスペースには、すでに2004/05/15で書いたように、いくつかの「紙物」が貼ってあるの
だが、メインとなる玄関脇直近のスペースに納まるべき、主役級のものがない状態のままなのだ。
そこで、いいものはないか?と探している中、思い出したのが、写真にある西川寧展の目録である。
「書」というものには、当然いろいろな側面があるわけだが、浅学の私にとっては、まず目にみえる
印象としての「書」が第一であり、意味はわからなくとも、まずはその全体をグラフィックとして、とらえ
たいと思うのだ。書家の方には怒られるかもしれないが、何事に関しても、「入門」というのは"形"か
ら入るというのが、日本の古来よりのやり方ではなかったか。
(なんて、意味が若干が違うが、気にしない。)
ということで、ぱらぱらとページを繰り、拡大コピーして飾れるようなものはないかと探す。そして見つ
けたのが、右の写真の書だ。
漢字の書体の基本は、5つあり、行書・草書・楷書・隷書・篆書である。(それにしても、「篆書」
がノーマルで変換できないとは情けないIMEだ!)
その中でも、書体におけるもっとも最初の典型が、「篆書」である。古来から現代にいたるまで、文
字は常に簡略化される方向に書体が変化してきた。だから、もっとも古い字体である書は、もっとも
造形的に複雑で、目にしたときの印象がもっとも絵画的である。しかし、その前段階である象形文字
とは明らかに異なり、「文字」としての風格を与えられいるのが「篆書」なのだ。偽造されにくいこと
から、現代の世の中でも未だに印鑑の書体に用いられるのも納得がいく。
写真のものは、漢字のひとつひとつが意思を持つようであり、その連なりとしての書はさながら、視覚
の音楽のように私の目に映った。これ以上の「グラフィックアート」はないように思えた。今日はかなわ
かったが、コピーをとり、額装の方法を工夫して、なんとか玄関でお客さんを迎えるにふさわしいもの
として、仕上げてみたいと思う。こういうものも、ある意味二次創作といえるだろうか?
- 2004/07/03(土)
(7/4 演奏会編追記)
 
突然思い立って、大阪は伊丹にある大阪空港へでかける。展望デッキから飛行機の写真を撮ろうと
思ったのである。実に、8年ぶりの伊丹。
8年前は、関空へのシフトなどの影響もあってか、随分と寂れたイメージがあったのだが、数年前に
改修し、純粋な空港利用客以外のお客さんを取り込むのに成功している様子。展望デッキがきれい
になり、幅400mにわたって、モダン家具のテナントが並ぶ。
しかし、昼間の空港、それも野外となれば、照りつける太陽の暑いこと。写真撮影もそこそこに、すぐ
に館内に待避してしまった。来るならば、夕暮れどきから夜にかけてがベストなのだろう。写真の絵
的にもぜひ狙いたいところだったが、そこまで粘る根性もなかった。この続きは、8月の東京行きの
際に、羽田空港でなんとかしたいと考える。
離発着数や、空港内のくつろぎスペースの充実さからして、やはり羽田には負けるのは致し方ない。
なによりその差を決定付けているのが、航空会社直営のグッズ販売店の有無である。羽田には、
たしかANAだったと思うが、飛行機の模型やポスター、客室乗務員デザインのスカーフや、旅行鞄、
はては、実際に使われていたシートまで売っている(昔)という、子どもとマニア垂涎の直営ショップ
が存在する。今回、伊丹にもできているか?と思って探したが、残念ながら、飛行機グッズの一部
を、テナントのおもちゃやで少し扱うのみだった。自分用のお土産を買おうと思っていただけに残念
だった。
さて、ついでに告白するならば、大阪モノレールよりも、東京モノレールの方が好きだ。あのパノラマ
度合いの高さにはしびれる。浜松町を出てからのビル街を縫うように走行したあと、木場方面のうめ
たて地の水場上空をすべり、最後にはギューんと東京湾を望みながらゆるやかで長いカーブを経て
羽田の地階ホームに滑り込む、あの様はなんど乗っても気持ちがよい。
それにしてもあれだ。空港というのは来るとなんだか、そわそわ、わくわくする。同じ旅であっても、
電車の駅では感じない高揚感を感じる。ちょっと、違う「よそいき」の感覚。その感覚に酔ってしま
って、ふらふらーっとチケットを買って、どこかの都市へいってしまいたくなる衝動に駆られる。幸い
明日も休みだし...というささやきが頭の奥から聞える。いや、今日は本当にかなり心揺れたのだ。
一応ボーナスが入ったという財政的な側面もあった。しかしながら、この後合唱の演奏会を聞きに
いく予定があったので、すんでのところで踏みとどまる。
大阪モノレールで、不二家ネクターを飲んで一休み。次の目的地、吹田に向かった。
(「金沢大学合唱団、大阪大学混声合唱団ジョイントコンサート編」に、つづく)
「金沢大学合唱団、大阪大学混声合唱団ジョイントコンサート編」
NCの指揮者、I東さんが合同の指揮を振るというコンサートに向かうべく、伊丹から(モノレールで蛍
池、そこから阪急宝塚線で十三へ。京都線に乗り換えて淡路。淡路から北千里線で、吹田へ。路線
図で見ると、「コ」の字型に移動したことになる。大阪の地理はよくわからないのだが、伊丹から吹田
への直通のルートというのはないのだろうか。神戸線、宝塚線、北千里線をよくにむすぶルートがあ
ると、それなりに便利と思うのだが。
吹田駅、徒歩1分の吹田市文化会館メイシアター大ホールに着く。到着後5分ほどで入場時間となり
休憩する場所も特にないので、早々にホール内に入る。パンフレットを受け取って、驚いたのだが、
金沢大学、阪大混声ともに100名を超える大所帯だった。昨今、これだけの大人数を維持できると
いうことは、それなりに実力もあり、マネージもできる団だと思うので、合同ステージだけでなく、単独
も期待できるかもと想像する。実は、両団体の演奏を聞くのは、はじめてなのだった。
エールが始まる。パンフでわかっていたのだが、両方とも女声の指揮者。金沢のエールに続いて、
阪大混声。よく考えると、意外でもなんでもないのだが、そのエールは「い〜こまのみーねーに、あ
さかーげ、さあしぃて〜」で始まる、大阪大学学生歌だった。この曲は、阪大男声でしか聞いたこと
がなかったので、阪大男声の歌だと思っていたのだが、学校が同じだから当然なのだ。混声で聞く
歌は、新鮮だった。
さて、期待の両団の演奏だが、なかなかに良かったのだ。なんというか、大人数合唱団のメリットを
ちゃんと生かせているというか、SATBの役割分担と構成が明確で、ベースがしっかり支えて、ソプ
ラノが旋律を歌うというところがはっきりしていた。両団を比較すると、明確な違いはソプラノの発声
の違いだろうか。優等生的な金沢に対して、ややはみ出した感じ、すこし幼さをたたえた阪大混声
というイメージをもった。
特に印象に残ったのは、阪大混声の指揮だ。縦に伸びやかに伸びる棒が、見ていて気持ちいい。
歌い手も同じ感情をもっているのではないかと思う。縦の棒は、ややもすると、自分の頭身を越える
部分でオーバーなものになり、テンポを維持できない「見かけ」だけのものになり易いと思う。しかし
彼女の指揮は、あくまでクールに、情趣に流されない節度があったと私にはみえた。
充実の単独に比べて、合同はやや完成不足に思える部分があった。人数の多さがやはり裏目にで
たのか、単独ではおそらく出ていなかった一回生が加わったこともあるだろう。全体としての声のま
じり具合がいまひとつかなと思った。単独それぞれのよさが、うまく掛け合わされる手前の声という
気もした。ただこれは、「八重山・宮古の三つの島唄」という民謡ベースの曲の特性上、やむをえな
かったという気がしないでもない。この曲に関して、私見をのべるならば、いわゆる沖縄本島の島唄
の華やかさの部分がややそがれ、もっと土着に近い朗誦や謡というイメージがした。
全体としては、3ステージとも満足のいく演奏会だったように思う。少しだけ、I東さんのことを語るなら
ば、変拍子の指揮はいまさらながら見事だなと思った。普段、4分の4とか、4分の3とかの基本の指
揮で入りをよく間違えたりする人とは思えない(笑)。
演奏終了後、馴染みのメンバーとロビーで顔をあわすが、なんとなく飲みに行く気分ではなかったの
で、私とTさんは淡路から阪急京都線で帰宅、S姐さん、S田さん、シロ村田くんは淡路で喫茶店に寄
って帰るとのことだった。だって、私とS田さん、シロ村田くんは、金曜日も一緒に飲んでたからナァ。
- 2004/07/02(金)
賞与、つまりボーナス支給日。うれしい、確かにうれしいのだが...、所得税・住民税、雇用保険、厚年
保険、etc,etcを全部足し合わせると、控除額計12万円弱。いったいなんなんだこの額は...支給明細
を見てしばし思考停止。+の方ではなくて、−の方に考えが行ってしまうのは、良くないと思いつつ、
少々ブルーな気持ちで、BKの練習に向かう。
ただいま練習しているのは、サンサーンスや、フォーレらの、フランス語の曲。もうまったく全然歌詞が
ついていかないのだけれども、とにかく音楽が美しくて、ただただその美しさに身をゆだねる。最近、
NCも含めて、東欧・北欧・イギリスの曲が多く、また学生時代を通じてもフランス語の曲というのは、
初めてである。
曲の構成や、和音というものは、非常にオーソドックスに感じるのだけれども、すごく色彩が明るくて、
穏やかな印象を受ける。フランスという国に感じるイメージがそのまま反映されていると思う。ある意
味、スタンダードで、こう来るなと思った音が必ずぴったりくる。しかし、だからといって退屈ではなく
て、なんというかスタンダードの洗練の極みという気がする。こういう曲こそ、基本のレパートリーに
してみたいな、と思わせるものがある。
歌っていると、税金のことなどどっかに忘れてしまう。仕事の後の合唱はやはりいい。
- 2004/07/01(木)
阪急電車の駅には、「TOKK」という名前の隔週刊のミニ新聞というか情報誌がおいてあり、これが
結構な人気で、置かれるとすぐになくなってしまう。7/1号の特集は、祇園祭と天神祭。
で、なにげなく見ていたのだが、この号を駅でとったのは先週末の金曜日で、まだ7月ではなかった
のだということに気づく。そう、昔からの疑問で、未だになっとくのいく答えが見つからないのが、この
謎なのだ。週刊誌や月刊誌の号数はなぜ、実際の週より一週、隔週刊なら二週、月間なら一ヶ月さ
きどりなのか?
昔、交通事情がよくなかったころに、全国にいきわたるまでに時間がかかってしまうから、先どりに
なってしまった、という話を聞いたのだが、どうも得心がいかない。それに、この先取り現象は、週刊
誌に限ったことではないのだ。普通の出版物などの奥付を見ると、実際の発売日の一月先がかいて
あったりする。だから、正確にその本が発行されたのはいつか?というのは奥付を見ても判断できな
い。一応「公式」にはその日付ということなんだろうが、雑誌と違って、地方発送が遅れたからといっ
て問題になるわけでなし、非常に不思議な慣習(?)といえる。
そもそも、日本で出版が始まって以来のことなのか、あるときから始まったことなのか。案外調べて
みると、面白いテーマかもしれない。
もうひとつ不思議なのが、この現象は、日刊と季刊には影響を及ぼさないということだ。今日売られ
ている新聞は、今日の日付であって、明日やあさっての日付ではない。夏に発売される号は、夏号で
あって、秋号ではない。いや、だってそんなのおかしいじゃないか、と言われれば、そうなのだが、だ
ったら、6月に発売されているのに、「7月号」の雑誌に対しておかしいと感じなければ嘘ではないだ
ろうか。
べつにこのことで不利益をこうむって、怒っている!というわけではないのだが、いまだに解けない
謎だけに、ときどき思い出しては悩んでいる。
|
|