|
電波暗室 2004/09
- 2004/09/30(木)
今日から秋と認定。背広の上着が必要だから。
この前炊いたご飯がもうなくなりそうで、明日の朝ごはんにはちょっと足りない。帰宅が遅か
ったので何かと面倒な気分。で、ごはんを研ぐ気になれず、コンビニでバターレーズンロール
と、牛乳を買う。ようはパンがたべたくなったのだ。
本当はかりっとした食パンにバターを塗ったのを食べたかったがあいにくとトースターがない
ので、あきらめた。
わたしは社会人になっていらい朝食はご飯と決めていたのだが、どうも最近ご飯の食べすぎで
飽きてきた。正確に言うと、朝食はご飯一杯にふりかけ、お茶のみでおかずがないのだ。引越し
当初はいろいろおかずをつけていたが、毎日惣菜を買うと高くつくし、毎日ソーセージを焼く
時間があるほど朝はゆっくりしていない。(ぎりぎりまで寝てしまうから)
塩ラーメンの一件で料理する時間が必要だと目覚めたのだから、朝調理してもいいのだが、
どうせなら、パン食をとりまぜて見ようかと思う。ちょうど寒くなってきたので、朝ミルク
ティーを飲むのもいいなぁと思う。おりよく、郵便受けに寺町の電気屋の広告が入っていた
ので、この機会にトースターを買う決意を固める。
なんだか新生活の始まりのようだ。欧米の新学期が秋から始まるというのは理にかなってる
なぁなどとかなり根拠のないことを考えながら、風呂の準備をするのだった。
- 2004/09/29(水)
昨日の夜、二時くらいまで本を読んでいたのだが、昼間は眠いということはなく。だが、
夜になって急に眠気がしてきたので、明かりを消す。どうも私はまぶしいと逆に眠くなって
しまうようで、暗いほうが目がさえてくる。
本のタイトルは「第六大陸1」(小川一水著、ハヤカワ文庫。第35回星雲賞受賞作品。)
お気づきのようにSF。一昨日読み始めたばかりだが、昨日帰宅後に本格的に読み始めると
とまらなくなってしまったのだった。
しかし、この本を買ったとき思ったのだが、本屋のSF関係のコーナーはなんとさびしいの
だろうか。時代小説や、ミステリー、恋愛小説、エッセイetcなどのコーナーには、あっち
こっちにおすすめポップ(店員さん手作り)がたっているというのに、SFにはただのいっ
っぽんもたってないのですよ!店によるのかもしれないが、大多数の本屋では似たような感じ
だろうと推察される。
名作、力作、感動作はいっぱいあるのに、なぜそんなに人気がないのだろうか。やっぱりSF
=凝った設定=マニア=オタクっぽい、というような図式が世間一般にはあるのだろうか。
まぁ、ある意味その認識は正しいのだけれども。
SFっていうのは想像力の世界である。現実にはない世界を、どれだけ文章からリアルに想像
できるか。それは書き手の力だけではなくて、読者にも力を要求されるようなところがあるよ
うに思う。SFが読まれないっていうのは、「何かを想像するのがしんどい」ということなの
かもしれない。いや、もしかしたら「想像できない」のか。それはとても不幸なことに思える。
- 2004/09/28(火)
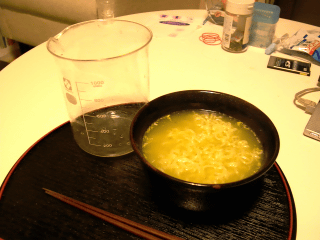
「白菜、しいたけ、にーんじん。季節のお野菜いかがです。」
会社の歓送迎会。料理が少なくて、お茶と氷をついばんでばかりになってしまう。
なにせご飯ものが全然なかったので、おなかすくだろうなーと思い、帰宅途中に塩ラーメンを
買う。塩ラーメンは良い。なぜならあんなにおいしいのに、カップ麺よりはるかに値段が安い。
家で調理して食べるなら断然お得だ。
早速調理。お湯をわかすだけなのだが、今回は袋に記載どおりのレシピにしたがってみた。水を
500ml沸騰させてから麺をいれ、3分間煮込んでから火をとめ、調味料(スープの元と、特製ごま)
をいれる。こんなこともあろうかと、私の部屋には1リットルのビーカーがあるだ。
湯をわかすかたわらで、米を研ぐ。ことこと、ぐつぐつ。沸騰したところに麺をいれる。ことこと、
ぐつぐつ。不思議だ。こんな簡単なことをしているだけなのに、いつもはさびしげな台所が急に活気
づいたような錯覚におちいる。湯が煮える音、麺のほのかなにおい、かすかな湯気。どうも、そんな
デティール達が、脳裏の記憶を呼び覚ますみたいだ。いつも、ご飯だけ炊いていたときには想像もつ
かないような、期待感と安らぎ(?)みたいなものを感じる。...生活に必要なんだなぁと思う。
きっちり3分後に火を止め、調味料をいれてどんぶりにうつす。できあがった塩ラーメンは、スープ
の量、濃さ、それに麺の固さまで、完璧だった。塩ラーメン生活云十年目にして初めて知るレシピの
偉大さ。
- 2004/09/27(月)
私は朝ごはんを食べながら、食卓に乗せたノートパソコンでメールチェックをするのだが、
今朝は早く起きて寝ぼけていたのか、お茶の入ったボトルを盛大に食卓にぶちまけてしまった。
もちろん、ノートパソコンにもジャバーとかかってしまった。何の根拠もないのに、大丈夫だろ
うと思って、そのまま操作を続けていたら、スピーカーから「ピー、が、がっ」という異音がな
たあと、キーボードも、タッチパッドも効かなくなってしまった。で、立ち上げなおすと、OS
ではなく、バイオスからのメッセージが。「キーボードエラー」そのまんまだ。
時間がなかったので、とりあえず食卓だけ拭いて、PCはそのままに仕事に向かった。
これは修理にださんとだめかなぁと思うと、メインマシンも不安定な今、ちょっと参る。
で、帰宅後、念のためもう一度立ち上げると、なんと通常通り立ち上がった。こぼれたお茶で
回路がショートしていただけのようだ。乾いてしまって直ったのだろう。いやーそれにしても助
かった。そして、このノートの強靭さに感謝する。
で、ここで終わるかと思ったが、この文章を書いていて、気づいた。左のシフトキーを押しながら
のO,P,)←右括弧、’←アポストロフィーが入力できない。今回浸水した箇所とは離れている
のだが…。ほかにも出ない文字があるかもしれないが、右括弧は多用するので、ちょっと困る。
右シフトなんて普段つかわないから押しにくいことこの上ない....。結局のところ修理が必要な
感じである。とほほ。
- 2004/09/26(日)
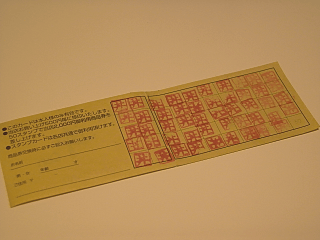
弁当屋のスタンプ、あとひとつ。全部押すと金券と交換なので、写真にとっておいた。
500円でひとつなのだが、ご飯抜き(100円引き)を頼むことが多かったので、8ヶ月くらい
かかってしまった。
- 2004/09/25(土)
明日、奈良に行くかどうか迷う。
明日だけのことではないので、コンクールまでの期間、身体が持つか自信がない。
いまは病み上がりほやほやなので、思考も逃げ気味なのかもしれないな。
- 2004/09/24(金)
一時的に熱がひく。
小児用ジキニン(24ml。6回分。)を毎食後に一本ずつ飲んだのが効いた。
夜、一時的にぶりかえすも、絶え間ない水分補給と発汗で体温を下げる。
- 2004/09/23(木)
__| ̄|○
- 2004/09/22(水)
____○_
- 2004/09/21(火)
仕事→集中→頭痛・肩こり→熱→吐き気→食欲なし→寝。
- 2004/09/20(月)
NCの練習はないけれども、YKの練習はあるらしい。
終日、自室で仕事。なんで休日に仕事せにゃならんのだ。(名目:自己研修)
合宿後だからゆっくりしたかったのに...精神的に疲れる。
友人にもらった梨(豊水)を食べる。うまい。
ちょびっと元気が出た。
- 2004/09/19(日)
NC合宿 in 奈良。第二日。
朝、目覚めるも身体動かず。木、金と熱があったのに無理したせいか。熱はひいたものの、疲労
感が激しい。仕方なく、午後からの練習に参加。
18:00帰宅。昨日届いていた通販の品物を吟味する。「サンエーパール」という研磨剤と、
セルベットという研磨布。何を磨くかというと、時計の風防だ。
時計の風防とは、文字盤の上の透明な覆い、つまりガラスやプラスティックのカバーのことだ。
大概の時計はガラスが使われおり、そのなかでもサファイアガラスの場合、これに傷がつくこと
はまずありえない。だが、昔の時計や現代の時計でもスウォッチなんかの場合、風防はプラステ
製で、容易に傷がつく。実は、この前かったアテネオリンピックモデルのスウォッチにいつのま
にか大きな引っ掻き傷がついていたのだ。出かけたときにはまったく気づかず、帰宅後はずして
みて初めて気がついた。いったいぜんたいいつついたものやら見当もつかない。
驚きと同時にかなりショックを受けてしまった。それはそうだ、買ってから一日くらいしか経っ
てない。風防の中央部でかなり目立つ....。というわけで、しばらく立ち直れなかったのだが、
いつだかアンティーク時計屋のおっちゃんが、「プラスティック風防は研磨できるで〜」といっ
ていたのを思い出した。さっそくネットで検索したところ見つけたのが「サンエーパール」だっ
た。
直径5cm、高さ3cmの靴磨きのような容器に入ったペースト状の物体。ふたにはワープロ的
な文字で「サンエーパール」とだけしか書いていない。ネットで見つけたショップ、どこを見て
も同じ容器、同じ文字だったので、作っているのは同じメーカーなのだろう。それにしても一切
の主張がない。なんとなく怪しい感じすら漂う。価格は700円と、分量の割りに安い。
セルベットにサンエーバールを少量とり、風防表面で円を描くように研磨する...。一回目およ?
細かい傷がきれいさっぱり。二回目、でかい傷がだんだん目立たなくなってきた。てな具合で4回
くらいの研磨で今回ついた傷はきれいさっぱり消えてしまった。もちろん傷以外の部分はそのまま
だし、風防は透明なままだ。すごい、すごいよ〜。静かな感動が湧き上がってくる。
これはいけるということで、別のプラスティック風防でも試す。なんだか磨くという行為には没頭
してしまう。時が経つのをわすれるくらいだ。合宿の疲れからきていた頭痛がいつの間にかなくな
っていた。
ふと気がつく。サンエーパールには見覚えはないが、このセルベットというオレンジの縁取りの黄
色の布、昔見たことがある。クリームで汚れて、研磨で黒くなったあの布。そうだ、祖父の家だ。
時計を磨いたかどうかわからない。でも、祖父は日曜大工好きだったので、何かを研磨するのに
この布を使っていたような気がする。あの布だ。妙になつかしい思い。
将来、だれかが私が時計を磨いていたことを思い出したりするだろうか。
そのとき、サンエーパールと、セルベットは残っているだろうか...たぶん残っているような気が
する。こういう商品はしぶといものだ。
- 2004/09/18(土)
NC合宿 in 奈良。第一日。
近鉄特急で奈良へ、34分ほどで着く。実は、合宿なのに私は合宿所には泊まらないことにして
いた。合宿所はYHなのである。当然相部屋の雑魚寝。昨年の合宿所もYHだったが、相部屋だが、
2段ベッドで個別の空間はあったのでましだった。単に雑魚寝が嫌というか、いびきをかく人が
いると私は寝れないのだ。で、今回はあまりきれいなところでもないし、それなりの宿泊料を払
うなら、奈良市内にホテルでも取ろうと思っていた。しかしこれが甘かった。
合宿はちょうど三連休の頭からで、奈良市内のホテルは本当にどこを探しても満室。はっきりい
って観光都市奈良をなめていた。実はF栄も同じ考えで、奴はそうそうにホテルを予約していた
にもかかわらず、ダブルブッキングに合ってしまったくらいなのだ。(つまりキャンセルがほと
んど見込めなかった)(なんとかホテルの手配で別ホテルに泊まれたらしい。)
というわけで、練習後京都まで帰って、つぎの日にまた出てくることにしたのだ。近鉄特急なら
身体もらくだし。だが、ここでも私は予測が甘かったというか、事前の調べが足りなかった。
ホテルに向かうF栄の車で、近鉄奈良駅におくってもらったはいいが、時刻表をみると21時ジャ
ストの特急が最終だった。結局それから30分くらい待って、京都行きの急行に乗った。所要時間
46分。雑誌アイデア「特集:原研哉のデザイン」を読みながらだったので、あまり退屈はしなか
ったのと、彼の文章のおかげで疲れていた頭がとても整理されてすっきりしたので助かった。
スタートレック・ヴォイジャーを見てから寝る。今日奈良に泊まっていたらこのエピソードを
見れなかったかと思うと、宿が取れなかったことを感謝しないといけないかもしれない。
- 2004/09/17(金)
BK練習。日本語の歌は、誰が聞いても意味がわかるので、うまい下手がすぐにわかってしまう。
今回やる演奏会の曲のなかで、じつは一番難しいのかもしれない。普段、主旋律を歌うことが
あまりないベースは特に。
半年ぶりにI倉が来たので、みんなで飲み会に行く。しかしI倉は車なので飲めないのだった...。
ひさしぶりにいった「くれない」は、どういうわけか注文の品が漏れなく、すばやく来るように
なっていた。TOYOTAのOBがカイゼン指導に入ったのだろうか。今日一番の謎である。
カイゼン指導というのは、具体的なノウハウがあるのかどうか不明だが、TOYOTAで働いた人は、
みなその素質をそなえることになるのだろうか?だとすると、下手な資格などよりもよっぽど
役に立つ実学だと思う。それで生計が立てられるかどうかはその人の情熱次第だろうが、身ひとつ
で実行できる能力をもっているということは、生きてゆくうえでなんらかの「自信」につながる
のではないかと思う。
実は「楽譜が読める」、という音楽人にとってはあたりまえすぎる能力も、世の中からみれば、
かなり特殊で「うらやましがられる」ことなのかもしれない。(みんな義務教育中にちゃんと習っ
てるはずなのに、会社で「楽譜読めるってすごい」とか言われることがよくあります。不思議)
- 2004/09/16(木)
めまいの症状と、不規則の発熱が続くので早めに帰宅。といっても残業していないだけ。
帰宅後、ニュースで京都府庁の旧本館の活用方法を検討する委員会が設置されたとのニュース。
明治に立てられた西洋建築であるが、現在はほとんど使われていないそうだ。ただ、府庁前の通り
からみえる旧本館の姿は美しく、たて壊されたりすると景観がいっぺんするのは確かだ。ニュース
では国に重要文化財の申請をしたとあった。いままで指定されていなかったのか!とかなりおどろ
いたが、とりあえず立て壊す意思がないのは安心である。
旧本館は府庁の敷地内からかなり奥まったところにあるため、きちんと撮影したことがない。でき
るならば、かなり傷んだ様子の内装をきちんと治して、敷地内部や本館内部を一般公開してもらい
ものだ。その際、ありきたりでおざなりな貸し会議室みたいな活用はやめてほしいと思う。どうせ
なら「府庁ホテル」(ホテルのロビーというものはパブリックスペースなので、「一般公開」とい
うものと矛盾しない。)くらいの大胆な方法をとらないと、「維持しつつ保存」することはできな
いだろう。維持費をまかなうのは税金なんだから。
かなりつらいので、もう休みます。
- 2004/09/15(水)
「孤独に歩め、悪を為さず、求めるところは少なく、林の中の象のように」(仏陀)
映画「イノセンス」には、古今東西あまたの箴言が引用されているが、なかでもこの仏陀の言葉は
ひとつのキーワードとしても重要な意味をもっている。ストーリー上ではなく、隠れたテーマとし
である。映画館で見たとき、そしてDVDで見たときには、本作の主人公であるバトーの「虚無感」を
あらわすものであると思っていた。それは間違ってはいなかったが、正確ではなかったのだ。
本作「イノセンス」は、士郎正宗原作の漫画「攻殻機動隊」を原作とする映画「GHOST IN THE SHELL
〜功殻機動隊〜」の続編にあたる。功殻機動隊について説明することはかなり難しい。
ストーリーだけならば、
http://www.production-ig.co.jp/anime/gits/index.htmlや、
http://www.innocence-movie.jp/story.html
を見ていただければいいのだが、本質的なところはやはり原作を読んでいただくのが一番だと思う。
わたしは、もう1巻、2巻(続きもののようで続き物ではありません。)をそれぞれ10回以上読み
返しているが、読むたびに自分の認識力の拡大を迫られるという稀有な漫画である。
さて、本編DVDには付録として「鑑賞前・鑑賞後用のガイドDVD」がついている。DVDを見たあとに、
作品をさらに理解するためのものとして、提示されたものに先の仏陀の言葉があった。実はこの言葉
の前後には、このような言葉があるのだという。
「もしも思慮深く聡明でまじめな生活をしている人を伴侶として共に歩むことができるならば、
あらゆる危険困難に打ち克って、こころ喜び、念いをおちつけて、ともに歩め
しかし、もしも共に歩むことができないならば、国を捨てた国王のように、また林の中の象の
ように、ひとり歩め。
愚かな者を道伴れとするな。」
ひざをうった。深く考えた。そう、イノセンスの主人公バトーは、かつて相棒であった少佐こと、
草薙素子を前作「GHOST IN THE SHELL」で失っている。(死んだわけではなく、違う次元に移動し
てしまったというのが近い)相棒(伴侶)の不在が、バトーのその後の生き方を決めたということ
を示した言葉なのだ。そして、誰よりも「相棒」を求めているということも。
公開前に、「この映画はある種の恋愛もの」みたいな監督の言葉を聞いた。映画をみた直後も、DVD
を見た直後もはっきりとは、それがわからず、もどかしい思いがしていた。だが、この言葉の意味を
知った今、もう一度映画を見返してみたいと思う。今すこしだけその意味がわかりかけている。
興味のある方、ぜひ見てください。
知人の方、原作と「イノセンス」はお貸しします。「GHOST IN THE SHELL」はなぜか持ってないの
で自分で借りてください(笑)
- 2004/09/14(火)
木、金、月、火と4日間に渡って、故障したワークステーションの復旧作業を行っていた。今日、
ようやく終わり、明日から普通の仕事ができる。本職ではないが、私が管理するシステムを運用
するマシンだけに復旧責任があった。もう頭くらくらの、へとへとで、今日などは極度の疲労で
起き上がれず午後に出社した。脂汗がだらだら出る。
「UNIXワークステーションの管理・保守のスキルは、どれだけひどい目にあったかで決まる」とは
SEをやっている友人の言葉だが、入社以来結構ひどい目に合わされつづけているので、マイレージ
に例えれば、香港旅行できるくらいのポイントがあると思う。しかし、いくらスキルがあがっても
私の場合、これが本職にはほとんど関係ないスキルであるということが問題である。「ひどい目」
にあっている間、本来やるべき業務がほとんど手をつけられないので、仕事がたまっていく。この
仕事をあとでリカバーせねばならず、二重三重の苦痛になる。
高校のとき合唱部で私は同学年がひとりもいないという状況に立たされた。かなり「ひどい目」に
あったと思う。卒業した先輩からもらった手紙に「山Dが味わった経験というのは、いつか必ず血と
なり骨となり肉となるはず」と書いてあったことがある。今、思い返すとあのときの経験がなにか
に役だったとかそういうことはない。自分の人格形成に影響を与えたことは確かな気がするが、あ
まり良い方向には働かなかった。「孤独に耐える」というスキルは得た。あまりうれしくないが。
いまのこの苦しみが何か、将来に自分にとって良かったと思える方向に働いてほしいなぁと、つか
れた頭でぼんやり願望する。いまは何か前向きなことを考える気力がない。
明日は早く帰って、明日発売の「イノセンス」のDVDを見よう!
頑張って、これくらいかな。
- 2004/09/13(月)
一年前のよどこんの演奏会の時期の暗室を読み返してみる。
ついつい、前後の日記を読みふけってしまう。一年前に書いたことなんてほとんど覚えていないの
で、なんだか本当に自分が書いたのか不思議な気分である。月日が経つのは早いなぁと感じる最近
であるが、こうやって過去一年間の記録を見ると、そこにはただ流れるだけでない時間の積み重ね
が確かにあったのだと実感できて、すこしうれしい。なにごとも続けてみるものだ。
話は変わるが、私の家のベランダにはやたらとダンボールがある。地上から眺めてもあれはなんや
と思うくらいだ。引越しの際の段ボール箱は、かなり初期に処分したのだが、部屋づくりをはじめ
てから購入した本棚などのダンボールがたまりにたまっていた。というのも、マンションの決まり
で、ゴミ置き場には、引越しなどで使ったダンボールはおかないことと決められており、処分する
には市の清掃局に依頼せよということになっていたからだ。
いちいち清掃局に頼むは面度だし、だいたい役所は土日に仕事をしないから勤め人には不可能だ。
ではどうするかというと、古紙回収が唯一の手になる。ところが、「まいどおなじみの〜」という
スピーカーの声を聞いて、ベランダから回収者の存在を確認した時点で手遅れなのだ。一階までダ
ンボールをもって降りる間に走り去っている。実家の近くではあれほどのんびり走っている回収車
がうちのまえの通りは飛ばしどころ?なのか自転車でないと、とても追いつけないくらいなのだ。
そういうわけで、ほとほと困っていて、最近ではもうたまるにまかせていた(ダンボールというの
は自然とたまっていくものなのです。)だが、最近の台風の襲来の多さと、地震で目覚めた防災意
意識からこの状態はまずいという認識はあった。もし火事にでもなったら、燃えやすいものをため
ていた非を問われる、なんてことも考えた。で、金曜日の夜に一念発起してベランダからすべての
ダンボールを運び出した。どういうつもりかと言うと、あらかじめマンションの外に運んでおいて
車を見つけたらダッシュするだけのこと。あまりにも多いので、今回は少量を1Fのゴミ捨て場脇に
おいておいた。
ところがである。土曜の朝10時くらいに様子を見に行くとなんと、昨日おいたはずのダンボールが
ない。え?なんで?と一瞬思ったが、実はこういうことは前からあったのだ。マンションの決まりと
はいっても、ダンボールを出す人はいる。そういうのが、知らないうちになくなっているのを不思議
に思っていた。だが、よく考えると答えは簡単で、回収業者の人が依頼せずとも勝手に回収していた
のだ(多分)。このあたりは和装業者が多く、ほとんど毎日店のそとに真新しいダンボールの山がな
らぶ。当然それを回収する業者がいて、その人たちがついでにマンションのゴミ捨て場をのぞいてい
くものと思われる。昨今、古紙の回収率というのはかなり下がっているらしく、依頼仕事以外でもダ
ンボールが欲しい、というような話を聞いたことがある。
ということで、労せずして処分できたことをいいことに土曜の夜、日曜の夜と小出しにだしておいた
ところ、いずれも次の日の朝にはなくなっていた。これはもう絶対確実である。この調子で毎日回収
してもらえれば、後2日くらいで我が家のダンボールはなくなりそうである。(ってそんなにあるの
か...)
こんなことならもっと早くにやっておけばよかった。ひろくなったベランダでごろんと横になったり
するのであった。
- 2004/09/12(日)
淀川混声合唱団、第16回演奏会。いずみホールにて。
Asian & Pacific Songs、Salve Regina(Richard Dubra)、Romancero Gitano、どちりなきりしたん
の全4ステージ。1ステのはじめのほうは、調子が出ていないようで不安定な部分もあったが、アジ
ア各国の歌はどれも親しみやすく、技術的な面よりも曲の雰囲気が伝わってくることのほうが重要だ
ったと思う。ここではインドネシアの「O lani Keke」という、可愛い女の子を青年たちが冷やかし
ているという歌が良かった。
つづく2ステは、部分部分でとても引き込まれて、敬虔な気持ちにさせられることがあったけれども
よどこんの力は、まだまだこんなもんじゃないだろう?と思う面もあった。細かい部分を精査して
いけば、もっともっといい曲になる、そう感じたステージだった。
インターミッション。いつものごとくいずみホールのラウンジで水を飲む。水は自由に飲んでよいの
で(^ ^;まわりを見渡しても、あまり知り合いがいない。個人的に思うことは、よどこんとNCでは観
客層が微妙に違うような気がする。こう、よどこんの方が若干平均年齢が高い、そんな程度でしかな
いのだけれど。知り合いをみかけないのは、その知り合いの多くがオンステしているからだろうなと
は思う。ステージから客席は見えているのだろうか。偶然、目が合ったりする(気がする)と気恥ず
しくなるのだが、経験上客席が暗い場合でこちらの視力がよくない場合、視線の位置まではわからな
い。目のいい人の場合、どんなもんなんだろうか?聞いたことがない。
3ステ、ギターと合唱の協奏。実は、この曲を一番期待していた。以前、偶然によどこんの練習に紛
れこんでしまったときに聞いたのがこの曲で、スペイン的な叙情にあふれるいい曲という印象が強く
残っていたからだ。しかし、こうやって7曲を連続して聴くと少々疲れるのだった。これは曲のせい
というよりも、やはり演奏のぎこちなさ?によるものかなぁと思った。曲にあふれる濃くて、血がた
ぎるような情熱が、いまひとつ伝わってこない。曲に振り回されているような感じがしたのだ。
4ステ、千原英喜のどちりなきりしたん。第一声から、3ステの混濁を払い飛ばすようなサウンド。
2ステと3ステに足りないと思ったものがすべてここにあった。軽やかに伸びやかに、4つのパート
が重なりあって、大きな慈悲と祈りにつながっていく。一小節目から最終小節まで音楽がとぎれない。
歌っているみんなが、曲の全体をきちんと俯瞰しているように思えた。最終章の祈りの直前、わたし
はこのまま心臓が飛び出していってしまうような、じわりじわりと高まっていく気持ちでいた。
そして、最終章で高まりをやさしく解きほぐすような救済。ああ、なんだこれ。気持ちいい。
どちりなきりしたんは、最近コンクールでもよく取り上げられる曲だ。曲自体の良さはもちろんあ
るけれども、今日のこのよどこんの演奏のように、「何か」を感じられる演奏は少ないんじゃない
かと思う。私が感じたのは、「高くて大きな空間」と「風」だった(抽象的で申し訳ない)。
聞いていて、なにか物足りないと思うとき音楽は合唱団の目の前にしかないのだと思う。本当にす
ばらしい音楽があるとき、合唱団はるか上の天井にまで音楽が満ちている気がするのだ。合唱団は
常にその音場(高くて大きい)とともにあるように感ずるのだ。
風、これはいっそう表現が難しいけれど、舞台から確かに風みたいなものを感じた。それは単なる
音圧だったのかもしれないけれど、人はその物理現象を物理現象ではない方法で説明したくなる。
風を受けた私は、とても清明で心地よい雰囲気になっていた。恍惚とも違う「それ」は、いままで
体験したことのないものだった。
だめなところは探せばいっぱいある。でもそのことに意味があるとは思えない。メンバーが自覚し
ていることだと思う。
今日聞きにきてよかった、それだけがもっともわかりやすい確かな感情だった。
- 2004/09/11(土)
最近、地震があってから以来だと思うのだが、体の平衡感覚がおかしくなっているような気がする。
地面などちっとも揺れていないのに、ふらふらして頭が落ち着かない。ゆれているように思うと、
実は勝手に体が動いているだけだったりする。一度、夜中目が覚めたことがあって、あれは余震だっ
たと思っていたのだが、今考えるとどうにも自信がない。
目や、三半規管をつかさどる部分で必要な栄養がたりないのだろうか。といってもそれがどんな栄養
なのかわからないのだが。関係ないかもしれないが、最近魚をほとんど食べていないのだ。これはよ
くないと自分でも思っている。ガスコンロはあるので、魚焼き用の網でもかってきて食べないといけ
ない。
もう秋だ。うまいさんまや、鯖を食べのがすわけにはいかない。
- 2004/09/10(金)
サントリーの緑茶、伊右衛門については前に書いた。味はともかく、CMは良い。
9月に入ってから、新しいバージョンのCMが流れ始めたのだが、私はこのCMが流れるのを心待ちに
している節がある。新しいといっても、シリーズものの最新バージョンである。お茶作りの師匠に
「よう、がんばらはったな」と褒められる伊右衛門。一緒に来ていた妻(宮沢りえ)が夫より先に
「おおきに」と頭をさげる。あげた顔はほんとにうれしそう。帰り道、感情を表さない伊右衛門に
「てれ〜」とちょっと甘えたような感じでよりそい、そっと手を握る妻(宮沢りえ)。
これをはじめてみたとき、わたしはしばし悶絶しましたね。ええ、本当に。
こんなファンタジーがあっていいのだろうか?いや、いいんだ。と何度も煩悶。
それで、いてもたってもいられなくなって、サントリーのHPを探したら、あったあったよ、ありま
した。伊右衛門の広告紹介が。http://www.suntory.co.jp/softdrink/iemon/menu.html
ストリーミング放送で、保存はできないけれども、これでいつでも好きなときに何度でも悶絶できる!
- 2004/09/09(木)
帰宅するとポストに、郵便局からのお知らせが入っていた。年末年始のアルバイトの募集である。
わたしは学生時代4年ほど中央郵便局で内勤、つまり年賀状の仕分作業のアルバイトやっていた。
これは一見退屈なバイトなのだが、習熟するとそれなりに面白さを見出せる仕事なのだ。はじめの
うちは郵便番号を見て、仕分け棚に入れていくのだが、そのうち住所の方をみてしわけができるよ
うになる。これができるようになると、大勢のその他のバイトさんが、郵便番号がなくてはねたも
のを回収して、それを専門に仕分けする仕事につける。
これは別に上司がそういうように指示して就くのではなく、あくまで自主的な判断としてやるので
ある。いわば自分で仕事を見つけてくるのである。番号の書いてあるものなどは、ほとんどやる気
を感じなくなる。あぶれている年賀状達をいかに早くしわけて、待っている人たちに届けるか。そ
ういう使命感みたいなものすらあったと思う。年末の限られた時間では、一便早くなるかどうかで
到着時刻がだいぶ変わってしまうからだ。
しかし、仕事に習熟すればするほど、納得のいかないことが起きる。2年目くらいだろうか。大量
の内勤者が雇われたのだが、彼・彼女らはとにかく仕事が遅い。それはそうだ。いくら短時間にた
くさんの葉書を処理したとしても、給料は変わらないのだ。3年目などは、あきらかにいかに早く
届けるかよりも、いかに時間内で仕事をしないかという人が多くなっていたように思う。おまえら
それでも給料もらってる学生バイトかぁ!と言いたくなるときがよくあった。友達とよく愚痴りあ
った。
たとえ彼らの隣のブースにはいって、郵便番号もない、時には区と町名があっていないような住所
の葉書を、いかに正しく、早くわけるかに異常な情熱を燃やして、すごいスピードで仕分けをして
も、彼・彼女らがそれに感化されるということはなかったように思う。
なんだか、すごいえらそうなことを書いてしまっている。だけど、こうやって「ゆうメイト」募集
の葉書を見るたびに、あのとき感じた「正直者(頑張るもの)が馬鹿を見る」という感覚が鮮明に
浮かんできて、いい思い出がひとつも思い出せないのだった。
ネガティブな思い出話に終始して申し訳ないです。たまにはこういうときもあるですよ。
- 2004/09/08(水)
昨日の話のつづきになるのだが、大丸で「リサとガスパール絵本原画展」というのをやっていた
ので、見に行った。ご存知ない方のために説明すると、リサとガスパールはフランスの子供向け
絵本のシリーズで、リサは白い体に赤いマフラーの女の子、ガスパールは黒い体に青いマフラー
の男の子で、格好は犬みたいなのだが、架空の動物という設定。人間たちと同じ学校に通ってい
る。普通絵本というと、セル塗り(むらのない塗り方)に近い絵が多いと思うが、この絵本は、
油絵なのである。塗りも均一でなく、タッチがよく見える。だからかもしれないが、とても「手
作り感」があって、みていてなんだかほっとするものがある。親が子供につくってやったただひ
とつだけの本という感じがするのだ。
わたしが知ったのは確か去年の11月に神田の本屋にいったとき、洋書のコーナーにあったのを目
にしたときだと思う。それ以来の出会いなのだが、その間に別の雑誌でみたとか、TVの登場した
という話を聞いたこともなかったので、こういう展覧会が開かれるほどの人気があるとは思って
いなかった。(まぁ絵本ですから、それほど劇的な売り上げとかがあるものでもないので。)
この本は、旦那さんが絵を描いて、奥さんが文を書くというコンビで、このシリーズをはじめる
ときに知り合ったそうである。何か、出会うべくして出会ったようなところがあって、うらやま
しいような気もする。さて、展覧会では絵本の原画だけでなく、二人の創作風景や、製作道具な
どもあって面白かったのだが、なかでもいちばん驚いたのは、立体物である。
二人は、劇中に登場するリサやガスパールなどの人物を紙粘土で立体にし、それをモデルに絵を
描いているのだ。また、リサの家が登場する回があるのだが、そのときは家そのものを紙でつく
っている。話がそれるが、家といってもリサの家はすごい。彼女の家は、ポンピドー・センター
(あのパイプがいっぱい外壁にくっついているやつ)のパイプの中だったりする。なんか秘密基
地っぽくてうらやましいと思うのは私だけだろうか...。
さて、一通り見終わったあとのお楽しみは、ミュージアムショップなのだが、あるわあるわグッ
ズの数々。でもこれは絵本の原画展なんだから、その絵本を買わないでどうする!と思って絵本
のコーナーへ。なんとリサとガスパールシリーズは、ちゃんと邦訳も出ているのだ。で、ちょっ
と見てみてなんか違和感がある。で、すたたーと走って、端っこのほうに原著のフランス語版が
あったので、そっちと見比べる。。。。その違いは何かというと、文字なのだ。
原著は、フランス語であるが、すべての文字が作者による手書きなのである。本のタイトルから
裏表紙のあらすじ紹介(ポラロイド写真風の絵がまたよいのデス)、はては著作権表示にいたる
まで、すべて手書き。作者の絵本づくりへのこだわりが垣間見える。それに対して、日本語版は
すべて活字。丸ゴシックを使って、優しい雰囲気を出そうとしているのはわかるのだけれども、
一度原著を見てしまうとその差は歴然なのだ。絵と手書きの文字がよりそうようにある原著と
絵からどこか浮いた感じのする訳書。絵本だけれども、「文字」自体も重要な要素なのだ。
だからといって、日本語のひらがなの手書き文字だったらいいのかというと、それは良いとも
悪いとも、私にはいえない。邦訳の出版社の編集者も悩んだに違いない。訳というステップが
はいる以上、もうオリジナルではない。だったら無理に手書きにこだわることもない、手書き
はオリジナルだけの要素なのだ、と考えることもできる。
この本を子供さんに買ってあげるならば、それはもちろん邦訳がいい。でも、大人が自分向けに
買うならば、フランス語がよめなくても原著版を買うべきだろう。ひとつの本として鑑賞したい
のならば。(意味はわかります。邦訳を読んで覚えるのです。文章少ないし。)
大丸の店員さん、いくら私がフランス語読めなさそうだからといって、「洋書版でよろしいです
か?」と確認しないでください(^^;
- 2004/09/07(火)
昨日の仕事で異常に心身ともに疲労したせいか、頭痛とひどい倦怠で目覚める。起き上がれない
ので、電話して休ませてもらうことにする。あとで仕事を思い出し、電話して後輩に指示してや
ってもらう。ふつらふつらしていると、また地震。もとから頭がぐるぐるしているので、地震で
ゆれているのか、どうかわからなくなる。薬を飲んで一眠りする。
夕方、すこし気分が落ち着く。風がひどくなり始めたなか、ロフトに向かい2年くらい前に電池
がきれてしまった時計の電池を交換してもらう。サービスで10気圧の防水テストをやってもら
うが、「全然問題なくて良い状態です。これからも大事にしてくださいね」と言われ、いい気分。
さて、ついでなのでスウォッチコーナーをのぞいてみると、おや先週あったはずのアレがないな..
アレが終わったからかな?と思いながらもぐるぐる回るがやはりない。アレとはオリンピックのこ
と。スウォッチは、アテネオリンピックの公式時計を担当していて、オリンピックモデルを発売
している、いや「た」のである。オリンピック中に店でみつけて、いいなーと思っていたら、終わ
た瞬間にもうなくなっていたというわけである。
それほど強い執着があったわけではないが、最近のスウォッチのなかではあまり気に入ったデザイ
ンがなかった自分としては、どうしてもあの突き抜けるようなさわやかさなをもう一度みておきた
いという思いがあって、そのまま大丸のスウォッチショップに向かった。が、ここでもやはり店頭
に見当たらず。平日なので、あまりうろうろすると目立つし、店員さんに聞いてみた。すると店頭
には出してないんですが...といって箱を取り出してきた。やった!あれ、なんかすごい箱が大きい。
どうやらスペシャルパッケージらしい。あけてみると、時計の左側にアテネのマラソンコースの立
体模型が。このモデルは"フェイディピデス"といって、マラトンからギリシャ軍の勝利を伝えるた
めに42kmを走った英雄の名前がつけられたものだった。
肝心の時計は、うんうんやっぱりいい。しかし、店頭表示品だったせいかえらく汚れがはげしい。
これじゃぁ買おうって気がなぁ。と思っていたら、「在庫があれば取り寄せできますよ...ふんふん
っと、あぁあります。在庫ございます。」と畳み掛ける店員さん。え、え?あるのか、手に入るの
かと思った瞬間、「お願いします」と頼んでいた。
いやー、当初はそれほど手に入れたいというわけでもなかったのに、あのときの店員さんのセール
スのタイミングは絶妙だったと思う。カジノのディーラーは、席についた客の呼吸のタイミングを
はかってカードを配ることで、お客を「支配」してしまうそうだが、あの店員さんもそれと同じ
テクニックをつかったのかもしれない。まぁ欲しくもない商品などではなく、どちらかというと
欲しい商品だったので、それはそれでよかった。むしろあのタイミングがなければ、決断するのに
結構時間がかかったように思う。届くのが楽しみだ。
「リサとガスパール絵本原画展」を見てから、大丸をあとにした。
- 2004/09/06(月)
昨日の夜中に、もう一度同じ規模の地震で目が覚める。一度ならず、二度までもということで
かなり動揺。あわててリュックに手持ちの保存が利きそうな食料や、ペットボトルのお茶、
着替え、薬、重要書類(免許証、保険証)、現金、ツールナイフ、懐中電灯、ラジオを詰める。
短時間に必要そうなものがそろったのは、日ごろの整理整頓のおかげかも。実家にいるときは
こうはいかなかった。
友人からのメールで気づかされて、寝る前に寝床のわきに靴を持って来た。何も起こらないこと
を祈って就寝。
今朝は、会社にいくとき、念のため昨日用意した装備を一式もっていくことにした。しばらくは
続けてみるつもりである。それほどかさばったり、重いわけでもないので。帰宅時に、コンビニ
で携帯電話の緊急充電キットを購入。これで最低限といえるだろうか。
防災ばかり意識していては普段の生活ができないので、別なことを。
帰宅後、TVを見ているとNHKで韓国ドラマのあらすじ紹介をやっていた。冬のソナタとは違うもの
だ。すこし見たのだが、どうにも違和感がある。これは冬のソナタをちょっとためしに見たとき
にも感じたことで、結局そのまま見続けなかった原因でもある。純愛ストーリー?(なんですよ
ね?)がいやだからとかそういうのではなくて、「吹き替え」に問題があるのだ。
日本の声優さんの能力というものは世界No.1である!と言い切ってもいいと思うのだが、韓国ドラ
マに関して、違和感を感じたのはなぜか?理由は2つほどあると思う。1つは、言語の問題。2つ
目は、慣れの問題。
画面をみていて思ったのが、俳優さんの韓国語をしゃべる口の動きと、声優さんの日本語の声が微
妙にずれているということ。韓国語にはくわしくないのだが、たしか韓国語も日本語も、膠着語と
いって、動詞が活用し、その前後に品詞がくっついていく言語なのだ。この言語体系はひたすら
に長い文章がつくれること、主語、述語の位置が自在であるなどの特徴がある。これに対して、
中国語は孤立語(動詞が活用しない)、英語などの欧米語は屈折語(動詞が活用する。位置関係
によってしか主語・述語が特定できない)という。
何が言いたいかというと、韓国語と日本語は同じ言語体系であるということだけなのだが、それ
がかえって、吹き替えをやりにくくしていると思うのだ。体系が同じゆえに、韓国語の口数と
日本語でしゃべるときの口数は、同じことを話している場合、非常に近くなると思う。(だん
だんあやしくなってきた...)近いが、発音が違うので、口でみるときの言語と聞くときの言語
に相違があることが際立ってしまうのではないだろうか。
もうひとつの「慣れ」は、韓国語の吹き替え自体の経験が浅い、ということだ。
英語の吹き替えなどは、本当にその俳優が日本語をしゃべっているかのように錯覚するほどに
完璧である。それはひとえに、英語の口のうごきと、日本語をあわせるという技術が長年にわ
たって蓄積された結果ゆえのことだと思う。そして、この俳優にはこの声優という専任制度が
違和感を薄めていったのだろう。だから韓国語ドラマもこれから何年にもわたって日本に定着
するようになれば、言語の問題を克服する「技術」が生まれるかもしれない。
ちなみに、英語以外の吹き替えで完璧なのは広東語だろう。カンフー映画の吹き替えなどは
芸術的とさえいえる。ジャッキーチェンは石丸博也、サモハンキンポーは水島裕以外にありえ
ないし、俳優が背中を向けているときに「セリフにない日本語までしゃべってしまう」広川
太一郎など、役者がそろっている。今回の話と全然関係ないですがお勧めです。
- 2004/09/05(日)
夜、突然の地震。結構ゆれるうえ、なかなかおさまらない。
なんともいいしれぬ恐怖を感じて、ゆれがなくなったあとも一時間くらい心臓がばくばくいって
いた。阪神大震災のときに感じたあのゆれ(京都でもかなりの震度を記録した)を、体が思い出
したのだろう。(戸建の実家と違い、マンションだから余計にゆれたという事情はある。)
あれからもうすぐ10年経つ。体はあの恐怖を覚えているに、頭の方の防災意識というのはあの時
以来、進歩がないように感ずる自分である。
中島らもの「とらちゃん的日常」(文春文庫)を読んでゆっくりこころを落ち着かせていった。
- 2004/09/04(土)
NC練習後、NCメンバーのKさん、F栄とともに、同じくNCメンバーであるK原の家にお邪魔する。
東灘の山の手、リビングから見える神戸の夜景はすばらしい。代償は自転車なんかではとても
上れない坂と、出没する「いのしし」。
高低差のほとんどない京都にいると、時折むしょうに高いところに上って、なにかを見晴らし
たくなる。高所恐怖症なのに不思議なことだ。
午前3時ごろまで、こんこんといろんなことを語る4人。
朝、10時ごろから14時ごろまでまたしても、いろいろ語り合う。
ちょっと語りすぎて疲れたが、飲み屋などでなく、薄明かりの静かな食卓で、語りつくす面白さ
を知る。休日の朝、軽い食事をとりながら会話を楽しむ面白さを知る。
- 2004/09/03(金)
ひさしぶりにBK練習に参加。
練習後の宴会は、なんと午前1時半にまで及んだ。最長記録だ。
会社以外に、自分のもどるべき場所があり、お馬鹿な会話をする仲間がいて、話合うことのできる
相手がいることの幸せみたいなものを、しみじみではなく、じんじん感じた宴会だった。
- 2004/09/02(木)
突然涼しくなって、会社の半そでの制服では寒いくらい。
昨日は早く会社を出るつもりだったのだが、急なトラブルで帰るに帰れなくなってしまった。
原因は文字コード+αである。
会社のイントラネットが別サーバーに引っ越すため、わたしの部署のHPも移行作業をおこなってい
たのだが、移行後のサーバーでなぜか、Netscapeでは正常に表示されるのに、IEでは文字化けが起
こるという現象が起きた。全部文字化けならよいのだが、デコードする文字コードをEUC、シフト
JIS、他と切り替えるたびに、化けたり、化けなかったりするというやっかいなもの。
どうやらEUCコードと、シフトJIS、JISが混在してしまったらしい。Netscapeがそれを正しく解釈で
きる理由は不明だが、とにかくすべてのテキストを一旦、EWS(UNIX)からPCにおとして、テキスト
エディタで、EUCコードで保存し、ふたたびEWSにアップした。これで直るはず。
・・・全然直らない。文字コードじゃないのか?
と頭を抱えていたところ、外注さんのプログラマーのKさんが「山Dさん、改行コードがLFとCRが混
じってるみたいですよ...」と教えてくれた。彼の使っているテキストエディターは、改行コードの
判別が容易にできるのだ。
文章の最後で使うリターン、これをうつと改行をあらわすコードが、文章に埋め込まれる。もちろん
画面上では改行として表示される。このコードには二種類あり、LFとよばれるラインフィールド、
CRと呼ばれるキャリッジリターンがある。なぜ二種類あるかは知らないのだが、この2つが混在する
とやっかいらしい。(MACがLF、WINDOWSがCRだったかな?)
とりあえず、両者が混在することが文字化けの原因らしいので、エディタで文字コードはEUC,改行コ
ードはCRで統一して保存。10数あるファイルを開いては保存、開いては保存を繰り返したところ、
みごと文字化けはなくなった。しかし、この解析と単純作業だけで1時間くらいかかってしまい、
帰宅予定時刻を大幅にオーバー。本当は8時前までに京都について、大丸の地下食品売り場で
晩御飯を買うはずだったのに....くそう。
予定というほどの予定ではないのだが、今日はこういうスケジュールでいくぞ!と決めているとき
ほど、このような緊急の仕事が入りやすく、また予期せぬ残業をすることになってしまう。こういう
ときは、たとえ普段と同じ残業時間であっても、なんとなく憤懣やる方なしというか、非常なストレス
を感じてしまう。事実、胃が痛くなった。そんなたいした仕事じゃないのに。ストレスというのは相対
的なものなんだろう。
気持ちをやすらげるために、本屋に寄ってから帰宅した。
- 2004/09/01(水)
いつも暗室を書いているメインマシンが突然落ちる現象が頻発しているため、ノートでノートパッド
を使って書いています。昨日から段組みが変ですが、お許しください。
新聞に「八木アンテナ再分社化」という記事があった。八木アンテナというと、どこのうちの屋根に
でも立っているあの魚の骨みたいな細い鉄パイプの組み合わせのアンテナのことだが、会社組織と
して「八木アンテナ」があることは知らなかった。そのうえに、再分社化とはいかなる事情か。
八木アンテナというと、必ず出てくる話が、戦争中のエピソードで新聞にも話がのっていた。英米の
飛行機を入手したり、暗号書を見ると必ず、アンテナそのものかYAGIということばあって、日本の軍
部は悩んだらしい。で、捕虜に聞き出してみると「このアンテナは日本の技術だ。知らないのか」と
いわれてあわてた、というもの。
わたしは、高校一年生のときにアマチュア無線の、当時は電話級とよばれた四級の免許をとるため
大阪の無線講習会に参加していた。5日間程度の日程である。この話はそのときに先生から聞いた
のだが、先生は「八木宇田アンテナいうのが正しい」と力説していた。宇田というのはアンテナを
発明した八木氏の弟子だそうで、実質的な発明者だということ。真偽はわからないが、いまでは八木
しか残っていないのは無常である。
こういう二人の名前を取った名前の会社というのは結構あると思うのだが、どちらかが脱落する例と
いうのはあまり見たことがない。ヒューレット・パッカード、メルセデス・ベンツ(これはちょっと
違うか。名前は名前。)、P&G(長い)、....といいつつあまりすぐには思いつかない。ジョンソン&
ジョンソン...はジョンソンさんとジョンソンさんなんだろうか?外国の企業に多いようだ。日本では
個人名の会社は多いが一人だと思う。SONYなんかはもしかしたら、MORITA&IBUKAとかだったかも
しれないなぁなどと思う。
八木アンテナの話にもどると、もともと八木アンテナで、それがほか3社と日立国際電気として合併
し、今回再び分社ということらしい。もともとBSアンテナの隆盛で落ち込んでいた売り上げが最近の
BSデジタルの放送開始で、また伸び始めているとも記事にあった。まさかだれもデジタル放送をあの
昔ながらのアンテナで受信するようになるとは思わなかったに違いない。なんかデジタルってイメー
ジがしないものあの形は。
|
|