|
電波暗室 2004/10
- 2004/10/31(日)
「みたいや」と呼ぶ法事。もう三週間弱経つのか...
法事のあと、マンションにもどる道すがら大丸により、靴を買う。私は、基本的にというか、
応用的にも靴は常時一足しかない。社会人としてどうかとも思うが、だいたい2年くらい通勤
や、私生活ですり減らしてから新しいのを買うことが多い。買うのはASICSのPedalaか、同じ
シリーズのWALLAGEと決まっている。
今はいているものは、かつてはいていたものをソールをまるごと取り替えたもので、さすがに
靴底が大丈夫でも本体がだめになってきた。まあそれでも5−6年前の靴だから対したものだ。
ところで、靴のサイズというものを、これまで靴屋さんの店頭で、あっていると思われるサイズ
を履くことで確かめていた。今日も、前に履いていた靴のサイズで、3Eのものを買った。なの
で、本当の自分の足のサイズというものがわからなかった。本当に靴のサイズなのか?実際の足
のサイズと、靴のサイズはずれがあるんじゃないか?
こういうことは原点に立ち返るのが良い。帰宅後、メジャーでつま先からかかとまでの距離を測っ
てみた。ぴたり25.5cm。靴のサイズと完全に一致している!どうでもいいことなのに、ちょっと感
動を覚えてしまった。と、同時にかつて高校生くらいのころ、買っていたスニーカーのサイズが、
確か26.5くらいだったのを思い出した。アレ?小さくなってないか...。スニーカーと革靴ではサイ
ズ適用能力のマージンが違うのだろうけど、1cmも差があるのはなぜだろう。
ちなみに、足のサイズは左右同じだが、幅にかんしては右足が若干大きいので、EEか、EEEか
EEEEか、どれをえらぶかがいつも迷う。まえのは右足にあわせてEEEEにしたが、革が伸び
ると左足がすかすかになることがわかった。今日のところは右足を我慢してEEEである。
- 2004/10/30(土)
かなり長編の夢を見る。いくつかの断片なのだが、舞台はいつも同じ場所で、エピソードの積み重ね
のような感じ。舞台は大学?。学園祭の前日準備のようだ。知り合いがたくさん登場。
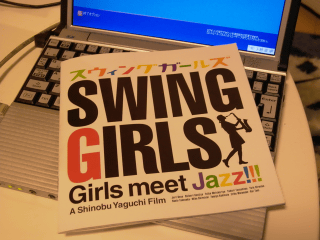
NC練習前に、映画を見に行く。「スゥイングガールズ」!!
なんか、!!をつけると、JOJOに出てくるスタンドみたいだ。
で、映画の話。なぜだがわからないけれど、みる前からわくわくしっぱなし。なぜかというとパンフ
に載っているガールズ達が、指でリズムをとっている写真を見たから。なんていい表情なんや〜〜。
これはきっと楽しくて楽しくて、面白いに違いないと確信。そして、それは正解だった。
音楽って楽しい。みんなとあわせるって楽しい。クライマックスシーン、私は映画をみながら、足で
リズムをとっていた。向こうはJAZZ、こっちは合唱。ジャンルは違うけれど、わかる。伝わる。
「感動」とはちょっと違うのが、監督の手腕なんだろうなぁ。あくの強い竹中直人が目立ちすぎない
し、冷静に考えると説明がいるようなはずの背景とかそんな部分を見事にすっ飛ばしても、ちゃんと
なりたってるし、面白い。
監督・脚本は「ウォーターボーイズ」の矢口史靖監督。あまり知られてない?のかもしれないけれど
神田神保町にある映画・演劇・戯曲の専門書店「矢口書店」が実家であるらしい。画面をみていて、
映画が好きなんだなぁと感じさせるのは、そんな環境のせいなのかもしれない。
大阪に移動したあと、本町の紀伊国屋書店で思わず「スゥイングガールズ絵コンテ集」を買いそうに
なってしまった。いや、ほんとに欲しかったので買ってもよかったのだが、もう一回見てからにしよ
うと思っただけ。絵コンテじゃあ、あのスゥイングは聞こえないから。脳内に刻み付けて自動再生で
きるようになれば、絵コンテでも楽しめるはず!
- 2004/10/29(金)
今日の目覚めは、そんなに悪いものではなかった。
三方が窓の部屋に座り心地の良い寝椅子が置かれていて、わたしはそこに座っている。
まどからは深い緑の山々。あれはたぶん箱根、宮ノ下の富士屋ホテルから見える景色だ。泊まった
ことはないけれど、食事なら何度もしているのでわかる。行くときはいつも雨か、天気が悪くて、
山には霧がかかっていることが多い。その緑。私がもっともリラックスする景色かもしれない。
座っていると足腰や、腕肩をマッサージしてくれる女性がいる。顔はよく思い出せない。疲れが
とれるのを感じる。近づきすぎて、ちょっとドキドキする。
と、いう夢。こんな夢を見て、気分が悪いということはありえない。
BK練習。3〜4人の最小単位のアンサンブルにいくつも分かれて練習する。
隣や、前のひとと、顔を見合わせて、目をあわせて、息を合わせることを感じながら歌う。NCで
最近よくやるけれど、どうも勝手が違うなぁと思ったら、視線の位置だった。隣で歌う女声と身長
差があるから、何もしなくても目があうNCと違って、お互いがより意識して、視線を合わせない
といけない。途中、なんどか視線がすれ違って、ぎこちない。一度だけ、一瞬だけ、互いの視線が
あう。それだけで、息がそろう、声が寄り添う。歌がとめどなく流れる。
そのあと、一緒になりすぎて、音まで一緒になってしまったのは失敗だった。私が間違えたんだけ
ど。これが自然にできるようになるには修行が必要だなぁ、と感じた一日だった。
- 2004/10/28(木)
早く寝ても、しんどいのに変わりはなく。心の問題なんだろうか。
どこかの宿泊施設に立ち寄ると、学生がそこら中で寝ていて、どうも大学学生合唱団(混声)の
合宿所に紛れ込んだらしい、という夢を見る。トイレに入ったら、扉の向こうから女学生にあと
がつかえてます...みたいな文句を言われたところで目が覚めた。混声合唱団の合宿経験はないの
に不思議だ。願望夢か、予知夢か。そういえば、BKには創部以来、合宿みたいなものがない。
トイレにはなぜか洗い場2つと腰掛2つがあった。
11月からの仕事の打ち合わせをする。予想以上に難しそうなテーマ。コンクールやら昇格研修
やらで忙しいのに、取り組んでいけるのか不安になる。10月の仕事がようやく終わりそうなの
で、終わったら一息つきたかった。
1プロジェクト終えたら、強制的に休暇!というような制度ができないだろうか。確実にモチベ
ーションがあがるのだけれど。
- 2004/10/27(水)
研修資料、いきなりピンチ。画面上どおりに印刷されず、ぐちゃぐちゃ。体裁を整えるのに本文を
考えるのと同じくらい手間暇がかかるっていうのは、うーむである。
大量の文章を印字するのが前提の資料で、ベースフォーマットにWordならまだしも、Excelを使うと
は、人事担当者の見識を疑いたくなる。いつか婉曲に罵倒してやりたい。PCの液晶画面に悪態を
つきながら、ひたすら作業作業。
学生時代、研究室にいたころはLaTeXを使っていた。レイアウトを考えなくてもよいのは楽だった。
卒論も修論もLaTeXで書いた。しかし、投稿する学会がLaTeX対応とは限らない。5つくらいの論文は
結局、切り貼りか、Wordで書いたのだった。(私も人の子なので、利器にはさからえない。)
いまはまったく使っていないが、企業に勤める人でLaTeXを使っている人はいるのだろうか...あのtext
ベースの軽さは今でも魅力的なのだがなぁ。
ここ数日、不眠である。正確には寝つきが悪く、起きたとき寝ていた気がしない。会社ではあくびな
どはでないので、睡眠不足とは違うのだろうが、それでも帰宅すると非常に疲れていることがわか
る。むしょうに眠くなるのだが、寝付かれないのだ。今日は、とりあえず早めに床についてみる。
- 2004/10/26(火)
とりあえず研修の資料ができたので、ほっとひといき。これから何度も修正が入るのは確かなの
だが、何もない状態からとりあえず形のあるものができたので、それだけでも気分が違う。
以前から気になっていたことがある。駅前の横断歩道のことである。朝、わたるときはとおりゃん
せの音楽がスピーカーから流れるのに、夜帰るときはまったくならないのである。盲人の方を誘導
するための音楽なので、信号が動いている限り流しているものとばかり思っていたのだが、一定の
時間しか流れないのはいったいどういうわけか?夜流すと響くから地域に配慮してのことなのか?
と考えたが、駅前には一般の民家はまったくないので、考えにくい。第一、昼であろうと夜であろ
うと誘導は必要なはずだ。不思議だ。
ただ、私自身の個人的なことをいうと、「とおりゃんせ」の音楽そのものは、あまり好きではない。
大阪にいったときなど、横断歩道でかならず流れるのを聞くのはちょっといやなのだ。(京都では確
かどこにも使われていないはずだ。)好きではないというか、あの音階と歌詞がこわいのである。
なにしろ天神様であるし、行きはよいよい帰りはこわいなんて、誰が考えたのか。もしこの音階が、
和音階ではなくて、歌詞も「キリスト様の細道」ならこわくなかったかもしれない。なにを言ってる
のか?と思われるかもしれないが、ちょっと真剣に考えたのだ。
あの音階は和の音階だが、この音階は日本人の根源的な音で土着の匂いがきつい。音楽というより
も雰囲気としての何かが伝わってくるかんじがする。それにくわえて、「天神様」である。日本の神
である。日本の神道というものは、八百万の神というくらいで、どこにでも神様が存在する。火の神
様、道の神様、川の神様、山の神様、異郷の人、まつろわぬ民...もすべて神様だ。
神様といっても、そういう神様達は、何かを願いをかなえてくれたり、清廉であったりする感じはな
く、すがる気持ちよりも、畏怖の感情の方がさきにたってしまう。子供の頃、どうしても我慢できず
に風呂場の洗い場で用をたしたとき、「お風呂の神様ごめんなさい!」なんて唱えたものだ。
土着の匂い+どこにでもいる神様=漠然とそこに何かが存在することを感じさせる、あるいは何かを
現出させようとする、そういうものが「とおりゃんせ」にはあるように思うのだ。だから怖い。あり
うべからざるものが、本当にありえるように感じさせる、だから怖い。そんなところだろうか。まあ
天神様は、神様のなかではかなり上級であるので、そんなことを感じるのはおかしいのかもしれない
が、細道には別の神様がわんさかいるんじゃないかとか、想像力が豊かになってしまう。
西洋の音階は、おおむねキリスト教に端を欲していると思う。だからあの音階が、西洋音階ならば、
歌詞がどうあれ、怖さを感じたりはしないだろう。むろん、これはキリスト教に「畏怖」がないとい
っているのではない。畏怖よりも安らぎとかそういう気持ちがさきにくるような気がするのだ。だか
「いきはよいよい帰りはこわい」なんていわれても実感がわかないだろう。
ひょっとしたら、音大の修士論文などを検索したら、このあたりを深く研究している人がいるような
気がする。また、日本の土着に近いと思われる「隠れキリシタン」の歌は、どういう解釈ができるだ
ろうか?いろいろ拡張していくと非常に興味深い。歴史とか音楽とか、キリスト教などにくわしい方
面白いテーマがあったら教えてください。
- 2004/10/25(月)
ちょうど一ヶ月後は、誕生日である。0x1E歳になってから、早かったような、長かったような。
昼過ぎに、急にお腹の調子が悪くなる。突然である。朝食べたものが原因だったり、空調で冷え
たりというなら、前兆があると思うがなにしろ突然であったので、これはどうも昼ご飯に原因が
あるようだ。ごはん、フライもの、きゅうりと鳥の酢の物...この最後のが怪しい気がする。結局
定時退社までに4回くらいトイレにこもるはめになった。ただでさえ定時退社日(本日は給料日)
は忙しいのにたまらんです。
定時退社というと、今週は今日を入れて3回もある!これはちょっとしゃれになってない。残業が
好きなわけではなくて、FLEXを目いっぱいつかっている身としては、就業時間がマイナスにな
ってしまう。なので、残業できる日に貯金するのだが、結局足し合わせると、プラスマイナス0に
毛が生えたくらいにしかならない。残業代も貴重な給与のうち。会社の緊急経営対策としては、こ
れはかなり効果あるだろうなぁというのを身をもって知るのだった。
帰宅すると、管理会社から契約更新の通知。来年1月末なのに、早いなぁ。と思っていると気が付い
た。連帯保証人は父だったのだ...。この通知がこなければ、すっかり忘れるところだった。こういう
ところはなかなか気が付かないものですね。。。。
- 2004/10/24(日)
自宅で仕事。というかこれは自己研修か。
宿題をやるのと同じで、わたしの場合「やる気」になるまでに相当時間を食ってしまう。
実作業時間は現在のところ、3時間半ほどだが、それにいたる間もただ単純に時間を浪費していた
わけでなく、こういう手順でやるか?とか、ここはこういう考察がいるだろうなど、かなり断片的
だが、頭のなかを整理していた。これは学生時代のレポートにおける「考察」パートを書くときも
同じだったが、考えられうるすべての内容をミックスして、考えて考えて最後にしぼりだす。
といっても、その前段階の本当に考えはじめるまでの時間も長いので、自宅で仕事する場合はそれ
を見越してはじめなければならない。
この研修作業をはじめようかと思ってノートを見ていると、こんなことが書いてあった。
『座学はどうして眠くなるのか? 1座学の形態をとっているから 2(空白)』
まぎれもなく私の字でかかれているのだが、書いた記憶がまったくない。内容からして、この前受け
た研修の最中に、睡眠状態で書いたものと思われる。睡眠状態でこんな考察をしているとは・・・
しかし、このテーマは興味深い。眠くなる条件がそろった昼一番の座学でもまったく眠くならない
場合があるし、どんなに意欲があっても眠くて眠くて仕方がないこともある。要因を分析すれば、
研修講師をする立場のとき、役に立つかもしれない。(一年に一回ある。もうすぐ。)
だめだ。いい加減しんどくなってきた。今日はもうやめよう。
なんとかなる。
- 2004/10/23(土)
NC練習。関西までの練習を一度破壊し、再構築するところから始まる。
昨日からの葛藤(?)を未だにひきずっている。答えなどでるはずもなく、悶々とする。
- 2004/10/22(金)
楽しかったり、苦しかったり、いろいろぐるぐるする。
ぐるぐる、ぐるぐる、まわる。
いまは、あまり書きたいことがない。
- 2004/10/21(木)
40冊中、あり19冊、なし21冊。
私の部屋にある新潮文庫のことである。新潮文庫は7年前から「Yonda?」というパンダを
キャラクターにした読書キャンペーンを夏冬にやっている。カバーについているマークを集める
と冊数によってグッズがもらえるのだ。
どこで知ったのか、この前母が突然「集めるのだ!」と言い出したのと、ちょうどたまたま、
この前買った『広告批評』が、「Yonda?」の特集だったので、まぁ数えてみるかと思った
次第。
8年前以上のものは応募マークがついていない。それが21冊。ありが、19冊。こうしてみる
と、意外に少ないなぁという感想。グッズは5,10,20,30,50,100冊区切りとな
っていて、「30冊はゆうにいくだろうなぁ」と思っていたが、ぎりぎり20に届かないという
結果で少々残念である。最近、電撃文庫、コバルト文庫(マリみて)などのライトのベルか、ハ
ヤカワSFの比率が高かったので、伸びなかったのだろう。
グッズの狙いとしては、100冊のYonda?ハーブティー&ポットか、50冊のYonda
?クッション、30冊のYonda?絵本、Yonda?キャラクター人形、10冊のYond
a?ビデオを考えている。まぁゆってみれば、読書人の勲章というか、自己満足の証みたいなも
のだが、どれも結構品質が高そうなものばかりなので、やってみようという気になる。本だけ買
って、グッズだけもらうという本末転倒なことも当然可能なのだが、相手が本となると、どうあ
っても読まずにいられない。先にいったように勲章なんだから、やはり文勲(武勲)を立てねば
ならないのだ。
グッズは毎年リニューアルされているが、応募券はいつのものでも使える。まぁあと10冊の上
乗せに挑戦してみたい。
そういえば、小学生のとき私は図書委員だったが、そのとき「読書マラソン」なるものを企画・
実行したことがある。あのときはページ数ですごろくのようにこまを進めるというのだった。景
品とか賞状とかを作ったのだろうか?憶えていない。
- 2004/10/20(水)
台風接近。会社は14:30まで。
一晩だけ実家に帰る。実家には母と犬しかいないので、不安なのだそうだ。
行ってみると、窓やらあちこちに防犯センサーあり。まだ取り付けていない防犯ライト
もあり。聞いてみると、電気屋さんに頼んでさらに何か取り付けてもらうらしい。
不安といいながら、意外としっかりしていて安心した。
四十九日がすぎて、すべてかたづいたら、銀座にいってみたいという。
京都に暮らしていながら、なぜか銀座通な母である。(若いころに「通った」らしい。)
父も、旅行好きで国内で知らぬところはないほどであった。
私は旅先の切符、半券、パンフレットを集めて保存する癖があるのだが、どうも祖父→父ゆずり
のものらしい。遺品を整理していてわかった。ちなみに母はすべて捨てるか、失くす。
- 2004/10/19(火)
昨日から長袖の制服を着ていたが、今日は雨のせいか特に寒い。今日から冬と認定。
容赦なく、仕事は降りかかる。いつもここに書いているような考察ができず。
夜、友に電話で話しを聞いてもらい、落ち着く。多謝。
- 2004/10/18(月)
久しぶりに出勤。
熱がでてきたので、早めにネル。
- 2004/10/17(日)
父の遺品を整理していると、いつも使っていた引き出しのなかから、手紙が出てきた。
わりとすぐ見つかるようなところに、ほかの書類や写真なんかと一緒にあった。
それは、母から父にあてた、結婚一周年の感謝状(?)だった。30年前の手紙。
いまは、思いを伝えるのに簡単に電話や、電子メールが使えるので便利だ。でもその便利
さゆえに短命だ。手紙は、不便だけれども何年、何十年も残すことができる。時空を超え
て何かを伝えられる...。
電子メールも、いつか時空を超える日がくるんだろうか。それとも、100年先も誰かが
誰かの手紙を見つけて、こめられた思いに驚いたり、恥ずかしがったりするんだろうか。
- 2004/10/16(土)
身内に不幸がありまして、実家に戻っておりました。
はっきり言ってしまうと私の父。亡くなったのは。
今日、NC−VINE間で、おめでたいことがあったので、それがひと段落するまでは、と
思い伏せさせてもらっていた。生きているひと、これから幸せになるひとの方が大事だとい
う考えでの判断。こればかりは、良いも悪いもないと思うが、関係者の皆さんすいません。
しかし、あれだ。いろいろ思うところがありすぎて、何を書いたらよいのかわからない。
救急車、病院、帰宅、通夜、葬儀、斎場。これがこの3日間に一時に起こったことなのか
と思うといまでも信じがたく。感情が表に出てくるまえに、流れ去ったよう。
肥大型心筋の致死性不整脈による心肺停止。不整脈による呼吸困難は、今までも何回かあって
そのたびに、命に別状はなかっただけに、今回のことは家族も、そして当人ですらも、大事に
いたるとは思いも寄らなかったはず。この病気は、はっきりとした根源治療がないのだ。
不整脈がでたら、除細動するしかない。緊急救命室で20回くらいやってましたかね。で
もだめだった。
死亡確認したときは、それはもうチアノーゼがひどくて、「もうだめなんだ」と不思議と諦念
の鎧みたいなのができていた。透徹したような感じ。でも心臓の奥でギューっと締め付けてる
だけで、意思の力で押さえつけているというのは自分でもわかった。でもこれは、技術者とし
て、何かの事実を受け止めるときの心境と同じだったかもしれない。因果なものだ。ありのま
まに感情を吐露することが、素直にできない。強がってるわけではなくて本当にそう。
だが、自宅に着替えをとりに帰ったあと実家にもどると、母が父の好きだった60年代のアメ
リカナンバーをかけていた。それを聞くと涙が抑えられなかった。また、だれかが父の思い出を
語って涙ぐむのを聞くと、悲しみが襲った。
それらを直接の死に対するものを一次的感情、間接的に死を浮かびあがらせるものを二次的感情
と呼ぶならば、わたしは一次的感情が希薄で、二次的感情は人並みにあるということだろうか。
こんなことまで知らず知らず、仮説を立てて分析してしまうなんて...業の深いことだ。
...しかし、近い心臓を持っていて、近い不整脈を持っているというのはなんだか、落ち着かない
もの。ただ、私の場合、父と違って不整脈のトリガーがわかっていること、呼吸はくるしいもの
の呼吸困難には至らないという点などかなり症状が異なるようだ。しんどくてつらいのは変わら
ない。
「だから、独身でいるとか考えなくてええやんで」などと、母はのたまったが、それは考えすぎ
だ母上どの。親とは、都合のよいように考えてくれる...。
やはり、なんだかまとまらないので、今日は終わり。
- 2004/10/15(金)
- 2004/10/14(木)
- 2004/10/13(水)
- 2004/10/12(火)
本日のお酒、吉野川。
さいきん、友と食事をするときに酒をくちにするのだけれど、居酒屋のように単品メニューを
つつく間に飲む感じで、酒そのもののものめずらしさから、ひとくち、ふたくち飲ませてもらう
ということが多かった。
今日、コースの料理を食べてながら飲むお酒にはなんとなく、必然性みたいなものがあった。
料理と料理の間を滑らかにつなぐ、あたかもスラーのように。同じ酒でも料理のたびに異なる
味わい。飲めないからといって、そこでお茶やジュースを飲んだらだめなんだ、と感じた。
飲んだら、そこで終止してしまうようなそんな気がした。
だから、いつも一口、二口の杯も、今日は三口、四口。友人に杯をわけてもらった。
酔っているという実感はないけれど、気持ちが良かった。
ひとりや、大勢ではこういうお酒は飲めないな、と思う。
感謝する。
- 2004/10/11(月)
うれしいことが二日つづくってことはあるものなのだ。
Ensemble Vine、一般A部門シード、全国合唱連盟理事長賞おめでとー。
淀川混声合唱団、一般B部門シードおめでとー。
昨日の演奏について、まずよどこんを先に聞いたので、よどこんから書こう。重複して聞いた人
は同じことなので、許してください。(といっても二人にしか話してないな。)
全体としての感想を言うと、技術的なあらは見え隠れするのだけれど、ほかの団体にはなかった
ものがよどこんの演奏にはあったと思う。それは客席まで包んでくれる何かがよどこんの音楽か
らほわほわーと放射されていたというか、とにかく伝わるもの、それがあった。ソプラノの持続
力のなさ、f系の際の、テナーのつぶのそろい方などは、結構耳につくはずなのにである。がむ
しゃらに、ひたむきに頑張るという感じのものではなく、もっと温かなものがあった。だが、こ
れはコンクールなので、技術的な部分の減点はあっても、そういう技術とは違うものに加点はあ
るのかというと、審査員次第なのでわからないなー、と思っていた。が、ちゃんと審査員にも伝
わっていたようなのでよかった。
つぎに、バイン。一般Bのあと、9日に書いた所要で一旦京都にもどり、15分ほど歌ってから
また石橋にもどってきた。そのため、バインの出ている一般Aの演奏は23団体中、6団体程度
しか聞けていない。そのことを前提に書くと、もっとも一般A,つまり少人数合唱らしい合唱を
やったのはバインではないかと思った。どういうことかというと、「別にAででなくてもいいじゃ
ないか」という団が少なからずあったということ。あと少し頭数をそろえれば、Bに出れる。B
と同じか、あるいはそれ以上の声量がある。Bのような大人数でやるような選曲。
ほかの団体にくらべて、バインは明らかに声量の面ではがくんと落ちるーという始まりだった。
でも、曲がすすむにつれて、そんなことは問題じゃないということがわかってきた。のびやかに、
しゃーぷに、しなやかに進む音楽。気が付くと、わたしだけじゃない、客席のみんながひきこま
れていたように思う。客席の集中力を測定できるなら、それを審査に加えて欲しい、そう思った
くらいである。演奏が終わって、後ろの席の女性が「はぁ〜、素敵...」とため息交じりにつぶや
いていたのが、印象に残っている。
審査発表のまえの講評で、審査員のどなたかの感想に、「Aグループで歌う意味を考えて欲しい」
とあったのは、まさに私が思っていたことと同じで、審査の方向性がきちんとAとBで違うのだとい
うことがわかった。もちろん、いつもそうなのかどうかはわからないが。とにかく、バインの歌を認
めてくれそうだとわかったのがうれしかった。そして、事実満場一致に近い形で、バインは一位をと
った。うれしかった。
つねづね、わたしはバインのこの演奏を、全国の場で、全国から来る人に聞いて欲しい!とひとり
のファンとして真剣に思っていたので、今日のシードも予想できたこととはいえ、いまから全国の
客席がどんな反応をもって、バインの演奏を聴くのか、楽しみでしょうがない。...たぶんというか
絶対に翌日の一般Bに向けたNCの練習があるので、その場にいられないのだが...なんとか抜け出
せないかなぁ練習。
さて、よどこんの全国出場。この発表のときは、思わず近くにいたよど団員と顔を向き合わしていた。
お互い、「えっほんまに?」という顔をしていたと思う。三位金賞であったので、まぁそれはないだ
ろうというのが一致した意見だったのだが、BK団員のK岡によれば、一般A二位の団体にくらべれ
ば、よどこんの音楽のほうが断然いいということだったので、それほど意外な結果でもないらしい。
(実はBKでもまだ、ほとんど知られていないが、K岡の耳はかなりするどく、感想も的確だ。)
というわけで、怒涛の三連休が終わった。個人的には、9,10,11と歌いづくめで、確かに疲れ
もしたが、なんとなく後味のよい疲労感ですごせたのが良かったと思う。明日、ちゃんと起きられる
ことを祈る。。。
- 2004/10/10(日)
わがことのようにうれしいってことはあるものなのだ。
Ensemble Vine、関西合唱コンクール一般A部門一位金賞おめでとー。
淀川混声合唱団、関西合唱コンクール一般B部門三位金賞おめでとー。
くわしいことは明日書こう、そうしよう。
それにしても、石橋商店街の薬局のおばちゃん、この聞いたことのないメーカーの頭痛薬、
あまりわたしには効かないようです(泣)。ばいんの演奏中だけ痛みが消えたのは脳内麻薬
が出ていたからに違いない。
- 2004/10/09(土)
学生時代の合唱団が創部100周年ということで、明日、「内輪向け」のコンサートを開く。
行く気はなかったのだが、東京方面の同期が何人も来ると聞いて顔を出すことにした。何学年
かでまとまって演奏をするのだが、われわれの代が含まれるグループは、私が一回生のときに
歌った「ラマンチャの男」をやるというので、それも理由。どうでもいいが、「ラマンチャ」が
「ラマン茶」と変換されてしまうのはちょっと悲しい。
先輩と同期と後輩が集まるとやっぱり懐かしくてうれしい。ただ、練習で少しかんじたことが
あった。皆、かつて声を合わせた仲間だから、指揮者のちょっとした指示にすばやく反応する
し、声量バランス、歌いまわしなどは、ベースについてはNCよりもよっぽどいいくらいなの
だ。で、気持ちよく歌っていて、ふと「あっここはこういう曲づくりの方がいいな」と思い、
とっさにベースや、ほかのパートにむかって声をかけそうになった。で、ふみとどまった。
この行動は、NCではごくごく当たり前のことで、わたしに限らずみんながやっていることだ
と思う。個人個人の気づきを全体に反映させたり、お互いに声をかけあう。だが、大学学生合
唱団、それもグリークラブの場合、音楽の形をつくるのは指揮者で、団員が意見をいうという
のは最上回生ならともかく、下回生が言うということはありえなかった。
そういう意識がとっさに浮かび、これはまずいと思っていうのをやめた。そして、できるなら
指揮者が指摘してくれるのを待った。....上級生を頂点とする高い統率力、それが大学グリー
の力の源であったと思うけれども、同時にそれが、それより高みにいけない弱みなのだなぁと
そのとき気づいた。そして、OB合唱団であるかぎり、ぜったいにその枠組みから抜け出すこ
とはできないのだと、身をもってしったのだ。NCで歌っている自分でさえそうなのだ。OB
だけで歌っていては、絶対に超えられないと思う。
NCはよく大学グリーOB合唱団と間違われるのだが、実際の演奏をきいてもらえれば、それ
がまったく違うということに気づくと思う。今日集まったメンバーよりも、はるかにへたくそ
で、自分でも驚くことがあるのだけれど、音楽のひろがりという点では比較にならない。本当
はもっとうまくあるべきだと思うけれども...。NCで歌えるよろこびや、幸せをかみしめなけ
ればならないな、と思った一日だった。
- 2004/10/08(金)
ひさしぶりにBK練習に参加。
指揮者から男声がほめられる。これで今年はもうほめられないだろう。
当面の間、金曜日が定時退社日となったので、これからはきちんと練習にでれそうだ。
- 2004/10/07(木)
本日は、更新おやすみです。
- 2004/10/06(水)
日曜日に買った「牛腸茂雄 作品集成」(写真集)をまだ開いていない。
ジュンク堂で写真集を買うと、大概セロファンというか、薄いビニールで包まれているのだが、
これをうまく開いてやって、表紙・裏表紙の見返しに余った部分を折り込んでやると、うまい具合
に扉カバーになるのである。見本誌などはこの手法が用いられいる。
しかし、この作業うまくやらないと、ビニールにも目があって、いい加減に開いてしまうとつつっー
と切り裂かれて、回復不能な状態に陥ってしまう。ようは、じっくり時間をかけて、そうプラモデル
に墨入れしたり、デカールをはったり、塗装するがごとき集中力をもって臨まないとうまくいかない
のだ。ついあせって、びろーんといってしまったあとなどは、残骸となったビニールを前に言いよう
のない、敗北感が漂う。
いまは、どうも心に余裕がない。こんな心持では写真を楽しむこともできないだろう、と自分を納得
させて、今日も表紙だけながめている。
- 2004/10/05(火)
CETEC開催。行きたいのであるが、仕事の都合上難しい。4〜5年前から、大阪での開催
がなくなって、幕張一本。仕事でなくても、週末にふらっと行ける首都圏在住者がうらやまし
い。
こと、この手の展示会となると、幕張か東京ビックサイトかのどちらかしか選択肢がない状態
で、これは関西圏にまともな展示場がないからであろう。インテックス大阪はそれほど大きい
わけではなく、交通の便も悪いので、これにかわる新しくて、「まともな」施設が関西に欲し
いなぁと思う。
今日のWBS(TV大阪)で、会場におとずれた電機メーカー各社の社長にインタビューをし
ていたのだが、各社ディスプレイに力を入れているようで、インタビューもそれが中心。だが
ただひとり、松下の中村社長だけは、今日一番の関心は?と問われ、「デバイス(半導体)」
と即答していたのが印象的だった。半導体は、こういった展示会ではまことに目立たない存在
で、一般客へのアピールの低さは随一であろう。WBSでも、中村社長のこの発言を大きくと
りあげるでなく、さらっと流していた。だって半導体ウェハーがうつっても絵的に面白くない。
半導体業に従事するものとして、もうちょっと一般への半導体というものの重要度とかが認知
してもらえると、モチベーションがあがるように思うのだが、そういう意味で、中村社長のこ
の発言は、ほんの一瞬であったが、世間に「なんで半導体に関心が?」と思わせるきっかけに
なるのではと思わせるものだったので、正直ありがたいと思うのだった。
(業界的には半導体がキーデバイスというのは周知であるが、一般マスコミにそれを明言する
のはまれである。)
- 2004/10/04(月)
わたしの携帯電話の呼び出しは、常にマナーモードになっているので、電話がきたりメールが
着たりすると、ぶるぶる震える。ところが、身につけている状態であっても、このぶるぶるを
感知できないときがあるのだ。ズボンのポケットにいれていると、気づかないうちにメールが
来ていることがある。それではというので、胸ポケットに入れておいても、これも気づかない
ことが何度もあった。歩いている状態では、ポケットと身体が密着する状態よりも、中空にう
いている状態の方が多いようで、そのせいで気づかないようだ。
帰宅すると、床かふとんの上のおいておくので、気づかないということはないのだが、今度は
逆に過敏症になってしまう。身に着けていないので、「ぶるぶる」するときの音で着信を判断
しようとするのだ。身の回り、エアコンや、換気扇などはこの種のぶるぶる音を発生させやす
いので、よく勘違いして、びくっとなったりする。文章を書いたり、本を読んだりして集中す
ると、耳がとぎすまされるせいか、ほんのちょっとの音でも反応してしまう。集中すると、ま
わりの音が聞こえなくなる人がいるようだが、わたしの場合は、逆のようだ。
音と光以外の感覚で呼び出す方法はないものだろうか。たとえば、着信があるとカレーの匂い
がするというように嗅覚なんかどうだろうか。人によってにおいを設定できると面白い。「こ
れはあの人の香りだー」なんていいながら電話をとるというのはちょっとあぶない人かもしれ
ないが。しかし、匂いというものは単独であるものではなく、何かと結びついて思い出される
ことが多いし、なんとなくロマンチックではある。
電車のなかなどは、いろんな匂いが混ざり合って大変なことになりそうだから、技術的に可能
でも実現しないかもしれないな。
ノーベル医学生理学賞で、嗅覚に関する研究が賞を受けたというニュースを見て。
- 2004/10/03(日)
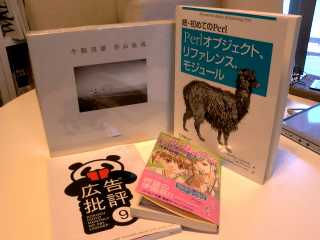
本日の査収物4点。
まったく脈絡がないなぁ・・・・。
- 2004/10/02(土)
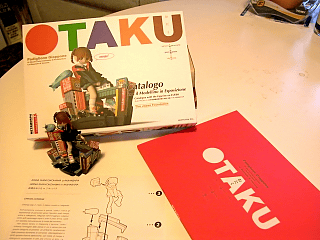
10:00-18:30休日出勤。
会社を出て、NCの練習のため大阪に向かう。昼ごろにNaに電話をもらわなかったら、練習場所
を間違えるところだった。この時間に本町から桜ノ宮まで行く羽目になったら、たぶんくじけて
帰っていたことだろう。感謝。
さて。うえの写真はなんなんだとお思いだろう。例によって駅前の本屋に寄った際に購入した、
「ヴェネチア・ビエンナーレ第9回国際建築展○日本館 出展フィギュア付きカタログ」。
うそをつけ!といわれそうだが真実です。現実はわれわれの想像のはるか先を進んでいるのだ。
どうして国際建築展に「オタク」なのか。それはこのカタログを読んではじめてわかることだが、
このカタログについてくわしく書いてみようと思う。
ほかの多くの人と同じように、私もフィギュア目的で購入したのである。フィギュアの原型師、
それにパッケージデザインが、今年上期に発売され全国のお兄ちゃん達に圧倒的に支持された、
フィギュアつき書籍「週間わたしのおにいちゃん」とまったく同じなのだ。(デザイン:よつば
スタジオ)これは買わないわけには行かないのである。お兄ちゃんとしては。
なので、そこに「逆輸入品」だとか、「ビエンナーレカタログ」などと書いてあっても書籍とし
ての価値に期待などしていなかった。そもそもどういう内容なのか予想しえなかったので、期待
のしようがなかったのである。(なお、誤解のないように言うが「わたおに」の書籍は、フィギ
ュアと同等以上に面白かった。)
ところがである。このカタログ、実に良い。内容の半分は展示の紹介と論文に費やされているの
だが、日本館のテーマ「人格=空間=都市」について、オタクという人格が秋葉原という都市を
規定するという、従来では考えられなかった建築・空間論が展開されているのである。そして、
そもそもオタクとは何か、国内でもこれまで非常にあいまいな定義のまま放置されてきたものを、
展覧会に来る一般の人にもわかる言語で規定化して説明している。
なかでも特に秀逸なのは、精神科医斉藤環による『おたくのセクシャリティ』であろうと思う。
氏は「おたく」とは、『虚構コンテクストに親和性が高い人。(中略)虚構それ自体に性的対象
を見出すことができる人』と"記述"している。("定義"とはしていない)ここまで明快な記述は
これまでどの文献にもなかったように思う。
そもそも、日本のジャーナリズムは最近になって、「アニメ・ゲームは日本の文化」と言い出して
いるのに、それを消費する重要な要因としての「おたく」について分析したり研究したり、論じた
りしたものがまったくない。このビエンナーレのカタログのような「準公文書」的なもの、つまり
「国」に先をこされてしまうとは、なんとも情けないことではないだろうか。国・公のわくぐみで
あった建築を、個(おたく)によって規定するようになったことは実に対照的である。
全64ページのなかには、論文以外にも今回付属するフィギュアモデルの少女「新横浜ありな」の
キャラクター設定が、原型師の大嶋優木の手書き文字によって詳細に書かれるなど、ただのカタ
ログではないところがうかがえる。そもそも「絵」で語られることの多い日本の漫画・アニメ・
ゲームあるが、それらはストーリーや設定というバックグラウンドがあってはじめて「生きてく
るのであって、今回付属のフィギュアであってもそれは免れない。ただの造形物ではなく、その
背景も含めて理解するのがおたくなのである、ということを示したい(多分;)のかもしれない。
さて、内容物で気になるのが一枚紙に書かれたもの。フィギュアの組み立て方法がのっている。
普通、この手の彩色済みフィギュアなどには解説書などないのだが、これは普通に考えるとおか
しいのだろうか。想像と工夫でなんとかする、というかつての(いまもそうか)PC文化の名残
りというものは、そういうものがないであろうイタリアでは通用しないに違いない。しかし、組
み立てだけなら、絵だけですむはずだが、イタリア語オンリーで何か解説が書いてある。フィギ
ギュアとは何かの解説だろうか?それともこのフィギュアの重大な秘密についてだろうか。
ランドセルをしょった女の子であるが、「モデラー」ならばすぐに気づくのだが、服の部分が前後
にわかれ、スカートも着脱できる。つまり、「ぱんつ一丁にしてかざることもできますぜ。」とい
うことなのだ。しかも女の子の上半身には裸に赤いベルトがついている。そう、ご丁寧にも裸ラン
ドセルとなるよう作られているのだ。すさまじい造りこみ!日本のお兄ちゃん達ならともかく、異
国の方達がこれに気づくのかどうか...そのための解説だとすると、すごい。
まぁ、はじめから大量に「逆輸入」されることが前提の商品であるが「カタログ」といえでも、こ
うやって「商品価値」を高める努力(笑)がなされているのは、さすがメイドインジャパンなのだ。
(ああ、そこのひとあきれないで。)
- 2004/10/01(金)
仕事が忙しく、BKの練習に間に合わない。
宴会のみ参加。明日は休日出勤のためあまりテンションあがらず。このところ練習に参加でき
ていないせいもある。
漠然とした寂寥感を感じたまま、帰途につく。あれやこれや考えながらあるいていると、同じ
方向に向かう5人のはるか前方を歩いていた。振り返っても姿がみえないくらい。
せっかくなので、いつもと違うルートで家に帰った。
|
|