|
電波暗室 2005/03
- 2005/03/31(木)
三角黒糖蒸しパンを食べる。フランスパンと並んで好きなパンである。
見た目は小さいので油断しがちであるが、食べ終えると結構お腹がふくれるので、コストパフォー
マンスは高いといえる。記憶が正しければ、子供のころ食べた三角パンは、たしか二等辺直角三角
形で、2つあわせて正方形にしたりして遊んだものだった。ところが最近売っているものはただの
直角三角形なである。まぁただのといってもそれなりにバランスのとれた形状をしているので、別
に気に入らないわけではないのだが、変遷の理由を知りたいものだ。
一つ仮説を立てるならば、昔と今で体積に変化があるかどうかわからないが、二等辺に比べて、
長辺と短辺で構成される今の三角パンは、見た目がスリムである。それに直角以外のひとつの
内角は約30度ほどで、二等辺の45度と比べると差が大きい。これはすなわち、「なんとなく
食べやすそう」に見える形なのではないだろうか。45度では一口で口に入る部分が少なく、
むしゃぶりつくか、角度を変えつつ侵食しなければならない。それに比べて30度くらいである
と、一口で食べられる部分が大きい。そのうえ、角度を変えずともそのまままっすぐ口のなかに
進行可能だと思われる。
もしかすると、これは子供から大人、老人までが食べやすい形状を目指して開発されたのだろう
か。あるいは、若い女性層の開拓を狙ったものかもしれない。三角パンが従来はどんな層に売れ
ていたのかわからないが・・・。(そもそもこんな定番パンでマーケティングをやったりするの
だろーか。)
明日の帰りには、また寺町でフランスパンを買おうかなぁ。
- 2005/03/30(水)
三信ビルは現時点で無事、屋内アーケードの店舗も営業中とのこと。連絡多謝。
 
長野県小布施から春の祝い。
白き輝きの幻惑…。
- 2005/03/29(火)
むかしから、CDやDATなどをヘッドフォンで聞くときに、よくやっていることがある。頭のなかで
歌の歌詞を飛ばしてしまって、伴奏のみを集中して聞くのだ。それも伴奏全体でなく、2小節に
いっぺんしか出てこないリズムセクションであるとか、主伴奏を終えたあとのピアノであるとか、
とにかく陰に隠れがちな部分や、定位の端っこのほうにある音を聞いてみる。
音楽は普通、総体で聞くから要素としての音というのは意識しない限り、独立したものとして聞こ
えない。その音階やリズムをあえて聞くのである。これは聞きなれた曲ほど、それと編曲が重厚な
曲ほど面白いのは想像がつくと思う。1つの曲だと思っていたものが、耳の傾け方次第でいくとお
りにも楽しめるのだ。その結果、逆にそれらを分解していくことで、なるほどこの曲がいいのはこ
こにこういう配置があるからなんだーと、音楽の「ヒミツ」を垣間見たりすることがある。
子供のころ、レコード大賞などを見ていたときに、歌手や、作詞家、作曲家が賞をもらうのは納得
できたのだが、編曲家とよばれる人たちが「編曲賞」を受賞しているのはまったく理解できなかっ
たものだ。作曲と編曲の違いもわからなかったのだから仕方もないが、なんとなく作曲家のほうが
偉い!編曲で賞をもらうなんてずっこいとか思っていたような気がする。(やな子供だな)
むろん、いまでは編曲の妙というものを感じ、それを理解しているつもりだ。どんないい曲も編曲
次第で沈むか、飛ぶかが決まる。それは聞く人みんなが無意識に音楽を総体としてとらえているか
らだろう。旋律だけで成り立つのではなく、複雑な要素がうまく融合してひとつになっていること
を感じ取っているのだ。
そういう曲は、部分部分を取り出して聞いてみてもやはりいいものだ。単楽器に限らず、バックの
目立たない部分での複数楽器の組み合わせだけでも、曲になるほどの力がある。みなさんもお気に
いりの曲があれば、一度試してみて欲しい。
まぁ、いい曲にいい編曲があるのか、いい編曲がいい曲をつくるのか、一概にどちらともいいきれ
ないけれど。
「個体の作り出すものもまた、その個体同様、遺伝子の表現形のひとつ」
という言葉を思い出す。が、関係あるようで関係ない。編曲は表現形のひとつとして、曲から独立
しては生きていけないはずだから。あくまで内在するもの、全体を構成する要素であって、それは
ひそやかに楽しむべきなのだろうな。
- 2005/03/28(月)
合同懲戒、もとい朝会という行事があったため定時出社。昨日早く寝たのに眠い。
午後6時くらいからやっと調子が出始める(遅すぎ!)。なもんで結局いつもより長く残業して
しまった。やっぱり朝はダメだ。
帰宅したときエレベーターで、住人らしい夫婦と乗り合わせた。奥さんが「電気代払った?」と
聞き、旦那さんが「忘れてた、ガス代もカバンのなかや〜」と回答。そこではっと気がついた。
NTTに光ファイバーの料金を払ってなかったのだ!もうすぐ月末だ、やばーい。
実はそんなに驚くべきことではないというか、いつものことというか、毎月こんな調子なのだ。
しかも、督促状が着てから払っている。なんでこんなことになっているかというと、ひとえに銀
行振り替えにしていないせいだ。毎月、支払い案内が来るのだがそれは封筒に入っていて、あけ
るのがめんどくさいのでほっとく。そうすると葉書型の督促状が来るのだが、これは中を開くこ
とのできるタイプで、開くと即コンビニ支払いできる請求書になっている。どちらもコンビニ支
払いできるのは一緒で、封筒を開くというちょっとしたことなんだが、意外と心理的な障壁には
違いがあるのだった。
もうひとつ、督促状の場合「○月○日停止予定」とはっきり書いてあるからかもしれない。
こんなことを続けているとちょっと困ったことが起きる。たまに気まぐれで封筒をあけてしまう
ことがあるのだが、そうするともうすでに督促状で払った先月の料金か、今月の料金なのかがわ
からなくなるのだった。(督促状は一ヶ月くらい遅く来る。)
まぁ自分でもよくないなと思いはじめているので、そろそろ銀行振り替えにしたいのだが、これ
がまた障壁が高くてくじけてしまう。引っ越した当初、絶対コンビニ支払いはできないと思って
電気・ガスはすぐに申し込んだのだが、光ファイバーはしばらく迷ったのと開通に時間がかかた
ので、申し込みをしなかった。みなさんも経験があるでしょう、銀行振り替えの書類書き。書く
ところが多いうえに、ハンコもたくさん押さねばならぬ。しかも、申しこんでから一ヶ月以上
時間がかかるのが当たり前になっているのも、ちょっとなぁという理由。
なんで事務処理にそんなに時間がかかるのか、よくよく考えれば理解に苦しむのだが、なぜか
あたりまえになっている。自分のずぼらさを転嫁しているが、普通のサービス業ならありえな
いことだからいってもいいと思う。リテールリテールといいながら、根本的なところは何も改
善されていないのではないだろうか銀行は。
日経産業新聞を取るとき、とりあえず三ヶ月様子を見ようと思ったのだが、三ヶ月だと銀行振り
替えができるころに契約が終わってしまうから勘弁して、と言われた。で、結局1年契約にして
しまった。あれは新聞屋のテクニックだとしても、ああそうだねと納得できてしまうのだな。
まぁ、新聞はいいです。毎月、集金に来てくれるから。土曜がいいですといったら、ちゃんと
そうしてくれたのもポイントアップ。
さて、その日経産業新聞に、先週口座振替手続きができる携帯決済端末を電機メーカーが発売と
いう記事が載った(3/23付け)どうやら、大手の金融機関では携帯端末による決済が可能になっ
たかららしい。やれやれ、ようやくかぁというところ。保険会社がすでに採用を決めているらし
い。
ここはひとつNTTも採用して、家まで手続きに来てくれないだろうか。無理か。
- 2005/03/27(日)
(昨日のつづき)
オートフォーカス一眼レフに疑問を抱いたのは、オートフォーカスではないカメラを併用してい
たからだと思う。BESSA-Rというカメラは、ピントは手動、シャッタースピードも手動、絞りも
手動、巻き上げも手動という、一昔いやふた昔は前の機能しかないのに、当時の新製品であると
いう一般的には「変」なカメラだった。一眼レフと違って、レンジファインダーという、かつて
一眼レフに駆逐されたファインダーを持つカメラでもある。
カメラメーカーの広告的に言えば、「ピントも巻き上げも全自動だから、人間は作品を撮ること
に集中できる」のがオートフォーカス一眼レフである。たしかにそうで、それですばらしい写真
を撮っている人はたくさんいるし、今私が使っているデジカメも全自動の恩恵にずいぶんと浸っ
ている。
しかし、街歩きで路上探検、観察するような用途の場合、全自動ではどうもしっくりこないのだ。
このまえ、自転車と写真のリズムが合わないと書いたのと同じように、リズムがあわない。何か
を見つけて、ファインダーを覗いて、露出をあわせて、巻き上げて、シャッターを切る。これは
一連のリズムであって、それが街歩きにはよく合うような気がする。全自動だと、前につっこみ
すぎて、物足りない。デジカメの場合、比較的そのもの足りなさがすくないのは、画像がすぐに
確認できることによって充足されているからだと思う。
さて、そういうわけで長い間F80sは使われないままで、もったいないなぁとはずっと思っていた。
自分は使わなくても、使ってくれるひとはいるだろうから売ることも当然考えたのだが、そう思
いはじめたころからデジカメの隆盛が始まった。カメラメーカーから新作のフィルムカメラは出
なくなっていたので、これはもう中古の需要はないだろうから売れないかもなぁということにな
り、機会を失っていたのである。
そんなときに金曜日の話になったのだが、問題はいくらで譲るかである。いったいこのご時世に
フィルムカメラの相場とはいくらくらいなのか、まったく見当もつかないので、中古カメラ屋の
HPを見て回ることにした。それが昨日のNC練習前である。
結果として、意外なことにF80sの中古価格は予想していたよりも非常に高いことがわかった。本
体だけでなく、交換レンズなどは新品の価格と大差ないくらいで取引されている。これはとりも
なおさず、世の中にはまだまだフィルムカメラの需要があるらしい、それも下火の一眼レフであ
っても、ということを示している。ついでにニコンのHPに行ったところなんと、F80s自体はまだ
生産されていることがわかった。HPに掲載されている「お知らせ」には、様々な型番のデジカメ
の生産終了のお知らせが載っているのに、5年も前のカメラが堂々と発売されている。カメラ店
のHPでも、未だに定価の6〜7割の価格を維持していて、需要があるという事実を裏付けている。
中古でも4割程度もあるのだ。正直2割あればいいかなと思っていた。たぶん買取は2割くらい。
というわけで、買取よりは高く、中古より安くの範囲で設定することに決めた。
念のため、今日実際の中古店に見に行ったのだが、だいたい適正のようだ。そして高値なのは
F80sに限らず、ほかのフィルムカメラでも同じだということもわかった。隅のほうにあるデジ
カメの中古の安いこと、安いこと。おそらく性能は高いのだろうけど、こうやって陳列されて
いるなかに混じると、モノとしての存在感がそのデジカメには決定的にかけているように見え
た。精密機械から、電機製品になったものの地位の低さをみるようで、少し悲しい。
(自動車があんなに高値で取引されるのに、電機製品というのはなぜあんなにもダンピングに
さらされてしまうのか。それは「存在感」だけのせいではないとは思うが・・・)
店を出てから、純機械カメラのBESSA-Rにモノクロフィルムを詰めて、京都の縦の通りを行った
り来たりして過ごした。
途中、リニューアルして図書館のようになったジュンク堂で、
・「旧暦ライフ温故知新」(画・文、川口澄子、ピエブックス刊、1300円)
・「鏡の国のおっぱい」(撮影・文、伴田良輔、二見書房刊、1600円)
の2冊を査収。
- 2005/03/26(土)
昨日の送別会で、私の持っていたデジカメに、職場の外注さんのひとりがかなり興味を示された。
聞くと、デジカメというよりも写真好きらしい。長いこと一緒に仕事をしていてはじめて聞いた。
そういえば、むこうはいつも喫煙コーナーなのだ。なんでも使っていた一眼レフカメラを空き巣
に盗まれてしまったそうで、新しい一眼レフを買うか、デジタル一眼レフを買うかで迷っている
という。で、なんの気なしに「私のF80sを買いませんか?」と半分冗談で持ちかけたところ大層
乗り気で、少し驚いた。まぁ普通の一眼レフを買うつもりがあるというのは、昨今は珍しいので
あるが、F80sにそれほどの興味を示されるとは思っていなかった。
F80sというのはNikonの一眼レフで発売は確か2000年か、2001年ごろ。いずれにせよかなり前なの
だ。しかし、三ヶ月という超短期サイクルになってしまったデジカメと違い、フィルムカメラの
一般的なサイクルとしては5年、10年は割りと当たり前だったので、昔なら古いカメラとは言われ
なかったと思う。いまは一眼レフそのものが「風前の灯火」(by源平討魔伝)である。
当時のNikonのフラグシップであるF100の機能を継承しつつも、軽量コンパクト化を狙ったF80は
大変使いやすく、バランスのとれた中級機として、発売直後から大ヒットした。社会人になって
写真を始めた私は、愛機GR1sではカバーできない、鉄道写真などの分野で本格的に使える一眼レ
フとして、F80sを選定した。
ところが、写真を始めてわかったことだが、私の写真の方向性というものは町なかでのスナップ
ショットが主で、風景写真や鉄道写真にはあまり向いていないことを悟った。F80s自体は非常に
コンパクトな一眼レフであるが、やはり街歩きには取り回しづらかった。また、持っていたレン
ズも問題だった。あろうことか、一眼レフ初心者なのに50mmと85mmの二つの単焦点をF80sと同時
に買っていた。この二つの焦点距離は素人が写真をとるには非常に難しい画角を持っている。
画角とは写真にうつる範囲を角度であらわしたもので、焦点の短いレンズほど画角が広い。通常
は35mmレンズの画角が一般的で、街中でスナップを撮るにはさらに焦点距離の短い28mmのレンズ
が有効である。(GR1sのレンズ)
50mmというのは人間の視野角に近いレンズといわれ、そのために練習次第では大変魅力的な写真
をものにすることができる。練習すれば良かったのであるが、それは根気のいることで、はじめ
たばかりの人間にはそれがつらかった。85mmも同様で、次第に使う回数が減り、いつしか主力は
再びGR1sや、取り回しの効くBESSA-Rに移っていった。もうひとつ、F80sそのものの優秀性は少
ない使用回数でも十分わかっていたのだが、オートフォーカス一眼レフそのものの存在に疑問
を抱くようになっていた。前述したBESSA-Rを使いはじめたからだった。
(明日に続く)
- 2005/03/25(金)
会社の送別会まで時間があったので、高槻市内で「スウィングガールズ」のDVDを買う。
パッケージが三種類あって、プレミアム、スペシャル、スタンダードの3つ。プレミアムはすで
に売り切れだった。だって、うちの近所の店でも3月のはじめ時点で予約受付終了していたくらい
であるから、手に入らないことは予想できた。選択肢は2つ、スタンダードとスペシャルのどちら
かだ。1枚か、2枚組かで、値段差は約2000円。通常、DVDのスペシャル版にくっついてくる
メイキングであるとか、予告集というのはわざわざ時間をかけてみるほどの内容があるかという
とそうでないケースが多いので悩みどころであったが、最後はパッケージそのもののデザインで
決めてしまった。スタンダードが映画のポスターと同じデザイン、スペシャルがパンフレットと
同じデザインである。あ、で結局スペシャルエディションを買ったのである。
送別会終了後、酒を飲んだわけでもないのに、すこし脈が変だったのでBKには行かず帰ることに
した。寒い夜空でずいぶん話し込んだもんだから。(今日は彼岸過ぎとも思えない寒の戻り。)
さて、去年の秋映画館で見て以来のガールズである・・・
・・・やっぱり、いいな。すごくいい。
映画館で見たときに感じたこと、そのままをまた感じた。
変わらなかった。楽しい。いきいきする。
ひとつだけ、映画館ではわからなかったこと。ヘッドフォンだからよく聞こえたんだと思うが、
エンディングの曲、ナットキングコールの「L-O-V-E」。LOVEのLは〜、Oは〜とLOVEを分解して
女性に語りかけるおなじみの歌だけど、"L"の発音がすごくよくわかるのだ。(普通"L"のみ単独で
発音してる曲なんてほかにないもんなぁ。)それは"O"も同じ。やっぱりちゃんと”オウ”って二重
母音なのだね。"E"は普通なんだけど、なんといっても白眉は"V"。たっぷり唇で歯をこすって
"ヴィー"なんだ。これが"V"の決定版だといわんばかりの余裕たっぷりの"V"。音楽もいいんだけど
英語の発音だけでこんなに感動したのははじめてだ。ふふふ何か笑ってしまう。たのしくて。
これは本当にみんなに見せたい、聞かせたい映画デス!
ところで映画そのものだけじゃなくて、このDVDの内容についても是非触れておきたい。
DVDのメニュー画面っていうのは結構千差万別で、手を抜こうと思えばほんと文字だけ、絵だけの
手抜きもできれば、こりにこり過ぎて、うざったくなるくらいのものまで本当にいろいろ。スウィ
ングガールズのはどちらかというと凝ってる。メニューが出るまでの映像とアニメーション、メニ
ュー画面のレイアウト、文字、写真の選択、チャプター画面の作り方等々。そのどれもが凝ってる
けれど、うるさくない。統一感がとれていて、シンプルなくらい。そういうデザインはクールな
印象を受けるのが普通だと思うのだが、そこから感じる、いやにじみ出るのは穏やかな微笑みの
ような、はにかみのような。ちょうど川原の対岸で向かい合って演奏するときに主人公の智子が
うかべる笑みのようだ。
それは多分、このDVD製作スタッフの映画に対する愛情のなせる技なんだと思う。映画をみていて
思った、映画製作スタッフの映画への思い。それがそのままDVDのスタッフにも受け継がれている
ような気がした。本当にいいものは、伝染するのだ。たぶん。
本編ディスクのボーナストラックに、曲目の解説がある。映画館でパンフレットを見たときと同
じ解説。パンフを見たときは曲とタイトルが当然一致しなくて、あれどんな曲やったかなぁと
記憶をたぐりよせないといけなかったが、DVDだとさすがに違う。解説の画面にPLAYボタンがあり
押すと本編の演奏シーンが再生される仕掛けなのだ。DVDだったら至極当たり前のようにできてし
まうことだけど、実際にきちんとやっているところがえらいと思う。
この本編ディスクだけでも十分満足なんだが、スペシャルエディションの2枚目。いろいろ入っ
てる。メイキング、矢口監督インタビュー+映画のできるまで、未公開映像といったおなじみの
ものから、サイドストーリー(ガールズ達が出演するミニドラマを7編収録)、簡単JAZZ講座、
舞台挨拶全記録、なんていうものまで。これはこれでおまけの範囲を超えて、ちゃんとプラス
2000円の価値があるなぁと納得した次第。映画の製作話である「スウィングガールズの作り方」
は特に、監督だけでなく、撮影、照明、音楽いろんなスタッフが登場して、それぞれの考えがわ
かって面白い。この映像のエンディングは本編のエンディングと同じL-O-V-Eにのせて、キャスト
にかわってスタッフチームが登場する。
さて、このディスクをあれこれ見ていて、ひとつすごいのがあった。全スタッフロール+DVD製作
スタッフロール。なんとほんとに全員の名前が表示されるだけでなく顔写真つきなのだ。1ページ
に5人表示されてそれが26ページもある!なんて贅沢な使い方か。見ているとなんとなくうれし
い気持ちになる。これだけのメンバーみんなで一つの映画を作った、ひとつのDVDタイトルを作っ
た、その共同作業の記念碑なのだ、これは。
スタンダードエディションを買っていても、たぶん同じように熱にうかされていたように暗室を
書いていたと思う。だから、スペシャルエディションでなければならない理由はない。でも、
このスタッフロールを見ることができたのは、なんとなくちょっと得した気分だ。ちょっと変か
な。ま、いいや。いまはいい気分だ。
- 2005/03/24(木)
万博のことを書こうと思ったら、前に紹介したMASRさんのHPでも機を同じくして書かれていた。
ただ、電車のなかで簡単な文の構想を考えていたので書いてしまおう。
日経産業新聞の4,5面には少し前から、企業や団体が出展する機器のレポートが囲み記事で掲載さ
れているのだが、今日のものはNECが構築したシステムが紹介されていた。会場内の二酸化炭素
濃度や気温などの情報を自動収集し、インターネットで公開するもの。緑地による削減効果など
も三次元アニメーションで表示するという。
なぜ、今日の記事だけとりだして紹介したのかというと、おそらくは万博の開催テーマに沿った
ものだったからだ。これまでずっと見ていて、ほぼ初めてのことだ。今回の万博のテーマを皆さ
んご存知だろうか。・・・・「自然の叡智」。非常に高尚で理知的で、静謐なものすら感じるテ
ーマのはずだ。
ところがだ。この欄で紹介されているのは毎回、ロボットだとか、無線LANだとか、そういうも
のばかりなのだ。産業新聞だからテクノロジーを取り上げるのは仕方がないにしても、とりあげ
たものに、おせじでも「環境にやさしい」とか、自然の叡智に学んだとか、そういう文言がない
のである。これは記事を書いている人間のせいではなく、ひとえに出展している企業・団体の問
題であり、ひいては博覧会を運営している団体の問題ではないかと思う。
要するにテーマは本当にお題目で、結局中身は最先端テクノロジーの誇示であったり、新製品や
先行品のプローモーションでしかないのではないだろうか。この囲み記事に限らず、マスコミに
登場するのは「大画面」であったり、「迫力の映像」であったり「未来のロボット」であったり
するのだ。幕張や有明の展示場でやっている展示会と何も変わらない。少なくとも、情報媒体を
通じて伝わってくるものを見る限りではそうだ。これではわざわざ名古屋(厳密には名古屋では
ないらしい)くんだりまで出かける気にもならない。何のための万博か?万博にそれほどなにか
期待していたわけではないにしても、ちょっとなぁというが本音だ。
もしかしたら、なかには「まじめに」テクノロージーと自然の共生を考えてる出展団体があるか
もしれない。でもそういうものは地味だからたぶん表には出てこないし、会場でも結局目立たず
に注目をひかないかもしれない。悲観的だが。
以前紹介した原研哉の「デザインのデザイン」で語られていることだが、当初万博を誘致するた
めの基本理念の形成、立案にかかわったほとんどの人間、プレゼンテーションやポスター、カレ
ンダー、コンセプトブックを担当した原氏本人を含めて、今の万博事業には一切関与していない。
どこでどうなったのかはわからないが、原氏のデザインしたコンセプトブックの図案や、デザイ
ンを見ているだけで、いまの万博のあり方と当初考えられていたあり方がまったく違うことがみ
てとれる。そこには手書き文字で愛嬌を振りまくような「愛・地球博」といったロゴもなければ
キッコロとモリゾーのような「誰にでも愛される」キャラクターはない。なぜなら、そんなもの
は万博に本来必要ないからだ。何が「愛」なんだろうか。(愛知でやるからだろうな...)
トヨタをはじめとして、愛知・中部地方はモノづくりの町だ。でも、理念のないモノづくりなら
世界中のどこでもできる。中国がまさにそうだろう。日本が日本でしかできないモノづくりのあ
り方、「テクノロージーが進化するほど自然に融合する」(原研哉のことば)ようなモノづくり
を示す機会であったはずなのだ、万博は。(すごく理想的なことばかり書いているけれども、そ
れでいいのだ。世の中にない理想を見せるのが万国博覧会であったはずだから。)
地元の人はどうおもってるんだろうか。すごく盛り上がってたりするのだろうか。新聞を見ると
関西からのツアーも増えているようなことが書いてある。でも、すくなくとも京都の人間はいか
ないだろうな、名古屋には。その工業力を嫉妬しながらも、内心でバカにしているだろうから。
なぜなら、テクノロジーの誇示だけが目的の万博なんて、もう「古い」のだ。
100年以上前の明治28年に開かれた『内国勧業博覧会』において、水力発電による電力で日
本初の路面電車を走らせたのは、ほかでもない京都なんだから。いまさらリニアモーターカーな
んて見たくもない。(負け惜しみか…)
あー、いますごくたくさんの人を敵にまわしたような気もするが、まぁいいか。
たまには刺激的なことも書いてみたくなるのデス。
- 2005/03/23(水)
やはり、とても痛くて一度伏せてから、もういちど読み始めるまで2〜3分かかってしまった。
あゆの問い、花本先生の答え。どちらもつらいなぁ。ハチクロ。
さて、6巻、7巻と竹本君が自転車で旅に出ていることとまったく関係なく、全然その気もなかっ
たのだが、急に自転車のことを考え始めた。さっき届いたダイレクト電子メールにこうあったから
だ。「電動アシスト折り畳み自転車はいかがですか」。電機メーカーだけど、自転車部門もあった
っけそういえば。
電動アシスト自転車、一時期すごいもんができたと思い、実際のってみて驚いたこともあったが、
乗り続けてみるとあの独特の「後ろからずっと押されている感じ」に慣れなくて、あまりいいもの
ではないかもという印象だけが残ってしまった。実は実家にあったのだ。その思いは家族も同じだ
ったのか知らないが、数年前母の患者さんに売ってしまった。
おそらくあのときから改良されてはいるのだろうけど...、どうしても欲しい品物かといわれると
たぶんちがう。そんなことを考えているとだんだんと、普通のいい自転車ならどうなんだと思い
はじめた。私は、ある時期をのぞくと子供のころからずっとママチャリタイプの自転車にしかの
たことがないのだ。(ある時期というのも昔のスポーツタイプのものでママチャリに近い)
ときどきBKの帰りにK岡のマウンテンタイプのものを奪取することがあるが、あれはなかなか
いいなと思う。街中で走るには運転しにくそうだが、遠乗りでどこかをかっとばすと気持ちよさ
げだ。ただ、いまはまだ寒いせいかそれほど熱があるわけでもない。そして、これは絶対欲しい
という自転車が具体的にあるわけでもない。街乗りにもよくて、遠出にも耐えられるようなタイ
プの自転車で、所有欲をくすぐられるもの、そういうのを暖かくなるころに探してみようかなと
思いはじめた。
気になるのは自転車に乗ると写真を撮れないこと。というよりもシャッターチャンスを逃すこと
が多いのだな。歩いていると見える景色が自転車にのると気づかずに通りすぎる。そういうこと
がわりと多い。ああ、いまのいい写真が撮れそうだけど、わざわざ10mも引き返して撮るのは
やっかいだ、というシャッターチャンス。いい写真を撮れそうな気がしたときがやっぱり一番の
撮り時であって、それは歩くスピードともっともシンクロしているような気がする。慣れの問題
かもしれないが。
暖かくなったとき写真を撮りに行くか、自転車で走るか、なかなか難しい選択だなぁ。
追記:22日建築家丹下健三氏、逝去。戦前の最後の大建築家が行ってしまった。
- 2005/03/22(火)
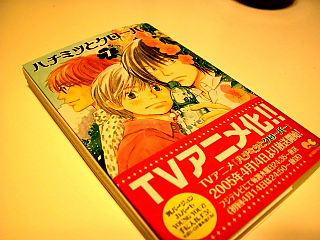
ハチクロ7巻、発売。
今日は、仕事のしすぎで、頭がどよーんと重たいので、いつものように小難しいことは考えられぬ。
ハチクロ読んで、とても切ない気持ちのまま眠る予定。
- 2005/03/21(月)
『宸翰』
あなたはこの熟語の読みと、その意味を知っているだろうか。
こたえは5秒後、CMのあとで(みじかいな)。
読みは「しんかん」。意味は「天皇直筆の書」。
わたしはこの熟語を生まれてはじめて見た。「宸」の字はかろうじて、『紫宸殿』や『宸襟』の字
で見たことがあったが、「翰」はさっぱりである。(「う」って読むのかと思った)
さて、どこでその『宸翰』という文字を見たのかというと、京都国立博物館である。今日は、天気
もよいし、休みであるので午後からの散歩でもするかと思いでかけたのだが、一応目的があって、
国立博物館の写真を改めて取り直すため。昔、フィルムカメラで撮ったことはあるがデジカメで
撮ったことはなかった。(正確には門だけ撮ったことがある。中に入るのはお金かかるので)
今のシーズンは特別展をやっていないので、人も少なくちょうど良い。
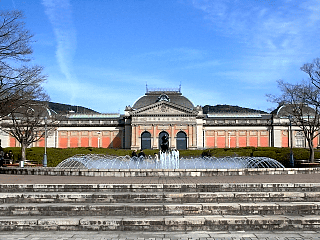

旧京都帝室博物館。明治の巨人、辰野金吾(東京駅、日銀本店の設計)のライバルともいうべき
片山東熊が設計。代表作は、迎賓館(旧赤坂離宮)、奈良国立博物館。
ファサードの上部にはなぜかインドの芸術・工芸の神様のレリーフがある。
さて、一通り撮影を終えて、陳列館へ常設展示を見に行く。写真の本館は、特別展のときのみ使用
されているようだ。常設展示のなかにも、特別展ほどの規模ではないが、特集陳列というものがあ
り、いまは3つの特集が組まれていた。「仏像と写真」「伊藤若沖」、そして「宸翰」である。そ
う、文字だけではなくて実際の「宸翰」を見てきたのである。
陳列されているのは国宝5件、重要文化財10件と、いずれもかなり貴重なものらしい。だって
そうだ、いずれも12〜14世紀の書である。それも作品としての書ではなく、いずれも「消息」
つまり、手紙なのだ。残っているだけでもすごい。しかし、後白河、高倉、後鳥羽くらいまではわ
かるにしても、後嵯峨、後深草、後宇多、伏見、後伏見、後二条あたりの天皇は初耳に近い。あと
わかるのは花園、後醍醐くらいだもんなぁ。文字として特徴的だったのは後宇多天皇と花園天皇だ
ろう。どちらも大変力強く、文字も大きい。後宇多天皇は力強くも、端正。花園天皇は豪放磊落と
いった感じだ。もうひとつ、非常に面白いものがあった。「御手印」といって、書の内容を証明す
るために、朱で手形が押してあるのだ。(後白河、後鳥羽、後宇多天皇のもの。)書だけでも十分
すごいのに、手形である。書という間接的な痕跡ではなく、その時代の頂点に生きた人間の直接の
痕跡。手の形、手のひらの筋まではっきり残っている。平家物語に登場するような人物の生の痕跡
が目の前にあるって、本当にすごいことだ。
他の特集陳列、常設も見てから一時間半ほどで出た。そういえば、今日はやたら着物の人が多い。
大半は女性。卒業式帰りの学生にはみえない。どうやら、今日は着物を着ているひとは無料の日
であるらしい。見ているとなかなかに皆おしゃれ。ほとんどが20〜30代であるのも特徴的。
普段着物など着ない(普通はそうだ)友人が、着物を着て髪を結い上げたらどうなるかなぁー
などと、しばし妄想...。しかしあれだ、せっかくの和装なのに、花粉症対策のマスクをつけてい
る人がいたりして、そうするとパンクロックにしか見えず、なんとももったいないのだった。
日和がよいので、そのまま鴨川の河川敷を北上することにした。以下、絵日記風に沿岸の景色
をつづる。

五条大橋たもと、料理旅館「鶴清」。

松原橋たもと、The River Oriental。ここも元は老舗の料理旅館だった。
いまは、式場・レストランになっている。

五条〜四条間、どこかの日本旅館。こじんまりとした日本家屋。
京都に住んでいるけれど、こういうところに泊まりに出かけるのもよいかも。


四条大橋たもと、料亭「ちもと」と中華料理「東華菜館」。四条大橋を挟んで「いづもや」。
「東華菜館」は同志社関係の建築を多く手がけているヴォーリズの設計。いっぺん入ってみたい。
「いづもや」は京都ローカルのCMで有名。こちらも一度も入ったことがない。

四条付近、うちすてられた自転車。というより、河川敷から転げ落ちたのかも。
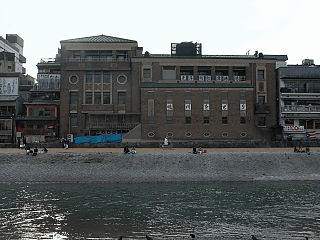
三条大橋近く、先斗町歌舞練場。武田吾一(同志社栄光館、京都市役所ほか)の設計。

二条大橋たもと、こんなところに紅梅が咲いている。(「がんこ寿司」別館の庭。)
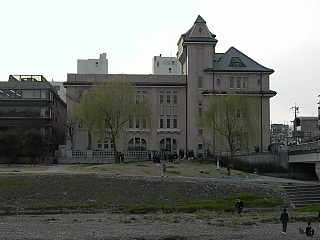
丸太町大橋たもと、3/18に紹介した旧京都中央電話局上京分局、カーニバルタイムス。
なぜか中学生が群がっていた。河原では女子学生が石投げに興じる。なんだったんだろう。

荒神口、京大東南アジア研究センター+アフリカ地域研究センター。(この建物だけ、東岸。)
この後、出町柳まで北上。今出川を西進し、同志社今出川キャンパスを経由。卒業式直後の雰囲
気を味わう。頭のなかに「♪春の調べのうぐいすよ〜」が流れてくる。さすがにもう知り合いは
いない。今出川に戻り、やや西進。室町通を一気に高辻まで下がり、帰宅。すこし疲れた程度の
のだるさ。今日はしっかり眠れそうだ。
おやすみなさい。
- 2005/03/20(日)
お彼岸のため、高雄の菩提寺へ行く。普段なら山のお墓(ご先祖)と寺のお墓に参って終わりな
のだが、今回は父の追善供養のため、彼岸の施餓鬼に参加する。檀家が本堂に会して法事をおこ
なうものらしく、普通の法事の拡大版だと思っていた。
が、本堂に入ってすぐに気づいたのは住職の席以外に、5つの席がしつらえられていること。時間
になると、やはり住職以外は普段見慣れないお坊さんが5人入ってこられた。これだけで、かなり
気合の入った行事であることが見て取れる。さらにお経が通常のものと違った。5人のうち、鐘を
たたく人が先導となり唱え始めると、住職と残りの4人がそれに重なっていく。経を読むというよ
り声明である。時折、住職による「ソロ」である経が入るが、その経も聞いたことのないものだっ
た。よくみれば、普段見ない拍子木や銅鑼のような仏具もある。
書き出すときりがないのだが、もの珍しさもあって1時間20分というかなり長い時間を寝そうに
なることもなくすごした。(風邪を引いているので、もうもうとした線香のにおいで頭がちょっ
とくらくらしかけたが)。ときどき、こっそりと声明の通奏低音にあわせて、声をだしていたのも
覚醒できた理由だろう。どこから声が聞こえるかわからないような感じだったので、隣の見知らぬ
檀家さんには私がそんなことをしていたとは気づかれなかったと思う。経を習ったわけでもないの
に、声明とずれることなく「歌」えていたのは、合唱をやっているからというよりも、日本人の土
着の、刷り込まれたものによるもののような気がする。(コード進行が単純だから読みやすいとい
ってしまえばそれだけかもしれない…)
すべての式が終わり、山を降りてタクシーを待っている途中、ひとつの疑問がとけた。あの5人の
お坊さんのことだ。今日はどこもかしこもお彼岸の行事で人手が足りないはずだ。なのに普通の寺
が5人もの人数を集めるのは大変だろう。だから、本山の知恩院からの派遣なんじゃないかと思っ
ていた。だが、どうもそれは違ったようだ。道に立てられた掲示板には「高雄地区、彼岸予定」と
かかれた紙が貼られており、それには家の菩提寺を含む6つの寺の名と、彼岸施餓鬼の実施日が
記されている。18、19、20、21(午前)、21(午後)、22日と日程がずらしてある
のだ。おそらく、それぞれの寺の住職が協力して他の寺の施餓鬼ために出張する、そういうこと
なんだろう。街中ではなく狭い山のなかの寺だからこその、密接な関係だと思う。
ところで、ひとつ豆知識。京都では寺の住職のことを「お坊さん」とは呼ばない。敬意をこめて
「おっさん」と呼ぶ。大阪弁の「おっさん」とはアクセントが違い、語頭にアクセントがあるの
で注意しよう。
帰宅後、寺からもどったばかりだというのに、物欲に敗退。
昨日、ヨドバシで現物を見てしまったせいだ...。

iPod shuffle 512MB.
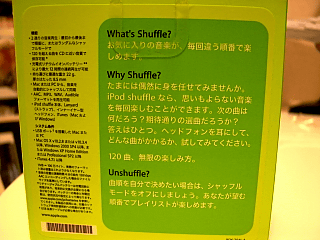
パッケージや、マニュアルの日本語は相変わらずの直訳風味。
原文から一切逸脱しないそのローカライズ精神は、徹底したブランド管理のなせるわざか。
現地法人があるのに、ここまで「翻訳する意思なし」なのは尊敬に値すると思う。この直訳風味
こそが、日本におけるアップルの「味」として認知されていることを狙っているとしか思えない
からだ。(誉めてるんですよ、一応)
- 2005/03/19(土)
NC練習前、ヨドバシカメラで二代目のMDR-E888(3/15参照)を購入。初聞きはCDプレーヤー
で、坂本真綾の"easy listening"。やはり、聞き始めは音が固い印象。帰宅後、音源を同じく
坂本真綾の"Grapefruits"に変えて、初代と聞き比べてみた。思ったとおり、かなり違う感じ。
初代のほうがやはり音がこなれているように思う。それだけ歳月を経ているのだ。このまま引退
させるのは惜しい。
買ったばかりのスピーカーや、ヘッドフォンというものは実際に音を出したことがない。それゆ
えに駆動部が電気信号によって「ドライブされること」に慣れていない。合唱でいうなら音取り
直後の状態に似ているかもしれない。潜在的な能力をもっていても、それを十分に発揮させるま
でにいたっていない状態といえる。いろいろなテンポの音楽、様々な音階すなわち周波数の音楽
を響かせることによって、スピーカーを構成する物理的な部品と部品の組み合わせの状態が微妙
に変化していく。プラモデルの部品と部品が仮止めされていたものが、かちっとはまり完成品に
なるように「あるべきベストな組み合わせ」となるのだ。このための過程を「エージング」とい
う。
エージングに要する時間というものがどれくらいか?というのは機器によって様々であるが、
たとえば夏に買ったヘッドフォンケーブルの場合だと説明書には"100時間かけるべし"と書か
れていた。100時間ってあなた、毎日一時間音楽を聞いても100日かかるってことですよ!
普通ならそれ以上の日数がかかるということになる。実際、私の初代E888の場合、納得できる音
が出るまで1年以上かったような気がする。
というわけで、おろしたての二代目E888の「修行」の日々が始まった。
もうひとつ。
今日の午後、TVで鉄腕ダッシュのスペシャルの再放送をやっていた。今回のスペシャル企画は
「ヨーロッパ一万円でどこまでいける?」。リーダー、達也、長瀬の三人の勝負。スイスのチュ
ーリッヒがスタート地点である。そう、ここからだとフランス、イタリア、オーストリア、ドイ
ツのいずれの方面にもいけるのだ。(列車が主だと思ってたら、陸路、水路のルートも様々)
駅の係員、道行く人、お店の人たちに話し掛け、交渉してルートを決める様は真剣だけど、楽し
そうだ。ツアーでもない、バックパッカーでもない。ゆるやかな「勝負」。ああいう旅を一度や
ってみたいものだ。
それにしても初夏のヨーロッパはなんと美しいのか。達也のマッターホルン越え然り、長瀬のリ
ヒテンシュタイン縦断しかり。しかし、なかでも心奪われたのが、リーダーのとったバーゼル経
由でのフランス行きの一シーン。おいしいワインを求めての移動という、当初の目的を忘れがち
な道の途中、路地の奥に突然広がる葡萄畑・・・。なだらかな丘を埋め尽くすの青い緑の房。
あの空の色と、葡萄の青のコントラストは、湿気の多い日本ではたぶん見れないだろうと思う。
あの景色をこの目で見てみたい。できるなら、飲めるものならワインも飲んでいい気分になって
みたい(しんどくならない程度に)。
私の会社は現行の制度が続くならば、入社10年でかなりまとまった休暇がもらえることになっ
ている。まだ少し先だが、そのときはヨーロッパを列車で周遊して、この夢を実現できるだろう
か。(スミソニアン博物館にも行ってみたいのだが。いまは7:3でヨーロッパに軍配)
- 2005/03/18(金)
BK練習。練習後、小規模飯会@ろぐ。終了後、K岡と二人でR嬢を家まで送る。徒歩だと35分
くらいかかり実は遠かった。よくよく考えると、そこからだとそのまま実家まで帰れるくらいの
距離であった。千本を下り、寒いので三条会のアーケードを通って、そのまま烏丸まで帰った。
よく歩いた。
皆さんは河原町丸太町にあるカーニバルタイムスというレストランをご存知だろうか。ここはもと
もと京都中央電話局上京分局の建物で、大正13年建築の由緒ある建築である。装飾性はあまりな
いが、西洋建築にはあまりない大きな屋根が特徴のなかなかスマートな建物で、傍らを流れる鴨川
とよく調和している。
この建物を設計したのは当時の逓信省営繕課に所属した吉田鉄郎という建築家である。彼の設計し
た建物が、あと2つ現役の建物として東京と大阪にひとつずつ残っている。
話は、今日の昼に飛ぶ。昼食後に組合の事務所でいつものごとく週刊ダイヤモンドを読んでいた。
(どうでもいいことだが、ダイヤモンドを知らない人が聞くと、『週刊宝石』と混同されたりする
んだよなぁ)たまたま時間があったのでいつもは読まない政治評論のページを読んでいると、そこ
に本筋とは関係のないが、とても重要な記述を発見した。
記事の内容は郵政民営化の国会議論の話だったのだが、3月3日に郵政検討委員会で答申された
内容が問題だった。「東京、大阪の両中央郵便局を高層化し、賃貸オフィスにより収益をうる」
という内容。実施時期は民営化の2007年を目処に。寝耳に水とはこのことである。
職場にもどってネットで検索したところ、3月2日づけのニュースで政府がこの方針を発表し
たとあった。
そう、くだんの高層化がもくろまれている東京中央郵便局、大阪中央郵便局こそが、吉田鉄郎の代
表作にして、現存する残り2つの建物なのである!

東京中央郵便局(2002.04.30撮影)
東京中央郵便局は東京駅丸の内南口を出てすぐ左手に位置する、白いタイル張りがひときわ目立
つ建物である。角地の形状に沿ってゆるやかに描く曲線が優美である。インターナショナルスタ
イルと呼ばれる柱と梁が中心の直線的なスタイルで、装飾性はなく大変シンプルであるが、その
連続性には見るものを捕えて離さない魅力がある。昭和初期のモダニズム建築の傑作である。
一方の大阪中央郵便局も、東京と同様駅の真横に存在する。大阪駅桜橋口を出て右手に黒っぽ
いタイル張りの建物がそうである。角地にはなく道路に直角に接するため、東京中央郵便局のよう
な曲線の優美さははないが、やはり直線で構成されたスタイルであり、地味ながらも存在感のある
建物である。東京が昭和8年、大阪が昭和14年の作。戦時色が濃くなっていく時代だったため、
当初、大阪も白タイル張りの計画であったのが、黒(グレー)に変更されたと聞く。
両方の建物とも、当時国内だけでなく国際的にも高い評価を受けている。
このまえ話をした「三信ビル」は昭和4年の作であるが、まったく違うスタイルの建築であるのが
実際に見てもらうとわかると思う。(建築家によってこれだけ建築というのは変わるのです)
だが、どのビルもやはりどこかに”時代の空気”というものがあるように感じられないだろうか。
私自身がその時代を生きたわけではないが、戦前の昭和のどこかストイックな雰囲気をただよわせ
た品格のあるたたずまい。都市の表玄関に存在する建物としてふさわしいと思う。
今回、ネットで検索した新聞社ニュース記事、どれを見ても高層化によって壊されようとしている
この両郵便局が、吉田鉄郎の代表作であること、高い評価を受けた歴史的な名建築であることにつ
いてまで掘り下げたものはなかった。大阪の一部記事のみが、梅田の戦前の建物と紹介するにとど
まっている。明治、大正のいわゆる「赤レンガ建築」であれば、こんな扱いではなかったように思
う。いわゆるオフィスビル建築というのは近年になるまで、建築に関係深いひとびとの間でもあま
り評価されていなかったようだから仕方がないといえばそうかもしれない。よくよく見ないとなか
なかその魅力には気づかないかもしれないが、それでも立派に都市のランドマークとしての役割を
担っているのである。往々にしてなくなってから気づくのであるが。
まだ、政府方針であり、3日の検討委員会では建物の価値の話は当然出てこないにしても、そもそ
も賃貸事業としての見通しが激しく不明瞭であるということで、与党内からの批判が集中したよう
だ。民営化の是非、うんぬんはここでは書かないにしても、確かに政府発表の試算はおかしい。
賃貸事業だけで数十から数百億の利益が出るというのだから。
六本木、汐留、品川、丸の内、八重洲の再開発で東京は今、オフィス・高層住宅の供給過剰に陥っ
ているということは、素人目に見ても明らかなのだ。いくら東京駅前だからといって、あまりに天
下り的な発想ではないだろうか。大阪にいたっては、大阪駅前という立地であっても、今の関西経
済の情勢からして、需要そのものがあるように思えない。
ということで、ここはなんとか高層化案だけは廃案になってはくれないかと思っている。かつて
東京駅も同じような運命をたどろうとしたが、いまは逆に往時の三階だてドームを復活させよう
という話が決定されているくらいだ。これは多くの一般の人たちの署名運動が発展した結果だ。
ただ、多くのひとが利用する駅とは違い、郵便局という建物の性質上、そこまでの愛着を一般の
人たちに持ってもらえるかというと、かなり難しいといわざるをえない。
民間の建物でない分、逆に保存される可能性が低いというのが今の日本の現状である。
残念な結果にならないことを切に祈る。
- 2005/03/17(木)
昨日の疲れがたたってか、いつもより30分遅い出社となってしまった。(だめだ_| ̄|○)
今日はドリンク剤を飲んだせいかなんとかなった。いま、あるツールの仕様書を書いている
のだが、これはなかなか疲れる。午前中から夕方にかけてやっていたプログラム作成の方が
気分的には楽である。(プログラムは「動く」ので、「結果」がすぐわかるのが良い点)
プログラムというのは文法が決まっていて、それを逸脱すると当然動かない。逆に考えると
こうすれば動くというある一定の形がある。どういうアルゴリズムにするかや、より効率的
に動かすための工夫を考えるのは手間であるが、それはプログラムの領域のなかで思いをめ
ぐらせば良いので範囲は限定される。(プログラミングが簡単だという意味ではない)
だが、仕様書というのはそういう限定された要素というものが少ない。(いや、本当の仕様書
というものはそうではないのだが、プログラミング工学を勉強したわけではないし)限定され
ない要素のひとつが言語だ。日本語で書くのだけれど、プログラムと違って決まった用法とい
うものはないから、多様な書き方ができる。当然だ。そうすると、いかに考えている仕様をわ
かりやすく、かつ簡潔に書くかという工夫が必要になり、その部分にかなり頭を使うのだ。
書く内容もそうであるし、全体の構成も考えないといけない。この順番ではこちらの機能の説
明がややこしくなるし、あっ、これを説明するならこれも書かないと、という感じで要素が増
えることも多々ある。プログラムと同じくらい、全体と細部との関係を把握しなければならな
いので、頭がこんがらがることがある。そうならないようにはじめに項目を決めて目次を先に
作るのだけど...だいたい当初のものより構想が膨らむ。そうすると関係性も増える。
というわけで、数ある仕事のなかでも頭が疲れるのであった。
文系のひとからすると、理系の人間がこんなに文章を書いているとは思いもしないかもしれない。
特に学生はそう思うだろう。文章といっても論文とも少し違うのであるが。ただすべては読む
人を納得させ、内容を理解させるものでなくてはいけないという点では似ているかもしれない。
そのためには文章力というものはとても大切なのである。理系だから必要ないということは
決してない。
文の構成を考えるという意味では文系のひとも、数理的な思考・概念が必要だと思うので、文系
理系という区分けはあまりすべきじゃないと常々思っている。なのになぜ高校生とかの早い段階
で分けてしまうんだろうか。
理由の考察はいろいろとできるけれど、しんどいのでやめ。
寝る。頭の重いの重いの飛んでゆけ〜。
- 2005/03/16(水)
うぃー、いつもとそんなに変わらない時間しか働いていないのにこの疲れっぷりはなんだ。
やっぱり、一定以上の早起きは私には向かんのだろうか。おとついの一時間早め出社がぎりぎり
の均衡点みたい。

お彼岸も近いのでおはぎ...ではなく、今川焼きを買ってきた。あんこのお菓子は好きだ。
コンビニで柿の種を買う(お菓子ばかり買ってるなぁ)。パッケージを見るとコンビニのプライベ
ートブランドであるが、製造者を見るとやはり亀田製菓である。昔は結構TVで亀田製菓はCMを
流していたと思うのだが、最近はまったく見なくなった。お菓子のような商品は流通のほとんどが
コンビニ経由になってしまったから、そのことと無関係ではないはずだ。
こういう「おかき」系商品というのは定番商品だから、緑茶飲料のような商品棚をめぐる争いとは
無縁だろうし、一定量の出荷が見込めるだろうから、なかなか考えたなぁと思う。OEM(相手先
ブランドによる商品供給)というのは電化製品や、製薬の世界では結構普通に行われていたと思う
けれども、そもそもあまりブランド力が必要と思われないこの世界で、コンビニのブランドと組み
あわせたこと(ここでいうブランドはネームバリューというより、コンビニにいったらあれ売って
るという、連想作用を指すと思う)は発想の転換というか、誰も考えなかったことだろう。
米菓類の出荷量は増えているのか、減っているのかはわからないが、老舗のメーカーもしっかりと
生き残りの戦略を練っているということなんだろうなぁ。経済は専門ではないので、ひじょうに素
人くさい分析であるが、そんなことを思った。
さて、明日も一応、一時間前出社を目指してみる。
がんばろう。おやすみなさい。
- 2005/03/15(火)
疑う人がいるかもしれないが、今日ちゃんといつもより一時間早く出社できた。えらい!
(えらくない)
「あぁ、早いねぇ〜」と思って居室にいったら、9割方出社してたのでちょっとショック。みんな
勤勉すぎる。午後FLEX解除で定時退社だったせいもあると思うが、そうでなくても早いからな
あ。ほとんどワーカホリックだと傍目に見て思う。みんな既婚者なのによく家族がなんもいわんな
とも思う。大阪から長岡天神まで通っていて、朝8時に出社して、夜10時半に退社する同期がい
るのだ。しかも新婚ちゃうかったか。私が怒ってもしゃーないが。ひとそれぞれだし。
夏のボーナスのときや、暗室の書き始めのころにヘッドフォンの話を書いた。そこで書いたのは
映画や、家で音楽を聴くときに使うSENNHEIZERのHD-580の話だった。HD-580はオープンエアーと
いって、見た目は耳を覆っているスピーカーがついているが、実は音は外に抜けるタイプなのだ。
ヘッドフォンをしている側に近づくと、小さいが音ははっきり聞き取れるので、音がいいからと
いってもこれを外で聞くときには使えないのだ。もちろんでかいからっていうのが一番の理由だ
けど。で、外出時にCDやSDオーディオで音楽を聴くときに使うのが、SONYのMDR-E888なのだ。
MDR-E888はインナーイヤフォン、つまり携帯音楽端末で聞くときに一番よく使うタイプだ。最近
出てきた耳栓のように耳の奥まで差し込むものでもなく、ごくごくノーマルな耳のくぼみに押し
込んでひっかける式。見た目はまったく普通。でもこれがSONYの現行のイヤフォン"NUDE"のなか
では最高ランクに位置づけられている。何が最高かというと、もちろん音質である。(値段も相
応に高いけど)
「そんな音質って変わるの?」と思うかもしれない。これが全然違うのだ。別にクラシック音楽
とか、合唱のアカペラを聴かないと比較できないような「微妙な違い」ではなくて、わたしの聞
くようなゲームやアニメの主題歌、サントラといった普通の音楽(普通じゃないかもしれない)
でもはっきり体感できる。(クラシック>アニメ音楽という比較をしたいわけじゃないが、世間
一般には、このような構図が成り立っている節があるのでわかりやすいたとえとして使った。)
なにが一番違うかというと、音の解像度だと思う。どこまでも澄んでいてて、きりりと立ち上が
り、さらりと立ち下がる。これは抽象的な表現に聞こえるかもしれないが、音はスピーカーによ
って電気音響変換される信号なので、その立ち上がりと立下りの様子を可視化すれば、実際に
このような印象をうけるはずだ。原音の信号に対して、いかにタイムラグなく立ち上がるか。
それが、音の違いになって現れる。だらっと、時間をかけて立ち上がれば、もとの音楽とは
まったく違う印象になる。これを応答性という。電気信号には過渡応答という時間に依存する信
号変化がつきもので、これは信号が伝わる線に含まれる抵抗分(CR)によって変わる。音響信
号の場合も同じだが、電気抵抗とちがってより物理的なものが抵抗になる。スピーカーを駆動す
るコイルや、スピーカーそのものがそうだ。
はっしょっていってしまうと、こういうイヤフォンを構成する材料の違いによって音が変わるの
である。値段の違いはその材料の違い。高い材料は、こういった応答性やそれ以外の特性が普通
のものより格段に良いのだ。オーディオの世界には奇妙な迷信が多いのも事実だけれど、こと
音が出てくるものであるスピーカーや、イヤフォンは高いものはそれなりにいい音を聞かせてく
れるというのは割と事実。(あんまり高いと、飽和してしまって区別がつかないけれど…。)
まぁしかし、高い材料を使っているからというのは極端な話で、じっさいはそれをどう組み合わ
せているかが最終的な結果になる。それが各社の「音づくり」というものなんだけど。
わたしは、このMDR-E888を買うまえに、3つくらい各社の割とランクの高いものを買って、比較
してみたが(6年くらい前)、どれも自分の好みではなかった。そう、深みが足りない。これは
ほんとうに抽象的だ。イヤフォンをつけることで、そこに別の「音だけの世界」が広がる。この
広がりがどこまであるのか、トイレくらいなのか、ワンルームくらいなのか、教室くらいなのか。
本当に良いイヤフォンというのは、もう一つの地球がそこにあるくらいに感じる。さえぎるもの
のない、どこまでも広がる地平線。南極大陸のど真ん中にたったような気分。でも光は見えない。
音だけ、音だけで構成された澄んだ世界。私は微妙な音程も、和音のきまりも、自信をもって指
摘したり、絶対音感で歌うこともできない。でも、音の広がり、音場のもつエネルギーのような
あいまいなものの違いは、なんとなくだがわかるような気がするのだ。その感じた違いの結果が
MDR-E888なのだ。非常に大層なことを言うまでもなく、音楽な好きな人たちの間ではすでに評価
されているイヤフォンなのだけど。(音には好みがあるので、これが一番とかではない)
こんなちいさな器械に世界がつまってる。すごい、すごい。
ときどき、そう感じながら音楽を聞いている。(ちょっとかっこつけてみた)
しまった、明日は午前も午後もFLEX解除。今日よりもさらに早く起きないと。
寝る前にごはんたかにゃー。
そういうわけでおやすみなさい。
3/16朝、追記。眠い。
一番、いいたいことを書くのを忘れてた。今使っているMDR-E888、接続部のあたりの接触が悪く
なってしまって、ときどき右側から音が出なくなる。移動しながら使うと、ぶつぶつ音がとぎれ
てしまうのだ。ということで新しいやつを買わないといけないなーと思うのだが、いまだにE888
が最高クラスで、これを超える機種がないらしい。むかしあったE464の復刻がマニアから要望さ
れているらしいので、もしかしたらE999という形で出ていないかと思ったのだけれど。
- 2005/03/14(月)
仕事で、どうも集中力が欠けぎみである。忙しいはずなんだが、目の前のこまかい仕事に手がの
びて、大きなやつに手がのびず。あいかわらずエンジンかかるのが遅い。ここはあれだ、荒療治
をやってみる。あした、いつもより一時間早く出社する。公約する。明日できたら、その次の日
も考えよう…と思ったんだが、あさっては春闘(死語かも知れぬ)の回答指定日なので、必然的
に早く出社しなければならないのだった。(FLEXが解除される)
だいたい、うちの職場は予約制の機器を使う関係上、早く来ても遅く帰り、遅くきても遅く帰り
というパターンなのだ。早くて来て、早く帰るってのが理想なんだけどなぁ。予約が20〜22時に
あったたりしたら目も当てられない。7〜9時ってのも一度あたったけど、死にそうだった。
去年の春闘でも同じこと書いてるな、たぶん。
日本海弁当を買ってきたら、↓が二つも入ってた。

ほんとうは白身のフライにかけるソース(袋)が入ってるはずなんだけど。もしや?と思って、
吸ってみたが、両方ともしょうゆだった。やはり、この容れモノは「しょうゆいれ」なんだな。
正式名称とかあるんだろうか。それと、ものごころついてはじめて目にしてから形がかわってい
ない気がするのだが、モデルチェンジとかあったのだろうか。あと、どこでつくっているのだろ
うか。
こういうことを考えるのは結構、子供のころからのくせで、いろんなものに対して、「ここにい
ま存在するということは、どこかで作ったからだ。ではどこで?」とよく思っていた。それは特
に日用品に多くて、輪ゴム、わりばし、旅館の歯ブラシ、洗面器、たわし、アイスクリームにつ
いてくる木でできた匙、弁当の容器、などなど。電化製品だとか値の張るものというのはたいが
いメーカー品で、ブランドがあって、だいたい説明書がついているからそれに製造場所も書かれ
ているけれど、こういう日用品にはブランドはあっても知る人ぞ知るという程度だし、説明書不
要だから、どこで誰が作ったのかもわかりにくい。さっきの金魚のしょうゆいれなんて、本当は
淀川あたりで、自然に繁殖しているのじゃないだろうか?それをおっちゃんが毎日、すくって近
所の荒物屋さんに卸しているのだ。(中島らもだったら、そう答えたかも知れないナァ)
そんなふうに思えるほど、実は身の回りには雑多で、その数だけどこかに工場があるなんて信じ
られないほどのモノがある。どんなに質素に暮らしていても、100はくだらないほどの。
そうやって疑問に思ったものの製作現場に出くわしたことは一度もないのだが、ときどきその
断片をかいま見ることがある。今日、風呂に入っていたときに洗面器をひっくりかえすと、
「販売者:イズミヤ 大阪西成区、製造者:ソーコー 東京都中央区東日本橋」と書かれた
シールが貼ってあった。この洗面器はお江戸日本橋生まれの、大阪西成育ちという波乱万丈?
ともいえる人生を送って、いま我が家にいるのだ。こういうことが少しでもわかると、愛着と
まではいかないが、なんとなく感慨深い。知っている地名だったりするとなおさらだ。
最近は、こういった日用品のほとんどが「中国製」とだけ書かれていて、非常に味気ない。
想像できないからだ。中国なら中国でいい。せめて、もう一段階の地名が欲しい。そうすれ
ば、アトラスでも広げて、ほほうここで作られたのなら、このルートを通って、日本へは船
便だな、とか思い巡らすこともできように。
おお、もうこんな時間か。
おやすみなさい。
- 2005/03/13(日)

スゴイダイズ、1000ml。飲み終わったあと飾ってみたい。
(隣は比較のための料理酒180ml。)
朝、寝ていた。金曜の晩からのどの調子が急に悪くなったので、昨日も寝る前に感冒薬を飲んだ。
この薬は大変よく効くけれども、異常なほど眠くなるのでつぎの日が休みであったり、休む覚悟を
決めたときにしか飲めない。そういうわけですごくよく寝た。
昼、実家に帰る。が、留守。母に電話してみたが通じない。うっかりしたことに鍵を忘れた。
しかたなく、阪急西院まで歩いて帰る。途中で、スゴイダイズと野菜生活と、正露丸を買う。
金曜の夜から、お腹の調子が悪いのである。土曜の昼、NC練習に行く前のいきつけ(?)
であった阪急そばで、てんぷらそばを食べる。270円。てんぷらはお腹に悪そうだ。でも、
あとで正露丸を飲むからまあいいかと思う。
西院の駅から阪急に乗るのは久しぶりである。実家や、実家の近辺では「なつかしさ」のよう
なものはほとんど感じないのに、ここは不思議となつかしい感じがする。烏丸で降りるとき、
ああいまはここが自分の「駅」なんだと思った。
自宅に帰る途中で雪がひどくなる。あとからあとから降り続く雪を見ていると、まるで自分が
無限に落ち続けるような錯覚に襲われる。映画のフィルムの同期がはずれて、映像はずっとそ
こに映っているのに、つねに下降しつづけているようだ。自分の目にうつる都市の風景と、ま
るで相容れないように、雪は自分だけの位相を持っていて、同調しない。意識して錯覚をおこ
すと面白くて、しばしぼーっとする。この楽しみは私だけのものか、それとも誰しも感じるこ
となんだろうか。
夜、京都シネマで「トニー滝谷」を見る。私は村上春樹暦は浅いが、始まりも終わりもすべて
が村上春樹の透明で孤独な世界で満たされていたように思った。パンフレットに載っていた
監督、市川準の言葉『全部説明してくれるようなテレビ的な映画って貧しい。』。映画を見終
わったあとにロビーで、ある男性が連れの女性に『文学的な映画やったね』といっていたのが
とても印象的だった。
帰り道、コンビニで、きれていた水と、チョコチップスナックを買う。そういえば、昨日の晩
もチョコチップスナックを食べてた。店内で、コートを着た外出帰りとおぼしき中年の夫婦と
すれ違った。妻が焼きプリンを2個抱えていて、夫はそれにおつまみを追加しようとしていた。
映画を見た直後だったからか、その光景を見たとき、とても複雑な感情が一瞬去来して、気づ
いたときにはなぜだか、プリンを買おうと決めていた。同じ焼きプリンは「おこがましい」よう
な、身の丈にあっていないような変な気がして、慣れ親しんだ「プッチンプリン」を一個買った。
甘くてうまかった。
早めに就寝。
おやすみなさい。
- 2005/03/12(土)
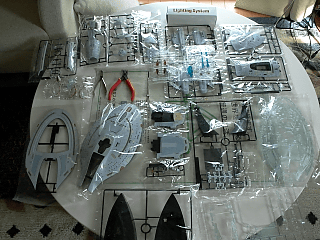
全パーツ、約100点。大型成型の部品が多いため、組み立てはそれほど難しくない。

4時間31分後、完成。500mlのペットボトルと対比。かなりの威容を誇る。
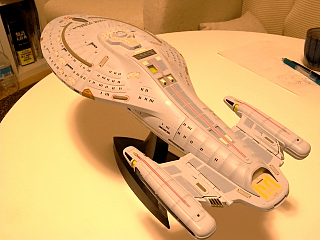
バックビュー。第1船体と第2船体が直結。ワープナセル可動。
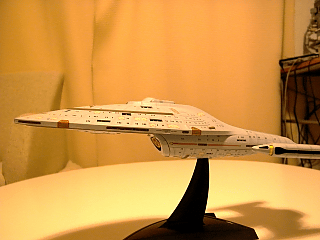
サイドビュー。高速艦らしくかなり扁平な形状。

アンダービュー。
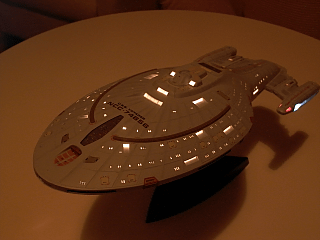
ライトアップ。暗闇に浮かぶ姿はなかなかに美しい。
2003年8月8日に組み立てた初代エンタープライズの進水が2245年、そしてこの宇宙艦ヴォイジャー
の進水は2371年。実に126年の隔たりがある。プラモデルで見るとその差はわずか2年であるが、
その違いは大きい。それはエンタープライズに比べて、はるかに組み立てやすくなっているという
こと。特にライティングシステム周りはすべてユニット化されているのがありがたい。前回はムギ
球レベルでの配線がかなり複雑で、メインのライティング部の組み立てだけで一時間はかかったと
思う。(接触不良のクレームが多かったと思われる。)またパーティングライン(パーツとパーツ
の継ぎ目)がほとんど目立たないパーツ分割には驚くばかりである。大型パーツの一体成型のレベ
ルの向上によるものだろう。
エンタープライズ発売後に、エンタープライズE、NC−Xが発売されているが、ヴォイジャーま
での間にきっちり問題点を修正し、設計に反映させているところはさすがBANDAIである。
しかし、いつになったら大本命のエンタープライズDが発売されるのだろうか。やはりあの大型の
第一船体と、スリムな第二船体では、重心が前過ぎて船体をディスプレイするのが難しいのだろう
か。あるいは第二船体とワープナセルの接続部が薄すぎることによる、強度的な問題か。
というか、よく考えてみて一番の問題は価格とサイズではないか。エンタープライズDをこれまで
と同じ1/850にすると、かなりとんでもない大きさになるはずだ。(全長45〜50cm?)そうすると必
然的に価格も高くなるわけで、ただでさえ売れないのがもっと売れなくなる。たぶん10000円
いくんじゃないだろうか。(ちなみにヴォイジャーは7140円。高いと思うか安いと思うか。)
いずれにせよ、気長に待ってみよう。スタートレックはなぜか日本では非常にマイナーなSFドラ
マだ。それにもかかわらず、こうやってメジャーメーカーからプラモデルが発売されているのだ。
文句を言ってはいけない。われわれファンはいつだって、耐え忍んできたじゃないか。
- 2005/03/11(金)
BK練習、ボイストレーニング。今年1月から、松下めぐみさんにご指導いただいているのである
が、今日は初めて男声陣も見ていただくことになった。やや緊張。ボイストレーニングというと、
大きく、滑らかに出すための練習が中心だと思っていたのだが、今日の練習では小さな音を出すと
きの緊張感の維持ということを具体的に教えていただいた。フレーズの終わりや、同じ音が続く場
合の中間など、思っている以上に簡単に声が落ちてしまう。頭ではわかっているつもりだったこと
も自分自身で自分の声がはっきり聞こえる少人数練習だと「あたた〜頭いてえ」というくらい痛切
に「できてない加減」がわかってしまった。同時に、ちょっとした加減で変わる、変えることがで
きるいうことも実感できた。ある程度の声量が期待できるNCや、BKのベースで歌っていると全
然きづかないことだった。
終了後は宴会もなく流れ解散。なんとなくそういう雰囲気。
みな、一人になり、二人になって去っていった。
O西さんの車で四条烏丸まで送ってもらう。しまった、またしても財布を車に忘れた。なぜかO西
さんの車に乗せてもらうと、普段絶対落とすことのない後ろポケットから、するりと財布が抜けて
しまう。非常に不思議。同乗しているR嬢に電話をかけて探してもらうとやはり後部座席にあった。
まだ近くだったので、引き返してもらうことに。助かりました。
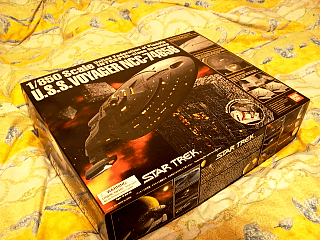
明日は、NC練習休みなので、これをつくるぞ!(楽譜見ないつもりか...。)
惑星連邦宇宙艦隊所属イントレピッド級宇宙艦ヴォイジャー、NCC-74656のプラモデルである。
写真だと箱の大きさがわからないと思うが、31cm×39cm×10cmというかなりの大きさ。組み立てる
と全長が40.5cmにもなる。1/850スケールだから、実物の大きさは約344mである。でかいなぁ。
ワープスピードはギャラクシー級(エンタープライズD)の9.6をしのぐ、9.975。速いなぁ。
ああ、わくわく。
- 2005/03/10(木)
夜の京都駅を探検した。昼間に写真を撮りに来たことはあるが、夜に時間をかけて歩いたのは初め
てである。屋上は酔い覚ましにはちょうどよい。というか酔ってない。雰囲気だけ酔ったつもり。
空中歩道に行こうと思って、大階段から内部に入ったところ、通路は封鎖。そのうえ今度は建物から
大階段側へ出られなくなってしまった。別のルートで行こうと思ってエレベーターや、階段を上がっ
たり下がったり。なんだかダンジョンクエストみたいになってきた。京都の駅ビルは吹き抜け空間を
異常なまでにとりすぎたせいか、建物の内部はとても狭く感じる。これはちょっともったいなかった
なぁと思う。ダンジョンみたいに感じたのはそのせいかも。
結局、店じまい中のお店のひとと「会話」することで脱出経路の「情報」を得た。2階の南北自由通
路から、ふたたび吹き抜けへ上るとそこは大階段の下だった。空中通路は次回のミッションに繰越し
である。できれば、再び夜に来てみたい、そう思って帰宅後駅ビルのホームページを探したのだが、
利用時間が書いてないじゃないですか。駅ビル自体、23時で追い出されるのは今日わかったのだけ
ど、そのことも書いてないナァ。伊勢丹やグランヴィア、飲食店だけじゃなくて、「場」としての解
説が欲しい。「駅ビルの手引き」ってところクリックしてでてきたのが、「京都駅の歴史」ってなん
か間違ってる…。これなら建築・観光の個人サイトの写真つき解説のほうがよっぽど役に立つという
うもの。お金にならないところに手間暇かけられないって感じがしてちょっと嫌である。
まぁでも、いまはなんだかいい気分。
今度、直接いって調べておこう。
いい具合に眠くなってきたので、おやすみなさい。
- 2005/03/09(水)
まずはここに掲載されている写真をごらんいただきたい。
三信ビル。東京の日比谷にあるこのビルは昭和四年に立てられたオフィスビルである。
皆さん、このビルを見たことがありますか?もし、見たことがなければ、今すぐにでも東京へ行って
その目で見て欲しい。私のつたない写真では、とてもこの建築の良さを伝えきれない。こんなに美し
く、気品にあふれたビルは他にない。
そのビルが解体されるという話を不覚にも今日知った。
東京人2005年4月号の特集は「東京なくなった建築」である。そのなかで、所有者である三井
不動産が1月21日に解体を公表したとあった。すぐにHPを見に行ったところ事実であった。
頭を突然横殴りされて、そのまま立ち上がれないような衝撃。胸が詰まって、嗚咽を発しそうな
ほどに、苦しい。どうすればいいのか。
東京人の記事によると、公表後すぐさま日本建築家協会から保存要望書が提出されたが、これだけ
でなんとかなるものではない。記事のよると、この建築を歴史的建造物、もしくは文化財登録をし
ようともくろんでいた矢先のことらしい。
惜しいとか、悲しいとかいう個人のレベルの問題ではない。この建物はなくしてはいけない!!!
この近辺の都市景観が一変してしまう。京都の人間が何をいう、なんて言葉は聞いていられない。
良い建築を、良い都市を後世に残すのは現代の人間に共通した責任なのだ。一国の首都たる東京
でオフィスビルひとつ残せないなんて、なんという情けないことかと思う。とても国際都市だなん
て世界に向かっていえない。
この問題は何もいまに始まったことではない。東京の、日本の歴史的建造物はそれこそ過去から毎
日、どこかでいまも消えているのだ。
わたしは直接、目にしたことはない。写真でしかみたことがない。それゆえに現存していたなら、
感動のあまり涙を流すんじゃないかと思う建物がいくつかある。東京証券取引所。三信ビルと同じ
く、日本のオフィスビル建築の先駆者だった横河工務所の建築。それから、第一銀行本店のドーム。
毎日、こんなところで働いていたい、そう思わせる優美さ。(第一銀行、後の第一勧業銀行は
歴史的建造物の仇敵かも知れない。いまのみずほ銀行である。特に烏丸三条に存在した第一勧業
銀行京都本店に対して行った所業は許しがたいものがある。建物を一部でも保存せずに、外観を
そっくり模しただけの、「コンクリートでできた書割」を同じ場所に建築した。あの建物を見る
たびに私は、こんな建物が京都にあるなんてと情けない思いでいっぱいになる。)
建物の保存になんとか尽力したい、そうは思ってもことは個人レベルでは難しいの現実だ。たいが
いは有識者による検討委員会の手にゆだねられる。が、この委員会もどこまで信用していいのかわ
からない。銀座の交詢社ビルディングも当初は保存計画で動いていたように思うのだが、急転直下
の全面立替が決まり、建物のファサードのごくごく一部だけが現在の建物の正面に飾られている。
かつて、その建築が放っていた街への潤滑剤のような輝きは、そこからは微塵も感じられない。
東京丸の内の日本工業倶楽部会館の検討委員会も同じようなものだったと思う。
なんだか、熱くなってしまった。この思いをどうしたら、いいのやら。一建築ファンには過ぎたこと
なのか。・・・・せめて、自分のできること、写真を撮って誰かに伝えよう。少しでも都市に生きる
人たちが、周りの歴史的建造物に魅力を感じたり、愛着を感じてもらえれば、所有者の思いだけで解
体されることは減るんじゃなかろうか。夏コミに出す本はやはり東京編からはじめよう。一番はじめ
は三信ビルにしようと思う。それまでにもう一度写真を撮っておきたい。GWまで持ってくれよ...。
東京人と一緒に、もうひとつ本を買った。久しぶりのハードカバーだ。「対岸の彼女」角田光代著。
第132回直木賞受賞作である。なんとなく前から気になっていた。それは内容を読んでのことでは
なく、広告や帯に書かれている作者、角田光代の言葉に引かれてのことなのだ。帯の言葉を引用。
『おとなになったら、友達をつくるのはとたんにむずかしくなる。(中略)けれどわたしは思うのだ。
あのころのような、全身で信じられる女友達を必要なのは、大人になった今なのに、と。』
わたしは男だから、女性の感じる友達感というものがわからない。ただ、傍でみていて、男の思う
友達というものと、決定的に違う何かが女同士の友達というものにはあるなということはわかる。
そういうものの本質を、この小説は読ませてくれるんじゃないか。著者の言葉からそんなことを
感じ、読んでみたいと思った。
読み終えて感ずるところがあったら、女性の友達に話を聞いてみたい。
- 2005/03/08(火)

せっかく写真を撮ったので掲載。ご当地福島県猪苗代出身、野口英世ビール。
(水と緑の音楽祭レセプション会場にて)
以前、弁当屋のスタンプの話を書いたが、あのあとしばらくしてからスタンプが満杯になったので
2000円の金券と交換してもらった。1000円のものを2枚であるが、この弁当屋の弁当はた
いがい500〜600円代なので、そのまま使うと差額分がもったいない。なので、機会があるま
でとってあるのだが、どう考えても1000円、2000円を使うことはないと思われ、このまま
期限を迎えてしまうのではないか?と、時々気をもんだりする。すでに存在をかなり忘れかけてい
るので、ここに記しておく。期限はあと1年半くらいあったはずだ。友達が遊びに来たときなどに
振舞うくらいしか思いつかんナァ。
さて、問題がもうひとつある。金券交換後に、あらたなスタンプ台紙をくれるのかと思いきや、
一向にその気配がない。もしやスタンプ制度はなくなったのか?とも考えたが、レジにはちゃんと
スタンプがあるし、押してもらっている人を見ることもあるから、それはない。だいたい、私が台
紙をもらったきっかけもはっきりしないのである。弁当屋に行った初回ではなく、何回かわからな
いが多分、一、二週間くらいしたときに突然もらったのである。
知らない間にフラグ(注)を立ててしまったのだろうか?そして、いまだスタンプ交換後、何ヶ月
も立つのにもらえないのはフラグが立っていないからだろうか。レジで「台紙ください」といった
ら、もしかしたらすんなりもらえるのかもしれないが、どうやったら向こうから自然にもらえるの
か確かめてみたい気もする。新たにもらったときに「どうしてくれたんですか?」とたずねるのも
なんだか変であるけれど。
注:「フラグ」アドベンチャーゲームや、ロールプレイングゲームなどで、プレーヤーの行動があ
る条件を満たしたことを示すもので、これによってストーリーが分岐する。昔のアドベンチャー
ゲームはいかにこのフラグを立てるかが命であった。フラグとは「旗」(flag)のことである。
ゲームに限らず、プログラマーが分岐処理に使う変数を一般的にはフラグと呼ぶ。
なお、私はフラグと聞くと条件反射的に、なぜか「ラリーX」を思い出してしまう。これは特殊な
例なので、憶える必要はない。
- 2005/03/07(月)
疲労のため、一回休み。
追記:早めに床につくが、腹が痛くて眠れない。たまらん。
- 2005/03/06(日)
「水と緑の音楽祭」出演。気持ちよく歌えた。お客さんの反応もよく、よい演奏会だった。
ただし、午前からの長時間練習と、朝からお腹の調子が悪いため、疲労困憊。
終演後、貸切バスで福島空港へ。疲労と空腹と閉鎖環境のため、久しぶりに酔う。
同じ閉鎖環境でも、その後に搭乗した飛行機では、割とゆったりとすごせたのは空調の違いか?
この大阪行きの飛行機、実は出発前にオーバーブッキングのため、明日の便への振り替え要請とい
う珍しい事態に遭遇。明日午前の航空券と宿の手配、それと協力金二万円か、マイル加算の条件。
学生のS村田君にすすめたところ結構考え込んでいた。春休みの学生なら手をあげてもおかしく
ないはず。結局、ぎりぎりなんとかなったらしい。
搭乗後、出発を待っているとまたしても問題発声、もとい発生(IMEの変換癖だ...)。客室内で
水漏れが発生しているという。原因究明するまで離陸できない。結局、空調配管の結露ということだ
ったが、どうも腑に落ちない。寒冷地への飛行など普通のことで、結露が起きるなど想定されている
現象のはずだが?もうひとつ気になったのがパイロットの状況説明。明らかに人前で説明することに
なれていない調子で、たどたどしいうえに敬語の使い方がおかしく、はっきりいって聞き苦しかった。
一時間弱の遅れで離陸。飛行前にM川さんの指摘でわかったのだが、21時前に伊丹に着陸できな
いと、関西国際空港に回される可能性があった。こんな時間に関空だったら泊まるしかないないぞ。
結局、20時55分着。上空からみる梅田近辺は美しかった。
さて、伊丹からの帰路、かなり状況判断できない状態だったので、I東さんと空港バスに乗ってしま
った。のどもと過ぎれば、にしては早すぎる忘れ方であるが、乗換えがないから楽だろうと思って
いたのかもしれない。見事に今日二回目の酔い。
22時30帰宅。疲労の極み。
もう何日も京都にいなかったような錯覚。
なんとか無事に帰ってこれた。しかし、25%くらいが酔いのせいかも知れぬ。飛行機そのものは
嫌いではないが、空港までの主な移動手段が車に限られているという点が私にとってはネックであ
る。しばらく、バスには乗らないと決めた。
- 2005/03/05(土)
朝10時26分京都発、14時25分郡山着。東京駅から東北新幹線に乗り換えるのだが、乗り換え
口はかなり狭い感じだ。前回は気づかなかったが、NCの50人ほどの団体でもかなりごったがえし
てしまうのだから、盆暮れの帰省のときはかなり大変だろうと想像する。
郡山は積雪あり。しかし、今日は晴れのいい天気で、思ったほど寒くなかった。駅舎の中がかなり改
改装されていて、以前のどこかほの暗い感じの2階コンコースから、明るい印象に変わった。しかし
3回も来ているのにホールと駅前のことしか覚えていないのはもったいない。コンクールと違ってこ
こういう機会なのだから、演奏の準備は万全にしておいて、少なくとも前日は滞在先のことを楽しみ
たかったように思う。それは、迎える側の心理にもそういうことはあるのじゃないだろうか。
今年の夏、京都で行われる世界合唱シンポジウムには世界・日本各地ら合唱団がやってくる。
その人たちが、ホテルとホールだけを行き来して、本番以外は練習ばかりして、京都のことを見てく
れないとなると、京都の人間としては複雑な気持ちになるはずだ。甲子園を目指しているわけじゃな
いのだから、練習ばかりではちょっと。それは郡山の人も同じかもしれない。(招かれての演奏が×
では本末転倒なのはわかっているけれど。)
ホテルで荷物を降ろし、郡山市民文化センターへ移動。舞台にてたっぷり2時間の練習。
レセプションの席にはやはり郡山市の観光案内をまとめて置いてあった。それを読んで非常に参った
なあと思ったのは、郡山には歴史的建造物が多いということ。いままで気づきもしなかった。パンフ
レットに載っているだけで、3つの西洋建築物がある。開成館という擬洋風三層楼建築、現在は安積
歴史博館となっている明治時代の中学校。大正時代建築の公会堂(中ノ島公会堂を模して造られた
ものらしい)。郡山にいながら、これらを見る機会なく帰ることになるとは!もう一度こなければい
けないなぁ・・・。
私の建築探訪が東京・大阪・名古屋などの大都市に集中してしまうのは、一度の滞在で複数の建築
を見ることができるということと、そのレベルが高いからだ。地方都市ほど、こういっては失礼だが
交通費と時間をかけてでも見たいという建築はやはり少なくなる。だから、「何かある」とわかって
いても、その建築のためだけに足を運ぶことに慎重になってしまう。そのせいか、いい建築をさがす
という目が曇ってしまってるのかもしれない。自分の趣味をおろそかにしてはいけないと反省。
鏡開きされた酒樽の笹の川、若関を口にする。笹の川の辛さが強烈ですぐに酔いが回る。お酒を口
にすることへの抵抗(しんどくなるのが怖い)感は薄れてはいるけれど、この感覚はやはり自分が飲
めない体質であることを思い出させる。ここを超えるとダメだが、この手前ならいい気持ちで寝られ
るに違いない、そんな自分にとっては針の穴ほどに見つけにくい領域の衛星軌道にしばらく滞在する。
21〜23時、ホテルのロビーにてマネージ。演奏会関係の配布と集金のため、休めず。
23時ホテル近くでラーメンを食べる。二次会帰りの人と遭遇。マネージがちょっと嫌になる。
読書、心落ち着かせる。というより、没頭していた。かか25時就寝。
- 2005/03/04(金)
コダーイの「マトラの風」、歌ってみるとかなりいい曲だった。楽しみ。
明日は、福島県郡山市で開かれる「水と緑の音楽祭」(開催は3/6)に出演するため京都を発つ。
なのでBK練習後すぐに帰宅。といっても徒歩なので、それなりにゆっくり。いつもとは違い、
御池通りからは寺町を南下して帰ってみる。途中でパン屋を発見。22時まであいているという
のは珍しい。明日の朝ごはんにとおもって、フランスパンを買って帰る。
わたしはパンの中でもあまりお菓子に近い系統のものよりも、食パンやフランスパンに近い系統の
もののほうが好きだ。特にフランスパンの生地のように、一見人を拒んでいるかのような態度なの
だが、腹を割ってみるとなかなかに人当たりの良いあの独特の食感が好きである。固い生地を噛み
きるさまは原始人が生肉を引きちぎって食べるようであり、なかなかにワイルド感が漂うのも普通
のパンと違ってよい。わたしはラーメンの袋であるとか、薬の袋とか、とにかく何かと歯で切るこ
とが多いのだが、そのなかでも最高度の噛み切り具合を味わえるのがフランスパンだと思う。
私のフランパン好きのルーツは、小学生時代にさかのぼる。受験のため塾に通っていたのだが、夕
方から夜9時すぎ、ときには10時くらいまで塾にこもることが多く、日曜日にいたっては朝9時
からだったので、ほとんど塾に住んでいた。個人経営だったので何かとアバウトで教室で昼・夜を
食べたものだ。親からは一日100円をもらい、50円で飲み物、50円でパンを買った。その
50円で買えるパンが近くの駄菓子屋兼パン屋のフランスパン生地の丸いパンだった。握りこぶし
よりも少し大きいくらいだったが、それはもう50円とは思えないほどの食べ応え感で、量は多く
なくとも、一生懸命かまないと食べられないので、それはもうたくさん食べているような気分にな
ったものだ。小学生なりに100円で最大の効果をあげようと考えて行き着いた最適解がそこには
あったように思う。(自画自賛)
さて、いまではそんなハングリーさも忘れてしまって250円もするフランスパンを買ってしまう
わけだが、もしゃもしゃ、この暗室を書きながら、もしゃもしゃ、すでに3分の1近くも、もしゃ
もしゃ、ごくごく(水を飲んでいる)、平らげてしまった。明日の朝食までになくなってしまうか
も知れぬ.....。
それではおやすみなさい。
いってきます。
- 2005/03/03(木)
診察前、看護師さんによる問診を受けているとき、隣のカーテンの向こうで先生と患者さん(同じ
会社のひと)のやり取りが聞こえる。ちょっと悲観的な話っぽくて先生も話にくそうである。なお
る確率が低いとかどうとか。ここは成人第3部、循環器科。
なんの根拠もなく、自分には無縁だと思っていたのだが、そうでもなかった。診察結果は予想と異
なっていた。私の心臓にいまのところ病名らしきものはない。でも病名がないからといって健康か
というとそうではないのである。事態は進行していた。
5年くらい前から、この健康管理センターでデータを取り続けているが、12mm,13mm,13mm,13mmだ
ったのが、今年は16mmになっていた。これは右心室と左心室を区切る、心臓の「中隔」の厚さの
ことである。正常なひとの場合、11mが標準である。ここが厚くなると何がまずいかというと、
厚くなる分、心筋に負担がかかるのである。心臓の肥満みたいなものだ。だったら肥満のように
ダイエットできるかというと、それはわからない。そもそもなんで肥大するのかがわからないの
だ。遺伝的な要素が大きいらしい。
ずっと、この厚さに変化がないか注目してみてきたのだが、ここにきて急に増えていることと、
実際に心エコーで見せてもらったその厚さには、けっこうなショックを受けた。いますぐ、明日
あさってにどうこうなる状態ではなく、薬を飲む必要もない状態なのであるが、ときどきなる
細動には注意がいるという。厚い状態での細動はあまりよろしくないそうだ。また中隔には心臓
のリズムを刻むための神経が通っているのだが、肥大化はこれに悪影響を及ぼすという。
...ということなので、もし今後悪くなったときのために、主治医を持てというようなことをい
われてしまった。ここは健康管理センターなので、投薬などはできないそうだ。うむむむむ。
とりあえず、母親に相談。父の主治医は避けたいということで意見が一致した。致死性の不整脈
であったとはいえ、その前兆を二度は見ていたはずなのに、結局何も出来なかった人に親子二代
でかかるのは気分がよろしくない。というわけで人脈を介して検討中なのだった。
それにしても、すぐどうこうなるものでもなし、普通に生活できる体だし、こういう症状のひと
はごまんといるとわかっていても、やはり自分の身のことなので、不安はないかといわれると、
そんなことはないのだった。10年、20年先、その先はどうなんだろうか。情けないことだが
父の死に思い至らないはずもなく。漠然とこわいのだった。
診察は昼ごろ終わって上司に電話をいれてから会社に向かう。で、ああ電話したときにこのまま
直帰させてくださいって言えばよかったと思う。健康管理センターへは出張扱いなのである。
(こういうところは、なぜか異常なほど行き届いている会社だ。)なんとなくこんな気分では仕事
できない。しかし、実際に会社についてみると、どういうわけか私にしかできない仕事が2〜3件
集中して来ていた。それにかかりっきりになったせいか、ずいぶん落ち着いた気がする。まぎらわ
すという言い方をするほど深刻ではなかったが、いちいち気にしていたら生きていけないのだ。
(それともあれか、諦観してしまったのだろうか。そんなに人間できていないはずだが。)
というわけで明日からも普通に生活したいと思う。
- 2005/03/02(水)
あるフィギュアを探しているのだが、全然見つからない。秋葉原のどの店でも売り切れで、発売元
の直営店ですら売り切れていたのでこれはだめか?と思っていた。が、一極集中する秋葉原よりも
入荷数は少ないとしても、求める人口が少ない逆に京都を探したほうが見つかるのではないか?と
考えた。そんなわけで、仕事が終わってから「ありそうな場所」を回ってみたのだが、跡形という
よりも、存在した形跡すらなかった。今日回れていないところが2軒あるのでそこに期待。今日い
ったところよりも確率は高いはずだ。それにしても約10年前のゲームのキャラクターがいまもなお
フィギュア化され、爆発的に売れるというのはそれだけ深く、われわれ(一般化したらいかんか)
の脳裏に刻まれているということだろうか。(その後アニメ化された影響もある。)
10年前というのは、18禁ゲーム業界に大作ブームがまだ起こるまえであったと思う。そのキャ
ラクターの登場するゲームは、それ以前ともそれより後とも少し違う形で登場したもので、段々に
消費者の心を捉えて、ついには18禁からコンシューマゲーム、いわゆる美少女ゲームの先鞭をつ
けたものであった。さきに書いたようにアニメ化され一般向けの作品として放映されるまでになっ
た。コミケなどでもそのゲームの独り勝ちの状態が結構続いたと思うが、その後の別メーカーの攻
勢や、一般には泣きゲーなどと評された大作モノの登場でだいぶその存在感は薄れてしまった。
しかし、その大作モノの時代もあっという間にすぎ、いまは群雄割拠、ジャンル細分化の時代とな
っている。かつて消費者はゲームのキャラのなかから自分の好みに近い嗜好の女の子をアイドルと
したのであるが(そもそもヒロインの数が少なかったので、かなりステレオタイプな分類だった)
いまは消費者固有の「好み」にぴったり合致するほどの数のキャラクターがあふれる時代となった。
それだけゲームの中の女の子達にも個性が生まれたといえるだろう。しかしそうすると、かつての
ように多くの人から爆発的に支持され、何年にもわたって文字通り「君臨」しつづけるキャラクタ
ーは出なくなってしまった。それはコミケを見ているとよくわかる。夏と冬の間に存在し、コミケ
に間に合っても多くは1〜2回のみしかジャンルが形成されない作品が増えた。(このへんの事情
はアニメの方面も同じ)
メーカーが今回10年前のキャラクターを出すのは、キャラ自体の良さがあるのはともかく、この
世界で「共通言語」として通じるゲーム・キャラクターが10年まえにしかなかったからではない
だろうか。少量生産の組み立てフィギュアならマイナーキャラでも良いが、大量生産の完成塗装済
みフィギュアとあっては売れないと困るからだろう。うがった見方でちょっと嫌だが。
わたしがさがしているキャラクターは通称「いいんちょ」(私服バージョン)。その名の通り委員
長で、おさげで、眼鏡。めがね。メガネ。でも私服バージョンではメガネはずして、髪もおろして
いる。どっちもカワイイのでよし。コアな人は私服バージョンのフィギュアにメガネパーツをとり
つけているという。(メガネパーツはなんと、「汎用品」として市販されている。)
見つかるだろうか...。
明日は、朝から循環器検診。これでも要管理者なのですよ。
昨年の2月以来、発作は起こっていないのは僥倖。
早く寝なければ。
おやすみなさい。
- 2005/03/01(火)
この話はしたようなしていないような、そういえば会社の所感で話したような気がする。
2001年6月発行、第二刷であるから、暗室では書いていないだろう。
きのう丸谷才一が登場したので、せっかくだからもう一冊本を紹介したい。
「挨拶はたいへんだ」(朝日新聞社刊)である。装丁・イラストはやはり和田誠。
どういう本か、帯にはこう書いてある。
「結婚披露宴でのスピーチ 喜寿の祝いでの乾杯の辞 友達の葬式での弔辞
パーティの主人側としての挨拶 そんなとき、どうすればいいか?」
これだけ読むと普通はスピーチの実用書であると思い込む。しかし、帯の上のほうを良く見ると、
和田誠のひょうひょうとした気の抜けたような絵が載っている。はて?と首をかしげる。いったい
なんだろう?と思って読み始める。この帯を書いた編集者はえらいと思う。というのは、さっきの
べたような効果を狙っているばかりか、本を読みを終えたときには実用書以上にスピーチという
ものがわかる気がするから、結果として「どうすればいいか?」という問いにつづく答えにこの
本はなっているからだ。
どんな内容かというと、丸谷才一という人はいろんな場所でするスピーチで必ず原稿を書くので
ある。たいがいが5分以内に収まるものから、乾杯の唱和まで。それを本にまとめたもので、
帯にもあるように結婚式の祝辞、葬式の弔辞、文学賞選考での挨拶、逆に受賞の挨拶とさまざ
まだ。もとは挨拶の文であるから、口語なのだがそのせいか、文章になったときにそのリズム
がよくわかる。それを読んでみると、いかに氏のスピーチがリズムに富み、おもしろいかがわ
かる。原稿を書いているのだからあたりまえだ、といわれそうだが、話すことを想定して書く
文章でリズムを考えるのはなかなかに大変ことだと思う。読んでみて面白くても、話すと普通
に聞こえてしまう。逆のこともある。そのどちらから見ても、面白いというのは実はとても稀
有なことで、この本をスピーチの実用書と思って買うと、とてもこんなスピーチは真似できな
いや、ということになってしまう。
しかし、読み続けていくと、スピーチとはどんなものかという感覚がわかってくる。それがど
んな感覚かというと具体的に言いづらいのが困るのだが、やはりリズムなのだと思う。一本
調子でもいけない、トリッキーに動いても聞く人があたふたする。流れる、止まる、のバラン
スのよい組み合わせ、それが聞く人にとって意味のあるスピーチのように思う。われわれは
そこかしこの結婚式やら、演奏会のレセプションやら、同窓会やらときには組合で政治家のス
ピーチを聞いたりする。そのなかには良いもの悪いものいろいろあるけれど、ほとんどが悪い
スピーチ、つまりお手本にならなくて、聞いていて退屈なスピーチなのである。そんなのばか
り聞いていても、勉強にはならないのだ。良いものを聞かなければ。そう思ったらこの本を読
ばいいと思う。
この本にはいろいろな挨拶があるけれども、一番すごいなと思うのが弔辞である。亡くなった
人のことを話すのである。やはり一番紙幅が取られているが、話てみるとそれほど長くないは
ずだ。5分〜10分というところか。そんな限られた時間のなかで、故人の生き方や自分との
かかわりを話す。あとがきの対談で井上ひさしは言う「弔辞は小さな伝記」である。そう、こん
なに高密度にそのひとの生き様から人となりまで聞いている(読んでいる)人にわからせる、
納得させるものはないんじゃないだろうかと思う。仮にこの本を読みはじめて、こんなに全部
読んでいられないよ、という忙しい方がいらしたら、ぜひ弔辞の部分だけでも読んでほしいと
思う。飾らず、照れず、実直に素直に述べられた言葉は、どれも故人への想いに満ちていて、
一篇の小説を読んでいるかのように感ずるはずであるから。
さて、ここまでで本の話は終わる。
ここまでは前置きだったのである。私は今日、ささやかながら祝杯をあげたいと思う。それに
あたって、どんなスピーチをしようかと思ったこともあり、この話を書いた。しかし、ごくご
く私的なことで、誰かと分かち合うことも難しくて、うれしさばかりが立つものでもなし、人
にとってはなんだそんなもの、と思われないでもないし、世間一般の風潮でも必ずしもそれが
いいことなのかわからない。でも、ひとついえることは誰かが私のことを認めてくれていると
いう証でもあり、それはそれでうれしいものなのだった。
付け焼刃のスピーチはできないので、ありきたりの一言を。
おめでとう、私。よく頑張った。
お祝いに弁当のご飯についてきた梅干を食べた。
|
|