|
電波暗室 2005/04
- 2005/04/30(土)
NC練習15−21時。終了後、梅田にてマネ会。12時半帰宅。
いつの間にか、初夏の風。
- 2005/04/29(金)
夜、御池通りを烏丸で左折すると、ふいに目の前にほのかな明かりに照らされた木々がとびこん
できた。新緑の葉の間に、白く大きな花をいくつものぞかせているのだ。その緑と白がやけにま
ぶしくて、しばらくぼーっとみあげていた。花の名前はわからない。
いつも、よく通る道。そんなところにも、気がつけば、何か新しい発見があるのだなぁと思うと
うれしくなった。
YK練習帰りのできごと。
- 2005/04/28(木)
日月堂行きがダメになったあと、西荻へ行くぞ!と書いたが、偶然にもその直後にその日月堂さ
んから、「ぶらぶらするなら西荻あたりの古書店は面白いのでどうか」という提案を頂いた。
ふむむ、古書好きは古書好きを知るということだろうか。つづきのメールで丸善の話などする。
京都の丸善は衰退、かたやすばらしき東京丸ノ内店。日月堂さん曰く、「探究と散策の両方が
楽しめる店は貴重」。そう、大型新刊書店のポイントはそこにあると私も思う。それを可能にす
るのはやはり店舗設計なのだが、京都のように長方形にしか土地を使えない場所ではかなり制限
があると思う。
散策を可能にするのは回遊できること。出入り口が複数あって、そのどこからも人が入り、出て
行ける場所でないと難しい。京都のビルの場合、入り口は常に道路に面したところにしかありえ
ない。土地に対して建物を狭くし、二面、あるいは三面をとっても結局は同じ方向にしか進めな
いのでは「通り抜けられない」。京都で唯一回遊をつくり出せる状態にあるのが、Book1stである
が、河原町通り一面に対して、出口が3箇所あるというのがポイントだろう。北から入って南に
に抜けるという流れを作れるから。一応、道路二面に接触してはいるが、事実上長い一面がある
だけで、かなり有効である。これはデパートとよく似ている。
丸善京都店の場合、人の多い河原通りに接していながら、入り口は一面のみ。もし、通り抜けを
作るならどうすればいいか。南側には狭い蛸薬師通り、東は木屋町通りがある。そこで考えられ
るのは、狭い蛸薬師を補う形での東西の通路を作ること。丸善の店舗は当然木屋町までは面して
いない。そこでだ、蛸薬師沿いの店舗と共同戦線を張って、東西ぶち抜きの建物をつくり、1〜
3階くらいまでを丸善、4〜6階までを他店舗でシェアするのだ。建物は3つくらいに分割して
空中通路でつなげたりなどのアクセントは必要だろうが、とにかく長い、うなぎの寝床の本屋を
つくるのだ。蛸薬師にずらりとならぶ出入り口。蛸薬師側の南面はすべてガラス張りにし、建物
の南側はすべて通路として、本棚を置かないようにする。見上げたときに狭い通りに圧迫感を出
さないようにするためだ。ああ、なんか考えるだけでワクワクしてきたぞ。
木屋町までぶち抜きなので、当然木屋町側にも出入り口あり。木屋町は飲食街であるから、そこ
に本屋があるとなると、ちょっとした風穴めいて、そこを基軸に周りの雰囲気も変わるかもしれ
ない。なにより、これは確実に人の流れを変える。というのも河原町から木屋町への通り抜けは
四条、三条以外の通りはいずれも狭いうえ、雰囲気的に暗くて、人気もなく通りにくいのだ。
また、店舗のなかをただ通るだけでなく、蛸薬師も歩きやすい雰囲気になるのではないか。外か
ら書店を眺めながら歩くのもいいものだ。(そう思うのは私だけか...。)
いやー、本気で誰かやってくれないだろうか。というか丸善がやらないと意味がないのだが。
自社ビルを売ろうという状態ではさすがに無理だろうか。でも、かつて京都に丸善ありと誇ら
しく思った、あの栄光をもう一度取り戻すには、これくらい大胆でなければいけないだろう。
規模を縮小したりなんかしたら、何のとりえもない、雑誌と漫画とベストセラーしか置かない
街中のやる気のない書店に成り下がってしまう。梶井基次郎もそれは望まないはずだ。(たぶん)。
起てよ丸善。
追記:本屋回遊論からすると、ジュンク堂は出入り口が一面しかないので、人が集まらないは
ずであるが、本屋それぞれの正確の違いのようなものがあって、ジュンク堂は人を流してとり
こむのではなく、どんどんどんどんうちにこもらせて、外に出さないいくタイプなのだ。ジュ
ンク堂の分析についてはいずれ気が向いたらやってみたい。
追記2:昨日「家守綺譚」を読了。次なる本として「太陽の簒奪者」(野尻抱介著、ハヤカワ
文庫JA)を、Book1stで購入。第34回星雲賞受賞作。ひさしぶりのハードSF。裏寺町、新
京極を経て、スタンドで一杯(の水)。(本当は日替わり定食を食べた。)
- 2005/04/27(水)

甘夏とデンマーク
小学生のころ、学校で日記を「書かされた」人は多いだろう。毎日、先生に提出して赤ペンで
先生が感想を書いてくれるという形式だった。小学生であるから、何かを考察したり、思索に
ふけったりすることはなく、とにかくなんでもいいから早く書き上げることが至上命題だった。
小学生の世界は狭いから、てっとりばやくかけそうなのは、今日は何をして遊んだかと、今日何
を食べたとかくらいしかなかったように思う。
そうやって書いていた小学2年生のときの日記の一編を今でも憶えている。憶えているのはそれ
きりである。ほかのものはなぜか記憶にない。その一編というのが甘夏の話だった。「今日の夕
ごはんは、ごはんと××でした。デザートに夏みかんがでて、すごく楽しみにしていたら、ぼく
以外はだれも食べなかったので、ひとりでいっぱい食べれてうれしかったです」というような内容。
このときの心情は記憶にある。夏みかんは一人一人に出されたわけではなく、家族4人で1個分
がむいた状態で供されていた。あの大粒でたわわな実が口のなかではじけるのが好きで、みかん
やオレンジ、グレープフルーツよりも自分のなかでのグレードは高かった。当然、家族のだれよ
りも早くご飯を食べ終えて、夏みかんに一番乗りすることを子供ながらに虎視眈々とねらってい
たのである。しかし、ふたをあけてみれば、夏みかん争奪杯にエントリーしたのは私一人であっ
た。拍子抜け、などと思うほどひねてはいなかったので、素直に大喜びでぱくついたのだった。
日記は、その心情をそのまま書き綴っただけなのだが、素直なところがよかったのか、週一くら
いで発行されていたクラスの文集に先生が載せてくれた。どちらかというと日記を書くのは嫌い
であったが、いざ公になるとなにやら誇らしい気持ちにさせてくれたのが、不思議である。さて
その文集を喜びいさんで親に見せたのであるが、親は苦笑。「いややわぁ、いつもこんな食事な
んかって、みんなに思われるやんかー」とのたまった。そう、この日の夕飯はよりにもよって、
母曰く、超手抜きの日であった。ご飯と料理一品だけで、付け合せも、椀モノもなかったのであ
る。私は夏みかんのことしか頭になかったので、品数が少ないのは好都合としか考えておらず、
そんなことは気にも留めなかった。しかし、今考えるとさすがに正直に書いたのはまずかったか
なあと思う。子供って恐ろしい。
そういえば、もうひとつ書いたことを思い出した。同じく2年生のときに、「お父さんの給料は
○○万円です。先生の給料はいくらですか?」という、家庭のヒミツも、遠慮もへったくれもな
いことを書いてしまった。こればっかりは、いま思いだすと非常に恥ずかしい。さすがに文集に
は載らなかった(あたりまえか)ので公知にはならなかった。この日記のことは親は知らず、今
も先生と私だけの秘密である。
大丸で買ってきた甘夏みかん、風呂上りに食べてみよう。
なお、デンマーク(味付け食パン)には特に思い出はない。おいしいから買ってきただけデス。
- 2005/04/26(火)
お腹イタイ。そこの方、またかよと思ったデショ。でも違うのだ。私がよくなる腹痛は胃腸系の
もので、これは皆さんも経験のあるとおり、どーんと重たい感じの痛さ。それが、昨日就寝直前
から、右下腹あたりが時々、ピクッと痙攣して、ツンとした痛みが瞬間的に走る。筋を違えたと
きの痛みに少し似ている。最初は、位置からして「盲腸?」と思ったのだが、時々くるというこ
とからどうも違う。
これはあれだ。とうとう来てしまったのだ胆石の痛みが。たぶん。
もともと何年も前から胆石があるのはわかっていて、薬で溶かそうとしたりもしたのだが、おも
わしくなかった。半年にいっぺんくらい胆汁の出が悪くなって消化器系にダメージを受けるくら
い(結構しんどいけど)で、これまでは胆石そのものによる痛みというのは経験がなかったのだ。
噂によるとそうとうしんどいらしい。
このままではさすがに健康に支障をきたすだろうと思って、演奏会の後、5月に超音波破砕をし
に行く予定だった。うむむ、今週末まで様子をみて良化しなければ、カンタート前にいかないと
いけないだろうな。何があるかわからんので、できればGW明けまでもって欲しいのだけれど。
朝、会社に行く前にいつも思うのだが、洗濯機に靴下を両足そろえてくれる機能というものは
つかないだろうか。漫画家の毒田モロ男氏もおんなじことを言っていたが、朝寝起きの状態で
しかも急いでいるときに、そう簡単に両足そろって見つけられない。時間がないのでいらいら
してしまう。そんなものは、寝る前に用意すればいいじゃん!という人は、整理整頓ができる
人だろうから、このめんどくささはわからないだろう。朝、めんどうなことは、寝る前もめん
どうなことなのだ。
最近、個人認証技術のなかで、顔認証や虹彩認証など、かなり高度なものが実用化されはじめ
てきた。このような認証技術は、画像のうちの特徴点を、エリアごとに分割して記憶している
ケースが多い。これを応用すれば、靴下の判別も出来るのではないだろうか。靴下を判別する
ポイントは、1色、2形状、3模様、4ワンポイントのマーク(ないものもある)ぐらいだと
思うので、個人認証に比べれば情報量は少ないと思う。
問題は、たくさんの洗濯物のなかから靴下のみを、物理的に選別できるかということだ。くしゃ
くしゃに丸まった状態では、認証のしようがない。もうひとつは、水分だ。どの時点で認証する
かによって、乾きの状態が異なる。そうすると色情報があてにならなくなってしまう。そして、
もうひとつは、単に認証するのではなく、二つをまとめるという技術。ソフトウェア上の変数な
らともかく、物理的な形状を持つ靴下を一時保管するバッファ領域がないと、まとめることがで
きない。現実には、どれくらいの数の靴下が洗濯機に投入されるかわからないのと、空間の制約
から、そのようなバッファ領域の確保は数が限られることになって、実現は難しいだろう。
こんな考察をするまでもなく、そんな機能がついていても買う人がいるかというと、疑問だ。
であるが、世の中にあふれる電化製品、あるいはその機能の一部というものは、いまの考察と同
じで、技術的に可能か?というところが出発点になっている例が多い。本質的には不要な部分で
付加価値をつけようとする思考である。しかし、実際世の中で支持を受けている商品というもの
は、その逆をいっているケースがある。ぱっと思いつくのがiPodシャッフルだ。
携帯用の音楽プレーヤーに必須と思われていた「液晶表示画面」をなくしてしまった。他者の同
レベルの製品には必ずついているのに。しかし、音楽を聴くということを突き詰めて考えれば、
本来そのような画面は不要なはずだ。(ついていないと安心できないという人はいるけれど)
だから、けずってしまった。そうすると、電流は食わないし、液晶を制御する回路がいらない
のでコンパクトにできる。部品点数が減る分、組み立てが楽だし、歩留まりも上がる。結果的に
コストを安くできるから、消費者に低価格で提供できる。そして、機能を絞った結果、デザイン
性を強く打ち出すことができた。それが、消費者にとっては付加価値とうつったと思う。プラス
から考えるのではなく、マイナスしていくことで生み出される付加価値だろう。
単に技術的に可能か?といった発想は、出発点ではありえない時代になっている。デジカメが画
素数競争から、付加価値・機能競争に突入してメーカーの明暗がはっきり分かれるようになって
きた。この先、その競争がどういう方向に進むのかはわからないが、かつてのフィルムコンパク
トカメラや、家電製品のように「なんでもできる型」の付加価値を追い求めていくと、アップル
のような別の視点からモノを見ることができるメーカーに足元をすくわれかねないと思う。
さて、靴下の話にもどって、今日も今日とて靴下のペアがなかなか見つからなかった。で、結果
的にどうしたかというと、「すでにそろっているもの」に手が伸びてしまった。そう、昨日はい
て、脱ぎ捨てた両靴下をもういっかいはきました。まだ夏じゃないし、なんとか大丈夫。
(それでいいのか>自分、と思わないでもない。)
今日も、NCマネージ忙しい。
疲れた。
追記:4/22の日月堂へのリンクが変なことになっていたので直しておきました。興味のある方は
再度、リンクをたどってみてください。
- 2005/04/25(月)
列車転覆事故、まことに痛ましい。亡くなられた方の冥福と、怪我をされた方の回復を祈るばかり。
助かった方へのTVのインタビューで「もう二度と(電車には)乗りたくない」という答えがあっ
た。鉄道を愛するものとして、非常に悲しい一言であるが、その気持ちは少しはわかるのだ。
私は、踏み切りの前に立つのが怖い。高校生のころだったか、大学生になったころか、いずれにせ
よ山陰線が丹波橋〜花園間が高架下される前にさかのぼる。その日、わたしは二条駅に程近い、旧
二条通の踏切の前で、列車が通りすぎるのを待っていた。目の前に徐行した列車が近づいた瞬間の
のこと。目の前の線路から一直線に飛んでくる「何か」の残像が見えた。その直後、自転車のハン
ドルを握っていた右手の甲にとんでもない衝撃が走った。足元に、手のひらで包めるくらいの石が
転がっていった。列車が線路に置かれた置石を跳ね飛ばしたのだ。
幸い、手は腫れただけで済んだが痛みはそうとうなものだった。気が動転していて、自宅に戻って
から二条駅に文句?の電話を入れたのだった。どうしてあのとき、すぐに駅に行かなかったのか自
分でもよくわからない。そのとき電話でいわれたのは「証拠が欲しい」というようなことだった。
手にあたった石をもってこいというのだ。石はまた電車が跳ねたらいけないと思い、とっさに線路
わきのバラストのところに放り投げておいたのだ、見つかるはずもなし。当時、踏み切りにはほか
に2〜3人の人がおり、大丈夫?と声をかけてくれた人もいたので、証人もそろっていたのだ。で
も、一緒に駅までいってもらうといったことまで、頭が回りようもなかった。
ただ、ただくやしく、怒りの持って行き所もなかった。踏み切りにいたる直前、近所の親子連れ?
が線路内から踏み切りを通って出てきたのを見ていた。おそらく、バラストで遊んでいたのだろう。
置石をしたかどうかはわからない。故意でなくても、石を踏み切りにこぼしただけで、そんな事故
は容易に起こりうるのだ。JRの記録には残っていないが。
それからしばらくして、私は自分が踏み切りの直前に立つことができないことに気づいた。たぶん
いまでもそうだと思う。あのとき、手にあたってよかった、目に、メガネに向かって飛んでこなく
てよかった、頭にとんでこなくてよかった、そう思って忘れようとしたけれど、頭では忘れようと
しても、身体が忘れてはくれないのだった。記憶の奥底からは消えないことというのは本当にある
のだと悟った。
事故にあわれた方はこれからずっと、そういうものの何倍も、何百倍も恐ろしい経験と立ち向かわ
ないといけないのだ。せめて、せめて事故原因説明と、十分に誠意を尽くした謝罪をJRはしっか
りするべきだ。(当然、やるだろうが、誠心誠意というところが重要デス。)
十分とはいえなくとも、少しは心の負担が軽くなると思うから。
うーん、NCマネージであたふた。
休む間なし。
- 2005/04/24(日)
YK、東京カンタート練習。曲には慣れてきたが、いまだに自分は浮いているのではないかという
不安がつきまとっている。なぜかというと、きちんと自己紹介していないからである。指揮者をは
じめ、BKとNCで一緒に歌っているメンバーは多いし、彼彼女らにフォローしてもらっているの
だが、そのせいかどうも紹介不要みたいな感じでここまで来てしまった。よどこんメンバーの方は
いぶかしがったりしてないのかしらん...。であるが、参加初回のときに顔だけはしっていたF氏
に「あっ山Dさんですよね?お話はかねがね...」とか言われてしまったのにはびびった。いった
いどんな話が、誰から伝わってるんだヨ!不安だ。
東京滞在のホテル、二日分予約完了。前日は、定宿高いバージョンのインターコンチネンタル。
まる一年ぶりか。定宿の割にはなかなか泊まれない。当日は、当初というか昨日あたりをつけて
いた上野不忍池のほとりのソフィテル東京(2003/11宿泊)が今日見ると満室になっていたため
予定を変更せざるをえなくなった。ホテル予約というのはほんとに瞬間勝負だと感ずる。この
ホテルは上野駅からは徒歩15分以上離れた閑静な場所にあるため、ぜったい大丈夫だろうと
思ってたかをくくっていたのだが。まぁ、終演後に錦糸町から上野(もしくは湯島)まで移動
して、さらに歩くのはややきついかなと思っていたので、よしとする。
で、問題はここからで5月3日という日付で、"コンフォート"なホテルを探すのは骨が折れた。
結局見つけたのは、灯台下暗しというか、もっとも便利でありながらその存在がまだ、あまり知
られていないところ。ずばり丸ノ内ホテル。丸ノ内OAZOとともに新装開業したホテルだ。
これなら、大手町まで一直線で済む。当日、帰る人たちを送りがてら向かうこともできる。
新規ホテルチェッカー(今考えた)としての役割も担えるのでちょうどよかった。やや予算オー
バーであるが、階下に丸善があるということで帳消しにできる。本屋に隣接するホテル、ありそ
うでなかったなぁ。(そういう基準で選ぶのは変か?)
- 2005/04/23(土)

今年初の冷やし中華。
わたしはもともとマヨネーズが苦手で、マヨネーズの派生系と思しきタルタルソースは今でも苦手
で、白身の魚フライなどにあれがかかっているとまず食べない。であるが、マヨネーズ単体だとダ
メでも、あの白いのがどこかに隠れてしまうと、おいしいなぁと思う。代表的な例はお好み焼きで、
ソースやらアオノリやらと混じってしまうとOKなのだ。で、その次の例はこの冷やし中華だ。も
ともとマヨネーズ以前に、冷やし中華そのものが解禁になったのはかなり近年のことである。
冷やし中華はきゅうり、紅しょうが、もやし、たまごなどの具に麺が絡んだものである。私は、こ
のように、メインの食材(ここでは麺)に、他の具がぐちゃぐちゃに混じったものが苦手だった。
山菜ごはんとか、ちらし寿司などもこれにあたる。具それぞれの味がくちのなかで混在するのが気
持ち悪くて、またせっかくのメインが味わえないのが嫌な理由である。
そういうこともあって、私は長らくご飯ものなどは、「ご飯純血主義」を貫いていた。ただ、これ
は相当いい加減なもので、ちりめんじゃこ、振りかけ、味付けのりなどは例外であった。夕飯を食
べるときなども、おかずは一品一品すべて平らげ、つぎに味噌汁などの椀物を片付け、最後にご飯
のみを食し、最後の最後でお茶のみを飲んでいた。いま考えると相当変だ。学生時代の途中くらい
まではそんな風であった。
それが、いつのころからか、自然と「三角食べ」できるようになり、そのころから「まぜまぜ」系
のものもだんだん食べるようになっていった。まぁ、味覚が大人になり、許容範囲が増えただけの
ような気もするが、舌の感覚として、細かいひとつひとつの味わいを分別して感じるのではなく、
ものの総体として捉えることができるようになったのだ。子供時代にそれができていたら、給食を
食べられず、昼休み残されたりしなかったかもしれない。
この舌の感じ方というもの、舌の感覚器官("味蕾"だったか)と脳神経の働きによるもののはずだ
が、個人差がかなりあるのは不思議なことだ。子供のころからいろいろなものがおいしく食べられ
る人もいれば、大人になってからわかる人、一生だめな人と様々だ。視覚や聴覚というものは基本
的にははじめから、あるいは幼少期にほとんどが完成されると思うが(あくまで基本機能の見る、
聞くとして。)そこからの個人的な発達というものに味覚ほどの差はないように思う。音感という
いうものは聴覚の発達というよりも、脳の部分の働きが高いのだろうが、これにはある程度の限界
点というか、飽和領域があるように思う。だが、味覚というものはそのような飽和はなく、際限が
ないように思う。やはり、味覚を感じる→ものを味わう行為は生存に直結するため、もともと強化
されているのだろうか。
最近になって、脳科学の分野が何かと騒がしい。名前を忘れたが、あたらしい概念が取り入れられ
たことで急速に進歩しているようだ。この分野がすすめば、非常にあいまいであった味覚や、ふれ
なかったが嗅覚の謎も明らかになるのではないだろうか。明らかになったからといって何かが変わ
るかどうかはわからないが、人間とは探究することをやめられない動物なのだから仕方がない。
ところで、残念なことだが、日月堂に問い合わせたところ、5月の連休中は外販の仕事のため、店
の営業はおやすみなのだそうである。このうえは神保町へ行くしかないかと思うが、日曜休日は休
みのところが多い。うん、今考えた。神保町以外の古書スペースが東京にはほかにもある。中央線
沿線、吉祥寺、荻窪、三鷹方面だ。手元にある「東京古本とコーヒー巡り」によれば、結構個性的
な古書店がそろっている。街自体も魅力的で写真もとってみたい。よし、行くぞ荻窪、古書音羽館、
興居島屋!
- 2005/04/22(金)
まもなく連休であるが、休みの3分の2は合唱をやっていることになる。で、残りの3分の1で
何をしようか考える。東京カンタートで東京に行くため、ここはやはり日月堂へ行き、ゆっく
りと、紙モノの森にうずもれたいと思う。ちょうど、2月末から3月にかけてパリで仕入れられ
た"新作紙モノ"たちが、展示されているはずだ。紙モノというジャンルはマイナーであるが、そ
れゆえに愛好者・コレクターの熱意は高いものがある。よい出物は結構すぐに売れてしまうので
ある。
しかし、ぱっと見で売れ筋のもの以外でも、ちょっと切り取って額装するだけで見違えてしまう
紙モノはたくさんある。ぺらぺらの状態の紙から、そういう場面を想像するのが選んでいて楽し
い時である。2月に行ったときは書類入れ2箱分を床に座って、一時間以上吟味していた。選ん
だあと、店主に「こんなの選んでみました」と"報告"するのも楽しい。これなんぞはまさにコレ
クターの戦利品自慢(?)みたいなものなので、理解してくれる人は少ない。
昔から旅行に行くとチケットやらパンフレットやら、レシートやら種々雑多な、その場で捨てて
しまうような紙モノを持って帰ってきては、ためていた。旅の記録とかいう形でアルバムなどに
まとめるなんて、几帳面なことはやっていない。ただ、かんかんに溜め込んで、ときどき発掘し
ては、「これはいつ、どこへ行ったときのやつだ」ということを思い出すのである。たいがいは
よれよれであったり、折り目がついていたりするが、それは旅行中にカバンにつっこんだり、胸
ポケットにいれてついた汗のせいであったりして、それら痕跡のひとつひとつがなんらかの記憶
と結びついている。そういうものがむしょうに愛おしい。
紙モノを買う理由はいろいろあるけれど、そういう誰かが残してくれた過去の痕跡を少しでも拾
い上げて、この世にとどめておきたいという思いが根底にはあるような気がする。いうなれば、
考古学者の気分か。時代のスケールが違うし、全然学術的じゃないけれど、探究心だけは受け継
いで、今日も今日とて紙を拾い集める。こっちにあるガス請求書も、あっちにあるNCのチケッ
トも、いつか次代の紙モノイストたちのコレクションになるのだろうかなんて考えながら。
- 2005/04/21(木)
今日の晩御飯はとんかつ弁当!ただのとんかつではなくて、「さぼてん」のとんかつ。うまい。
長岡京駅前ビルの案内図に「新宿とんかつ-さぼてん」の名前を見たときは、なんとこんなところ
に「さぼてん」が来るのかと半信半疑であった。今日は仕事が遅かったのでどこかで食べて帰ろ
うと思っており、それならせっかくだからと駅ビルに向かった。
ところが駅ビルをぐるっと回っても、ほかの飲食店はあるのに「さぼてん」だけが見つからない。
まだ、シャッターの閉まっているところもあるので、開店していないのかと、ややがっかり(たべ
る気満々だったので余計に)して帰ろうとしたのである。ところが、途中同じビルのスーパーの壁
に店の配置図を発見し、さぼてんの位置を捉えることができた。なんと同じスーパーの敷地内で
はないか?ややいぶしかみながら、店内へ。夜も遅いのにえらく盛況である...んんんひょっとし
てあれ、あそこか?スーパーのレジを出たところに、何店舗かテイクアウトの弁当や食材を売る店
があり、そのひとつに「さぼてん」の姿が。でもなんか雰囲気が違う...カウンター方式か、やや
狭そうであるし、こんなにぎやかなところで食べるのもなぁ。
!正面までたどり着いて、明らかになる真実。テイクアウト専門店だった。だったらそう書いてお
いて欲しかった。二度目の期待も、やや裏切られショック。しかし、腹がすいているので、弁当を
買うことに。会計のとき、「ポイントカードはありますか?」と聞かれ、
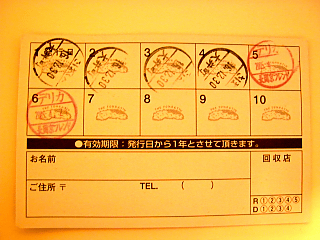
取り出したのがこれである。まさか、長岡京で使えるとは思っていなかったのでおそるおそる。
ちゃんとハンコ押してくれました。500円でひとつなのだが、500円未満を切り上げてくれている。
開店サービスだろうか?これまでこのカードには大井町(東京)のハンコしかなかったので、新鮮
であるな。
帰り際、ふと気がつく。
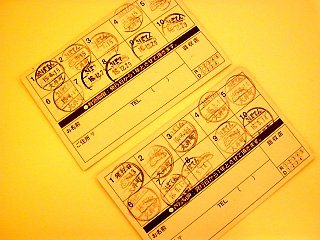
満杯になったカードを2枚も持っていたのだから、これで「ロースかつ」か「特ひれかつ」に交換
してもらえばよかったのだ。家にはご飯あるのだし。お腹が空いていると、いろいろ頭が回らない
ものである。
なぜ、そんなにカード持っているのかというと、前にも書いたが盆暮れの東京では、三日三晩とん
かつを食べるという風習があるため(うそ)、ポイントがすぐたまるのである。一食1500円と
して、3ポイント、それが3人分×3日、計27ポイント。一枚10ポイントのカードなど余裕で
コンプリートしてしまうのであった。いつもは特製ドレッシング(ごま&ゆず)に交換して、実家
への土産にしている。(せこい)
しかし、改めて見てみるとさっきも言ったように「さぼてん」以外の店もテイクアウト形態であり
狙ったようにレジ側で、駅からもっとも近い入り口からもっとも遠い入り口まで一直線に軒をつら
ねている。おそらくスーパーでは買い物をしないが、お腹はすかせている独り暮らしの通勤客をタ
ーゲットにしているのだろう。なかなかヤル。意図は違ったが見事にかかっているし。
スーパーを出ると、雨。あやや。きびすを返して、傘を買いに行くのだった。
開店しててよかった。
- 2005/04/20(水)
ようやく、volvicがもとの味に感じられるくらいまでに。NC合宿帰宅後のevianはおいしかっ
たので、やはり体調によって水も変えるべきなのだと感ずる。
傘が折れる。出勤途中に、突然。柄の根元からぽっきりと折れて、スポッと抜けてしまった。
まだ雨が降っていたので、傘本体を盾のように左手でむんずとつかみ、掲げながら歩いたので
あるが、疲れることこの上ない。ばねの力で傘は閉じようとするので、開いているのも一苦労
なのだ。右手には折れた柄を抜き身で持っていたので傍目にはちょっと危ない人だった。
兆候はあった。三週間くらい前に、急に柄が縮まらなくなって、調べてみると根元の部分が凹
んでいたのである。こんなところ何かとぶつけたりしようもなく、原因はよくわからなかった
のであるが、ダメージが蓄積されていたのか、今日の結果となってしまった。
思えば、この折り畳み傘は3コミケ(冬、夏、冬)くらいしかもたなかったことになる。近年
雨、風、雪の過酷なコミケ状況を勘案して、わざわざ登山専門店で買ったものだったのに...。
ダメージとしては昨年の台風と、冬コミの雪が大きかったのかもしれない。あまり、思い入れ
とか、思い出とかを残さずにお釈迦になってしまったので、特に感慨はないのであるが、私が
もつ唯一の傘であったので、実用的な面では困ったことになってしまった。今日は雨がやんだ
が、明日も雨だろうか。
何か、ものを買い換える必要があるとき、惜しむ気持ちもありながら、たいていはわくわくす
るものだと思うのだが、傘に限ってはあまりわくわくしない。デザインであるとか、機能面で
の進化がほとんどないので期待感が薄いからだろう。(女性はそうでもないのか?)つまり、
あまりわくわく感がないので、実用的に困っていても買うぞという気持ちが起こらないのであ
る。そんなわけだから、今日は早く帰れたのであるが、傘を買わずに本(漫画)なんぞ買って
しまった。500円以上買ったので、書店くじ一枚付き。
そいういえば、書店くじって今まで、抽選日まで残していた記憶がない。
一等、イタリア旅行60本。なぜイタリアなのか、わからないが二位の図書カード1万円分を
狙って、目に付くところに残しておくことにする。
- 2005/04/19(火)
『季節の営みの、まことに律儀なことは、ときにこの世で唯一信頼に足るもののように思える』
−「家守綺譚」南蛮ギセルより−
このような文章に出会うと、ああ本を読んでいて良かったなと心底思う。
季節は春。日向に居つづけると暑いくらいである。そんななか、ふっと春風が吹き抜けるのを
感じると、ふいにこのままどこかへ出かけたくなる。昼休み、食堂から居室へ向かう途中の道。
春の風というものは、夏の風のように「ああ涼しくて気持ちがいい」だけの即物的なものでは
なくて(それはそれでまぁ良し)、なにやら身体やら心やらに積もってなかなかとれない埃を
一気に吹き散らしていくような気がする。
思うに、季節の営みというものを何十年とこの身に感じながら、一度も春風に惑わされるまま
いまやっていることを放り出して、突然どこかへ出かけたりしなかったのはなぜだろうか。
勤めのある身としては、こころでは思ってもままならいのは仕方ないにしても、学生時代にそ
ういうことをしなかったのはとんと不思議である。時間のある身分ではそういうことも思いつ
かないものか。グリーで、工学部な当時としてはあまり時間があるような気分ではなかったし、
院生のときは夏休みも冬休みもなかったのであるが、所詮は学生の身分。
やはり、忙しい忙しいといっても勤労していたわけでなし、自由に対しての思いというのもは
現在には遠く及ばないのだろう。自由というか、制限されたなかでの何かへの思いというもの
は制限されればされるほど、水鉄砲の穴からとびだす水のごとく強いものになるのだろう。い
やむしろ、そうでなければ自分の意思とはいえないのかもしれぬ。
学生の時間のときには学生の時間のなかで感ずることが多くあったはずだ。いまは忘れてしま
ったが。そしては今は今で、今の時間のなかだけで感ずることがあるはずなのだ。春風に何か
を感じたように。歳を重ねていくということは存外面白いことなのかもしれない。こんなこと
をつらつら考えしまうのは、やはり春だからだろうなぁ。
- 2005/04/18(月)
恵文社バンビオ店オープン。バンビオというのは、よくわからないが長岡京駅前の複合施設の
名称らしい。会社を出た後、なんとなくそわそわしてちょっと早歩きである。JRの地下通路
を出て、見上げるとそこには暖色系の灯りがともる店が!そうだあれが新しい恵文社に違いな
い。駆け足に変更。施設自体はまだ工事中のため、道路はガタガタだし、もっとも近いルート
の歩道橋も使えずもどかしいったらない。一旦施設に入り、内階段で2階へ。そこから2階の
バルコニーにでて通路を進んでようやく到着。
すごい、すごいよバンビオ店。本が山のようにあるよ。インテリアは一乗寺店と共通で棚も同
じもののようだ。30分ほどかけて、それはもうぐるぐるぐるぐると歩き回る。店舗面積は前
の2倍以上あるので蔵書数が増えているのはもちろんだが、配架や本のセレクトを見ていると
以前に比べ充実度が高い。文藝コーナーでその傾向が強く、一棚一棚の趣味性やセレクトはか
なりのものだ。察するに配架設計にあたって一乗寺店のスタッフが絡んでいる。この店作りを
維持するために、異動してきているかもしれないな。
以前の店の特長であった、漫画・同人誌コーナーは狭くなってはいるが密度が高いので心配す
る必要はないようだ。ここで発見して読むようになった漫画も多いので以前のように応援キャ
ンペーンのような販促展開(オリジナルの展示など)は続けて欲しいなぁと思う。
さて、今日買ったものであるが、以下の3点。
・「鉄子の旅」2巻。
遠からず、買うだろうと自分でも思っていた。
・特別同人誌「恵文子ちゃん」。
なんと恵文社オリジナルの同人誌。全国でもこんなことをする本屋はほかにないだろうなぁ。
キャンペーンガールの恵文子ちゃんをテーマとした作家さんたちのイラスト集。何気にすごい
人たちが描いている。恵文社おそるべし、というか店長の宮川氏の人脈のなせるわざか。
(村田蓮爾、羽海野チカ、ワダアルコ、JASONほか、総勢22名参加)
・谷川俊太郎詩集「これが私の優しさです」(集英社文庫)
合唱をやっていて谷川俊太郎の詩に接したことがない人はあまりいないだろうと思う。合唱を
やっていなくても国語の教科書や、CMやらで目にすることは多い。しかしながら、その詩集
を買ったことがあるひとはなかなかいないかもしれない。わたしもそのひとり。子供のころは
文字の持つ、重みとか深さをなかなか理解できなかったから、すきまだらけのその本は文字の
わりには高いものだーなどと思っていたのかもしれない。
しかし、歌を歌うようになってから言葉の大切さを知り、合唱を深めていくにしたがって、
いままで知らなかった詩人達の世界に興味が出てきた。草野心平を知ったのも、北原白秋を
知ったのも(童謡の作詩者としてでなくて)、中勘助を知ったのも合唱からだ。なにげに全
部、多田武彦の作曲であるが、多田武彦の詩の選択眼の確かさというものは多くの人が語る
ところである。
この詩集は代表詩選集であり、氏の処女詩集「二十億年の孤独」をはじめとして20近い詩集
の作品が載っている。いろいろな詩人のセレクト棚に置いてあったもので、本当は一作一作
の独立した詩集を読んでいこうかと思っていたのだが、時間とお金を考えて文庫にした。
文庫であっても、言葉や詩のすばらしさが褪せるわけでもない。買うにあたって、ひとつ
だけ確認をした。「かなしみ」という詩が載っているかどうかを。以前、友が「今日は
詩(『かなしみ』)に書かれた空のようだ」と言っていたのを思い出したから。どんな空
なのか知りたかったのだ。
- 2005/04/17(日)
NC合宿、第2日目。やっぱり二日目の方がしんどい。
実は一日目の練習開始には15分ほど遅刻。理由は大阪までこれを買いに行ったから。
 
ライツ社、Summicron 50mm f2.0(Lマウント、沈胴型)。左、Summaron 35mm f3.5・右、Summicron。
面倒だとかいいながらも結局、カメラの大林まで行ってしまった。さすがに品揃えが違う。
Lマウントのレンズだけでも、50以上陳列されておりかなり壮観である。今回合宿の直前のた
め時間がなかったのだが、本当ならレンズと一緒にライカ本体をゆっくり見たかった。まずはと
にかく目当てのSummicronを探してみるのだが、これがなかなか見つからず。すぐ目に付くのは
同じSummicronでも固定胴鏡といって、沈胴しないタイプ。このタイプは中古価格が高くて10万円
はくだらない。
で、ショウケースをなめまわしていると、値段表がむこう側に向いているものがある。あ、鏡じゃ
なくて、向こう側にも陳列されてるんだと気づいて、回り込んでみる。反対側にもさらに50本の
レンズがあったのだ。その一番隅っこの手前に、このSummicronがあった。値段は...カメラを売っ
た収入とほぼ同じ。買える!(相場の最低ランク)
しかし、値段表には気になる但し書き「レンズ、カビあとあり」。うむ、それで安いのか。外見は
見ての通りの美品。どんな程度なんだろうか?直接見せてもらう。レンズにカビがあるケースは写
りに影響が出るけれど、「カビのあと」なら多少あっても大丈夫じゃないか?そこで直接見せても
らう。中古品なので細部のチェックはちゃんとお客自身がするのがルール。んん?見たところどこ
にもそれらしきものがないなぁ...。このカビあとってどこのことですか、と尋ねて店員さんにみて
もらう。店員さんも相当注意深くみて、「ほらここのはっしこの丸いやつです」と教えてくれるが、
これはほとんど肉眼ではわからないレベルで、写りに影響が出ようもないだろう。
「こういうふうにちゃんと書いとかないと、クレームが来ることがあるんですよ」という。まぁ私
としては、そのおかげで安い値段で買えるのだからありがたい。即、購入。
昨日、買ってそのまま合宿に直行したので、まだ一枚も撮影できていないが、いま本体につめて
いるモノクロフィルムは、Ultron,Summaron,Summicronの3つレンズでの撮影になり、どんな違いが
でるのか、非常に楽しみである。
おまけコーナー。沈胴レンズのヒミツ。
 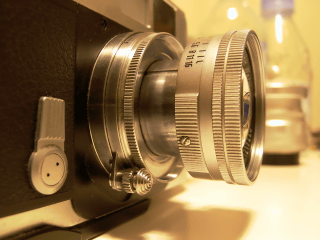
左、普段持ち運びはコンパクトに。右、撮影時にはこんな風にニュルニュルと伸ばして使う。
- 2005/04/16(土)
NC合宿、第1日目@青少年文化創造ステーション。宿泊は隣接の新大阪YH。
練習後、疲れを癒すために「鉄子の旅」を読んでくすくす笑う。
- 2005/04/15(金)
久しぶりにvolvicを飲む。実は日曜日の晩以来、飲んでいなかった。ずっとお茶ですごしていた
のである。というのも、日曜日の夜中に頭痛、熱、吐き気で目が覚めたときに、とにかく水分補
給だと思ってがぶがぶ飲んだところ、これがまた気持ちいいくらいに嘔吐を誘発してくれたから
である。飲み始めて、いつもはかろやかで甘い味のはずがが妙に違和感をあるなぁと思っていた
ら、お腹のそこのほうから、むくむくむく〜と何かが持ち上がってきた。あとはもう、あれだ。
以前、BKの飲み会の帰りにNaが「お酒に酔ってるときにvolvic飲むと気持ち悪くなるねん」と
いっていた意味が理解できた瞬間だった。ああ、こういう感じなんやろうなぁーと。うすれゆく
意識の奥でひとつの感覚をつかんだ瞬間でもあった。
とまぁ、そういうわけで復調しないうちに口にするのが怖かったんである。急にお茶を沸かす気
になったのもそういう理由から。今日飲んだときもいつもの感覚とはやや違って、ちょっと微妙
な味わいである。もしからしたら、こういうときは軟水ではなくて、硬水、たとえばevianの方が
すっきりするのかもしれないな。明日、飲んでみよう。
- 2005/04/14(木)
特許の仕事を中心にやる。締め切りをすぎていたので、短期集中。120%の状態で突っ走ると
側頭部の上あたりになにやらひんやりというか、刺激というか、じわじわ〜としたものがひろが
っていくのを感じる。これはTOEICであるとか、適性試験のような、極限集中思考をしたときに
よく似ている。特許は目をさらのようにして、請求範囲に抜けがないかを調べないといけない。
それも文章の表現相手なので、プログラムのようにロジカルに調べる方法というのはないのがつ
らいところー。
こちこちの脳を和らげるために、別のことを考えてみる。この前話していた一眼レフが社外工の
ひとに売れたので、臨時収入である。ここは一発、あたらしいLマウントのレンズを買いたい。
新しいといっても中古なのだが。それともう目星はつけているのだった。初代Summicronの50mmで
沈胴型のやつだ。沈胴というのは、読んで字のごとくで、レンズの胴体の部分が内側に沈むので
ある。コンパクトカメラで、スイッチを入れるとにょきにょきとレンズが伸びてきて、使い終わ
ると、するするともとのサイズに戻る、あれのことである。昔のレンズなので使うときは手動で
引っ張り出さないといけないだが、それがまたいいと思っている。
問題はどこで買うかである。以前なら京都のカメラのナニワの中古コーナーであるが、最近は
中古の出物が少ない。三条大橋のたもとにあったメディックスはかなり前に、中古専門店を閉め
てしまった。あとは大阪梅田の大林か。大林も交通の便が良かった三番街店を閉めてしまって、
大阪駅の桜橋に移転してしまった。阪急ユーザーにとってはあそこまでいくのはかなり遠い。
大阪駅前第三ビルに確か専門店があったが、一度しかいったことがないので不安である。
カメラのナニワ、梅田店ならいいかと思うが、ここしばらく行っていないので状況は不明だが、
開店から一年くらいして、中古コーナーが大幅縮小されてしまった経緯がある。以前は贅沢にワ
ンフロアすべてにガラスケースがところ狭しと置かれ、照明も暗く落ち着いた雰囲気だったのだ
が、縮小後はガラスケース2個くらいまでに圧縮されて見る影もなかったと記憶する。
こうして列挙してみると、中古カメラ業界の情勢というのは昨今かなり厳しい状態にあるようだ。
5〜6年前は中古カメラブームと言われたが完全に沈静化している。店が減る→流通が減る→買う人
が減る→売る人も減るという悪循環なのだろうな。まぁブームじゃないからこそ、やたら高値がつ
いたりしない可能性もあるわけで、静かに末永くやろうと思っているひとにとってはチャンスなの
かもしれない。ブームのころのライカなどは投機目的で売買するひともいたようだから。
うむ、あまり頭の固いのはとれない。やはり実物を目の前にしないと、想像だけでは無理なレベル
に来ているのだろう。昨日の暗室で妄想パワーを使いすぎたようだ。
今日はもう寝よう。
いや、40分だけマリ見て読んでから寝よう。
むむ、また声が聞こえる(空耳)。
- 2005/04/13(水)
体調の悪いときは本屋に行くに限る。会社の近くのおなじみ恵文社は、4/18駅前ビルに新装開店
する準備のため、休業中。オープンの暁にはお祝いを兼ねてたくさん本を買おうと思っている。
というわけで、本日は四条の談へ。
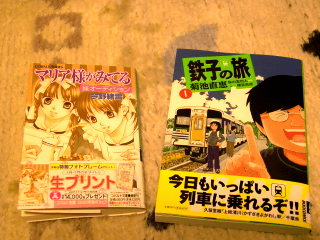
本日の二冊。両極端の世界...と思いきや、実は読者層はかなり重なっているはず!(たぶんね)。
「マリア様がみてる〜妹オーディション」(今野緒雪著、コバルト文庫、集英社刊)
前に、内容は書いたことがあったかなかったか。私立リリアン女学園の生徒会、『山百合会』が
舞台の学園もの。コバルト文庫、乙女の世界。表紙を見れば一目瞭然ですな。
読んだことがない人からすれば、「どうせかわいい女の子がいっぱいでてくるから読んでるんだ
ろう」と思われかねないのであるが、違います!断言する。非オタクの世界の人からすると、オ
タクの世界の理解というのは非常に均質化された一元論でとらえられがちであるが、そんな世界
の何が面白いのか?というのが「こちら側」からの意見である。(まぁ、そういう世界も含んで
いるという点は否定しない。)
このシリーズ(今回でもう19冊目だよ・・)の良いところは、純粋に学園モノとして面白いと
いうことである。大人になりきれていない高校生の純粋で真剣で、でもイマドキの高校生である
ところの心情や、高校生のときでしかありえない「上下関係」の機微。そういうものが、主人公
である普通の女子高生代表のような福沢祐巳の目を通して描かれている。この福沢祐巳は普通代
表でありながら、実はひじょうに丁寧に、飛躍することなく、ものの考えや、人の心情をただし
く理解しようと努めている。この姿勢が普通普通と言われながらも非凡なところで、非常に好感
がもてる。だから感情移入できる。シリーズが進むたびに「おっ、祐巳ちゃん成長したな」など
と思うのだ。
いまや、コミケでは一大ジャンルを築いてしまった「マリ見て」であるが、漫画でもアニメでも
ゲームでもなく、小説がこういう地位を占めたことはかつてなかった。もし、一元論的な理解で
あれば、こういうことはありえなかったはずだ。でも、実際にある。両の目をカッと見開いてこ
ちらの世界をちゃんと見て欲しい。一人一人にとって、そちらにはなくて、こちらにあるものが
何かあると思う。(ようはコミケにおいでよーと誘っているわけですね。)
「鉄子の旅」(まんが:菊池直恵、旅の案内人:横見浩彦、IKKI COMIC、小学館刊)
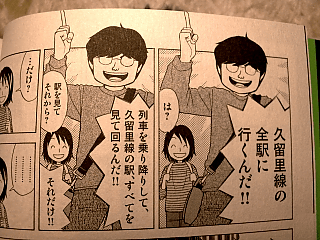
こういう漫画デス。
目次を見れば、さらに理解が深まることでしょう。
第1旅 久留里線全駅乗下車
第2旅 130円・一都六県大回り
第3旅 東京-鹿児島2泊3日鈍行の旅
第4旅 長野電鉄「木島線」最終日
第5旅 土合・湯檜曽・・・鉄子流デートコース
第6旅 大垣夜行で行く有田&紀州鉄道
第7旅 岩手県の自然を味わう旅
第8旅 銚子電鉄全駅乗下車
・・・どんなもんでしょ。これはすべて実録。鉄道に興味のない漫画家が、鉄道好きに日本全国
つれまわされるお話。しかし、一巻のなかに二つも「全線乗下車」が含まれるとは恐ろしい。
私も元来鉄道好きで、中学のときは鉄道部で上のような旅行をよくしていたので、よくわかる。
そして、寝食を忘れるほどの入れ込みはできず、一般以上、マニア未満の立場でもあるので、
鉄道に興味のない人が引っ張られることの恐怖もわかる(気がする)。この本の作者もそうで
いやでいやで仕方なかったことも途中から、ごくごく一部だけでも「なんかいいな」とか思う
ようになっていく、そういうのがシチュエーションとしては好き。(なんのシチュエーションか)
店頭に一話だけ読めるお試し版があり、それを読んで購入を決定。みんなも探してみよう。
ああ、こうやって二冊並べるといったいどちらから読めばいいのだ。
大いに悩む。
(「実はまだちょっと目がつらいが、本を読めば直る。」)
(「そんなことしてるからだめなんやてー」という声が聞こえる。)
(「30分だけマリ見て読ませてくれろ。」とお願いしてみる。)
(「しゃーないヒトやなぁ30分だけやで。ほんとに(といいつつ目を細める」)
( −夢見がちな日常。終劇- )
- 2005/04/12(火)
夕方から目の疲れがひどいため、あまりPCに向かって思考できず。書きたいと思っていたこと
のトピックスのみ記述。面目ない。
・くすり(大衆薬)はなぜ高いのか。
・びんづめの錠剤、上部の三分の一はなぜ空き空間となっているのか。
・コミックマーケット68受付確認ハガキ到着。(当落通知は2ヶ月先。)
・4/10 合唱指揮者、関屋晋氏逝去。R.シュトラウス、Drei Mannerchoreと鉾をおさめての思い出。
・4/9 建築家、清家清氏逝去。建築界の大物が相次いで亡くなっていく。
目の疲れをとるために「アリナ○ンEX」が欲しいところであるが、高くて手が出ない。
今度実家に帰ったときにストックをもらってこよう。
- 2005/04/11(月)
久しぶりにご飯を炊き、お茶を沸かす。しばらく米が切れていたのだ。
食欲がないため、ご飯一膳を味付け海苔で食べる。食後の番茶が非常にうまい。疲れて果て、気力
がなくなった体を落ち着かせ、整え、回復させてくれるようだ。
思うに、ここしばらく水を日常の水分補給源としていたので、かつて日常のものとしていたお茶を
それほどまでにおいしく感じたのだろう。酒断ち、煙草断ちなどはよく聞くが、茶断ちは昨今では
聞かない。茶が日常のものではまだなかったころには、何かを祈願するときに茶断ちをしたという
ようなことを、古典だか、落語(もし落語だったらあまり古い話ではない?)で聞いたことがある。
別に目的があって茶断ちをしていたわけではないが、結果的に同じ状況になったため、何か断って
いたものを解禁したときの「そのものの旨さ」を味わい、その気持ちを理解できたように思う。な
にごとも、日常的に食べたり・飲んだり、あるいは体験していると、そのものの新鮮さが失われて
いくことは皆さんも日々経験していることだと思う。そういうときにちょっとした我慢をし、葛藤
することで、そのものの良さを知り、新しい味わいを発見できるというのは、生活に潤いをもたら
すように思う。
食べ物には旬というものがあり、旬の時以外は手に入らないか、食べてもまずかった。いまは旬と
は関係なしに手に入るせいか、多くの「ありがたさ」がうせてしまったような気がする。どちらか
を選べといわれると困るのだが。この旬のものをありがたがるという性質は、別の形でいまも残っ
ていると思う。DVDでよくある「初回限定」がそれだ。旬とは直接関係なくなって、手に入らな
いという点だけ残った。こういう食・商習慣ともいうべきものは、外国にもあるのだろうか。
さて、久しぶりにひどい体調不良になったのであるが、この頭痛やらいつまでも消えない肩こり、
倦怠、吐き気、胃部不快感というのは、久しぶりになったからといって、うれしいものではない。
病気や体調不良という負のものには「断ち」の効果はないようだ。当たり前か。もし、『あ、頭痛
になった、イイ感じやー』とか言い出したら困る。
- 2005/04/10(日)
晴れている。普段、天気予報は見ないので雨が降るということをK岡から聞いていた。どうやら
はずれてしまったようである。ちなみにK岡は私に天気を教える係とかではなく、「桜を見るな
ら土曜日中や」ということを言っていたのだった。
東京カンタートの練習に大阪へ。練習場についてから気づいたのだが、YKにとっては普通の練習
日であり、カンタートの曲だけやるとは限らない。もらった楽譜のうち前半5曲しか音をとってな
かったのでやばいなーと思っていたら、案の定やってなかった二曲から練習開始...。
指揮者は同じなのに、団が違うというだけでこんなにも緊張するとは思っていなかった。NCや
BKで一緒に歌っているメンバーもいるというのに。やはり団には団の個性がはっきりあって、
それに馴染むためには時間が必要なのだと思う。
そういうわけで大層疲れてしまった。そうそうに帰宅し、途中マッサージ屋さんで凝りをほぐし
てもらった。が、いつもやってくれる店長さんではなく別のひとだったのでいまいちであった。
指名制にできないもんかなぁ。
早めに寝て休むことにする。
- 2005/04/09(土)
晴れている。普段、天気予報は見ないので晴れるということはK岡から聞いていた。どうやら
正しかったようである。
朝、洗濯物を干す。ようやくベランダに出ても寒くなくなった。今後の課題として、春夏の洗濯
回数の増加に備え、物干し竿の追加配備が必要なことがあげられる。現行装備の伸縮型ものほし
ざおは、マンションのゴミ置き場から調達してきたものであり、経年劣化等の要因でこれ以上の
加重への適用は不可である。昨年はベランダの手すりを活用してしのいでいたが、風による落下
が多く、そのたびに洗いなおしが生ずるため効率が悪かった。
昼、花見にでかける。
うちの近くの仏光寺へ。ここにはどういうわけか、宮妃お手植えの桜が数本ある。いずれもしだ
れ桜で、枝ぶりが非常に良い。あまり知られていないのか、雑誌などに掲載されているのも見た
ことがない。人が少なく、境内に座ってのんびりできる。本堂の修復工事のため、三笠宮妃お手
植えの桜以外は、白い囲いのなかで、足場の間からわずかに見えるのみ。窮屈そうな桜がなんと
もかわいそうである。
寺町へ。母の実家の菩提寺がある。墓参りがてら桜を見る。墓のすぐそばにあるため、ここまで
桜を見に来る観光客はまずいない。街中の寺なのに、おだやかな静けさを保っているこの場所が
子供のころより好きである。母方の祖父母は私が生まれる前になくなっているのだが、そのわり
にはあまり縁遠く感じないのは、折につけ母がここへ連れてきてくれたからであろうと思う。墓
参りのあとは、寺町からくだって大丸や高島屋にいけるということも、子供にとっては魅力的で
はあった。
その後、昨日通った道を逆に進み、冷泉通りに至る。しかし、恐ろしいほどの人出である。昨日
夜桜を見ていてよかったと思う。

は〜るのうら〜らのぉ〜すぅみぃーだがわ〜、といいたくなるが疎水なのだった。屋形舟がでて
いた。誰か手でも振ってくれるかと思ったのだが、皆一様にうつむきがちである。恥ずかしいと
いうよりも、あまりの陽気に中てられたような感じ。
四条京阪より京阪にて大阪へ。北浜で下車。
 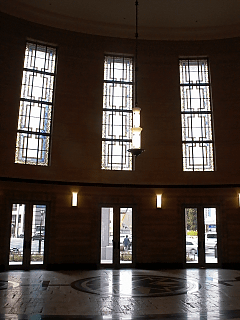
大阪証券取引所を見るためである。数年前、北浜淀屋橋界隈の近代建築を写真に収めていたとき
すでに証券取引所は解体工事が始まっていた。大層くやしかったのであるが、その後の工事をみ
ていると、特徴のある丸型のファサードだけは解体されていなかったので期待をしていたところ
最近になってリニューアルが完了した。以前の姿はよく思い出せないが、あまり違和感なくかつ
てのファサードと隣接る高層ビルがつながっている。これは建築保存の好例のように思う。
付近の建築の無事を確認しながら、NC練習のため本町まで歩く。この界隈は証券・金融・商社
・繊維問屋の近代建築が多く残っている。本業として現役のものだけでなく、うまく改装して
別の業種に生かされているケースが多い。跡形もなく破壊されたということは少ないと思う。
大阪の人間は効率優先のように世の中には思われている節があるが、効率優先、経済優先、土地
優先で、つぎからつぎへと建築を破壊しているのはむしろ東京のほうではないだろうか。
練習場から徒歩10分ほど離れたところにある紀伊国屋書店に立ち寄る。ここはスペースが広い
が全体の見通しがよく、すきな書店のひとつである。(阪急梅田の紀伊国屋は大嫌い)
今日は時間があるので端から端までじっくり見ていく。以前はあまり気づかなかったが、スペー
スを生かして雑誌のバックナンバーの平積みが多い。それも単に雑誌コーナーにあるのではなく
て、その特集に応じたジャンルに配置されている。だから建築コーナーに、Meetsと大阪人が一緒
に並べられていたりする。こういう試みはほかの書店ではあまり見かけなかったりする。
さて、店舗の西から東へ移動すると、やはりあった。本屋大賞コーナー。予想よりもはるかに書
店に根付いているようだ。しかもジュンク堂では未対応だった、あのHP掲載のオリジナル帯が
カラープリントされてすべてのノミネート本にかけてある。エライ!
「対岸の彼女」の余韻があるため長編小説は控えたい(ってすでに何か買う気になっていた)
と思っていたところ、目に付いたのが「家守綺譚」(梨木香歩著、新潮社刊)である。28の
掌編からなるのだが、冒頭の『サルスベリ』を立ち読みして、やられてしまった。文体がそう
明治時代の文豪のごとく、余計なものがそぎ落とされ、陰影のはっきりした実に心地のよいリ
ズムを持っていて、まあそれは時代設定のせいかもしれないが、これがいい。好みである。
綺譚であるから、不思議なお話ばかりである。亡き友の実家である庭付き、池つき、電燈つき
の二階家と、家守の「私」に起こる”あやかし”の世界。それは現実のものではないはずなの
に、この本を読んでいるとそれがあってもおかしくないと思える。だって、『サルスベリ』な
んか、庭の"サルスベリの木に惚れられる"の話ですよ?そのうえ床の間の掛け軸から亡き友が
時々出てきたりする。それがちっとも不思議ではないから不思議だ。まぁだまされたと思って、
まずは冒頭だけでも読んで欲しい。気に入らなければ、立ち読みだしお金もかからない。
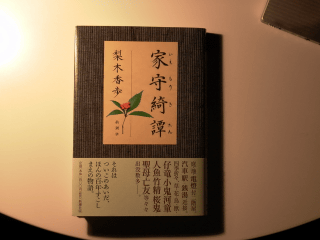
写真も本の雰囲気にあわせてみた。
ああ、また一編、また一編と読みついでしまう。危険である。思いきって寝よう。
おやすみなさい。
- 2005/04/08(金)
夜桜、千鳥ヶ淵ではなくて、鴨川東岸の桜を見ながら荒神橋から二条まで歩く。
途中、桜迷路のようなところで立ち止まり、手をのばしてそっと花びらに触れる。やわらかい。
こんなに、やわらかい花はほかにないないように思う。やさしく手を触れる。匂いをかぐとほの
かに甘い。天を仰ぐと幾層にも枝が重なって視界がすべて埋め尽くされる。空が降ってくるよう
な錯覚をおこす。そのすきまに星ひとつ。周りの色がすべて消え、ただ桜の白い花だけがうかび
あがっている。ライトアップなんかしなくても、ただそれだけできれいなんだということに気づ
いた。
本日のお酒
佐々木酒造、蔵出原酒・・すきっとして、飲みやすい。後味がじわわ〜と気持ちいい。
佐々木酒造、古都・・・・丸みのある口あたり。でも舌のうえでぱっとはじける潔さ。
浦霞(宮城)・・・・・・薄く丸い口あたりでするるとのどの奥までくる。初めての感覚。
立山(富山)・・・・・・スタンダードですごくシンプル。私にはきついかも。
「対岸の彼女」読了。阪急のなかで読んだあと、とまらなくなって、人通りが少なくなくる御池
から荒神口までの間を歩きながら読む。残り40ページくらいからの静かな胸のたかまりをその
ままにしてBKの練習に出ることはできなかった。練習場に入ったとき残り二ページ。ちょうど
休憩になったので、本を抱えて外へゆき、もどかしく階段に座る。
手のひらにひろがる残り二ページには、はるか昔と今とを一瞬にしてつないでしまう魔法があっ
た。ただ、何も考えずにいたあの遠い昔と生きることに一生懸命な今が、ぜったい相容れないと
思っていたものが、ふいに通じる。胸の奥の深いところではなくて、それはなんだかもっと身近
なところにあるはず。そんなふうに思った。
なんども反芻して、練習場に戻る。ほんの少ししか時間はたっていなかった。だのに幾日も旅に
でていたような不思議な充足感がいつまでも続いていた。
さくら、きれいだった。ほんとうに。
おやすみなさい。
- 2005/04/07(木)
届いた。
PSE PRODUCTS #01 SKIPPER.
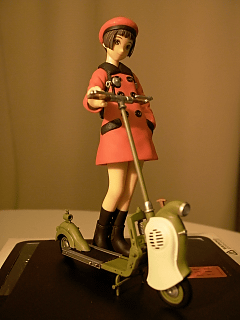 
どこから見ても絵になる比類なきデザイン。デザイン・監修、村田蓮爾。
 
女の子の名前は竹緒。SKIPPERも、竹緒のコート、帽子、ブーツ、リュックもすべてオリジナル。
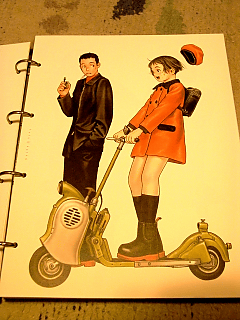 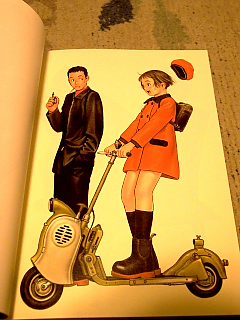
原画。左がfuturhythm版、右がrefuturhythm版。インクが若干違うのです。
定食屋で豆腐を食べたら、なんだか変な味だった。ソースをかけていた。
今日は相当疲れている。
おやすみなさい。
- 2005/04/06(水)

買ってきたもの。

買うであろうもの。(4月27日、5月27日、6月28日)
"long life design"は2号目は出るのかと心配になってきたところでちゃんと出た。
本の雑誌増刊「本屋大賞2005」(本の雑誌社)は昨日の今日であるが、ジュンク堂に入って
正面にどーんと、「夜のピクニック」と並んで置いてあった。やるなジュンク堂。昨年・今年の
大賞・ノミネートも含めて並べてある。この雑誌のポイントは3つである。
ひとつ、「本屋大賞メッタ斬り!」(大森望×豊崎由美)が秀逸。立ち読みするならここを読む
べし。ふたつ、1次投票の結果と推薦文。なにごとも、大多数の同じ意見よりも、主義主張いり
みだれる少数意見のほうが面白いと相場は決まっている。みっつ、あるノミネート作品の書店員
さんの推薦文のなかのひとこと。『・・「よかった」「泣けた」だけの感想は、もういいかげん
やめにしたいと思う。』。この言葉を目にしなければ、もしかしたら買わなかったかもしれない。
井上ひさし、彼の著作に出会わなければ、私はこれほどまでに「ことば」を「日本語」を好きに
なれただろうか。
******
春の匂いが漂ってきた。一度帰宅してから、普段着に着替えて、いつもより薄着で自転車に乗って
出かけた。デジカメの写真をプリントアウトしたのと、プリンを買うだけの短い時間だったけれど
も。もう一度出かける気分になる、これが私にとっての春の定義かもしれない。
- 2005/04/05(火)
帰宅してなんとはなしにニュースを見ていると「2005年本屋大賞」決定のニュースをやってい
た。おお、ニュースになるまでになったんだなぁ本屋大賞。
本屋大賞とは、本屋さんを表彰する賞ではなくて、本屋さんが本を表彰するのである。つまり、
いわゆる文学賞みたいなものだ。文学賞と違うのは主催が出版社ではないこと、選考委員とよばれ
る人がいないことだ。じゃあどうやって選ばれるのかというと、全国の有志の書店員の「投票」に
よる。主催も、書店員有志である。本屋さんが実際に読んで、これはいい、みんなに読んで欲しい
と思ったものを熱烈に推薦し、投票する。出版社の理屈ではなくて、現場の声で本を売るためには
じめたものらしい。
2004年から始まって、第一回の本屋大賞は、ライブラリーでも紹介した小川洋子著「博士の愛した
数式」である。そして、第二回の大賞は恩田陸著「夜のピクニック」。名前だけは聞いたことがあ
ったのだが、女性だったんだなー。ちなみに、わたしが今読んでいる角田光代著「対岸の彼女」も
ノミネート10作品に入っていた。(会社の生き帰りに細々と読み続けている。)
さて、この本屋大賞のいいところは選考の方法はもちろんなのだが、選ばれる本の傾向がいわゆる
非常に一般受けしそうなベストセラーからやや外れているところにあると思う。いい本が必ずしも
売れる本ではないことは現場の書店員さんは身にしみてわかっている。だからこそ、いい本を売り
たい、読んで欲しいという強い思いがノミネートに現れていると思う。最近の書店ベストセラーを
見ると、大半は実用書か中高生しか読まないような泣かせの恋愛小説しかなくて、見ていて悲しく
なるときがある。それは書店員さんも同じなのだろう。
もうふたつある。この本屋大賞を受賞しても、出版社の賞ではないから当然、販売促進の施策を
出版社がとってくれるわけではない。だったら、書店の側からやろうというのだ。オフィシャルの
HPには、受賞やノミネートをアピールするための販促グッズがPDFファイルの形で掲載されて
いる。本につける帯やカバー、ポップ、ポスターの類である。全国の書店に向かって、自分達の手
で売りましょうとアピールしている。熱意がなければできることじゃない。
オフィシャルHPはこちら→http://www.hontai.jp/index.html
で、もうひとつのいいところ。副賞が、図書カード10万円分!そう、作家さん自らに本を買って
もらおうというのだ。なんて気が利いているんだろうか。第一回の受賞者の小川洋子さんが購入し
た本とその解説が→http://www.hontai.jp/winner2004.htmlに掲載されている。10万円あったら
どんな本が買えるだろうか。自分のことでなくてもわくわくする。そして、その人がどんな本を買
うのかというのはとても興味深い。個性がそこにはあらわれてくるからだ。そのリストを読んだわ
れわれが、そこで新たな本を知ることができる。そういう連鎖がなんともいい。
まだ二回だけれど、これから何回も、何十回も続いていって欲しいと思う。
追記:
YKの楽譜届きました。楽譜を手配してくださったCさん、CDを手配してくださったkatoponさん、
そして楽譜をハンドキャリーしてくれたNaに感謝します。
- 2005/04/04(月)
実験開始。
おととい、NCの練習に行くとき駅で水を買おうと思ったらevianしか置いていなかった。ずいぶん
と水を飲むことにも慣れたので、もしかしたらevianもおいしく感じるんではないか?と期待を抱い
て買ってみたところ、やっぱりevianはevianの味で、volovicとは違うのだった。なにか、辛いお酒
を飲んだような後味が舌に残る。前に飲んだイタリア産のものよりも、いくぶんソフトなのだけど、
がぶがぶ飲めないなーという感じ。ミネラルがきついのだろう。
そういうわけで、NCの練習のときにとりあえずのどを湿らすために飲んだだけで、結構あまってし
まった。昨日も飲みきれず、そのうえvolvicを補充したので、今日も余っていて、あと少しある。
そこで思いついたのであるが、volvicとevianをブレンドしたらどのような味になるのだろうか?
さっそく、湯のみに1対1で両者を混合、よくかき混ぜてみた。
いろ:変化なし
匂い:判別できず
で、味であるが、evianに比べると飲みやすい気がするが、うまくもまずくもない。ただ蒸留水のよ
うに味気のないイメージではなく、ちゃんと味はある。後を引かないという変化ははっきりした。
で、比較のためにevianを飲んでみると、舌が慣れているせいか似たような味。volvicを飲むとあき
らかにすっきり味。逆に甘〜い感じがする。うむ、ブレンドしてもやはりevianの個性は簡単に埋没
するものではなかったようだ。なかなか歯ごたえのある奴。
成分表をみたところ、
ナトリウム カルシウム マグネシウム
evian 0.5mg 7.8mg 2.4mg
volvic 1.16mg 1.15mg 0.8mg
(100mlあたり。volvicにはさらにカリウム0.62mg含有。)
という違いがあった。カルシウムで7倍、マグネシウムで3倍も違いがあったら、そら味は変わる
よなー。1対1でまぜてもあまり意味はなかった。そこで今度は1対3(vol増量)くらいにしてみ
た。マグネシウムを1対1にし、唯一volvic有利のナトリウムを増量、カルシウムを半分のレベル
に持っていった。
うおー、まだevianのテイストが若干の残っている。ずいぶんと飲みやすくなったが。それでもま
だ安心できるレベルではない...。ということで、彼我の違いの大部分はカルシウム含有量に起因
するのではないかという、非常にアバウトな実験結果が導き出された。これから店頭で、volvicも
evianもなく、他の水を見かけた場合、カルシウム量に着目して購入するかどうかを決めてみたい。
実験終了。
- 2005/04/03(日)
第5回ジャパンユース合唱団演奏会を聞きに神戸へ。三宮から徒歩でJR神戸近くまで移動。かな
りの陽気で上着はいらなかった。
ジャパンユースの演奏を聞くのは二回目であるが、単独の演奏会としては初めてだった。いつもの
ようにわかりにくい例えをするならば、この合唱団の音楽は「風」だったと思う。
音楽が空から降りてきて、聞く人のこころをやさしく撫でて、すぅーっと通り抜けていく。演奏会
だぞということで身構えなくてもいい。ただ、そこに身体をさらすだけで気持ちがいい、そんな歌
声だと思ったのである。個々人の力というものはユースということで十分すぎるほとすごいのであ
るが、そのレベルをさらに飛び越えて、ひとつの合唱としてのふところの深さのような「柔らかい」
音楽が常に流れていた。
演奏に臨むにあたって合宿をし、すごい練習を積んでいるらしい、ということは聞き知っていたが、
音楽にはそれが出てこない。がむしゃらでもない、かといってはるか高みにあって手の届かないよう
なクールさでもなくて、あたかも「風」のような自然なものがあったと思う。
演奏会のうちのほとんどを目を閉じて聞いていたら、そんなことを感じた。
眠くなったりしない、でも無理やり覚醒させるものでもない、だから目を閉じたまま演奏を楽しめた。
そんな一日。
- 2005/04/02(土)
 
BESSA-R with Summaron 35mm f3.5 and ULTRON 35mm f1.7
美しいものを眺めていたい、手を触れていたい、自分のものにしたいという欲求、写真とカメラに
はそのすべてが詰まっているような気がする。
ULTRONのレンズキャップを触ったNaは、「カメラじゃないやろコレ...」とつぶやいた。それは正し
く、これらのものの本質を捉えた言葉だったかもしれない。本当にすばらしい工業デザイン(もの
フォルムだけでなく、存在感や手触りといったものを含む)というものは、人間の五感にうったえ
かけるものがある。そのものの本来の用途を満たしながらも、なおそれ以上の「何か」を放つ存在。
ただの金属の物体であるはずなのに。
昨日、BKの宴会の場で、久しぶりにBESSA-R+ULTRNを使ってみて、別のレンズも使いたくなった。
そこで今日、実家に帰って保管箱から取り出してきたのが、Summaronである。ライツ社のLマウント
レンズ。5年以上前に購入して、一度だけカラープリントで使っただけだった。今なら、自分の腕で
もいい写真が取れそうな気がした。いま詰めているのはモノクロフィルム。Summaronが現役で使わ
れていた時代にはモノクロが普通だったから、こちらのほうがあっているように思う。
現代のULTRONと、半世紀前のSummaron、いったいどんな違いが出るだろうか。
打ち明け話:BKではみな、このカメラを初めてだと言っていたが、実は松下耕合唱講習会のレセプ
ションに持っていって、そのときもモノクロで撮影している。あの頃はみんな若かったね。
- 2005/04/01(金)
新しい年度。今年の年休計画を提出したら、課長に「ほんとにこれでいくのか?」と聞かれたので
「えっ、とりすぎということなんやろか」と思い、どこかまずいですかと聞きなおす。どうやら、
もらえる年休のうち9割以上を消化する予定になっていて、残り2日しかないことにおどろかれた
ようだ。つまり、『計画以外に君はたぶん体調くずして休むやろ』ということがいいたかったよう
であるのだ。こちらとしては、その体調悪くて休む分を織り込みずみで計画したのである。
9割とるといっているのに、5割しかとらなかったりすると、組合との協定でまずいというのもあ
るらしい。たぶん大丈夫、一年の合唱計画から考えてここらへんは計画突発年休を取るというのを
考えてのことであるから。また、年が明けてからの後半戦はわりと合唱OFFシーズンなので、
休むことは少ない。昨年、最後の年休を郡山後にとってからは、体調にきづかってなんとか休む
ことなく年度末を迎えられたし。(一年通じて、気遣えよという意見もある。)
ほんとは精神的にはある程度のマージン、つまり過去の年休未消化分の積み立てがあるといいので
あるが、入社してからの分は2003年4月に休職したときに全部使ってしまった。入社したころはほん
とに年休が必要なかったのだが、いまは無理だー。
今日、興味と成り行きと、ちょっとの天の配剤によって東京カンタートで歌うことになった。
最終日の日曜一日で回復させないと突発的計画年休が増えてしまうな...。
プラネテス4巻を見て寝ます。、
|
|