|
電波暗室 2005/06
- 2005/06/30(木)
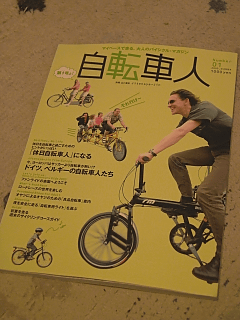
「自転車人」第1号(別冊山と渓谷、山と渓谷社)
ゆえあっての連続・長時間残業もなんとか終わり。疲れを癒すべく、本につかる。といっても、
目がいたくて頭も重く、文字が読むのがつらかったので、流れるプールよろしく雑誌コーナーを
つらつら眺めて過ぎる。時計コーナー、ああバーゼル特集はこの前買ったし、芸術新潮..今月は
民芸の特集、お、和田誠の小特集もある、これはいいな、鉄道コーナー、そろそろ18切符とか
夜行列車の特集シーズンだねー、カメラコーナー、さらばコンタックスか、京セラはとうとう写
真をきってしまうか、さすがだね(皮肉っぽく)、っととと。アウトドアコーナー前、自転車支
部に到着。
自転車を買ってから、やはり気になる自転車情報。7月2日からはツールドフランスも始まるこ
とだし、いい本はないかなと探してみる。すると、あれ結構あるのだな、自転車の雑誌。けいぶ
ん社が特別なのかもしれないが、ぱっと見るだけで6〜7冊、特集扱いの一般誌をいれると10
近くも並んでいる。これは比べ応えがあるというもの。で、ながめていて気づくのは、自転車雑
雑というと、どうしても自然豊かなところへ本格的なツーリングに行くか、ツールのような欧州
のレースの2つの特集記事に大別されてしまうようだ。昨日、今日、自転車に目覚めたような私
のようなビギナーが読んで面白いものは専門誌では扱いにくいのだろう。
そんななか、見つけたのが「自転車人」。雑誌に”〜人”がつくものはなんとなく、あたりのよ
うな気がして、手にとって見た。ふむふむ、おー、私が一番読みたかった「街乗り自転車」が冒
頭で特集されている。街乗りでいかに楽しむかが、実際のコースに沿って書かれている。当然な
がら自転車そのものや、アクセサリーのカタログも載っているが、その記事と無理なく連動して
いて、単なるカタログっぽくないのがいい。街乗りのあとは、長距離ツーリングの記事だ。初心
者とベテランの組み合わせで、楽しみかたや、注意点があり、最後にノウハウがまとめてある。
あくまで初心者がやってみたくなったときに、どうすればいいか?を丁寧にフォローしているつ
くりがいい。…なんだか、「雑誌のつくり」に視点がいっていますか私?
もうひとつの特集は、「ドイツ・ベルギーの自転車人たち」。欧州の普通のひとたちが、ふつう
の生活のなかで、どんなふうに自転車にかかわって、どんな自転車にのってるのかが紹介されて
いる。日本との違いは、「自転車専用道路」があるかどうかが大きいみたい。日本じゃ、日本道
路公団は自動車のためにしか道路作んないもんなぁ。あっ、いま唐突に気がついた。なんで自転
車に魅かれたのか。電車と同じ「酔わない」からじゃなかろうか。
そのほか後半の読み物記事では、京都自転車紀行があったりして、それがなんとなくうれしく。
初心者がぱっと眺めて、読むにはかなりいい。もう一冊、別に初心者向けの本があったのだが、
特集の組み方や、レイアウト、それからカラーページ以外の編集のよさでは、自転車人にいま一
歩およばすという感じであった。(あっ、また「つくり」の視点になってる)
ところで、これはどうしても仕方のないことだが、街乗り自転車特集は、やはりというか東京が
舞台。あ、いいな、こういうコースで走ってみたいなと思っても、東京まで愛車を持っていくの
は難しい。レンタルサイクルでは、なかなかいい自転車はないもの。東京に限らず、どこかの都
市をとりあげるとやはり、近隣のひとしか楽しめない。自転車にはこのジレンマどうしてもつき
まとうのだ。もっと気軽に、簡単に自転車を運ぶことができる公共交通機関があればいいのにな
と思ってしまう(自動車に頼るのは嫌)。10年前、グリーの演奏旅行でドイツ、ベルリンにい
ったとき、ほんとうに日常的な感じで電車の最後尾車両に自転車が立てかけてあったことを思い
だす。(実はこの話には後日談があるのだが、それはまた。)
<おまけ>
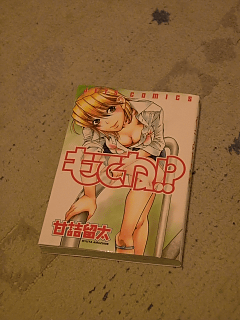
「もてね!?」甘詰留太著、JETS COMICS(白泉社)。
あー、えー、まー、これはなんとなく。甘詰留太なので。
- 2005/06/29(水)
以前書いた特許の明細書を特許事務所が修正したものの、修正確認チェックをやっている。同じ
特許で実に三度目である。一回目でかなり大幅に「訂正」し、二回目で小幅に「訂正」し、これ
でももう大丈夫というくらいの再修正指示書を書いて、送り返した。のであるが、三回目のチェ
ックをやっていると、修正指示書の内容が全然理解されておらず、ショックを受ける。そのうえ
修正された部分の文脈がおかしくて意味を成していないことに気づく。…どうも今回も怪しいと
思って、読み進めていくと、修正指示のない場所で独自に修正がかかっていることを発見して、
もういやー!という気分になったので、帰宅した。
自分の出した修正指示書がおかしかったのかと思い、読み返すが実に論理明晰であるなぁーと自
画自賛したくなるわかりやすさ!この日本語がわかってもらえないとなると、非常に困る。自分
が書いた明細書から、あきらかにブラッシュアップされているのはわかるのだが、ところどころ
で推敲していないとおぼしき箇所が第一回から散見されるほか、論理的に通らない部分が多すぎ
るのだ。この特許事務所。
特許を代理出願する弁理士は、国家資格である。弁護士や医師国家試験に匹敵するか、それ以上
の難関とも言われている。その理由は明白で、さまざまな権利条項をすべて文章、言葉のみで漏
れなく網羅するため、類まれなる国語能力・技術が要求されるからだ。ひとつひとつの文書に、
個人の、会社の未来を左右しかねない重みがあるのが特許なのである。
それなのに、一介の技術者にこれほどまでに、文章の非論理性を指摘させる弁理士、特許事務所
っていったい"どやねん"(cf. MBS『せやねん』)。ぷんぷん。たぶん、「たいした特許じゃな
い」から、手を抜かれてるんだろうナァ。それはそれで非常にくやしい。
あたまクラクラのまま帰宅。「椰子・椰子」川上弘美著、新潮文庫を読む。あたまがスコーンと
晴れやかになり、「ぷんぷん」も脱力感もどこかに行ってしまった。これも同じ文章の力かと思
うと、ほんとに不思議なものだ。
「前線通過、前線通過」と、唱えてみる。雨、降るかなー。
- 2005/06/28(火)
ようやく降ったと思った雨も止んでしまいましたなぁ。京都。
毎年、夏場の入浴はシャワーで済ませるのであるが、最近はお風呂につかるようにしている。
一ヶ月近い咳との戦いが収束しはじめた今、体中が筋肉痛で痛いからだ。このコリコリをほぐさない
と復活とはいえない。せきはまだ続いていて、そのせいか背中が特に痛い。
そのお湯の温度、昨日まで43℃にしていたのを、一℃さげて42℃にした。うーん、これでもまだ
熱かったかもしれない。子供のころはそうでもなかったが、入浴の妙味に目覚めてからこのかた、わ
たしは熱い湯が好きで、冬場などは45℃くらいにしている。熱いお湯につかるほうが「あー」とい
う声とともに抜けていく疲れが大きく、その分気持ちいいような気がするのだ。心臓には悪いらしい
のと、熱がり(猫舌)、暑がり(汗かき)なのに、こと入浴だけは別である。・・・であるが、この
外気温の高さにはさすがに身体が参っていて、温度を下げた。
中国料理には薬膳の思想があり、夏野菜をつかって身体を涼しく保つといったことを聞いたことがあ
る。このところ、病気疲れをいいことにまともな食事が滞りがちになっていることだし、(日曜日の
鯖はひさびさにまともな食事だった。)ここは夏本番が来る前に食事改善をしていきたいところであ
る。といっても、そんなに簡単にできるわけもないので、いまは麦茶(また大量にパックを買ってき
た)と、volvicをがぶがぶ飲んで、「水冷」しているのだった。
窓、開けても風が入ってこないなぁ...。
- 2005/06/27(月)
暑いですな。そろそろ夜寝苦しくなってくる季節であるが、せっかく風邪がなおろうかというところ
なのに、また体調を崩しそうだ。
現在、あるものをネットオークションで競っている。といっても開始価格100円。入札単位10円
のものなのだが。オークションに参加するのはこれが2回目という初心者である。はじめてのときは
限定版のCDを競った。というか買った。相手の希望価格をいきなり入札する「即決」という方式。
なので、いわゆる競争相手と入札を繰り返す形式は今回がはじめてなのだ。現在価格が110円だっ
たのでいきなり200円を入れてみた。するとすぐに再入札を求められる。相手が即座に210円を
いれてきたのだ。正確には「自動入札」。自分の払える上限を設定しておくと、勝手に入札してくれ
るというもの。うむむ、残り期間はあと3日。相手が相当この商品に入れ込んで高額の設定をしてい
た場合、この段階でどんどん入札を繰り返すのはめんどうだし不利な気がする。わたしもこの商品は
欲しい。開始価格が100円なのであなどっていたが、双方が自動入札で最高金額が近い位置にあっ
たとすると、開始価格の低さはあまり意味がないことに気づいた。
とりあえず、これから毎日様子をみて、締め切り直前からこちらの希望価格での自動入札をかけて
みる。それでだめだったらあきらめよう。何を買おうとしているか?まぁ、想像してみてください。
過去ログを丹念によめばわかるかもしれないなぁ。(注:当てても何もでません。後日結果を見て
あたってたら喜べるくらい。)
しかし、なんだ。最近、買い物が多いような気がする。体調不良のストレス緩和策なんだろうか。
じつは、いまも暑さと早起きのせいでぐったりしている。早起きは身体によくない。私の場合。
早く寝よう。
- 2005/06/26(日)

「たち吉」で焼き物用の角皿を買う。以前から、魚を食べるのに適当な食器がないため、欲しいと
思っていた。じつは、五条坂までさがしにいったのだけれど、日曜日のせいか、ほとんど店がしま
っていた。商売っ気がないというか。父と母が昔よく立ち寄っていた三年坂下の陶器屋にもいって
みたのだが、ここは茶碗と湯のみが多く、角皿そのものがほとんどなかった。気がつくと、結構汗
だくになって疲れてきた。うーん、今日は買うぞ!と決めて家を出たものだから、なんとなくもや
もやする。このまま、八坂までくだって、そこから新門前通、古門前通に行こうかと考える。
(「新」門前にはなぜか古美術・陶芸品が多く、「古」門前には新品の美術品が多い。謎。)
が、あまり知らない道を、つーつーと道なりに下っているといつの間にか、建仁寺にあたりにでて
いた。このあたりは、京都WINSがあって、ひとひとひとで、ごみごみしていて好きではない。
せっかく情緒ある雰囲気がある場所なのに。そこまで来て、そこから北上するのがめんどくさくな
り、えーい、今日はも本だけ買おうと方針変更する。で、例によってジュンク堂に行き、川上弘美
の文庫本を一冊買ってでたのであるが、実は通りを隔てて東側にあるのが、「たち吉」なのである。
「たち吉」は京都では有名な陶器屋さん。作家の陶器だけでなく、オリジナルの陶器も売っている。
店の雰囲気はやや敷居が高いように思えるが、入ってみるとそうでもなかった。って、気づくと入
っていたのだ。店のひとに相談し、いくつか角皿を見せてもらう。普通、この手の陶器は組でしか
売らないものだと思っていたのだけれど、一枚からでも買えるとわかった時点でかなり購入に傾き
はじめる。結局、いろいろな魚にあい、扱いやすく、洗いやすい(結構重要)、写真のものを選ん
だ。1枚、1575円ナリ。
つつんでもらっている間、「どうぞ」と冷たいお茶が差し出される。(もちろん私は接客席にすわ
っているのである。)たかだか、1500円程度の皿を買ったくらいで、お茶を出してもらうなん
てなんだか、申し訳ないような気持ちになったのであるが、同時にこういう買い物もいいなーとも
思っていた。コンビニや、スーパーでの買い物に慣れた人間にとって、買い物の際に声をかけられ
たり、相談したりということはなかなか気がすすまない。でも、気恥ずかしさを乗り越えて、対面
してみると、じつはただ、商品をレジに差し出して買うよりも、買い物そのものがとても有意義で
気持ちのいいものになることに気づいたのだ。これはいったいどういう心の働きか。歳を重ねたせ
いなんだろうかな。
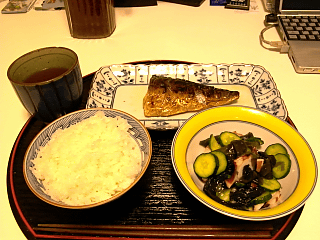
今日の夕食。惣菜屋でさっそく鯖を買ってきた。うん、うん、これでこそ焼魚を食べてるという気
持ちになれる。食事の用途や、種類によって皿を変えるということ、そして用途にあった皿がある
ということ、その意味がわかったような気がした。
- 2005/06/25(土)
NC練習@京都、洛南高校。世界合唱シンポジウムのクロージングコンサートで演奏する「涅槃交響
曲」の合同練習であった。東寺の北側に隣接するというか、東寺の境内に学校がある。市内なので、
当然ながら自転車で移動。真夏の日差しのなか、ひさびさの中距離サイクリングが気持ちよい。練習
後、あっという間に我が家へ到着。ああ、なんだか新鮮。NC練習、隔週でも京都でやってくれると
いいのだけれどなぁ。
帰り際、五重塔がナトリウムランプのオレンジ色の光でライトアップされているのが見えた。みると
あたり一面にひかりがなく、闇のなかにぼぅっと浮かび上がっている。通常のライトアップのような
昼光色ではなく、単色光であるがゆえ、ライトアップされているのに、そこには幽玄の暗さが漂う。
まるで鬼火に燃え上がるようだ。京の都の果て、羅生門も真近の東寺だけに、じっと見つめているの
がこわくなってくる。まわりにあかりがないのに、まるで星が見えないからだろうか。かつて、都は
城壁で囲まれていた。その南端に位置したのが東寺。教王護国寺として、都の守りを固めたその寺
は、いったい何から都を守っていたのか。城壁の外、羅生門の外にいったい何があったんだろうか。
城壁もなく、羅生門もない、いま。市内に住む京都人が、どんなに用事があっても京都駅より南に
足を運ぶことをためらってしまうのは、「恐れ」の遺伝子がどこかに残っているからなのかもしれ
ない。
- 2005/06/24(金)
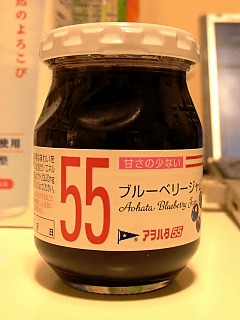
アヲハタ55、ブルーベリージャム。
明日の朝食は、焼きたての食パンにブルーベリージャムと決めた。なので、会社帰りにコンビニで
アヲハタのジャムを買う。うちは祖父、父と代々の朝食は食パン派であったが、わたし自身は会社
に入って以来、ずっとご飯派である。が、一時期、残業食で毎日、カフェオレと食パンを食べてい
た時期があった。そう朝のパンは口のなかが乾いた感じなるのがいやだったのだが、こばらを満た
したくなる夕方ごろは断然、食パン派なのだった。たぶん、毎日続けていて、結構太ってしまった
ので、いつのころからかやめていた。
すでに紹介したように、ひとりぐらしのわがやにオーブントースターがやってきた。昨日、ためし
に食パンを焼いたところ、それはもう見事に焼き色と、網目のついたパンに仕上がって、うれしい
ことこのうえなかった。その時点ではチューブ式のバターしかなかったので、これはもうジャムを
買うしかないと思い立ったのである。
こうやって、買ってきてみるとまずその容器の形にこころ引かれるものがある。手に馴染むサイズ。
円と角、Rの絶妙な組み合わせが生む形状、そしてビンから金属のふたをはずすときの、やや乾い
た硬質な音。どれもがアヲハタのジャムを構成する大事な要因になっていることがわかる。初めて出
会ったのは、祖父の家で25年以上も前のことだったろうか。ジャムといえば、この形として、あた
まに刷り込まれている。父はバター派だったため、実家にジャムはほとんどなかった。
ところで、アヲハタとキューピーのCMは妙に似ているなぁ、と思っていた。キューピーのジャムの
ブランドとして、アヲハタがあるものだと思っていたら、実はそれぞれに独立した別会社だった。と
いうことをついさっき調べてわかった。調べるきっかけは、容器に書かれた販売会社である。当然、
アヲハタ、あるいはキューピーと書かれているとおもっていたら、そこに書かれていたのは以外とい
うべき名前だった。「株式会社 中島董商店」。えっ?いったいどういうこと?
で、さっそくアヲハタのHPを調べた。どうやら、キューピー・アヲハタグループというものがある
らしいが、関連会社を調べても、「中島董商店」の名前は出てこない。もしかして、このジャムは
ニセモノなんかなぁと思いはじめたところ、事業概要や沿革のページにたどりついた。そこには、
アヲハタは、キューピーを創業した中島董一郎が営んでいた中島董商店を起点としているとあった。
どういう関係性かはわからないが、事業部のような形ではなく、キューピーも、アヲハタも独立した
会社として、それぞれの食品分野を担当する形をとったものらしい。しかし、その起点となった中島
董商店が現在も、別会社として存在するのがなんとも不思議。キューピー、アヲハタの流通部門を
受け持つほかに、不動産業や、コンピュータソフトウェアの企画、開発、販売までやっているようだ。
ブランド名=会社名が多いと思われる食品業界のなかで、このような三社の関係というのは非常に
珍しいのではないかしらん。面白い。調べてみるものだ。
そういえば、昨日のWBSで知ったことだが、三菱ハイユニで有名な三菱鉛筆、じつは三菱財閥、
現、三菱グループとはまったく関係がないらしい。しかも、スリーダイヤのあのマークは、三菱財閥
よりも、先に商標として登録されていて、現在も普通に使用されているのだから驚きだ。会社の歴史
というものはいろいろあるのだなーと、きのう、きょうと感じ入った次第。
- 2005/06/23(木)
近頃、といってもこの一週間のことであるが、本屋に行ってもなかなか新しい本を買う気がおこら
ない。うーん、買おうかとおもってふみとどまってしまう。原因は、すでにいま通勤中に読んでい
る本のためだ。なかなか読み進まないのである。だから別の本を、と思って探すのだけれど、まだ
読み終えていないのにという罪悪感めいた感覚と、読み進まないけれど、離れがたいという雰囲気
が本と私の間に横たわっているからである。
「今、何してる?」角田光代著、朝日文庫、500円。
という本。読み進まない理由は簡単で、1行、2行読むたびに本から顔をはなして、もの思い?に
ふけってしまうというか、いろいろ考え事をしてしまうからだ。角田さんのエッセイを読むのは
はじめてであるが、ふつうのなんでもないおだやかな文章のなかにするどい洞察が秘められている。
いや、するどいという言い方は適切ではなくて、ちっともするどくも痛くもないやわらかな言葉な
のに、見下ろす視線ではなく、ふつうに生活している人間の視線でひとのこころのこみいったとこ
ろを、ときほぐして、ほらね、こんなじゃないかなぁと、わたしたちにみせてくれる。
この本、エッセイの前半は恋愛の話、後半が旅と本の話。この恋愛の部分が曲者だった。前半の前
半は、雑誌の連載モノらしく、「相性」「錯覚」「料理」「悪人」・・・といったキーワードに対
して、角田さんいうところの「珍妙な恋愛」経験を素材にして書かれている。一項目、3ページ半
くらいの短いエッセイ。なのに、これが読むのに5分も10分もかかってしまう。なんどもなんど
も本をはなすからだ。珠玉のことばがかかれているからというよりも、恋愛経験のほとんどない、
それも男からすると、”ごく普通に恋愛してきた”という女の人の語ることばには、いちいちおど
ろかされたり、感心させられたり、うならされたり、わがみをふりかえったりせざるを得ないので
ある。
いちいちそんな調子であるから、前半の前半がおわっても、前半の後半の「恋の言葉に溺れるな」
を読んでいても、苦しくってしかたがない。だから電車に乗ってから手が伸びるまでにも時間がか
かっていたりする。まぁ、結局読んでしまうのは、なにかひそやかにのぞきみたい、というような
あまり健全じゃないけど、健康な精神のせいであるかもしれない。(エロとか、エロスとか、また
はそれをにおわすようなエッセイは全然ないのですよ、ええ。言い訳っぽいけど。)
女性にしかわからない女性の視点というもの、それを女性自身が語ってくれることはなかなかない。
それをこんなにも、わかりやすく、ああそうなんだーと、強引にでも納得させてくれて、それでと
きどき、男の考えている単純なことをはっといいあててみせる、そういうエッセイだから、苦労し
ながらもなんとか読み進めている。
あと20ページ。それで、いよいよ旅と本の後半戦に突入である。あと20ページ。読み終わるま
でどれくらいかかって、読み終わるまでに何度もの思いにふけるんだろうか。
「夢で逢いましょう」最終話、矢田亜希子の長い結婚式シーンよりも、はるかに短い長塚京三の退
官シーンのほうが、万感胸にせまる、そんな自分はいろいろと矛盾している。
- 2005/06/22(水)
二日間ほど寝込んでました。が、やっとせきは治りつつあります。長かった…。
更新できず申し訳ありません。
さて、昨日到着したもの。10日後って聞いていたのに、2日で到着。はやければ早いで、給料日
前だったりすると困るのであるけれども、来てしまったものは仕方がない。なんだかんだいっても
欲しかったものがきたからうれしいのだった。

箱。
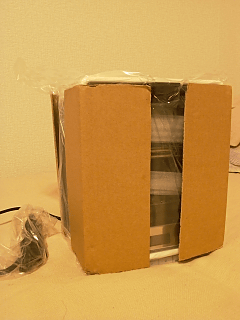
まだわからず。

なんだろう四角い。

正面から見たところ。
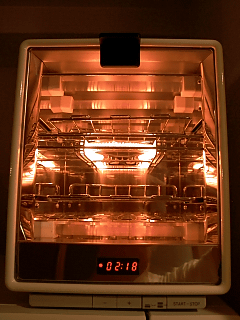
オーブントースターでした。オレンジ色の光が落ち着く。

電子レンジと並べたところ。バランスをとるためには2つ必要か?
と、ここで焼き上げたパンの写真を載せたかったのであるが。食パンを買ってくるのを忘れてし
まった。まだ寝ぼけているようだ。
デザインは深沢直人。私の生活にはこのオーブントースターがあっている。(まだ使ってないけど)
興味のあるかたはこちらを参照。
追悼、ジャック=キルビー氏(ICの発明者。ノーベル物理学賞受賞)。
あなたがいなければ、わたしの仕事は存在しなかった。
- 2005/06/21(火)
(*_*)
- 2005/06/20(月)
(x_x)
- 2005/06/19(日)
大阪府合唱祭@貝塚コスモスシアター。
YK、NCで出演。
8時半京都出発。貝塚の駅から徒歩で、ついたのは10時50分ごろ。集合は11時だから、早く
出たつもりでもぎりぎりだった。YK、NCと立て続けに演奏をして、13時15分解散。そのま
ま朝来たルートを逆にたどって、途中で阪急そばを食べたりしていたが、帰宅したのは16時だっ
た。
大阪府合唱祭ですごした時間、演奏した曲数、合唱祭での充実度からすると、この移動時間はあま
りにも長すぎる。長すぎるのだが、その割りにはそれほど長い時間を移動していたという実感がほ
とんどなかった。帰りは本を読んでいたからかもしれないが、行きはただぼけっとしていただけで
あるし、なぜだろうか。烏丸〜梅田(阪急)、梅田〜難波(御堂筋線)、難波〜貝塚(南海)とい
うルートである。ここに何かヒミツがあるのか。
昨日、大和高田へ行ったときのルートは、京都〜大和西大寺(近鉄京都線)〜大和八木(近鉄天理
線)〜大和高田(近鉄大阪線)〜鶴橋(近鉄大阪線)〜大阪(JR環状線)〜本町(御堂筋線)で
あった。
大和高田にいく途中に感じたこと、それは奈良は京都とだけつながっているのではないということ
だった。地理を勉強していれば当たり前の話だし、奈良のひとからすれば、何を言っているの?と
いうことだと思う。申し訳ない。私のなかでは奈良にはJR奈良線か、近鉄奈良線で行き、やはり
同じ路線で帰ってくる、行き止まりに位置するところというイメージがあったのだ。山の奥にひっ
そりと隠れている古都という認識でもあった。しかし、大和八木での乗り換えのとき、そのホーム
の構造と案内図を見て驚き、そして気づいた。行き先案内板には「大阪方面」「京都方面」さらに
「橿原方面」があり、なんと「伊勢・名古屋方面」まであるのだ。東西南北、縦横無尽なのだ。
JRや、阪急になれた人間からすれば、「京都方面」と「大阪方面」は同じ方向を示すものか、
あるいは始点と終点でしかないのであるが、それぞれが独立して存在するのが奈良という土地の
地理的位置なのだ。そして、ここからは関西からは遠く離れていると思われる、名古屋という土
地と実はダイレクトにつながっている。その事実に、自分のなかの地理が一次元でしか構成され
ていない至極単純なもので、視野狭窄そのものであったことに気づかされた。ショックだった。
そう、昨日のルートは貝塚よりは近いけれども、そのルートの二次元的複雑さによって、自分の
なかに、新たな地理的感覚が植えつけられていくという経験を得、一種「旅」をしている気分を
味わうことができた。所要時間としては、客観的には短いのに。
しかし、今日の貝塚までのルートは、いつものなれた京都−大阪の一次元ルートの延長上にあっ
たため、ともするとそれまでの自分の経験を超えることはなく、単に時間を費やしたとしても、
そこに移動による楽しみを見出すことができなかった。一年に一回だけの移動だとしても、すで
に3回だか4回、経験していることだから。退屈だから時間を長く感じるということはあるが、
逆に「当たり前」すぎることがかえって時間の経過を感じさせないことがある。それが今日の体
験だったのではないだろうか。
さて、帰宅後、床について、昼寝というか夕方寝をして身体を休めていたのだが、さる筋から
の電話で起こされた。今日は、佛教大学混声合唱団のサマーコンサート、その演奏会にて、
この夏行われるNCと国立音楽大学女声合唱団アンジェリカとの合同コンサートのチラシを
配りに行くことが急遽決まったのである。実は、昨日の用事も、奈良県合唱祭に来る方への
ホール前でのチラシ配りであった。
京都在住のメンバーからチラシを受け取る手はずをし、眠気まなこのまま着替えて出動。合唱祭
演奏後に続けて聞きに来ているはずのNaにもメールで手伝いをお願いし、準備はなんとか整えた。
落ち着いたところで最終ステージのヨーロッパ歌めぐりを聞く。終演後の仕事開始までのひととき。
・・・・・すごい、きれい、美しい、力強い。なんて気持ちのいい演奏なんだろうか。ぶっこん
は、また知らない間に新しい姿に進化していた。OBでもないのに、嬉しかった。しんどいから
とあのまま寝ていたらこんな経験はできなかった、突然だったけれども、NCの仕事に感謝しな
ければなるないなぁ。なんだって、ただ寝ていて経験できることは少ないのだ。
演奏会も、仕事も終わり、外に出ると、涼しくて気持ちのいい風が吹いていた。ただただ、忙し
くて、体力的にはしんどかったこの週末だったけれど、こうやっていい音楽に癒されて終わった
あと、さらにデザートをもらえたようだった。
これでまた明日からも頑張っていける。そのはず。そうだといいな。
追記:あああ、いま何時。3時か。喉の奥から、これでもかというくらい、何か毒素でもしぼり、
はきだすように盛大に咳込む。これまで最大級だった。見越して、のどまわりにサロンパスを貼っ
ておいたので持ちこたえている。かわいたのどに何かが張り付いているような嫌な感じはなくなっ
たが、疲労することはなはだしい。具体的にたんでもでれば、これが原因かぁと思えるのだが、い
まのところからぜきばかりで、「せきのしがい」がない。しんどい、疲れた。ただ、ゆっくり眠り
たいだけなのに、いまは眠るのがこわい。どうすればいいんかいねー。xxxxxxx
- 2005/06/18(土)
雨、降らなかったですな。むしろ気持ちいい天気。
本日、ゆえあって奈良県合唱祭へ。場所は大和高田市。その道中、京都、奈良、大阪の地理的関係
と交通網について、思うことがあり、それを少し書いてみようと思う。
であるが、その大和高田での滞在、行き帰りで思った以上に疲労していることがわかり、その後の
NC練習でも半ば見学状態であったので、現在それだけの内容をしっかり書くことができない。
ということで詳細は明日。
しかしなぁ、明日の行き先は大阪の南の彼方に位置する貝塚。今日より疲れるのは明白だよなぁ。
- 2005/06/17(金)
すみませぬ、ようやくページ分割しました。m(_ _)m
日中の咳き込みがひどく、たんがでないかわりに、ときどきもどしてしまう。今朝も道で過呼吸に
なって、見知らぬ人に大丈夫ですか?と気遣われてしまう。全然治らないなぁ。
BK練習後、ごはん。いも焼酎初体験。この匂い、香り、どこか遠い昔にかいだ記憶。
あしたは雨だという。自転車に乗って出かけたかったのだけれど。
- 2005/06/16(木)
誕生日おめでとう。Alles Gute zum Geburtstag !
その頃の夢もうれしや、越えくれば なみだの谷も
みめぐみの いずみとなりしと さとる今日かな
>私信
帰宅後、TVをつけると矢田亜希子と長塚京三が出ているドラマをやっていた。なんと、長塚京三は
海上自衛官の制服を着て墓参りに来ているではないか。普通であれば、長塚演じるお父さんの職業
は自衛官であるという設定を示すためだけのものになりがちだ。しかし、成り行きを見守っている
と、なんと横須賀で行われている基地祭(あるいは観艦式か)に向かうシーンが出てきたではないか!
基地を見学する矢田と婚約者らしき男、護衛艦のブリッジを見上げると客を案内する父の姿。なかな
かよいシーンであるが、私はおおー、護衛艦!、おーかなたには第一潜水艦隊!ともう、ふだんめっ
たなことではみれない艦船の実物をドラマのなかとはいえ見ることができて、そちらにばかり集中し
ていた。登場する基地のシーンでは実際の基地祭の様子とおぼしきカットがたくさんでてきて、実際
の横須賀基地でのロケであるようだ。
近頃話題のローレライや、亡国のイージスなどのような軍事モノと違って、普通のドラマにこうやっ
て自衛隊が登場するなんてすごく珍しい。しかも、話をおっていくと、なんと長塚は潜水艦の艦長で
あったらしい。部下から「室長」と呼ばれていることから、いまは陸(おか)にあがって、資料編纂
室のようなデスクワークに転じた様子。この設定もなかなかすごいと思うが、そのお父さんをさらり
と実感たっぷりに演じている長塚京三がかっこいい。
ラスト近く、港の向こうに浮かぶ潜水艦を眺めている父に語りかける矢田。そのなかのひとこと、
「結婚式に制服姿のお父さんに出てもらうのが夢だった」。このひとことにぐっと来た。そうだよ
そうだよねと。別に私にそういう夢があるとかではなく、海上自衛官の制服・礼服姿は数ある制服
のなかでも抜群にかっこいいということに共感したのである。見るべきところを間違っていますか
私?いやいやそんなことはないはずだ。あの姿は、男女問わず、子供にとっては憧れの姿のはず。
ドラマのなかの、矢田の子供時代の回想シーンに登場する、お父さんはまさにそのように描写され
ていたと思う。制服姿のお父さんを描いたクレヨン画がそれを象徴していた。
中学三年のとき、廃止された青函連絡船が、青函博というイベントにあわせてしばらく就航をつづ
けていた。その連絡線に乗り行くため、友達3人と連れ立って青森、函館へと旅行したことがある。
そのとき、船上で船長服を着せてもらって4人それぞれ写真を撮ってもらったのだ。あの写真にう
つった自分はえらく固い顔で、まだ体格もなかったのであまり似合っているとは自分では思えなか
ったが、他の3人には「(いろんな意味で)一番制服が似合うのはおまえや」といわれたことを思
いだす。そう、確かにそのころから制服のもつつきりりとしたものや、海の男の郷愁であるとか、
孤独がかもし出すかっこよさに憧れていたのだと思う。
そんな自分であったが、その関連の道に進まなかったのは職業として意識するほどではなかったと
いうことと、すでに技術屋になりたいという思いがあったからだが、根本的なところで、船酔いす
る体質であったことが一番の問題だったのかもしれない。(前に書いたが、電車は酔わないことか
ら好きになった。)
さて、ドラマでは次回が矢田亜希子の結婚式のようだ。結婚式の場合、参列者が制服を着ていなく
ても本人が制服を着る職業の場合、制服を着て式にでる場合がある。アメリカ映画などでおなじみ
のシーンであるが、日本では制服職業のひとのうち、どれくらいの割合で着るものなのだろうか。
紋付はかまや、タキシードなんかに比べれば、よっぽどいいと個人的には思うのであるが。もし、
自分が、あるのかどうかわからない自分の結婚式で好きな服を着れるなら、海上自衛官をはじめと
する海の男の制服を着て、あの制帽をかぶってみたいものだ。(まちがっても、会社の作業服はき
ないだろうなぁ。)
・・・と、よく考えてみると、それってただのコスプレではないか。
- 2005/06/15(水)
帰宅直前、銀行によって通帳記入する。会社へ福利厚生の申請をするのに家賃の支払い実績が
必要なのだ。去年の12月あたりから記入をしていないことであるし、残りページも少ない。ここ
はまた自動で新しい通帳を作るところが見られるだろうか?と考えていたところいつの間にか記入終了。
・・・・ダメじゃん!「合計記入」されている。しかも5月末までだから、一月も家賃の支払いが入っ
てないじゃないか、ぬぬぬ。なになに、「合計記入の詳細は窓口にお問い合わせください」ですとぉ。
窓口来いって、そんな普通の会社員が9〜15時の間に窓口いける訳がないじゃないか。ぷんすか!
ほんとに銀行のATMには困ったもんだ。だいたい、合計記入する基準が事前に示されていないのが
インターフェースとして失格である。
1、人間が要求していないことはしない。
2、判断が必要な事項は人間に要求する。
この2つは大原則ではないだろうか。まず、私は合計記入しろとはいっていない。通帳を記入しにく
る人間の目的をまったくわかっていない。このインターフェース設計者は。通帳記入は誰が、いつ、
いくら振り込んだのかを知るためだ。ならば、最優先事項はそれである。もし、通帳の残りが少なく
て、合計記入したほうがいいですよというならば、「するかしないか」を判断させるべきだ。あるい
は「いつから、いつまでを合計記入するか」を選ばせればよい。そんなことを聞いていていると、
処理開始まで時間がかかるので、全部自動のほうがよいという意見があるかもしれない。しかしです
よ、処理時間が遅いのはプリンタがいまだにドットインパクトだからではないだろうか。あれば、レ
ーザープリンタになれば処理時間は早くならないか?もしかしたら、機械のメンテナンス的な理由か
らそうなのかもしれないが、もうちょっと進化があってもいいのではないかしらん。
(トナー代が高くて、ランニングコストがかかるのと、サイズが大きなるデメリットは確かにある。)
ワードを使っていて、英単語の先頭を勝手に大文字にしてしまったり、エクセルを使っていて同じ単
語ではじまると、残りを自動的に埋めてしまうといった機能も、第1の原則に反している。なんてこ
とを考えていると、ふと、自分が設計しているシステムのインターフェースが頭に浮かんだ。
今日、以前作ったシステムに機能追加しているとき、1、2の原則とは違うが、入力者の立場からす
ると面倒なインターフェースを書いてしまった。理由は、機能追加の工数を減らすため。つまりは
自分の面倒を、入力者に押し付けてしまったのだ。ああ、えらそうなことを言っておいて、これだ。
反省、反省。確かに工数を減らして完成を早めることは必要なのだが、ちょっと頭を使って工夫すれ
ば便利な入力画面になるのだ。逆に入力回数を減らす方が、入力することによるミスを防げる。その
ミスを検知するコードを書くことは必要だが、間違いをしないための工夫をすることが、あとあとの
サポート工数を考えてもずっと有効なのだ。
「情けはひとのためならず、まわりまわりておのがため」ちょっと意味は違うが、つまりはそういう
こと。わかりやすいインターフェースは、使うほうにとっても、そのシステムを使ってもらうほうに
とっても有益でなければならないと思う。
- 2005/06/14(火)
病院の吸引+加湿器のおかげ(?)か、就寝前・起床後ともに咳は出ず。身体のだるさと頭痛のみ。
なんとか治る方向に進んでいるようで一安心。身体のだるさはドリンク剤でなんとかなるし、頭痛は
いつも飲んでいる頭痛薬でクリアできる。
その頭痛薬であるが、去年のいつごろか、それまで飲んでいたものから、錠剤が小さくて即効性のあ
るものに変えていたのを、今回またもとの頭痛薬に戻した。もともと飲んでいたものは錠剤は大きく
て、苦くて、水が少ないとすぐのどにつまってしまうし、なにより効きはじめるのに時間がかかる。
それなのに、わざわざ戻したのは効果の違いが大きかったからだ。
頭痛そのものをとめることに主眼を置くならば、痛みのもとと伝わりをブロックする○○○○ースの
ほうが、よいといえる。しかし、頭痛というものはその痛みだけでなく、頭痛によって生じた気分の
悪さや、痛みをかばう姿勢をつづけることによる肩こりなどの二次的な痛みを伴うケースが多いと思
う。その二次的な痛みまでの回復を求めるならば、多少の短所に目をつぶっても○○○○ールの
ほうがよいと、判断したのである。頭痛の症状はひとによって違うと思うので、あくまで私の場合は
ということになるが。
別にあぶない成分が処方されているからというわけではない。2つの頭痛薬の成分を比べると、同じ
目的なのに、主成分はまったく異なっている。同じなのは眠気を抑える成分の無水カフェインのみ。
添加物もおなじようで半分以上が異なるのだ。これはあきらかに頭痛に対するアプローチの仕方が
違うことを意味しているのだろう。後者の主成分は鎮痛剤の代名詞ともいえるアスピリンである。
アスピリンは商品名で、そのものの名称の頭痛薬もあるが、これは日局アスピリンのことだ。
アスピリンには血液の凝固作用を阻害する働きがあるとされていて、この成分が主に肩こりを主原因
とする私の頭痛に効いているのかもしれない。ほかの頭痛薬の場合、頭痛がなおったなというのは
わかるが、○○○○ールの場合は、頭痛がなおっていくという経過が自覚できる。身体から脳への
血流がスムーズになり、あたかも森林浴をして呼吸が楽になったような感覚を受けるのである。その
ことが頭痛だけでなく、精神的なつらさをも緩和しているような気がする。
大衆薬にかぎられるが、こんなふうに自分にあった薬を見つけるというのは結構大事なことのように
思う。比較検証はやってみるべきだ。(なお、アスピリンにはアレルギーを持つ人もいるので注意。)
ともかく、咳がでない、頭痛も治った、肩こりもなおりつつある。
食欲も出てきた。あとすこし。はやく治りますように。
- 2005/06/13(月)
昨日の夜は心地よい疲れとともに安らかに眠りについたのであるが、帳尻を合わせるように今朝は
盛大に咳き込む。気道近くにたんが絡み、息ができなくなったのだ。そのたんを吐こうと反射で咳
が出る。息ができないのに咳は出るという有様で、過呼吸のような感じであった。少々、パニック
気味で、このままおさまらなかったら、死んでしまうのではないかとあらぬ想像も浮かんだりした
が、生きるための潜在能力か、口をふとんでおさえつけて、無理やり鼻から息を数回吸い込むこと
でなんとかおさまった。心臓に悪い。
ぜんそくが出やすい季節だから、とNaに言われていたこともあって、出勤前に病院にいく。特に検
査はしなかったが、風邪の後遺症で喉と鼻がかなりやられているらしい。蒸気で薬を鼻から吸い込
む、吸引装置を使って少し楽になった。毎日吸引したほうが治りが早いと先生に言われたので、
明日から出勤前に通院することにする。
前日に体力を消耗したのであれば、会社休むしかないか、と思うのだが、前日までは心身ともに
元気であったのに、朝になって消耗した場合、どういうわけか「昨日あれだけ遊んでいたのに会
社を休むわけには・・・」と考えてしまう。(それが普通か)というわけで、結構ふらふらのま
ま出勤。あまり細かい仕事はしないようにする(ミスをするから)。
帰宅後、この季節には絶対使わないはずの加湿器を稼動させる。引き始めのときに少し動かして
いたのだが、その後も続けるべきだった。ともかく、蒸気口に顔を近づけて、鼻で蒸気を吸い込
むようにして、吸引装置がわりにする。(子供は真似したらだめ。やけどします。)これでしの
げればいいのだけれど。
そういえば、梅雨なんだよなぁ。
全然、降らないなぁ。
- 2005/06/12(日)
長い一日。
YK練習、前半、中盤に参加。大阪府合唱祭で演奏する曲の練習だけ参加するつもりであったが、
コンクール課題曲もいつの間にか、歌っていた。もっともっと磨いていけそうな気がする。歌って
いて気持ちのいい時間だった。
夕刻といっても、日の高いうちに京都へ戻る。
スタンドにて夕食。72歳のおじいさんに家庭生活の"こつ"を伝授される。いつきても、いろんな人
と出会うところだ。
寺町を上がったり、裏寺町を下がったり散歩してみる。30数年間、一度も通ったことのなかった路
地を発見し、探検。この場所のように、わかったつもりでも見えていないところ、これから見えてく
るところが、まだまだたくさんあるに違いない。
ビーバーレコードを周遊。今週は特に新譜なし。気がつくと閉店時間。電気を消されてあわてる。
Book1stを周遊。今日の一冊、「FILING〜混沌のマネージメント」(株式会社竹尾編、織咲誠、
原研哉+日本デザインセンター原デザイン研究所、企画構成。宣伝会議刊、3500円)を購入。
何かがひとあじ違う本だなーと思ってながめていたら、原研哉+竹尾の組み合わせだったことに後で
気づく。この本から新しい「きっかけ」が得られる予感に若干興奮気味になる。気がつくと、またし
ても閉店時間。電気は消されなかった。
いままで外から眺めていて、勇気がなくて、入ったことのなかった喫茶というか、ラウンジ?のよ
うな寺町の店に思い切って入ってみる。クールな内装に反して、以外にも人当たりのいい、気さく
な接客だった。ハニー&ミルク(シナモン入り)を飲む。照度の低い照明が目に優しい。暗いとは
思わない微妙なひかり加減。ゆるゆるするのにちょうどいい場所。
しばらく、ふらりふらり歩く。アンティークショップらしき店のウィンドウ。よく見ると軒先から
蜘蛛が見事な巣を張っていることに気づく。よく、人間がひっかかることなく、できたものだ。窓
との隙間は10cm以上はあるというのに。
ゆっくり帰宅。今日は、せきがでないといいなぁ。
今日はありがとう。(私信)
- 2005/06/11(土)
NC練習の帰り、林号のなかで珍しくFMラジオがずっとかかっていた。京都に着くというちょうど
そのくらいに、クラシック番組に変わってギャラクシー賞(TV・ラジオ番組の賞)を受賞したとい
うラジオドラマが始まった。「博多天神モノ語り」というタイトル。
ストーリーは、ある日東京から博多に主人公の理恵が帰ってくるところから始まる。久しぶりの実家
の前には、なんと電車があるではないか。なんでも「おじいちゃん」が買ってきたものらしく、近所
でも評判になっている。母によるとおじいちゃんは一日中、電車のなかにいて独り言をしゃべってい
るそうだ。そもそも理恵を博多へ呼び戻したのはおじいちゃんだった。東京での生活に疲れた理恵は
渡りに船と帰ってきたのだが、おじいちゃんの目的は・・・?
皆さんは、ラジオドラマというものに馴染みがあるだろうか。ほとんどの人が、その言葉自体初耳で
はないかと思う。想像はつくと思う。言葉による会話劇。でもはたしてそれが面白いの?と思うに違
いない。アニメの世界では、このラジオドラマ(の形式)は割と昔からポピュラーで、アニメ化の前
に声優がパーソナリティーを務める番組の合間に放送されたり、本編の放送と並行してCDで番外編
のようなドラマが発売されたりしている。この形態が成り立つのは、アニメーションを支えている重
要な要素の多くが、声優の演技と演じるキャラクターに寄って立つからである。簡単にいってしまえ
ば、演じるキャラクターに固定のファンがいれば、内容はともかく聞きたいという需要があるのだ。
その一方で、純粋にラジオドラマを放送している場合がある。多くは劇団の人が演じており、吹き替
えなどで登場する声優もまったく出ない。勝負はストーリーにかかっている。こういうものを放送し
ようというラジオ局はめったにない。そう、だからNHKでよくやっているのだ。いや、やっていた
というべきか。私は最近、ラジオを聞く機会がないので、わからないのである。わたしがラジオ小僧
であったことは、昔書いたが、あれはいつのころだったか。中高のころだったと思うが、ラジオドラ
マを聞く機会が多かった。特定のラジオ番組を聴き終わった深夜。暗闇のなかで手探りでチューニン
グをしていき、たまたま同調できた番組を聞くのを楽しみにしていた時期があった。ラジオを握る感
覚と、聴覚だけの世界は、机やら、ベッドやら、本、衣類でいっぱいにあふれた狭い世界とは違う、
電波という光でつながった、無限の闇のように思えたころだった。
NHKは全国各地に周波数をもっているため、もっとも同調しやすい。そのため地方のNHKを傍受
することが多かったが、まあ番組は全国共通だ。ちょうどそのころ、NHKラジオの24時間放送が
始まっていて、ラジオ深夜便という深夜の帯番組にあたることが多かった。24時間放送なので、枠
が異常にあってラジオドラマも30分なり、一時間なりと長時間だった。TVのように連続ではなく
そのとき、そのときに違うストリーが流れるので、聞くほうも状況や設定を聞き漏らすまいと真剣
だった記憶がある。さきにも述べたように、この手のラジオドラマはストーリー重視なので、あま
りはずれということはなかった。まあ、そのために有名劇作家などが脚本を書いていることが多く
て、別役実のものが当時は多かったことを憶えている。
そんななつかしい世界を今日、偶然に思い出すことができた。そして、練習で疲れ会話も途切れて
いた車中で、いつの間にか、乗り合わせたみんなが傾聴していることが感じられ、なんだかうれし
かった。
ストーリーは、その後転機を迎える。ひょんなことから自転車が「語り始める」声を聞き取れるよ
うになった理恵。自転車だけかと思いきや、枕やら机やら、洗濯機までが理恵に話しかけてくる。
そして、自転車とのやり取りを通じて、おじいちゃんが電車のなかで独り言をしゃべるのは、自分
と同じようにモノとしゃべっているからではないかと思う。おじいちゃんに尋ねた理恵。はたして
その通りであったのだが、おじいちゃんが語りかける電車は、こたえてくれないのだということを
しる。学徒動員で戦時中、その電車の運転士だったおじいちゃんは、くず鉄工場でかつての「友達」
を見つけて、買い取ってきたのだ。長い間、ひとにその存在を忘れられた存在は、魂をなくしてし
まい、しゃべれなくなると語るおじいちゃん。おりしもその日は、6月19日、福岡に空襲があっ
た日だった...、と私が聞けたのはここまで。
うーん、あのつづきは一体どうなったのか、非常に気になる。理恵の高校時代の同級生で、思い人?
とおぼしき渡辺君(4歳の子供がいるバツイチ)との展開やら、おじいちゃんは電車と話すことがで
きたのかやら、これからというところだったのだが。うちには今FMラジオがないし、車から降りた
あと自転車を取りにいき、コンビニに行ったので、ラジオがあったとしても聞き逃していたはずであ
るけれど、残念だ。昨今は、TVでもドラマの再放送がほとんどなくなってしまったが、それ以上に
再放送というものが存在しないのがラジオ。それがラジオの哀しさでもあり、よさでもあるのだが。
今晩、眠るまでの間、深夜TVを見ないでAMラジオでも聞いてみようかと思う。
....という結びの文章を書いている途中で、急にせきこんで、夕飯のあと食べた"カール"を吐いてし
まった。とほほ、いつになったら、この咳は治るのやら。
また、体力を消耗したよ…、誰かほんとに助けて。
- 2005/06/10(金)
「『大改造!!劇的ビフォーアフター』見てて、これからは日本の家がみんなああなっていくんだな
って思うと、僕、その感じがゾッとするんです。シンプルで、頓知入れて。(中略)デザインも困っ
たもんです。」(広告批評2005年6月号、対談大貫卓也×深沢直人より、大貫氏の発言)
いまのデザインのありようについての発言であるが、あの番組を例えにもってくることができるの
がさすがである。マスコミ媒体ではっきりと、あの番組の持つたとえようのない「気持ちの悪さ」
をさらっと述べた人はいないと思う。
今日、気づいた。実は6月4日の時点で電波暗室2周年でした。いつもごらんいただいている皆さん
に感謝。それから、いつもハーボットに足跡を残してくださる皆さんに感謝します。なつこさん、
katopoさん、モスさん、kenさん、まさこさん、あなた方の足跡があるから今日も書こう、明日も書
こうという気持ちが湧いてきます。ありがとう。
- 2005/06/09(木)
24時間心電図をはずすため健康管理センターへ。途中で大阪市営地下鉄に乗るのであるが、最近
切符の自動販売機に赤い色の新型が導入されている。大きい液晶画面のついたタイプである。この
タイプのものでで切符を買うとき、何度も同じミスをして、そのたびに機械に八つ当たりをしてい
るのであるが、今日もやってしまった。
液晶画面は、地下鉄に乗り入れている他社線の切符を買うか、地下鉄線のみを買うかを選択させる
ようになっているので、まず地下鉄のボタンを押す。で、そのあとが問題で、つぎにどのボタンを
押せばいいのかがわからないのだ。画面では「地下鉄」が選択されているのみで、別画面にきりか
わる風でもない。かなり悩むが解答がでない。と、視線を下にうつすと、従来の自販機と同じプラ
スチックの四角い押しボタンが「200」と赤い文字を光らせているのに気づく。ここでようやく
このボタンを押せばいいとわかるのだった。
同じことを、もう3回くらいやって、そのたびにこのインターフェースに毒づいている。液晶画面
があって、それはタッチパネルの機能を備えているのに、なぜ最後のところだけ従来のボタンにし
ているのかが、不明である。阪急や、JR、それに東京の地下鉄で同様の液晶タイプを採用してい
る場合、切符の値段の選択はすべて液晶上で完結しているのに。弁護するならば、タッチパネル式
の場合は応答速度に時間がかかる場合があるので、確実性の高いボタンを採用したといえるかもし
れない。でもそうならば、従来どおりすべてボタン式でよいのだ。人間の視線移動や、行動を予測
するならば、このようなインターフェースはどう考えても変である。
大阪市営地下鉄の独自路線はほかにもあって、乗り越し精算機がこれまた変だ。またしても比較に
なるのだが、スルッと関西系列や、JRの場合、切符を入れると、不足運賃が表示される。これは
わかりやすい。ところが、地下鉄の場合、載った区間の運賃につづいて、「投入金額」が表示され
る。不足分にたいして、補充していく分の金額だなと思うのであるが、切符やカードをいれた時点
で、その金額分が「投入金額」として表示されるのだ。これは一見すると正しい認識だ。切符や
カードの残額はお金と一緒であるから、それを金額換算して表示するのは理にかなっている。しか
し、「投入金額」=金券の金額相当分であると即座に認識できるものだろうか?特に精算のような
急いでいるときに。ここで、「お金」を入れたわけでもないのに金額が表示されるものだから、あ
れ?この金額はなんだ?と戸惑うケースの方が多くないだろうか。
理にかなっている、正しいことを表示していることが、かならずしも使う人に正しい認識をもたら
すとは限らない。不要な情報は省くことが、近道であることがある。こういったインターフェース
に関する知見というものは、実は体系的に整備されていたり、基準化されていたりはしないのでは
ないだろうか。それだけ、学問として深堀されていないということかもしれないが、世の企業がい
ろんなところで、UD(ユニバーサルデザイン)を標榜するならば、インターフェースデザインこ
そ、もっと真剣に取り組むべきなんじゃないだろうかと、寝不足でぼっーとした頭で自販機に文句
をたれながら思うわけである。
- 2005/06/08(水)
眠りにつくまではは割と平穏だったのであるが、夜中になって咳がひどくなる。せきをしているの
か、なにかを吐こうとしているのか傍目には区別がつかないだろうと思う。一時間置きに目が覚め
てしまう。日のひかりのもとで仕事をしているときはおとなしくて、眠りにつこうとするときにな
ってあばれだすというのはなんだか理不尽である。そういうわけで寝不足気味であった。
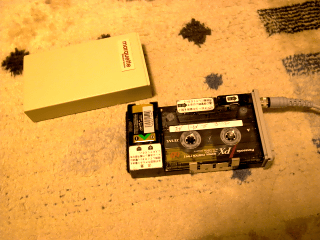
午後になってから出張扱いで健康管理センターへ24時間心電図を取り付けに行く。心電図とはい
いながら、実は身体につけた5つの電極の先がつながっているのはテープレコーダーそのものであ
る。60分テープに24時間分のデータを記録するのだ。だから、よく見ると通常の24分の1と
いう低速で回転しているのがわかる。しかし、どうにも不思議なのだが、通常の心電図装置にして
も身体に取り付ける電極は似たようなものだが、あれはいったいどのような理屈で、心臓の動きを
波形としてとらえているのだろうか?音をとらえているわけではなく、電気信号らしいということ
はわかるが、身体にぺたっと貼り付けるだけで、それとわかる信号をキャッチできるのか?ノイズ
のようにたくさんの信号が入り乱れていたりしないのだろうか。人間の身体と機械のインターフェ
ースというのはどうも直感的には想像や理解しづらいものがある。
帰社後、通常通り仕事。本日は定時退社日。
帰宅途中に「古道具 中野商店」(川上弘美著)を読了。阪急河原町に到着した時点であと5ペー
ジほど残っていたので、藤井大丸横の寺町通りに面した出口から地上にでて、道との境にたってい
るポールに寄りかかったまま、さいごまで読んだ。人通りの絶えない通りに面して、自分だけが静
止しているというのは面白い。川上弘美は相変わらず、あいまいな感覚や感情をすくいあげて、あ
いまいなまま人に伝えるのがうまい。深く掘り下げると、際限のない気持ちを文字ではなく、口伝
のように軽やかに伝えてくる。後味のよい小説だった。

ジュンク堂に寄って、広告批評を買う。しばらく買っていなかったのであるが、特集が「深沢直人
の仕事」だったので買うことにした。
そういえば、月初めなので「東京人」も出ているはずだ。1階に探しに行くがなかなか見つからな
い。あきらめて帰ろうかと思ったところ、赤い炎のようなめらめらしたデザインの表紙を見つけた。
特集は「新宿が熱かったころ」。そんなことをいわれても全然ピンとこない。たぶん安保闘争とか
そういう時分のことをいっているのだろうけど、あの時代を生きていたわけではないし、アングラ
っぽい雰囲気も好きではないし、なにより新宿という街が好きになれないので、買うのをやめた。
雑誌を買うとき基準にしているのは、その場限りで読み捨てられる記事が少なく、じっくり読めて
あとからもまたもう一回読める記事が多いかという点である。つまりは貧乏性なのだが、その境目
となるのは分量の多い特集記事である。いつも買う雑誌だから買うということはしない。特集が自
分にとって面白いと感じられるかが勝負なのだ。
追記:起きているときの咳はほとんどなくなってきて、「こほこほ」程度なのに、横になってから
の咳は、「げぼぉ、げぼぉ」と、とたんに激しくなってしまう。咳止めも役に立たず。両者の違い
は気道の状態、呼吸数の違い、舌の位置の違いか。喉がやたら敏感に反応する。昨日も加湿器をつ
けて寝たのだが、さしたる効果なし。咳き込んだ後に蒸気で喉を癒すくらいにしか使えない。
このままだと毎日、睡眠不足になってしまう。とりあえず、身体を起こしたまま眠れるよう、
ソファに座って眠る努力をする。(26:30追記す。)
みなさんも夏風邪を引かぬよう注意してください。会社でも咳をしてる人が多いです。
- 2005/06/07(火)
なんとか出勤。咳が続くと、治った後にひどい肩こりが残る。それを考えるとしばらくは安心でき
ない。本日も、咳、微熱が続く。
帰宅途中、学習塾(というか小学生受験予備校か)の前を通るのであるが、これまであまり気に留
めていなかったが、小学生たちの自転車がたくさん並んでいる。自転車を買って以来、街中で他
人の自転車が非常に気になるのだが、ここでも同じで観察してしまった。なんと10台中、ほぼ
全台が、子供用のマウンテンバイクなのだ。これはいつごろからの傾向なのか?90年代のはじめ
は割と子供用MTBは贅沢品のようなイメージがあったのだけれど、これだけ普及するほどに廉価
になったということだろうか。それとも子供一人当たりにかけられる予算が増えたのか。まぁどち
らにせよ、結構息の長いブーム?というか、子供の自転車としてはスタンダードになった。
ひるがえって20年前の自分のころはどうだったかというと、男子に限ってのことだが、これはも
う「スーパーカー的自転車」が全盛であった。最近、まったく見かけないので説明すると、まず色
は黒一色。ハンドルはやや低めで、場合によってロードレーサーのようなドロップタイプ。前には
かごはない。リアキャリアだけでなく、折り畳み式サイドキャリアが必ずついている。(特徴1)
つぎに、フレームは平行四辺形で、ハンドルとサドルの間をフレームが横切っている。つまり、
乗り降りするには足を後ろに回さないといけない。(だからこそ男子オンリーであった。当時は
ズボンをはいている女子は少なかったので)そして、このフレームにオートマ車の変速レバーの
ような前後に動くレバーがついた変速機がついていた。(特徴2)そして、極めつけはライトで、
車のヘッドライトのような四角いものが左右に2個ついていた。(特徴3)
想像していただけるだろうか。このタイプの自転車の差別化要因は主に特徴2と3にあって、変速
が多い(5段よりも7段)、ライトが多い(フォグランプが別についているか、リアにもライト)
ほど「偉い」のである。単純ですな、男子は。こういった何かの数が多いほどすごいというのは、
これまたわたしの子供時代と重なるが、筆箱の段数でも同じであった。80年代という時代を象徴
しているような、そうでもないような。
このタイプの自転車は80年代後半には完全に姿を消しているけれど、寿命が短かったというより
か、実は70年代にはすでに存在していたようだ。わたしのスーパーカー的自転車は親戚の兄ちゃ
んのお下がりだったが、彼は私より6〜7歳は年上だったので。70年代から80年代途中までそ
の姿があったということは20年弱、いや15年くらいのブームであったわけだ。これが現代にも
あてはまるのならば、いまの子供達の自転車も、やがてはMTBから別のタイプに代替わりするん
じゃなかろうか。つぎにどんなのが来るかは大人の自転車を見ている限りは想像つかないないが、
MTB以外だと、クロスバイクのような街乗りタイプか、タイヤ径の小さい折り畳みタイプだろう
か。子供用はもともと径があまりないから、折り畳みの線はあるかも。
- 2005/06/06(月)
普通に出勤。夕方から咳、熱。
更新休みます。
- 2005/06/05(日)
体調が上向きになり、普通に外に出られるようになったので、髪を切りに行く。金、土と風呂には
いっていないため、シャンプーが非常に心地いい。家の洗面台は取り回しができるシャワー対応の
蛇口なので、風邪のときなど頭だけ洗うことも可能なのだが、あくまで物理的に可能なだけである。
実際のところは頭だけ洗おうとするとかなり窮屈だ。それならいっそ風呂に入ってしまったほうが楽
とさえ思う。
風邪のときに風呂に入るのはよくないとされているが、体調さえ許せば風呂に入るほうがかえっ
て精神的にも衛生的にもよい効果をもたらすといったレポートを聞いたことがある。通説というもの
は、いろいろな人間の経験を集約し、ろ過したうえでもたらされた「もっとも一般的で正しい」内容
であると思うが、それが科学的にみても正しいか?ということを検証するのは面白いことだと思う。
なるほどその通りであったり、実はなんの根拠もなかったりすることは多いかもしれない。
今回の風邪の場合、セキを伴うもので気管支がつらいので、風呂に入ると悪化するなぁという感覚が
あった。なので、髪ものびているし、散髪に行こうと考えた。
さて洗髪の話にもどるが、美容院・理髪店でのこのシャンプーというものを、本体の髪を切るという
業務から切り離すことはできないものだろうか。つまり、「シャンプー屋」というものは成り立たな
いだろうかと、やってもらいながら考えていた。
入浴ができない場合だけにとどまらず、他人にシャンプーをしてもらうことの心地よさは誰もがしっ
ていることであるから、マッサージと同様に「癒し」効果を求めてやってくる人は多いと思う。マッ
サージにしても、シャンプーにしても自分で同じことができるのに、なぜ他人が介在するとこうも
感じ方が違うのか。おそらくそれは、自分自身では、自分自身の動きが無意識に制御され、過度の
刺激をかけることができないことと、ルーチンワークにちかづくと、動きがパターン化されて刺激と
は認識されないからだろう。他人の手の動きや、力の加減は予測がつかない。こう考えてみると、
自分自身を自分自身で癒すということは案外難しいことなのかもしれない。
さて、商売として成り立つかどうかは、集客だけでなく、役所に認可されるかにもよる。頭を洗う
だけとはいえ、公衆衛生にかかわることであるから資格は不要にしても、銭湯に準じるくらいの許
可は必要であろう。そうするとこれは各地方自治体の保健所の管轄か?国家資格・認可であれば
国内のどこでも同じやり方で通じるかもしれないが、自治体の管轄であると、地方ごとに認可の受け
方や基準が違ったりするのだろうなぁ。全国チェーン展開はなかなか難しいとみた。ここは手堅く、
地域特化型にすべきか・・・。
もし、この文章を読んでどなたか本当にこの商売を始めて、成功した暁にはビジネスモデルの考案
原案料をくださいませ。シャンプー回数券とかでもいいですよ。
- 2005/06/04(土)
終日静養。
最近、ギターの音色を聞いていると非常に落ち着くことに気づいた。
- 2005/06/03(金)
風邪ひいた。ちょっときつかったが、BKの練習には参加。
練習後、「喝采」と、「ジャカランダの丘」と、「木綿のハンカチーフ」を対比してみた。
「ジャカランダの丘」が収録されているレーズン(旧姓グレープ)の「あの頃について」をとりだ
して眺めてみると、「涙のストロガノフあるいはご来訪」が目に入ってきた。
さだまさし自身がライナーに書き記しているが、
「雨やどり」→「涙のストロガノフあるいはご来訪」→「関白宣言」「秋桜」「親父の一番長い日」
→「朝刊」(ん十年を経て)→「関白失脚」という流れがあるのがとても面白い。こういうことがで
きる歌手というのはほかにあまりいないかもしれない。
油断していたら、熱が出てきた。
- 2005/06/02(木)
ネット通販で自転車のパーツを買った(さっそく)のであるが、まだ届かない。店は神戸で、今日
発送したとの連絡あり。21〜23時の時間指定をしていたので、これは余裕で届くかなともっていた
のだが、23時をすぎても届かない様子。配送会社の追跡サービスを確認すると、神戸を出発したの
は今日の20:09だ。2時間見れば京都には着くとして、22時。23時までには来るとふんでいたのだけ
れども。神戸を出発して以降の足取りはまだつかめない。
いまどこにあるか?ということがわかるのはいいのだが、じゃあいつごろ配達できるという予定も
表示してくれるとよいのだが。そうすれば、今日来るのかな、それとも明日なんかな?と期待しな
がら待たずともいい。実際、ベランダに出るときも、トイレに行くときも配送のひとからの電話を
受けとりそこなわないよう携帯を持ち歩いていたくらいなのだ。ベランダに出ていたのは自転車に
乗るためである。帰宅後、サドルにまたがって走行する姿をイメージするのが日課になりつつある。
しかたない。明日はいまのままの状態で乗っていこう。
パーツ、つけていきたかったナァ。
- 2005/06/01(水)
えー、いい加減この暗室ページを分割せねばと思うのであるが、思っているうちに6月に。週末に
なんとかやってみますです。重いもんね。
さて、本日の「水曜どうでしょう」(どうでしょうリターンズ)であるが、ちゃんと録れていたの
でまずは一安心。直前にやはり野球放送があったので、気になって放送開始予定からトレースして
いたのだが、10分遅れで放送開始。30分の自動延長に無事収まったのである。
しかしだな、先週は1時間以上、今週は10分とまるで予測がつかないこの動き。いったいどうな
ってるんだ。先生、昨日言ったでしょう、時間通り終わりなさいって。昨日だかTVをぱっとつけ
たら、野球がちょうど終わったところで「死闘4時間59分のぉ〜」などとアナウンサーがしゃべって
いたので、はっきりいってあきれた。なんですか、その時間は。東京行って戻ってこれるじゃない
か。火曜サスペンス劇場を二回見てもまだあまる。まったく、後番組はいったいどうなったのやら。
野球中継が延長になった場合、後番組は当然遅れてしまう。そのとき、後番組の視聴者はいい迷惑
であるが、その番組のスポンサーのCMは、どういう扱いになるのだろうか?後番組が遅れに遅れ
て視聴率が下がった場合、CM放映料は値引きされるのだろうか。その番組を見る視聴者に向けて
メッセージを送っているのに、想定される効果が得られる可能性を逸してしまうわけだし。また、
CMの値段は一般的には時間帯によってレートが決まっているはずなので、その境目を割り込んで
しまった場合、値段はやはり変動するものなのだろうか。
もし、放映料が変動するのであれば、TV局は野球中継に相当のリスクを払うことになる。下手す
れば放映権料が払えないこともあるはず。そうなれば、延長があっても定時で終わるはずだろう。
それをしないで、のびたらのびただけ放映するということは、そんなことないということか?あっ
いま気がついたのであるが、野球中継が延びれば、その分中継中に放映するCMが増えるのだ。
そこで相殺しているのか...いや、しかしその延びた分のCMはあらかじめ用意しておかないとい
けないのであるが、そのCMはいったいどういう契約になっているのか。放映されるかされないの
かわからないわけだし。仮にすでに放映したものを繰り返すにしても、その分をスポンサーに要求
できるのか?スポンサーは突発の放映でも払うのか...。
そんなことを気にしてもしょうがない、とは言い切れないかもしれない。CM料を払っているスポ
ンサーの商品をわれわれは買うかもしれないのだ。そのCM料のもとをたどれば、商品の値段に
はねかえってくるか、もしくは品質にはねかえってくるのではないだろうか。デジカメのCMタレ
ントの契約料が何億円とする場合がある。その分のコスト削減をするのに、どれだけの努力が必要
か。モノをつくってる側からすれば、そう思わないでもない。まぁ、売れなければどうしようもな
いわけで、そのためにはタレントの知名度が必要でというのもわかるのだけれど。
さて、そんな心配もあるにせよ、身近に問題なのはやはり、後番組が延びることである。これを改
善する方法はないものか。
○現在の9イニング制をやめ、4イニング制くらいにする。うまくすれば1時間くらいで終わるの
ではないか。そうすれば、やや遅めに始めてもいいので、会社帰りにナイターにいく人が増えるか
もしれぬから、球団にとってもいいのでは。(かなり適当に考えているので突っ込まないで欲しい)
○イニング制+時間制限にする。野球は攻守が入れ替わるので、制限時間がきて、表だったら裏ま
で、裏であればそのイニングで突然終了することにする。緊張感が生まれるし、試合展開の戦略が
いろいろと増えるのではないだろうか。ロスタイム制を導入すれば、あと少しで次のイニングに
いくか、いかないかという駆け引きもできよう。制限時間の残りは選手達には一切知らされないこ
とにする。
どうだろうか。
半分くらいは、本当にならないかなぁと思っているが、これ以上書くと野球が好きなひとに怒られ
るのでやめておこう。そのかわり、野球中継を延長するということは、それなりに恨みを買ってい
るということも忘れないないで欲しいものだ
戦いは続く。
|
|