|
電波暗室 2005/7-12
- 2005/12/31(土)
冬コミより無事に帰ってきました。
部屋の掃除をしてから、実家へ帰ります。
腰を痛めてしまったので、全然進みませぬ。
今年一年ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
1、2日は更新を休みます。
皆様良いお年をお迎えください。m(_ _)m
追記:2006/1/3
・7:30起床。8:15出発。いつものように朝マック。大井町店は改装されてきれいに。
・大井町→品川→恵比寿→神谷町。徒歩5分。友人宅に9:30到着。
・PS2を買おうと思ってるねん、という話をすると、友人H、幸雄さんともに変な顔をされる。
PS3が出るからということらしい。でも、実際にまだ出ていないのだし、どうせ高いのだし、
PS3でないとできないゲームはたぶん、RPGでわたしの苦手分野だから関係ない。と、
いう話をすると、友人HがPS2を無期限貸与してくれることに!ラッキー。
・というわけで、初代PS2+HDDを借りる。HDDはいらんといったら、HDDをもってかえ
るのが貸与条件であるという。でもってFFをやりなさいということらしい。RPGはやらない
のだけどなぁ。
・友人Hも今日、京都に帰るので、一緒にマンションを出る。
・神谷町→霞ヶ関→東京。12:00着。
・12:20発、新大阪行きのぞみ。自由席乗車率110%くらいか?5分おきに出発する新幹線の
ダイヤに感心する。例年、こんなだっけか?
・14:37、京都着。タクシー乗り場で、二人と別れて、マンションへ帰宅。
・16:00〜19:00、トイレ、風呂掃除。腰が痛いのにやるんじゃなかった...。
・19:30、実家帰着。
・坂本真綾、押尾コータローの曲をiPodで聞きながら、年越し。
- 2005/12/30(金)
コミックマーケット69、第二日目。
サークル参加。
東ヌ−14b「山Dの電波暗室」
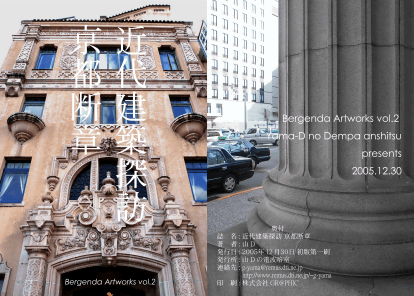
新刊「建築探訪 京都断章」(B6判、24ページ中綴じ、フルカラーオフセット)。
頒価500円。

既刊「建築探訪 東京横浜篇1」(B5判、16ページ中綴じ、フルカラーオフセット)。
頒価500円。
スペースにてお待ちしております。
追記:2006/1/3
・7:00、起床。7:40、出発。
・やはり、本の移動がネック。寒さのせい+カートの引き手の短さ+重さ、で見事に腰をいわして
しまう。スペースに到着した時点で、まっすぐ腰を伸ばせないという事態に。痛くなってからで
は逆効果か?と思ったが、これ以上冷やさないためにカイロを腰に貼る。
・文具コーナーへ買出し中に、ムサシノ工務店(廃墟の写真集を刊行)の武部さんが挨拶にこられ
たとのこと。あわてて新刊+既刊オフセを持って挨拶に。いただいた新刊「ランズエンド」はま
るで、海外旅行のガイドブックと見まごうほどの美しさ!!プロの編集さんは違うなぁ。勉強に
なります。
・10:00、開場。メカミリコーナーの両エンドは男性向けに挟まれて、いわば干渉地帯。そのため、
開始直後はまったく前の通路を参加者が通らないという状態。あっても、ほとんどが指名買いの
人たちで、知名度も実績もないうちとしては、流れの参加者にどれだけ見てもらえるかが勝負な
だけに少々困る。250冊*2という冊数は重かったか?とはやくもあせり始める。
・中央通路が、壁に向かう男性向けの行列で北エンド、南エンドに完全に分断。いよいよもって、
人が来ない状態に。夏コミではムサシノ工務店からの流れで、こばんさめ的に売っていたことも
あり、ここが分断されたのはかなり痛い。北エンドは、ミリタリー一色なため、ほかの同じ写真
サークルさんとも、はじめから切り離されている。不安なスタート。
・10:15ごろ、はじめてのお客さん。安堵する。分断されたことで、通路が男性向けとは関係のない
参加者の迂回路として利用されてはじめたようだ。以降、5分間隔で手にとってもらえるようにな
る。が、声かけは積極的にするように努める。
・夏コミに来てくださったお客さんが何人か来られる。本を読んでひとこと「きょう、来てよかっ
た」と言ってもらえる。こんなにうれしいことが、あるだろうか。本をつくってよかったと、
真に思う瞬間だったなぁ。なんと、そのあとでビックサイト名物おでんの缶詰を二人分、差し入
れに頂いた。本を買った後で、買いに行ってくださったんだな...ほんとうに感謝する。
・11:00、20冊ずつくらい売れている。幸雄さん、買出し出発。12:00帰着。
・MAD WORKSのTAM氏来訪。今回撮影に使用したLUMIXと、GRDigitalの発色の違いについて話す。氏
でなければ、気づかない観点にうならされる。さすがである。
・12:00、一般入場規制解除。予想通りお客さんが増える。壁の男性向けが完売したせいか、行列
が解消。早くもメカミリの遊撃が始まっている。遊撃の人を捕まえるコツをなんとなく掴む。
列に入ってくるひとの視線をチェックし、食指が動きそうだと判断できれば、一呼吸おいて、
「見本見てってくださーい」と声をかけるのだ。スペース前を通りすぎた人でも、声がけによ
って、戻ってきてくれたり、周遊後も来訪してもらえるケースが多かった。見本を見てもらえ
れば、買ってもらえる確率はかなり高い。あと、女性のほうが建築写真には反応が良いようだ。
・13:00、買出し出発。14:00、帰着。創作系をじっくり回る時間がなく、事前チェックもかなり
とばす結果に。しかし、ビバメガネくんと、ふともも本がちゃんと買えたので満足。この時間、
すでに完売となっている創作サークルが出てきており、平均律+Selfish Geneの本が買えなかっ
た。
・留守番をお願いした、すきやき工房のS降に感謝。
・留守中、なんでも写真のセレクトが良い、おさえるべきところをおさえている、とほめてくださ
るお客さんが来られたらしい。水墨画?をよくするひとらしく、「シャア専用朱ザク」という、
朱雀の絵を頂いた。その場で、すごい勢いで描かれたとのこと。どんな人だったんだろう(謎)
・14:00、幸雄さん第二陣出発。15:00帰着。
・15:00、帰宅するサークルがちらほら。まだまだあきらめずに、声がけをつづける。立ったりす
わったりだが、腰はなんとか持ちこたえている。メカミリの特徴なのか、他ジャンルに比べて
カップルで買いにくる人が多い。この場合もたいてい本を買うのは女性である。不思議。
・15:00〜15:30、創作系の10列ほどを特急で遊撃。
・16:00、二日目終了。メカミリ恒例行事、全員で三本締め、万歳三唱。いやー、皆さんお疲れさま。
・合計、304冊頒布。セット買いがほとんどだったけれど、新刊のみ、既刊のみのひともいた。その
わりには結果的にほぼ均等に売れたようだ。(まだ集計していない)
・スペースにお越しいただいた皆さん、ほんとうにありがとうございました。次回もよろしく。
・16:30、撤収。このころ、すでに腰がかなりやばいことになっていた。
・17:30、ホテル着。古畑任三郎の再放送を見る。
・18:00、大井町アトレ、神田グリルにてハンバーグを食す。付け合せを選ぶ方式は面倒なのか、
廃止されていた。食事後、二階の薬局で湿布とキネシオテープを購入。腰の治療を試みる。
・22:00、東京在住の友人と電話でコンタクト。明日、友人のマンションを見学してから、帰京予定。
・24:00ごろ就寝。
- 2005/12/29(木)
コミックマーケット69、第一日目。
一般参加。
追記:2006/1/3
・5:30。自宅を出発。カートに積んでいるものの、予想よりもはるかに本が重い。階段だらけの
地下鉄五条駅を使うのは無理。タクシーで京都駅へ。
・奈良からくる幸雄さんと6:31ホームで合流。同時刻発車ののぞみに乗り込む。5〜15分間隔
で出発するためか、意外と空いている。滋賀県のみ豪雪。雪煙?で視界0のところも。
・9:00より前に品川到着。実質2時間くらいに感じる。下車、京浜東北線大井町へ。
このときの乗り換えで、電車の段差が運搬にはかなりネックであることに気づく。
・大井町の交番前ロッカー\400スペースに荷物を分割格納。りんかい線に乗り換え。
・9:30東京ビッグサイト到着。西館待機スペースへ。
・10:30、入場。やぐら橋をもくもくと超える人並み、突然ひらける視界に飛び込む逆三角形、それ
だけで、心が沸き立つ感覚。たぶん、このとき、この場所にいる者でなければ、絶対に理解でき
ないし、説明もできないもの。
・12:30、いつものやきそば+ポテト+からあげの昼食。やきそばを食べないとビッグサイトに来た
気がしない。
・15:00、撤収。二日開催の一日目ってこんなにも行くところがなかったか?というくらい本を買っ
ていない。三日の配分に慣れているだけに違和感多し。エロ分が極端に少ないのも気になる(購入
一冊のみ)。
・本日一番の収穫は、同人誌委託コーナーで見つけたサークル”うめしそぷろじぇくと”の創作漫画
「リファレンス」シリーズ。本探しの天才、関口彼恋が主人公。ゆえに図書館や古本屋が舞台。勝
手に「ROD」本として分類。第6話まで刊行。続編が読みたいなぁ。
・16:00、大井町アトレ、さぼてんにて、みぞれとんかつ食す。豚汁の大根が胃にしみわたる。一瞬
とんかつなくてもいい、とさえ思ってしまった。
・17:00、アワーズイン阪急にチェックイン。毎回微妙に進化するアワーズ。今回は16階大浴場に
いたる廊下、休憩スペースがじゅうたん張りになっていた。落ち着き度アップ。
・21:00、入浴。体重67kg、適正かな?
・23:00ごろ、就寝。
- 2005/12/28(水)
朝、電車に飛び乗った直後から腹がゴロゴロ。だんだん悪化。とうとう我慢できなくなり、ひと
つ手前の駅で下車。トイレに急行した。今日は、雪こそ降らなかったけれど、そうとう寒い。し
かし、前日何でもなかった腹をここまで直撃するものと思ってなかった。トイレのなかから、会
社に遅れますコール。一日中、変な感じだった。
きょうは、ミーティングと設備の立ち下げ作業と、ちょっとのコーディングで仕事終了。いやは
や、やっと終わり。久しぶりの立ち下げ作業はちょっと手間取ってしまった。電気機械だという
のに、DIAG(診断)をかけるときにちょっとした「コツ」がいるのだ。年明けには年明けで、こ
の逆の作業が待っている。火を入れた(通電させること)直後は暖気が必要で、それまではなか
なかDIAGが通らず、擬似エラーを出しまくるのだ。皆さんがイメージする電気製品というより、
車やオーディオ、PCに近い機械だと思う。しかし、それらとは違って愛着がわかないのが難点。
だって、数千万から億単位もする機械なのに手がかかりすぎる。手をかけた分、何か返してくれる
かっていうと、そうでもないし。その名は「半導体テスター」、因業な機械であります。
ユニクロの買い物ついでに、スタンドで夕飯。この前、年内最後とかいってたのに。お腹痛いと
か言ってたのに。懲りない性格というか。
さて、いよいよ明日出発。帰宅後、準備をする。途中、新刊とオフセット版の既刊を、校正をし
くれた友人に渡しにいく。しばし、本と写真の話をする。気に入ってもらえた?みたいなので、
ほっとする。コミケで頒布するのにちょっと自信をもらった。
iPodに音楽をつめる。tek310さんの影響で、ミュージックストアから押尾コータローのPanorama
というアルバムを購入。坂本真綾の曲と一緒に入れておく。新幹線で聞くつもり。
それでは、いってきます。
31日には帰ってくるので、年の瀬の挨拶はまた。
- 2005/12/27(火)
昨日、マンションの契約更新届けをポストに入れるとき、ちょっとした戸惑いがあった。差し入れ
口は二つ。左が「はがき・封筒」で、右が「大型・速達・外国」というのが通常のスタイルなのだ
けれど、この時期になると、皆さんも覚えがあるとおり、「年賀状」、「年賀状以外」というシール
が貼られるようになる。
ここで困ったのは、「はがき・封筒」の文字の上に「年賀状」が貼ってあるのではなくて、並行して
貼ってあるということ。つまり、わたしが送りたい「封筒」は、左の「はがき・封筒」に該当するが
「年賀状」ではないので、入れられない。で、「年賀状以外」である右に入れればいいかというと、
「大型」でも、「速達」でもないので、入れられない、ということになるのだ。
いや、別に無視して入れても構わないのだけれど、いったい郵便局としてどういう扱いをしているの
かわからないので、不安である。しばし、考えて右に入れた。少なくとも「年賀状以外」のほうであ
れば「年賀状」扱いされて、一月一日に届くということはないだろうし、もし「大型・速達」にまわ
されても、そこで普通郵便の方に回送されるはずだ。年賀状の方に回ってしまった「普通」のはがき
や封筒はたぶん、見過ごされる可能性が高い。なにしろ、年賀状は特設コーナーでてんやわんやの
状態でやっているもんだから。(じつは高校と大学のとき、季節バイトしてた。そのわりには上記の
事情とか取り扱いはよく憶えてない。)
まぁ、更新料は先に振り込んであるから、多少遅れても大丈夫だと思うけれど...。
さて、さて。いよいよ、あと一日。
がんばろう。
- 2005/12/26(月)
自然な覚醒を信条とするわたしだが、社会生活とはどうも相容れないため、やむをえず目覚ましを
使っている。携帯を5分間隔で三回振動させるのだ。二回目で覚醒しはじめたときが危険である。
三回目がうるさいと思って解除してしまうのだ。あるいは振動する瞬間を察知してとめる。記録
によると、今日は三回目は解除していなものの、とめてしまったらしい。振動を聞いた記憶がな
いから、「らしい」だ。
つぎに目が覚めたのは、メールの着信振動だった。その時点でデッドラインまで15分。このタイ
ミングでメールがなければやばいところだった。偶然だったけれど、感謝。
残業二時間。あまりアウトプット出ず。うむむ...。いろんなことがあたまのなかの同じところを
ぐるぐる回っているせいか、ほかのことも巻き添えをくって外に出てこないのだな。無限遠心加速
みたいなものだ。エネルギー準位だけが高くなるというか。
コミケを前に浮き足立っている、というのではないのだけれど。
どうしたんだろうかね?
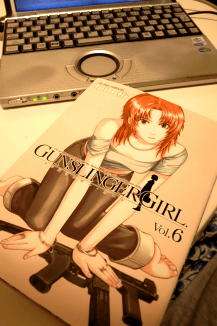
Gunslinger Girl vol.6、相田裕著、メディアワークス刊。550円。
相変わらずの美麗な絵。
線の細かく、丁寧な書き込み。
そして、どこまでも救いのない話。
でも、読むと落ち着く。偽物でも、小さな幸せでも、ないよりはあるほうがいい。
新人さんメインだったので、トリエラとクラエスの出番無し。やや哀しい。
(リコとヘンリエッタは出てたけど)
本文とは関係ないけれど、こういう装丁の仕事を一度やってみたいなぁと思ったりする。
"ガンスリ"(略称)の単行本はどれもハイレベルなので、装丁愛好家としては眼福このうえない
のであった。これも、ちょっとした小さな幸せというべきかな。
- 2005/12/25(日)

昼ごろに新刊+既刊=500冊が届いた。注文してから、搬入のことをまったく考えていないこ
とに気づいて、いったいどんなサイズのダンボールが何箱になるんやろうと気が気ではなかった
のであるが、なにぶん薄い本なので、それぞれ一箱ずつになってやってきた。これならなんとか
ハンドキャリーできそう。
とはいっても一人で抱えるのは無理なので、あわててカートを買いに鴨川沿いのニック(ホーム
センター)へ。998円なり。耐荷重25kgとある。載せてみるとかなり動かしづらいので、
これは25kgは超えているかも。できれば、一日目終了後に前日搬入したいなぁと思ったのだ
が、説明書によると事前許可制。まぁダンボール二箱というのは微妙なラインだし。
通常は、宅配搬入といって、自宅、もしくは印刷屋さんから直接、ホールの自分のスペースに送
り届けるようだ。これはかなりこわいので、自分ではやる気にはならない。だって、あの何万ス
ペースという場所の、どこも同じような場所(机しかない)に正確が荷物が届くかなんて、すご
い賭けだ。実際、この夏に自分スペースに行くとどういうわけか、ダンボールが置いてあったの
だ。もちろん、よそのもの。列を二つくらい間違えて搬入されていた。そのサークルさんが来る
まで預かっていたのだが、わたしたちが届けるまで気が気じゃなかったのは見てとれた。印刷屋
直送はもっとこわい。現物確認が当日ってことになるから。はじめてのオフセットでは勇気がい
ること。よほど信頼関係がないと。
しかし、最大の危険要因はこのところの天候による、輸送遅れ。自分じゃどうにもならない要因、
それも天の采配次第だから、これほど不安なことはありませぬ。だから、できる限り手搬入でや
っていきたいと思う。というか、これ以上部数を作ることはありえない。
ああ、こうやって考えてみると本を作って、実際に頒布するまでの間にいったいいくつの障壁が
あるんだろうか。そしてそこに費やされるエネルギーはどこから生み出されるのか。思うに、あ
のコミケという場全体から、いやわたしも含めて参加する全員からそのエネルギーは供給されて
いるのだ。わたしがサークル参加したい、本が作りたいと思ったのは、とつぜん天啓があったわ
けではなくて、長年通って本を買っているうちに、その本を読んでいるうちに発露してきたもの
なのだ。それはつまり、本を通じて発信される作者の思いがコチラに伝わってきて、その思いが
自分のなかにある何かを揺り動かしたということだと思う。そういうエネルギーの行き来があの
場所にはあふれている。(当然、本を買ってくれた参加者からのフィードバックもある)
ゆえに、サークル参加する者もやはり、本は買うのだ。当然だな。
今日、実家に帰っていたにもかかわらず、M1グランプリを見ながらサークルチェックをやって
いたのはそういうわけなのだ。ああ、犬とも遊びました。みかん食べてると、くれくれというの
で困るのであるが。
あと勤務は三日。
がんばろう。
- 2005/12/24(土)
朝、まどろみ。一度起きる。でも、またすぐ寝てしまった。
昼、お腹の調子が悪い。原因はたぶん、昨日の昼夜二回公演のために、朝と夕方二回ドリンク
剤を飲んだからだと思われる。酔っ払っていた(?)せいか、帰宅してからもう一ビン飲んだ
のがとどめを差したのかも。そういうわけで、昼食以外はほとんど外に出ずに読書。昨日買った
マリみて最新刊を読みきってしまった。
夕方、部屋の掃除を始める。ちゃぶ台の表面が見えるようになった。明日は、ちゃぶ台の周り
に退いた本やら書類を片付けよう(単に物体が移動しただけ)。
夕方、NHKで高校講座「物理」を見る。ときどき深夜にやっている同じ高校講座「化学」も
見ている。実験と解説のバランスがよくてわかりやすい。ものごとの原理原則というものが、
こんなに単純な法則や数式で表されてしまってホントに良いのか?と時々感動を覚えたりする。
物理はともかく、化学は高校で必修だったのは化学Iのみで、無機の後半と有機はまったく勉
強したことがない。だから、とてつもなくちんぷんかんぷんな時もあるのだけれど、その分新
鮮に感じるのだ。
夜、スタンドで夕飯。もしかしたら年内は最後かもなぁと思って。いつもの日替わりではなく、
スタンド定食(焼肉+ミンチカツ)を食べる。20円高いだけだけれど、まあ今日くらいは。
旅行に来たとおぼしき中年夫婦(おそらく東京人)が、ほかの人の日替わりを見て、「あのハン
バーグが食べたい」と言った。店のひとによると、単品であるらしい。でも、店内にかかってい
メニューには載ってなくて、そのことを旦那のほうが突っ込んだ。これを因縁をつけるという。
まぁ、別にそのことに怒っている様子ではなくて、上品な感じの客だったのもあって、店の人も
わたしもその「因縁」の真意を測りかねたのであるが、店の人(それもバイトのお姉ちゃんだっ
た)はちょっと考えてから「載っているときと、載ってないときがあります」と切り返した。
客は、ちょっときょとんとしていた。さすがである。いいものを見せてもらった。
夜、「トップをねらえ2」の1巻を続けて二回見る。メインタイトルが出るまでの旅立ちの列車
のシーンがともかく良い。戦闘シーンがなくても、ここだけで見る価値がある!がっちり掴まれ
た気がする。
深夜、KREEKのPsalms of Davidを聞く。来年の楽しみができた。
こうして、おなかのちょっとゆるい、おだやかな日を終えた。
- 2005/12/23(金)
第7回合唱団葡萄の樹くりすますこんさーと@京都文化博物館別館ホール。
昼公演:13:00開場、13:30開演。入場料1000円。
夜公演:17:30開場、18:00開演。入場料1000円。
プログラム
・コダーイ合唱曲集、『マトラの風景』他
・「合唱のための12のインヴェンション」(間宮芳生)より
・アラカルトステージ、"Ave Maria"(Raminsh)、他
いまからでもまだ間に合いますでの、お時間のある方、ぜひお越しください。
追記:演奏会無事終了。いまから自画自賛する。いままで7回のコンサートを経て、今回
やっぱり何かが変わったと思う。音楽的なことも、マネージのことも。いままでばらばら
に動いていたことが、ようやくひとつの糸によりあわさってきたなんだなーと思う。葡萄
の樹の名前、そこにこめられた願いの通りに、葡萄のつるが伸びはじめたんだなって、
いま感じているところ。
打ち上げの最後に、もう一度みんなで歌った「翼」を、わたしは生涯忘れないと思う。
- 2005/12/22(木)
大雪。
BK、本番直前練習。練習直前になって急にいつもの練習場が使えなくなっていて、急遽
場所変更なんてハプニングもあったけれども、あとは明日だ。明日が勝負。BKもなんと
なく、NCと遠いようで、近いところがあるのかもしれない。本番にならないと全員そろ
わないとか、当日勝負とか。ミラクルが起こるかはわからないけれど、あとできることは
楽しんで歌うことだけだと思う。皆で顔を見合って、お客さんとも顔を見合って。
直前ということで、すぐ帰宅。
ネットを回っていると、たまたま見つけた。
>コバルト文庫新刊「マリア様がみてる 未来の白地図」2005年12月22日発売
今日やん!そろそろかなー、そろそろかなーと、最近コバルトコーナーをうろちょろして
いたのに。明日、集合の前...は本屋は開いてないないな。昼公演が終わったら、すぐに
大垣書店にレッツゴーなのだ。それにしても、未来の白地図ってなんか、ちょっとシリア
スな予感がする。とうとう決まるのか?妹が。
では、明日頑張ろう。
おやすみなさい。
- 2005/12/21(水)

「夜と昼の間」(1/10sec,F2.4,ISO64、ノートリミング)
最近、原稿作業のためや、練習、補習のために定時ダッシュをしていると、こんな風景を見る
ことができる。無骨で無機的な鉄の塊が、とても複雑な影絵に変貌する。日が沈みきってしま
うまで、わずか10数分間の短編映画。
でも、きょうは雨。冷たい風。
この前の雪の日より寒いよぉ。
18:30〜21:00、BK男声補習@おうき会館。暖房がほとんど効かない会議室。芯から
冷える。同じ部屋で先々週やった女声補習は、さぞやつらかっただろうなぁ。終了後、「花いち
りん」にて、生姜焼き定食を食べる。美味。練習後、さくっと食事だけでも、というときは、こ
こで食べて帰ることにしよう。
BK演奏会まであと1日。
- 2005/12/20(火)
ひさしぶりに会社帰りに本屋に行く。入って正面の平台に「生協の白石さん」という本が置い
てあったのでちょっと読んでみる。なんでも30万部とか、売れているらしい。売れている本
には手を出さないというのがじぶんのなかの流儀なのだけれど、立ち読みするくらいならいい
だろう、という程度の流儀でもあったりする。
皆さんご存知なのかもしれないが、東京農大だっけかの大学生協に寄せられる質問や要望に、
職員である白石さんが返信したものをまとめた、というのがこの本の内容。その返信内容がえ
らく誠実で、それゆえ普通の質問よりも、一言「ナブラチロアー」とか書いてあるだけのよう
なものへの回答の方が、その誠実さとそこから生み出される面白さが際立っている。そこが良
いというので、本になったものらしい。本にしようとした編集者はなかなかヤル。
しかし、である。一ページの上段に質問、下段に回答というスタイルなのだけれど、これずっ
と読んでいると、なんだか飽きてくるというか、つまらなくなってくる。ひとつひとつ抜き出
してみれば面白いのに。最初に期待していたような、どんな回答が?っていうわくわく感がな
くなってくる。
これはもう、もととなった白石さんの回答や、とっぴな質問を投げかける学生のせいではむろ
んなくて、あきらかに編集のせいではないかと思う。えんえんと同じ構成の本なんて、読んで
いてあきないわけがない。だったら、白石さんの回答を、傾向別や内容別に、たとえば「普通
篇」「クール篇」「熱血篇」、「生活篇」「学問篇」「恋愛篇」というように分類するといっ
た工夫があってよかったのではないかと思う。だって白石さんのパーソナリィで成り立ってる
本なんだから、それをより先鋭化するほうが、親しみがわくはずだろうし。もっと簡単なくく
り「春夏秋冬」でもいいのかもしれない。それぞれの季節感がわかるような質問を並べてゆき、
時間の流れをだすことで、読んでいるひとに学校生活を想像させるのだ。学校という、白石さ
んの職場をリアルに感じてもらうための工夫になるのでは。
あと、全部活字なのも飽きてくる原因かもしれない。こういう質問は全部手書きなのだろうか
ら、それをそのまま載せるほうが、質問にうそっぽさがなくなる。白石さんの回答はもしかし
たら、手書きではなくて、活字なのかもしれないが、その対比が面白さを生むかもしれない。
手書きだったら、全部の回答が同じひとの字なのだから、これまた親近感を生む。
そう書いていてきづいた。この本に足りないのは親近感なのだ。
さて、なぜにここまで話をするかというと、先に書いたように、編集がよくないと感じるから
だ。もっというならば、ありもののテキストをそのまま使って、なにもしないで儲けようとい
う編集サイドの魂胆が、この本にありありと透けてみえるのが、気に食わないのだ。
電車男の本、見たことがあるだろうか。あの本をだすにあたって、新潮社が出版権を獲得した
のは編集者が、2chの掲示板の雰囲気をどうやって紙面に再現するのか?ということを、試
行錯誤して考え、フォントやレイアウトを工夫し、それが2chの担当者に共感を生むものと
なっていたからだという。「ありもの」のテキストだからこそ、編集者の努力や熱意というも
のが違いとなってあらわれてくるのだ。
そういう点で見て、この本はわたしとしてはいい本とはいいがたいし、買いたいなと思わない。
回答や質問の「索引」でもあれば、考えたかもしれないけれど。しかしなぁ、わたしがそうお
もったからといって、この本は現に売れに売れているわけだから、それはもう白石さんの文章
の力が編集者の思惑なんか以上にすごいということなのかもしれないなぁ。
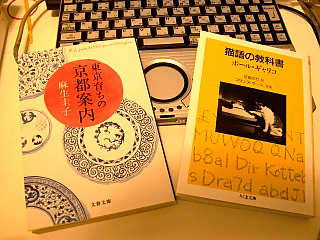
今日買った本(左)と、この前「読み終わったら紹介します」といっていた本(右)。
今日、紹介を書こうかと思ったのだけれど、白石さんネタを考えたのが先だったので、
また今度ちゃんと書きます。どちらもいい本なので、さきに写真だけでも。
あしたはBKベース補習。忘れないようにしないと、いつものくせでスタンドで食事してるかも
しれない。気をつけねば。
おやすみなさい。
- 2005/12/19(月)
冬コミ新刊、入稿しました。
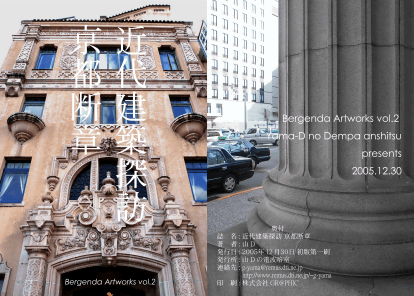
新刊「建築探訪 京都断章」(B6判、24ページ中綴じ、フルカラーオフセット)。
頒価500円。

既刊「建築探訪 東京横浜篇1」(B5判、16ページ中綴じ、フルカラーオフセット)。
頒価500円。
コミックマーケット69、東ヌ14b「山Dの電波暗室」にて頒布いたします。
今回は、新刊・既刊ともに夏コミの5倍刷りましたので、開始一時間でなくなるなんてことは
ないはずです。夏にお買い求めいただけなかった方、その節は大変申し訳ありませんでした。
皆さん是非お立ち寄りください。よろしくお願いします。m(_ _)m
*****
さて、前回の本は写真が主体だったのだが、今回は文字+写真のエッセイ風のつくりとなって
いる。文字数が増えるので、仕事で雑誌を作成している友人に文字校正をお願いした(前回の
本でも少なからず誤字・脱字があったので、必要だと思った)。いやぁ、やってもらってよか
った。本当に。自分でも当然ひと通り読んではいるのだけれど、まったく気づいていなかった
重複や、句読点抜けがポロリ、ポロリと出てくる。客観的な視点というのは、やはりどれだけ
注意しても、本人が持つことは難しいのだ。
もちろん、それだけではなくて、さすがプロだなと思ったことがいくつかあって、まず指摘さ
されたのが誤字・脱字ではなくて、カッコを使うときの句読点の位置という、なかなか意識で
きない点だったこと。これは文字を組んだときのバランスの違いを見ると、なるほどって思う。
それから、表記の揺れを統一した方が良いよっていう指摘。とくに揺れやすい例を書いてもら
ったのだけれど、結構ひっかかっていた。「実は」と「じつは」や、「見る」と「みる」、
「中へ」と「なかへ」、「上」と「うえ」などの漢字とひらがなや、「12月」、「十二」と
「一二」や、「10m」と「一〇m」といった数字表記がそう。本人は全然そのつもりがなく
ても、FEPで文字変換していると知らない間に変換されていたりする。特にレイアウトの都
合上、細切れに変換を繰り返すとよくやってしまうみたいだ。
ほかにも、文字ピッチや段組、章立てにまで話が及んで、正直自分が考えていた校正作業って
いうものが、誤字・脱字くらいの本当に狭い範囲しかみていなかったことに気づかされた(誤
字・脱字チェックを軽んじているわけではないです)。
文字のデザインや、レイアウトにうるさい人間だったつもりだけれども、もっとちゃんと勉強
しないと駄目だナァとも思った。
それで、校正をみてもらった後、キンコーズへ行き修正作業開始。指摘箇所の修正だけでなく、
それをきっかけに文章のつながりを再度見直すところまで及んだ。結果として、昨日までの文
章がネジ半回転分、キュッとしまりがよくなったように思う。最後の最後で納得のいくものに
仕上げることができた。これも校正のおかげ。
改めてありがとう。>私信
最後に、印刷屋さんごめんなさい(受付時間を過ぎてから無理やり入稿した)。
−まさか、自分がこのセリフを言うことになるとは(心の声)。
−やっと同人らしくなったじゃないか(悪魔の囁き)。
おやすみなさい。
- 2005/12/18(日)

「雪屋根」(1/440sec,F3.5,ISO64、ノートリミング)
日本全国、雪でえらいことになっていますが、京都市内はそれほどでもなく。自転車の車輪で
雪を「きゅっ、ミシっ、きゅ、ミシっ」と鳴らしながら走るくらいの余裕もあり。ニュースで
見た高知や、広島といった、ふだん雪と全然無縁のところが別世界のようになっていたのには
驚いてしまった。年末に東京付近で、いや全国で降らないことを祈るばかり。雪でビッグサイ
トにたどりつけないっていうのは、サークル参加、一般参加どちらにとっても無念極まりない
こと。
ひるすぎ、いったんキンコーズに行くも、満席。年賀状を作ってるひとが多いのだ。その後、
もう一度見に行くと、人が入れ替わって再び満席。しかたがないので、時間をつぶすために
時計屋へ行く。こんな日だから、店主も話し相手が欲しかったらしい。はなしのついでに、
ぶどうの演奏会のチケットを買ってもらう。前回、文博でやったときの演奏を気に入っても
らえたらしい。

「IWCインジュニア」(1/32sec,F2.4,ISO64、マクロモード、ノートリミング)
生産中止品なので、アンティークとよんでいいと思う。インジュニアとはドイツ語でエンジニア
のこと。技術者向けに作られた、耐磁能力(80000A/m)を強化した時計。(一般に時計は磁力に
弱い)。同じ名前で、今年復刻されたけれども、デザインを見る限りはどうみても昔の方がいい
ので、中古価格は相変わらず堅調。下げがまったくない。この時計を手にするのはかなり先のこ
とになりそう。思い切りも相当いるだろうなぁ。ええ時計。
15:30〜16:30、キンコーズにて作業。既刊の手直し。
17:30〜18:00、印刷屋へ既刊の入稿。明日の夜、新刊の入稿予定で調整。
作業も収束に向かい、やや安心。あと少し。
母親が香港からもどったらしい。WTOの会議ともろにぶつかっていたが、観光できたんだろうか?
あしたも雪みたいだ。
おやすみなさい。
- 2005/12/17(土)
12:30〜13:30、キンコーズにて作業。MOが壊れる。二回目。一枚目をさしこみ、
ファイルをPCにうつす。そのあと、二枚目を差し込むと、なぜか一枚目と同じ内容のファイ
ルが表示される。MOの構造はよく知らないが、どうもTOC(Table of contents)情報が
誤って、二枚目に書き込まれてしまうらしい。一度この情報が書き換わると、二枚目のディス
クのファイルは二度と読めない。二回ともキンコーズで発生。別ディスクにバックアップをと
っていなければ、終わりだった。こわいので、別のPCに替えてもらい、作業続行。店員に話
したが、たぶんわかってない。家のMOや、実家で使っていたMOではこんな現象はなかった
から、十中八九あのPCにつながってるドライブのせいだと思うだけれど...。どーも、なにか
しら障害が立ちはだかるよーだ。ここまで来て、くじけられるか。
・冬コミ作業進捗
○表紙、裏表紙 完成
○P2〜3 完成
○P4〜5 完成
○P6〜7 完成
○P8〜9 完成
○P10〜11 完成
○P12〜13 完成
○P14〜15 完成
○P16〜17 完成
○P18〜19 完成
○P20〜21 完成
○P22〜23 完成
あす、文字校正後に丁合い作業を行って、入稿準備が完了する。この最後の作業が面倒なんだ
よなぁ。どのページとどのページが一緒になるのか、紙に書き出していても混乱するから。そ
れから、既刊について、若干の手直しが必要。一緒に入稿せねば。
15:00〜17:00、NC演奏会関連発送マネージ。相変わらず、本町の喫茶店で作業。
机と椅子をがばっと確保する。周りの目であるとか、店員の視線とかを受け流さないとやって
られないのであった。とはいえNC事務所、本気で欲しい。近くにSOHO用の貸部屋が一ヶ
月40000円程度であるのを見つけた。それだけの定期収入があればなぁ。あるわけないけ
ど。
17:00〜21:00、NC練習。演奏会の曲をほぼ全曲音取り。
21:30〜23:25、NC忘年会。終電ぎりぎり。淀屋橋まで早足。
バックアップとってから寝ます。
- 2005/12/16(金)
BK練習。練習の時間だけでは、全曲を反芻するのは難しい。人が増えて、先週の練習に比べ
ると音楽が大味になったようなところがある。簡単な和音が決まらなかったり。声の組み合わ
せをもっと考えにゃーとおもうのだけれど、ついつい塗りこめるような歌い方をしてしまうの
だった。というわけで、来週は男声だけで補習をすることにした。ほら、試験の直前に勉強し
たことっていうのは案外、出たりするもの(一夜漬けみたいで喩えが悪いけど)。直前に少し
でも「音色をそろえる感覚」が共有できたらなぁと思う。
BK宴会、ロングバージョン。皆を巻き込んで、マネ会も行われる。こういう有機的な連携の
あるマネージってNCにはないもの。BKではほとんどマネージにタッチしていないので、少
しうらやましく思ったりする。今年の委員会はひとあじ違う。なんだか、とてもいい。
眼鏡交換会、モノクロ写真撮影会を経て終了。
きょうは、冬コミ作業はお休み。残り日程をがんばろうっていう気持ちで家路についた。
- 2005/12/15(木)
夕方、母親からメール、「明日から香港行ってきます」。えらくとつぜん。たまったマイルを
使うのだろうけど。お土産に漢方薬を期待し、無事を祈る。
19:45〜23:30、キンコーズにて作業。
こんなに長時間になってしまったのには、訳があって、昨日完成していた分の校正刷りを出力
してから、作業をしていたところ、2時間経ってから、「プリンターが壊れてるのです」と、
店が言ってきたから。出力に時間がかかることがわかっていたから、早めに作業していたのに。
そこからファイルを開いて別のプリンターに出力しなおし。あまりにも腹が立ったので、何度か
無言の圧力をかけ、80分の料金を値引きさせた。余分にかかった時間の間に作業はしたけれど
も、感情を抑えていたのと、あまりの脱力感で、進捗ははかばかしくなかった。今日はきりのい
いところで切り上げて、ゆっくりするつもりだったのにな。値引きさせたところで、とられた時
間は返ってこないのだぁ。「この、時間ドロボウ!」って罵ってやりたい。
・冬コミ作業進捗
○表紙、裏表紙 完成
○P2〜3 75%(残り、中表紙のみ)
○P4〜5 完成
○P6〜7 完成
○P8〜9 完成
○P10〜11 完成
○P12〜13 完成
○P14〜15 完成
○P16〜17 完成
○P18〜19 完成
○P20〜21 完成
○P22〜23 完成
あまり愉快でないことを書いてしまって申し訳ないです。あまりに腹に据えかねたので、どこか
ガス抜きが必要なのでした。なんとか、残り時間で良いものにしあげたいと思います。m(_ _)m
前回も思ったことですが、本を作るって簡単にはいきませぬ。
- 2005/12/14(水)
どうやらニュースを見ていると各地で大雪が降って、朝も滋賀からやってくる電車が遅れて
いたりするのであるが、京都はというと、とにかく芯から冷えるものの、目に見える形で雪
が降らない。いや、降ったみたいなのだが、すくなくとも朝起きて、屋根にうっすら積もっ
ているとか、そういうレベルではないし、なによりわたし自身、ちらつくとこさえ見たこと
がない。雪が舞うのを見れば、すこしは楽しげなのに、いまのままでは寒いだけで嫌だなぁ
と思う今日このごろ。
そういえば、JRで「雪害の影響で列車が遅れましたことを...」とアナウンスしていたの
だが、あれは変だろう。列車が遅れるということそのものが雪害ではないのか?それに「害」
というものはすでに起こってから確定した事象で、それに「影響で」という現在進行に近い
言葉がつづくのは違和感がある。すなおに「雪の影響で」とか「積雪で」と言えばいいのに。
ようやく、冬コミカタログを購入。ちゃんと、644頁の3段目4列目に載っていた。スペー
ス番号は東ヌ14b。カメラ・写真のスペースは全部で7つだから、夏コミと同等。2日間開
催で軒並み当選率が下がっているなかでは健闘していると思う。しかし、まえに比べて比率が
変わってきた。7つのうち、5つが写真、2つがカメラ(メカ)。2年くらい前までは9割方
メカだったのに。やはり画質のいいデジカメが普及して、個人でも写真集が作れるようにな
ってきたからだろうなぁ。銀塩中古カメラ市場は衰退の一途をたどっているし。
なにはともあれ、これでまた気持ちが奮い立ってきた。
あと少し、がんばろう。
19:30〜22:30、キンコーズにてレイアウト作業。
・冬コミ作業進捗
○表紙、裏表紙 完成
○P2〜3 50%(テキスト完成)
○P4〜5 75%(テキスト完成)
○P6〜7 75%(テキスト完成)
○P8〜9 75%(テキスト完成)
○P10〜11 75%(テキスト完成)
○P12〜13 完成
○P14〜15 完成
○P16〜17 完成
○P18〜19 完成
○P20〜21 完成
○P22〜23 完成
そういえば、去年の冬コミ、東京は雪だった。
- 2005/12/13(火)
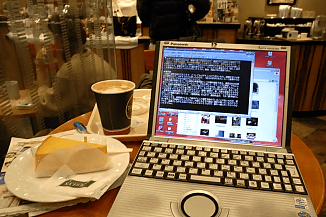
こんな感じで。
ラテ+かぼちゃチーズケーキ=650円。高い!もういっかい夕飯が食べられるじゃないか。
まぁ、いすわってるのだから文句は言わない。チーズケーキは高いなりにおいしかった。テキ
ストを生み出す養分になったと思う。
19:30〜21:30、昨日と別の喫茶店にて作業。
23:00〜23:45、自宅にて続き。
それなりに、なっとくのいくものができた。あとは、レイアウトの段階で削っていかないと
ならないだろうな。わずか1行の削除でもつらい。書いた時点では完結した文章だから。ま、
その苦労のおかげで、もっとよくなることがあると思ってやるしかないのだ。いよいよ大詰め。
ふたたび、キンコーズへゆくぞ。
・冬コミ作業進捗
○表紙、裏表紙 完成
○P2〜3 50%(テキスト完成)
○P4〜5 75%(テキスト完成)
○P6〜7 75%(テキスト完成)
○P8〜9 75%(テキスト完成)
○P10〜11 75%(テキスト完成)
○P12〜13 75%(テキスト完成)
○P14〜15 75%(テキスト完成)
○P16〜17 75%(テキスト完成)
○P18〜19 50%(テキスト完成)
○P20〜21 50%(テキスト完成)
○P22〜23 50%(テキスト完成)
あしたもがんばるさー。(ちょっとハイかも)
おやすみなさい。
- 2005/12/12(月)
熱のせいか、薬のせいか、なにコラ関係と思われる行事でイタリアを列車で移動している夢を
見る。乗っているのはどうも日本の車両のようで、いまいち旅行している気分にならない。
気がつくと目の前に、あのセザンヌが終生描き続けた、サント・ヴィクトワール山が迫ってい
た。おかしい、イタリアを南に向かって旅行しているのに、フランスの山が見えるなんて。途中
の駅で、普通列車に乗り換えて、ようやく目的地へ。すると、すでに見知った顔がいるではない
か。声をかけると、どうも乗り換えなくても先の列車に乗っていればついたらしい。乗り換えた
せいで、滞在時間が残りすくないことを嘆くのであった...。変な夢。
そのわりには、目覚めはよかった。熱もひいていた。けれど、なにか納得がいかないなぁ。
帰宅後、外で食事をし、そのまま烏丸通り沿いの喫茶店へ行く。一度でも自宅に腰を落ち着けて、
そのままくじけてしまうのを警戒したからだ。夕飯を食べたばかりで、喫茶店にはいってもなにも
注文する気になれなかったのだが、居座るのが目的なので買わないわけにもいかない。脳に糖分が
必要だろうと思って、チーズケーキとカフェモカを頼む。470円、ちょっと高いと感じる。
わりと大きなところで、二階席の窓際なんかが作業にはよさそうだ。とおもったら、いいと思える
ポジションは、わたしと同じ目的、勉強や仕事で長時間粘る人たちで埋め尽くされていた。相席す
るわけにもいかないので、一階の一番隅っこに陣取った。スピーカーの真下だったことにあとで気
づく。
19:00〜21:30、テキスト作成。なかなかの集中度。音楽もなっているし、それなりに
がやがやしているのに、筆が進む。途中、おばちゃん6人組が目の前に来たときは、その大音量
ヴォイスにややひるんで、ノートを閉じかけたが、こんじょうで筆を動かしつづけた。20分も経つ
と出て行ったので、わたしの勝利である。(何人か、読書や勉強していた人が逃げていた。)
はじめのうちは、文章が硬くなって、なんども書き直していたのだが、途中から自分の地のものを
文章に出せるようになってきたと感じる。単なる建築のガイドブックでは同人誌である意味がない。
オリジナリティをどこまでだせるか、そのことと読者に楽しんで読んでもらうことのバランスを
意識しながら、書いてゆく。
きょうは5件分を仕上げた。残り4件。
あしたも、喫茶店に行こう。気分を変えて、別のところへ。
・冬コミ作業進捗
○表紙、裏表紙 完成
○P2〜3 50%(テキスト完成)
○P4〜5 75%(テキスト完成)
○P6〜7 75%(テキスト完成)
○P8〜9 75%(テキスト完成)
○P10〜11 75%(テキスト完成)
○P12〜13 75%(テキスト完成)
○P14〜15 75%(テキスト完成)
○P16〜17 0%
○P18〜19 50%
○P20〜21 0%
○P22〜23 0%
おやすみなさい。
- 2005/12/11(日)
熱っぽいためか、作成に集中できず。テキスト完成度は10%。
それと、自宅でやるとやはりだめなのかもしれない。喫茶店で原稿を書く作家の気持ちがわか
るような気がする。
くすりをのんで早めに寝ます。
- 2005/12/10(土)
11:30〜16:00、NCにてハンドベルのコンサートに賛助出演@伊丹アイフォニックホール。
18:00〜20:10、同志社グリークラブ定期演奏会@京都コンサートホール。
21:15〜23:15、冬コミ新刊作成作業@キンコーズ。
・冬コミ作業進捗
○表紙、裏表紙 完成
○P2〜3 0%
○P4〜5 50%
○P6〜7 50%
○P8〜9 50%
○P10〜11 50%
○P12〜13 50%
○P14〜15 50%
○P16〜17 0%
○P18〜19 50%
○P20〜21 0%
○P22〜23 0%
写真レイアウト作業、思ったよりも、疲労。やはり、当初予定よりもいろいろといじりたく
なってくる。しかし、そういうときは新入社員当時の研修で教えられた言葉を反芻する。
「拙速は巧遅に勝る」
ようするに、「締め切りに遅れたらダメ」ということです。しかしなぁ、午後の予定で
かなり疲労していたと思われ、集中力は2時間が限度だった。明日は、まず全テキスト
を完成させるのが目標。この作業はキンコーズに行かなくても良いので助かる。
というわけで、いまは集中力がなくて、頭も痛いので、同グリ演奏会の感想は明日に。
課題は多いにせよ、演奏会としては悪くなかったなぁというのが感想の要約。
風呂に入って寝ます。おやすみなさい。
- 2005/12/9(金)
BK練習、輪になって練習。とても良い音がときどき鳴る。あとはもっと顔をあげられたら
いいのになと思う。最後はやっぱり顔で歌うのです。
BK宴会、きょうは長丁場。帰宅すると、いつもよりたくさんの「ろぐ臭」(お好み焼き屋
の臭い)が漂っていた。ちょっと、ぼーっとしている。眠たいんだと思う。きょうはひさし
ぶりにたくさん話を聞いた気がする。歯を磨いて、寝ます。
明日の目標:
全頁の写真レイアウト完了まで。解説は日曜日に一気にやりあげるつもり。
- 2005/12/8(木)

「建築現場のメリークリスマス」(1/100sec,F2.4,ISO64、ノートリミング)
仕事が終わってからキンコーズに向かう。ちょっとばかし混んでいたので嫌な予感がした
ら、的中してしまった。Photoshopを使えるマシンが空いてないのだ。今日、作業しないと
ずるずると何もしなくなってしまうような気がして、どこかで時間をつぶすことにした。
北上して、大垣書店へ。
昨日、文庫を読み終わったばかりで、次の本を探さないと、と思っていたのに、いざたくさ
んの本を目の前にすると、そこから一歩も踏み出せないのだった。それはつまり読後の余韻
があわあわとではあるが残っているからにほかならなくて、この気分を打ち消すのは無理だ
なぁと思った。で、小説はやめようと。(あくまで本を買うことはやめない)
エッセイか何かにしようかと思ってさがしていたが、小説の世界からエッセイにとびうつる
と、文章が妙に生っぽく感じてしまって、落ち着かないのだった。やれやれ。広告、美術、
デザイン、漫画、ライトノベルと回ってみたけれど、ぴんとこなくて、あきらめかけたとこ
ろである本を見つけた。それは表紙を見ただけで買わないといけない!とまで思ったし、
実際に少し立ち読みしてもその通りで、いい勘してるなぁ自分は、などと自分で自分をほめ
る始末。
その本というのは...、読み終えたら紹介しましょう。焦らさないともったいない。
ところで、本を読み終えたときはまだしも、本を読んでいる最中に本屋に入ったらどうなる
か。そういう経験をこの前の日曜日にしたのである。映画を見るまでに時間があったので、
Book1stへ行ったのである。でもこの時点で本当は本屋に行きたいのではなかった。ちょう
どきのう紹介した本を読んでいて、それが左のぽっけに入っていたのだから、それはもう
その本が読みたくて仕方がなかったのだ。しかし、時間はあるし、雨は降っているし、寒い
しという状態では、ほかにすることを思いつかなくて、本屋にいったのである。ひとときの
休息のつもりだった。で、そこでとうとつに思ったのは、「本を読むスペースが欲しい!」
ということだった。
それなら、喫茶店に行けばいいというのは正しいのだけれど、わたしはあまりこの界隈の喫
茶店に通じていなかったのと、雨のなか、落ち着いて本が読める場所をさがす余裕もなかっ
たのである。だから、本を読むスペースが欲しいというのは、第一には街中において、本が
快適に読める場所を常にキープしておくべきだということの表現である。スパイが世界のあ
ちこちにアジト(ふるい言葉だなぁ)を持っている(断定)ように、いごごちのいい場所を
もつのだ。それはもちろん、晴れてるとき用、雨のとき用、雪のとき用、泣きたいとき用、
(泣きたいときに本は読まないか)を想定しておく。
第二には、本を読むためだけのスペースがあったらなぁということだ。喫茶店はかならず
しも本を読みたいひとだけでなくて、おしゃべりがしたい人も来るからだ。みんな本を読
んでいる場所。カップルも、友達同士も、ここに来るときは必ずマイブック(?)を一冊
は持参して、本を読まないといけない。きまりはそれだけ。飲み物はコーヒーか、紅茶か、
牛乳があればいい。本屋に併設してくれるといい。でも、売り場のまじかだったり、丸見え
なのは嫌だ。できれば、二階にあがりたい。窓から、一階の売り場スペースが眺められる。
そういうところがいい。窓際にずらっとカウンターのみあって、少し高めの丸いすにすわる。
そんな商売をやったら以外と評判を呼んで、店を増やして....とだんだん不純な方向に想像
が進んでしまうのは経済誌の読みすぎのせいかもしれない。反省反省。
ともかく、自宅以外で本を読める場所があればなぁと、いう願いにも似た欲望が起きたとい
うのが結論である。
21:00〜22:30、キンコーズにて作業をしてから帰宅した。
表紙だけでも形になると嬉しい。楽しみが加速していくのを感じた。
・冬コミ作業進捗
○表紙、裏表紙 完成
○P2〜3 0%
○P4〜5 30%
○P6〜7 0%
○P8〜9 0%
○P10〜11 0%
○P12〜13 0%
○P14〜15 0%
○P16〜17 0%
○P18〜19 0%
○P20〜21 0%
○P22〜23 0%
おやすみなさい。
- 2005/12/7(水)

「京都文化博物館にて」
技術シンポジウムのため出張。ポスターセッションの海を行き交い、たくさんの人と話す。
久しぶりの同期と出会い、研究室の同期とも再会する。業務上関係ありそうな発表をわたり
あるくうち、いつしか単なる一技術者として、好奇心のおもむくまま泳ぐ。なにか、力強い
もので内側から満たされていくような錯覚を覚える。
帰宅後、機材をもって最後の撮影地、京都文化博物館別館ホール、旧日本銀行京都支店へ向
かった。外観撮影を終えて、なかに入る。内部撮影はかまわないという。思い切って三脚は
どうかとたずねると、本来ならだめだが、この暗さなのでいたしかたありません、かまいま
せんよ、との返事をもらった。こういうことはふつうないことだ。ありがたかった。
撮影後、スタンドで夕飯。本を読みながら、やや長居をする。すぐ北にある錦天満宮に気ま
ぐれで立ち寄り、お参りし、おみくじをひき、牛の頭をなでて、自分の頭をなでてから、
家路についた。今日は作業しない。このなんとなく、ゆるゆるとおだやかな水面のような
気持ちのまま、本を読み、眠りにつきたいと思ったからだ。
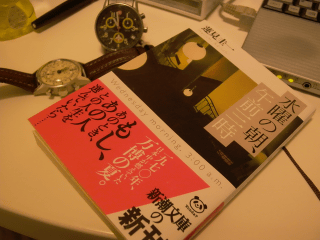
「水曜の朝、午前三時」、蓮見圭一著、新潮文庫。476円。
土曜日に談で買って、NC練習に行く阪急で読み始めて以降、5日間ずっと読み続けて、
さっき、読了した。裏側のあらすじを読めば、すぐにわかることだが、恋愛小説である。
まぎれもなく。ただし、とても厳しくて、まっすぐで、せつない。そして、とても思索
にあふれている。なくしたものへの惜別でもなければ、涙の枯れた諦念でもなく、その
先には人生と家族というものが続いている。それは一見、重たいものではあるが、この
小説の白眉ともいうべき、プロローグとエピローグを読むうちに、ゆるやかに受け入れ
ることができるように思う。静かで力強い言葉とともに。
いつか、もう一度読むだろう。いや、なんども読むような気がする。
- 2005/12/6(火)
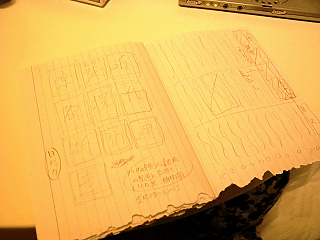
B5のノートを6枚破って重ね、二つ折りにすると、中綴じB6、24ページの小冊子ができる。
これをつかって実際の本のレイアウト原案を鉛筆で書いていく。漫画のネームみたいなものだ。
(実物を見たことないので想像。たぶんあってる。)
こうやって、「形」を伴うと、完成形が頭にイメージできて、ずいぶんと製作に対する心理的な
不安は取り除かれたような気がする。実際のところ、キンコーズの時間貸しのPCで作業する訳
で、考える時間は作業する時間にまわさないともったいない。これはそのための台本なのだ。
とはいっても、いざPCの前に座って、写真と文字と組み合わせはじめると、あーでもない、
こーでもないとやりだすに違いない。そして、そういった試行錯誤のある瞬間、とつぜんに思い
もかけない、レイアウトを「発見」するのもまた事実なのだ。そう、発見。それはそこにはじめ
からあるのだ。それを見つけられるかどうかは、自分の眼がどれだけ開かれているかにかかって
いるような気がする。
あすは出張で早いため、これでおやすみなさい。
- 2005/12/5(月)
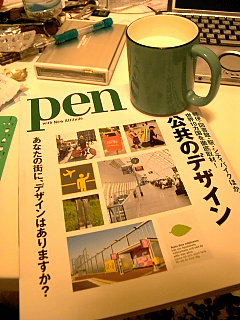
雑誌「pen」12/15号、特集「公共のデザイン」。
公共のデザインと聞いて、まっさきに思い浮かぶのが「駅」である。わたしの場合。これは何度
も書いているような、そうでもないような、確か何年か前の会社の所感で話そうと構想をねって
そのままほっておいた話かもしれない。まぁ二回目だったら許してください。
京都駅が立て替えられると聞いたとき、あれは学生のころであったが、非常に期待をした。なぜ
って、当時の京都駅は1000年の古都の玄関先としては、非常に情けない駅ビルが立っていて、
新幹線駅舎である八条口はまだましにしても、雑居ビルのような印象がただよっていた。駅舎と
しての「品格」でいえば、ローカル線である山陰線の駅、二条駅の方がその規模に比べてずっと
玄関口というにふさわしい様子であったのも一因だ。なにせ二条駅には貴賓室まであったくらい
である。(現在は、梅小路蒸気機関車館のエントランスとして移築されている。)
で、多大なる期待の末に、工事がはじまってみて、駅ビルの全貌はわからないものの、どこか
おかしいということに気づき始めた。わたしは当時、山陰線で京都駅までゆき、そこから跨線橋
をわたって、ちょうど反対側の近鉄乗り場まで行き、近鉄に乗り換えて大学に通っていた。その
こせんきょうの南北連絡通路が、まず閉鎖された。そのせいでただでさえ駅の端っこにある山陰
線の位置から、いまのこせんきょうの位置まで+50mは遠くなってしまった。これは朝の時間
がない時には大問題だった。そして、しばらくすると、今度はこせんきょうに上る階段の幅が、
なんと「半分」になってしまった。半分ですよ!半分。朝のラッシュ時に密度が倍になるってこ
となのだ。そして、そのうちに信じられないことが起きた。橋上に改札口ができたのだ。
一見便利に見える橋上改札。でもこれがいけない。南北の人の移動に、改札という左右の余計な
導線を混入してしまったからだ。おかげで朝だろうが、昼だろうが、常に大混雑。道筋がみえな
いので、自分の通るところが道になる。それが通勤客分だけあるのだから、ホームに下りるのに
一苦労である。
そして、完成した駅ビル。そう完成したのは駅ではなくて、駅ビルだった。駅とはほぼ、無関係
に存在する、形はちょっと面白いけれど、通勤客にはなんの意味もなさないビルだった。あれ、
やっぱり同じことを書いたような気がしてきた。まぁいい、つづき。駅が改装されると聞いたと
きに期待したのは、確かに立派なビルだったのだ。なぜビルにしか思いいたらなかったかという
と、見た目はともかく、京都駅のホームはそんなに使いにくいわけではなかったからだ。
それが、どうだろう。ホームへの導線はくずされ、階段は狭まり、山陰線のホームはより遠ざけ
られてしまった。駅ビルをデザインした原広司は、駅ビルはデザインしたけれども、駅はデザイ
ンしなかったと思う。そう、それこそがこの雑誌の特集を見て思ったこと。公共の建物をデザイ
ンするとき、建物単体でものを考えてはいけないのだ。
駅というものは、あらゆるものの複合体で、いってみれば一つの小さな都市なのだ。都市をつく
るときに、マンションやオフィスビルだけがあっても意味がない。そこに生活するひとの移動
する道を考えないといけないし、サイン(標識)も考えないといけないし、街灯や公園だって
考えるだろう。それと同じで、駅なんだから、まずホームのデザインを考えて、電光掲示板
の位置を考えて、切符売り場の場所や、案内図の大きさを考えて、列車の到着をしらせるスピ
ーカーの音響も考えなきゃならないだろう。そして、今度は駅から周りの施設への移動や、駅
内部の施設へのホームからの移動を考える必要があるだろう。導線計画だ。地下に入ったなら
照明がいるだろう、エレベータや、エスカレータ、階段の数や配置だって重要だ。駅のなかで、
ご飯も食べたいし、キヨスクでコーヒーも買いたい....考え出せばいくらでもある。これらす
べてが、「駅」なのだ。
建築家によるコンペで、駅ビルの設計は決まった。そこに駅をトータルとして提案した事例は
果たしてあったんだろうか?もし、そこになくても、トータルデザインを先導する「場」があ
ればせめて結果は変わっていたように思う。実際の都市計画と違って、駅の事業は鉄道会社が
ただ一人で実権を握っているのだから、やろうと思えばできたはずなのだ。
できた例がある。わざわざ特集に乗っているフランスの例(これがまた良いのです!)を持ち
ださなくても、すぐ近くにあった。「阪急梅田駅」である。ターミナル駅としての完成度は、
30年以上前の建築なのに、現在と比べても他に例がないほど高く、京都駅など足元にも及ば
ない(とわたしは思っている)。周囲への人の流れの誘導(3つの改札)、公共の場所として
期待されるダイナミクス(非常に高い天井、二階中央口の大階段)、他交通との連動(JR、
地下鉄)、他施設との相乗効果(百貨店、地下街)、どれをとっても、駅に求められるものを
そなえて、かつ都市として成り立っている。くわしく調べたわけではないが、列車の発着時刻
さえも、駅と連動して考えられているのではないかと思える。表層的なデザインという点では
確かに古さが目立ってきてはいるが、それは些細なこと。駅を都市と同じと考えるならば、そ
の評価基準は「そこにいることが心地よいか」であるべきだ。
わが町京都の駅はもう仕方がない。いま21世紀の新しい視点でリノベーションされた、
新しい「駅」を見てみたい。これが日本の公共デザインだ!と世界に胸をはれるような、デザ
インを目にしたい。特集を読みながら、考えたのはそんなこと。
今日の飲み物:冬らしくホットミルク。冬場はNCの練習前にスタバでよく飲む。
冬コミ作業進捗:
・既刊の誤字、脱字を校正し、第二版を作成する。面付けをしなおさないとならない。
・新刊のレイアウトまでやりたかったのだが、久しぶりの作業で予定の半分もできなかった。
・撮り下ろしの写真、今日は建物の休館日のため、またも延期。明日こそは。
・文字数検討、ひとつあたり600〜700字。既刊は1000字くらい書いていたから、
そんなに苦ではないはず。たぶん。まず、本文を先に書いてしまわないと。
・きょう、作業中にはやくもくじけかける。あぶないあぶない。だから、ホットミルクで
気持ちを落ち着かせたのだ。
おやすみなさい。
- 2005/12/4(日)
夜、街を歩いていると、クリスマスシーズンの電飾がそこかしこに見つけられるけれども、
今年、いや去年くらいからか?ある特徴が目立つようになってきた。白色LEDと青色LED
の多用である。かつては、技術上の問題で存在しえなかったものが、量産されるようになって
市場にあふれ出してきた。
電飾の主催者の意思というよりも、それを請け負う業者からのプレゼンという形で増えたので
はないかと思う。電飾が買い取りか、レンタルかはわからないが、すくなくとも単価という点
では従来の電球色に比べて高いはず。ただし、ランニングコスト安いはずなので、そこをアピ
ールしたのではないかと。主催者側はそれと、目新しさもあってのことではないかと。
で、なにが言いたいのかというと、あの白や青の光の電飾を見ても、ちっとも「きれいだな」
とか、「ああ、いいねぇ。HPで皆に教えたいな」とかそういう感情が沸いてこないのだ。
どんなにきれいに配置されていても、そこから発する「色味」自体のイメージをくつがえす
ことは難しい。白や青は、寒色なのだから、寒い夜空にクールさをかもし出せても、温かみ
をかもし出すことはできない。
電飾の明かり、かつての電球色のあかりは、闇を照らす灯火の象徴ではなかっただろうか。
落ち葉ひろいのあとの焚き火のように、身体をあたためるだけでなくて、ひととのふれあい
であるとか、おいしい焼き芋がたべられるとか、そういういろいろなものを想起させる。
たとえ、具体的に経験したことがなくても、遺伝子の記憶として残っているんじゃないだ
ろうか。そう思う。
寒い夜はやっぱり明るくて、あたたかい気持ちでいたい。
冬の星、全天でもっともあかるい星、シリウス。孤高に、白く輝く星が空にある。だから、
地上にはそんなにたくさんの白い光、青い光はいらないと思う。
冬コミ作業進捗。
・640MbyteのMOドライブ購入。MOはサイズが小さいので取り回しが便利だ。
・ラストの一枚の撮り下ろしが進まず。昨日、NC練習帰宅後に行くと、ライトアップ
が終了していた。今日、映画を見終わった後に行くと、ライトアップはされていたが、
肝心の「扉」が閉ざされていて、「絵」にならない。もっと早めの時間帯に行かないと
だめみたいだ。ふう、寒空に三脚かついで、走り回るのはしんどいデスよ。
・頭のなかで、各建築に対する「文章」を考える。いつも暗室を書くためにしているように。
おやすみなさい。
- 2005/12/3(土)
新刊の写真を撮りに行こうと思って、自転車で出かけた。四条大橋西詰にある目的地に
向かうには、四条通りを東進すればよいのだが、河原町から木屋町、大橋にいたる道は
歩道が狭く、祇園へ向かう人々が密集して行きかうので自転車では走りにくい。そこで
いったん御池通まで北上して、別の場所の写真を撮ってから鴨川河川敷に入り、そのま
ま南下することにした。京都の地理がわからない方にはちんぷんかんぷんだと思うが、
簡単に言うと、人通りの少ない道へ迂回しただけのこと。
失敗したァとすぐに気づいた。西岸の河川敷は自転車が走るようにできておらず、やた
ら石が埋め込まれていたり、土砂を固める基礎ブロックが露出していたりして、MTB
なんかでないとまともに走れないのだ。おりしも運悪く、つぶの大きな天気雨。北風と
来た。
風にあおられながら、逃げ場のない河川敷(御池から南は中州になっているため)をひ
たすら南下する。平面の多い道の両端を走りたいのだけれど、風に片手に傘の運転だと
鴨川に転落しかねない。えっちらおっちら、なんとか四条にたどりつく。ついたはいい
けれど、服はあちこち濡れているし、眼鏡は雨粒だらけだし、そのうえ、四条大橋にあ
がるには自転車を担いで、階段を上らないといけない。
風はびゅーびゅー、かさはあおられて閉じることもできない。だいいちこんな天気じゃ
ゆっくり構えて建築写真を撮るなんてことがままならない。ああ、サイアクやーと思っ
て自転車の向きをかえるため、振り返ったら、そこにそれはあった。

"somewhere over the rainbow way up high..."
虹だ...。それも、とびきり大きい。
まるで鴨川を渡るためにかけられたかのような。
ただ、息をのんでそのまま目が離せなかった。
こんなにきれいで、大きな虹をみたことがなかったからだ。
そして、そのあとはじめて、虹が消えていくのを見た。
ワイパーで円弧にそってふき取るように、左岸から消えていく。
アニメーションを見ているようだった。
気がつくと、そこに虹があったなんてまるでウソのように北の空に晴れ間がひろがっ
ていた。ほんの2、3分のできごとで、それは偶然のできごとだった。
でも、きょうここに写真を撮りに来たことも、自転車で迂回したことも、全部必然
だったんじゃないかって思えるくらい、虹の発生と消失はわたしに深く、静かで大
きな印象を残した。ただ、美しかった。一瞬であるがゆえに美しい。おおげさなこ
とをいえば、それは音楽だった。音のない音楽そのものだった。誰かに伝えたかった。
四条通りにあがると、雨はやんでいた。だから、写真を撮った。
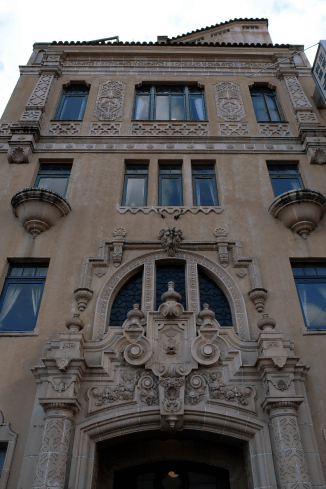
四条大橋西詰「東華菜館」。
きょうの写真はなんだか特別だ。たぶんね。
12月10日、伊丹アイフォニックホールで行われるハンドベルのコンサートにNCが
賛助出演する。そのラストで、ハンドベルと共演する曲が"Over the Rainbow"。あの虹
を見た今なら、その歌詞の意味をリアリティをもって感じることができる、そんな気が
している。
- 2005/12/2(金)
BK練習。演奏会の曲をざぁーっとやる。やや汗ばむくらい。本番の京都文化博物館
別館ホールはお客さんが本当に間近にいるので、なんど演奏しても緊張する。緊張す
ると楽譜を見ている余裕がない。だから暗譜でなければ、歌えない。いい顔をして歌
えない。今日はなるべく楽譜の持ち方、集中の仕方など、本番に近い状態に。テンシ
ョンもあげる。まだまだだけど、歌に力がでてきた。でも、立て続けは疲れたな。
みんなもそうだったんだろう。きょうの宴会では皆、黙々と食べていた。出された
品は5分とたたずに消費されるありさまで、飲みも少なかった。後半、久しぶりに
すこし日本酒が入ったくらい。とにかくよく食べた。
だから、帰ってから野菜ジュース(一日分)を飲んだ。
最近、すごくずぼらなことをしている。正直よくないなと思うのだが、8:30に遅れ
ずに出社するには、これしかない。朝、目が覚めるとベッドのわきにおいてあるフラン
スパンを手にとって、寝たままもぐもぐ食べるのだ。ね、すごく行儀が悪い。しばらく
すると血糖値があがってきて、ようやく起き上がれるようになる。で、顔を洗って、歯
をみがいて、着替えてでかける。朝、一連の流れのどこかでも時間をくってしまうと、
間に合わない。そのためには、食事の時間と、起きれずにぐたーっとしている時間を削
るしかないのだ。(いやまっとうな人間ならもっと早く起きるとか考えるだろう。)
ああ、本当はちゃんと朝はごはんを食べて、お茶を飲んで、ちゃんと目が覚めて、よし
今日もやるぞ!なんて、はつらつと出かけてみたいのだが、そう甘くはないのだなぁ。
FLEXなのに、8:30出社義務。やっぱりおかしい...。助けてほんとにって、毎日
思う。中高のころ、礼拝出席のために朝一番に学校に到着していた自分とは思えないな、
ほんとに。
あしたは、惰眠をむさぼります。
おやすみなさい。
- 2005/12/1(木)
乳白色が好き。
入浴剤の話しなのだ。透明のお湯に身体をつけていると全身が中に浮いているようで
なんだか落ち着かない。露天風呂であったりすると、つねに沸き立つ湯気で視界がお
おわれるからいいが、家庭の風呂となるとそんなわけにもいかない。
2回に1回の割合で、いつもと違う入浴剤に手を出してしまう。ドラッグストアにず
らっと並んだ数々の名湯、秘湯、薬湯を目の前にすると、いろいろと試したくなるの
は仕方がないじゃないか。で、結局、ああいつものが良かったなぁ、なんて後悔する
のだ。しっとりと、お肌に優しい、保湿成分の入った乳白色のやつに恋焦がれるのだ。
きのうも、そうやって失敗?した。同じように保湿成分の入ったやつで、同じシリー
ズのものを買った。お湯の色は白濁とあったから、色は同じはずだ。どういうふうに
違うのか興味があった。帰宅して湯をわかし、缶をあけると...あれ、青色??。
よくよーく読むと、湯の色は「ミルキーブルー(微白濁)」と書いてある。ミルキー
という部分と、白濁だけしか目に入ってなかったみたいだ。まぁ、「微」でもあった
らいいじゃないかと思って、とけゆく姿を見守っていた。しかし、なんと正確なのか、
それは本当に微白濁というか、判白濁というか、中途半端な青っぽい半透明のお湯と
なったのだった。
やや落胆しつつ入る。うむ?む?湯ざわりが変だ。かさつくお肌にとか書いてあるの
にちっともすべすべしないではないか。それどころか、みょうに「つっぱる」感じが
する。缶を取り出して見ると、肌にいい成分は確かに入っているのだが、同時に「お
肌引きしめ成分」なるものも入っていたのだ。この成分はわたしの肌には過剰に反応
したのか、それとも分量が多すぎたのか、とにかくぴちぴちして気持ち悪い。わたし
は「つっぱる」感じが大変苦手なのだ。服やYシャツで極端に相性が悪いときがある
のだけれど、そういうときはたいていどこかがつっぱっている。
しっとりしつつ、ぴちぴちというのがやはりよい。そういうのはもちもちというのか
な。なんのはなしか。そうそう入浴剤だった。
今日、もったいないなと思いつつ、使い切るまで、風呂に入るたびに不快になるのは
いやだったので、いつものやつを買いなおしにいった。余ったやつは誰か相性のよい
人に譲ろうなどと都合のいいことを考えながら。しかし、なんということか乳白色の
しっとりすべすべ入浴剤は売り切れ!よく見ると、きのうから売り切れていた。いつ
ものと思っていた(デザインがよく変わるので、また変わったと思っていた)のは隣
のスペースからはみ出した、同じシリーズの別のものだったのだ。
またも落胆しつつ帰路についた。
さいきん良いことがありませぬ。
冬コミ作業進捗あれこれ。
・写真セレクト完了。撮り下ろしも決定。
・判形決定。B6、24ページ。
・キンコーズでは部数がきついので、オフセットにする。
・必然的に締め切りが厳しいことに。
・でも、作業はキンコーズで。お世話になります。
・640MのMOはやっぱり便利だ。自宅用に買おうかな。
・がんばろう。がんばろう。手をゆるめたら、くじけてしまう。
おやすみなさい。
- 2005/11/30(水)

「ペンダント」(1/6sec,F2.4,ISO64、ノートリミング)
冬コミ新刊の計画を立てよう。わたしのサークル参加日は12月30日。残り約1ヶ月。
出発は一日目の29日。28日まで仕事だから、準備があわただしい。だから、12月第
4週末には完成していなければならない。
第1週、写真セレクト。判形、レイアウト原案決め。といっても、金、土は事実上動けな
い。足らない写真の撮りおろしは土昼、日曜日にまとめてするしかないだろう。今回は文
章は縦書きにしたいと思っている。フォトショップで縦書きレイアウトはできないことは
ないだろうが、できればページメーカーを使いたい。しかし、いまから基本操作をキンコ
ーズで習得していたら間に合わないか?あした、ためしにやってみよう。
第2週〜第3週、写真レイアウト、文章レイアウト。実質はこの2週間が勝負だ。
写真はストックがあるが、文章のストックはない。セレクトした写真ごとの解説兼心象
描写を同時並行で考えていかないといけない。前半で文章は固めないといけないだろう。
第4週、仕上げ。前半には入稿しないといけない。必然的にぎりぎりまで作業できるキン
コーズ印刷になりそうだ。判形を絞って、なんとかコストを抑えないと、既刊の増刷がで
きない。(既刊はオフセットにする。)
それで、12月23日のぶどうの樹の演奏会には完成させておきたいな、と思う。
がんばれ山D。くじけるな山D。
いまから励ましておこう。
- 2005/11/29(火)
創立記念日、母校の。だからといって休みではないのだな。ざんねんである。
8:30出社で3.5hの残業はしんどい。"コンクールの帳尻あわせ"だから仕方ないけど。
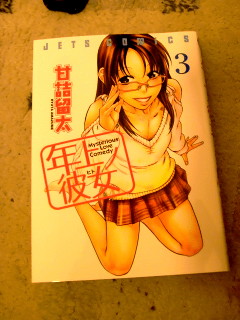
買ってきた。(本文中では眼鏡かけてません。)
読んでから寝る。きょうはちゃんとはやめにねむるのだ。
みぎのわき腹が痛い。野菜が足りないのだと思う。
おやすみなさい。
- 2005/11/28(月)
12月の中ごろに居室が移動になるため、先週末は部署全員で大掃除をしていた。その
途中で、なんだこれはというものを見つけてしまった。誰も興味がなさそうだったた
ので、わたしが勝手に譲り受けることにした。わたしもはじめは小型の半田ごてかな
にかと勘違いして捨てそうになるところだったのだ。あぶない、あぶない。
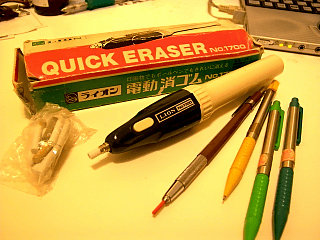
じゃーン!これぞ電動消しゴム。
いやぁ、実物を見るのははじめて。一見、細身のフェイザー銃(スタートレック世界
の光線銃)。本体の中に単三電池を二本入れる。先端にアタッチメントで取り替えら
れる円筒型の消しゴムが差し込まれており、ボタンを押すと回転する仕組み。
今日、早速電池を入れて使ってみた。なにせ印刷物でもボールペンでもきれいにきえ
るとの謳い文句である。さぞや劇的に消えるに違いない。ノートにシャーペンで落書
きをしてから消し消し作業に入った...。ボタンを押すとギュルルーンとたのもしい
振動音。さて、ノートに触れるぞ....きゅうーん、音を立ててとまってしまった。
接地したときの摩擦だけでモーターが回転力を失ってしまうほど非力なのだ。かな
りがっかりした。
よくよく考えてみれば、このサイズで、単三二本だからトルクはそれほど高くはな
いのはわかりきっている。しかし、こんなので実用になったんだろうか?残ってい
た消しゴムを見ると、そこそこ使っていたような跡があるのになぁ。そう思って、
いろいろ試していて、だんだんコツがつかめてきた。押し当てて、広範囲を消すよ
うな使い方は使用範囲外のようだ。鉛筆のようにもって、消しゴムの淵があたるよ
うに斜めに傾けてやる。そして回転させつつ、表面を這わせるように線にそって、
こすっていく。おお、ちゃんと消える。
そう、これはあくまで特定用途の事務機器だったのだ。うちの会社の仕事を考えれ
ば使い方も想像がついたはず。なにか?製図用だ。文字を消したりするのではなく
線を消すのが目的。それも狭い範囲を消すため。
半導体の回路設計はいまではワークステーション(技術者用のPCみたいなもの)
で行うが、昔はでっかい紙に手で書いていたのだ。テンプレートや定規を使って。
逆に言えば、手で書いて、信号を追うことができるほどの回路規模だったのだ。
電動消しゴムと一緒にでてきたのはカラーシャーペン。赤、黄、青、緑。信号の種
類(入力、出力、入出力)によって塗り分けるためのものだ。たぶん、設計者必携
アイテムだったんだろうな。実は、どれも紙にハンコを押したテープが巻かれてい
る。部長の名前だ。宴会のときにでも、どんなふうに使ってたか聞いてみようか。
さて、めずらしいものには違いないが、用途を考えると、いまでも建築なんかは
紙で図面をひくこともあるわけだし、さがせば「電動消しゴム」っていうのは見
つかるような気がする。さすがにこれほど古風ではないにせよ。ライオン事務器
はいまも現役のメーカー。サイトに行って調べてみよう。
電動で検索したが無し。消しゴムで検索すると普通のプラスチック消しゴムが出
てきた。うーん、やっぱり消滅してしまった商品なのか。ならば、仕方がない。
後世のために大事にとっておこう。(こうして山Dの部屋にまたいらないものが
ふえるのだった。)
22:30〜24:00、NC予算編成。
きょうは、きょうこそはゆっくり、早く寝ようって思っていたのに...。
少しだけ指揮者に不平を言う。しんどいときはしんどいということに決めた。
まぁ、ちょっと遠慮気味に。やや、譲歩してもらえたので、いっぽ前進。
しんどい。
かたこった。
ねむい。
きょうも同じこといってる。
おやすみなさい。
- 2005/11/27(日)
以前買った時計のバンドを変えてみた。

交換前。黒革。

交換後。こげ茶+ステッチ入り。
写真ではややわかりにくいかもしれないが、以前の黒バンドに比べて、時計の「顔」が
きれいに浮かび上がってきたように思う。盤面が鏡面仕上げのため非常に明るく、そこ
に黒バンドであったため、両者のコントラストが高くなり、盤面とバンドの両方が同等
に目を引いてしまう状態で、結果として盤面の印象が弱くなってしまっていた。また、
黒はどうしてもドレッシーな印象を与えるため、カジュアルな服装では着用しづらい
雰囲気になっていた。
黒からこげ茶に替えることで、両者のバランスがとれ、カジュアルのみならず、背広
などの着ているときでも違和感なくつけられるようになった。ほんの少しの色の差で、
その時計が活かされるということの好例だと思う。これがまた、ステッチのありなし
でもインパクトは大きく変わる。交換料1000円。ちなみに「お得意さん」価格な
ので、普通にバンドだけ買うなら、3000〜20000円とピンキリ。
新品の時計だと時計にあわせたバンドが、というよりもバンドを含めてひとつの時計な
ので、こんなことは考える必要はないのだが、アンティークの時計の場合はどうしても
オリジナルのバンドが残っているケースは少ないし、場合によっては本体のみで取引さ
れることもある。だから、時計屋さんが適当にバンドをあてがうケースが多いのだ。こ
うやって、色の組み合わせや革の種類を考えるのもアンティーク時計の楽しみのひとつ
つである。
あ、べつに現行品でもバンドを替えるのはありなので、ちょっと飽きたナァとか、新し
いの買うのは無理...というときは試して下さい。そのとき、注意したほうがいいのは、
色や革を選ぶときはなるべく腕につけた状態で比較したほうが良いということ。はずし
た状態とつけた状態では、これまたまったく印象が違ってしまうので。金属←→革とい
うのもなかなか面白いもの。
*****
本日のスケジュール表
NCマネージ@自宅、14:00〜16:30。
NCマネ会@同志社寒梅館。総勢9人が集結。
第一部、2006年予算編成、17:00〜19:00。
第二部、演奏会予算編成、19:00〜20:15。
第三部、情宣計画他検討、20:15〜22:00。
第四部、楽譜音源他準備、22:00〜22:45。
おなかすいた。
あたまいたい。
かたこった。
ねむい。
おやすみなさい。
- 2005/11/26(土)
NC練習17:00〜21:00。
指揮者のいない日。3人の副指揮者によるリレー練習。21:00には撤収完了。
NC宴会に出て、12時過ぎに帰宅。風呂に入って、録画していたスタートレックボイジャー
を見て、さらにその裏で録画していたERIXを見る。土曜日の夜のパターンだ。ただ、
重厚なドラマの世界にこころを置くことで、限りなく普段の自分の生活や思い煩いが姿を
消してゆく。星のない宇宙のような、無に近づいていく思いがする。
きのう、仕事をしていてふと思ったことがある。人間というのは連続なのだろうか。非連続
なのだろうか。というのも、1ヶ月半ほど都合でとめていたプログラムを再開するにあたっ
て、書きかけのソースとそのときのノートを見ていたのだが、その時にいったい自分が何を
考えてこんなプログラムを書いたのかまったく理解できない箇所が多数でてきた。ノートを
見ても、「○○は××のチェックが必要」と書いてあるだけで、必要な理由が書いていない。
手をつけようにも、どこを端緒にすればよいのか。かつての思考プロセスを無視すると、一
から作り直すことになりかねないし、ほとほと困って、そしていらついた。他人の考えてい
ることがわからなくて、理解できなくて、思い悩んだり、いらだったり、苦しんだりするこ
とはよくある。しかし、ことはほかならぬ自分のことだ。それも抽象的な思考ではなくて、
プログラムという、論理(ロジック)のカタマリが相手だというのに。
そのとき、一ヶ月前の自分と、いまの自分は果たして、時間軸でつながった連続した自分な
んだろうか?などと考えてしまった。逆に考えてみると、自分自身が連続していると保証す
るものは、自分の記憶しかないのではないだろうか。書き残したものからすら、理解ができ
ないのであれば、そうとしか思えない。
記憶力が衰えたとかそういうものではなくて、記憶が薄れている部分があるとすれば、それ
はそこで、自分の思考というものが、その時点から新しくなっているのではないか。常に
一定の単位で新しくなる思考が、前の思考を引き継いで、自分という人格は成り立っている、
そんな気がする。その思考がうまく引き継げなかったり、断絶が大きすぎると今回みたい
なことが起きる。その新しい「思考」はいったいどこからやってくるんだろうか...。
まぁ、苛立ちを紛らわすためのヨタ話なんですけど。でも自分のプログラムを読めなくなく
なるのはプログラムの世界ではよくあることなので、そんなときのために、自分の思考プロ
セスのエッセンスを、コメントとしてプログラムに埋め込んで置くというのは、ひとつの
テクニックであったりするのだ。前回はよほど余裕がなかったのか、コメントをほとんど
書いていなかった。ノートの一部には、「○○なんて、やってられるかボケ!」と雑務に
対する文句を書いている。この文句を書いたときの気分はちゃんと覚えている。
あなたは、きのうの自分といまの自分がつながっているっていえますか。
- 2005/11/25(金)
BK練習。演奏会に向けて、だんだんとねじをしめてゆく。音楽の骨格ができてゆく。
BK宴会。演奏会の演出、飾りつけについて皆で意見を交わす。これまでのぶどうで
は見られなかった光景。じぶんたちの演奏会なんだという実感がともなってきた。あと
は他のメンバーにもこれを伝播させていかないといけないなぁと思う。
気がつくと、日付が変わってわたしの誕生日は終わっていた。
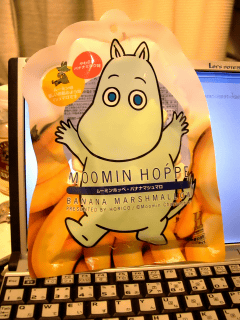
ムーミンホッペ・バナナマシュマロ
コンビニに売っていたので、ケーキの代わりに買って食べることにした。
ちなみにノンノンはイチゴ味。有名キャラクターを用いた商品としては、なかなか
パッケージデザインがグッド!なところにもひかれた。
(数分経過)
マシュマロってひとりでたくさん食べるもんじゃないナァ。後引いてきた...。
おやすみなさい。
- 2005/11/24(木)
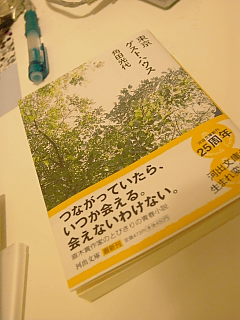
「東京ゲスト・ハウス」、角田光代著、河出文庫。450円。
きのう、買った本ではない。いつ買ったのか忘れたが、確か夕食をスパイス(カレー屋)で
食べたあとに、Book1stで買ったのだ。それだけは覚えている。ずっと、本屋の袋に格納さ
れたままになっていたのを、きょうたまたま発掘した。こういうことはよくある。
疲れたこころに角田光代。べつに癒してくれるというのではなくて、高すぎもせず、低すぎ
もしない文章が、すーっと拡散する胃薬のように頭の中に溶けていく。そのことが心地よい。
そしてじわじわしみこんでいくはずだ。その先にあるのが、よろこびでも悲しみでも、せつな
さでもかまわない。「つながっていたら、いつか会える。会えないわけない」これは本文の
引用なんだろうか。なんて希望にみちた言葉だろう。
すこしずつ読む。
そういえば、きょうはThanks giving dayではなかったか。中3のとき、はじめて礼拝に遅刻
したのが、この日だったような...。正直、何に感謝すればよいのかわからなかった。いまも
あまり変わらない。だから、こうやって毎日本が読めることに、よい本が収穫できたことに、
誰かとその楽しみを分かち合うことができること(ここを読んでくださった皆さんが、興味を
もって本を手にとってくだされば、それは果たされるはず)に感謝しようと思う。
- 2005/11/23(水)
久しぶりの何もない休日。自転車で恵文社一乗寺店へ。今のわたしには至福のとき。
くまなく店内を巡り、本を開き、本を閉じる。気がつくと一時間半がすぎていた。
いくつかの本と、ここ恵文社一乗寺店でひらかれていたサビニャック展のオリジナル
ポスターを買う。
たしか、去年もこの時期に来たのだと思う。あのときも今のように乾ききっていた
だろうか。それとも気力にあふれていただろうか。一年前のことなのに思い出せない。

「詩仙堂にて」(1/10sec,F2.4,ISO64、ノートリミング)
恵文社のほど近く、自転車で5分ほどゆくと、一乗寺下り松があり、そこを上ってゆ
くと、紅葉の名所、史跡「詩仙堂」がある。人は多いが、市街地からややはずれてい
ることもあって、嵐山方面のような人ごみではない。静けさが保たれたなか、ゆっく
りと紅葉の庭を回遊する。ここを訪れるのはやはり夕暮れ時が良いなぁ。庭に向かっ
てたつ建屋の座敷に正座して眺める紅葉もきれいだ。今年はやや正面の紅葉がくすん
で見えるのが残念だった。
北白川から、疎水沿いに今出川へ。百万遍から学園祭に沸く京大の横を抜け、近衛
通りの一本北の道を西へ。川端通りを下がってゆく。

「荒神橋にて」(1/250sec,F4.0,ISO64、ノートリミング)
BKの練習が鴨芹会館であるとき、荒神口で宴会をやることが多い。
だから、ここを訪れるのはいつも夜だ。昼間の景色がとても新鮮に映る。
(ずっと以前は日曜日の午前中も練習していたのだけれども)
河原町通りの一本東のわき道を下って丸太町へ。御所の南にある時計屋でしばし
歓談する。そういえば、秋〜冬になったのに、あまりアンティークの時計をつけ
ていなかった。

「うちのいぬ」(1/3sec,F2.4,ISO64、ノートリミング)
夕刻、新潟の土産を持って実家へ帰る。土産の柿の種は、大変好評であった。
しばし、いぬとあそぶ。
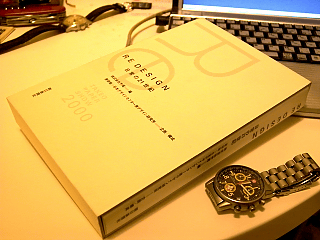
「RE DESIGN 日常の21世紀」
株式会社竹尾=編、
原研哉+日本デザインセンター原デザイン研究所=企画/構成、
朝日新聞社刊。3000円。
食事後、今日買ってきた本を読む。第1刷が2000年の本であるが、2005年の今になっても
まったく内容が古びていない。だからこそ、2005年に第6刷と重版を繰り返しているわけ
であるが。その内容は、日用品と呼ばれるものを「デザインしなおす」というもの。紙の
商社竹尾の100周年記念事業の一環として企画されたもので、いずれも「紙」と関係がある。
トイレットペーパー、祝儀袋、不祝儀袋、タックシール、ゆうぱっく、タバコ、名刺、
おむつetc.。なぜ、これらをデザインしなおさなければならないのだろうか。
それはこれら商品のなかに「デザイン」というものが完全に落とし込まれていないまま、
商業的な側面を強調されて「デザイン」されて日常化してしまっているからだ。前者の
デザインと後者のデザインが意味するところは違う。前者は概念であり、後者は単なる形
や輪郭でしかない。デザインとは何か?それは、企画を担当した原研哉の著書「デザイン
のデザイン」(岩波書店刊。以前紹介済み)をぜひお読みいただきたいと思う。概念であり
ながら「リデザイン」されることで具現化された日用品は、一見するとおしゃれで、スタイ
リッシュな「輪郭」に見えるかもしれないが、そこには見た目の美しさ以上に五感を刺激す
るような「何か」を感じることができると思う。展覧会そのものは世界を巡回中と聞く。是
非この眼で見たことで感じたそれを、手にとって感じてみたいものだ。
もうひとつ重要な側面として、それら商品が紙と関係しているということがある。このこと
に関しては、本文前書きの原研哉の言葉を引用しておきたい。
「紙は情報をのせて運ぶメディアであるだけでなく、ひとの感覚をうるおす素材」なのであ
る。原研哉は”ペーパーレスという言葉こそ20世紀に置いてくるべきである”ともいって
いる。展覧会の記録が、このような本という体裁をとっていることは、それらの主張と無関
係ではないだろう。DVDによる商品画像や、インタビュー映像という形式をとっても良か
ったはずである。そういった先端メディアによる記録こそ、21世紀の「デザイン」にはふ
さわしいような気さえする。でも、それは錯覚なのだ。手で触れて、感じるということの意
味を考え直す、「RE THINK」の時代が21世紀なのだろうと、本を手をとりながら「感じた」。
こういう休日のすごし方を久しく忘れていた...
- 2005/11/22(火)
砂漠の鯖作戦報告書。
<概要>
砂漠の鯖作戦について、記憶が薄れてしまうまえに書き残しておきたい。この作戦は普段
の練習に比べて格段に人数が増えるコンクール前日、当日練習において、どうしても名前
も顔も知らない人が増えてしまう事態が音楽に及ぼす影響、個人のモチベーションの低下
を懸念して立案された。
その方法は単純で、「名札による個人特定」である。相手の名前がわからないとき、それ
をたずねることから、コミニュケーションは始まるが、80人もの人間がそこからはじめ
ていては、とうていコンクール練習の期間中には間に合わない。名前に付随する情報は実
はメーリスなどでの発言や、先輩後輩からの情報でわかる。ならばあとは顔と名前が一致
すれば格段に個人の認識度はあがり、御互いの理解を得やすい。
名札といっても、IDカードのようなものはまず役に立たない。目にとまらないからだ。
だから、大きさはたて15cm,よこ20cmとした。名札としてはありえないサイズだが、だか
らこそ、名札本来の役割である「名前を知らしめること」を強調できる。これは大学グリ
ー時代の名札の大きさがそうであったからでもある。
<作り方>
1、80cm×55cmのボール紙を14枚用意する。
2、長辺を4つにくぎり、20cm×30cmの四角を4つ線引きする。
3、のこり25cm×80cmの長方形に20cm×30cmの四角を各短辺側からひと
つずつ線引きする。これで1枚の用紙から6つの台紙がとれる。
4、線にそって、はさみで切り離す。14×6=84枚の台紙ができる。
5、20cm×30cmの台紙の、長辺半分、つまり15cmの位置に裏面からカッター
で線を入れる。
6、線にそって、裏面から表面にむかって半分に折り、折り目をつける。折り目がついた
ところで、裏面が内側になるように逆に折り込む。こうするときれいに半分に折るこ
とができる。
7、かみひもを用意し(ひと巻き70m)、1mずつに切り離していく。84台紙分なの
で、ふた巻き必要。
8、1m長のかみひもの両端を手でほどき(こより状になっている)、平らにひろげる。
9、ふたつ折にした台紙の4隅と、上辺の中央の計5箇所をホッチキスで綴じる。その際
上辺の2端に、かみひもの左右それぞれを挟み込み一緒に綴じる。これで完成。
<反省点>
・首にかける方式を採用したが、かみひもと名札部の接合がホッチキスであったことから
強度上の問題があり、80弱を運搬中にひも同士の絡まりなどによって外れるもの多数。
・サンプルをつくり、何人かで分担するか、水平分業(製図、切り離し、降り、ほどき、
とめ、名前書き)にするべきであった。一人でやるにはあまりにも作業量が多すぎた。
結局、名前書きは個人に任せることになった。
<解決と応用>
・破損品は、バビリ用に用意していたビニールテープでかみひもを台紙に貼り付けること
で修理できた。はじめからテープ留めにすれば、作業の複雑さを減らすことができたと
そのとき気づく。ばかだなぁ。
・また、くびかけ式ではなく、ビニールテープと安全ピンを組み合わせたものを台紙の上
方部に貼り付ける方式の方が、やはり作業は楽であったと思う。これは現状のものから
ひもを取ってしまえば改造、あるいは併用可なので、個人にまかせたい。
・台紙には、パート、名前、なにわコラリアーズの文字を書いてもらうことを想定してい
た。リバーシブルに使えるので、所属団体が複数ある場合は、両面を使ってもらえばよ
いと考えていた。しかし、実際には利用者のほうが、応用に長けていた。複数団体を同
時に書くことで、個人のステータスを表すことができるのだ。学生合唱団所属のものな
ら、その名前となにコラの名前を書いておけば、「学生」である情報をえることができ
る。出身団体まで書くとさすがに見た目がうるさいかもしれないが、それが会話の糸口
にもなる。パート上下を記す者もいた。指揮者の案は、裏面には特技や、星座を書くと
いうもの。なるほど、履歴書みたいなものだ。
<結果>
名札があったことによって、何か良かったことがあったという話は誰からも聞かない。
ひとり、途中会計を委託したF栄からは、集金に役に立ったという話を聞いたが、はた
して、それ以外に皆のためになったのか、なにコラの音楽のためになったのか、はわか
らない。結局その程度のものだ。マネージャーはマネージに対して、見返りを求めては
いけない。(名札だけつくってたわけじゃないデスヨ!)
以上、報告終わり。
ML上で、すでに熊本に向けてのマネージ活動、選曲活動が開始されている。
確かに、わたしはきのう、反省と次回に対する抱負のようなことを書いた。
前向きであるべきだと思う。
しかし、この数ヶ月、いやこの一年のNCの音楽とマネージで、わたしはずいぶんと
疲弊し、擦り切れてしまった。一番つらくて、でもそれを隠して、いや根性でなんと
かしてみせている指揮者や、新潟統括マネージャーに比べれば、たいしたことをして
いるわけではないが、他人との比較をしてもはじまらない。わたし自身にいまは、気
力がない。なんの安らぎもないところから、もう一度立ち上がっていくには、時間が
必要なのだ。長い時間が。「弱音を吐くな、社会と戦え」と宴会の締めに指揮者は言
った。
そうありたいのだけれど、いまは無理だ。
もうしんどい。
- 2005/11/21(月)
Ensemble Vine、一般A部門、金賞受賞おめでとう。
なにわコラリアーズ、一般B部門、金賞、新潟県知事賞、受賞。
淀川混声合唱団、一般B部門、銀賞受賞。
マネージャー全員がそれぞれの役目を果たして、なんとか新潟遠征は無事に終了した。
マネミスをして、Hさんに迷惑をかけてしまったことだけが非常に心残りで、申し訳
なかった。指揮者が指揮に、歌い手が歌に専念できるマネージをもっと考えておくべ
きだった。自分に余裕がなかったな。次回はちゃんとしたマネ会をやろう。
NCもYKも歌に後悔はない。
16:30帰宅。コンビニで売っている一番高いユンケルを買ってきた。
今日はとりあえずこれで休む。
- 2005/11/20(日)
全日本合唱コンクール全国大会@新潟、第二日目職場、一般B。
なにわコラリアーズで出場。
淀川混声合唱団で出場。
- 2005/11/19(土)
全日本合唱コンクール全国大会@新潟、第一日目大学、一般A。
Ensemble Vineを応援。
NC練習。
YK練習。
- 2005/11/18(金)
NCマネージ@自宅、19:00〜20:30。
BK練習、20:50〜21:00。
NCマネージ@キンコーズ、21:30〜22:30。
NCマネージ@自宅、23:30〜26:00。
スケジュール表みたい。やっぱりなにごとも、ぎりぎりだ。
いよいよ明日は、全日本合唱コンクール@新潟。
みんな一緒に力を尽くして。
関西のときと同じ言葉を記す。
この二日間、新潟がそうでありますように。
NCとYKと、VNの歌のあるところが、そうでありますように。
"ubi caritas et amor."
26:00、風呂に入る。
26:30、靴をみがく。
27:00、就寝。
おやすみなさい。
いってきます。
- 2005/11/17(木)
現在、砂漠の鯖作戦遂行中。
製図は得意。
じつは胃が痛い。ストレスがここに来てピークに達してしまったのもあるだろうし、今日
の仕事で、どうあっても原因がわからないデータベースのエラーに遭遇してしまい、解決
に4時間くらい費やしてしまったことがトリガーになったみたいだ。それに今日はやたら
電話が多かったので、いらいらに拍車をかけてしまった。こういうときはおもいっきり笑
ったりすると治るのだろうなぁ。むかしのように深夜ラジオを聞いて、ちっそくするほど
笑ってみたい。うわべだけでなくて、本心からにっこりしていたい。
新潟へきょう出発するひと、気をつけて。千円札と小銭はもちましたか。みかんと柿の
種と飲み物を忘れずに。のど、足、腰冷やさぬよう。土曜日、元気な笑顔で会いましょう。
いってらっしゃい。
いよいよ新潟まで一日。
- 2005/11/16(水)
あまりにも寒いので、靴磨きを買うつもりでよった高島屋で、冬服を買ってしまった。
靴を買う金はないといいながら、この体たらく。一貫性のない行動である。とはいって
も靴は一応はけるものがあるのに対して、冷静に考えると寒冷地仕様の服の準備がまっ
たくなかったのは事実なので、まあ許してください。
紳士服売り場を一回りして、結局もとのところに戻ってきた。"HenryCotton's"という
ブランドである。わたしの服はここのものが多い。ややお高いのであるが、ブランド名
の通り、オールコットンの服は肌触りがよくて好きなのだ。洗濯してもかたくずれしな
い仕立てのよさや、明るい色合いと、いろんな服に合わせられる落ち着きが同居したデ
ザインも好き。こういう服ははPapasと同じで10年20年経っても着ることができる
のだ。長い目でみれば高くない(ただし、Papasはすごく高いのでほとんど買えない)。
と、じぶんを納得させる工程が必要。
そういえば、まえにもここで寒冷地仕様の服を買ったのだ。札幌のコンクール前だった。
そして、あのときも今日と同じように店員さんと合唱の話をしたことをおぼえている。
以前の店員さんとは違って、きょうの店員さん(ふたり)のうち一人はするどいヒトで
あった。新潟で合唱コンクールがあるので...と話していると、「男声合唱ですか?」
と聞いてきた。驚きだった。ふつう、合唱のはなしを初対面のひとにすると、「ああ、
ソプラノとか、アルトとかの...」や、「第九の...」という反応がかえってくるはずな
のに。男声合唱というものがあること自体、認識しているひとは少ないというのに。
一瞬、なにコラのことをしっているのか?と思ったのだが、聞き返すと「男声合唱をさ
れているというイメージがしました」との答え。うーん、どんなイメージなんだろうか。
それほどまでに『女性の気配のなさ』がにじみ出ているということなんだろうか。おど
ろきと、悲しさの入り混じった気持ち。いや店員さんは悪くない。その眼力で服を選ら
んで薦めるのが商売なんやから。
結局、綿シャツの上に着る薄手のウール100%のセーターを買った。さわさわしてみて、
ひじょうによい心地。あったかい。あったかいのは好きですよ(しまったまた同じこと
を書いてしまった。)
やわやわのセーターの着心地に気持ちを隠して、帰宅した。
あ、いや、正確には靴磨きを買って、スタンドでご飯を食べてから帰った。
帰宅後NCマネージ。秘匿作戦"Operation Desert Mackerel"(砂漠の鯖作戦)発動。
計画立案、山D。実行部隊、山D(単独任務)。
- 2005/11/15(火)

1/20sec,F2.4,ISO64、ノートリミング
靴というものにあまり執着しないたちである。厳密に言うと、時計のようにあれもいいな
これもいいな、と迷わない。一足気に入りのやつがあればいいなという程度である。社会
人ならば、最低3足、色違い、形状違いの革靴をそろえるべきという指南はよく聞くこと
であるが、初期投資が高いのでなかなか気がすすむものではない。だいたい営業職や外回
りの業務ならば、「見られる」ことを常に意識しないといけないのでそういった忠言もわ
かるのだが、こと開発職となると、革靴は通勤時のみで、職場では上履きが原則である。
通勤時も背広ではない人が多いから、お手本となるようなびしっと決めたひともいない。
しかし、通勤靴とステージ靴を兼用させるのはさすがにちょっと無理になってきた。くた
びれ度合いがよくわかるのだ。新潟までに新調するような余裕はないので、この件はつぎ
の機会にするとして、この週末はなんとか靴をぴかぴかに磨いて臨みたいなと思っている。
帰宅後、NCマネージいろいろ。新潟でのコミュニケーションを円滑にするため、小道具
を用意することにした。材料を買い込む。間に合うかナァ。
22:00〜22:15、NC京都補習参加。というか、ステージオーダーを指揮者にわ
たしにいくのが主目的だった。本日また1人参加不可。全82+1人。5列オーダー。
きょうは短い参加だったものの、5日連続はしんどい。
疲れた。毎日疲れた疲れた、いってますな。
新潟終わったら、この疲れも癒されるんやろか...?
おやすみなさい。
- 2005/11/14(月)
体中が痛くてあまり眠れなかった様子。無理な力がかかったまま歌ってる証拠だなぁ。
NC大阪補習、19:00〜21:00。
参加11人。バリトン下以外はそろう。
このメンバーでの手ごたえをなんとかつかむ。(ようやく)
帰宅後、BKマネージ少々。NCマネージ多々。
しまった、また寝不足だ...。
帰りの電車できょうの新聞を読んでいると、ピーター・ドラッカー氏が11日に亡くなった
との記事が載っていた。「巨星堕つ」、という言葉が頭に浮かんだ。
ドラッカー氏は経済学の父として知られるが、その論はひろく社会、産業のあり方、もっと
ミニマムで身近な、「仕事とは何か、なんのために働くべきか」というべき、根源的な哲学
にまでおよんでいた。
というものの、わたしは氏の著作を直接読んだことはない。あるのはダイヤモンド誌に掲載
されている「3分間ドラッカー」という連載記事における冒頭わずか20字程度の引用にすぎ
ない。しかし、この20文字の引用のなかに、経済のあり方、社会のあり方、個人のあり方の
すべてが詰まっていると感じる。
わかりやすい、という言い方は適切ではないかもしれないが、平易で適切な言葉の組み合わ
せだけで、全体をしっかりと見通す論がそこには構築されていた。経済を一面的、即物的な
面で論じた凡百のビジネス書よりも、毎週読むその20字の方がはるかに社会人としてのマイ
ンドに働きかけるものがあったと思う。そして、それはあらゆることのきっかけを与えるも
ので、決してこういうときには、こうせよという矮小なハウツーではなかった。そこから、
なにかをくみとるのは読んだ人間に託されているかのようだった。
経済関係者だけが、その死を悼むべきではないと思う。
こんなお手軽読者ではあるが、感謝と祈りを。
- 2005/11/13(日)
YK練習、13:00〜17:45。
NC練習、18:00〜21:00。
午前中、NC新潟関係の状況に変更があったため、キンコーズによって宿泊費ほかの修正
をしてから練習へ。帰宅後、状況がさらに2回変更。本日の練習で得られた情報が明日の
午前中に出る予定になっている。やはり当日まで確定は無理か。
行きの阪急で指揮者と会う。自由曲のパート構造を確認し、ベース上下への練習方法を指
示される。別件の用事があるため、指揮者は茨木で降りた。烏丸で見かけて、降りるまで
ずっと楽譜をみて研究していた。そういう人なのだ。
YKは全体として、音楽がいい方向へぱっと変わるのを実感できる、とてもいい雰囲気の
練習ができたと思う。新潟直前の仕上げでそういう音楽ができたことが、すなおに嬉しか
った。
NCは...やっぱり83人(本日時点)全員がそろう当日(前日でもそろわない)でないと、
どういう状況になるのか予測がつかない。
わたしはやはり、プレッシャーに弱い。落ち着いて歌おうとすると、どこかがスコーンと
抜けることがあるし、集中しすぎると息があがる。きのう、今日と繰り返し練習の過程で
どういうバランスに精神状態をもっていくと、うまくいくのかを考えながら、パラメータ
を微調整しつつ歌ってみた。こればっかりは人に頼れない。ここまで微調整を綿密に考え
たのは今回のコンクールがはじめてかもしれない。
とても疲れた。
あしたも補習。歌えるのか。
そのまえに、明日起きる自信がない。
おやすみなさい。
- 2005/11/12(土)
NC新潟参加者の宿泊費、弁当代などの計算をする。通常こういうものは全員同じ料金に
なるか、社会人と学生の2種類だと思うのだけれど、NCの場合パターンが40種類もあ
ることがわかった。これに交通費が含まれていたらと考えるとおそろしい。何がおそろし
いって、集金がですよ。40種類でも十分おそろしいけれど。たしか、去年は26種類く
らいだったのになぁ。
NC新潟のオーダーを考える。オーダーシートを作るだけで疲れてしまったので、途中で
やめる。○を80コ、扇形に書くのは以外と難しい。だいたい、きょうの練習でも40人
いくかいかないかなのに、オーダー作っても並べない。すべては前日、いや当日決まる。
きのうの速報で2人、きょうの練習中に1人、帰宅後1人、オンステできないことが判明
した。NCというか、社会人の男声合唱団の宿命を感じる...。いろいろ手を尽くした同期
もオンステ不可。残念だ。
気がつくと出発時間。キンコーズで印刷している暇はないな。
NC練習16:00〜21:00。
練習後、林号で送ってもらう。きょうちらっと楽譜を目にしたOver the rainbowを口ずさみ
ながら、窓の端に頭を寄せて真上の空を見ていた。木星?のような惑星と何か一等星が見え
ただけだった。もっと、たくさんの星空を眺めたいものだなと、ふと思った。どこか遠くへ。
それとも、どこか近くのプラネタリウムへか。新潟の空は星がきれいだろうか。
コンビニで弁当を買う。飲み物として、明治のカフェオレを探すが見つからない。つい、ひと
月前まであった場所にないのだ。これはここのコンビニに限ったことではなくて、ある商品
が気がつくとなくなっているということはよくあるし、レイアウトやその商品群そのものが
ごっそりと変わっていることがある。ほんとうの意味での定番商品しかコンビニでは生き残
れなくなってしまっている。そのノウハウによって、大手コンビニの売り上げは非常に高い。
しかし、これは消費者本位の行動ではないような気がする。
マイナーな商品に固定のファンがつくことはよくある。それが年月を重ねることで、隠れた
ロングセラーになったり、火がついて売り上げが伸びるということもあるはずだ。しかし、
現状のコンビニやり方では、あのお菓子今度食べてみよと思ったら、もう次はない。ファン
になる暇すらない。
コンビニに商品を供給している企業各社はコンビニの販売チャネルを失うと、売り上げを
維持できない。つまり、コンビニで売れなかった商品は生産を維持することができない可
能性がある。「コンビニで売れない」というのは、商品力が欠けているからだろうか?そ
もそも、「売れない」という事実は正しいのか?大多数に売れる商品だけが残るのが本当
に企業にとってよいことなのか。いろいろ考えをめぐらしていくと、控えめでも長く売れ
続ける、ロングライフな商品はコンビニからは実は生まれないのではないだろうか。いま、
コンビニある「定番」はコンビニ以前から存在するものが主流のような気がする。
明治のカフェオレ、ペットボトルのあたまからずぶっとストローを突き刺すスタイルが好
きだった。部屋に転がっているかなぁと思って調べたら、残していなかった。しまったな
ぁ。いつでも買えると思って油断していた。こんど見かけたら、ちゃんととっとこう。
(私は気に入ったデザインの缶だとかボトルをとりあえず収集するくせがあるのだ。)
あしたも半日練習だ。がんばろう。
ねむい。おやすみなさい。
- 2005/11/11(金)
BK練習。やまない雨。
BK宴会、きょうはなんだかよくしゃべった。いつもしゃべらないのに。
雨はやまなかった。だから、ひと気のない寺町と四条のアーケードを独りで歩いて帰った。
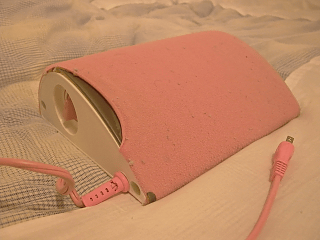
あなたのあたたかみを感じていたい...低温火傷するまで。という夢を見た(ウソ)
冬の必需品をいよいよ戦線(ふとん)に投入。それにしてもものごごろついてから、電気あ
んかを使い続けて、云十年。まだ、二代目。だいたいこの種の電化製品はこわれようがない
ので、買い替えのポイントは、表面の生地がはがれてしまったかどうか。そういう意味では
現行機もなかなか微妙な状態になってきた。10数年前は普通に売ってたけれど、あと数年
先、いやいま売ってるんだろうか...心配になってきた。
一度湯たんぽも使ってみたい。どちらがあしごごちがいいのであろうか。むふふ、想像する
と顔がゆるんできた。暑いのは苦手だが、あたたかいのは好きですよ?
ちょっと、自分でテンションをあげてみた。
おやすみなさい。
- 2005/11/10(木)
きのう紹介した「新東京ウォッチング」のなかに、世界の高層建築を同じ縮尺の絵で並べ
て描いた図を表示してくれるその名もスカイスクレイパーページドットコムのことが書か
れていた。http://skyscraperpage.com
グラフィックばかりなので、ちょっと遅いが暇つぶしに眺めるものとしては、非常に面白
いので、おすすめ。高さ順がデフォルトだが、フロア数、幅、年代、でもソートできる。
もちろん日本も網羅していて、我が京都のもっとも高い建物はやっぱり京都タワーだった。
実際に建築されたものだけでなく、構想として描かれたものもあり、1000m級のもの
なんか縮尺がおかしいのかと思う。一番興味ぶかいのはdestoryed、つまりとりこわされ
たもの。一番は645mもあったポーランドの通信アンテナ。こわされたものの上位はこう
いった通信系のものがほとんど。技術革新で高いアンテナが不要になってきたということ
なのだろうか?で、よく見るとそれらに混じって建物がある。911のWTCの2タワーだ。
まさしくスカイスクレイパーの代表的存在であったのに...。
このジャンル、日本に限定すると、浅草十二階と、なんと戦艦大和(263m)が出てきた。
縦にすると東京都庁よりも高いのだ。巨大さを実感できる気がする。
ひとつ不思議なのが、ここで表示される大変細密な絵は誰が書いているのか?どうやって
かいているのかということ。描いた人間の名前は書かれているが、日本の建物でもほとん
ど外国人である。日本にいても、これだけの絵をかくためには資料集めだけでも相当難儀
しそうだと思われるのに、いったいどうやって。もしかすると、建築の世界というものは
そういう資料を全世界にオープンにする窓口のようなものがあるのだろうか?コンペでも
なければ、そういうことはないような気もするのだけれど。
- 2005/11/09(水)
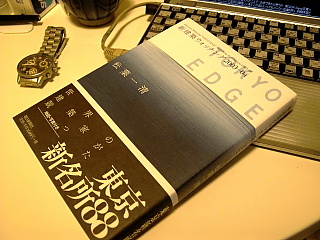
「新建築ウォッチング2003-2004 TOKYO EDGE」、松葉一清著、朝日新聞社刊。1600円。
日本近代建築の写真を撮り続けながら、東京を歩いていると、自然とそれよりも多くの現代
建築に出くわす。それら現代建築は、一面的な見方をすれば、近代建築を破壊したうえにな
り立つことが多いため、両者は相容れない存在であるといえる。しかし、現代のそれも21
世紀の建築を見つづけていると、人間が暮らす都市空間をいかに快適にするか?ということ
に対して、真摯に取り組まれているものが少なくない。そこに明治・大正・昭和が目指した
建築に対する思いと同様の、しかし冷静な熱を感じることもある。
そういうとき、自然と現代建築にもカメラを向けることがある。
そして、実はその写真だけで、新刊が一冊できるくらいの量になっている。
この本は、東京の汐留をはじめとする再開発ラッシュであった2003-2004年に竣工した現代
建築のガイドブックである。朝日新聞東京版に連載されていたものに加筆修正されている。
実際、私が東京で目にし、見るたびにカメラに収めてしまう汐留「電通本社ビル」を筆頭に
六本木ヒルズはもちろん、江の島展望灯台まで88の建築が紹介されている。
現代建築はその流麗な外観とはうらはらに、とかく、どれも同じに見える、あたたかみがな
い、無味乾燥といった批判的な言葉にさらされてきたように思う。実際、そのような建物も
少なくないし、それはほとんどの場合正しい。だが、しかし、見る者が真摯にそれを批評し
たことはこれまでなかったのではないだろうか。ただ、「批判」するだけでは何も変わらな
いのだ。無味乾燥でなくするには、無味乾燥でない現代建築は何が違うのか?そこのところ
を解き明かす丁寧な作業が必要となるはずだ。
著者である松葉一清は建築学科出身の建築評論家として、これまで近代建築から現代建築ま
で広く批評を行ってきた人物である。その文章はつねに高い批評性に溢れており、やみくも
に褒め上げたり、逆に無意味に貶めたり、けなしたりすることがない。しかし、どうか?と
思う建築のあり方にははっきりとモノを言う。それも読んでいて、不愉快のない物言いであ
るのが気持ちよい。実に大人な溜飲の下げ方をする。
普段、わたしは氏の文章には、かつて東京人で連載されていた巻頭言「東京発言」や、建築
特集の際に接しているが、今回のこの本に関しては、元が新聞連載ということもあり、語り
口はいくぶんおとなしいものになっていると感じた。1件2ページという紙数の制約も関係
しているだろう。しかし、リニューアルされた交詢社ビルディングのあり方については、そ
の批評性はぎゅっと凝縮され、本領発揮というべきものがあった。
ひとつひとつの建物の説明はみじかいものの、ガイドブックとしての役割以上の読後感を残
してくれると思う。
おまけ
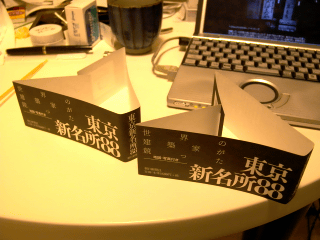
まったく同じ帯が、重ねて巻かれていた。
買うときも立ち読みしてるときもまったく気づかなかったし、レジでカバーつけてもらった
際もなんの違和感もなかったのになぁ。あした見たら4つになってたりしないだろうな。
- 2005/11/08(火)
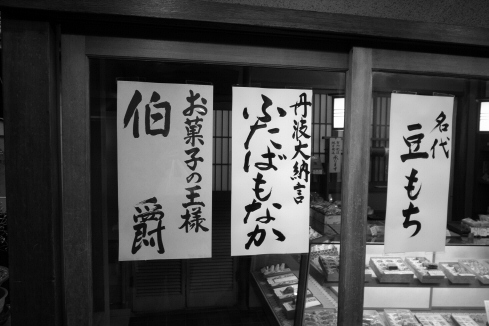
1/20sec,F2.4,ISO64、ノートリミング
掲載している写真の感じが変わったことで、おきづきかと思うが、実はGR Digitalを買っ
てしまった。ここに正式に報告。いまどこの店にいってもメーカー在庫切れ、納期未定と
いうとんでもない品薄状態なのに、なぜ予約もせずに堂々と買えてしまったのか。いや、
わたしもまさか買えるとは思わずに店に行ったのだ。可動見本に触れて、その指先の感触
だけでもう買わずにはいられなかったのだが、いろいろいじっていると、そーっと背後か
ら店員が忍び寄り(本当)、『いまなら一台だけありますヨ』と囁いたのである。
こういうのを悪魔のささやきというのか。実際に経験すると本当にそう思える。
店員が取り出してきたのは、まぎれもなくGR Digitalの箱(箱の外観は確認済みだった)
だったが、ひとつ違ったのはシールが貼ってあったことで、それが手に入れられた理由
でもあった。『予約特典SET』、それはGRD専用の皮製ケースが付いたもの。つまり、わ
たしが買ったGRDは、予約キャンセルで浮いたものだったのだ。それが10月29日のこと。
発売日が10月21日なので、1週間の取りおき期間がすぎた直後だったのかもしれない。
年末年始や、お盆のころになると、ニュースで「キャンセル待ちの客でいっぱいです」
などというセリフが聞こえるが、そんな不確定なものを待つなんて、とよく思っていた。
でも、ものは違えど、こうやってキャンセル品を買えたことを考えると、狙って待つと
いうのは、実は正しい選択のひとつなのだと理解できた。(今回は偶然だったけど)
しかし、正しくはあっても賭けには負けることもある。そして、わたしは賭け事に弱い
方なのだ。ずーっとほうっておいた新潟の宿泊を、今日やっと予約した。宿がいっぱい
になるときは、とことんいっぱいになるということを先日のM田さんの京都宿泊手配で
経験済みだからである。そして、念のため、年末の冬コミの宿も押さえた。こちらも、
何年か前に、油断していていつもの宿が満室になっていたことがあるのだ。
これでとりあえず、音楽以外の準備はできた。え、交通はどうしたかって?それだけは
誕生日割引航空券というのを先に押さえていた。誕生日に得られる唯一といっていい特
典を利用しない手はない。が、気づいたときは残席1だったので、じつはやばかった。
運があるのやら、ないのやら。紙一重のところを生きている私である。
(去年の松山でも利用すればよかったと、今年気づいた)
ちなみに帰りは新幹線。
はくたか+サンダーバードは、この時期たぶん車内が暑くて酔うから。
酔うか、酔わないかというのは重要な基準です。
- 2005/11/07(月)
冬コミ受かりました。12月30日(金)東6ホール、ヌ-14b、山Dの電波暗室です。
新刊は建築写真の京都編を予定。もちろん、予想を上回る反響であっという間に完売し
てしまった夏コミ既刊も増刷いたします。お手にとっていただけなかった皆様、その節
はご迷惑をおかけしました。ようやくお届けできます。m(_ _)m
...しかし、今回は夏コミに比べて、時間と精神的余裕がないのがネック。11月20日
コンクール全国大会(新潟)、12月23日BK演奏会、この2つの間になんとか原稿
作業をやらねばならないのである。忘れているわけではないが、仕事もあるのだった。
12月完了のが何件か。
でもがんばろう。そう、がんばろう。
(じぶんで自分を励ます)
*****
NC大阪補習。18:50〜21:00。
京都在住の私が、なぜか大阪補習をセッティング...。しかし、NCはもともと大阪の
団体ということで、大阪練習の需要は高く、11人が集合。皆で意見交換しながらの
練習は普段の練習では得られないものがあった。自分の弱点もよくわかった。実は同時
刻に京都補習もあった。ほかにも日時は違うが東京、札幌でも現地メンバーが集合して
の練習が行われていて、四都市開催という団体はほかにはないような気がする。なにも
指揮者が全国を飛び回っているのではなくて、各地で指揮・指導できる人が中心となっ
て自主的に開催しているのだ。こういうところ、NCのいいところだなと、自画自賛し
てみたくなる。
10時半帰宅。冬コミ当選封筒を受け取り、練習報告を書き、いまに至る。
風呂にはいって寝ます。明日から、細密スケジューリングせんならんなぁ。
- 2005/11/06(日)

「雨滴」
YK練習、13:00〜17:00。
行きの阪急のなかで、坂本真綾5thアルバム「夕凪LOOP」を繰り返し聞く。
冬、雨空。坂本真綾のうたには、そんな季節と天気がほんとうによくあっている、と思う。
それがどんなに明るい曲でも、あかるい日差しの差すうたであっても、それは冬の寒さや、
雨空のせつなさをしっているからこその深さがどこかにあるように感じる。飢餓的に求めて
いるというのではなくて、楽しいことも哀しいこともその身にしっかりうけとめて、ゆるが
ない。そういうこえだ。そのこえがつむぐ歌だからかもしれない。悲しいうたにもこの身を
つつむ優しさを感ずることができる。さびしくても大丈夫だと思うことができる。
7曲目の「月と走りながら」が好きなのですよ。
そういえば、きのう私は月と走っていたのだな。
- 2005/11/05(土)
三田市民合唱祭、NC招待演奏。11:15〜15:00。
同地にて、NC練習。15:00〜17:00。
いつも日がしずんだ直後の空を撮りたいとおもっていた。カーテンのすきまからもれで
るかのような光の線が刻一刻と減り、さーっとよるの闇がのしかかってくるとき、その
あいだに昼間でもない夜でもない不思議な空間ができる。光のような、闇のような、蒼
い空だ。
そんな空を見れるときは少ない。働いているときは、気がつくと日が暮れているし、合
唱の練習があるときは日が暮れるころに移動して、その瞬間はたぶん、ちょうど発声を
はじめたくらいだろうから。
だから、決まってそれをみるときは、NCの合宿帰りであったり、今回のような遠征の
帰りの林号の車窓なのだ。
山間の三田市内からは丹波の山々が見えた。薄くたなびいたくもが明るさを失って、夜
の色になっていく。今日は、それだけではなかった。明るい金星を支点として、ブラン
コで後ろに下がりきったかのような位置に、薄く細い下弦の月が見えた。いつまでも、
どこまでいっても、その関係は変わることなく、微動だにしなかった。蒼い空の金星と
月はどこまでも冷静に距離を保ったまま、お互いに美しいひかりを放ちあっていた。
すし詰めの車内で右を向いて、窓に顔をあててずっと眺めていた。この空を撮りたいと
思ったし、それを見せたいとも思ったのだけれど、揺れて高速で走る車内から、この光
の少なさではうまく撮れないことがわかっていた。できるならば、その場から降りて、
しっかり構えて、じっくり撮りたかった。でもまぁ、しかたがない。この目で見たのだ。
また違った場所、違った時間に、もっと違う空が見れる日があるだろう。
疲れているはずなのに、みょうに落ち着いて、さえた目のまま考えていた。
酔わないように、小倉マーガリンパンを食べるころには、いつのまにか金星と月は姿を
消していた。
酔わずに京都到着。よかった。
- 2005/11/04(金)
BK練習。仕事で墓穴を掘り、穴埋めに時間がかかったため、20:30到着。
ちょっとまえまでは、このくらいが標準に近かったことを考えると、
はじめ近くから練習にいけるってすごいことなのだ、と改めて思う。
BK宴会、YKのM田さん、きたる。帰り、宿までNaとともに送ってゆく。
道の説明、建物の説明、いつのまにか案内口調。そういえば、こうやって
逆に誰かにどこかを案内してもらったという記憶がないことに気づく。自分
の案内は、案内される側にとってどんなふうに聞こえるんだろうか。ちゃん
と案内になっているのか。想像できないので気になる。しかし、ひとつだけ
注意しないといけないことがわかった。徒歩の感覚がひとよりみじかく感じ
るので、「近いですよ」といってしまうと、客観的には遠いようなのだ。
富小路御池から地下鉄烏丸御池までは、少し遠いよねぇ。
京都市役所前から乗るようにすすめるべきだったなぁ...。
M田さんごめん。
- 2005/11/03(木)
NC練習、15:00〜21:00。
*sigh*...(スヌーピー漫画風に)
もういっかい壊れた。今日は自滅。
どうしよう。
けっきょく、自分しか信じられるものがないのか。
合唱なのに。
悩む。
- 2005/11/02(水)

1/6sec,F2.4,ISO64、ノートリミング

1/20sec,F2.4,ISO64、ノートリミング
with GR Digital.
no words.
what you see is everythig.
- 2005/11/01(火)
体調がもとに戻ってくると、部屋の掃除を始めたくなった。なにせ今年は初夏からずっと
合唱の行事が途切れることなく続いているため、ほとんど休日に部屋にいない。平日散ら
かしたものを休日に掃除しているので、結構すごいことになっていた。体調が悪くなると
もうやりたい放題。
てはじめにこれを調達。
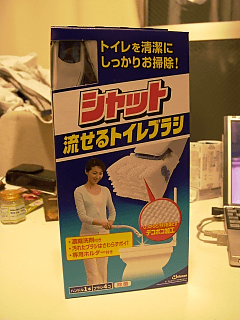
じゃーん!
わたしはTVを見るとき、CMというものをあまり情報源とか購買意欲をかきたてるため
のものとしてみていない節がある。番組と同じで、どちらかというと鑑賞してしまうのだ。
見せ方がどうだとか、面白いか面白くないか、かっこいいか、だめなのか、そういう観点
でながめてしまう。子供のころ、CM時間は目を休める時間、と親に言われたのだけれど
CMも等価値に見ていた記憶がある。CMあてクイズという遊びを編み出したこともある
くらいだ。
ところが、このトイレ掃除具はCMを見て、「これ欲しい!!」と初めて切実に思ったの
である。ここまでずびっときたことはない。なにせ、普段のトイレ掃除(トイレだけはすぐ
汚れるので、わりとまめにやっている)で、どうしても落ちない汚れは、トイレットペー
パーを割り箸でつまんで、それでごしごし洗っていたのだ。しかし、ペーパーはすぐにと
けるので、あまり持続力がないし、トイレの底には届かない。さて、どうしたものかと思
ったまま、汚れがたまっていたのだ。
それを見事に解決する商品だった。使い終わったら、手を汚さずにぽいっと捨てられるの
がとてもよい工夫。

この曲線があらゆる曲面にマッチ!
実際に使ってみよう。お、きゅきゅとこすっているうちに替えペーパーから青い洗剤がし
みだしてきた。この洗剤パワーもあって、いままでとれなかった水あかを、ごりごりはが
していけるではないか。おおー、しかも底まで、奥まで届く。くるくる回転させて、ふち
のあたりもしっかり磨ける。快調快調。なんだか、こうやっているとその形状からか、耳
かきで耳のあなをほじくっているように思えてくる。
いやーいい。もうぴっかぴか。ひさしぶりに気持ちよく掃除できた。山Dおすすめ商品。
しかし、欠点もある。ペーパーにしみこませている洗剤が強烈に洗剤くさい。有毒物質の
原液をしみこませたかのような臭いである。たぶんあまり吸い込まないほうがいい。なに
なに、原産国アメリカ?さもありなんというか。おおざっぱなパワーを感じる。
もうひとつは欠点というか弱点で、名前。「シャット 流せるトイレブラシ」。紙の箱を
みないと思い出せないくらい印象が弱い。メーカーは、ジョンソン。ふむ、つかいやすさ
やアイデアからして、花王あたりかと思ったのだけれど、外資系メーカーか。ネーミング
力がないのは仕方なし。小林製薬あたりなら、10年は忘れられない名前をつけただろう
に。
さて、掃除を終え、最後にタンクにおく洗浄剤兼芳香剤をつけかえる。ベース部から容器
部をはずしてあたらしいのをつける。そういえば、このまえ実家に帰ったとき、同じ芳香
剤をつかっているのを見つけたのであるが、なぜか容器部だけがタンクの上に置いてある
ではないか。これだと、なかの液体がどぼどぼでちゃうんじゃないのか・・・。
曰く「台座のとこのやつ、前のといっしょにすててしもたし。なくてもいっしょやろ。」
母はなんでも捨てるしな...と、つっこむのも忘れて、納得してしまったのだった。
- 2005/10/31(月)
「許可なく構内への立ち入りを厳禁とする 工場長」
という、珍妙な、しかし大きな看板が会社の通用門の脇に立っている。2年くらいまえか
らだろうか。この看板を目にするたび、ため息をつきたくなるのだが、毎日ため息をつく
わけにもいかないので、いまでは半ば無視している。
この看板の文言がどこかおかしい、ということは見ればわかるし、どのように直すのが適
切かということもわかる。しかし、そのおかしさの理屈を系統立てて、ひとに説明できる
かというと、どうもこれがしっくりくる説明ができそうにないので、そのことがずっとひ
っかかっていた。だいたい朝眠いといきか、疲れている帰り道に思い出すので、よけいと
考えがまとまらない。無視しているという割には、ずいぶんととげが深い。
ところが、きょうの帰り、唐突に気づいた。なんの前触れもなく。
「構内への立ち入り」という体言に対して、「許可なく」という副詞句がかかろうとして
いるからおかしいのだ、と。だから、副詞句を形容詞句に直すか、もしくは体言を動詞句
にかえてやれば、すっきりするはずなのだ。こうすればよい、と直感的にわかっているこ
とに対する説明がこれできっとついているはずだ。
「許可なく」→「無許可の」
→「無許可の構内への立ち入りを厳禁とする」
「立ち入り」→「立ち入る」
→「許可なく構内への立ち入ること」→「許可なく構内へ立ち入る」
→「許可なく構内へ立ち入ることを厳禁とする」(動詞句全体を体言化して「を」で受ける。)
どうだろう。まだ収まりが悪いが、どうしようもない原因はとりのぞけるように思う。
それにしても、いったいどうやって、誰がこの文章を考えたのだろうか。どうも、言葉
の使い方からすると、なんとなく威厳や威圧感がありそうな言葉として、漢文調の体言
どめを思いつき、ばらばらのそれを無理やりつないでみた、というようにしか思えない。
まさか、本当に工場長が書いたわけでもないだろうが、工場長だってこの看板を見ている
のに直させようともしないのは、書いた人と同じくらい言語センスがないからだろうか。
(言いすぎか?)
こういうどうしようもない文章を往来にさらして、恥ずかしいのは当の工場長ではなく、
社員たるわれわれなのだけどなぁ。しかし、身内から指摘しても直らないのがこういうも
のの常であろう。いままで指摘するひとがいなかったとも思えない。ならば、ここは大得
意先の社長さんや、取締役、監査の人など、外部の人から「変ですよね」といっていただ
けるのを待つしかないように思える。「外圧」というものに、日本的なもの(古い企業)
は弱いはずだろうから。
経営感覚だとか、技術のレベルでは太刀打ちできないような「偉い人」に対して、こと
言語に関してだけは、立ち会っていけるという過剰な自信がいまふつふつと沸いている。
その感情を発散させるために、この文章を書いているような気がする。過剰な自信は身を
滅ぼしかねないので、ガス抜きがいるのだ。
ひょっとして、会社に対して無形のストレスを感じているんだろうか?
- 2005/10/30(日)
YK練習。
アイコンタクト的な練習。昨日NCでもやったが、あちらはリズムをずらさないための
読唇術だった。今日は目で意思を共有したり、リードしたり、エネルギーを送ったりと、
語彙力のいるものだったのでやりがい(?)があった。しかし、目と目をあわすというの
は、女声がいると照れる。照れずにやっているように見えるのは、じつは照れ隠しであっ
て、本当になんでもないようにできてしまう人はじつはとてもキザか、鈍感なのかもしれ
ないなぁ、などとおもったりする。
- 2005/10/29(土)
NC練習。
あともう少し、「ねじ」が締められていたら、ちょっとあぶなかった。
リハビリというには、消耗しすぎたかもしれぬ。
まぁ、そんな時間はもうないのだから当然か。
本番までにもういっかい壊れないように注意しないとなぁ。
- 2005/10/28(金)
気分が悪くなったため、保健室、もとい健康管理室へ行く。ちょっと横にならせても
らおうと思ったのであるが、問診を受けないとだめらしい。厳しいのである。
まず、体温。35.9℃。平熱だ。さっきまでのあの熱いのはいずこへ。
つぎ、血圧。うえ、144。ウソだー。
もういっかい。155。ますますもって信用ならん。
デジタル体温計、デジタル血圧計。デジタル疑心暗鬼。
こう、水銀がするするーとあがっていったり、さがっていったり、聴診器で血流を聞い
たりっていうアナログな診察をしてほしい。病気のときは特にそうだ。デジタル測定さ
れていると、なにかリモートで操作されているような錯覚に陥る。手と手が確かにふれ
ていないと、相手の体温も脈拍もわからないじゃないか。
まぁ、それはともかく。問診のすえ、薬をもらう。先生、これは強烈に眠くなるやつな
んですけど、午後はずっと寝てていいってことなんでしょうか...。
30分だけ、寝かせてもらう。
すこし、よくなった。
BKへ行く。歌っていることで、からだのなかの毒が汗と一緒に出て行くような感じが
した。ちょっとしんどくても、練習にきてよかった。
- 2005/10/27(木)
最近、カルテになりつつある。
だるさは残るがかなり調子がよい。ただ、まだ仕事を集中してやるにはつらい感じ。
帰宅すると、ぐったり。仕事をしているときは多少なりとも気が張り詰めているか
らだろう。微熱ってどれくらいかと思い、熱を測ったら37.0度だった。微熱じゃな
いかも。
いつの間にか、発売になっていたGR DIGITAL。今月号のカメラ雑誌の記事ではとり
あげられてはいるものの、記事自体は発売前のものなので、あまりセンセーショル
な感じではなく、作例もぱっとしない。記事の主流は一眼デジカメのようで、やや
心配になっていた。
しかし、RICHO公式ページや、それに対するトラックバックをたどっていくと、発売
直後から、購入者の作例がどしどしあふれだしてきた。
すごくいいじゃないですか!
相手にする気があんまりない雑誌よりも、こうやって実際に使っている人たちの写真
の方がずっと参考になる。で、そのどれもがいい描写をしている。このカメラでしか、
GRでしか切り取れないであろう空間がみごとに映し出されている。この感覚はGR1
そのものだと思う。GRは正しく継承されたと言っていいんじゃないだろうか。
発表されている作品はどれも、デジカメで日常を写したというよりも、フィルムカメラ
で撮影するスタンスに近いものが多いように思う。これもまた、GRならではというべ
きだろうか。
とりあえず、公式ページからカタログを取り寄せる。PDFファイルで掲載されている
がやはり、印刷されたものを見てみたい。こうやって、じわじわと購買欲を盛り上げて
いくという意味もある。突発的に買って、自ら製品サイクルをみじかくするようなこと
はせずに、じわじわとゆっくりと、考えて、検討して、購買する層が増えるような気が
する。その昔、はじめてフィルムカメラを買ったときを思い出すように。
なお、カタログを店までとりに行かないのはもったいぶっているのではなくて、ちょっ
とそこまで、と出かけるのがつらいからなのだった...。
- 2005/10/26(水)
胃腸、やや復調。全体の体調悪し。微熱続く。
冬服だと熱がこもって気分が悪くなってきたので、夏服を着る。
やや異端な感じがただようが、頭がぼーっとしているので気にならない。
めんどくさくてほうっておいた、頭は使わないが面倒な部分のプログラムをする。
あたまは疲れなかったが、目が疲れた。失敗。
回復を祈願するため本屋におもむいたが、めまい。
症状にあっていなかったようだ。
「ぷーねこ」(北道正幸著、アフタヌーンKC)を買って帰る。
笑って、免疫力を高めるのだ。
「灼眼のシャナ0」はあるのに、「灼眼のシャナ」がなかったのは残念だ。
折り返しを見ると、0はなんとIV巻の設定とある。あわてて買わずによかった。
目ぇーの奥、痛いナァ。
- 2005/10/25(火)
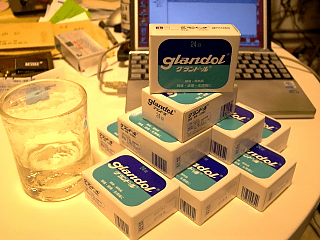
君は『上海』をしっているか(ネタが古いか...)
相変わらず体調は悪いまま。そんななか、ひとつの暗雲と光明が見えた。
日曜日に近所の薬局に行った際、いつも飲んでいる頭痛薬がないことに気づいた。品切れ
というわけではないようだった。そのスペースには別の薬が収まっていたからだ。しかた
なく、別のものを買った。しかし、この2日間ほど頭痛は治まったものの、ぶりかえしの
きざしは常にあり、すっきり感がない。せめて頭痛だけでも完全にぬぐいされれば、気分
は楽になるのにと思い、今日別の薬局に行ってみた。
さがす余裕もなかったので、単刀直入に「グランドールって頭痛薬ありますか」と聞いた
ところ、なんと「一般向けの販売はなくなりました」という驚きの事実が返ってきた。こ
れはわたしにとっては存亡にかかわるといってもいい問題だ。あわてて、医療系ルート
(あやしいルートみたいに聞こえるなぁ)での入荷を探ることにした。簡単にいうと、
鍼灸師である母親に電話したのだ。
「そう、もううってへんねん。困ってる。」
なんと、完全に店頭在庫しか残っていないらしいのだ。我が家ではこのグランドールとい
う解熱鎮痛剤によって、代々の命を永らえてきたといっても過言ではない。(まだ親子二
代やけど。)どうして、こんなことが起きてしまったのか。理由は製薬会社の統廃合だと、
言う。そう、パッケージの裏を見ると、「発売元:ゼファーマ、製造元:中外製薬」とあ
る。それで、だいたいの理由がわかった。
「グランドール」はもともと藤沢薬品工業が発売していたのだが、藤沢薬品は今年になって
山之内製薬と経営統合してしまった。その結果、医療系はアステラス、大衆薬系はゼファー
マという会社に再編されたのはご存知の通りである。ふたつの製薬会社が合併するとどうな
るかということの例がこの「グランドール」であろう。同じジャンルのくすり、つまり風邪
ぐすりや、頭痛薬が、両方の会社にあった場合、それらは競合商品になってしまう。そうな
るとどちらかを淘汰しないといけない。ゼファーマの場合、現在解熱鎮痛剤のリストには、
「サリドン」がのっており、「グランドール」が負けたのだ。
製造元である中外製薬が新たな形でグランドールを出すことは考えられないと思う。くすり
の世界は詳しくないが、おそらくはライセンスを握っているのは発売元であるからだ。また
中外製薬が仮にライセンスをもっていたとしても、中外にはすでに大衆薬部門は存在しない。
これも医薬再編のあおりだ。
というわけで、いっときは途方にくれたのであるが、道はないわけではなかった。グランド
ールの主成分と似た薬ならば、我が家の体質にあっている可能性がある。実際に、母親はい
ち早くその可能性をさぐっていた。その結果の代替薬品はバイエル社の「アスピリン」だ。
アスピリンの前に道はなく、アスピリンの後ろに道はないといえるくらい、有名なアスピリ
ンは、鎮痛剤の王者といえる。(もともとは商品名でアセチルサリチル酸のことだ。)
ちょっとややこしいのだが、「グランドール」の主成分はアスピリンとアセトアミノフェン
である。日本薬局方ではアセチルサリチル酸のことを、アスピリンと称するため、こんなこ
とがおきている。以上、うんちく。
で、「アスピリン」があるからいいのか?というと話はそうは簡単ではなくて、アスピリン
は胃をやたらと刺激する薬品なので、「グランドール」の場合、メタケイ酸アルミン酸マグ
ネシウムという「制酸剤」をいれて、これを中和していた。簡単にいうと、「アスピリン」
だけを飲むと、胃の弱いひとは、胃をやられるかもしれないということなのだ。だもんで、
うちの親も、「アスピリン」+「胃薬」の組み合わせを推奨した。
はぁ、しかたない。とりあえず「アスピリン」を買いなおしに行くかと思い、その後別の
薬局に入ったところ、なんと!そこでは「グランドール祭り」を開催していたのだった。
単に頭痛薬コーナーで「おすすめ!」品になっていただけなのだが、これはチャンスとば
かりに、いっぺんに10箱を買い占めた。財布には非常に痛いが、将来の頭痛に備えるた
めにはやむをえない。半分は親に譲ればいいし。
さて、大量の薬、それも鎮痛剤を購入するということは、じつは非常に怪しい行動なので
ある。案の定、定員に「鎮痛剤は、用法容量を守ってください」と説教されてしまった。
もっと厳しいところなら、理由を聞かれたかもしれないが。でも、聞かれもしないのに、
後ろめたさがさきにたってしまい、「この薬、もう売ってないんで」と言い訳したところ
「え、そうなんですか?」と逆に質問されてしまった。こわい薬屋だなぁ。
実は、要望にこたえて再生産決定!とかだったらうれしいのに...
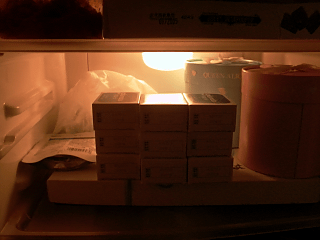
冷暗所にて、厳重に保管。
- 2005/10/24(月)
出社するも、絶不調。
年休が残り少ないので休めないのと、今日提出の課題があった。
なぜか仕事ははかどる。不可解。
更新休みます。
- 2005/10/23(日)
半年にいっぺんくらいやってくる絶不調のため、立ち上がることすらできず。
朝から夕方まで「うー、誰か助けてくれー」と七転八倒。トイレの前で寝る。
YK練習、行きたかった。
- 2005/10/22(土)
早朝、頭痛で目が覚める。くすりを飲んでもう一度寝る。
東京に行っているとき、電車に乗っていて地震にあうという夢を見た。電車を降りて、
家に帰ろうと、別の電車から降りてきた人に道を尋ねる。東京の設定のはずなのに、
降りてきた人は「私は京阪沿線の人間だから、阪急沿線のことはわかりませんねー」
とこたえた。どこかの高校のテニス部の顧問らしい。女子高生(部活のポロシャツ着
用)を引率していた。
というところで、もう一度目覚めた。呼び出しベルが鳴ったのだ。
届け物だ。

igsルーペ[金属製](発売:印刷学会出版部)
これは、「印刷解体vol.2」へ行ったときの後日談である。10月16日の写真に活字と一緒
にルーペが写っているが、あのルーペも一緒に買ったものである。しかし、上の写真の
ルーペは微妙に違う。あのときのルーペは[樹脂製]で、こちらは[金属製]なのだ。
あの日、活字をひろったあと、展示販売を見ていると、こんな文句が飛び込んできた。
「色収差,像面歪曲収差が完全に修正された3枚レンズ構成の
シュタインハイル型高級ルーペ。印刷・製版の技術者,営業
マンに30年以上愛用されている」
わたしは、こういうプロ向けの道具に弱い。それも「印刷向け」で、「ルーペ」という
マイナー要素がそろっているとくれば、めためただ。TKO負けしてしまい、購入する
ことにした。2種類あって、それが金属製と樹脂製だった。金属製のほうが質感がある
だろうと思って、レジで金属製をくださいと言ったのだが、現物しかないので確認して
くれといわれた。そこで展示されていた2つのルーペをよく見ると、デザインが少しず
つ違う。レンズ面へ向かう傾斜がすり鉢状になっているか、階段状になっているか、シ
ボ革状の仕上げか、ストレートな仕上げか、というもの。
階段状でストレート仕上げの方が気に入ったのだが、そちらは樹脂製だった。それで
こちらに変更してもらった。
ところが、これが間違いのもとだった。何時間もして、京都に帰ろうとしたそのとき、
突然気づいた。買ったのは樹脂製なのに、会計は金属製の値段になっていたのだ。その
差は500円。微妙なところだ。いまから、渋谷まで行く気力も、時間もなかった。
いったんはあきらめて、帰宅したのであるが、あとになると、わずかな差とはいえお金
を無駄にするのはよくないし、間違いをそのままにするのは気分が悪いなぁ、とくよく
よ考えはじめてしまったのだ。
で、とりあえずレシートにあった電話番号にかけた。まぁ、むこうのミスではあるのだ
が、こっちにも非はあると思うので、すぐに「どうしましょうか」という相談になった。
クレジットカードで買った品物の金額訂正は、そのクレジットカードの現物が必要であ
る。東京に行く用事はしばらくない。結果、樹脂製と金属製を交換することになった。
それが一番シンプルである。金属製のデザインがどうしてもいやというわけではなかっ
たし、性能は同じである。
そして、今日届いた。
封筒には、おわびの手紙と、それに「わずかながらのおわびの品」が同封されていた。
何かの商品でも、商品券といった類のものではなく。
それはほんとうに「わずかながら」の紙とはがき。
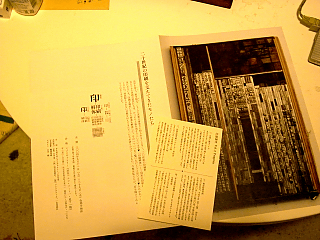
印刷解体vol.2リーフレット、ダイレクトメール
”二十世紀の印刷を支えてきたモノたち”と題された、そのシンプルなリーフレット
は初めてみるものだった。おそらく、今回の会期前、中にギャラリーで配布されたも
のなのだろうが、わたしが行った時点(閉幕の前日)には、会場にはなかった。もし
しあったなら、こんなステキなモノにきづかないわけがない。こうやって、わざわざ
送ってもらえたということは逆にはやい時点で配布が終わってしまったということの
証なのかもしれない。DMはこれよりももっと数が、少なかったに違いない。
2ツ折のリーフレットの中は活版印刷と写真植字の工程解説があり、そして裏表紙は
もっとも目を引きながら、誰もが見たことがないであろうものだった。このリーフレ
ットの表紙そのものの「組版」だ。つまり、このリーフレットは活版印刷で刷られた
ものにほかならない。組版は活字を単に並べるわけではないことが、これを見るとよ
くわかる。行間を調整するための仕切りの金属板が、こまかくレイアウトされている
のだ。反転状態でこの作業を行うことの高度さには、一種芸術性をも感じる。
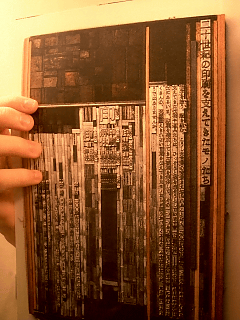
組版を鏡に映すと、この通り。
それにしても、なんともうれしいおわびの品である。なんの事情も知らないひとから
すれば、そんなものもらってもしかたないと思うかもしれない。それはそうだ。でも
これは、印刷解体というイベントにやってきて、活字をひろい、ルーペを買っていっ
た私という客へのおわびなのだ。そういった人が、どういうものを好きで、どういう
ものだったら喜んでもらえるのか。それをちゃんとロゴスギャラリーの人はわかって
いた。そのことに、とても感心したし、驚いた。金額を取り違えてもらってよかった
とすら思えた。
で、ルーペも届いたことなので、いまいろんな印刷物をかったぱしから覗き込んでい
るのだった。ただひとつ、金属製の欠点である「重さ」を右手に感じながら。
- 2005/10/21(金)
BK練習。演奏会3ステージ目の曲の音取り。2時間があっという間。
練習後、宴会。BK宴会史上最速10:40に撤収。ほとんどマネ会だったからなぁ。
全員1杯しか飲んでいないのも新記録か。
- 2005/10/20(木)
携帯メールがなって、べらんだに出ると、
月の真横に飛行機雲がでていた。
地面から立ち上る煙のように、月に届いていた。
なんだ、ロケットに乗らなくても、月にいけるじゃないか。
- 2005/10/19(水)

きのう、NCの用事で手紙をしたためていたのであるが、シャープペンで書いていると、
どうしても筆致が硬くなってしまう。そうすると、力が入るため時間が経つにつれてずいぶ
んと疲れてきた。あとになって、万年筆で書けばよかったときづく。
封を終えてから、久しぶりに愛用のものを取り出してみると、案の定インクが切れてかけ
なかった。正確にはカートリッジが切れている。(私のは吸い上げ式ではないのだ。)
こうなると、書いてみたくて仕方なくなって、仕事がえりに大丸へ向かう。ひさしく買っ
ていなかったので値段がわからない。手持ちが2000円しかなかった(社会人として、
それはどうかと思われる)ので、足りないかもと不安になってくる。それに型に合うもの
がないかもしれない...。意を決して「○○○○○のカートリッジありますか」と聞いて
みた。店員さんに声をかけるのは苦手なのである。(声をかけられるのはもっと苦手。)
店員さんは、型式をたずねたりせず、色のみ聞いた。黒を頼む。果たして、詰むや詰まざ
るや。「525円です」。6本いりだから、1本100円以下だ。リーズナブルで助かった。万
年筆メーカーは、こんなところで商売しようとは思っていないのだろう。型の問題があっ
たので心配だったが、店員さんが見せてくれたカートリッジは見覚えのあるものだった。
この万年筆はわたしの持つ筆記具のなかでもっとも所持歴が長い。15年はこえていると
思う。手に入れたばかりのころは、それこそ使い道がなく、ちょっとした大人気分を味わ
うくらいしかできなかったのだが、大学時代はよく使った。ふつうに手紙を書いたり、
時には実験レポートも書いた。罫線が細かったので、教授はさぞ読みづらかっただろう。
手紙は、高校の先輩によく書いた。グリーの演奏会の案内をだして、一年に4度くらいの
往復書簡をしていたのを思い出す。携帯メールのある今からはとても想像がつかないのだ
けれども。
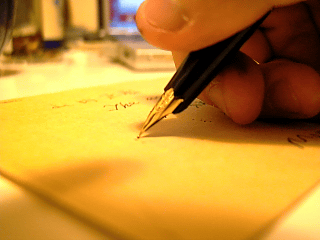
帰宅してから、カートリッジを2つ背中合わせにしていれる。ふたを閉めるとき、ぱちっ
と栓となっているボールが外れる音がする。ペン先を少し水に浸してやると、インクがに
じみだしてきた。15年経っても同じカートリッジが使える設計思想にすこし感嘆しなが
ら(これ以上進化のしようのない道具だからとも言える)何を書こうかと考える。
名前を書く。漢字。ひらがな。
ゆきづまる...、むむむ。
そもそも書く必然があったわけではないので、これといった文章や書き物が浮かばない。
結局、「湯葉」「先付」「松茸」と書いた。つけていたTV番組がたまたま旅番組だった
からだ、きっと。
恋文...でも書いてみるかなぁ。(誰にだ)
- 2005/10/18(火)
のどの左奥がいたい。風邪だろうか。熱もないし、だるくもない。ただ、のどの通りが
悪く、なんども痰きりのようなせきをする。耳のあたりも痛い。
仕事に集中できないせいか、昨日暗室に書こうとおもって、あたまのなかで推敲してい
たのだが、途中で忘れたことを急に思い出す。せっかくなので、書こう。
日曜の朝、インターコンチネンタルの一階にビュッフェの朝食を食べにいったのである。
席につくと、ウェイターが「おはようございます」と挨拶。こちらも返そうとおもった
ところでつまってしまい、会釈だけになってしまった。
「おはよう」と返すには自分はまだ若いし、鷹揚な感じがしていやである。かといって
こちらも「おはようございます」と返すのは堅苦しいし、長い。おっかなびっくりしゃ
べるたちなので、「ございます」まで言い切れないかもしれない。
と、右隣にヒスパニック系の男性が、左隣に英国系の男性がやってきた。ウェイターの
挨拶は「ぐっ、もーにん、さー」。返事はもちろん「ぐっ、もーにん」である。なんだ
かとてもスマートである。わたしもこれなら言えそうであるが、一度挨拶を受けている
ので二度目はない。考えてみるに、こういうウェイターと客の間がらというものに、
マッチした日本語の挨拶、中の下くらいの友好度におけるあいさつというものは、日本
語にはないように思える。「おはよう」「おはよう」という挨拶は、むろん好きである
が、それの拡張版というものはない。
英語にしても、もちろん抑揚やスピード、身振りなどが加味されたうえでの意味という
ものがあるはずだが、ねむい頭には音節がみじかい言語の挨拶は楽そうに思えるのだっ
た。あ、そういえば、むかしここでウェイターに中国人ビジネスマンと間違われて、
英語で席に案内されたことがあったなぁ。こちらも途中で、「日本語、話せます」と
小芝居なのか、日本人ですって言いたかったのか、よくわからない応答をしたことを
思い出す。
念をいれて、風邪薬を飲んだので、本日はこのへんで、おやすみなさい。
- 2005/10/17(月)
家に帰る途中にときどき、「プロヴァンス料理」と書かれた看板の前を通る。肉料理の
ような写真も写っている。店のなかからはやわらかい昼光色の明かりと、煮込み料理の
匂いがもれてくる。
であるが、そこの料理を一度として食べたいなぁと思ったことがない。なぜだろう?と
考えてみると、実にたんじゅんなことだった。その道を通るのは、近くの定食屋だので
夕飯を食べた帰りなのだ。たいていは満腹感でいっぱいである。
そんな状態だから、どんなにおいしそうなものがそこにあっても、それ以上食べたいと
思わない、いや食べられない。その状態が頭に刷り込まれているので、空腹のときに通
っても、興味を引かれなくなってしまった。
そのことに今日気づいて、急にプロヴァンス料理が不憫になるのであるが、
前を通るときは、やはり定食屋の帰りなのだった。
食べられないものは、食べられないよなぁとひとりごちながら、家に帰った。
- 2005/10/16(日)
「印刷解体vol.2」、ロゴスギャラリー、観覧。
http://www.parco-art.com/web/logos/insatsukaitai_2/
http://www2.odn.ne.jp/nichigetu-do/
追記:10/17
こんなモノを手に入れた。
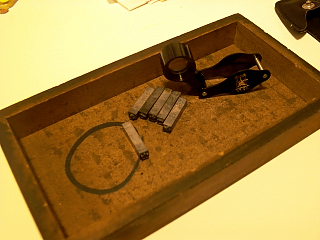
文選箱と活字と、印刷確認用ルーペ。
渋谷パルコパート1、地下一階にリブロという本屋があり、その奥に小規模なギャラリー
スペースがある。ロゴスギャラリーという。ロゴスとは言語、思想、論理。キリスト教で
は神の言葉という意味もあるようだが、もとがギリシャ語であるから、そちらは後付けで
あろう。そのギャラリーで今回開かれたのが「印刷解体vol.2」である。
解体されるのは活版印刷である。印刷分野の電子化というものはかなり前、十数年以上前
からすすんでおり、活字を組んで印刷する活版印刷そのものは、もはや商業印刷ではほと
んど存在しないはずである。しかし、活字から写植への転換など、普段の生活でよほど注
意しなければ、わからなかったはずで、活版印刷の実態というものもこれまで人目にふれ
ることはなかった。
さて、この展覧会はその活版印刷で実際に使われていた活字や、活字台をメインの展示と
し、なおかつその活字をすべて販売するという、まさしくひとつの活版所を解体してしま
うものなのだ。上記のURLを参照してもらえれば、会場の様子がわかるのだが、壁一面
をあらゆるポイント数の活字が埋め尽くしている。活版で刷られた印刷物や、組版の道具
などの展示もあるが、入ったとたん、活字をひろいたくなくってうずうずしてくる。こん
な経験は、今後することができないに違いない。
そう、活字はひろって組む。その活字を拾って収めていくのが、うえの写真にある小さな
木箱である。文選工と呼ばれた職人が、原稿を読み、活字台から一字一字活字を選んでい
く。さあ、実際にやってみる。まずは名前など...。開始1分で絶望的な気持ちになる。
ここにある活字台は実際に使われていたものそのもので、活字の配置もそのままだ。だが、
その配置がまずわからない。国語辞典で慣れた五十音や、画数順ではないのだ。どちらか
というと、「扁」や「つくり」で分類されているように見える。見えるが、それがまたど
ういう順なのかが見ていて想像できない。
一辺が1cm近くある活字もあるが、大部分は4mm程度のもの。びっしり詰め込まれたそれら
は横がだいたい1m、立てが2mくらいで一単位だが、ようは文庫本サイズの文字で書かれた
壁新聞のなかから、目的の一文字を探す(実際には一文字5〜6個の活字がある)ような
ものだ。それが3〜4枚あるのだから、途方にくれる。山Dの「山」なんて字はポピュラ
ーであるから見つけやすいかなと思いきや、まったくの逆で、これだけ漢字があふれてい
ると、単純な字ほど見つけにくい。名前の字がすべて小学校6年生までに習う漢字で構成
された私の名前など、逆に難易度が高いのだ。
この展覧会では、文選工だった人による実演と、印刷を会期中に何度かおこなっていた
ようだが、いったいどのように文字をひろっていくのか、どうやって一人前になるかな
ど聞いてみたかったと、体験してみてしみじみ思う。
漢字をひろうのは10分くらいであきらめ、ひらがなをひろうことにする。これならな
んとかなりそう...と思ったら、なんと「いろは」の順に並んでいるではないか。前後
関係をいちいち「いろはにほへと、ちりぬるを」とやって考えるので、これも一苦労。
で、なんとかそろったーと思ったら、一文字だけ「活字切れ」していることが発覚。
そう、ここではひろった活字を販売しているから、とうぜん売り切れもあり。漢字より
も少ない分、それからひろいやすい分、なくなるのも早かったようだ。それにしてもな
ぁ、なんであの文字だけないのか?助詞でもないし、名前に頻繁に出る字でもないのに。
文字の大きさ(ポイント数、号数)の違う活字ならあったのだが、やはり同じ大きさで
そろえたかったので、全文字制覇はあきらめ、ない部分は漢字で補うことに。そんなこ
んなで一時間かかって、「山」とその他、6文字をひろった。ひえー、こんなんで文章
組めって言われたら、何日かかるんだろうか。
あ、そうそう、活字ひろいの難しい点を書くのを忘れていた。活字は、はんこと同じ。
つまり鏡文字で彫られている。もっとも活字台にはインデックスが手書きで書かれてい
るのだが、ひろった活字が本当にその活字なのか確かめるのはしょうしょう頭が混乱す
るのだ。ひらがなは要注意。「さ」と読めるのは「ち」で、「ち」と読めるのは「さ」
なのだ。ときどき、だれかが戻し違えたのか「さ」の欄に「き」が混じっていたり、
「し」の欄に「つ」が混じっていたりした。
会場では、銀河鉄道の夜の「印刷所」の章を組版したもの、その紙版(組版は保存でき
ないため、厚紙に写し取ったもの。活字が減ってきた場合など、そこから型をとって版
を作る。)を予約販売するなど、活字中毒者にはうれしいものもたくさんあった。Jコ
クトーの限定51部の活版刷り小冊子が12000円で販売されていたのに、目がくらみ
そうになったのだが、このところ合唱で物入りが続くので、自制した。おちついたら、
日月堂に問い合わせよう。活版印刷の組版は静かな芸術品といってもいい。そのこじん
まりとした美しさが好きである。
活字が80×6円、自分が活字ひろいにつかった文選箱が500円であった。
文選箱は、家の鍵や自転車の鍵を入れるの使うことにした。もともと活字を入れるのに
つかっていただけあって、金属のものとは相性が良いようだ。
渋谷をあとにして、一時間。友人に会うため、千葉県松戸市へ。
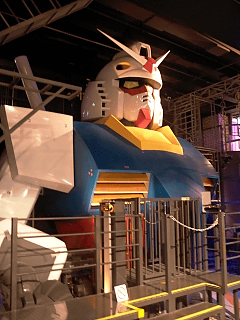
1/1、RX78ガンダム。
そこでこんなモノを見てきた。バンダイミュージアムというところ。
この初代ガンダムの前で、ガンダム世界の軍服を着て写真が撮れるのだが、友人による
と子供達のほとんどが「ザフト」か「連合」の制服を着るらしい。なんだかなぁ。
一通り回ってみたが、ガンダム関係の展示やアトラクションはやや物足りないものがあ
る。どうせなら、ホワイトベースや、アーガマのブリッジを再現するとか、もうちょっ
と世界感にのっとった展示を増やして欲しいところ。ザクマシンガンなんて、単なるガス
銃を打つだけだもんなぁ。
で、そろそろ帰るかというときに、震度3〜4の地震に遭遇。突き上げるような縦ゆれが
数秒間続いて、かなり怖かったのだが、こちらの人は平気な顔で、普通に模型を見たりし
ていたのに逆に驚いてしまった。係員は大慌てでガラスに近づかないでくださいと叫んだ
り、脱出経路の確認とかやっていたのに。ちょっとかわいそうな気持ちになった。
在来線は少し遅れていたが、新幹線は定時運行だったため、特に混乱はなく京都へ戻った。
そういえば、ロゴスギャラリーの活字台は大丈夫だっただろうか...。
- 2005/10/15(土)
耕友会コンサート@第一生命ホール、を聞くために東京へ。
追記:
感想等は後日、記載予定。
耕友会の皆さん、おつかれさまでした。
ひとついえることは、合唱をやるためのエネルギーを、気力をこの演奏会でもらった
ということ。
- 2005/10/14(金)
BK練習。
研修疲れのため、BK宴会早退。
- 2005/10/13(木)
出張研修@吹田。
更新休みます。
- 2005/10/12(水)
これは絶対買うぞ!と勇んで買った本よりも、あれこれ出てたんや!と店先で気づいて買う本
のほうが、よろこび度合いが大きいのである。買うぞと思っていた本が品切れの場合、落胆す
るほかないが、そもそも気づいていなかった本に対しては失うものは何もない。リスクがない
分、よろこびが素直になるのやもしれぬ。

「東京日記 卵一個ぶんのお祝い。」、川上弘美著、絵・門馬則雄、平凡社刊。1200円。
自転車の雑誌を買おうと思って入ったジュンク堂の店頭で見つけ、駆け寄り、前にいた人の
横から手をぐいっと伸ばして手にとる。雑誌「東京人」に連載されているものを3年分まと
めた本である。随筆とかエッセイではなく、日記である。毎月、3〜4日分のみじかい日記
が掲載されているのを読むのである。3〜4日分でひとつきぶんの効能がある。これより多
くても少なくてもいけない。
しかし、人間が横着にできているので、まとめて読みたいなと思うときもある。そういうわ
けで、単行本にならないかなーとばくぜんと思っていた。川上ファンは、いつ出るんだ!な
んてせっかちなことは考えないものなのである。たぶん。で、今日がその日だったというわ
けなのだ。奥付をみると、「9月23日初版第一刷発行」とある。きょうではなかった。
日記なのだけれど、あとがきによると5分の4くらいがホント日記で、残りはウソ日記であ
るらしい。「椰子・椰子」という本は、ぜんぶウソ日記だった。連載の紙面にはウソとも
ホントとも書いていなかったので、とつぜんあきらかになった真実にびっくりする。はじ
めて読んだ人はたぶん全部ウソだと思うだろう。わたしは川上弘美検定<中級>くらいな
ので半分くらいホントだと思っていた。5分の4とは高確率である。
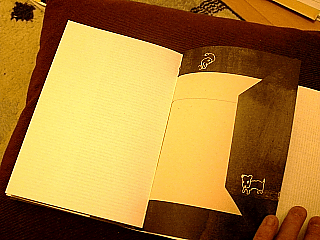
手作りのような簡素な装丁。
この本はみょーにめくりやすいので、開いてみると表紙・裏表紙に本体がぺたっと平付け
にしてあるため、表紙が180度ぱかっとひらくのである。そのかわり、あんまりひらき
すぎるので、いつ外れるのかとしょうしょう不安になってしまう。そういえば、似たよう
な本を見たことがあるなぁと思って、本棚を探したら、「センセイの鞄」も同じ本作りで
あった。ちなみに同じ平凡社で、製本会社も同じ。「センセイの鞄」は読んでいるあいだ
いつも、はずれへんかなぁーと思っていたが読み終わっても大丈夫だった。だから、この
本も心配ないだろう。
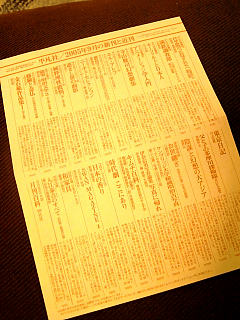
平凡社、9月の新刊と近刊案内。
文庫本ならば、うすくてつやのある蛇腹折のやつだが、ハードカバーになるとなんだか
紙も上等である。二つ折りというのも、つつましやかで品格よさげである。判断基準を
聞かれると困る。紙飛行機を折ったならよく飛びそうではある。これも判断基準を聞か
れると困る。
それよりも、ひとつにつき20文字×4行と、実に文字数が多い。それがびっちり裏表
に44冊分も掲載されているのにしびれてしまう。活字中毒者にはなんという眼福なので
あろうか。壁に貼って、朝食のときに毎日眺めてみたいと考える。
ところで、レジに差し出すとき、ふと思いついたことを質問しよう考えた。どのタイミ
ングで話すか迷う。ひとに話しかけるのは苦手なのである。結局、おつりをもらってか
らはなす。「この本の出版記念のサイン会とかないですか」「そういう話はないです」
「そうですか」...すごすごとレジをあとにする。
- 2005/10/11(火)
淀川混声合唱団、関西合唱コンクール一般B部門金賞&全国大会出場おめでとう!!
Ensemble VINE、関西合唱コンクール一般A部門金賞&全国大会出場おめでとう!
伊丹ではホールのためか、自らは感じることのできなかった"Ubi Caritas et Amor"
を、新潟ではお客さんと、そしてYKのみんなと一緒に感じられたらいいなと思って
いる。
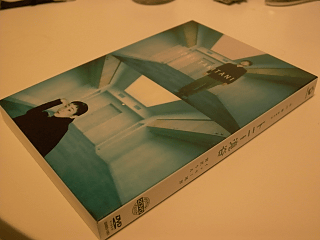
「トニー滝谷」、監督:市川準、主演:イッセー尾形、宮沢りえ。
9ヶ月ぶりに見たトニー滝谷は、やはり切ない。
そして、宮沢りえはやはり美しく、かわいい。
ちなみに同い歳デス。(←だからどうした。)
集中力回復のために、ばいか鍼で頭をたたく。
- 2005/10/10(月)
関西合唱コンクール@伊丹ホール。
NC、シード演奏。こんじょだこんじょ。
追記:
こんなに真剣に指揮を見たのははじめてであった。
一週間分くらいの集中力を使い果たしてしまった。
どうやって補充すればいいのか、途方にくれる。
「こんじょ」にも限界があることをしる。
そして、すこしのあいだだけ、たくさんのやすらぎを得た。
眠っているあいだに、こころのなかで涙が出た。
現実の世界でも、すこし涙が出た。
- 2005/10/09(日)
関西合唱コンクール@伊丹ホール。
YKにて出演。
伊丹ホールが、Ubi Caritas et Amorとなりますように。
追記:新潟で歌えることになりそうです。よかったね、YKのみんな。
25:00、これから、NCのオーダーを作ります。
- 2005/10/08(土)

もらった。
うちで栓抜きを使うことはないので、お守りにすることにした。
はて、何のお守りか?
風呂の湯船がいっぱいになるまでの時間というのは、なぜこんなにも中途半端なのか。録画して
おいた30分のアニメを見終わるまえに湯があふれ、その日の暗室を書いている途中でも湯があふ
れる。タイマーなんてつけたくない。耳を研ぎ澄まして、その一歩手前でとめるのだ。まだまだ
修行が足らぬなぁ。
起床時間まで残り5:50。
- 2005/10/07(金)
day 5.
早起き記録更新ならず。
一応、FLEXで助かった...。
- 2005/10/06(木)
day 4.
早起きの朝会にもいいことはある。
今日の朝会当番のひとがのっけから、「わたしはときどきモデルグラフィックスで原稿を書いて
いるんですが...」と所感を始めたのである!みんな、おーっとか、ざわざわとか、どよめいた
りしないのか?しかし、どんな記事を書いてはるのか?
「4歳になる双子の息子が駆逐艦やら、戦艦の名前を全部覚えてしまうのです」、あれ、もしか
してそういう方面なのか、と思っていると、最後に「『吃水線の会』というところで、艦船模
型を作ってますんで、興味のある方はどうぞ。ちなみ関西支部長をやってます」。なんですと!
そんなにすごい人が会社にいたなんて、と脳内大興奮。
わたしが、最上を作るきっかけとなったモデルグラフィックスの特集記事と、その作例を手がけ
たのが、艦船モデル作成の集団、「吃水線の会」である。いやぁ、艦船模型なんていうのは、
マイナーな模型趣味のなかでもさらにマイナーな趣味なのに、そのマイナー中のエリート(!)
が身近にいるなんてすごい確率だぁ、といたく感激した。
居室に戻って、こっそり公式HPを見てみると確かに朝会当番の人物の写真が載っている。で、
隣の部署の人に「これ、朝会の人ですよ」と見せたところ、「ああ、○○さんね。あの人はすご
いよ。」「私も今、最上っていう艦をつくってるんですよ」「紹介したげよっか」「??」
○○さんを知っているのか?...話を聞いていると、「いやー、戦艦ばっかりつくってるとあき
てくるんや〜。やっぱり駆逐艦とかがいいねー」などとのたまったのである。あなたもですか!
いやはや、長いこと仕事を一緒にやってる人なのだが、ぜんぜん知らなかった。
会社での所感の話題からすると、草野球やスポーツをやっているという人が多く、今回のような
同好の士(艦船模型は初心者だが)が存在する確率は限りなく0だろうなんて思っていたのだが
社員の規模から考えると、可能性は0ではないのだな。そう0じゃない。建築写真だって、神保
町だって、紙モノだって、スタートレックだって、同人誌だって、コミケだって、頑張っている
同好の士はいるかもしれない。いつの間にか、同じフロアの狭い人脈のなかでしか考えることが
できなくなっていたのだ。部署異動になって、はじめて気がつくことができた。
視野をひろく持ちつづけるというのは、以外と難しいものなのだな...。
(そのことが何かを生み出すかどうかは別として)
あ、そうそう。本日も突発残業(3時間)でございました。
何の因果だ。とほほ。
- 2005/10/05(水)
day 3.
なんとか耐えている。しかし今朝は朝食を食べたあと、「ちょっとだけ横に...」などと考え
てしまう瞬間もあり。危なかった。
昨日の音楽効果を考えて、今日は帰りに前から欲しかったフタコイオルタナティブのサウン
ドトラックでも買いに行くかーと思っていたのだが、とっぱつの残業が!30分で終わるなぁ
と思っていたら2.5時間もかかってしまった。待ち仕事+チェック仕事は予想がたてにくい
ものなのだ。どうも、残業するなーといわれてから、「どうしてもやらないと困る」という
残業が増えたような気がする。調整のためにコアタイム終了と同時に帰れーとか言われたら
困るなぁ。7.75時間たまったら、年休一日と交換してくれないやろか?
毎週、水曜日の夕食は「スタンド」で食べてたのに行けず。こんな日もあるやね。
しかたがないので、昨日と同じくコンビニ弁当にウィンナーと味噌汁をプラス。
さて、あれですな、今年もグッドデザイン賞が発表されましたよ。大賞と金賞は現在選ば
れているベスト15から選ばれるのであるが、普段はグッドデザインをまるで無視してい
るかのようなマスコミも、今回はなぜだか小さくともとりあげているのが気になる。理由
はiPod shuffleが入賞しているからだ。いや、iPodには文句はない。それどころか、あの
デザインの潔さは以前も暗室でちゃんと褒め上げております。
ところで入賞15点について、商品概要・審査員評・デザイナーの主張が掲載されたペー
ジを読んでいくと面白いことに気づくのだ。1つはくだんのiPod shuffule。概要のページ
には、その商品のプロデューサー、ディレクター、デザイナーの名が別々に記されていて、
どれもがきっちり個人名まで書かれている。そう、工業デザインで個人を特定できるという
ことはめったにないものなのだ。デザイナーにとっても栄誉であろうし、消費者としても顔
が見えるというのはなんだか安心感があるじゃないか。
ところがですね、皆さんiPod shuffuleのページを見て御覧なさい。
ここ
どうですか。すごいことです。ほんとうにイメージ戦略が一貫しているというべきなのかも
しれないな。
つぎにベスト15のうちのいくつかに、えなんだこれ?というものが入っている点。
インスリン用注射針、needleholder、大口径マルチスライスCTスキャナーってどれも医療
機器なのである。しかし、デザインという観点で考えると実は不思議ではないのだろう。
思わなかっただろうか、「グッドデザインっておしゃれでかっこいいものを表彰するんじゃ
ないの?」と。確かに、わたしも昔はそう思っていた。でも川崎氏の講演や、原氏の著作を
読んで「デザインとは何か」を考えるようになってからは、それは違うだろう、それはデザ
インというものの一面であって本質ではないだろう、となんとなく思われるようになってき
たのだ。
じゃあ、うえの医療機器のどこがグッドデザインなのさーという問いには、わたしからでは
「評価ポイント」を見てもらったほうがいいと思う。評価基準は全点同じで、そのうち何が
評価されたのかにしるしがついている。たとえば、インスリン用注射はこれだ。
ここ
どうですか。これが全部、デザインを、グッドデザインを評価するポイント。すなわちデザ
インとは何か、デザインは何ができるか、何をすべきなのかを表しているともいえるのじゃ
ないだろうか。(これもまた一部の観点であるが、すくなくとも見た目だけじゃないという
ことをしっていただきたいのだ。)
興味のあるかたは、審査員の講評も読んでみて欲しい。どの商品、どの商品もそれぞれに
なぜ”グッド”なのか、そしてグッドデザイン賞が何を目指しているのか?というものが
感じられるように思うから。
グッドデザイン賞公式ページ
http://www.g-mark.org/index.html
ここ
- 2005/10/04(火)
今日、気がついたのだけれども、睡眠時間を同程度とれたとしても、何時におきるかによっ
て体の調子というものは全然異なるのだ。
昨日はあまりの苦しさに11時過ぎには寝床に入ってしまったのだが、目覚めはあまりよいも
のとはいえず、結局朝から定時になるまで目の前に紗がかかったようなすっきりしない感覚
がつきまとった。時折頭痛もあり、昨日寝る前に一度、今日午前中に一度頭痛薬を飲んだが
完全に解消しない。おかげで虎の子の頭痛薬が切れてしまった。このまま、あした以降も頭
痛がつづくようだったら、くすり手当てを出してほしいくらいだ。(頭痛薬は高い)
すっきりしないまま帰宅。
このままではいかんなぁと思い、ちょっと目先を変えてみた。最近、外食やコンビニ弁当が
多いのであるが、ほんの少しだけ調理という要素を復活させてみたのだ。主食はコンビニで
買ってきたスパゲティ。いつもなら、これだけだが、まずシャウエッセンをフライパンで焼
いてみる。一人暮らしをはじめたころの朝の定番にしていたのを思い出したのだ。それから、
実家から持ち帰ってきた生協のインスタント味噌汁に湯を注ぐ。味噌2種類、具3種類を組
みあわすことができるのだ。やたら親が絶賛していたので食べる気になった。
どちらも大したものではないのだけれど、これがよかった。台所ににおいがたちこめ、熱が
こもり、灯がともると、なんだかよくわからないが部屋全体に活気が出てきたのだ。眠気が
なくなってしまうくらいに。簡単な調理をすすめながら、同時進行でスパゲッティを電子レ
ンジにかけ、お茶をつぐ。そんな動作をてきぱきやっているからか。それも着替えずにYシ
ャツからネクタイをはずしたままという、ちょっとだけくつろぎ、でもまだくつろがすとい
う半オフの状態でやる。すこしだけ緊張感を残したままにして、完成直後にぱっと着替える
ことで、一気にリラックスすることができた。これも予期せずやったことだが、いつもと違
うということがいい結果を生み出したのだろう。
夕食後、あまりすることもない。楽譜を見ることにする。どうせならCDを聴きながらいい。
あやつり人形劇場と、Ubi Caritas et Amorを聞いているうちに目が閉じてきた....きがつく
と2曲をエンドレスで聞きながら30分ほど軽く眠っていた。軽くというのはあたまのどこ
かでつねに曲が流れていたからだ。昨日の晩のようにただただ眠くて、ねむっても気分がよ
くない状態とは正反対に、まだゆるい眠りの途中なのにたいへんおだやかで気持ちがいい。
これは、あやつり人形の「ふかーく眠る」の暗示と、Ubi Caritasの持つ人を優しくする力
のおかげではないかしらん、と思う。
かくして、毎日暗室を書けるかどうか心配というくらいな状態から脱して、いま穏やかな気
分のままこの文章を書いている。融通のきかない会社の仕組みも、漠然とした不安やあせり
も、いまなら赦して、忘れてしまえるような気がする。
音楽が日々の生活のなかに息づいているって、じつはこういうことなんじゃないだろうか。
ただ週末に必死になって歌って、必死に覚えて、一瞬一瞬気持ちいいこともある、そういう
うことに苦しさを覚える時間が増えていたけれども、歌は日常にこそ歌われるべきで聞かれ
るべきものなのではないのかな?
じぶんのなかで何かターニングポイントになりそうな、そんなひらめきである。
- 2005/10/03(月)
眠いのです。
フレックス勤務、朝会あり8:30から。残業不可(今年度中)、つまり定時退社。
これが10月1日からの私の勤務。
1それはフレックス勤務ではない。
2設計開発部門より先にテスト開発部門が帰ってどうする。えらい人は現場を知らない。
3朝から晩まで眠たくて、体がだるくて、熱くて、頭がいたいなんて理不尽だ。
ということを胸にしまって、あしたも元気に出かける予定だ。
「千日紅の恋人」、半分まで読む。扇荘というアパートが舞台。まだ恋はでてこない。
住人が亡くなり、葬儀を営む大家である主人公。その途中のなんでもない一文を読んで、
突然涙が出そうになり、窓に顔を向けてしまった。一年前と重なったからというのでは
なくて、あまりにも善な人の行いが風景描写のようにあっさり描かれていたものだから、
ふいをつかれてしまった。
しかし、その後続く、野辺送りの部分はやはり、何かを思い出してしまって、そのまま
読み続けることはできなかった。どうも、心が弱くなっているよーだ。
そうそう、帰宅前に
「夕凪の街 桜の国」、こうの史代著、双葉社刊。800円。
雑誌「Pen」10/15号、特集『集合住宅で、豊かに暮らす。』。500円。
を買う。
昨日は、
「d long life design」、第5号。580円。
を買った。
これから、毎日定時退社となると、一月の書籍代がどんなになるやら心配である。
いや、毎日本屋に行くのは楽しみが半減するから避けたいな。
だいたい、帰ってからこんなに眠たくなってしまっては、せっかくの本が読めないのだ...。
まとまりのない内容になってしまったなぁ。
しんどいので寝ます。
- 2005/10/02(日)
父の一周忌、納骨法要。
母からの宿題であった写経をすっかり忘れていたり、あわてて出かけたため数珠を持っていな
かったりと、親不孝も甚だしいうえ、出席者17人のなかでは二番目に若いため何かと気後れ
のする一日であった。きごごろの知れた叔父・叔母たち、従兄弟、母方の親戚なので、いづら
いといったものではなく、自分自身の感じ方の問題である。
会社のなかでは中堅の位置におり、自分より歳上のひとたちと議論もし、仕事をしているので
あるが、こと一族郎党というもののなかで見ると、齢を重ねたとしても自分の立ち居振る舞い
のなかに、自分自身で幼さを感じざるをえないのである。これは誰しもそうなのかもしれない
が、やはり歳を重ねたうえ、世帯を持ち、生活を営んできた人たちから自然とはなたれている、
あるいは身にまとっている、「何か」と対等にわたりあうということは、いまの自分にはとて
つもなく難しいことのように思われたのだった。会社の生活のなかでは、そういったものは自
然と遮蔽されているようだ。技術者としての経験や、能力を推し量り、感じとる目のほうが
大きく開かれているのかもしれない。
世代の近い従兄弟であっても、世帯をもっているというだけでどこか違う印象を受けるのは
不思議だった。自分にはうかがいしれないものを身につけ、守っている、そういう気がする。
そして、自分はそういうものを身につける日が来るのかということすら想像しえないまま、
これからも生活するのではないかという、怖れのようなものがあらわれては消え、あらわれ
ては消えるのだった。
かつて、はるか昔、父も同じことを考えたりしたのだろうか。存命していたとしても、それを
聞くことはできなかったように思う。父と私はあまりに世代が違いすぎたし、わたしは臆病な
人間であるから。
それにしても、「お母さんを早く安心させてやれ」のような遠まわしなものから、「孫」と
いった直接的な単語まで飛び出す宴席というのは、「寅さん」世界のような、かつての古き
よき日本映画のなかにしか存在しないものだと思っていたのだが、現実に存在して、自分が
当事者になるなどとは、まったく思いもよらず。参った。
- 2005/10/01(土)
10月ですなぁ。
NC練習に向かいつつ20分程のサイクリング。四条からではなく、西京極から阪急に乗る。
天神川沿いの道は気持ちがよい。しかし、ひとりで自転車をこいでいると、単なるトレーニン
グだということに気づき、あまりの秋晴れの心地よさとの落差にちょっと切なくなるのであっ
た。
NC練習16〜21時。
飲み(飲んでないけど)21〜23時。
飲まずにはいられない(飲んでないけど)。
- 2005/09/30(金)
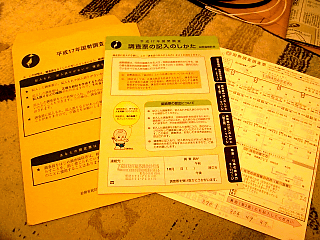
BK宴会帰宅途中、思い出した。明日は、↑を提出しなけりゃいけなかったのだ。そう、国勢
調査である。調査員の人には明日の午前中なら在宅していますと告げていたので、これからか
かないといけない。NC合宿直前にもらってから、一度もなかを見ていないのだが、えらく
面倒なものだったらどうしようか...
書いた。丁寧に気を使って書かねばならなかったが15〜20分くらいのものか。それほど難しい
ものではないことは、書かれた人ならお分かりであろう。しかしなぁ、こんな細かいことまで
書いて、これを本当に統計にできるんだろうかと心配になってくる。だいたい職業までならま
だしも、その仕事の内容まで書くとは!統計とはすなわち類型の分類であろう。どこまで分類
するのか、またその判断基準は本当に正しいと言い切れるのか。いったいどんな人がやるのだ
ろうなぁ。
国勢調査の結果というのは、いったいどういう形ででるものなのか。本か?官報みたいな書面
か?考え出すと、きりがない...。あ、入っていた説明書によると、項目によってこれこれに
利用されるとある。たとえば、従業地の調査からは人口の動き、昼間人口などわかり、それを
もとにして、道路交通整備計画や、上下水道整備計画が行われるのだという。
あ、いやこれは利用方法だ。個別に利用されるだけで、全体として結果が出るも出ないも書い
ていないな。統計としてまとまれれるとしか書いていない。ネットで調べるのもいいけれど、
眠くなってきた。あした、調査員のひとに聞いてみることにしよう。
ちゃんと、眠れるだろうか。
また、夢を見るだろうか。
夢見ることは願望で、希望なんだろうか。
そうかもしれない。たぶん。
ふつらふつら考え出す。
いつの間にか眠る。
おやすみなさい。
- 2005/09/29(木)
朝の日差しはややきついものの、夕刻になるとぐっと気温も下がる今日この頃。いよいよシー
ズンの到来であろうか。そうだ、秋こそは腕時計の季節。汗が大敵の皮ベルト&アンティーク
の時計をこころおきなく身につけられるのだ。
ひさしぶりに4つの手巻き時計すべてのねじを巻いてやる。いつも巻けなくてごめんよ。
テンプの振れる音、秒を刻む音のあいだに、虫の音が聞こえます。
ああ、秋だな。
- 2005/09/28(水)
今使っているクレジットカードの期限は、この9月末までである。なので、先週新しいカード
が送られてきた。今回のカードから、カードのランクが上がったのだが、その案内状を読んで
いると非常に重要なことがさらりと書かれていた。
『カードの番号が変わります。お取引先へのご連絡はお客様ご自身でお願いします』
!!!ランクがあがったんならそんなのカード会社がやってくれよぉ!!!!
いや、それ以前にになんで番号を替えるんですか。もうすぐ携帯の番号すらキャリアーが変わ
っても持ち越せるようになるというのに、ちょっとなぁ納得いきませんよ。
クレジットカードをあまり使わない人のために説明すると、カードの使い方というのは3種類
ほどあって、1普通に買い物で使う、2キャッシングする、3サービスの決済に使うがそれで
ある。1に関しては、カード番号の変更は問題にならない。2も関係ないし、ましてキャッシ
ング(カード会社にお金を借りること)などしない。3は、電気ガス電話などの公共料金のひ
きおとしをカード会社が代行するものだ。このサービスはあらかじめ各会社にカード番号を届
け出ることで行われる。つまり、カード番号変更の影響を受けてしまうのだ。
文句を言っていても始まらないし、9月ももう終わり。つぎの決済日までに切り替えをすませ
ないと、料金の引き落としができなくなる。えーっと、わたしはこのカードで何を決済してた
のだろう。
1携帯電話料金
2ハーボットの拡張サービス料金
3プロバイダー接続料金
の3つであった。おお、どれもネット関連であるから、変更はウェブ上で割合簡単にできそう
であるな。やれやれ助かった...と思って、今日までほったらかしていたのだが、そうは簡単
にいかなかったのである!
○携帯電話編
NTTD●C●M●のホームページに行くと、支払方法の変更というページがあったので、
さっそくクリック。すると、i-modeを使えとある。いやだな、携帯でネットにつなぐのは入力
が面倒なので好かないのである。仕方なく、料金サイトに接続し、変更ページに行く。つぎは
なんだ、「ネットワーク暗証番号を入れよ」。なんだそれ?どうやら、契約時に書いた4桁の
数字のことらしい。そんなの憶えているはずがない。あてずっぽうで入力していると、3回以
上間違ったので、ロックしましたとの非道メッセージが表示されたが、これくらいのことでは
動じない。しかし、そのあとが問題だ。ロックされた場合、暗証番号の変更が必要です、と説
明されているが、その方法の説明がどこにも書いていない。サービスセンターに相談しろとい
ういうあいまいな記述。サービスセンターは20:00まで。まったく!馬鹿にしてますな。
面倒なので、ドコモショップに直接乗り込むことにするが、これも20:00までなのでアウ
ト。やれやれだ。というわけで、未解決。
○ハーボット編
ハーボットは基本的には無料なのであるが、会員登録をすると拡張サービスを受けられるの
である。月額315円なので、負担ではない。で、その会員登録はプロバイダーのSo-netを
通じて行うのだ。しかし、ここでも問題が。支払方法変更を行うには、会員No.とパスワード
が必要なのは当然であるが、肝心の会員No.もパスワードもわからないのである。というのも
普段ハーボットを使っている人間にしてみれば、So-netの会員であるということをまるで意識
しないので、So-netのほかのサービスを使うこともない。だから、会員No.なども入会したと
き以来、目にしたことがないのだ。しかも、その申し込みを行ったのは今は死んだままにな
っているメインマシン。なので、メインマシンのメールにはおそらく会員情報がテキストで
残っているのであるが、お亡くなりになっているため、見ることは不可能なのだった。
どうしようもないので、こちらのメールアドレスだけを情報として書いて、So-netのサービ
スセンターにメールした。ネット会社なのにすぐに返信が来ない。まさか、普通の会社と同じ
営業時間帯にならないと返事がこないのか...。というわけで未解決。
○プロバイダ編
光接続はFLETSで、こちらは都度振込みにしていることは以前書いた。プロバイダ自体は
学生のときから同じ。サービスや保守も良いので継続している。で、支払い方法変更をさがす
と...「オンライン不可。PDFファイルの申し込み書を印刷して送付」とのこと。うーん、
あまり腹はたたない。むしろ堅実でまじめであると言える。安全面からすれば。しかしなぁ、
暗号化技術は進歩しているし、ネットでカードを使って買い物をするのがある程度普通になっ
ている今現在なら、オンライン変更をやってもいいんじゃないだろうか。だって上記の二つは
条件が整えば変更可能なんですよ。わが家にはプリンタがないし困ったことだ。会社でこっそ
り印刷しないといけいないじゃないか。というわけで未解決。
というありさまデス。ああ、なんといっても元凶は番号を変更してくれたカード会社なのであ
るが、各社ここまで手続きがめんどくさいとはおもわなかった。くわしくは書いていないが、
変更場所へたどり着いたり、その情報をえること自体もかなり面倒だったのだ。ネット社会と
いっても、いろいろなことが届け出制なのは実社会と変わらないのだな。パスワードやIDを
憶えておくのも限界がある。ここはやはり、実用化のはじまった生体認証手段が個人レベルで
普及してくれることに期待したい。いや、ほんとうに。くたびれたー。
虹彩・網膜認証なんかサイバーでいいよなぁ。(夢見がち)
- 2005/09/27(火)
この、しとしととふる雨は、朝夕がすごしやすくなったり、空が高くなったりといったことよ
りはっきりと、夏の終わりは過ぎ、秋がおとずれたのだということを私達に告げているように
感ずる。
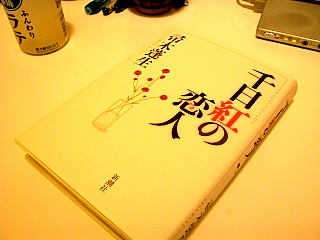
「千日紅の恋人」、帚木蓬生著、新潮社刊。1600円。
帚木蓬生と聞いて、ピンと来る人はまれである。源氏物語を読んだことのある人ならば、ある
いは、おやっと思うかもしれない。『帚木』も『蓬生』も源氏物語の段の名前なのだ。しかし
私を含めた多くの人がそうであるように、源氏物語を読み通したことのない人が大多数であろ
う。そして、その名を冠した小説家を知る人は、源氏物語を読み通した人よりは少しは多いく
らいかもしれないといったら、帚木ファンとしてはあまりに自虐的すぎるだろうか。
帚木蓬生は、TBSに勤務した後、精神科医となったという異色の経歴を持つ、いまも現役の
医師である。そのためか、初期の作品は医療をテーマに扱ったものが多い。その後、昭和の戦
争を描いた歴史物が続いていた。氏の作品に共通しているのは、その自然描写のたくみさであ
る。ばつぐんに比喩がうまい。奇をてらったり、感性に理解を求めるような難解な喩えは決し
て使われることがない。ただわれわれの日常にあるもの範囲で、これほどありありとその姿を
思い浮かべることができるのかと、ときに驚き、ときに沈黙させられるようなものばかりだ。
それら比喩の連鎖のなかに物語が封じ込められているように思う。人物を語る視点も、風景を
自然を見るのと同じ視点で、しずかな観察(しかしいつくしみのこめられた)のうえに成り立
っている。
そんな印象的な作家であるが、近年少し離れていた。が、今日久しぶりにその名を目にして、
思わず手にとったのである。しかし、そこに書かれた文句にはいささか閉口した。なにしろ、
「感涙の恋愛小説」である。それ以前にタイトルに「恋人」なんて文字が入っている。これに
「千日紅」と花の名前など入れば、これを恋愛小説だと思わないひとはいないだろう。
こうもはっきりと恋愛小説、感動!とわかる売り出し方をされると、こちらとしてはかなり警
戒してしまう。感動を歌う作品に感動はあるのか?と疑心暗鬼になってしまうのだ。しかし、
である。帚木蓬生が恋愛を書くからには何かあるはずに違いないという期待感が浮かんでくる。
20〜30代半ばの駆け出しの男性小説家が描くようなものでは決してないはずなのだ。帚木
蓬生が描く以上、そこにはただ深くて、静謐な世界があるはずなのだ。帯に書かれた「大人の
ためのラブストーリー」なんて野暮ったいものではなく、渡辺淳一が書くような生々しい大人
の男女の世界でもないだろう。
帰りの電車で30ページほど読んだ。まぎれもない、帚木文体でなんだか安心した。のと同時
に、まだ登場しない「恋愛」をどんなふうに読ませてくれるのか期待感もある。秋の長雨にあ
わせてゆっくり読んでいこう。
追記:
帚木作品の多くは新潮文庫に収められている。「閉鎖病棟」「賞の柩」を読まれることをおす
すめしたい。
- 2005/09/26(月)
更新休みます。
- 2005/09/25(日)
NC合宿@奈良、二日目。09:00〜16:00。
集中力がときどき、ふっととぎれてしまう。自分が何をやってるのかわからなくなる。
ひとりで上歌うのは限界や。もうしんどい。だめや。
根性でなんとかなるものとならんもんがある。
帰りの近鉄電車からしずむ夕日がみえた。真っ赤な夕日とちがう、黄金の日の入り。
こんなときに限って、カメラをもっていないのだ。ついてない。
- 2005/09/24(土)
NC合宿@奈良、一日目。14:00〜21:00。
またまた奈良へ行って来ます。
いろいろつらい。でも、宴会は楽しい。半分くらいマネージやったけど。
それがNCらしい。
- 2005/09/23(金)
13:30〜17:00、YKコンクール練習参加。
(練習そのものは10時から開始)

自転車用ヘルメットデス。みればわかるか。
給料が入ったのをいいことに自転車用のヘルメットを買うことを決意。やはりスポーツバイク
で、ロングツーリングをする可能性があるならば、必要だろうと思ったのである。YK練習後
に天六近くにある、Via Cycles Villageへ。この前、グローブを買ったところである。大きい
店舗で自転車本体以外のパーツやアパレルも大概そろっている。京都に、この規模の店がない
のは残念だ。
さて、買う前にいろいろと検討して、これがいい!というヘルメットがあったのだが、今回
まったく想定していなかったモノを購入している。理由は、お目当てのヘルメットに頭が入
らなかったから…。笑ってはいけませんよ。これはすごく重要なことで、頭部を守り、長時
間着用するヘルメットはフィット感が命。頭が入らないのは論外で、はいってもどこかに圧
迫感があると当然よくない。目当ての製品はサイズがS、Lしかなく、Lでもかなり小さめ
なので、入らない人はわりといるのだと、お店の人が教えてくれた。
で、仕方がないので、まずは頭が入るものをさがし、そのなかでデザインが自分にあうと
思われるものを探していった。その結果がGIRO社製のMONZA。まったく違和感なくポスッと
頭が入った。頭の形はほんとひとそれぞれで、サイズが大きくてもあわないものはある。
これから買おうと思っている人は通販なんかでかったりせず、店で着用して決めたほうが
良いと断言する。
さて、家に帰って食事をしてから、腹ごなしとテストも兼ねて、ヘルメットを装着しての
ショートドライブを敢行。おお、ベンチレーション(穴)を通る風が涼しくて、全然蒸れ
たりしないし、装着感が良いので守られている!という安心感がある。6.5kmほど走行。
約22分。このペースで会社に行くと45分くらいかかるということだ。待ち時間を含めた電
車通勤と同じくらいか。試してみる価値はありそう。
ところで、インターネットで調べると、当初考えていたMET社のヘルメットは日本人の頭
の形にフィットする、とあちこちで書かれているのに対して、GIRO社のものはやや横が
狭いと書かれていた。ということは私の頭の形は日本人離れしているということなんだ
ろうか。GIROのほうがゆったりしているように思ったのだけれどなあ。
皆さん、自転車に興味がなくても、どこかでみかけたら是非、自転車用ヘルメットをか
ぶってみることをお勧めしたい。自分のあたまの形がなんとなく把握できるのでおもし
ろいと思う。
ちなみに、今この文章は、ヘルメットをかぶったまま書いてみた(←馬鹿だ)。
- 2005/09/22(木)
職場の飲み会。自転車話で盛り上がり、課長以下、ロードバイク(ハイスピードで、舗装道路
専用の自転車。レース仕様。)が欲しいという話になる。話は、スポーツ、城と武将、カメラ、
カーナビ、オーディオ、時計、映画、プラモデルと展開し、それぞれに皆、造詣が深いことが
判明。やはり、男子が通る道というものは似たりよったりなのだなぁと思う。
さて、飲み会は京都であったので私はLGS FIVEで店まで行った。帰りがけ、何人かに「それで
会社通ってんの?」と聞かれたのであるが、そういえば京都から、職場のある長岡京までは自
転車で通えるものなのだろうか、と考えた。都市間の移動はもっぱら電車に頼っているため、
電車のルートしか思いつかず、道路でたどりつく手段がてんでわからない。「いっぺん、休み
の日に試してみーや」と課長にも言われて、調べてみることにした。
帰宅後、いつもつかっているgooで、ちょうどルート検索のサービスがあるのを見つけた。よ
し、入力開始...。すごい、町名はもちろんのこと番地まで指定できる。カーナビよりも地図
の人間でもこれは便利かもしれない。おおまかなコース設定だけでもあるのとないのでは違う
からなぁ。で、検索結果はかなりあっけないものだった。西大路通まで行き、南下すると国道
171号線にぶつかる。あとは道なりに西へ、南へ向かうだけだった。そーかー、確かに大阪
方面から京都に下道で行くときは、自動車なら171号線が普通なのだよな。地図をおってい
くことで、JRや阪急、途中わたる桂川との位置関係もわかり、ようやく頭のなかでつながっ
た。(幹線道路には弱い山D)
距離は12.6km。思ったよりも短い。それとも実際に走ると長いのだろうか。休みの日にふらふ
ら走ってみると10kmくらいはわりとすぐに到達するのだけれど。まぁ、距離はおいておいて、
問題はやはり171号線沿いに走るということだ。交通量が多い、自動車の。安全と健康の面
からいって、どちらかというと避けたいルートである。自転車用のサービスではないから仕方
ないが、もっとヘルシーなコースを自分で考え直す必要があるなぁ。
うまいルートが見つかって、時間的に苦痛でなければ自転車通勤をやってみたいところである
が、ひとつだけ問題がある。ないのだ。会社に。駐輪場が。うそーと言いたくなる。厳密にい
うと、今現在空きがないというのが正しい。自転車通勤を希望している人は多いのに、駐輪場
がないからあきらめている人が結構いるのだ。おい、おい総務部!あんなだだっぴろい工場の
敷地の、どこに場所がないっていうんだヨ。駐車場を一台分つぶすだけで6〜7台は自転車を
おけると思うのだけれどな。総務部にはいろいろとまだまだ言いたいことはたくさんあるので
あるが、いま一番言いたいのはこのことだ。阪急の駅からだけでも自転車に乗れれば通勤はず
いぶんと快適になる。何度も書いているが、JRの駅から会社を結ぶ一本道のそれはそれは
狭くて、単調で苦痛なことといったらないのだ。ああ、あの道をすぃーっと駆け抜けてみたい。
きっと世界が変わるだろうな...。(おおげさ)
追記1
この前書いた、自転車を電車に乗せて移動する件だが、自転車雑誌に情報があって、一部の
鉄道会社ではすでに実施している。それもどこの会社も無料!惜しむらくは地方のマイナー
路線がいまのところ多いということ。確かに都市部ではきついのかもしれないが、徐々にで
も増えて欲しい。<近江鉄道本線、近江鉄道多賀線、近鉄伊賀線、近鉄養老線、松本電鉄上
高地線、北陸鉄道石川線。日時指定アリ>
追記2
最上の模型の写真を見て、船なのになんだか薄っぺらいなと思った人がいるのではないだろ
うか。くわしく説明していなかったのだが、これは洋上模型、ウォーターラインモデルなど
と呼ばれるタイプのもので、吃水線より上のみ模型化している。わかりやすくいうと、海に
浮かんだ状態を表しているのだ。机など平らな地面を海面と見立てて、そこを航行する姿に
思いを馳せる模型なのである。もちろん、実際の艦船は水面下にも船体はあり、その状態を
あらわしたタイプの模型もある。
- 2005/09/21(水)
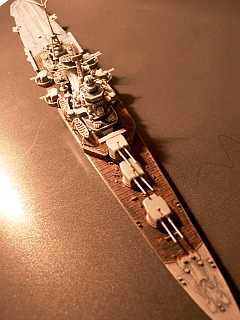
最上<艦載機無しバージョン>。進水まであと少し。
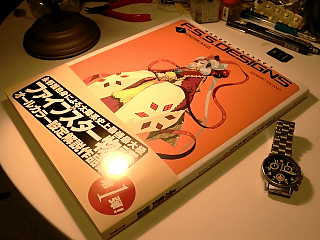
"F.S.S.DESIGNS" I EASTER;A.K.D.、永野護著、角川書店。
オールカラー、P180ページの副読本の第1巻。第4巻まで出版される予定。
...こんなの作ってたら、そりゃ出ないよなぁ"F.S.S."12巻。いったい何年くらい待ってるのか、
勘定するのが怖くなってきた。Newtype本誌を読んでいないため、状況がわからなかったのであ
るが、あとがきに「連載は止まっています」とか、「(DESIGNS4発売と)連載再開は同時」な
どという恐ろしい言葉が並んでいる。まぁ、ナガノセンセを信じて待つしかないのだ、われわ
れわれファンは。自分たちの支持しているものが、(いろいろな意味で)世界最高のものだと
信じて。
今日の日経産業新聞に富士通が電子ペーパーの広告を一面広告で掲載していた。カラー、電源
不要、折り曲げ可能という、ちょっと前なら夢のようだったものが、実現されつつある。大阪
万博から、つくば博のころまで想像していた未来とは、いまは違うかもしれないが、ちょっと
だけ注意深く観察すれば、新しい未来を想像できるかもしれない、とおもわせてくれる商品が
実はたくさんあるのかもしれない。
その広告には携帯などの端末で内容書き換え可能とあった。宣伝の絵は宇宙飛行士がスポーツ
新聞を読む図。ちょっと待てよ?と現実的な考えが浮かんでくる。紙媒体の場合、輪転機にか
けられたあとの記事を改竄することは、ほぼ不可能である。それに対して、この電子ペーパー
で新聞が供給されるようになった場合、いつどこでだれにその内容が改竄されるかわからない
といった、これまでになかったリスクを負うことにならないだろうか。もしかしたら、webと
同じような原理で供給されるのかもしれないが、いずれにせよ、供給されているものが発行
元のものであるという保証が必要だと思う。
電子ペーパーの普及を見込んで、いまからそのための認証技術を考えられれば、ビジネスに
なるんではなかろうか。電子ペーパーがインターネット端末なのか、独立媒体なのかによっ
て方法は変わると思うが、端末にすると単価が上がってしまうので「媒体」となる可能性が
高いのではと思う。
富士通のことだから、すでにそのことは考えて特許をとっているかもなぁ。
- 2005/09/20(火)

コンパクトフィルムカメラの一つの頂点、GR1。
一週間ほど前になるが、リコーからGR DIGITALが発表された。かつて、短いながらも一時代を築い
たフィルムカメラGRシリーズの名と、ライカマウントの単体レンズまで発売された驚異のレンズ、
「GRレンズ」の名を継承したデジタルカメラである。
デジカメとしてはLUMIX-LC5に愛着を感じていることは以前書いたが、同時に私はGR1ユーザーなの
である。どうしても期待しないではおれない。
デザインはどうみても万人受けを狙っているものではなく、リコーのホームページの扱いを見ても
わかるが、ストライクゾーンは非常に狭い。だいたいコンパクトデジカメの宣伝にMTF曲線なん
て載せているメーカーは他にない。リコーという会社が、というよりも開発部署+αで頑張ってい
る(けれど主流にはなりえない)という地味さ加減が、応援せざるをえないような雰囲気をかもし
だしている。リコー→カメラという図式はどう考えても一般にはないから。昔、カメラジャーナル
でGR1を取り上げていたころ、リコーの社員が複合機の宣伝に来たのでGR1の話をしたところ
「わが社でカメラを作ってるなんて知りませんでした」と言った、という笑い話があるくらいだか
らして。
発売まで1ヶ月であるが、カタログはまだ製作中である。デジカメにしては珍しく作例中心の構成
だという。昔、GR1を買ったきっかけは、雑誌の裏表紙の一面広告だった。断崖絶壁の上に立つ
洋館。コンパクトカメラでこれほどの写真がとれるなんて!あのとき受けた衝撃はいまも思い出せ
る。たった一枚でいい。あの写真をこえる一枚があるならば、私は万難を排してGR DIGITALを買う
だろう。GRを超えられなければ、GRじゃない。そうだろう?
GR1s、取り出してみてたらフィルムが6枚残ってた。前にとったのはいつだったか思い出せない。
近いうちに撮り切って、スリーブで現像してみよう。18枚目と19枚目の間に横たわる時間を、
そこに感じ取れるだろうか。
- 2005/09/19(月)
9〜16時、YKコンクール合宿参加@奈良。
YK合宿に初参加したのであるが、疲れ方の質がNC合宿と少々違うように思う。YKのベースは
安定しているので、一緒に歌っていて音楽的なことに集中できる。アンサンブルでもいろいろな歌
いまわし、ブレス位置などを自分なりに工夫したり、みんなとどう合わせるかということを考える
ことができて、正直楽しかった。だから、純粋に肉体的な疲労だけだったような気がする。まあ、
それでも昼休憩のときは20分くらいソファで寝てたんだけれども。あれは体力配分を考えてのこ
となので、とりたてて体調が悪かったわけではないです。(ちょっとお腹がゆるかったけど)
心配かけました。
来週というか、今週末はNC合宿。「訓練」とか「耐久」にならないようにしたいものだ。
- 2005/09/18(日)
13〜21時、YKコンクール合宿参加@奈良。
夜、実家に帰宅するため、更新はお休みです。
留守番して、犬にえさやって、散歩させねばならんので。
<追記>
中秋の名月だったらしく、なるほどきれいな月夜でした。
- 2005/09/17(土)
15〜21時、NC練習。
秋ですなぁ。自転車に乗るのに最適な季節がやってきたという実感がある。この前買ったスペーサで
ハンドルの高さを調節、さらにサドルを5mmほどあげたところ、腕と脚のバランスが最適位置にお
さまり、これまでにない一体感を得られることとなった。長時間走っても疲れない姿勢がとれるよう
になったので、ちょっとした買い物のときや、銭湯の帰りでもやたら寄り道して帰ることが増えた。
ちょっと、自転車小旅行などしてみたい今日この頃。
NC練習前にJR大阪駅の本屋で自転車雑誌を立ち読みしていると、そういったツーリングの記事が
あった。倉敷や、京都などの観光地には自転車が最適といったことが書いてあるのだが、注目すべ
きは、自転車の運び方。折り畳み自転車を直接運ぶ、車で運搬しパーク&ライドする、などの方法に
まじって、「宅配便で送る」という手段があった。これは盲点であった。
忌野清志郎氏が自転車を盗まれて、戻ってきたというニュースがあったが、そこでちょくちょく話題
になっていたのが、9月25日にハワイで行われるロードレースにその自転車で出場するつもりであ
るという話だ。(レースの詳細→http://www.jal.co.jp/hawaii/sports/centuryride2.html)
このレースは、ホノルルマラソンの自転車版みたいなものだが、以前雑誌の記事で特集されていて、
そのときに自転車はどうやって運ぶのか?というQ&Aも載っていたのを思い出した。ハードケース
(自転車用のものがあるらしい)か、自転車梱包用のダンボール(メーカーからお店に運搬するとき
に使うものでいいらしい)に入れれば、航空便で送れるというのだ。
そう、航空便で送れるのだったら、陸運でも送れないはずがないのだ。実際に各宅配業者の値段
が掲載されていて、京都−東京間だと、だいたい6500円前後(片道)で済むらしい。これを高い
と見るか、安いと見るか。現地のレンタルサイクルでツーリングに適した自転車を借りられればいい
が必ずしも確実な手段ではないし、もろもろの手間を考えて、とにかく自分の自転車でいろいろなと
ころを走りたい!というのなら、実はお得な手段なのかもしれない。
今でもあるのかどうかわからないが、上野発、札幌行きの寝台列車には、”モトトレイン”という
車両が連結されていたことがある。バイク専用の運搬車両なのだ。自転車が乗せられたかどうかわ
からないが、ああいう車両が一両まるまるとはいわないが、新幹線のどこかにそういうスペースを用
意できないものだろうか。3000円くらいまでなら、使ってみたいなと思う愛好家はいると思うの
だけれど。本気でJR東海に投書してみようか。無理かなぁ。自転車雑誌とか、自転車業者などのタ
イアップで、地球に優しい鉄道&自転車キャンペーンとかできたらいいのに。
さて、帰宅してから、もうひとつの可能性、折り畳み自転車について調べてみた。この世界では、
ドイツ製のBD−1という自転車がスタンダードらしいが、いまいちデザインが無骨な感じでどう
も愛好者が褒め上げるほど、好きにはなれなかった。やはりひとめみて気に入るかということは
重要なのだ。
ところがこのBD−1の2006年モデルというのが発表されていて、これがいい。すごくいい。
(→http://www.2plus4.net/BD06.html)
デザインもいいのだけれど、「新型モノコックフレーム」という説明にわけもわからず、魅力を感
じてしまうのである。モノコック、それだけで素晴らしいという刷り込みがあるようだ。紅の豚世
代のメカミリ愛好家には。
でもなぁ、今の愛車が4台は楽に買える値段というのはさすがになぁ。それだけの値打ちものだと
いうのは写真で見るだけでわかるけれども、ちょっと手が出ないかも。セカンド自転車のほうが高
いっていうのもあれだ。しかし、ライカやハッセルを買うのを我慢したり、アンティークの時計を
買うのを控えれば、捻出できない額ではないな...などと考えてしまうのであった。物欲ってこわい。
ともかく、インフラができるそのときまでは、LGS−FIVEで京都近辺を制覇してやろう!
もっとちゃんと整備もしよう。で、どうしてもでかけたくなったら、6500円払おうぞ。
- 2005/09/16(金)
一週間ほど、照明の下につりさげていたタオル(直接光がまぶしいのでさえぎるため。過去ログ参照)
を、きまぐれというか、最上の建造に手元が暗かったこともあって取っていたのであるが、やはりま
ぶしいので元にもどした。明るいのがだめな私。
そんなことはさておき、今日BKの帰りに四条烏丸を通りがかったときに、とても捨て置けない重要
な案内を目にしてしまった。正直、不安で仕方がない。
「UFJ銀行烏丸支店は12月5日に、移転します」
ひぇーである。予感はあったけれども現実のものになるとは。いや、別にUFJの行員で、転勤にな
るとか、UFJに口座があってATMが遠くなるとか、そういったことではない。建物なのだ、心配
なのは。四条烏丸の四つ角はすべて銀行、信託銀行(三井住友、東京三菱、住友信託、UFJ)で、
どの銀行も、京都のメインストリートにふさわしい、壮麗な歴史的建造物である店舗を構えていた。
過去形である。三井住友は、昭和50年代ごろにはすでに、住友信託も5〜6年前には、そしてつい
最近になって東京三菱の建物、すべて姿を消した。あとには近代ビルが残る。三井住友はファサード
の一部を保存しているが、あれはないのと同じだし、東京三菱は部分保存?をするようなしないよう
な状況であるが、どちらにせよ新しい建物が主体になるのはわかっている。
そんななか唯一残っているのがUFJの建物なのだ。一見すると特長のなさそうな外面だが、烏丸側
の入り口に立つ、巨大な二本の列柱がそんな印象を吹き飛ばしてくれる。ありえないくらい太く、そ
して高くそびえたつそれは、国内でもほかに例を見ないと思う。設計者を調べたことはないが、やや
大阪の三井住友本店に似ているような気もする。まぁ、ともかく、その建物が心配だ。店舗が移転す
るということは、今の店舗が空くということだ。いったいどうするつもりなのか...。嫌な想像が頭
をよぎらずにいられない。
いまのところ、日本建築学界から保存要望書が出されていないことから考えて(あの建物に対して、
保存要望がでないはずがない)、進退は決まっていないものと思われる。でも、とりあえずいまの
ところはだ。移転は目の前に迫っている。使われない建物がどうやって廃れていくのか、何度もみ
てきただけに行く末が気になる。できれば、有効に活用されてほしい。ほんとうに、切に願う。
のだめ13巻を読んで、こころ落ち着けてから寝よう。ふー。
- 2005/09/15(木)
木曜日はなんとなく銭湯の日になりつつある。きょうは先週休みだった薬師湯へ行く。烏丸通りから
わずか一筋のところなのに、道が入り組んでいて少し奥まった場所にあるせいか、目立たない。薬師
堂の提灯のあかりを目印に進む。提灯の「明るいのに暗い」感じが好きである。
はじめに言ってしまうと、ここの銭湯がいちばん私にはぴったり来る。来週からはここに来ると決め
た。ほんとですよ。
入り口は男湯、女湯にわかれているが、入ると下駄箱スペースがあって、女性側とつながってる。さ
らに扉をくぐると番台。といっても女湯との境のついたてがへこんでいて、そこに机があり、おやじ
さんが椅子に座っている。机にはノートパソコンが置かれていて、おやじさんはそれを眺めていた。
はばは狭いが奥行きはある。入ってすぐ気づいたのだが、ここは亡き祖父のうちと同じ匂いがする。
あれはなんの匂いだったろう。そうたぶん、木の匂い。木を加工する日曜大工、ハンドメイドする場
所に特有のにおいなのだと思う。そこにかすかな湯気。祖父のうちの風呂は祖父自身が作った。
あの風呂と同じにおいがするのだ、ここは。それだけでもう、ここを好きになっていた。
脱衣場にはトイレとサウナが併設。浴室のわきのすりガラスには山水画のような浮き彫りがあってな
かなか凝っている。中にはいると、女湯との境に湯船があるタイプ。湯船は大きな半円形をしていて
同心円となっている。外側の円は左右に区切られていて、左が深め、右が浅めとなっている。内側の
円には右がわから入れるようになっていて、ちょっとした小部屋のようだ。中心にはギリシャ彫刻の
ような高さ50cmくらいの裸婦像がある。その裸婦が抱えた水瓶から湯が湧き出す仕組みになって
いる。内側の浴槽は壁にジェットが埋め込まれていて、水流となり水瓶から溢れた湯を全体に攪拌す
るようになっている。うまいものだ。同心円の左横に家庭用の浴槽くらいの四角い湯船がくっついて
いてこれはぬるめの薬草湯のよう。ジェットつき。やや離れたところに水風呂がある。水風呂の水は
壁のライオン口からこんこんと湧き出しているのはどこも同じだ。
女湯との境に湯船があるため、仕切りは途中までがタイルだが、上半分は半透明のガラスブロック
になっている。向こうの様子は全然うかがいしれないけれども、近づいたら肌の色ぐらいはわかるだ
ろうという透明度。このガラスのおかげでなんとなく明るく、開放感がある。しきりのうえには双方
を照らす蛍光灯がついているのだが、その台座の模様はアールヌーボー風だ。この銭湯、細かいと
ろでいろいろとおしゃれである。入り口を振り返ってみると一部に螺鈿のタイルが使われていて、
きらきらと光る。うーむ、やるなぁ。
先週のように浴室の真ん中に浴槽があるわけでなく、壁を背に入れるから落ち着く。ちなみ先客は2
人いたが、どちらも私が体を洗っているうちに出て行った。つまり今は貸切じょうたい。よけいに気
持ちがいい。このあたりは住宅街だが、マンションが多いからか、夜遅くに(21:30〜)来る人はほ
とんどないのだろう。それでも常連さんはいるようで、脱衣所には置き洗面器がたくさんあった。
今度は逆、浴室に背を向けて円の内側を向く。裸婦像からあふれるお湯を眺め、しきりの半透明
ガラスを眺めてと目のやり場あるので圧迫感がない。これも落ち着く。お湯は先週までの二軒に比
べると1〜2℃低くて、誰でも入りやすいだろう。ゆっくりつかるにはこれくらいがいいのかも。
熱いのも好きだけど。
湯上り、番台の上方にあるTVを眺めながら、20円投入してドライヤーを使う。飲み物コーナーに
はコーヒー牛乳はなかったが、なんと珍しい「ひやしあめ」があった。小学校のときに近所の商店街
の夏祭りで飲んで以来だなぁ。ん、おおたしかにしょうがの味。でもかなり今風な味付けで、きゅー
っと残る後味はひかえめな感じ。はちみつ入りと書いてあったけれど、どちらかというとはちみつが
主体でしょうがが隠し味にまわっているようだ。あの、きゅーっとした甘辛いのが飲みたかったな。
びんを返して、さいならーと外に出る。湯上りだけれど、汗をかかない。そう、もう秋風が吹いてい
るのだ。こんな風に気持ちいい帰り道をすごせる季節は短くて、あっという間にコートにくるまるよ
うになってしまうのだろうけれど。ほんのちょっとの時間、ちゃんと味わいたい。夏の終わりと秋の
はじまりのかけはしのような季節。
来週はゆっくり歩いてこようか。
- 2005/09/14(水)
今日は、第1〜3砲塔と、高角砲、機銃座、メインマスト、ファンネル(煙突)、後部艦橋を作成。
作成しながら、頭では「階名唱と移動ドと主和音」について、いかに順序だてて説明するかを検討し
ていた。このような「順序だて」は学生時代に実験レポートの考察を書く前によくやったものだ。ぎ
りぎりまで頭のなかで組み立てて、まとまったところで一気に栓を抜く。ダムの放流のように猛烈な
勢いで、一気呵成に文字に落とし込む。頭のなかで完成しているので、推敲なし、清書なし。
レポート担当教授に一度「なかなかよくできているが、字が汚いので書き直しなさい」といわれたこ
とがあった。結局、メサイア演奏会の当日の午後一に再提出にしにいったのを覚えている。字がきれ
いで損をすることはあまりないが、汚いと確実に損をするなぁと、思ったような思わなかったような。
さて、最上の建造に話を戻すと、こんなにたくさん作ったのに、今日は達成感が低い。なぜなら、
ファンネルをのぞくと、スケールが小さい部分ばかりだったからだ。全長28.6cmと聞くと割と大きい
ものだな、と思うかもしれないが、あくまで船体の大きさであって、そのうえの構造物のスケールは
驚くほどちんまいのだ。これが1/700というものなのか。論より証拠
 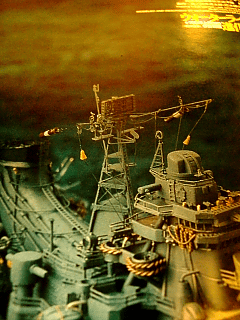
左:メインマストの素組み。右:MG誌の作例、メインマスト部の拡大。
メインマストの部品、0.5mmのシャーペンの芯なみである。これが扱いづらいのは想像できると思う
が難しいのは組み合わせである。ガンプラの部品などのように、パーツとパーツがぴたっとくっつ
いて、接着しなくてもOKなどということはありえない。艦船模型の場合、「任意の箇所」で点と
点、線と点を接着するなんてことがざらにある。実は、このマストの一部、部品をぽっきり折って
しまったのを修復している。接着剤をあらかじめ置き半田の要領で接着箇所に塗り、部品を適当に
差す。あとは接着剤の粘性に頼って角度をつけ、折れた部品と接合する。自分的には神業に近い作
業でえらく疲れてしまった。
できあがったマストは写真のごとく。ところが、右の作例写真をごらんいただきたい。よく見ると
マストの形状が違う。あきらかにキットの部品ではない!解説曰く「真鍮線とプラ板で自作」…。
そのうえ、吹流しやらアンテナ線、はしご、手すりまで作りこんである。はじめこの作例を見たと
きは1/700のサイズというものを実感していなかったので、根気のいる作業だなぁぐらいにしか思
っていなかったのだが、このサイズで、この接写で、このデティールを作ってしまうなんて、こ
れこそ人間業じゃない。呆れてしまう。
昔、心臓外科医の先生が、血管縫合の修行のため、ピンセットで針と糸を持ち、ティッシュペーパ
ーを棒状に縫合するという練習をしていたのをTVで見たことがある。ティッシュペーパーに何
のダメージもなく縫い合わせていくさまを見せられると、神業というより悪魔にだまされているん
じゃないかと思ったのを思い出した。それくらい信じられない技であった。それに近いなこれも。
というわけで、完全に素組みの状態である私の最上は、完成の暁にはなるべく遠目にみて、その
外観やシルエットを楽しむようにしてみたいと思っている。
皆さんは手先、器用ですか?
- 2005/09/13(火)
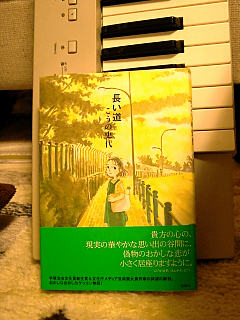
ACTION COMICS「長い道」、こうの史代著、双葉社刊。
この漫画と、あることのおかげで、今日はほんわかとあたたかく、こころ和む日となった。
さて、艦橋の組み立てに励むとしますかね。
- 2005/09/12(月)

海軍山D工廠にて建造中の最上。
過去、プラモデルを作るのは休みの日であった。それ以外の選択肢は考えられなかった。三角食べ
ができない私は、何かする作業を途中でやめるのはしょうにあわなくて、時間のあるときに一気に
作ってしまうのだった。過去とぎれながら作った例はほとんどない。あっても土、日にわけてとい
ったぐあいである。
しかし、今日思い立って、途中まで作ってみることにした。いや、途中という視点ではなく、毎日
少しずつここまでやってみようというポジティブな考えではじめてみた。平日のそれも23時をすぎ
てから、こんな趣味の作業をやるなんて、今までなら考えられなかったことだ。自分としては。
こういうことをやってみよう、できるんじゃない?と思えたのは、やはり夏コミに向けての本作り
で得た経験のおかげであろう。毎日少しずつの時間を捻出して、少しずつの作業を積み重ねて完成
を目指すということは、本作りに限らず、こういったことにも応用がきくことだったのだ。世間的
には至極当然のことなのかもしれないが、時間の使い方が下手な私にとって、この知見を得られた
ことは大きい。知見なんて大げさなものじゃないな。ちょっとした気づき程度かな。
じつは昨日、こんなものも買っていた。
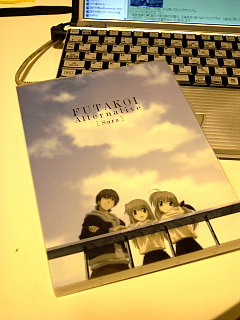
フタコイ・オルタナティブDVD-BOX I [Sara]。
2話収録、UMD付き、ポストカード付き、書き下ろしジャケット限定版が6500円。
VI巻のみ3話収録7800円。合計40300円。
DVD-BOX I [Sara]、1〜6話収録、15000円。II[Souju]、7〜13話収録、17500円。
合計32500円。
UMD(PSP用ディスク)なんていらないし、2006/01の完結まで待てないので、DVD-BOXを選択。
もう、大人なので「両方買う」とか、「ポストカードが欲しい」とか思ったりしない。
(ジャケットは欲しいのか?)
作品がいいんだから、余分なものはいらないのです。
- 2005/09/11(日)
淀川混声合唱団第17回定期演奏会@いずみホールの日がやってきた。昼ごろ着替えて出発しよう
としたら、ズボンがない。あれ、昨日どうしたっけか。...そういえばえらい汗をかいたので洗濯
して...干すの忘れていた!冬のズボンは充実しているのだが、夏はけるものがほとんどなくて、
一応替えは見つかったが、やはりいつものズボンがよい。リミットまで一時間ほどあるので、あ
わてて洗濯機の乾燥機モードに放り込む。1時間、微妙である。
若干、というかかなり冷たい部分を残したまま出発することに。まぁ、まだ暑かったので途中で
乾いた。志津屋でできたてのカツサンドを買い込み、阪急+環状線でいずみホールへ。ちょうど
開場時間。濡れたままがよくなかったのか、手洗いに駆け込む。
さて、定刻通り14時に開演した。プログラムは以下の通り。
1ステ、シェークスピアソング
2ステ、歌でめぐる中南米の旅
3ステ、Ubi Caritas et Amor
4ステ、思い出すために
最初にいうと、すべての演奏を聴き終えた時点での感想と、冷静に思い返してみた感想というの
はずいぶん違う。いやな言い方をすると、「終わりよければ」という感じを残した演奏会だった。
1ステ、シェークスピアの戯曲を題材にとった曲だけに、重々しく、どんよりと幻惑的な曲調の
ものばかりだったのだが、演奏がどうもあっさりしすぎているように感じる。部分部分の難しい
ところはよくやっているなーと思うこともあったが、全体としてそれらのパーツのつながりが見
えてしまうような気がした。曲を全体としてとらえ切れていないような。だから、曲のもつ魅力
を十分伝えきれずに終わったように思う。ホールの特性のせいか、響きとしてすばらしい部分が
あってもそれが音圧として伝わらない。どうも、調子が乗らない感じがつきまとい、終始不安の
残るはじまりだった。
2ステ、5月の東京カンタートで演奏した曲の再演。私自身、東京では一緒にオンステし、歌っ
た曲だけに非常に楽しみにしていたのだが、どうも1ステの感想をひきずっていたせいか、楽し
むことができない。5月よりももっと練り上げられた曲がきけるような気がしたのだが、ここで
もやはり音圧として響いてこない。あの暑い練習場で一緒に歌っていたときの方が、ずっといい
音楽できてたやん!と思うと、むしょうにもどかしくて仕方がなかった。
15分の休憩。このまま不完全燃焼のまま演奏会が終わってしまうような気持ちでブルーになる。
昨年、一昨年と比べて、パートごとの音のまとまりなどは進化しているように思えるのに、なぜ
こうにも伝わってくるものがないのか。考えてみてもこたえがない。
3ステ、Lauridsenの宗教曲。美しい旋律、パートの絡み合い、高まり。すべてできている。なの
に、わたしの胸に響いてこない。終始、目を閉じ、祈りながら聴いていたのだけれど、あと少し
で祈りが天にとどくというところで、絶対的に手が届かず天の恩寵に浴せないようなジレンマを
感じる。もっと、もっと欲しいねん!と心のなかで唱えていた。うまく拍手ができない。
そして、4ステ。寺山修司の詩による、信長貴富の曲。ピアノが高いテンションで始まり、合唱
の入りがくる...あ、違う。どうして、なんでこんなにも違うのか。歌っているみんなのテンショ
ンがだんだんと伝わってくる。ピアノに後押ししてもらったけれども、1曲目の序盤から確実に
音楽が外へ向かって解き放たれてくる。fのときも、pのときも、ppのときも音楽のすみずみ
に息が、意思が、いきわたっていると感じる。まったくとぎれることのない音楽が私の脈拍をど
んどんあげていく。そう欲しかったのはこの感覚。緊張して緊張して、解き放たれる喜び!
みんな、どうしてそれを3ステでできなかったんだよぉーと言いたくなる。このときに気づいた
のだ。テンションの高まりがないまま迎える和音にはなんのカタルシスもないということに。
和音の多くを占めるのはアーメンだ。アーメンという言葉は独立して存在しえない言葉だ。その
前の言葉をつよく肯定するための意思の表れだ。だから、何に対してわれわれはアーメンという
のかが伝わってこないと何の意味もない。3ステにただ曲の美しさ以上のものを感じられなかっ
たのは、その部分だったのだと思う。精神論ではなく、音楽の構造を全体としてとらえる視点が
弱かったように思うのだ。
さて、高いテンションを維持したまま4ステは最終曲に進む。ああ、なんて強くてきれいなんだ
ろうか。音楽が生きている。終わったとき、みんなの音楽がからだにしみこんでいくのを待って
から、やっとすがすがしく、思い切りの拍手をすることができた。
アンコールはやはりシェナンドだった。中南米の曲で唯一外されていたから。男声と女声が舞台
で向かいあって並び、女声が、男声と客席に歌いかける。わたしはじっとそれを見つめていた。
恥ずかしいという思いはなかった。ただ、歌いかけるあなたと、受け取るわたしがいる。舞台と
客席がとても強くてあたたかいものでつながれているような気がした。女声の歌に、男声のユニ
ゾンがこたえる。ああ、こんなにきれいな男声のユニゾンはないよ、ほんとに。何の迷いもおそ
れもない、照れもない、まっすぐな男声のユニゾンだ。そして、女声と男声が歩みより合唱とな
った。もうそのあとのことは言葉でうまく語ることができない。
曲が終わったとき、顔を手で覆って、そしてなぜだか手をあわせていた。圧倒的な感情が押し寄
せてくるのをゆっくりと、ゆっくりと整理して、鎮めていった。何か、何か、誰か、誰かにいま
ここに、この音楽があることを、精一杯感謝したかった。ありがとうといいたかった。
もう一曲のアンコールは「やさしさに包まれたなら」。舞台のあちこちに思い思いにちらばった
みんなが、すがすがしくもやさしい表情で歌ってくれた。感極まって、不安定になっていた心を
ときほぐしてくれたように思う。
それにしても、どうしてこれほどまでにステージごと、1,2,3と4以降で差が出てしまった
のだろうか。不思議でならない。終演後にメンバーと話してみて、みんなもそれを理解していて
課題も何か?というものはわかっているらしい。ならば、ここで私があれこれ詮索する必要はな
いだろうと思う。
気持ちのいい時間をすごさせてくれてありがとう。
いまはそれだけ。
<おまけ>
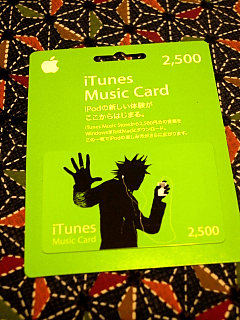
帰りにヨドバシでiTunes Music Cardを購入。これでiTunesをつかって曲を買うことができる。
買った曲はもちろん、荒井由実「やさしさに包まれたなら」と、「ルージュの伝言」。この
2曲はセットで聞かないと落ち着かないのだ。『魔女宅』世代としてはね。
帰宅してから、急に頭痛がしてきた。しんどいのだけれど、どうしても今書いておきたくて
かけるだけ書いてみた。おかしなところがあっても許してください。
昼間、頭痛薬かっときゃよかったなぁ。
寝て直します。
- 2005/09/10(土)
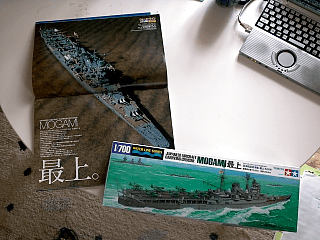
1/700WATER LINE SERIES No.341 日本航空巡洋艦 最上<もがみ>(TAMIYA製)
作例写真:月刊モデルグラフィックス2003年4月号より。製作、大木清太郎氏。
モデラーと名乗るはおこがましくとも、さりとて一度燃え上がったわずかばかりの模型作り魂を、
容易に吹き消すことあたわず。
簡単に言うと、「ひさしぶりにプラモデルが作りたくなった」ということ。さっそく、模型屋に向
かう。ガンプラならば、談(本屋)の3階に行けばあるのだが、今回作りたいのは艦船模型である
からして、単にプラモデルを扱っている店に行ってもまず見つからないのはわかっている。うちか
ら比較的近い模型屋ということで八条口方面の店に向かう。
出張先に近いため前は何度も通ったことのある店。入ったことは一度もない。ショーウィンドウを
見ると、一応フルハル(船底まで再現されている)の艦艇模型が飾ってある。だが、まわりはほと
んどが鉄道模型。しばし、HOゲージに目を奪われるが、旗色は悪そうと思いながら入店。...7
割は鉄道であとはガンプラと航空と車が一割ずつか。お、一箱だけ、ほんとに一箱だけ艦船がある。
なんとハセガワの三笠であった。MGの記事にもあったが、この三笠のモデルは普段模型を作らな
い人、艦船模型を作ったことのない人がかなり買っているそうで、もしかしたらそういう事情でこ
こにもぽつんとおかれていたのかもしれない。
箱を開けてみて、そのスケールの大きさに驚き「買ってしまおうか」とも思ったのであるが、はじ
めて艦船模型を作るには1/350は大きすぎてハードルが高いように思えた。それにこの世界の定番
ともいえるウォーターラインモデル(吃水線より上のみ再現)をひとつも見ないで決めるのはどう
かとも思い踏みとどまった。それに7140円もするしなぁ。
あと思いつく模型屋は三条商店街の京都模型くらいだ。堀川を北上。よくよく考えるとうちから
八条にいくのと、三条にいくのとでは、距離にして二条分くらい三条のほうが近いのだった。はじ
めから京都模型にいっときゃよかった。で、さすがは老舗。ちゃんとウォータラインシリーズが
どーんと積まれているではないか。それも入り口に近いところに。
あらかじめ予習して、だいたいどういう艦艇がいいかは目星をつけていた。(たまたま2003年に買
っていたMG誌の特集がウォーターラインシリーズだったので。いや、艦船特集だったから買った
のかもしれない。)戦艦のように艦橋が高いのが好みなので、ハセガワの戦艦伊勢か日向がいいか
とも思ったのだが、なんといっても作例の最上が抜群にかっこよかったので結局はそちらにした。
航空巡洋艦といっても、もとは大型軽巡洋艦なので連装砲塔が前面に三基もついていて、飛行甲板
と、ブリッジ部と、それらが絶妙なバランスで配置されている姿は、美しいとさえ言える。
懐古趣味というのではないけれど、そこには現行艦の主流であるイージス艦には持ち得ない、艦に
対する何かしらの思い入れのようなものを想起させるようだ。戦史には詳しくないので、艦船の
たどった運命であるとか、戦果のようなものにロマンチシズムを感じることはほとんどない。どち
らかというと、造形いや設計というべきものに心魅かれてやまない。たとえ軍艦であっても、なん
らかの美意識をもって設計されているように思えてならないのだ。あるいはそれは近代戦の初期の
戦略・戦術ゆえに生み出された必然の設計なのもしれないが、それでもやはりどこかに巨大建造物
をつくるならばこうありたいと願う設計者達の意思があったのではないだろうか。
最新鋭の機器を搭載し、戦略的にもっとも重要な位置づけにあるイージス艦は、そういった思い入
れといったものを一切排除し、純粋に兵器としての要求仕様を満たした結果こうなりました、とい
うようなデザインをしているように思う。実物を見たら、もしかしたらかっこいいと思うかもしれ
ないが、美しいとは思えないかもしれないような気がする。ひらたくという「あのデザインは好き
じゃない」。
われわれは実際に兵器を運用する立場にあるものではない。趣味として造形を楽しむ人間だ。だか
ら艦の形状のよしあしにこだわるのはとても重要なことなのだ。そこのところだけわかっていただ
けると、模型好きとしては嬉しかったりする。
さて、あしたは淀川混声合唱団の定期演奏会。ばっちり体調整えて、しっかりゆったり楽しもう。
え、出演しないのかって?どうもここのところ多数のひとに誤解されているのであるが、私はYK
のメンバーではないのだ。YKの演奏をこころから楽しみ、音楽を分かち合う聴衆の一人なのだ。
一緒に歌う楽しさ、嬉しさ、喜びもある。でも、それを聴き、楽しみ、伝え、話す喜びもある。
それらはすくなくとも私のなかでは等価で、どちらも大切なことだ。
思いを伝える者と、受け取る者がいるから音楽は音楽でいられる、と思っている。
んー、言葉をこねくりまわしているようで、しっくりこない。
もっと簡単に。
あなたの歌がききたいから、わたしはここにいる。
これでよし。
- 2005/09/09(金)
BK練習、宴会より帰宅して、水を飲む。ちょっと物足りないので、ストックしている伊藤園の
「一日分の野菜」を飲んでみる。と、ふと最近よく考えていることを思い出す。こういう一日分
と銘打ったものはいつ飲むのが一番よいのだろうか。もし夜中に飲んでしまって、日付がかわる
と効果がリセットされたりしたらいやだ。あるいは飲んでから何時間分は一日となるのだろうか。
人間の身体は機械とは違うから、いつ飲んでも効果は同じということはないように思う。
同様に、いわゆるサプリメントなんかも一日何粒と書いてあるだけで、朝食後飲めとか、食間に
飲めといったことは書いていない。医者でももらう薬であれば、毎食後などの指示があるのになぁ。
逆にそういった指示を書いたら駄目なのだろうか。薬事法などの関係で。
最近、わたしはそういう系統のものはすべて朝食後に飲むようにしている。朝食というのは吸収が
早いような気がして、ほかのものもそれだけ即効性があるのではないかと思っている。全然根拠の
ない話ではなくて、朝、頭痛がひどいときに朝食を食べてから頭痛薬を飲むと、会社につく45分
後くらいにはくすりが効き始めているのが実感できて、デスクにつくころには痛みが完全に治まっ
ているということがよくある。(逆に仕事中に頭痛になった場合、昼食後や、夕食後に飲んでもな
かなか痛みがひかない。頭痛の質の違いというものもあるのだろうけれど。)
いまは、バイタリティと集中力の維持のためにききそうな亜鉛とDHAを飲んでいる。ほんとうは
食事で摂取できれば一番いいんだけれど。とりあえず、効いているような気がしているのでつづけ
てみようと思っている。コンビニで売っているのは2週間分。切れるとまた、つぎに買うまでにイ
ンターバルがあきそうな予感がしているが、ちゃんと続けてみよう、うん。
- 2005/09/08(木)
今週も銭湯へ。自転車で3分以内のところに2軒あり、まずは烏丸松原に程近い「薬師湯」へ。
あいにくこの4日間ほど臨時休業との貼り紙。とって返して今度は西へ。西洞院高辻東入ル、一筋
目下ルにある「白山湯」を目指す。外見はもだんな感じ、自転車が多く九時半をまわっていたが、
お客さんは多いようだ。ちょうど、小学生4人組が出て行ったところで、「錦湯」とは客層にかな
り違いがある。
入り口はひとつで、正面に下駄箱、右手にあがると番台がある。談話スペースのような感じで、椅
子が並び、おおアイスクリームボックスと、飲み物ボックスもちゃんとある。談話スペースに男女
の入り口が並んでいて、ここで分かれるようになっている。完全に別々かと思って脱衣場に入ると
普通の銭湯と同じように天井でつながっていて、湯船にはちゃんと湯気抜きがある。昔風の銭湯を
改装したのだろう。
浴槽は、なんと浴室の中央に円形の泡風呂と、同じ円形の普通湯が8の字に並んでいる。そして奥
にサウナ、そのとなりにライオンの口から滝が流れる水風呂(地下水と書いてある)。さらにその
隣に薬湯がある。そして入り口に一番ちかいところに電気湯(多分)。最初泡風呂につかったがな
んとなく落ち着かない。広い空間の真ん中というのはそういうもので人間の特性としてはやはり、
端っこに行きたくなるもの。となりの普通湯は熱めで、浴槽も深めで腰掛けられるタイプだったの
でちょっと落ち着いた。あとは冷え性に効くという薬湯でゆるゆるすごす。
風呂上りには待望のフルーツ牛乳を飲む。ところがである。あの牛乳瓶のふたをあけるツール(緑
いろのとってに太い針、丸い安全環みたいなのがついたやつ)がないのだー。番台にもおいていな
いみたいで、しかたなく手動であけることに...。案の定、ふたが皮一枚でめくれてしまう。私は
深爪なんで、こういうの苦手なのだ。さいごはもっとも情けない方法、つまりふたを内側におとし
こんで何とかあけることに成功したのだった。もっとスマートに飲みたかったなぁ。
ちょっと人が多いので、あまりゆっくりできない感じ。来週は薬師湯にいってみようと思う。
帰宅後、コダーイの「マトラの風」練習。
その後、ネットで本をさがすことにした。
ほしい本があるのである。正確には雑誌の増刊号で2003年発行のもの。バックナンバーをおい
ているジュンク堂でこの前さがしたのだが、その号だけない。人気なのである。実は一冊もってい
るのだけれど、事情があってもう一冊欲しい。(そういう人がいるから、見つからないのか?)
昨日、一度アマゾンや、bk1といったネット書店で検索をかけたのだが、どうやら版元で売り切れ
ているらしい。これはもう市中在庫を探して歩くしかなさそうだ。アマゾンだと中古をオークショ
ンに出品していることがあるのだが、この本の場合1300円の定価に2700円がついていた。
おお、さすがだなぁと妙なところに感心してしまう。まぁ、人気はあるけれども世間一般に流行し
ている雑誌ではないから、バックナンバーを丹念にさがせばみつかるはずで、わざわざ倍額だすの
もどうかと思った。
そういうわけでバックナンバーを置いてある店を検索してみた。すると、古書店の目録がヒットし
たのである。ほう、この雑誌なら古書店にあってもおかしくない。むしろ、新刊書店よりも、そう
いう雰囲気とよくあっている。めだたず、さわがす、どこかふんわりとあたかみのある装丁が目に
うかぶ、って一冊は手元にあるのだから、まざまざとイメージできるんだけれども。
欲しい増刊号を含めて、100冊以上のバックナンバー。どれも1冊ずつの入荷。目録の更新が7
月21日なので、残っているかどうか心配である。価格は1000円。おそらく、増刊号の特集で
分類されたならば、狭い古書業界、本好きの道のこと、一日持つかというところだろうが、幸いに
も雑誌名で分類されているから望みはあるかもしれない。
東京は豪徳寺にある玄華堂というお店のオンラインショップである。さっそく注文する。店舗紹介
を見ると、思想書、美術書、建築書、美術展カタログなどが中心の様子で、もろ私の好みだ。この
秋に「印刷解体」を見に行く前後にでも寄ってみようかな。(え、秋は忙しいのではないのか?
って?まぁ、その通りなんだけれども、ほんのわずかな隙間というものはあるのですよ。)
雑誌の名前はユリイカ(Eureka)。
さて、わたしが探しいているのはどの増刊号か、おわかりになるだろうか。
ヒントはなし。例によってあたっても何もでないのだが。
- 2005/09/07(水)

月刊モデルグラフィックス10月号より、ハセガワ1/350戦艦三笠。
山Dと船のかかわりをまとめてみよう。
幼年期
・家族旅行でいった城之崎温泉で遊覧船に乗った記憶あり。
小学生時代
・修学旅行にて伊勢。「ぶらじる丸」にて昼食の思い出。
・現役就航船に乗船した記憶がまったくない。このころは車に酔うのに忙しかったのかも知れぬ。
中学生時代
・中学3年夏、青函博のため臨時復帰していた青函連絡船に往路・復路とも乗船。
・往路では停泊中の船内(ブリッジ、車両甲板、機関室)を見学させてもらった。
・復路では青森港に停泊中の船内に宿泊。翌朝、今はなき特急白鳥にて帰京。
高校時代
・高校2年夏、瀬戸内航路にて南港〜宮崎。真夏の夜の星空に心底感動した。
・宮崎より陸路、鹿児島を経て、海路にて屋久島へ。4時間の船旅。ほとんど寝ることで船酔い回避。
・復路は、高速船で約1時間半であった。
大学時代
・2回生夏、グリー演奏旅行。函館より大間まで連絡船。大時化のため、全員半死半生状態。
・弘前にて解散後、大間か大湊かどちらかから室蘭まで連絡船(いまはもうない航路かと)。
・異例の冷夏のなか道南を旅行。小樽〜敦賀航路にて帰京。
・2回生冬、香港。スターフェリー乗船。
・3回生夏、グリー演奏旅行。瀬戸内航路再び。神戸〜別府航路。
院生時代
・M1秋、南港〜足摺岬航路。エンジン音が異常にうるさいため寝るのは至難の技であった。
・M1冬、大分空港〜大分港。国内唯一のホバークラフト航路。舗装されていない道路を、トラックの
荷台に乗せられて移動しているような感覚だった。
・M2夏、仙台〜名古屋航路。乳頭温泉郷へ行った帰りに利用。カプセル型の個室。外洋のため
かなり揺れる。東京湾近辺は夜も灯りがこうこうと点り、星空などまるで仰げず。
・M2春、天草〜八代?(記憶があいまい)をフェリーで。
社会人
・NCにて合唱コンクール全国大会in広島。宮島航路。朝、心房細動になるも観光。死に掛ける。
・二代目南極観測船ふじ(名古屋港)乗船。船内見学。
・初代南極観測船宗谷(船の科学館)乗船。船内見学。停泊中なのになぜかはげしく酔う。
(ふじは船体固定されていたので揺れないが、宗谷は係留に近い状態だったためやや揺れる。)
・氷川丸(横浜港)乗船。船内見学。
・琴電を撮るため、四国上陸。帰路、高松〜宇野航路。宇野線は本数が少なくて参った。
・日の出桟橋〜浅草、隅田川観光水上バス乗船。橋の写真ばかり撮影。
・97年夏〜2005年夏まで、毎年夏・冬、有明〜日の出桟橋水上バス乗船。
以上が現在に至る履歴である。ここまで書くのに一時間近くかかってしまった。
こうやってみてみると、酔い体質にもかかわらず、かなり果敢に船に挑んでいることがわかる。
実際、船酔いした経験は意外と少なく、周到な準備(飲むタイプの酔い止めアンプルを服用)
のうえ乗船することがほとんどであった。車と違って、自由に動き回れる場所が多いのと、
なにより、甲板で当たる風が気持ちよいので好きである。
さて、船の乗船はこんなに多いのに、艦には一度も乗ったことがない。皆さんは船長と艦長ってなに
が違うかご存知だろうか。船長は一般の船の長、艦長は軍艦の長のことである。そう、艦とは軍事船
のことなのだ。(私はネモ船長に教わった。)
男子たるもの、一度は軍艦にあこがれるもの。であるが、軍艦に乗船する機会などそうそうあるはず
もなく、それどころか目にすることすら難しい。(昔、テムズ川に戦艦が停泊?定置されているのを
見たが乗船できず。)であるが、写真の三笠は、横須賀に現存し、船内外を見学することができる。
もちろん日露戦争時代、つまり100年前の艦だから、現役ではないがそれども立派な軍艦なので
ある。ああ、行きたいな横須賀。足を伸ばせば、横須賀基地も見れるしなぁ。
でも、この秋は無理だねぇ。冬行ったら、さぶいだろうねぇ。
ついでに書くなら、かみちゅの紹介でちょこっと書いたのだが、尾道には今、戦艦大和の1/1映画セッ
トが<停泊>中なのだ。こちらはこの秋までの限定。セットだけど見たいなぁ。
でも、合宿があるから無理だねぇ。
・・・そうだ!金曜日の夜に出て、土曜日の夕方帰ってくればいいのだ。むむむ、ほんとにやるか?
かみちゅ&大和ツアー!
追記:
今調べてみると、来年3月まで公開!やっほーい。聞き間違いか延長か。どちらにしろよかった。
- 2005/09/06(火)
ネットで買い物をすると、発送後に荷物問い合わせ番号というものが届いて、いまどういうステータス
なのかがわかるというシステムがある。この暗室でも以前Timbak2を米国から輸入したときに、UPS
の問い合わせサービスを使って荷物を追跡した話を書いた。
きょう、おなじようにある買い物の番号が届いたので、さっそく運送会社のHPで番号を入力した。
「番号をお確かめください」...あれ?ん、ん、あそうか。間違って商品の受付番号を入力していた
のだ。気を取り直して、今度は確かに配送番号をカット&ペーストで入力。
「番号をお確かめください」...なんでやねん!わたしはコンピュータなどのシステムに何度も同じ
要求をされると、きれてしまうのたちなのだ。
で、気を取り直してもう一度。やはり変わらぬ。で、すこし考えて、あることをしたら、きちんと
「○○店発送、輸送中。」というステータスが表示された。あることって何かおわかりになるだろ
うか。これはあなたの身にも起こりうることかもしれないので、考えてみて欲しい。こたえは5秒
後に。数字はたとえばこんなの。→"00002354893412"
5秒経ちました。正解は、数字の頭についている0を全部とって入力する。これはプログラミング
であるとか、システム系の仕事をしてる人なら、わりと慣れっこな問題かもしれないが、普通はな
かなか気づかないもの。わたしは、つい最近仕事で、数字のどのビットに最初に1が立つか?とい
うルーチンを書いていたので、ひらめいた次第。
だって、送り主が送ってくる番号が間違ってるだなんて誰も普通は思わない。いや、正確にはまち
がっていないのかもしれないし、やっぱり間違っているのかもしれない。すべては頭に0をつけた
0が有効かどうかによる。送り主が送った番号は14桁であるが、これは送り主というよりも、
配送業者が送り主に通知した番号であろう。この処理が行われるときの処理は「14桁」でおこな
われていたはずだ。ところが、おなじ配送業者のHPのシステムの説明を読むと、10桁あるいは
12桁の番号をお入れくださいとある。
問題がいくつかある。ひとつは当然ながら、同じ会社のなかなのに、処理番号の桁が統一されてい
ないこと。配送業者としては10桁の番号を伝えたかったが、誤って伝えたということも考えられ
るが、流通業者としてそれはあってはいけないことだろう。あるいは送り主側が14桁で処理する
システムだったかもしれない。この場合でも、10ないし、12桁で扱って欲しいという説明がな
されるべきであったと思う。
もうひとつ。HPのシステムのインターフェースである。10桁、ないし12桁の数字が入力され
たときの処理というものは、誰でもしっかり考える。だが、本当は正しい入力がなされなかったと
きの処理こそ、十分に注意を払うべきなのだ。14桁の入力があった場合、12桁、あるいは10
桁まで有意な数字が現れるまで数字をカットするということも方式としては考えられる。たしかに
客にとっては便利だ。しかし、この方法は入力されたものを、入力者の意思とは無関係に加工する
といった点でやや危険である。入力者が00という数字を有意な番号として入力していても、シス
テムがそれを無意と判断してしまうと、それ以降、入力者の想定外の処理が進む可能性があるから
だ。では、どうするのがよいか。「14桁の入力は無効、10、12桁になるように頭の0をとっ
てから入力してほしい」というメッセージを返すのが有効ではないだろうか。(ほかにもあると思
うけれど)
「番号をお確かめください」は確かに正しいけれども、ほとんどの場合、問題解決の助けにならな
い。反面、この方法は開発者にとっては大変楽なのである。流通とはいえ、リテールを扱う部門な
らば、ホームページの画面こそ接客の窓口である。そこではあらゆる入力を想定するべきだ。しか
し企業として妥協点は探らないといけない。ならば、なにが原因で受け付けないか?を示すことは
客に納得してもらうというプロセスを踏むことで、客としては手間がかかっても、いきなり「なん
でやねん!」となることはないはすだ。
もうひとつ問題がある。0を有意とみなすか、そうでないかという問題である。2005年09月
と2005年9月は同じものか、違うものかといえばわかってもらえるだろうか。入力を促すシス
テムを作る場合、この問題のケアを忘れることが多い。単位や場面によって有意かどうかは変わる
ので、それを把握することは大変重要なのである。09と9の場合、単にカレンダーなどであった
ら、0は無意味である。しかし、同じ月を表していてもクレジットカードの有効期限の場合、0は
有意である。(正確には桁数の問題だが)09と入力すべきところで9を入力してはエラーが返っ
てくるはずだ。
小中学校、いや高校になっても、大学でも理系でなければ、「0」とは何か?ということについて
概念や、哲学の話をしてくれる授業は存在しないはずだ。実生活のなかで無関係に見えて、今回の
例のように実は深く関係していることが多いのにもかかわらず。数学というものを教えるときに、
計算式から入るのではなく、こういった概念から入れば、数学嫌いだといか、むやみやたらに毛ぎ
らいする人は減るのではないだろうか。できるできない、ではなく、なぜそうなのかというプロセ
スが面白いと感じられればいいのだけれど。単純にできるできないを勝負するひとや、答えが一つ
しかないから好きという人には退屈で、実はそういう種類のひとが多いのかもしれない。教える側
に。
- 2005/09/05(月)

ぎゃぼー。ついに出た。
のだめカンタービレSelection CD Book。のだめと千秋の出会いの曲であるベートーベンのピアノソナ
タ悲愴から、Sオケで演奏したラプソティインブルー、千秋の卒業演奏の村の居酒屋での踊り、そし
て、指揮者コンクールの「ティルオイゲンシュピーゲルの愉快ないたずら」という具合に、作中に登場
した曲の数々がセレクション!
わたしは、あまりクラシックに詳しくないのであるが、のだめに登場する曲というのはいわゆる、ほん
とに素人でも知っているような有名曲よりも、ちょと大向こう受けするような感じの曲が多いような気
がする。(あくまで気がするだけ。せめないで〜)そのためか、これっていったいどんな曲なんやろう
とよく思っていた。今回のセレクションはそんな読者の思いを汲み取ったかのように、メジャー(長調
ではない)、マイナー(私的に)とりまぜてのCDだったので、なんとなく嬉しい。
モーツァルトのオーボエ協奏曲なんてのも初めて聞いたのであるが、非常にいいですな。作中に登場
する『いぶし銀の武士』である、くろきんこと黒木君がのだめを想ってピンク色の演奏をするシーン
が、この曲を聞いたことでより鮮明にイメージできるようになった。ああ、そうそう初回特典のしお
りのデザインは写真の通り、くろきんであった。
もうひとつ、このCDのとりは海老原大作の「ロンド・トッカータ」。マラドーナピアノコンクールで
課題曲になっていたあの曲が!なんとほんとに作曲されてしまうとは。この曲、解説を読むとなおおも
しろい。和声や、構成する音素が、のだめや、千秋の名前からとられているそうなのだ。NODAME→
ADEAの完全音程のみ和音や、Chiaki Shinichi→CとEs(S)といった具合で、さらに主題はA,C,Es,H,
Cis,Aisと、千秋の名前のアナグラムになっている。懲りすぎ。これを作曲した大澤徹訓という人、
すごいオタクだ...。曲そのものは、古典風の曲名とはかなりちがって、すごい現代曲でジャズのよう
な感じ。かとおもうと、すごく根暗な旋律がつづいたり。まるで、調子よくピアノを弾いていたら、
千秋にいじめられて、いじけるのだめのようであった。
****
帰宅時、一階の郵便受けを見ると隣の部屋の郵便が混じっていた。内側からは入れられない仕組み
なのでいったん外にでて、隣の郵便受けに差し込んだ。そのとき目に付いたものがある。私の部屋
の真下の部屋の郵便受けになにやら紙に書いたメッセージが貼ってあるのだ。曰く「郵便職員の方
へ○号室あての料金後納郵便やDMは入れないでください。返送をお願いします。」...すごい、
こんなお願い、聞いてくれるのだろうか。いや、それよりも気になったのが、字だ。あきらかに女性
の文字。だが、階下に住んでいるのは男性なのだ。(一度、夜中に騒いでたので注意しにいったので
知ってる)ん、とすると、これを書いたのは...前の住人ではないだろうか。たしか女性だった。
(面識はなかったが、時々うたの練習をする声が聞こえた)
もし、もしですよ、前の住人が書いたのがそのままだったとして、郵便職員がお願いを聞いてくれた
としたら、現在の住人のもとにはDMが一切届いていないということになるのではないか。料金後納
も。この貼り紙にきづいていなかったとしたら、相当不思議に思うのではないか。なぜ一通のDMが
こないのか。DMだけならいいが、料金後納というだけなら、必ずしもDMとは限らないかもしれな
い。大事な書類や証書が届かないとなると困るだろう。
このマンションのような郵便受けの場合、内側は毎日みるとしても、外側なんてめったに見るもので
はない。入り口の横のちょっと奥まったところにあるので、ほとんど行く機会はないのだ。だから、
まえの人が何か貼ってたしてもきづかないという可能性は十分ある。わたし自身も引っ越した当初以
来である、こうやって外から見たのは。
自分のまったく伺いしれないところで、いつのまにか自分にかかわることが処理されている。これっ
て非常に怖いことだ。郵便受けに名前を書かない賃貸住宅特有の事象が、この怖さを生む原因の
一つになっているように思う。悪意がないだけに、よけいにわからないのかもしれないな。
知ってて利用してるという考えもないではないが...まぁわざわざ聞きにいくわけにもいかないし、
本人の字という可能性もある。何より、そうでないにしても、騒音野郎に親切に教えてやる義理は
ないのである。(教えるにしても、いったいなんていうのか。そちらのほうが難しいな。)
自分のテリトリーの事は自分で気づき、自分で守り、管理する。マンション生活ではそれが必要な
のだと思った次第。
- 2005/09/04(日)
昨日の日付間違えてました。
ほんじつは、更新をお休みします。すいません。
体調が悪いとかではなく、すごく眠たいので。はい。
では、おやすみなさい。
- 2005/09/03(土)

NC練習前に梅田と天六の間にある自転車ショップへ行き、グローブとスペーサを買う。わたしの
自転車は標準状態でややハンドルの位置が低いため、前傾姿勢がきつめである。そのため、ハンド
ルを持つ手にやや負担がかかるのが気になっていた。サドルの高さ、前後を調整することで改善は
できたが、もうあと少し調整できないか?と思い、ハンドル位置を引き上げることにした。
スペーサとは、ハンドルを取り付けているヘッドパーツとハンドルとの間に挟みこんで高さを調節
するパーツのこと。サドルのように上下位置を動かすことのできるハンドルもあるが、多くのスポ
ーツタイプの自転車はスペーサを使うのが一般的のようだ。で、店に入ってパーツをさがすとすぐ
に見つかる。単なる丸い輪っかなので逆に目立つ。いろいろ調節できるよう1cmを2つと、0.5
cmを1つ選んだのだが、よーく説明書きをみると、「オーバーサイズ」「○○.○mm」と径が二
種類ある...これは困った。自転車の部品って、ほぼ共通仕様だと思っていたのだけれど。
こういうときは素直に店員さんに聞く。自分の自転車のメーカーとモデル(モデル名と年式)をつ
げると、たぶんオーバーサイズでしょうとのこと。そのあとすぐに店内の展示モデルで確認してき
てくれたので確定した。これでよし。
つぎは、グローブ。ハンドリングしやすくなると、手への負担が減るだろうと思って。実際前傾
姿勢での長時間走行では、グリップの滑り止めが手のひらでこすれて痛いことがあったのだ。こ
れが改善されれば、もっと楽しくなるに違いない。で、グローブコーナーに行くと、ああ結構点
数があるものだ。まず手袋タイプと、指先出しタイプに分かれる。まだまだ暑いし指先の操作が
感覚が失われるのがいやなので、指だしタイプに。冬はどうせ普通の手袋をすることだし。あと
は実際にはめたときにしっくりくるか、と外しやすいかで選んだ。軽量化や通気性を優先させす
ぎるとどうしても素材優先になってしまい、その分つけ心地が犠牲になるように感じた。
意外なことにいくつかの専業メーカーのものよりも、アディダス製のものがもっとも手になじん
で違和感が少なかった。自転車用のアパレルまで手を伸ばしていたとは知らなかったが、細かい
部分のつくり(縫製や、手のひらのクッション)が丁寧で、抜かりがないというか、ブランドの
名前は伊達ではないと知った。(ちなみに値段はほかと同じ程度で、高くない。)
NC練習後、四条烏丸にとめておいた自転車で帰宅する際にさっそく使用。お、これはなかなか。
当然手のひらは痛くないし、ハンドルとしっかり固定されて手首に負担がかからない。パッドの
厚みの分だけ、手の位置が後ろにさがり、身体を起こすがことができるので、胸郭が楽だ。ホン
の数mm程度の違いなのに、歴然とした差が表れるものなのだなぁ。もともとグローブをつけて運
転することが前提なんじゃないのか思うほどだ。あれか、モビルスーツに搭乗するときはパイロ
ットスーツを着用しないと、身体がうまく固定できないというのと同じなのだろう。(わかりに
くい例え?)
スペーサの取り付けは明日午前中にやることにしたが、グローブの件もあるのでその効果のほど
が楽しみである。私は自動車の趣味はないけれども、自動車好きのひとがパーツをチューンアッ
プしていく理由がわかったように思う。自転車も同じメカモノだから、実はそのあたりの気持ち
は一緒なのだな多分。
さて、いまこの文章はグローブをつけながら書いている。あんまりに手にフィットしているもん
だから外しがたい...。(タイプするのに最適なグローブってあったらすごいなぁ。)
おまけコーナー

梅田へ戻る道すがら。
梅田〜天六を結ぶ大通りを一筋下がると、そこは喧騒とはかけ離れて、どこか昔の商店街の雰囲
気が残っている。むしょうに路上観察したくなる、そしておそらくしがいのある町並みだ。人通
りは少ないのに日用品の店だけでなく、雑貨屋やアパレルショップも点在している。ふらっと、
立ち寄る人がいるのだろうな。ゆっくりした買い物ができそうだ。
- 2005/09/02(金)
きょうは日中も、日が暮れてからもえらい暑くて、汗のかき通しだった。ふだん、通勤のときは
ワイシャツのしたに、うすい綿のシャツをきているだけれど、夏場は必ず替えをもっていく。会社
について、作業服に着替えるときにもうその替えをきるのだ。家を出て、駅まで行き、電車にのっ
ているだけならば、汗なんてほとんどかかないのだが、最寄駅から会社までのわずか10分足らず
の間にかく汗の量がすごいのだ。なんで、こんなにというほど。前にも書いたと思うが、この区間
には遮蔽物がまったくないため、日差しをもろにくらうためだ。
で、着替えたあとに居室に赴き、パソコンの電源を入れる。じつはこの間にももうれつに汗がふき
だしている。これは他のひとにはなくて、汗かきの私だからかもしれない。なんというか、クール
ダウンするためにかく汗というか、一度着替えてほっとしたあとに、身体の内部からもっと冷やそ
うとする感じで汗をかく。だったら着替えたときにしばらく休んでればいいやんと思わないでもな
いが、ほっとしたときにどうしても出るものなので、ロッカー室にいようと、居室にいようと汗を
かくのに変わりはないように思う。
この汗が冷えて、お腹が痛くなったりすることがよくあるので、この時点でもう一度着替えたいく
らいである。そんなことをしていると、洗濯が追いつかなくなるのでなんとか一日2枚ですごして
いるのが現状である。
単に汗かきというよりも、心肺機能の問題で身体を適温に保つ機構がやや弱いのだろうなと思う。
ゆっくり時間をかけて冷やさざるをえないのだ。ひとより多くの汗を、長い時間かけてかくのはそ
ういう理屈なんではないだろうか。
本日は、純粋に暑かったので、いつもの二割増しは汗をかいたような気がする。今日の私、汗臭か
ったんじゃないだろうか。制汗スプレーとか持ち歩いたほうがいいのかなと、思うときもあるのだ
けれど、汗をかくということ自体は、冷却する必要があるからで、それを抑えてしまうと、熱中症
になって倒れてしまうんじゃないかとも思って、こわくて使えないのだった。
- 2005/09/01(木)
銭湯に行ってきた。温泉とか、スーパーのつかない、普通の街中の銭湯。
昨日、かなり根をつめて仕事でプログラミングをしていたせいか、頭が重い。やや遅めに出勤。
そんな状態であるから、今日の進捗は亀のごとくそろりそろり。ここでついつい雑なことをする
と、結局後で大変になるので、前半は昨日とは違う仕事をしてゆく。ああ、こうやって見ると、
いろいろと未着手の仕事が多いことであるよ。
しかし、こんな感じでは明日もこの体調を引きずるなぁと思い、何か帰宅後にリフレッシュでき
る方法を考える。家とは違う環境で開放感があって、疲れも取れるところ…、で思いついたのが
銭湯だった。
銭湯、じつはうちの近く、四条の近辺のような繁華街のまちなかに、結構残っているのだ。そん
んななかで一番街中に近いところに行く。堺町錦下ルの、ずばり「錦湯」。三層の木造作りの正
面がいかにも銭湯という感じだ!それにしても、銭湯に行くのは何年ぶりか。確か、前にいった
のは13年前、それも函館だった。グリーの演奏旅行で、旧ロシア領事館のようなところに宿泊
したのだが、ユースホステルよりも規模の小さいところで、当然男60人が一時に入れるような
風呂はなかった。そこで、宿から近場の銭湯5〜6軒を紹介されて、めいめい出かけていったと
いうわけだ。
あのとき、銭湯の料金はいくらだったろう?そしては今はどれくらいなのか。見当のつかないま
ま、のれんをくぐる。番台のわきには、話しやすそうな温和な感じのおっちゃんがいて、なじみ
の客と話していた。おもったよりも、奥行きがない脱衣場だ。女湯はやはり絶妙な角度づけでみ
えない。それはそうか。料金は370円。わりと高い。毎日、入りにくるとしたら、きつい値段
である。
脱衣場のあちこちに、常連客の洗面器やらタオルやらが整然と置かれている。かごのいくつかに
屋号やら名前が入っていて専用のもののようだ。ずいぶん古い。浴室は脱衣場と同じくらいの奥
行きである。奥行き、奥行きというのは、子供のころ通っていた銭湯が、どこも縦に長かったよ
うな記憶があって、そのせいだ。しかし、洗い場も風呂も適度な大きさがあって、窮屈にはみえ
ず。普通風呂2(深い・浅い)、電気湯1、泡風呂1、水風呂1と種類も多い。
洗い場、やっぱりこれだ。赤いレバーと青いレバー。下に引くとジャーと出る。洗面器をおいて
両方いっぺんにだして、適度な湯加減に調整する、あの作法が一瞬にして思い出された!おお。
ん、ん、あれ赤いレバーだけで適度な湯加減だ。まぁいいか。
先客同士が普通風呂で話しこんでいたので、じゃまにならぬよう、端っこにあった泡風呂へ。バ
スクリン(緑)色をしている。
あーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー。きもちいいですよ。ほんとに。
この開放感はやっぱり家の風呂にはない。風呂に窓でもついていれば別だけれども、うちの風呂
の位置からすると、エレベータの竪穴か、隣の部屋の風呂がみえるだけだろうな、などとばかな
ことを考えながらつかる。あ、いままできづかなかったけれど、ちゃんと天井は空気抜きがあっ
て女湯とつながっている。おばちゃん声がわやわやがやがやと、湯音にまじって聞こえる。のん
びりした感じ。「おーい、石鹸ー」「はいー」なんて、幻聴は聞こえないけど、目をつぶって、
必死に祈ったら聞こえそうだよ。古い人間ですから、私。
普通湯にもつかって、足をしっかり伸ばしてからあがる。番台でのやりとりが聞こえる。
客「おっちゃん石鹸ちょうだい」
お「ほい」
客「高級品?」
お「高級品。3000円。でも今日は100円。」
ここは錦市場が目と鼻の先にあるので、ほとんどが市場の関係者なのだろう。お客同士の挨拶が
頻繁だし、若いひとも実は入りにきている。わたしのように、ビジター的なひとはいない。まぁ
それでも居心地の悪さは不思議と感じないのが助かる。普段はみない野球中継を皆にまじってぼ
ーと見ていた。おっちゃんの人柄のせいかもしれぬ。でるときも愛想良く、常連と変わらない調
子で見送ってくれたのがなんとなく気持ちよかった。
唯一、残念だったのは飲み物コーナーが見当たらなかったこと。お客のひとりが、ビールを飲ん
でいたので、どこかから出してくれるのか。ひょっとして女湯側に冷蔵庫がおいてあってそこか
らもってきてくれるのか。謎である。定番としてやはり、ここはコーヒー牛乳か、フルーツ牛乳
をぐぐっと飲りたいのですよ。
外にでて、自販機を探す。いつもと違うモノでも飲むかと思って、ジンジャーエールを買う。あ
まり外で売ってるのを見たことがないし。そのまま髪を乾かしつつ、ほてった身体をひやすため
自転車で遠回りしながら、いえに帰った。銭湯のあとは夜風にあたるに限る。
なにげなく家と会社を往復していると、じつはこんな生活もできるのだっていうことを、ついつ
い見落としてしまいそうになる。普通はそういうことは学生時代にきづくのだろうな、とも思わ
ないでもないが、あのころは家と研究室と練習場をぐるぐる回っていたから、いまより余裕がな
かったのかもしれない。
ま、いま、こうやって気持ちのいい時間をすごせているからいいのだ。
- 2005/08/31(水)

「再び女たちよ!」伊丹十三著、新潮文庫。
さて、伊丹十三が亡くなってから8年。いまでは、その名がTVや雑誌で聞かれることもまったく
なくなってしまった。中高生や大学生にしてみれば、誰それ?という名前であるかもしれない。
わたしの年代にとっては、もちろん映画監督で、それもヒットメーカーであった。
今年になって、氏の著作が5冊新潮文庫から復刊されており、ちょっとした伊丹ブームが起こって
いるようだ。あんな映画を撮る人であるから、文章も面白いのだろうなと思い、手にとってみてお
どろいたことがあった。著者紹介の経歴を見ると、映画監督というのが最後なのだ。その前がある。
「映画俳優、デザイナー、エッセイスト、後に映画監督」。そう、この本は、決して映画監督の余
技で書かれたものではなくて、「本職」としてかかれたものだったのだ。中高大生が映画監督伊丹
十三を知らないように、わたしもまたエッセイスト伊丹十三を知らないわけで、偉そうなことはい
えないのである。
その文章は、ともかく洒脱であった。あの山口瞳をして、「随筆をエッセイに変えた」といわしめ
たというのは、なるほど納得である。洒脱ではあるけれども、決して軽々しくない。しっかりとし
た背骨があることがわかる。昨今、恋愛小説ばかり書いている男性作家達のような弱弱しく、薄っ
ぺらで、夢見がちなポエムとはとても比較できない。骨太というのではない。難しい言い回しも、
胸をうつような比喩もない。そこにはあるのは確かな構成力であると思う。それが読みやすいのに
しっかりしたあと味を残す文章を生み出している。ああ、これがエッセイというものなんだ、と毎
日毎日、日記なのかなんなのか、よくわからない文章をひねり出しているわが身を省みながら、読
み進めているところである。
‐『独り者であることの不都合の一つは、思い出を分けあう相手がいないということかも知れぬ。
なにしろ記憶というものに対する愛惜の念がまるで起こらない。要するにどうでもいいのだ昨日の
ことは』(「狼少年」より)
- 2005/08/30(火)
帰宅してから、ネットを見ていてヘッドフォンアンプが欲しい病が再発する。おそらく、LX1を
買わなかったことの後遺症のような気がする。ハッセルブラッド(中判カメラ)が欲しくなったの
と同じで、おそらくデジタルっぽさの少ないアナログなもので、ソリッドなものを求めているのだ
と思う。真鍮だとか、スウェーデン鋼だとか、アルミ削り出しだとか、そういうものに元来弱いの
は確かだが、心理学的な分析するとこれは何か意味があったりするのだろうか。
さて、そういうこととはあまり関係なく、鎮静剤代わりにアンプ関連のサイトを巡回した後、なに
げなくいつものヘッドフォン(HD580)で音楽を聴いてみたところ、どうもしっくりこない。
どこか、押しが足りない、物足りなさ。ボリュームをあげても変わらないことから、根本的に何か
が欠落したような感じする。インナーフォンのMDR-E888に変えても、どこかそんな感じがぬぐえな
いことから、ヘッドフォンではなく、自分の耳の調子ではないかと思われる。
耳の調子。別に中耳炎などの耳の病気をわずらったわけではなく、あくまで調子のよしあしの話な
のだが、今日に限らず、日によって同じヘッドフォン、ソースとなるCDでも、聞こえ方や、そこ
から得られる満足度というのは、結構増減することを経験的にしっている。ただ、増減するという
ことはわかるのだが、いったいどういうときによく聞こえて、どういうときにいまいちなのかまで
は、把握できていないのだ。一概に体調のいい時はよく、悪いときは悪いというものでもないのだ。
そんな例を持ち出すまでもなく、人間の耳の聞こえかたというのはさまざまに変化することは、皆
さんよくおわかりだと思う。で、音楽をやるもの、合唱をやるものにとって、この能力を一定に保
てるか、どうかというのは演奏をするうえで非常に重要なこともお分かりだと思う。聞くことによ
ってはじめて、歌うことにフィードバックできるからだ。
耳を鍛えるというと、ピッチの微妙な違いを聞き分けて、それを声に和音に反映させるということ
だといえるが、常にそれを良い状態に保つということも鍛えることに含まれるような気がする。
今日の私のように、どこか納得のいかない状態(多分に主観的だが)にあっても、それを即座に
補正するような「調音練習」?のものがないものだろうか。もしかしたら、発声でやっている和
音練習がそうなのかも知れないが、やや違うような気もする。こう、もっと機械的に、測定器の較
正をするように、テスターの0Ω調整をするような、そんな方法というのがあればなぁと思う。
まぁ、人間の耳に絶対的なものというのはないし、絶対的でないのに、多人数が声をあわせる合唱
が、数学的にも裏づけできるような、すばらしい和音を作り出すというのは面白くもあり、不思議
でもあると思う。
以上、雑感。
- 2005/08/29(月)
実は、夏休みに入ってすぐ、入ったその日の夕方に眼鏡を新調した。普段かけている眼鏡は作っ
て1年と少しなのだが、顔の側面にあたるフレームの部分の塗装がはげてきていたのだ。正面から
みたところはまったく問題なく、そこだけ。ちかづいて、よく見ないとわからない。ただ、ちょっ
とみっともないかなぁと言う気持ちと、以前BKで眼鏡の掛け合い(互いの眼鏡を交換して似合う
似合わないを品評する)をしたときに、ある眼鏡をかけたときに顔の雰囲気がずいぶんと変わった
ような気がしたことがあって、それが気になっていた。
その眼鏡とは銀縁である。銀縁は、顔そのものよりも、眼鏡そのものが浮かびあがって見えるので
自分にはあまりあわないし、なんとなくはずかしいと思っていた。であるが、昨年の夏コミで私と
同年代のあるサークルの方が銀縁をかけてらっしゃったのを見て、おお、銀縁って実はかっこいい
のではと思うようになった。また、台北のさわやかメンである台北メールクワイヤーのメンバーも
実は銀縁が多かったように思うし、時代は銀縁なのか?と自分のなかでは実は土台は築かれつつあ
たのである。そこにきて、眼鏡交換会で(自分的には)印象は悪くないと思い始めたのである。
で、夏だし、夏期休暇だし、夏っぽくキラリンとひかる銀縁に挑むことにした。
でいま、日常的にかけているかというと違う。会社にいくときはいつもので、週末もいつものであ
る。かけたのは、宝塚のときと、夏コミのときくらい。なんでかというと、目があわないのだ。ま
だまだ。以前、割と大きなレンズをかけていたときから、いまの細いタイプの眼鏡にかえたとき、
度数は同じだったのだが、あまりの視野の違いにまったく目がついていかず、かけて30分ではき
そうになって、それでも毎日装用時間を少しずつのばしていって、だいたい3〜4週間くらいかか
たのだ。はかなくなるまで(なにかと体弱い...)。
さて、今回の銀縁であるが、度数はやはり同じ。レンズタイプも同じ。ところがだ、縦方向の長さ
が2mmほど短い。たった2mmなんだけれども、これがまたえらく目には負担らしく、連続装用はかな
り目にこたえる。まぁ、前回のような劇的な変化はないので、まる一日かけていてもなんとかたえ
られるかなというレベルなのだが、それでもこれをかけて仕事しろといわれるとつらい。
夏期休暇にはいってすぐにしたのも、もしかしたらそういうこともあるかも、と思って仕事がない
リラックスした状態で、慣れの時間が欲しかったからなのだ。というわけで、いまはもっぱら週末
家にいる時間にすこしずつ装用して慣らしている状態。この文章も銀縁モードで書いている。まだ
すこししんどい。慣れるときは、すぱっと急になんともなくなるもんだが、はやく普通にかけられ
るようになりたいなぁ。
ところで、新調してすぐの宝塚のとき、自分からいうまで誰も気づいたり、指摘されたりしなかっ
たのはちょっと残念であった。誰も、わたしの眼鏡なんて見ていないということが立証されたわけ
で、残念というか哀しかったです。はい。人生そんなもんだ。
追記:
眠れないので、ハチクロ8巻を読み始めてしまう。
そして、最後まで読んでしまう。
くるしくなって、もっと眠れなくなる。
それから、カシオペアに乗りたくなる。
- 2005/08/28(日)

コカコーラ、夏のキャンペーン。中途半端な枚数のまま、〆切(8/31)が迫る。
よくわからないが、今年は「KUMA」がキャンペーンキャラクター。応募口数10点のミュージ
ックーマ(iPod Shuffle+KUMA型スピーカ)を目指していたのだが、ひと夏あれば十分だろうと思
っていたら、いつのまにか8月も最後の日曜日だった。14点あるから、一応一口は応募できる。
夜はだいぶすずしくなって、冷房なしですごせるくらいの気温になり、夏が遠ざかっているのを
感じるこのごろだけれども、いつもならば夏コミの終了とともに押し寄せてきた、あのどうしよ
うもない『喪失感』が今年はない。(文章長いか)
アンジェリカ合同、世界シンポジウム、夏コミサークル参加、軽井沢と、休むひまなく何かをや
ってきた夏。でも、それらが終わっても、そこで完結してしまわない何かをそれぞれに得たから、
こうして脱力することもなくすごせているんじゃないだろうか。合唱なら、つぎの合同に向けて、
3年後のコペンハーゲンに向けて、来年の軽井沢に向けて、今年のコンクール、演奏会に向けて
良い具合に弛緩することなく、下期(合唱暦では夏の終わりから)の活動につながったような気
がする。NCでも昨日からコンクール練習が始まって、気力が高まってきた。
コミケならば、夏コミ終了と同時に冬の申し込みが完了して、あと4ヶ月でつぎの新刊を作らな
いといけない。どんなことをしようか案を考え、取材(自転車でうろうろする)をしていること
で常にさきのことを意識して、いまからわくわくしている自分がいる。
だから、夏がさっていくことに、ことさら郷愁を感じて、勝手に気力がダウンするなんて暇がない
のだ。ちゃんと足元をみて、つぎの季節に手を伸ばしていることを自覚する。これはいままでに経
験したことのない、夏の終わりだ。季節のめぐりのなかで、自分は同じことを繰り返しているよう
な錯覚をおぼえ、いつしかそれでもいいやと思うようになっていた。でもそれは違うのだな。いつ
もと同じなんてことはありえないのだ。いつも違う毎日で、いつも違う季節。そのことにきづいた
夏だった。
- 2005/08/27(土)

「よつばと!」4巻発売(あずまきよひこ著、メディアワークス刊)
みなさんは、本の帯はとっておくほうだろうか。普通の文芸書や、文庫本の場合、読むときは
たいがいカバーをかけていて、読み終わったらカバーをとるので、たいがい帯は残っているの
だが、漫画の場合、そのまま読むので、読むのに邪魔な帯はとってしまって、読み終えたあと
そのまま忘れて、どこかにいってしまうというのが、私のいつものパターンだ。
漫画の場合、買う時期によって帯がよく変わる。TV化、映画化、漫画賞受賞、何もないとき。
だから、帯をつけて並べると、たとえ見えるのが背表紙だけでもどこかぶそろいな感じがして
落ち着きがない。それだったらとってしまったほうがいいと思うのだ。そんなこともあってあ
まり帯を残すことにはこだわらない。
そんななかでも、「のだめカンタービレ」と、この「よつばと!」だけはちゃんと残している。
なぜなら、カバーデザインと帯が一緒にデザインされているからだ。帯つきでもよし。帯をとっ
てもよし。並べてもよし。じつはそこまで考えている本はとても少ない。この二作だけだといっ
てもいいかもしれない。
そのふたつのうちでも、「よつばと!」がいちばん好きだ。クラフト紙に二色刷り、よけいな
惹句はなくて、明朝体で書かれた短いフレーズが並んでいるだけ。余計なものをそぎ落とした
というのではなくて、はじめからそこにそうしてあるが普通のように感じる、そんな帯だ。
デザインはよつばスタジオの里見英樹氏。カバーデザインだけではなくて、本全体のデザイン
と編集も里見氏の仕事だ。こういうものを、いいしごとっていうのだろうな。宣伝のはいって
いない帯を営業部門に認めさせるというか、帯まで含めてデザインの領域にしてしまったのは
本当にすごいことだと思う。
さて、そういうことを言っているわりには、わたしのよつばと1巻にはなぜか帯がない。いっ
たいどこへやってしまったのか。捨てた憶えはないのだけれど...。誰か帯だけゆずってくれな
いものだろうかなぁ。
- 2005/08/26(金)
どうやら、ふらふらは一日置きにくるようだが、今日ははっきり自覚できるほどに前後に
ゆれる。しんどい。でも仕事はちゃんとやらねばならぬ(あたりまえだ)。
一時間だけ残業してから、大阪に向かう。今日はLUMIX-LX1の発売なのだ。欲しい欲しい
とは思っていたが、この目で確かめないことにはやはり買う気になれない。目指すは梅田
はヨドバシカメラ。車中、文庫本を読んで体調を整える。
到着。一時間経過。
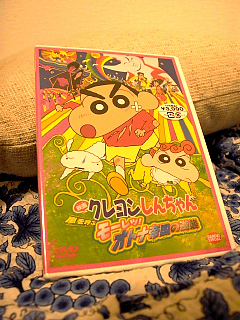
「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!大人帝国の逆襲」を購入。
あれ...。いったい私の頭の関数はどうなっているのか。
LX1の名誉のためにいうならば、非常に良いデジカメであることに間違いない。なにより、もの
としての手触りがいい。正直、持っていたいと思わせるものがある。
ではなぜ買わないのか。買いたいと思わないのか。簡単にいうと、グリップだ。手に持ったと
きに、手のひらに吸い付く感覚が希薄だった。この持ち方では自分の普段撮っている写真はと
れないなとわかってしまったのだ、そのとき。これはほかのデジカメでもコンパクトと呼ばれ
るものは多分みんな同じような気がする。カメラを安定して構えることができるというのは
写真を撮るうえでの安心感につながる。たとえ、手ぶれ補正がかかってぶれのない写真がと
れるとわかっていても、シャッターを押すときの気持ちというものがまるで違う。ひとつの
シャッターに全身全霊を込めるなんてことはいわないが、一瞬の静寂というものがシャッター
を押すときには欲しい、となんとなく思うのだ。
その感覚はかつては銀塩カメラにしかないものと思われていたが、デジカメにもそれを感じる
ことのできるものはある。いまつかっているLUMIX-LC5がそうだ。右手にしっかりと収まる感
覚。それに拮抗するカメラの自重。いまや、この重さを感じないで、建築写真や路上観察、
そしてポートレートを撮ることを想像できない。
いまはむしょうに重たいカメラで軽快に、でもスローに写真を撮って歩きたいと思っている。
そうだなぁ、HASSELBLAD 500C/Mの中古でも探しに行こうか。新品のLX1よりも中古の500C/M
が高いのはわかっているのだけれど、モノの値段が問題ではないのはいつものことだ。
その手に持ちたいか、持ちたくないか。
その手に重さをちゃんと感じられるかどうか。
そのカメラで写真を撮りたいと思うかどうか。
それだけだ。
クレヨンしんちゃんに至る経緯はややこしいので割愛。
追記:
『大人帝国』、噂に違わぬ傑作で、名作だった。
明日もっぺん、見よう。
- 2005/08/25(水)
落ち着いてきたので、この夏に日月堂で買ってきたものを紹介。

全8点。撮影地、パークホテル東京。(この写真だけ))
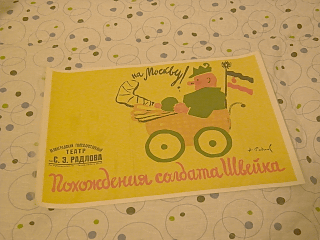
ロシアの演劇ポスター。2500円。
「グッドソルジャーシュバイク」1935年、レニングラードにて上演。
原作は「グッドソルジャーシュバイクの冒険」という小説らしい。ポスターの作者は
NIKOLAI RADLOV。絵本のようなユーモラスなタッチ。もともとは絵本画家なのではな
いだろうか。幻と呼ばれるロシア絵本の開花時期1920-30年代とも符号するし...。
資料を調べてみたが該当する名前は見つからなかった。
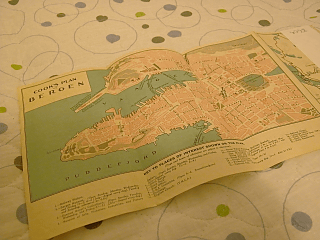
ベルゲンの観光地図。300円。
この地図を買ったのはBergenという文字が目に留まったから。Bergenとはドイツ語で、
「山」。そう、山Dの山である。であるが、ベルゲンという街はいったいどこにあるの
やら、日月堂さんともどこだろうねぇと話していた。で、調べたところ、ノルウェー
第2の都市で、古くから天然の良港としてしられ、現在も文化芸術都市としてしられ
る街と判明。・・・いやぁ、まったくしらず。グリーグの家や、グリーグホールという
のがあるらしい。この地図は地図・時刻表で有名なクック社のもので、1928年?版。
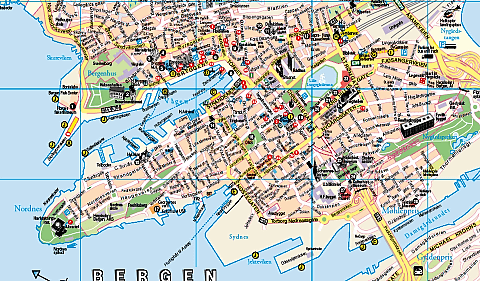
ちなみにこちらが、現在のベルゲンの地図。桟橋の形が若干変わっているのと、高速道路
が走っている以外はほとんど変わりがないように見える。これも何かの縁であるから、い
つか、1928年の地図をもっておとずれてみたいもの。
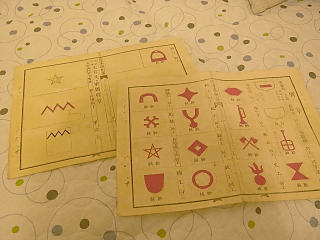
旧帝国陸軍服制図、肩章のページ。1500円。
陸軍が発行していた基準書のようなもの。軍服の肩につけるマークの図案を規定している。
軍医部、教導団から、喇叭手なんてものまで肩章が決められていたようだ。よく見ると、
「馬医部」というものがある。おそらく仕官の乗る軍馬専門獣医の部門だろう。独立した
部ということはそれだけ重要視されていたのだろうな。マークの由来はあぶみ?
母方の祖父(軍服姿で馬上の写真が残っている。)ならわかっただろうか。
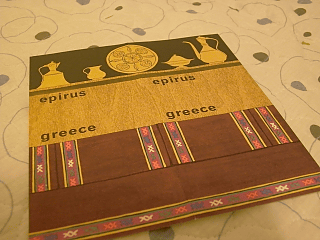
ギリシャの観光パンフレット。年代不明。300円。
いかにもヘレニズムといった雰囲気と香りが漂う美麗なデザインにひかれて。

フランスの製薬会社のリーフレット。300円。
この紙質の良さ、印刷のよさ、濃い赤の発色のよさ!おそらく多色刷りであろうとのこと。
職人による印刷技術の粋が、こんな小さなものにまで溢れていた豊かな時代、を感じる。
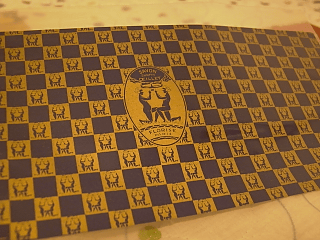
フランスの石鹸の包み紙(おそらく未使用品)。2000円。
今回の収穫物のなかで、もっとも美しい。紺地に金の模様という組み合わせは、このうえなく
上品であると思う。オリエント急行の車体なども、この配色である。なぜか同じ配色は日本で
は見られないのが不思議で、着物の図柄などにあっても不思議はないと思うのだが...といった
ことを日月堂さんと話していた。
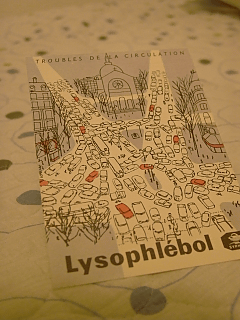
製薬会社のダイレクトメール。800円。
うーん、これのどこが製薬会社のもの?と思うかもしれない。書かれている文字を読むと、
"TROUBLES DE LA CIRCULATOIN"とある。つまり、循環器のトラブルにはこの薬!という宣伝。
そう、詰まった血流を、渋滞の道になぞらえているのだ。なかなか洒落ているというか。
現代の製薬会社のパンフレットにはさすがにこんなのはないだろうなぁ。
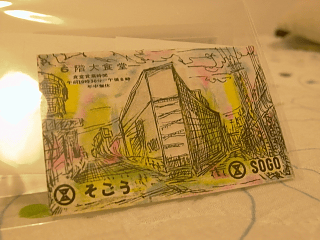
有楽町そごう、6階大食堂のマッチラベル。200円。
今回最大の掘り出し物。有楽町そごうって知ってますか?そう、あの山の手線有楽町駅から
見えるあの変わった建物。現在のビックカメラ有楽町店。建物そのものは「読売会館」らし
いのだが、有楽町そごうとして名の方が有名。設計、村野藤吾。
この絵の図柄、虹のような彩色、ペン画....どこかでみたようなタッチ。おそらく名のある
画家によるデザインに違いないと日月堂さんと意見が一致。サインがないため誰か不明だ。
というわけでいかがだったろうか。毎度、毎度、そんなの買ってどうするのと問われたなら、
「どうしようかねー」としか答えようがないのだけれど、小さくても、目立たなくても、街
ゆく人に無視されようとも、これは私にはきらきら光ってみえる、とても美しいものたちな
のだ。大切にしまっておいて、ときどき「鳩サブレー」や「甚五郎せんべい」のかんかんか
ら取り出して、眺める。ときどきは本棚に飾ってみたりする。そういう愛すべきもの。
みんながみんな、これを気に入るのだったら、ぜったい私のもとにめぐってこなかっただ
ろうと思う。逆にいえば、縁あって私のもとにやってきた。おおげさにいえば、これらの
ものの集合がわたしという人間の思うこと、感じることを具現化しているような気がする。
あすは早い。もう眠ろう。
おやすみなさい。
- 2005/08/24(水)
まだ身体が本調子じゃないみたいで、モニター仕事をしていると、くらくらくる。お腹が
すいているわけではないらしい。
台北メールクワイヤーのメンバーからメールが来ていたので、リプライ。英語でメールを
書くのは、会話するよりかはいくらかは気が楽なものの、気がつくと主語抜き、時制がむ
ちゃくちゃだったりと、文法をかなり忘れていることにきづく。ちょっとした返事+質問
だったのに、相当疲労。やはりモニターを注視できないせいか。
昨日は割合文章が書けたのに、今日はこんな体たらく。このムラはなんなんだろうか。
- 2005/08/23(火)
苦いものが飲みたい、最近。具体的にはコーヒーか。
この最近というはものすごく最近で軽井沢にでかける1〜2日前くらいからだ。
休憩するために売店にいったとき、たくさん並ぶお茶やら、スポーツ飲料やら、紅茶
やらを目の前にしても、これが飲みたい!と積極的に選び取るものが頭に浮かばない。
水...は2月以来ずっと飲み続けているが、仕事の気分転換にはなっても、エネルギー
にはならないかもなーと、消極的である。
で、頭ではなくて、舌だとか喉、口の中が欲しがっているものを選んだらそれが、苦い
もの、コーヒーだった。暑さでじとっとしているか、冷房のために生ぬるく乾いた口の
なかを一掃してくれるような苦さが欲しかったのだろう。
苦いといっても、私の場合、二アリー苦い。ライク苦い。つまりはブラックコーヒーだ
とかの本格ではなく、ちょっと苦い程度でよいのだ。砂糖なしは飲めないので、明治ミル
クと珈琲・ふんわりラテだとか、ジョージアエメラルドマウンテンとかだったりする。珈
琲好きのひとからすれば邪道なのだろうけれど、とにかく砂糖が入っていようといまいと
あの後味が欲しいだけなんだ。
軽井沢では水分補給に徹したので水、お茶メインだったが、帰ってきてからはやはり、
コンビニにはいっても欲しくなるのは珈琲飲料である。わたしは、どちらかというと珈
琲は胃に来てしまうので苦手な飲み物で、冬場に飲む暖かい缶コーヒーは好きだけれど
も積極的に飲みたいなと思うものではなかった。
しかし、いまは、どこかの名店のおいしい珈琲を飲んで目覚めたとか、そういう革新が
あったわけではなく、水を飲み始めたときのようなチャレンジがあったわけでもなく、
ただ身体の求めるまま、珈琲を飲んでいる。あまりにも突然の変化で、自分でもなにが
起きたのか、なにかが変わっているのかわからない。もしかしたら、また突然飲まなく
なるような気もする。
ということで、この現象を記録にとどめておく。
冬コミの当落は11月であるが、それまでまっているわけにはいかないので、新刊の構想を
練る。近代建築探訪問vol.2、京都断章。vol.1とは違う形を、と以前から述べているが、断章
ということで、レイアウトを組むほど写真点数もなく、目立たない建物の隠れたディティール
のようなものを紹介したいと考えた。ストックのなかから、探してみるがおもったより少ない
これはもういちど歩いて、発掘する必要がありそうだ。8月末にLUMIXの16:9,28mmのLX1が出る
ので、これで撮りおろししてみたいなぁと、いまのところ思っている。実売はいくらくらいな
んだろうか。
「ハチミツとクローバー」最新第8巻を買ってきた。
今日は読まない。切なくなるにはそれなりに心構えが必要なのだ。
- 2005/08/22(月)
ああ、休みたいー!と思うが、やらないといけない仕事が少なくとも3つ頭に浮かんだので、
しぶしぶ出社。というか、残業しないとシンポジウム関係でやたら早退したため、勤務時間が
足りなくなってしまうのだった。今年はハードスケジュールすぎる。
写真整理、ウェブ上の個人専用ギャラリーにアップ。明日、BKのみんなに公開する。
夜中にたまたま、TVで「ハツミツとクローバー」を見てしまい、切なくなる。
しまったなぁ...。
- 2005/08/21(日)
軽井沢合唱フェスティバル、三日目。
昼ごろ終了。夕刻に帰京予定。
19:00帰宅。写真やGPSデータの整理をしていたら、くらくら来たので、休みます。
いろいろ書きたいのに、ふらふらです。
8/22追記
・午前中、橋本靜一氏の発声講座。新鮮。発見。隣の人と背中叩きで触れ合い。
・つづけて合唱指導、シンガポールのジェニファー・タム女史。Dragon Danceや、Tangareeは
BKでいずれやるような気がする。
・クロージング。各団に参加証が手渡される。
・岐阜高校のバスをみんなで見送る。いつまでも手を振るみんな。
・記念撮影。最近、記念写真をとることの意味合いのようなものがわかってきた。ただの写真
じゃないってことも。
・弁当が6+1個もあまる。みんなで手分けして食べたり、夕食に持ってかえったりする。
・それぞれに解散。
・山Dは一路東京経由、新幹線で京都へ。いろいろ振り返るには一人のほうがいい。
- 2005/08/20(土)
軽井沢合唱フェスティバル、二日目。BKで出演。
@軽井沢大賀ホール(こけら落し公演)。
8/22追記
・招待合唱団演奏会。岐阜高校、歌姫の演奏に圧倒される。
・BKは...。違う雰囲気は作り出せたかもしれないけれど、反省点が多かった。みかんの花
だけはなんとかお客さんに何かを伝えることができたような気がする。
・演奏中、雷雨。そう、昨日も夕立だったらしい。涼しいのはこのスコールおかげなんだろう。
・終演後、雨上がる。
・皆、思い思いに30分の休憩をすごした。
・耕友会の演奏、これが同じ合唱人の音楽かと思わされるほどに揺さぶられる。ちょっと疲れた。
・交流会、一次会、二次会とつづく。書ききれないほどの楽しさ。
・夜中、談話室にてBK鈴木さんを囲む会開催。AM3:00まで開催された模様。
・花火、京都から買っていったのに結局やる時間なし。条例もあって夜は静かな軽井沢。
・しかし、交差点の歩道の真ん中で、ど派手な花火をやっていた地元のひとも居た。
- 2005/08/19(金)
軽井沢合唱フェスティバル、一日目。参加できず。
夕方、移動。夜、軽井沢泊。
8/22追記
・上越新幹線は乗ってからかなり長い間、ひらけた土地を進み、どこもビルが林立する都会。
このまま一時間で本当に軽井沢に着くのかな?と心配になる。
・軽井沢到着10分くらい前から、延々とトンネル突入し、GPS測定不能に。トンネルを抜け
ると、いきなり静かにたたずむ軽井沢の山中だった。
・駅前の温度表示は22度。京都と10度も違う!ひんやりとした山の夜気を感じて、合宿を
思い出す。
・改札にはなぜかたくさんの犬達。そう、東京方面から帰宅するご主人を待っているのだ。
新幹線で一時間の距離は十分通勤できる距離なのだ。ここと東京がつながっているなんて
なかなか想像がつかない。名古屋や北陸経由でのイメージしかないものだから。
・駅から5分ほど歩いてペンションに到着。当然のように冷房がない。
・談話室のようなところで酒なし宴会。
- 2005/08/18(木)
明日より、軽井沢へ避暑に出かけます。
といっても、仕事が終わってからなので現地入りは22時過ぎになると思われる。
今回の楽しみのひとつは、はじめて上越新幹線に乗るということ。GPSを持っていくので、
京都から東海道新幹線で東京を経由し、軽井沢まで全行程の軌跡が残せるかどうかチャレンジ
してみたい。東海道は京都〜名古屋がうまくとれない。名古屋〜東京はかなり鮮明に記録でき
きることがわかっている。はたして、山間部とトンネルの多い、上越ではどうだろうか。
- 2005/08/17(水)
朝から体調がすぐれない。仕事中も脂汗のようなものが出っぱなしである。
この一ヶ月ほどのかなり無理やりなスケジュールの疲れが出てきた模様。
すいませんが、本日の更新はお休みです。
早々に横になります。
- 2005/08/16(火)
朝、家から会社までの間が静かである。ひと気がない。やはりお盆休みは16日までのところが
多いのだろう。その静けさに、あと一日休みが欲しかったなぁと思う。
仕事は早めに切り上げ、実家に戻る。おもてで火をたき、先祖と父を送る。うちからは送り火は
見えないのである。KBSの五山送り火TV中継をぼんやりと眺める。昔、父が舟形の火を灯し
にいったことを思い出す。おもりものが食べきれないというので、水羊羹やら、ぶどうやら、た
くさん土産に持たされて自宅に帰る。
キンコーズにてサークルカット作成。いざ保存しようとすると、なんとSDカードがロックされ
ていて書き込めないというエラー。持っている2枚とも駄目。しかたなく印刷だけして、データ
は放棄。家に帰って、試したら普通に書き込みできるじゃないですか。とほほ。PCのせいか。
サークルカットもまた一つの作品なのに...くやしい。
というわけで写真に撮ってみた。
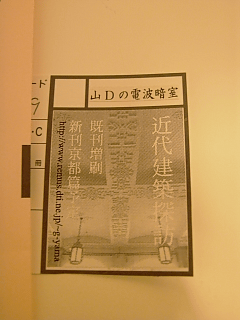
これで書類は準備OK。明日、朝にもう一度内容を確認してから、投函する。
冬は2日間開催。前回の冬は確率46%だったとのこと。なかなか厳しい。
受かって、既刊増刷、新刊発行できますように。
- 2005/08/15(月)
・朝、荷物を宅急便で送り、マクドで食事。
・丸の内OAZOの丸善で、しばし新刊書と交流。
・一階の日経の検索スペースに椅子と机あり。次回申し込み書を記入。
・東京中央郵便局にて次回参加費振込み。15分くらい待たされる。窓口は7つあるのに、
なぜに4人しか配置されていないんだ...。ほかにも振り込みに来た同志を見かける。
・旧SUICAカードを新SUICAに切り替え。ペンギンマークがついてないと、電子
マネーとして使えないらしいのだ。8/12にエラーを経験済み。
・神保町へ。ブックブラザー源喜堂の地階がなにやら別の店に変わっている。ショック!
・東京ランダムウォークにて、記号・暗号・符号・文字などの観念部品カタログ「ZERRO」
を購入。以前、この場で「京都でみつけたら買おう」思って、そのまま忘れていた。やはり
買おうと思ったそのとき、その場所で本は買わないといけないのだろう。
・ボンディにて野菜カレー。
・隣で会話していた若い主婦が流しにキノコが生えた話をしていたせいか、急にナウシカが
見たくなる。そういえば長いこと見ていない。
・学士会館を撮影。旧7+2帝大、現7国立大学の卒業者以外には無縁。と思っていたら、角
をまがったところに、「新島襄生誕の地」の碑を発見。安中藩江戸屋敷がこのあたりにあっ
たということか。碑をたてたのはなんと地元の町内会と小学校で、学校法人同志社の名はな
い。遠く関西の学校の創始者を地元の人が顕彰してくれているのがなんとなく嬉しかった。
・御茶ノ水に向かう途中で自転車ショップを発見。ボトルキャリアーと、自転車トラブル解決
ブックを買う。またしても本...。
・友人と新幹線乗換え口で待ち合わせ。今日、帰京するというので一緒に帰ることに。
・18時、帰宅。ひたすら申込書を書く。あっ、サークルカットだけはまたキンコーズに行って
作らねばならない。明日作成して、あさって郵送。ぎりぎりだ。
・ダイジェストとはいえ、いっぺんに書くと疲れる。詳細はそのうち、ぽつりぽつりと追加。
- 2005/08/14(日)
コミックマーケット68、3日目@有明ビッグサイト。
おそらく、世界でいちばん暑い夏の日。
追記:8/15
・快晴。待機行列は強烈な暑さに見舞われるが、4時間をそれほど長く感じず。慣れか。
・10:15入場。15:30撤収。
・男性向けと動物系をのぞく、創作系のほぼすべての列を遊撃。おなじく遊撃していた
同行の幸雄さんとは、購入した本がまったくかぶっていない。あ、kowa's innの
「もちもちした制服さんファンブック」だけは二人とも買っていた。
・そうそう、kowaさんには無理いってスケブを書いていただいた。感謝感激。
・水上バスにて帰ることにする。ひと夏に一回は乗らないと気がすまない。
・なぜだか、水上バスの切符を買う列が異常に長い。なんと窓口がひとつしかない!
本来は3つあり、いつもフル稼働なのになぜだろう。そして、いつのまにか、窓口
の横に一台のみ券売機があるではないか。しかし、処理が遅い。これまたなぜだか
警備のおっちゃんが、券売機の操作をしている...。あのおっちゃんをまどぐちに
座らせたほうがはやいんじゃないのか。これは絶対MR(マンガレポート)のネタ
になっていると思う。
・パレットタウンから乗ったお客さんと一緒になる。なんか...あきらかに怖がって
いるか、奇異の目で見られている...。もう慣れた。(開き直り)
・日の出桟橋から浜松町まで、夕日をさえぎるものがなく、実は一番しんどいポイント。
・17時、帰宿。
・大井町アトレ、さぼてんにて、特選五島ロース+キムチカツ。
・実家への土産に、ごまドレッシングを購入。レジ横に見本としておいてあったもの
を渡される。たしかに賞味期限は来てない、けどなぁ。ちょっと引く。
・19:30、阪急大井町ストアの「てもみん」へ。
・待ち時間の間、「Hard off」を見る。ブックオフの電機雑貨版。単コンのオーディオ製品
がずらりと並んでいる。B&Wのスピーカーや、マランツ、テクニクス、DENONのアンプ
まである。テクニクスのレベルメーター付きのPA2000欲しい...。(定価25万が79800円。)
・「てもみん」、しっかりもんでくれるのはいいが、ことごとく私のくすぐったいポイント
になっていて、笑いをこらえるのに体力をずいぶん使ってしまう。近所のマッサージ屋の
ような満足感は得られず。一応、効果はあるのだけれど...。これも慣れの問題か。
- 2005/08/13(土)
コミックマーケット68、2日目@有明ビッグサイト。
西1地区、ら−24b「山Dの電波暗室」でサークル参加。
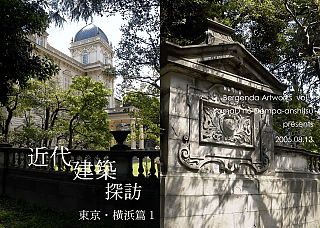
頒布物:建築写真集「近代建築探訪vol.1 東京・横浜篇1」
B5版16ページ、フルカラー。頒価500円。
東京湾大華火大会に巻き込まれないうちに撤収しないと。
追記:8/15
サークルにお越しいただいた皆さん、初参加のサークルにもかかわらず関心をもっていただき
本当にありがとうございました。そして、開始1時間で完売してしまい、まことに申し訳あり
ませんでした。サークルチェックしていただきながら、お渡しできなかったこと大変心ぐるし
く思います。
今回、いったいどれだけの方が建築写真というものに興味を持ってくださるのかまったくわか
らないまま参加を決めたこと、また印刷の予算の都合もあって、40部という部数で臨んだわ
けですが、予想をはるかに上回るかたがたに手にとっていただき、買い求めいただくことにな
りました。それにしても開始後、1時間というのはまったく予想の範疇を超えていました。
その場にてお約束させていただいたとおり、冬コミに受かりましたら増刷をかけたいと思って
います。ただ、予算の都合もあって、今回よりは多くするのは確かですが、それほど多くはす
れないかもしれません。何とか、直前まで方策を考えてみたいと思います。
それから新刊ですが、いまのところ今回の本とは違う形式のものを企画しています。同じ形式
のものは次回の夏以降の予定です。冬はやはりスケジュール的に厳しいためです。(合唱の方
が、この夏以上に大変忙しくなることもあります。)
今後とも、当サークルをよろしくお願いします。
・7:30時、サークル入場。小ぶりの雨。
・シャッターが開く前の西館は思ったより蒸し暑い。
・10:00〜16:00、の間も蒸し暑いままであった。
・11時に完売し、大変あせる。急遽、HPお知らせ名刺を作成。来ていただいた方に配布。
・16時終了。気がつくと西館にはメカミリサークルのみ残留。ほかのジャンルはすでに椅子
をあげて帰宅。濃い部分が残ったような感じ。拍手、三本締め、万歳に参加。
・早々に完売したことで心ぐるしかった面もあるが、すがすがしい気持ち。サークル参加
できてほんとうによかった。
・17時、帰宿。
・大井町アトレ、グリル神田にてハンバーグ。つけあわせを、ベークドポテト、コーン、なす、
ブロッコリー、フライドポテトのなかから2つ選択できるので、「ベークドポテトと、フライ
ドポテト」を注文。周りを見ると、普通はポテトとコーンを頼むようだ...。
・サークルチェック中、窓にどーん、どーんと響く音。東京湾の花火の振動がここまで伝わって
来ているのだった。花火もよく見える。
・早めに就寝。
- 2005/08/12(金)
コミックマーケット68、1日目@有明ビッグサイト。
じつは行くところがほとんどなかったりするのだ…。
昼からは谷中・根津にでもいこうかな。
追記:8/15
・なくて七癖などというが、それと同じ(?)で、行くところがほとんどないと言いながら、
実はたくさん本を買った。
・入場前に一時間ほど並ぶが、かなり暑く、つらい。こんなにきつかったかなぁと正直、3日目の
場待機が不安になる。
・16時、大井町のアワーズイン阪急に投宿。これより3泊。
・大井町アトレのさぼてんにて、みぞれとんかつ。
・京都にいる友人より「とんかつ食べたか」メール。行動パターンを読まれてるナァ。
・23時ごろ就寝。
- 2005/08/11(木)
・銀座グラフィックギャラリー(銀座)
・日本民藝館(駒場)
・古書日月堂(青山)
へ行く予定。
宿泊は「パークホテル東京」(本日のみ)。昨年のリベンジである。
(注:昨年も山Dは、東京初日にパークホテルに宿泊したが、なんと歩きすぎで捻挫になり、
滞在を思うように楽しめなかったという苦い経験を持つ。)
追記:8/15
・銀座グラフィックギャラリーに10時到着。開館は11時だった。
・電通銀座ビルを撮影。
・昼過ぎ、駒場へ移動。東京大学教養学部、大学生協に潜入。「教養セット」を食べる。
・同構内、駒場博物館にて開催中の「錯覚展」を鑑賞。目の錯覚以外に音の錯覚もあると知る。
・暑さのため、民藝館までのわずか10分の道のりがつらく感じ、予定を変更。
・15時〜17時、表参道の古書日月堂にて、紙モノ探索。池袋古書市の準備であわただしいとこ
ろ対応いただき感謝。収穫物は後日紹介。
・パークホテル東京に投宿。夕食は新橋駅前ビル地下の家庭料理「和」にて生姜焼き定食と、
生グレープフルーツジュース。ジュース以外は去年と同じ店、同じ定食。
- 2005/08/10(水)
できてきた。本。
すごい遠くのほうから、波がゆっくりゆっくり押し寄せてきて、だんだん心が満ちていく。
やった、やったよと、誰かに伝えたくなる、聞いてほしくなる気持ち。これなんだ。こうい
う気持ちは、はじめてだ。何かモノを作るってこういうことなんだ。仕事や、BK、NC関
係(歌うこと以外)でも、なにかをデザインして、みんなに配ったりしたことはあるけれど、
本をつくるということは、やっぱり特別な何かがある。なんだろう、説明できるような語彙
がみつけられるほど、こころが平常じゃないみたいだ。いまは。
もちろん、もっとよくできる面だとか、途中で妥協してしまったところはあるのだ。解説部分
は力をいれて書いたけれど、レイアウトや文字数の都合で、ほんの少しだけカットしたりもし
た。ひとりでやっているから、まともに校正もできていないし。
さてさて、あとは手に取ってくれたお客さんがどう思ってくれるかだけ。
すこしでも、日本近代西洋建築のことに興味を持ってもらえたら、それだけ。
ただそれだけ。
- 2005/08/09(火)
あー、何もかいてなかったのだが、8/6から夏期休暇である。今日は部屋を掃除。ポリ袋4袋も
ゴミが出たのはちょっとびっくりというか呆れた。まだゴミ捨てと整理しかできておらず、台所
風呂、トイレ、廊下の清掃と、洗濯物を干すのとたたむのは明日に延期した。洗濯物は干せば夜
のうちにかわいてしまうのでよいのだが、干しているときが暑くてたまらない。夜干すのもしん
どいくらい最近暑い。
掃除の途中に気がついて、さがしだした。忘れるところだった。

コミケ待機行列、三種の神器。1つ足りない。
ここ数年、夏コミで雨に降られる確率は50%を超えているように思われる。3日間雨のコミケ
は記憶に新しい。猛暑対策は十分にしていても、雨対策は忘れられがちである。待機行列三種
の神器とは、折り畳み椅子、折り畳み傘、雨ガッパのこと。椅子は晴雨関係なく使えるが、雨
の場合、地べたにすわることは不可能なため雨のときの有用度は高い。傘があるのに、カッパ
が必要かというと、必要なのである。椅子にすわり、傘を差した場合、有効範囲から漏れる部
分がどうしても出てくる、たとえば膝や背中の一部がそうである。また隣近所の傘からしたた
り落ちる雫も侮れない。カッパのみであると雨に打たれ続けるだけで身体を冷やしてしまう。
なにしろ、4時間以上待つのだから。
さて、写真のとおり、カッパと椅子はあるのだが、傘がない。たたんだときに小さく、しかし
ひろげたときは大きく、という折り畳み傘を持っていたのだが、いつぞやの暗室に書いたよう
に風にあおられて折れてしまったのだ。条件にあう傘を調達しなければならない。
できることなら、晴れてほしい。
できることなら、ほどほどに晴れてほしい。
具合のいい晴れ具合を「貯める」ことができればいいのになぁ。
追記:
サークルチェック中に、いつも行っている写真・カメラサークルが落選していたことが判明。
写真で本を作るというスタイルを、そのサークルさんから教わっていたこともあって非常に残
念。挨拶にいくつもりだったのに。マイナージャンルの当選率は高いもの、と思い込んでいた
のだが、全体における申し込み数が少なければ、席そのものが減ってしまう。私が建築という
ジャンル、いやもしかしたら写真ジャンルで当選できたのは、非常に運がよかったのだ。冬は
2日間開催だから、もっと確率は減る。
与えられた「夏」を最大限に頑張らないと!
- 2005/08/08(月)
入稿。8/10完成予定。8/11には出発するので実はぎりぎりのタイミングだった。今日はしんど
いからいいかな、と思ったことが何度もあったのだが、あれで一回でも心が傾いていたなら、
間に合わなかったのかもしれない。何しろ、今日は13:00〜17:00と、いつもの倍以上の作業量
で、一日で吸収できる作業量としては集中力的に限界だった。
ぎりぎりの作業になってしまったのは、全体の作業量が読めなかったからだ。写真のセレクト
はしたものの、どういった見せ方をするのか、文章はどうするのかといったことがまとまった
のはPhotoshop上でレイアウトをはじめてからというもので、仕様書もなしにプログラムを書
きはじめるようなものだった。最初の1日で方向性が見え、ある程度サブルーチン化できたの
は幸いだった。
今後も同じ手法で本を作っていくかどうかは買っていただくお客さんの反応次第だが、冬は
できれば違う企画(でも建築)でやってみたい。冬の参加も見越して、すこしだけ多く刷るこ
とにしている。
さて、いまはまだモノがあがっていないので、充実感や昂揚感のようなものはあまりない。
入稿の直後にはNCの仕事をやり、その関係で出かけた後、帰宅したのが21時をまわってい
たので、脱力する余力もなかったのだった...。明日は、映画でも見に行こうと思う。
・・・脱力する余力って変だな。余裕の間違いだ。でも、脱力するのにも、なにかしら力が
いるような気がする。

「からくりからくさ」、梨木香歩著。新潮文庫。
そうそう、帰り際に三条の大垣書店に寄ったので少しリフレッシュできた。この夏の旅の供
として、これを選ぶ。「家守奇譚」の梨木香歩著。2Hの鉛筆で楷書で書かれたような硬質
な筆致が、昨年のネスカフェアイスコーヒーのCMのように、日陰でゆったりすごすがごと
く、つつましやかな涼感を呼ぶに違いない。
- 2005/08/07(日)
夕刻より墓参り。山でもかなりの暑さ。ただ、日が傾きはじめると風が吹き涼しげになった。
暑いから、涼しいことが気持ちいいなんだよなぁと、本堂の読経を聞きながら考えていた。
進捗状況。
表紙、裏表紙 完成。
2〜3ページ 完成。
4〜5ページ 完成。
6〜7ページ 完成。
8〜9ページ 完成。
10〜11ページ 完成。
12〜13ページ 完成。
14〜15ページ 80%。
解説、あとがき脱稿。キンコーズのPCスペースがうまっていたため、レイアウトは明日に延期。
あとは丁合い作業をすれば入稿できる。
もう少し。
- 2005/08/06(土)
第21回宝塚国際室内合唱コンクールを聞きに宝塚ベガホールへ。1日目を最初から最後まで
すべて通して聞くのははじめてである。朝10:00の開始から、17:00まで、延べ34
団体。(うち2つは生で聴けず。ホワイエにて)
午前中行われた女声合唱14団体は、どこも聞き応えがあり、朝も早かったのだが居眠りなど
まったくできず。するのももったいない演奏が続いた。今コンクール一番の充実度であったと
思う。そのなかでも秀逸はやはり、BKとジョイントした台湾のフォルモザシンガーズの女声部
で、その力強さと伸びやかさは、頭ひとつ以上抜きん出ていた。単なる「強さ」の比較では彼
女たちに失礼かもしれない。表現者として一級で、さわやかでかっこいい。嫌味であるとか、
プロのような傲慢さがないのだ。その逆である弱々しさもはかなさもない。表現する人として
地に足がついている確かさを感じる。これは、フォルモザの男声もまったく同じだった。
男声部門、混声部門は、選曲やホールの使い方、雰囲気のつくり方で、かなり好調、低調な団
体がはっきりとわかれてしまったように思う。(フォルモザとEST除く)総じて、力強さ
を全面に押し出すとこのホールは逆に響かなくなる傾向がある。それから、このコンクールに
出場する合唱団は、かなりのレベルの力をもったところが多いけれども、聴いていてつらいな
と思うところは、個々人の力が強すぎて、ソリスト集団になっている場合だった。特定の誰か
とその他、独立した4パート、そんな感じだ。以外なほど、レベルの違いはあれ、こういう傾
向の直線にほとんどの合唱団が乗ってしまうように思えた。
ただ、ひとつ身びいきを承知で書くならば、女声合唱のコールシェリーだけは、ほかの団体と
まったく違うベクトルをむいていたように思う。それは、弱々しいか、力強すぎないか、バラ
ンスが取れているか、という判断基準のうえではまったく評価のしようのない音楽を作りだす
というベクトルだ。
二次元グラフの第一象限にしか音楽はないと思っていたら、シェリーはまったく唐突にあっさ
りと向きを変えて、第三象限や第二象限に、いやもしかしたら三次元のグラフに現れたのだ。
それはわかりやすい言葉でいうとなんていうんだろうか、雰囲気を、音楽を楽しむ雰囲気、聞
くひとの心を優しくゆり動かす、周りとともに楽しむ雰囲気。そういったものを目指している、
そんなふうに、私には感じられたのだ。今回出場した団体、入賞した団体が、それを目指して
いないとは決していえない。けれども、表現の先に何かをしっかり見据えているところは少な
いのかもしれないなと思った。特に混声部では。シェリーのメンバー自身も、そこまで明確に
何かを思っているわけではないかもしれないけれど、自然の発露としてそういった雰囲気を創
りだせるところが、すごいな、素敵だなとつよく思った。
実は、シェリーの演奏後、あんまりにも自分自身感じ入るところがあって、しばらく余韻に浸
りたいと思っていたら、すぐさま次の団体の演奏が始まってしまったのである。だが、こころ
がジンジンするのに任せていたら、いつの間にかその団体の演奏が終わっていた。ほとんど聴
いていなかった。こんなことが本当にあるのです。歌はほんとにすごいね。
進捗状況。
表紙、裏表紙 完成。
2〜3ページ 完成。
4〜5ページ 完成。
6〜7ページ 完成。
8〜9ページ 完成。
10〜11ページ 完成。
12〜13ページ 完成。
14〜15ページ 20%。
ラストスパート。
- 2005/08/05(金)
『散髪屋で耳を切られると次の日よい事がある。』〜ケルト人の古い言い伝え〜
ウソです。いま考えました。けっこうざっくりいってしまって、鏡で見るとずいぶん痛々しい。
髪は早めに切りにいけ、という教訓としよう。しかし、演奏会もあらかた終わってしまってから
行く気になるというのは相変わらず、タイミングがずれているというか。日本古来の美意識、
「はずし」の技法を用いたものなのか、自分でもよくわからない行動である。軽井沢のために
とっておいたという解釈もある。
進捗状況。
表紙、裏表紙 完成。
2〜3ページ 50%。
4〜5ページ 完成。
6〜7ページ 完成。
8〜9ページ 完成。
10〜11ページ 完成。
12〜13ページ 完成。
14〜15ページ 20%。
余白の部分を裁断して、とりあえずの本の形にしてみた。
こ、これはちゃんと本になってるやん!...ちょっと感動した。気が早いか。
- 2005/08/04(木)
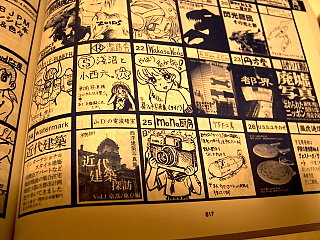
ちゃんと載ってた。817ページ、下段左から2つめ。
昨日のできごとは夢?と思うほどに、くっきりはっきり現実の今日。仕事は割と普通にはかどっ
たのが救いだったかも。いや、昨日までが充実してたから、普段の日々も、仕事の時間も気持ち
よくすごせるのだろう。
コミケカタログに載っている初の自分のサークルカット。そのまわりのたくさんのカット。むず
むずしてきた。そうだ、あの暑い夏が今年もやってくる!。本を買って、買って、読んで、読ん
で、並んで、並んで、歩いて、歩いて。売って、売る。
今年は、前日に捻挫しないようにしないとなぁ。
進捗状況。
表紙、裏表紙 50%。
2〜3ページ 50%。
4〜5ページ 完成。
6〜7ページ 完成。
8〜9ページ 完成。
10〜11ページ 完成。
12〜13ページ 完成。
14〜15ページ 20%。
表紙、裏表紙、2−3の構想固まる。
やはり、文章は最後になりそうだ。
日曜入稿、月曜完了を目指す。
追記:
「空中庭園」(角田光代著、文春文庫)読了。
普通にあこがれることと、普通じゃないことにあこがれること、どちらが「普通」なんだろうか。
普通じゃないことを求める人間は、ちょっとでも普通のことを求めたらいけないのだろうか。
どこまでも、どんなことも普通ではいられない。そんな覚悟でいないといけないのか。
読み終わって、そんなことを考えた。
- 2005/08/03(水)
世界合唱シンポジウム、クロージングコンサートin京都コンサートホール。
黛敏郎作曲、涅槃交響曲。大友直人指揮、京都市交響楽団。
合唱、クールジョワイエ&なにわコラリアーズ。
この夏の演奏のなかで、一番気がかりだったのだが、なんとかやりきることができた。音楽的な
こと、発声的なことで得ることは少なかったかもしれない。ただ、数少ないオケ合わせで、大友
氏のシンプルだけれど、きっちりと楽譜に忠実な演奏をまずやるという姿勢に、あたりまえのそ
のことが、十分できていないのがわれわれなんだと気づかされた。これが大きな反省かな。たま
には真摯に反省しないといけないのだ。
本番後に第2部のステージの演奏を聞く。ブラームスとメンデルスゾーン。かなり見事に眠りの
国へ旅たつことができた。いや、旋律がほんとうに美しかったから。
演奏後、ホールの1階ホワイエで、大レセプションに参加した後、帰宅。
数人で電車を待っていると、声をかけられた。おお、台北メールクワイヤーのメンバー達。「宝
塚を憶えていますか」。もちろん、もちろん。電車が来て、四条につくまで演奏のこと、メンバ
ーのことを話し合う。自分たちでもびっくりするくらい、なんとか英語が出てくるのは、たぶん
昨日のレセプションでモードが移行していたおかげかもしれない。
英会話、それもこういった交流の場での基本は、やっぱり5W1Hから始まる文章だと思う。
What,Where,When,Why,How。これらの例文さえ頭に入っていればあとは単語とジェスチャーで
なんとかなるものだと気づいた。あともう一つは、1対2の法則だ。一人でだめでも、二人な
ら補間しあいながらなんとか会話ができる。あ、もうひとつある。あせらなくてもいいのだ。
こっちが伝えようとするのと同じように向こうも伝えようとしてくれる。一人で会話するのっ
てむずかしいことだ。0.5+0.5でひとつの会話が成り立つんだから、0.5を出す努力があればい
い。台北のメンバーたちとは、ゆるやかな友誼で結ばれていることもあって、親近感があるか
らこそ、こんなことが言えるのかもしれないれど。
NCで松下耕の刈干切歌をやったとき、台北の演奏を聞いて練習したと言ったら、びっくりし
たような照れたような様子で"interesting!"と。われわれもいつか、異国の地で逆に言われて
みたい。
さて、次回の世界合唱シンポジウムはデンマーク、コペンハーゲンにて2008年。いってみ
たい...と漠然と思っていたのだけれど、さっき気がついた。行けるかも...2008年という
と入社10年の年になる。このまま制度が変わらなければ、長期の休暇がもらえる。夏休み前
にうまくつなげられたら、コペンハーゲン行きも夢ではない。今、一つの明確な目標ができた
ような気がする。あっ、でもでもスミソニアン博物館に行くという夢も、まだ捨てきれないな、
どうしたものかなぁ。
・・・ま、いまは次の目標、夏コミに向けて頑張ります。
その一週間後は軽井沢だ!
追記:
あ、Whoが抜けてた。Whoはあんまり使わんかも知れぬ。
- 2005/08/02(火)
世界合唱シンポジウム・コミュニティコンサートin京都府民ホールアルティ。
カンティクム室内合唱団(オーストラリア)、フォルモザ合唱団(台湾)、VOX GAUDIOSA(埼玉)
そして、葡萄の樹(京都)。
・・・・本当に楽しい時間を過ごせたと思う。個々の演奏は残念ながらモニターでしかきけなか
ったのだが、合同ステージ、松下耕氏指揮のAveMaria、そして、カンティクムの指揮者の方によ
る、Cantus omnibusはなんていうんだろうか、その場にいた全員で本当に声をあわせているんだ
合唱をしているんだという気持ちでいっぱいになった。久しく、同じ指揮者の指揮でしかうたっ
ていないこともあって、音楽の表現の仕方という点でも新鮮な刺激を得られたようにも思う。
同じ仲間だけ合唱していると、自然と気持ちが通じあってそれが団の持ち味につながったりする
と思うが、合同で今日はじめてあわせたような合唱の場合はどうなのか?その正しい答えが今日
あった。歌を通じて、気持ちを通じさせよう、コミュニケーションしようという気持ちがあの場
にはあふれていた。そしてその気持ちがとてつもなく、優しくて豊かで心地のよい音楽をうみだ
した。なるほど、確かに合唱は、歌はバビロン以来の人間が作り出した世界共通言語なのだ。
この気持ち、合唱団だけでなくて、お客さんにも伝わっていただろうか。だったらいいのだが。
レセプションでの、ワルチング・マチルダ、武満の翼・・・忘れられない歌がまた増えた。
こんなふうに積み重ねていく日々。
- 2005/08/01(月)
「鉄子の旅」4巻、購入。今日は読む時間ないなーと思っていたら、いつの間にか二話くら
い読んでいた。危ないなぁもう。
単行本の中表紙の前に、「鉄(テツとは」という解説が載っているのだが、前半の二行は
毎回同じだが、後半二行は毎回異なる。これは作者のキクチさんが考えているのだろうか。
非鉄の人からみた、とてもするどい観察がなされていると思う。以下、引用と感想。
1巻『テツの中でも、車両好き、駅舎好き、切符好き、スイッチバック好き・・・などなど
いろんなタイプに細分化される。』
→私は、旅の手段として総合的な鉄道好き。一般教養課程在学中みたいなもんか。
2巻『自分がテツであることを主張しないテツも多く、職場、学校、家の近所など意外なと
ころに存在したりする。』
→一見してわかるテツと比べて、一般人に非常によく溶け込んでいる人が多い。だからばれ
ないのだが。いや、ばれたら困る趣味でもないだろう。昔のさだファンと似てる。隠れファ
ンが多かったところが。
3巻『鉄道をたしなむには大変なお金と時間と労力がかかるため、テツは周りの人々の協力
なしに成り立たない。』
→そうか、一般的に見てそうなのか。知らなかった。
4巻『自由に乗ったり、撮ったり、噛みしめたりしたいので、旅の間は、基本的に個人行動
を好む。』
→・・・思い当たる節がある。好むというか、「もしここに同行者がいたら、この数時間の
私の行動原理は理解してもらえるものなんだろうか」と、ふと思い浮かぶことが時々ある。
現場に至っては臨機応変。それが個人行動を好むように見えるのかも。鉄子の旅のように、
誰かを案内してめぐる旅というのは実はやったことがない。この風景を一緒に見れたらナァ
と思うことが、ひと旅のなかに一度や二度は必ずあるのだけれど。だから、写真を撮ってる
のかも知れないな。
進捗状況。
表紙、裏表紙 20%。
2〜3ページ 20%。
4〜5ページ 完成。
6〜7ページ 完成。
8〜9ページ 完成。
10〜11ページ 完成。
12〜13ページ 完成。
14〜15ページ 20%。
表紙写真のセレクト完了。裏表紙がなかな決まらない。
解説文、主要データ調査完了。テキスト20%完了。気合が入れば一気に書けそう。
あとがき、奥付、その他、構想のみ検討。まとまり感をだせるかがポイント。
序文、少し手をいれる必要あり。
中表紙、レイアウト検討完了。
最近、寝不足気味。
おやすみなさい。
- 2005/07/31(日)
10:00〜12:30 コミュニティコンサート、BK練習。
15:00〜17:00 クロージングコンサート、オケ合わせ。
18:00〜21:00 仮眠。
22:00〜23:20 キンコーズにて、編集作業。
進捗状況。
表紙、裏表紙 0%。
2〜3ページ 0%。
4〜5ページ 完成。
6〜7ページ 完成。
8〜9ページ 完成。
10〜11ページ 完成。
12〜13ページ 完成。
14〜15ページ 0%。
最終形が見えてきた。テキストを固めねば。
きのう書き漏らしていたことがある。会議場でのコンサートをくつろいだ気分で聴いていると
まるで自分はいま避暑地の合唱祭に来ているかのような錯覚を覚えた。終演後、会場のそとに
出て、練習のため地下鉄の駅に向かっていると、こんどは自分はなんで、会議場の向かいにあ
るホテルで旅装を解き、ロビーで談笑してから、夕食をとるために友人と「旧市街」に出かけ
ていないのだろうと思いはじめていた。
そう、この世界合唱シンポジウムには世界中からお客さんがきているのだが、なかにはすぐ帰
国する人がいるにしても、大半はバカンスを兼ねてこの京都にやってきているのだ。会場を出
るとき、「See you, next Monday!」と声を掛けられて、日曜日は休みなのだと気づいた。日曜
にもやってくれたら、BKの練習のあと聞きにいけるのに、とオケ合わせのことをすっかり忘れ
て思ったのであるが、週末にしか休みのない人間から見るとこの考えは普通かもしれないが、
一週間も二週間もバカンスでシンポジウムに参加している人たちにすれば、中日に休まないの
はおかしいのかもしれない。観光をしたり、地元の教会にいったり、ホテルで休憩したりして
ゆったりと一日を過ごす。そういったことも含めて合唱シンポジウムを楽しむのだ。
くしくも、この前のアルティ声楽アンサンブルで、松下耕氏が「一週間以上まるまる仕事を休
めるような環境がないと、こういったフェスティバルを楽しむことはできない。そういう社会
を目指さないといけない」といったことを言っておられた。今、わたしにはこの言葉を実感し
ているのだ。悲しいことに、楽しめない立場に立って。
練習はシンポジウムのためのものだから、それ自体が嫌なのではない。練習と本番ともに、
音楽のことだけ考えて、心から音楽を楽しみ、友人とその楽しみを分かち合う、そんな時間が
欲しいだけ。昨日、今日、練習が終わって、明日になると会社に行き、仕事をして、それが終
わったらまた音楽をやって。普段ならそれでもいいのだけれど、せめて世界の音楽が聴けるこ
んな機会にだけは、仕事のことは考えないでいたかった。コミニュティコンサート、クロージ
ングコンサートが終わった後、演奏の余韻にだけ浸っていられたらいいのに。
第6回世界合唱シンポジウム・ハイライトCDを聞きながら。
- 2005/07/30(土)
第7回、世界合唱シンポジウムin京都、アフタヌーンコンサート出演。
気負わずに、歌おうと思っていたのだけれど、私自身、友人によると結構テンションが高かっ
たみたいだ。普段演奏を聴いてもらっている関西のお客さんだけでなく、全国のコンクールで
聴いてくれるお客さんだけでなく、いつも近くで聞いていてくれる友人だけでなく、本当に世
界中の音楽好きの人が目の前にいて、耳を傾けてくれている。こんなにやりがいのある演奏会
がほかにあるだろうかと思うと、自分のできる最大限のことをしないといけないなと無意識に
思ったのかもしれない。たしかに、こんなに笑い(ニヤニヤ?)ながら歌ったことはなかった
かも。いつもは、ベースの上は少ないから...と気負いの方が大きかったのに、今日は冷静さ
を欠くことはなかった、と自分では思っている。
演奏後、シンポジウム会場である京都国際会議場へ移動。CDなどの物販販売もやっており、
ロシアの民謡と、男声合唱曲、それから第6回の合唱シンポジウムのハイライトCDも買った。
売っているのはみんな外国人で、買っているのも圧倒的に外国人が多いのに、お金のやり取りは
すべて円だったのが面白いと感じた。
17:30から、世界的な講演や、学会が行われる大会議場で、VocalLineという団体のコンサート。
あの広い会議場が満杯である。普通、ここでコンサートがおこなわれるなんて想像もつかない
し、会場側も想定外だった思うが、始まってみるとこれがなかなか心地のいい空間だとわかっ
た。もともと快適に会議を行うためのゆとりのある空間、全体にいきわたるための音響、出席
者が疲れないための椅子、その配置など、目的は違えども音楽をやるにはこれほどぴったりの
場所はないわけだ。
もう一つ、ここで感じたこと。合唱とは無関係だが、この会館の建物だ。逆三角形の組み合わ
せ、斜めの柱、打ちっぱなしともやや違う、コンクリート造形の壁とデザイン、内装、そのど
れもが、よくよく見れば、とてつもなく未来的というか、非日常というべきか、斬新すぎる。
しかし、この建物が建ったのはバブルの20世紀末でもなく、最先端の21世紀でもない。
1966年、昭和41年。70年代の建物かと思ったが、それよりさらに前だった。これは
驚くべきことだと思う。同じ逆三角形の建物として連想される、東京有明の国際展示場なん
かよりも、はるかに先進的で、そして今日感じたのは、時代を超える普遍性を持っていると
いうこと。
ここに立ち入るのは3回目、大会議場に入ったのは高校一年のとき、ホーキング博士の講演
が行われたとき以来だ。あのころはその巨大さに圧倒されたこと、世界的科学者の講演を生
で聞くことに夢中で、建物自体にはここまで感心を払えていなかった。ときとともに、私の
なかに知識と経験が蓄積された。今、このときだからこそ、良さを十分に感じることができ
るのかもしれない。だから、若いときに気づけなかったことを悔やむ気持ちはなくて、建築
でも音楽でも、いろんなことはすべからく、そんな側面を持っているのだろう、そう思う。
18:30〜21:00クロージングコンサートの曲の練習。真近で見る大友直人氏は、思っていた
よりもずいぶん背が高かった。
22:00〜24:00キンコーズにて、編集作業。
進捗状況。
表紙、裏表紙 0%。
2〜3ページ 0%。
4〜5ページ 完成。
6〜7ページ 完成。
8〜9ページ 完成。
10〜11ページ 完成。
12〜13ページ 0%。
14〜15ページ 0%。
やっと折り返し。もうすぐ8月だ。追い込み追い込み。
そういえば、まだサークルチェックはおろか、カタログも買っていなかった。
いそがしい一日もやっと終わり。おやすみなさい。
あしたも忙しくなる。
- 2005/07/29(金)
昨日、録画した「電車男」のラストの方を見て、エンディングのサンボマスターの曲、「世界は
それを愛とよぶんだぜ」を聞く。なぜだか、なんどもなんども聞きたくなって5〜6回リピート。
このドラマはなかなかよいです。現実と夢のほどよい加減のファンタジーが、疲れた脳天を直撃
マッサージしてくれる。サンボマスターのギターと歌声が、それをいい具合にあんぷりふぁい。
昨日、録画した「かみちゅ」を見る。尾道が舞台のアニメで、中学生の女の子がある日突然、
かみさまになってしまうお話。カミサマといっても、「あぁ女神さま」のような西洋風のでは
なく、やおよろずの神さま、つまり日本のかみさま。そこにもあそこにも、ここにもいるたく
さんのカミサマたち。そのひとりにとつぜんなってしまって、友達の家の貧乏神社の神様をや
りはじめるのだ。お話とか、描写とかそれはもうほのぼのしていて、いいのだけれど、なによ
りひかれたのは、主人公が通う学校なのだ。
第一回の放送の番組がはじまって、地形とか風景から「尾道かなぁ」と漠然と思っていた。
それが主人公達が、昼休みに屋上に出る場面で、校舎のうえから引きの画面になったとき、
ああ、あそこだ!ここは絶対尾道だ!と確信した。そして、それはたぶん地元の人でなければ
自分にしかわからない!、というとても自信過剰な思いとともにあったのだ。
側面に上のほうが半円形になった窓が連なる、すこし細長い直方体の校舎。それこそ、はじめ
て尾道を訪れたとき、歩きに歩いて、歩きつかれたさきに現れた古い建物だった。いつのころ
かはわからないけれど、たぶん昭和初期くらいの面影のあるデザイン。小学校か中学校かはわ
からない。でも夏の初めの夕方の光に映える校舎がとても美しくて、行く手をさえぎる塀のう
えにカメラを乗せて、その姿をパチリと留めたのだった。
いまアニメのなかにあの校舎が映っている。なんだそんなことと思われるかもしれないけれど
架空の世界のなかに実在する、それも寸分たがわぬ姿で映っていることに、私はいたく感激し
てしまったのだ。このアニメを作っている人たちは、尾道に来たときにこの建物をそのままの
形で映さずにはいられなくなったのだと思う。勝手な思い込みかもしれないけれど、作り手と
受け手がその思いを共感できたこと、それがなんだか嬉しくて、「その思い、私にはわかる!」
などとおもってしまったというわけだ。
もちろん、尾道のよさは、その建物だけではない。それは物語中の街の描写からも伝わってく
る。「かみちゅ」、TV朝日、毎週金曜日、午前3:20放送中。いっぺん見てください。
あれ、この一連の行動は実は、わかりやすい逃避?
まだオーダーできてなかった。ショック...。
- 2005/07/28(木)
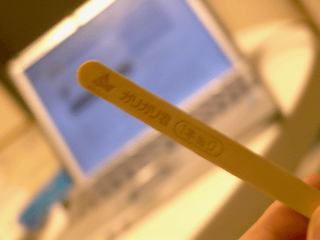
当たった...。たぶん十何年ぶりに。
パッケージには「当たりスティックは買ったお店で早めに交換して下さい」とある。
「早め」ですか。もしかして、焼印が消えてしまうんじゃないだろうナ。
明日は、NC練習。あさっては本番である。オーダー決めなきゃならんのだが、しかしいつもよ
り難しい。京都合唱祭のとき、BKの本番前にひとしきり時間をかけたのが「オーダー練習」だ
った。京都コンサートホールの山台は円弧を描いているため、前列と後列の人数を変えないとい
けないのだ。円弧を正面からみたときに美しい配置、そして最適な音色となるように。
BKならともかく、NCの皆にあの配置ができるか心配だ。
- 2005/07/27(水)
進捗状況。
表紙、裏表紙 0%。
2〜3ページ 0%。
4〜5ページ 完成。
6〜7ページ 完成。
8〜9ページ 完成。
10〜11ページ 0%。
12〜13ページ 0%。
14〜15ページ 0%。
今日、キンコーズで編集中に、SDカードのファイルを開こうとすると、「壊れています」とい
う恐ろしい表示が出た。幸い、そのファイルは自宅PCにバックアップをとっていたのだが、か
なり背中がぞぞぞーと来た。一応、製本見本用に出来上がるたびにカラー印刷しているので、そ
れを見ながら作れないこともない。が、あきらかに前よりも凝ったことがしたくなるので、それ
がこわい。6ページ分の印刷をこうやって並べてみると、あきらかに今日作成したもののほうが
レイアウトがうまくなっているのがわかるのだ。
漫画を単行本に掲載する場合や、映画をDVD化する場合に、加筆したり、再編集したりしたく
なる製作者の気持ちというのが、すこしわかった気がする。そして、だんだん同人誌の産みの苦
しみというものも、感じつつある。同人の大半は、私同様社会人が多い。仕事が終わってから、
毎日、決まった時間だけ作業を続けていると、だんだん肉体的、精神的疲労が蓄積されていくみ
たいだ。この感覚は合唱をやっているときの疲労と、似ているようでやや異なる。
一瞬の刹那の芸術性のために、繰り返し力を尽くすか、あるいは永続的な輝きのために、日々積
みあげていくか。目指すところの精神性は限りなく近いかもしれないが、そこに至る道のりは大
きくことなるし、物理的なものもかなり違う。途中で感じることが異なるのは当然だな。
お、ベランダのうえに、目をうつすと、雲間から月が。きれいや、ほんとに。
- 2005/07/26(火)

copyright NASA
私は、ただいまケネディ宇宙センターにいる(つもり)。今日、日本時間23:39にスペース
シャトルが打ち上げられる。コロンビアの事故から2年と半年。もっとながかったような気もす
る。H2Aも無事上がった。あと20分、無事に飛び立って欲しい。
今回のミッション、日本ではどの程度取り上げられているのだろうか。不覚にも一般紙をとって
いないのでうかがいしれないが、あまり盛り上がっているようには見えない。宇宙関係の映画を
あわせてTV放映することもなし。せっかく日本人宇宙飛行士、野口さんが搭乗するのになぁ。
しかも、ただ乗るだけじゃない。船外活動で、国際宇宙ステーションの組み立てをやるのだ。
船外活動ですよ!宇宙空間で、宇宙服一つで複雑な作業をする。想像もつかない。
ところがですよ!びっくりマークばっかりだが、その想像もつかない作業が生中継されるのだ。
http://www.jaxa.jpから、NASA提供の映像がストリーミング映像で、ミッションの全13日間
放映される。
もちろん、打ち上げ直前の今も絶え間なく放送されている。わたしのPCにはスペースシャトル
が打ち上げ位置に移動しているのが写っている。あと5分。ノズルから冷却材が出ている。もう
すぐだ...。
うちあげ成功!!やりました!発射から、メインエンジンが離脱するまで11分、まったく目が
離せなかった。高度があがるにつれそこに見えてきたのは漆黒の宇宙と、それをくっきりと区切
る地球だった。今、私は、世界中でこのストリーミング放送を見ている人は、地上にいながら、
宇宙から自分達がいる地球を見ているのだ。これってほんとにすごいことだと思いませんか。
打ち上げそのものの興奮もあるのだけれど、一般人である自分の眼が、高度何万キロという宇宙
にまで届いてしまったことに、しずかな感動を覚えずにはいられない。えらい時代に私達は生き
ている。
The right stuff、<正しい資質>を受け継ぐ者たちに乾杯。
追記:WBS(録画)を見ていて、尾道に行きたくなった。もともと夏休みに小旅行しようかと
思っていたのだが...あれはすごいなぁ。見たい。この目で見たいぞぉ。
- 2005/07/25(月)
夏コミ本、進捗状況のお知らせ。いやぁ、誰に知らせるってわけでもないが、しいていうなら
自分のためだろうか。いやいや、夏コミカタログ、CD−ROM版にはURLを掲載しているはず
なので、興味をもった方が見に来てくださっているかもしれぬ。進行は遅いですが、ちゃんと
13日に本は出る予定ですすめてますので、ご安心ください。夏休みに入ったら、別ページを
設けます。
「近代建築探訪 vol.1」、B4、16ページ、フルカラー。頒価500円(予定)
表紙、裏表紙 0%。
2〜3ページ 0%。
4〜5ページ 完成。
6〜7ページ 完成。
8〜9ページ 0%。
10〜11ページ 0%。
12〜13ページ 0%。
14〜15ページ 0%。
今日も、キンコーズにて作業を行ったのであるが、レイアウトに手間取り、1時間半かかって
しまった。作業の遅れはコストに跳ね返るため、後半は結構あたふた。しかし、考えてみるに
たとえ一時間半でも、結構疲れるもの。一日の作業量としてはこれが限度なのかもしれない。
下手に家で作業できていたらなば、凝り性の自分のこと、限度を忘れて深夜までということに
なっていた可能性はある。
さて、編集はキンコーズでやるとして、2〜3は序文と中表紙、14〜15は解説とあとがき
なので、テキストさえ打てれば良い。つまり家で並行してできる作業のはずである。ところが
である。これができないのだな。序文はほぼできているが、それ以外が手につかない。なぜか
というと、わたしはシーケンシャルな作業を好む人間なのだ。映画でいうと、作品の時間進行
通りに撮影を進めていくようなもの。本文の10ページを終えてから、あとがきなどの本文に
付帯するものを固め、仕上げるという形でないとなんだか落ち着かない性分なのだ。
なので、いまは思いついた文章を、ちょこちょこっとメモにとる程度。このメモが結構重要で
数多くの断片を後で、化学反応によって一気に化合物に仕立て上げるのである。学生時代の実
験レポートの考察はそうやって書いていた。この方法の欠点は、〆切直前までどんな形になる
のか自分でもわからないこと。かなりスリリングなことを毎週やっていた。おもえば、賭け事
は苦手なのに、よくあんな博打のような勝負を平気していたものだと思う。存外、マゾ体質な
のかも知れぬ。身体弱いのに。
- 2005/07/24(日)

成恵の世界、8巻発売。
朝、まどろみ。
昼、実家へ帰るも、誰もおらず。しばし犬と遊ぶ。マッサージ椅子に2回かかってから帰る。
昼、キンコーズにて編集作業。昨日作成したものに手をいれる。ちょっとネジが締まった。
夕、京都府立大学にてBK練習。
夕、京都府合唱祭。京都コンサートホール、大ホールにてBK演奏。
夕、資料用として演奏テープを買う。しまった、うちにはテープを再生するものがない...。
夜、終演直後から頭イタイ。
夜、談にて「成恵の世界」8巻を買う。
夜、大丸にて食パンを買う。最近、食パン生活。
「成恵の世界」を読むと、ほかほかと幸せな気分になる。人に優しくなれる。そんな気がする。
だから好き。
- 2005/07/23(土)
NC練習前にキンコーズへ行き、夏コミ本の編集をする。もともとメインマシンのPhotoshopLEを
使って編集しようとしていたのだが、メインマシンがお亡くなりになってから久しい。それなら
ばと思い、実家に帰ってインストールディスクを探したが、CDやらCD-ROMの山にうずもれてみつ
からず。八方手を尽くして、最後に思いついた手段がキンコーズであった。そういえば、カタロ
グイラストも結局、ここで作ったのだ。
Photoshopを使うのは、単純に慣れの問題で、そんなに高度な機能を使いたいわけではない。レイ
ヤーと、文字レイアウト機能、解像度変更くらいなものか。編集していて気づいたのは、LEでは
とてもこの作業はできなかったなーということ。LEはレイヤーが3つまでしかないので、それを
こえるといちいち結合しなければならない。今回のように多数の写真をいくつもレイアウトする
場合には無制限のレイヤーがないと話にならないのだった。
事前に写真を絞りこみ、机上でレイアウトを検討していたが、「現場」に赴くとやはり「臨機応変」
になる。作業をしながら、やりたい形が定まっていく。1時間半かかってようやく二ページ分の作
成を完了し、ためし刷りしてみた。そう、実はオフセット印刷ではなく、大量プリントアウトによ
って本を作る計画なのである。ここならば、作成→入稿はもちろん、印刷、裁断、製本までできる
のだ。オフセットでは難しい小部数生産もできる。だってオフセットは最小100部から。どう考
えても100部は売れないよねぇ。
難点は一部あたりのコストはやはりオフセットにはかなわないということ。トータルコストでも、
3〜4万円の差しかないし(絶対額が結構あるのです)、印刷する紙の選択肢も実は少ない。
しかし、その難点をおぎなってあまりあるのが、すべての同人作家にとって最大の問題、納期ある
いは〆切である。オフセット最短5日に対し、キンコーズ印刷1日!しかも現場でぎりぎりまで手
直しできる。もちろんPC利用代金はかかるのだが、それくらいの制限があるほうがかえって、緊
張感で集中力が増して作業効率がアップする。特に私のようなギリギリ人間の場合。
まぁ、本音をいえば、カラープリンターを買って、家内制手工業でちょぼちょぼやるほうがお金は
かからないので、次回からはそうしてみたいが、社会人にとっては時間は貴重なのと、今回はまだ
探りなので、細かいことは終わってから考えることにしたい。
残り12ページ+表紙+裏表紙。まだ終わらないうちから、買ってくれた人に何かおまけを差し上
げたいなぁとか、冬は少し別の企画で、夏にまた同じ形態のものにしようとか、いろいろ浮かんで
くる。頑張ろう、頑張ろう。今自分で考えて、自分だけでできることは、これしかないんだから。
- 2005/07/22(金)
電車のなかで、消費者金融の広告を見ながら思ったのであるが、最近のそれら金融の広告に面白
い現象が起きているように思う。曰く、「ご利用は計画的に」という、本来は広告の最後に警告
として表示される文言が、広告そのもののメッセージとなっている点である。
海岸で半身だけ日焼けしてしまったり、バナナボートを牽引するものを用意できなかったり、は
たまたバーベキューで肉を忘れてしまったりと、すべてが「計画的に」ということをうったえて
いる。これは広告の本来の目的をあきらかに逸脱しているではないか。計画的であることをコン
ト仕立てで、面白く見せることに力が入り、それがすっかり主体となっている。
これに対して、銀行系の金融、モビットやアットローンなどの広告はむしろ積極的にこんなとき
には借りましょう、借りれればいいことがありますよとまで言い、「借りさせる」つまり、本来
の広告の目的に忠実に作成されている。
よいか悪いかは別にして、このほぼ二極化した現象は、分析するに値する非常に興味深い現象で
あるなぁとふと考える、BK練習に向かう車内であった。
きょうを思い出すことば:よこがおと、水と自転車。
- 2005/07/21(木)
コーラ牛乳割り、賛成1票。
暑いです、会社が。私がいる2階のフロアは普段から、空調がわるく、もともと暑い職場だったが、
それでも夏はやはり外に比べると格段にすずしいのだった。それが、最近、お昼の所感で「暑い」と
公言するひとが増えてきた。わたしもむろん暑いのはいうまでもない。それもこれも28度設定のお
かげである。
6月に風邪をひいた原因は空調が24度くらいになっていたせいだが、それが一転28度になると、
これまた逆に熱中症になりそう。頭がぼーっとしてきて、片手うちわが手放せない。所感でもあった
意見なのだが、うちの職場の総務はおかしい。28度にしろー!というだけで、その代替手段を何も
示さない。つまり、クールビズにしていいですよとか、作業服を脱いでTシャツでもいいですよとい
ったことだ。本社に命じられるまま、温度をあげているだけ。いったいなんのためにやっているのか
わかっていない。ちなみ、エアコンの端末のまわりにケースをつけて、南京錠をとりつけてある。そ
んなところに金と手間をかけるなら、いかに快適に仕事ができるかを考えるべきなのにナァ。
普段、何も文句を言わないひとが「暑い〜」というから、よっぽどのことなのだ。仕事がなんとか
できるかなぁというのが日が暮れるくらいなんだから、業務効率は下がっている。うちは27度にし
ます、理由はこうだからです、って本社に言えないのか。世間に対するポーズだけの28度はいらな
いぞ。ぷんすか。
ネガティブなことを書いてしまいました。お許しを。
- 2005/07/20(水)
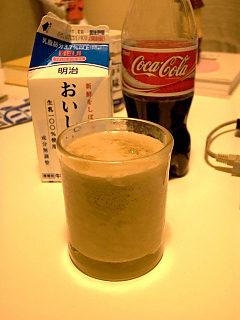
コーラと牛乳を1:1。一見、カフェオレ。
夏はやっぱりコーラの牛乳割りである。親から子へ、そして孫へと伝えられるべきものと信じてい
たのであるが、世間に出てから(小学生以降)というもの、ただのひとりも賛同者に出会ったこと
がないので紹介することにした。我が家では割と定番であったが、いつのころからか飲まなくなった。
そうだなぁ、コカコーラの容器がビンからペットボトルに変わったくらいからか。
重たくて、丈夫そうで、つややかな緑いろの瓶をもって、夏の夜道をタバコ屋(パン+お菓子屋)
に行くのである。瓶を返却すると返してもらえる30円を足して、またまた1.5リットルの瓶を店の
冷蔵庫から引き抜く。びんとともに引き抜かれる白い冷気が、一種神々しかった。あれが私の
夏の原風景。
- 2005/07/19(火)
仕事帰りの本屋で学研の「大人の科学」を見つけた。今回は「スピーカーを作ろう」とある。
スピーカーユニットを手作りしようという企画。さらにそのユニットをとりつけるためのボディ
をいろいろと紹介し、設計図までのっている。これはー、なんというかかなりマニアック路線で
あるなぁ、と思いながらながめていると、「長岡鉄男の残したもの」という記事がある。
あれ、残したものってことは亡くなったのか...?いま思い返すとすでに3〜4年前にその訃報
を聞いたような気もするのだが、すっかり忘れてしまっていた。そうか、スピーカー特集でこの
人を抜きには確かに語れないもんな。
長岡鉄男はオーディオ・音楽評論家としての顔と、「毎月スピーカーを設計して作っているおっ
さん」のふたつの顔があった。後半の顔は、中学生のときの私が思っていたことだ。当時、愛読
していた「ラジオの製作」という電子工作・アマチュア無線・オーディオの雑誌があって、その
なかで、毎月、ほんとに毎月、設計も含めて完全自作のスピーカーを製作する記事を連載してい
たのが長岡鉄男だった。まだ、オーディオに目覚めていなかったわたしは、ほとんど読み飛ばし
ていたのだが、いま読んでも理解できるかというと自信がない。スピーカーの設計って何するの
かというと、あのスピーカーの箱の中の空間をどういう風に区切るかということにつきると思う。
バッフル板といって、音源のまわりに設置する板の形状によって音響というものは変わる。そし
て、音というものは、前だけでなく、後ろにも進むので、音源のうしろの音がどのように流れる
のか、通り道をせまくしたり、広くしたりすることで、そのスピーカーの音の特長が決まるので
ある。音がすすむ方向を工夫してもよい。わかりやすい例は、トランペットやホルンなどの金管
楽器だろう。チューブがくねくねと何重にもなっているのがそれだ。
で、まぁスピーカーの場合は四角い立方体の空間をくぎるだけなので、かなり単純なものだった
りするのだが、それでだいぶ音質が変わるようなのだ。そんな設計を長岡鉄男は数千以上てがけ
たらしい。それも商売でなく、自分の趣味でだ。
で、記事を読み続けていくと、長岡鉄男を師とあおぎ、その志、つまり高価なスピーカーをかわ
ずとも、きちんと設計し、製作することで自作のものでもいい音はなる!ということを受け継い
だ人たちがたくさん登場。ああ、こんなのを見るとあおられてしまうのが自分なのだ。いつのま
にか、スピーカー作ってみたいナァなどと思ったりしているのだ。
スピーカーは基本的に合板をカットして組み合わせるだけなのだが、このカットがやっかいで、
特にユニットをとりつける丸穴はいかにもめんどくさそうだ。そういう部分で敷居が高いため
興味はあってもおいそれとは手をだせない。はずだったのだが、いろいろ調べてみる(調べてる
時点でやる気)と、カット済みの合板のキットが売っているではないか。それもいろいろな形状
のもので、値段も5000円〜1万円前後。(ユニット抜きだが)合板の種類や、仕上げによっ
て若干変動するようだ。それでも木工ボンドひとつで組み立てられるとなると、プラモデルくら
いしか経験のない自分でも作れそうな気がしてくる。
・・・やってみたい。よし、今年のどこかでやると決めた。
追記:この手の分野に女性の姿がまったく見えないのは、なぜなんだろうか。興味をそそられな
いんでしょうか?聞いてみたい。
- 2005/07/18(月)

麩屋町三条上ル、晦庵河道屋(みそかあんかわみちや)。
突然、自分のなかでディスカバー京都キャンペーンが開催されることが決まった。京都の人間は
京都のことをあまり知らない。観光地にはありがちかもしれないが、自分の生活圏以外にある神社、
仏閣、店などにはほとんど行った事がなかったりする。そうすると、よそから来たひとに京都を案
内してほしいだとか、お土産にはなにが良いであるとか、お昼はどこがお薦め?などと聞かれると
実は返答に窮してしまうことがあったりする。お土産のお菓子などならば、自分の経験でこたえら
れる場合もあるが、いかんせん経験が浅いので幅が狭い。この間も親に聞いて最適解を導き出した。
親に知恵を借りるのはまだしも、情報雑誌を見てなるほど〜と、うなづかされるのは、なんとなく
癪である。(素直に、「情けない」といえないのだな。)というわけで、急遽名前は知っているけ
れども行った事のない店、入ったことのない場所などに出向いて、見聞をひろめようと思った次第
である。
不定期連載の第一回は、麩屋町通り(たての通り)を三条通り(よこの通り)から、上がって(北
に向かう)いくと左手に見えてくる、晦庵河道屋にした。有名なおそば屋さんである。外から見た
ことはあったけど、その外観におそれをなして入るのをためらっていた。なんだか料亭旅館のよう
であるので、おしながきに値段が書いていないとか、ノーネクタイでは入れないとか想像して、勝
手に敷居を高くしていた。であるが、入る前に店先にある値段表をちゃんと見ると、ほかの普通の
そばやと大差ない。そうしているうちに食べ終えたお客さんがでてきたが、いたって軽装の観光客
のようであったので、なんだ気軽に入ってもいいんじゃないかと勇気がでた。
もともとこういう落ち着いた建物は好きだ。ためらうことはない。石畳を歩き、いりぐちに手をか
ける。木陰になっていて涼しい。
なかにはいると、屋根のように木で組まれた中央がとがった形の天井となっている。数奇屋づくり
?なのだろうか。奥までつづく長い土間の左に小上がりの畳敷きがある。照明はほぼ中庭からふり
そそぐ太陽光のみ。私好みの「自然のあかりの反射光」と「ほどよいくらがり」じゃないですか。
席はほかに中庭の奥にある別室に椅子席があるらしい。私のあとに来たお客さんは人数が多かった
のか二階に通されていた。雰囲気がよかったので、そのまま小上がりの一角をひとりで使わせても
らうことにした。
これは特長だと思うのだけど、机の高さがえらく低い。あぐらをかいて座ったときのひざくらいの
高さだから、20cmくらいか。正座してたべるとなるとかなり前かがみになってしまうから、ここは
あぐらをかくのが一番なんだろう。なので、スカートの女性は椅子席の方がいいのかもしれない。
注文してほどなく、目の前に器がおかれる。いたってシンプル。量もほんとに普通の「にしんそば」
を頼んだ。にしんそばって、関西にしかないというのはほんとなんだろうか。関東ではやはりそば
にはてんぷら、かきあげなのかもしれない。とにかく、ずるずる食べる。もちろん熱い。暑い夏に
熱いそばを汗をかきながらふうふう言いながら食べるのが、なぜだが気持ちがいいのである。
食べ終わって、畳のうえで少し足を土間の方に伸ばしてくつろぐ。厨房の音がすこし聞こえるだけ
でなんと静かなのか。時折聞こえるほかのお客さんのずるずる音が、いいリズム。ここは単に食事
をするだけでは収まらない居心地のよさがある。いままで来た事がなかったなんて、もったいなか
ったなぁ。というわけで、まだ椅子席、二階席は未体験なので、インターバルを置いてまた行って
みようと思う。
お腹がふくれたところで、アルティ声楽アンサンブルフェスティバル2005の二日目に出発。
今日は、少人数アンサンブルが中心の公募5組、招待1組。きょうは短めに。昨日の演奏はどれ
も豊かで押し寄せるものが中心だった気がしたが、今日はどの団体の歌を聞いていても、高原で
森で、海でゆっくり深呼吸するように音楽を吸収することができる、そんな気負わない優しい歌
を感じた。夕飯を気持ちよく、たっぷり食べることができたのは、そんな音楽のおかげだったの
かもしれない。
追記:マイケル・J・フォックス主演のコメディ「SPIN CITY」が最終回。ああ、これ
から何を楽しみに月曜日をすごせばいいんだぁ。あんなお馬鹿なコメディはなかったというのに。
人生には歌と笑いが必要...。
- 2005/07/17(日)
アルティ声楽アンサンブルフェスティバル2005を聞くために、14時すぎにアルティへ。
山鉾巡行は正午くらいに終わっているから人も引けているだろうと思っていたら、まったくの見
当はずれで、室町から、新町から人が溢れてくるくる。そう、巡行が終わったあと、各鉾町へも
どる姿もまた見物なのだ。そして帰ったあとは分解作業もある。本当に無駄なところがひとつも
なく、ひとつひとつの作業までが祭りであり、文化財なのが祇園祭なんだなぁと再認識した。友
人からのメールに「町中人がいっぱい」と書かれていたのは、そういう理由だったのだな。
さて、アンサンブルフェスティバル。今日と明日開かれて、初日の今日は公募団体4、招待団体1
の演奏のほかに、作曲家・合唱指揮者の松下耕氏のワークショップがあるのである。テーマは和音
とカノン。一時間の内容をここでひとつひとつ再現はできないので、そっちょくに思ったこと。な
んだろう、モデルの曲もないし、五線譜を使った説明もない。ただ、耳をつかって、記憶をつかっ
て、皆で声を出す。それだけのことなのに、すごく楽しいと感じる。合唱をやっていると感じるの
だ。じゃぁ、昨日の合唱は楽しくなかったのかというと、それは違って、今日体験したことがあれ
ば、明日からの合唱は昨日よりも、もっと楽しく、もっと美しいものになるんじゃないかというこ
となのだ。
合唱で大切なのは耳を使うこと。でもそれを、今日まではすごく狭い意味で考えていたのかもしれ
ない。あるいは一次的すぎた。松下氏は耳を使うことは、記憶することと言った。その次にあるの
はたぶん、想像力なのだろうと、いま思っている。
印象に残った演奏について記録しておこう。
枝幸ジュニア合唱団。数年まえ、はじめて聞いた歌声から、たしかに彼女達の声は変わっていて、
素直な発声はそのままに、とてもしっかりした、ぶれのないものになっていた。音が発せられる
そのとき、自転車がするりと動き出すように、滑らかで、よどみがない。そこかしこに流れてい
る音楽の川を、ひょいときりとって自分たちの頭上に流れをつくりだす。なんの不自然もない。
北海道岩見沢という土地ではぐくまれたことに、それは無関係ではないのだろうなと思う。この
アルティという日本でも稀有な響きを持つホールでさえも、彼女らの歌を存分に表現しきるには
十分じゃないんじゃないかと、そんな錯覚を起こしそうになるほどだった。どんな歌声もききも
らすまい、そんなおももちでずっと目をつぶって聞いた。
徳島男声合唱団「響」。三木稔の阿波、そして松下耕の日本の民謡より、NCが昨日演奏した
刈干切歌、津軽じょんがら節。それが彼らのいつも演奏スタイルかどうか、わからいけれど、
これら民謡を基調とする作品を演奏するのに、指揮なしというのはとても自然なことに思えた。
そうなのだ。民謡は自発的なもの。主役に対する脇、脇に対する主役の切り替わりや、あいのて
の入り、それらは歌い手同士の相互の呼吸で感じるのが当たり前なのだ。
演奏はまさに、互いの呼吸を感じ、伝えることがわかる、本当に密度の濃いものだった。そして
きちんと合唱だった。これ以上ないくらい5度が鳴り止まない男声合唱。同じ男声として、これ
を目の前にして、一緒に歌いたくなる気持ちを押さえるのに苦労した。うずうずしっぱなし。
女声アンサンブルJuri。うまい合唱というものは、見方によってはとてもつまらなく聞こえて
しまうことがある。あまりにもきれいで、精緻なものに触れるとそういう反応を起こしてしま
いそうになる。しかし、本当にうまい合唱というものは、そんな雲をかんたんに突き抜けて、
想像もしたことのない新しい音楽の世界を垣間見せてくれることがある。Juriの演奏はまさに
そうだった。技術的なことをいうと、今日演奏をした団体のなかで、一番ホールの使いかたが
うまかったと思う。自然にまかせて、ホールに身をゆだねる合唱ももちろんある。でも、ホー
ルのもつ特性を理解して、それを最大限活用するという歌い方もあるのだ。そして、それをで
きる合唱団にはあまり出会ったことがない。というか、私自身今日まで、そのことをここまで
はっきり実感したことはなかったのだ。
昨日は、演奏をやる立場での合唱の喜びを得た。でも、すごく疲れたのも確かだった。今日ま
た同じ合唱によって、身体と精神が不思議なくらい元気を取り戻していくことがわかった。こ
れが演奏を聞く立場の合唱の喜びなのだ。どっちの喜びも味わうこと、合唱をやっていくうえ
で、それはとても大切ことなんじゃなかろうかと思う。疲れたら取り戻さなくては。疲れるだ
けの合唱、音楽ではいずれ力を失ってしまう。相対するものがあること、それがいろいろなこ
とを生かしているはずだ、と私は思うのだ。
- 2005/07/16(土)
国立音楽大学女声合唱団アンジェリカ&なにわコラリアーズ合同コンサート@NHK大阪ホール。
09:00 統括マネージャー、ステージマネージャー集合
10:00 ロビー統括マネージャー、パートマネージャー集合
11:30 団員集合
12:00 リハーサル開始
17:00 開場
18:00 開演
つかれたけれど・・・、こんな気分のいいつかれかたは、嫌いじゃないのです。
- 2005/07/15(金)
BK練習を休んで、NC本番直前練習。
帰宅後、NCマネージ。
演奏会の前日、ゆっくり眠れたためしがない...。緊張してというナイーブな理由ではなくて、
ただ単純にマネージのせい。ようやくオーダーも決まったので、風呂に入って寝る。前日が一番
しんどい。
- 2005/07/14(木)
予想通り、四条室町から下って帰宅することは不可能。綾小路にある弁当屋ですら人ごみで看板
すら見えない。それはそうだ、弁当屋の真正面に鶏鉾が立っているんだから。長岡京で、さぼて
んのロースかつ弁当を買っておいてよかった。のだが、室町から烏丸まで取って返すのもなかな
か大変だった。本当に人が多すぎる。鉾がほとんどない烏丸も、御池あたりから、高辻にいたる
まで、迂回路を形成するために歩行者天国となっているのだが、鉾もみずにたむろっている人た
ちのなんと多いことか。あの人たちは、いったいどこから来て、何をみて、どこへ行こうってい
うんだ。
浴衣を着て、屋台を冷やかして、祭り気分を味わいたいだけなら、よそにいってほしい。もっと
静かで、味わい深い、大人な祭りであってほしい。こんなこと思うのは京都人のイケズ精神のせ
いなんだろうか。
帰宅後、NCマネージ。
(ほんとは仕事中もちょこちょこ。内緒。)
- 2005/07/13(水)
早いもので、祇園祭の山鉾の鉾立て、飾りつけも終わり、今日から提灯に灯がともりはじめた。
まだ屋台が出ていないので、道も歩きやすく、帰宅しながら眺めることができた。地元の人間が
楽しめるのは今日までかもしれないなぁ、と思いながら歩く。いやぁ、やっぱりうちの近くでは
船鉾がよいですね。
さて、祇園祭りはさせておき、オークションの話である。過日、落札しそこなったと述べたので
あるが、需要あるところ供給あり、私の予想は見事にはずれて、またもや探していた商品が出品
されたのである。今回は過去の落札ゾーンを踏まえて、慎重に落札額を決定。最初から最高額を
狙って入札した。結果として、ほぼ落札ゾーン内の価格で落札。オークションといえども確かに
「相場」というものが存在するということを確信した次第。なお、落札した直後、また別の人か
ら、同じ商品が出品されており...あきらかに、多数の人が様子を伺っていることがわかる。
約束でしたので、披露いたします。とくとごらんあれ。
 
コトブキヤ、ToHeart保科智子、私服版。1/8スケール、塗装済み完成品フィギュア。全高約20cm。
 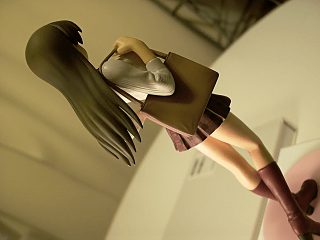
原型製作、TSUKURU SHIRAHIGE。良い仕事です。
解説、ああちょっとそこの方、引かないで。最後まで見てってください。では、解説。コトブキヤ
というのはフィギュアのメーカー。もともとガレージキットといって、プラモデルの上級版ともい
言うべきキットのメーカー。このフィギュアも3〜4年前?にガレージキットとして発売されてい
る。つまり、色は塗っておらず、全身が6〜8程度のパーツに分かれた状態が標準で、価格は1万
円以上した。その製作工程は素人にはなかなか難しく、モデラーと呼ばれる模型製作趣味に通じた
ある意味、忍耐力特性を持った人間でないとこのような完成品に仕上げることは至難の業であった。
それがいまや、このレベルの完成品状態で、価格は3分の1近く。お察しのとおり、中国製です。
フィギュアは顔、特に目の塗装が難しいようなのだが、いともたやすく量産してしまう中国の職人
さんは正直すごい。こんなものが売っていると、ますます普通のプラモデルからステップアップし
てフィギュアを作ろうとうい人は減るんじゃなかろうか。というかすでに減っていると思われる。
解説2、ToHeartとは、保科智子とは、私服版とは。ToHeartは1995〜6年ごろに発売されたPCゲーム
で、ジャンルは18禁。学校が舞台の恋愛アドベンチャーなのだが、ノベルウェアといって画面の女
の子の絵のうえに、ストーリーや会話が文字で記述されるという「読ませる」形式のゲームで、当
時は非常に珍しい形式だった。これがいわゆるほんとに普通の学園18禁ゲームだったのにもかかわ
らず、コミケにおいて、美少女ゲームジャンルを築かせるきっかけとなる大ブームを巻き起こした。
それにとどまらず、なんと18禁をとってしまいPSなどの一般ゲーム機に移植までされた。そのうえ
アニメ化までされたのである。18禁ゲームがアニメ化される場合、そのまま18禁アニメになりそう
なものだが、ToHeartの場合は深夜枠とはいえ、かなり正統純粋な恋愛ストーリーとして描かれ、
作画、演出のレベルの高さは皆(アニメのひとたち)を驚かせた。なお、昨年二度目のアニメ化
がなされている。なんだか、概論ばかりであるが、勘弁。
さて、保科智子とは作中に登場する女の子のひとりで、主人公のクラスの委員長をやっている。
おさげで、関西弁で、眼鏡である。メガネ、めがね。主人公に対する好感度は女の子中、最低と
なっている。オープニングでも睨んだ顔しかうつっていない。ところが、これが彼女に近づけば
近づくほど、「ええこや〜」ということがわかるのである。主人公に心を開いていくあたりは、
作中一かもしれない。そんなわけで、地味なのに、その「可愛さ」にやられてしまった人は多い
のではないかと思われる。人気の度合いはあきらかにヒロインの女の子を食ってしまった。
ところがである、上の写真はおさげでもないし、メガネもかけてない。ゲーム中では一度もメガ
ネをはずさないのに!そう、美少女の定番、メガネとったらカワイイというのも、委員長につい
ては例外で、メガネをかけていてもカワイイのである。であるが、アニメ化されたおり、なんと
私服で外出する委員長が描かれたのである。メガネをかけててもカワイイ委員長はメガネをとっ
ても可愛かったので一安心。それどころか委員長ファンの入れ込みは加速したのだった。
で、長かったがこれがこの委員長フィギュアの成り立ちである。前にも述べたが2月に発売され
たおり、あっという間に完売。ほかの女の子ももちろんフィギュア化されたが、ここまで圧倒的
に売り切れたのは委員長だけだったようだ。というわけで、私は見事に買い逃した。
なお、コトブキヤの別売りのキットで、このフィギュアにちょうど合う「メガネ」が用意されて
いると聞く。やはり、委員長にはメガネをかけさせたいので、こんど買ってこよう。
おわり。(今日はなんだかつっぱしってしまった・・・。)
- 2005/07/12(火)
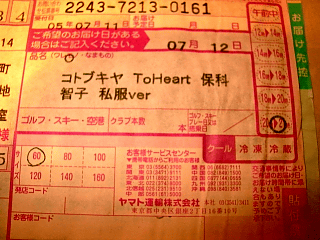
オークション落札品が到着。詳細は明日。しかし、こんなにはっきり書かれるとは。恥ずかしいナァ。
親(鍼灸師)に電話し、まぶたのけいれんについて対処法を聞く。計6箇所のつぼが関連。うち、
痛みのある2箇所を告げると「軽症」とのこと。NCマネージをしながら、”ばいかしん”(過去
ログ参照・・・日付は忘れた)で、血が出るまでぶったたき中。
- 2005/07/11(月)
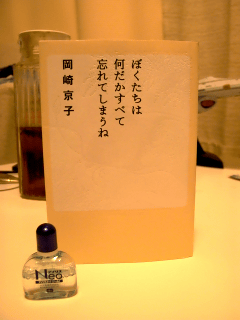
頭が、振り子のようにお腹のあたりを軸にして、前後に振れるのである。これをめまいというのか、
立ちくらみというのか。座っていても、起きるのだから、めまいなんだろうな。相変わらず、左の
まぶたがけいれんするので、左目を閉じたまま、右目をあける練習をしてみた。そんなことは誰で
もできると思うかもしれない。でも違うのだ。片方の目だけ、眠るように自然にまぶたを閉じるの
である。普通にこれをやると、しかめっ面になってしまい、なかなかに難しいのである。
私の場合、左目閉じ、右目開けでは国体優勝くらいのレベルなのだが、左目開け、右目閉じとなる
とまるでビギナーなのである。利き腕や、利き目と関係がるのやもしれぬ。私の利き目は左なのだ
が、その左目を閉じる方が得意というのは、なぜだろうか。やはり筋肉の運動なので、利き腕の影
響力のほうが強いのだろうか。
こんな日に限って、仕事がうまくいくのである。並行してすすめている仕事、いずれもプログラム
であるが、3つとも詰まっていたのが、今日一挙に3つとも前進しはじめたのである。そうなると
ずんずん進めたくなるのが人情だけれど、目と頭と手の連結が悪くて、進まない。停滞していない
からといって、ものごとは進んでいくとは限らないのだった。
帰り道、目が痛いのを忘れて本屋に寄ってしまい30分をすごす。そう、「ぼくたちは何だかすべ
て忘れてしまうね」とは、まさにそのときの私のことだった。買ったはいいが、しばらく読めない
のだろうなぁ、と店を出てから気づくのだった。
早めに寝ます。
- 2005/07/10(日)

いつの間にか、スルッとKANSAIのカードを集めている。カードホルダーにファイリングして
いるのだが、先ごろ120枚入りがいっぱいになってしまった。一応、使ったものはすべて残して
いるのだけれど、やはりこれは特に残しておきたいものというのが何枚かある。今度、集めたもの
のなかから、セレクションして別のホルダーに収めようと考えている。
そのセレクションにすでに入ることが確定しているカードが写真の4枚である。ほかにもあるのだ
が、うえの4枚はいずれもKカード、つまり京阪のカードなのだ。そして、私の持っているKカー
ドはこの4枚ともう1枚の計5枚のみ。その1枚はうつし忘れただけでセレクション入りの予定。
つまり、持っているものすべてがコレクションに入るという、他社のカードと比べて群を抜く選抜
率の高さなのだ。
見ていただければわかるというか、まぁこれは私個人の基準なのだけど、選抜率が高いのは、その
デザイン性が群を抜いているからである。昨日、淀屋橋から帰る時、手持ちが2000円しかなかっ
たので普通に切符を買おうと思っていたのだが、販売機に示されたKカードが、写真左下の電車の
写真のものだとわかったとたん、1000円を突っ込んでいた。阪急のラガールカードにも、保有
車両の写真をつかったものはもちろんある。が、それはいずれも「鉄道写真」と呼ばれる、走行風
景を写したものをそのままカードとして使っているだけのものだ。
それに対して、このKカードはそういった鉄道写真とは一線を画している。阪急に比べて色とりど
りでデザインも豊富な車両をそろえているのにもかかわらず、モノクロ。そして、台座にあたる部
分が赤一色という大胆な組み合わせ。およそ、鉄道が写っている写真としては想像できないデザイ
ンなのである。そして、カラーの場合でも右上のように、写真は使わず模式図のような車両を使っ
ている。それも普通に考えられる走行状態ではなく、模式図の域をあえてはみださず、まるで模型
が宙に浮かんでいるかのような図としている。Kカードのデザインには筋が一本通っていると私は
思う。どのような素材であれ、Kカードとして高いデザイン性で統一するという意思が感じられる。
アーティストの絵を使った2枚のデザインにしてもそうだ。アーティストの絵が主体でありながら、
"Moving Kyobashi"というメッセージ性がそれに負けずに主張されたレイアウトになっている。
結局のところ、何が言いたいのかというならば、Kカードは同じ値段でも手にしたときに、ちょっ
と得したような、そういう気持ちにさせてくれる。プレミアのような存在感がある。だから、必然
的にセレクトしたくなるのだと思う。
京阪に乗ることは少ないけれども、淀屋橋から帰るときは、なるべくカードを買って帰るようにし
たいと思っている。
- 2005/07/09(土)
 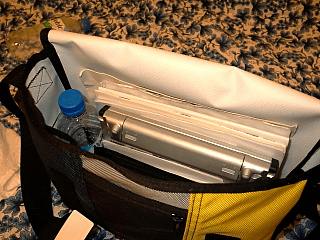
TIMBUK2、クラシック・メッセンジャー(スモールサイズ)。
・色は、Navy blue - Silver - Yellow。インナーはWhite、ロゴマークはGoldを選択。(+$10)
・左下げ仕様(ストラップのアジャスターが、正面向かって左についている)を選択。(+$0)
・自転車乗りには必須の、リフレクター(反射板)装備を選択。(+$0)
・オプションとして、Grab(持ち手)を装備。(+$10)
・スモール標準$60+$10+$10=合計$80。
スモールとはいいながら、A4サイズの楽譜、B5ノートPCが余裕で入るし、500mlのペットボトル
も縦にすっぽり収まってしまうから、見た目よりも容量がある。週末のNC練習に行くのにぴったり
だし、通勤もこれでいけそうだ。ビニールレザー素材にありがちな安っぽさがなく、各部のつくりも
とてもしっかりしている。ひとめで、長くつきあっていける相棒であると感じた。ふふ。自然と笑み
がこぼれてしまう。
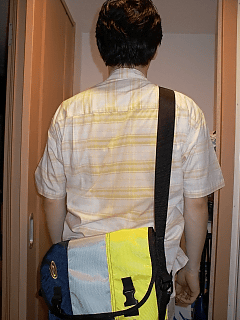 
モデル:山Dさん
自転車に乗る場合は、バッグ本体を腰にまわし(写真左)、サブストラップで固定する(写真右)。
このサブストラップのおかげで、驚くほどバッグの安定性が増すのだ。これこそ街の自転車乗り、
メッセンジャーの知恵から生まれた工夫。ちょっとしたことなんだけども。
肩こりによる疲労のためか、めまい。自宅に戻ったあと、19時ごろまで休息。正直しんどかった
が、マネージがあるため半ば義務感でNC練習に遅れて参加。しかし、今日は久しぶりの復活メン
バーも多く、みんなの歌声も活き活きした感じ。そのせいもあって、すこし元気回復できた。
練習終了後、マネ会+ところにより宴会。23時20分、淀屋橋発特急にて帰京す。
発車直前にトイレに向かったNC指揮者が、乗車できたかどうかは定かではない…。
- 2005/07/08(金)
天下一品、京極店(八千代館まえ)で「ハンバーグ定食」を頼んだら「春巻定食」がでてきたので
びっくりした。春巻が意外においしかったので、まあよいか。・・・語尾の「ぐ」が弱かったか。
今日はBK練習後、宴会参加者が皆無だったので、一人で食事した次第。
TIMBUK2、メッセンジャーは、無事到着したのだが、なぜだか実家にある。昼ごろに親から
「ガイコクヨリ、ニモツトドク」というメールがあってわかった。どうやら、申し込み時に書いた
実家の電話番号にUPSが電話したようだ。クレジットでモノを買う場合、登録電話番号との照会
をする場合もあるので、そのようにしたのだが、まさか電話番号で実家の住所までわかるはずもな
い。親に直接確認したところ、「こっちに届けてもらうようにゆった」とのこと。まぁ、こちらは
留守宅なので、そのほうがありがたい。それにしても、UPSは意外と融通がきくのだなぁと感心
する。
ここで、TIMBUK社には謝らないといけない。まだモノを確認できていないが、確かに私のオ
ーダーしたものは届いているはずなのだ。そう、昨日、オーダー確認のメールをちゃんと読み直し
て見たところ、「カスタム品の場合は、ちょっと時間が欲しい。1〜2日で仕上げるから」と書い
てあることがわかった。では、21日という数字はなんの数字か?
"For international customers using E.U. Consolidated"の場合らしい。らしいと書いたが、こ
のE.U.Consolidatedってのはなんなのだろう。固有名詞でもなさそうであるし。ともかく、UPS
を利用できない場合は、こちらに当てはまり、毎週金曜日に発送で、それが21日かかるというの
だ。わたしは最初読んだとき、インターナショナルと、21日の部分にしか目がいっていなかった。
「1〜2日」というのは読んでいたのだが、アメリカ国内の場合だろと勝手に解釈していた。
実際は国内外問わず、配送込みで4日間という驚異的な早さだったのだ。
21日だと誤解した理由はもうひとつあって、日本国内でカスタムオーダーしていたときは、ど
この店でも納期は約1ヶ月であったらしく、その日数と21日(つまり土日を入れると一ヶ月)
がぴったり来るので、直接オーダーでもその日数だろうと思ったのだ。よくよく調べてみると、
日本の場合は、オーダーを一か月分とりまとめて、米国に発注していたのだ。そのため、最短で
は一ヶ月、最長では二ヶ月もかかっていた。これが待てない人は、直接発注していて、そういう
人のHPも見つけた。やはり4〜5日という短さで、今回の私のケースとも合致する。
これほど日数に開きがあるのに、なぜ皆が直接発注しないのか(いまは、カスタム品は直接発注
しか方法がないが)には理由がある。
ひとつは輸送費。$35もかかる。約4000円なので、安いとはいえない。
もうひとつは、この前ちょろっと書いたが、関税である。
ネットで買い物をすると、ついつい忘れてしまいそうになるが、外国からものを買うことはすな
わち、国内への輸入になる。商品によっては関税がかかって当たり前なのだ。いまつかっている
ゼンハイザーのHD580というヘッドフォンはかつて、米国から「輸入」したもので、そのと
きはじめて関税がかかることを認識した。関税といっても面倒な手続きは輸送業者が代行してく
れているので、その業者に関税分を振り込めばいい。前回ならFedex、今回ならUPSだ。
HD580の場合、輸送費と関税を払っても、国内で同じものを買う場合の半額以下だったの
で輸入するほうが断然お得であった。今回の場合は、カスタムオーダーでも国内販売額と値段
は同じであったらしいので、純粋に日数のメリットしかない。まぁ国内オーダーが不可のいま
は自分のオリジナルが手に入るというメリットが加わるけれども。そういうわけで、国内で手
に入る品物の場合は、相応のメリットがなければ、無理して外国から買う必要はないと思うの
で、海外ネット通販を考えているひとは、慎重に情報収集したほうがよい。
さて、実物はいったいどんな感じか。買い物のもっとも楽しい瞬間は、買うまでの期間である
なんて、うそぶくことがよくあるけれども、できればずっと楽しみたい。長く使える品物であ
ってほしいと思う。
- 2005/07/07(木)
昨日よりも3時間も帰宅が遅かったのに、今日の方がなんだかゆったりした心持である。昨日より
も本を読んでいる時間が長いように思う。
夏コミの本の構想を練る。岩崎邸、前田邸、鳩山邸、三信ビル、大山崎山荘、このあたりが全体、
そしてディティールに至るまで、ぎゅっと西洋建築の面白さが凝縮されており、初めての人にも
お薦めできるように思う。そう、本のテーマは西洋建築の愛好者を増やすこと。なので初回とし
ては、「内部見学できる」ということにもポイントを置いてみた。横浜の「外交官の家」も入れ
てみようか。内部見学できる場所は、見られることを意識しているから保存状態も概して良いし。
第二回目からは特集を組んでもいい。京都にゆかりの深い、武田五一特集(京都市役所、同志社
栄光館)や、これまた京都とかかわりのある幻想動物の使い手、伊東忠太特集(築地本願寺、東
京復興記念館、一橋大学)。学校別だけでも特集できる。早稲田、慶応、東大、東京商船、同志
社、明治学院、数えてみるとずいぶん撮りにいっているのだと気づく。京大がないって?そうい
えばそうだ。半端に新しかったり、古かったりするのであまり食指をそそられないのである。建
モノなんかどうでもいい、という精神の闊達さがあの学校にはあるのかもしれない。建物という
もは、学校にしろ、役所にしろ、銀行にしろ権威の象徴という側面を持つものだから。まあ、そ
れでもアジア、アフリカ研究所なんかはちゃんと押さえているのだ。いつかちゃんと探究してみ
ようと思う。
7月は実は合唱がずいぶん忙しいのである。マネージもじわりじわりと迫ってくる。どこまで
思っていることができるか。やや不安であるが、趣味だからこそ時間と金をかけてやる意味が
ある、とある指揮者が言っている。がんばろう。がんばれ自分。プレッシャーをかけないと、
すぐにさぼってしまう私である。
おやすみなさい。
- 2005/07/06(水)
貨物の進行状況:
2005年7月6日
6:22 ANCHORAGE, AK, US ARRIVAL SCAN
2:17 ONTARIO, CA, US DEPARTURE SCAN
2005年7月5日
22:41 ONTARIO, CA, US ARRIVAL SCAN
21:25 OAKLAND, CA, US DEPARTURE SCAN
19:54 US BILLING INFORMATION RECEIVED
19:35 OAKLAND, CA, US ARRIVAL SCAN
18:50 SAN FRANCISCO, CA, US DEPARTURE SCAN
18:05 SAN FRANCISCO, CA, US ORIGIN SCAN
(いずれもUS東部標準時)
注文したのは4日前だというのに、どうだろう、サンフランシスコのTIMBUK社をバッグ
が出発しましたよ、という案内がUPSから届いてしまった。京都到着は、7月8日の予定と
なっている。"approximately 21 business days for delivery"って、どこがやねん!
あまりにも早すぎると、ちゃんとオーダー通りのバッグが来るのか心配になってしまう。
とにもかくにも、もうアンカレッジまで来た。既製品のバッグが来たりしませんように、祈る。
関税、いくらくらいかかるかなぁ...。
おぼえがき
昨日くらいから、左目まぶたがけいれいん。プログラムで煮詰まっているせいか。目薬をさして
も変わらず、目の疲れそのものとは関係ない様子。うっとおしいのでテープで固定したい。
- 2005/07/05(火)
今朝がた見た、短い夢。
友人と並んでプレステ2で遊んでいる。友人がプレイ中である。ゲームはハーボットが主人公の
アクションパズルゲームのようだ。ロードランナーのように地面をほって、ドリルマシンのような
乗り物にのって移動する。ロードランナーと違うのは真下だけでなく、ななめ方向にも掘れる点。
どうも、この斜めに掘るのはコツがいるようで、夢のなかでわたしはしきりに「うまいなぁ」と友
人の妙技に、声をださずに感心している。ところが下方に掘り進んだところで、ハンマーを持っ
た敵(サングラスをかけたハーボット)が現れてピコピコ叩かれてしまう。それで3アウト、ゲー
ムオーバーとなってしまった。
「(いいところだから)コンティニューすればよかったのに」という私に、友人は「もういいよ」
といって、私にゆずってくれた。で、同じゲームかと思いきや、ぱっと画面が変わって別のゲーム
がはじまったのである。え、ディスク交換もせずにゲームが切り替わるなんてすごいなーと思う夢
のなかの私。始まったゲームは「ガンダムIII」のタイトル。画面にはなぜだかロザミア・バダムが
うつっているのだが、わたしは全然違う聞いたことのない人物の名前を口走っていた。有名なエピ
ソードのようである。(注:実際のガンダムIIIにはロザミアは登場しません。)
というところで、終わった。いつもと違って、穏やかな目覚めだった。
それにしても、書いていて気づいたがロードランナーとはひどく懐かしい。当時のTVゲームの主
流はアクションか、アクションパズルゲームで、スーパーマリオもあのころだった。いまはRPGが
全盛の時代だけれど、社会人にRPGなんぞやっている時間はない。短時間でも楽しめて、攻略の
楽しみもあるああいったゲームらしいゲームを、今のハードでできないのはとても残念だ。PC上
のエミュレーターなんかではなくて、家庭用のTV画面でもう一度やってみたい。そして旧作ばか
りではなくて、新しい「ゲームらしいゲーム」が出てくれないものかと思う。
ちなみに、夢でみたPS2であるが、私はもってません。
帰宅後、NCマネージ。ほか1件。
おやすみなさい。
- 2005/07/04(月)
雨のせいで、朝から暗い。昨日、寝つきが悪かったこともあり、少しだけ寝坊した。夏のかんかん
でりの日差しのなか寝坊するのと、梅雨空の下で寝坊するのを選べといわれたら、後者を選ぶだろ
うと思う。直射日光が苦手なたちなのである。(晴天が嫌いなわけではない)
帰宅後、寝転がって本を読むと、天井につるした照明が目を射抜きまぶしい。まぶしいと目を細め
てしまう。まぶたが開かなくなると反射的に眠くなってくる。本は読みたし、されど眠たしという
ジレンマになる。目の前に掲げている本で照明を隠せばいいのだが、ちょっとでもずらすとまぶし
いので、きゅうくつだ。
それならばと思い、白地のタオルを照明のかさの部分にガムテープでつけて、開口部を覆ってしま
うことにした。われながら良いアイデアである。とたんに部屋の様相が一変したのでおどろいた。
タオルからの透過光と、タオルにあたって反射し、傘から漏れた部分から天井にあたった光の、そ
のまた反射光の、ふたつがあわさったひかりが注いでいる。ふとんも、つくえも、じゅうたんも、
本棚も、本も、本棚に飾られた写真も、ふだん目にしているものが、ことごとく淡くてやわらかい
光で照らされ、ことごとく違った姿形をみせていた。するどい光と、するどい影がうせて、あいま
いもこな光と、あいまいもこな影で構成された世界だ。あかるくもない、くらくもない。それがな
ぜだかここちいい。不思議である。
それからひとしきり読書をたんのうした。
そして自然な眠気がやってきた。
おやすみなさい。
- 2005/07/03(日)
雨。やっと梅雨らしくなってきた。夕食の買い物以外、終日出かけず。この1ヶ月、荒れ放題で
あった部屋の片付け、掃除、洗濯、食器洗い、ゴミすてに時間を費やす。部屋の状態と、心理状態
というものは、絶妙にシンクロするものだ。
突発的な咳や、のどのはれがひかないのは、肩こりが原因である、と親に指摘されされたこともあ
り、約2ヶ月ぶりに、買い物ついでにマッサージ屋にいく。ここでは9割の確率で店長にやっても
らっているのだが、それはいつも外からみて店長の手が空いているから確認してから、入店してい
るためである。理由は簡単で、店長が一番うまいというか、わたしの肩こりに一番フィットするも
み方をしてくれるから。
であるが、今日の晩、雨がぱらつく中でかけたところ、姿が見えなかったので、15分ほど時間を
つぶしてから、もう一度前を通る。やはり店長おらず。肩の深い部分でかなりこっていることが金
曜日のBK宴会時にわかったので、やってもらわないわけにはいかない。仕方なく、はいることに
した。待ち受けていたのはナンバー2と思われる人だった。
20分経過。
おお、かなり効く。前にナンバー2の人にやってもらったときとは全然違う。あきらかにうまくな
っているじゃないですか。おかげでだいぶ楽に。店長とこの人は大概、店にいるので、これならい
つきても、安心してやってもらえそうだ。(烏丸仏光寺東入る「安穏」というお店です。なかなか
良いたたずまいで、マッサージ屋さんぽくないお店。興味のある方はどうぞ。)
雨のなか、あちらこちらの鉾町から、祇園囃子の練習が聞こえてくる。密集しているから、うるさ
いくらいである。この時期に旅行に来た人はびっくりするかもしれない。雨乞いの祭りに、聞こえ
なくもないなぁと思いながら帰る。
夜、NCマネージ。なぜだか疲れる。
おやすみなさい。
- 2005/07/02(土)
NC練習、練習後NCマネ会@明治維新。今回も驚くほど何もできていないことに気づき、愕然
とするマネージャー一同であった。ジョイントコンサートまで、ちょうど2週間。
NC練習のまえに、心斎橋へ。目的は、TIMBUK2というカバンを買うため。「自転車人」
をながめていて、ふと思いついたのである。というのも、スポーツ車には基本的にキャリアがな
いため、荷物は身に着ける必要があるのだが、夏場にリュックを背負って5分でも自転車にのっ
たならば、汗だくのべとべとになるのは明白。背中が空いているかどうかは放熱効果上、大変重
要であることは、自転車に乗らずとも炎天下のコミケで経験上わかっている。単に汗をかいて気
持ち悪いという以上に、熱中症のほうが怖いのだ。
ということで、カバンを肩からたすきがけにし、腰の辺りで固定するようなスタイルが自転車乗
りにはもっともいい。で、「自転車人」で見つけたのがTIMBUK2、メッセンジャーという
バックなのだった。メッセンジャーという名前の通り、自転車でメールを届けるメッセンジャー
御用達のバッグで、世界中で絶大な支持を得ているという。いってみれば、プロユースなのであ
る。そういう品物は信頼できる。
日本代理店のHPを見つけて、関西方面の取扱店をさがしたところ、京都はロフト、大阪は心斎
橋の東急ハンズにあることがわかった。で、さっそく向かったのであるが、結果、京都ロフトで
は影も形もない状態だった。で、NC前に向かった東急ハンズでは入り口を入ってすぐに、まる
で私が来ることを予測したかのように、TIMBUK2コーナーが用意されていた。で、大きさ
や、感触を確かめてなかなかいいことはわかったのだが、問題は色だった。ありがちな黒一色か
赤のワンポイント、黒とグレーの三種類しかない。正確には、ハンズにはその三つしか置いてい
なかったのである。
TIMBUK2、メッセンジャーはHPによると結構なカラーバリエーションがある。バックを
たてに3つのゾーンにわけて、それぞれが色違いであったり、真ん中の部分のみ色違いといった
パターンとなっている。どうせ買うなら、地味目なものは避けて、自分の好み+控えめに目立つ
=自分のカラーを出したかったので、別の店で探そうと思い、心斎橋を離れた。
マネ会、帰宅後にHPでTIMBUK2取り扱い店を探す。公式ルート以外にも、当然たくさん
存在するはずだ。その途中、個人でTIMBUK2の紹介をしているページをいくつか発見し、
覗いてみると、あれカラーバリエーションにないメッセンジャーだ。年度ごとにデザインがかわ
ったりしているのだろうか、HPに掲載されているものよりかこちらのほうがいいなぁ。さらに
調べていくと、なんとTIMBUK2は3つのゾーンの色の組み合わせを自分でオーダーできる
ことがわかった。おお、さっきの持ち主だけのオリジナルだったのだ。よし、急ぐものでもない
し、せっかくだからオーダーしようと決める。
ところがところが、日本語公式HPにはオーダーのことは一切書いていない??販売店の説明に
よると、代理店が変わった都合で、日本でのオーダー受付は2005年6月末までということら
しい。おいおい、もう7月になってるじゃないですか。一足遅かったか...。
とあきらめかけたところで、日本がだめなら、本国に直接オーダーすればいい。海外から直接品
物を個人輸入することは、いまやそんなに面倒なことではなく、普通にネット通販するのと手間
は変わらないのだ。さっそく、ここに飛ぶ。あったあったちゃんとありま
した"Build Your Own Bag"の文字。ここで、画面上で色の組み合わせを試すことができるので、
試してみて欲しい。
さて、ここで2つ問題発生。1つ、色の組み合わせのうち、あるゾーンに黄色を選択したので
あるが、画面で表示されているのは、どう見ても黄緑色なのだ。黄緑の選択もあるだが、やや
色が変わる。GOLDと表示されている色のほうが、黄色に近いが、これはどちらかというとオレ
ンジ色だ。黄色がいいのだけれど、ほんとに黄色になるのか。画面の黄緑でもおかしくはない
配色だがなぁ。(結局、個人HPに掲載されていた情報で解決。黄色の注文で、きちんといわ
ゆる普通の黄色のバッグが届いている様子)
もうひとつの問題は、ちょっとやっかいだった。組み合わせを決め、注文画面で住所や、支払
い方法を入力していたら、クレジットカードナンバーの入力欄の下に、見慣れない欄があるの
だ。"Security code, CVV"とある。え、暗証番号をいれろっていうのか?そんな要求するのは
おかしいぞ...とにわかに心配になってきた。でもなぁ、最近は日本でも、店頭でサインでは
なくて、暗証番号を入力させるようになっている。ネット通販でもそうなのかなぁと考える。
もし、暗証番号ならば、困ったことになる。わたしはカードの暗証番号など、とっくの昔に忘
れているからだ。このままではカード会社に問い合わせないと、買うことができない。むむむ
どうすべきか。
先に、わからないことを調べることにしたら、結果、暗証番号はやはり不要だった。カード会
社のホームページで、海外通販をする場合の注意事項を見つけたのだ。CVVというのは、
カードのセキュリティ番号のことを差すという、具体的にはカード裏面のサイン欄の上に書か
れた17〜19桁の番号の末尾3桁のことらしい。手元にクレジットカードがある人は見てほ
しい。そこにはカードの番号だけでなく、実は余分な数字が書かれているはずだ。それこそが
CVVなのだった。いままで、まったく気づかなかったよ...。というか日本のネット通販で
は使っているのを見たことがない。別の方法でセキュリティー対策しているようにも見えない
のだが、なぜせっかくあるものを使っていないのだろうか。ソフト対策で不要なのか、それほ
ど期待できないということなのか。(両方の可能性があると思うけど)
というわけで、すべての入力を終えて、無事注文完了。一時間以内に、発注確認のメールが来
るとある。まつことしばし…、来ないじゃないか。おかしい。普通こういうものは、ほぼ一瞬
でくるはず...またもや不安にさいなまれる。そろそろ一時間経つのに。
あ、もしかしてと、一時間後に気づいた。海外からのメールということでプロバイダがかって
に「迷惑メール」と判断して、題名に「MEIWAKU」とつける場合がある。メーラーの設定でそれ
自動的にゴミ箱行きにしているのだが、案の定、それはゴミ箱のなかにうずもれていた。やは
り、注文してすぐの時間に送信されていたことがわかる。
なかなか一筋縄ではいかない。ともあれ、あとは待つだけ。21 business day、つまり約4週間
後に届くはずである。ああ、疲れた。寝よう。
おやすみなさい。というか人によっては、おはようございますの時間になってしまったよ。
- 2005/07/01(金)
いよいよ7月。ツールの夏、祇園祭りの夏。6月の体調不良の分、元気に過ごしたいところ。
BK飲み会帰宅後、さっそくオークションの結果を参照する....ののの!やられた。今朝まで
わたしが最高値をつけていたのだが、入札終了30分前になって、いままでまったく入札してい
なかった参加者により、最高値、それも今朝の倍額以上をつけられていたのだった。
落札できなければ、あきらめると書いてはみたが、やはりどうにもくやしい。昨日、今日の時
点では確実だと思って、結構わくわくしていただけに。賞与がはいったのだから、多少でも無
理目の最高入札額を設定しておくのだったなあ。もう、この商品が出てくる機会はほとんどな
いかもしれない。発売から5ヶ月、即完売の商品であったし。
というわけでは、いま、何か無気力。昨日までは賞与が入ったら、時計でも買おうかなぁなど
と思っていたが、この結果、ほかのものに対する購買意欲も失われるという有様。
と、そんなとき、なぜだか思い出したかのように、時計のコレクションを眺めることにする。
夏場はなかなかできない、アンティークの手巻き時計を取り出してきて、ねじを巻いてやるの
だ。時間をあわせ、腕にはめる。こちこちと動く秒針をみつめているうちに、何かを買わねば
といった強迫観念のような気持ちが薄れていく。たぶん、明日の朝までしかこの気持ちはもた
ないと思うけれども、今は、もやもやも、くやしさも晴れた。
OYSTER JUNIOR SPORT。
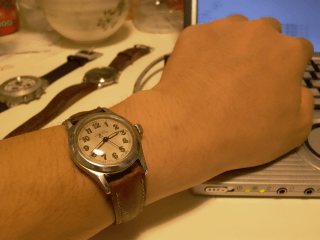
時として、時計はひとの気持ちを大きく動かす。悪い例で恐縮であるが、大学2回生のときの
ことだ。夏季試験の直前、それまで愛用していた時計をトイレのタイルに落として、ガラスも
ろとも壊してしまった。しかたなく、家にあったとにかく動いている時計をはめて、電気回路
学の試験に臨んだのであるが、結果は芳しくなかった。大学の試験は勉強してれば解けるとい
うものでもなく、ある種のひらめきに左右されることが少なからずある。(本人の努力とか才
能はこの際、問題にしない)そのひらめきを生み出すのに重要なのは、試験時間中のコンディ
ションが何より重要だとわたしは考えていた。
ひらたくいえば、どれだけリラックスした状態を保てるかということ。それに大きな影響を与
えるのが、実は時計なのだ。不思議なもので、残り時間が気になってしかたがないような時計
もあれば、あとこれだけも時間があると思える時計もある。それがあと5分、あと1分のとこ
ろで大きな差を生む。あのとき、時計がこわれていなけば、なんだか落ち着かない気分で試験
をうけることはなかったんじゃないか、もっとできたんじゃないか、他力本願で、現実逃避も
はなはだしいが、切羽詰ったとき、それがたかだか、大学の試験であっても、人間何かに頼り
たくなるものじゃないかなーと思う。時計にはその力がある。そういう気持ちを受け止めて、
跳ね返してくれる力がある。
普段、私がはめている時計は、2000年から使っている。結構長い。WENGER社のMOUNTAIN
COMMANDという。この時計を見ていると、1時間、60分という時間が常に力に満ち溢れてい
る気がしてくる。文字盤の1分のすきま、6度のスペースに時間がびっしり詰まっている、そ
んな感じなのだ。だから見ていると元気になる。さぁ、この仕事片付けるぞ、という気持ち
になるのだ。
あなたの使っている時計は、あなたをどんな気持ちにさせてくれるんだろうか。
|
|