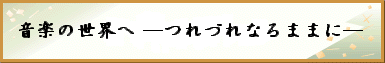
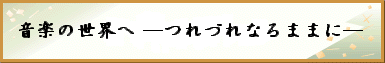
音楽の世界へ - つれづれなるままに - 前回の”音楽の楽しみ”を終了させて頂きましてから、もう1年と7ケ月が過ぎました。
書く作業は、おかげさまで、自分自身の勉強に直接つながりまして、考えを明らかにしていく過程で、また新しい発見をする事もありまして、非常に有意義な期間でした。
ただ、演奏会等の批評を中心とした試みでしたので、責任上、いくつかの資料にも目を通す必要がありまして、時間と精神面の両方に余裕がある時でなければ、出来ない作業であったなぁと、つくづく思います。
以前は、"Poohのちょっと辛口(?)音楽談義"と云うテーマで再スタートさせて頂こうか なと考えて居りましたが、見方が偏ってしまうような気がして参りまして、書きたい事柄が沢山あったのにもかかわらず、結局、考えがまとまらずに、断念いたしました。
これからは、クラシックの音楽に関する話題を、折りにふれて、ゆっくりとしたペースで、また書いてみたいと思います。
テーマは、音楽の世界へ - つれづれなるままに -
現在の心境は、このようなしっとりした感覚の方が、合うようです。
1.演奏家と批評家 (それぞれの在り方について)
2.作曲家(シューベルト(1797ー1828))
3.番外編 第1回仙台国際音楽コンクール 雑感 (ピアノ部門第2位 イ.ヂンサン(韓国)について
4.音の主治医
5.整理整頓
6.フィクションの奥義(その功罪)
NHK大河ドラマ ”江(ごう)”(姫たちの戦国)を例に
記念すべき大河50作目のこの作品を、初回から興味深く見続けてきた。
脚本家による、人間愛あふれる肌理細かな心理描写は、特筆すべきもの。
その細部にまで忠実に応える俳優方の奥深く確かな演技には、毎度、感動させられる。
・・・しかし、如何せん、その独特な内容は、万人向けとは言い難い。
世評をインターネットで検索してみたところ、案の定、保守的な大河ドラマファンは、戸惑いを感じているようだ。
・・・評の詳細はともかくとして、
ドラマの内容は、織田信長の姪である三姉妹(茶々、初、江)が主役で、特に、三の姫、江の眼で戦国の世が語られる造り。
当時の女性に関する史実の記録は少なく、相当な分量の創作が必要である。
そこで、原作者でもある脚本家は、江に狂言まわしの役目もさせ、名立たる武将をはじめ、後々の自らの成長に関わる魅力的な人物達との出会いを設定した。
政治の駒として徳川家に嫁ぎ、波瀾万丈な人生の中で泰平の世を祈り、やがては大奥の礎となる健気でたくましい女性像を描いている。
それにしても、江を取り巻く環境の豪華な事!
信長、秀吉、家康の三英傑がそれぞれ伯父、養父、義父で、武将を演じる表向きの顔と、江に引き出された、ふとした時に見せる素顔とのギャップが面白い。
実父を知らない(父は浅井長政、母は信長の妹のお市の方)江が、生まれてはじめて父を意識したのが信長の存在で、その哲学「己の信じる道をゆけ。人生は短い。」がアイデンティティーとなる。
これは、ドラマ初期の重要な場面の為、あえて子役は使わずに、長身の20代の主演女優が7歳の子供の扮装をして演じたのだが、製作側の意図が世間には伝わらなかったようで、かなりの不評。残念ながら、前途多難な放映になってしまった。
他、特徴としては、
1、戦国時代にしては、絡む登場人物(武将)が限定され過ぎている。
2、合戦シーンが極めて少なく、女性が中心のホームドラマ仕立て。
3、分り易さを求めた結果?噛み砕いた現代語が多用されている。
4、不謹慎なお笑い要素が少なくない。 ・・・等
(私の想像だが)源氏物語か何かが、脚本家の着想の根底にあるのかも知れない。
(一見、狭い世界観の中に、全てが凝縮されているという思想。)
例えば、舞台劇ならば、年配の役者が幼少期?を演じる事もある。
又、客席にメッセージが伝わり易いように、大袈裟なきわどい演技、過度の演出が必要なシチュエーションもある。
ライブだからこそ・・・の熱い空気。
・・・しかし、それと同質のものをテレビドラマで試みれば、極めて悪趣味、グロテスクな仕上がりになるのがオチだ。
民放のコメディータッチの若者向け(?)の時代劇であれば、歓迎されたのかも知れないが、NHKの大河ドラマというブランドが求めるものは、くだけた感覚のホームドラマでは無い。
今日に至るまで築き上げた伝統と誇りには、慎重に敬意を払うべき。
視聴者には、正統派(?)の時代劇を楽しみにされる、歴史に詳しい年配の方々も数多くいらっしゃるのだ。
品性を保ち続ける為には、そのような背景も考慮に入れるべき。
・・・歴史をドラマにするのは、作家の腕の見せ所だ。
公式文書に忠実に、実在の人物を取り上げるのだから、責任は重大である。しかも、史実を羅列するのではなく、どのような歴史的背景があり、我々が知る定説に至ったその訳を徹底的に推察し、生きた人間ドラマに仕立て上げなければならないのだ。
歴史の裏側には諸説がある。(学者同志でも、様々な憶測が飛び交う。)
それらのどの部分に惹かれ、最終的に選択するか?
・・・それは、作家の器量。
フィクション(創作)は所詮は架空のものだが、良質なそれであれば、隠された真実?や柔軟な発想は楽しめる。
(私が以前に読んだ)永井路子著の「歴史をさわがせた女たち」(日本篇)に、”秀忠夫人、お江”が載っているが、”水が器にしたがうように、それぞれの境遇に淡々とたえて来た、戦国武将のだれにもまして、ツヨイツヨイ女性・・・”との説明がある。
江は、春日局に政治力で負け、姉の淀君(茶々)と較べれば、地味で、ドラマの主人公には向かないような気がしていたのだが、この一文で、実はイメージがかなり変わった。
今回の大河ドラマを見始めた理由は、これかも知れない。
・・・しかし、実際のドラマは・・・
・・・複雑な気持ち・・・
「NHK大河ドラマ・ストーリー」によると、このドラマの裏テーマには、”平和への希求(反戦)”があるそうだ。
又、恋愛至上主義と云っても過言では無い程、家族愛、姉妹愛も含め、相思相愛論にかなりの時間が使われ、展開されている。
食うか食われるかの戦国時代に、そのような幻想的な発想がありえたのか、甚だ疑問だが、問題は、脚本家自身が、自らに課したそのテーマに縛られ、史実に登場人物の個人的理由をこじつけてしまったのが、どうにも安直に思え、本末転倒に思え・・・・・
・・・とは云え、今まで一回も欠かさず、見続けてきた訳は、その禁断の?内面を現す人間愛の台詞にこそ、何を隠そう、じいんと心に沁みる、懸命に生きた、その時代の方々に対する誠意を、稀有な洞察力を感じるからだ。
失礼な表現になるのをお許し頂ければ、”あばたもエクボ”に見えるような心地よい酔い方?
(女性視線による)その世界に浸らなければ味わえない繊細な魅力がある。
例えば、他所では何かと悪女扱いされる淀君を少女時代から描き、亡き母親の代わりに妹達を精一杯守ろうとする気概と優しさが、気高く、素晴らしい演技で表現されている。
相思相愛であった?秀吉没後、わすれがたみの秀頼を命を懸けて守り抜く勇姿は、既に、我々がよく知る苛烈なヒステリー淀君だ。
しかし、そこに至るまでの感情が丁寧に描かれていた為、試練続きの彼女の数奇な人生において、理不尽な目に遭う度に、強くならざるをえなかった過程がよく理解出来、孤独感、心細さ、哀しさを秘めながらも、誇り高く闘い抜く激しさに、思わず感情移入させられてしまう。
又、主人公の江と徳川秀忠夫妻。
この時代には珍しく、秀忠が側室を持たなかった事から、一般には江が嫉妬深く、秀忠が恐妻家のように伝わっているが、このドラマの中では、愛妻家として、良心的に描かれているのが嬉しい。
・・・しかし、史実を調べたところ、(江が多産なので、夫婦仲は良かったのだろうと思い込んでいたのだが)江の最期は悲惨だ。
家康から江への訓戒状(跡継ぎ問題で長男か次男かで揉めた。)以来、秀忠に忌み嫌われ(?)、春日局の取り仕切る江戸城で突然、亡くなる。しかも、毒殺の疑いがあり、当時では珍しい火葬。江が溺愛した次男の忠長だけが(臨終には間に合わなかったが)駆け付けた。
いかなる理由か?秀忠と長男(後の三代将軍家光)は葬儀にも出ていない・・・
・・・勿論、史実は勝者側の捏造の可能性もあり、全面的には信用は出来ないが、それでも、ドラマのように、都合良くハッピーエンド・・・は残念ながら、有り得ない。
「NHK大河ドラマストーリー」には、家康を演じる大御所、北大路欣也の記事があり、”対岸から乱世を見つめる群像劇”の面白さを語っている。
「僕は、あるべき現代の姿を見つけたいなら、時代劇に答えがあると常々思っているんです。一瞬の判断ミスによって命が絶たれる時代だけに、感覚は冴え、決断は潔い。人智の輝きを感じます。政治にしても、昔の方がよほど進んでいた気がします。だから、歴史上の人物はあこがれの対象であり続け、現代に敏感な人こそ、時代劇を楽しめると思います。」
淀君を熱演する宮沢りえの記事では、
「歴史上の人物を演じるときはいつも、”ご本人に恥じないように”との思いに駆られます。」・・・
作品(群像劇)に込められた魂を世に示す為、高い志を一つに、抜群のチームワークを見せるプロの俳優方・・・
優れた審美眼は、脚本の枝葉末節を気にしない。
・・・巷の澱んだ空気「月を指せば、指を認む。」とは、一線を画す世界である。
余談
私(筆者)の仕事は、クラシックのピアノ指導と演奏。
他分野でも、表現者の世界には共通する感性がある。
西洋音楽史では、ギリシャ神話の神アポロ(均整美の象徴)とディオニュソス(バッカス(酒神)の異名を持つ陶酔型)が、人間の内側にある表裏一体のものとして、よく例に出される。
時代により、その捉え方は異なるが、ディオニュソスの要素が強い画期的?な作品は、公表当初は冷遇され、等身大の価値が認められるまでには、様々な紆余曲折があるようだ。
音楽学者や著名な演奏家達の長年の研究により、クラシックの表現法には、守るべき型がある。
大体が17世紀~(J・S・バッハ~)20世紀頃の作品を扱う為に、その時代に即した演奏法の特徴があり、それに、作曲家の個性(ベートーヴェンはこう、ショパンはこう・・・という具合に。)が加わる。
プロの演奏家の発表は、それに準じたものでなければ、出鱈目と評される訳だ。
・・・とは云え、案外、型は窮屈ではない。
同じもの?を目指しながらも、ひとつとして同じ演奏が無いと云うのは、単なる個性の違いだけでは無く、クラシック音楽そのものの器、許容範囲に融通性、柔軟性が含まれている為・・・と思う。
演奏会には、例えば、主催者の要望で、自身の意向とは異なるプログラムが組まれるものから、自主リサイタルまで、色々な形態がある。
・・・ 勿論、演奏で本音が言えるのは、全てを自分自身で企画した方だ。
しかし、落とし穴がある。
本音を聴衆に理解?させるには、まず、演奏家自身が冷静に、客観的に自分の音を聴く、そのような意味のテクニックが必要だ。その努力?を怠ってしまえば、いわゆる独り善がりな結果・・・になるのがオチ。
・・・勿論、聴衆に問題がある場合も少なくは無いけれど・・・
又、演奏会を聴きに出掛ける場合、(私は)演奏曲目そのものよりも、誰が弾くか・・・に興味がある。
要は、曲目を通して、独自な解釈を知りたいのだ。たとえ、自分の感性とは大きく異なるそれでも、視野が広がる良い機会になる。
解釈・・・とは、作曲家の心情と同化するまで、自己を追い込む作業ではないだろうか?
同化・・・の定義は難しいが、決して、作曲家を自分のレベルに引き摺り降ろすのでは無い!!
逆である。謙虚に素直に、作品の忠実な僕(しもべ)になるのみ。
・・・世に作品を発表するのは、本当に命がけである。
世論、客観性、多数決・・・は"厳しいけれど温かいもの"ばかりでは無い。時として、暴力でさえある。
無残に一刀両断されたものの中に、もし、価値のあるものが含まれていたら・・・
そう思うと恐ろしい・・・・・・
「人間の心の深奥へ光を送ること、これが芸術家の使命である! 芸術家が幾月も、幾年もかかって思案したことを、しろうとの愛好者は、
一言で抹殺する気かしら?」 (ロベルト・シューマン)
(参考文献:NHK大河ドラマストーリー、永井路子著 歴史をさわがせた女たち、シューマン著(吉田秀和 訳) 音楽と音楽家。)
ご感想はこちらにお寄せ下さい。
