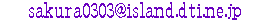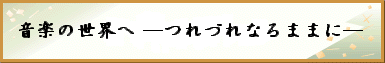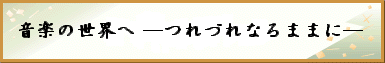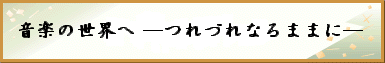
2.作曲家(シューベルト(1797ー1828))
19世紀前半、(ロマン派初期)ビーダーマイヤー時代のウイーンで活動。
(ビーダーマイヤーとは、ドイツ、オーストリアでの芸術様式の一つ。ナポレオン戦争後、1814年のウイーン会議から、1848年の三月革命までにおける、庶民(?)のごく日常的な生活感情そのものを表現している。社会の不安定な状態が、人々に現実離れのした何かを求めさせ、幻想の世界へ逃避し、芸術方面にも、神秘、怪奇現象、異国情緒、童話等の要素が数多く見出せる時代である。)
シューベルトは、ドイツ歌曲の王として知られ、その数は600曲以上もある。シューマン、ブラームス、R.シュトラウス、ヴォルフに影響を及ぼしている。また、器楽曲においても、歌曲の精神を生かした、情緒溢れる、自らの内面に忠実な旋律が、胸を打つ。
"ベートーヴェンのあとで何ができるだろう?"
シューベルトは、友人のシュパウンに絶えずこうもらしていたそうだ。ベートーヴェンはこの時代の作曲家達の大きな目標であり、作曲家として世に出る為に越えなければならない(?)常に目の前に立ちはだかる存在かつ大いなる課題であったのだ。(ベートーヴェンは1827年に亡くなっているが、奇しくも、その翌年に、シューベルトは世を去っている。)
シューベルトは、"さあ、作曲を!"という構えが、驚く程少なく、まるで日常茶飯事のようにごく自然に内から溢れ出てくる旋律を創作し続けた人であるのだが...。
私事で大変恐縮だが、シューベルトは個人的に大好きな作曲家だ。以前は何がなんでもシューマン!だったのだが、生徒のレッスンで勉強したのがきっかけで親愛感が増してしまったのだ。
歌曲をはじめとして、器楽曲、室内楽曲、交響曲、その他、オペラ等、わずか31年の生涯の中でその範囲は多岐に渡っているが、やはり、生身のシューベルトが伺い知れるのは、歌曲と器楽曲の一部(小品)ではないかと思う。
シューベルトは、モーツァルト、ベートーヴェンの後を受けて、古典派の残した遺産をそのまま引き継いだというべき存在ではあるが、本質的にはロマン派に属している。というのは、あくまでも論理的、意志的に楽曲の動機を展開していく古典派の形式とは異なり、独特の美しく流れる旋律を中心とした、作為的なところなど一つも見当たらない、情緒的な、いかにも自然な語り口で、作品が紡がれているからである。勿論、心優しいだけでなく、人一倍傷つきやすい、本物の芸術を愛する誠実な人間の悲哀と慟哭が割合ストレートに表現されているのだが...。ただ、それはベートーヴェンの試みとは、また違うのだ。ベートーヴェンには、激情と憂愁の息づかいが感じ取れ、彼の内部の火の存在が一般聴衆にも分かり易い形で表現されている訳で...。
シューベルトの音楽は、たとえ長調の曲でも、どこか淋しい。"僕は淋しい男です。"そんなつぶやきが、いつも聞こえてくるような...。(あまりにも私見かも知れないが、詩人の中原中也や、一昔前のsingerサイモン&ガーファンクルと非常に共通するものがあるのでは...?芸術作品として全面的に成功しているのかどうかは分からないが、世俗的なものに関係ない美しさ、純粋さとでも云えば良いのか、独特なこの世のものとは思えない透明感があるような...。)
ベートーヴェンというよりも、モーツァルトの生まれ変わりかも知れない。モーツァルトの書き残した手紙"僕が君のことを思っているくらい、たびたび僕のことを思ってくれているかしら?...君の大事な身体を僕の為にも大切にして下さい。.....命ある限り誠実なモーツァルトより"
---シューベルトの曲を聴くと、いつもこの宝石のような手紙を思い出してしまう。
小品と云う形態は、個人の生活感情の動き(その場そのときどきの喜びや嘆き等)を表現するのには、最も適した器なのかも知れない。そして、これは、シューベルトの魅力を解き明かすのに充分な(19世紀と云う時代の)産物である。
シューベルトが目指したのは、内燃的なロマン主義である。外面的な華やかさは無く、情熱を内に燃やし、沈潜させようとした。そして、この想いは、メンデルスゾーン、シューマン、ブラームスに引き継がれている。
"ファンタジーを持たぬものは、この曲に近づくな。"
これは、シューベルトの後期のソナタ(フィナーレ)についてシューマンが書いた言葉であるが、本当にその通りだなあと思ってしまう。聴く者の内側に音楽的な芽が育っているか否かが問われるある意味で厳しい人物かも知れない。シューベルトは.....。それこそ、馬鹿がつく程愛さなければ、シューベルトが淋しがるだろう。誰でもが、シューベルトの友達になれる訳ではないのだ。
(因みに、彼の当時の友人達は、興味や努力の対象、志を同じくする知識人、画家や音楽家等、芸術家が多かったようだ。)
シューベルトの曲に潜む彼の特徴かな?と思われる事柄を列記してみようかと思う。
自然愛好家。素朴。
自然な流れ。音には開放感がある。そして同時に透明感がある。
気高さ。気品、品格を感じさせる。しかし、冷たく突きはなしたものではない。
身体が健康でない。(死と向かい合わざるをえない。)
切ない。淋しい。何かを悟っている。致命的な心の傷。
そして、時として、激情。(古傷が痛むように、時折、彼の心の中には、魔王が現われる。)
優しさと鋭さ。この極端な対極性。独特な緊張感。(甘ったるいところなど、微塵もない。)
秩序を重んじ、常に己を律している。しかも、ベートーヴェンとは、又、違ったやり方で。
(ベートーヴェンよりも、感情の幅が広い。)
連作歌曲集において、愛の辛い体験、愛への距離の遠さをいやというほど思い知らされる。そして、それは死を誘うほどの、人生の挫折の体験であったのだ。
半音の微妙な用い方。(転調したかしないか、計算ずくではないあくまでも自然な曲の流れ。)
抑制が利いている!若き青年の清潔感。若さ故に、道ならぬ行為を許す事ができない!
冒険(?)を試みるが、そのために、挫折している。(若者に子守歌が歌えるだろうか?)
正義感が非常に強く、その為、自分も相手も縛ってしまう。生き方に限界がある。とても長生きは、無理。(自分にも相手にも厳しいのだろうか?)
失礼を承知で申し上げると、"羊の顔したサド男"の感がある。
余りにも、世俗的なものに関係ないところで、不思議な純粋さを発揮していて、清濁併せ飲むと云う大人の知恵が入り込む隙がない。
ナルシスト。相手の過ちを許す柔軟性に欠ける。とにかく、達観しているようで、若いのである。
.....。以上のものが総動員されると、シューベルト特有の深い叙情と力強い感情のほとばしりを感じさせる音楽が誕生するのではないだろうか。
最後に、シューベルトと、この時代の画家ドラクロワの語った言葉を書いて、終わらせたいと思う。
"この世は、それぞれが自分の役割を演じている劇場のようなもので、喝采や非難は、来世のもの。"(シューベルト)
"この悲惨な、われわれ人間の条件のなかでも特に悲しいことは、絶えず自己自身と向かい合っていなければいけないということだ。それだからこそ、気心の知れた仲間と付き合うのがあんなにも楽しいのだ。彼等は、しばしの間、彼等と一体になっているような気にさせてくれる。しかし、その後で又、自分だけの悲しい世界に落ち込んでしまう。ああ、最も愛する女性、優れた仲間なら、この重荷を一緒に背負ってくれるというのだろうか?そうだとしても、それはほんのわずかの間でしかない。彼等も又、それぞれに自分の重いマントを引きずって生きていかなければならないのだ。" (ドラクロワ(1824年))
P.s
とりとめのない、支離滅裂な文章になってしまった。
こんな形で、思の丈を述べられたのだろうか.....?
シューベルトに愛される人間になれたら、どんなに幸福だろう.....。
とにかく、これが私の精一杯!
だから、決着を付ける。.....何の決着.....?
ご感想はこちらにお寄せ下さい。