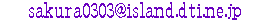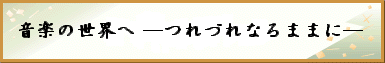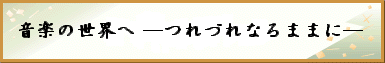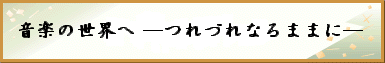
1.演奏家と批評家 (それぞれの在り方について)
(現代の演奏家について)
一昔前との大きな違いは、演奏家になる為のきわめて合理的なエリートコース(例 国際コンクール等)が用意されている事だ。しかもその数が年ごとに増えていくものだから、コンクール入賞者が結局は沢山存在する訳である。従って、淘汰されない為には、早いテンポでなにもかもをこなしていく術を身に付け、自己を何らかの形でアピールし続けていかなければならないと云うすこぶる過酷な試練が待っている。悲観的な見方をすれば、演奏家としてだけの成長を急ぐあまり、人間としての成長が伴わないと云う困った問題も抱えているようだ。---もっともこの現象は、音楽以外の全ての分野にも共通するのかも知れないが、、、。
コンクールは、客観的な評価により、自己の実力を再確認させた上で、世間にアピールさせると云う社会的な機能を一応は果たしているのであるから、問題とされているのは、コンクールそのものよりも、むしろ、その利用の仕方なのかも知れないが、しかし、コンクールの果たせる役割には、如何にせん限界があるのではないだろうか?トライアスロンに近いと云っても過言ではないような強靭な体力、運動能力と、あくまでもノーマルな(!)優秀性のみが要求されている場にしかすぎないのではないかと思われてならない。(そして、それは、よくも悪くも暗黙の了解の内に行われ続けてきた訳だ。)
それにしても、音楽(芸術)の真の魅力とは一体何だろう?120%健康美に溢れた音楽なんてものが、この世に存在するとは、到底思えない。音楽を創り出すのは、なんと云っても生身の人間であるのだから、、、。
私見で恐縮だが、この世で最も美しいものには、知らず知らずの内に、どうしようもなく病的な色合いを帯びてきてしまう、なまめかしさが、いついかなる時にも混在しているように思う。楽曲に描かれた作曲家の想い(微妙な心理的な襞の濃やかさや、アブノーマルなエキセントリックな人間像を彷彿とさせるような、まさに、崩れ落ちる寸前のような危うい美)を追求していくには、演奏家の方にも、それらを充分に掌握するだけの度量と才能プラス経験に基づく磨き抜かれた知性が、要求されているのだ。---才能とは、具体的に云えば文学的(?)感受性(特に弱音域ppppからpまでの(音量と音質の両方における)はかり知れない広さを掴み取れるだけの鋭敏な五感と、それに伴う表現の多彩さ)である。
俗な言い方をすれば、演奏家は、精神的なストリッパーなのである。ステージでの演奏ぶりで、即座に、精神分析されてしまうのだから、恐ろしい。聴く人が聴けば、その演奏家の人間的成熟度までが、如実に分かられてしまう訳だ。
批評では、音楽的、音楽性、個性的、自己主張、等の単語が、頻繁に用いられるのだが、それぞれに複雑な意味合いをふくんでいて、一言で定義するのは困難である。
”音楽的”とは、いい感じに歌って弾く事と、全く勝手気ままに出鱈目な調子で弾くのとを区別する場合に使用され、その音楽での構成や様式、及び、演奏をする際の約束事を念頭に置いた実体的な奏法を指している。(作曲家の人間性や、歴史的背景も当然考慮に入れた、感覚だけではない学術的な教育を受けているか否かを試されている訳である。)
"音楽性"とは、即ち才能であり、(ステージマナーは勿論、その演奏家の人間的魅力が、演奏を開始する前から既に客席に伝わってくるような)後天的な技術を越えた、(やや病んでいたとしても)人の気持ちを惹き付けてしまう生得のものなのではないだろうか?
"個性的"とは、どうしても、そのようにしか表現出来ないと云う事。無意識な所でにじみ出てしまうものなのだ。(良くも悪くも。)
最後に、"自己主張"だが、この定義が一番難しい。現代の演奏家が奏するのは、殆どが他人の作品である。一昔のように作曲家兼演奏家は居ないに等しい。しかも、現代の作品は、発表される機会が少ない。(専門過ぎて、一般聴衆が受け入れにくい為。)従って、頻繁に登場する作品は、大体が、18世紀以降のものであり、その作曲家に関する最高の資料は、唯一残された楽譜だけなのである。(勿論、音楽学者による作曲家に関する研究書は、沢山あるが、作曲家の人となり、癖、思想、美学が伺い知れるのは、なんと云っても、楽譜を通してこそなのだ。)
作曲家と聴衆の間に、演奏家は存在する。伝言ゲームではないが、演奏家の使命は、作曲家の心情を読み取り、それを、聴く耳のある人々に伝え続ける事なのだ。時によっては、作曲家と自己が同化するまで、追い込んでいく作業なのだから、愛するあまり、同じ痛みを感じる位にのめり込んでしまい、精神を病んでしまう事も有り得る。傍目には、奇妙に、不気味に映るのだろうが、それはなんという美しさなのだ!----瞬の時の中に永遠があるのだ、、、。
"自己主張"が有り得るとしたら、それは、演奏家と作曲家との時を越えた美しくも哀しい恋愛だ。音符の表面には決して現われない屈折した叫びを感じ取り、救えるのは、同じ悩みを持つ者だけだ。温室育ちではダメだ。苦労して自分の足で歩き出した事の無い人間に、挫折を経験した事の無い人間に、作曲家が、心を開くとは思えない。
斎藤勇著の心理学の本に、恋愛の定義が触れてあった。
1.相手に親和的、相互依存的欲求を強く持つ。
2.援助欲求や慈愛の気持ちを強く持ち、献身的になる。
3.2人だけの世界を深めていこうとする、つまり排他的欲求が強くなる。
等々書いてあったが、なるほどと思う。内面の充実があってこそ、自己主張も自然なものとなる訳だ。
余談だが、最近、昔流行った歌謡曲を大変懐かしく聴いた。当時は、多分そうとも気に止めずに、深く考えもせずに、聞き流していたのだと思う。現在は、自分も歳を重ねてしまったし、相当疲れてきたのだろうか?以前は感じ取れなかった様々な思惑をゾクッとする程リアルに肌に感じてしまうのだ。例えば、森高千里。正直言って、大嫌いないやらしい声の響きだし、曲もせいぜい3分あれば書ける程度だし、その内容もひねりが無いと云うか、不謹慎と云うか、とにかく当時は、決して良いイメージを持っていなかったのだが、(あまり、よく知らなかったし、、。)ところが、今現在聴いてみて、驚いた。(自分が変わったのだろうけれど、、、。)一途なのである。健気なのだ。簡単に何の衒いもなくサラッと書いたようなあけすけな彼女の作詞は、言葉の選び方も適確で、思わず、この子は天才だなと思ってしまった。そして、大事な事には、ほんまもんの変態である。(何でも、本物は良いのだ。)常に捨てられムードを装っている、平安時代の可憐なプレイガール、和泉式部みたいである。とにかく、善し悪しは別として、真実を衝いている。本音が聞けるのだ。胸が痛くなる程に、、、。
ああ、演奏家もこうでなければならないとつくづく思った。建て前ではない本音のある音楽を目指さなければならない。人間としての成熟が必要である。つまり、声を大にしては言いにくいが、芸術とは、不健康なのだ。まさに、狂気の世界なのである。
余談の余談だが、男の描き出す世界はやはり、一段上である。(想像外である。)
勿論、中には、女の腐ったような奴も混じって居るのだろうが、、、。(失礼。)
(批評家について)
演奏会にいっても、仕事がらみだと、楽しめないらしい。
ご苦労な仕事だとは思うが、啓蒙性のある職業なのだから、演奏家の陰なる努力を認めながら、具体的に、どのように勉強していくべきなのかを示唆するようにして頂きたいものだと思う事がある。けなしっぱなしで、何のアドバイスもしないのは、人間として最低。演奏家と聴衆を育てる上で、温かい眼は必要不可欠なのだ。
批評の批評がもしあったら、面白いでしょうね。
それにしても、音楽評論家の吉田秀和氏は、本当に素晴しい方だ。
ps.
確信犯万歳!
マニアックで過激な内容になってしまって、ごめんなさい。
ご感想はこちらにお寄せ下さい。