3.プラトン的愛とは何か
ちょっと教科書的な意味からはずれるかもしれませんが、ルネサンスという時代は人々の思考の枠組みが、あくまでもキリスト教を根本とした社会という状態を維持しつつも、急速に柔軟になり、思考の幅を広げた時代であった、ということができると思います。
後継者不在のためか哲学史ではあまり重要視されませんけれども、マルシリオ・フィチーノであるとか、ピコ・デッラ・ミランドラといった博識で独創性豊かな哲学者が出てきたためです。
彼らはそれまでのキリスト教を補強し、多彩にするための手段として、主にプラトンの思想と、プラトンの後継者とも言える、「新プラトン主義者」であるプロティノスの思想、さらに古代エジプトの神話学、また、ユダヤ教の秘密の教義であるカバラや魔術、錬金術というようなものさえも貪欲に吸収し、ルネサンスのイタリアに紹介していきました。
特に彼らのもたらした哲学的成果のうちでも「新プラトン主義」という思想とそれに基づく世界観は、当時の文化、芸術に深い影響をもたらしました。
ちょっと抽象的議論になるのですが、図でもって説明しますと、下の図のようなかんじです。
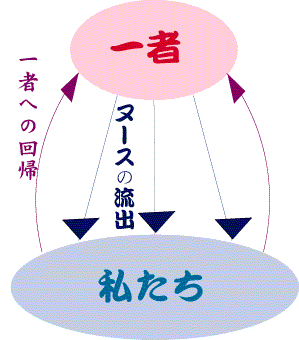
とにかく、プロティノス(新プラトン主義の始祖)が「一者」と言っているものが世界にはあって、世界のいろんなものはみんなそこから流れ出して、我々にもたらされているわけです。この「一者」はプラトンが言うなら「イデア」、キリスト教で言うなら「神」であるということができるでしょう。
要するに昔の哲学というのは、まず「世界は何でできていて、どういう仕組みになってるの?」というのが最初の疑問なわけで、新プラトン主義では「一者というものがあって、そこから流れ出てくるもので世界はできているんだよ」と説明しているわけです。
一者から流れ出るものをプロティノスは「ヌース」と呼んでいて、これはまあ世界を形作るもとのものだというくらいに考えればいいと思うんですが、これは、一者は存在の最高であるがゆえに最高の善であり、善なるものはみな美しいので、この「ヌース」は美に満ちていると考えられています。
わたしたちはこの「ヌース」によって一者とつながっているわけですが、このヌースの備えた「美」を愛することによって、私たちは存在の根本である一者=神の方を向くことができます。そして、神=一者を愛すれば愛するほど、今度は神の領域に近づくことができるんですね。最終的には、神と一つになる、「神秘的合一」といいますけれども、その様な状態が最高とされています。
愛を持ち、美の世界に身を浸すことで、神と世界と我々とをつなぐ、流出と神への回帰の循環の中に参加することができる。
その様な生き方がもっとも幸福であり、真理の道にかなったもの、と考えられたわけです。
フィチーノはこれを見て、こういう思想はキリスト教の本道にもかなうものだと考えました。彼と彼の仲間はプラトン・アカデミーというサークルをフィレンツェに作り、そこでプラトンやプロティノスの著書をラテン語訳するとともに、「プラトン神学」や「愛について〜プラトン「饗宴」注解」などの書を出して、当時の人々の反響を得ました。 こうした思想によって、「人間を神によって創造され、世界内部においてその恩恵を受けるだけの受動的な存在としてではなく、すくなくとも芸術、技術の領域においては、人間もまた神のごとく創造に参加できる存在として位置づけた。世界内における人間の能動的価値の認識」が行われたと言えます。(世界美術大全集「マニエリスム」小学館版の解説より) ルネサンスはジョットーなどによる絵画技法の発展なども大きいのですが、このような新しい哲学を神学の中にとりいれた動きがあったからこそ、現代我々が目にするようないきいきした豊かな内容を花開かせた芸術が現れてきたことも見逃してはならないと思われます。