
3(補筆).フェアリーというもう一つの幼児形
ところで少々脱線になるが、この宮武外骨の文章でもう一つ気になるのは「尤もそれは蝶々の羽根をつけないで云々」というくだりである。蝶々の羽根をつけた、といえば英国ビクトリア朝時代に流行した「妖精」の図像が思い起こされるが、このころには妖精の図像がエンゼルと解釈されることがあったのであろうか。
蝶の羽根を持った幼児を妖精(フェアリー)像として流行させたのはビクトリア朝イギリスの画家リチャード・ドイル、エリナー・ボイルたちだったと荒俣氏は書くが、ここで指摘しておきたいのは「蝶の羽根を持ったクピド」という図像がルネサンス期にも存在していた事実である。
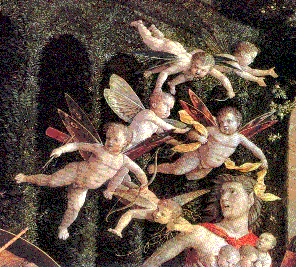 それはマントヴァの宮廷画家マンテーニャのいくつかの作品にみられ、とくに「美徳の勝利」あるいは「徳の森より悪を追い出すミネルヴァ」として知られる作品においては、徳を象徴する存在のミネルヴァによって追い払われる愛欲というマイナスの象徴として多くのクピドが描かれている。これがクピドであることはその弓と矢というアトリビュート(持物)から分かるが、その翼は明らかに鳥のものではなく、蝶々の羽根である。さらには、ミミズクやフクロウの頭を持ったクピドも描かれており、ここでは神であるよりも悪魔により近い存在として描かれていることが分かるのだが、それにしても「蝶の羽根を持ったクピド」というのは面白い存在である。この蝶の羽根のある童子というモティーフは同時代の画家としてはマンテーニャばかりが描いており、彼が何故このようなモティーフを取り上げるに至ったかは興味深い問題である。
それはマントヴァの宮廷画家マンテーニャのいくつかの作品にみられ、とくに「美徳の勝利」あるいは「徳の森より悪を追い出すミネルヴァ」として知られる作品においては、徳を象徴する存在のミネルヴァによって追い払われる愛欲というマイナスの象徴として多くのクピドが描かれている。これがクピドであることはその弓と矢というアトリビュート(持物)から分かるが、その翼は明らかに鳥のものではなく、蝶々の羽根である。さらには、ミミズクやフクロウの頭を持ったクピドも描かれており、ここでは神であるよりも悪魔により近い存在として描かれていることが分かるのだが、それにしても「蝶の羽根を持ったクピド」というのは面白い存在である。この蝶の羽根のある童子というモティーフは同時代の画家としてはマンテーニャばかりが描いており、彼が何故このようなモティーフを取り上げるに至ったかは興味深い問題である。
もう一つ面白いので取り上げたいのは、私が新潟にいる時に行った「ロマンの泉美術館」という書票画を主展示品とする美術館で見た、「薔薇とエンジェル展」の一展示品である。このビクトリア時代のバレンタインカードの中に、鳥の翼をもつ幼児と蝶の羽根を持つ幼児が混在しているのである。もはやどれがエンジェルでどれがフェアリーであるとはっきり区別できない状況にまで至っている。蝶の羽根を持つクピドや天使というものはあまりポピュラーではないが、少なくともビクトリア朝においてはこれらはごく自然に出回っていたことが分かるし、となると同じころの日本で「エンゼルは蝶の羽根を持つもの」として受け入れられたとしても不思議はないであろう。
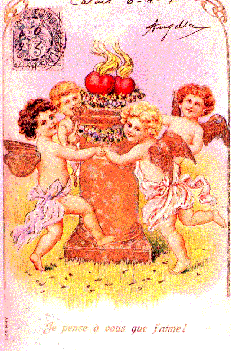 さらにマンテーニャの画にみられる「蝶の羽根をもったクピド」を考えに入れると、事態は更に複雑になる。蝶の羽根を持った幼児形に出会った場合に、エンジェル、クピド、フェアリーという3つの可能性があり得るのだから。
さらにマンテーニャの画にみられる「蝶の羽根をもったクピド」を考えに入れると、事態は更に複雑になる。蝶の羽根を持った幼児形に出会った場合に、エンジェル、クピド、フェアリーという3つの可能性があり得るのだから。
次の章を読む
いろいろ研究室に戻る