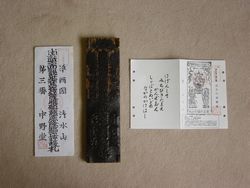|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ƒzپ[ƒ€پث”ژ•¨ٹظ‚ج‘‹پث–¯‘‚ج‘‹ –¯‘‚ج‘‹پi•½گ¬26”N“xپj پ@ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| پ@”ژ•¨ٹظ‚ج–¯‘•ھ–ى‚إ‚حپA–¯‘’²چ¸‰ï‚ً‚ح‚¶‚كپA‚³‚ـ‚´‚ـ‚ب‹@‰ï‚ً‘¨‚¦‚ؤ‘ٹ–حŒ´‚ً’†گS‚ةژü•س’n‹و‚ًٹـ‚ك‚½’nˆو‚جƒtƒBپ[ƒ‹ƒhƒڈپ[ƒN‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚حپu”ژ•¨ٹظ‚ج‘‹پv‚إ‚àگG‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپAچ،‰ٌ‚ح‚TŒژ28“ْپiگ…پj‚ةچs‚ء‚½گ…—j‰ï‚جƒtƒBپ[ƒ‹ƒhƒڈپ[ƒN‚ة‚آ‚¢‚ؤ‹L‚µ‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB پ@ پ@گ…—j‰ï‚حپA’أ‹vˆن‹½“yژ‘—؟ژ؛‚ة•غٹا‚³‚ê‚ؤ‚«‚½–c‘ه‚بژ‘—؟‚ًگ®—‚·‚邱‚ئ‚ً–ع“I‚ةژn‚ـ‚ء‚½‰ï‚إپA‚±‚جژO”N”¼‚جٹش‚جٹˆ“®‚إ–ٌˆê–œ“_ˆبڈم‚جژ‘—؟‚ج–عک^‚ًچىگ¬‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½پAژ‘—؟گ®—‚جگ¬‰ت‚ًژ¦‚·“Wژ¦‚ً–ˆ”Nˆê‰ٌژہژ{‚µ‚ؤپAژہ‚ة‚³‚ـ‚´‚ـ‚بژ‘—؟‚ً‘½‚‚جٹF—l‚ةŒ©‚ؤ‚¢‚‹@‰ï‚àگف‚¯‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB‚»‚µ‚ؤپA‚»‚ꂼ‚ê‚جژ‘—؟‚ة‘خ‚·‚é—‰ً‚ًگ[‚ك‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپAچ،Œم‚جٹˆ“®‚ة‘خ‚·‚éˆس—~‚ًˆê‘wچ‚‚ك‚邱‚ئ‚ًژه‚ب–ع“I‚ئ‚µ‚ؤپA”N‚ةڈtڈH‚ج“ٌ‰ٌ‚ظ‚اٹضکA‚·‚é’nˆو‚جƒtƒBپ[ƒ‹ƒhƒڈپ[ƒN‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB پ@
پ@چ،”N‚جڈt‚جƒtƒBپ[ƒ‹ƒhƒڈپ[ƒN‚حپA”ھ‰¤ژqژsگَگى’n‹و‚جچbڈB“¹’†‹Œ“¹‚ئ”ھ‰¤ژqڈéگص‚جŒ©ٹw‚ًٹé‰و‚µ‚ـ‚µ‚½پi‰ء“،‚ًٹـ‚ك‚ؤ12–¼ژQ‰ءپjپB‚ـ‚¸Œك‘O’†‚حپAچً”N‚جڈH‚ة’†‰›گü‚جڈم–ىŒ´‰w‚©‚ç“،–ى‰w•û–ت‚ةŒü‚ء‚ؤچbڈB“¹’†‚ج‹Œ“¹‰ˆ‚¢‚ةژc‚éڈم–ىŒ´ڈh–{گw‚â”شڈٹگص‚ب‚ا‚ً–K‚ꂽ‚ج‚ة‚آ‚ب‚°‚éˆس–،‚à‚ ‚èپAچ،‰ٌ‚ح“r’†‚ة‚»‚ر‚¦‚éچbڈB“¹’†‚جڈ¬•§“»‰z‚¦‚ح‚ـ‚½‚ج‹@‰ï‚ئ‚µ‚ؤپAڈ¬•§“»‚ً‰z‚µ‚½ک[‚©‚çچ‚”ِ‰w‚ـ‚إ‚جƒRپ[ƒX‚ئ‚µ‚ـ‚µ‚½پB“r’†‚إ‚حپA‘نچہ‚ة‘ه‚«‚پuڈ¬•§ڈhپvپiچbڈB“¹’†‚جڈhڈêپj‚ئڈ‘‚©‚ꂽ”n“ھٹد‰¹“ƒپiچO‰»ژl”Nپm1847پnچؤŒڑپj‚â‹î–ط–ىڈh‚ة‚ ‚éڈ¬•§ٹضڈٹ‚ب‚اپAچbڈB“¹’†‚ج–¼ژc‚è‚ًژ¦‚·‚à‚ج‚âپAچ‚”ِژRگM‹آ‚ئ‚àŒW‚ي‚éژض‘ê’ƒ‰®گصپA’†‰›–{گüٹJگفژ‚©‚ç‚ج—ùٹ¢چ\‘¢•¨‚ب‚اپA‚¢‚ë‚¢‚ë‚ب‚à‚ج‚ًŒ©‚ب‚ھ‚çڈ‚µ‘پ‘«‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½‚ھ•à‚«‚ـ‚µ‚½پB پ@
پ@ŒكŒم‚©‚ç‚حپAڈ¬“cŒ´‚ة–{‹’’n‚ًژ‚؟پAچL‚گ¨—ح‚ًŒض‚ء‚½ڈ¬“cŒ´–kڈًژپ‚جڈd—v‚بژxڈé‚إ‚ ‚ء‚½”ھ‰¤ژqڈéگص‚ةŒü‚©‚¢‚ـ‚µ‚½پB”ھ‰¤ژqڈé‚ح“Vگ³18”Nپi1590پj‚ة–LگbڈG‹g‚جٹض“Œگ§ˆ³‚جˆêٹآ‚ئ‚µ‚ؤ‘O“c—ک‰ئ“™‚ة‚و‚ء‚ؤچU‚ك—ژ‚ئ‚³‚êپA‚»‚ê‚ة‚و‚ء‚ؤڈ¬“cŒ´ٹJڈé‚جˆّ‚«‹à‚ئ‚ب‚èپAڈG‹g‚ج“V‰؛“ˆê‚ھ‚ب‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚إ‚à—L–¼‚إ‚·پB‘ٹ–حŒ´ژs—خ‹و‚ج’أ‹vˆنڈé‚à‚±‚جژ‚ةپA“؟گى‰ئچNŒR‚ة‚و‚ء‚ؤچU‚ك‚ç‚ê‚ؤ—ژڈ邵‚½‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB“–“ْ‚حپAژR‚جڈم‚ة‚ ‚é–{ٹغگص‚إ‚ح‚ب‚پA”ھ‰¤ژqڈéگص‚جƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAƒKƒCƒh‚ج•û‚ج‚²ˆؤ“à‚جŒ³پAڈéژه‚إ‚ ‚ء‚½–kڈًژپڈئپiڈ¬“cŒ´–kڈًژپژl‘م“–ژهپEژپگ‚ج’يپj‚جٹظ‚ب‚ا‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éŒنژه“aپi‚²‚µ‚م‚إ‚ٌپjگص‚ً’†گS‚ةŒ©ٹw‚µ‚ـ‚µ‚½پBƒKƒCƒh‚ج•û‚ج”MگS‚بگà–¾‚ح‚Pژٹش30•ھ‚ة‚à‹y‚رپAگيچ‘ژ‘م‚ً‘م•\‚·‚éڈéگص‚ًٹ¬”\‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚؟‚ب‚ف‚ة”ھ‰¤ژqڈé‚حچ‘‚جژjگص‚إپAپu“ْ–{•S–¼ڈéپv‚جˆê‚آ‚ة‚àگ”‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB پ@
پ@‚±‚ê‚ـ‚إ‚àڈq‚ׂؤ‚«‚½‚و‚¤‚ةپAƒtƒBپ[ƒ‹ƒhƒڈپ[ƒN‚حژہچغ‚ة’O”O‚ة•à‚«پE•·‚«پEŒ©‚ؤ‚¢‚«‚ب‚ھ‚çپA’nˆو‚ً’m‚èپAچl‚¦‚é‚à‚ج‚إ‚·پBچ،Œم‚ئ‚àژs–¯‚ئ‚ئ‚à‚ةƒtƒBپ[ƒ‹ƒhƒڈپ[ƒN‚ًگد‚فڈd‚ث‚ب‚ھ‚炳‚ـ‚´‚ـ‚بٹˆ“®‚ً“WٹJ‚µپAƒtƒBپ[ƒ‹ƒhƒڈپ[ƒN‚ً’ت‚¶‚ؤ•ھ‚©‚ء‚½’nˆو‚ج—ًژj‚╶‰»‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚àگد‹ة“I‚ةڈذ‰î‚µ‚ؤ‚¢‚«‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پi–¯‘’S“–پ@‰ء“،—²ژuپjپB |
||||||||||||||||||||||||||||||
| پ@‘OپX‰ٌپi‡‚68پj‹y‚ر‘O‰ٌ‚جپu–¯‘‚ج‘‹پE‘ٹ–حŒ´‚ج–¯‘‚ً–K‚ث‚ؤپi‡‚69پjپv‚إڈذ‰î‚µ‚ؤ‚«‚½’أ‹vˆنٹد‰¹—ىڈê‚ج‚²ٹJ’ ‚حپAŒكچخ‚ج–{ٹJ’ ‚حژOڈTٹش‚ئŒˆ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚ج‚±‚ئ‚إپA‚TŒژ11“ْپi“ْپj‚©‚ç31“ْپi“yپj‚ـ‚إ–³ژ–‚ةژہژ{‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB پ@
پ@ڈ‰“ْ‚ج11“ْ‚جٹد‰¹—l‚جٹJ”àژ®‚حŒكŒم‚Oژ‚©‚çچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚ـ‚¸ژہچsˆدˆُ’·‚ً‚ح‚¶‚ك‰½گl‚©‚ج•û‚©‚炲ˆ¥ژA‚ھ‚ ‚èپAچً”N‚ج12Œژ‚©‚ç33–¼‚جˆدˆُ‚ج‚à‚ئ‚إڈ”ڈ€”ُ‚ًگi‚ك‚ؤ‚«‚½‚±‚ئ‚âپAƒIƒqƒCƒ`چىگ¬‚âŒن‰r‰ج‚جٹz‚جڈC—‚جŒo‰ك‚ب‚اپA‚³‚ـ‚´‚ـ‚بŒنٹJ’ ‚ةŒW‚ي‚é“_‚ة‚آ‚¢‚ؤ•ٌچگ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚»‚µ‚ؤپA’nŒ³‚جŒ÷‰_ژ›پi’أ‹vˆنڈéژه‚إ‚ ‚ء‚½‚ئ“`‚¦‚é“à“،ژپ‚ج•و‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚إ—L–¼‚إ‚·پj‚جڈZگEپE•›ڈZگE‚ة‚و‚é“اŒo‚ج’†پAژQ—ٌژزˆê“¯‚ةڈؤچپ‚ھ‰ٌ‚³‚êپA8–¼‚جڈ—گ«‚½‚؟‚ة‚و‚éŒن‰r‰ج‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚»‚جŒمپAڈZگE‚جˆ¥ژAپA‹L”OژB‰e‚ئگi‚ٌ‚إچ§گe‰ï‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB‚ـ‚½پAچإڈI“ْ‚ج31“ْ‚ة‚ح•آ”àژ®‚ھ‚ ‚èپAŒكŒم‚Qژ‚©‚ç11“ْ‚ئ“¯—l‚ةڈZگE‚ة‚و‚é“اŒo‚âڈ—گ«‚جŒن‰r‰ج‚àچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB پ@
پ@چ،”N‚جŒنٹJ’ ‚ة‚ح‘S‘ج‚إ750–¼‚ظ‚ا‚ج‚²ژQ”q‚ھ‚ ‚èپA‹كڈê‚ح‚à‚؟‚ë‚ٌ‚ج‚±‚ئپA‰“‚‚ح“s“à‚âٹ™‘qپA‚ ‚é‚¢‚ح‹{ڈ錧‚âگأ‰ھŒ§‚©‚炨Œ©‚¦‚ة‚ب‚ء‚½•û‚à‚ ‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚·پB‚¢‚¸‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚à’nŒ³‚جٹF—l‚ج—ح‚ًچ‡‚ي‚¹‚ؤژہژ{‚³‚ꂽ•½گ¬26”N‚جŒكچخ‚ج–{ٹJ’ ‚حڈI—¹‚µپA‚U”NŒم‚ج’†ٹJ’ ‚ـ‚إٹد‰¹‘œ‚ج”à‚ح•آ‚ك‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپAچ،‰ٌ‚جٹد‰¹—l‚ض‚جژQ”q‚ئ‰½‚و‚èچھڈ¬‰®’†–ى‚جٹF—l‚ج’g‚©‚¢‚à‚ؤ‚ب‚µ‚حپAژQ”q‚ة–K‚ꂽ‘½‚‚جگlپX‚جگS‚ةژc‚é‚à‚ج‚ئ‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚حٹشˆل‚¢‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB پ@ پ@چ،‰ٌ‚ج’†–ى“°‚جٹد‰¹ŒنٹJ’ ‚جڈ€”ُ‚©‚çژہژ{پEڈI—¹‚ـ‚إ‚ج’²چ¸‚ةچغ‚µ‚ؤ‚حپA‹e’nŒ´–«‚³‚ٌ‚âŒنٹJ’ ژہچsˆدˆُ’·‚جˆہگ¼‰p–¾‚³‚ٌپA•›ˆدˆُ’·‚إژ©ژ،‰ï’·‚جژآ“c—²•v‚³‚ٌپA“¯‚¶‚•›ˆدˆُ’·‚جژR–{‘پ•c‚³‚ٌپAڈ¼–{ڈt”ü‚³‚ٌ‚âژ©ژ،‰ï‚ج•›‰ï’·‚ج•ûپX‚ً‚ح‚¶‚كپA’nŒ³‚ج‘½‚‚جٹF—l‚ة‘ه•د‚²‹¦—ح‚ً‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پB‰ü‚ك‚ؤگ[‚‚¨—ç‚ًگ\‚µڈم‚°‚ـ‚·پi–¯‘’S“–پ@‰ء“،—²ژuپjپB |
||||||||||||||||||||||||||||||
| پ@ ‘O‰ٌ‚جپu–¯‘‚ج‘‹پE‘ٹ–حŒ´‚ج–¯‘‚ً–K‚ث‚ؤپi‡‚69پjپvپv‚إڈذ‰î‚µ‚½’أ‹vˆنٹد‰¹—ىڈê‚ج‚²ٹJ’ ‚حپAڈ—گ«‚½‚؟‚ة‚و‚éƒIƒqƒCƒ`چى‚è‚ً‚RŒژ‚X“ْ‚ًٹـ‚ك‚ؤ‚S“ْٹشچs‚¢پA‘S‘ج‚إ600Œآ‚à‚جƒIƒqƒCƒ`‚ًٹ®گ¬‚³‚¹‚é‚ب‚اڈ€”ُ‚ھگi‚ك‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚»‚µ‚ؤپAکA‹x’†‚ج‚TŒژ‚R“ْ‚جŒك‘O‚Xژ‚©‚ç‘S‘ج‚ج‚µ‚آ‚炦‚ھ‚ب‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB
پ@چى‹ئ‚ح–ىٹO‚ئژ؛“à‚ئ‚إژè•ھ‚¯‚µ‚ؤچs‚ي‚êپA–ىٹO‚إ‚حپA‰ٌŒü’Œ‚ً—§‚ؤ‚½‚è’Œ‚ج‰؛‚ةگ™—t‚ًڈü‚éپAژQ”qژز‚ھکkŒûپi‚ي‚ة‚®‚؟پj‚ً’@‚‚½‚ك‚جچj‚ً•ز‚ق‚ب‚ا‚جچى‹ئ‚ھ’jگ«‚ة‚و‚ء‚ؤچs‚ي‚ê‚ـ‚·پBژ؛“à‚إ‚حڈ—گ«‚جژè‚ة‚و‚èپAژP‚ًڈم‘¤‚ة•t‚¯‚ؤ‚»‚ꂼ‚êŒq‚°‚½ƒIƒqƒCƒ`‚ًٹد‰¹—l‚ج—¼‘¤‚ةڈü‚è‚آ‚¯پA‚±‚ê‚ئ‚ح•ت‚ةŒآگl‚ج•û‚©‚ç•ٍ”[‚³‚ꂽگç‰H’ك‚ب‚ا‚àڈü‚è‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤپA’jگ«‚جژdژ–‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپA’ٌ“”‚ًژو‚è•t‚¯پAٹد‰¹‘œ‚جژè‚ةŒ‹‚ر‚آ‚¯‚邨ژèچj‚ئ‚»‚ê‚ً‚آ‚ب‚®ŒـگF‚ج•z‚ب‚ا‚ج—pˆس‚àچs‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚ب‚¨پAŒـگF‚ج•z‚ً’ت‚¶‚ؤٹد‰¹—l‚ج‚¨ژèچj‚ھŒ‹‚ر•t‚¯‚ç‚ê‚é‰ٌŒü’Œ‚حپAƒIƒqƒCƒ`‚ئ“¯—l‚ة12”N‚ةˆê“x‚ج–{ٹJ’ ‚جژ‚ةگV‚µ‚‚µ‚ؤپA‚»‚جٹش‚ج’†ٹJ’ ‚جچغ‚ة‚ح•\–ت‚ًچي‚ء‚ؤژg‚¤‚»‚¤‚إ‚·پB پ@
پ@‚±‚ج“ْ‚جڈ€”ُ‚حŒك‘O’†‚ة‚حڈI‚ي‚炸‚ة•ذ•t‚¯‚ب‚اپAˆê•”‚جچى‹ئ‚ھŒكŒم‚©‚ç‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB ‚±‚¤‚µ‚½‚³‚ـ‚´‚ـ‚بڈ€”ُ‚ًŒo‚ؤپA‚و‚¤‚â‚‚TŒژ11“ْ‚©‚ç‚جٹJ’ ‚ًŒ}‚¦‚邱‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB “–“ْ‚ج’²چ¸‚ة“–‚½‚ء‚ؤ‚àپAˆّ‚«‘±‚«‹e’nŒ´–«‚³‚ٌ‚âپAŒنٹJ’ ژہچsˆدˆُ’·‚جˆہگ¼‰p–¾‚³‚ٌپA•›ˆدˆُ’·‚جژR–{‘پ•c‚³‚ٌپAڈ¼–{ڈt”ü‚³‚ٌ‚ً‚ح‚¶‚كپA’nŒ³‚ج‘½‚‚جٹF—l‚ة‘ه•د‚²‹¦—ح‚ً‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پi–¯‘’S“–پ@‰ء“،—²ژuپjپB
| ||||||||||||||||||||||||||||||