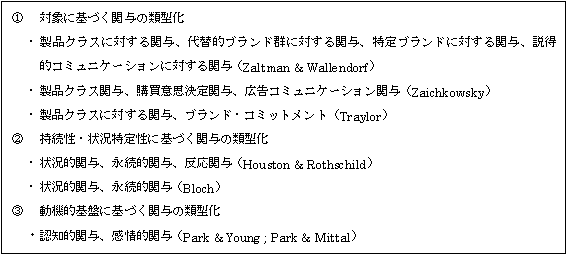
表1 関与概念の諸類型(1989,青木)
今日まで、数多くの研究者によって、「関与(involvement)」という構成概念の研究がなされてきた。しかし、研究者間で必ずしも意見の一致をみるに至らず、各々の研究者が研究文脈で独自に「関与」概念を規定し始めた。結果として、「関与」についての多種・多様な概念規定が並存することになり、非常に混乱した状況に陥った。
そこで、本章では今まで行われてきた関与概念の研究の整理をしたいと思う。
近年、消費者行動論の分野で数多くの研究がなされるようになった「関与(involvement)」という用語の概念は、社会心理学の社会的判断理論(social judgement theory)において導入された「自我関与(ego-involvement)」をその起源としている。しかしながら、今日の消費者行動研究において「関与」という用語が用いられる時、それは本来の意味での自我関与概念からは次第に離れ、ヨリ広い概念ないし自我関与とは多少異なる成分を持つ構成概念をさす用語として、それを用いる研究者の関心により様々なニュアンスで使用されている。
このように同じ関与という用語を用いながらも研究者により意味するものが異なるという同床異夢的な状況が出現してきた背景としては、消費者(個人)が何かに関与している(being involved with)状態を等しく説明すべき現象の重要な媒介変数としつつも、関与の対象や媒介変数としての関与ないし視点の違いが重要な要因として挙げられる。すなわち、研究上の視点や力点の置き方により、同一の現象や対象について異なった捉え方や位置づけがなされるのは、ある意味では当然であるが、関与研究における今日の混乱の原因は、異なる位置付けと捉え方による関与概念が、厳密な概念規定なしに等しく「関与」の名の下に取り扱われてきたことにある。従って、無用な混乱を避け関与概念についての共通理解を得るためには、何よりも先ず、従来関与という用語が用いられてきた研究上の文脈を整理し、そこでの関与の捉え方を位置付けの異同を明らかにする必要がある。
そこで、今日の関与研究の源流を3つに大別し、各々における関与の捉え方と位置付けの特徴を概観することにする。
(1)自我関与としての関与概念
これまで繰り返し述べてきたように、消費者行動論における関与研究の源流の一つを遡って行くと、数多くの関与概念の原型をなす「自我関与」の概念とその母体である「社会的判断理論」へと辿り着く。
ここで言う社会的判断理論とは、M.Sherifとの彼の共同研究者らの手によって始められた諸研究の総称であり、態度や態度変化の基礎にある心理的過程を判断との関連において説明しようとする社会心理学の一アプローチのことを指している。すなわち、この理論の主たる関心は、個人が既に保持している態度に関連した事物を判断しようとする際に生じる歪みの問題や、そのような判断の過程と態度変化との関連性の問題等を明らかにすることにあり、自我関与はその際の重要な媒介変数の一つとして捉えられている。
例えば、Sherif, Sherif & Nevergallによれば、ある問題(ないしは態度対象)に対する個人の立場(position)は、それと関連づけられた刺激を判断する際に準拠点(reference point)ないしは係留(anchor)としてはたらき、同化効果(assimilation)や対比効果(contrast effect)という判断過程における歪みを生じさせるが、個人のその問題(ないし態度対象)に対する自我関与の程度が高ければ高い程、また、特定の立場に対する個人のコミットメントの程度が強ければ強いほど、その立場は係留として強くはたらき、結果として受容可能な立場の範囲を狭くして反対に受容不能な立場の範囲を広くするという。また、この結果として、自我関与が高い場合には、個人の態度上の立場と大きく異なるような唱導内容を持つコミュニケーションは反対に対比効果をもたらし、場合によっては唱導内容とは全く逆の方向への態度変化(ブーメラン効果)を生み出すとしている。
このようにSherifらは、態度変化やコミュニケーション効果を判断過程との関連において捉え直し、その際の重要な媒介変数として自我関与という概念を導入した最初の研究者であった。その後、彼らの基本的な考え方は説得的コミュニケーションと態度変化との関係を研究する多くの研究者によって踏襲され新たな展開を見せることとなったが、それに伴い「自我関与」という初期の用語や概念に代わって、「事象関与(issue involvement)」や「個人関与(personal involvement)」といった用語が用いられるようになってきた。しかしながら、この研究の流れにおける関与概念の捉え方と位置づけを明らかにするためには、その原型をなす自我関与の概念との関連において、次のような諸点について検討しておく必要があろう。
第一に、社会的判断理論における自我関与とのその流れを組む関与概念は、考察対象である態度形成事象(attitudinal issue)が当該個人にとって重要である程度を指す概念である。例えば、Sherifはその初期の研究において、自我関与を価値と対象物との統合の程度として捉え、対象物が自己の価値と高度に関連づけられた状況を高自我関与とし、その反対を低自我関与として定義している。その後の研究における自我関与概念も、また、事象関与や個人関与といった関与概念も、当該個人にとっての重要性の程度と関連した概念であるという点で、基本的に一致している。
第二に、M.Sherifが自ら言及しているように、彼らが用いた「自我(ego)」という用語は、フロイト派や新フロイト派の言う自我概念とは明らかに異なるものである。この点、共同研究者の一人であるC.W.Sherifは、後年、無用な混乱を避けるため自我関与に代わって「自己関与(involvement of self)」という用語を提案しているが、彼らにとっての自己(ないし自我)とは、対象、個人、状況、およびその他の環境上の事象(environmental event)との関係を規定する心理的体制のことであり、過去の生活体験を通して形成された相互依存的な態度の体系(自己体系)のことを指す。このような態度の相互依存的な体系としての自己体系(self system)は個人の階層的な価値体系(value system)と結びついており、自己体系内の個々の態度は重要性の点において各々異なっている。従って、自己(ないし自我)が関与するのは重要性の点において異なる個々の態度であり、自我(自己)関与とは「自我が関与している状態(ego-involving attitude)」のこと他ならない。
第三に、それが故に、自我(自己)関与の程度は、個人が当該態度対象に対して保持している態度の相対的重要性によって規定される。すなわち、上述のように、自己体系は価値体系を密接に結び付いており、また、価値体系は階層的構造をなしていることから、ヨリ上位の中心的な価値と結び付いた態度対象ほど自己体系との関与(すなわち、自己関与)の程度が高いということになる。また、自我関与は対象が個人の価値と本来的に関連しているが故に生じる対象への関心や重要性であり、この点で「反応関与(response involvement)」や「タスク関与(task involvement)」といった関与概念とは異なっている。
最後に、Freedmanが指摘しているように、関与概念には"態度対象に対する特定の立場へのコミットメントを前提としそれを含んだ"関与概念と"特定の立場へのコミットメントを前提としない関与ないし態度対象に対する興味や関心の一般的水準"としての関与概念があるが、社会的判断理論において用いられた自我関与の概念は前者のものであり、暗黙のうちに特定の立場(attitudinal position)を前提としそれへのコミットメントを含めた概念であった。
このように今日の関与研究の源流の一つをなす自我関与概念とその流れを組む関与概念は、あくまでも社会的判断理論という研究上の文脈の中から生み出された概念であり、それが故に以上のような概念的特性を持った構成概念であるということを十分に認識しておく必要がある。
(2)媒介関与としての関与概念
消費者行動研究の分野において関与という概念を初めて導入したのはKrugmanであるが、以降、彼の一連の精力的研究の成果により関与概念は広告コミュニケーション効果の研究においてもっとも重要な媒介変数の一つとして捉えられるようになった。
当初、Krugmanは、テレビ広告がブランドの知名率を上げるのには効果があってもブランドに対する態度を変化させることにはほとんど効果がないという事実に関心を持ち、このような現象を説明する原理として無関与学習(learning without involvement)という概念を提示した。すなわち、彼によれば、通常受け手はテレビという媒体を通して提示される広告内容に対して特別の注意を払っておらず、メッセージは無意味な素材として関与の低い状態で受容されるという(その意味で、テレビ広告への露出中に生じる認知的処理は、無意味綴りの学習に似た関与の低い学習である)。また、このような低関与状態で受容されたメッセージは、高関与状態で受容されたメッセージとは異なり、認知的反応や行動に先立つ形での態度変化といったものは引き起こさず、認知的反応や行動に先立つ形での態度変化といったものは引き起こさず、認知構造を僅かずつ変化させて行くだけの効果しか持たない(認知構造の変化は実際の購買状況において初めて表面化する)。従って、テレビ広告は、その反復的露出の効果によりブランドの知名率を上げはするが、購買前に態度変容をもたらすだけの効果はなく、それが真に効果を発揮するのは店舗内での実際の購買状況においてということになる。
Krugmanは、以上のようなテレビ広告における無関与(低関与)学習の実態を実証するために、関与を「視聴者が彼自身の生活と刺激との間で行う1分間当たりの橋渡し経験(bridging experience)、関連づけ(connection)、および個人的参照(personal reference)の回数」として操作を定義し、その測定を試みた。具体的には、広告を一定時間露出させた後、広告と被験者自身の生活内容との関連性を言語によって報告させるというプロトコール手法を用い、広告に対する関与は、高関与製品の場合にはテレビ広告より活字広告の場合に関与が高く、低関与製品の場合には両者の間に差異がないという結果を報告している。
このようにKrugmanは、自らの関与の定義の基づき、広告露出中の受け手の関与水準が、使用される媒体によって規定されることを明らかにした。その後、彼は媒体による関与水準の相違を脳波(brain wave)によって測定する研究に取り組み、テレビ広告の場合より活字広告の場合に精神活動の覚醒状態を示すベータ波がヨリ多く検出されることを研究した。また、1977年の研究論文では、活字広告からの情報の処理が主に大脳の左半球で行われるのに対して、テレビ広告からの情報の処理は大脳の右半球で主として行われるという説を提起し、この結果としてテレビ広告の効果は左半球における視覚的イメージを中心としたものになることを示唆した。
以上の議論から明らかなように、Krugmanが用いるところの関与概念は、先に検討した社会的判断理論における自我関与の概念とは若干内容に異にする。すなわち、自我関与があくまでも態度と密接に関連した関与であり態度形成事象と自我(自己体系)との結び付きの強さを反映した概念であるのに対して、Krugmanの言う関与は媒体の特徴やコミュニケーション状況の相違による受け手(聴衆:audience)の情報処理のタイプや強度を反映した概念であり、それは「媒体関与(media involvement)」、「聴衆関与(audience involvement)」、ないし「コミュニケーション関与(communication involvement)」とでも呼ぶべきものであった。このように両者の間には同じ関与という用語を用いつつも構成概念の内容にズレがあるが、特に次のような相違点は明確に認識されてしかるべきであろう。
第一に、自我関与は上述のように態度形成事象と階層的価値体系としての自己体系との結び付きの強さの程度を表す状態概念であるが、Krugmanの言う関与はコミュニケーションの中で与えられた刺激と個人の生活経験との間でなされる関連づけによって規定されるものであり、その後の個人の情報処理のタイプや強度を含むヨリ包括的な課題である(但し、最近では、Krugmanは関与をヨリ生理的に測定しようと試み、後者の情報処理の面が更に強調される様になってきている)。
第二に、自我関与は態度形成事象を自己体系との結び付きの強さを反映したものであることから、その性格はある程度永続的で状況横断的なものである。これに対して、媒体関与ないしはコミュニケーション関与は、コミュニケーション時における媒体の特性やコミュニケーション状況によって規定される情報処理のタイプや強度を反映した概念であり、結果としてその性格は状況特定的で一時的なものとなる。
第三に、自我関与は個人の価値体系に基盤を置くことから、同一の態度形成事象についても関与の程度は個人間で大きく異なるであろう。これに対して、媒体関与やコミュニケーション関与は媒体の特性やコミュニケーション状況によって規定されることから、個人間の差異よりも媒体間等での差異の方が差異のヨリ大きな源泉として考えられる。
(3)購買重要性と関与概念
今日の関与研究の源流をなす第三の流れは、いわゆる「購買重要性(importance of purchase)」の概念とそれに関連する研究の流れである。
購買重要性という概念は、消費者の購買意思決定過程全体に影響を及ぼす重要な変数としてかなり早い時点から認識されてきた。例えば、消費者の購買行動についての最初の包括的モデルであるHoward and Shethモデルの中においても、購買重要性は購買意思決定過程に影響を与える外生変数(exogeneous variable)の一つとして定式化され組み込まれている。
彼らの定義によれば、購買の重要性とは、"消費者の活動を支配する動機(motive)の相対的強度であり、ある製品クラスと他の製品クラスとの相対的関係を規定するもの"あり、それは時として"関与の程度(degree of involvement)、購買の重要性、課題の重要性、ないし結果の深刻性(seriousness of the consequence)"という様々な名前で呼ばれているという。
購買重要性をこのように広く捉える立場に立つなら、関与と購買重要性とは互いに大きく重なり合う相互に代替的な概念として捉えられる。事実、最近の関与に関する実証的研究の内の多くのものは、関与概念を操作化を行っており、また、二つの概念を全く同義なものとして捉える研究者さえ存在する。
このように購買重要性と自我関与は長らく混同され、極端な場合には同一視されてきたが、本来、これら二つの概念は重なり合う部分を持ちつつも独自の内容を持つ別個の構成概念として捉えられるべきものである。この点において、次のような両者の相違点は明確に認識される必要があろう。
第一に、自我関与は購買重要性を規定する重要な要因の一つであるが、購買重要性の規定因は何も自我関与のみに限らず、他にも知覚リスク(perceived risk)等の要因が考えられる。すなわち、例え自我関与の面において関与度の低い製品であっても、その製品を購買する際に知覚するリスクの程度が高い場合には、消費者にとって当該製品を購買することの重要性(=当該製品の購買意思決定にヨリ多くの情報処理努力を払ってもよいと考える程度)は高くなるであろう。実際、消費者は製品の購買に際して様々なリスクを知覚しており、その結果として購買重要性が高まるような種々のケースが考えられる。
第二に、先にも述べたように自我関与という概念は、態度形成事象と自己体系との結びつきを反映した概念であることから、それはある程度永続的で状況横断的な性格を有するものと考えられる。これに対して、購買(意思決定)の重要性は具体的な購買状況や予想される使用状況との関連において知覚されるものであり、必然的にその性格は状況特定的で一時的なものとなるであろう。
第三に、前述のように、購買重要性の概念において問題となるのは、ある製品の特定状況下における購買(意志決定過程)の成果を当該個人がどの程度重要視しているかということであり、そこで知覚される重要性の程度は、ヨリ良い購買意思決定の遂行というタスク(課題)の達成によって実現される手段的価値(instrumental value)を基盤としている。(その意味では、購買重要性は前述のタスク関与の概念に類似している)。これに対して、自我関与の程度は、態度形成事象の価値体系における中心性を反映した概念であり、自我関与の高さは究極的価値(terminal value)との結びつきの強さを基盤としている。
以上、本節においては、今日の関与研究の源流を3つに大別し、各々の研究の流れにおける関与概念の捉え方と位置づけの異同について検討してきた。その結果からも明らかのように、ここで取り上げられて3つの関与概念は、それぞれの研究上の視点や力点の置き方の相違から同じ関与という名で呼ばれながらも互いに重なり合わない部分を持つ概念であることが確認された。特に、社会心理学の分野で開発された自我関与概念と消費者行動研究における2つの関与概念との間には幾つかの点で注意されるべき相違があった。
従来の関与研究における混乱は、このように本来異なる研究文脈において開発・使用された構成概念が等しく関与をいう名の下に用いられていることから生じているように思われる。従って、無用な混乱を避け関与についてのヨリ包括的で厳密な分析枠組みを構築するためには、以下のような問題の広がりを十分に踏まえた上で関与概念について再規定を行うことが必要となる。
これまでの検討からも窺えるように、従来の関与研究における混乱の源泉は、研究対象としての「関与」概念がその内容面において極めて多種・多様な形で用いられてきた点に求めることができ、また、その概念的特性の規定が必ずしも十分明確な形で行われてこなかったことに起因している。
そして、その後、前者の概念的内容の多様性の問題は数多くの研究者による関与概念の類型化の試みと相まって、また、後者の概念的特性の不明確性の問題は関与概念を操作化し測定しようとする試みと相まって、研究上の混乱をヨリ深刻なものにしていった。
第一に、1980年代に入り上述のような関与研究の概念的内容面での混乱が指摘されるようになるにつれて、そのような概念規定上の混乱を解消するための試みとして関与概念の類型化を目的とした概念的研究が数多く発表されるようになるが、それらの試みはそこで用いられた類型化の基準自体が研究者によって異なっていたことから新たな混乱の火種を残すこととなった。
例えば、表1は、これまでの概念的研究において提示されてきた様々な「関与」概念の類型化の試みを、①関与の対象による分類、②関与の持続性ないし状況特定性による分類、③関与の動機的基盤に基づく分類、という3つの分類基準に従って整理したものであるが、同表が示しているように、多種・多様な分類基準が相互に関連付けられぬまま並存するといった状況は、問題を解決するどころかかえって研究上の混乱を増幅する結果となっている。
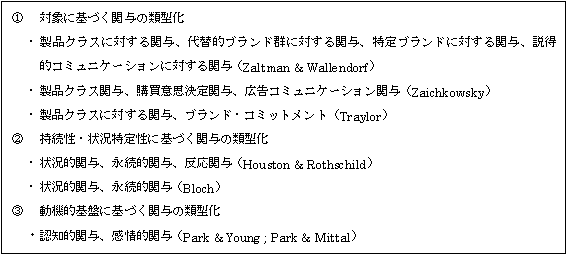
上述のように、現在まで行われてきた「関与」研究は、各々の研究者が独自に「関与」概念を規定してきた。そのため、類似の用語を使用して、異なることを言及しているという問題が生じている。ここでは、非体系的な用語集として、関与概念の種類(理論)を整理する。
①自我関与 (ego-involvement)
Sherif & Cantrilが問題にし、Ostrom & Brockがはっきり定義した。「事物または考えが個人の価値体系の中心に関連する程度」を指す。ただし、Greenwaldのいうように自我関与ということばは多様な意味で使われている。
②コミットメント (commitment)
「ある問題の特定の立場への関与」のこと。問題自体に対する関与と異なる。特定の車だけではなく特定の車のタイプに価値を見いだすように、自我関与はコミットメントなしにも存在する(Muncy & Hunt)。また、知覚したリスクが高い場合などに、コミットメントは自我関与なしにも存在し得る。コミットメントは「ロイヤリティ」という名のもとで研究されている。
③コミュニケーション関与 (communication involvement)・広告関与(advertising involvement)
Krugmanが問題にしたもの。Muncy & Huntはコミュニケーション関与といっている。「特定の時におこるもので、場面特有で、一時的なもので、コミュニケーション、特に広告に関する関与」である。個人の生活のある特定の側面に結び付いていて個人の中心的価値体系を関連していない。特に消費者の情報処理と関係している。現在、広告関与と絡めて、広告の情報処理に関する理論研究・実験研究が多く行われている。
④購買重要性 (important of purchase)・購買関与 (purchase involvement)
Howard & Shathがとりあげた。自我関与や知覚したリスクなどによって購買重要性が高くなる。購買関与と他の関与との関係を描いたものにBloch & Richinsがある。購買関与は状況関与と反応関与の側面がある。
⑤反応関与 (response involvement)
2つのタイプの定義がある。一つは、Houston & Rothschildが提案した、「消費者の意志決定全般を特徴づける認知過程および行動過程の複雑性」という定義である。高反応関与者はできるだけ多くの情報を集め、最適の選択に到着するように集めた情報を使う。
もう一つは、Zimbordoの「自分の反応の結果つまり自分の意見の結果についての関心」という定義である。これに対する関与は問題関与である。Johnson & EaglyはZimbordoの実験からすると反応関与というよりも印象関連関与であるとしている。
2つの反応関与は全く異なる定義である。消費者行動のなかでは反応関与というとHouston & Rothschildの意味で使用するのが普通である。この考えには、単に関与の結果であって関与といえないという批判もある(青木幸弘など)。反応関与は関与している場合おこなわれる状態を指しているものであり、この側面は関与と呼ぶよりも「情報処理の複雑さ」、「処理水準」などと呼ぶほうが混乱を招かないであろう。実際の測定ではこの反応関与の側面を測定することが多い。また、関与を行動としてとらえると反応関与こそが関与ということになる。
⑥永続的関与 (enduring involvement)
Houston & Rothschildは新行動主義のS-O-Rの立場かあら関与を分類しているが、その中のO(生体)の部分に対応する関与である。その状況以前から個人の中にあり、個人間の差異を説明する関与である。
Blochは製品関与と同じものとして永続的関与を見ている。ここでは、Richins & Blochを参考にして、「購入場面と独立して存在し、自我または快楽的楽しさとの関連程度によって動機づけられる関与」としておく。永続的関与の代表例に製品関与がある。
⑦状況関与 (situational involvement)/⑧課題関与 (task involvement)
Houston & Rothschildによると、状況関与は「ある状況がその状況においてその人の行動に対する関心を引き起こす能力」のことである。代表的なものは購買関与である。課題関与も含めることがある。
消費者行動における課題関与は購買目的の違いによって生じる関与である。状況関与が購買状況と非購買状況を区別することが多いのに対して課題関与は購買場面に限定されている。例えば、Gardial & Biehalは「カメラを友人のために選ぶ」というのと「単にブランドを選ぶ」という設定で課題関与を操作している。また、Clarke & Belkにおいても課題関与を贈り物として買うか、自分の使用するものとして買うか区別している。課題関与の区別は微妙である。多くの研究は課題関与を状況関与と区別していない。
一方、達成動機の研究のなかで課題関与は問題関与とよく似ている。たとえば、Nichollsは、競争場面におくことで自我関与を高めるのに対し、非競争場面において課題関与を高めている。課題関与においては課題に対する遂行の改善が目標であり、課題のマスターが最終目標であるのに対し、自我関与は自己の能力が他人より優れていることを示すことが最終目標であり、課題のマスターは手段にしかすぎない。
購買関与と課題関与の関係は、購買という課題ととるか、購買の中での課題区分ととるかによってわかれるところである。消費者行動の枠組みのなかで考えるならば、購買課題中か否かよりも購買の中での課題区分のほうがより生産的な問題となる。
⑨問題関与 (issue involvement)/⑩個人的関与 (personal involvement)
Zinbardoによると、問題関与は、「個人の欲求、価値に関連するものであり、そのものに対する関与」である。Zinbardoは従来の関与研究を問題関与としてまとめ、それ以外の側面として反応関与を考えたので問題関与そのものは実験的に操作していない。
現在、説得に関する関与の研究の多くはPettyとCacioppoのパラダイムに基づいている。Petty & Cacioppoにおいては「問題関与」、Petty, Cacioppo, & Goldman では「個人的関与」、Petty & Cacioppoでは自我関与、問題関与、個人的関与を同じように扱って、「個人的関連性 (personal relevance)」という語を使っている。
Zinbardoの定義からすると、自我関与そのもののように見えるが、Johnson & Eaglyは実験方法からすると問題関与というよりも結果関連関与であるとしている。なお、個人的関与はC. W. Sherifが自我関与という用語に対する誤解を避けるために使用している。社会的判断理論のものは価値関連関与である。
⑪製品関与 (product involvement, product class involvement)
製品関与は「購買目標がないときに、リスクに基づかず、製品と個人の欲求・価値・自己概念との関連の強度によって生じる関与」である(Bloch)。製品によって関与が違うことはよく知られている。乗用車、家などの高関与製品から歯ブラシ、電池などの低関与製品の区分は一般に製品によって関与が異なることを基盤にしている。しかし、このことは製品関与が製品に付着していることを意味しているのではなく、個人がそれぞれ関与しているものであり、製品に対する関与のことである。ただし、関与の平均値に大きな違いがあるので、製品によって関与を操作することは間違いではない。
⑫認知的関与 (cognitive involvement)/⑬感情的関与 (affective involvement)
「ブランドの性能を強調する功利的動機から生じる」のが認知的関与であり、「実際の自己像や理想の自己像を表現する側面に情緒的に美的にアピールする価値表出的動機から生じる」のが感情的関与である(Park & Young)。Park & Mittal、および彼らが共著者となっているZaltman & Wallendolfにおいて2つの関与による処理方式の違いを詳細に論じている。基本的に認知的関与は論理的、分析的処理をし、感情的関与はアナロジー的、全体的処理をすると仮定している。この考え方は態度の機能論(Katz)から来ているものである。態度、動機、関与に関係する微妙な問題に関わっている。
⑭意志決定関与 (decision-making involvement)/⑮購買意志決定関与
意思決定関与はBaker & Lutzが提案している。「消費者がブランド反応するのに使っている認知的努力の程度を規定する動機の構成体」である。Houston & Rothschildの反応関与の一部といえる。Baker & Lutzは広告処理を重点においているが、購買に関する意思決定関与も別にある。青木は状況特定的関与の課題のとらえ方として購買意思決定関与という用語を使っている。