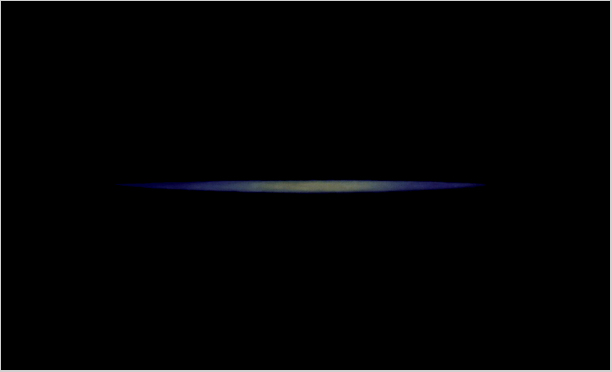ANNE BOLEYN Museum of Art
「Meditation」シリーズ Work-2009 No.2 (M) 油彩 キャンヴァス 90.0×136.0cm
小原 義也 Ohara Yoshiya
現代日本美術会会員/評議委員アン21美術館/館長
高知県香美市に、市立<小原義也奥物部美術館>開設
1935 高知県生まれ
1955〜2011
国際青年美術家展
毎日現代美術展
シェル美術賞展受賞
日本国際美術展
日本現代美術20人展招待
アメリカ、オランダ、ベルギー、韓国、国際美術交流展
RINEART FEST(ベルギー)国際美術見本市出品1997 高崎元尚+小原義也の現代美術2人展(香美市立美術館企画)
こんなアバンギャルド芸術があった!(高知県立美術館企画)
1999 日韓現代美術交流展出品(ソウル)
2000 日蘭交流400年記念日本現代美術展出品(アムステルダム)
2001 国際美術見本市LINEART(ベルギー)
神奈川県・PENAN州友好記念美術展(横浜)
第1回現代美術CAT展2010年まで開催(神奈川・相模原市)
2002 相模原市文化財団評議員(〜2007)
2003 高知の美術史150年の100人展に選出(高知県立美術館企画)
2009 相模原市収蔵作品展(神奈川)
2010 川崎市主催IBMギャラリーファイナル展招待(神奈川)
2011 小原義也展(1975〜2010)(高知・香美市立美術館企画)
2012 高知県立美術館収蔵60年代の前衛作家展 (県立美術館企画)
2013 日西交流400年記念展(カナリヤ諸島グランパレス)個展70数回、グループ展多数
その他美術館企画展、収蔵展
国内美術館、公共施設等作品収蔵日本美術家連盟会員
小原義也のようにキャリアの長い作家を
限られた紙幅で論ずるのはむずかしい。そこで最近作だけを対象として、そこに提示された問題性について論じておきたい。
いずれも100号に近い大作ばかりだが、私たち人間には全体像をイメージしにくい宇宙空間とか、サイバー空間のように形而上学的に措定され、実在を背景としていない空間を連想させる暗青色があって、その中心に光が“ある”という画面構成である。私は、その深い宗教性を前にして、受肉した神の物語を綴ったジャック・マイルズの初めの部分をありありと思い出していた。一見すると、画面中央に蝋燭を置き、
その放射状の光で人物を描きだしたフランス・バロック古典主義のラ・トゥール、あるいは高島野十郎が生涯、描き続けた蝋燭の焔の構図を連想させるのであるが、小原の「光」は、もっと神学的な思索を踏まえた高い次元のものだと直観したのである。
ラ・トゥールの光は、まさに人間の「内なる光」、存在の内部に中核として実在している理性を象徴した光である。ところがマイルズの一節を思い出しながら眺めてみると、小原の光は、光がまだ存在する前の「光」だと確信してしまう。ヨハネ福音書の冒頭は
「初めにことばがあった、ことばは神と共にあった。ことばは神であった」という有名な一節で始まるが、これは「万物は言によって成った。成ったもので、言によらずに成ったものは何一つなかった。言のうちに命があった。命は人間を照らす光であった」(ヨハネ1、3-4)につながっていく。3-4節に出てくる「光」は、神の開口の言葉によって生まれた光ではないわけだが、小原が描こうとしているのは、この「光」だと思う。
そもそもヨハネ福音書の冒頭部分は、神がなぜ受肉してイエスという「人」となったかを物語る、「天上のプロローグ」とも言うべき位置づけにある。「世界創造」以前に神と共にあった
「ことば」が受肉して、キリストとなるわけだが、冒頭の一節は、旧約聖書「創世記」にある世界創造の端緒となることば、「光あれ」を言うまでの沈黙の間、神が何を考えていたのか、という「世界創造の幕開け」以前の独自の起源を啓示している。この世の覇権を与えた人間は神から離れ、自分の民として選んだユダヤ人の多くが神を拒絶した。そこで、神はこの民、ひいては人類全体と和解する最終手段として彼らの一人となったが、その時も神は拒絶されてしまった。しかし、この拒絶を通じて神はある栄光を勝ち取るのである。受肉して磔刑にかかり復活するという形で、神は自分の生涯をやり直した。
だからこそ神の被造物たる人間も、
罪多きその生涯を新たに始められ、神との新たな関係性を結ぶことができるからである。全知全能の神は、その世界創造に先立って、結論として立ち現れてくるこの物語をすでに知っている。そこで「光あれ」という前に黙して語らぬ神的自己意識があるわけだが、そこには小原の描く、創造以前のことばの命にある「光」があるのかもしれない。
こういう思索を可能にさせる
小原義也の画面を前にしては、粛然たる思いに駆られずにはいられない。
index