「ニッポンのエンゼル」〜日本における「天使」図像について〜
「背中に鳥の羽根が生えている子供」というと、皆さんは何を思い浮かべるだろうか。多くの人は、あの森永キャラメルのマークにも使われている「エンゼル」を思い浮かべるであろう。しかし一方で、今やマヨネーズの商標としてしか覚えている人はいないものの、ダッコちゃんなどとともにかつての子供大好きキャラクターの一人であった「キューピーちゃん」を思い浮かべる人もいるのではなかろうか。
2.西洋におけるキューピッドと天使の図像
・天使(エンジェル)
3.日本における有翼の幼児たち
3(補筆).フェアリーというもう一つの幼児形
4.森永エンゼルの成立
5.キューピーと現代のエンゼルたち
<8278字>
(注釈)
(参考文献)
(展覧会)1.「キューピーちゃん」と「森永エンゼル」
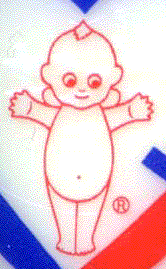

「エンゼル」というと西洋の天使、そこから私たちはヨーロッパの絵画に数限りなく飛び回るあの子供たちを想起したり、またはハンナ・バーベラのアニメ「トムとジェリー」でトムが(いつものごとく)爆死したりすると直ちにトムの魂を天に連れていく天使たちを思い浮かべたりすることであろう。
また、「キューピーちゃん」という名前から容易に想像できるのは愛の神、キューピッドである。これもまた特にバレンタインデーの時期にはおなじみのキャラクターであり、思いを寄せる人のハートにしっかりと狙いを定めたキューピッドの存在を、ちょっと乙女チック(死語)な女性ならば願っていたりするのではなかろうか。
ところで、それではキューピッドというのは天使の一種なのだろう、と普通の人なら思うだろう。「愛の天使」なんて枕詞をキューピッドについて聞いたこともあるし…しかし、その判断は正確にいえば正しくない。キューピッドとはギリシア・ローマ神話におけるクピドという愛の神のことであり、神である以上は一神教であるキリスト教とは相いれない存在であるからだ。
いったい、「キューピー」とは何なのか、「エンゼル」とは何なのか?実に長年接してきたこの二つの図像について、私はその出自を何も知っていないのだった。
ところが最近、その長年の「?」に解答の手がかりを与えてくれるたいへん面白い本に出会った。荒俣宏の「広告図像の伝説」(平凡社)という本で、ここにはエンゼルマークの由来が簡単に論じられている。それはこの「キューピーちゃんはエンゼルか」という問にも手がかりを与えてくれる内容だったのだが、この本をもとに、以降「キューピーちゃん」と「森永エンゼル」の正体について、少々詳しく考察をすすめてみたい。
・キューピッド(クピド)
キューピッドとはギリシア神話におけるエロスという愛の神であり、これをローマ人はクピドと呼んだ。キューピッドはクピドという言葉から出た発音である。クピドの図像が羽根を生やした裸体の幼児であるというのは既にローマ時代の美術にも見られるものであるが、神話においては必ずしもクピドは幼児であると定義されていたわけではなかった。クピド=幼児の図式が大幅に流布するのはルネサンスからバロックにかけての時代である。有名なところではボッティチェリの「プリマヴェーラ(春)」(図3)の画面上方に、目隠しをされたまま先の燃える矢を弓につがえたクピドが登場している。ここでクピドが放とうとしている燃える矢は「燃える愛」の象徴であり、それは画面左方で舞い踊る三人の美神のうち「貞節」に対して放たれようとしている(注2)。このように、思想、道徳の寓意画が多く描かれたルネサンス〜マニエリスム〜バロックに至る時代では、「恋」や「愛」という抽象概念を絵画上で寓意的にあらわす時に多く使われたのがクピドの画像であった。また、この頃のクピドは目隠しをされた状態で描かれる事が多かったが、それは「恋は盲目」ということの図像化であり、目隠しをされないクピドも多く描かれた(クピドの目が何故隠されたかについてはパノフスキーの古典的な研究がある:注3)。
「クピド=愛」の寓意は、画家たちだけでなく、エンブレムとしてイエズス会宣教師や錬金術師によっても利用された。エンブレムとはある教訓を寓意図とセットで表現したもので、こうしたエンブレムを集めた書物が16〜17世紀ヨーロッパでは多く刊行され、浸透していったのである。
クピドについては以上のように「羽根を生やし、弓矢を持った裸体の幼児(目隠しをされることもある)=クピド=愛」という形で浸透していったのだが、そのころ、天使はどのように描かれていたのだろうか。
キリスト教における天使(エンジェル)とはサンスクリット語のアンギラス、ギリシャ語のアンゲロス(いずれも「使者」をあらわす)から転じた語で、もともと聖書に登場するミカエル、ガブリエル、ラファエル以外はあまり重要視されてこなかった(注4)が、イスラム教の影響、さらには偽ディオニュシオス・アレオパギタの「天上位階論」をはじめとする教父神学によって「数多くの天使が存在する」と考えられるようになった。三大天使以外にも、多翼の上級天使セラピム、ケルビムなどが中世・ビザンツ絵画やステンドグラスにも登場してくるが、しかしそれらはいずれも翼こそ生やしているものの、衣を着た成人の姿をしており、幼児というクピド的・「森永エンゼル」的な姿をしているわけではなかった。ところがルネサンスになると、天使はどんどん数多く描かれるようになり、それらの外見も裸で有翼の幼児という、クピドとほとんど見分けがつかなくなる様なものが多く現れた(図4/ティツィアーノ「聖母被昇天」16世紀)。一体何故このようになったのか。
荒俣宏氏はこれに対して16〜17世紀に流行した守護天使の流行をあげている(注5)が、それよりはおそらく当時流行した新プラトン主義哲学の影響が大きいのではないだろうか。新プラトン主義はメディチ家の庇護のもとでフィレンツェを中心に流行した哲学思想の一潮流だが、ボッティチェリからミケランジェロ、ティツィアーノなどのルネサンスの芸術家に多大な影響を及ぼした。それまで厳格なキリスト教の信仰によって軽視されてきたギリシア・ローマの哲学や美学をキリスト教内部に取り込むことによって、キリスト教神学のより一層の充実化をはかろうとしたのが新プラトン主義であったといっていい。この新しい哲学の流行があったからこそ、それまでは思いも寄らなかった異教的(古代神話的)画題が取り上げられるようになったのだが、そうしてギリシア的な思想をキリスト教の中に回収する作業の中で、キリスト教絵画にギリシア哲学的テーマが見られるようになり、ついにはギリシア的図像(つまりクピドの図像)そのものがキリスト教絵画の中に流入してきたと考えられるのである。
こうしてクピドと天使は識別困難な形で16〜17世紀の西洋に流布していった。日本人が最初にこれらの有翼の幼児像に触れるようになったのもこのころである。
日本に直接こうした図像が流入した最初は、イエズス会の宣教師が持参した教化用の銅版画(図5)であろう。ここにあげた一枚には十字架上のキリストのまわりに有翼の幼児が飛び回っており、クピド形の天使である事が推察される(衣をまとっているのは、イエズス会がいたずらな裸体の露出を嫌う傾向にあったためだろう)。こうした銅版画がどれだけ日本で流布したかは分からないが、かなり大量に輸入されてはいたようである。もちろんこれらはキリシタン禁制によって隠されるようになっていくわけだが、この有翼の幼児がキリスト教と不可分のものであるとは考えられていなかったと思われる。というのは、江戸期に描かれた絵のいくつかに有翼の幼児像が登場するからである。
ひとつは司馬江漢がオランダ通詞の吉雄幸作に贈った幸作の肖像画(図6)で、神格化の手法として天使を描いている、と日本美術史学者のT・スクリーチは解説している(注6)が、いかにオランダ通詞が相手とはいえ、キリシタンの天使図像と知っていて肖像画に書き込むという危険を司馬江漢が犯したであろうか、という点は疑問である。司馬は有翼の幼児を描き込むことが西洋的な神格化の手法であったことは知っていたが、これが天使であることは知らなかったか、あるいは当時、有翼の幼児がキリスト教と関係あるという事は日本人に知られていなかったと見るべきであろう。
田沼意次と関係深い司馬江漢とライバル関係にあったのが、松平定信に庇護を受けていた亜欧堂田善である。田善もまた西欧画を学び、西欧画の手法を活用した洋風版画を多く残しているが、その一つに「アツケル女神像」という版画がある(図7)。その上方には確かに有翼かつ裸体の幼児が登場しているが、これはローマ神話の釣鐘草の女神の絵画ということで、これまたキリスト教との関連は考えられていなかったようだ。だからといって田善がクピドというものを知っていたかどうかはまた疑問であるが。
荒俣氏は江戸中期から明治にいたるまでの天使図像受容の諸相を以下のように記している。長くなるが引用しよう。「日本人が天使の像に初めて触れたのは(中略)江戸中期の平戸藩主松浦静山の大著『甲子夜話(かっしやわ)』であろう。静山は、なんと!羽根が生えた天狗の像は西洋の天使の姿を借りて生じたものだ、と主張した。(中略)しかし明治になると、『クピド』が書物や建物の装飾に使われだす。明治5年に刊行された東京日日新聞(やまと新聞社)は、錦絵一勇斎芳幾の筆になる『クピド』を開板広告から使いだし、毎号のカルトゥーシュ(りぼん形の飾り縁)にもこれをあしらうのだ」(注7)ということで、明治時代にいたると東京日日新聞の新聞広告に有翼の幼児像が登場してきたという事が分かる。ここに一枚あげるのは新聞そのものではなく、高橋克彦「新聞錦絵の世界」(角川文庫ソフィア)から引用した新聞錦絵だが(図8)、画面上方に「東京日日新聞」のタイトルを両側から支え持つ有翼全裸の幼児が見える。新聞錦絵は、刊行まもない頃の新聞の内容を、文字をあまり読めない人々のために解説するべく刷られた浮世絵ニュースといったものだが、残酷な情痴殺人を報じるショッキングな絵に、愛の神クピドがあしらわれている様はなかなかの奇観といえるだろう。
もう一つぜひあげておきたい例があるのだが、私の田舎(ちなみに新潟である)で発見した日露戦争の画報「日露戦争写真画報」第二巻(博文館発行)の一コーナー「戦時お伽噺」にあしらわれたカットである(図9)。「海底軍艦」で有名な日本の冒険小説作家押川春浪が戦地の小話を書いているこのコーナーに捧げられたカットには、明らかに鳥の翼を生やした幼児が登場しているが、体は裸ながらも軍帽をかぶり、帯刀しているのがわかる。また、翼が生えているのだから要らないはずの馬にまでまたがっているが、これはどうも玩具であるようだ。クピドは弓矢といったアトリビュートを捨て、軍装を身にまとうようにすらなっているのだが、これは新聞錦絵などにクピドの図像が使われていたことから、どうもジャーナリズム的内容に対する添え物としての有翼の幼児像が一種の定式と化しており、天使とか愛の神といった意味内容がほとんど考えられることがなかったために、こんな全く不似合いと思われるようなところにまで顔を出すに至ったのだと考えられる。
この有翼の幼児像は明治期に一体何者だと捉えられていたのか、という点については当時のジャーナリスト宮武外骨の記述がある。やはり荒俣氏の書から孫引きで恐縮だが引用しておく。「エンゼルというものを、わが国の画家も書くようになったのは、いつ頃からかと思っていたところ、明治八年十月、大阪で創刊せられた錦画百事新聞の引札に、もうそれが描かれていた。尤もそれは蝶々の羽根をつけないで、鳥の羽をつけた、ややぶざまな格好をしているが、画家は勿論エンゼルとして書いたのに違いない」(「東天紅」より・注8)大阪の百事新聞より東京日日新聞の方が古いのだが、ここではとりあえずあの有翼の幼児像は「エンゼル」と認識されていた事が確認できる。
ところで少々脱線になるが、この宮武外骨の文章でもう一つ気になるのは「尤もそれは蝶々の羽根をつけないで云々」というくだりである。蝶々の羽根をつけた、といえば英国ビクトリア朝時代に流行した「妖精」の図像が思い起こされる(図10)が、このころには妖精の図像がエンゼルと解釈されることがあったのであろうか。
蝶の羽根を持った幼児を妖精(フェアリー)像として流行させたのはビクトリア朝イギリスの画家リチャード・ドイル、エリナー・ボイルたちだったと荒俣氏は書く(注9)が、ここで指摘しておきたいのは「蝶の羽根を持ったクピド」という図像がルネサンス期にも存在していた事実である。それはマントヴァの宮廷画家マンテーニャの「美徳の勝利」あるいは「徳の森より悪を追い出すミネルヴァ」(図11)として知られる作品で、ここでは、徳を象徴する存在のミネルヴァによって追い払われる愛欲というマイナスの象徴として多くのクピドが描かれている。これがクピドであることはその弓と矢というアトリビュート(持物)から分かるが、その翼は明らかに鳥のものではなく、蝶々の羽根である。さらには、ミミズクやフクロウの頭を持ったクピドも描かれており、ここでは神であるよりも悪魔により近い存在として描かれていることが分かるのだが、それにしても「蝶の羽根を持ったクピド」というのは面白い存在である。
もう一つ面白いので取り上げたいのは、私が新潟にいる時に行った「ロマンの泉美術館」という書票画を主展示品とする美術館で見た、「薔薇とエンジェル展」(図12)の一展示品である。レンズ付きフィルムで撮った写真なのでぼんやりとしか写っていないのが残念なのだが、このビクトリア時代のバレンタインカード(図13)の中に、鳥の翼をもつ幼児と蝶の羽根を持つ幼児が混在しているのである。もはやどれがエンジェルでどれがフェアリーであるとはっきり区別できない状況にまで至っている。蝶の羽根を持つクピドや天使というものはあまりポピュラーではないが、少なくともビクトリア朝においてはこれらはごく自然に出回っていたことが分かるし、となると同じころの日本で「エンゼルは蝶の羽根を持つもの」として受け入れられたとしても不思議はないであろう。
さらにマンテーニャの画にみられる「蝶の羽根をもったクピド」を考えに入れると、事態は更に複雑になる。蝶の羽根を持った幼児形に出会った場合に、エンジェル、クピド、フェアリーという3つの可能性があり得るのだから。
三章補筆で述べたような複雑な状況はあるものの、それが蝶の羽根あれ鳥の羽根であれ、とにかく有翼の幼児像が「エンゼル」の名で明治期には受容されていたという事は分かった。その状況が分かれば、森永が有翼の幼児像を「エンゼル」として社票にした事の理解も容易になるだろう。森永の開祖、森永太一郎が森永西洋菓子製造所(森永製菓の前身)の登録商標としてエンゼルマークを登録したのは明治三十八年のことである。森永社史にはこう書いてあるようだ。
「森永の世界に誇るエンゼル・マークは創業まもなく生まれ、星霜五十四年(昭和二十九年現在)、大衆に親しまれている。現今の森永はあらゆる食糧に従事しているが、創業当時は珍菓マシマローなどに力を注いだ。この菓子はアメリカではエンゼルフード(天使の糧)とも賞せられ、創業当時の撒布文にも特のその製造に力を致したことが記してある。」(注10)
ここで森永太一郎が登録した最初のエンゼル・マークがこれ(図14)であり、はっきりと鳥の羽根をもった幼児として描かれている。もしもこれが蝶の羽根を持ったフェアリー的な天使であったら、日本における「エンゼル」という図像の理解にはまた違った状況が生まれていたかもしれない。また、森永太一郎はクリスチャンであったが、彼がもし異教的図像に反感を抱き、ルネサンス以前の正統的な天使像を採用していたら、森永のエンゼルはグリコのスポーツマンの様な大人のエンゼルであったかも知れないのである。歴史に「もしも」はないとは言え、面白い想像であるとは言えないだろうか。
有翼の幼児としてのクピド像はヨーロッパからアメリカに渡って「キューピー」というキャラクターとして商品化された。キューピーちゃんはさらに幼児化が進み、生まれたばかりの赤ん坊の様になっているが、きちんと羽根は生やしていてキューピッドの属性を持っている。このキューピーちゃんは現在キューピーマヨネーズの商標として一般に知られているが、日本において「有翼の幼児像=クピド」というもう一つの図式を知らしめる代表選手と言えるだろう。また日本でも、バレンタインデーの時期になると、弓と矢を持って相手のハートを射止める恋の神様としての本来的なキューピッド像が多く見られるようになるが、「愛の天使キューピッド」などといった、キリスト教的属性とギリシア神話的属性がごっちゃになった呼称が聞かれたりするのは、宗教的属性への関心の低い日本ならではというべきだろう(例えば"Cupid,
the angel of lovers"といったような言葉が成立しうるだろうか?)。
森永エンゼルに代表される天使像が、それがもともと西欧の図像混淆から引き起こされたものとはいえ、結果的には極めて日本的な、宗教色のとれた天使像…いうなれば「日本的エンゼル」というべきもの(これゆえにこの小論のタイトルを「ニッポンのエンゼル」としてみた)であるのと同様、日本のキューピッドもまた、西欧的クピド像からはかけはなれたまさに「ニッポンのキューピッド」であると言えるだろう。
最後に、現代における「天使」画像について述べておきたい。現代においては、「天使」という概念は図像的にますます混淆している…というよりも、かなり自由な解釈が可能な抽象的存在になっていると言えるだろう。「天使」や「クピド」といった伝統的な具体的存在としてよりも、「天使的なモノ」という一種の雰囲気によってそれらは印象づけられる。内藤泰弘の漫画「TRYGUN」に登場する天使(図15の右下方)には羽根が存在するものの、この天使は未来のバイオテクノロジーによって作られた人工物(機械のエネルギー源となる生命体という設定のようだ)で、キリスト教の天使との直接関連はない。アメリカ映画「シティ・オブ・エンジェル」(図16)はヴェンダースの「ベルリン天使の詩」のリメーク映画であるが、そこに登場する天使は人間と変わりない姿で、伝統的なキリスト教図像学的にみた「天使」の定義にあてはまるものではない。更に庵野秀明のアニメーション「新世紀エヴァンゲリオン」では、訳語が"Angel"でありながら日本語では「使徒」(キリスト教の言葉では「使徒」の訳語は"Apostles"となる)という名称を持った奇怪な存在(図17)が登場する。彼らは外形もまったく異なる様々な存在であり、「人類の敵」である「使徒」という名付けによってのみひとくくりにされる集団である。ここでは"Angle"という存在について伝統的な名称やその指示内容といったことには縛られない、良く言えば自由な、悪く言えば無茶苦茶な解釈が行われていると言える。この最後のような例は、現代日本のような天使/クピド/フェアリーといった意味と図像の混淆が進んだ状態でなければ生まれ得なかった、とすればやや結論を急ぎすぎることになるであろうが、日本がその様な自由な解釈が生まれやすい土壌であることは間違いないことと思う。なにしろ、西洋の国を相手にした戦争(日露戦争)で西洋の天使に日本の軍服を着せて(図9)雑誌に載せてしまえる国なのだから。
注1:荒俣宏「広告図像の伝説」(平凡社)第一章「逆立ち天使のいたずら」
注2:高階秀爾「ルネサンスの光と闇」(中公文庫)187ページ。
注3:エルヴィン・パノフスキー「イコノロジー研究」(美術出版社)「盲目のクピド」。
注4:荒俣宏,前掲書37ページ。
注5:同上。
注6:タイモン・スクリーチ「大江戸視覚革命」(作品社)36〜40ページ。
注7:荒俣宏,前掲書31ページ。
注8:同上。
注9:同書37ページ。
注10:同書24ページ。
荒俣宏「広告図像の伝説」(平凡社)
高階秀爾「ルネサンスの光と闇」(中公文庫)
日本の美術No.36「洋風版画」(至文堂)
タイモン・スクリーチ「大江戸視覚革命」(作品社)
イタリア・ルネサンスの巨匠たち17「マンテーニャ」(東京書籍)
高橋克彦「新聞錦絵の世界」(角川文庫ソフィア)
内藤泰弘「TRYGUN」(徳間書店)
「新世紀エヴァンゲリオン・フィルムブック」(角川書店)
「薔薇とエンジェル展」新潟県巻町「ロマンの泉美術館」
いろいろ研究室に戻る